「首流し」
紅葉を眺めそぞろ歩く人々のなかで、真っ白な風呂敷包みを抱いた母の姿は、あきらかな異様を呈していた。
僕は、その背に隠れるようにうなだれて後に従いた。
「ここじゃいかん、まだ先だ」独り言を呟きながら、ひと二人がやっとすれ違うほどの路を母はずんずんと進んでゆく。数限りない嘲りの視線がその手元にぶつかるたび、僕の顔はますます地面と向き合うのだった。
長い石段を登りきると、紅や黄の濡れ落ち葉に屋根を染めた庵がみえた。散策路の終点だった。ひと息つこうという僕を尻目に母は庵を素通りし、低い垣を跨いで奥の雑木林に入っていった。
小枝で蜘蛛の巣を払い、立ち木を躱しかわし歩くうち、せせらぎの音が耳元に迫るほど近くなった。朽ち倒れたカエデの巨木に行く手を塞がれた處で、肘でクマザサを分けながら川岸へと降りた。
晩秋の渓流は、透き通るというより、乳色がかる碧に濁って見えた。
「ここだ」と、やや上流にいた母が声をあげた。足を滑らさぬよう注意しながら近づくと、川幅半分をせき止める大きな岩の下、ゆっくりと渦巻く淵を母は指差してみせた。
「なんで、こんなとこにするんだ」僕は責めるように訊いた。
「すこしでも長く見とれるから・・・・・・」消えいるような声で母は答えた。
「いまさら未練出してもしょうがないだろ。はやく済ませて帰ろまい」言葉の終わりで、僕は怒鳴りかけていた。
しゃがみ込んだ母がもたもたした手つきで風呂敷の結び目をほどくと、眼を瞑った人の首が現れた。父の首だ。
今日は父の十日祭、仏でいう初七日にあたる。
残りの身体はどうしたのか? 誰がいつ切り離したのか? 定かな記憶はまるで無い。ただ十日祭に、遺族は故人の『首流し』をする務めがある、という言い伝えだけが、不思議と心に刻まれていた。
今際の際の蒼白さを留めた父の顔を、母はしばらく見つめていた。
「はよ、天の奥津城に送ってやろまい」僕が決心をうながすと、母は、前にならえをするように『父』を持つ両腕を差し出した。
「ごめんね、お父ちゃん」
母の手のひらから父がころんと落ちた。短い水音をたて、父はいったん深く沈んだが、すぐに面を上にして浮かび上がってきた。
蒼白さが水の碧に溶け、硬直した輪郭が失われた。安らかな眠りをたたえた眼鼻口だけが、くるくると回りながら早瀬の方に引き寄せられていった。
たすきがけの流れに乗り、しだいに小さくなる父の顔。すべての風景が消尽する彼方の一点で、その魂は故郷の山河と和解を遂げるのだろう。そして迷わずこの場所を選んだ母は、かってこの渓谷を父と訪れ、きょうの日の約束をしていたに違いない。
「ワシが死んだら・・・・・・」案の定、母が口を開いた。
「おまえの手で、ここへ流してくれんかのう」
何も聞こえない振りをして、僕は立ちあがった。
了
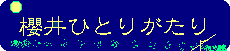
© Rakuten Group, Inc.






