「朝影」
夜明け間近の大路を往きながら、若き日の諭信は、母の叱責を思い返していた。
「あなたが、あの女とうたかたの夢を貪るあいだにも敵兵は国境を侵し、我が新羅の民の命を奪っているのですよ。ましてや、あなたの弟のような若者が矢面に立ち、今日も死を覚悟で闘っているというのに。それでもあなたは、国の要職にあるものですか。いやそれ以前に、一人前に腰に剣を下げることを許された男といえますか」
「私が間違っていました。二度と、あの女とは会いません」
諭信は、平身低頭して母に誓った。
――母の言うことはもっともだ。貧しい者に苦労を押し付け、女色に耽る自分が悪い。しかし、この国の危難のすべてを、私が引き受けねばならぬという道理があるだろうか。
馬上の諭信は胸の内で問うた。母にああ誓ったものの、心から反省していた訳ではない。本音は、顔に火がついたような羞かしさから逃がれたかっただけなのだ。
木犀の梢の下にさしかかった。星屑のような花が、甘い匂いをただよわせていた。
――万人が幸せに暮らせるわけではない。誰かが楽を求めれば、誰かが苦を荷う。そう、あの女だって、重い哀しみの石を背負って生きているのだ。
諭信は、妓女の真白い胸に憩う自分を想い出す。
「私の故郷は国ざかいの小さな村で、父はその土地台帳を管理する役人をしていました。田舎にはもったいないほど美しい母と親子三人、富むでもなく、栄えるでもなく、それでも満足におだやかな日々を過ごしていました」
いつか寝物語に聞いた彼女の生い立ちだ。今ごろなってはっきり耳に響いてくる。
「そんな暮しも、とつぜん村に攻め入った百済の兵に奪われてしまいました。目の前で父母を殺され、ひとり生き残った私は、輜重の車に曳かれて敵国に運ばれることになりました。自分が奴隷にされると聞かされた時、私は子供心にも死を望みました。・・・・・・しかし、情けある人はどの国にもいるもの。同い年の娘を持つという士卒が、夜営の間に私の縛めを解いてくれたのです。私は、幕舎を抜け出して闇中をひたすらに走り、野中の一軒家にたどりつきました。驚く家の人に事情を話すと、たまたまそこに宿を借りていた商人が『都で親代わりになってやろう』と声をかけてくれました。当時の私には、その言葉が意味するものを知るよしもなかったのです」
諭信は、しだいに耳を塞ぎたくなってきた。そのささやきが母の声となり、その打ち明けが母の叱責と混ざり合い、彼の心を苛んだからだ。
「こうしている間にも、国ざかいの村々では、たくさんの『私』が生まれています。そして、こんな風にあなたの情けを享けることなく日陰の生を終えていくのです。涙の河は果てしなく連なるのに、けっしてこの国を潤すことはない。同胞の嘆きを肌身で知りながら、都で嬌名をうたわれ生きることに何のよろこびがありましょう。どうぞいつでもひとりの私を捨て、数限りない『私』のために、新羅の將として起ってくださいませ」
ここで諭信はかっと眼を見開いた。そのとき彼の乗る馬も、主の緊張を気取って立ち止まった。驚いたことに、そこは妓女の邸の前だった。「ちがう、進め」と手綱を引き腹を蹴っても、愛馬の脚は微動だにしない。けわしい表情で馬を降りると、諭信は剣の柄に手をかけた。
短いいななきに続いて、どっと何かが崩れる音がした。
夜通し待ちつづけていた妓女は、門口に面した窓に駈けよった。朱い格子を透かして、横たわる馬の背から剣を抜く愛人の姿が見えた。彼女が何事と戸惑うあいだに、男は邸に背を向けて朝霧の中に身を消した。
妓女はすべてを悟った。孤閨に引き返し、わずかな涙を流したあと、鞘を払った小刀の切先で自分の喉笛の位置をたしかめた。
甍の波を越え、曙光が大路に射しはじめた頃、葦のようにひょろ長い我が影を見つめながら後の名将はこんな繰言を呟いていた。
「私だって弱い人間だ。だが男ゆえ、涙の河に連なることはゆるされない」
了
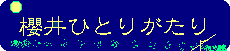
© Rakuten Group, Inc.






