(二)
路面電車を降り、本丸址へとつづく石畳の坂道をのぼった。
陽は西の山ぎわ近くまでかたむいていた。南面する格子の連なりは白々と金属的な光沢を帯び、対する北面の家並は、冷たい陰の中に軒をしずめていた。
あちこちの辻に、時代ドラマのロケ場所をしめす看板が立っていた。各店舗のショーウインドウには、何代にもわたり受け継がれてきた商売道具や帳面が陳列され、ひとつひとつ筆書きの説明が添えてあった。以前はなかった観光客向けの演出だ。俗っぽさが鼻につき、僕は興ざめの感をいだいた。
気分を変えようと脇路に入った。なまこ壁がつづく裏通りには、仔猫とたわむれる子供たちや、おっとりしたご当地言葉であいさつを交わすご婦人方がいた。素直なくらしの光景は今も変わっていない。路脇の溝をはしる水のせせらぎに余計な考えは洗いさられ、やはりこの町に来てよかったと思いなおした。
ふたたび表通りに出て、県文化財の指定を受けている武家屋敷の前にさしかかった。ちょうどそのとき、向こうから花嫁の門出の行列が近づいてきた。
紋付姿の仲人を先頭に、各々祝いの品を持つ親類縁者の列がつづく。最後に、縁起ものの鶴や松を描いた打掛をまとう花嫁が、提灯を提げた少女に手をひかれ、お供の女性がさしかける赤い日傘とともに屋敷の門前を横ぎる。その美しさをほめそやす人々にまぎれ、僕は、かってこの門が長い輿入れの列を送りだした当時のことを想い描いた。
宵闇が濃さを増すころ、長持をかついだ男たちが築地塀に沿って並び立つ。そのうしろ、明々と燃える門火に照らされた長屋門から、定紋入りの挟箱、守り脇差、長刀のあとに、花嫁を乗せた輿があらわれる。映画の撮影カメラのように、僕の視点は彼女の横顔にせまる。綿帽子の下、頷を引きかしこまった女性の無表情に、なぜか久遠橋で見たあのひとの面影がかさなる。栗色に潤みかがやく瞳が火影を宿してゆれている。ゆれながら玉をなした光が、ふと留まることあきらめたよう手の甲にこぼれ落ちる。目頭に指をそえたあと、何かを思いつめた様子で彼女は懐から細く折りたたんだ紙を抜きとった。そしてそれを、深いお辞儀とともに僕の目の前にさしだした――
・・・・・・予期せぬ情景におどろき我に返った。沿道の人々はとうに散り、輿入れの列が向かった先には日傘の影さえ見つけることはできなかった。つよく吹きだした日の暮れの風にせかされ、僕はいそぎ足で坂をくだった。
宿にもどって、夕食も摂らずベッドに身を横たえた。寒風にこごえた肌は、一刻もはやく柔らかい毛布の感触につつまれることを欲していた。
つい昨日まで、こうして明かりを消すと、元恋人のするどい目付きが闇を裂くようにせまってきた。憤ろしさと、消しさることのできない恋慕のはざまで、僕は夜通しあえぎつづけた。
なのに今夜はちがう。脳裏は、わずか二度見ただけの横顔で占められている。ましてや白昼の人中にありながら、そのまぼろしに正気をうばわれるなんて。僕の胸奥にひそむ多情な性のなせる業か。ちがう、そんなかりそめの恋ごころじゃない。彼女の面影がもたらすものは、過ぎ去った幸福を夢に視たときと同じ、あのしんとした甘がなしさだ。このやさしい感傷は、この懐旧の想いは、自分のどこを源としているのだろう。
「あのひと、頭おかしんいだから」女子高生の言葉は本当かもしれない。そういえば、手紙を読む彼女の目つきは尋常じゃなかった。でも、それがなんだ。婚約者とキスを交わした元恋人の、あの僕を凍らせた目つきにくらべれば。
いや人のことは言えない。たかが女で、仕事と日常の生活を棄てた自分だって狂っている。その僕を笑った少女たちも、無関心な顔でかたわらをゆき交う人々も、みな一様に狂っている。この地上をおおう濁流のような狂気のさなか、ひとりあのひとだけが澄んだ瞳の色を保っている、これこそ正しい答にちがいない。
何があの瞳を清らかにさせるのか、どうしてあのひとの面影が自分を遠い過去の追想へといざなうのか、すべてあきらかになるまでこの街に留まってみたい。そんな希みが、はやくも僕の胸にきざしていた。
* * *
翌朝もあのひとは久遠橋の中ほどにたたずんでいた。
三十分ほど時間を遅らせただけで人通りはすくなく、傍若無人な少女たちの姿も見あたらない。僕は橋の上に歩み出て、束柱一本分はなれたところから彼女の横顔を目で盗んだ。
きょうの彼女は髪をうしろに束ねており、例の美しい耳殻を陽光にさらしている。うなじに向けてぴんと張った縁のかたちが、すらりとした頬の輪郭に幼げなアクセントを添えている。肌は白い。化粧の粉っぽさを感じさせない白さだ。だから紅をひいた気配のない唇も、雪を割る花のようにきわだっている。
けれどなにより僕を惹きつけるのは、相かわらず川の流れに向けられた彼女の眼だ。うすくけぶる額髪の奥で銀の粉をちらす瞳を注視するうち、我しらず身体が彼女ににじり寄り、左手がじりじりと欄干を這いすすむ。その指先が肘先に触れる刹那、不意にコートの袖がひるがえった。僕はいそいで腕を引き、川下を眺める姿勢をつくろった。
かさかさと紙のこすれる音がした。欄干に肘を置いたまま横目で様子をうかがった。彼女は例の手紙を取りだして、昨日と同様、食いいるようにそれを読みはじめた。
十五分、そして三十分・・・・・・・・さすがにしびれが切れかけたころ、あのひとはやっと封筒を懐中におさめ、僕に背を向ける格好で歩きだした。
彼女は橋のたもとを左に折れ、電車通りの歩道を早足ですすんだ。僕は適当な間合いをはかりながら、そのあとについていった。
市街地が背中に遠ざかり、道脇には煤けた民家ばかりが目だつようになった。その屋並も路面電車の終点とともに途切れ、景色が郊外の様相を帯びてきたところで歩道が二筋に岐かれた。一本はまっすぐ車道に沿って延び、もう一本は幹線を逸れて川畔へとくだる。あのひとは後者の道をえらんだ。
やがてその道は、長い自然堤を活かした緑地公園の遊歩道に合流した。左手には葉の落ちたソメイヨシノの並木がつづき、黒い幹の間から、対岸の汀に憩う水鳥の群がながめられる。右手の芝生広場では、母親が幼い子供を遊ばせている。
学生時代、僕もよくこの道を散策した。周囲の景観はあの頃への郷愁をかきたてるが、いまは懐かしさにひたるべき時じゃない。僕はしいて彼女の背中だけを視野におさめつづけた。
芝生広場を過ぎてほどなく、背丈よりもやや高い、御影石の碑の前で彼女は立ち停まった。碑は、かってここの川岸に船着場があったことを示すものだ。ならんで一体の阿弥陀如来が祀られている。
あのひとは懐から白い封筒を取り出し、碑の台石に立てかけた。橋で読んでいたものとちがう。紙の真新しさが僕の注意をひく。しゃがみ込み、しばらく拝むようにうつむいてから彼女は腰をあげた。そして僕の気配を察知することもなく、また坦々とした足取りで歩きはじめた。
小さくしぼむうしろ姿を見送るうち、いま置かれた封筒の中身をたしかめたいという欲求にかられた。ところがそのとき、側の植込みの陰から作業服姿の男が現れ、碑に近づこうとする僕の進路をさえぎった。柄の長い竹箒を手にしているところを見ると、この公園の清掃職員らしい。彼はすっと腰をかがめて封筒を取りあげ、胸のポケットにしまいこんだ。
僕は、つい「あっ」と声を洩らした。すると、険しい表情で振りかえった彼が、頭から突き進む格好でこちらに迫ってきた。その勢いにうろたえて斜めに後ずさった。血ばしるまなこで前方を見すえたまま、彼は僕のすぐ脇を通りすぎていった。
* * *
フロントマンから部屋の鍵といっしょにメモ書きを渡された。
「矢口さんとおっしゃる方からお電話がありました。お帰りになったらこの番号に連絡ください、とのことです」
「どうもありがとう」おざなりの礼を言ったあと、紙片をポケットの中で握りつぶした。
一夜にして、僕はまどいの内に引きもどされた。
碑に向かい祈るようにうつむくあのひとの残像が、まぶたの裏をはなれない。また僕自身、きょう訪れた船着場に何らかの執着をのこしているはずなのに、それすら思いだせないまま眠れない夜をすごしている。途中までぼんやりと暗い情景がよみがえる。だけどいざ具体的な像を結ぶ段階になると、手に入れそこねた封筒の白さや、それをうばった男の紅ら顔があらわれては邪魔をする。
とうとうあきらめてベッドを降りる。小さなスタンドを点し、冷蔵庫から出したビールをあおる。冷えすぎで味を感じない。まるで氷水を飲んでいるみたいだ。でも、この頭の芯にせまる冷たさが、気持ちの切りかえをたすけてくれるかもしれない。
一口あおっては、長く息を吐く。それからぎゅっとまぶたを閉じ、喉元の感触を神経のすみずみまでいき渡らせる。繰りかえすうち、まぶたの裏が無地の灰色におさまってきた。そこにすかさず、あの場所にまつわる記憶を定着させようとこころみる・・・・・・
――――時は夜だ。対岸のあかりを背に、黒光りする碑の影が立つ。その手前にも人影が・・・・・・亜紀子だ。同じゼミで学んでいた、学生時代の恋人だ。
「もう、ほんとに性欲の塊なんだから。ああ、ベタベタして気持ち悪い。このへんにお手洗なかったかしら」
あきれた口調で彼女が言う。ホテル代も持たない僕らはここで闇にまぎれ、たがいの身体をまさぐりあった。どうにも我慢しきれない欲望を、僕は彼女の手を借りてしずめざるを得なかった。その直後のせりふだ。
「トイレはずっと先だ。そんなに気持ち悪けりゃ、川の水で洗いなよ」
「そんな、足を滑らせたらどうするのよ。顔でもケガしたら、あなた責任もてる?」
「責任もつ、ってどういうこと。もしかしてお嫁にもらえってことかい」
「そんなつもりじゃないわ。でも・・・・・・お嫁さんかあ・・・・・・」
亜紀子は小さくため息をついた。そしてまた、僕に歩み寄ってきた。
「ねえ、ここって船着場の跡でしょう」
「ああ、昔は上流にダムも分水路なかった。水量はもっとゆたかで、乗合船がらくらく通えたはずだ」
「そうなんだ。きっとたくさんの女の人が、ここから下流の町に嫁いだのね」
右肘に亜紀子の腕がすべりこんだ。僕らは闇に馴れた眼で見つめあった。亜紀子の顔つきがリスのようにあどけない。彼女、こんなに子供っぽかっただろうか。とまどいが、意図せぬ皮肉となって口をついた。
「よしてくれ、君にそんな夢想は似合わないよ」
「どういうこと」彼女は、僕の鼻先すれすれに顔を近づけた。
「ほんとうのわたしを探すため哲学の道をえらんだ、なんて格好つけてた君なのに、女性が自己滅却を強いられた時代に想いをはせ、うっとりするなんておかしいよ」
「そうかしら」
自分でもあきらかに言いがかりだと分かっていた。でもそのときの僕は、なぜか喉元にわだかまる言葉をとどめきれなかった。
「死を想う時、人はたまらない不安におそわれる。しかし、この不安に打ち克とうとする努力の裡に人間が人間たる証しがひそむ。哲学はこの証しをたずねる仕事、つまりおのれの死と真正面から向きあう仕事だと、僕は、僕なりの信念をはぐくんできた。おそらくこれは、君のような秀才にすれば自明の理で、自分みたいな劣等生がいまさら口に出すことさえ恥かしいと思ってた。ところがどうだ。君は夜の川を見て、ただいにしえの花嫁に憧れる本心をさらけだした。不安と孤独を怖れ、家や夫に隷属する生き方に甘んじた女性に、みずからの努めを忘れて共感の意をしめした。そんな態度は、僕たちが師と仰ぐ先達の労苦をないがしろにするものじゃないか」
「私、ここまで来て研究室の会話をつづけるつもりはないわ。今夜はやけにつっかかるのね」
亜紀子は眉をひそめた。からめていた腕をほどくと、彼女はまた、ひとりで碑の影に近づいていった。その目線の先には、黒い鱗のように川波がひろがっている。
「だったら、あなたはどうなの」彼女は、背を向けたまま僕にたずねた。「この暗い流れを見て、何を想うの」
すこし考えてから、僕はこう答えた。
「補陀落渡海だね」
「『ふだらくとかい』って、あの神仙思想の?」
「そうだよ。一千年むかし、海の向こうにある天国の島をめざして粗末な屋形舟を漕ぎだした人々。ここから河口へとくだり、本土を発った例もあったにちがいない」
「そんな大仰な言葉を持ち出して、あなたこそ感傷たっぷりのロマンチストじゃない。とても私を非難する権利はないわ。ひょっとして、あれしきのお酒で酔ったの」
「いや酔っちゃいない。僕はただ、補陀落渡海の言い伝えを通して、死とは何かを考えてみたいんだ。平安初めの話とはいえ、ただ極楽浄土への憧憬だけで、人々は帰らぬ旅を決意しただろうか。生まれ育ちによる束縛は今よりもはるかにきびしい時代だ。彼等にゆるされた世界は狭く、一山向こうの里に移ることさえ涙を誘う離別をともなった。くるしみを将来への希望でおぎなえるほど寿命は永くない。おそらく彼らは不老不死なんて望んじゃいなかった。むしろみずからすすんで死のまねきに応じようとした。なぜなら死こそたましいの解放であることを、そして本来の自分を取りもどすただひとつの道であることを、彼らは無意識のうちに悟っていたからだ」
亜紀子はまだ振りむかない。腕を組むうしろ影が、古寺の御堂に垣間見る観音立像を想いおこさせる。
「私はちがうな」小さいけれど、よくひびく声で彼女は答えた。「私はやっぱり女だもの、どうあっても明日を生きぬく道をもとめていきたい」
「生と死のとらえ方に、性差があるというのかい」
「あるわ。哲学を死の学問に仕立てあげたのは、あなたもふくめた男のひとたちよ。私が既成の哲学に興味を持ったのは、まるで自分の考えの裏うつしだから・・・・・そう、あなたたちの死という言葉を、『生』そして『産み』と置き換えてごらんなさい。私たち女の哲学がよく解るはずだわ」
「それは哲学じゃなく、君たち女性の本能だ」
「自分でたどり着いた考えだもの、なんと呼ばれようとかまわない。私たち女は、新たな生を宿し、産み、はぐくむ可能性としてみずからをとらえている。どんな状況にあっても、子供が、孫が、そして累々とつらなるその子孫が、この生命を受けついでくれると信じて進むべき道をえらぶ。難しい理屈なんて知らなくても、わが子のためなら火中にでも飛び込む強さを生まれながらに持ちあわせているのよ。たとえそれが本能にすぎないとしても、男たちが机上にきずいた死の哲学に比べてどれほどの遜色があって。行動は恒に思想よりも尊ばれるべきだわ。女にとって、いのちはみずからの血が流れる川を意味するのよ」
「・・・・・・・・・・・・」
「あなたの言う補陀落渡海の舟に、この世をはかなみ乗り組んだ女性もいたことでしょう。でもきっと彼女たちは、死を求めてなんかいなかった。どこまでも生を求めて、このいのちが永遠に受けつがれることを信じて、はるかな楽園をめざしたはずだわ」――――
・・・・・・・・ここで僕はまぶたを開く。椅子をたち、この部屋でひとつきりの窓から深夜の通りをうかがう。
すっかり灯の消えた飲食街の前に、ふたりの女がたむろしている。若そうな身なりをしているが、ときおり通りかかる男を呼ぶ声はみじめにうるおいを失っている。
本当に彼女たちも、みずからを生にかかわる存在としてとらえているのだろうか。あるいはまた、夜が明ければ、ゆるやかな流れの果てを見つめるであろうあのひとも、南国の香気あふれる楽園を夢見ているのだろうか。
ますます、あの封筒に秘された謎が気になってくる。
(三)へ続く
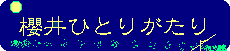
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- イラスト付で日記を書こう!
- 一日一枚絵(11月21日分)
- (2024-12-05 00:40:28)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 僕は君たちを支配する 2巻 読了
- (2024-12-03 19:05:07)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
© Rakuten Group, Inc.



