(四)
雪は明け方までにやんだ。太陽はまだ雲を割らない。今朝の僕は、はじめから船着場跡に足を向けている。
実をいうと、目覚めた時から喉が痛い。背筋には不快な寒気を背負いこんでいる。まちがいなく風邪のひきはじめだ。連日の夜ふかしがたたったのだろう。だが、それも借りものの肉体に起きたこと、心だけの自分にいささかの影響もおよぼすはずはない。
郊外は、北国を想わせる雪景色だ。人気ない遊歩道の脇では、サクラの並木が、広場のハボタンが、水鳥の声や羽ばたきにおどろくことなく純白の布団の下にまどろんでいる。一歩一歩、新雪にスニーカーを埋めながら、僕はこの先の展開を想いうかべる・・・・・・・・・・
――――この積雪にもかかわらず、彼はいつもと同じ場所で僕を待ちかまえていることだろう。「どうした。ばかに早いじゃないか」と声をかけてくるにちがいない。
「あといちどだけ、彼女の顔をまっすぐ拝みたいんです」とこたえて、僕はきのう借りた手紙を返す。
「いくら恋いこがれても手のとどかない相手だよ。これを読んでふんぎりがついたか」
「ええ、とても眼中に入れてもらえる余地はなさそうな、かといって、忘れるには時間がかかりそうな気がします」
「べつに忘れる必要はない。そのつらさを耐えて男は一人前になっていく。こんなワシでも、若い時分はいろいろ悩みがあったもんさ」
「そうですか・・・・・・」
大仰なやりとりに辟易しながらも、僕は神妙な態度をくずさない。あくまでも低姿勢をたもちつつ相手の人の良さにつけこんでいく。
「ひとつお願いがあるんですが」
「なんだ」
「今回だけ、僕に彼女の手紙をとらせてください」
「ああ、かまわんよ。ワシも雪掃きでくたびれたし、ここらで休憩をとろうと思ってた。また倉庫に遊びに来いよ」
「ありがとうございます」
何のうたがいもいだかない様子で彼は管理棟へと引きかえす。そのうしろ姿が植込みの陰に消えるのを見とどけてから、もうひとつの封筒を上着のかくしから取りだし、碑の台石に立てかける。
そして空をあおぐ。雲間から光の縞がもれている。やがてこの場所にも薄日がさすだろう。そのとき僕は視る、風にさらわれた雪の粉がきらめく奥に小さな人影があらわれるのを。
遠近のけじめもつかぬ雪景色の彼方から、拡大する映像のようにあのひとの姿がせまる。吐く息のせわしなさは、きっと履き慣れないブーツのせいだ。ボタンを外したコートの内では、薄いニットのセーターが胸のふくらみを強調している。
その姿を陶然とながめる僕をやりすごし、あのひとは碑に相対する。なに気なく腰をかがめた直後、彼女の横顔が青くこわばる。ふるえる手が下に積もる雪さら台石上の封筒をすくいあげる。立ちあがると同時に、指のすきまから洩る雪がブーツの甲をかくし、雪煙をなびかす足もとから編上の影が消える。そのまま軽々と宙に浮き、風にさらわれるようにして、彼女は雪景色の彼方に去ってゆく――――
・・・・・・半時間後、僕の想像は寸分たがわず現実となった。より正しくは、想像が現実をまねき寄せた、と言うべきだろう。肉体のくびきを捨て去ったことにより、僕は、みずからの意志でみずからの未来を創造する力を獲得したのだ。
* * *
ホテルにもどり、暗くした室内で瞑想にふけった。次々と頭に浮かびくる未来像をたしかめ、自分なりの修正をほどこしていたところへ、フロントからの内線電話が入った。
「矢口様とおっしゃる方からお電話です」
「つながないでください」
「えっ」
「彼と話したくありません。つながないでほしいんです」
「では、何とお断りすればよろしいでしょうか」
「その人はここを発った、と伝えておいてください」
「しかし・・・・・・・」
「いいんです。どうせ明日にはチェックアウトしますから」そう言って電話を切った。
矢口と話すのが億劫だ、という訳ではない。僕はもう彼の識らない人間なのだから、軽々しく接してはならない、すべての言葉は明日の再会のため温存されるべきだ、それが友との会話をこばんだ唯一の理由だった。
* * *
これまでの宿泊代を精算してホテルを出た。
もともと温暖なこの地方だ。ずっと日陰になる場所をのぞき、あたりの雪はすっかり溶けていた。ゲーム喫茶の看板が目につく裏通りをすぎて、商店街のアーケードに入った。途中、デパート前の有料ロッカーに手荷物をあずけて身軽になった。鏥の浮いた銀屋根や、閉ざされた店舗のシャッターに、高く僕の足音がこだました。
僕の手紙は読まれたはずだ。あのひとも、ふたりの希いがかなう瞬間を待ちこがれているだろう。だから徹夜で、その時に至るための筋書きを用意した。何度も練りなおし、完璧に仕上げたからには、失敗を懼れる理由はない。
しいて障りをあげるとすれば、昨日よりもひどくなった咳と悪寒か。厚いシェットランド・セーターを着こんでも、身体の震えがとまらない。
けれどこの身もしょせん仮の宿、彼女と結ばれるまでの数時間もってくれれば充分だ。僕はそう割りきっている。
アーケードを抜けると、すっかり目になじんだ朝の情景がひらけた。群集の切れ間を透かしてあのひとの姿をたしかめる。いつも通り、男もののコートに身をつつみ、彼女は橋の中ほどに立っていた。手元でちらつく紙の白さがまぶしい。
通りをよこぎり橋上の歩道をすすんだ。落ちつかない彼女の仕草が読めてきた。ひっきりなしに両のたもとに目を配り、唐突に宙をまよった指先でみだれてもいない髪をくしけずる。
いったんバルコニーに身を寄せて人波をのがれた。それと同時に、あのひとの目線が僕をとらえた。はやくも気づいてくれたかと思ったが、一度まばたきしただけであちらを向いてしまった。ふたたび人の流れにもどり、早足で彼女の背後にさしかかった。
肘先でさりげなくコートの背をかすめてみた。するどく肩をそびやかし、彼女は左右を見まわした。向こうのたもとまで歩いてきびすを返すと、色白の頬が燠火のように朱く染まっていた。
すぐ名乗りでたい、そんな衝動に駆られた。だがそれでは、夜通し練りあげた筋書きが意味をなさない。しばらく待とう。この脈拍と血のぬくもり、微弱な肌の匂いを伝えるには騒がしすぎる時間帯だ。半時間も待てば朝の混雑はおさまる。それまでの辛抱だと自分をなだめた。
ところが、ここで余計な邪魔がはいった。先ほどから人待ち顔で辺りをうろついていた男が、あのひとに近づいていったのだ。短く刈りこんだ金髪に、よごれた皮ジャンパー、落書きだらけのジーンズといういでたちで、夜通し遊んだあとの煙草と酒の匂いを、不潔な風貌からただよわせていた。
「だれか待ってんの」とヤツが声をかけた。もちろん彼女が相手にするはずもない。だがヤツは性懲りもなく袖をすり寄せ、軽薄な誘い文句をならべたてた。「よかったら、朝のコーヒーをおごらせてくれない。あんたみたいな美人がひとりじゃもったいない」
僕が予見する未来のたしかさは、僕の想念の純粋さに拠っている。それを汚し、疵つけるゴミは、いそいで取りのぞかなければいけない。ここは、不測の事態に対処すべき場面と判断した。
男の肩をたたき、「彼女になんの用だ」と声をかけた。相手は急に口をつぐんだ。僕はいっそう低く声をひびかせ、ニキビ痕もみぐるしい顔を脇からのぞきこんだ。「彼女になんの用だ、と訊いてるんだ」
「うるせえな、邪魔すんなよ」と言ってヤツは目を逸らした。みてくれのわりに肝は細いときめつけ、僕は喧嘩腰をよそおった。
「おまえこそ人の待ちあわせを邪魔するな。ナンパがしたけりゃ、そのへんのガキを相手にしてろ」語勢に乗じて胸ぐらをつかもうとしたら、ヤツはすばしっこく跳び退いた。そしてこう言い放った。
「おれだって女に不自由しちゃいない。ひまつぶしにこいつをからかってみただけさ」
「はなから相手にされていないのに、だれをからかったつもりでいる」
「なんだと」と口ではすごむが、爪先は早やあさっての方を向いている。さっさとケリをつけるため、僕はこぶしを固めながらつめ寄った。
「今度はおれがおまえをからかってやろう。ほら、かかってこいよ」
「うるせえ、てめえ覚えとけよ」
吐きすてるがはやいか、ヤツはかたわらの雑踏におどりこんだ。たちまちジャンパーの焦げ茶が人のあいだを縫うようにはしり、交差点の彼方に遠ざかった。
やや拍子抜けの気分を味わいながら、僕はあのひとの方に向き直った。じっとうつむいた姿が、くじけた彼女の気持を代弁していた。あるいは、あいつにだまされたと思ったのか。このままでは手紙の真偽さえ疑われかねない。もはや僕は、自分の正体を秘すことに堪えられなくなった。
「気を取りなおしてください。その手紙は本物です。あいつは何の関係もありません」思いきって、相手を指した口調で話しかけた。垂れた額髪の下、彼女の眉根がびくんと動いた。
「こころの眼をひらくんです。あなたが元のかたちこだわるかぎり、待ちびとの姿をとらえることはできないでしょう」
なめらかな喉の線を波打たせ、彼女はしずかに唾を呑んだ。
「今朝、ここで会おう、と彼は知らせてきたんのすね」と、自分が書いた手紙に目をやり、僕はなおも語りつづけた。
「その人は遠い地に赴くことになり、あなたに同行をもとめた。けれど、あなたは訳あってその希いにこたえられなかった。それで、彼の言葉を信じてその帰りを待つ一方、もしや恋人の縁を絶たれたのではという危惧をいだきつづけてきた。ちがいますか」
彼女の瞳がゆれはじめた。ゆれながら横目で、僕の背格好を上下になぞった。
「でも事実はこうです。不幸なことに、彼は慣れない土地で心の病にかかってしまった。そして、あなたとの恋もふくめたいっさいの記憶を無くし、別人として生きることを強いられた。けれどもう大丈夫、彼はやっと本来の自分を取りもどし、なつかしい歳月の匂いに惹かれてこの街に帰ってきました。そしてあなたのすぐそばで、その姿をみとめてもらう時をこころ待ちにしています」
あのひとの視点が、僕の顔だけをさしたまま動かなくなった。わななく唇がもの言いたげにひらくのを見た瞬間、彼女に先んじるつもりで答をあきらかにした。「そう彼とは、いまあなたが目のあたりにしている、この僕のことなんです」
いったん蒼ざめた頬に燠火の朱がよみがえった。それを歓喜のしるしと信じ、すがりくる恋人のために身がまえた。ところがここにきて、事態は僕の筋書きをうらぎる方向に急転した。
いきなり怒りとも嘆きともつかぬ形相に頬をゆがめ、あのひとは「ああ、ああっ」とわめきはじめた。そして癇癪をおこした子供のように、欄干の手すりにこぶしを打ちつけた。うろたえた僕はその手首をとらえ、相手を説きふせにかかった。
「姿かたちに捕らわれちゃいけない、記憶だけがふたりの真実だ。あの夜、川風のなかで交わした約束、ともに手をたずさえて楽園へと旅だつ約束を忘れたわけじゃないだろう。ほら、この手紙を書いたのは僕なんだ。最後に書かれている倶會一處の合言葉をほかに知る者はいない。ここまではっきりしているのに、なぜ目前の真実をこばむんだ」
一気呵成にまくしたてたあと、異様な雰囲気を背後に嗅ぎとった。振りむくと、老若男女いりまじった人垣が、僕らを扇状にとり巻いていた。みんなの好奇にみちたまなざしが、あのひとの手をはなした自分に集中した。
「あ、いや、僕と彼女は・・・・・・・・」もつれる舌で弁明をこころみた。だが、その先をさえぎるかのごとく、橋上にかん高い悲鳴がひびきわたった。
つられてまたも向きなおった。あのひとが泣きながら欄干越しに両腕を突きだしていた。さらにその手の先から、ふたつに裂けた便箋が舞い落ちるさまが目にはいった。
とっさに体当たりで人垣をつきやぶった。誰か彼かの罵声をあびながら、僕はやみくもに通りを駈けぬけた。心臓が頭の中でおどっていた。風笛が狂騒の音を耳元でかなでた。街が紅く燃えて視えたのは、熱くたぎる涙のせいだろうか。
(五)へ続く
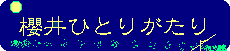
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- ウィニング勝利の経営 =4章 発言権と…
- (2025-11-29 00:36:41)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0943 キーエンス 最強の働き…
- (2025-11-29 00:00:12)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- レジスタ! 1巻 読了
- (2025-11-24 23:38:36)
-
© Rakuten Group, Inc.



