(五)
休める場所をもとめ、複雑に家が建てこむ住宅地を僕はさまよっていた。
たてつづけに咳が出る。身体が焼石のように熱くて重い。もう一歩も動けないとあきらめかけたそのとき、袋小路の奥に小さな公園を見つけた。手洗い場の水をがぶ飲みして、ベンチにどさりと倒れこんだ。喉をうるおしたおかげで咳はしだいに治まってきた。けれど身体の苦しみが和らぐと、こころはかえって非情な現実に直面せざるをえなくなった。
しらけた冬空のまぶしさがつらい。こらえきれずまぶたをおろせば、悲憤にゆがんだあのひとの表情が思いおこされる。ふたり交わした約束にまちがいはなかったはずなのに、なぜ僕の告白は聴きいれてもらえなかった。それともこのすくいようのない状況は、あまりにも彼女を待たせすぎた罰なのか。
精も魂もつきはてて背中からベンチにしずみこんでいきそうだ。ここで寝込んだら、冷気は容赦なくこの命をうばうだろう。
でも考えてみると、死はあのひとへと近づく唯一の道すじかもしれない。これまで僕はいつわりの肉体とともにいつわりの過去を引きずってきた。そして今にいたってもなお、かりそめの世で起きたできごとをしつこく悔やみつづけている。こんな中途半端な状態では、どんなに手をつくしても彼女の記憶と同化できる見こみはない。そこに、みずからの目論見が破綻した理由を見出せる。やはり僕は、死によって彼女にあたえた悲しみをつぐなうべきだ。やすんじてこの身を無に帰して、心だけの自分になってあのひとに寄り添おう。
そうと肚をくくれば、いのちあるうちの再会にこだわる理由もない。ふたりのあらたな在り方へのいとぐちをもとめ、僕は意識のたがをゆるめていった。
頭に靄がたちこめた。そのあいまいな乳色の向こうに、星をも呑みこむほど暗い裂け目が待ちうけていた。「行っちゃいけない」と、どこかで父母の声がする。けれどもう僕は、彼等のもとに帰るつもりはない。こだまのように声は遠のき、靄は左右に分かれてしりぞいた。いよいよむきだしの漆黒を目のあたりにしながら、僕はなお記憶の糸をたぐりよせ、彼女とともに在った日のできごとをたしかめる・・・・・・
――――「あんなことになってしまって、どこにもふたりの居場所はない」地にうずくまり涙まじりの声でつぶやく僕は、あたりを照らす月光と、迫りくる人馬のまぼろしにおびえている。何者かに追いつめられたすえ、物陰に彼女とひそんでいるらしい。
顔前にかざす手のひらにまだらな染みがついている。生ぐさい匂いが鼻をつく。新しい血の匂いだ。
「だいじょうぶ。あの様子なら、いのちをそこなう傷にはなっていないはず」そう言ってあのひとは僕の手をとり、自分の懐へといざなう。裸の胸にふれる。鼓動が手のひらを伝う。そのゆったりした調子にみちびかれ、僕はいくぶん落ちつきを取りもどす。
「舟はどうする。彼らの眼にふれず、船着場までたどりつけるはずがない」
「番所の守役にも私たちの味方がいるから、先のことは心配しないで。ここにいれば、朝霧にまぎれて迎えがきます。それまでしずかに身体を休めていましょう」
「でも」
「いいの、安心して。ふたりいっしょなら、どんな希いもかなうはずだから」
彼女は僕の頭を抱きよせ、「安心して、ずっといっしょにいるから」と子守唄のように繰りかえす。
絶間ない瀬音のようなささやきにつつまれ、おもむろにまぶたを閉じる。拡散する意識の底、このまま覚めない眠りにおちてしまいたいと僕は希う。――――
場面はそこで、黒い帳の向こうにとざされた。
* * *
どれくらい時が経っただろう。こごえた膚の感覚をともなって意識がよみがえってきた。
暗い、そしてひどく寒い。節々にはしる痛みをこらえて身を起こすと、あたりに点々とにじむ炎がうかがえた。あれが彼岸の迎え火かと、まだ靄のはれない頭で考えた。でも瞳の焦点が定まるにつれ、炎はみな四角い窓明りとなって、建ちならぶ家々の影を浮きたたせた。
なんのことはない、昼間と同じ公園のベンチで僕は目を覚ましたのだ。ため息をつき「なぜ死ねなかった」とつぶやいた。すると、ベンチのうしろに樹つ鈴懸の梢が高くきしみ、そのこだまが尾をひいて、人の言葉を宙につむぎだした。
――それは、あの方へのつぐないが済んでいないから。――そう聴こえた。やや低い、齢のいった婦人の声音だった。ごく近くで響いていたが、けっして目のとどかないしじまの奥から発せられていると僕は直観した。
あるいは幻聴と推しはかりながらも、「やはりそうか」と相づちを打った。それからこう訊ねてみた。「そのつぐないを果たせば、彼女とひとつになれるのか」
――おっしゃる通りです。けれど、そう易々とかなう希みではありません。
「むずかしいのは承知の上だ。もういちど彼女に近づく方法を教えてくれ」
――とにかく生きること、生きぬいて、水をうばわれた魚のような苦しみを味わい、あの方の悲哀を肌身で思い知るほかに希みをかなえるすべはありません。
「なぜそこまでする必要がある。もともと一心同体の誓いでむすばれた仲じゃないか」
――考えてもみてください。どんなにあたたかな陽ざしでも、厚くはりつめた氷をひといきに融かすことはできないはず。ましてや、あの方が堪えた時の永さを想えば、あなたの身勝手な死が、そのつぐないとなりうるでしょうか。
「……なるほど、あんたの言う通りかもしれない。自分は性急に答をもとめすぎた。その誤りをただすため、あのひとが拒絶の態度を示した、それが本当なんだな」
――ええ、あの方の意志があなたを生かしたのです。当のご本人は、まだ久遠橋を立ち去ることができず、きびしい底冷えの中にたたずんでおられます。すぐにここから引きかえし、あらためて帰らぬ旅路に連れ添ってほしいと訴えかけること、それこそが唯一、あなたの罪をつぐなう手だてとなるでしょう。
「わかった」と僕はベンチを立った。そして、つむじ風をともない遠ざかる人の気配を見おくった。
もういちど、かっての恋人として彼女の前に立つ決意はかたまった。そのためにまず、ここにいたるまでの道のりを振りかえり、戻るべき方向の見当をつけなければ。
はやる気持ちをしずめ、枯枝で地面に十字の線をひいた。そして縦線を大通りに、横線を、久遠橋から交差点をへだてた店舗街につづく道にみたて、みずからの足取りをたどりはじめた。
人の輪を抜けて街路に出た直後、路面電車の軌道をまたいだ。橋から川下、つまり南の方角を望んだとき乗降場は左手に見えた。だから、僕はまず東詰めのたもとに向かって駆け出したことになる。そして電車通りを横ぎって対面の横丁に入り、市街地から遠ざかるようにジグザグに歩きつづけた結果、郊外の丘陵地にひろがるこの住宅地にいたった――そんな風に推察できる。だとすれば、途中どんな経路をとったにせよ、ここが電車通りより東に位置することはまちがいない。ひたすら西へ西へと歩けばいい。そうすればやがて南北の大通りにぶつかるだろう。
頭上をあおいだ。目立つ冬の星々と中空にかかる満月を見わたすうち、おおよその方角がつかめてきた。月明りでぼやけた夜空に眼をこらし、カシオペアを頼りに北極星をさがしあてた。そのまたたきを右手にたしかめながら、僕は公園の門を出た。
行く手の空ひくく、赤い光をはらんだ雲がたなびきはじめた。予想通り、街の中心に近づいているあかしだ。
とはいえ実際の道のりは、頭に描いたほど単純なものではなかった。迷路もどきの細路にはまりこみ、路地の奥で行きどまりにでくわしたりもした。幾度も堂々めぐりをしたあげく、やっと南北の大通りに行きあたったとき、重い疲労が僕の双肩にのしかかっていた。
交差点の標識が、久遠橋より三・四キロ南に下った町名を示していた。歩道橋を渡って四つ角を右に折れ、僕は通りを北にさかのぼった。無理に早足で歩むうち、ふたたび身体に熱がこもりはじめた。一刻も早くと願う心とはうらはらに、鉛の靴でも履いたように足の運びは鈍っていった。さらに悪いことに、ここまで治まっていた咳がぶりかえし、ついに呼吸すらままならない状態へと僕は追いこまれていた。
酸欠がめまいを呼び、路面がゆがんだ渦を巻いた。ふっと意識が遠のくたび、ヘッドライトの幻惑に身をあずけたくなった。それでも膝を折らなかったのは、左手に添う川の流れのおかげと言ってよかった。この水が静脈を通う血のようにふたりを結びつけている、そんな確信を杖に、僕はかろうじてわが身をささえつづけた。
やがて郊外にもどる車の流れも一段落したころ、彼方に久遠橋らしき影があらわれた。一歩ずつあきらかになる輪郭に力を得て、足どりも安定をとりもどした。だが近づけば近づくほど、橋はふだんと異なるきびしい貌を僕の眸につきつけてきた。
鋼のアーチは竜の鱗のようにかがやきながら反りかえり、石づくりの橋脚は、岸から投げられた光の束をつよく脚下に踏みつけていた。その挑みかかるような圧迫感に、つよく胸さわぎを掻きたてられた。
折しも、二艘の小型ボートが川をさかのぼってきた。すんなり僕を追いこすと、ともに船首をななめに振って対岸方向に進路を変えた。水泡が白い軌跡を描いた先にまたたく赤い灯を見出したとたん、極限までふくれた不安が肉体の疲労をしのいだ。
久遠橋では、下手の欄干にびっしり取りついた人が、投光器に照らされた水際を見おろしていた。右岸は白日のもとにあるように明るく、堤防一帯の状況がこの目ではっきりつかめた。川筋の道には警察のパトロールカーや消防の救助工作車がつらなり、そこから岸までの間をせわしなく人が行き来していた。
西のたもとへ橋を渡りつつ、ひとりひとりの背格好を横目でたしかめた。しかしあのひとらしき姿は見あたらない。せまい川縁の道も、堤防の胸壁ごしに眼下のなりゆきを見まもる群集で充ちていた。僕は野次馬よけのロープぎりぎりまですすみ、彼等の間に顔を割りこませた。
折りしも、警官や消防隊員が河原からひきあげてくるところだった。彼らは高水敷にあつまって、人の形に膨れた覆いをとりかこんだ。
「何があったんですか」だれにともなしに訊ねてみた。「身投げらしいですよ。若い女の」と、僕の横にいた男性がこたえた。
「若い女?」
「ほら、いつもあの橋に立ってる――」と彼が指をさしかけた時、警察のワゴン車が奥の辻から進入してきた。僕をふくむ見物人たちは、「どいた、どいた」という声にせかされて沿道にしりぞいた。
衆人注目の中、ワゴン車の後部座席から年老いた男性が降り立った。カッターシャツにカーディガン・セーターという部屋着のままのいでたちが突然の召喚をものがたっていた。
両脇を警官に支えられて護岸の石段をくだり、老人は先ほどの覆いのそばにつれていかれた。ぐったりと濡れた外套が彼の前にひろげられた。すると、セーターの肩先がぐらりと動いた。それは、あのひとが着ていたのと同じベージュのトレンチコートだった。追うちをかけるよう、衝立代りのシートの内側で懐中電灯の光がゆれた。老人の両膝が砂地に落ちた。
* * *
すべての野次馬が立ち去っても、はげしく咳きこみながら僕はその場所にとどまっていた。
担架に乗せられた遺体にすがり、泣きじゃくる老人の姿が瞳をはなれない。おそらく彼が、心病むあのひとをまもってきた唯一の身内なのだろう。
彼の役割は終わった。そのわずかな余生は無にひとしいものとなった。あの老人も、この夜に生きながらの死をむかえたのだ。
だがそんな彼でさえ、いまの自分にくらべれば若干の幸福にめぐまれている。彼はいまだいとおしい者に殉ずる権利を持っている。ともに暮らした部屋の中、愛孫のかたわらに横たわり、二度と明けない夜に身をゆだねることもできる。ひきかえ僕ときたら、すでに自分をこばむはずもない彼女に近よることさえゆるされず、ひとり夜気の底にのこされ途方にくれている。このへだたりは途方もなく大きい。
あの日のように風が吹く。流れる雲がひとつになる。枯葦がさわさわと呼び交わし、明滅する灯火をさざなみがむすぶ。いつかはほろびゆくさだめにあろうとも、万物はなにがしかの連鎖をもって時のながれに参画する可能性を有している。なのに、僕だけがそれらをむすぶ生成流転の環からはじきだされ、裸の蓑虫さながら、虚無の峪に宙づりとなっている。
ひとりでいることが怖い。足もとにひろがる淵の深さに目がくらむ。だれでもいい、僕を僕とみとめてこの声を聴いてほしい。だれか、だれか・・・・・・
地に両手をついてうずくまる。ふたたび咳がぶりかえす。「矢口、たすけて」みだれきった息の下、思わず友の名を口ばしっていた。
(六)へ続く
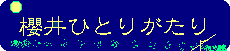
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 雑誌『映画秘宝 2025年 1月号』 冒頭…
- (2024-12-04 09:00:10)
-
© Rakuten Group, Inc.




