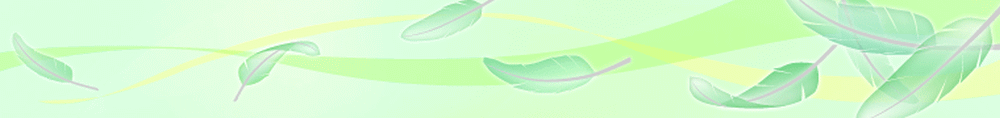最高の調味料
俺がルフィの船に乗り込んで、当然ながら毎日の食事は俺に一任された。
ナミさんを除いて、ロクに味なんてわかりっこない野郎共だが、とにかくえらい量を食いやがる。それでもまだ足りないのか、ルフィは隙を見てはつまみ食いをしようとする。
毎日がバラティエにいた時と変わりのない忙しさだった。あの時の別れを思い出す間もないぐらいに。
仲間になった中で、改めて観察をしていると面白い奴がいる。マリモ頭の剣士だ。
寝汚いし、レディに対するマナーもろくでもないが、食事の作法は悪くない。
隙あらば人の皿を狙うルフィをうまくかわしながら、食う様子は見苦しくない。というよりも、あんな見かけによらず、きれいな箸遣いで食っている。それに好き嫌いもなく、出されたものはきっちり平らげる。
ルフィに時々蹴りを入れながら、俺はゾロの食べっぷりをこっそり観察することが密かな楽しみになった。
そうしてしばらく観察を続けていると、ゾロのおかしな癖に気がついた。
いただきます、と言ってから必ず一度腹巻きに手を突っ込んでゴソゴソと探るのである。そして、はっとして手を抜き出して食べ始めるのだ。
時には俺の顔をちらっと見て、食事を始める。
表情からこいつが何を考えているのか、読み取れるほど俺の観察は進んじゃいねえ。
あの腹巻きに何を潜ませているのかもさっぱり検討もつかなかった。
ま、俺様の料理をどうこうするつもりなら、その場で制裁を加えてやるだけだしな。
何を考えているのかわからないゾロの観察は続くのだった。
ところが、ある晩のことだった。騒々しい夕食を終えて、片付けをしているとのっそりとゾロがキッチンに入ってきた。
「お、酒か?飲み過ぎるなよ」
皿を洗いながら、声をかける。
「ちげぇ。これをやろうと思ってよ」
振り返ってゾロを見ると、一升瓶をこっちに突き出してくる。黒い液体が入っている。
「これは醤油だ」
「ショウユ?」
ゾロの故郷でよく使われている調味料らしい。
俺は蓋を開けて、匂いと味を確かめた。さっそくこれを使ってどんな料理が出来るものかと頭の中を駆け巡る。
「これでうまいもんを作ってくれ」
「ああ…。今までなんで隠してた。こういうものはとっととよこせよ」
「そうだな…」
ゾロは頭をかいている。
こいつらしからぬ言い訳はこんなだった。
ゾロはルフィと出会う前から海賊狩りとして放浪していたわけだが、その頃から醤油を持ち歩いていたそうだ。
出されたものは何でも食うが信条の奴だが、それでも時には箸が止まっちまうような代物もあったらしい。
どんなものでも醤油をかければ、食える味になるんだ、とゾロは自慢げに言う。小さい頃からこの味には親しんできたし、お袋が作ってくれた飯は醤油の味が多かった、と。
そして、俺の作る料理にも気に食わなければ、醤油をかけようとしていたらしい。
腹巻きに仕込んでいたのは、醤油だったんだな。
俺が作る料理は怪しいかもしれないと思いつつ(失礼だ、とここで一発蹴りを入れてやった)、一口食べてから醤油をかけようとこらえていたみたいだ。
だが、食うもの食うものことごとくうまい。当たり前だ。俺が作ったんだからな。さらに醤油をかける必要なんかどこにもない。
毎日毎日出される料理は見た事のないものばかりだが、どれも外れがない。
このコックが作る料理には、醤油をかけてごまかすような味はないんだ。
自分が醤油を持ち歩く必要はないとやっと気づいたとゾロは言う。
「ばーか。やっと俺様の偉大さに気づいたか」
濡れた手をタオルで拭いて、ゾロの頭をポスポスと叩く。
ああ、よくわかった」
マリモがやけに素直に頷いたので、ちょっと焦る。
「お前が仲間になってくれて、本当に良かった」
「なんだ?素直すぎて気味が悪いな」
「これはお前に任せるから、うまい飯を頼む」
醤油瓶を手渡された。
頼むだって。仕方のない奴。
それから、事ある毎に俺は醤油を使って料理をしてやった。隠し味程度に使ってもゾロにはわかるようで、心なしか顔が弛んでいるのがわかる。それがわかるようになったのも日々の観察の賜物だ。
この上陸した島で、醤油を使った郷土料理がたくさん載っていた本を見つけた。アイツの誕生日のメニューは決定だ。
でも。
アイツはわかっていない。最高の調味料っていうのは、醤油じゃない。塩でもない。
食わせたい奴への愛情なんだぜ?
早く気づけよ。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 読書
- [楽天ブックス]「業界地図」 検索…
- (2025-11-20 02:18:48)
-
-
-

- 人生、生き方についてあれこれ
- 税金・地方交付税から行政法まで!国…
- (2025-11-19 09:04:40)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
© Rakuten Group, Inc.