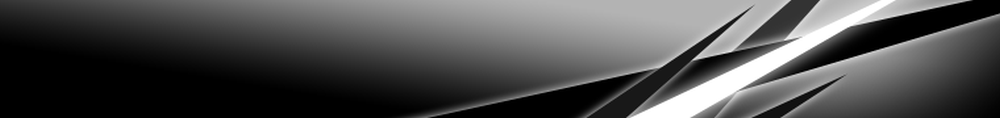第六話 大切な、事
特に緊急のアラートは無かったが、少しイザコザがあった。
今日の午前、ティアナがなのはに模擬戦で叩きのめされた。
彼女は独自の方法で特訓を重ねていた。
その為、本来伸ばすべきである射撃能力が疎かになってしまっていたのだ。
そこを多分なのはは怒ったんだと思う。
今は日も沈んだ夜。アラートが鳴り響く。
なのは、フェイト、智が出撃。前線メンバーとはシャーリーに呼ばれ、ヴィータとシオン、シグナムはそれについて行った。
第六話 たいせつなこと
―――六課隊舎ロビー
シャーリーがコンソールを叩く。
座っているのはエリオ、キャロ、スバル、ティアナ。
向かいにシャーリー、シャマル主任医務官、シグナム。
部屋の端でシオンとヴィータが立っていた。
「昔ね、1人の女の子が居たの」
シャーリーが口を開く。その言葉に前線メンバーが顔を上げる。
「その子は本当に普通の女の子で、魔法なんて知りもしなかったし、戦いなんてする様な子じゃなかった」
ロビーの画面に1人の少女が大写しになる。
茶色の髪の短いツインテール。恐らくなのはだろう。そんな面影がある。
(どうやって撮ってたんだよこんなの。犯罪スレスレだぜ全く)
シオンは心の中で呟く。
「友達と一緒に学校に通って、家族と一緒に、幸せに暮らして。そういう一生を送る筈の子だった」
「だけど、事件は起こったの」
シャーリーは続ける。
「魔法学校に通っていた訳でもなければ、特別なスキルがあった訳でもない」
「偶然の出会いで魔法を得て、ただ魔力が大きかっただけの、たった9歳の女の子が」
「魔法と出会ってから数ヶ月で、命懸けの実践を繰り返したの」
フェイトとなのはが戦っているシーンが映る。
「これ・・・」
エリオも解った様だ。
「フェイトさん・・・」
キャロも。恐らくスバルも、ティアナも。
「フェイトちゃんは当時、家庭環境が複雑でね。あるロストロギアを狙って、敵同士だったって訳」
シャマルが話す。
「この事件の中心人物は、テスタロッサの母・・・その名をとって、プレシア・テスタロッサ事件、或いはジュエルシード事件等と呼ばれる様になった」
シグナムがこの事件の名前について語る。妥当といえば妥当な事件名だ。
「収束砲!?こんな大きな!!」
エリオが絶句する。スクリーンに映ったのは、巨大な桜色の収束砲だった。
「9歳の・・・女の子が・・・」
スバルも口に出ていた。
「只でさえ、大威力砲撃は体に負担をかけるってのに。世界は、こうも腐ってる」
シオンは忌々しく言った。別になのはの実力を妬んでた訳じゃない。純粋な怒りだ。
争いを止めぬ人類への、怒り。
「そして、さほど時も措かず、戦いは続いた」
「私たちが深く関わった、闇の書事件」
シグナムとシャマルが交互に話す。
「襲撃戦での撃墜と敗北」
なのはがヴィータのハンマーで吹き飛ばされる所がスクリーンに映された。
「それに打ち勝つ為に選んだのは」
シグナムは目線をスクリーンからフォワード陣に移す。
「当時はまだ安全性が危うかった、カートリッジシステムの使用」
「体への負担を無視して、自身の限界を超えた出力を引き出すフルドライブ、エクセリオンモード」
4人が驚く。
「誰かを救う為、自分の想いを通す為の無茶を、なのはは続けた」
なのはやフェイト、智は現在戦っている様だ。シオンの端末にだけメールが来た。
「だが、そんな事を続けて、体に負担が生じない筈が無かった」
「事故が起きたのは、入局2年目の冬。異世界での調査任務の帰り。ヴィータちゃんや部隊の仲間達と一緒に出かけた場所に現れた未確認体」
シャマルが話し始める。
「いつものなのはちゃんなら、きっと何の問題も無く味方を守って、落とせる筈だった相手。だけど、溜まっていた疲労、続けてきた無茶が、なのはちゃんの動きを鈍らせたの」
そしてコンソールに手をかける。
「その結果が、これ」
スクリーンには上半身を包帯で巻かれ、顔には酸素マスクが付けられたなのは。
4人が絶句する。もちろんシオンも。
「なのはちゃん、『無茶して迷惑かけて御免なさい』って。私達の前では笑ってたけど」
「無茶をしてでも、命を懸けてでも譲れぬ場はある。だが、お前がミスショットをしたあの場面は、自分の仲間の安全や、命を賭けてでも、どうしても撃たなければならない状況だったか?」
シグナムがティアナに尋ねた。
「訓練中のあの技は、一体誰のための、何の為の技だ?」
ティアナは黙って俯く。
「なのはさん、皆にさ、自分と同じ想い、させたくないんだよ。だから、無茶なんてしなくてもいい様に、絶対皆が元気で帰って来られる様にって、本当に丁寧に、一生懸命考えて、教えてくれてるんだよ」
シャーリーが口を開く。
「んで、私達の事も解った所で、気になる所がある」
今まで口を閉ざしていたヴィータが、始めてこの時口を開いた。
アイゼンを展開し、シオンに歩いて行き、
シオンに、アイゼンを向けた。
「「「「「「「!!!???」」」」」」」
座っていた皆が立つほど驚いたらしい。
肝心の向けられたシオンは動じた様子も無い。
「答えろ。お前はどうして、シオン・ストリンドヴァリだと名乗る?」
「当たり前のことを訊くな。それは俺の名前が」
「お前の名前はミリアルド・ストリンドヴァリの筈だ」
「・・・」
シオンが黙る。
「黙ってないで答えろよ!!」
「・・・いいだろう。答えてやるさ。」
シオンはその紅い眼を閉じた。
「俺は4年前、俺はミッド地上部隊と新統合軍の間で起きた戦争に参加していた」
「そこで俺は右腕を斬られ、心臓を貫かれた」
「え?でもシオンさんは今・・・」
「この右腕は義手。心臓も動いてる。心臓が動いてるのは、『キュレイウウィルス』の所為だ」
「キュレイウィルス・・・?ちょっと待ってください・・・ウィルスアーカイブにありました」
キュレイウィルス: 感染者のDNAを書き換え、種の壁を越えて伝染する事は無いウィルス。
DNAを書き換えられた細胞はガン細胞のように増殖していくが、このキュレイウイルスはガン抑制遺伝子であるp53をも変異させて無力化させるため、増殖が阻害されない。
これによってDNAが書き換えられて誕生するキュレイ種は、体内でテロメラーゼと呼ばれる酵素を作り、無制限に細胞分裂を繰り返す事を可能とし、結果不老化する。
かといって無限に分裂を繰り返す細胞がガン細胞のように生命を脅かすような事はない。
いわば全身の細胞を「分裂回数を適切なレベルにコントロールできるガン細胞」へと変貌させるウイルスであると言える。
一般的に「キュレイウイルス」と言う場合「ヒト・キュレイウイルス」の事を指す。
感染する対象は純粋な人間「ヒト属サピエンス種」のみである。
変異体としてサルにしか感染しないものや、ネズミにしか感染しないものの存在も確認されている。
なお、基本的にウイルスというものは特定の種、特定の細胞にしか感染しないという特徴を有する。しかしキュレイウイルスの場合は当てはまらず、全身のあらゆる種類の細胞に感染する事が可能であるらしい。
しかしこれはあくまで一応可能であるというレベルでしかないのかもしれない。全身のDNAが書き換わった例は稀であるからである。無論、感染者自体が少ないのだからまだ断言はできない。
そしてキュレイに感染した人間の事を基本的に『キュレイ種』と呼んでいる。
特徴とした以下のようなものが挙げられる。
・テロメアの回復による不老化
体内でテロメラーゼという酵素を作り、テロメアを無限に回復させる事を可能とする。
・自然治癒力の増大によって不死に近くなる
怪我に関しては全治2ヶ月、元通りにに歩けるようになるまで更に数ヶ月を要するほどの重傷が1日で回復し、歩きまわれるようになってしまうほど。
これら自然治癒力の向上に関するメカニズムはまだ解明されていない。
新陳代謝が活性化され、細胞の分裂速度が異常に速まる事によって怪我や病気に対する快復力が著しく向上するのではないかと考えられている。
なお、代謝効率の著しい向上による副次的効果として運動能力の上昇もみられる。
「これの事ですよね?」
「そうだ」
シオンが頷く。
「じゃぁまさかシオン・・・その容姿が変わらないのは・・・」
ヴィータが絶句する。
「そうだ。俺はミリアルド・ストリンドヴァリ。だがミリアルドはあの時で戦死扱いだからな。現に死んだ。だからこうしてシオン・ストリンドヴァリとして生きている」
シオンは続けた。
「俺はキュレイのキャリアで・・・化け物だ」
そこに居た皆が何も言えなくなった。
だが、スバルが口を開いた。
「でもっ!!シオンさんは人間じゃないですか!!」
「見てくれはな。中身は完全な化け物さ。俺は類稀な『純粋種』なんだからな」
「でも・・・人の心は失ってません」
エリオが言った。
「だって・・・じゃなきゃ貴方は管理局に居ないでしょう?」
「ふん・・・違い無いな。確かに、俺は化け物だったら破壊を楽しんでるだろう。そこを考えれば、まだ俺は人間か」
シオンはその紅い目で鉄の壁に隔たれた天を仰ぎ見た。
―――六課隊舎屋上
なのは達の過去の話、シオンについての話から数十分後。
シオンは独り星降る夜空を見上げていた。
「・・・智か。お疲れさん」
「ちょっとドア開けただけなのに、凄いねシオンは」
「凄くなんかねぇよ。なのはなんかより全然だ」
ふと下を見ると、なのはの膝でティアナが泣いていた。
その少し離れた茂みでフォワード陣とシャーリーが見ていた。
「あいつはすげぇよ。俺なんかより、ずっとな」
「なのはちゃんか・・・凄いよね、彼女」
「ああ。俺達も早くハイパーゼクターを完成させなきゃな」
「そうだね。・・・ねぇ、僕は・・・ずっとこのままなのかな?」
「・・・それの事か。安心しな。いつか皆にも話せ。やむを得ず、お前は今の姿だ。ノロイは俺が斬れるから」
「・・・うん」
―――翌日
「技術が優れてて、華麗で優秀に戦える魔導師を、『エース』って呼ぶよね?その他にも、優秀な魔導師を表す言葉があるんだよ」
フォワード陣4人とフェイト、シオンが並んで歩く中、フェイトが話し始めた。
「その人が居れば、どんな状況も打破できる。どんな厳しい状況でも、突破できるそういう信頼を持って呼ばれる名前」
「『ストライカー』だな」
シオンが頭の後ろで手を組んで言った。
「ちょっとキメさせて欲しかったかな」
「ごめん」
「なのは、訓練始めて直ぐの時から言ってたよ。『うちの4人は絶対、優秀なストライカーになれるはずだ』って」
「すっげーなそれも。んじゃ、」
そう言って、右手の親指を立てて5人に向ける。
「昔の先生に教えられてな。ちょっとヘコんでた時に『地球っていう星の古代のローマという国で、満足できる、納得できる行動をした者にだけ与えられた仕草だ。お前もこれに相応しい男になれ』って、『笑顔のためにがんばれる男になれ。いつでも誰かの笑顔のためにが頑張れるって、すごく素敵なことだと思わないか。先生は、そう思う』って、言ってくれたんだ」
「凄いんですね、その先生」
ティアナが言った。
「ああ。尊敬してる先生だ」
そんな事を話しながら、6人は練習場を目指した。
To Be Continued...
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 楽天市場
- 【2μmm超微細なミスト・5重除菌】 目…
- (2025-11-21 11:56:06)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- 「ばけばけ」次週予告にネット沸く「…
- (2025-11-21 13:00:06)
-
-
-

- 株主優待コレクション
- 【株主優待】パンパシからのmagicaポ…
- (2025-11-21 12:09:22)
-
© Rakuten Group, Inc.