PR
X
とし坊の青春
としひでちゃんさん
ケンボーの中国アク… 在中日本人ケンボーさん
目指せ!マルチリン… まそまるさん
Cafe Ammonite シーアンモナイトさん
真真の中国滞在記 もっこひゃんさん
ケンボーの中国アク… 在中日本人ケンボーさん
目指せ!マルチリン… まそまるさん
Cafe Ammonite シーアンモナイトさん
真真の中国滞在記 もっこひゃんさん
Comments
2025.11
2025.10
2025.09
2025.10
2025.09
2025.08
2025.07
2025.07
Freepage List
カテゴリ: 日本社会
1588年秀吉の刀狩令がだされた。
中略
日照りの夏に用水を争う二つの村は、それぞれ近隣の村々に応援を求めた。すると、武庫川下流域の東側の村はすべて鳴尾村に、川の西側の村々は瓦林村に味方した。数多くの村々は、たがいに弓・鎧をそろえ、馬に乗って合戦を交え、あげくは、双方ともに数多くの死傷者を出した。刀狩り後の村にも、それだけの武器があり、戦いの体験も豊かに蓄えられていた。
この大がかりな「村の戦争」が、秀吉の知るところとなった。すべての村々から代表一人ずつが京都に呼び出され、秀吉奉行人による糺明のあげく、牢に入れられ、処刑された。鳴尾村からは十三人が、また反対側からは二六人が、それぞれ処刑されたという。
中略
なお、先に噂のあった身代わりの処刑については、意外な伝えが現地の村々に遺されていた。合戦に参加した六つの村では、それぞれ庄屋の身代わりに乞食をだした、という。いくつもの村が、村の犠牲に乞食を身代わりにしていた。もともと武装を日常とした中世の村は、予期される身代わりの犠牲として、ふだんから、村として乞食を養っていた。
藤木久志著「刀狩り」には、こんな物語が書かれている。
明治元年の次の年、1869年、特権のある百姓・町人の帯刀「一切廃止」令がだされる。
翌1870年には、太政官布告は、一般の百姓・町人の刀について「百姓・町人ども、襠・高袴・割羽織を着し、長脇差を帯し、士列に紛らわしき風体にて通行いたし候儀、相成らず候事」と規制していた。
戦国時代に刀狩りが行われた後も明治まで、かなり多くの百姓・町人が帯刀をしていた事を物語っている。
一般に現代日本の社会は、武士社会から発展してきたと考えられているようであるが、私は常々不思議であった。わずか人口の数パーセントであった武士社会が現代日本社会の原型となりえたのだろうか。全く武士社会が現代に影響を与えてないとは言い難いが、村人達の行動をみているとそこにはもっとはっきりと現代日本社会の原型を見ることができるように思う。
村人達は、鳥獣の狩猟、害獣の駆除、犯罪者との対決の為にも武装が必要であったようであるが、隣村との争い、戦争からの防衛という直接戦争の目的でも武装していた。時には、戦争をしている武将達から、敵の落人狩りを命じられる事もあったようである。その命令に反すれば、その武将の敵と見なされ、村が焼かれてしまう事もあったであろう。彼らにとっても、どの武将に味方するのかは、生存をかけた決定であったようである。
村人や一般民衆が強かったのかは、福島正則、加藤清正、石田三成が物語っているのではないだろうか。彼らは、秀吉の子飼いの武将達であり、姻戚関係にある者もいる。秀吉自らが半農半兵の出身であるのと同様に彼らもまた一般民衆の出身なのであった。
とはいっても残念ながら専門の戦闘集団として発達した武士や僧兵などにはかなわなかった。彼らは生き残る為には、いろいろな手段を講じたようである。
日本社会というのは、平和なときには大変いい面がでてくるが、困難に直面すると弱い者を生け贄にする社会構造ができているのではないかと不安になる。
このように日本の村々には、厳しく恐ろしい掟が存在する。それは、日本に限ったことではない。中国においても家族や友達などの親近者に対しては、不道徳な要求であろうともその要求の答えなければ、恐ろしい制裁がまっているという慣習が存在する。そしてその慣習が腐敗を助長してしまうのである。
団結すると言うことは、そのしわ寄せをどこかで吸収もしくは放出する必要があるのであろう。その吸収、放出の仕方によって、各社会の悪い面がでてきているように感じる。
ただ、日本社会と中国社会の大きな違いは、その管理体制にあるのではないか。中国社会は、皇帝を中心とした大きな Hierarchy を構成する。そして末端と中央をつなぐ管理体制は大変緩やかなようである。一方日本においては、武士社会が農村から発達してきたという面が有るせいか大変細やかである。各村々には、その村を支配する富農が存在し、その富農達と地方の豪族が結びつく。豪族達は集団で、武士集団を作り上げ、さらに権力争いで、トップの武士集団がきまるのである。トップが決まったからと言って、すべての村々を直轄するのではなく、武士集団をトップが管理しているにすぎない。260年ほど続いた江戸時代でさえ、この構成は変わっていないのである。
戦国時代の地図を見てみると、中国の管理体制との大きな違いがわかる。日本の国土面積の25倍、26倍とも言われる中国を一人の皇帝が統治するのと比べると壮大な違いである。
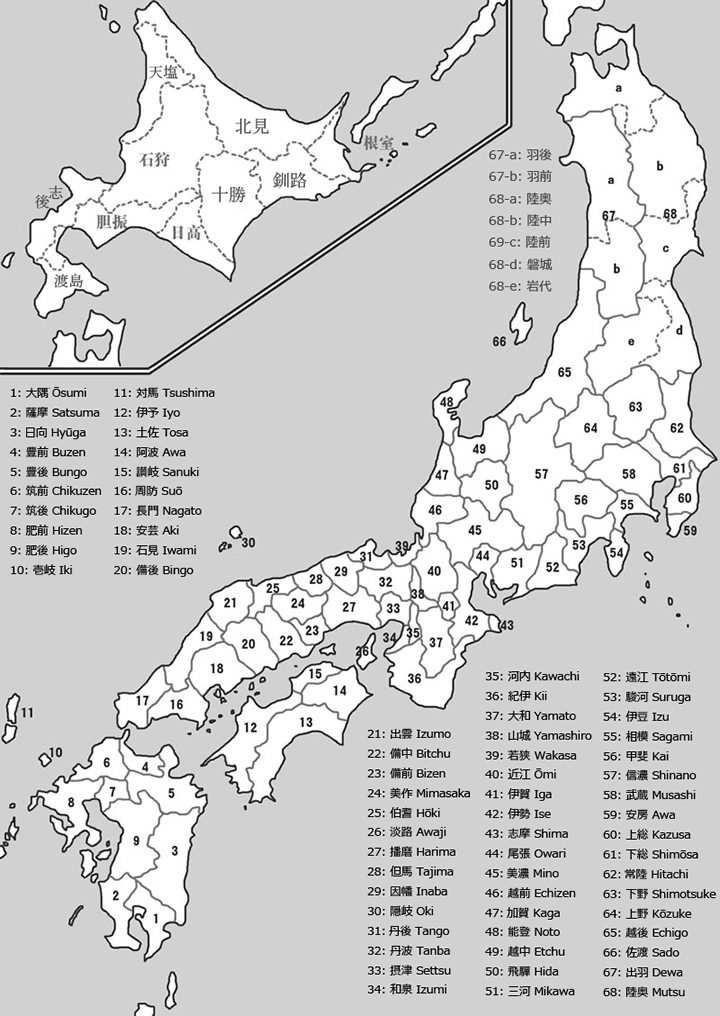
つづく
中略
日照りの夏に用水を争う二つの村は、それぞれ近隣の村々に応援を求めた。すると、武庫川下流域の東側の村はすべて鳴尾村に、川の西側の村々は瓦林村に味方した。数多くの村々は、たがいに弓・鎧をそろえ、馬に乗って合戦を交え、あげくは、双方ともに数多くの死傷者を出した。刀狩り後の村にも、それだけの武器があり、戦いの体験も豊かに蓄えられていた。
この大がかりな「村の戦争」が、秀吉の知るところとなった。すべての村々から代表一人ずつが京都に呼び出され、秀吉奉行人による糺明のあげく、牢に入れられ、処刑された。鳴尾村からは十三人が、また反対側からは二六人が、それぞれ処刑されたという。
中略
なお、先に噂のあった身代わりの処刑については、意外な伝えが現地の村々に遺されていた。合戦に参加した六つの村では、それぞれ庄屋の身代わりに乞食をだした、という。いくつもの村が、村の犠牲に乞食を身代わりにしていた。もともと武装を日常とした中世の村は、予期される身代わりの犠牲として、ふだんから、村として乞食を養っていた。
藤木久志著「刀狩り」には、こんな物語が書かれている。
明治元年の次の年、1869年、特権のある百姓・町人の帯刀「一切廃止」令がだされる。
翌1870年には、太政官布告は、一般の百姓・町人の刀について「百姓・町人ども、襠・高袴・割羽織を着し、長脇差を帯し、士列に紛らわしき風体にて通行いたし候儀、相成らず候事」と規制していた。
戦国時代に刀狩りが行われた後も明治まで、かなり多くの百姓・町人が帯刀をしていた事を物語っている。
一般に現代日本の社会は、武士社会から発展してきたと考えられているようであるが、私は常々不思議であった。わずか人口の数パーセントであった武士社会が現代日本社会の原型となりえたのだろうか。全く武士社会が現代に影響を与えてないとは言い難いが、村人達の行動をみているとそこにはもっとはっきりと現代日本社会の原型を見ることができるように思う。
村人達は、鳥獣の狩猟、害獣の駆除、犯罪者との対決の為にも武装が必要であったようであるが、隣村との争い、戦争からの防衛という直接戦争の目的でも武装していた。時には、戦争をしている武将達から、敵の落人狩りを命じられる事もあったようである。その命令に反すれば、その武将の敵と見なされ、村が焼かれてしまう事もあったであろう。彼らにとっても、どの武将に味方するのかは、生存をかけた決定であったようである。
村人や一般民衆が強かったのかは、福島正則、加藤清正、石田三成が物語っているのではないだろうか。彼らは、秀吉の子飼いの武将達であり、姻戚関係にある者もいる。秀吉自らが半農半兵の出身であるのと同様に彼らもまた一般民衆の出身なのであった。
とはいっても残念ながら専門の戦闘集団として発達した武士や僧兵などにはかなわなかった。彼らは生き残る為には、いろいろな手段を講じたようである。
日本社会というのは、平和なときには大変いい面がでてくるが、困難に直面すると弱い者を生け贄にする社会構造ができているのではないかと不安になる。
このように日本の村々には、厳しく恐ろしい掟が存在する。それは、日本に限ったことではない。中国においても家族や友達などの親近者に対しては、不道徳な要求であろうともその要求の答えなければ、恐ろしい制裁がまっているという慣習が存在する。そしてその慣習が腐敗を助長してしまうのである。
団結すると言うことは、そのしわ寄せをどこかで吸収もしくは放出する必要があるのであろう。その吸収、放出の仕方によって、各社会の悪い面がでてきているように感じる。
ただ、日本社会と中国社会の大きな違いは、その管理体制にあるのではないか。中国社会は、皇帝を中心とした大きな Hierarchy を構成する。そして末端と中央をつなぐ管理体制は大変緩やかなようである。一方日本においては、武士社会が農村から発達してきたという面が有るせいか大変細やかである。各村々には、その村を支配する富農が存在し、その富農達と地方の豪族が結びつく。豪族達は集団で、武士集団を作り上げ、さらに権力争いで、トップの武士集団がきまるのである。トップが決まったからと言って、すべての村々を直轄するのではなく、武士集団をトップが管理しているにすぎない。260年ほど続いた江戸時代でさえ、この構成は変わっていないのである。
戦国時代の地図を見てみると、中国の管理体制との大きな違いがわかる。日本の国土面積の25倍、26倍とも言われる中国を一人の皇帝が統治するのと比べると壮大な違いである。
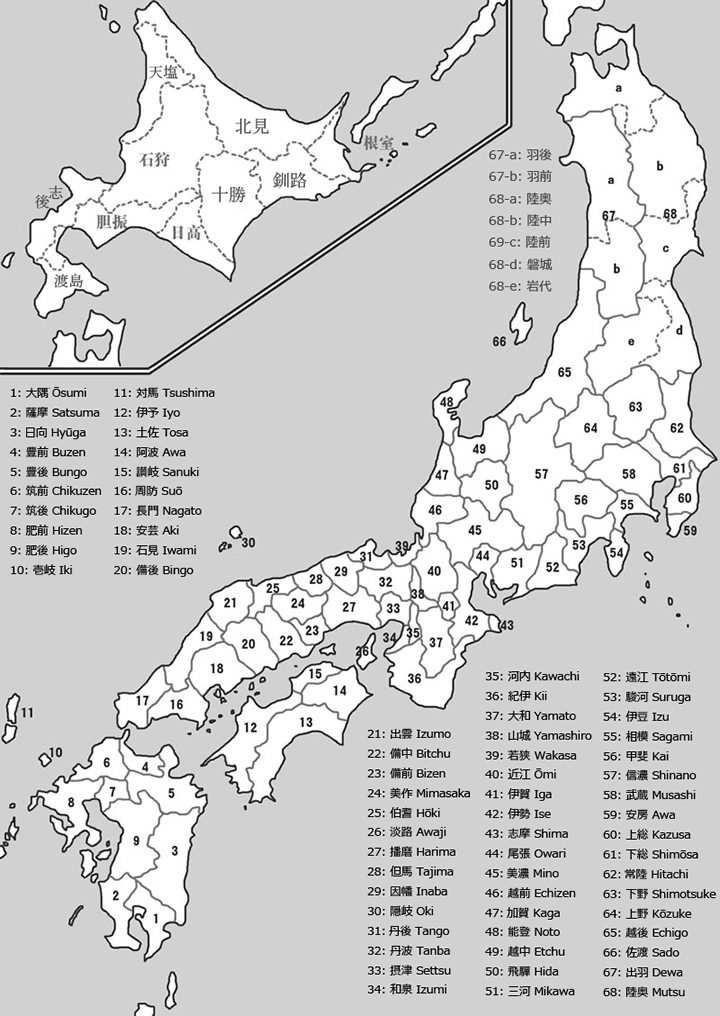
つづく
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[日本社会] カテゴリの最新記事
-
日本の近代化は、明治維新から始まったの… 2009.06.17 コメント(35)
-
マスクに見る日本人 2009.05.31
-
網野善彦著「東と西の語る日本の歴史」-真… 2009.05.29
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










