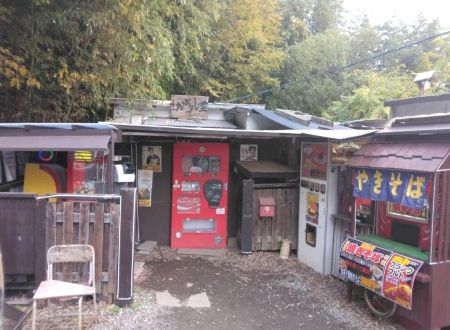自動巡回スパムブログでお困りの方へ
(2013.03.19)
HOME › 自動巡回スパムブログでお困りの方へブログのアクセス履歴に毎日のように足跡を残してくれる訪問者がいたとします。
あなたのブログを楽しみにしているブロガーであれば、何度足を運んでいただいても喜ばしいはずなのですが、ちょっとしたお礼のつもりでその訪問者のブログを訪れてみると、アフィリエイトリンクの嵐で、コンテンツらしいコンテンツすらない……。
そのような訪問者は、 自動巡回ツールを使ったアフィリエイトブロガー と思った方が良いかもしれません。
私自身は自動巡回ツールに興味はありませんし、そのツールを使っている人たちすべてを否定しているわけでもありません。 ブログを始めたからには、なるべく多くの人にコンテンツを読んでもらいたい、ランキング上位を目指したい、アフィリエイトのクリック数を増やしたい、など、自動巡回ツールを取り入れる理由は様々だと思います。
しかし、実際そのブログを訪れてみると、もう何か月もコンテンツが更新された形跡が見られない、アフィリエイトリンクだけでまともな文章が書かれていない、わけのわからない成人向け画像のオンパレードだったり…… そういったブログが連日のように一日に何度もあなたのブログに足跡を残し、しかもあなたのブログの内容など読んじゃいないとなったら、あなたはどのように感じますか?
私はそういった自動巡回ブロガーについて、このように思います。
コンテンツを何か月も何年も放置しているのなら、わざわざログインして他人のブログを巡回する必要もないはずです。
アクセス数、クリック数を稼ぐために一日に何度も自動巡回ツールを実行することで、他のブロガーに多大な迷惑がかかっているだけでなく、ブログのサーバ負荷が無駄に高くなりますので、サーバ運営側も迷惑を被ることになるのです。
こういった迷惑行為は規制されるべきです。
しかし、自動巡回スパムブロガーが来てくれることが、あなたにとってプラスに働く場合もあります。
考え方一つですが、もし、あなたのブログがそれなりに読み応えのあるコンテンツを抱えていて、定期的/頻繁に更新しているのなら、自動巡回スパムブロガーたちの迷惑行為を逆手に取ることができます。
自動巡回スパムブロガーはあなたのブログ更新のタイミングに集中しやすく、またその中でもヘビーユーザになると一日数回自動巡回ツールを実行してくれたりします。
そういうわけで、別にあなたが外部のブログランキングサイトに登録したり、積極的に宣伝活動をしたりしなくても、自動巡回スパムブロガーたちの意図しないところで、あなたのブログのランキングを自動的に上げてくれていたりするわけです。
嫌われようが批判されようが、そんなことは彼らにとっては重要ではないのです。 目的はただ一つ。アフィリエイト収入が得られればそれで良いのです。
つまり、 訪問者増加→アフィリエイトリンクのクリック数増加→アフィリエイト収入が得られてラッキー という流れができれば、彼らの目的そのものは達成される仕組み。
ですから、その流れをあなたのところで止めてしまえば良いわけです。
要は、ブログの運営を地道に続けながら、自動巡回ツール利用者の足跡リンクは極力クリックしないようにする。
それが彼らが一番イタいと感じるところではないでしょうか?
中にはニックネームを頻繁に変えることで、あたかも別人がアクセスしてきたかのように装う訪問者もいますが、URL をチェックすれば同一人物であることがわかりますので、URL をチェックする癖も付けておくと良いと思いと思います。
最後にもう一度申し上げます。
ただ、自動巡回スパムブログの足跡リンクは辿らないようにすればよいのです(意図的に無視)。
しかし、今までずっと我慢してきて、そういった自動巡回スパムブロガーの足跡を見るたびに血圧の上がる思いがする方は、楽天の方に機能改善要望を出したり、苦情申し立てしたりした方が精神衛生上良いかもしれません。
- 楽天ブログの要望、ご意見投稿フォームはこちら
- 規約について(【楽天ブログ】ヘルプより)
- ページの内容、著作権、ユーザー間トラブルについて報告をしたい(【楽天ブログ】ヘルプより)
- ツール利用による連続アクセスについて(楽天スタッフブログ 2005年06月24日の記事)
- スパムアクセスブロックのお知らせ(楽天スタッフブログ 2006年09月01日の記事)
本ページの内容について賛同いただける方、ご意見がおありの方は、以下の記事よりコメント、 トラックバックが可能です
*(その際は関連する内容でお願いします)。
* 楽天ブログのトラックバック受付機能は、2011年4月19日を以て終了しました( 楽天ブログサービス公式ブログの発表はこちら )。
【自動巡回スパム撲滅バナー】
自動巡回スパムブログによる被害で悩んでいらっしゃる方で、ちょっとしたバナーのようなもので訪問者に注意を喚起したいという方は、ご自由にお持ち帰りください。
ただし、このバナーに直リンクはせず、画像を保存してお持ち帰りください。
使用に際して連絡は不要です。 楽天ブログ以外の方も、一般サイト管理者の方もご自由にどうぞ。
![]() ↑ 自作バナーですのでデザインが残念な所はどうかご容赦ください。
↑ 自作バナーですのでデザインが残念な所はどうかご容赦ください。
カルガモ君
様に素敵なバナーを作成していただきました。(2011.03.06)
ありがとうございます。
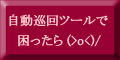
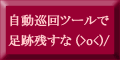
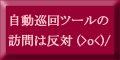
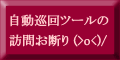
本ページはリンク自由です: http://plaza.rakuten.co.jp/shophunter/004000
本ページの文章はご自由に引用していただいても構いません。
引用、一部流用は許可しますが、本ページに酷似した文章を書いて、著作権を主張するのだけはどうか御遠慮ください。