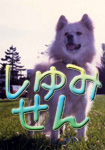PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
カテゴリ未分類
(7697)ウチのいぬとねこのこと
(27)動物病院で思うこと関連
(5)TVドラマ(大河・時代劇・現代劇)
(51)新選組や幕末のこと
(12)歴史で気になること
(7)小説のこと(読書感想ほか)
(30)フィギュアスケートand五輪
(136)しごとのこと
(69)オチているとき
(64)妙なメール(笑)
(10)カレンダー
火野さんに郷土を教…
New!
いちろん92さん
絵本「いのちをいた… New!
みらい0614さん
New!
みらい0614さん
記憶にない作品 ちぇちぇこりんたさん
ちぇちぇこりんたさん
飛ぶように売れる製… 鍛冶屋の息子さん
アフィリエイト・プ… 藍玉.さん
絵本「いのちをいた…
 New!
みらい0614さん
New!
みらい0614さん記憶にない作品
 ちぇちぇこりんたさん
ちぇちぇこりんたさん飛ぶように売れる製… 鍛冶屋の息子さん
アフィリエイト・プ… 藍玉.さん
コメント新着
テーマ: 本のある暮らし(3320)
カテゴリ: 小説のこと(読書感想ほか)
他人を見下す若者たち
(講談社現代新書 著者:速水敏彦)
っていう本を読んでいます。帯には 「自分以外はバカ」の時代
とあります。
でも、中身は、 若者に限らず ってことだと思います。
タイトルに惑わされずに読みたいと思います。
・・・と書いてから数日経過。
ようやく読み終わりまして^^;
やっとこ何か書こうかなってとこです。
予告なんかするもんじゃありませんね~
「他人を見下す若者たち」というなかなか刺激的なタイトルと、帯の漫画「The3名様」からは想像できないくらい真面目な本です。心理学的な側面から実験したり検証したりしている結構本格的な内容なので、同じ新書でも、養老さんなんかの本のようにエッセイっぽいものではなく、スイスイ読める内容ではないと思います。
現代の日本社会は、「誰もが「オンリーワン」の気分を持ちやす」く、「オンリーワンというのは(略)比較対象がないことで(略)誰もが自分を並み以上と持ちやすい」
小中学校などで、成績以外の多方面からの評価を下されることで、客観的な判断を下されることが減って、逆に長所が見つけにくい点もあるようだ。
その結果、どちらかというとネガティブで自己卑下的・自己批判的だった日本人が、だんだんポジティブな自己肯定感を持つようになってきている・・・ということでいいのかな(オイオイ)
若い人の自己愛が高いのは自然ではあり、そうでなくてはならない部分もあるのだが、現代はその傾向が強く誇大的になっているという。
自分を客観しできないのは、たとえば受験の場合、自分の学力とかなりかけ離れた学校を志願することが増えていて、「甘い将来像を描きやす」く、高校中退者にもその傾向が見られる。
筆者は前半で、「現代は誰もがこぞって 自己肯定感 を求める時代」であることを例を上げて説明し、「その自己肯定感の中には特に 他者軽視 を通して生じる 偽りのプライド 」に着目して、「 仮想的有能感 」と名づけて後半を展開していく。自己愛との違いは、自己愛は「自己評価の形で生じる」のに対し、仮想的有能感の場合「他者評価の仕方を通して生じる」点にあるようだ。この場合の「他者」とは「情報が希薄な」赤の他人で、自分勝手に自分より下にみなすことができる「大衆」であると言ってもよい。
つまり、小さな失敗をした人を見て「何やってんだよこのバカ」とチラッとでも思う度合い=仮想的有能感ということ・・・と私は受け取ったがどうかな^^;
で、若者がはこの仮想的有能感を持ちやすくなっている理由として
1.コンピュータや携帯・デジカメ等を自由に操作できること ・・・・・・自分でできるのは操作だけであって、出来上がるものはコンピュータの性能に負うところが大きいにも関わらず、自分自身が有能になったような感じを持ちやすい。
2.マスメディアの発達 ・・・・・・世界の情報が瞬時に入るため、できなかった人に比べると世界そのものが手中にあると錯覚しやすい。また、マスコミが伝えるものについては、当事者ではないため、誰もが観察者・解説者の気分になれ、上から物を見下ろしている感覚になる。
3.個人主義が先鋭化し、人間関係が希薄化。相手の力量を直接関わらずに判断しようとする。・・・・・・特に他者の優れた部分についてはあまり意識しないようになっている。
4.人を軽く扱う風潮・・・・・・テレビのお笑い番組など。他者の欠点を笑うものが増え、視聴者の受けを狙うマスコミはこぞって相手を丸裸にし、特に欠点をクローズアップする。(また、そういうものが受けるのも問題だと思うが^^;)
等と分析している。
この仮想的有能感、若い世代も高いが、中高年も高い傾向があるのがミソである。
「他者軽視に基づく仮想的有能感の高い人たちは自分自身に関係する出来事には注意の度合いや覚醒の度合いが高いが、 自分に無関係なことにはそれが低い 」
そして、現代の若者は、自分自身に関することにはすぐに怒ったりするが、社会的な問題=直接自分に関わってくる度合いが低いものに関してはきわめておとなしいことにもふれる。
仮想的有能感を持つ人は本質的に自己中心的で、自分のことには関心が高いが他人のことには薄い。「悲しみ」を共感することができない。
そのため、某「贈ることば」の歌詞「人はかなしみが多いほど人には優しくできる」ような悲しみは、なかなか見つからない。
また、仮想的有能感の高い人は多くの苦労をしてまで努力目標を達成するとは思えず、障害に当たると怒りを爆発させてしまい、失敗を正当化して別の目標に移行させてしまうので、ひょっとしたら喜びの量も減っているのかもしれない、なんていうことも書いている。
終章で印象的だった部分抜粋
「現在、多くの人たちが、この厳しい世の中で自分だけが犠牲者で、ストレスを多分に受けていると思い込んでいる。家族ですらも母は娘に「あなたがまじめに勉強しないから、私はストレスがたまって食事も十分にできない」と嘆く。娘は娘で「お母さんがあまりうるさいからストレスがきつくて下痢が続き、勉強どころではないといってキレる。上司は、いたらない部下のせいで自分がこんなにストレスに苦しめられていると思っており、部下は、上司がもう少しマシだったら、俺たちの仕事のストレスは半減すると考えている。
ストレスということばが広まってから、ほとんどの人は、自分が他者にストレスを与えたなどとは考えず、自分だけがストレスを被っていると考えるようになった 。これらもおそらく、人々が心の深層に仮想的有能感を抱いているためであるように思われる」
仮想的有能感から脱却するための方策も書いてあるけど、種明かしはしないことにしよう。
要は、「 謙虚になろうよ 」ってことじゃないのかな。
(・・・あっ、仮想的有能感・高!?(爆))
でも、中身は、 若者に限らず ってことだと思います。
タイトルに惑わされずに読みたいと思います。
・・・と書いてから数日経過。
ようやく読み終わりまして^^;
やっとこ何か書こうかなってとこです。
予告なんかするもんじゃありませんね~
「他人を見下す若者たち」というなかなか刺激的なタイトルと、帯の漫画「The3名様」からは想像できないくらい真面目な本です。心理学的な側面から実験したり検証したりしている結構本格的な内容なので、同じ新書でも、養老さんなんかの本のようにエッセイっぽいものではなく、スイスイ読める内容ではないと思います。
現代の日本社会は、「誰もが「オンリーワン」の気分を持ちやす」く、「オンリーワンというのは(略)比較対象がないことで(略)誰もが自分を並み以上と持ちやすい」
小中学校などで、成績以外の多方面からの評価を下されることで、客観的な判断を下されることが減って、逆に長所が見つけにくい点もあるようだ。
その結果、どちらかというとネガティブで自己卑下的・自己批判的だった日本人が、だんだんポジティブな自己肯定感を持つようになってきている・・・ということでいいのかな(オイオイ)
若い人の自己愛が高いのは自然ではあり、そうでなくてはならない部分もあるのだが、現代はその傾向が強く誇大的になっているという。
自分を客観しできないのは、たとえば受験の場合、自分の学力とかなりかけ離れた学校を志願することが増えていて、「甘い将来像を描きやす」く、高校中退者にもその傾向が見られる。
筆者は前半で、「現代は誰もがこぞって 自己肯定感 を求める時代」であることを例を上げて説明し、「その自己肯定感の中には特に 他者軽視 を通して生じる 偽りのプライド 」に着目して、「 仮想的有能感 」と名づけて後半を展開していく。自己愛との違いは、自己愛は「自己評価の形で生じる」のに対し、仮想的有能感の場合「他者評価の仕方を通して生じる」点にあるようだ。この場合の「他者」とは「情報が希薄な」赤の他人で、自分勝手に自分より下にみなすことができる「大衆」であると言ってもよい。
つまり、小さな失敗をした人を見て「何やってんだよこのバカ」とチラッとでも思う度合い=仮想的有能感ということ・・・と私は受け取ったがどうかな^^;
で、若者がはこの仮想的有能感を持ちやすくなっている理由として
1.コンピュータや携帯・デジカメ等を自由に操作できること ・・・・・・自分でできるのは操作だけであって、出来上がるものはコンピュータの性能に負うところが大きいにも関わらず、自分自身が有能になったような感じを持ちやすい。
2.マスメディアの発達 ・・・・・・世界の情報が瞬時に入るため、できなかった人に比べると世界そのものが手中にあると錯覚しやすい。また、マスコミが伝えるものについては、当事者ではないため、誰もが観察者・解説者の気分になれ、上から物を見下ろしている感覚になる。
3.個人主義が先鋭化し、人間関係が希薄化。相手の力量を直接関わらずに判断しようとする。・・・・・・特に他者の優れた部分についてはあまり意識しないようになっている。
4.人を軽く扱う風潮・・・・・・テレビのお笑い番組など。他者の欠点を笑うものが増え、視聴者の受けを狙うマスコミはこぞって相手を丸裸にし、特に欠点をクローズアップする。(また、そういうものが受けるのも問題だと思うが^^;)
等と分析している。
この仮想的有能感、若い世代も高いが、中高年も高い傾向があるのがミソである。
「他者軽視に基づく仮想的有能感の高い人たちは自分自身に関係する出来事には注意の度合いや覚醒の度合いが高いが、 自分に無関係なことにはそれが低い 」
そして、現代の若者は、自分自身に関することにはすぐに怒ったりするが、社会的な問題=直接自分に関わってくる度合いが低いものに関してはきわめておとなしいことにもふれる。
仮想的有能感を持つ人は本質的に自己中心的で、自分のことには関心が高いが他人のことには薄い。「悲しみ」を共感することができない。
そのため、某「贈ることば」の歌詞「人はかなしみが多いほど人には優しくできる」ような悲しみは、なかなか見つからない。
また、仮想的有能感の高い人は多くの苦労をしてまで努力目標を達成するとは思えず、障害に当たると怒りを爆発させてしまい、失敗を正当化して別の目標に移行させてしまうので、ひょっとしたら喜びの量も減っているのかもしれない、なんていうことも書いている。
終章で印象的だった部分抜粋
「現在、多くの人たちが、この厳しい世の中で自分だけが犠牲者で、ストレスを多分に受けていると思い込んでいる。家族ですらも母は娘に「あなたがまじめに勉強しないから、私はストレスがたまって食事も十分にできない」と嘆く。娘は娘で「お母さんがあまりうるさいからストレスがきつくて下痢が続き、勉強どころではないといってキレる。上司は、いたらない部下のせいで自分がこんなにストレスに苦しめられていると思っており、部下は、上司がもう少しマシだったら、俺たちの仕事のストレスは半減すると考えている。
ストレスということばが広まってから、ほとんどの人は、自分が他者にストレスを与えたなどとは考えず、自分だけがストレスを被っていると考えるようになった 。これらもおそらく、人々が心の深層に仮想的有能感を抱いているためであるように思われる」
仮想的有能感から脱却するための方策も書いてあるけど、種明かしはしないことにしよう。
要は、「 謙虚になろうよ 」ってことじゃないのかな。
(・・・あっ、仮想的有能感・高!?(爆))

ガラス デジタルスケール
スクエア/ダイエット体重計
健康器具 ダイエット
5,800円 (税込6,090円)

草木染めTシャツ
4,000円 (税込)

【ULSTER WEAVERS】
Printed PU Floor Mats
(フロアマット)
Cats in Waiting
可愛いニャンコ柄
3,900円 (送料税込4,095円)

ナチュラルナース
キャットフード2.5キロ
【送料無料】
5,800円 (送料税込6,090円)

【SAVOY】サボイ☆
デニム地の定番型
チェック柄トートバッグ♪
3,465円 (税込)

SNOW カードブック
4,500円 (税込4,725円)
★ 介助犬を
応援する方法 ★
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[小説のこと(読書感想ほか)] カテゴリの最新記事
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.