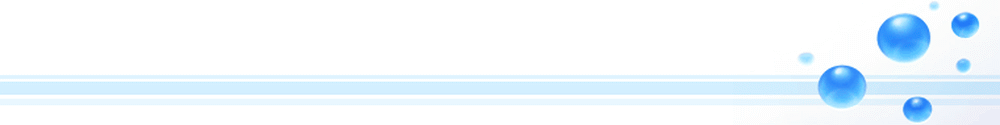NARUTO 14~16
リクエスト小説 サスケ奪回編後、付き合い始めたシカマルとテマリの初デート物語です。(シカテマ・ほのぼの)
『いつか木ノ葉の里へ』(NARUTO14)
「その……木ノ葉の……、お前の里を、見てみたいんだ」
始まりは、その一言だった。サスケ奪回任務後、間もなく付き合い始めたシカマルとテマリ。けれどテマリが砂隠れの里へ帰ってからお互い任務が忙しく、一ヶ月もたった今日やっと会うことが出来た。それぞれ任務の帰り仲間と別れ、森の中で二人きり。
テマリの言葉に、シカマルはすぐにそれがデートの誘いだということを察知した。そして二人の休日が一致した三日後に約束をして別れた。
その夜シカマルは、ベッドで天井をじっと見つめ考えていた。
「あー……、わかんねー……」
IQ200のシカマルの頭を持ってしても、生まれて初めてのデート。女の子が喜ぶデートスポットなんてまるで分からなかった。けれど男として、自分が完璧にリードすることだけは心に決めていた。そこで翌日任務中いのに聞いたり、情報雑誌『木ノ葉Walker』を購入したりして、おしゃれな場所やおいしいお店などを研究した。そしてスケジュール調整を完璧に整え、よそ行きの服――緑のチェック柄シャツにアイロンをかけた。めんどくさがりのシカマルとしては異例の行為である。けれどシカマルは、まるでサスケ奪回任務のときのごとく真剣だった。
ついにデートの日。朝早くから木ノ葉の門で待ち受けていたシカマルのもとに、テマリはあらわれた。
「お前、なぜいつもと服装が違う」
テマリは会うなりいぶかしげな顔でシカマルの姿を見つめた。対するテマリは、いつもと変わらぬ服装である。唯一違うところといえば、大きめの籠バックを持っていることくらいだ。
「なんでってそりゃ……ってかお前こそなんで任務そのままの格好なんだよ」
いつもの扇まで背負っているテマリに、シカマルはしかめっ面で聞いた。言葉とはうらはらに、一人わざわざよそ行きの服を着てきた自分が少し恥ずかしくなったシカマルである。
とにもかくにも、二人の初デートは始まった。
朝日が降り注ぐオープンカフェで、二人はコーヒーを飲んでいた。この店は例の『木ノ葉Walker』に掲載されていた「女の子が喜ぶおしゃれカフェ」特集でナンバーワンなのである。そこでシカマルはブラックコーヒーを、テマリは砂糖にミルクを入れて飲んでいた。通りにだんだん人が増えていく中、シカマルは妙に落ち着かなかったが、平静を装いテマリにたずねた。
「サンドウィッチとかも食うか?」
「いや、朝食は家ですませてきた」
テマリは、そっけなく答える。全く喜んでいる様子のないテマリに、シカマルは『木ノ葉Walker』の情報に疑問を感じた。そして気が付けばテマリが既に飲み終わっているのに気付き、シカマルもあわてて苦いコーヒーを一気飲みすると、気を取り直して次の場所へテマリを誘った。
そこは、木ノ葉遊園地だった。いのに勧められたとき、シカマルはジェットコースターにでも乗ればいいと思っていたのだが、そうではなくメリーゴーラウンドが良いとのことらしい。なんでも、女はロマンチックなものに弱いのだそうだ。そして馬に二人乗りというのがベストだそうだが、テマリとの身長差を考えるとさすがに恥ずかしく、シカマルはテマリを連れて馬車にのった。向かい合って座り、素敵な音楽とともにメリーゴーラウンドはまわり始める。テマリは足を組んで、シカマルを見ている。
「おい、天井とか見てみろよ。ありがたそーな天使の絵とかが描いてあんぞ」
テマリは黙って見上げたが、特に興味もなさそうだった。シカマルは、手すりにひじをつきそんなテマリを見ながら、いののヤツ……と不機嫌になっていた。
三度目の正直! という言葉を信じ、シカマルは遊園地を早々に後にし、テマリと共に予約していた店へ入った。そこは他国の料理を扱う店で、白い布がかかったテーブルにナイフやフォークがずらりと並べられている。
「コース料理だぜ。ありがたく食えよ」
運ばれてきたスープを目の前に、シカマルはぶっきらぼうに言った。そして一口すする。なかなかこった味ではある、とシカマルは思い、同じくスープを口にしたテマリにたずねた。
「うまいか?」
「ああ……」
言葉とは裏腹に、相変わらずなテマリ。いや、不機嫌そうにさえ感じるテマリにシカマルはさすがに焦りを覚えた。だが、いくら考えても原因が分からない。シカマルはIQ200の頭脳をフル活動させて考えながら、コース料理をもくもくと食べていた。
「……シカマル」
「……」
「おい……シカマル!」
考え込んでいたシカマルは、二回目のテマリの呼びかけにやっと我に返った。テマリは、シカマルを睨むように見ていた。
「……何だよ」
「お前は……おいしいのか?」
「はぁ?」
シカマルは、突然のテマリの発言にとまどった。
「遊園地でメリーなんとかに乗るのが好きなのか? いつもカフェでコーヒー飲んだりしているのか?」
「……オレがそんなことするわけねーだろ。オープンカフェなんてこっぱずかしーとこ誰が行くかってーの。遊園地なんてガキの頃行ったきりだし、コース料理なんてのもオレは好みじゃねー」
シカマルのだるそうな言い方に、テマリはダンッと両手をテーブルについて立ち上がった。
「ならお前は……お前は自分が楽しくもないところに私を案内したというのか!?」
客が注目するのも気にせず、テマリは怒鳴った。シカマルはカチンと来て同じように両手をバンとテーブルにつき立ち上がる。
「オレの好みなんかどーだっていいだろ! オレはせっかくお前が喜ぶように一生けんめー調べたり聞いたり――」
シカマルは途中ではっと口をつぐんだ。そしてテマリから目を背け、顔を赤くする。
「……すまない、シカマル」
シカマルの上から、テマリの声がふってきた。その言葉が本当にすまなそうだったので、シカマルは顔をあげてテマリを見た。テマリは力無く、すとんと椅子に座った。
「私は……ただ……、その……、お前が里でどんなふうに過ごしているのか……知りたかっただけなんだ……」
テマリはシカマルよりさらに顔を赤くして、うつむいた。シカマルはそんなテマリに心臓をバクバクさせていたが、テマリの言葉を完全に理解すると、ふと肩の荷が下りた。
「なんだ……。そーか。……早く言えってーの」
最後の言葉は精一杯の強がりだったが、シカマルは自分が一人からまわりしていたことに恥ずかしさを覚えていた。
「分かった。けど、これだけは食えよな。もったいねーから」
二人は食べ終えると、店を後にした。
「悪ぃ、待たせたな」
奈良家の近くで待っていたテマリに、シカマルは小走りにかけてきた。その姿は、いつもの中忍ベストの格好である。
「オレも一応忍者だからな。休日ったって普段はこの格好だ。んじゃ行くぞ」
シカマルがテマリを案内したのは、どこまでも広い野原だった。
「オレが休日過ごす場所っつったら、ここくらいだぜ。ほとんど一日中な」
シカマルは原っぱに寝転がった。
「オレぁ、ここで雲を眺めんのが大好きなんだ。ぼーっとして、何も考えないで過ごすのが至福のひとときだな」
実は最近は、その至福の一時でさえテマリのことで頭がいっぱいなシカマルなのであった。それがまた、シカマルにとっては以前とは違う意味で心地よい時間なのである。
「おい、お前も寝っ転がれよ」
「あ、ああ……」
テマリは、シカマルの横にそっと体を横たえた。テマリの目に、青い空がどこまでも広がった。白い雲が、ゆったりと浮かんでいる。テマリは、初めて穏やかに笑った。
シカマルは、もう雲なんか見ていなかった。青空の下、太陽に輝く緑の草に包まれたテマリ……。シカマルはテマリをあまりにも愛おしく感じた。シカマルは、黙ってそっとテマリの手をにぎった。初めてつながれた手に、テマリは空を見たまま驚いていたが、やがて頬を赤くしてシカマルの手を握り返した。
二人は手をつないだまま、しばらく空を眺めていた。お互いの心臓の鼓動を、心地よく重ね合わせながら……。
「あーのど乾いたな」
シカマルはポーチから竹筒を出そうとしたが、テマリは遮った。
「お茶でよければ、持ってきている」
テマリは、籠バックから保温機能の付いた水筒を取り出した。シカマルはそのとき、籠バックに二つのお弁当が入っているのが見えてしまった。
「おい、その弁当……」
「気にするな。お前が店を予約しているとも知らず、勝手に作ってきた私が馬鹿だったんだ」
テマリは恥ずかしそうに頬を赤らめながら、熱いお茶をついでいた。
「……食わせろよ、それ」
シカマルは、ぼそりと言った。
「気を遣うな。さっき食べたばかりだろ」
「いーから……食わせろ。……つーか、食いてー……」
シカマルはそっぽをむいたまま、顔を赤くして手をテマリに突きだした。
「……ばか」
テマリは、同じく顔を赤くしながら、布で包まれた弁当をシカマルの手にそっとのせた。弁当の中身は、ご飯に煮物にウインナーに卵焼きに……とても家庭的なものだった。そんな彼女の一面を初めて見たシカマルは、驚きつつも一口食べる。とてもあたたかみがある味だった。
「……うめぇ」
シカマルは、めずらしく食べるのに集中している。
「少しにしておけ。お腹こわすぞ。ほら、お茶も飲め」
テマリに渡されたカップの熱いお茶を、シカマルは飲んだ。
「ふぅ。やっぱ茶が一番だぜ。コーヒーなんて、オレには柄でもねー」
「そうだと思った。お前がブラックコーヒー苦そうに飲んでたの、ばればれだったぞ」
「余計なこと言うなっつーの」
苦笑いするシカマルに、テマリはニシっと笑った。
夕方、シカマルたちは小さな公園へ足を運んだ。誰もいない公園のベンチに、二人は並んで座る。
「オレがガキの頃よく遊んだ場所だ。最近はあちこちに遊び場が出来たから、ここはさびれちまってよ。静かで邪魔がはいんねーから、今でもたまにこのベンチでぼーっとしてる」
「そうか……」
辺りは、真っ赤な夕日に包まれていた。口には出さなかったが、このベンチの正面から西日があたり、公園いっぱいがその赤い光で満たされるのが、シカマルは好きだった。
「シカマル……今日はありがとうな」
恥ずかしそうに笑うテマリにシカマルも笑い返したが、ふとシカマルは真面目な表情になった。
「なぁテマリ……。木ノ葉の里、気に入ったか?」
「ああ……」
しみじみと答えるテマリをシカマルはしばらく見ていたが……やがて言った。
「じゃー、……そのうち住んでみるか?」
シカマルは、赤い夕日を見つめたまま言った。テマリは夕日のせいか顔が真っ赤なシカマルを見つめていたが、やがて答えた。
「ああ」
シカマルとテマリの目が合ったその瞬間――シカマルはテマリの肩に手を置き、そっとくちづけをした。
その数秒後、シカマルは何かにはっと気付くと、急いで立ち上がった。
「じゃ、またな。テマリ」
「えっ? 門まで送ってくれるとさっき……」
「だいじょうぶだ。代わりに迎えが来てる。あいつに悪ぃとこ見せちまったぜ。……木ノ葉にくるのは、お前の役目が終わってからでいーから。じゃーな」
シカマルは小声でささやくと、去っていった。テマリはそんなシカマルを不思議そうに見ていたが、ふと人影に気付く。公園の隅にある木の陰から出てきたのは、我愛羅だった。
「我愛羅……お前どうしてここに……」
テマリは顔を赤らめながら、弟にたずねた。シカマルと同い年の我愛羅がやけに子供に見えるのは、身長のせいではなく、彼氏と弟という関係の違いのせいだろう。テマリにとってシカマルが守ってくれる存在なら、我愛羅は逆に守るべき存在である。
「任務帰りだ。お前が木ノ葉に行くというから、迎えに来た」
「そうか。ありがとうな」
テマリは笑ったが、我愛羅は黙って姉を見つめていた。夕日のせいか、我愛羅の表情は何故か不安定で、いつもの殺伐とした感じではなく……どこかさみしそうだった。
「どうした、我愛羅……」
「木ノ葉へ……行くのか?」
じっとテマリを見つめる我愛羅の目は、夕日の反射でゆらいでいる。
「まだ先の話だ。今はやらなければならないことがある。例えば、任務を終えた可愛い弟に弁当を食べさせてやることとかな」
テマリは我愛羅とベンチへ座ると、昼間食べ損ねた自分用の弁当を我愛羅に渡した。我愛羅は黙って食べ始めたが、その表情はどこかほっとしているようだった。この子にもうさみしい思いはさせたくない。テマリは心からそう思った。
シカマル……お前の言うとおり、今の私には大切な役目がある。けれど、いつかきっと……。
テマリは、夕焼け色に染まる空を見上げた。
☆あとがき☆
哀鈴様からのリクエスト小説です。
管理人 初!のシカテマ小説です。シカマルを書けるようになるのさえ長い道のりがかかった管理人……シカテマが書けるようになるまでも相当の時間を要しました(というか、なんか書けてないような・汗)
ほのぼのというご要望だったのに、前半ほのぼのしてないし…ってかギャグ化してるし(泣)後半はいきなりぶっとんでるし(爆)なんかご要望のない甘甘が入ってるし(涙)
目撃者ありというご要望を頂いたのですが、何故かそれがオチっぽくなっている……! とんでもないですね^^; そういえば我愛羅書いたのって初めてです。いきなりキャラ壊れてるし。まるで「十五で姉やは嫁に行く、弟は…」ってなあの歌(題名不明・笑)のようになってるし……。ああでも、砂三兄弟好きの哀鈴様のために兄弟愛を深めてみました(言い訳)
やっぱり哀鈴様の小説にはとてもかないませんでした。すみませんでした! 次はもっと精進いたします。
では、この度はリクエストありがとうございました。
この物語を、哀鈴様に捧げます。
追記:哀鈴様が、この作品をご自分のHPに掲載してくださいました。とても光栄です。本当にありがとうございます。
お礼リクエスト小説 サスケ奪回任務後。責任を感じる小隊長シカマルとフォローするキバの物語です。(キバとシカマル 友情もの・シリアス)
注:この物語はキバとシカマルの友情がメインです。それにより、チョウジの存在が少しだけ軽んじられています。シカマルとチョウジの友情を少しでも軽んじる話は我慢出来ない! と思われる方はお読みにならないほうが良いと思います。管理人自身、シカマルとチョウジの友情は推奨派ですが、今回はテーマを優先させますので、ご了承ください。
『闇夜の墓場 友達の意味』(NARUTO15)
サスケ奪回任務に失敗したその夜、シカマルは独り暗闇の墓場にいた。月は雲に隠れ、暗闇の中にあるのは、見渡す限り広がる数々の盛り上がった土に木が刺さっている墓のみである。
シカマルはその中に独り立ち、重い雰囲気を噛みしめるように苦痛に満ちた表情で、負傷していた指をボキ…と折った。
「……っ」
激痛に顔を歪め、痛みを身に刻みつけるように、シカマルはうめき声がもれるのを必死で我慢した。そしてまた暗闇の墓を見つめては、指を折り、耐え難い痛みに歯を食いしばる。
何十回繰り返しただろう……。シカマルは、ガクンと膝をついた。既に骨折しているであろう指をさらに何度も自らの手で折ったシカマルは、痛みで気が遠くなる。
「……っきしょー…。まだ……まだ足りねぇ……」
シカマルはさらに指を折り曲げようとしたが、手が震えてガクガクする。それでも指に手を加えようとするシカマルの腕を、突然誰かがつかんだ。
「オイ何やってんだよ!」
息も絶え絶えに振り向いたシカマルの目に映ったのは、キバだった。
「バカ! お前こそ何やってんだ! 絶対安静のはずだろ!」
包帯だらけで立っているのがやっとなキバに、シカマルは肩を貸そうと立ち上がりかけたが……。
「くっ……」
激痛が走り、気を失いかけた。キバは、見かねてシカマルの隣りに座る。キバもその動作に、腹の傷を押さえうなり声を上げた。
「キバ……バカやろ……。早く病室……戻れ」
「ヤダね。オレはお前をさがしにきたんだぜ」
キバは、今回の任務を共にした仲間を、一人ずつ見舞った。もっとも一番重傷のネジはいまだ面会謝絶だったが。ところが、病院にいるはずのシカマルの姿が見えなかった。シズネに、シカマルが今回の任務に責任を感じて泣いていたという話を聞いたキバは、心配になり鼻を頼りにシカマルをさがしに病院を抜けてきたのだった。
「キバ……。お前は……重傷なんだ……。オレが何してよーが、勝手だろ。いーから……早く戻れ……」
「お前って、自虐行為が趣味なわけ?」
キバはシカマルの言葉を無視し、傷の痛みを隠すように無理に口元の端を上げニヤリと笑う。
「んなわけ…ねーだろ……」
とぎれとぎれに、言葉を紡ぐシカマル。その体は、ガクガクと震えている。
「シカマル。お前の方が重傷だぜ」
キバの意外な言葉に、シカマルはいぶかしげにキバを見る。
「オレは……、オレは……一番軽傷だったんだぜ。小隊長のくせによ……」
「けど心ん中の傷は、ナルトと同じくれー重傷だろ?」
キバは、月のない闇の空を見上げる。そして、シカマルに目を戻す。
「その震え、痛みのせいだけじゃねーだろ」
「……」
震えが止まらぬまま、黙り込むシカマル。少しの間沈黙が続いたが、やがてキバが口を開いた。
「お前ってさ……。自分のこと誰にも話さねーだろ。苦しいこととか」
「あー? オレは…男だぜ……。誰が――」
「チョウジにも、だろ」
「……!?」
はっとするシカマルに、キバはニヤリと笑う。
「シカマルって、そーいうタイプだぜ。仲間の話は聞いてやるけど、自分のことは話さねぇ」
「……だから…なんだってんだよ……」
キバは真顔に戻り、少し黙り込んだ。そして言った。
「いいこと教えてやるよシカマル。辛いときには、ダチに甘えていいんだぜ」
キバは、ガバッと片手をシカマルの首にまわし肩を組んだ。シカマルは、驚いて目を見開く。
「話してみろよ。楽になるぜ」
キバの言葉に、シカマルはじっと考え込んでいたが、やがて言った。
「今回、運良くみんな助かったけど……もしかしたら……死んでたかもしんねー」
「……」
「分かっとかねーと……いけねー気がした……。死ぬって……どーいうことか……」
「……」
「暗闇ん中に埋められたヤツらは……静かすぎて……怖かった……」
「……」
少し落ち着いていたシカマルは、再びガクガク震えはじめ、負傷した指に手を当てる。
「逃げ出したくなるたびに……指を折って傷つけた……。死ぬことの意味が分かるまで……何度もそーした……けど分かってくるたび苦しくてお前たちの命が重くて……オレのせいで失ってしまったかもしれないと思うと気ぃ狂いそうで――」
キバは夢中で、シカマルを抱きしめた。腹の傷が痛むのを我慢して。
「シカマル大丈夫だっみんな生きてる」
キバは必死で言葉を紡いだ。不器用で、とっさに上手い言葉は出なかったが、キバなりのストレートな気持ちだった。それから、少し頭の中を整理して、再びシカマルに語りかける。
「お前が……独りで責任抱え込むことねーだろ」
シカマルを抱きしめたまま、キバは少し落ち込んだ表情をする。
「オレが……弱かったせいでもあるだろ……」
「キバ……」
「ゴメンなシカマル。けどよ、独りで苦しんで泣いてんじゃねぇよ。オレのとこ来りゃあ済むことだろーが」
キバの言葉はぶっきらぼうだったが、言い方は優しかった。シカマルは、いつの間にか震えがおさまっていた。
「サンキューな。キバ……」
シカマルは無理に笑ったが……何かが崩れたようにキバにしがみついて泣き始めた。
「…わりぃ……」
シカマルは震える声で、泣きながらそれだけ言った。
「いーって」
キバは優しく、シカマルの背中をポンポン叩いてやった。
闇夜の静かすぎる墓場だったが――シカマルはその中で命の尊さと、そして初めて大きなあたたかい存在に気付いた。その存在――キバは教えてくれた。友達の意味。独りで苦しまなくてもいいということ。
シカマルの苦しみを、初めて受け入れてくれたキバ。二人はその後、お互いにとってなくてはならない友となる。
☆あとがき☆
うっ……ずれてる。ずれてるよぉ……(泣)ここここんなはずじゃ(アセアセ)
すみません! 「シリアス・墓場」のリクエストに、頭の固い管理人はこんなんしか思いつきませんでした。多分リクエスト者様がお好きなシカマルはもっとクールで、キバはそんなシカマルに甘えてるみたいな感じだったと思ったのですが……(多分)
こんなダークなものを書いたのは初めてです(爆)しかも最後は道徳の教科書みたい^^;
しかもしかも自分で突っ込んでしまうのですが、「シカマルは苦しいとき誰にも話さない」←うそつけ!って感じです。すぐ、めんどくせー、とだれかれ構わず言ってる気が……汗
で、でも……リクエスト小説なので……では……。
この物語を、キリリク ヒナタ絵のお礼としてサツキ様に捧げます。
追記:管理人、初!のキバ書きです。(わざわざ追記してまで言わないと気が済まない変な管理人)
お礼リクエスト小説 第七班新米当時、復讐者故に苦しむサスケとその身と心を案ずるサクラの物語です。(サスサク・シリアス+ほのぼの感動少々)
『桜雨』(NARUTO16)
「ねぇサスケくん。私ね、今日お弁当作ってきたの。一緒に食べよ」
めずらしく午前中だけだった任務帰り。サクラは、いつものようにサスケを追いかけていた。
「自分で用意した握り飯がある。オレはこれから修業だ。ついてくんな」
サスケは、振り向きもせず早足で歩いていく。サクラは、森へ入るサスケを追いかける。
「で、でも、おにぎりだけじゃ栄養足りないよ? 私、卵焼きとか作ったし、あっほら、サスケくんの好きなトマトも入れたし!」
「トマトなら朝食ってきた。余計なお世話なんだよ……」
「サスケくん……」
サクラは、落ち込んで足を止めた。うつむいていると、ふと気付く。サスケが、まだそこにいることに。サクラが顔を上げると、サスケは半分振り向いて片手を付きだした。
「一緒に食うのはごめんだが……捨てるのももったいないしな」
「サスケくん……!」
泣きそうになっていたサクラが、ぱっと表情を明るくする。そしてサクラはバッグから青い包みの弁当を取り出し、サスケに渡した。サスケは受け取ると、何も言わずに去っていった。
「ありがとう、サスケくん……」
サクラは、それだけでうれしかった。
サクラは、サスケと別れた場所に腰を下ろした。サスケは、この森で昼食を取り修業をするのだろう。離れていても、同じ森の中にいるだけで、サクラはうれしかった。バッグから桃色の包みの弁当を取り出し、サスケを感じながら独り弁当の蓋を開ける。
「エヘヘ。包みもお弁当箱も中身も、サスケくんとお揃いなんだよね」
サクラは、ちょっとだけさみしい気持ちをごまかすようにニコッと笑い、箸をつかむ。
「いただきまー……」
サクラは、思わず身構える。森の奥で、木がざわめく音がしたからである。それはサスケが足を向けた方向ではあるが、サスケ独りでないことは、忍のサクラにはすぐに分かった。嫌な予感がしたサクラは、バッグや弁当を置き去りに、急いでその方角へと向かった。
サクラが駆けつけて影から様子をうかがったときには、既にサスケが刺客らしい男を倒した後だった。サクラは出ていこうとしたが、サスケが男にものすごい剣幕でなにかを問いつめているのを見て、思わず足を止める。
「アイツが木ノ葉に来ているというのは本当なんだな!」
「ああ……。今言った里はずれの宿で……確かに見た……」
サスケに襟首をつかまれながら、男は息も絶え絶えに答える。
「アイツ……?」
サクラは、小さくつぶやいた。そして感づく。事情はよく分からないが、サスケがたまに口にする、復讐者……。その人のことを言っているのだと。
サクラがあっと思ったときには、すでにサスケは里はずれに向かって木々を飛び、すでに追いつけないほど遠くなっていた。
サクラは、倒れた男の元にかけより、肩をゆさぶった。
「ねぇっ、サスケくんに言ったこと、ホントなのっ!?」
サクラの猛烈な勢いに、男は逆にフンと笑う。
「オレがそんなこと知るわけねーだろ。命をとられちゃ困るからよ、情報屋のふりをして、アイツが知りたい情報とオレの命の保障を交換したってワケよ。けっ、こうもあっさりだまされるとは、所詮はまだガキだな」
サクラは怒りで肩が震え、男を殴ろうとしたが、それもばかばかしくなり男から手を離した。
「アンタなんか……さっさと里から出ていきなさいよっ!」
「ああ……そうさせてもらうさ」
男は、瞬身の術でさっと消え去った。
「サスケくん……。冷静なあなたなら、普通はこんな嘘にひっかからないはずよ。そんなに、その人のこと憎いの?」
サクラは独り、辛そうにつぶやいた。
その夜、サクラは自室の窓から外を眺め、サスケのことを考えていた。
「今頃サスケくん、嘘に気付いて落ち込んでるだろうなぁ。あの男に、里はずれの宿の場所を聞いておけばよかった。そうしたら……」
そこで、サクラの言葉は途切れた。そうしたら……自分が迎えに行ってなぐさめたら、サスケはよろこぶだろうか……。そんなはずはないと思った。今日、弁当さえ迷惑がっていたサスケである。
ふぅとため息をついたサクラだったが、突然はっとした。もしかしたら、その宿には、男の仲間がいるのではないだろうか。サスケは複数の敵に、襲われていたりしてはいないだろうか。サクラの頭に、そんな不安がよぎった。
その予感は的中していた。宿へ着いたサスケは、突然先程の男とともにあらわれた数人の忍者にとりかこまれ、「アイツ」の情報が嘘だったことを知らされる。あざ笑う敵たちを、サスケは怒りに身を任せて倒したが、サスケもかなりの重傷を負った。
「くそっ……。こんなカッコわりぃ話、知られるわけにはいかねぇ……」
サスケは簡単にだまされた自分を責めながら、病院ではなく自宅へと足を運んだ。里はずれで人影もなく誰にも気付かれなかったが、腹からぽたぽた血がしたたり落ちる。サスケは足を引きずるように重い足取りで歩いていたが、たびたび目はかすみ、意識がもうろうとする。サスケは、辺り一面殺風景な草むらが続く一本道を歩いていたが、すぐにでも倒れて気を失いそうだった。
その時、サスケは遠くの道ばたにぼんやりとした光を見た。どうやら、電話ボックスのようだった。サスケはなんとかそこまでたどり着き、腰を下ろした。電話ボックスの壁を背に、うずくまるように地面に手を突くと、懐から何かが落ちた。サクラの弁当だった。
サスケは、ハァハァしながら、弁当を手に取りそれをじっと見つめた。
「とにかく……何か食べねぇと……」
サスケはガクガク震える手で、包みをほどき、弁当箱の蓋を開けた。ご飯の上におかかが敷き詰められ、おかずは卵焼きとハンバーグとプチトマト。
「アイツ……オレより料理ヘタだな……」
サスケは震える手で必死に箸を持ち、形が崩れた卵焼きを口にする。
「甘ぇし……」
そしてプチトマトを手に取り、口に入れる。
「オレは……普通のトマトが好みなんだよ……」
ぶつぶつ言いながらも、今度はハンバーグに手をつける。
「中まで焼けてねぇぜ……。バカ……」
最後に、おかかご飯を食べる。
「……サクラ」
サスケは、それだけつぶやいた。弁当の中身はほとんど残っていたが、重傷のサスケはこれ以上口にすることは出来ず、蓋を閉める。そして、空を見上げた。満面の星空だった。
『一緒に食うのはごめんだが……捨てるのももったいないしな』
『サスケくん……!』
泣きそうだったサクラが、あのときにっこり笑った。
ほとんど残した弁当を、サスケは苦しげに見つめる。そして、ふと思った。
「アイツ……あれから森を抜けただろうな……。ヤツの仲間に……襲われてねぇだろうな……」
ちょうど後ろには、電話ボックスがある。サスケは少しためらったが、立ち上がり電話ボックスの中へ入った。ポケットから財布を取りだし、小銭を電話の挿入口に入れる。
プルルルル……ジジ……ジジジ……。壊れているのか、小さな雑音が聞こえる。
「はい。春野です」
いまだ続く雑音とともに、電話口の向こうから聞こえたのは、サクラの声だった。
「……」
サスケは、何も言わずに電話を切ろうと思った。サクラの無事。それだけ確認出来れば、サスケは十分だった。サスケが受話器を置こうとした時……。
「……サスケくん?」
受話器から、再びサクラの声が聞こえた。サスケはあわてて電話を切ろうとしたが――
「待ってっ!!」
サクラの必死な声に、サスケは受話器を置くのをためらった。
「サスケくんなんでしょう?」
「ああ……」
既に感づかれているサクラにわざわざ無視するのも逆にまずいと思い、サスケは答えた。
「怪我……怪我してるのね!?」
サスケはどきりとした。サクラの勘の良さに。
「待っててサスケくん! すぐに行くからっ!」
「いい……来るな……。第一……お前ここの場所……分かってんのかよ……」
「声の伝わり方からして、電話ボックスからかけてるでしょ。それにその雑音の電話、私使ったことあるから知ってるわ」
それきり、電話は一方的に切れた。
「バカ……」
そう言ったきり、サスケは電話ボックス内に座り込んだ。サクラが家を出た以上、もう待っているしかない。夜道を独りかけるサクラを残して、帰るわけにはいかない。
まもなく、雨が降り出した。瞬く間に、どしゃぶりになる。
「アイツ、ぜってー傘持って出てないだろうな……」
サスケは、ふらつく体で外に出て、ボックスの壁によりかかり座った。ずぶぬれになりながら、サスケはぼそりとつぶやく。
「アイツも……濡れてるんだろうな……」
サスケは一本道を少しでも歩いて、サクラとの距離を縮めたかった。けれど、サスケの体は、もうほとんど動かなかった。
サクラを待った。サクラの家からここまで、かなりの距離がある。
「バカ……風邪ひくぞ……」
待ちながらサスケは、独りつぶやく。待つ時間は、異常に長く感じた。サスケはふと、地面に置き去りにされた弁当に気付く。そばに、ぐしゃりと雨に濡れた、青い布包み。サスケは弁当を軽く布包みにくるむとそれを両手に抱え、これ以上濡れないように、かばうようにうずくまる。そうしたまま、じっとしていたら、ふいに雨と違うしずくが落ちてきた。サスケが顔を上げると、サクラがそばに立っていた。
サクラは、案の定傘も差さずびしょぬれで、激しく息を乱しながら……泣いていた。肩を震わせ、しゃくり上げるサクラの涙が、サスケに降ってくる。
「何……泣いてんだ……」
サスケは、最後の気力を振り絞って立ち上がった。サクラは、サスケに抱きついた。その拍子に、サスケが持っていた弁当箱が地面に落ちた。ろくに包んでいなかったので、蓋が外れて中身がこぼれた。
「その……、後で食うつもりだったんだが……」
「……うっ、うぇっ……、サスケ……くん……」
サクラはサスケに抱きついたまま、激しく泣きじゃくる。
「けど……少しは食ったぞ……。その……、おかかの飯は……まぁまぁだった……」
「……また……うっく……、つく…る……ね……」
サスケは、サクラの背中にそっと手をまわした。雨に濡れたサクラの身体は、冷たかった。
「……ひっ…ひっく……、サス…ケ……くん……」
酷く泣くサクラに、サスケは何を思ったのだろうか。サスケは少し辛そうで、けれどその目には、どこか安堵の色があった。
サクラは、何も聞かなかった。だからサスケは、サクラが今回の事情をすべて知っていることに気付いた。なぜなら、知らなかったらサクラは必ずしつこいほどに聞いてくるからだ。知っていて、何も言わないサクラの気遣いが、サスケはうれしかった。
帰り道。自分で歩くと聞かないサスケに、サクラは無理矢理肩を貸していた。
「オイ、このことは誰にも話すな……。いいな」
「うん。その代わり、今度一緒にお弁当食べてね」
サクラは、にっこり笑った。
「……調子に乗ってんじゃねぇ」
そう言いながらもサスケは、数日後に待ちかまえているであろうサクラと二人きりの弁当タイムを想像して、少し頬を赤らめた。
いつの間にか、雨は上がっていた。サクラはふいに流れ星を見た。サクラは、小さく小さくささやいた。
「サスケくんが、これ以上復讐で苦しむことがありませんように……」
「何か言ったか?」
「ううん」
サクラは、サスケに微笑んだ。サスケは一瞬つられてかすかに笑ったが、またいつものクールな表情に戻った。
「ねぇ。サスケくんなら流れ星に何を願うの?」
「……別に何も」
そっけなく答えたサスケだったが……サスケがたった今思っている小さな願い――それは、サクラともう少しこの道を歩いていたい……ただそれだけだった。
☆あとがき☆
管理人、初!のサスサクです。
「桜雨」(さくらあめ)は造語です(あ、いえ辞書に載ってないだけで、いろんな方たちが使ってそうですが……)サスケたちが新米当時、春だったとの勝手な管理人の思い込みと(NARUTO世界に季節があるか知りません)春=桜…サクラ、雨はクライマックスの重要小道具だったので、「桜雨」です。それだけです。
今回、めずらしくリクエスト要素はうまく入ったように思えます。ただ、話がベタすぎる気がします。もっと、心にぐっとくるような、切なく甘い恋愛ものを書いてみたいものです。あ、あとがきなのに話が脱線しました・汗
この物語を、弥彦絵並びに日頃大変お世話になっているお礼として美月様に捧げます。
追記:美月様が、この作品をご自分のHPに掲載してくださいました。とても光栄です。ありがとうございます!
ご感想、日記のコメント欄か 掲示板 に書き込みしていただきますと、とても励みになります。また、ご希望により裏話をお教えいたします。
NARUTO小説(短編)目次
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年新年1号感想…
- (2024-12-03 13:19:08)
-
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 🌀✨2024年、大ブームになった漫画特…
- (2024-12-05 07:50:06)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- 悪役聖神官ですが、王太子と子育て恋…
- (2024-10-04 21:52:45)
-
© Rakuten Group, Inc.