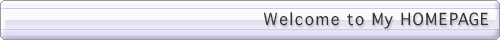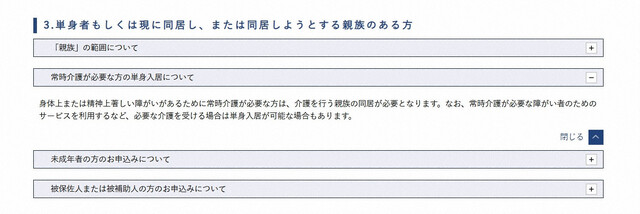高まる日本茶ブームと晩霜
新聞各紙の報道で日本茶を巡るニュースが増えた。産地表示問題の懸案解消を指摘される中、新しい歓迎すべきブームがある。間もなく新茶の香ばしい匂いと一服が楽しみな季節。安全・安心な食品や健康志向の人々に、若者が加わり本来の味と効用が見直され評価が高まる。
お茶の種を日本に持込み広めたのは、鎌倉の禅僧で臨済宗の開祖千光国師栄西。
2度中国(当時の南宋)に渡海し禅宗を極めた。2度目の帰国途上難破漂着した温州で、修業を終へ持ち帰ったらしい。
1211年71歳の時「喫茶養生記」で、茶の効能・病気と養生の法を著した。
74歳で書き改め、3代将軍実朝の病気平癒を祈願献上し翌年没。
安土桃山時代の信長の庇護の下、武家好みの茶の湯・茶道へと変化を遂げ、秀吉は北野の大茶会で人々を驚かせた。
江戸時代を経て近年に至るまで、渋い味覚やわび・さびの世界の代物として日本文化の一翼。
昨今、食べるお茶としてのアイディア商品が続々生まれ若者の支持が広がる。
定番抹茶ソフトクリームに抹茶カステラ・あめ等、オープン間もない汐留地区の和風喫茶は若者の行列。仕掛は京都の宇治茶の専門店。老舗の風格と甘味処を上手く時代に合わせた。
元来、日本茶は暮らしに馴染んだ飲料であり、イメージの工夫や現代風の販促・インスタント化でオフイスのOLに歓迎されつつある(日経産業)。
全国的に、がんの死亡率が低い静岡県の中で西北部大井川流域が際立っているとの調査結果から、薬効が再認識されている。この地区では濃い目のお茶を何度も入替えて飲む。がん予防に効くお茶の成分カテキンは優れた抗活性酸素の働きがあり、ビタミンA・C・Eも含まれる。
一杯のお茶で約0.1gのカテキン、10杯で1gを摂取。一方、お茶の葉6gに約1gのカテキン。よって、お茶の葉を丸ごと食べることを筆者は勧める(毎日)。
さて、立春から八十八夜(5月2日)の頃、茶農家泣かせの晩霜(別れ霜)がしばしば降りる。その有無と対策が、初摘みのお茶の収穫量と農家の1年を決定付ける。ブランドよりブレンドで、消費者の心を射止めるよう天に祈る。
© Rakuten Group, Inc.