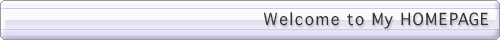気候変化に対応した農業を!
平成16年1月22日
先週は北海道地方を中心に記録的豪雪となったが、昨年一年間のデータでは、西日本を中心に暖冬傾向が継続中。
世界気象機関(WMO)の発表では、2003年の世界の気温は、1861年に機器観測が始って以来、3番目の高温を記録。
ちなみに、第1位は98年、第2位は02年。76年以降、温暖化のスピードがハイペースで上昇中。その影響で気候のパターンが変化し、世界各地で異常気象が頻発し、農業でも大きな災害が発生している。気象情報利用の判断力の是非がますます重要となっている。
気象情報を活用して成果をあげた具体例に南氷洋捕鯨があった。
その船団長には二つのタイプ、「漁場重視型」と「気象活用型」がいたという。
漁場重視型は過去に大漁した海域を重視して操業。
一方、気象活用型は実績にとらわれず、天気が安定した海域に船団を移動して操業すれば、必ず何頭か捕獲できるという確実性を重視したマーケティング志向。
両船団長の漁労方法を農業と気象の関係で見ると、漁場重視型の農家は種まきや定植などの時期を暦や気候の平年値で決める。
一方、気象活用型の農家は、長期予報や最新の気象情報をぬかりなく入手・検討し、種まきから施肥、農薬散布の時期、水稲の場合には水深の管理などを気象の変化に合わせて行なうだろう。
今後も続く地球温暖化の進展に伴う気象変動で、農業でも過去の実績がだんだんと通用しにくくなることが予想される。タイムリーに情報を入手し、体験を加え、独自に分析を行い、気候変化に対応した農業生産の向上を図っていただきたい。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 懸賞フリーク♪
- 明治MICHITAS(ミチタス) カップ白…
- (2025-11-30 16:40:25)
-
-
-

- 政治について
- 【門田隆将】大至急見て⚠️国民は黙っ…
- (2025-11-30 20:20:32)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 🐼楽天ブラックフライデー🐼お疲れ様…
- (2025-11-30 22:56:15)
-
© Rakuten Group, Inc.