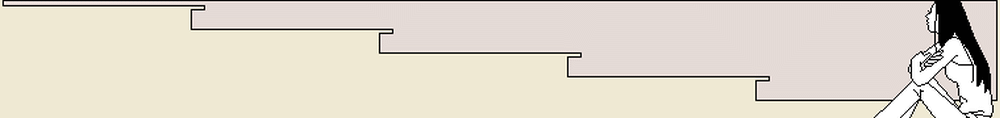カテゴリ: 夏の歳時記

石橋秀野句碑
次に訪れたのは中山町の中里神社。「鶴」で活躍した女流秀野の句碑がある。句碑には石田波郷の筆で〈風花やかなしびふるき山の形〉と刻まれている。秀野の句碑は地に蹲るように置かれ美しく、大山に連なる船上山へ向いている。
*補足 「船上山は山岳霊場として、和銅年間に赤衣上人か智積上人によって、智積寺として開基されたと伝えられる。南北朝時代の初めには、隠岐を脱出した後醍醐天皇を伯耆の豪族、名和長年が迎え、船上山に行宮を築いた。後醍醐天皇方の名和長年と鎌倉幕府方の佐々木清高との間で激しい戦い(船上山の戦い)が繰り広げられた古戦場である。山頂付近の蒲ヶ原には行宮碑がある。1932年(昭和7年)に国の史跡に指定された。」
秀野が夫山本健吉とともに山陰の地に移り住んだのは、昭和20年4月から翌21年7月まで。肩身の狭い疎開者として窮乏生活の極みを経験したようである。〈火桶抱けば隠岐へ通ひの夜船かな〉の句に、寒々とした情景を読み取ることができる。病弱な秀野一家にには厳しい生活だったが、鶴山陰支部とのあたたかい交流があった。21年7月、健吉の京都新聞社への転勤に従い京都へ転居。疎開地の無理がたたり結核を発症。22年9月26日、三十八歳の短い生涯を終えた。(『定本 石橋秀野句文集』参照)
秀野句碑に触るる縁や露涼し
クリックしてね
↓
人気ブログランキングへ
俳句・夏・天文、露涼し、秀野句碑、中山町中里神社、船上山の戦い
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
コメント新着
まだ登録されていません
2025年11月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年10月
2025年09月
2025年08月
2025年07月
2025年06月
2025年05月
2025年04月
2025年03月
2025年02月
2025年05月
2025年04月
2025年03月
2025年02月
カレンダー
© Rakuten Group, Inc.