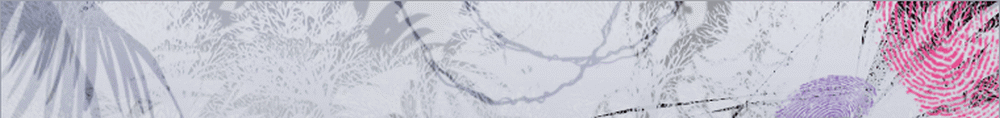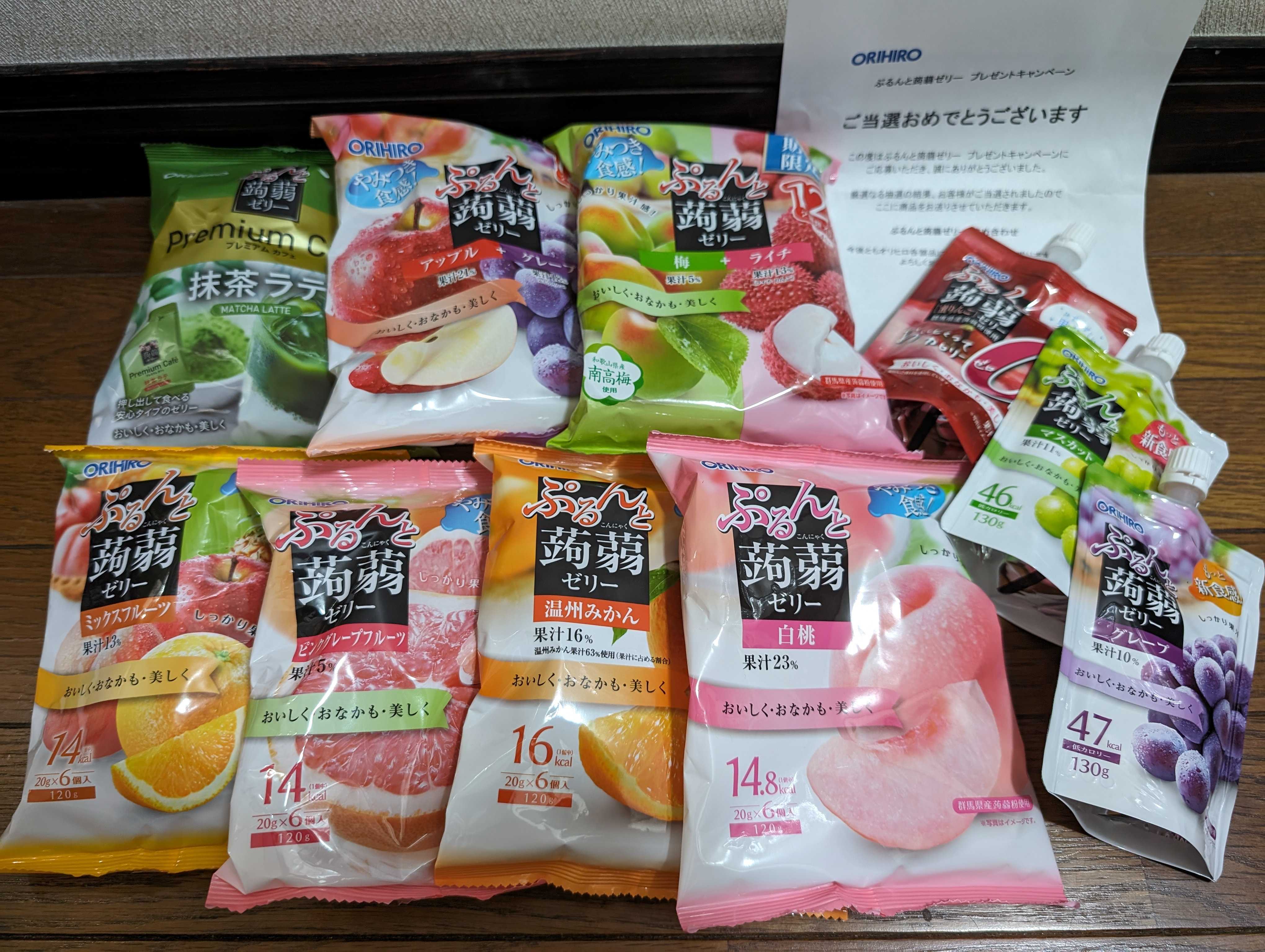税務・会計メモ
(2008.09.27)
後入れ先出し法11年3月期廃止
企業会計基準委員会は26日、棚卸し資産の評価方法についての会計基準を改正し、「後入れ先出し法」を2011年3月期から廃止することを正式決定した。日本の会計基準と国際基準の違いをなくす作業の一環だ。
後入れ先出し法は企業が仕入れた商品を売上原価に計上する際に、直近に仕入れた在庫から先に出荷したとみなす方法。物価上昇時には「総平均法」などに比べ利益が少なくなる傾向がある。
評価方法を変更する際には利益が膨らみ一時的に税負担が重くなる可能性があり、後入れ先出し法を採用する企業からは税務面で配慮を要望する意見が多いという。
[2008.09.27日経朝刊]
(2007.09.15)
日本インターネットポイント協議会がポイント発行の会計処理のガイドラインを公表。
1.適切な引当率算定により引当金額を計算すること。
2.ポイント引当金率の見直しを年1回以上行うこと。
3.ポイント引当率算定方法を継続すること。
(2007.08.21)
企業会計基準委員会は、建設工事やソフトウェア開発などに関して、工事の進行度合いに応じて売上や利益を計上する「工事進行基準」の原則適用を義務付ける。従来は完成時に計上する「工事完成基準」も認めてきたが、国際会計基準との整合性を重視して進行基準に一本化する。二十四日にも草案を議決して公開した上で、詳細を詰める。
適用の対象となるのは、建設工事や土木工事などの建設業や、造船や機械装置の製造、受注政策のソフトウェアなど。工事の期間や受注額の代償に関わらず、収益や費用、工事の進捗度が合理的に見積もることが出来る場合には、工事進行基準の適用を義務付ける。二〇〇九年度以降に着手する工事から義務付ける。
これまで、どちらの会計基準を採用するかについては各社の判断にゆだねていた。建設業では清水建設や戸田建設が工事完成基準を採用しているほか、他の企業でも小型工事については完成基準を使用している。
だが、国際会計基準では原則として工事進行基準の適用が義務付けられているため、会計基準委は進行基準へ原則一本化する方向で検討を進めてきた。
一般からも意見を募り、適用の詳細を年内にもまとめたい考え。[2007.08.17日経朝刊]
(2007.08.03)
DES額面額処理でも資本金等の額は時価相当が増加する。
(2007.07.30)
H20.4.1以降契約を締結する所有権移転外リース取引は売買取引とされる。
新株予約権を用いた買収防衛策が発動された場合、買収者には権利の行使が認められないため、一般株主に対する有利発行となり、買収者から一般株主への価値の移転が起こり、課税関係が生じるとされる。
一方、買収者自身には権利行使不可でも、第三者に譲渡可能な新株予約権の場合、買収者も間接的に権利行使が可能となり、株主間での価値移転が起こらず、課税関係が生じないとされる。
(2007.07.29)
日本国にはBSはあるけどPLがない。それが問題だ。
(2007.07.21)
固定資産の残5%の減価償却で、5年均等償却で生じた端数は5年目に調整して問題なし。(6年でやるのが正統なやり方。)
© Rakuten Group, Inc.