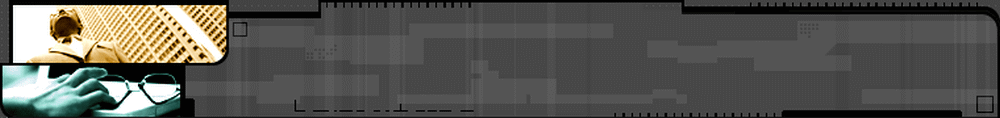第2話 タイムステーション
タイムステーション
一日の授業を終えて職員室へ戻ったファルコ・スーランは、自席に座るなりフゥーっと吐息を吐いた。転校して来たタンジ・アクーナの家は二十四区の店を閉めて五区で新たにヒト専門のレストランを移転させた。そのことを思い出すと、何故か吐息が漏れる。
食肉にされるために飼われているヒトがすべてはない。どこかに身を隠してひっそりと暮らしているヒトもいることは周知の事実だった。中央管理局はあえてそれを追い込もうとしない。どうせヒトにはアルバ星の政権を転覆させるだけの力は無いのだ。身を潜めているヒト同士がまた子供を作り子孫を増やして飽和状態になったところでまた、ある程度のヒト狩りをして食肉市場に持っていく。ヒトは食べられるために自ら増え続けるのだ。
しかし、そんなヒトの中でも幸運をつかむ者も稀にいることを中央管理局は知っているのだろうか。アルバ星にもヒトに優しいアルバはいる。ヒトは頭に触覚こそ無いが、アルバと体型がほとんど変わらない。ヒトを美しいと思うアルバもいる。そして、そんなヒトと愛し合って子供を密かに生む女性のアルバもいるのだ。事実、ファルコの母親がそうだった。
ファルコにはヒトの血が混ざっている。その事実を知る者は母親と娘のファルコ以外には存在しない。幸い、ファルコはアルバの母親の遺伝を受け継いだようで頭の触覚は周囲のアルバと何の変わりもなかった。だから、ファルコはヒトを食べたいとは思ったことがないが、ヒトである父親に同情をしたこともない。父親となったヒトは、母とファルコにヒトの言葉を教えていた。だから、ヒトの言葉を理解できるのはアルバの中でも母親と自分だけだろうと思っているが、中央管理局は専門家を育成することもなく、単にヒトを食用としか考えていない。あくまでも、ヒトは獣なのだ。父親もいつ見つかって捕らえられるかわからない。だからと言ってヒトである父親にそれほど同情の思いもない。ただ、一応は身内としての情は持っているつもりだ。あるいは、それは父親をペット程度に思っているだけなのかもしれないが、家族となったペットにもそれなりの愛情はある。
吐息をついたファルコに「どうしました?」と、隣の席の女性教師が声をかけて来た。目が悪い女性教師は大きなコンタクトを目に嵌めている。
「ミミリー先生は、ヒトを食べたことありますか?」
女性教師、ミミリーの大きなコンタクトを嵌めた目がギラギラと輝いた。
「あれは・・・・感嘆すべき美味しさですわよ。少しポイントが高いですけどね。もっとヒトが増えてくれればもっと安くなるのに、残念ですわ」
「そういえば、今日ファルコ先生のクラスに転校してきた男子生徒の家って、ヒトのステーキレストランでしたよね」
少し離れた席から、中年の男性教師が大きな声で訊ねてきた。
「ええ、まあ」
ファルコが肯くとミミリーの目が更にギラギラ輝いた。
「羨ましいですわ。家庭訪問の時に、もしかするとご馳走して頂けるかもしれませんわね。いつ行かれるんですか?」
アルバの学校では転校生が来れば、担任がその家に赴いて父兄に学校生活の細かな注意事項を説明しなければならない慣わしがある。特に法律とか学校の規律としてあるわけではない。いつしか、それがアルバ星の教師としての暗黙の約束事になっていた。
やはり、今日行くしかないか。ファルコは、ヒトの肉を勧められないように食事をしてから行こうと心に決めた。
アルバ星の歩行はわずかだ。何歩か進めば、いたるところに全身を映すほどの大きな鏡のようなガラス板がある。それがタイムステーションだ。アルバは、タイムステーションを通過して目的地に向かう。ひとつのタイムステーションで10kmほどの移動が一瞬で可能になる。しかし、他の地区へ行くためには本当の意味でのタイムステーション、つまり駅のようなところに一度出なければならない。
学校は3区にある。タンジの家がある五区に行くために、ファルコは一度ステーションに移動をした。ステーションの中には、レストラン村があり香ばしい匂いを漂わせている店が軒を連ねている。その中には一件だけ、ヒト料理を置いてある店があった。
ファルコはその店の店頭メニューを目で追いながら通り過ぎ、その隣の店内に足を踏み入れようとしたその時だった。
背後からパタパタと走って来る小さな足音が聞こえて来た。ステーションのレストラン村の中を、息を切らせて走って来る小さな影。頭からはこげ茶色の布をすっぽりとかぶり、顔を布の隙間から少しだけ覗かせていた。布のせいで頭の触覚は見えないが、もしかするとヒトの子供なのか。
誰かに追われているようだった。まだ子供のヒトを見つけても中央管理局が追うとは思われない。追っ手は中央管理局ではない、一般のアルバだろう。
ファルコは屈んで子供の目線になり、走って来る小さな体を優しく止めた。
「誰かに追われているの?」
ファルコはヒトの言葉で訊ねた。こんな場面を誰かに聞かれたら、自分もどうなるものかわからない。
幸い、子供は素早く小さく肯いた。ファルコは小さな声で「こっちよ」と言いながら子供の手を引いてタイムステーションを通過した。
ファルコはタイムステーションを何度か通過してたどり着いたのは、自宅のエントランスだった。
「ママ!ママ!」
ファルコの呼びかけに母親のブルーネがどこからともなく現れた。
ブルーネはバスに入っていたようだった。頭をタオルで拭きながら小さな子供に目をやった。
「ファルコ、この子はあなたのクラスの子じゃないわね」
「ステーションで誰かに追われていたようなの」
茶色い布の中から警戒をするような目がブルーネを見上げた。
「あなたは、ヒトの子?」
ブルーネは子供の目の高さになり、優しく声をかけながら茶色の布をそっと子供の頭からずり下ろしたが、子供は何の抵抗もしないでブルーネの目をじっと見ながら、肯いた。
「あなたのパパかママもこのアルバ星に来ているの?」
ヒトの子供の警戒のまなざしは消えずに、ブルーネを見ていた。
ブルーネは優しい波動を体から発散させて警戒を解こうとした。これは、ヒトには無い能力だと獣であるブルーネの夫、つまりファルコの父親は言っていた。すると、突然ヒトの子は泣き始めた。
「捕まったのね・・・・中央管理局に」
ヒトの子は肯いた。それは、ヒトの子の親は食肉になったことを意味する。
「しばらくここにいなさい。その方が安全よ」
泣き止まないヒトの子の体をそっとブルーネが抱きしめた。
そういえば、アイツはどこに行ったのだろう。ファルコは周囲を見回した。それを察したブルーネは、部屋の奥の扉を見て言った。
「パパはバスよ」
さっき、ママは頭を拭きながらバスから出てきたようだった。一緒に入っていたのだろう。ファルコは複雑な心境だった。確かにあのヒトはファルコの父親でもある。自分にヒトの血が流れていることにはそれほど憎んだことはあった。だが、今こうして自分はアルバとして普通に育ち普通に生活をしている。自分にヒトの血が流れていることをあえて意識しなくなった。しかし、ヒトはアルバに食べられる獣だ。その獣とママが一緒のバスに入っているそのことを想像すると鳥肌が立つ思いだった。
しかし、目の前にいる小さなヒトの子供は可愛らしい。この子供を通じてならヒトを獣よりも昇格させることが自分の中で出来るだろうか。ファルコは僅かなその思いに賭けてみたかった。
© Rakuten Group, Inc.