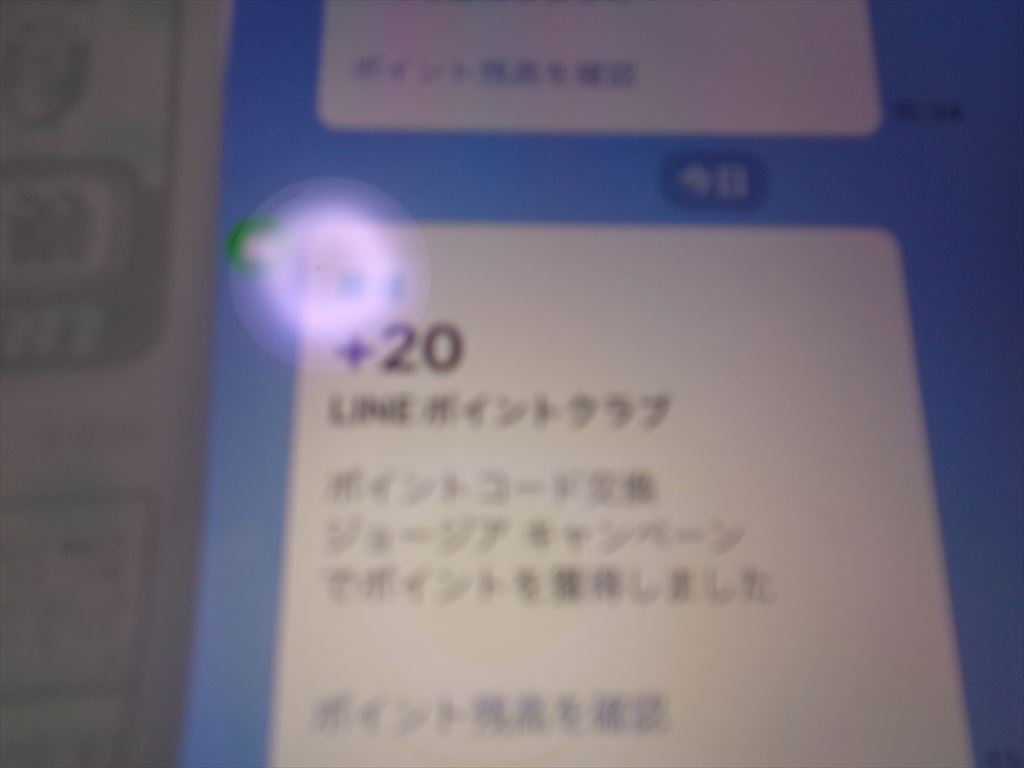ヒトヅマ☆娼婦17
やっちゃんのことが気がかりなまま、あたしは水島さんの待つホテルのロビーへと向かった。
あたりをきょろきょろしていると、後ろから声を掛けられた。
「まるでおノボリさんだな。」
振り向くと、水島さんだった。
「こんにちは♪」あたしはありったけの笑顔を向ける。
ヘアスタイルだって変えたし、メイク道具も揃えた。あたしは前よりキレイになってるはず。
でも水島さんはあたしの顔も見ずに、いつもの冷たそうな表情のまま、さっさと歩き出す。
あたしは慌てて後を追った。
ホテルの1階はブティックになっていて、その店のひとつに水島さんが入っていった。
あたしも遅れて店に入る。
「まあ、水島様。いらっしゃいませ。」マネキンのようにキレイな女性が近づいてきた。
「この前の服と靴、それからバッグを貰いにきたよ」
水島さんは、ソファに腰掛けて脚を組む。
「はい。いつもありがとうございます。」
「その前に、この子に試着させて」
「・・・はい。」その女性があたしの方をチラっと見る。
「どうぞこちらへ」その女性に促されて、フィッティングルームに入る。
「あの・・・」戸惑うあたしに女性が服を手渡す。
「このワンピース。あ、こっちのも着てみていただけます?」
しかたなく、言われるままに試着する。
「いかがですか?」女性に声を掛けられて、ドアを開ける。
黒地にパープルとピンクの花柄のワンピースを着たあたし。
「まぁ!よくお似合いですよぉ。こちらをお履きになって。」
黒のエナメルのパンプスに脚を入れる。
「サイズもピッタリ!髪の毛をアップになさったら、一層お似合いですよ!」
あたしは戸惑いながら、水島さんを見る。
「いいね」水島さんのメガネが光る。
「もう一着も着てみて」
言われるままに着替える。
今度は光沢のある白いワンピース。デザインが個性的。大きく胸が開いている。
「秋を先取りして、ベージュのブーツがよろしいかも♪」
女性の勧めるブーツを試着する。
「お客様の雰囲気にピッタリですね!水島様のお見立てはさすがです!」
女性は一人はしゃいでいる。
「じゃ、これも貰っていくよ。バッグも一緒にね」
「ありがとうございます♪」女性は満面の笑みを浮かべた。
あたしは水島さんに言われて、試着したままの格好で水島さんとホテルのレストランへ向かった。
水島さんは窓際の席をリザーブしてくれていた。
席に着くなり、水島さんはじっとあたしを見つめた。
「・・・なんですか?」あたしはその視線に耐えられず、うつむきながら聞く。
この水島さんの視線に、あたしは弱い。
逃げ場がないような、追い込まれるような気持ちになる。
「その白いワンピース、よく似合ってる」
その言葉にあたしは嬉しくなって、顔を上げて笑顔になる。
「本当に?よかった~♪」
「僕はワンピースが好きなんだ。詩埜にはいつもワンピースを着ていてほしい。」
「はい」
「髪の色、いいね。僕の希望通りだ」
「はい!」
「リップライナーをきちんと引いていないね。手を抜いてはいけない」
「・・・はい・・・」
「それから、歩き方がなっていない。レッスンの時だけできているんじゃ意味がないよ。
常に意識していなさい」
「・・・・・はい・・・・」
あたしがまたシュンとしたからか、水島さんは話すのをやめて、グラスに注がれたワインを一口飲んだ。
「ワインは嫌い?他のものを頼む?」水島さんは珍しく、やさしい口調であたしに尋ねた。
「いいえ。ワインでいいです。」あたしも一口、口に含む。
苦くて、少しぴりっとした。
オードブルが運ばれてきた。
水島さんが食べるのを見計らって、あたしもいただく。
「ナイフとフォークは上手に使えてるね」
「ありがとうございます」
水島さんがまた、あたしを見つめた。
水島さんと、目が合う。
水島さんが目をそらして、料理に視線を落とした。
「詩埜は・・・」
「はい」
「詩埜は、僕のどこがいいの?」
「え?」そんなことを聞かれると思っていなかったから、驚いて聞き返した。
「いや、、、僕と、どうして契約したのかと思って。もちろんお金が必要なのかもしれないけど、
それでも、よく決心したなぁと思って」
そう言いながら水島さんは、何度もワイングラスを口に運ぶ。
「どうしてかな。よくわからないけど・・・」
あたしは考える。
どうしてだろう。
水島さんは、厳しくて冷たくて。
でも、なんだろう。
任せられる、って言うんだろうか。
あたしのカラダを任せられる。そう感じたのかな。
「水島さんに、あたしをお任せしたかったんです」
「任せる?」
「あたし、誰かにあたしを、あたしのカラダを委ねたかったんです。でも、誰でもいいわけじゃなくて。
水島さんに契約のことを聞かされた時、この人だって思ったんです。
どうしてかわかんないけど、そう思ったんです。だから。」
あたしがそう言い終わるまで、水島さんはじっとあたしを見ていた。
なにか言ってくれるかと思ったけど
水島さんはただ、「そうか」と一言つぶやいただけで
次に運ばれてきたオマール海老のソテーと向かい合っていた。
© Rakuten Group, Inc.