(7)
 |
|---|
| (7) |
| 3月。 私は大学院の試験を受け、なんとか合格することができた。急遽受けることになったところではあったが、勉強したい内容に変わりはない。 彼はその私を心から祝ってくれた。 「お祝いは何がいい?」 と聞いてくれた彼に、私は 「じゃ、映画に一緒に行こうよ」 と提案した。 私がK君のこと抜きで彼と二人で会うのは、このときが初めてだった。 彼はまだK君のことを引きずっていた。 映画を観て近くの喫茶店でお茶を飲んだが、その時もK君のことが話題になった。 「オレは結局、あいつにとってなんだったんかなぁ」 彼は寂しそうにそうつぶやいた。 その彼を見て、私は一つ悲しい事実を悟った。 彼は、私に会うとK君のことを思い出してしまうのだ。 私はK君のことについて、いつも相談役だった。 それは、私が彼のことを好きだから、彼を支えたいから、自分で買ってでた役回りだった。 でも、K君とのことが終わってしまった今、彼にとって私はつらかったK君とのことを思い出させるだけの人になってしまったんじゃないか・・・そんな思いが心の中に湧いてきていた。 彼とK君のことが、どんな形であれ一段落したら、私は自分の本当の気持ちを彼に伝えるつもりだった。相談役としてではなく、一人の女性として私のことを見て欲しいと。だけど、彼にとってK君とのことは、簡単に一段落できるようなものじゃなかった。 彼の中でK君とのことが一段落するのは、K君のことを過去のこととして振り返ることができるようになるときだ。そうなるまで、彼にとって私はK君のことの相談役でしかありえないのだろうか。 こんなはずじゃなかった・・・ そう心の中で繰り返している自分に気づいて、私は愕然とした。 私は彼のために、自分の気持ちを押し殺して彼の相談に乗っていたつもりだった。 だけど、その気持ちはいつしか計算に摩り替わり、彼とK君のことが終わった後の段取りを、勝手に算段していた自分がいたのだ。 これが終わったら、私の物語を始められる。 これが終われば、彼と私の物語が始まるのだと。 そう、私は彼とK君が終わることを心の底で願っていたのだ。 彼のため・・・そういう大義名分の下で、私は自分のことばかりを考えていた。さらに始末が悪いことに、私はそのことに気づいてさえいなかったのである。 そのことに気づいて、私は自己嫌悪に陥らざるを得なかった。 K君とのことが終わり、自分の院試が終わったから、これでやっと自分の物語が始められると、彼を映画になんか誘った自分が情けなくて、恥ずかしくて、私はその場にいられなくなった。 私は彼とのお茶を楽しむことができず、早々に帰ることにした。 「用事があったのを思い出した」 彼にはそう伝えた。 帰りの電車の中、彼は私を気遣ってくれて、 「前の居眠りしてる人の首が、あり得へん角度で曲がってる」 とか 「赤ちゃんを抱っこしてる女の人のシャツに、ナメクジが這ったような跡があるのは、赤ちゃんの鼻水だろう」 とか、小さな楽しいことを見つけては、私に話して聞かせてくれた。 自分の心がまだ血を流すような思いをしているのに、そういう気遣いをしてくれる彼が、どうしようもなく好きだった。 別れ際、彼はまた私の手を握ってくれた。 そして、 「合格おめでとう。次の芝居、がんばろうな!」 と言って手を振ってくれた。 こんなにも暖かい心にしてくれる彼に、申し訳ない気持ちで一杯で、駅から自転車で家に帰る道すがら、思いっきりペダルを踏みながら泣いた。 その年の夏、私は劇団の公演に初めて役者として舞台に立つことになっていた。彼と同じ舞台に立つ初めての芝居だった。 彼とはしばらく会わない方がいいような気がしていた。 でも、芝居の稽古があるからそういうわけにはいかない。 私は自分の中の彼への気持ちを整理できないまま、ずるずると彼に会う日を待っていた。 (つづく) |
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 赤ちゃんが欲しい!
- いつでも安心見守りカメラ紹介!!
- (2025-10-02 15:03:20)
-
-
-
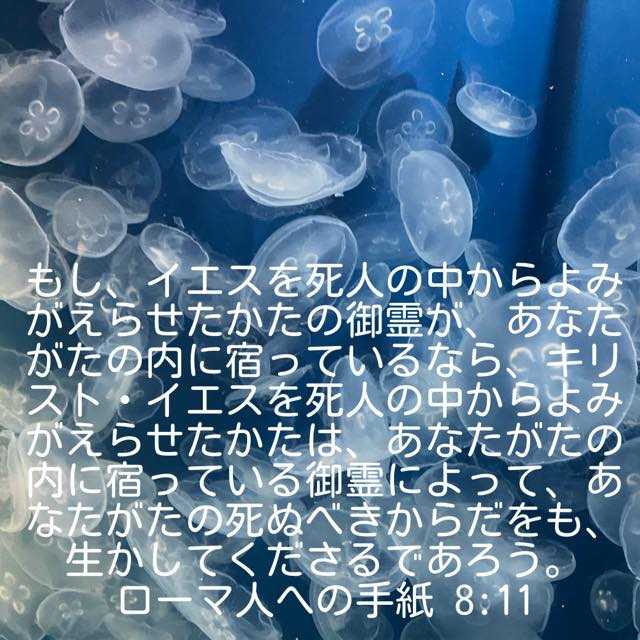
- 共に成長する家族!子供と親の成長日…
- 我が家の「沈黙の戦隊」
- (2025-10-24 09:33:10)
-
-
-

- 楽天アフィリエイト
- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…
- (2025-06-15 15:14:58)
-
© Rakuten Group, Inc.



