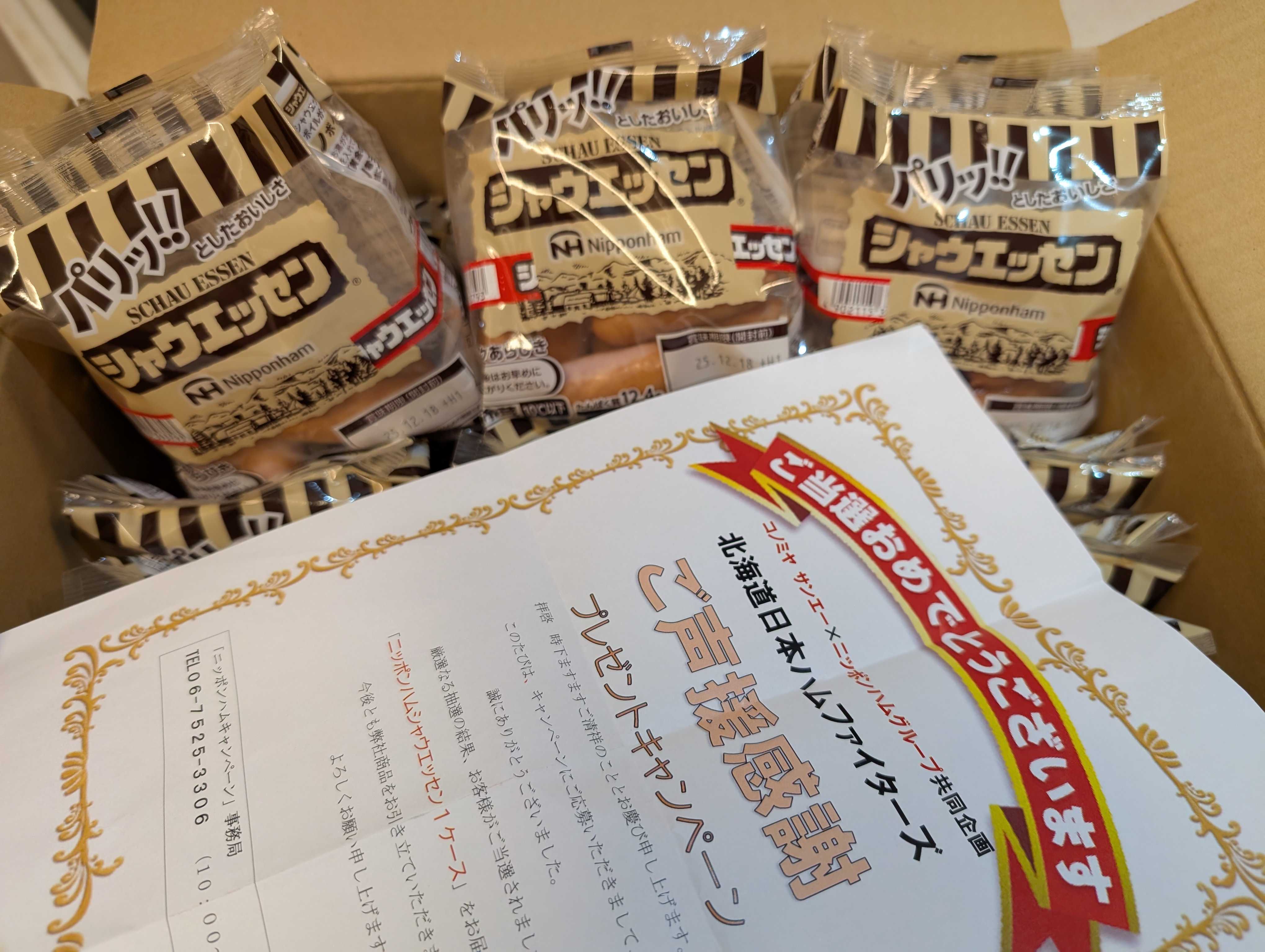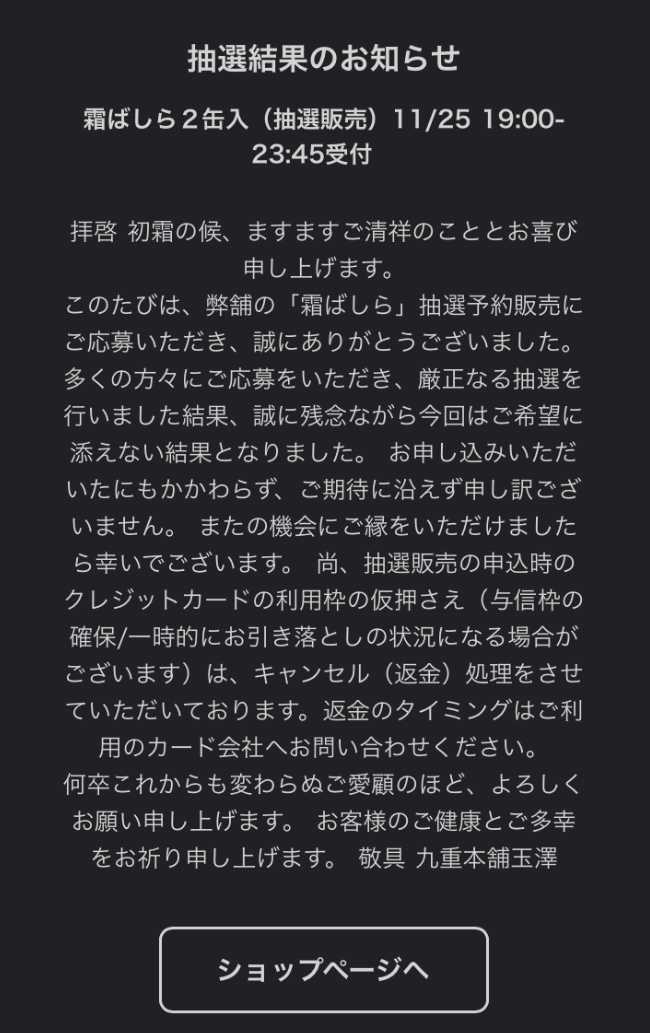05.司法改革の現実(17.11.15)
一つは桶川事件、もう一つは国籍条項の件。
桶川事件では遺族への賠償請求は認めながらも警察の責任を認めなかった
これは、裁判官が
「一般市民は見殺しにされても仕方ないよ、殺されてしまったら犯人は私が裁いてあげるから」
と言っているのに等しい判決。
国籍条項の件では最高裁で公務員の管理職に国籍条項を課す事は憲法に反しないことが事実上、確定した。
原告である鄭香均さんの口から出た
「世界中に言いたいです。日本には来るな(と)。日本に来て働くということは『ロボットとなる』ということ。人間として決して扱われない。哀れな国だと思います」
というコメントを果たして外国のメディアは、どの様に報じたのだろうか。
(17.11.15)
司法改革の一環として裁判員制度が数年後には始まる。しかも重罪に限って
採用されるという。そもそも重罪を一般市民の感情的なモノサシへ諮って良いのだろうか。とても疑問に感じる。たしかに裁判官の言葉は判りづらいけど。
それでも事実認定や量刑などは重罪になればなるほど専門性が求められると、私は思うのです。
あるいは法科大学院。これも司法関係者への門戸開放みたいに見えるけれど実際は逆に法科大学院へ入るのに必要な金が工面できない奴らを司法から排除するように機能すると思う。おそらく刑事弁護なんか今のような手弁当で請け負う弁護士が早晩、いなくなってしまうような気がしている。
こうやって考えていくと司法改革は別に庶民のために行われるのではなく、むしろ大企業や富める者の権利行使を容易にするだけのものではないかと思うのである。これは私の穿った見方なのだろうか。
重罪の刑事裁判に市民の訴訟参加が制度化される一方、基本権に関わる裁判官の常識は以前にも増して歪んでいる。
(17.6.19)
「事後審査」的な要素を今の司法改革では大切にしているのだ、と思う。
一見、わかり易さは、それ自体が好ましいような印象を受けるけれども、
人間の沙汰というものが果たして単純な条理だけで裁けるものだろうか。
重罰化路線も前提となる捜査機関の規律確保が制度的に保証されたうえで
初めて意味を持つのであって徒に立法が加速化する現象は安穏とできない。
こんな「脆い現実」を『改革』と呼ぶなら、その行く先は暗澹としている。
© Rakuten Group, Inc.