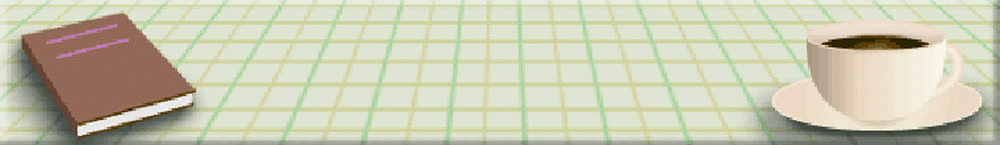図書館
私は、図書館が大好きだ。なんとなく薄暗い入り口や、きちんと整列している本棚や、あふれんばかりの本のにおいや、涼しくて湿った部屋の空気や、そういうものが、とても好きだ。
どんなことがあった日でも、図書館に行けば癒される。疲れたとき、悲しいとき、図書館は元気な私を取り戻させてくれる。うれしいとき、楽しいとき、図書館はいつもの私を思い出させてくれる。
本は私を絶対に裏切らないし、図書館は、いつだって私を迎え入れてくれるのだ。
図書館で勤めよう、と決めたのは、幾つのときだっただろうか。
カウンターでぼんやりと天井を眺めながら、ふと、そんなことを思う。
私が図書館通いを始めたのは小学生のときだったから、たぶんそのころだったんだろう。あのころ私は漫画家になるのが夢で、図書館勤めから帰ったらたくさんの絵を書く毎日を夢想していた。
今では、私は絵を描かない。代わりに、毎晩毎晩パソコンに向かって、たくさんの文章を書いている。私の今の夢は、作家、だ。
あのころの自分と今の自分、大きく違っている気もするが、まったく同じのような気もする。どちらにせよ、あのころの自分はもう、よく思い出せない。ついこの間までしていた大学生生活だって、このごろではよく思い出せない。時間の感覚がどんどん麻痺している。時だけが進んで、私だけが置き去りにされてゆく感じ。私だけがひとりぼっちになっていく感じ。
特に今日のように憂鬱が心に立ち込めている日は、本当に私は世界に忘れられている気がしてしまうのだ。なんにも心が記憶しない。動かない気持ち。
「あら、あめがふってきたのね。」
隣に座る私と同じエプロンをした山本さん(私はしばらく彼女がいることもおもいだせなかった)が言う。言われて窓の外を見てみると、新緑がつややかに濡れていた。
「雨降りでお昼時だもの、誰も来ないわよね。林さん、お昼にしていいわよ。」
優しげな笑顔で山本さんは手で、どうぞ、というしぐさをする。私は遠慮をあまりしないので、素直に、ありがとうございます、と言ってエプロンを取り、カウンターを出た。
外はしとしとと、雨に濡れている。私は傘を持っていなかったので、しとしとと濡れながら、近くの洋食屋まで歩いた。
あの日も、そういえば、雨だったなあ、と思う。
あの日、初めて、あなたと心が近づいた日。ちょうど同じように、新緑が光る、初夏の午後だった。
悲しそうな私と、申し訳なさそうな、優しいあなたの顔。
「どうしてあなたが振られているの」
私の理不尽すぎる問いかけに、あなたは苦笑いするだけだった。ほかにしようがなかったのだろう。あなたの目の前で、失恋したのはあなたのはずなのに、私は今にも泣き出しそうだった。
「どうして、あなたが選ばれないの。」
さらに私は言った。彼の顔がほんの少し、やわらいだ。
「どうして、きみが泣くんだよ。」
「まだ、泣いてないわ。」
「泣きそうだ。」
「泣かないわ。」
きっぱりとそう言うと、私は正面から彼の目を見据えた。まっすぐ、まっすぐ。
私には、あなたが選ばれないなんて、純粋に信じられなかった。優しくて、不器用で、頼られやすいあなた。
あの子にも、あなたの良さが伝わっていると、そう信じて疑わなかった。あなたなら、あの子とお似合いだと、僻みではなく、嫉妬でもなく、いじけているわけでもなく、ただ単純に、そう思っていた。
「世の中、何か間違っているわ。」
だんだん腹が立ってきた私は、仕舞いには彼をにらみつけながら、そう言った。
「それでいて、あなたは私を代わりにもしてくれない。それは正しいのに、どうしてこんな間違いが起こるの。」
あなたは私の言いたいことの半分も理解していないようだった。ただ、優しい淋しい困った顔で、「ありがとう。」と、「ごめんね。」を繰り返していた。
あの日も私はこうして雨に濡れながら、近くの洋食屋さんに急いだ。お気に入りの、オムライスを食べるために、大学の近くの、いつも行く洋食屋さんまで、いつもよりも早足で歩いた。あなたは疲れと戸惑いで延々と山手線で回っていたという。
私はなんにも変わっていない。うまく気持ちを伝えられない不器用さも、機嫌を損ねると何も言えなくなるところも、傘をささずに雨の中にいるところも、こんな日はオムライスが食べたくなるところも。
足早にカウンターに戻って、山本さんと交代をする。
「いつも林さんは早いわね。気を遣わなくってもいいのに。」
やわらかい笑顔と「じゃあ、行ってくるわね」という先輩らしいセリフを残して、山本さんは外に出る。小柄なのにとても大きく感じる、背筋のピンと伸びた、存在感のある後姿で。
また、カウンターでひとりぼっちになってしまう。
そのとき、ポケットが小さく震える。バイブの振動が嫌いで携帯はいつもサイレントモードにしているのだけれど(大学のころと違って、私に急ぎの連絡などない)、メールが来ると、なぜかバイブのように、ポケットが暖かく小さく震える気がするのだ。あなたからの、メールだけは。
「ありがとう。ごめんね。」
短いメールを見て、私は思わず笑ってしまう。
あなたも、ちっとも変わっていない。優しくて、淋しげで、とても不器用で。
たぶんあなたも、憂鬱な一日を過ごしたのだろう。あのときのように山手線を回り続けるような時間はないだろうけれど、気持ちはきっと、山手線だったに違いない。戸惑うあなたの顔が見える気がして、なんだか一度に、軽くなった。
私のオムライス、あなたの山手線、誰かの何か、きっと、何も変わっていない。私たちは、常にどこかに行きながら、きっとどこにも行けないのだろう。
仕事が終わったら、あなたに会いに行こう。
私は、図書館が大好きだ。なんとなく薄暗い入り口や、きちんと整列し
ている本棚や、あふれんばかりの本のにおいや、涼しくて湿った部屋の空気や、そういうものが、とても好きだ。
本は私を絶対に裏切らないし、図書館は、いつだって私を迎え入れてくれる。
そして私はいつだって、いつだってここに帰ってこれるのだ。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年52号感想その…
- (2025-11-26 13:50:15)
-
-
-
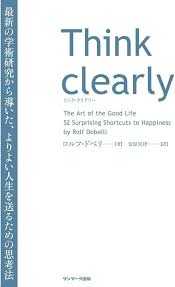
- 読書
- シンク クレアリー ロルプ・ド…
- (2025-11-28 05:00:06)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0942 30代を無駄に生きるな
- (2025-11-28 00:00:15)
-
© Rakuten Group, Inc.