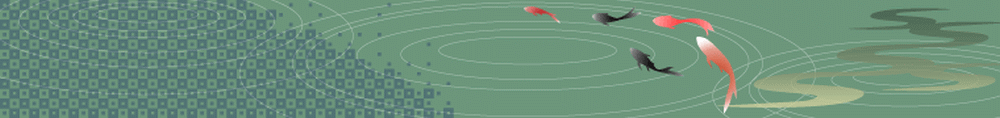日本語版
しかしながら、日本史における天皇の特殊な役割は過小評価されるべきではないでしょう。日本の天皇家は未だに現存する世界最古の王朝として存在しつづけています。なぜ天皇家はこうも長続きし、どのように成立したのでしょうか?
天皇家の起源については、現存する二つの古い歴史書である、8世紀に編まれた古事記と日本書紀のみが伝えているに過ぎません。その記述は非常に神話的で、それをそのまま歴史的事実と受けとめることは出来ません。例えば初代天皇である神武天皇は紀元前660年に即位し、137歳で崩御したなどという、この歴史書以外の歴史資料とはまったくかみ合わない内容が書かれています。
7世紀もしくは8世紀という、これらの歴史書が編まれた時代は、日本が中国を手本とした国家建設を進めていた時代でした。有名なイギリスの歴史家アーノルド・トインビーに言わせれば、日本は中国の模倣によりはじめて文明段階に到達し、その後も中国文明を手本とし続けその模倣を余儀なくされた、とのことです。
日本国家は中国の影響で突然成立したのでしょうか?この問いに対し、我々は否といいます。というのは、日本は既に発達した国家組織をもって文献史料による「歴史」の世界に登場しました。日本の国家形成にはそれ以前に長い前史があるのです。
既に述べたように、日本人の残した文献資料によって日本における国家形成を追う事はほとんど不可能です。先史時代の日本に関する中国の文献資料も存在しますが、それはきわめて僅かであり、その記述も紀元後1世紀までしか遡ることが出来ません。
このように、考古学資料のみが、日本における国家形成の様子を明らかにする鍵となるのです。
ここで少し日本の先史・原史時代の概観とその特徴を述べておきましょう。
考古学では、ユーラシアの大部分の歴史は、その物質文化の発達状況により3つの時代に分けられることが出来ます。これはいわゆる「三時期区分法」といわれ、石器時代、青銅器時代、鉄器時代と区分されます。石器時代はさらに細分され、旧石器時代と新石器時代に分けられます。狩猟採集生活を営んでいた旧石器時代をもって人類史は始まり、新石器時代に農耕・牧畜生活を始めます。
これに対し日本は、この「三時期区分法」のあてはまらない、ユーラシアでも数少ない地域の1つにあたります。日本においては石器時代のあとにいきなり農耕・牧畜を伴った鉄器時代が始まります。すなわち、「典型的な」新石器時代や青銅器時代は存在しないのです。このような状況はユーラシアの古代文明から遠く離れた地域、例えばサハラ以南のアフリカ大陸やポリネシアのような地域で見ることが出来ます。
日本列島はアジア大陸からそう遠くは離れてはいませんが、その地理的位置により日本列島の住民は、望みさえすれば、孤立することが可能でした。この地理的条件は日本の歴史、とりわけ国家形成の歴史に大きな刻印を残しています。
日本の先史時代は四つの時代に分けられます。最古の時代は他の地域同様旧石器時代と呼ばれます。日本列島における旧石器時代の最古の確実な遺物は三万年前まで遡ることが出来ます。
その後、紀元前一万年頃に縄文時代が始まります。この時代名は土器様式に基いています。縄文(ジョウモン)とはドイツ語で「縄模様」という意味です。縄文土器は世界最古の土器の1つであると考えられています。この時代の特質は、その生活が狩猟・漁労および採集に拠っており、農耕は未だ存在していなかったことが挙げられます。この時代の遺跡はしかしながら、この文化は既に定住生活が営まれていたことを示しています。この独特な縄文文化は、「定住を伴う旧石器時代」、もしくは「農耕を伴わない新石器時代」とでも表現することが出来るでしょう。この特殊性は間違い無く、多様な日本の植生にその起源を求めることが出来ます。
弥生時代は初期農耕の時代です。弥生という名前は、この時代の土器が最初に発見された東京の地名に基いています。その開始はこれまで紀元前4世紀もしくは3世紀とされていましたが、つい最近(2003年5月)行われた自然科学的分析によれば、弥生時代は実際にはずっと以前、つまり紀元前10世紀に始まったと指摘されています。農耕に関して言えば、こんにちまで日本の文化におおきな意味を持ちつづけている稲作の起源は、この時代に遡ります。貴人のための墳墓や戦争の存在は、社会の階層化を示しています。いっぽう、弥生文化の広まらなかった日本列島の南北では、縄文文化が継続的に発達しました。
続く時代はいわゆる前方後円墳に代表されます。それゆえに古墳時代と呼ばれます。その時代は3世紀後半から7世紀終わりまでです。弥生時代の階層社会が発達して、奈良における統一日本国家に至ります。
日本における国家形成という今日の講演のテーマに関しては、弥生時代と古墳時代が重要ですので、この二つの時代のお話をしたいと思います。
約一万年続いた縄文時代のあと、弥生時代は始まりました。この時代の初めに稲作が朝鮮半島から伝わりました。それに続いて農耕社会が形成されました。道具の素材として、石のほかに新しい素材である青銅と鉄が加わりました。その他、防御的集落や墳丘墓がこの時代の新しい事象として挙げられます。
考古資料の示すところによれば、稲作の技術は朝鮮半島から日本に伝わりました。その後稲作は急速に九州・本州・四国の各地に広まりました。このスライドは、日本列島最初の農民が使用した、初期弥生時代農具の一覧です。これは石包丁で、稲の収穫に使われました。
ここにみるように、既にその初期から、農耕の基本的な道具が揃っていることが分かります。このことは、日本における稲作や新しい技術が、朝鮮半島もしくは中国にその起源を求めることが出来る裏づけとなります。
住居は縄文時代と大きくは変わりません。この時代の新しい建物としては高床倉庫が加わりました。
この青銅の鐘は農民の祭りに使用されました。この「銅鐸」と呼ばれる青銅の鐘は、本来朝鮮半島からもたらされたものです。しかしながら日本においてもすぐに独自の生産が行われるようになりました。時代の変化と共にその外観が重視されるようになり、大きなものが作られ、楽器という本来の機能は副次的なものになりました。
これらの青銅製の武器は中国の武器を模倣したものです。これらの武器は本来の機能を喪失し、祭器として使用されました。
弥生時代には様々な様式の墓が営まれました。このスライドは北九州の中期弥生時代の墓地群です。大甕が棺として使用されました。副葬品の差異によって、この墓地群内での被葬者の階層社会化が窺えます。このような装身具や中国の銅鏡は、特別な人物の墓からしか見つかりません。日本海沿岸には四隅突出形墳丘墓が社会の一部階層の為に築かれ、他の墓とは明らかに一線を画していました。
考古資料からは、地域の集団間で戦争が行われていたことが読み取れます。戦争の犠牲者の遺体が弥生時代の墓から多く見つかっています。
このスライドは、防御のための堀を備えた集落です(吉野ヶ里遺跡)。弥生時代にはこのような防御的集落が多数営まれました。
ここに見るとおり、階層的社会分化と戦争は、農耕の開始と共に始まりました。中国の史料が伝えるように、この時代の支配者はおそらく祭司的役割を果たしていました。このスライドは、大阪にある紀元前52年頃の弥生時代集落の遺跡です(池上曽根遺跡)。集落の中央にあるこの巨大な建物は祭祀に使われたと見られています。
支配者は使者を送って中国から様々な貴重品を得ていました。これは九州北部で発見された有名な金印です。その印面には「漢により任命された倭の奴国の王」という字が読み取れます。紀元後57年に中国皇帝から北九州の奴国の王に贈られたこの印鑑については、東漢(後漢)の記録に詳しく述べられています。銅鏡も中国・朝鮮から頻繁にもたらされました。このような海外の貴重品によって、支配者はその威厳を誇示しようとしたのです。
貴重品のみならず、実用品、とりわけ鉄と青銅も、大きな意味を持っていました。この時代の日本では鉄も銅も製錬されていませんでした。その重要性はこんにちの石油と比べることが出来るでしょうか。こんにちと同じく、この時代も重要な資源の交易路の支配をめぐって戦争が行われたことでしょう。例えばこの防御的集落(妻木晩田遺跡)は山の上に営まれています。このような高地性集落は農業よりもむしろ防御を目的に営まれたものです。このような集落はしばしば中国や朝鮮半島との交易路であった海路に沿って作られています。
後期弥生時代には既に、続く古墳時代の兆候を、高い農業生産と交易上の要地であった地域に認める事が出来ます。
これは弥生時代後期の近畿地方に特徴的な墳丘墓です(有年原・田中遺跡)。支配者の墓は外見上社会のほかの階層の墓とは大きく異なっています。しかしそれらは同一の敷地に営まれました。墳丘の上にはたくさんの土器と器台が並べられています。この土器と器台は古墳時代には埴輪へと発達してゆきます。この発達は主に中国地方で起きました。
墓の形は地域により大きな違いがあり、いわゆる前方後円形の墳丘墓は奈良地方のものです。円形の部分は主体部で埋葬が行われ、方形の部分は元来円形部分への陸橋だったものです。方形部は続く古墳時代には巨大化し、死者の祭祀の場所として大きな意味を持つことになります。
これは奈良にある箸墓古墳の模型です。こんにち多くの研究者が、この墓は中国の歴史史料に言及される女王卑弥呼のものであると考えています。彼女は239年に魏(ウェイ)に使者を送り、中国皇帝から日本の女王の称号を受けています。この墓は最古の前方後円墳の一つで、既に述べたとおり、この墳形は既に後期弥生時代の近畿地方に見ることができます。この古墳に副葬された埴輪は、その起源を弥生時代の中国地方に求めることができます。古墳時代開始期の古墳は弥生時代の墳丘墓と多くの共通性をもっているのです。3世紀半ばに様々な地域の支配者たちはその葬礼を混合し、共通の葬礼を作り出しました。それゆえに、各地域の支配者は連合を組み、一人の王もしくは卑弥呼のような女王を選出したと考えられています。この推測は、中国の史料からも裏付けられます。
これは前方後円墳の分布域です。前方後円墳は地方的な墳形から、いまや日本全国の標準的なものへと変化しています。この地図はまた、日本における最初の政治的かつ宗教的統一がどのくらいの範囲に及んでいたかを示しています。土器に関しても、その地域的な差異が小さくなります。
これは初期古墳時代の典型的な竪穴式石室です(黒塚古墳)。この中には木棺が置かれました。鏡もしくは呪術的意味を持つ腕輪がが主な副葬品でした。弥生時代には既に九州北部の墓に副葬されていましたが、初期古墳時代にも鏡は頻繁に副葬されています。
その鏡の中に、三角形の縁をもつ型式があります。この型式の鏡は中国の史料に基いて、中国皇帝から、上述した女王卑弥呼に贈られた鏡と推測されています。これは三角縁神獣鏡の分布図です。この線は同じ鋳型から作られた鏡同士の関係を示しています。これらの鏡は日本国内において大量に複製され、また模造品も作られました。この分布図からは、分布の中心が近畿地方にあったことが分かります。このことは、王もしくは有力な支配者が鏡の流通をコントロールしていたことを窺わせます。この近畿地方の支配者はふつう「大和政権」と呼ばれ、この政権がこんにちの天皇家の祖先であったと考えられています。日本最初の統一政権は、おそらく政治的・祭儀的共通性を基盤としていたものと思われます。
古墳時代初期の支配者は、弥生時代同様、祭司的な役割をもっていたと考えられています。副葬品は基本的に祭具です。つまり、鏡、腕輪、石製のミニチュア容器などです。古墳時代には支配者の墓は通常の墓とは離れた場所に営まれました。階層間の差は弥生時代よりも大きくなっています。
これは神戸にある五色塚古墳です。この古墳は5世紀初めに築かれ、近年造営当時の姿に復元されました。斜面には丁寧に築かれた葺き石を、またテラス上には円筒埴輪をみることができます。
この弥生時代からの伝統を多く見ることが出来る初期古墳文化は、5世紀に大きく変わることになります。
5世紀の日本に関する文献史料に目を向けて見ましょう。高句麗(コグリョ。こんにちの北朝鮮)王である広開土(クワンゲト)王の碑文によれば、5世紀のはじめに日本の兵士が朝鮮半島南部、すなわち新羅(シルラ)と百済(ぺクチェ)に侵入し、高句麗軍に敗れたことが記されています。一方、中国の年代記は、日本の大王が421年から478年の間に五世代に渡って中国南部の宋(スン)王朝に使者を送り、日本及び朝鮮半島における中国総督の称号を要求したことを伝えています。
この時代の日本にも、同時代の銘文が鉄剣に刻まれています(稲荷山鉄剣)。この非常に短い銘文からは、大王が親衛隊もしくは常備軍のようなものを組織していた可能性が窺えます。この銘文は多分朝鮮半島もしくは中国からの移住者によって書かれたものです。5世紀の日本では文字の使用はまだ常習ではなく、我々は考古史料に頼らざるを得ないのです。
5世紀には巨大前方後円墳の分布の中心は大阪にありました。最大のものは大阪府の大仙古墳です。長さ486m、高さ35mを測り、ある試算によれば、その建設には2000人の労働者で15年かかったものと推定されています。その面積は、世界最大の墳墓と呼んでいいものです。日本は決して全てのことで「盆栽の国」ではないのです。
この墓は19世紀から、宮内庁によって仁徳天皇の墓とされていますが、発見された遺物からは仁徳天皇の推定在位期間よりややのちの時代のものであるということが分かっています。ついでながら、大きさ上位30位の前方後円墳のうち25までが皇族の墓と指定され厳しく保護されています。これまでのところこれらの古墳で学術的な発掘が行われたことはありません。
このような巨大な前方後円墳は近畿地方のみならず、岡山、宮崎、群馬のような他地域にも造営されました。このことは当時の日本国家のあり方、すなわち大和政権の指導による様々な地域の首長の連合体という性格を推測させます。
副葬品としては鉄製の武器、とくに胸甲(短甲)が支配的です。支配者の社会的性格は祭司の指導者から軍事的指導者に変化しています。時に大量に副葬された鉄器は、当時の支配者のこの金属への並々ならぬ関心を示しています。しかしながら、今のところ5世紀において日本で鉄が生産されていたという考古学的証拠は発見されていません。おそらく鉄の大部分は鉄テイの形で朝鮮半島から輸入され、日本国内に流通していたのでしょう。大和政権は鉄の流通をコントロールし、鉄製武器の生産を独占することにより、支配を確立しようとしたと思われます。既に述べた日本による朝鮮半島での軍事活動には、おそらくこの政治的・経済的背景が関係していたと思われます。日本は朝鮮半島に兵士(援軍・傭兵)を送り、その見かえりに鉄や新しい技術を受け取っていたのでしょう。
中国との接触は政治的なものに限られ、文化交流はもっぱら朝鮮半島南部、すなわち百済とカヤとに集中していました。5世紀におけるユーラシア内の文化交流の驚くべき例として、新沢千塚126号墳から出土したローマ・ガラスを挙げることが出来ます。これらの品はシルク・ロードと朝鮮半島を経由して西洋から来たものです。日本はシルク・ロードの東端の終着駅であり、東西交渉はその痕跡を日本の貴族層の文化に残しているのです。
この時代の日本には都市も城塞もありませんでした。貴族は集落外に方形のプランをもつ館を築いて住みました。このような館の一つで見つかったたくさんの倉庫群(法円坂遺跡)は、この館が経済的・政治的中心として機能していたことを示しています。この時代の城郭遺跡の完全な欠如は、日本国内では戦争が頻繁には行われなかったことを示している、と考えられます。
5世紀の一般的な住居の復元例もお見せしておきます。
8世紀はじめに編まれた日本の歴史書、古事記と日本書紀は、様々な政治的事件について伝えており、その記述は6世紀以降からについて詳しくなります。これらの書物は、皇位継承をめぐる紛争や北九州での反乱など、6世紀前半の政情不安について伝えています。
考古学的見地からは、この時期に大和政権の鉄流通や武器生産の独占体制が崩れたことが推測されています。時を同じくして日本国内での鉄生産が始まったと見られています。おそらく上述の政情不安はこの経済的構造変化と関わっているのでしょう。
6世紀には日本は中国との接触はほとんどありませんが、朝鮮半島との文化交流は頻繁に行われました。それにより、中国北部を支配していた騎馬民族の文化が朝鮮半島経由で日本に伝えられました。この時代の典型的な副葬品は馬具もしくは冠です。武具としては北東アジアの騎馬民族が使用したような小札甲(ケイ甲)が主流になりました。帯金具、馬具、金(金銅)製の装身具は「(ゲルマン)民族大移動期」の文化の騎馬民族的要素として、ヨーロッパの考古学者にもなじみが深いものです。大阪の通称安閑天皇陵から出土した同時代のペルシア製ガラス碗は、特別な対外交流を物語っています。
6世紀の古墳は5世紀のものにくらべ全般に小さくなっており、中国に起源を持つ横穴式石室が急速かつ広域に広がりました。副葬品の量や墳丘の大きさはもはや重要ではなく、副葬品の品質や石室の精巧さが重要になったのです。6世紀にはまた、関東地方を中心に形象埴輪が流行しました。このような埴輪像は墳丘の上や周囲に並べられました。大型古墳のほかに、有力農民のためのより小型の群集墳が数多く築かれました。3世紀から7世紀の間におよそ20万基の古墳が日本列島内に築かれましたが、その大部分はこのような群集墳です。
6世紀最大の事件は538もしくは553年の百済からの仏教伝来でしょう。最初の仏教寺院は既に6世紀末に建設されました。仏教の導入により、古墳の造営は徐々に流行から外れていくことになります。
589年に隋(シュイ)王朝により、そしてその後継者である唐(タン)王朝により618年に、中国は400年に及ぶ分裂から統一されました。この東アジアにおける政治的大事件は、近隣諸国に大きな影響を及ぼしました。日本政府は対外的には、100年に及ぶ中断ののち、中国に使者を送って外交関係を回復しました。対内的には、国家の中央集権化がこの時代の大きな目標となりました。
7世紀のはじめ、推古女帝と聖徳太子は仏教の権威を借りて日本の中央集権化を試みましたが、この試みは有力貴族の抵抗に会い失敗しました。聖徳太子の築いた法隆寺は、驚くべき良好な保存状態でこんにちも奈良の地に立っています。一方7世紀はじめには前方後円墳はもはや築かれなくなっていました。この現象はおそらく推古女帝の政治改革に関連するものとみられます。皇族や貴族の墓としては、中国の影響を受けた方形や八角形の古墳が築かれます。
645年、天智天皇はいわゆる大化の改新を始めました。彼は新たに中国を手本とした中央集権的な国家行政組織の建設を目指します。その第一歩として、646年に古墳の造営は上層階級のみに制限されました。実際には多くの群集墳がその後も築かれつづけたのですが。
7世紀後半になると、朝鮮半島の政治情勢は日本にとり不利になる一方でした。660年、中国の軍隊は日本と連合していた百済を征服しました。3年後、日本は百済を奪還するため軍隊を朝鮮半島に送りましたが、この企図は白村江(ぺクチョンガン)における唐・新羅連合艦隊に対する大敗に終わりました。
この敗戦に衝撃を受け、中国の侵略に備えまた対内的威信を保つために、日本政府は朝鮮式山城を西日本各地に築城しました。日本にとって、これは最初の外圧でした。
一方で日本は改めて中国文明の先進性を悟り、わき目も振らずに、中央集権的な徴税システム、律令の施行、国史の編纂、(行政言語としての)漢字の使用、中国式都城の建設など、中国の行政システムの模倣を図りました。同時に仏教は広まり、仏教式の火葬が流行しました。
7世紀の終わりに古墳時代は幕を閉じます。中国や朝鮮半島の影響を多分に受けた壁画で有名な高松塚古墳は、終末期古墳のもっとも素晴らしい一例でしょう。
このようにして日本は最初の統一的中央集権国家を建設し、東アジアでの「パクス・シニカ」(冊封)体制における地位を得ました。しかし我々は、中国の巨大な影響にもかかわらず存在した日本の独自性を強調せざるを得ません。日本においては、貴族階級に対して天皇は制限された権力しか持たず、儒教は社会一般には浸透しませんでした。この日本の「原始性」は、のちの日本の歴史に影響を与えます。日本は東アジアの中でも独自の道を歩まざるを得なくなるのです。
最後に、もう一度まとめておきたいと思います。日本の考古学者の間では、日本国家がいつ成立したかという議論があります。この議論は「七五三論争」と呼ばれます。3世紀には最初の、均質的な文化を伴う地域を越えた連合が成立し、日本列島の大部分を包含します。5世紀末までには行政システムが発達し、日本は最初の対外戦争を行います。日本の天皇家はおそらくこの時代に起源をもつのでしょう。この3世紀から5世紀にかけての時代は、初期国家もしくは原初国家と呼ばれるものです。7世紀末までには中央集権化された中国をモデルとする国家が建設されました。
日本における国家形成において、中国や朝鮮半島の役割は看過できないものがあります。何よりも、この両国から多くの移民・技術者が日本に来ました。こんにちの「均質な」日本民族は、日本の先史・原史時代の混成住民に起源をもつのです。
以上は断絶の無い、しかし劇的な変化でした。日本の原史時代は外的な影響を自分の文化的アイデンティティに発達させていった、受容と自己変容の時代でした。日本のエトスは既にこの時代にも認める事が出来、おそらく、西欧文明の影響に対処せざるを得なかった19世紀後半以降の日本の歴史と比較することも可能でしょう。
ご静聴ありがとうございました。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- フランスあれこれ・・・
- 【ソルボンヌ広場界隈】2025年11月28…
- (2025-11-30 04:49:05)
-
-
-

- 国内旅行どこに行く?
- 12月14日まで!鬼滅の刃ナイトウォー…
- (2025-11-30 22:10:24)
-
-
-

- 海外生活
- 10年のアニバーサリー
- (2025-11-13 22:52:13)
-
© Rakuten Group, Inc.