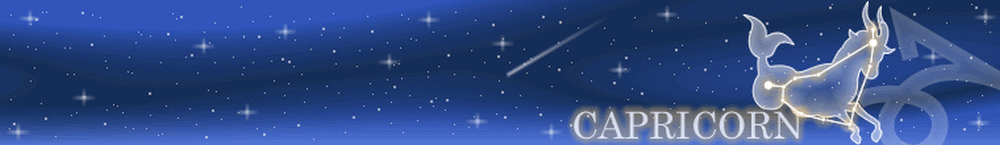2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2007年04月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-

『名もなき毒』
地元紙に連載された時は嬉しくて久しぶりに新聞小説を読んだけど、なかなか話が進展せずあえなくリタイア。単行本になると評判がよろしいようなので再チャレンジ。新聞で読んだのは1/4程度でやや長い前置きの部分だった。半分過ぎた辺りから俄然面白くなる。犯人探しのミステリーとしては物足りないが、様々な家族の物語として面白かった。お人よしの一流企業サラリーマン、絶縁状態にある田舎の父母、おっとり妻、その父親は資産家の会社会長、うそつきのお騒がせ女、泣いて謝罪する老父、殺害された老人、孫の女子高生、外資系企業に勤めるシングルマザー、老父の愛人、定職につかない演劇男、運送会社を経営する父、コンビニの元店員、育ての母である祖母、死期の迫った退職警官、元妻・・・・特殊なようで意外と普通にいそうな人々ばかり。切っても切れない家族の縁。成人しようが家庭を持とうが親はいつまでも子のことを心配し、責任を感じるものだというしがらみのあり様の描き方が実に上手い。自殺した女性の遺品から青酸が見つかったが入手経路も飲ませた方法も解明されないまま犯人と断定するのは強引すぎるし、当然の疑問を誰もが無視したままなのは不自然だ。と思ったらここに仕掛けがあった。やはりねぇ。青年の性格と境遇や経済状態を考えたら犯行の動機はやや薄弱なのだけれど、最後の山場であのセリフを言わせるために必要なコマだったと納得。プロットの巧みさはさすが宮部みゆき。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>幻惑されて 上 / ロバート・ゴダード博士の異常な発明 / 清水義範 となり町戦争 / 三崎 亜記 (読了)<今日の音楽>Aerosmith / Just Push Play
2007.04.30
コメント(0)
-
昭和の日
いや~、聞いてないよー。今日は「昭和の日」だってさ。初耳。「たかじんのそこまで言って委員会」を見て知ったから、関東地方ではまだ知らない人が多いはず。いや、まさかそんな。。。新聞を急いで広げると「事件・人・話題」面にちゃんと書いてあった。てっきり「みどりの日」だと思ってたら、みどりの日は5月4日に移動してたのね。5月4日って去年までは連休構成以外になんの趣旨もない「国民の祝日」だったのに、立派な名前がついてよかったよ。で、今日は「激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす」のが趣旨・定義となっている日。昭和を偲ぶ日ができるなんてねぇ。。。。昭和生まれには違いないけど激動の日々は経ていない。なのに、なんだかすごい年寄りになった気分。そういえば、昭和の時代はゴールデンウィークじゃなくて、飛び石連休だった。近所の幼稚園は5月1日2日は振り替え休日(後日振り替え授業をするという意味)となって完璧な9連休だとか。昭和にはなかった発想だ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>名もなき毒 / 宮部みゆき (読了)博士の異常な発明 / 清水義範 日本語の乱れ / 清水義範 <今日の音楽>Aerosmith / Just Push Play
2007.04.29
コメント(14)
-

洋風懐石@「勝」
うちは結婚記念日というものを祝ったことがない。いつも見事に忘れてる。25日は給料日でもないし、連休前の慌しさに掻き消えて過ぎてしまってから「あ、そーいえば・・・」と気づくことの繰り返し。潜在意識で避けたがっているのかもしれない。お互いなかったことにしたいと。今年は一応Tも覚えていたし子供の年から勘定すると節目に当たる事も判明。急遽レストランを予約したが、Tの都合でドタキャン。で、今年もいつものように当日スルーとなった。今日はその振替で食事に。ごく近所のレストランなもんで盛り上がりに乏しく、Tはすっぽん鍋(先週食べたばっかりなのに)が食べたいといいながらパンを2回お代わり。あとで筍ご飯がでてきてびっくり。kellyは冷酒を手酌で。 空豆のムース、トマトのピュレ あかざエビの香草焼き、ナス、筍 ポタージュ スズキのポアレ、キャベツのソース、グリーンアスパラ、インゲン グレープフルーツのグラニテ ヒレステーキ、トマト、ナス、筍 筍ごはん、味噌汁、香の物 苺とクリームのムース、ラムレーズンアイスクリーム、フルーツ コーヒー ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>名もなき毒 / 宮部みゆき食べる日本語 / 塩田丸男日本語の乱れ / 清水義範 <今日の音楽>Aerosmith / Just Push Play
2007.04.28
コメント(6)
-

『福沢諭吉は謎だらけ。心訓小説』
近代日本の知の巨人でありながら、多くの謎と誤解を遺している福沢諭吉。彼の著作や三女が書いた本、司馬遼太郎が書いたもの、慶応義塾大学の福澤研究センターの発表などを検証し、諭吉とは何者だったのかを解く。というと全然つまらなさそうだけど、話はガラリと変わって認知症老人介護を巡るドタバタ家族劇も同時進行して、とても読み易く面白い小説に仕上がっている。姉妹本「漱石先生大いに悩む」は中途挫折したままなのだけど・・・・日本で初めて授業料を徴収したのが慶応義塾だそうだ。明治六年の改暦の時に「改暦弁」という解説ハウツー本を出して大ベストセラーになり、この印税収入が慶応義塾の財政基盤となったらしい。合理的経済活動を説くだけでなく実践していたが拝金主義者ではなく金勘定は大嫌いだったと三女が書いている。司馬遼太郎は諭吉の偉大さを認めながらも大きな瑕きんがあると非難している。問題になっているのは「時事新報」の「脱亜論」とその後のアジア蔑視論説である。この本では、脳卒中の発作で失語症となった後の諭吉の論説は他の論説委員の手になるものが混じっている形跡がある、という説を推している。人の言動が正しくそのまま未来へ伝わるとは限らないし、時代によって評価が変わるのはこの世の常で致し方ないし、それが後世の人にとって謎となるのだということがわかる。心訓七則世の中で一番楽しく立派な事は、一生涯を貫く仕事を持つ事です。世の中で一番みじめな事は、人間として教養のない事です。世の中で一番さびしい事は、する仕事のない事です。世の中で一番みにくい事は、他人の生活をうらやむ事です。世の中で一番尊い事は、人の為に奉仕して決して恩に着せない事です。世の中で一番美しい事は、全ての物に愛情を持つ事です。世の中で一番悲しい事は、うそをつく事です。福沢諭吉作として流布している心訓七則は、慶応義塾図書館のHPできっぱりと否定され参考文献を呈示している。現在も作者不詳。作中のS氏(著者の分身)は九州で昭和25年(諭吉の50回忌)ごろに作られたのではないかと想像している。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>名もなき毒 / 宮部みゆき正直じゃいけん / 町田康<今日の音楽>70's American hits
2007.04.27
コメント(4)
-
廃業
顧客のとある会社が急に廃業することになった。先月廃業した近所の同業者は後継者がいないというのが理由で、国道に面した広大な敷地はあっという間に更地になった。経営不振で廃業という会社もあるが、そういうのは珍しくてギリギリまで踏ん張って不渡り手形出しまくったあげく倒産というのが普通。うちの子会社はペーパーカンパニーなので事務処理が面倒になって会社清算した。と廃業にもいろんな理由がある。で、この会社はわが社の顧客の中では中程度の売り上げがあって、公共事業も請け負って経営順調。なのになぜ? と訊いたら「本業」が忙しくなったので、とのこと。オーナーの名前は各方面で有名だから表には出せず、登記簿上はうら若きオーナー夫人が社長になっている。その社長が事務所では「あねさん」と呼ばれていたと集金人からの報告があって以来、経理担当M嬢が電話する回数が減る。あの業界に取り立ての電話してるんだもんね。エライよ。堅気になる転業するために興した会社と思いきや、子会社共々まさかの店じまい。とっても景気が良さそうなんだけど、「本業」について詳しく聞くのは差し控えておいた。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>名もなき毒 / 宮部みゆき正直じゃいけん / 町田康福沢諭吉は謎だらけ。心訓小説 / 清水義範 (読了)<今日の音楽>Earth wind &Fire / Millennium
2007.04.26
コメント(2)
-

『エバー・アフター』
貴族の老女がグリム兄弟をお城に呼んで祖先のフランス王妃の話を聞かせるというスタイルになっている。シンデレラを元ネタとしながらも、これがシンデレラ伝説の真実の話としている小憎らしい設定の映画。ペロー童話やディズニーのように魔女やかぼちゃの馬車が登場しないところが本当っぽいし、中世の田舎の景色や衣装や舞台装置がとてもいい。黒豚を連れてトリュフ探しに行く場面がナイス。「ビビディ・バビディ・ブー」はないけれど、その代わりがなんとレオナルド・ダヴィンチ。宮廷画家としてフランスにやってきた(しかも「モナリザ」持参で)彼が王子の話相手となったりヒロインを力づけたりの重要な脇役。キーアイテムの靴を拾うのもレオナルド。この靴、英語では「スリッパ」。ぺったんこではなくヒールの高い靴だけど、かかとがないスタイルの靴(ミュール)はスリッパと呼ばれる。うすい羽のついたブルーのドレスがきれいできれいでまるでおとぎ話のよう。っておとぎ話だったわー。継母に虐められる少女をドリュー・バリモアが好演。体力も教養もあり運動神経も抜群で気が強い、そして素直さや可憐さも併せ持っている。世間知らずだが決してバカではない王子の后としてはそうでなくっちゃ、と思わせる役柄。魔女顔のアンジェリカ・ヒューストンがえげつないな継母を演じて上手すぎ。ヘタな恋愛映画よりもよっぽど面白かった。1998年の作品。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>正直じゃいけん / 町田康福沢諭吉は謎だらけ。心訓小説 / 清水義範<今日の音楽>Earth wind &Fire / Millennium
2007.04.25
コメント(8)
-

『銀座の怪人』
1970年代以降20年以上にわたって絵画・骨董の贋作を日本で売りさばき、2004年FBIに逮捕されたイラン人画商イライ・サカイを追ったルポ。骨董・美術品は眺めるだけで充分、もともと胡散臭い業界の話だからしてたいして興味はなかったのに読んでいく内にすっかり引き込まれて迫力満点。著者はNY在住で英語堪能らしく本人との会見に成功している。「銀座の怪人」は気のよさそうな小太りのおっさんだ。『世界をだました男』のアバネルもそうだが、一流の詐欺師には人を惹きつける魅力がある。ハングリーさとコンプレックスも必須条件か。日本の風土と時流を上手くつかんだサカイの「商活動」は古代ペルシャの秘宝贋作「三越事件」で発覚。やがて岡田社長の解任へと進展するが、その発端に松本清張がかんでいた事実が興味深い。この辺りは当時を知っているので読み出したら止められない。国立大学教授、一流画廊、美術評論家を巻き込んだ贋作事件は舶来品崇拝で権威に弱い日本が世界一のカモとなった。1970年初頭の絵画ブームには全国の美術館に贋作がばらまかれ、バブル期には通貨代わりだった絵画がやがてババ抜きのごとく被害者が加害者となって流通する。しかし関係者は「恥」を隠すため沈黙。日本の文化がおのずと招き入れた陰謀だったと著者は結んでいる。たしかに美術取引の豊かな土壌と経験があるヨーロッパではこんなに上手くいかなかっただろう。失踪した古美術商や贋作作家は未だに行方不明。レゾネも信用できなくなった。イライが持ち込んだ贋作は官・学・実業界に広く深く蔓延している。中部電力、熊本県立美術館、横浜美術館の絵画のその後はどうなったのだろうか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>銀座の怪人 / 七尾 和晃(読了)<今日の音楽>Earth wind &Fire / MillenniumJorge Bolet / Liszt : etudes d'execution transcendante
2007.04.24
コメント(0)
-

『失われた時間』
老人と少女が住む屋敷では夜7時45分から翌朝まで使用人夫妻は立ち入り禁止となり、夜ごと屋敷からは少女の悲鳴が聞こえる。そして、屋敷の主人が殺害される。容疑者は絞られるが、アリバイを調べるうち10分間の矛盾が生じる。謎をとくのは私立探偵といった古典的なミステリー。老人の行状が明らかになると、この殺人が歓迎ムードとなって犯人探しは二の次になってくる。メインはあくまでも「失われた10分間」の謎。しかし、これが作為的なアリバイ工作でないことは明らか。そして、「失われた10分間」の謎は最後にふとしたことから解ける。論理的な解明でなく、ごく自然に呆気なく。でもねぇ、他所の家の時計はいつも合ってるって保証はないでしょうに。。。。ま、人の心理の深さを描いているのだけど、単純にエラリークイーンのなんとかの悲劇を連想。出来事は面白いのだけどどうも盛り上がりに欠ける。緊迫感がないのだ。翻訳はセリフの書き分けができてなくて平坦、誤訳と思われる言葉も発見してイマイチ。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>銀座の怪人 / 七尾 和晃失われた時間 / クリストファー・ブッシュ(読了)<今日の音楽>Earth wind &Fire / MillenniumSalene Jones / sings Jobiim with the Jobim'sJorge Bolet / Liszt : etudes d'execution transcendante
2007.04.23
コメント(0)
-

『東京番外地』
元テレビディレクターの著者と彼をライターにスカウトした(文中では「筆おろし」したと表現)編集者が二人で東京を歩き回ったルポ15編。行き先の条件は、「過剰であるか、希薄であること。自由である。澱のように滞っている。エアポケットのような施設・・・・」 東京拘置所、身元不明相談所、東京都慰霊堂、芝浦と場(屠場)、多磨霊園など死の匂いのする場所のレポートが特に詳細。TDRのアトラクション「イッツアスモールワールド」は死後の世界のように感じる、黄泉の国のようだと書いている。そんなことは思いもしなかったが、水の上を行くライドは三途の川の舟なのか・・・まるでなにかにとりつかれているような独特のタッチがある。山谷のドヤ、上野公園、東京タワー、皇居といった賑わう場所のレポートにもそこはかとない寂しさが漂う。西郷隆盛と西南の役の影響、代々木上原のモスクの寛大さ、東京入国管理局の外観が拘置所に似ているのは偶然でないかもしれない、という記述が特に印象に残った。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>東京番外地 / 森達也(読了)李陵・山月記 / 中島敦(読了)失われた時間 / クリストファー・ブッシュ<今日の音楽>Jorge Bolet / Liszt : etudes d'execution transcendante
2007.04.22
コメント(2)
-

『目の玉日記』
白内障というと老人定番の病気で手術するのは60代以上だと思っていた。小林よしのりはTと小中学校が一緒、家も近かったけど「運動神経が鈍すぎて遊び相手にならんやった」(@T)という。も一人の有名人同級生甲斐よしひろとは気が合ってよく遊んだらしい。甲斐と小林は同じ高校に進んだが二人の仲が良かった形跡はなし。この3人を比較すると外見はTが一番老けているが、裸眼2.0老眼なしという日本人離れした視力で未だに眼鏡は持っていない。義母も眼鏡を買ったのは60過ぎてからというので良い遺伝子をもらったのだろう。で、50歳そこそこの小林がかかった白内障。その症状が克明に漫画で描かれるので非常によくわかる、しかも失明寸前の状態だし・・・あ然。手術の様子も話には聞いたことがあるが、百聞は一見にしかずで漫画だとよくわかる。水分の補給が少なすぎると目の血管が細くなって網膜が薄くなる、というのは初めて知った。水分って体にすみずみまで影響するんだな。小田原の佐伯眼科といえばピーコが眼球摘出した時にたびたびマスコミに登場した有名なクリニック。しかし、他の患者が後ろにずらりと座っている丸見えの診察室ってプライバシー尊重の今時珍しい。大勢の他人が見ている前で医者に怒られる図が笑える。なんで早く治療しなかったんだ?!目は大切。近視乱視入り混じるkellyの目の衰えは人より激しいだろう。コンタクトレンズの度は買いに行く度に上がる。景色も本も映画もTVも見られなくなったら楽しみは半減どころじゃない。歯は入れ歯でなんとか凌げるけど目の代わりはない。目だけに限らず体の異常には早めの対処が必要とつくづく思うのだった。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>東京番外地 / 森達也目の玉日記 / 小林よしのり (読了)<今日の音楽>Jorge Bolet / Liszt : etudes d'execution transcendante
2007.04.21
コメント(6)
-

一番眠れた映画
風邪の一歩手前みたいな状態がずっと続いている。朝夕は洟とくしゃみの連続、昼間はだるねむ状態でスキッとしない。治療中の右の奥歯が噛むポイントによってズキッと痛んでいた。先生に訊くと「神経のない歯が痛むはずはないんですがねぇ、様子を見ましょう」と。原因不明の痛みで気分はどんより。今朝から右の耳下腺が腫れてきて耳の奥が詰まったかんじ。中耳炎っぽい。と同時に奥歯の痛みが消失。本当は耳の神経に障っていたらしい。奥歯と内耳はすごく近い。あー、やっと週末。明日は何の予定もなくてラッキー。一日ごろごろして眠り倒そうなんて思いながらお風呂にぼんやり浸かってると 「今までで一番眠れた映画はなんだろう?」という課題が頭に浮かんだ。やはり、「めぐりあう時間たち」がダントツに眠れた。 疲れきって一人でレイトショーに行ったわけではなく、真昼間に喋りたい盛りの女3人で見に行って3人が3人とも微妙な時間差で眠ってしまった。終了後お茶しながらそれぞれの話をつきあわせてみたがあらすじさえ不完全。「ダロウェイ夫人」が呪いの本のように時代を巡っていく、って「リング」かよ・・・起伏のない暗くてどんよりした映画だったけれど、高尚すぎてついていけなかったのが真相だろう。「 ヴァン・ヘルシング 」も喧しい音響やド派手な特撮にもかかわらず合間でけっこう寝てしまった。不思議だ。たまには韓国映画を、と借りた「二重スパイ」は見ると必ずうたた寝してしまって出演者も話も全然記憶に残らないまま返却。「バッファロー66」もかなり眠って、なんであんなにもてはやされたのか分からずじまい。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>東京番外地 / 森達也中庭の出来事 / 恩田陸 四畳半神話大系 / 森見登美彦 <今日の音楽>Jorge Bolet / Liszt : etudes d'execution transcendante
2007.04.20
コメント(10)
-

『きつねのはなし』
いいねぇ・・・こんな話にこんな表紙。大好き。古道具屋の女主人とアルバイト学生、古い屋敷、着流しの主人、節分祭、からくり幻燈、狐の面、そしてケモノ。短編4話がそれとなくニアミスして関連がありそでなさそな雰囲気、なんだか秘密がありそうな曖昧さにゾクリとする。京都の町には薄闇が似合う。「水神」のダイナミズムに圧倒される。所詮小説は嘘話。完璧に辻褄を合わせれば一層嘘くさくなる。ましてや己の狭小な体験と引き比べてリアリティが有るとか無いとか言って評価するのは愚の骨頂。イメージが伝わってくるかどうかが肝心。なんだか分からないけどこんなことがあった、っていう話は意外とすんなり胸に収まる。大嘘だとわかっていても。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>中庭の出来事 / 恩田陸 きつねのはなし / 森見登美彦 (読了)<今日の音楽>Astrud Gilberto / The Girl from Bossa Nova
2007.04.19
コメント(0)
-

『禁じられた楽園』
世界的なアーティスト、感じる視線、失踪、烏の絵、熊野の山、謎の財団、ヤタガラス、死者の映画、サブリミナル・・・・道具立ては充分、仕掛けは大きく、導入部の迫力満点。ひたひたと迫る見えない恐怖と謎。恩田陸のこの手の話はホラー・ファンタジーとでもいうのだろうか、ぐいぐい引き込まれる。なのに終わり方がいつも中途半端だ!なんでもかんでも解決してきっちり完結してほしいわけではない。謎が残ってそれが程よい後味となる話だってある。が、これなんかもう脱力感いっぱいの最後でがっくし。話の最後なんて意外と覚えてなかったりするもんだけど途中が面白ければそれでいいのか。いい夢みせてもらいました、って満足すべきなのかなぁ。のっけから出てくる「インスタレーション」という言葉がわからなかった。文脈から美術あるいはデザイン関係の用語とわかるが、これって一般人が知ってて当たり前の言葉なのか。インスタレーション[installation] (原義は、取り付け・据え付けの意) 現代美術において、従来の彫刻や絵画というジャンルに組み込むことができない作品とその環境を、総体として観客に呈示する芸術的空間のこと。(大辞林より)なるほど、インスタレーションが主人公の話なのだった。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>禁じられた楽園 / 恩田陸 (読了)きつねのはなし / 森見登美彦<今日の音楽>Adam Harasiewicz / chopin: the 21 nocturnes the 26 preludes
2007.04.18
コメント(0)
-

『太陽の塔』 森見登美彦
「この手記を始めるにあたって、私はどこで生まれたかとか、どんな愛すべき幼稚園児だったかとか、高校時代の初恋はいかにして始まりいかにして終わったかとか、いわゆるデビッド・カッパーフィールド式のくだんないことから初めねばならないのかもしれないが、あまり長くなると読者も退屈されると思うので手短にすませよう。」 という一文から始まる。めちゃ好みのタイプ。いや、顔ではない。「現在の私は「休学中の五回生」という、大学生の中でもかなりタチの悪い部類に属している。」 が最初の章の終わり。 次の章は 「大学に入ってから三回生までの生活を一言で表現すれば、「華がなかった」という言葉に尽きるであろう。」 で始まる。 その次の章が 「しかし、そろそろ社会復帰は無理という色合いが濃くなり、これ以上男だけのダンスを踊ると本当に後戻りできなくなる、・・・・・」 で始まり、「彼女はあろうことか、この私を袖にしたのである。」 で終わる。完璧な導入部。こんな小説が面白くないはずがない、という確信を持って読んだ。間違ってなかった。 明るく歪んだ学生生活が生き生きと描かれる。古典文学的な大げさな熟語使いがこれまた絶妙。小さなエピソードひとつひとつが妙にリアルで作者の体験が基になっていることは想像に難くない。 「私、部屋に余計なものが増えるのは嫌です。」 とクリスマスプレゼントを拒否された「ソーラー招き猫事件」には彼女側に深く同感。こういうトンチンカンなプレゼントを贈る困った男は多いんだな。ま、惚れた男がくれたのなら何でも嬉しいのだが。ロンドンを放浪した後、友人らに「自分探しの旅に出た」とからかわれて、大英博物館に陳列してある「自分」を見つけた、ブリキの箱に入って可愛いリボンがかかっていた、と話す件も好き。ちょっと海外に行ったくらいでナニモノカをみつけた気になってる若者といっしょくたにされるのはかなわん、といったブライドを持って何の衒いもなく可笑な話をする愛すべき男たちなのだ。それにしても京都というのはヘンな学生が日本一似合う街だ。しかも一部の京大生というのは「変人」としてはピカイチではないだろうか。どこかトイモイ日記に似通っているようなカンジがしたのはなんでだろ・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>禁じられた楽園 / 恩田陸きつねのはなし / 森見登美彦 <今日の音楽>Adam Harasiewicz / chopin: the 21 nocturnes the 26 preludes
2007.04.17
コメント(2)
-
『子供は判ってくれない』
ブログや雑誌で内田樹の本が面白いと知って、何冊か読んでみた。全部読んだ本もあれば、途中までしか読めなかった本もあるが、一応半分以上読んだ本が以下。『下流志向─学ばない子どもたち、働かない若者たち』 『子供は判ってくれない』『態度が悪くてすみません―内なる「他者」との出会い』 『知に働けば蔵が建つ』 『身体知―身体が教えてくれること』『健全な肉体に狂気は宿る―生きづらさの正体』 『身体(からだ)の言い分』この中で一番面白くて共感できる部分が多かったのは、『子供は判ってくれない』なんだけど、すらすら読めて実はとりとめがない。「たいへん長いまえがき」からして面白い。「誰にも向けられていないメッセージ」の無意味さには同感。「正論」の問題点にも同感。互いに正論を述べ合う論客たちは自説の正しさを証明したいだけ、具体的な解決を望んではいない、という皮肉な見方は見逃していた事実。だから「大人」は不毛な論争で物事を単純化したりしないと読める。ところが、そういう風に物事を単純するのはやめようと仰ってもいるので、結局なんだかよくわからない。「あとがき」によれば、分かったと誤認するより分からない方が害がないらしいのでやっぱいいのか。これで。考察は考察すること自体が大事でかならずしも結論が出なくてもいい、と感じたのが収穫。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>タイムスリップ水戸黄門 / 鯨統一郎シュレーディンガーの猫 / 小倉千加子<今日の音楽>Chopin
2007.04.16
コメント(6)
-
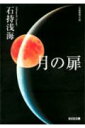
『月の扉』 『薄い月』
ハイジャックされた飛行機のトイレで死体が発見される。密室での二つの事件の絡みがどう推移するのか興味津々で読む。ハイジャック犯は普通の男女で、要求はある人物を外に連れ出すだけ。 奇妙な要求の意図は? ハイジャッカーから指名された乗客の男がなぜかすらすらと論理的に推理して死体の謎を解く。一体何者なんだ、と気にかかるが彼の正体は不明のまま。「月」と「師匠」の関連も明かされないまま。壮大な話を匂わせつつこじんまりと収まった感じで、事実の説明はついても心情的には納得いかないことが多い。なのになんだか妙に後をひく。表紙の赤い月がファンタジック、と同時に不気味でとても良い。月つながりで、『薄い月』(海月ルイ) 指名手配犯の写真を記憶し、街頭で見つけ出す「見当たり捜査」という特殊な捜査方法がテーマ。非科学的だが検挙率はかなり高いらしい。500人もの顔を記憶している専従捜査官は、整形しても変装しても顔の本質は変わらないという。人は顔の部分を見ているのではなく全体像を「顔」として認識している。事件のカラクリは複雑だが解決の仕方があっけなくてインパクトのない話になってしまった。向田邦子は昼間に出るこの薄い月を「大根の月」と呼んだ。「大根の月」という印象深い作品がある。ドラマでも見た。飛行機事故で亡くなったのは50歳くらいだったろうか。忘れがたい作品がいろいろあって惜しい人だったと思い出す。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>シュレーディンガーの猫 / 小倉千加子それってどうなの主義 / 斎藤美奈子<今日の音楽>Journey / Generations
2007.04.15
コメント(2)
-
『失踪日記』 吾妻ひでお
売れっ子の漫画家(らしいが、実は読んだことない)が鬱と不安と妄想から仕事も家族も捨てて失踪。山で自殺しそこなってムシロと腐った毛布にくるまってホームレス生活、といった実体験の漫画。食べ物はゴミ袋をあさって探す。カビたパン、吸殻が混じったうどん、シケモク、天ぷら油はデザートその他もろもろに使用、・・・・んー、ホームレスは強靭な体力がないとできないな、とまずはお門違いの感想。現実逃避のためにこんな過酷な生活を選ぶメンタリティは何なんだ。弱いんだか強いんだか。2度目の失踪では配管工として働く。周囲の人物描写が面白い。家に連れ戻されてもなお通勤するが結局人間関係が難しくなって辞める。ガテン仕事で筋肉もりもりになったが、することないからまた漫画を描いた。そしてアル中になって強制入院。単なる酒好きとホンモノのアル中との歴然とした違いを知る。不治の病なんだって。。。人は同じことばかりしていると疲れる。漫画家は室内の頭脳労働だからアウトドアで肉体を酷使して生きることを体感したいという無意識の欲求があったんだろうな。シビアな話なのに丸っこいユーモラスな絵で一見深刻にみえないのがいい。漫画を読むのはとても時間がかかる。この本は特にコマが多い。絵をみて字を読んでと視線をあちこちに飛ばすのには慣れが必要で文字だけの本より疲れるのだけど、面白くて1日で読み上げた。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>失踪日記 / 吾妻ひでお (読了)きつねのはなし / 森見 登美彦<今日の音楽>Journey / GenerationsDef Leppard / Yeah!
2007.04.14
コメント(6)
-

『押入れのちよ 』 荻原 浩
表紙がいいねぇ。あまりに面白くて久々に一気読み。短編9作。このごろ「これは好みの小説だ」というのが書き出しでピンとくるようになった。「最初から嫌な予感がしていたのだ。」 この文で始まる「押入れのちよ」は会話から細部の設定までかなり面白い。こういうとぼけたテイストの幽霊談は大好き。明治39年生まれ14歳のちよの経歴に謎とひねりがあるのもよろしい。「お母さまのロシアのスープ」・・・出だしが児童文学風で情景が美しい。世の中を知らない子どもが描写する語り口が面白い。最後の一行が余計。ほんの少し違う双子という伏線でほぼ予測がつく。そんなオチじゃなくて、もっとグッとくる意外な秘密を期待してたのだけど。。。。 「コール」・・・超常現象研究会の3人。語り手の正体がホラー。「老猫」・・・やっぱ、猫はホラーの王者だ。凄みのあるラスト。「殺意のレシピ」・・・主婦としてこの展開は期待通り。愉快痛快。筒井康隆ばり。 「介護の鬼」・・・鬼嫁と寝たきりの義父、最後のバトル。 「小説新潮」に連載されていた寝たきりの姑が嫁と互角に渡り合う漫画『極楽町一丁目』を思い出す。しかし笑えない。「予期せぬ訪問者」・・・マンションの1室を舞台にしたコント的作品。「木下闇」・・・15年ぶりに訪れた母の実家での一夜。ホラーやミステリーもれっきとした文学だ。巨大なくすの木のある情景が眼に浮かんでくる。映像的なイメージがわく作品。「しんちゃんの自転車」・・・浅田次郎か朱川湊人か。。。。せつなくほのぼのした余韻。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>押入れのちよ / 荻原浩 (読了)失踪日記 / 吾妻ひでお<今日の音楽>the very best of Sonny Rollins
2007.04.13
コメント(4)
-
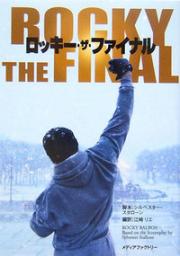
『ロッキー・ザ・ファイナル』
ボクシングにもスタローンにもましてやロッキーには全然思い入れはないけれど、ジーンときてしまった。前半はややタルイ。小さなレストランを経営して客に過去の栄光を語るロッキーの姿は見てはいけないものを見たような気分になる。だが、こんなじいさんになってまで闘う気になった布石をしっかり敷いているのだった。後半は人生訓のようなセリフがそこかしこで語られる。言い尽くされ感たっぷり耳タコ感覚の言葉ばかりなのだけど、ロッキーだと臭く感じないのはリアルタイムで1作目から見ている郷愁ゆえだろうか。摩訶不思議な映画である。「ロッキー」といえばコップで生卵をまとめてゴクリ、生肉サンドバッグ、図書館の階段が名シーン。この3点セットがきっちり押さえてあると、記憶の怪しい頭にも30年前に見たシーンが甦ってくる。しかし、今回の重要な脇役リトル・マリーについては全然覚えていないので少々もどかしい。チャンピオンは腕以外の筋肉が少なくて育ちよさげで、リングサイドのマイク・タイソンの凶悪犯のごとき極悪面とは対照的。スタローンがやや大きく見える絶妙な配役。試合場面は上映時間にして15分程度だろうか。2ラウンドまできっちり見せて、途中は軽く流して最終ラウンドへ。試合結果はしごく妥当な線に落ち着く。誰もがほっとする瞬間だ。そして、なんといっても印象に残るのはテーマ音楽。へこたれそうな時に聴くのには一番の音楽。今回はことさら感動を煽るアレンジではなくあっさり目のアレンジ(しかし脳内では聞きなれたヤツも同時に流れる)でトレーニングシーンのバックに流れる。サブリミナルのごとく過去のシーンが挿入されるのは総集編&完結編のお約束で効果絶大。墓場から始まり墓場で終わる。ロッキーシリーズ堂々完結。中には駄作もあったといわれるが、スタローン、最後にきっちり落とし前つけてお見事。試写@都久志会館 (いつになく中高年男性が多くて異様な雰囲気)
2007.04.12
コメント(16)
-

『彼女の命日』 新津きよみ
4章に別れている中編だがそれぞれ主人公が違っていて、連作4話ともいえる。本当の主人公はずっと同じなんだけれど外見は別人という趣向。ドラマ化するとすれば主演が毎回変わってナレーターが主人公ってかんじで面白そう。死者の目から見た「生」を描くといえば、「デスパ妻」ちっくだけど、やっぱ違うわ。。。。通り魔に殺された独身女性が命日の一日だけ他人の体に入って現世に戻ってくる。とはいえ、ホラーでもサスペンスでもなくその奇妙な設定さえのぞけば様々な人間模様の物語として読み応え充分。1年後は妊婦、2年後は中学生、3年後は逃亡中の殺人犯、4年後は自殺願望の不倫女。どうも不安定な心理状態の女性に入り込むようになっているらしい。自分の家族の現在を知って嘆き驚き案じ憤る。体の主の人生を変えないように気遣いながら行動するのがせつない。母や妹に会っても他人なのが哀しい。しかもつきあっていた彼の結婚相手はアレだし・・・犯人探しをメインにしない構成が好ましい。余韻のある読後感となっている。思わせぶりなラストがにくい。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>薄い月 / 海月ルイ (読了)四畳半神話大系 / 森見登美彦それってどうなの主義 / 斎藤美奈子<今日の音楽>Fuzjko Hemming / Carnegie Hall Live 2001
2007.04.11
コメント(0)
-

『睡蓮の教室』 ルル・ワン
メンテ工事は順調、3月締めも一応終了。やっと余裕がでてきたと思ったとたん気が緩んだのか風邪ひいた。これからは3月半ばに読んだ本の覚書&感想をぼちぼち書いていこう。『睡蓮の教室』は表紙の睡蓮の絵にひかれた。淡い色調でなんとものどかな優雅さを醸し出しているけど、内容は大違いの過酷さ。差別と圧政のもとに生きる少女二人を克明に描いた自伝的小説。1972年、文革時代の中国の12歳の少女の水蓮は知識階級にあったため母と地方の「再教育施設」に送られる。体は弱いし、母は厳しく、友達はいない。けれど、「師」には恵まれた。各界トップクラスの(同じく収容された)知識人から水を吸う砂漠の砂のごとく学んでいく。知識や教養は学力競争のために身につけるのではなく、知識欲は自然な欲求としてあるんだな。学びたいのに学べないのは悲劇。学校は学びたい者だけが行くのが本来の姿だと思った。後半は北京の学校生活で、極貧の二つ年上の少女張金とクラスメートになり友情をはぐくむ。階層差別はすさまじく、批判文の口汚さはさすが中国と思わせる過激さ。罵り言葉に乏しい日本人にはゼッタイ書けない。張金はしだいに変貌し、まるで想像もしなかったラストとなって呆気にとられる・・・・バトルロワイヤルか蝿の王か・・・・こんな話になるとはなぁ。意外度90%感銘を受けた数少ない本の1冊、ユン・チアンの自伝「ワイルドスワン」と同じ時代の物語、ほぼ同世代の作者。12歳で「大地」を読んで以来、一種のトラウマか、虐げられる中国女子の物語に弱くてこの手の話はなかなか心から剥がれない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>薄い月 / 海月ルイ<今日の音楽>Def Leppard / Yeah!
2007.04.10
コメント(0)
-

月刊ケリー
oliveさんが名古屋でご一緒した時の写真をCD化して送ってくださった。それと同封されていたのがケリーバッグ、じゃなくて「KELLY」という名古屋限定発売の月刊誌。さすが日本一元気な都市、名古屋である。この本は以前ウヌニコさんのブログで紹介されてて名古屋に行ったらぜひ拝見せねばと思いながらも、イタリア村やら水族館やらミッドランドスクエアやらをうろちょろしてるうちに本屋さんに行くのをころっと忘れてしまっていた。oliveさんは覚えててくれたのね。どうもありがとう。なになに・・・・5月号は今までとちょっと違うらしいよ。「今月号から美人雑誌化宣言」だって。 ナゴヤ美女104人のアンケート、即効、女を磨くメソッド24、イタリアン特集、とナゴヤ美女(略称「ナゴ美」)のための情報が詰め込まれている。しかも全体の1/4は美容整形関係の全面広告だ~どれどれ・・・美容と健康の原点は正しい食事、結婚しても自分の人生、失敗したダイエット法=食べないダイエット・単品ダイエット・ダイエット食品、よく読む雑誌はCLASSY、この辺は全国共通のような気がする。好きなスキンケアブランド1位はアルビオン、これは使ったことがないなぁ。抑えておきたい新刊に「不都合な真実」(2940円もするよ!)があってナゴ美は地球環境の現実を学ぶことも怠らない。結婚相手に求める条件で重視しないもの(この設問が絶妙)、1位は共通の趣味、2位は容姿、3位社会的地位。 どうやらkellyとナゴ美は価値観が似ているらしいな。。。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>薄い月 / 海月ルイそれってどうなの主義 / 斎藤美奈子<今日の音楽>BON JOVI/ Bounce
2007.04.09
コメント(10)
-
F1@セパン
二日連続の呑みごとですっかり疲れてしまった今日は一日中家でごろごろ。それでも選挙だけは律儀に出かけた。朝も昼も飲み物だけでお腹いっぱい。夜はTが買ってきたエビバーガーを1個食べただけで満腹。昼間だらだら過ごしてたのはF1を見る準備でもあった。セパンのレースだけはどうしても見逃せない。オーストラリアは昼間に放送したのにどうしてセパンはライブじゃないのか納得いかないけど12時を待った。マッサがPP取って今度もフェラーリか、と思いきや意外や意外の面白い展開になった。アロンソが鋭くトップをとって、ハミルトンが見事な援護でマッサとライコネンの2台を寄せ付けない。序盤のハミルトンがとにかくすごい、本当に新人なの?! マッサは一瞬ハミルトンを抜いたが素早く抜きかえされて熱くなったんだろう、6周目でスピンしてコースアウトした時点でマクラーレンの1・2フィニッシュは決まったも同然。その後ハミルトンは安定した走りで2位をキープ。デビュー戦3位はフロックじゃなかったと見事に証明。ライコネンは冷静さが裏目に出て精彩を欠いた走りだった。それにしてもマクラーレンが赤っぽくなってトップの4台が赤とは紛らわしくてかなわん。マクラーレンにはハッキネンが走っていた頃のモノトーンがよく似合う。あの頃のクールな走りがなつかしい。ホンダはGのディスプレイに注目。あれって役立つものなの?1位アロンソ、2位ハミルトン、3位ライコネン。 マクラーレンがやっとドン底時代を抜けたみたい。ルノーはどうした? スーパーアグリが2台とも完走したのも特筆もの。バーレーンではフェラーリが巻き返しを図るだろう。見逃せない。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>中庭の出来事 / 恩田陸<今日の音楽>Bounce / BON JOVI
2007.04.08
コメント(6)
-
バーベキュー
毎年恒例のお花見バーベキュー。とは言っても、桜の名所に行ってガンガン火を焚くわけにもいかないし移動も大変だし他所の酔っ払いと騒ぐのは御免だし夜は寒いし・・・ということで、桜の木は1本もない会社敷地内で実施。買い物は免許とりたての甥っ子が運転するワゴン車で行き、他に2名の助っ人が来たのであれこれ指示するだけで完了。ちょっと前までは若くもない女手4本で四苦八苦して20人分の食材と酒を買ってきてたのに言う事をよく聞く若い男が二人いるだけでウソみたいに楽ちん。じっくり炭火で網焼き&鉄板焼きのBBQ。一番人気は手羽先。炭火でじっくりと二度焼きすると旨い。だんだん牛肉の消費量が減ってるのはメンバーの高齢化のせいか? お酒もビールから焼酎に移行してきた。しかも芋がダントツ人気。kellyは白いふっくらご飯のおにぎりが好きだけど、焼きおにぎり好きが多くて最後は醤油をたらした焼きおにぎりで締める。家族のお迎えや代行運転で帰る人が増えたのが今年の特徴かな。日当たりのいい街路にある木はもう葉桜になっている。さ、来週は新学期。 春も本番。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>中庭の出来事 / 恩田陸<今日の音楽>Diana Ross / voice of love
2007.04.07
コメント(0)
-

誕生会@ヴィニュロン
Y氏の不惑を祝う会を「ヴィニュロン」で開催。MLでの募集では1日で定員に達してしまうほどの大人気で結局貸切となった。2万円近い会費を払って17名も集まる誕生会ってなかなかあるもんじゃないわ。ヴィニュロンのお料理とワインの魅力も大きいのだけど、やはり人徳というか人間的魅力というか。。。。どんな時もオトナな対応ができる人だから普段は歳なんか意識せずに話してたけど、Yさん今まで30代だったのね。ま、会がすすむにつれて誕生日をダシにして美味しいものを食べよう美味しいワインを飲もうという全員の心意気が顕になってきたのも否めないが、これは我々の宿命でいつものこと。ケーキが出てきたのが11時過ぎ。話はつきず4時間があっという間のパーティーだった。ドレスコードはセミフォーマル。ブルーシフォンのクルタ(2年目にしてやっとデビュー)で出席したら、アオザイとよく間違えられた。参加できなかった方々からは、クリュグ MVを3本、特注の巨大ケーキ(NICO)、ゴルゴンゾーラのアイスクリーム(プティジュール)、バラの花束が差し入れられた。なんて愛情あふれる誕生会なんでしょ! グロンニェ ブラン・ド・ブラン M.V. クリュグ ‘04 キスラー ‘89 シャトーヌフ・デュ・パプ ‘02 エシェゾー ‘97 シャトー コスデストゥルネル ‘89 シャトーギロー 計16本 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>太陽の塔 / 森見登美彦<今日の音楽>Christina Aguilera / Stripped
2007.04.06
コメント(0)
-

囲われた我が家
満11歳となった我が家のメンテナンス工事が今日から始まった。昨日はご近所6軒に挨拶回り。今日は足場設営とシート張り。2名で一日がかり。我が家はすっかり囲われてしまった。1月に点検してもらって、屋根の塗装と外壁のコーキングが必要とわかった。屋根は10年に一度の塗り替えが目安になっているという。自分で登って確かめれないので職人さんに写真を撮ってもらって見ると、あまり傷んでないが北側にコケがついている。去年工事を終えたお向かいさんと比べたら色あせているのがわかる。セラミック壁は汚れにくくて丈夫だが弱点は継ぎ目のコーキング。南側がかなり傷んでいた。2月になって具体的な工事内容の説明、見積もり、値段交渉。3月になって再見積もり。決算価格で値引きしました、という。ご近所Fさんの後押しもあって大幅な値引き。しかし3月は忙しいので工事を延ばしてもらった。ついでに営業マンも3月は忙しくで契約書を交わしたのは4月になってから。税込みでキリのいい価格になった。明日は空けて明後日は洗浄。屋根から外壁、シャッター、ガラスを水洗い。 お化粧直し中ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>たまには、時事ネタ / 斎藤美奈子太陽の塔 / 森見登美彦<今日の音楽>Green Day / American Idiot
2007.04.05
コメント(14)
-
『ブラッド・ダイヤモンド』
うわー、4月になってもう4日も経ってしまった・・・・1日の日記から遡って書きたいところだけど、今日見た映画を忘れないうちに書きとめておくことに。シエラレオネのどかな山村が襲撃されるショッキングな場面から始まる。ピンクの巨大ダイヤモンドを巡る争奪戦は、発見者の漁師、反政府軍のボス、元傭兵の密売人、アメリカ軍人の間で繰り広げられる。根底に流れるのは家族の絆。2時間20分という長尺ながら退屈はしないが、戦闘・爆破&殺戮場面が多すぎてなんとも重苦しい残像が消えない。そんなにバンバン殺さなくても想像力というものもあるし事の悲惨さは充分伝わると思うのだけど・・・アクションの比重が大きすぎて思考回路がぶつ切りにされる感じ。デリケートな人には向かない映画。アフリカの美しい景色と雑然とした街の対照的な画面は「ナイロビの蜂」に似ている。最近アフリカの映画が流行ってる?!内戦の記事を書いている女性ジャーナリスに漁師が 「それを読んだら誰か助けにきてくれるか?」と訊くと、「たぶんこないわ」とあっさり答えるところが実も蓋もなくて非常に現実的だった。アフリカには今も20万人の少年兵士がいるという。痛ましい。戦争は大人の軍人だけをどこかに集めてやってもらうわけにはいかないの? なんのかんの言っても日本に生まれてよかった、と思わずにいられない。遠い異国の不幸と引き比べて幸福を実感するとはなんとも暢気なことよ。キンバリープロセスというものを知る。およそ日本人女性でダイヤモンドをひとかけらも持っていない人は少ないと思うけど、手元の屑ダイヤでもひょっとしたらこの映画のように紛争の血にまみれているかもしれないと思うとドラマチックである。試写@明治安田ホール
2007.04.04
コメント(10)
-

『不細工な友情』
光浦靖子は知っているが大久保佳代子は知らない。「オアシズ」というユニットを組んでいるが、大久保はOLと芸能活動をかけもちしているという。片方だけが売れるというのはお笑いコンビの宿命のようだ。愛知県で小学校から高校まで一緒、大学は東京外大と千葉大に別れたがずっと友達。しかし、その底辺に流れるのは愛なのか憎しみなのか、という意味深な出だしにそそられるふたりの往復エッセイ。関節炎とジンマシンから始まって家族、女の友情、食事、別れ、お金、欲望、と読ませる話題が続く。文章は断然大久保のが面白い。ゆれる自己を分析、迷いを迷いとしてつらつらと書き綴っていてきちんと気持ちを書き表せないもどかしさを表現しているのがよくわかる。 光浦の彼を寝取った過去を暴露され、「人より性欲が強い」と言い切る大久保。しかし、光浦の友人のオカマから「それは性欲のタンクが満たされていないから」と断定され、当たっているのが可笑しい。長年の友人であり相方であるが、なんだか複雑な感情が渦巻いているカンジを醸し出している。微妙な距離感を感じるのは公開エッセイのせいなんだろうが、いくら長いつきあいでもよくわからない部分があるのが人の面白さ。あまりにも似通った境遇の二人だからして大論争にならず盛り上がりに欠けるのが残念。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>たまには、時事ネタ / 斎藤美奈子太陽の塔 / 森見登美彦<今日の音楽>Green Day / American Idiot
2007.04.03
コメント(0)
-
LIVE 当たった
合わせになった青と白の葉書をベリッとはがすと 「ご当選おめでとうございます。」の赤い文字。"THE SUPER DRY LIVE " の当選通知だ!!! 全席招待のプレミアライブだからしてお金では買えないチケット。母娘3人の名前と住所を駆使して、東京と神戸の両方に応募したら、kellyの名前で送った東京会場分が当たった。チケットは5月下旬に発送、座席は当日会場で抽選になるという。うー、正直当たるとは思ってなかった。ありがとう アサヒビール。武道館に参上いたします。6月は予定が立て込んで厳しいけど、なんとかしなくちゃ。JONに会いにいかねば。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>太陽の塔 / 森見登美彦子どもは判ってくれない/ 内田樹<今日の音楽>New York Voices / hearts of fire
2007.04.02
コメント(8)
-

老木・古木
須恵からしょうけ越えを抜け、飯塚から田川へ。後藤寺の丸山公園に着いた時は薄暮になっていた。おまけに今日は寒い。花冷えとはよく言ったもので、どんなに温かい日が続いても桜が咲いている頃には必ず寒い日が混じる。こじんまりとした公園は満開の桜の木に囲まれ、歩道はうっすらと桜色の花びらで覆われてそれはそれは美しい。宴会を始める家族連れやグループもちらほら。横の広場にはイカ焼、たこ焼、ソフトクリーム・・・・これまでお花見といえば大きく枝を広げてびっしりと花をつけた木、より花いっぱいの木、より美しい木ばかりを探して見ていた。今日ここではそうでない木に目をひかれた。公園の横の坂道を登ると神社がある。小高い丘になっている周辺のゆるやかな坂道も一応桜並木。斜面には若い木が植わっているが、周囲はほとんど枝もない老木や古木。樹齢なんてわからないけれど、滅多に見ないものすごく古い木ばかり。直径30cm以上ある幹のほとんどがウロになっていたり、半分以上が朽ちてしまったり、大きな枝は打ち払われて細い枝が1本だけだったり、切り株状態になっていたり・・・・老いた桜の傷み方はそれぞれ違う。それでも細々と何輪かの花を咲かせている。痛々しいけれど様になっている。すっかり日が落ちて写真は撮れなかった。こういう桜に目が向いてしまうのは、人生の黄昏時にきたせいか?! もうひと花咲かせようなんて大それたことは思わないけど老いさらばえて朽ちていくだけというのもなんだかなあ。。。。 桜のじゅうたん まだまだ頑張るーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー<今日の読書>太陽の塔 / 森見登美彦<今日の音楽>Neil Young / DecadeNew York Voices / hearts of fire
2007.04.01
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- 仕事しごとシゴト
- バー小林の25/11/13
- (2025-11-14 09:55:52)
-
-
-

- 地球に優しいショッピング
- ☆洗たくマグちゃん プラス☆
- (2025-09-04 23:16:08)
-
-
-

- *雑貨*本*おやつ*暮らし*あんな…
- ドクターシーラボ✨New Year Happy B…
- (2025-11-14 21:16:01)
-