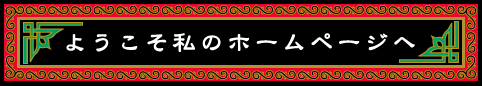ホウレンソウ(菠薐草)自立神経、貧血便秘
「緑黄色野菜」はかって「有色野菜」と言っていた一群の野菜の一部であるが、この場合“色”は「ビタミンAを大量に含む野菜類の濃い色」を指しており、
その場合のビタミンA含有量の基準は「食べる部分の100g中にカロチン600ugを含む」ということである。
この条件にかなう野菜というのは、
ホウレンソウ(3100ug)
ニンジン(7300ug)、
シュンギク(3400ug)、
ニラ(3300ug)などであり、
日本カボチャは620ugでやっとパス、トマトは390ugで不合格ということになる。
ビタミンAとは、レチノール(ビタミンAの化学名)とカロチンという二つの成分を総合したものである。
レチノールは、食べればそのままビタミンAとして腸から吸収され、動物性食品(たとえばウナギ、レバーなど)には多く含まれるが野菜類にはほとんど皆無である。
一方、カロチンというのはプロビタミンAともいわれるように、そのままではビタミンAではないが、小腸から吸収されるときにビタミンA(レチノール)に変わる。
そこで、食品中のカロチンやレリノールが、体内に入ってどのくらいビタミンAとして働くかを表したものが「A効力」と呼ばれる計算値で、単位にはIU(国際単位)が用いられている。
一日に必要な平均的A効力は、男性で2000IU、女性で1800IUとされている。
ビタミンAは、胃腸や気管などの粘膜を活性化させ、皮膚を養い、病菌の抵抗力を強め、夜盲症を防ぐといった効能があり、
さらに成長促進に関係しているとされ、また、粘膜を活性化する作用がガン細胞の増殖を抑制するのではないかとも考えられている。
ほかにビタミンB1・B2・D・E・K(病的な出血を抑える)、葉酸(貧血、下痢、舌炎を治す)などを含み、ミネラルとしてはカルシウム、鉄、ヨード、銅、マンガンなどをバランスよく含んでいる。
タンパク質も3.3g(生100g中)と比較的豊富で、アミノ酸もリジン、シスチン、トリプトファンなどが多く、その組成は動物性タンパク質によく似ている。
こうした栄養素の総合的効果によって、不眠症、自律神経失調症、更年期障害、皮膚の過敏症、便秘、胃弱などを治し、体力強化に役立つ。
ただし、従来その豊富な鉄分によって、貧血症改善の切り札のように考えられてきたホウレンソウであるが、
じつは含まれているしゅうさん蓚酸によって鉄やカルシウムの吸収が妨げられ、
かえって貧血やカルシウム不足による
骨粗鬆症(こつそしょうしょう)などを助長するとする研究も発表されている
(1994年、広島女子短大家政学部)
© Rakuten Group, Inc.