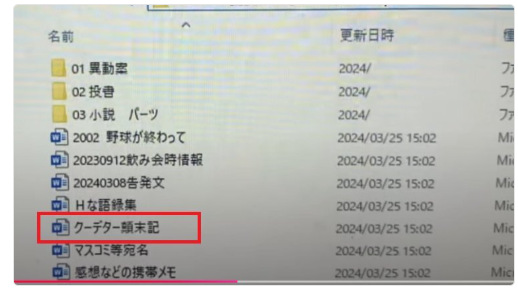2011年09月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
福島第一原発が事故を起こした直後に菅政権は原発周辺に10年から20年の間人は住めなくなると推測、都民の避難も考えたと松本元内閣参与が豪州のテレビに語った
福島第一原発が事故を起こした後、菅直人政権は深刻な汚染状況を認識、原発の周辺には10年から20年の間、人は住めなくなることを理解していたと松本健一元内閣官房参与はオーストラリアのテレビ局ABCの取材に語っている。自身が4月に語ったことを確認した形だ。東京の住民を避難させなければならないかもしれないと菅首相は考えていたとも松本元参与は明らかにしている。 NRC(原子力規制委員会)によると、福島第1原発の敷地から1マイル強(約2キロメートル)ほどの範囲で核燃料棒の破片が見つかっているのだが、委員会のゲイリー・ホラハン新原子炉局副局長はその破片が原子炉の内部にあった燃料棒のものだと推測している。 3号機の使用済み燃料プール内で核反応(核暴走)が起こり、プールが「大砲」のような役割を果たし、煙や瓦礫が上空に向かって真っ直ぐに噴出、その際に燃料棒の破片も飛び散ったという見方があったのだが、圧力容器の内部にあった燃料棒からのものだとするならば、ベント(放射性物質を含むガスを外部へ噴出させる)の際に飛び出したのか、格納容器の内部で何らかの爆発が起こり、蓋を壊して噴出したということになるだろう。 その原因はともかく、原発の周辺数キロメートには燃料棒の破片が飛び散った可能性が高く、粒子状の放射性物質が広い範囲に存在しているだろう。プルトニウムの汚染がないと考える方が不自然だ。チェルノブイリ原発の事故を考えると、10年や20年で戻れるとは考えにくい。事故の進行具合や風向きによっては、東京の住民を避難させる事態になっても不思議ではなかった。そうしたことを十分に理解した上で、政府や東電は嘘をつき、おそらく嘘を承知で大手マスコミは「安全デマ」を流していたのだろう。
2011.09.30
-
カダフィ後のリビアでは、民族浄化、劣化ウラン弾、そしてアル・カイダが大きな問題となり、武器がイスラム武装勢力へ横流しされ、世界中で紛争が激化する可能性も
リビアの内戦はイギリスとフランスを主導する形で勝利を手中に収めた反ムアンマル・アル・カダフィ派を「解放軍」と呼ぶことはできない。大きな問題をはらんでいる。さまざまな勢力の寄り合い所帯だということもあるが、その中心にアル・カイダ系の武装集団、LIFG(リビア・イスラム戦闘団)が存在していることも大きい。 すでに「親リビア軍」が武器を各地のイスラム武装勢力へ横流ししている疑いも指摘され、アフガニスタンやイラク、あるいはシリアでの戦闘が激しくなる可能性も出てきた。この点をアメリカ政府は懸念しているようだ。 反カダフィ軍はサハラ以南のアフリカ人を敵視している。肌の色が黒いというだけで拘束、行方不明になっている人が少なくないようだ。黒人の大半は労働者だと言われているが、傭兵だとしても暴力的な扱いは許されていない。また、数百の死体を反カダフィ軍は親カダフィ派の墓地へ投げ込んでいるとも言われ、処刑も疑われている。 今後、リビアでは放射線障害が問題になってくる可能性もある。リビアの内戦でNATO軍は劣化ウラン弾を使用したと指摘されているのだ。アメリカのシンクタンク「FPIF」のコン・ハリナンやイギリスの反核活動家、ケイト・ハドソンも指摘している。 カダフィ政権はサハラ砂漠以南のアフリカを自立させようとしていた。リビアの石油利権だけでなく、アフリカ中南部の資源利権がイギリスやフランスを動かした大きな理由だと考えざるをえない。アフリカに中国やロシアが食い込んできたことも「西側」にとっては脅威だったはずで、カダフィ排除は急を要したのだが、6月頃まで反政府軍は1000名ほどの規模にすぎず、傭兵を使うしかなかったようだ。 反カダフィ軍には参加した傭兵はカタールやアラブ首長国連邦などで雇われたり、チュニジアの失業者やカダフィ体制に不満を持っていたリビア人が集められた。コロンビアで「死の部隊」に所属していた人物も含まれていると言われている。 傭兵はイギリスが中心になって編成されたようだが、当初はフランスと関係の深い人物が司令官を務めていた。リビアで儀典局長を務めていたノウリ・メスマリのフランス亡命が内乱の始まりだということを考えると不思議ではない。 この司令官とはリビアの元内相、アブデル・ファター・ユニスなのだが、7月に暗殺されている。その直前、暫定国民評議会の内部で解任劇があり、ユニスも粛清されていた。暗殺したのはムスリム同胞団だといわれているが、この組織は創設時からイギリスと深い関係にあることは本ブログで何度か書いた通りだ。 ユニスが粛清されるころからイギリスはトリポリ攻略作戦の準備を開始、数週間をかけて武器、通信機器、そして精鋭部隊をトリポリに送り込んだ。首都攻撃作戦も最終的にはMI6(イギリスの情報機関)が作り上げ、さまざまなアドバイスをしていたという。 内戦のクライマックス、首都トリポリの攻略ではイギリス空軍が精密誘導爆弾のペイブウェイ IVやトルネードGR4戦闘機でカダフィ軍を攻撃、通信系統も破壊している。またメディアを使って偽情報を流し、リビア国民だけでなく世界の人びとを混乱させようとしていた。 そのトリポリで反カダフィ軍は住民から歓迎されていないようだ。市内では今でも銃声が聞こえ、重火器を搭載した車両が走り回っている。カダフィ体制の崩壊で住民は解放感を味わっているようだが、数百名の武装した兵士が市内にいることにうんざりしはじめているともいう。そうした感情が怒りに変わる日は、そう遠くないだろう。新政府が成立するまでの数カ月かかるというが、そんなことは言っていられないはずだ。
2011.09.30
-
世界を支配しているのはゴールドマン・サックスであり、金融機関や投機ファンドはカネ儲けだけを考えていると主張するトレーダーをBBCが番組に登場させ、話題になっている
9月26日にBBCが放送した番組に登場した株式トレーダー、アレッシオ・ラスタニの主張が話題になっている。「政府が世界を統治しているのではない。ゴールドマン・サックスが世界を支配している。」こうした巨大金融機関や投機ファンドが関心を持っているのはカネ儲けだけであり、国の経済、まして庶民の生活がどうなろうと知ったことではない。日本政府が不景気と災害で庶民が苦しんでいる中、法人減税と庶民増税を強行しようとしているのも、背景は同じだ。 多くの人は「そんなこと、わかりきっているじゃないか」と思うだろうが、そうした見方に組しないのが西側の有力メディア。庶民から富を搾り取ることだけが経済政策だと叫び続けてきた。そうしたメディアのひとつであるはずのBBCがラスタニの主張を伝えたことが注目されているようだ。 資本主義経済は基本的に弱肉強食、強者総取りのシステムであり、富が一部の人間に集中し、投機が盛んになって金融資本が政治経済を支配するようになるのは必然。資金を循環させるのではなく集中させる仕組みである以上、破綻するのは避けられない。 富の集中にブレーキをかけるために労働者の権利を認め、投機を抑制するために商業銀行と投資銀行を分離したのがフランクリン・ルーズベルト大統領だった。最高裁の妨害にもかかわらず、この時代には巨大資本を規制するルールが定められたのだが、このルールを最終的に破壊したのがロナルド・レーガン政権である。その理論的な支柱がフリードリッヒ・ハイエクやミルトン・フリードマンだ。 ちなみに、ウォール街での抗議活動11日目、9月27日の様子は・・・。 ライブは・・・。
2011.09.29
-
1%の人間が40%の富を支配する経済システムを変えるためにウォール街で抗議活動を続けている人を警官隊が排除しようとしているが、その様子をMSNBCも報道
第2次世界大戦後、アメリカは戦争と投機に没頭してきた。勿論、その間にも違った政策を探った大統領もいる。例えばソ連との平和共存を訴えた「平和の戦略」を宣言、インドシナからのアメリカ軍撤退を決断したジョン・F・ケネディはダラスで暗殺され、デタントに舵を切り、中国を訪問して毛沢東主席と会談、米中国交樹立への道を進み始めたリチャード・ニクソンはウォーターゲート事件で失脚している。 実体経済が衰退する中、投機経済が急速に肥大化していったのはロナルド・レーガン政権の時代。強者総取りの新自由主義経済が幅を利かせ、一部の富裕層/巨大企業が富を独占し、庶民は貧困化していく。こうした経済の仕組みが投機をますます盛んにしていく。そして1%の人間が40%の富を支配するということになった。 1990年代の後半になると、そうした仕組みに対する反発は強まるのだが、2001年9月11日の出来事によってアメリカは「愛国者法」という名前の「戒厳令」に支配され、アフガニスタンやイラクへ先制攻撃、戦時体制に入る。 そうした異常な状態に気づいた人びとはバラク・オバマの「チェンジ」に期待したのだが、結局、政策はチェンジされなかった。自分たちが立ち上がらなければ何も変わらないと自覚した人びとがウィスコンシン州の議事堂を占拠、ウォール街で抗議活動を続けていると言えるだろう。 そのウォール街での警察による暴力的な規制をMSNBC(ネットワーク局のNBCがマイクロソフトと共同で設立したニュース専門の放送局)も報道している。ペッパー・スプレーを女性に吹き付けた警官も特定された。
2011.09.28
-
湾岸の独裁産油国バーレーンでの民主化弾圧を黙認してきたアメリカ政府は5300億ドルの武器売却を計画、自国でも強欲なウォール街に抗議するデモを弾圧
アメリカ政府は民主化運動を弾圧している国に手を貸してきた。数え上げたら切りがないが、最近の一例がバーレーン。イギリスやアメリカと親密な関係にある湾岸の独裁国家だ。 こうした国々の支配者は民主化の弾圧で手を組み、バーレーンで抵抗運動が始まるとサウジアラビアが約30両の戦車を送り込んだりしている。3月11日に予定されていた示威活動への対策として、4日には北東部の地域へ約1万人の治安部隊を派遣した。 弾圧の一環としてバーレーンの治安当局はシーア派のモスクを次々と破壊しているだけでなく、医療関係者も逮捕していった。治安当局による暴力で負傷した人を治療したことが理由になっている。こうした弾圧は現在でも続いているのだが、アメリカのバラク・オバマ政権は弾圧を黙認するだけでなく、5300億ドル相当の武器を売却しようとしている。有力メディアも大きくは取り上げていないようだ。 アメリカやイギリスの情報機関が仕掛けて内乱状態になったリビアやシリアとは違い、バーレーンの場合は平和的な抗議活動。そうした活動が弾圧されているのだが、「西側」はあまり関心がないようだ。 有力メディアが無視しているという点では、ウォール街での抗議活動も同じだ。アメリカ、ヨーロッパ、日本などの経済が行き詰まっていることが話題になっているが、これは富を集中させる、つまり一部の富裕層が大多数の庶民からカネを吸い上げる仕組みに根本的な原因がある。経費削減や市民への増税で解決できるはずがないのである。こうした仕組みに対する抗議が世界的に広がっているが、アメリカでも行われているということだ。
2011.09.27
-
冤罪の製造装置「迷惑防止条例」の精神が法律全体に浸透していることを陸山会事件の判決は示しているが、その影響は小沢議員周辺だけでなく日本人全てに降りかかる
政治資金規正法違反で起訴された小沢一郎議員の元秘書に対し、東京地裁の登石郁郎裁判長は9月26日に有罪を言い渡したようだ。この事件について詳しく調べたわけではないのだが、報道されている情報から判断する限り、公正とは到底言い難い。 ジャーナリストの江川紹子さんも指摘しているように、この裁判で問われているのは、1) 2004年に購入した土地代金の支出を、翌年の政治資金収支報告書に記載したことの是非2) 土地購入に際し、小沢議員が4億円を立て替えたことを報告書に記載しなかったことの是非3) 小沢議員の他の政治団体との間で行った資金の融通を報告書に記載しなかったことの是非だったはずだが、判決を受けての報道は「ゼネコン裏金認定」が前面に出ていた。 すでに多くの人から指摘されていることだが、あえて事件を簡単に振り返ってみる。 裁判の中で検察は、4億円の中には水谷建設からの闇献金1億円が含まれ、その闇献金は大型ダム建設の工事受注を巡る謝礼だと主張する。東京地検特捜部に対し、水谷建設の川村尚元社長が「六本木のホテルで石川秘書(当時)に5000万円入りの紙袋を渡した」と供述したことから出たストーリーなのだが、この証言を裏付ける証拠がない。 水谷建設の運転士が記録していた運転日誌にも該当する記載がなく、「社長をそのホテルに送ったのは翌年以降」だと運転手は証言している。 また、水谷建設の最高実力者だった水谷会長(当時)は、裏金を渡す時には必ず授受を目撃する「見届け人」を同席させるなどのルールがあつたのに、川村社長がそれに従っていないことに疑間を呈したともいう。(江川紹子、「裁きようのない茶番法廷」、週刊朝日、9月2日号) 判決を聞いた水谷元会長は「会社から裏金が出たことは事実だが、石川議員らに渡したところは私は見ていない。」と語っている。川村元社長が闇献金という名目で会社に出させたカネを着服した疑いもあるのだが、こうした点を裁判所は考慮していないようである。 ジャーナリストの魚住昭さんも書いているように、もし、1億円の闇献金が事実なら悪質であり、今回の判決で有罪とされた元秘書たちに執行猶予がつくのは奇妙な話。法律に詳しくないので、この献金が「贈収賄事件」として成立するかどうかは判断できないが、腑に落ちないことは確かだ。 もっとも、日本の裁判所が信頼に耐えないことは昔から言われてきたことであり、今回の判決に驚きはない。江川さんは今回の判決に対し、「何人かが『やった』と言えば」裏づける証拠がなくても「事実になってしまう」と批判しているが、その通りである。冤罪の製造装置になっている「迷惑防止条例」の精神が法律全体に浸透しているようにも見える。 敗戦までの日本には政府に批判的な人びとを弾圧する強力な仕組みが存在していた。特高警察、思想検察、そして裁判所のトリオである。戦後、この仕組みは生き残り、「大本営発表」のマスコミが取り込まれていった。 小沢議員に好意を持っていない人の一部は、今回の判決に拍手喝采しているようだが、こうした判決は小沢議員の周辺だけでなく、日本人全てに降りかかるのだということを忘れてはならない。
2011.09.27
-
ウィスコンシン州の議事堂に続いてウォール街で抗議活動が繰り広げられている背景には、支配層の強欲なカネ儲けに対する庶民の怒りがある
日本のマスコミにとって、原子力問題は数あるタブーのひとつにすぎない。天皇制にしろ、経済にしろ、外交にしろ、軍事にしろ、表面を撫でるだけで本質に迫ろうとはしてこなかった。こうした問題は相互に関連し合っているわけで、支配システムとも言えるだろうが、その根っこの部分にはカネ儲けに血道を上げる強欲な人びとがいる。 こうした強欲なカネ儲けに異を唱える人たちが世界各国で増えている。例えば、アメリカでは今年の初め、ウィスコンシン州ではスコット・ウォーカー知事の政策に抗議する人びとが議事堂を占拠している。 ウォーカー知事は財政赤字を理由にして、警察や消防を除く公務員の医療保険負担や年金負担を大幅に引き上げ、労働組合の団体交渉権を剥奪するという日本のような政策を押しつけようとしたのだ。 知事の後ろ盾になっているチャールズ・コークとデイビッド・コークの兄弟は石油関連企業を所有している大富豪で、環境保護を主張する人びとを敵視、気候変動の研究を攻撃するキャンペーンのスポンサーとしても知られている。大気汚染にうるさい気象学者を排除し、あらゆる規制を撤廃させようとしている。 そして、9月17日からはウォール街で抗議活動が始まった。富裕層や大企業を助けるために庶民に犠牲を強いる政策に反対している。平和的な活動だが、警官隊は排除に乗り出している。 現在、ウォール街で抗議活動を続けている人は数百人程度のようだが、同じ気持ちのアメリカ人は決して少なくない。実は、ロナルド・レーガン大統領やティー・パーティーはそうした気持ちの人びとに支えられた。言うまでもなくレーガンにしろティー・パーティーにしろ、実際は富裕層や大企業の味方。ところが、「社会主義」に対する恐怖を植えつけられているアメリカ人は巧みにミスリードされたようだ。 こうした状況をアメリカや日本のメディアは触れたくないようだが、アメリカやイスラエルから狙われているイランのテレビ局は批判的に報道している。当然だが。 アメリカの盟友、イギリスでデモが一時的に禁止されたのも象徴的だ。
2011.09.26
-
社会から富を吸い上げ、投機につぎ込み、失敗したら庶民からカネを巻き上げる金融界に対する抗議がウォール街で続いているが、警官隊が90名以上を動物のように逮捕
庶民が暮らす社会から富を吸い上げ、「余ったカネ」を投機に使って資産を膨らませ、損をしたら庶民からカネを巻き上げる経済システムに対する抗議が9月17日からウォール街で続いているのだが、ついに警官隊が排除に乗り出した。抗議に参加していた人びとを、動物のように捕まえていく映像が流されている。日本なら、こうした抗議活動は開始した直後に機動隊(暴動鎮圧部隊)が投入され、暴力的に排除されただろうが。 24日、抗議に参加している数百名が国連ビルへ向かおうとしたところで警官隊と小競り合いが起こり、少なくとも96名が逮捕されたとも報道されている。その際、動物捕獲用の網だけでなく、催涙スプレーも使用されたようだ。アメリカのメディアは大きく取り上げていないようだが、中東やロシアのテレビ局は注目している。 現在、世界的な経済危機が叫ばれているが、その原因はウォール街やシティに代表される投機の肥大化にある。アメリカでは人口の1%が富の40%を独占しているというが、そのアメリカよりも日本は富裕層/大企業が優遇されている。この問題を解決しない限り経済危機は解決できないのだが、富裕層/大企業の強欲さが解決を許さない。侵略/略奪で乗り切れる時代ではなくなっている。
2011.09.25
-
国際的に孤立しているイスラエルを支援するアメリカとイギリスは最終的に暴力で黙らせる「テロ政策」に頼るしかないだろうが、それに同調すれば日本は破滅しかねない
パレスチナ自治政府は9月23日に国連への加盟を申請した。この申請にイスラエルとアメリカ両国政府は激しく反発、イギリス政府も同調しているが、大半の国は申請に好意的である。 その背景には、イスラエルのパレスチナ人に対する政策がある。ヨルダン川西岸での違法な入植を強行する一方、ガザに対する兵糧攻めを継続中で、軍事侵攻による施設の破壊と住民虐殺も繰り返されている。 例えば、2008年12月にもイスラエル軍はガザへ軍事侵攻しているのだが、そのときには高温で肉を溶かしてしまう白リン弾、あるいは大きな破壊力を持つGBU39(スマート爆弾)も使用されている。そうした兵器で住民を殺害し、住宅を破壊している。 攻撃のターゲットには学校、救急車、病院、そしてUNRWA(国連難民救済事業機関)の施設も含まれ、殺害された住民は1300名以上、負傷者は4000名以上に達したと言われている。 この軍事行動を問題視した国連は独立調査委員会を編成、委員長は、南アフリカ出身で「ユダヤ系」のリチャード・ゴールドストーンが指名された。この委員会が出した報告書でも、イスラエル軍に人道法や人権法に違反する多くの行為があったと指摘されている。 スーザン・ライス米国連大使が報告書を受け入れられないと発言、イスラエルは中東和平交渉を崩壊させると脅しているのだが、その際、パレスチナ自治政府がアメリカに協力したとする話が流れ、騒動になった。そのときに信頼を失った自治政府としては、国連加盟の申請で妥協することはできない。 ちなみに、報告書は国連の人権理事会に回されて採択されている。賛成25カ国、反対6カ国、棄権11カ国、無投票5カ国。その内訳は次のようになっている。[賛成]アルゼンチン、ブラジル、中国、ロシア、バーレーン、バングラデシュ、ボリビア、チリ、キューバ、ジブチ、エジプト、ガーナ、インド、インドネシア、ヨルダン、モーリシャス、ニカラグア、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、カタール、サウジアラビア、セネガル、南アフリカ、ザンビア[反対]アメリカ、ハンガリー、イタリア、オランダ、スロバキア、ウクライナ[棄権]ベルギー、ボスニア、ブルキナファソ、カメルーン、ガボン、日本、メキシコ、ノルウェー、韓国、スロベニア、ウルグアイ[無投票]イギリス、フランス、マダガスカル、キルギスタン、アンゴラ イスラエル側の圧力が強まる中、ゴールドストーンは後に報告書の内容をトーンダウンさせようとする発言をしているが、これは反発を招いただけだった。イスラエルに厳しい目を向ける人が世界的に増えているわけだ。 そうした流れの中、ガザで秤量攻めにあっている人びとを助けようという動きも出てくる。そのひとつの結果が2010年のガザ支援船団である。 それに対し、イスラエル政府は公海上で船団を襲撃する。同国の特殊部隊「シャエテット13」が襲撃し、トルコのマビ・マルマラ号では9名を殺害、多数を負傷させている。襲撃の際、イスラエル軍はジャミングで通信を妨害し、撮影機材などを没収するなど外部に事実が漏れることを極度に警戒していた。 トルコで行われた検死の結果、殺された9人のうち5名は至近距離から頭部を撃たれていた、つまり「処刑」だった可能性が高い。この出来事が原因で、イスラエルは友好国だったトルコを失っている。 国際的に孤立の度合いを強めているイスラエルに肩入れすることでバラク・オバマ米大統領は自らも孤立する道を選んだのだが、2009年にはイスラエルへ55発のGBU-28(バンカー・バスター)提供していたことも明らかにされた。ガザへイスラエルが軍事侵攻した直後ということになる。 この爆弾は地下深くに建造された施設を破壊でき、ジョージ・W・ブッシュ大統領も2005年に100発の提供を承認している。イラン攻撃用だと見られていた。 イスラエルは核兵器を保有している。1986年にサンデー・タイムズ紙が掲載したモルデカイ・バヌヌの内部告発によると、イスラエルの核弾頭数は200発以上、イツァク・シャミール首相の特別情報顧問を務めたアリ・ベンメナシェによると、1981年の時点で300発以上、またジミー・カーター元米大統領は150発だとしている。 こうした核兵器を使用させないため、バンカー・バスターを提供した可能性もある。最後は暴力で脅し上げるしかないと思っているのではないか、ということだ。要するに「恐怖(テロ)政策」。このアメリカに従っているのが日本なわけである。
2011.09.25
-
パレスチナの国連加盟問題が注目されている国連で野田首相は事故を起こした原子炉の「冷温停止」を年内に達成という妄想を振りまく一方、アフリカの資源利権にも色気?
今、国連で最大の問題はパレスチナの国連加盟申請だろう。加盟を支持する国が圧倒的に多い中、拒否権を使って阻止すると明言しているアメリカ政府は追い詰められている。 アメリカ政府がイスラエル支持を鮮明にしている理由を「ユダヤ系社会」に求める人もいるようだが、ユダヤ系市民が他の市民に比べてイスラエル政府の政策に好意的だとは思えない。 1970年代以降、イスラエル政府を支えているのは「ユダヤ系団体」と結びついている「ネオコン(新保守)」やキリスト教系のカルト、いわゆる「シアコン(神保守)」だ。シアコンは「キリスト教原理主義者」とか「聖書根本主義派」と呼ばれることもある。この勢力と手を組むことでイスラエルではリクードが実権を握ることができた。 グレース・ハルセルの『核戦争を待望する人びと』(朝日選書、1989年)を読むと,聖書根本主義派の信者数は4000万人だという。核になる「熱心な信者」は30万人程度だとも言われているが、大きな影響力があることは事実。「保守系の草の根運動」と呼ばれている「ティー・パーティ」の中心もシアコンだ。 この勢力は巨大資本の意向も代弁しているのだが、その一方で新約聖書に書かれている最終戦争を全面核戦争だと信じ、「第三次世界大戦」を夢見ている人もいる。破壊される地球の環境を考えることなど、こうした人びとにとっては何の意味もない。こうした考え方は環境破壊を伴う産業、例えば石油関連企業に好かれる一因になっている。勿論、核戦争を実行する為には原子力産業も必要だ。 ジョージ・W・ブッシュ大統領を担いでいたのもネオコン/シアコン。2001年9月11日以降、ホワイトハウスで主導権を握った。ブッシュ政権は2003年3月にイラクを先制攻撃してサダム・フセインを排除しているが、これは1990年代にネオコンが描いた青写真の中に含まれていた。 この青写真ではパレスチナ問題の平和的解決にも消極的な姿勢が明確にされている。パレスチナ側が義務を果たさなければ、つまりイスラエル政府にとって気に入らない言動があれば、1993年の「暫定自治原則宣言(オスロ合意)」には拘束されないとしている。 ネオコンにとって好都合なことに、合意の当事者だったイスラエルのイツハーク・ラビン首相は1995年に暗殺されている。2000年にはリクードの党首で軍事強硬派として有名なアリエル・シャロンが1000名以上のイスラエル人警官を引き連れ、エルサレムにある「神殿の丘」を訪れ、その場所はイスラエルのものだと宣言した。 その丘にはイスラムの聖地「岩のドーム」もある。シャロンの言動はイスラム教徒を挑発し、和平の機運を粉砕することが目的だった。そして2006年、イスラエル軍がレバノンやガザに軍事侵攻した一因も、合意を破壊することにあったと見られている。 さらにイスラエルはヨルダン川西岸で違法入植を続け、ガザ地区を封鎖して兵糧攻めにしている。昨年はそのガザに物資を運ぼうとした支援船をイスラエルの特殊部隊が公海上で襲撃、その結果、友好国だったトルコとの関係が悪化して国際的にも孤立の度合いが高まることになった。その延長線上にパレスチナの国連加盟申請はある。 そんな国連で野田佳彦首相は、福島第一原発で事故を起こした原子炉の「冷温停止」を年内に達成するという目標を掲げ、南スーダンでの国連平和維持活動にも積極的な姿勢を見せたようだ。 メルトダウンしている原子炉の冷温停止など意味不明。溶融した燃料棒は床から鋼鉄製の壁を溶かし、コンクリートから地中へと沈み込み、放射性物質は土地だけでなく地下水を伝わって海を汚染している可能性が高い。「冷温停止」などという妄想を振りまく前に、汚染が外部へ広がらないように最大限の努力をすべきなのだ。 南スーダンの問題はリビアの内戦とも関係している。本ブログでは何度も書いていることだが、イギリス、フランス、アメリカがリビアを攻撃した大きな理由はリビア国内の石油利権とアフリカ中南部の資源利権。リビアのムアンマル・アル・カダフィ政権はアフリカ中南部の自立を支援、欧米の利権を脅かしていたのである。そうした中、中国をはじめとするBRICSがアフリカへの影響力を強めつつあった。アメリカに従属することで中国に対抗、「お零れ」を頂戴しようとしているようにも見える。
2011.09.23
-
一部の人間に富を集中させる経済システムに抗議する運動は9/11で下火になったのだが、再び盛り上がりつつあり、ウォール街でも抗議活動が続く
福島第一原発の事故によって空気、土地、そして海が放射性物質で汚され、多くの日本人が数年、あるいは数十年という年月をかけて殺されつつある。 ところが、この期に及んでも原発の利権に目が眩み、核武装の幻影を追いかけている人たちがいる。政治家、官僚、大企業の経営者、学者、報道機関の社員など、一般にエリートだと見なされている人びとの中に,そんなタイプは多い。 こうした人たちは、これまで原発の大事故は自分たちが現役の時には起こらないと高を括り、事故が起こったら誤魔化せると高を括り、誤魔化しきれなくなると放射性物質は危険でないという「神話」を作り上げて逃げ切ろうとしている。 大本営の作戦参謀たちもそうだったように、今でも日本のエリートは状況を的確に判断できない。そうした現実を庶民が見抜いて「ノー」と言えば、どんな独裁者であろうと何もできないのだが、実際は愚かな支配者の言いなりになってきた。支配層に人心を操作する能力があるのか、あるいは日本の庶民が騙されやすいのか・・・。 いや、騙された振りをしているのかもしれない。個人的な目前の利益を考えるならば、強者に立ち向かうのは損。ならば、騙された振りをして責任を回避しつつ、「お零れ」にあずかる方が得、と考えているのではないだろうか。 中には、強者から無視されるような小規模なサークル内でおだをあげ、満足している人たちもいる。そういう人は、何らかの事情でサークルへの参加者が増えてくると排除にかかったりする。庶民の気づかないことに気づいている自分、という「エリート意識」に傷がつくと思う人もいるようだ。そんな気がする。 ところで、原発は一部の人間に富を集中させる仕組みのひとつでもある。ミヒャエル・エンデは『ハーメルンの死の舞踏』で「ねずみ」と「金貨」をひねり出す怪物を登場させているが、原発とは放射性廃棄物とカネを生み出す怪物と言える。カネを欲しがる権力者たちは、人間に死をもたらすネズミを手放すことができない。 富の独占を露骨に肯定しているのが新自由主義経済。フリードリッヒ・ハイエクやミルトン・フリードマンが考え出した「理論」で、「市場の自由競争」を絶対視、「私有化」や「規制緩和」を掲げている。実際にやっていることは、国境を越えて資金を動かし、資源を独占し、人びとを劣悪が条件でこき使うということ。 国境を越え、規制などない状態で活動している企業を「多国籍企業」と名づけ、アメリカ議会が問題にした時期もある。1970年代はそうだった。今では活動形態に注目、「グローバル化」と呼ばれている。 1970年代の終盤以降、グローバル化を推進したのは、マーガレット・サッチャー英首相、ロナルド・レーガン米大統領、西ドイツのヘルムート・コール首相、そして日本の中曽根康弘首相たちだが、中国やロシアのボリス・エリツィンも新自由主義に舵を切っている。 こうしたグローバル化に対する怒りは世界で高まり、1999年には激しい抗議活動が展開されている。WTO(世界貿易機関)の閣僚会議が開かれたシアトルには、抗議のために約10万人が集まった。 この流れは2001年9月11日の出来事で断たれるが、ここに来て再び盛り上がっている。投機の尻ぬぐいをさせられようとしているギリシャだけでなく、最近ではアメリカのウォール街でも抗議活動が展開されている。こうした運動をアメリカの有力新聞が大きく扱わない理由は言うまでもないだろう。
2011.09.22
-
日本のマスコミが政府の広報機関になることを宣言した1960年、約10万人のデモ隊が国会を取り囲んだが、こうした事態の再来を防ぐために監視システムが強化されている
政治家,官僚、大企業経営者たちの多くが原子力政策の推進を望んでいるのに対し、庶民の中で「脱原発」を支持する声が高まっている。9月19日に東京の明治公園で開かれた「さようなら原発5万人集会」には予想を上回る6万人が集まったようだ。 6万人は決して小さな数字でないが、それ以上の盛り上がりを見せた出来事もある。例えば、1960年5月20日には約10万人のデモ隊が国会を取り巻き、6月4日には全国で460万人が参加したというストライキが実行されている。5月19日に国会へ警官隊を導入、会期の延長を自民党が単独で採決し、20日の未明に新安保条約が採決されたことを受けての抗議活動だった。 6月10日にはホワイトハウスの報道官だったジェームズ・ハガティを乗せた旅客機が羽田空港に降り立ち、警察の護衛なしに空港出口に向かってデモ隊の中へ突っ込み、アメリカ海兵隊のヘリコプターで脱出するという出来事があった。 いわゆる「ハガティ事件」だが、その3日前、岸信介首相はマスコミの幹部を官邸に呼びつけている。読売新聞の正力松太郎社主、産経新聞の水野成夫社長、NHKの前田義徳専務理事、毎日新聞の本田親男会長、東京新聞の福田恭助社長をそれぞれ個別に官邸へ呼び、その翌日には共同通信、時事通信、中日新聞、北海道新聞、西日本新聞、日経新聞、さらに民放の代表を招き、9日には朝日新聞の代表にも協力を要請している。駐日大使のダグラス・マッカーサー2世も7日に各新聞社の編集局長を呼んで「懇談」したという。 そして6月15日にもゼネストとデモがあったのだが、その後、東京大学教養学部の自治会に所属する学生など全学連主流派約8000人が国会の南通用門から構内へ突入、警察隊と衝突して東大文学部国史学科4年だった樺美智子が死んでいる。転倒に伴う圧死だと警察側は主張しているが、家族の希望で行われた解剖では目にひどい鬱血が認められ、膵臓の出血もひどかった。つまり、樺は首を強く絞められたうえ、倒れたところを激しく踏みつけられたことが示唆されている。 そして17日に有名な「共同宣言」を東京の7新聞社、つまり朝日新聞、産業経済新聞、東京新聞、東京タイムズ、日本経済新聞、毎日新聞、読売新聞が掲載している。その宣言は、「6月15日夜の国会内外における流血事件は、その事のよってきたるゆえんを別として、議会主義を危機に陥れる痛恨時であった。」という一文で始まっている。政府の責任を不問に付すという宣言だったわけだ。 支配層としても、こうした事態は避けたいはずで、運動が盛り上がる前に潰してしまいたいと考えているだろう。そこで監視システムの整備が急務になる。2001年9月11日に航空機がニューヨークの高層ビル突入、ペンタゴンが攻撃された事件を経てアメリカ政府は憲法の規定を機能停止させ、監視システムを強化している。 勿論、アメリカ政府が国民を監視するようになったのは、「9/11」のはるか前、1950年代のことである。FBIが国民監視プロジェクトの「COINTELPRO」をスタートさせ、さらにCIAが67年に通信監視を目的とした「MHケイアス」を始めている。 FBIは途中からターゲットを反戦/平和運動に搾り、集会やデモに捜査官を潜入させただけでなく、平和運動を支援していた著名人の尾行、電話盗聴、郵便開封、さらに銀行口座の調査も実施している。CIAの封書開封は1974年に発覚している。 その後、コンピュータ技術が急速に進歩、そうした先端技術を使って個人情報の収集と分析、通信傍受、ターゲットの追跡を行うシステムが築かれてきた。 通信の傍受はアメリカとイギリスの電子情報機関、つまりNSAとGCHQが中心になって実行されている。両者が公式に手を組んだのは1947年か48年だと言われている。「UKUSA(ユクザと発音)協定」が結ばれたことを受けてのことだ。イギリスのジャーナリスト、ダンカン・キャンベルによると、イギリス南部にあるコーンウォールのモーウェンストー基地で傍受が始ったのは1971年だという。(詳しくは拙著『テロ帝国アメリカは21世紀に耐えられない』を) 勿論、情報機関や治安機関は通信を傍受しているだけではない。例えば、米国防総省のDARPA(国防高等研究計画局)が開発したTIAではあらゆる個人情報、つまり学歴、銀行口座の内容、ATMの利用記録、投薬記録、運転免許証のデータ、航空券の購入記録、住宅ローンの支払い内容、電子メールに関する記録、インターネットでアクセスしたサイトに関する記録、クレジット・カードの利用歴、電気やガスの使用状況などのデータを集め、分析することを目的にしていた。このプロジェクトが露見すると別の名前のシステムが稼働している。 市民の権利を擁護する活動を続けているACLU(アメリカ市民自由連合)によると、シーズント社はスーパー・コンピュータを使い、膨大な量のデータを分析、「潜在的テロリスト」を見つけ出そうとしているともいう。つまり、どのような傾向の本を買い、借りるのか、どのようなタイプの音楽を聞くのか、どのような絵画を好むのか、どのようなドラマを見るのか、あるいは交友関係はどうなっているのかなどを調べ、分析しようというのだ。 日本政府はこうしたアメリカの動きを追いかけているはず。例えば、不特定多数の個人情報を収集、分析、保管することのできるシステムに関する概説資料と研究報告の翻訳を法務総合研究所は1979年と80年に『研究部資料』として公表している。当時、駐米日本大使館に一等書記官として勤務していたのが原田明夫。そうしたシステムの中に東電も組み込まれている可能性がある。少なくとも、そうした方向で動いているはずだ。
2011.09.21
-
脱原発を訴える集会に6万人が集まった19日、細野原発相はIAEAの総会で福島第一原発を年内に「冷温停止」させたいという非現実的な表明をした
脱原発を訴える「さようなら原発5万人集会」が9月19日に東京の明治公園で開かれ、集会の後で参加者は都心をデモ行進した。 集会には予想を上回る6万人が集まったようだが、読売新聞やテレビは約3万人と報道している。現場にいれば3万人という数字が事実と乖離していることは明白なのだが、警察発表の2万7000人に配慮したのだろう。 昔から、警察は主催者発表を半分にした数字を「推定」として発表している。今回、主催者が事前に「5万人」と言っていたので、警察は「2万5000人」を推定数字として想定し、予想より多かったので2000人増やしたのだろう。それでも警察の数字が小さすぎることは明白だったので、読売新聞などはさらに3000人増やしたのかもしれない。が、その程度では警察発表の垂れ流しの範囲内だ。 19日には細野豪志原発相はウィーンで開かれたIAEA(国際原子力機関)の総会で演説し、「冷温停止」を年内に達成するという目標を掲げた。原子炉の冷却システムが1気圧で華氏200度(摂氏95度)まで低下、再沸騰の可能性がなくなった状態なのだというが、この定義にはシステムが正常に作動しているという前提があるはずだ。 事故発生から現在に至るまで日本の政府や東京電力は重要な情報を開示せず、偽情報を流し続け、そうした情報操作に大手メディアは協力してきた。原発推進団体のIAEAからも日本政府や東電の情報隠蔽は批判されるほど情報操作はひどいのだが、それでも原発のシステムが機能していないことは明らかである。 稚拙な情報操作は原発を推進する上でもマイナスだとIAEAは考えているようだが、IAEAも原発推進が目的なわけで、福島第一原発の「安全宣言」を早く出したいとは思っているはず。「冷温停止」の話も裏ではシナリオができているかもしれない。 しかし、福島第一原発の事故を人為的に収束させられる状態だとは思えない。少なくとも1号機では溶融した燃料棒が周囲の危機を溶かしながら圧力容器の底に落下し、底を何らかの形で通過して格納容器の底へ落ちていると考えられている。制御できていないということである。 燃料棒の融点が二千数百度だということを考えると、床のコンクリートと反応しつつ沈み込み、融点が一千数百度である鋼の壁を溶かし、その下のコンクリート、さらに地中へという道筋のどこかにあるはずである。 つまり、圧力容器の中に溶融物はない可能性が高く、熱源がなくなった圧力容器の底部の温度を測定し、そこの温度が摂氏100以下になっても大きな意味はない。 新たに設置したという「冷却システム」もコンクリート、あるいは地面の中にある溶融物を効率的に冷却できているとは思えず、この状態を「冷温停止」と呼ぶことはできない。 建屋の下にあるコンクリートに地震で無数の亀裂が入っていると考えられていたが、そうした亀裂から1日に数百トンの地下水が流れ込んでいる可能性があると東京新聞は報じている。地中なら勿論、溶融物がコンクリートの内部にあっても、その亀裂から放射性物質が漏れ出ていると考えなければならないだろう。 福島第1原発の敷地から1マイル強(約2キロメートル)ほどの場所で見つかったという核燃料棒の破片の問題も無視できない。エネルギー関連のコンサルタント会社、フェアーウィンズ・アソシエイツ社で主任エンジニアを務めているアーニー・ガンダーセンさんは3号機の使用済み燃料プールから飛んできたと考えている。つまり、プールの内部で核暴走が起こり、プールが大砲のような役割を果たして上空へ向かって煙が激しく噴出したというシナリオだ。 これに対し、NRC(原子力規制委員会)のゲイリー・ホラハンさんは圧力容器の内部にあった燃料棒の破片だと語っている。この推測が正しいならば、「ベント」の時に放出されたのか、さもなければ、これまで知られていないような爆発が圧力容器か格納容器の内部であり、壁を壊して飛び散ったということも考える必要が出てくる。 いずれにしろ、日本政府や東電の宣伝とは違い、福島第一原発はまだ安心できる段階にはない。
2011.09.20
-
リビアでは肌の色を理由にした拘束が続き、多くの行方不明者が出ているが、フランスでは劣化ウラン弾の使用などが人道的犯罪だとしてサルコジ大統領を告発する動きも
リビア攻撃の切っ掛けを作ったのはフランス政府であり、途中から主導権を握ったのはイギリス政府である。アメリカはこの2カ国を追いかけている形だ。 フランス政府の最高責任者はニコラ・サルコジ大統領。その側近とリビア政府の元高官がパリで秘密裏に会ったところから内戦は始まっている。イタリアのジャーナリスト、フランコ・ベキスによると、その高官とは儀典局長を務めていたノウリ・メスマリ。昨年10月、機密文書を携えてパリへ渡った。フランスとイギリスが相互防衛条約を結んだ11月、フランスは「通商代表団」をベンガジに派遣し、メスマリから紹介されたリビア軍の将校と会っている。 このサルコジをフランスの法律家が人道的犯罪容疑で告発しようとしている。単に空爆で多数の市民を殺害しただけでなく、劣化ウラン弾を撃ち込むことで放射性物質を撒き散らし、ガンや心臓病などの健康被害の原因を作ったということのようだ。 イギリスではトニー・ブレア元首相が批判されている。アメリカの巨大金融機関、JPモルガンのロビーストとしてリビアのカダフィと会談していたのだが、リビア市民の殺害という点ではブレアよりデイビッド・キャメロン首相の責任が重い。 市民殺害では反カダフィ軍による「民族浄化」も大きな問題。肌の色を理由にして多くのアフリカ系住民が拘束され、そのまま行方不明になっているのだ。反カダフィ軍は数百の死体を親カダフィ派の墓地へ投げ込んでいるとも言われ、処刑も疑われている。 拘束している黒人は「傭兵」だと反カダフィ軍は弁明しているのだが、その多くは労働者だとされている。勿論、傭兵だとしても拷問や虐殺は許されない。 カダフィ軍と戦うため、NATOは傭兵を組織した。カタールやアラブ首長国連邦で雇われたほか、チュニジアの失業者やカダフィ体制に不満を持つリビア人、あるいはコロンビアで死の部隊に所属して人間も含まれているようだが、それより大きな問題がイスラム武装集団。 その集団とはLIFG(リビア・イスラム戦闘団)だが、その幹部のひとり、アブデル・ハキム・アル・ハシディは自分たちとアル・カイダとの緊密な関係を認めている。やはりLIFGの幹部でリビアの反政府軍を率いているアブデル・ハキム・ヘルハジの場合、「テロリスト」としてCIAから拷問を受けた過去がある。こうした集団がリビア軍を動かそうとしている意味は重い。
2011.09.19
-
来年の米大統領選挙で誰が勝ってもアメリカ経済の再建は難しく、日本経済を食い潰し、中東の石油利権やアフリカ中南部の資源を支配しても本質的な解決にはならない
来年はアメリカで大統領選挙がある。民主党は現職のバラク・オバマだろうが、共和党はまだ多くの人が候補者として名を連ねている。2008年の選挙では「チェンジ」というフレーズで人気を得たオバマだが、結局目立った変化をもたらすことができず、戦争は続き、景気は低迷ということで苦戦を強いられている。 オバマが再選されなかったとしても、アメリカの置かれた状況が好転することはありそうにない。イランに関しては、オバマ政権よりも強硬、つまり攻撃すべきだとしている。ロン・ポールは軍事費やイスラエルへの支援も削減する意向を示しているが、支配層の支持を得ることは難しいだろう。 アメリカを含む西側の不況は経済構造に根ざしたもので、解決は難しい。チリで最初に導入され、「先進国」ではマーガレット・サッチャー英首相が採り入れた新自由主義経済とは、富を一部の人間に集中させて「カネ余り」という現象を作ると同時に庶民を貧困化させる仕組み。一部に滞留した資金が投機市場に流れ、「カジノ経済」が出現したのは当然のことだ。 そして戦争。アフガニスタンやイラクを先制攻撃して軍需産業は大儲け、傭兵ビジネスも急成長した。破壊した街を造り直すという仕事もある。 ただ、問題は誰がカネを出すのかということ。とりあえずはアメリカ政府が出すわけだが、そんなことをしていれば財政は破綻する。どこからかカネも持ってくる必要がある。日本も狙われているだろうが、戦争が儲かるのは侵略した先で略奪するから。中東なら石油ということになる。 イランの石油も欲しいだろうが、北アフリカのリビアでは「西側」が石油利権を奪うことに成功したが、早くも内部で利権争いが起こっているようだ。 リビアのムアンマル・アル・カダフィ政権を倒す目的のひとつは、アフリカ中南部の自立を阻止するということにあった。カダフィ政権はアフリカ中南部の自立を支援、イギリスやフランスの利権を脅かしていたのである。 リビアの内戦では肌の色が黒いというだけで反カダフィ軍に拘束され、行方不明になっている人が続出している。その一部は処刑されていると言われている。それだけでなく、反カダフィ軍/NATO軍による市民の虐殺も問題になりはじめている。劣化ウラン弾の使用も指摘され、今後の影響が懸念されている。市民の命を守るなどという最初の大義名分はどこにも見あたらない。 市民の命という点では、武器の拡散も懸念されている。反カダフィ軍の主力はアル・カイダと緊密な関係にあるLIFG(リビア・イスラム戦闘団)。反カダフィ軍が新政権を作るとするならば、親リビア軍はアル・カイダ系の軍隊ということになる。 武器庫から消えた兵器はアル・カイダのネットワークで中東全域に広がっている可能性がある。8月にアメリカ軍のヘリコプターを撃墜したミサイルはリビアから流れたものではないかとも噂されている。 新自由主義経済の暴走を止められず、「先進国」の経済は破綻している。その破綻を新たな植民地政策で乗り切ろうとしているようにも見えるが、昔とは違い、難しいだろう。「船が沈めば1等船室の客も助からない」と考えて富の集中にブレーキをかけるべきだとする意見も支配層の内部から出てきているが、「船が沈むならボートで逃げればいい」と考えている人も多い。グローバル化の進んだ現在、逃げ込む場所は見あたらないが。
2011.09.18
-
福島第一原発の事故は「想定外」の津波が原因だとする説明に説得力がなくなる中、人為ミスがなければメルトダウンは起こらなかったとする話が流されている胡散臭さ
津波だけが事故の原因だとする主張がIAEA(国際原子力機関)で通らなかったのかもしれないが、福島第一原発の核燃料棒がメルトダウン(溶融)したのは操作ミスが原因であるかのような話が流されている。事故の原因を津波に全て押しつける説明が説得力をなくす中で登場した新たなストーリーだ。 穿ちすぎかもしれないが、津波に襲われず、人為ミスがなければ原発は安全だから原発を再稼働させよう、そんな思惑も感じてしまう。ただ、故障や人為ミスは如何なる技術にも付きものであり、これがなければ、という議論は無意味なのだが。 人為ミスの可能性が指摘されている一例として、非常用冷却装置の問題がある。3月11日14時46分に福島第一原発の近くで巨大地震が発生、圧力容器内の圧力が急上昇した。それに対し、14時52分にA系とB系ふたつの冷却装置が起動したのだが、11分動いたところ人為的に止められた記録が残っている。これが問題になっている。ちなみに、津波の第1波に襲われたのは15時27分のことだ。 18時10分に冷却装置は再び起動するのだが、このときはA系だけが動いている。このときは15分で止められた。そして最後に開いたのが21時30分だが、このときも動いたのはA系だけである。 もしこの冷却システムを止めなければメルトダウンしなかったかのように主張する人もいるのだが、例えば、地震で再循環ポンプと圧力容器をつなぐパイプが破損していたような場合、非常用冷却装置を動かし続けたならば、すぐに水がなくなることが予想されるので意識的に止められた可能性がある。勿論、問題なくA系とB系が機能したとしても、冷却能力には限界があり、メルトダウンを防げたとは断定できない。 最近になって出てきた例としては、日本原子力研究開発機構によるコンピュータ解析がある。2号機では14日の16時までに注水すればメルトダウンは防げた可能性があるとしているのだ。12日の段階で1号機から3号機までメルトダウンしているとも推測されているので、シミュレーションの条件などについて専門家による検討を待つ必要があるだろう。 12日の15時36分には1号機で水素爆発、14日の11時1分には3号機で激しい爆発があった。3号機も水素爆発だったとする説もあるが、上空に向かって直線的に煙が噴き上がっている様子からしても核暴走と考える方が合理的だろう。水素爆発なら、水素は建屋の上部に溜まっていたはずで、爆発すれば煙は球形に広がるのではないだろうか。 つまり、エネルギー関連のコンサルタント会社、フェアーウィンズ・アソシエイツ社で主任エンジニアを務めているアーニー・ガンダーセンさんが指摘しているように、使用済み核燃料プールの内部で核暴走が起こり、プールが大砲のような役割を果たして上空へ向かって煙が激しく噴出したと考えた方が理解しやすい。 ガンダーセンさんの説を採れば、福島第1原発の敷地から約2キロメートルの場所で核燃料棒の破片が見つかった理由も納得できるのだが、これに関しては別の説もある。破片は圧力容器からのものだというのだ。NRC(原子力規制委員会)のスタッフがそのように推測している。3月12日に放射性物質を大量の放出する「ベント」を実施しているので、このときに炉内から破片も噴出されたのかもしれない。複数の圧力容器から燃料棒の破片が噴出したとするならば、別の原因を探す必要がある。 格納容器がどうなっていたのか、温度や放射線量がどのように変化しているかを測定できる特殊なカメラが建屋の中に設置してあったはずなので、機能していれば状況の把握に役立つことは間違いない。このカメラを設置したのはイスラエルのマグナBSP。事故の1年前にセキュリティ・システムを設置、その際、特殊カメラもセットしていたのだ。カメラはどうしたのだろうか? ハーレツ紙によると、マグナBSPが設立されたのは10年前で、拠点はディモナ。事故後も同社は何人かを現地に残していたとハイム・シボニCEOは語っていた。 また、ECCS(非常用炉心冷却装置)の中の冷却系の蒸発システムが取り外されていたという話も人為ミスのひとつにされているようだが、中性子の照射で圧力容器が脆化していたとするならば、ECCSを動かしたら一気に容器が破壊されると判断して外した可能性もある。
2011.09.15
-
21世紀になっても石油に依存した生活を続ける「先進国」だが、産油国を支配して覇権を握ろうとする動きも見える
21世紀に入っても「先進国」の人びとは石油に依存した生活を送っている。石油の時代は続いているということである。アメリカがサウジアラビアや湾岸の独裁国家と緊密な関係を維持してきた理由もそこにある。 国別で原油生産量を比較すると順位は次のようになっている。1位:ロシア、2位:サウジアラビア、3位:アメリカ、4位:イラン、5位:中国、6位:カナダ、7位:メキシコ、8位:アラブ首長国連邦、9位:ブラジル、10位:クウェート、11位:ベネズエラ、12位:イラク、13位:ノルウェー、14位:ナイジェリア、15位:アルジェリア、16位:アンゴラ、17位:リビア、18位:カザフスタン、19位:イギリス、20位:カタール こうした産油国でどんなことがあったか、振り返ってみたい。 先ずロシア。1993年にボリス・エリツィンが憲法を無視する形で議会を解散すると発表、抗議のために議員が立てこもった議会ビルを戦車で砲撃、100名以上とも約1500名とも言われる人を殺害して独裁的な権力を握った。自分たちにとって都合が良かったので西側諸国はこのクーデターを問題にしていない。 その後、ロシアでは「規制緩和」や「私有化」を推進、政府とつながった一部の人間が巨万の富を手に入れた。そうしたひとりがボリス・ベレゾフスキー。ユーコスという巨大石油企業を支配していたミハイル・ホドルコフスキーもそうした富豪のひとりだった。 ホドルコフスキーがユーコスを買収したのは1995年のことだが、その前、ソ連時代にロシアの若い女性を西側の金持ちに「紹介」していたという話も伝わっている。当時、彼はコムソモール(全ソ連邦レーニン共産主義青年同盟)の指導的な立場にあった。 ベレゾフスキーの部下でロシアのFSB(連邦保安局)に勤務していた経験のあるアレクサンドル・リトビネンコは殺される数週間前、イスラエルを訪れている。イスラエルに亡命していたユーコスの元幹部、レオニド・ネフツーリンと会うことが目的だった。 エリツィン時代に出現した富豪たちはウラジミール・プーチン時代になって配下に入るか、逮捕されるか、亡命するかしている。こうした富豪の多くはイスラエル系(いわゆるユダヤ系)で、ベレゾフスキーもイスラエルの市民権を持っていた。 2008年にグルジアはロシアが実効支配している南オセチアを奇襲攻撃、住民が攻撃に曝されるが、ロシア軍が素早く動き、戦闘車両一五〇両を送り込む一方、空爆で反撃している。 グルジア軍はアメリカとイスラエルから訓練を受け、軍事物資も提供されていた。アメリカの傭兵会社も訓練に加わっている。2001年からイスラエルの会社がグルジアに武器を提供、軍事訓練も行っていた。 奇襲攻撃では、イスラエル軍の機密文書が使われていたとする証言もある。イスラエルがグルジアを軍事面から支えてきたことはグルジア政府も認めている事実だ。ロシア軍の副参謀長を務めていたアナトリー・ノゴビチン将軍もイスラエルがグルジアを武装させていると記者会見で非難している。 イランでは2009年に選挙があり、マフムード・アフマディネジャドが圧勝している。アメリカのNPOが選挙の3週間前に30州で実施した世論調査では、2対1の割合で現職のアフマディネジャドがリードしていたが、実際の選挙結果はこの調査より現職は苦戦している。 客観的に見て、選挙に大きな不正があったとは言えないのだが、西側の主要メディアは不正があったかのように報道、イラン国内では「自由を求める勇気ある人々」がデモを繰り広げていた。 ベネズエラの場合、2002年にクーデター未遂事件があった。イギリスのオブザーバー紙によると、ジョン・ネグロポンテ、エリオット・エイブラムズ、オットー・ライヒなどのアメリカ政府高官がクーデター計画に関与していたという。この3人はイラン・コントラ事件(イランへの武器密輸、ニカラグアの反革命ゲリラ支援)に名を連ねていた。エイブラムズはネオコン(親イスラエル派)の大物だ。 イラクはすでにアメリカの支配下にあり、リビアも体制転覆に成功している。次のターゲットはシリアで、そこからイランを攻撃するという推測もある。 欧米の一部グループは世界の石油を支配するというプランを持っているようだが、どの国であれ、武力で石油利権を奪おうとすれば、攻撃する側の国も滅んでしまうだろう。国の衰退など気にせず「私人」として覇権を握ろうとしている人なら別だが。
2011.09.14
-
「脱原発デモ」に対する警察の締め付けが厳しくなっているようだが、孤立させ、暴走させ、徹底的に叩きつぶすのが権力者の常套手段であり、今は第一段階。
日本の原子力推進政策に異を唱える「脱原発デモ」に対する警察の締め付けが厳しくなり、話題になっている。9月11日に新宿で行われたデモでは12名が逮捕されたようだが、現場にいた人や、その場で撮影された映像を見る限り、暴力行為があったとは言えない。もっとも、昔からデモの取り締まりはそんなものだが。 明治維新以来、日本政府は民主主義を求める声を徹底的に潰してきた。自由民権運動潰しから始まり、1920年代からは特別高等警察(特高)という言論弾圧機関が猛威を振るったが、その背後には思想検察や裁判所もいた。そして戦後もそうした人脈は生き残っている。そうした人脈の一例が町村金五、つまり町村信孝の父親だ。 特高を指揮していたのは内務省警保局だが、金五は1943年から44年にかけて警保局長を務め、45年4月には警視総監、そして戦後は衆院議員や参議院議員、北海道知事を務めている。 金五が警保局長になる直前、1942年に細川嘉六が逮捕されている。雑誌「改造」に掲載された論文「世界史の動向と日本」が問題になった。捜査の過程である会食の記念写真が発見されたのだが、その写真から特高は「共産党再建準備の謀議」を妄想し、会食の出席者を逮捕していった。言論弾圧事件として有名な横浜事件の始まりである。 この弾圧事件では雑誌「中央公論」の編集者など60名以上が治安維持法に違反した容疑で逮捕され、4名が拷問で獄死している。釈放直後に獄中の心神衰弱が原因で死亡している人も何人かいた。金五が警保局長だった時期と重なっている。 当時、金五の上司にあたる内務次官だったのが唐沢俊樹。東条英機の側近だった人物だが、戦後は岸信介内閣で法務大臣に選ばれている。 このふたり以外にも、戦後、政府の要職に就いた人物は少なくない。例えば、内務次官だった灘尾弘吉、大達茂雄、館哲二、湯沢三千男、警保局長だった古井喜実、大村清一、岡田忠彦、後藤文夫、鹿児島県特高課長だった奥野誠亮、警保局保安課事務官だった原文兵衛等々。高村正彦の父親、高村坂彦は鳥取県特高課長、香川県特高課長、新潟県特高課長を経て警保局事務官になっている。 こうした民主化弾圧の歴史をさかのぼると、三島通庸という人物に突き当たる。薩摩藩(鹿児島県)出身の内務官僚であり、山形県令時代には農民の抗議行動を弾圧、福島県令に任命されると自由民権運動をリードしていた自由党に壊滅的打撃を加え、警視総監時代には「治安維持法」の前身となる「治安警察法」を施行している。 その三島は二女の峰子を大久保利通の次男、牧野伸顕(まきののぶあき)に嫁がせているが、そのふたりの間にできた娘と結婚したのが吉田茂。その孫が麻生太郎である。 弾圧の手順は、孤立させ、暴走させ、徹底的に叩きつぶす。誰でも参加できるデモや集会は権力者にとって最も危険な存在であり、参加しにくい雰囲気を作ることが第一歩。デモに行くと逮捕されるぞという宣伝も彼らにとっては大事な仕事なのだろう。 孤立したら、挑発し、場合によっては協力者や潜入者を使って「過激路線」へ導いていくのは日本でも欧米でも一緒だ。過激な発言をする人は要注意ということでもある。暴走してくれれば、徹底的に弾圧しても文句は言われない。 ちなみに、アメリカで「爆弾闘争」を展開し、反戦運動を孤立化させていったウェザーマンの幹部には奇妙な人物がいる。ウィリアム・エアーズと妻のバーナディーン・ドールンだ。ふたりとも現在ではエスタブリッシュメントの一員だが、そうした立場でいられるのは、エアーズの父親、トーマス・エアーズのおかげ。トーマスはコモンウェルス・エジソン(電力会社)のCEOを務めるほどの大物だった。この夫婦は、疑惑の目で見られている。 また、イタリアで活動していた赤い旅団。1969年に創設された。当初は穏健な理想主義団体だったのだが、1974年に暴力的な路線に変更している。その切っ掛けは創設メンバー、レナト・クルチオとアルベルト・フランチェスキーニの逮捕。ふたりに替わって組織のリーダーになったマリオ・モレッティに引きずられる形でテロリズムに傾倒していく。しかも、やることが特殊部隊顔負けの手際。この人物も疑惑の目で見られている。
2011.09.14
-
アフガニスタン、イラク、エジプト、リビア、そしてパレスチナ、ブッシュ・ジュニア政権が中東を先制攻撃して以来、米国の立場は悪化して収拾不能な状態に
ジョージ・W・ブッシュ政権が中東で始めた戦争は収拾がつかない状況になっている。アフガニスタンとイラクを先制攻撃、イランやシリアに対する工作も水面下で進められてきた。1990年代からネオコン(アメリカの親イスラエル派)はイラクのサダム・フセイン体制を倒し、パレスチナ和平の破壊するべきだと1990年代に主張していたわけで、現在の状況は思惑通りなのだろうが、アメリカは現在、窮地に立っている。 先日、エジプトでは数千人のデモ隊がイスラエル大使館を襲ったことをうけ、政府は非常事態を宣言、テレビ局のアル・ジャジーラを家宅捜索している。ホスニ・ムバラク大統領が辞任した後も「ムバラクなきムバラク体制」が続いている、つまり支配体制は基本的に変化していないと不満を持つ人がいても不思議ではない。 アフガニスタンではアメリカ大使館が攻撃されている。武装勢力や警察による人権侵害が問題になっているが、それ以上に問題なのがNATO軍による市民の虐殺。「消火活動」と称して「放火」を続けているようなものである。イラクの情勢も好転する兆しが見えない。戦争ビジネスや石油産業が儲けているだけのことだろう。 リビアの内戦も、結局は英仏米による体制転覆作戦にすぎなかった。「反政府派」もムアンマル・アルカダフィ体制を倒すために作られた集団。コロンビアの「死の部隊」に所属していた人物や、カタールやアラブ首長国連邦の人間、あるいはチュニジアの失業者やカダフィ体制に不満を持っていたリビア人が集められたとも言われている。 それ以上に問題視されているのがLIFG(リビア・イスラム戦闘団)。アルカイダと緊密な関係にあることは本人たちも認めている。リビアの反政府軍を指揮しているアブデル・ハキム・ヘルハジはLIFGのリーダーだが、「テロリスト」としてCIAから拷問を受けた過去がある。要するに、「テロとの戦争」というストーリーは完全に崩壊している。 リビアの内戦では「西側」が劣化ウラン弾を使用した疑いがあり、問題になっている。アメリカのシンクタンク「FPIF」のコン・ハリナンが指摘しているほか、イギリスの反核活動家、ケイト・ハドソンも同じ趣旨の発言をしている。今後、大きな問題に発展する可能性もある。 より深刻な問題がパレスチナの国連加盟。パレスチナ自治政府は国連加盟を申請する意向なのだが、これに対してアメリカ政府は拒否権の行使を宣言している。これをアメリカの「警告」と考えるのは正しくないだろう。「勘弁してくれ」とアメリカが泣きを入れていると言うべきだ。 ガザ支援船をイスラエル軍が襲撃、多くの死傷者を出した事件でアメリカやイスラエルに肩を持つような行動に出た結果、パレスチナ人をはじめ、多くの人から批判された自治政府としては、後に引くことはできないだろう。 もしアメリカが拒否権を行使したなら、イスラム諸国での影響力が大きく損なわれることになる。中東支配のカギを握る国、サウジアラビアとの同盟関係にもヒビが入ることは間違いない。拒否権を行使したアメリカと友好的な関係を維持しようとしたなら、サウジアラビアの体制が大きく揺らぐ可能性があるからだ。 イスラエルが自治政府の国連加盟を望まない最大の理由は、自分たちのパレスチナ人弾圧が「戦争犯罪」として裁かれる可能性が出てくるからだという。それだけのことを行ってきたわけで、イスラエルが懸念するのは当然だろう。アメリカとしても難しい局面だ。ここでシリアやイランに手を出したなら、本当に命取りになる。
2011.09.13
-
原発事故から半年を経ても収束するメドはたたず、大気、大地、そして海は汚染され続けているのだが、政府や東電は何も反省せず、いまだに情報を隠し続けている
今から半年前、3月11日に東北地方を襲った地震で福島第一原発は壊滅的な事故を起こした。その影響は世界的な広がりを見せ、莫大な損害賠償を請求される可能性もある。日本の政府や東京電力の宣伝とは比較にならないほど深刻な事態になっている。 福島第1原発周辺の地域に人が住めるようになるまでには数十年、場所によっては「世紀」単位の時間が必要になると覚悟するべきであり、そうした地域が「死の街」になっているとする表現を間違いだとは言えない。ただ、政治家の発言としては適切でないというだけのことだ。 9月1日、原発の南側3キロメートル圏内に自宅がある福島県大熊町の一般住民が一時帰宅しているが、その時に住民のひとりは「なんで国も県も町も、もっと早く(住めないと)言わねんだ。家が残っているから帰れると思う人が多いけど、こんな放射能じゃ無理だ」(毎日新聞、2010年9月2日)と口にしたそうだが、全くその通りだろう。 事故後、アメリカのNRC(原子力規制委員会)によると、福島第1原発の敷地から1マイル強(約2キロメートル)ほどの場所で核燃料棒の破片が見つかっていた。そうした破片を回収したうえでの一時帰宅なのだろうが、それでも汚染が深刻だという状況に大きな変化はない。 破片が飛び散ったのは14日の午前だと見られていた。この日、午前11時頃に3号機で大きな爆発があり、瓦礫が高く吹き飛ばされる様子が撮影されているからである。日本政府は「水素爆発」としているのだが、検出された放射性物質なども考え合わせるとプール内で核反応(核暴走)が起こった可能性が高く、説得力のある仮説だった。 これでも深刻な話なのだが、NRCのスタッフは別の見方をしている。破片はプールに貯蔵されていた核燃料棒ではなく、圧力容器内にあったロッドの破片だと推測している。3月12日に放射性物質を大量の放出する「ベント」を実施しているので、このときに炉内から破片も噴出された可能性がある。その時点で内部はグチャグチャだったということになる。 8月1日には1号機と2号機との間にある排気筒の下部にある配管で毎時10000ミリシーベルト以上(計測器の能力を超えていたので、実際の数値は不明)、2日には1号機2回の空調機室で毎時5000ミリシーベルト以上(同)の放射線を計測しているので、炉内から核燃料棒の破片が飛び出したことも確かに考えられる。 もっとも、この発表はNRCで会議が開かれた直後に行われた。炉内にあった燃料棒の破片が飛び散った理由に関する議論をミスリードするために発表したいう可能性がないわけではないが。 勿論、これだけが問題なわけではない。事故は現在も進行中であり、収束させるメドは立っていない。 炉心の溶融物が圧力容器から格納容器へ漏れ出た可能性が高いのだが、そうなると床のコンクリートと反応しながら中へ潜り込んでいることが予想される。融点の関係で鋼の壁を突き抜け、その下のコンクリートへ入り、さらに下へ落ちていけば地中に入ってしまう。 地震でコンクリートには無数の亀裂が入っていると思われ、海や土の汚染状況を考えると、そこから放射性物質は外部へ漏れ出ていることは間違いないだろう。建屋内に蒸気が噴出しているとする話も伝わっている。溶融物が地中に入れば、周辺への汚染はさらに激しくなる。建屋の地上部分を囲ったところで問題の本質的な解決にはならない。最大の問題は地下にある。 これだけの事故が起こった以上、農作物や水産物が放射性物質に汚染されたことは間違いない。こうした事実は「民間」や外国の調査で明らかにされてきた。政府や東電は情報を隠し、嘘をつき、被害を拡大させている。多くの庶民はそんな政府や東電を信じていない。実際、「問題ない」とされた食物からも放射性物質が検出されている。つまり、問題のある食物が市場で売買されているわけだ。 福島県、あるいは東北地方で生産される農作物は全て危険だとする主張は正しくないだろうが、政府が信用できない以上、防衛手段として汚染の可能性が高いと思われる食物を避けるのはやむを得ないことである。本来なら問題ない作物が忌避されているとするならば、その責任は政府や東電にある。そこを避けて通る議論は意味がなく、無責任である。
2011.09.11
-
「911」から10年を経た現在、巨大資本に寄生されたアメリカという国家は疲弊し、傍若無人なイスラエルは孤立、アル・カイダが影響力を強めているように見える
2001年9月11日に航空機がニューヨークの世界貿易センターにそびえ立っていた南北タワーに突入、ほぼ同時にペンタゴンが攻撃されるという事件が引き起こされた。その直後に「犯人」はアル・カイダとアメリカ政府は断定、アフガニスタンとイラクに対する先制攻撃につながり、アメリカ国内では憲法が事実上、機能を停止、ファシズム化してきた。 戦争へ突入するため、アメリカ政府が偽情報を広めていたこと、あるいは事実上の戒厳令と言われる愛国者法が短期間で提出された理由も明らかになっている。この法律のベースを作成したプロジェクトは1980年代の初め、つまりロナルド/レーガン政権のときには始まっているのである。 アフガニスタンを支配していたタリバンにしろ、「テロリストの象徴」に祭り上げられたアル・カイダにしろ、その歴史をたどるとアメリカの好戦派が産み育てたことは広く知られている。アメリカを中心としたNATO軍がユーゴスラビアを先制攻撃した際にもアル・カイダはNATO軍側で戦っていた。そしてリビア内戦。本ブログでは何度も指摘しているが、リビアの反カダフィ軍の主力はアル・カイダ系である。 最初からアメリカの好戦派はアル・カイダなどを相手にはしていないとしか思えない。本当の目的を達成するための隠れ蓑にすぎないのではないか、ということである。戦争を始めればアメリカという国が疲弊することは開戦前から指摘されていたことであり、アメリカの衰退も計算に入っていた可能性がある。 アメリカが戦争に突入した理由にイラクの石油利権も関係しているかもしれないが、それだけが理由だとは言えない。 サダム・フセイン体制を倒すという計画を1990年代に主張していたのはネオコン(親イスラエル派)であり、一連の戦争で最も潤ったのは戦争ビジネス。1980年代には、イラクのフセイン政権を仲間と見るか敵と見るかでネオコンはロバート・ゲーツやジョージ・H・W・ブッシュらと対立していた。(詳しくは、拙著『テロ帝国アメリカは21世紀に耐えられない』を) HWの息子、ジョージ・W・ブッシュ大統領はネオコンのプランにしたがってイラクのフセイン体制を倒したわけで、イスラエルにとっては思い通りの展開だったはずだが、ここにきてイスラエルは苦しい立場に追い込まれている。傍若無人な振る舞いも度が過ぎた。 苦し紛れにアビグドル・リーバーマン外相はPKK(クルジスタン労働者党)を軍事的に支援し、最近はイスラエルに批判的になっているトルコを攻撃させると叫んでいる。もっとも、イスラエルがクルド人を支援してきたことは有名な話で、「なにを今さら」といったところだが。 9月9日の金曜日には、エジプトのカイロで数千人のデモ隊がイスラエル大使館に押しかけ、数十人が中に入り、重要書類を外に放り出すという出来事があった。アメリカやイスラエルに対するイスラム社会の怒りは支配者の思惑を超えて燃え上がりつつある。 この怒りを抑え込み、中東/アフリカを制圧することは容易でない。リビア内戦で英仏米が手を組んだ武装勢力は「反黒人」の感情が強く、アフリカ中南部の自立を支援していたムアンマル・アル・カダフィ政権とは違う。リビア国内で黒人労働者を「傭兵」だとして拘束、あるいは処刑していると伝えられているが、女性に対してはレイプ事件を起こしていると批判する声もある。アル・カイダが軍を抑えるであろうリビアの新政権をアフリカ中南部の国々は簡単に承認しないだろう。 すでの日米欧という巨大客船は沈没しはじめている。船が沈めば1等船室の客も運命をともにすることになる。巨大資本は国家の資産を吸い尽くし、国家なき世界に君臨するつもりかもしれないが、富の集中が進めば経済は自壊、その世界も崩壊するしかない。
2011.09.10
-
海外製の簡易型放射線測定器は信頼できないと国民生活センターは発表、マスコミの中には「お上」を信頼しろと報道しているが、最も信頼されていないのが政府と東電
日本の政府や電力会社は福島第一原発の事故に伴う放射能汚染について情報を隠蔽してきた。深刻な汚染の状況はフリーランスのジャーナリスト、大学の研究者、あるいは環境保護団体の調査によって明るみに出てきたのである。つまり、この問題に関し、「国や自治体が公表するデータなどを参考に」することはできないということだ。 そうした状況の中では、多くの国民が自分たちの手で放射線量を測定したいと思うのは当然のこと。おそらく、早い段階から人気があった機種のひとつは「RADEX RD1503」だろう。ロシアのQUARTA社が製造、フランスのナノセンス社が販売している。 簡易型の放射線測定器(個人でも変える比較的安価な製品)を入手することが困難だった時期がある。政府が流通を止めているという噂もあったが実態は不明だ。ただ、外国政府から提供された製品が倉庫に死蔵されていたことは明らかにされているが。 需要の高まるにつれ、さまざまな測定器が市場で売られるようになったが、品質に問題のある製品も少なくないらしい。そこで国民生活センターが商品テストをしたというのだが、テストの信頼性はおくとして、その前段階である対象製品の選択に疑問がある。「信頼できない」という結論を導くため、恣意的に選んだのではないかとも思えるのだ。 ここでマスコミの報道内容をチェックしてみると、例えば次のようなタイトルがついている。朝日新聞:『ネット販売の放射線測定器、結果ばらつき 生活センター』東京新聞:『放射線計 精度「?」 安価な9製品 ばらつき』毎日新聞:『放射線測定器:「精度低い」 通販の10万円未満9種、誤差30%超』産経新聞:『10万円未満の放射線測定器 9種類すべてが不正確 国民生活センターテスト結果』NHK:『市販放射線測定器 誤差に注意』 この9製品とは何かということだが、朝日新聞では次のようになっている。「テストしたのは、6月下旬の価格が3万6千円~6万2千円の9商品。いずれも海外製か製造国が不明の機種で、通信販売のウェブサイトで人気商品として紹介されていたものという。」 「という」というのも変な話。国民生活センターは対象製品を公表している。「海外製か製造国が不明の機種」としているが、判明している機種は国名を明らかにしている。NHKも対象機種について、「インターネットで10万円未満で販売している9つの測定器について調べました。」とだけ伝えている。 それに対し、東京新聞、毎日新聞、産経新聞は次のように書いている。「測定器はいずれも中国企業の製品。3万~6万円前後でインターネットの通信販売サイトで購入できる。」(東京新聞)「センターは通信販売のサイトでいずれも中国製とみられる9商品を購入。」(毎日新聞)「テストしたのは中国製とみられる3万~6万円台の9種類。」(産経新聞) で、実際のところは次のようになっている。(簡体字は日本風に直した)1) AK2011(上海貝聖電子技術有限会社)2) BS2011+(上海貝聖電子技術有限会社)3) DoseRAE2 PRM-1200(華瑞科学儀器有限公司)4) DP802i(Shanghai ergonomics detecting instrument Co.,ltd)5) FJ2000(中国輻射防護研究院三輻電子儀器廠/中国製)6) JB4020(上海精博工貿公司)7) RAY2000A(濟寧科電検測儀器有限公司/中国製)8) SW83(上海朔旺儀器儀表有限公司)9) SW83a(浙江*群科技有限公司) いずれも名称からすると、中国を拠点とする会社のようだが、実態は不明だ。 考えてみると、日本政府はこうした製品が出回る環境を作り上げてきた。品質的に信頼できない製品が出回っているとするならば、信頼できる安価な製品を流通させる義務が日本政府にはある。過去を振り返ると、政府は逆のことをしてきたことも忘れてはならない。 マスコミも「簡易型放射線測定器は信頼できないキャンペーン」などする前に、政府や東電の情報隠蔽、あるいは改竄を放置し、そうした嘘を広めてきた過去を反省し、信頼できるデータを引き出す努力をするべきだ。
2011.09.09
-
10年前の9月11日に「テロリスト」の象徴になったアル・カイダだが、リビア内戦では米英仏軍と手を組み、カダフィ後の体制では軍を支配する見通し
今から10年前、2001年9月11日に航空機がニューヨークの世界貿易センターに立つ南北タワーに突入、両タワーとも崩壊した。同時にペンタゴンも攻撃されている。一般的には「911」、日本では「同時多発テロ」と呼ばれている事件だ。この出来事を機に、アメリカでは急速にファシズム化が進む。ロナルド・レーガン政権から練られていた戒厳令計画、つまり「COGプロジェクト」を実行に移したのだと考えられている。 事件の直後、アメリカ政府はアル・カイダが実行したと断定、アフガニスタンやイラクを先制攻撃した。これ以降、アル・カイダは「テロリスト」の象徴となり、アメリカが行う破壊と殺戮を容認させる「御札」としても使われるようになった。 ところが、今年、リビアのムアンマル・アル・カダフィ体制を倒すためにアメリカ、イギリス、フランスはアル・カイダと親密な関係にある武装勢力と手を組んだ。その勢力とはLIFG(リビア・イスラム戦闘団)。LIFGの幹部、アブデル・ハキム・アル・ハシディはアル・カイダとの関係を認めている。 現在、リビアの反政府軍を指揮しているアブデル・ハキム・ベルハジもLIFGの創設メンバー。やはりアフガニスタンでソ連軍と戦った経験があるのだが、その際、そこでオサマ・ビン・ラディンと会っている。言わば「同志」だ。 ジョージ・W・ブッシュ政権の時代、ベルハジはCIAから「テロリスト」として拷問を受けている。2004年にCIAはベルハジをマレーシアのクアラ・ルンプールで逮捕、バンコックの秘密刑務所へ一旦投獄してからリビアへ送っている。ベルハジによると、そこで拷問を受けた。 アル・カイダの歴史を振り返ると、アメリカの軍や情報機関と深く結びついていることがわかる。アフガニスタンでソ連軍と戦っていた1980年代は勿論、2001年にも接触は続いていた。フランスのル・フィガロ紙によると、オサマ・ビン・ラディンとCIAの人間がドバイの病院で会っているのだ。7月4日から14日にかけてビン・ラディンはその病院に入院していた。 サウジアラビアの富豪一族に生まれたオサマ・ビン・ラディンを武装勢力へと導いたアブドゥラ・アッザムはムスリム同胞団に参加していたと言われる。エジプトでアンワール・サダトが大統領に就任するとムスリム同胞団を国内へ引き入れ、アッザムもエジプトへ移動した。そしてサウジアラビアの大学で教鞭を執ることになる。そのときの学生の中にオサマ・ビン・ラディンもいたというわけだ。 1984年、アフガニスタンでイスラム武装勢力がCIAの下でソ連軍と戦ったいる最中、アッザムはビン・ラディンとMAK(礼拝事務局)をパキスタンのペシャワルで創設しているのだが、この組織は後にアル・カイダと呼ばれるようになったという。 今年に入り、中東/北アフリカでは「民主化要求運動」が盛り上がっているが、エジプトやシリアではムスリム同胞団、リビアではアル・カイダの名前が出てくる。米英仏などの欧米諸国はイスラム武装勢力と手を組んでいるようにも見える。 こうしてみると、「911」でアメリカ政府は本気でアル・カイダを危険視していたのかどうか疑わしく思えてくる。実際、アル・カイダと敵対関係にあったイラクを攻撃してサダム・フセイン体制を破壊している。 「テロとの戦争」をはじめる切っ掛けになった「911」自体にも疑問は多い。4機の旅客機がハイジャックされ、そのうちAA11便とUA175便が世界貿易センターの超高層ビルに激突したとされているが、ペンタゴンへ突入したというAA77便の痕跡が現場には見あたらず、ピッツバーグとワシントンとの間で墜落したはずのUA93便は消えたままだ。 ちなみに、2001年5月31日から6月4日までの期間、NORAD(北米航空宇宙防衛司令部)は軍事演習を実施している。この演習が注目されている理由のひとつは、巡航ミサイルでアメリカの東海岸が攻撃されるという設定になっていて、演習のシナリオの書かれた文書の表紙にはオサマ・ビン・ラディンの顔写真が印刷されていたということがある。 「911」の前、イラクを含む外国、あるいはアメリカ国内の機関から「テロ計画」に関する警告が事前に出されていたのだが、アメリカ政府は反応しなかった。そうした情報が証券市場にも流れていたようで、「プット・オプション」(株式などを特定の日か一定の期間に、一定の数量を一定の価格で売る権利)が大量に買われた。問題の買い手はアレックス・ブラウンという会社だったと言われ、1998年まで同社の会長を務めていた人物はその後、CIAの幹部になっている。 水面下でどのような動きがあったのかは不明だが、表面に出ている部分を見ていると、アル・カイダは「911」から10年後の現在、役割が「テロリスト」から「自由の戦士」へ戻ったようにも思える。
2011.09.08
-
ゲーツ前米国防長官から「恩知らず」と罵られ、米国の議員に影響力を行使、米国の市民の意見を形成しようとしたことが露見したイスラエルの孤立
イスラエルを取り巻く環境が厳しくなっている。これまでは封印されてきた不満や怒りが表面に漏れはじめたということだ。ロバート・ゲーツ前国防長官もイスラエルを「恩知らずな同盟国」と表現しているが、アメリカにとっても「お荷物」になりつつあると言えるだろう。もっとも、1980年代にゲーツはイスラエル/ネオコンとイラクをめぐって対立した人物だが。 ちなみに、ゲーツのバックにはジョージ・H・W・ブッシュ副大統領(当時)やジェームズ・ベーカー財務長官(同)がいた。が、それでも、これほどあからさまにイスラエルを批判したことはなかっただろう。 イスラエルを信頼していないという点ではFBIも負けていない。ワシントンDCにあるイスラエル大使館を盗聴していたことが発覚したのである。FBIの翻訳官、シャマイ・レイボウィッツがリチャード・シルバースタインにその情報を漏らし、翻訳官は懲役20カ月を言い渡された。 しかし、話はそれで終わらなかった。イスラエルがイランの核施設を攻撃する可能性、あるいはイスラエルの外交官がアメリカの議員に影響力を及ぼしたり、国民の意見を形成しようとしていることをレイボブィッツは懸念していたことも表面化した。 イスラエルは以前から傲慢な国だったが、21世紀に入ってから度が過ぎる。その背景には旧ソ連圏からの亡命者や移民の増大があると言えるだろう。 1991年7月にロシア大統領となったボリス・エリツィンだが、それでは満足できず、独裁的な権力を握るために1993年、議会を戦車で攻撃して100名以上、あるいは約1500名の議員を虐殺している。クーデターを「西側」は非難しなかった。 エリツィン政権ではミルトン・フリードマン流の経済を推進、「規制緩和」や「私有化」といった掛け声で国民の財産を特定の人物へ二束三文で払い下げ、一握りの富豪を生み出し、庶民は貧困化させた。富豪たちは情報機関や特殊部隊の隊員、あるいは元隊員を雇って武力抗争を展開していく。中でも有名な人物がチェチェン・マフィアと手を組んでいたボリス・ベレゾフスキーだ。 しかし、1999年になるとエリツィン時代は終焉を迎える。庶民の怒りが独裁者を「玉座」から引きずり下ろしたのである。2001年にベレゾフスキーはイギリスのロンドンへ亡命、「プラトン・エレーニン」と改名した。 エリツィン時代に甘い汁を吸っていた少なからぬ富裕層がイスラエルへ亡命しているのだが、このベレゾフスキーも少なくとも一時期、イスラエルの市民権を持っていた。 こうした富裕層には勿論、財産がある。その財産によって、イスラエルの政治にも大きな影響力を持つようになった。旧ソ連圏からの移民も大きなインパクトをイスラエルに与えた。 21世紀に入ってからのイスラエル首相は、リクード/カディマのアリエル・シャロン、カディマのエウド・オルメルト、そしてリクードのベンヤミン・ネタニヤフ。いずれの政権とも和平には背を向けている。ガザ支援船「マビ・マルマラ」を襲撃した事件はイスラエルの現状を示している。 この襲撃は昨年5月、公海上で行われた。実行部隊はイスラエル海軍の特殊部隊「シャエテット13」で、ジャミングで通信を妨害して外部との連絡を絶ったうえで襲いかかり、マビ・マルマラ号に乗っていた9名が殺されている。その際、襲撃部隊員はジャーナリストらが撮影した映像を押収し、事件後に外部の調査に抵抗したものの、国連で非難されることになる。モサド(イスラエルの情報機関)の長官を務めていたメイア・ダガンがイスラエル議会で支援船襲撃を批判するほどの愚かな行為だった。この一件で「友好国」だったはずのトルコが離反、イスラエルは孤立しつつある。
2011.09.07
-
リビアの内戦には石油利権やアフリカ中南部の自立問題、つまり新植民地主義の問題が絡んでいるが、視点を変えると米英仏とBRICSとの戦いも見えてくる
ムアンマル・アル・カダフィ派が多いとされる都市、バニ・ワリードを反カダフィ軍は攻撃するとしている。NATO軍の空爆にカダフィ軍は為す術がないようにも見えるが、反撃のチャンスを待っているようにも思え、先行きはまだ混沌としている。 そうした中、反カダフィ軍の中から問題が早くも出てきた。本ブログでは何度も書いているように、リビアの反政府軍を指揮しているアブデル・ハキム・ヘルハジは「テロリスト」としてCIAから拷問を受けた過去がある。 イギリスとフランスが主導したとはいえ、少なくともリビアでは、アメリカもアル・カイダと同盟関係にある。手を組んだ相手から拷問に関する謝罪を求められたアメリカ政府はどう出るのか・・・。 ベルハジがリーダーを務めていたLIFG(リビア・イスラム戦闘団)がアル・カイダと緊密な関係にあることは自他共に認めているところ。ヘルハジの要求は「テロとの戦争」が間違いだったことを認めろと言っているに等しい。 反カダフィ軍が「黒人狩り」をしていることも大きな問題になっている。アメリカ中南部の出身だと思われる人びとを「傭兵」として拘束、一部が処刑されているとする情報もある。その大半は労働者だと言われているが、傭兵だとしても暴力的な扱いは許されていない。それとも「敵戦闘員」だから何をしても良いというのだろうか? ともかく、米英仏はかなり強引なことを行った。リビアの石油利権やアフリカ中南部の自立問題が絡んでいることは間違いないだろうが、その背景を見ると中国やロシアの存在が見えてくる。BRICS(ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ)の影と言っても良いだろう。リビアの内戦は米英仏とBRICSの戦いなのかもしれない。
2011.09.05
-
米英両国の情報機関がカダフィ政権と緊密な関係にあったことを示す秘密文書が発見され、あらためて米英両国がリビア攻撃に踏み切った理由が注目されている
アメリカとイギリスの情報機関、つまりCIAとMI6(正式にはSIS)がムアンマル・アル・カダフィ政権と緊密な関係にあったことを示す秘密文書をジャーナリストや「人権擁護団体」のHRW(ヒューマン・ライツ・ウォッチ)が発見したと報道されている。 文書が発見された場所は、カダフィの右腕と言われた治安の元責任者、ムサ・コサの個人オフィス。この人物は1994年から2009年までリビアの情報機関を統轄、その後外務大臣を務め、今年3月にイギリスへ亡命している。 問題の文書が作成された時期は1994年から2009年まで、つまり情報機関を統轄していた時期と重なる。1980年にイギリスから追い出された人物の亡命をイギリスが認めた理由は、コサが米英両国にとって都合の悪い情報を握っているからだとも言われている。 発見された秘密ファイルの中には、2002年から04年にかけてリビアがアメリカの「テロとの戦争」に協力したいたことを示す文書も含まれ、ステファン・ケイプスCIA副長官(当時)との協力関係も明らかにされているようだ。リビアの反政府軍を指揮しているアブデル・ハキム・ヘルハジはこの時期、CIAから拷問を受けていると語っている。 ベルハジはLIFG(リビア・イスラム戦闘団)のリーダーで、アフガニスタンでソ連軍と戦った経験もある。本ブログでは何度も書いていることだが、このLIFGはアル・カイダとの関係を公然と認めている団体。「テロとの戦争」を掲げていたアメリカの情報機関がヘルハジを拷問した背景は、おそらくこの辺にあった。 アメリカの情報機関がリビアと協力関係を結んだのは遅くとも1970年代だと考えられている。そうした工作の一環で武器をリビアへ密輸したのがエドウィン・ウィルソン。海軍情報部(ONI)やCIAの所属、リビアへ武器を密輸したなどとして懲役52年の有罪判決を受けたが、2004年に釈放されている。 この事件は「個人的な犯罪」だとされたが、ウィルソンにリビアへ行くように命じたのはCIAの「元高官」(CIA長官候補になったこともある)のセオドア・シャックレーだとするウィルソンの主張を信じている人は多い。ウィルソンの周辺はシャックレーだけでなく、ベトナム戦争での秘密工作や「イラン・コントラ事件」でも中心的な役割を果たしたリチャード・シコード空軍退役少将もいた。 ウィルソン、シャックレー、シコードたちとインドシナで一緒だった人物のひとりがリチャード・アーミテージ。このときの秘密工作は麻薬の密輸が深く関係、元グリーン・ベレーのジェームズ・グリッツ(通称、ボ・グリッツ)中佐によると、アーミテージは麻薬密輸で犯罪組織とアメリカ政府をつなぐキーマンだと主張していた。(詳しくは拙著『テロ帝国アメリカは21世紀に耐えられない』を参照してください) 今回、イギリスはこうしたリビアとの関係を清算、アメリカも追随し、アル・カイダとも手を組んでカダフィ体制を破壊した。リビア国内の石油利権も大きな要因だが、本ブログでは何度も指摘しているように、アフリカ中南部の自立問題も大きい。だからこそ、AU(アフリカ連合)がリビア攻撃に反対してきたのであり、反カダフィ軍がアフリカ中南部の出身者と見られる人びとを拘束、処刑している一因になっている。 リビアの石油利権をめぐり、反カダフィ派は「西側」と友好的な関係を結ぶとする一方、ロシア、中国、ブラジルとは「政治的な問題」があるとしているのだが、アフリカ中南部の問題でも中国の存在がイギリスなどを刺激したようだ。
2011.09.04
-
西側のエリートはリビアに続いてシリアに矛先を向けて揺さぶりをかけているが、米国がシリアの体制転覆工作を本格化させたのは遅くとも2005年のこと
まだリビアは内戦状態だ。NATOと反カダフィ軍(アル・カイダを含む)の連合軍が優勢ではあるが、カダフィ軍は降服せず、殺し合いが続いている。そうした中、「西側」はシリアを次のターゲットに定めて動き始めた。すでにシリアも内戦状態で、多くの死傷者が出ていると伝えられている。シリア内戦も単純な「民主化運動」ではなく、西側の思惑が強く反映されている。 現在、シリアの大統領はバシャール・アル・アサド。アメリカのバラク・オバマ大統領やヒラリー・クリントン国務長官などはアサド大統領に対して退陣を求めているのだが、シリアの体制転覆を目指す秘密工作をアメリカ政府が本格化させたのは、遅くとも2005年のことである。米国務省がシリアの反体制派に資金を提供していたことを示す外交文書が存在するのである。 この件についてはすでに本ブログで取り上げているので詳細は割愛するが、シリアの反体制派は「MEPI(中東協力イニシアティブ)」や「民主主義会議」なる組織を通してアメリカから資金を得ているという。アメリカの外交文書によると、2005年から10年までに1200万ドルが流れている。 2005年といえば、イラクからサダム・フセインを排除してシリアとイランに矛先を向けた頃。レバノンでは、この年の2月には大きな出来事もあった。ラフィク・ハリリ元レバノン首相が暗殺されたのである。国連国際独立委員会のデトレフ・メーリス調査官は早い段階からシリアの情報機関が犯行の黒幕だと決めつけ、別の可能性を示す証言や証拠を無視していた。 2005年12月にはアブドゥル・ハリム・カーダム元シリア副大統領がハリリ暗殺とアサド大統領とを結びつける発言をしているが、このカーダムを中心とする勢力はパリを拠点として反政府運動を展開してきた。カーダムと並んでシリアの反体制派として注目されているのは、バシャールの伯父にあたるリファート・アル・アサドを中心とする勢力だ。ムスリム同胞団の存在も無視できない。 2005年10月にメーリス調査官はこんなことを言っている:「ラフィク・ハリリ元首相の殺害がシリアの治安機関幹部の許可なく、またレバノンの治安機関内部の共謀なしに実行されることはありえないと信じる有望な根拠がある。」 とにかくシリアが怪しいと言っているだけだが、このメーリスが行った調査は杜撰で、例えば、暗殺に使われたとされている三菱自動車製の白いバン(キャンター)がどのように調達されたかも明確にされていない。2004年10月12日に日本の相模原で盗まれ、アラブ首長国連邦のドバイを経由してベイルートに運ばれたというのだが、その間に誰がどのようにして運んだのかは示されていないうえ、本来の所有者が誰なのかも不明だ。 メーリス調査官が採用した証人の信頼度に疑問を投げかける人も少なくない。例えば、ドイツのシュピーゲル誌によると、同調査官の重要証人であるサイド・サディクは有罪判決を受けた詐欺師であり、この人物を連れてきたのはシリアの反体制派リファート・アル・アサドだというのだ。サディクの兄弟によると、メーリスの報告書が出る前年の夏、サイドは電話で自分が「大金持ちになる」と話していたという。 もうひとりの重要証人、フッサム・タヘル・フッサムはシリア関与に関する証言を取り消している。レバノン当局の人間に誘拐され、拷問(ごうもん)を受け、その上でシリア関与の証言をすれば130万ドルを提供すると持ちかけられたと話している。 また、アーマド・アブ・アダスという人物が「自爆攻撃を実行する」と宣言する様子を撮影したビデオをアルジャジーラは放送しているのだが、この人物が本当に実行犯ならばメーリス調査官のシナリオは崩壊する。そこで、アブ・アダスが途中で自爆攻撃を拒否したのでシリア当局に殺されたということにされた。 ヒズボラの指導者、ハッサン・ナスララーは今年の8月9日、暗殺前にイスラエルのスパイ機がハリリについて調べていることを示す映像などを公表し、イスラエルが暗殺に関係していることを示唆しているとしている。 実は、アル・カイダのメンバーが2006年にハリリを暗殺したと証言している。2005年12月と翌年1月にアル・カイダのメンバー11名をレバノン当局が逮捕、いずれもすぐに暗殺を認めたと報道されているのだ。 後に「拷問による自白」とされたが、この拷問話に疑問を持つ人は少なくない。逮捕した内務省の幹部にとってアル・カイダが実行したとする話は都合が悪く、実行者にしかわからない情報が含まれ、調書を読んでも拷問があったとは思えないということだ。 それでも国連の調査はアル・カイダに関する情報を無視する一方、2007年にリチャード・チェイニー米副大統領(当時)はジョージ・W・ブッシュ米大統領(同)に対してシリア爆撃を進言した。この話はチェニーが自叙伝の中で明らかにしている。
2011.09.02
全27件 (27件中 1-27件目)
1