第五話 サンガララの戦(1)

【 第五話 サンガララの戦(1) 】
トゥパク・アマルの直観は正しかった。
彼の側近フランシスコの追跡も虚しく、キスピカンチ郡の代官カブレラは、この時、這う這うの体(てい)で、しかしながら、ついにクスコに逃げ込むことに成功したのだった。
真夜中の来訪者のもたらした、そのただならぬ知らせに、このクスコ市に多く在住していたスペイン人大物役人たちは顔面を蒼白にした。
翌朝には、トゥパク・アマルの反乱の噂はクスコ市全土にたちまち広がった。
人口2万5千の、このかつてのインカの旧都は、上を下への大騒ぎになった。
クスコ市の代官バルデスは大至急、戦時委員会を組織した。
本営を旧イエズス会の教会に置き、そこに集めうる限りの武器を集め、クスコ市内外のトゥパク・アマルの仲間が急襲をかけてくるのに備えた。
さらに、至急、哨兵をクスコ市内や近郊のインカ族の多い集落に配備し、武力蜂起の勃発に険しい眼を光らせた。
そして、すぐさま、副王ハウレギの膝元であり、且つまた、植民地支配の中枢、インディアス枢機会議本部の置かれている首府リマに向けて密使を走らせた。
戦時委員会によって使者に持たされた書面には、概ね下記のようにしたためられていた。
『ティンタ郡のカシーケ(領主)たるトゥパク・アマルが、当地の代官アリアガを殺害し、民衆を扇動して武装蜂起。
これより、トゥパク・アマル一味の討伐に向け、クスコ市の戦時委員会ならびにスペイン王の全臣民は、国王のためにいかなる犠牲をも惜しむものではありませぬ。
しかしながら、トゥパク・アマル率いる暴動は既に幾つかの郡に渡っているため、大至急、援軍をお送りください。』
つまるところ、その内容は、早急なる援軍要請であった。
その重大なる情報をもって、スペイン側の密使は、今、ついに首府リマに向けて走りはじめたのである。
そして、クスコの僧侶たちもこれに呼応して行動を開始した。
このクスコには、当植民地におけるカトリック教会の頂点に君臨する最高位の司祭、かのモスコーソがいた。
トゥパク・アマルが反乱決行前に、この人物との目通りを試みたことをご記憶の読者もおられるかもしれない。
モスコーソ司祭の豪邸で開かれた僧侶たちの会議では、多額の軍資金の援助が定められ、市民からも莫大な現金を集めることが可決された。
また、僧侶たちは、多数の鉄棒を至急作り、武器として供出することを誓約し、さらに、100頭の牛を軍に貸与することを決議した。
しかし、この時、スペイン人の誰よりも、いかなる行為よりも、その影響力を振るったのは、さすがにモスコーソ司祭、その人だった。
トゥパク・アマルの反乱を知ったモスコーソは、普段は不自然なまでに慈愛深気に細めているあの目さえ、もはや周囲のスペイン人が見てもその変貌ぶりに恐れをなすほど、あからさまにギラギラと血走らせ、その貫禄づいた体を怒りに震わせた。
「トゥパク・アマルめ…!!
余の忠告を聞き入れずに、このようなことをしでかしおって…――!!」
モスコーソは憤怒に燃える眼で歯軋りしながら、窓外に垂れ込める灰色の空を激しく睨みつけた。
「この国でカトリックの頂点に立つ副王陛下に盾つく反乱行為は、神への反乱行為ぞ!!」
そして、「たかがインディオの分際で…!!たかが、インディオごときが…余が司祭であるこの時に…!!」と唸りながら、呪いに満ちた形相で、次なる一手を打つべく這うように書斎へと向かっていった。

書斎の豪奢な机に伏すようにしながら、モスコーソ司祭は地底から湧きだすごとくの低いしわがれた声で呻く。
「トゥパク・アマル、目にもの見せてくれるわ…!」
もはや、怒りの極みに歪むその顔には、青白い不気味な炎が炯炯と燃え上がる。
モスコーソは、わななく手でペンを握ると、その「司祭」という絶大な名望と権力の名において、国中の司教区の神父たちへ回状を書きはじめた。
歴史上の資料に残るその内容は、概ね、下記のごとくである。
『トゥパク・アマルの反乱に徹底的に抵抗せよ。
各地の司教は、決して、己の任地を放棄し、去ってはならぬ。
司教がその教区に住まうことは、教区民の災難、生命の危機、疫病のときに、ひときわ重要である。
イエス・キリストが言われたように、よき神父とはその子羊のために生命を犠牲にするものである。
逆に、牧者の名に値しない神父とは、狼が子羊を食べにやってくるのを見ながら、彼らを危機に置き去りにするものである。
トゥパク・アマルはティンタ郡で代官殺しという残忍な罪を犯した後、多数の人々を扇動して集落を襲い、災害と恐怖を与えている。
これは考えられる限りにおける危急重大な事態であり、いってみれば狼が子羊を喰おうとしている場合に他ならぬ。
もし、神父がトゥパク・アマルの襲撃を恐れて己の教区を見捨てるならば、その教区の子羊たちは、無学文盲であり、将来を見通す力も皆無な上に、自己への尊重も責任も持たぬ故に、反乱の暴徒に与(くみ)し、神と宗教と王に叛(そむ)くであろう。
そのような事態を決して招いてはならぬ。
従って、余はこの回状を緊急に発送することが必要と考えた。
よって、教区の神父ならびにその代理は、いかなる口実、動機があろうとも、己の任地を決して離れてはならぬ。
そして、それぞれの教区の信者たちには、スペイン王とその配下の役人たちに、忠誠・愛・服従を捧げ、決して反逆者トゥパク・アマルの悪事に加担せぬよう、うまく、また終始、説得するのだ。』
モスコーソは、鬼のような形相で一気にそこまで書き上げると、ひと通り全文を見渡した。
そして、決して書き忘れてはならぬことを、最後に、力をこめて書き足した。
『なお、それぞれの教区の信者たちに次の点をよく言い含め、この反乱に与(くみ)することの、その罪の重大性を強く認識させよ。
万一にも、この反乱に加担する者は、全財産を失い、その一族は末代までの恥となり、神にも人にも忌み嫌われるであろう。
そのことを、よくよく言い聞かせるのだ。
特に、各教区内のインカ族の者には、重ねて言い含めよ。
そして、万一にも、以上の命に反する神父やその代理は、破門、その他、余の保有する権限で厳罰に処するであろう。
最後に、この書面を受け取り筆写したしるしに署名をせよ。
クスコにて。
1780年11月14日
司教フワン・モスコーソ』
こうして、モスコーソ司祭を筆頭として、これらクスコのスペイン人有力者たちの反乱への対抗行動が、堰切ったように開始されたのだった。
だが、既にこの頃には、トゥパク・アマルの数年間に渡る周到な反乱準備によって手を結んできた各地の同盟者たちが、一斉に立ち上がりはじめていた。
さらに、トゥパク・アマルの派遣した側近ディエゴの分遣隊はそれらの一斉蜂起をよく援護し、反乱の火の手はますます勢いを増しつつあった。

一方、トゥパク・アマル率いるインカ軍本隊は、各地に転戦してその勢力を拡大しながら、植民地支配を瓦解せしむためには必ずや奪還せねばならぬ、かつてのインカ帝国の旧都クスコ目指して軍団を進めていた。
そして、その道程にある各郡を統治下へ治めるべく、対抗勢力との闘争を重ねていた。
流血の事態は、トゥパク・アマルとて決して望むものではない。
しかしながら、牙城クスコ奪還に向けて、クスコ周辺の主要な郡を統治下に治め、代官の職能を廃絶し、民衆を解放し、且つまた、兵力を増強するために、各郡の抵抗部隊――それは、スペイン側の抵抗部隊であるが――との戦闘は避けられぬものであった。
そして、その日も、クスコへの道程にあるクシパタ郡への進軍を予定していた。
クシパタ郡はコルディエラ山脈の谷間にある山岳地帯の郡で、長大なビルカマユ川がその郡の輪郭に沿うように悠然と流れている。
かくして、この郡には既にクスコの戦時委員会から派遣されたスペイン人から成る援軍が銃器を携え、厳しい警護の目を光らせていた。
また、当地の代官お抱えの部隊も、小銃を携え、且つ、よく訓練されていた。
まともに正面から戦闘をしかけても、勝機は無い。
トゥパク・アマル及び参謀オルティゴーサを中心に、アンドレスを含む各連隊長たちは、事前に慎重な戦略を練っていた。
まずはその地形を詳細に吟味し、戦闘場所を絞り込む。
そして、クシパタ郡の入り口付近にある街道沿いの低地にその場を定めた。
そこは、コルディエラ山脈とビルカマユ川とにちょうど挟まれた山岳部の街道の一部で、敵がインカ軍の侵攻を食い止めるための進軍途上で、必ずや通るはずの場所だった。
クシパタ郡の哨兵の目を逃れるため、深夜、その街道に密かに侵入したインカ軍の兵たちは、敵方の進路にあたるその街道の一角に、その進路を塞ぐがごとく石や木で巨大な障害物を構築した。
土地勘に優れたビルカパサ率いる連隊が、主にこの障害物建造を担当した。
この時は、武器を持たずとも参戦できたため、コイユールも障害物造りに参加した。
そして、オルティゴーサやアンドレスら率いる複数の連隊からなるインカ軍本隊は、総指揮官トゥパク・アマルのもと街道に面した山の上に身を潜めた。
街道の向こう側は、ビルカマユの川が流れ、自然の要害を成している。
オルティゴーザ率いる連隊は、これまでの戦果として入手した小銃で武装し、アンドレス率いる連隊は主にサーベル、棍棒、斧などで武装していた。
やがて、早朝、インカ軍討伐に向けてクシパタ郡の代官率いる部隊及び、クスコからの援軍が、つまりは、スペイン兵が、この山と川に挟まれた街道を進軍してくるのが見えはじめる。
突如、街道沿いに出現した巨大な障害物に目を見張ったスペイン兵の前衛部隊が除去作業をはじめた時、山上に潜むインカ兵から一斉にオンダ(投石器)による無数の石が放たれ、スペインの前衛部隊を混乱に陥れた。
トゥパク・アマルの号令と共に、機を逸せず、参謀オルティゴーサの連隊が小銃を中空に連発して敵の混乱を煽りながら、怒涛のごとく前衛部隊に突撃していった。
混乱の極みに達したスペインの前衛部隊はまともに戦うことのできぬままビルカマユ川に落ち、あるいは、後衛部隊であるスペイン本隊の方へ一斉に逃走しはじめる。
突如、前衛部隊が脱兎のごとく一斉に逃げ込んできたために、スペイン兵の本隊自体が混乱の渦中に陥った。
その機をとらえ、そのまま混乱したスペイン兵本隊めがけ、アンドレス率いる連隊がサーベルや鈍器を手に、側面から一斉に切り込んでいく。
アンドレスは黒馬に跨り自らが先陣を切って前線に立つと、その鮮やかな剣さばきで華麗に敵をなぎ倒しながら、同時に、軍団の兵たちを右に左にと指揮をして、いっそう敵を混乱に貶(おとし)めた。
一方、味方の将であるアンドレスの、自ら敵の真正面切ってのまるで軍神のごとくな勇ましくも美しい戦いぶりに、インカ軍の兵たちは魅了され、高揚し、その士気は大いに高まった。
さらに、インカ兵たちの打ち鳴らす激しい太鼓の音がアンデスの大地の神を目覚めさせ、角笛の高らかな響きが天空の神々を引き寄せる。
そこへトゥパク・アマルの指揮のもと、義勇兵も含む残りのインカ軍が雪崩れ込むがごとくの勢いで、一斉にスペイン兵本隊に突撃を加える。
戦闘が決するまで、殆ど時間はかからなかった。
あえなくスペイン側の兵たちは、殆ど全く何もできぬまま敗走したのだった。
今ここに、トゥパク・アマル率いるインカの民は、その武力と戦術によって、かつてこのラテンアメリカの地に広大なるインカ帝国を築き上げた、かの武勇に秀でた誇り高き民族たちの、まさしく、その末裔たちだったのである。

このようにして占拠した地で、トゥパク・アマルは、かつてのティンタ郡の広場における時のように、インカの魂を呼び覚ますべく各地の民衆に高らかな演説を続けて回った。
この頃から、彼の訴えの中では、この反乱が決して教会や僧職に逆らうものではないことを伝える色合いが強まっていた。
彼は、「我々の行動は、強制配給、その他すべての人民を脅かす悪税などの、言語道断な習慣、悪政を破棄するためのものであって、決してキリスト教の道に逆らうものではなく、信仰を変える必要もない。」ことを、縷々(るる)説明した。
それは、怒りの極みに達したモスコーソ司祭の発した回状――あのトゥパク・アマルをキリスト教の反逆者とみなし、徹底抗戦を激しく訴えた回状――を意識してのことである。
彼は、モスコーソの回状に、苦々しい思いを噛み締めずにはいられなかった。
反乱幕開け時から、キリスト教に反旗を翻すことは決してなかったトゥパク・アマルだったにもかかわらず、モスコーソの手によって、今やキリスト教へ楯突く呪うべき反逆者として仕立て上げられ、国中に広く宣伝されていた。
もとより予測していたことではあったが、やはり、このことによる打撃は看過できるものではない。
確かに、今、まだこの勢いのある時期は、その痛手も目立たない。
実際、インカ皇帝の化身のごとくのトゥパク・アマルの進軍によって、深く感動した各地の多くの民衆たちは、モスコーソ司祭のあれほどの強烈な脅しにもかかわらず、インカ軍への参戦を否まなかった。
だが…――と、トゥパク・アマルは、その事態を決して楽観はしていなかった。
大量の銃や大砲などの火器を携えたクスコ及びリマのスペイン軍本隊との直接対決が行われた暁には、その勝機は必ずしも保証できるものではない。
インカ軍の勢力に翳(かげ)りが出てきた暁にこそ、あのモスコーソの恐るべき影響力が多くの民の心に滑り込んでいくであろう。
その時こそ、自らに押された「キリスト教への反逆者」という烙印の痛手は、はかりしれぬものになるやもしれぬ。
特に、敬虔なキリスト教徒であることの多い、当地生まれのスペイン人たちの心が離れていく可能性は大きかった。
トゥパク・アマルも形の上では洗礼を受けており、キリスト者の一人とみなされているが故に、敬虔な信者たちである当地生まれのスペイン人たちも、安心して彼を信頼できている側面があることは否定できなかった。
いずれの方向から考えても、モスコーソの打ってくる手は、トゥパク・アマルには手痛いものであった。
トゥパク・アマルは、暗雲迫り来る近い将来を睨みつけるがごとくの険しい眼差しで、前方を見据えた。
だが、彼の目は、決して光を弱めてはいない。
その日の進軍を終え、夕暮れ時の荒野を野営場へ引き返す軍団を率いながら、彼は愛馬の手綱を握る手に力をこめた。
たとえ、モスコーソ司祭が、いかように己(おのれ)を悪し様に宣伝して回ろうとも、キリスト教に反旗を翻していないという事実こそが、真実だ。
トゥパク・アマルの毅然とした端正な横顔で、その美しい切れ長の目がいっそう鋭い光を放つ。
実際、彼は、民衆のキリスト教崇拝を否定することなど一切してはいなかったし、むしろ、統治下に治めた各地の教会を厳重に保護し、スペイン人の神父たちにも危害を加えることは決してなかった。
戦闘時にさえ、教会が血で汚されることのないよう、細心の配慮を払ってもいた。
トゥパク・アマルは己の頭を冷やすように、すっと冷たい夕刻の風を吸い込んだ。

吹き抜ける夕暮れ時の風は、既に初夏の気配がする。
正面では、コルディエラ山脈に沈みゆく太陽が、その日最後の透明なオレンジ色の閃光を放っている。
トゥパク・アマルを、そして、彼の跨る逞しい白馬を朱色に染めゆく陽光を、彼は真っ直ぐな目で見つめた。
神への反逆を行っているのは、あなたの方であろう、モスコーソ司祭よ。
永きに渡り、かの極道な代官たちが、非道な搾取や不法な税の取立てによって臣民の惨めな戸口から悉(ことごと)く金を搾り取り、かくして第二のピサロもかくやとばかりの暴虐の限りを尽くしていたのを、あなたは知りながらも放置し、否、それを利用して圧政を敷き続けてきた。
カトリック教会の頂点に立つ者として、あるまじき行いに加担し続けてきたのは、あなたであろう…――神を恐れぬ真の反逆者、それは、モスコーソ、あなたの方だ!!
そうである以上、あなたがどのような仕儀を行ってこようとも、決してそれに屈するわけにはいかぬ。
今や殆ど山の端に姿を消しつつある太陽は、しかし、その光は長大な山脈の輪郭をくっきりと浮き立たせ、荘厳で鋭利な美しさを描き出している。
トゥパク・アマルはその自然美を己の心に写し取るかのように、暫し、息を詰めて見守った。
再び、黄昏時の冷気を深くその身に吸い込むと、トゥパク・アマルはモスコーソのことを考えていた頭を切り替えた。
彼には、今、まだ確実に勢いのあるうちに果たしておきたいことが、もう一つあった。
トゥパク・アマルは、整然と隊列を成し、誇りを漲らせ、凛々しく歩みゆく義勇兵たちの方に視線を向けた。
そして、インカ軍のために勇敢にも馳せ参じてくれた多くの黒人の者たちを、熱を帯びた眼差しで見渡した。
黒人たちは、奴隷としてアフリカからはるばる南米の当地まで連れてこられ、スペイン人のもとで過酷な労働に従事させられてきた者たちである。
且つまた、彼らは、この軍に加わるために、主人の目をかすめていかに危険な逃亡を試みてきたことか。
トゥパク・アマルの心に、熱いものがこみあげる。
この父祖の地に住むインカ族の者さえ保護する者の殆どなかったこの国で、はるか母国から引き離され、物のごとくに扱われながらも、これまで彼らを保護する者はインカ族の者たち以上に存在しなかったはずである。
その苦難は、察するに余りあるものであった。
トゥパク・アマルは再び、その包み込むような眼差しで、今や混成の軍団の一部をしかと成している黒人の者たちを見つめた。
そう、トゥパク・アマルがもう一つ果たしておきたかったこと、それは、まさしく黒人奴隷の解放であった。

事実、歴史上の資料によれば、1780年11月16日、彼は黒人奴隷解放令を布告している。
トゥパク・アマルのこの解放令によって、彼及び同盟者たちの統治下に置かれた各地で、この日、すべての黒人奴隷が解放され、ついに己の身の、そして、心の自由を手にしたのだった。
かくして、解放令が布告された日の晩、高原の要所に陣を敷いたインカ軍本隊の広い野営場のそこかしこからは、打楽器のリズムと明るい歌声が上がり、高所に張ったトゥパク・アマルの天幕までそれらの音が流れ込むように届いていた。
天幕を抜けて、高台から義勇兵たちの野営地を見下ろすトゥパク・アマルの傍に、老練の側近ベルムデスが近づく。
ベルムデスは、トゥパク・アマルが幼き頃から、両親をはやくに亡くした彼の父親のごとく、近しく彼に接し、見守り、また、時に養育してきた壮年の重臣である。
二人の見下ろす視線の先では、眼下の野営地のあちらこちらで焚き火を囲み、複数の義勇兵たちがそれぞれに円陣を組むようにして座り、何やら賑やかに談笑している様子が見える。
よく見ると、そこに集っている兵たちは、多くが黒人の者たちのようであった。
ベルムデスはトゥパク・アマルの方に軽く目配せしながら、温和な笑顔をつくって言う。
「どうやら、黒人の兵たちが、祝杯を上げているようですな。」
トゥパク・アマルも合点がいって、「祝杯…なるほど、そうでしたか。」と静かに微笑む。
「皆、トゥパク・アマル様の出された黒人奴隷解放令を喜んでいるのでしょう。
とはいえ、もう夜も遅い。
そろそろ控えさせましょうか。」
問いかけるベルムデスに対して、トゥパク・アマルは野営地を見下ろしたまま、「いや、まだよいでしょう。」と、変わらず静かに応える。
「あの者たちは、永きに渡り、我々インカ族の者たちよりもさらに過酷な運命を侵略者たちによって強いられて参りました。
今宵は、存分に、羽を伸ばすがよいでありましょう。」
そう言って、眼下にゆるやかな視線を注ぎながら目を細めるトゥパク・アマルの横顔に、「それもそうですな。」と、ベルムデスもその目元に皺を寄せて微笑んだ。
涼やかな夜風を共に浴びながら、ベルムデスはトゥパク・アマルの横顔をそっとうかがう。
(あなた様は、昔から、他の者の苦しみを、どのような末端な者のそれまでをも真に己の苦しみとし、まるっきり己のことなど忘れてしまったように、常に、この国全体のことばかりを考えていらした。
いつもそればかりで、あなた様自身の幸福を置き去りにされているのではないかと、案ずる気持ちもあったが…。)
そんな思いを抱きながら改めてトゥパク・アマルを見るベルムデスの瞳の中に、恍惚たる表情のまま、瞳を輝かせ、祝杯を上げる黒人たちを見下ろすトゥパク・アマルの包み込むような眼差しが映る。
(あなた様は、歴代のインカ皇帝の、まさに生まれ変わりなのかもしれませんな。
生まれながらに、王なのか…――。)

ベルムデスは、思わず、ふっと微笑む。
と、トゥパク・アマルが不意にこちらを向いた。
「何か?」
少々訝しげに問うトゥパク・アマルに、「いやいや。」と、軽く手を上げてベルムデスが老練な穏やかな笑顔を返す。
「何です?」と、神妙な顔になって詰めてくるトゥパク・アマルに、「いや、本当になんでもないのです。では、私はこれで。」と、笑顔で頭を下げると、ベルムデスはさっと立ち去った。
トゥパク・アマルはそんなベルムデスの後姿を見送ると、暫し、眼下に視線を戻し、流れ来るリズミカルな打楽器の音と、微かに響いてくる笑い声に、再び耳を傾けた。
一方、ビルカパサの連隊の野営地の片隅では、かの黒人青年ジェロニモが円陣の中央に座り、素焼きの筒に皮を張った手製の打楽器を勢い良く打ち鳴らしていた。
大地の奏でるような「タンタンタン」と響く野趣溢れる乾いた音は、深く、熱く、魂に染み渡る。
彼の周りには、やはり、ビルカパサの連隊に参加している黒人男性たちが、老いも若きも、おおよそ30人ほどが集(つど)っている。
ジェロニモの傍には焚き木の炎が赤々と燃え、額に汗しながら陶酔したように楽器を打ち鳴らし続ける彼の姿を、夜闇の中に浮き上がらせていた。
その周りでは、数名の黒人兵たちがジェロニモのリズムに合わせ、ひょうたんを手に楽器のごとくに打ち鳴らしている。
彼らの周りでは、それらのリズムに合わせて地を踏み鳴らして踊る者、歌う者、談笑する者がおり、そんな彼らの間から、幾度も「トゥパク様、万歳!!」の祝声が上がっては、酒よろしく水を酌み交わす姿が見られた。
その集団の方に、コイユールを引っ張るようにしながら手を引いて、マルセラが元気な足取りで近づいていく。
「ほらほら、はやく!!
私たちも一緒に祝杯を上げなきゃ!!」
マルセラの勢いにやや気圧さたような表情のコイユールに、マルセラがずいっと顔を寄せた。
「あんた、最近、なんだか元気ないんだもん。
たまには、パーッと騒がなきゃ!!
ね、さ、いくよ!!」
そう言い終るか否かの間に、マルセラは集団の中に勢いよく乗り込んでいく。
「私たちも、入れてくれない?!」
他方、今や連隊長補佐官でもあるマルセラのいきなりの乱入に、黒人兵たちの方が肝を抜かれたように、一瞬、緊張の空気が走る。
しかし、すかさずジェロニモが人懐こい笑顔を向けると、「マルセラ様、入った!!入った!!」と、明るく呼び入れた。
「そのかわり、今日は、無礼講ですから!!」と、全く物怖じしない調子で、楽器を鳴らしながら言う。
そんなジェロニモに、「そういうセリフは、普通、こっちが言うんだけど。」と切り返しながら、マルセラも闊達に笑うと、円陣の中に入って座った。
その後に続くように、「こんばんは。私も、ご一緒に…。」と、ややはにかんだ表情で、しかし、澄んだはっきりした声で挨拶しながら、コイユールも集団の中に加わった。

コイユールの姿を認めると、ジェロニモが近くの黒人男性へ「これ、代わってくれ!」と素早く楽器をバトンタッチして、コイユールの傍に寄ってきた。
かたやマルセラは、「わ!何それ!手製の楽器?!私にもちょっと叩かせて!」と、ジェロニモが交替した男性の方に、興味津々の顔で近づいていく。
そんなマルセラの屈託ない様子に、むしろ感心しながら見守るコイユールに、ジェロニモが水の入ったカップを持ってきて、「祝杯だ!」と笑顔で言う。
コイユールが「ありがとう。」と受け取ると、「トゥパク様に乾杯!!」とジェロニモが朗らかな声を上げ、彼女のカップに自分のそれを勢いよく当てた。
それに合わせるように、二人の周りでも、「乾杯!!」の歓声が再び高らかに上がる。
コイユールは、そんな人々の恍惚とした表情を、眩しそうに見つめた。
カップを口からはずすと、ジェロニモは少しまじめな顔になって、コイユールの顔を見る。
「君の両親も、確か、ポトシの鉱山で亡くなったんだったよね。」
「ええ。」
「あそこには、たくさんの黒人奴隷もいたってこと、知ってる?」
「あ…、聞いたことはあるけれど。」
ジェロニモは頷くと、足元にカップを置き、焚き火の方に視線を向けた。
その眼差しの鋭さに、コイユールは息を呑む。
今までの、どこかふざけた様子の彼とは、まるで別人のようにさえ見える。
「君の両親も大変だったろうけど、黒人奴隷は、インカ族の者たちよりも、もっと、ずっと過酷な条件で働かされているんだ。
全くの使い捨てサ。
働けなくなったら、殺されるんだぜ。
ひでぇ話だろ。
ま、それもそうだよな。
黒人奴隷は、『金で買われた労働力』、モノと一緒なんだから。」
コイユールが絶句していると、ジェロニモはゆっくりと視線を彼女の方に戻した。
そして、微かにその瞳を震わせて、「俺の両親も、ポトシの鉱山に買われて行って、あそこで殺された。」と、呟くように言う。
胸を突かれたような思いに駆られ、コイユールは殆ど無意識のうちにジェロニモの手に自分の手を添えていた。
「スペイン人を…恨んでいるの?」
自分の手に添えられたコイユールの手の方が震えているのを感じながら、ジェロニモは「恨んでない…なんて言えば、嘘になるが。」と、感情を抑えた低い声で応える。
しかし、すぐに、落ち着いた、いつもの張りのある声に戻って言う。
「だけど、俺が戦いに参加したのは、奴らを恨んでるからってわけじゃあ、ないのサ。
奴らに壊された俺ら先祖や親たちの人生を…奪われた自由を、俺たち子孫の力で取り戻したいってだけだ。
あのアフリカの大地の民の誇りにかけて、ね!
それに、トゥパク・アマル様が、黒人奴隷解放令を出してくださった。
トゥパク様の統治下にある領地では、既に、解放がはじまっている。
国中の俺たち黒人の苦しみが終わる日も近いサ!!」
そう言って、「君だって参戦したのは、ただ恨みからってわけじゃあ、ないんだろ?」と、コイユールにあの出会いの日と同じ茶目っ気のあるウィンクを投げると、突然、自分の手に添えられていたコイユールの手を握り、「踊ろう!!」と立ち上がった。
思いがけぬ誘いに、コイユールが、「えっ?!」とビックリして目を瞬かせている間に、周囲からも和やかに囃(はや)し立てる歓声が上がり、一枚の彩り美しいハンカチが一人の黒人兵から投げられた。
「お嬢さん、俺らの踊りは、それを持って、だよ!!」
コイユールが呆気に取られつつもハンカチを拾っている間に、ジェロニモは自分の靴を投げ捨てるように裸足になると、「それから、俺たちは、裸足で踊る!靴、脱いで!はやく!!」と笑顔で急(せ)かす。
「えっ?えっ…。」と目を丸くして驚き、戸惑いながらも、観念したようにコイユールが靴を脱ぐ。
すると、アフリカ的な、そして、躍動的ながらも低音が深く心に響く打楽器のリズムが、黒人兵たちの手によって奏でられはじめる。
さらに、それに呼応するように、歌声が湧き上がる。
その歌は、強制労働を強いられた黒人奴隷たちが想いを込めて歌い続けてきた、自由と解放の悲願の詩…――。
彼らの奏でるそのリズムは次第にスピード感を高めながらも、時に哀愁を帯び、時に優雅に、時にゆったりと、そのテンポを自在に変えていく。
マルセラはといえば、相変わらず初めての楽器を抱えながら、しかし、さすがに運動神経の良い彼女は、他の黒人たちの演奏に混ざりながら、既にそれなりにリズムを取れている。
そして、「ほら、コイユール!!私の演奏じゃ、踊れないってワケ?」と、ふざけて軽く睨んでくる。
いつの間にか、周囲に座っていた黒人兵たちも立ち上がると靴を脱ぎ捨て、男同士ながらペアになり、ハンカチを片手に、あるいは、ハンカチに加えて水瓶やひょうたんも頭上に乗せて、リズミカルに、器用に、踊りはじめる。
「ほら、あんなふうに!!」
明るい笑顔を向けるジェロニモを、コイユールは、まだ躊躇(ためら)う表情で見上げた。
そんな彼女の耳元に、ふいに顔を寄せてジェロニモが言う。
「俺たちの祖先は故郷のアフリカから引き離され、無理矢理ここに連れてこられて、終わりなき強制労働だった。
心の支えは、ずっとこの歌とリズムだけだった…のサ!
この響きは、死にかけた俺たちの魂を生き返らせてくれる。
だから、今でも生きているこのリズム、これを守って、ずっと伝えていく!
さあ、踊ろう!!」
コイユールもやっと頷くと、笑顔を返し、見よう見まねで踊りはじめる。
(そういえば私たちにも、インカの時代からずっと愛されてきた優しい音色を奏でる楽器たちが、旋律が、生きているっけ…。)
コイユールは己の心にあたたかなものが満ちてくるのを感じながら、今だけは戦乱の中にあることを忘れて、大地から放たれる、躍動的で、それでいて、どこか哀愁を誘うリズムに、その身を委ねていった。
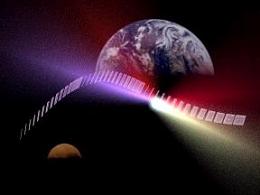
一方、ますます勢力を増し、黒人奴隷解放令なるものまで発したトゥパク・アマルに対して、かのクスコの戦時委員会では、いっそう気色ばんだスペイン人有力者たちが、血走った眼で顔をつき合わせていた。
しかも、敵はこのインカ帝国の旧都クスコ奪還を目指して、その勢力を増幅させながらジワジワと軍を進めてきているのである。
大軍を率いたトゥパク・アマルが当地を襲撃してくるのも、もはや時間の問題と思われた。
この期に及んでは、クスコのスペイン側にとって、事態は考えられ得る限りの最も深刻、且つ、身の毛のよだつ空恐ろしきものであったのだ。
クスコの名士たちが赤くなったり青くなったりしている間も、かのモスコーソ司祭は、それこそ頭から湯気を立てぬばかりの勢いで憤怒にわなないていた。
モスコーソは額によせた血管がはち切れぬばかりの憎悪と怒りに満ちた形相で、毒づくように言う。
「トゥパク・アマルにこれ以上、勝手なことをさせてはならぬ!!
反乱がこれ以上広がらぬよう、さっさと手を打つのじゃ!!」
己のしたためた教区宛の回状の効果がさして上がっていないことも、この司祭をいっそう苛立たせ、逆上させていた。
握り締めたその拳は、傍から見てもわかるほどに、わななき震えている。
常日頃の、あの不自然なまでに慈愛深気で懐柔的な態度のその人とは別人のような司祭の豹変ぶりに、クスコの名士たちでさえ恐れをなして、身を縮めた。
「首府リマに使者が到着するまでには何日もかかるのじゃ。
その上、援軍を待っていては、トゥパク・アマルの思うままにされてしまおうぞ。
これ以上、反乱の規模が広がる前に、もっと強靭な討伐軍を差し向けるのじゃ!!」

鬼のような形相でまくしたてるモスコーソ司祭の剣幕に押されながら、しかし、他の戦時委員たちも、「このままクスコに攻め込まれる前に、もはや早急に精鋭の討伐隊を差し向け、インカ軍を殲滅(せんめつ)させるしかあるまい。」と、意を決した険しい表情で同意した。
こうして、いよいよ本格的なスペイン側との戦闘の時が、確実に迫りつつあった。
そのような中、インカ軍の野営場では、その夜、アンドレスに嬉しい来訪者があった。
かのクスコ神学校時代の懐かしき朋友ロレンソが、インカ軍に参戦すべく援軍を引き連れて合流してきたのだった。
自分の天幕を訪れたロレンソを前にして、あまりにも懐かしいその姿に、アンドレスは大いに瞳を輝かせた。
ロレンソは、亡きインカ皇帝または貴族の血をひくインカ族の子弟たちが学ぶ特別な、あのクスコの神学校で、アンドレスと同期の学生だった。
神学校時代、二人は、ラテン語、スペイン語、ケチュア語、キリスト教、あるいは身体的競技も含めたあらゆる学科において、その成績を互いに競い合うライバル同士であった。
それと共に、スペイン人教師たちの目をかすめて、二人はこの国の将来に向ける思いと決意を熱く語り合う同志のような存在でもあった。
「ロレンソ、本当によく来てくれた!!」
アンドレスは眩しそうな視線で、ほぼ二年ぶりに会う朋友を見つめた。
ロレンソも懐かしさを隠せぬ瞳ではにかみながら、今や一人の将として成長しつつある眼前の友を、真っ直ぐに見つめ返した。
アンドレスは込み上げる懐かしさを噛みしめながら、今、再び身近に接することのできた友の、その存在を確かめるように、眩しげな視線を注ぎ続ける。
学生時代から、ロレンソはもともと理知的な大人びた雰囲気の少年だったが、今、こうして数年ぶりに会う彼は、見違えるように立派な一人の大人の風貌を備えている。
同じ18歳の青年のはずなのだが、自分よりも軽く2~3歳は年上に見えるのだ。
少し茶色がかった柔らかな自然なウェーブのかかる髪をもつ混血のアンドレスとは対照的に、ロレンソの髪はインカ族らしい漆黒の直毛で、そして、二人共同じように、それらの髪を肩より少し下のあたりで切りそろえている。
それは、かのクスコの神学校時代とあまり変わらぬ姿であった。
その髪型は、アンドレスにおいては、少年の面影を彷彿とさせるものであったが、他方、既に大人の風貌を備えたロレンソにおいては、少年時代と殆ど変わらぬその髪型さえも、飾らぬ鋭利な大人の雰囲気をいっそう高める要素となっている。

その褐色の彫りの深い顔立ちには知的な雰囲気と精悍さが以前にも増してうかがえ、その一方で、洞察の鋭そうな、あの懐かしい瞳の色は今も変わらない。
実際、少年の頃から、ロレンソには物事の本質を見抜く直観力の鋭さと、そして勘の良さがあった。
生い立ち的には、インカ皇族の彼は、代々インカ皇帝の片腕として皇帝を助けてきた腹心の家臣の末裔でもあった。
神学校時代、アンドレスは己の身の上について表立って語ることを控えていたが、勘のいいロレンソは、二人の会話の中でアンドレスの身の上を直観的に悟ってもいた。
「あの頃から、こんな日が必ずや訪れると思っていたよ。
ロレンソ、本当に、よく来てくれた!」
天幕を出て松明の揺れる夜の野営場を二人で歩みながら、アンドレスが感動を滲ませた声で言う。
ロレンソも同様に懐かしさを隠せぬような、それでいて、とても落ち着いた眼差しでアンドレスを見る。
「アンドレス様、わたしも、いずれはこのような時が来ると確信しておりました。」
アンドレスは、少し目を瞬かせた。
「ロレンソ、そんな話し方をしなくていいんだ。
以前と同じように、接してほしい。」
アンドレスの言葉に、ロレンソは穏やかな笑顔を返した。
「しかし、もともとあなた様は、インカ皇帝にも等しきトゥパク・アマル様のお血筋。
そして、今や千人を超す連隊の将ではないですか。
わたしの方こそ、神学校時代には、身分もわきまえずにあのように無礼な接し方をしてしまい、心苦しく思っているのですよ。」
ロレンソの瞳は真っ直ぐで、誠意に溢れている。
本気でそんなふうに思っているのだと、アンドレスには分かった。
アンドレスはやや困惑した表情でロレンソを見る。
それから、彼もまた、誠意をこめた声で言った。
「ロレンソ、身分のことよりも、俺たちはかつて寝食を共にした友であったし、今も俺は君の友でありたいと思っている。
これからも、かつての通り、友として接してほしい。
態度も、言葉づかいも。」
アンドレスの真っ直ぐな瞳を、暫し、真顔で見つめた後、ロレンソはフッとはにかんだ。
「本当に、よいのか?
…アンドレス。」
ロレンソが、慎重に言う。
アンドレスは明るい笑顔をつくって、深く頷いた。
周囲を瞬時に華やかせてしまうアンドレスのその笑顔を、ロレンソは懐かしそうに目を細めて見つめた。
再び、月明かりの注ぐ野営場の草地を歩みながら、ロレンソが力のこもった声で言う。
「アンドレス、そなたの噂を、ほうぼうで耳にしたぞ。
インカ軍の最前線に立って、軍神のごとくに鮮やかに戦う若い武将がいる、とね。」
アンドレスは、驚いたように目を瞬かせる。
まさか、そんなふうに言う者たちがあるなど、夢にも思ったことはなかったのだ。
言葉に詰まっているアンドレスを、ロレンソは誇らしげな目で見返した。
「アンドレス、そなたと共に、皇帝陛下のもとでインカ軍のために働けることを、身に余る光栄と思うぞ!」
ロレンソの先ほどの話にまだ驚きを抱きながらも、アンドレスもまた、その澄んだ瞳に力を宿して頷いた。
「ロレンソ!!
俺も、君と共に、インカのために働けることを、この上ない誇りと感じる!」
そして、二人はどちらからともなく、がっちりと両手を結び合った。
◆◇◆ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ 第五話 サンガララの戦(2) をご覧ください。◆◇◆
© Rakuten Group, Inc.





