第五話 サンガララの戦(2)

【 第五話 サンガララの戦(2) 】
それから間もなくの11月17日、クスコへの進軍途上、サンガララの地にて、トゥパク・アマル率いるインカ軍と、スペイン側のクスコ戦時委員会が送り込んだ精鋭の討伐軍とが、ついに対峙する時が迫っていた。
サンガララはアンデス山脈の高所にある高原地帯で、冬季は豪雪にうずもれる極寒の地である。
南半球の11月は既に初夏近い晩春であるが、当地の夜間の冷え込みはまだまだ厳しい。
スペイン側の隊長ランダ率いる討伐隊の軍団は、サンガララの集落の中央広場で露営をしていた。
ランダは天幕を出ると、まだ見ぬインカ軍を睨みつけるがごとく、険しい目で上空を見据えた。
見上げる夜空には、厚い灰色の雲が垂れこめている。
冷え切った空気の中で、ランダの吐く息が白く浮かび上がった。
その白い息の広がりの大きさから、この男の肺活量の不気味な多さがうかがえる。
クスコの戦時委員会によって、今回、インカ軍討伐隊の将として白羽の矢を立てられたこの男は、幾多の戦果を上げてきたベテランの現役軍人であった。
軍隊の中で鍛え抜かれ引き締った逞しい身体に、スペイン人らしい彫りの深い顔立ち、そして、黒々とした髪と鋭利な眼差しは、まるで、闘牛士を思わせる。

ちなみに、闘牛の発祥をスペインの地とする見解には幾つかの異論もあるが、イベリア半島において、古くから闘牛に類するものが行われきたことは事実である。
もともとは、騎馬で野生の牛を槍で突くという、貴族の狩猟の風習が闘牛の前身である。
時代の推移と共に、馬術に優れた社会の指導者層が、己の力を、そして社会的地位を民衆に誇示するため、華やかに正装し、牛に槍を突き立てる行為となり、それがやがて闘牛としての現在の形態に変遷してきた。
18世紀前半には一時低迷期にあった闘牛も、この時代には、騎馬ではなく徒歩闘牛士の出現によって、スペイン本国では再び隆盛を誇っていた。
いずれにしろ、この闘牛に象徴されるように、イベリア半島の民族たちであるスペイン人たちは、古来より、非常に闘争心の強い者たちであったのだ。
ランダは夜の暗雲を見上げたまま、その鋭利な目元を冷ややかに細めた。
今、突如、狂ったように暴れ出したインディオどもは、ランダには、まるで暴走をはじめた獰猛な雄牛に等しく思われた。
だが、どんなに荒れ狂おうとも、相手は、人ではない。
たかが、「牛」にすぎぬのだ。
今は狂暴になっている野蛮な雄牛ども…――武器とて火器はせいぜい奪った小銃程度しか持ち合わせぬ、ただ数だけ多い原始的な烏合の軍団にすぎぬ。
全く、そのような者どもを相手にしながら、敗走し、敵の手に落ちるなどとは、既にインカ側の統治下に置かれた地の代官お抱え部隊やスペイン側の援軍は、一体、何をしてきたのだろうか。
何という醜態、何という情けなきことか…――!!
ランダには、むしろ、インカ軍の戦果よりも、反乱勃発以来、各地で敗退をきたしてきたスペイン兵の失態を非常に苦々しく、いや、彼には全く信じられぬ思いで、噛み締めていた。
ランダは、討伐隊の本営の置かれた天幕の方から、今、こちらに歩み来るスペイン人の中年の男に、氷のような冷ややかな眼差しを投げた。
己の方に歩み来る男、それは、かのキキハナの代官、カブレラであった。
カブレラは、反乱勃発時、自らが治めていたキスピカンチ郡に迫り来るインカ軍の侵攻に恐れをなし、己の任地を放棄してクスコに逃げ込んだあの代官である。
今や、その失態の汚名を注ぐべく、カブレラは、この隊長ランダのもとで、討伐隊に参加していたのだった。
「ランダ様、インカ軍が付近まで来てはいまいか探るため、斥候を派遣いたしました。」
冷たい目で己を見下ろす隊長ランダに、怯え、へつらうようにカブレラが言う。
「うむ。」
ランダはいっそう冷ややかに細めた目で、ただ短くそれだけ応える。
カブレラは、恐れをなしたように一礼すると、そそくさと本営の中に引っ込んだ。
苛立ちを押さえられぬように、ランダは筋肉の塊のようなその拳を握り締めた。
たかがインディオごときに恐れをなし、己の任地を放棄して遁走するなど、全くもって、信じられぬ。
既に逃げるように己の天幕の中に消えたカブレラの後姿を、ランダは侮蔑に満ち満ちた眼で睨みつけていた。
むしろ、ランダには、インカ軍がこのサンガララの地に本当に現われるのか、そのことの方が疑問であった。
銃器や大砲を備え、しかも、これまでの弱体なスペイン兵とは全く質を異にする、この正式な討伐隊と、本気で一戦を交えるつもりがあるなどと、ランダには、むしろ考えにくかった。
もしトゥパク・アマルが、「牛」ではなく「人」であるならば、少し頭で考えてみれば、その勝機の乏しさは容易に計算できるはずである。
そして、やがて、カブレラの放った斥候たちが続々と本営に戻ってきては、「付近は全く平穏です。インカ軍の気配は露もありませぬ。」と、口々にランダに報告した。
やはり、とランダは思った。
さすがに、トゥパク・アマルも、己の身の程をわきまえているらしい。
ランダは、斥候たちの報告に、己の予測の正しかろうことの確信をいっそう深めつつ、ともかくも、インカ軍との決戦の時に備えて休息をとるようにと部隊に命じた。

一方、トゥパク・アマルは、サンガララから敢えて十数キロ以上離れた地にて野営の陣を張りながら、己の放った斥候の報告を待っていた。
まもなく丑の刻を回ろうとした頃、緊迫感を滲ませた側近たちが見守る中、トゥパク・アマルの元に、はるばるサンガララまで深夜の偵察に参じていた斥候たちが戻ってきた。
トゥパク・アマルは斥候たちの労をねぎらい、その報告を聞く。
「討伐隊は、サンガララの中央広場に露営し、既に就寝したもようです。」
思慮深い目をすっと細めて、トゥパク・アマルは呟くように言う。
「ずいぶん甘く見られたものだ。」
だが、そこまで敵が油断できるには、やはり、それ相応の軍備なり、戦術なり、かなりの自信があるが故に相違ない。
天幕の中は、暫し、静けさに包まれる。
深夜の空気は、しんしんと冷え込みを増していた。
「今宵は、雪になりましょうな。」
静けさの中、そう言いながら、参謀オルティゴーサが意味ありげな目でトゥパク・アマルを見た。
トゥパク・アマルも、意味深げにその目を細めて頷く。
「サンガララはこの辺りよりも、いっそう高地。
雪も深くなろう。」
実際、南半球の11月は晩春ではあるが、この高原地帯はこの時期でも雪に見舞われることがあるのである。
側近たちの目つきも鋭さを増す。
なお、この時の側近の中には、サンガララでの激戦に備え、分遣隊を率いて戻っていたトゥパク・アマルの従弟ディエゴの勇姿も見ることができた。
「運は、我々にある。」
地底から湧き上がるがごとくの、あの低く響く声で、トゥパク・アマルが言う。
それが合図であったかのように、まもなくインカ軍はサンガララに向けて深夜の行軍を開始した。
時を合わせたかのように、夜空を覆う灰色の厚い雲からは、はらはらと雪が舞い降りはじめる。
アンデスに降りしきる雪は、インカ軍の進軍を、見守り、庇護するかのように、その大軍団のなす行軍の音をすっと吸い込み、完全な静けさの中に包み込んでいった。

翌11月18日早朝4時、サンガララの中央広場に露営するスペイン軍の哨兵が全員起床の合図を出した。
目覚めた隊長ランダは、天幕の垂れ布を少し開けて外を覗き見る。
外はまだ薄暗かったが、それでもいつもの午前4時にしては明るい。
それは雪明かりのためだった。
しきりに雪が降りしきっている。
辺りは妙に静まり返っていた。
「雪か…。」
不意にランダは不穏な直観に憑かれ、天幕を飛び出した。
ランダが天幕を出たのと殆ど同じタイミングで、見張りの哨兵が顔面を蒼白にしてランダのもとに馳せ参じた。
哨兵の報告を待たずとも、ランダは己の目で、事態のただならぬことを即座に知った。
彼は、にわかに目を疑った。
スペイン軍が陣を張ったこの広場は、既に、無数の黒い影に取り囲まれているではないか…――!!
さらに、中央のランダの天幕の真正面には、数百メートルの距離を隔てて、降りしきる雪の中、白馬に跨り己を真正面から見据える、ひときわ目立つインディオの姿があった。
その男の黒いマントが、風に煽られ翻っている。
ランダは事態の非常に緊迫していることを知りながらも、ある種の感慨をもってそのインディオを見やった。
(あれが、トゥパク・アマルか…!!)
そして、その目元をわななかせつつも、にわかに口元をつり上げる。
「トゥパク・アマル、なんと愚かな…本当に現われてこようとは。」

ランダの視界の中で、その中央のインディオ――トゥパク・アマルは、マントの下に革と綿でできた分厚い胸甲を身に纏い、腰からは重厚なサーベルを提げ、ピストルを手に、射抜くような精悍な眼差しで、己の方にじっと視線を注いでいる。
そして、彼を中心に、まるで地平線を埋め尽くすがごとくの褐色の騎兵たちが、やはりその身に分厚い胸甲をつけ、鈍器やサーベルで武装し、こちらを険しい眼(まなこ)で見据えている。
そのインカ軍全体から、まるで青白いオーラのような激しい気が燃え滾(たぎ)っているかのような、不気味な錯覚に襲われる。
ランダはわななく眼でそちらを睨みつけながらも、さすがに戦歴豊富な軍人らしく、その態度はどっしりと落ち着いている。
彼は、すぐさま臨戦態勢に入るよう、無言のまま鋭い手つきで部下に指示を送った。
ランダ率いる討伐隊の中には、従軍僧や、他にも当地の神父、そして、炊き出しなどの協力を強いられている地元のインカ族の女性などもいた。
幾多の修羅場を駆け抜け、将としての器を磨いてきたこのスペイン人の隊長ランダは、さすがに、ひとかどの武人らしい人道的な心をも持ち合わせた人物だった。
ともかくも、彼は、広場中央にある教会を守っていた地元の神父と、そして、30名ほどのインカ族の女性たちを、教会の内部に大至急、避難させた。
一方、トゥパク・アマルは、馬上からランダのその行動を微動だにせず見つめている。
そして、その様子を見守るように、静かに目を細めた。
ランダも、トゥパク・アマルを見た。
はるかに距離を隔てながらも、互いの目は完全に合っていた。
二人の間を、白い雪が、乱れ、舞い飛びながら降りしきる。
なるほど、この男が互いの軍団の将か――と、しかしながら、それも頷けようと、二人は言葉を交わさずとも悟ることができた。
トゥパク・アマルは騎馬のまま、軍団の中から、前に進み出る。
そして、雪の中でも、はっきりと遠くまでよく響く、鋭い声で言った。
「わたしは、インカ軍の将、トゥパク・アマルだ。
スペイン軍の将に告ぐ。
もはや、そなたたちは完全に我が軍に包囲されている。
互いに無用な流血は不要。
今、このまま、貴軍は我軍のもとに、降伏せよ!!」
横風が強まり、トゥパク・アマルの纏う黒い翼のごとくのマントが音を立てて大きく翻り、長い黒髪も吹雪の中に乱れ舞っている。
自軍に目配りをしながらも、常にトゥパク・アマルの傍で変わらぬ警護に当たっているビルカパサの目には、トゥパク・アマルの横顔に、これまでないほどの決意に満ちた強い炎が燃え立ち、既に次の一手に頭をめぐらせているのが見て取れる。

アンドレスをはじめ、ビルカパサ以外の側近たちもまた、凛として各連隊の先頭に立ち、それぞれに陣を張った位置から、事の成り行きを険しい眼差しで見守っていた。
そして、事の推移によっては、次に為すべきことになるであろう、あらかじめトゥパク・アマルと共に練り上げてきた軍事的戦略を心の中で反芻する。
一方、雪は、何事もないように淡々と降り続け、静かに、しかし、まるで謀り事のように、確実に両軍の兵たちをその白いベールに包み隠していく。
ランダは、部下に命じて連れてこさせた逞しい愛馬に跨った。
それに呼応するように、ランダの背後に銃器を携えたスペイン人の騎兵部隊が、整然と連隊を成しはじめる。
さらに、その背後には、鈍器と大砲で武装した、同様にスペイン人の歩兵部隊が、一糸乱れぬ動きで連隊を成していく。
トゥパク・アマルは、ランダの返答を待ちながらも、スペイン人から成るそれら敵の軍団を鋭く見渡した。
ランダ率いる討伐隊は、騎兵部隊と歩兵部隊とを合わせても、せいぜい千人程度と見て取れた。
今や、トゥパク・アマルの軍団は、6千人の規模である。
数の上では、自軍が圧倒的に勝っている。
しかしながら、敵方には無数の銃器があり、且つまた、大砲も備えている。
このまま戦闘に入れば、互いにとって著しい流血の惨事は免れまい。
トゥパク・アマルの横顔は、これまでになく非常に険しくなった。
そして、また、討伐隊のランダも、トゥパク・アマルの軍団の規模の大きさに密かに驚愕していた。
これまで反乱軍の実情が知られぬよう、トゥパク・アマル及び彼の妻ミカエラが、厳重に情報の漏洩に目を光らせ統制してきたために、この期に至っても、スペイン側はインカ軍の規模、兵力、戦術など、その細かな実情を掴めてはいなかったのである。
だが、ランダの予測通り、インカ軍の武装は、外面的に見る限り、己の討伐隊に比して著しく脆弱なものだった。
せいぜい多少の小銃を携えているのみで、多くが斧や棍棒などの原始的な鈍器を手にした「インディオ」たちである。
(所詮は、数だけ多い見かけ倒しの暴走しだした「牛」どもだ…――!
恐るるには、足りぬ。)
ランダの緊迫した横顔に、不遜な笑みが浮かぶ。
ランダは、よく通る堂々たる太い声で、トゥパク・アマルに言い放った。
「我が軍に、降伏の意志は無い!!」

トゥパク・アマルは、すっと目を細めた。
流血の道を選択するのかと、その切れ長の目には冷ややかな中にも、深い悲しみが浮かぶ。
それと共に、この道は、己自身が開いてきた道でもあるのだと、トゥパク・アマルは思う。
「仕方あるまい。」
誰にともなく低く言うと、再び、ランダを非常に険しい眼で見据えた。
「やむを得まい!
だが、そなたが教会に匿(かくま)われた神父殿、そして、女性たちを教会の中から安全な場所へと避難させよ!!」
トゥパク・アマルは、ランダの方向に響く声で言い放ちながらも、教会の方を俊敏に横目でうかがう。
広場中央にあるその教会が、戦場の一部になる危険を感じていた。
そもそも、教会の周辺で戦闘を起こすこと事態、本来は限りなく避けたいことであった。
今や、かのモスコーソ司祭の策略によって、キリスト教に対する反逆者と見なされている彼にとって、この上、教会を血で汚すような事態は極めて避けたいことであったのだ。
だが、恐らく、隊長ランダは、そんなトゥパク・アマルの心理を見抜いていた。
然るに、当地の教会の膝元である、この広場での戦闘を密かに狙っていた。
ランダは冷ややかな眼差しで、トゥパク・アマルを見た。
だが、確かに、トゥパク・アマルの言う通り、教会に避難した神父や女性たちまで戦闘に巻き込むことは、ランダ自身の道理にも反することではあった。
ランダが教会内部の者に教会からの避難を命じようとしたその時、彼の予測に全く反して、インカ軍の放つ威光に恐れをなしたスペイン軍の一部の歩兵たちが、逆に教会の中に逃げ込んだ。
「何たることぞ!!
歩兵たちは、教会から即刻、出(い)でよ!!」
自軍の兵の信じられぬ虚弱な行為に激昂した鬼のようなランダの剣幕に、教会の建物ごと、ビクリと震え上がったかに見えた。
怯え切っている者に、それ以上の刺激を与えてはまずい…――と、トゥパク・アマルが直観した瞬間、再び、ランダは雷(いかずち)を振り下ろすがごとくの激しい剣幕で、教会の方向に怒鳴りつけた。
「即刻、歩兵たちは教会から出でよ!!
さもなくば、おまえたちから砲撃を食らわすぞ!!」
「待て、それ以上、言ってはならぬ…――。」と、トゥパク・アマルが思わず馬上から身を乗り出した時は既に遅く、隊長ランダの剣幕にひどく怯えた歩兵たちが、一斉に教会の出口から表に飛び出そうとした。
しかし、狭い教会の出口に殺到した歩兵たちは、次の瞬間、将棋倒しのごとく出口から外へと雪崩れるように倒れこみ、不幸にも、数名の負傷者と、そして、死者が出た。
双方の軍団が固唾を呑み、トゥパク・アマルもまた、息を呑んだ。

雪がいっそう勢いを増して、風に乱れ飛びながら白く降りしきる。
他方、教会の門前では、死者の赤い血が白い雪の上にジワジワと広がっていく。
神父が驚愕した目で真っ青になり、それから、すがるようにトゥパク・アマルの方を見た。
トゥパク・アマルは、思わず、神父の目に引きつけられた。
スペイン人の神父であったが、その眼差しはランダではなく、紛れも無くトゥパク・アマルに向けられ、そして、何とかこの混乱を救ってほしい!!…、と必死に訴えている。
トゥパク・アマルがその目に釘付けられた瞬間、ランダの目が鋭利な光を放った。
ランダの瞬間的な無言の合図によって、突如、教会の天窓に密かに装備されていた大砲から、トゥパク・アマルめがけて砲弾が放たれた。
「トゥパク様!!」
瞬時に、ビルカパサが身を翻して、トゥパク・アマルを砲弾とは逆の方に激しく突き飛ばした。
耳を劈(つんざ)く爆音と共に、地を裂くごとくの激しい地響きが足元を大きく揺るがした。
突き飛ばされた勢いで、トゥパク・アマルは馬上から、雪の上へと激しく転がり落ちる。
しかしながら、ビルカパサの捨て身の対応によって、幸いにもトゥパク・アマルは砲弾を逃れたのだった。
一方、砲弾はビルカパサの右肩をかすめ、彼の肩から真紅の血が流れ落ち、彼の跨る馬の背を伝って、その下にある雪を赤く染め上げた。
トゥパク・アマルは俊敏な身のこなしで馬上に戻りながらも、ビルカパサをひどく案ずる色の視線を投げる。
ビルカパサは「何ということはありませぬ。」と、激痛があるに違いないその腕を、手早く衣服を裂いて縛り上げ止血すると、いつもの精悍な笑顔で応じた。
だが、被害にあったのは、ビルカパサだけではなかった。
むしろ、実際に犠牲となったのは、別の兵たちであった。
トゥパク・アマルが素早く見渡すと、彼のすぐ背後に控えていた精鋭の兵たちのうち十数名にも及ぶ者たちが、雪を延々と赤黒く染めながら地に伏していた。
トゥパク・アマルの見開かれた揺れる眼差しを受けて、倒れた兵たちの周辺にいる兵たちが悲痛な表情で首を横に振る。
「皆、死んでおります。」
トゥパク・アマルの手綱を握る指に、ぐっと激しく力が入る。
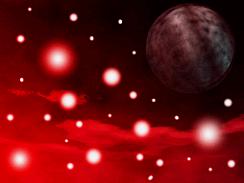
だが、間髪入れず、ランダは次の指令を発した。
それを合図に、スペイン軍の騎兵部隊が、トゥパク・アマルのいるインカ軍正面に向けて、一斉に突撃を開始した。
ランダ率いる騎兵部隊は、馬上から雨嵐のような銃弾を撃ちこみながら、怒涛のごとくトゥパク・アマル及びビルカパサ率いるインカ軍本隊正面に襲いかかってきた。
トゥパク・アマルの本隊には、義勇兵たちも多く加わっている。
もちろん、こうした事態はトゥパク・アマルには当然予測の範囲内であったため、インカ軍の歩兵及び義勇兵は本隊のはるか後方に控え、この時はまだ戦闘に加わってはいなかった。
この時、前線に出ていたのは、よく訓練されたインカ軍の専門兵であり、且つまた、騎馬の者たちだけであった。
とはいえ、さすがに鍛え抜かれ気力漲る精鋭のインカ兵とて、銃弾の嵐には、浮き足立たずにはおられない。
トゥパク・アマルは、「引け!!後方に引くのだ!!」と、険しい声で号令を発しながら、インカ軍本隊の騎兵部隊に退却を命じた。
トゥパク・アマルの号令に煽られるように、インカ軍が脱兎のごとく退却を開始するのを見て、ランダ率いるスペイン軍はますます勢いづいた。
隊長ランダは、インカ軍を殲滅(せんめつ)させるのはこの時とばかりに、「撃て!!トゥパク・アマルを捕えよ!!」と、狂った魔人のごとくの形相で馬を駆り立てながら騎兵部隊の先陣を切って、逃走するトゥパク・アマルを追い立てる。
互いの軍の馬たちが蹴り上げる雪煙で、前方が霞み、視界が危うくなるほどの激しい追撃が行われた。
雪煙のあまりの激しさに、思わず、ランダは眼を瞬かせる。
その瞬間だった。
後方に控えていた義勇軍の辺りまでインカ軍を追い詰めたかと思われた時、突如、トゥパク・アマルの眼が鋭い光を放った。
そして、天高く、その右腕を振り上げた。

その合図と共に、広場を挟むようにして、スペイン軍の視界から見えぬ広場の左右の空き地に潜んでいたディエゴの連隊、及びアンドレスの連隊が、突如、激しく雪を蹴散らしながらランダ率いる騎兵部隊に左右の両翼から襲いかかった。
その時に至って、ランダは無意識に額の血管が引きつるのを感じた。
しまった…――!!
トゥパク・アマルに謀られたのだ、と悟った時は、既に時は遅かった。
右翼からディエゴの軍団に、左翼からアンドレスの軍団に、そして、退却していたその踵を返して、今度は修羅のごとくの形相でこちらに襲いかかってくるトゥパク・アマル率いる本隊、及び、ビルカパサの軍、さらには無数の兵からなる義勇兵の軍に囲まれたランダには、もはや後方を振り返ることは不可能だった。
しかし、恐らく、否、確実に、後方の歩兵部隊もインカ軍の残党に襲われているに違いなかった。
トゥパク・アマルの「退却」は、退却に見せかけた、偽りの退却、つまりは罠だったのだ…――と、ランダが悟った時には、この隊長にも既にディエゴの放った槍が突き刺さっていた。
ランダは口から血を吐きながら、最後の力を振り絞ってその槍を抜こうとした。
槍を抜きながら、しかし、ランダの頭は妙に静かに冴えていた。
トゥパク・アマルは偽装退却でランダ率いるスペイン軍の騎兵部隊を誘い出し、敢えて、後方の歩兵と騎兵部隊を引き離したのだ。
そして、両者が十分に分離したところで反転し、両翼と正面から騎兵部隊の突撃を受け止め、反撃に出て壊滅させ…、同時に、分離させた後方の歩兵部隊へも奇襲を仕掛けて壊滅させる…。
次第に薄らいでいく意識の中で、ランダは苦々しげに笑った。
ランダの脳裏に、母国スペインの、あの闘牛の場面が甦る。
牛を槍で突くことはあろうとも、己がこのような最果ての地で、槍を突きたてられて果てようとは…――。
そのまま、おびただしい大量の血で辺りを赤々と染め上げながら、ランダはついには槍を抜くことを果たせぬまま、雪の中に深く沈んでいった。
今、インカ兵の放つ、あの大地の神と呼応する情熱的な太鼓の音と、天空の神を呼び覚ます冴え渡る角笛の響きが、渦巻くように戦場を包み、スペイン兵を呑み込んでいく。
アンデスに舞い飛ぶ雪は、スペイン軍の火器にも無情なまでに絶え間なく降りしきり、その威力を、まるで命を吸い込むがごとくに萎えさせる。
一方、精神的にも、肉体的にも、過酷な自然環境の中での白兵戦にもともと適した素養をもつインカ兵たちは、降りしきる雪の中でますます意気盛んであった。
そんなインカ軍の中央では、騎馬のトゥパク・アマルが、自ら銃とサーベルを振るって敵兵を討ち取りながら、炎のような目をして雄叫びを上げては、インカ兵を激しく鼓舞している。
その全身からは、黄金色のオーラが煌々と放たれる。
かくして、ランダの読みは正しかったのだった。
隊長ランダからも、騎兵部隊からも引き離されたスペイン軍の歩兵部隊は、広場の後方左右の地に兵を潜めていた参謀オルティゴーサの連隊及び、フランシスコの連隊によって、両翼から襲撃を受けていた。
広場の後方は切り立った山岳部になっており、自然の要害を成していて、窮地に追いやられたスペイン軍の歩兵部隊は後方への撤退はかなわず、かといって、前方では、騎兵部隊に襲いかかるインカ軍の本隊及びその他の強豪部隊が控えており、逃走経路を失ったまま、もはや両翼のインカ軍からの襲撃によって壊滅状態になっていた。
そこへ騎兵部隊を打ち破ったインカ軍本隊が怒涛のごとく雪崩れこみ、たちまち歩兵部隊も風前の灯火(ともしび)となった。
今、雪の中に沈みながら、まだ辛うじて息の残る隊長ランダの霞みかけた視界の中を、戦場の中央付近で、まるで蒼い光が走るがごとくに瞬速の動きで大地を馳せる何者かの姿がよぎる。
ランダは己の命の火が尽きていこうとしているのを感じながら、だが、その最後の力を振り絞るようにしてそちらに目をこらした。
その視界の中に、インカ軍の陣頭に立って銃弾をよけながら、次々とスペイン兵をなぎ倒していく一人の混血の若者の姿が映る。

その若者――インカ軍の若き連隊長アンドレス――は、騎上から聖剣のごとくに蒼い光を放つサーベルを天高く振り翳(かざ)す。
そして、馬から飛び降りると、次の瞬間、己の体の周囲に大きな弧を描くように、その重厚なサーベルを走らせた。
サーベルの放つ蒼い光が、彼の周りに完璧な円形の軌跡を描く。
一瞬後には、アンドレスの周囲にいた5~6名のスペイン兵たちの肢体から血飛沫が噴き上がった。
その血飛沫が飛翔するよりも速く、アンドレスは、瞬間、宙に跳躍すると、中空で反転し、スペイン兵の密集する場所へとサーベルを振り下ろしながら舞うように着地した。
着地しながら一人の兵を真っ二つに切ったかと見えた瞬間、間髪入れずにサーベルを水平に切り返すと、そのサーベルが再び完璧な弧を描いて走る。
蒼い残光と共に、彼の周囲にいた複数のスペイン兵たちが血飛沫を飛び散らせながら地に沈む。
その若者の表情は、もはや視界の霞みゆくランダには認めることはできなかった。
しかし、その全身からは、サーベルの光に呼応するがごとくの蒼い焔が燃え滾(たぎ)っている。
(あの者…何者か…――!)
だが、ランダは、そのまま雪の中でついに息絶えた。
それと時を合わせるように、ほどなく、決戦は終結した。
こうして、早朝4時からはじまったこのサンガララの地での決戦は、午前11時には全てを決し、幕を閉じた。
結果は、インカ軍の圧倒的勝利であった。
しかしながら、その戦闘後の惨状は、どちらの軍にとっても筆舌に尽くし難いものであった。
スペイン側の討伐隊は、ほぼ全滅だった。
汚名を注ぐべく参戦していたキキハナの代官カブレラも、一旦はクスコに持ち越したその命を、このサンガララの地でついに落とした。
そして、インカ側にも、多数の負傷者や死者が出た。
戦場となった広場は、降り積もった雪の上に累々(るいるい)と横たわる死体の流す血で、殆ど白い部分が見えぬほどに真紅に染まっていた。

今、雪は既にやんでいる。
インカ軍の多くの兵は生き残ってはいたが、皆、その手足に、顔に、髪に、服に、ベッタリと返り血を浴びて、呆然とその惨憺たる情景を見やっていた。
次第に日が高くなるにつれ、辺りに生臭い血の臭いが立ち込める。
まさしく、そこは地獄絵さながらであった。
トゥパク・アマルもまた、返り血で全身を染め上げたまま、その背筋も凍るような情景を眺めやった。
愛馬の純白なはずの肢体も、大量の血を浴びて、赤黒く染まっている。
トゥパク・アマルは愛馬の傍に立ち、その馬の体にそっと触れた。
その指が、微かに震えている。
彼は、愛馬の胸元に額を押し当て、じっと瞼を閉じた。
このような惨憺たる眺めを創り出したのは、一体、誰だ…――。
己自身であろう、と、彼の心の奥から非難めいた声がする。
馬はトゥパク・アマルの心の内を察するかのように、その鼻先で、血糊のこびりついた主人の髪に静かに触れた。
そして、また、心の激しい苦悶に喘いでいたのは、トゥパク・アマルだけではなかった。
生き残ったインカ軍の兵たちは、皆、自分の為した所業に、今更のように恐れ慄いていた。
殺(や)らねば、殺られるという究極の状況で、しかも、相手が銃を持っているという極度の恐怖感は、彼らを計り知れぬほどに狂暴にさせた。
今、我に返って、己の為したことを思うと、自らぞっとせずにはいられない。
多くの場合、一人のスペイン兵に対して、多数のインカ兵が鈍器を手に襲いかかり、一斉に殴り殺したのである。
そして、かのアンドレスも、頭のてっぺんからつま先まで血みどろになったまま、虚ろな目で屍の中に佇んでいた。
常に自ら最前線に立って敵に向かい、味方の指揮を執りながらも自ら剣を振るう己は、今日、まるで殺人マシーンのごとく、果たして何十人の敵を切り殺したのか?!
彼は鞘に収めることさえ忘れたサーベルを、ぼんやりと眺めた。
血糊にまみれたそのサーベルは、まるで自分の意志を超えて、敵の血をしきりに求める魔物のごとくに今は見える。
人を切る時のあの感触、悲鳴、飛び散る血、臭い、倒れる音…――すべてが渦巻くようにアンドレスの脳裏を襲い、そのまま彼は崩れるように地に膝をついた。
たとえ敵とはいえ、たった一つしかもたぬその命を、その歴史ある人生を、たかが一人の小さな人間でしかない己のこの手が、幾多にも渡って奪い去ったのだ。
アンドレスは、今更のように、己の為した所業の恐れ多さに自ら圧倒され、深く打ちひしがれていた。
手足が痙攣するように、震えている。
そんなアンドレスの傍に、静かにディエゴが近づいていく。
そして、アンドレスの肩に手を置き、その心を察するように、彼もまた苦しげな眼差しで、己の息子にも等しいアンドレスを見つめた。
「アンドレス、これが戦(いくさ)というものだ。」
ディエゴの太く、深遠な声に、アンドレスは虚ろな視線をゆっくり上げる。
その瞳に、ディエゴは頷き返す。
これが我々の負った業(ごう)なのだ、と、そんなふうにディエゴの目は言っていたかもしれない。
アンドレスは頷くことができぬまま、しかし、それでも何とか立ち上がった。

その時、彼の目の中に、遥かに聳えるアンデスの山々の姿がふと飛び込む。
山々はいつもと変わらぬ清冽な輝きを放ちながら、しかし、今日は、まるでその懐に全てを包み込もうとしているかのごとくに、その裾野を懸命に広げているかのように見える。
アンドレスは立ち止まり、心を奪われたようにその山々に見入った。
(アンデスの山々よ…ありがとう…。)
彼は心の中で小さくそう呟くと、山々の気を己の中に取り入れるかのように、一度、深く息を吸い込んだ。
そして、一歩一歩、トゥパク・アマルらのいる本営へと戻っていった。
インカ軍の本営では、少なくとも表面上は、既に平常通りの様子で振舞うトゥパク・アマルの姿があった。
彼は早々に血糊のついた服を新しいものに着替え、手足や顔、髪にまでベッタリとついていた血痕を拭い落としていた。
傍目から彼だけを見たら、何事もなかったように人は思うかもしれない。
今、トゥパク・アマルの前には、生き残り、捕虜となったスペイン軍の兵たちが30名ほど引っ立てられてきていた。
いずれの兵も負傷しており、その目は呆然と宙を漂い、放心状態である。
あれだけ多くの兵がいたというのに、生き残った者たちはこれだけなのかと、トゥパク・アマルの心は再び、ひどくざわめく。
「全員、治療をさせて、自由に立ち退かせよ。」
トゥパク・アマルの指示を受け、部下は恭しく礼を払い、捕虜と共に下がっていった。
下がった部下と入れ替わるように、他の部下が、最後の捕虜を連れてきた。
それは、討伐隊に所属していたスペイン人の従軍僧であった。
従軍僧は、もはや覚悟を決めた表情で、無言でトゥパク・アマルの前に立っている。
従軍僧なれば、釈放すれば、すぐさまクスコのモスコーソ司祭らの元に舞い戻るのは必定であった。
だが、トゥパク・アマルはやはり、「自由にこの地を立ち退かれよ。」と静かに言って、従軍僧の釈放さえ命じ、自らは広場の教会の方に向かって本営を出た。

彼は教会の前まで来ると、入り口でまだ折り重なったままの数体の死体の前に跪き、長い黙礼を払った。
それから、部下に命じて、入り口の死体を丁寧に移動させ、血痕を片付けさせ、もと通りの状態に整えた。
教会の中では、そんなトゥパク・アマルの行動を呆然と見やりながら、完全に放心しているスペイン人の神父の姿があった。
トゥパク・アマルが神父に近づくと、その神父はやっと我に返ったように、しかし、同時に怯えきった眼で、おずおずとトゥパク・アマルを見上げた。
トゥパク・アマルは深く頭を下げ、神父に礼を払う。
神父は驚き、言葉を失ったまま、しかし、喰い入るようにトゥパク・アマルの方を見ていた。
トゥパク・アマルも真っ直ぐに視線を返した。
その目は、このスペイン人の神父にさえわかるほどに、ひどく苦渋に満ちている。
トゥパク・アマルは丁寧に包んで持参した分厚い紙幣の束を、神父の方に恭しい手つきで差し出した。
神父の顔に、大きな戸惑いの色が浮かび上がる。
トゥパク・アマルは、再び、神父の方に深く礼を払った。
「神父様、何卒、これで教会を修繕し、死者の弔いをお願いいたします。」
ひどく驚いている神父に、トゥパク・アマルは「どうか。」と言いながら神父の手にその包みを握らせ、再び、苦しそうに深々と頭を垂れた。
◆◇◆ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ 第五話 サンガララの戦(3) をご覧ください。◆◇◆
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 陽だまりの月 2巻 読了
- (2024-11-25 21:41:16)
-
-
-

- 読書日記
- 「諸君、狂いたまえ」
- (2024-11-26 18:05:11)
-
© Rakuten Group, Inc.


