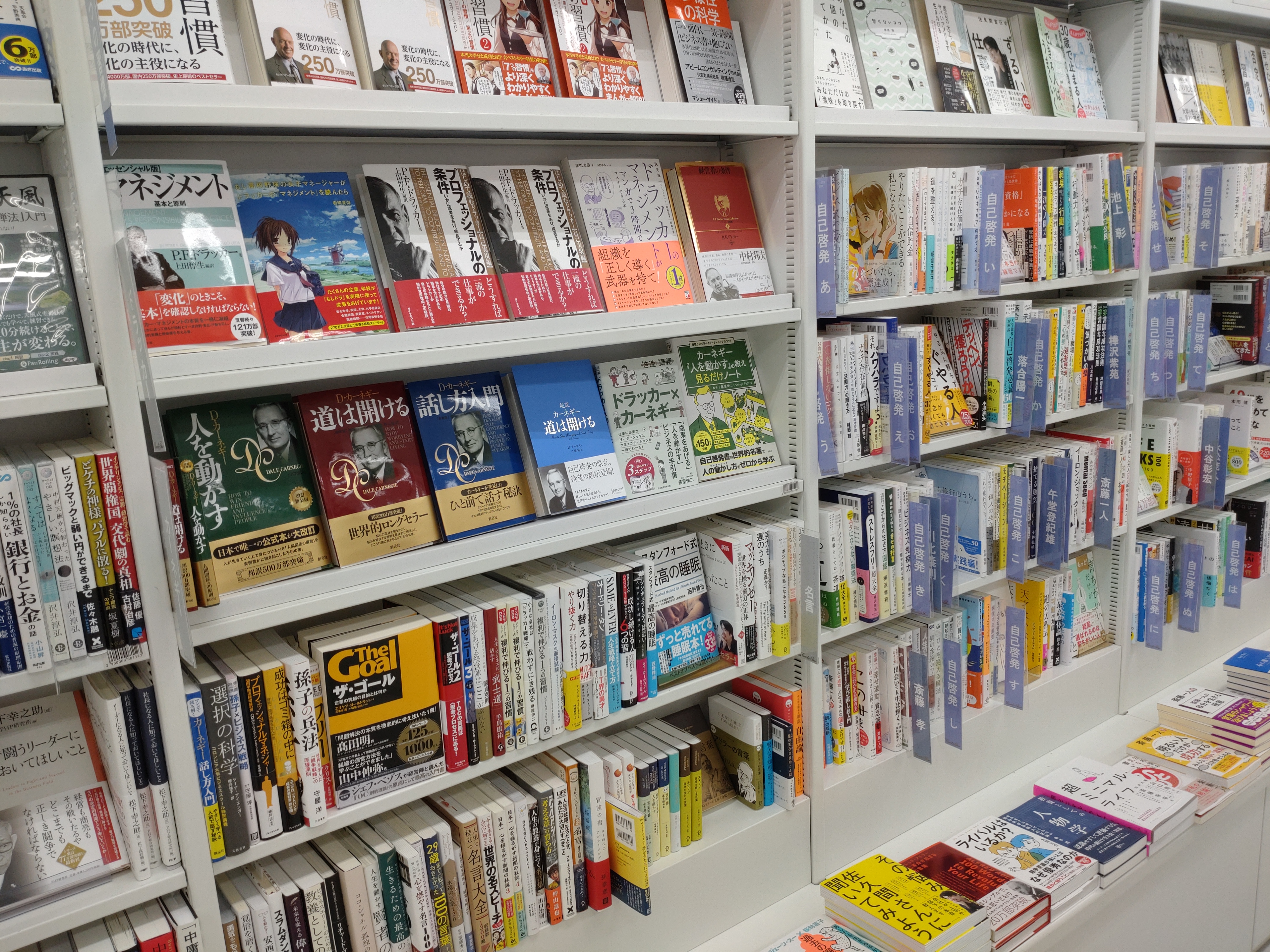2025年04月の記事
全14件 (14件中 1-14件目)
1
-

ホワイトカラー消滅~私たちは働き方をどう変えるべきか~ 冨山 和彦
冨山和彦先生のホワイトカラー消滅~私たちは働き方をどう変えるべきか~を紹介します。とても難しい本でした。30年間、物価も下がり、賃金も下がるデフレーションでした。それでも、日本経済は成長しない停滞する選択をすることで、従業員を何とか雇っていました。しかし、AIが進み、物価が上がり始めました(インフレーション)。そうなると、ホワイトカラーはAIに仕事を奪われます。とくにホワイトカラーの方は、働き方を変えないと生き残れないですよ。だから、生き残る方法を伝授しますといったことが書かれています。私がとくに参考になったことは3つあります。①介護・農業などの現場仕事の賃金が上がる。人手不足の職種であるにも関わらず、AIは現場仕事を行うことができない。よって、現場仕事の価値が上がっていく。②AIの登場により、ホワイトカラーは余り、学び直して、現場仕事を行うことになる。③東京での就職よりも、地方での就職を考える。物価の高い東京よりも、物価の低い地方に目を向けることが必要。地方にはたくさんの仕事がある。給料は低いが物価も低いので生活することができる。以上に述べたこと以外にも、感銘を受けた内容が多々ありました。AIの登場で時代が大きく変化しました。私も変化しないといけないと前向きになる本でした。
2025.04.29
コメント(0)
-
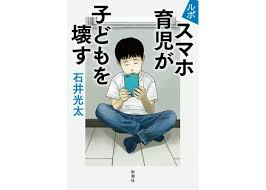
スマホ育児が子どもを壊す 石井光太
石井光太先生のスマホ育児が子どもを壊すを紹介します。読んだきっかけは、航空機に乗車した際にお隣の方がこの本を読書していました。表紙のインパクトもありました。また、病院の待合室等で親が子どもにタブレッツを与え、静かにさせて、自分もスマホで遊ぶといった光景を何度も目にしました。このブログでも紹介した「スマホ脳」からスマホの悪い部分は学んでいたので、子どもにどのような影響を及ぼすのかが気になりました。衝撃を受けた事実等を要約しました。①スマホ育児(子守歌をアプリで流す。読み聞かせをアプリで行う。)が良いと思っている親は年々増えている傾向にある。②小学生ぐらいまでは親のスマホ画面を見る時間がこどものそれと比例している。③コミュニケーション能力が低い子どもは、バズれば何をしてもよいと思っている。それ以外にもスマホ育児に関することだけでなく、最近の子どもの特徴等も社会的背景から述べています。ただ、客観的な数値データはなく、取材により体験談を集めたものとなります。何となく、幼い子供にスマホを長時間させると成人した人より悪い影響が出そうな気はしていましたが、ここまではっきりと書かれるとスマホ自体が怖くなってきました。
2025.04.28
コメント(0)
-

ボックス 百田尚樹
百田尚樹先生のボックスを紹介します。この本を読んだきっかけは、友人の勧めです。さわやかな青春ストーリーです。高校のボクシング部のお話です。主人公Aはボクシングセンスに満ちた不良です。いかにも青春ドラマにありそうな設定です。もう一人の主人公Bはいじめられっ子です。不良に囲まれているところをAに助けられて、Aと共にボクシングを始めます。Aは天才。Bは凡人。最初は雲泥の差がありますが、時が経つにつれて、Bの実力が上がってきます。努力に勝る才能なしです。ボクシングスタイルもBなりに身に着けていきます。Aは最強の高校生と戦うことになり、敗北します。その敗北から、更に強くなろうと努力をしていきます。最終的に強くなるのはA、Bどちら?ボクシングに関する細かい知識も多く、百田先生のボクシング経験や取材からの知識に驚かされされます。高校の部活ってこうでないとね。昔を思い出させてくれる一冊です。読み終えた後、とてもさわやかな気持ちになります。マンガにもなっているようです。
2025.04.27
コメント(0)
-
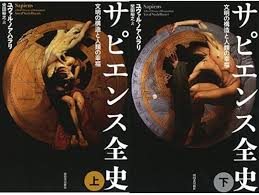
マコなり社長おすすめ「サピエンス全史」ユヴァル・ノア・ハラリ
ユヴァル・ノア・ハラリ先生の書いた「サピエンス全史」を紹介します。この本を読んだきっかけは、世界的なベストセラーなので一読する価値はあると思ったからです。上・下刊あり、私にとり内容は難しく、完読するのが精一杯でしたが、伝えることのできる範囲で紹介したいと思います。話の概要は、今まで人類はどのように進化にしていったのかです。私が勉強になった点をまとめました。①人類の祖先は、火を扱うことができるようなり、食物連鎖の頂点になる。火を使う前までは、食物連鎖の下層であり、猛獣が食べ残した動物の骨や木の実、昆虫を食べて過ごしていた。その期間は200万年。②3万年前、私たちの祖先のホモサピエンスは集団を形成し、他の種類の人類を絶滅させた。神などのスピリチュアルなことを信じることのできた脳を持つホモサピエンスは、100人規模の集団を形成することができた。他の人類はそこまで脳が発達していなかったので、10人程度の集団しか形成できなかった。③1万年前、狩猟から農耕へ変化して、人口が爆発的に多くなる。狩猟に比べて農耕は、食物を計画的に収穫し、保存もできる。食料が安定的に手に入ることができるようになったために人口が増えた。④農耕になり、寿命が短くなる。農耕には多くの労働時間が必要になる。ヘルニアや関節症で亡くなる人が増えた。また、1つの場所に定住するために感染症の増加、食物を取り合っての仲間同士の争いが起こるようになった。⑤5000年前、農耕だけでなく様々な職種が増え、お金が登場する。また、神様を信じる度合いが大きくなる。様々な職種が増えたために、食料の物々交換だけでは成立しなくなった。しかし、貨幣を信用する人が少なかったので、国王が貨幣で税金を納めさえるようにして、貨幣の信用度を上げた。また、病気で亡くなる人も多かったため神の存在を信じるようになった。⑥500年前 科学産業が発展するコロンブスがアメリカ大陸を発見する。これをきっかけに人類は自分たちが知らないことがあることに気づく。そこから、仮説検証を繰り返し、科学産業が急激に発展する。⑦産業革命以後、人類は時間で働くようになる。科学産業が発展し、発明にお金をかける資本主義が浸透する。工場などの設置により大量にモノづくりが始まる。当然、従業員は時間を提供し、貨幣を得るという労働と報酬のサイクルが確立される。本当に読み応えのある本でした。
2025.04.26
コメント(0)
-
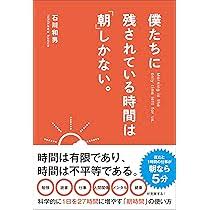
僕たちに残されている時間は「朝」しかない 石川和男
石川和男先生が書かれた「僕たちに残されている時間は「朝」しかない」を紹介します。以前までは、毎日の仕事が忙しく、時間が足りないと嘆いていました。しかし、明らかに自分より仕事をしているだろう先輩が生き生きと日常生活を送っている姿を見て、何故だろうと思い「アドバイス」をもらいました。先輩は朝イチに活動していると答えてくれました。朝に活動するメリットを詳しく知りたくてこの本を読みました。心に響いた点を3つにまとめました。①何か新しいものを入れるためには、何かを捨てる大原則がある。時間や脳の量は決まっています。詰め込みすぎはいけません。②残業2時間するならば、朝30分早く出勤して仕事をすべきである。夕方の仕事量の2倍、朝の仕事量が大きいといいます。なぜなら、脳が疲れていないからです。③先延ばしにしていることをパフォーマンスの高い朝の時間に行う。パフォーマンスが高い朝の時間に、テレビ、ユーチューブなどの視聴は決してしてはならない。学習や読書、仕事など有意義な活動を行うべきである。以上に述べた朝の活動だけでなく、コミュニケーションの部分や人生哲学的なことも書かれています。読みやすくて、わかりやすい1冊となっております。
2025.04.25
コメント(0)
-

むらさきのスカートの女 今村夏子
今村 夏子先生の「むらさきのスカートの女」を紹介します。この本を読むきっかけは、2,3年前に放送されたアメトークの読書芸人の回で、芸人のヒコロヒーさんがお薦めしていたので読んでみました。不気味な表紙がインパクト抜群です。 今村夏子先生の本は何冊か読んでいますが、設定や着眼点の斬新さ、登場人物の短所を上手に表現するところに驚いてばかりです。 この本は、主人公が公園で遭遇する「むらさきのスカートの女」と言われる女性が気になり、友達になりたくて近づいていくお話です。 主人公も変った人だし、むらさきのスカートの女も変わった人ですが、読みを進めていくうちに妙な愛着感が出てきてしまいます。 全部読み終えた後に私はいったい何を読んでいたのかな?と思うのですが、また、今村夏子先生の本を読んでしまいます。不思議な魅力です。 ぜひ、読んでほしいです。
2025.04.20
コメント(0)
-
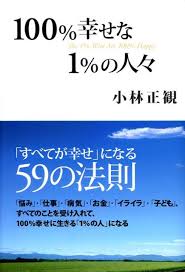
100%幸せな1%の人々 小林正観
小林正観先生が書かれた100%幸せな1%の人々を紹介します。小林正観先生の本は何冊も持っており、何度も読み返しております。この本も何度も読んだ1冊となります。本当に感銘を受けることばかりが書かれております。その中でも、私が日常生活でいつも意識している5点を選びした。①「他人を変える」ことはできなし、「自分が変わる」ほうが楽であえい、得である。②何事も起きず、普通に淡々と過ぎる日常こそ、幸せの本質である。③人に何かをしてあげることで喜ばれ、人の好意に素直に甘えて、感謝して生きる。④数字は気にしないで、ただ頼まれごとをやり、喜ばれるように生きていけばいい。⑤「戦うこと」、「争うこと」、「競うこと」だけの価値観で一生を終えてはいけない。一部を紹介しただけで、たくさんの人生教訓が書かれています。私は忙しくなってしまうとどうしても、わがままに振舞ってしまう悪い癖があります。3か月に1度、小林先生の本を読み、自分を律しています。
2025.04.19
コメント(0)
-
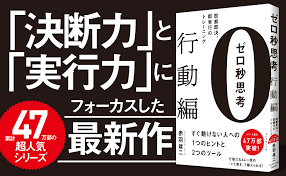
マコなり社長おすすめの「ゼロ秒思考」行動編 赤羽雄二
赤羽雄二先生が書いた「ゼロ秒思考」行動編の紹介をします。この本を読んだきっかけは、私が創造的(クリエイティブ)な仕事が苦手であったからです。前例があり、昨年度の計画資料をもとに改編していく資料作りはある程度の速さでできるのですが、新たな企画を立ち上げ、計画、実行に時間がかかってしまいます。参考になった点を4つ紹介します。①自分の考えていることをA4用紙に書き出していく。それをもとに、2×2のフレームワークに整理していく。②仕事の時間を短縮するためには、全体観(全体を見通す力)が必要である。全体観とは、仮設構築力、情報収集力、観察力、洞察力である。③仕事を円滑に進めるためには、他に人にうまく依頼し、頼ることが重要である。なので、全体観をもつことができる若手を見極め、指導していく。④やる気の高い友人、先輩などに定期的に会い、刺激を受ける。哲学的なことよりも、技術の部分が多く書かれた本となっています。わかりやすく再現しやすいと思います。向上心を高めることのできる1冊です。先月、私も学習会の仲間と会食しました。そのメンバーはどの方も自分の考えを持っており、エネルギーに満ちた方ばかりでした。その中で、私は自分の「考えや思い」を伝え、その「考えや思い」についてどう思うかのアドバイスをいただきました。この仲間がいることの大切さを改めて感じました。
2025.04.18
コメント(0)
-
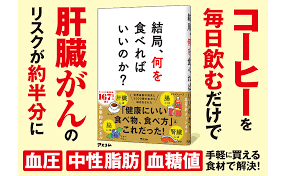
「結局、何を食べればよいのか?」本要約チャンネル
大人気ユーチューバー「本要約チャンネル」が書いた「結局、何を食べればよいのか?」を紹介します。この本に書かれていることは3つです。①何を食べるとよいのか。②何を食べるとだめなのか。③どのような食べ方がよいのか。簡単に説明します。①何をたべるとよいのかは、腸によい食物繊維やポルフェノールを取ることです。(例)バナナ・サツマイモ・ダークチョコ(カカオ70%以上)・ブルーベリー・キウイ②何を食べるとだめなのか。(例)砂糖・炭水化物・油最も健康を害するのはコンビニのレジ前においてあるホットスナックです。③どのような食べ方がよいのか。12時間・16時間断食を1週間に1,2回取り入れることです。とても読みやすくわかりやすい内容でした。私はこの本で書いてあった①の食べ物を積極的に取り入れることにしました。バナナを食べるようにしてからは、腸の働きが活性化したのか便通が良くなりました。
2025.04.13
コメント(0)
-

夢を旅した少年 アルケミスト
アルケミスト先生が書かれた「夢を旅した少年」を紹介します。以前、小説作家の喜多川泰さんの学び塾に参加していました。その時に紹介され、この本を読みました。とても読みやすいので是非読んでほしいです。概要は、羊飼いの少年が宝を探して、旅にでるお話です。旅の途中で様々な人と出会い人生哲学を身につけていく物語です。私が心に響いた内容を3つ紹介します。①夢を達成させるためには、困難があり、時間や労力がかかる。それが大きいほど、叶えた夢も大きくなる。②何かを望むことで、周り(宇宙全体)が協力してくれる。③自分の人生が良いものだったと思えるためには、宝探し(発見や挑戦の旅)をしなければならない。それ以外にもたくさんの教訓が書かれています。人それぞれ、心に響く部分は異なると思いますので、ぜひ読んでほしいです。読み終えた後に前向きになれる本です。やはり読書はいいなと再確認できる1冊です。
2025.04.12
コメント(0)
-
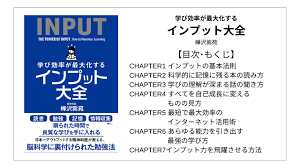
「インプット大全」樺沢紫苑
樺沢紫苑先生の「インプット大全」を紹介します。このブログでも紹介した「アウトプット大全」を読んだ後に、この本の存在を知りました。アウトプット大全を読んだ後に今回紹介する「インプット大全」を読むとより、話がスムーズに入ってきます。おすすめします。心に残ったことを3つ紹介します。①本はパラパラ読みでよい。目次に目を通して、興味があるところだけ読めばよい。それで本の内容はだいたいインプットできる。②覚える(インプット)を強化するには、人に教えるやノートに書く(アウトプット)が必要である。アウトプット前提でインプットする必要がある。③学習中に音楽を聴くとインプットは低くなる。貧乏性な私はせっかく購入した本を隅々まで読みたいタイプなのですが、①に挑戦しました。正直うーん?っといった感じです。雑誌の場合は興味のあるところしか読みませんので、本も雑誌のように読むこともアリなのかもしれません。
2025.04.11
コメント(0)
-
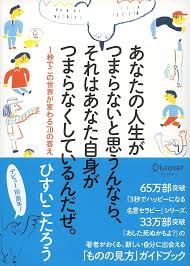
あなたの人生がつまらないと思うんなら、それはあなた自身がつまらなくしているんだぜ ひすいこたろう
ひすいこたろう先生の「あなたの人生がつまらないと思うんなら、それはあなた自身がつまらなくしているんだぜ」を紹介します。この本との出会いは本屋さんです。長いタイトルとインパクトのあるパワーワードに引かれて、購入しました。心に響いたことが多々書かれてありましたのでいくつか紹介します。①自分の誕生日は、生んでくれた母を祝う日である。②失敗の繰り返しの先に成功があるので、失敗という言葉は存在しない。③自分にとっての「幸せ」の定義をはっきりさせておく。④人を幸せにすることを仕事にするとよい。この本のタイトル通り、人生を楽しく感じることは他人のおかげでもなく、他人のせいでもなく、全部自分が決めて、感じること。人のせいにする人生から、「さよなら」しなさいと諭されているような感覚がありました。特に①の発想が自分にはなかったです。反省です。
2025.04.06
コメント(0)
-
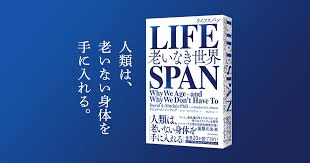
マコなり社長おすすめ ライフスパン老いなき世界 デビッド・A・シンクレア
デビッド・A・シンクレア先生の「ライフスパン老いなき世界」を紹介します。最近、健康に関することに興味を持ちはじめました。なぜなら、息切れがしやすくなったり、筋肉痛や腰痛がなかなか回復しなくなってきたからです。年を取ったいうことでしょうか?この本は科学的データを元に老いるとはどういうことがを説明していきます。結論は「老いるとは病気の一種である」と書かれています。病気の一種?ということは治るのでしょうか?疑問を持ちつつ読み進めていきました。老いるという病気にならないようにするための方法が書かれていました。①食べると危険なものはソーセージ、ハム、ベーコン。この3種類は過度な添加物が入っているので食べない方がよいそうです。ウインナーが大好きな私には辛いアドバイスです。②肉、乳製品、砂糖は控えて、野菜や豆類、全粒の穀物を食べなさい。これは辛いです。2週間に1度はピザを食べている私には、チーズは欠かせないです。これも辛いです。③サウナの後の水風呂や外気浴、寒い中での運動は良い。サウナは大好きな私、書かれていることで唯一、できそうなことです。寒い中の運動は勿論苦手です。生活習慣を徹底すれば、癌、心臓病などになる確率は低くなる。また、代謝も上がるので皮膚の張りも出てくるそうです。大好きな食べ物を断ってまで、長生きしてもな~。バランスが大事ですね。
2025.04.05
コメント(0)
-
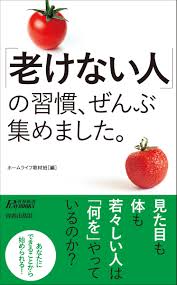
「老けない人」の習慣、ぜんぶ集めました ホームライフ取材班
ホームライフ取材班が出版した「老けない人」の習慣、ぜんぶ集めましたを紹介します。この本を読んだきっかけは、健康維持をしたいという単純な思いからです。目からウロコ的なことは書かれていませんでしたが、簡単に実践できそうなことがありましたので紹介します。①利き手とは逆の手を使用する。歯みがき、スマホ操作などの日常的な活動を利き手ばかり使っていると体が曲がってくるそうです。②とにかくよく噛んで食べる。噛むことによって顔が引き締まり若く見られます。それだけでなく、よく噛んで食べると脳の満腹中枢が刺激されて、すぐに満腹感がやってくるそうです。食べすぎを防いでくれます。③砂糖、炭水化物の量を調節する。老化の最大の原因は糖化です。白米、小麦、砂糖を減らします。特に炭酸飲料に含まれている砂糖の量は多すぎます。炭酸が抜けたジュースを飲んだことのある人ならばわかるはずです。以上の他にも実践できそうなことがたくさん書かれていました。私は①を実践してみようかなと思います。このブログを書いていて気づいたのですが、右腕と左腕の太さが異なるのです。利き手ばかり使用していたようです。
2025.04.04
コメント(0)
全14件 (14件中 1-14件目)
1