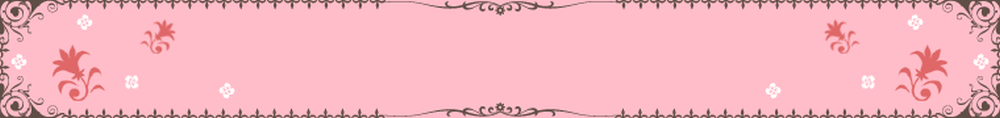第5章忌まわしき運命の日
「ごめんなさい、私のせいで」
「アンネローゼ嬢・・・」
エリアス卿はそそくさと離れる。
「普段は病院か、家だけなのだろう、仕方ない」
「ええ、アリスはだからいつも優しくしてくれて、ヴォルフリートも・・私がもう少し身体が強ければいいんだけど、他人が怖くて」
「他人は気にすることはない、君は今を楽しめばいい」
「お優しいんですね」
「オカルト話ほど無意味なものはないな」
また、唐突だ。
賢い皇太子は。勉強やら公務やら、特におそがしい以外は、こうしてやしきに来る。
「何、お化けでも見たんですか」
きっ、とにらまれた。
「いいか、ヴォルフリート、幽霊やお化け、妖精といったものはすべて暇を持て余した暇人者の創作物だ、つまりは勘違いだ、最低のしろものだ、ゴミだ」
「うん、とりあえずシェイクスピアに謝れと言っておきましょうか、それじゃ王宮近くの博物館や美術館はどうなるんです」
「記憶だ」
言い切られた。
ヒュウウウウ。
「ここは・・・」
アリスは塔を見上げると、とてつもなく高く、年代物のようだった。
「そこで何をしている?」
振り返ると、黒髪の長身の男がいた。
「貴方は」
「ダ―レス伯爵だ」
「伯爵さま」
あわてて赤いドレスのすそをつかんだ。
「大丈夫?」
「・・・え、ああ」
噴水前で休んでいると、なんか子役みたいな、さわやかオーラを背負った同い年の少年が声をかけてきた。
「顔の色悪いけど、具合悪いのかい」
「いや、ただの貧血」
その時、ありすがあわてて駆け寄ってきた。
「ごめん、待たせて」
「・・・・まず」
「こら、ヴォルフリート、アンネリーゼに失礼でしょう、謝りなさい」
「いいのです、アリス」
軽やかにアンネリーゼは笑う。
劇場のフロアでまるで劇のシーンのようにアレクシス・フォン・フェリクスにぶつかった。少し大人びた、優しい綺麗な少年。アルベルトとローザリンデと一緒だった。
けれど、なぜか素直にその手をとることができなかった。
「アレクシス、行くわよ―」
妹と姉らしき少女と兄らしい少年。
「ごめん、今行くよ」
柔らかくほほ笑まれ、アレクシスは戻っていく。
ちやほやされ、またはカリスマよろしく未来の皇帝として国を引っ張るリーダーとして、注目を集めるルドルフの姿をまたは10歳の少年を見つめる。子供に群がる大人というのも妙な図だが。
「眉目秀麗、成績優秀、君もあこがれるだろう」
「ああ、エリアス卿」
「何より美しいと思うだろう」
いや、まあ、確かに美形ですが。成人の大人が子供にいいます?
何か怖いんだけど。不気味だ。
「まあ・・」
「君も帝国の一員として、殿下を模範としていきたまえ」
完全に崇拝していた。
「はぁ・・」
ぼんやりした答えにエリアスは気合を入れろといきなり叫んだ。
「ふん」
唐突な大人だ。冷たい目で見た後、エリアス卿は去って行った。
ルドルフの方に視線を戻すと、女官に何やら愛を語っていた。頭の回転が速く、社交的で完璧。カリスマとはああいうものなんだろうか。ハイソでブルジョアで金持ちで王族で。
・・・何か傷つかない方法でお気に入りをやめれないだろうか。
「きついな」
何で友達を教師にしないといけないんだ。貴族あるある?
そんなきつい友達関係はやだな。
「薄っぺらいな、重厚感あるクラシカルな王子様に比べると」
ほんと、なんで田園ではなく、僕は都会のそれも宮殿にいるんでしょうか?これ、神様のいやがらせ?
華やかな宮廷劇を見ている気分だ。
「僕には関係ないかぁ」
上を立つ人は大変だ☆
宮廷の図書館から持ってきた分厚い呪文の本を手に持ち、今日も楽しくそれを紙に隅の方で書き留め、その数式や記号を解いていく。今まで文字は習わないでいたから楽しいな。
大人向きの本のせいか、難しい言葉も多いが、どうも火薬や花火、兵隊の絵も描かれているので兵隊の教科書らしい。大砲も書かれているのでそうなんだろう。何で兵隊の本でこんなに呪文や絵が多いのかわからないが。
「はーっ」
見事な演説だ。非公開ながらルドルフの言葉には自信と確信がある。
「すごいな」
「おい、しゃべるなよ」
観客の中にヴォルフリートの姿もある。
見上げた先に白亜の城があった。
アリスは驚いたように、エプロンドレスを翻して、その城に近づくと、窓からおとぎ話の御姫様のような女の子がこちらを覗き込んでいて。迷路のような庭に隣は薔薇園。大きな鉄製の門は漆黒に塗られていて。
哀しそうな菫色の瞳が覗き込んでいて。
探しに来た弟が赤いネクタイにベストを着て半ズボンをきて、切り返した。
「幻覚かしら」
「そうだよ、大体、ここにある城は有名な伯爵夫人のものだろう、彼女にそんな孫娘がいるわけないじゃないか」
「でも、確かに・・・」
振り返ると、白い布のようなものが窓から見える。
「いこう」
「ええ・・」
暇だなと自宅で本を読んでいると、視界の隅で父とディートリヒの姿が見えた。後ろにはエルネストの姿もある。基本的に仲がいいんだよな。
「ふぁーっ」
自分は一つ下のディートリヒが苦手だ。根っからのお貴族様で、生まれのいい彼は自分とは相性が悪い。エルネストとは仲がいいがやはり距離をとられている。ライバル意識が自分に向けられている。
「庭に行くか」
その時視界の隅で柔らかな金髪のウェーブヘアの少女が見える。
「お兄様」
柔らかなピンクのドレスに身を包んで、緑かかった青い瞳の。いかにもお姫様という感じの柔らかい印象の少女だ。
「先生が来るまで時間があるんです、一緒に部屋で遊びませんか」
母からいうと、フィネは自分になついているらしい。
「いや、ごめん、これから庭に行くから」
そういってフィネの横をすり抜けようとすると、フィネがあわてて追いかけてきた。
「お兄様、私も」
でも自分は彼女と過ごしていないし、親切にした記憶もない。姉さんとは仲良く遊んでいるのはみたことあるものの、彼女に慕われる要因を与えていない。ドジばかりしている。
「もう少ししたら、ディートリヒが来るだろ」
「お兄様はフィネがお嫌いなんですか?」
「はぁ?」
振り返り、彼女の方をみると泣きだしそうな表情で本を抱きしめている。
「いつもそっけない・・・、お姉さまばっかり」
ドレスのすそをつかんでいた。
「私お兄様ともっとおしゃべりしたい、遊びたいのに」
「何をしている」
その時、扉が開きディートリヒが入ってきた。
「新参者の分際でわが妹に手を出す気か」
「違います、ディートリヒお兄様、私は」
フィネの前に立つ。
「あのねぇ、でぃー」
宮廷で、皇太子の部屋を離れ、数人の侍従や従者に連れられて。アリスの母は、エリザベートのお気に入りでもあった。
―姉さん、エリク達のこと。
「・…ええ、院長先生が教会に火を放ったのよね」
場所は引き取られた2人の本当の家、ローゼンバルツァー。旅一座からウィーンに来た少女は、事件のショックを抱えながら、母親と弟に再会した。
ルドルフも同時期に起きた事件を聞いて、すぐにアリスを探させ、呼びよせた。彼女は犯人と真相の要求を求めた。
「あそこは隣国とも近く、政治的にも微妙な地方だ。それに犯人を探したら、わかっているのかね、未遂とはいえ、行方不明の院長以外にも関係のない村人まで容疑者に入ることになる」
執務室でローゼンバルツァーはそう言った。
「君は、そのものまで自分の真相を満たすために巻き込み気かね」
冷たい祖父の言葉にアリスはかっとなる。
「でも、民衆を守るのが王族や貴族でしょう」
「だが、一部の民衆のために守るべきものを犠牲にしていいという法はない、アーディアディト、お前がすべきは、今までのセカイやお前にかかわったものを断ち切ることだ、死んだ孤児のことは忘れろ」
所詮、歯車にすぎないといい捨てた。
「おじいさん・・・」
男の目は冷たい。
「それが彼らの運命だっただけだ」
弟の声にアリスは振り向く。
「・・・どうして」
「アーディアディト、僕には君の気持がわからないし、死んだ君の家族も知らない、君の祖父も言った通り、わが帝国のほんの一部の国民でしかない」
「・・・」
アリスは自分を見ていた。何かを窺うように。
「…だから教えてくれ、僕は外の世界を知らないから。君の家族休んでいたところを」
彼女の手に手を重ねる。
「勘違いするな、お前が特別だから、君が有力者の孫だからじゃない」
彼女の母はなぜ泣いていたのか。
「僕はいつだって僕のためにしか動けない、事件のことを父に暴動だと済ませた大臣がいたことも謝る気はない。だから教えろ」
姉は自分が姉がいないと何も出来ないと思っているようだが、自分は図太い。
ぐぅ。
「お腹すいた・・・」
すると、目の前に無造作に植えられている百合の花に囲まれた。光る苔がこびりついて、天道虫がついている門があった。
「・・・・オレンジ色の百合か」
ああ、しまった。植物図鑑か、昆虫図鑑でも借りてくるか、網か籠でも持ってくればよかった。
「もったいないな」
はぁと門に背中を預けると、いきなり、門がその姿ごと、ヴォルフリートの背中から消えた。
「え」
重点がなくなる。転げる。がたん、どたん。
草の匂いがした。
森の中でヴォルフリートは迷子になっていた。、先ほどから大人の一人も見かけない。
「姉さん、泣いていないかな」
困惑するとすぐ泣くからなぁ。
―それにしても、ルドルフ様って、偉いしたわれてるんだな。
。ここは悔しがるところだろうか。けれど本能的なのか、自分の性格か、ヴォルフリートは攻撃しないことが最大の防御であることを知っていた。
「だぁれ?」
振り向くと、軽やかな百合の匂いを漂わせた、春の妖精のような、かれんな少女がいた。服装からして、貴族の階級の子供だろうか。柔らかなウェーブかかった髪には赤いリボン。
「ここはうちの私有地よ、どこの家の子?」
ふわふわの砂糖菓子のような子。あまりの可愛らしさに自分の姿を急に思い出して。
「アッ、ええと、僕は・・・ヴァルヴぇるぐらオ家の」
目が開けると、首なしのギリシャ神話の女神たちの像が小さな泉や省スペースの花園があった。
「悪趣味だな」
像にまずは一言。頭の上には蛙が鳴いていた。小川に頭をつっこんだらしい。ドロの感触もある。こういうのをシャノン辺りに見られ絵羽、まず笑われるだろう。
エリクがいれば、仕方ないと悪態をつきながら、手を貸してくれそうだ。
「・・・・」
・・・・ここにある敷地を売るだけで、どれくらい、学校とかに行けるのだろう。
「起きようっと」
うんうん、やっぱり僕は本性は庶民とかなんだな。
「現実的じゃないよな」
成人したら、何か、家を出るりゆうをつけよう。
家を出たら。友達のコ都会っていたが。
「日々、精進だよな、うん」
どうなるのかと契約した時にルドルフ様に聞いたら、なぜか困った表情になったがなぜだろう。精神的だとかいったが。サポーターになれという意味だろうか。それもいったら、手で顔を隠された。変な子だな。
年下の子に可愛いとかとかいわれても少しも嬉しくないのだが、アレは遠まわしな嫌味だろうか。
コツン。
「?」
頭に何かぶつかった。
「石?」
ごろごろとヴォルフリートは転げ落ちる。猫はじっとヴォルフリートを見ていた。
棒には赤い血がついていた。
「じゃあ、猫、歩ける?とりあえず、綺麗な水がどこか、僕に教えてくれるか?」
当然、猫は答えないが背中を向けて歩き出す。
「よかった、じゃあ、傷を水で流さないとね」
隣を歩こうとした時、尻尾で叩かれた。視線で一定の距離を取れといわれた気がした。
門を抜けるとまた違う庭の中に出た。今度は色が違う、花々が咲いていた。ヒースににおいもする。中央には大きな木があった。
日が落ちる。
スソを引っ張られた。猫がじっと自分を見ていた。
「ゴメン、君の怪我、治さないとね」
ヴォルフリートは優しく頭を撫でた。
2
フォルクマ―ルと離れて、ダリルとともにメイズの中を迷い込んでいくと塔が見えた。
「あれは何なの」
ギクリ、としたようにダリルに緊張した様子が浮かぶ。すぐにアリスの肩を持ち、来た道に戻ろうとする。
「ただの貨物庫だよ、ローゼンバルツァーの先祖は国に仕えた騎士の家柄だから、その時の鎧や剣がおさめられているんだ」
「まあ面白そう」
行ってみましょうと言うと立ち入り禁止なんだ。
と言われた。
「エレオノ―ル様のところに戻ろう」
「駄目よ、弟を探さなきゃ」
その時だ、白い兎がアリスの前を横切ったのは。
「まあ、うさぎ!」
弾けるように明るい笑顔がアリスに浮かぶ。気づいたら駆け出していた。
慌てて、アリスが去っていくのをヴォルフリートは見かけた。
・・・何かあったのかな?
「・・・・」
けんか腰だからな、ルドルフ様も姉さんのこと、気に入ってるだろうに、何ですぐ喧嘩するかな。
「挨拶して、僕も帰ろうっと」
扉の前には、アリスを警戒したアレキサンダーが寝ていた。アリスを見て、敵だと判断したのだろうか。頭を撫でると、顎を摺り寄せてきた。
許してもらえたらしい。
「失礼します、ルドルフ様」
「入れ」
扉を開けると、ルドルフは広い窓の外の景色を見ていた。
・・・なんか、不機嫌そうだな。空気が重い。
「ええと、それじゃ、お元気そうなので、僕も家に」
ヴォルフリートは扉の方に下がりながら、ゴマするような笑みでそういった。
「・・・・無様だと思ったか」
「は?」
ヴォルフリートは教育を受けていない。アリスもだが。育った村でも無能だと、ドジでトロイとからかわれていた。のんびりして、変わっている。
頭の中も姉より鈍いのだろう。自分の話も半分は理解できていない、恐らく意味はわかっても聞き流している状態だ。痛められても、笑っていたらしい。泣き虫で甘えん坊で、姉の後ろに隠れて。
「女に弱いところを見られて、男なのに運ばれて、病気になって、・・・馬鹿だと思ったのだろう?」
弱みなど見せてはいけないのだ。ルドルフはヴォルフリートの方に顔を向けようと思わなかった。
「ええと?え?」
「僕は大丈夫だ、今日はヘンな所見せたな、下がれ」
「ええと・・」
う~ん、と首を傾ける。
「・・・・変な子ですよね、ルドルフ様って」
「は?」
「僕にはわからないんですが、何故恥ずかしいんです?病気になるのは、普通のことでしょう。病気になったら、誰だって頼りますよ。だって、怖いじゃないですか、そのまま死んだら」
「・・・あのナ、僕は皇太子だぞ。オーストリアのハプスブルクの。帝王は上に立つものだ、見本となる存在だ」
「身体が弱くてもですか?」
「貴様、侮辱罪だぞ、それは!!」
「ごめん・・・でも、9歳ですよ。甘える年齢だと思うんですが」
「僕は君と同じ子供じゃない、皇族だぞ。同じでいてはいけない、弱みは見せないものなんだよ」
「同じなわけないですよ、だって、僕とルドルフ様は他人、全くの他人ですよ。同じ人間なんて、僕はつまらないよ。いいじゃないですか、ルドルフ様が身体が弱くても、誰も責めてないんでしょう?」
元々勉強よりも、外で遊ぶ方が好きなカイザー・クラウドは目指す目標であるウィーン大学に入り、政治の世界に行くという夢のためにも、下々のものと触れ合うことも母が止めてもやめるつもりはなかった。
「坊ちゃん、いつまで、芝居じみたことを続ける気です」
馬に揺られながら、紐を引く執事のフェリクスにいつもの生意気な表情ではなく、子供じみた表情を浮かべた。
「アロイスの事か」
「はい、あのものは正直、不安なものを感じさせます」
「僕のやることに疑問があると?」
通りがかりに、エリアス・フォン・ゲハイムシェリフトが従者を連れて、カイザーに道を譲る。エリアスは、代々クラウド家に遣える騎士の家柄だった。同時に性格は相容れないものの、その実力で近衛隊の本体に所属するエリアスは、弁護士の資格ももっており、皇族にじかに仕えている。
「いえ、そのような・・・」
ふっ、と自信に溢れた笑みをカイザーは浮かべる。
「ならば、いいだろう」
ヒュウウウ―。
「あー」
完全に元のいた場所から離れてしまった。辺りは鬱蒼とした森の中だ。ダリルは追いかけてくれるかしら。
「仕方ないわね」
こういうときは動いても仕方ない。そう思って、アリスは雨をしのげる場所を探す。その時、あわてて馬車に乗るバドォール侯爵とその妻の姿が見えたが、二人にはアリスが見えていないようだった。
「なんだってあの人が来るのを忘れているんだ」
「親戚はもうあつまっているんでしょう」
何か家でトラブルでも起きたらしく慌てて乗り込み、去っていく。
3
「すごい・・・」
しばらくして森の中で狂ったように咲く青いバラの小さな家にアリスは辿り着き、重い錠の鉄製の扉を開ける。すると水の音が鳴り響き、しずくがアリスの持っていたペンダントの飾りに跳ね返る。
「まだ4月なのに・・・」
廃墟らしい。だが生活の匂いはのこっていた。貴族の私有地内とは思えないが、使用人か何かの家だろうか。木の床からは雑草や野草が見え隠れし、天井にはランプが下がっている。リビングと台所がセットになっており、木の階段からはほしたにおいがする。
だが薔薇が全ての雰囲気を奪っていた。写真立てや絵画が生活用品や家具の中にあるがここの主役は薔薇らしい。
きい、とその時、反対方向から音が聞こえた。
振り返ると、アリスは驚いた。
時刻は夕刻から夜になろうとしていた。
「あれは・・・もしかして」
アリスをみたという使用人とともに外れの家に向かうと金髪の少年が家の中から見える。
「本物の弟の―」
だがヴォルフリートが飛び込もうとした瞬間、中から激しい音が聞こえ、ヴォルフリートの小さな体を突き飛ばした。
「な!?」
カチッ。
ボーン。
ボーン。
柱時計の音が鳴り響く。
落ちる、落ちる。
大きな魔女に襲われる夢を、落ちていくアリスと金髪のヴォルフリートが大きい口に食べられる夢を。
落ちる、落ちる。
本宅の地下の扉の前で目が覚めると、アリスは泣きじゃくったヴォルフリートのそばかす顔を見上げていた。メイドのベッドの上にいた。使用人部屋で横になっていた。なんだか胸がぽっかりする。
喪失感を感じていた。
隣の部屋からはコンラ―トや父の声がする。
「聞いたか、今日の夜、バドォール家が襲われたらしい」
「一体、何が」
「それで伯爵夫妻や御子さんは!?」
バタバタ、と部屋の中に、金髪の貴族の男が入ってくる。
「エレオノ―ル、カイザーは!?」
「シーザー、彼なら今上でお医者様に見てもらっているわ」
気遣うような母と、整った容姿の30代くらいの男。
「そうか、悪い、カイザー」
違う部屋に向かう。
「ヴォルフリート・・・私、一体・・・」
阿多アがぼーっとする。身体も重い。
「・・・・古い家の中にガスがたまっていて、それが爆発したんだ」
「爆発・・」
そのせいだろうか、感覚が鈍い。
「そうだ、あなたに少し似たことであって、それで」
「姉さん?」
ぎゅっとヴォルフリートが握る。
身体から何本も剣が飛び出した夢をみたのだ、しかもそれが空に散らばって。
「そうよ、胸に・・・」
何かを刺されたのだ。
「胸に何か刻印のようなものが・・・!!」
家に帰ったとき、夕刻に近い時間だった。
アーディアディト・フォン・ヴァルフベルグラオが本宅に帰ると、メイド数人が迎えてくれた。
次男坊、ディートリヒ。貴族である事を誇りに持ち、カレからしたら貴族のフリをする詐欺師的存在であるアリス達きょうだいをみとめるきなどみじんもなく、初めての夕食会をボイコットし、卑怯といえる手段でアリスを攻撃し、嵐の中、地下室に二時間くらい閉じ込められた。ヴォルフリートは苦手なにんじんを二週間くらい入れられ、靴の中にネズミが入れられ、自分の支配下に置いた使用人に無視を実行させた。
蜂蜜色の髪に高貴なコバルトブルーノヒトミの少年は、音年13歳を迎える。彫刻のように整った高貴な顔立ちの美少年は、螺旋階段でアリスに会うと、鼻で笑った。
虫けらを見る目だ。
「これはこれは、麗しのおねえさまではありませんか、今日もご機嫌が宜しいようで」
「どうも、貴方もよさそうね、ディートリヒ」
「お姉さまほどじゃありませんよ」
ふふ、とディートリヒは笑う。
「家庭教師の先生を精神病院送りにしたんですって?」
「僕の頭脳と渡り合うには、彼女達には大変ですからね」
ふふん、と髪をかきあげて、ゆっくりした足取りでディートリヒが降りてきて、アリスのイル段に降りてくる。
白い顔が微妙に青い。また持病の頭痛にでもなっていたのだろうか。それとも得意の神経性以遠だろうか。何故、ディートリヒはいくら庶民育ちだからといって、自分に挑発的なんだろうか。
「・・・まぁ、もっとも?とてもとてもお優しい姉気味さまなら先生方ももう少し顔を曇らせないと思いますが」
優美で訓練された仕種や視線。動き一つ一つに生まれの違いや高貴なるものの柔らかさや鋭さがあった。
「姉様は、大人に取り入るのと人気取りがお得意ですからね」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 超合金
- 僕の夢のコレクション(146) 鋼鉄ジー…
- (2025-09-25 20:55:09)
-
-
-

- 美術館・展覧会・ギャラリー
- Alphabetシリーズ「Q」hamster
- (2025-11-19 06:58:20)
-
-
-

- ハンドメイドが好き
- 年末年始営業日のお知らせ
- (2025-11-10 12:53:16)
-
© Rakuten Group, Inc.