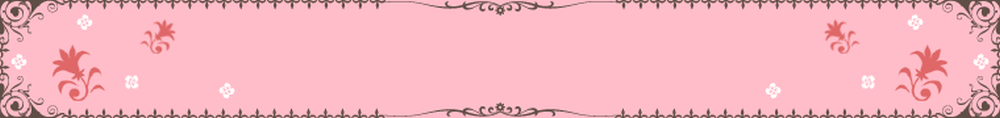第6章真夜中の金糸雀
シエラは少々、年上に生意気な一面を持つ。プライドもエレベスト級だ。
「貴方達、私に協力しなさい」
美術館の職員は突然現れた十代の少女に見るからにいやそうな表情をした。
「あら、うれしいでしょう、私みたいな美人にその声をかけてもらえるなんて」
我儘で男なら言うことを聞くと思っている。
「世界征服クラブって」
「姉さん・・・」
反対されたなら、新しい場所を作りましょうって。
「確かにクラブの代表は、女の子より男がいいけど」
「いい考えでしょ」
にこにこしている。
大学の研究員や紳士服の男性たちもいる。レオンハルトが主催したクラブらしいが、これはアイドルのファンクラブですよね、先輩のウタヒメの。
「あら、デートの待ち合わせ?」
にこりと公園で虫の時点を読んでいたらヘレネが供のものを連れてやってきた。
「いや、(唯一の)友達と待ち合わせ」
今はもう彼女だけが友達である。
「…女の子ね」
「どんな子?」
「長くて細い、年上の女の子かな」
フィネは朝が弱い。朝に早いアリスとしては早く起きてほしいがそれは仕方ないのであろう。アンティークや歴史の本にも弱く、目が見えないということは少女にはマイナスではないらしい。
「まあ、アロイス様が」
頬を赤らめ、うれしそうに微笑む。
「もう、アロイスなんて知らない」
バンっ、と扉を閉められた。
「・・・・・・・・・はぁ」
アロイスはすぐそばの階段を下り始める。
「ルドルフ様」
いさめるようにいうと、
「・…まあ、噂だけだが」
するとそんな2人に気づいたのか、少女が笑顔を浮かべ、手をふる。
「おお、皇太子殿下に手を振っておられるぞ」
「優しそうな方じゃないですか」
「まあかかわる分には温室育ちの令嬢なんだが」
あれ、ヴォルフリートはと振り返ると、後ろであげた手を下していた。
「お前もか」
「何がです?」
お前ではなく僕何だがな。
「一応言うがあれは社交辞令だ]
「そうですけど一応もしももありますし」
全く見―ハ―な奴め。
「くしゅっ」
「何だ風邪か?」
「?いや・・」
アリスが近寄ってくる。
「ヴォルフリート、医者の先生呼んでこようか」
「いいよ、自分で行く」
規律やルール、国の国是や正義、周囲の大人たちの抑圧を受け、その上、受けのいい大人しく、控えめで温厚な皇太子を演じなければいけないルドルフの肩には、双翼のわしの紋章がかかっている。元気がいいといえば、聞こえはいいが、ルドルフにはアリスが無作法で無神経に見えた。おせっかいのつもりなのか、皇太子という立場も気にせずに人の懐にずかずかと入ってくる。そのくせ、自分の大事なもののためには一歩も引かない。エリアスにからからかわれたときも双だ。大勢の貴族やくらいを持つ大臣や軍人の前で、紋章の入った懐中時計を見せた。
「言葉を撤回しなさい、私を馬鹿にするのは許すわ、けれど、貴方に私の父さんを、弟を愚弄する権利はないわ」
燃え立つような、生命の力に満ちた青い瞳。発言力のアル家柄のエリアスにも劣らぬ威圧感、その存在感。金色の長い髪は一国の女王のような、彼女の強烈な魅力を引き出していた。
格好は、ジュースで濡れて破けたドレスだというのに、どの少女よりも目立っていた。
「私はアーディアディト、レオンハルトとエレオノールの娘、アーディアディト・フォン・ヴァルフベルグラオです」
「君は一体・・・・・」
背中がざわついたのをルドルフは覚えている。
後ろからぎゅっと抱きしめられた。
「ヴォルフリート!」
振り返ると、ギ―ぜらがいた。ルドルフの姉の。
「ギ―ぜラ様?」
慌ててヴォルフリートは彼女から離れる。
「背が伸びたわね、それに男前になったわ」
いい子と頭をなでられた。
「ご結婚が決まったんじゃ」
「そうだけど、・・・ただ周りが変わりすぎるからね」
寂しそうにギ―ぜらは笑う。
「アリストも距離があるし」
「ギ―ぜラ様・・・」
にこっとほほ笑む。
「それじゃ」
・・・フロアの方でざわめきが上がっている。そろそろパーティーも終わりだろう。
「困った、風邪くすり聞かない」
喉を押さえて、首だけ会場の方に向ける。
華やかな会場に紳士服、ドレス、うわさ話。豪華な食事。
その全てはウィーンに来るまでかかわることのなかったものだ。炎、赤い血。
そしてエマ達の顔は―・・。
ぐっと柄をつかむ。
「大丈夫・・・」
冷たい汗が流れる。
「大丈夫だよ、僕は強い・・」
「強いんだから」
「サルヴァトール公、本当にやるんですか?」
「無論だ、今挑戦しなくてイツ挑戦するというんだ、行くぞシュテルンバステル伯」
陽光のせいで、今年で15歳になるヴォルフリートの顔はよく見えない。美丈夫といわれ、ルドルフに比べれば健康的なハプスブルクの問題児は、ロレンツ銃を手に新しく作られた小型爆弾に銃弾を放った。
パァン、スパパパン・・・・・!!
ドォン!!
空に煙が待った。
「・・・・・あの、花火みたいなんですが」
「よし、お前、見て来い」
「エーッ、俺ですか」
助けを求めるように、隣のヴォルフリートを見る。
「僕が行くよ」
これで、賭けは自分の負けとなるのか。
・・・僕、事務系というか、情報を集める方なんだけどな。
ハプスブルク家の紋章をイメージした飾りがついた帽子を整えて、大きめの軍服を揺らしながら、ヴォルフリートはそれに近づいた。
ダークブラウンの髪が乾いた風で揺れた。
「皇太子殿下!!」
ルドルフは、ヴォルフリートを見て、あからさまに誰に声をかけられたのか、わからないといった表情を浮かべた。
青い瞳は湖底を思わせる色合いに染まり、緑色の右目は濃く高貴さを滲み出してきており、日に焼けている右手には刻まれたような、十字架のような痛々しい傷跡があり、額にも同じような小さすぎる傷跡があるが、よく見ないと気付かない小ささだ。
「こんばんは!!今日はどのような気分でしょうか!挨拶が遅れてすみません、こちらに付くのが少し遅れてしまって・・・・」
「・・・ヴォルフリートか?」
薄暗さと日の光に中和されて、はっきりとその顔が見える。
そばかすが消えているが、その素朴さは変わっていないように見えるが、かなり整ってきている。柔らかく、可愛い印象だ。
「え、今、気付かれたんですか?」
今日は何なんだろうか、家に帰っても同じ事を何回も聞かれるし、街では変な目で動物のように女の人に見られるし。
「お前、化けたな、さすがはエレオノールの子供というわけか、血ってのは怖いな」
何故、ジーット見ているのだろう。
「それ、姉さんにも言われました、別に前と変わらないと思いますが」
「変わってる事に気づかないのか?」
「そういわれても、かがみ見るのが少ないですし」
「え・・・」
アリスの胸がときめく。
「お前のこと嫌いじゃない」
アロイスは確かにそう言った。
ざぁぁぁぁ。
「迷惑ではないさ」
雨が降っていた。
視界の隅にディートリヒやフィネの視線を感じたが、目の前のアリスの方に視線を戻した。
「モテ期が来たのかもしれないわ」
考え込みながらぽつりとそう言った。
「ギ―ぜラ様、あなたが好きなのかも」
「まさか」
あははっと笑う。
「国の皇女様が僕を好きになるわけない」
「それに、・・・ああっ、どうしよう、いえないわ!!」
頬を赤らめながら金髪の髪を激しく揺らす。
「そんな、なんて禁断・・・!!」
「楽しそうだね、姉さん」
ほう、と頬に手を当てる。
「ジ―クムントも同じなのよね」
「うん、そうなんだって」
ヴォルフリートはステーキを切り刻んだ。
「宮殿に行きにくいわ」
急にまじめにならないでほしい。
「僕も行きにくいよ」
友達が特殊な趣味ってきついわ。
「ルドルフ様は女の子に興味ないのかしら?」
ぴた、と手を止める。
「へえ、姉さん、ルドルフ様に興味あるんだ?」
何だ、僕がいないときに手を出したのか、あの野郎。少しばかり顔もいいからって。
「え・・」
かぁぁと頬を染める。何、その天使みたいな表情。
「別に私はそんなんじゃ、私、好きな人いるし」
痛い。
「ヴォルフリートの意地悪・・・」
ごにょごにょし始めた。どもる姿も可愛いけどきつい。気のせいか胸が重い。
雨の中の美しい少年と年下の少女。
きっとすれ違いもあったんだろう。けれど、少年はほほ笑んだ。それが外見だけではなく中身も男前で、綺麗な光景だった。
けれど、断絶した、別の世界だった。決して、自分が入ることはない。本当につがつながっていたら、痛みはなかっただろうか。恋。
「ただ、弟みたいなもので、放っておけないし」
恋なんて、エマもヴィンセントもできないのに。カールももう永遠に大人になれない。本当に自分が怪物なら助けられた。
・・カリーヌ。
何だ視界が揺らめく。
「・・そうなんだ」
声が震える。
柱の陰で、ヴォルフリートはたっていた。鋭いまなざしで。雨はやんでいた。
「ヴィルフリート」
後ろで気配がした。柔らかな紫のウェーブヘア。胸の中の暗闇は晴れない。
「お前か、アンネミ―ケ」
認めるものか、アーディア姉さんが今を認めても、俺は認めない。
「私に用って?」
手を指を重ねる。
「反対方向を向け」
「・・・どうして」
じろり、と見据えるように見るとヴォルフリートはにらむ。
「俺と話すときはイエスかノーだ」
びくり、とアンネミ―ケが肩を震えさせた。
「は、はい」
炎に包まれたあの日を俺は過去にしない。
「答えろ、孤児院での事件、お前の仲間がからんでいるのか、アテナの剣の手のものか?誰が俺の家族を殺した」
2
アリスはそのギャップに動揺する。いつも厳しいフォルクマ―ルが、子供に優しく話しかけて、笑っている。
「自由だ、民主主義だと叫ぶ反政府も外国の新しい技術を呼ぼうとする奴らも根元は同じ、この国を生き残らせようとしている」
「不思議だな、私の知るやつらとはアリス、君は違うようだ」
「え・・・」
「もっと近くで見ていいか」
「まさか、まだ復讐を考えていないよね」
「あの寒い国でのことは君にとって痛みしか与えないはずだ」
「フォルクマ―ル・・・」
カインベルク卿は、彼は緊張した。
経験上、ルドルフがこういう振る舞いをする時は不機嫌な状態だからだ。強気で傲慢で意地悪ばかり。からかうような、指摘することばかり、自分に言う。
そういう時とは違う。
「・・・・殿下、何故、ここに」
緊張で声が震える。いつもの自分らしくない。させてもらえない。
誰も彼と同じ立場になれない。親しいとはいえ、自分はたくさんいる皇族の臣下にすぎないのだ。
「何故、最初の段階で折れなかった?こいつの立場が後でますます悪くなると考えられないのか?」
「それは・・・」
「どうなんだ?」
至近距離で整った、美しい顔に見られ、動揺する。何を動揺するんだ。相手は年下の同じ男だぞ。
「とめるためだ、あそこでおれたら、ヴォルフリートは宮殿内でますます孤立させられる」
「だから?」
「・・・すみません」
口出す権利はない。でも、ルドルフにこんな言葉、言われたくなかった。理由はわからないけど。
「カインベルク卿は悪くありません、ええと、だから、苛めないで下さい」
「・・・はぁ?」
「侯爵様たちに僕が言い返せなかったのは僕の力不足です」
なんて頭が悪い奴だ、まずいとカインベルク卿は止めようとした。よりによって、殿下に意見するなんて。
「助けに来てくれたのは嬉しいですけど、これは僕個人とカインベルク卿の問題、朴達が解決することなんです」
じょうきょうがまずい。顔を青くして、にらみ合うルドルフとヴォルフリートを見る。
「僕に口出す権利はないと」
「はい」
はっきり言いすぎだろ、・・・・こいつ、頭おかしいのか?家の事、考えろ。
「で、殿下」
カインベルク卿は何とか空気をなだめようとする。え?
冷たい表情から、ルドルフは肩を震えさせていた。顔もぷるぷると震えさせている。初めて見るルドルフの表情だった。
「バカ、無神経・・・最悪だ、最悪・・・」
泣かないのはプライドか。顔が怒りで赤い。手を震えさせている。
「う・・・」
ヴォルフリートの手を引いた。
「バカがぁぁぁ!!」
走り出した。
嵐の晩の事を良く覚えていない、訓練が終わり、ルドルフ様に呼ばれて、ヴォルフリートは、ルドルフの部屋の中を通された。
「遅い」
いきなり、ルドルフに足を踏まれた。
「この僕を待たせるとは、お前も随分偉くなったもんだ」
意地悪な笑顔をルドルフが浮かべている。
「痛いぞ、ルドルフ様!!」
「僕を待たせた罰だ、僕に話す前に兵士なんかになりやがって」
かなり不機嫌だ、これは困った。
「僕の意志ですよ、貴方を、ルドルフ様を守るために、そう約束したでしょう?」
仕方ないな、と弟のことを思い出しながら、普通の声で当たり前のように言った。
「・・・ずるい奴だ」
「?」
何で、視線をそらすのだろう、皇太子だと同年代の友人を作る事が少ないからだろうけど。
「女性にも同じことを言うなよ、お前は誤解されやすいからな、バカだし」
「あーっ、バカにしましたね、僕がそういうのにブイからって」
「こら、ぽかぽか殴るな」
馬車の中で、ヴォルフリートは従者に声をかけられながら、肩に緊張感が走っていることに気付き、ゆっくりと肩から力を抜いた。
「・・・・つかれた~、・・・はぁ」
その時、白馬に乗ったアリスが、飛び込んできた。金髪の長い髪をリボンで結いこんでいた。その青い瞳はますます、母親に似ている。
今、まさに咲き誇る花のような、清廉な美しさを漂わせていた。ヴォルフリートも思わず、その美しさに見惚れる。
「・・・お待ち下さい、アーディアディトお嬢様!!社交界も前だというのに、そのような格好で」
「そうですよ、まずレディーらしく振舞っていただかないと、いい縁談もつかめませんよ!」
「いいのよ、私、歌手になるんだから」
「やめてください、まただんな様の貧血を起こす気ですか?」
アリスは馬から下りると、ヴォルフリートと視線を合わせた。
「・・・・ヴォルフリート、化けたわね、私と兄弟なのね、・・・ふうん、格好良くなったじゃない」
ぼおっ、とアリスはヴォルフリートに見ほれた。
アリスは、背後に気付くべきであった。、カールの周りに動き回り、火をつける役でもある我がまま娘のドロテアは黒髪の縦ロールをいつものように弄り回した。彼女が機嫌いいときに出す癖だ。事後処理に明け暮れる役のアリスのお世話係であるメイド、ソフィア・ジャスパーが、刑事と話をした後、戻ってきた。
長身のダークブラウンに水色の瞳の眼鏡美人で、アリスに忠実だ。冷たくヴォルフリートを見ると、ひるんだ表情をヴォルフリートは浮かべる。
「正義の味方とデスゲームなんて、お姉様はグレイトなお方ね」
「・・・あの仮面、奥手だな。顔はいいのに、自分の外見を生かさないなんて、もったいない。利用できるものは、利用できるようにしておかないと」
「まぁ、恋をしたことのないヴォルフリートお兄様にはわからないでしょうけど」
ふふんと誇らしげにアリスとアロイスの邂逅を見ているドロテアは同じく見ているヴォルフリートにそういった。根はおせっかいで世話好きとアリスからは聞いているが、その通りらしい。
「熱病は気がつかないうちに始まることくらいは理解しているさ、ドロテア。僕にそういう君は何故何回も殿下に振られているのに、殿下のことを好きでい続けるんだい?小あくまでわがままで、時々優しい甘えん坊のキャラ・・・演じるなら、一つに絞った方がいいよ。好きと叫ぶだけが、恋愛じゃないんだろう、お子様の僕と違って、賢く美しい君ならわかるはずだ」
蜂蜜のようだ。甘くて、まとわりつくようで、喉の置くがツン、とするような妙な感覚。
「・・・・当たり前よ、私、貴方ほど、立場をわきまえられなくないもの」
2
アリスの望みは勿論、歌手であり続けることだ。答えは決まっている。物事を単純にならないのは、貴族の立場ではない。家族という居場所だった。両親も、ヴォルフリートも、弟や妹も大事だ。
深夜の馬車の中、ソフィアに相談する。
「・・・家を出たほうがいいのよね」
「それはご相談ですか?決意ですか?」
真っ直ぐな目でソフィアがアリスを見る。
「・・・・何も言ってくれないのね」
リングの周りを走っていると、宮殿前の衛兵に呼び止められた。
「すみません、お嬢様、悪いのですが、この先の道は使わずに回り道をしていただきませんか」
「この先で工事をしておりまして・・・」
はい、と答える時を聞かせた御者が違う道のルートに馬を走らせた。
観客席の中には、アレクシスとその彼女であるデルフィーナの姿もある。スポットライトの中で、砂利が入っていたパンを食べて、口の中をきってしまったジュリエット役のアリスは観客を動揺させていた。
だが、その時、艶やかな春を思わせる色合いの髪を持つマリーベルは、ロミオとして、出番ではないのに、ジュリエットに近づいた。
「・・・・・え、ロミオ?」
「出番じゃないのに」
観客と同様、罠を仕掛けた役者も動揺している。
マリーベルさんが出るなんて、どうして・・・。
見つめあうロミオとジュリエット。筋書きを変えてしまっている脚本だからこそ、番狂わせは許されない。だからこそ、ここでマリーベルが出てきたことにジュリエットは動揺を隠すことが出来ない。
同時間の劇場内のバルコニーで、ヴォルフリートは吸血衝動に襲われていた。不定期に訪れる発作に従者のトルコ出身の褐色の少年は、聞きなれないウクライナの子守唄を歌って、対応している。美形だと思うが、奴隷として売られ、両親や刻に捨てられ、流浪した過去を持つ少年は感情を見せることがない。
サアラもとるコや東スラヴ系の民族であり、ソフィア・ジャスパーも純粋なヨーロッパ人に見えるが、元々はブコヴィナ地方のウクライナとドイツ系イギリス人の血筋とフィネから聞いたことがある。
劇場の外では帝国内の20パーセントを有するハンガリー人が点在している。
ヴォルフリートの視界の中には、今の特権が離れることなど考えないドイツ語をしゃべるオーストリア人、外交官のドイツ人。外ではクロアチア人やポーランド人が闊歩して、歩いてる。
帝国のどこを行っても、自由を自治獲得の声があった。 工業を握るボヘミア人、資本家が多いユダヤ人。
―立憲と民主主義?全く違うのに何故一緒に共存するの?
アリスは輝く目で横顔のルドルフを見ていた。上に立つものだけが掲げる理想。この人なら任せられる。
エリアスやベルクウェインはそんな目で幼いルドルフを見た。
―お前はどう思う?
あの時、何と答えたんだったけ?
観客席には、アルベルトの姿があった。
「見に来てくれたんだ」
「私もいますわよ」
ツィツィーリアはふんと鼻を鳴らした。
「ツイツィーリアも元気そうで」
「今日、少し元気がなかったけど、大丈夫?」
「え・・・」
どきりとなる。もしかして、心配してくれているんだろうか。
「アルベルト、ほら、お父様たちが着ますわよ」
「そうか、早いな、それじゃあ、アーディアディト」
「ええ」
笑顔で挨拶して、分かれた。
「あのバレエダンサー、やばくない?」
「悪くないな」
「可愛い」
「可愛いけど、ガキくさくないか」
「ベルクウェイン、君はストイックだからこないんじゃないのか」
「うるさいな、ベルは、たまたまチケットが手に入ったんだよ。ジャ泣きゃ、誰がこんな狂人と」
あはは、とヴォルフリートが笑う。
「酷いなぁ」
3
劇が終わる時に、アリスは散らばる脚と広大な観客席の中から、アロイ簾の姿を見つける。
・・・あの人。
「アリス?」
アリスは気付いたら、駆け出していた。
ロビーで、ギルバートはアリスの艶やかなドレス姿と、アロイスを見る。
胸がざわついた。
「待って、待って」
まさか。
ある予感がたぎった。
オーストリア領キュステンラント。帝国自由都市トリエステ、ゴリツィア・グラディスカ伯国、イストリア辺境伯領の3地域からなり、エドガー。グレムムントはスロベニア人とクロアチア人も周囲に囲むように住んでいたので、自然と彼らの言葉を覚えた。山から見える、澄み切った青い海のトリエステ、夏になるとそこに住む祖父母に会いに毎年、7人兄弟で遊びに出かけていった。ピランで、両親が恋に堕ちた話を祖母はよく語ってくれたが、祖父は口が重く語ってくれなかった。
エドガー・エドムント・ミーケ・フォンノイブルク男爵、大佐殿の教官室に呼び出されたのは、キュステンラントとでの巡回の仕事になれたときだった。
「君に隊長役を頼みたい」
「は?」
「今度、軍で内密に極秘事項の任務につく部隊を編成することになった。本来なら成人した時、君たちは出身のエリアに配備されるが、その部隊では実力のみで選抜され、あらゆるセンチに赴くことになる」
「と、いいますと」
ノア・ジークハルト・アイヒベルクは、エスターライヒ・ウンター・デア・エンス大公国、自分の故郷でいい目に合ったことはない。最初の記憶は路地裏のゴミ置き場で体を震えさせていた記憶だ。そんな環境から抜け出したくて、バドぉール家という貴族の屋敷から一枚の皿を盗み出した。
仲間を連れて、計画的な犯行だった。その日、雪が降っていた。
「はぁ・・・はぁ・・・・」
息を切らして、街の中を警察に追われながらぼろきれのような漆黒の服を着て、はだしで走っていた。
「待て、止まれ」
抱えるのは、金の縁で囲まれた綺麗な皿。ダンダンと力が抜けていく足。抜けていく感覚。ガラスで切った手。
だが、止まれば殴られるだけだ。監獄に入れられて、また死ぬより屈辱的なことをやらされる。父が金で、女達に自分を売ったように。
「はぁ・・・・」
そんな時、草叢から一匹の猫がノアの前を通り過ぎた。
―猫?
一瞬、止まるがすぐに走り出す。今、止まる余裕はない。そう思って走り出した時―
「あっ」
エルフリーデ、赤いリボンの黒髪ロングヘアの少女をお暇様抱っこしながら屋根の上を走っていたとき、銃弾に撃たれながら、ヴォルフリートは足を踏み外し、部隊の隊員候補の家を廻って板のあの上に落下した。
「きゃあああああああ!!」
「わああああ!!」
細い腕を必死にヴォルフリートに抱きついてくる。仕種も表情も人間の少女そのものだ。やっぱり、他人か。
「ちょっと、男でしょ、何とかしなさい!!」
「そんな子といわれても!」
ドサァァァァ。
「大丈夫か、お前ら」
ノアは2人を小さい体で見事に受け止めた。エルフリーデやヴォルフリートはぱちくりしている。
「え・・・」
「あ・・・」
エルフリーデがヴォルフリートに抱きついていたことに気付いた。
「変態、離れなさいよ!!」
「じたばたと」
顔や首、手を引っかかれた。
「暴れないでよ!!」
「・・・落ち着け、お前ら」
「・・・何してるんだ」
「・・・しっ」
すると、反対からアーデルハイトがでてきた。
「すみません、カインベルク卿、このあたりでヴォルフリートを見ませんでした。さっきまで近くにいたんですが」
「俺は見てないが」
「そうですか、それでは」
ドレスの裾を掴んで、アーデルハイトがメイドを連れて去っていく。
数分過ぎた後、出てきた。
15歳の頃、14歳のカインベルク卿はヴォルフリートと再会した。
「アーデルハイト嬢に何かしたのか」
ヴォルフリートがでてきた。
「・・・何も、良かった、いってくれて、あの人苦手なんだよ」
「女でも泣かせたのか、頬」
「・・・ああ、浮気がばれて、ふられただけだよ」
「不道徳だぞ、お前、まだ一つしか違わないのに」
4
「…怖いわ、ヴォルフリート」
「大丈夫」
「そばにいて」
「大丈夫だよ」
雷が鳴る中、ヴォルフリートはベッドにもぐりこんだアリスの体を抱きしめた。
「怖いものは僕に預けてくればいいから」
この前まで怖がるのは僕だったのに、ね。
「ヴォルフリート・フォン・ヴァルベルグラオの個人データだね」
「ああ、お前はこいつの成績をどう思う?」
ベルクウェインは同席を突然頼まれ、緊張していた。目の前に憧れのノアがいる。嬉しい、どうして。
「座学に状況分析能力や戦術、基本的なことは出来ているようだが、これが?」
ノアが一年での成績を見る。
「学校前でのこいつの基本的な生活環境や基礎体力や武術の経験についても調べた。優秀な教官がいたとして、すぐにこんなに結果を出させるか?身内の話でもとても軍人向きではないと判断されていたそうだ」
エルムントが改めて、データを見る。
「明後日のグラウンドでの試験にはまだ、候補生に空きが会ったね」
「試してみる価値があるかどうか・・・」
ふむ、とエルムントは考え込む。
「それともとんでもない詐欺師か、アホか、・・・変なガキだ」
ノアは書類の一部を投げ捨てた。
5
夜の屋敷、ダンスパーティー。
「ええ、幻滅しました」
「だろうな」
カインベルク卿は噂で聞くヴォルフリートと違う、名七マシさに嫌悪感を感じた。
「・・・奴はなぜ、本命を作らないんだろう」
そんなに人の気持ちをもてあそぶのがすきなのだろうか。いつも、女性を怒らせてばかりで。
ディートリヒが通りかかる。
「私には、彼が孤独を抱えているように見えるのです」
「アーデルハイト?」
「彼は何故、嘘をつくのでしょう?」
「確かに聞く話だと、印象がばらばらだな。ナンパな女好きだったり、下品だったり、Sだったり、いろいろと。だが、俺が見た限り、奴の生活に複雑な事情や悩みは露ほども感じないんだが」
むしろ、悩みさえないだろう、アレは。
「問題はそこです、お姉様のアーディアディトさえ、そうだと信じていることです。私はあの人はたくさんの人に囲まれ、愛されていても、殿下とはまた違う、私たちとは違う悲しみや孤独を抱えているように見えて、いつも寂しそうにみえて、胸がしめつけられます」
「・・・すきなのか?」
「いえ、ですが、そう見えるのです」
視界の隅で、両親と話すヴォルフリートを見る。
実験施設にあの子供が手伝いに来るようになったのは、別荘での儀式が行われた後だ。研究日誌に、研究者の一人、オスカーが担当の被験者であるヴィルフリートのことを書く。彼の集中力と執拗なまでの研究は異様だった。経歴からしても普通の子供の教育のスピードを超えて、今までの平凡な自分を捨て、急いで情報を技術を習得しているように見えた。
薄暗い部屋の中で、彼は時に異能者専用の医者ととある少女の記憶保持の為の治療法を一般の医療法、超能力の方面から語り合い、探っていた。元々頭の回転も遅く、運動神経も平均以下だった。
「違う・・・これじゃない」
地で濡れた手で壁や床に方式を書き、被験者の記憶、能力の持続時間、どの期間の初期段階からベストの結果が導き出せるか。彼は頭の悪さを自覚し、努力を重ね、慌てて自分の能力に変えていこうとしていた。
「この方式から、・・・が通常生活を送り、異能者であり続けるためには、違う、ああっ、どうして・・・」
目は血走り、体は披露で弱くなる。
「オカルト方面での、錬金術・・・不老不死、人体実験の方面なら・・・・・だめだ、数が足りない・・・うう」
そうだ、時々泣いていたことがある。
そんな時だ、ヨハネス・・・・課の家の当主が彼にささやいたのは。
「パンドラ・・・あの機械を覚えて折るな」
「・・・・ローゼンバルツァー公」
「わしはな、このところのお前の働きを見て、考えたのだ。お前、人の身を捨て、本当の悪魔に、わしの剣にならぬか」
「・・・・・」
「あるゲームの企画がある・・・・一つずるをしてみないか。数人の人間で王の座を競うゲームだ、勝利者にはある権利が譲渡される。その参加者全員を殺すか、奪うかすれば、お前の大切な家族は助かるかもしれん」
オスカーはぎくりとなった。にやり、と少年が笑ったのだ。
6
ヴィルマー卿はゴットフリート・フォン・クラーニヒブラルが嫌いだった。家が近いこともあり、幼馴染のような間柄だったが、家柄に鼻にかけ、面倒なことは父の仕事の失敗を縦に、何かと自分を頼ろうとする甘えも。憧れのアーデルハイト嬢が参加する宮廷の音楽会でさえ、意味のない自慢大会を貴族の子息達に話している。
「アルベルト・・・、君は大丈夫なのか」
「・・・・あ、いや」
「体調でも悪いのか」
「体調は大丈夫だ、ゴットフリートはずっとアーデルハイト嬢の兄上たちと話しているね」
「クラーニヒブラル家は最近、議会でもその影響力に幅を伸ばしているからな。・・・ああ、勢力を増しているといえば、チロルでまた抵抗運動が起こっているそうだ」
「チロルで?」
エドガー・ホルムグレンの放浪癖、アルベルトは思い出した。実力があるが、どういうわけか、舞台にたらいまわしにされている自由な友人ののんきな笑顔が浮かんだ。今は何の任務についているんだろうか。
「!」
デュドネ・ブレーズ、あの強硬派の侯爵の縁戚の少年と目が合った。アルベルトが笑顔を向けると、慌てて視線をそらした。
人見知りは直っていないようだ。
音楽会が終わり、フルートを吹き終わったアーデルハイトがゴットフリートの誘いを切り抜けて、馬車に乗って街中を眺めている時、雨が降ってきたことに気付いた。
「雨が・・・」
「ア、本当ですね、お嬢様」
お目付け役の女性が眼鏡を調えながら、外に視線を向けた。宮廷の花、いずれは名門の貴族の家に嫁ぎ、その跡継ぎを生む。それが貴族の家に生まれた少女の人生だ。政略結婚の道具なのだ。だけど、アーデルハイトは自分の境遇を嘆いたことはない。
「イヤですわ、物乞いですわ」
路地裏にボロ雑巾のような人々や恐らくはクロアチア人やルーマニア人の流れ者がいた。胸の奥が痛んだ。境遇を嘆いたことはない。
―気にすることはないわ。
太陽のような笑顔のあーディアディト、彼女は自分に言った。
―貴方は、貴方ができることをがんばればいいのよ。
輝くような金髪の眩しい少女。
出自は社交界デビューされる令嬢や子息には大事な条件であり、養子も徹底的に調べられる。過去の経歴や病歴も。自分の今の立場は貴族の母の血筋と先祖の栄光であり、リヒャルトの出世にある。優しい両親と兄や弟に囲まれ、友人に恵まれた愛らしい少女。純粋で一途そう、おしとやかで愛すべきわがままを持つ、誰からも愛される美少女。
家族も、周囲の人間、使用人までもが、アーデルハイトをそうだと信じていた。
レースがかかった窓からは、シーツで作った綱があった。幼いアーデルハイトはオーストリア領キュステンラントに観光に来たとき、煩い母やメイドから逃れたくて、屋敷から抜け出したことがある。凄くスリルがあった。
ドキドキした。海に面した綺麗な街、にぎわう人々。どんな楽しい事があるんだろう。そう思って、ドキドキしながら駆け抜けて、行き止まりで迷子になった。
実は従者抜きで一人で外に出たのはこれが初めてだった。
「お父様・・・お母様ぁ・・・エリー」
エリートは昨年までアーデルハイトの世話役だった女性だ。だが、ここにエリーの姿はない。周囲を見回しても、彼女に声をかける大人はいない。怖いごろつきもいたが、予想と違って、絹やレースの豪華なドレスを着た、アーデルハイトにちょっかいをかけてくることもなかった。
時間がたつごとに、景色も変わり、人も少なくなっていく。
「うっ、ううっ・・・・お母様・・エリー」
ぬいぐるみを抱きかかえながら、痛む足を押さえて、アーデルハイトは街中を歩く。
7
カラカラ・・・ン。
時計店の横で、アーデルハイトはうずくまり、泣きじゃくっていた。泣きつかれて、目が赤くなる。
「こらっ、くそガキ」
「ぼうっとしているじーさんが悪いんだろ」
「急ぐぞ、エリク!!」
時計店の店主、と少年達が追いかけっこしていた。
「・・・・」
おなかがすいてきて、広場に向って、噴水前まで歩いた。教会の十字架が見えた。
「お父様・・・・」
享楽的な父だが、教会には通っている。ふらついた足で、アーデルハイトは教会に向かった。
教会の前には、ある一座の馬車が止まっていた。アーデルハ意図は一時になったが、教会の中に入った。
教会の中には、イスと神様の像やピアノがあった。教会の前まで行くと、一番前の席に赤毛がいた。
いや、赤毛が混じったダークブラウンのそばかすの少年が。
「・・・・同い年?」
少年の周りには、古代史から、機械学、呪詛に英語やフランス語、ラテン語、男女にまつわる本や冒険談の本が並べられてあった。少年は性格には、籍ではなく柩の上で本に囲まれながら、寝ていた。
彼女の話す言葉はナイフのようだった。トランプの一番隊長であり、彼女の騎士の称号を持つジークベルトは、初めて、アンネミーケと遭遇した時、冷水のような言葉をかけられた。
「お前は毛虫か?蝶か?」
白銀に輝く剣を構えて、ウェーブヘアの騎士服の美女はジーくべるとの何もかも見ていた。白い頬には、触れてもいないのに痛みがはしった。
「それとも、ロバか?」
「・・・・貴方は」
剣先を向けられる。
「この場に来たということは、お前も私の赤の女王の座を奪いに来たのだろう?黒の異能者よ」
赤の女王、と聞いて膝を折る。
「これは失礼を・・・・、女王陛下。自分は今日貴方と相対する目的で、シスターリーザに召集された騎士です」
「リーザ?そんなものは知らん」
王者が、ジーくべるとを見据える。
「殺されるか、殺すか、貴様にこの場で残った権限はそれだけだ」
「~~っ」
押される、ジーくべるとはそう思った。
「さぁ、騎士ならば、私の剣たるか、己で証明してみよ」
家が騒がしくなっていた。アーディアディトもヴォルフリートも慌てて、エレオノール、彼らの母の元に向かった。
執事がエレオノールの部屋の扉を慌てて開いた。
「早く、開いて!!」
「はい!」
バン、と扉が開かれた。
「貴方達が、アーディアディト、ヴォルフリートね・・・」
強い生命の光を漂わせた美しい金髪の母が、まっすぐコバルトブルーの瞳を捕らえていた。
「お母様・・・」
後ろにいたディートリヒやフィネの声が震えている。
「・・・・お、お母さん?」
足元や肩が震えている、こうやって、面と向かって、彼女と接するのは今日のような青空の日がはじめてだからだ。
白い手がアリスに差し出される。もう片方の手はヴォルフリートにも差し出され、頬に添えられる。
「本当に、貴方たちなのね、アリス、ヴォルフリート・・・」
エレオノールは、2人をやさしく抱え込んだ。
「お母さん!!」
アリスの瞳が涙でぐちゃぐちゃになる。ヴォルフリートも嬉しさのあまり、涙を浮かべて、頬が緩む。
「・・・お母さん」
「会いたかった・・・」
優しい空気が、アリス達を包んでいた。
姉さんは、自分への好意に鈍い。
「・・・いいの、あのダンサー、姉さんのこと、好きみたいだけど」
アリスがきょとんとした表情になる。
「え?」
明らかに気付いていない、そんな表情だ。部隊に入ると、姉の志向は舞台の役のことや舞台中心になってしまう。情熱的なことはいいが、もう少し、自分を見る異性の視線も気にして欲しい。
この前なんか、知り合いのえリクの前で慌てたのか、突然舞台の騎士の衣装に着替え始めたからだ。エリクの目をふさいで、止めに入ったのは勿論、自分だ。
「デルフィーナ嬢」
「・・・まぁ」
ハートマークを飛ばしながら、デルフィーナ、アリスの友人のファンの金持ちの中年が近づいてきた。少々、小太りだ。
「ごめんなさい、アリス、私、挨拶に言ってくる」
デルフィーナは金持ちのこの男性が苦手だ。アリスは少々、同情する。
「がんばってね」
「ええ」
力なく、デルフィーナが答える。
曇り空ということで、一ヶ月ぶりにきたヴォルフリートはくすくすと笑って、寝そべるアンネローゼに関係を聞かれた。
「ねぇ?貴方にとって、わたしはなあに?」
蝶をスケッチしているとシートの上でアンネローゼが手足をばたつかせていた。
「友達だろ」
「14歳の女の子の家に男の子が来るという意味、わからないわけじゃないんでしょう?」
「・・・ああ、そういう」
困ったなと頭をかいた。
「私は女性?同い年の女の子?」
「あはは」
姉さんの記憶の治療の材料とはいえないな。純粋な友情とも。
「僕がイケメンになったら答えるよ、君にふさわしいような」
「まぁ」
「あれ?確か、フランス語教師の、ルイス先生だろ」
「ええ」
綺麗な絵本をぺらりとめくる。確か、一ヶ月前、わがままを起こしたアンネローゼに首にされた教師の代わりの。
「イケメンだよな、仲がいいんでしょ、付き合わないの?」
付き合ってるんだろうけど、飽きっぽいからな。精神的にも外見も大人の女の子の友達ってきついなぁ。付き合い始めて、感じた印象は女性だった。彼女からしたら僕は世間知らずの子供だろう。そんな子が何故、病弱で友達が作れない環境とはいえ、僕に付き合ってくれるんだろうか。
「・・・絶対、好きだろう、あの視線」
「そんな男、いくらでもいるわ」
「嫌な人だな、君は」
ア、着た。
「・・・アンネローゼ、何故俺を無視する」
修羅場か、と慌てて立ち去ろうとすると襟元をつかまれた。
「何のことですか?」
「約束が、・・・・・彼は誰だ?」
やばい、ライバル候補か?
「友達よ」
そうでしょうといわれた。
「本当か、君」
何、この面倒くさい状況は。黒髪で長身で大学出てて、海外留学してて、軍歴があるイケメンが14歳の女の子と。
「ああ」
「そうか」
納得が早いな。
「ヴォルフリート、10分位したら、部屋に戻るから先に言ってくれる。お弁当やシートを片付けて」
「わかったよ」
片付けて、去っていく時振り向くと、悪戯を思いついたような子供の顔をしていた。
女の子ってよくわからないなぁ。
頭をかきながら、歩いていった。
家の中で、アリスのドレッサーからドレスを取り出す。
「・・・」
「・・・・」
アロイス・ツァー・バルツァー。カイザー・クラウド。エレオノール、レオンハルト。ディートリヒ、フィネ。
「・・・・恋?」
味わったことなどない。いずれ姉さんは、結婚する。嫉妬に似た感情に支配されそうになるが、止めた。
当然じゃないか、何をアロイス相手じゃなく、姉さん相手に嫉妬している?
「・・・僕は間違いの子で、姉さんは」
そんな資格、知らない。必要ない。
「・・・助けてくれ」
ドレスを抱きしめた。
「助けてくれよ、姉さん」
僕があの女を滅多打ちにする前に。ぎゅう、と抱きしめた。
塔の中で情報交換と聞いて、ヴォルフリートは雨上がりの中、窓辺を見ながら待っていた。予定では、女王としての儀式がアルトブレーズ侯爵から聞いているけど、1日、ずれたのだろうか。
今日のことが脳裏に浮かぶ。
シャノンがエドガーに見せた表情。姉さんとアロイス。
・・・綺麗だけど、僕はまだいいかな。あそこまでなんか、人が変わったようになるとなると、なぁ。恋愛するのは人それぞれだ。僕はまだ当分いいや。可愛い女の子と遊んで、話すだけで。
扉が開いたことに気付かず、雨を見ていた。
カシャァァァ・・ン。
彼女の部屋の中の扉が開き、鉄の柵が姿を現す。
鍵が落ちた。暗くした室内のせいで、中の様子が見えない。柵の前まで足を運ぶと、ザァァァァと異常なほど伸びた髪が見える。外では雷が鳴り響く。なぜか、急に不安に似た感情が胸をよぎった。
・・・・ただ、ただ怖ろしい。
アンネローゼを前にすると、遊び友達と美しい女の子を一時的にとはいえ、独り占めできる喜び、それより何より、彼女が怖ろしくて怖くてたまらない。彼女が異能者で、猫に変身し、アンネミーケという姿を持つからか。
自分も能力が複数があるため、人格が分裂している。アンネローゼを怖がる権利なんかない。
ケラケラケラ。
クスクス。
「・・・・・・ローゼ、いるのか」
笑い声が止まった。
ガシャン。
「!」
びくり、と肩が震える。
ずる・・・ずる・・・。
暗闇から白い肩を丸出しにした、異能者の女王がいる。恐怖でヴォルフリートは動くことが出来ない。
ずる・・・っ。
整えられた手が、白い指が、柵を掴む。その手は、あの異形の魔女の手に似ていた。聖母というナの別の生き物に。
「・・・・アンネローゼ」
呼吸が乱れている。アンネローゼは苦しそうにしていた。
・・・・今ならば、血を掠め取ることができる。
―人殺し、お前なんか人間じゃない。
先日のえリクの言葉が鋭くヴォルフリートの胸に突き刺さる。胸が潰れるように痛い。その言葉は重い。エリクの恋人を僕は、僕は。
友達を裏切った。
―友達と思ったことなんかないくせに。
否定できなかった。冷たいといわれた。目撃者は殺せ、そう教育された。何度も何度もあがなった。迷う必要はあった、ためらいがあるはずだ。
ただ、頭は結果のみを示す。
決めてしまった瞬間、感情がシャットダウンされる。裏切り者を許すな、目撃者は殺せ。
「・・・アンネローゼ」
手は自然に銀が入った異能者の身体機能を奪う銃弾を銃にこめる。
―殺せ。
機械のような目で、目の前の標的を見る。殺せ、破壊しろ。血を奪え、支配しろ。彼女の頭に銃を向ける。
いやだ、いやだ、いやだ。殺せ、殺せ、殺せ。
打たれた鞭。狂ったような目の父親。記憶をなくして、姉さんから本物の笑顔が消えた。何も変わっていないようにも見えた。でも、あの症状と出会うとき、思い知らされる。慟哭、慟哭、慟哭。
魔物の家。目の前の吸血鬼を殺せ。人類の敵だ。
・・・・だめだ。
「・・・殺さない、殺さないぞ」
歯を深く噛む。身体を強張らせる。銃を持つ手からゆっくり力を抜いていく。汗が額から下へと落ちていく。
彼女の手がヴォルフリートのブーツを掴んだ。目を開けると、血にまみれた吸血鬼、いや、アンネローゼが白いドレスを乱して、こちらを見ていた。ルイスの血まみれたからだが横たわっていた。
金色の目が自分を見ていた。
「・・・?」
濡れたような、揺れた高貴な瞳。整った顔立ち。艶やかな髪。酷く大人びた表情。違和感を感じた。何度か、見た、恋人たちに向けるアンネローゼの表情に似ていた。だが、何だ、この人間のか弱い少女のような表情は。
何故、いつも傲慢でわがままで女王様っぽくて、理解しがたい女性が、常に上にいる王者たる人が、死神が、したのレベルの処分対象の監視月の異能者にまとうような目を向けるんだ?
「・・・」
誘惑して、からかう気だろうか。彼女ならそれくらいのことはする。
からかって、遊ぶ対象で、僕は相手にされないだろう。自身がないとか、行動することで傷つくことが怖いのではない。彼女は女王で、上に立つべき存在だからだ。
「・・・ヒスイ」
何を人間のふりをしているのだろう。でも、困っている女の子をこのまま放っておくのも変か。柵に一歩近づく。医者でも呼ぼうと思いながら。
雨が降っていた。
「・・・・柵の近くに」
彼女が柵の近くに立つ。
「え?ああ」
柵の、彼女の前に立つ。
「・・・・ヒスイ、私が好き?」
表情が顔を伏せているせいでみえない。
「アーディアディトは貴方の何?」
「大切な姉だよ」
「本当に?」
「ああ」
柵に手を書ける。
「具合が悪いなら、アードルフ先生に・・・アンネローゼ?」
胸元をぐっ、とつかまれた。
「喉の調子が悪いから、見てくれる」
「そう、喉を見せて」
© Rakuten Group, Inc.