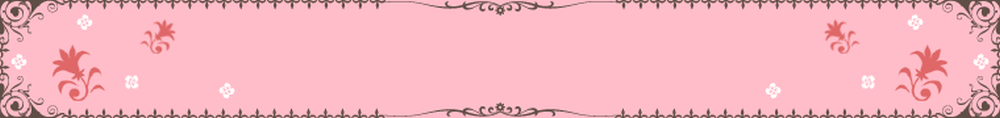第8章空の数え歌
赤い髪の少女は、エリザベートに言う。
汽車は目的地に向かう。天気は青空から曇りに向かおうとしていた。
「いいえ、皇妃殿下・・・」
おい茂る木々は何もかも包み込もうとしていた。
「世界は優しくはなりませんわ」
エリザベートは不思議そうに首を傾けた。
ガタン、ガタンと。
街中はどこか沈黙を無理に漂っている気がした。
石畳の街は、異国の地を持つヴリルをやはり拒んでいるようにも見えた。
「いいのか、公演をキャンセルして」
「先生が休むように言ったから」
アリスはほほ笑んでいるように見える。本当はいかにもお嬢様格好で出かけるのは嫌いなのだ。この少女はいつも、心配させないようにと頑張りすぎる。
家族、友人に近い立場だ。だが、それでも踏み越えてはいけないこともある。アリスは変化に敏感だ。それが彼女の欠点であり最大の武器でもあるのだが。
主を、友達を思うならば言うべきだ。兄弟の間に生まれつつある溝という問題に関して。
正直、ヴリルは気に入らない。
いつもいつもアーディアディトと一緒にいるのを邪魔をする。
「僕は・・・」
アルバートは空を眺める。
世界は安らぎと静寂が広がっているように宮廷司祭は見えていた。
伝統と誇り。
けれど、清浄な世界は作れない。一皮むけばそこは男子の社交場となり、今の体制に食いかからんとする革命家、スパイ、他国民、さまざまな立場の者がいきう場所となる。か真っ先に犠牲になるのは、当然、労働階級、成り上がり者だ。飢えたものを養う力がこの国にあるのか。
「何真剣な顔してるの」
「ああ、ミゼル司祭長の用事は終わったのか」
むねもとの大きく開いたドレス。化粧はしてるが実はまだ17歳。
「まあねやっと寝たわ」
「…すまないな、君にスパイのまねごとをさせて」
ガチャ。
「お帰り、姉さん」
「ただいま」
エレクの目には、なぜだか能天気な笑みがないているように見えた。
「まあ、別に嫌ではないけど」
「ダリルって、アーディアディトが好きなのか?」
「はあ」
「馬鹿か、あれは生意気で生意気だが、喧嘩友達みたいなもので」
「ん・・・」
その光景をルドルフは忘れたことがない。
「アンネローゼ、恥ずかしいんだけど」
「怪我を治すのはこれが一番よ」
「君という奴は」
「・・・」
「・・・・」
アリスもダリルもしゃべらない。何を新た待って緊張しているのか。
何度、同じことを繰り返すのだろう。
「お前の言っていることは綺麗事だ」
ヴォルフリートは目を見開く。
「おとぎ話だ、力による正義が国民を暴力やテロから守るんだ」
指先が震えそうになるのを必死で抑えた。
「そのために私は多くの血を流す、誰に怨まれようともこの国と国民を守るためならば」
それは正義の言葉なのに。
「しかし、中には女性や子供が・・・」
「恨むならそのような愚かな手段を選んだ男たちについたことを恨むしかない」
冷たい見降ろされた視線。
「殿下・・・!!」
「英雄になりたいだけなら、ひっこんでいろ」
「お前のその優しさはお前の足元を救うことになるぞ」
にらみ合うように、向かい合う主従。思い知らされる階級と隔たり。
彼は王者だった。
「僕は情を忘れたくない・・・!!」
「やはり、甘い」
皇太子は見下ろすようにほほ笑む。
ほほ笑みの下で、ヴォルフリートは暴力を手段とする過激な民衆を押さえたと、倒すのみという隣のカリスマ性のある将来の皇帝の言葉を素直に聞くことができなかった。冷たい、王者たるほほ笑み、救われた民、だが一方で悪とされたレジスタンスたち。
「攻撃を再開しろ、この地の国民を守るために」
誰よりも命の大事さをこの方は分かっている。だからみんな、ついていく。だが、足元には―。
「了解しました」
さまざまな情報やデータが集まっているのはいいが、肝心の姉さんの吸血衝動を抑えるための対策に使えそうな資料がないじゃないか。
「ちぇ」
アリアを歌ってくれた母親も厳しくむかつく事ばかりの父親も、双子の妹でさえも夜木屑のように転がっている。人が燃える匂い、アナだらけのしたい。
母親は、異能者の子供を傷つけようとした。
役に立たない、病弱な自分のせいで、おかしくなった。
ザァァァァァァ・・・・・。
―まだ、やられるわけには行かない。
銃で撃たれたエレクは嵐の中、裏街道の小さな道の中で、異能者狩りの男と争って、最後の最後の瞬間、襲い掛かる男を炎の矢で倒した。血が辺り一面に散らばる。エレクの華奢な体にも降りかかる。
「・・・・・」
紺色の髪をぐしゃぐしゃにして、立ち上がろうとした時、足音が聞こえた。警戒心があふれて、慌てて、男の銃を奪い、足音のほうを振り向く。
ダークブラウンの髪と日に焼けかかった白い肌のオッドアイの貴族の、12歳の少年が少し驚いたように見ている。
殺されるわけに行かない。
エレクはぐっと目をきつくして、銃口を握り締める。
2
「
華やかな光景だな、と庭先でギ―ぜラやルドルフという王族を見ながら、そう思った。ジ―クムントや姉さんも入れると、一枚の絵のようにも見える。
劇の一部にも見える、華麗なセカイ。
声をかけるのをためらう、世界だよな。
「どうした、ヴォルフリート」
優雅な美しい笑み。
隣をみると、女官や姉さん、はたまた衛兵もその彫刻のような顔立ちに見とれている。ジ―クムントが熱心に見ているのは忠誠心だろう、きっとそうだ。
「お茶にしましょう」
優雅な笑み、品のいい顔立ち、人形がしゃべっているようだ。
「ヴォルフリート、恥ずかしがってないでこっちで一緒にお茶しましょう」
「うん!」
ぱぁぁと明るくなる。
天国のように美しい光景だ。
ルドルフが袖を引っ張る。
「お前の席はこっちだ」
いつも通り不機嫌な表情だ。
「お前、ヴォルフリートか」
「お久しぶりです~」
宮殿に久しぶりに来て、従者と歩いていると、驚いたようにジ―クムントが見ていた。
「元気そうで、よかった、ウィーンは」
「本当にヴォルフリートなのか?」
首を傾ける。
「そうですけど、何か」
整った顔立ちに変化したヴォルフリートに驚いた。
「偽物だっ」
15歳になって、急に女性の視線をよく浴びるようになった。
「何だろう?」
「あ、あの」
目の前には可愛らしい女性。隣にいたジ―クムントがむっとなった。
「これ読んでください!」
アーディアディトとルドルフが三時半の頃に、供のものを連れて、ヴォルフリートの部屋を訪れた。机やイス、貴族のものにしては簡素なつくりといっていい、天蓋つきのベッドなど、見渡す限り、必要なもの以外のものが少ない。
・・・生活感のない部屋だ。
「・・・・ヴォルフリート」
「今、起きたばかりで・・・・」
あまりにも衝撃すぎて、自分達に本当に怒ったことなのか。受け止めることが出来るのか。何を言えばいいのか、アリスは言葉を詰まらせた。
「お前達、下がっていいぞ」
「はっ」
部屋の中はシン、と静まり返り、ルドルフとアリス、ヴォルフリートだけになる。
「ルドルフ様・・・」
しかし、ヴォルフリートは振り返らない。アリスとルドルフはお互いの顔を見合わせた後、ルドルフが声をかけた。
「ヴォルフリート、元気そうだな、体の調子はどうだ」
いつもの張り詰めたような、大人びた声ではなく、珍しく感情的な声にアリスは意外な思いをした。
「・・・・・普通です」
「え・・・」
気のせいだったのだろうか。今、突き放されたような感覚がしたのは。
アリスは顔を上げ、ヴォルフリートを見る。
「お前は、あの男に・・・・、あいつらに傷だらけで、その・・・・・」
深刻な表情だ、ルドルフ様も傷ついているのだろう。責任感が強く、人間らしい人だから。アリスはどこか冷静な頭でそう思った。
「暴力を振るわれて・・・・」
酷く動揺している。勿論、数人の人間に長時間殴られ、脅迫された所という。ヴォルフリートの記憶があいまいなのは、恐怖によるものだと医者は言っていた。アリスは、ルドルヴォルフリートの肩をつかんだ。
「ヴォルフリート・・・っ」
「―今回の事は僕の勝手な判断で、責任は僕にあるんですよ、ルドルフ様、貴方はあそこにいる人たちを助けた、そうでしょう?」
「ヴォルフリート、貴方・・・・」
こんな状態にされてまで、貴方は・・・・!!
貴方は他人に気を使うことが出来るの・・・!!
アリスはぎゅっとヴォルフリートを抱きしめた。
「・・・それは善意でしたわけではない」
あんな恐ろしい光景が脳裏から離れる事はない。信者たちの魂が抜けた表情や儀式よりも恐ろしかったのは、こいつの体を見たときだ。殴られた痕やうたれた痕、それに・・・・、この先は言葉に出すのははばかれる。
―ルドルフ、こいつはアウグスティーンにQQを振るわれた疑いがある。
言ってはいけない、こいつが忘れてるなら。
正気の人間がすることではない、これは神を否定する犯罪だ。殺人に等しい。
「ルドルフ様?」
村での事も、今回の事もヴォルフリートは被害者で、罪はない。
「犯人たちは全員捕まえる、お前はしばらく休め」
ルドルフが安心させるようにヴォルフリートの肩をつかむ。
正直に言えば、皇太子殿下としては期待しているし、努力もしているし、年上を年上と思わない不遜な態度もプラスになるのだから悔しい。ジゼル様をとても大切に思われるのも高得点だ。
「ディートリヒは君を嫌っているが、君はどうなんだ」
何故、この人と歩いているのだろう。
「仲良くなりたいと思っています」
「根っからの特権主義だからな、貴族としての誇りが邪魔してるんだろう」
悔しいくらいに、格好いいが、異性ではなく、人間としての格好良さだ。けれど、気を許してはいけない。
「捨ててしまえばいいと思います、私は正面からぶつかりたいです」
炎のような、意志の強さをアリスは青い瞳に漂わせている。
「・・・そうか」
ルドルフはふっ、と微笑んだ。
「ところで、薄栗色の髪のウェーブヘアのマリアに出会いたいのだが、紹介する気はないか?可愛いのだろう」
「・・・フィネの事ですか」
「たまには、計算なしで女性と関わりたいからな」
季節は四月半ばになっていた。
「だめです」
「何故?」
「・・・貴方が個人的に興味を持つだけならいいですが、あなたは殿下です、私はあの子を大人の世界に巻き込みたくない」
ルドルフの優しさにアリスは胸をなでおろした。
・・・・友情は本物なんだわ。
彼は恐ろしい人ばかりではない。ちゃんと情愛もある、優しい一面を持つのだと。温かい潮騒がアリスの中を駆け巡る。
「・・・ヴォルフリート」
シーツを握り締め、視線を下に向けている。ルドルフも状態が落ち着いたことに安心感を感じた。
「・・・・ありがとうございます」
そういった瞬間、アリスの前で弾き飛ぶような音が鳴り響く。
・・・・え?
アリスの背中にざわついた感じがはしる。
「・・・・ヴォルフリート?」
ルドルフはぎくりとなった。…なんだ??
ヴォルフリートはいつものようにルドルフと最愛の姉を見ていた。だが、問題なのは彼らを見る彼の目だった。
まるで、仮面を変えたようにがらり、と違う。
酷く攻撃的で冷ややかな、鋭い眼光。熱などあること自体が疎ましいとでもいいたげな鷹の鋭い目。全ての情愛を拒む、覇者の目。
「―だが、アウグスティーン・シュトルツマーケ・・・・・・あいつは、俺が嬲り殺す。例え殿下であろうと、邪魔は許さない・・・・!」
いつもの伸びやかな声ではない。冷え切った、鋭い声。アリスは完全に身体を強張らせた。逆らえば、目の前の少年はおそらく・・・。
そう考えた瞬間、罪悪感に似た感情があり酢の胸の中を駆け巡る。
「・・・・・奴は、俺の獲物です」
別人を前にしたようだ。ルドルフは直感でそう感じた。
2
大広間で、ディートリヒとレオンハルトはぶつかり合っていた。そう、白の女王―秘密裏に皇太子や国の要人を不埒な人間からもらう役目からディートリヒを下すと言ったのだ。ディートリヒに過去が脳裏に浮かぶ。
―たて、ディートリヒ。
自分は息子を生むはずだった母の望みをかなえるために行かされている。この時代、女が要職につく事も、ましてそのような影の役回りさえなければ適度な年齢でただ家のために通常通り、女の名前でレディーらしく育てられ、家にふさわしい聖と結婚されるはずだった。
「もういいです、リリー!」
「待て、どこに行く」
「避暑地に住む遠縁の祖母のところです!!」
強く言い放つとまだ叫ぶ父を残し、重い扉を閉めた。
剣を振り下ろすレオンハルト。
―男になれ。
小さい娘にディートリヒは容赦がなかった。
なぜいまさら女に戻れなど。
ディートリヒは頭がパンクしそうだった。
ガタン。
何だ、と控え室の扉を開くと、窓にアロイスがずぶぬれで座っていた。
「着ていたなら、挨拶位しろ」
女性名で舞台に立つエレクはいつものように化粧をして、流れ者の歌手エメロードとして狭い劇場で歌ってきたところだ。
「・・・・・」
体の半分を仮面で隠した、いつも黒衣の少年。火傷さえなければ、かなりの美貌の少年でもある。
「・・・・」
「・・・・・何か、あったのか?」
だが、アロイスはなにも答えない。
仮面の騎士、といわれ民衆に人気があることはあり巣も知っていた。直接、礼を言われ、助けたことにより、アリスの世界は広がった。アウグスティーン・・・・、メルクの司祭が憎い。神の像の前でアリスは祈りをささげる。
弟に一晩中、暴行するなんて。
私のヴォルフリートに・・・・今、その晩のことを創造しただけで怒りと恐怖、絶望がアリスを襲う。
―お母様、ヴォルフリートが。
「全て、神と皇帝陛下、警察に任せない。貴方は貴方ができることをすればいいのよ」
「私が犯人達をなぶり殺しに、だって許せない・・・・!!」
誇りを。
人格を。
正義感に強い、弟思いのアリスには許しがたいことだ。
「私はアウグスティーンを許さない・・・・!!」
憎悪の炎がアリスの瞳に浮かぶ。
ドォォ・・・・ン!!
「大丈夫ですか、ルドルフ様!!」
「殿下!!」
「ルドルフ・・・・!!」
馬車が激しく横転し、アンティーク店につっこんだ。ルドルフと共にいた軍人やヨハン、ヴォルフリートが駆けつけてくる。ルドルフは地面に転がった。
「・・・・・ああ」
ヨハンが駆けつけると、ルドルフは命令をする。
「何をしてる、犯人はまだ近くにいるぞ、追え」
「しかし・・・・」
「行け」
鋭い眼差しがヨハンを突き刺す。
「行くぞ!!」
部下とヴォルフリートがついていった。
足元には、額をうちぬかれた犯人とヴォルフリートの姿があった。打ち合いになったのか、肩から血が流、頬にもかすったようなあとがある。
「・・・お前が殺したのか」
「生きています、今は動けないと思いますけど」
軍人である事は十分なほどわかっている、人は変化する、生きているものは変化する存在だとわかっている。
「そうか」
「・・・どうも、他に動かしている人間がいるようでした、自分が不勉強なのもありますが、どうも北欧の言葉で最後喋っていて・・・・」
手袋で、胸ポケットからビニール状のものを取り出す。
「銃弾・・・」
「ええ、犯人が持っていた銃に使っていたものです、警察に渡しますか」
シュテファン寺院の中で、ルドルフはピルグラムの説教台付近で、ヨハンと話をしていた。
「狩りに出かけるだと」
「父上からの誘いだ、断る理由もないだろ、それに僕はこそこそ隠れるのは性に会わない、どうせなら堂々と前に出る」
青い瞳をルドルフはヨハンに堂々と向ける。
「狙ってくれといっているようなものじゃないか」
「狙うなら、この絵兵のまでも、大広間でも狙える、女官や宮殿に出入りできる人間を間者に使えるし・・・」
「ルドルフ!!」
その時、郵便係の人間がルドルフ達の下に駆け寄ってきた。
「皇太子殿下、陛下から速達の手紙です」
「皇帝陛下から?」
珍しい、と首を傾けた。
「見せてみろ」
「陛下の字だな・・・」
ヨハンはどこか自信なさげだ。ルドルフはしばらく考えた後、何かひらめいたような表情をして、手紙を破り捨てた。
「ルドルフ様!」
使いのものが悲鳴を上げた。
「父上は純粋なドイツ語しか使わん、チロルの方言はな、間者にしては手ぬるい」
「・・・・っ」
使いの人間は慌てて逃げる。ルドルフが追いかけて、身柄を押さえた。
「答えろ、誰の命令で皇帝の名をかたった」
自分の部屋の扉を開けると、本来ならヴォルフリートの存在しなければ腹違いのエルネストか、この自分が儚げで誰にも優しい慈愛の少女やオーストリアを守り、男として生きていくはずだった。野蛮で残酷な主義者や革命家。無慈悲な暴力。
貴族や王族は国民を国を守る義務を持つ。子息らしい簡素なシンプルな部屋。紺色の布で包まれた天蓋付きのベッド。先祖が王家からもらったという甲冑。大昔に活躍した先祖の肖像。暖炉に鹿の置物。
―貴方は厳しすぎるわ、ナタ―リエ。
アーデルハイトの後ろには、国に新しい主義を持ち込もうとする耶から~国民を守る同じ思いを抱いた銀の十字架の少女や少年たちがある。
泣きじゃくるシスターズサンナやりリ―い―ル。
―いいわよね、家業のきれいな部分だけの仕事をして、正義の味方気取りで。
異能者の双子の妹と殺し合い、元異能者の傷だらけのダ―リヤ。
この家の名で、弱者を国民を暴力から守る。
その一点だけは、戦闘用特殊部隊の少年、アルヴィンと同調している。
「・・・」
急にもようしたくなってきた。柱時計をみると、まだ他の家族は帰ってこない。父もさっきのケンカで来ないだろう。
・・・・さて、どうするか。
3
「だって、ずっとあなたに会いたくて」
熱いまなざし。困っているときに求めたのはアロイスだった。銀髪の年上のクールな少年。アーデルハイトの護衛役の。
「だから、ここまで来たのに」
柱越しにヴィルフリートの人格になりながら、ヴォルフリートは聞いていた。
苛められていた、追い詰められていた。今、初めて知った。
でも、どうして?
一番、そばに俺がいたのに。
何で。
「アーディアディト・・・」
「貴方さえいればいいの」
どうして。
家族じゃ、弟じゃ、力になれないのか。アーディアディト姉さんの一番は俺だと、相談する時も、何をするにも一緒だったのに。
たった最近会ったばかりのあんな・・・、あんな男と。
俺にはあなたしかいないのに。貴方は違うのか?
・・・俺ではだめなんだろうか。
「珍しいな、君が落ち込んでいるなんて」
顔をあげると、ルドルフ皇太子の姿があった。
・・・・ヴォルフリート?
鋭い眼光と意地悪そうな理知的な表情。雰囲気ががらりと違う。
「君が僕と姉上の問題に介入する権利はない」
「中途半端は嫌いだ」
「俺たちは友達じゃないのか?」
「友達だからって僕のすべてに介入する権利はない」
「君が言ったことだろう、皇太子殿下」
皇妃エリザベートに連れられ、乗馬につれられた時、ヴォルフリートは他の従者に値踏みされるように見た。まるで鷹に見つめられた小動物にでもなったような気分だ。どこからか、ウィーン少年合唱団のボーイソプラノのような音楽が聞こえてくる。林の中には、木の枝が転がっていた。
「見なさい、ヴォルフリート」
「はい」
「青い小鳥が雛を暖めているわ、ひばりの仲間かしら」
ヨーロッパ一の美貌を前にヴォルフリートは緊張してしまっている。一国の皇妃が何故、自分のような庶民と遊びの時間を共有しているのか。女神のように綺麗で優しく、誇らしい。王宮にいつかない変わり者の皇妃。皇帝に愛され、珍しい恋愛結婚をして、ルドルフ様の母親である人。
「どうしたの、わたくしが相手では退屈かしら」
八頭身の美人は腰が以上に細く、つややかな黒髪で、何かと扇で口を隠している。
「いいえ、滅相もない」
エリザベートはくすくすと笑う。
「冗談よ、小さな坊や。ヴォルフリート、貴方は本当に綺麗ね」
「は・・・」
ヴォルフリートはきょとんとした表情を浮かべた。
「太陽の光に照らされて、キラキラして、綺麗な太陽の髪、大地の髪だわ、瞳も深い翡翠の瞳に冷たい湖の高貴さを持っているなんて、贅沢ね」
「・・・そんな事、初めて言われました」
「私たちは、いいお友達になれそうね、ヴォルフリート」
「リリー」
用を済ませたディートリヒが恨めしそうな声をあげる。
「またお得意のドジか」
じろりと睨む。
「まあ、おほほほ」
ごまかすようにメイドのリリーが目をそらして笑う。
「見ろよ、皇族の犬だぜ」
「ああ、道理で土臭いと思った」
クスクスと下品な笑いが、ヴォルフリートの横を通り過ぎていく。
「どうも・・・」
一応の挨拶をして、去ろうとすると、肩を捕まれた。
「待てよ、侯爵殿、貴族様は人の話が聞けないのか」
「何の御用でしょうか?」
お父様が、姉さんを閉じ込めて1日たった、何とか話し合わないと。
「ふうん、とても、噂に名高いヨハネスの血筋だと思えないな、変な髪の色をして」
くすくすと兵士たちは笑う。
「悪魔でも取りつかれているんじゃないか?何だ、その瞳の色は」
じろじろと品定めをするように見られて、ヴォルフリートは戸惑う。
「お前、多くの人間を自殺に追い込んだ侯爵の孫なんだろ、どうやって、皇族方を誘惑したんだ?」
「ルドルフ皇太子殿下にも、ローゼンバルツぁー家お得意の作法で取り入ったのか?心中なんて、恥さらしな事をする女の息子だモンナ」
ヴォルフリートはにこりと微笑んだ。兵士たちは動揺する。
「知っていますか?アジアにはサムライという、部類の人間がいることを」
「は?」
「サムライは主や家族に恥をさらすものに自らの首を刀で差し出すそうですよ。ちょうど、料理人が大根で皮をはいでいくように・・・ここに刀はありませんが、自分がご披露しましょうか?」
どこからか、ナイフを取り出し、両手で持つ。悪戯を思いついたような、たくらむような表情。
「な・・・・っ」
兵士の一人にピタリと近づく。
「ああ、ローゼンバルツァー、我が家のナイフ仕込だから、手元が少々乱暴になるかもしれませんが、少々の我慢を」
「き、きさま・・・」
「なな・・・お前、キャラが・・・」
廊下の角で曲がった所で、ヨハンがその現場に遭遇する。
「母は、誇り高い人です。過去がどうであろうと、僕はあの人の息子です。興味があるなら、今度、我が家に来ますか?」
それが決めてだった。兵士たちは一目散に逃げていった。
「・・・・」
ヴォルフリートがヨハンのほうに振り向く。慌てて、表情を引き締める。
「すみません、定位置に戻ります」
「・・・お前」
ガチャリ。
扉を開けると、ズボンをずりおろし、布地が少ない下着をあげているディートリヒの姿があった。時が止まった。
だが沈黙は数分のことで――
ディートリヒのまぶしい細くもあり、白く肉感のある太ももや女性らしいラインのヒップがエルネストの前に現れる。
思わず何度も凝視しそうになる。
「おお・・・お前、女・・・・」
その時、遠くの方からフィネの声が聞こえる。
「エルネストのお兄様、どこですか?」
車いすの音が近づいてくる。
「貴様、出ていけ」
「あ、馬鹿、暴れるな!!」
エルネストはあわててディートリヒの口元を押さえる。
「~~」
じたばたと暴れて、エルネストの腹や足をけってくる。
「だから、落ち着け、暴れるなって」
可愛らしい声が近づいてくる。
「動くな」
「!!」
壁にあわててディートリヒは押さえつけられて―。
4
ア氏を押さえつけられて、恐怖がディートリヒを襲う。
「この馬鹿!」
頭をガンとする。
「痛いな、何をするんだ」
「さっさと離せ!」
にゃあ~
「え」
足もとに猫が。
「あ」
2人ともぐらりとなって。
「ええ」
そのまま崩れ落ちて―ア氏の間にエルネストの顔がうずくまるという格好に。
ふに。
「え・・・やわらかい・・・」
「・・・・・・ひっ」
悲鳴が鳴り響いた。
「いやあああああああああああああ」
「お前が見に来てると思わなかった」
「姉の舞台を見に来るのがおかしい?」
アレクシスの横にヴォルフリートとナンパしたのだろう少女とアルベルトの姿があった。
「いや、シスコンのお前らしいわ。でも、いいのか?」
「何が?」
アレクシスが肘を肘置きに預けた。
「噂のアイツ、お前の姉貴に近づいてるぜ」
ヴォルフリートの胸がざわついた。
「僕もいつまでも姉さんべったりじゃないんだ。子ども扱いしないでくれる」
「まあまあ、アレクシスも君が構ってくれないからすねてるんだよ」
貴公子アルベルトがそういった。
「それに彼女は美しい・・・」
夢見心地でアルベルトが言った。
「さすが魔性の女・・・・」
アレクシスは青ざめた表情で言った。ヴォルフリートはきょとんとした表情になった。
アロイスとアリスが劇場のバルコニーで甘く、熱く見詰め合っているのをアリスに会いに行ったヴォルフリートが見つけた。
眩しい、光の光景だった。漆黒の闇の中でヴォルフリートはその光景を見ていた。
「泥棒だ~」
舞踏会の中、誰かが叫んだ。厳重警護の、それも宮殿内で外の人間が入れるわけがない。ルドルフは頭ではわかっていたが、ヴォルフリートを置き去りにし、レオンハルトに預けた後、暗闇に逃げていく男を追った。
草叢を抜け、逃げる男を追いかけ、森の中に入った。
・・・逃げ足が速い。
くっ、とルドルフは顔を歪ませた。
「どうなされました・・・・」
ひばりのような美しい女性の声が後ろから聞こえた。振り返ると、付けぼくろをつけ、紫のドレスを着た貴婦人が漆黒の扇を持っていた。思わず、どきりとするほどつややかで秘密めいた美しさを持つ、女性だ。
「・・・・貴方は・・・・」
「貴方の慌てていらしたから、あの下手人をどうなさるのかと追いかけてきましたの」
「覗き見ですか、・・・レディーにしては悪趣味ですね」
ふ、と女性は笑う。
「予想通り、すばらしい方・・・。でも」
「?」
女性は指先でルドルフの胸を軽く突く。
「心に穴が開いているようですね、それもぽっかりと」
ルドルフは慌てて、女性から離れる。
「・・・・何者だ、お前は」
「わたくしなら、殿下を慰める方法を教える事ができますわ」
それは女神の微笑だった。
レオンハルト、アリスの父親がアリスを部屋に閉じ込めた。
「レオンハルト、なんてことを」
「アーディアディト、お前に考える機会をやろう、その間、自分の選択がどういうことか良く考えるように、一人になれば、十分考えられるだろう」
「やめてください、貴方・・・」
エレオノールが慌ててとめる。
「これは、この家と君を守るためだ」
「開けて、お願い、開けてっ」
アリスは扉をどんどん、と叩いた。
―僕は大丈夫だ。だから、決めたのなら、行動して、姉さん。
勿論、被害者のヴォルフリートを方っておけるわけがない。精神状態も安定していない。けれど、部隊や歌に対する情熱の炎がアリスを支配しようとする。
歌わなければ、アリスは生きている実感もない。
唄っている時、ああ、私は生きているのだとそう思う。
父が過保護に近い状態で大きな愛で自分を愛してくれるのも、母がどんなにか自分を求めて、妹は愛してくれて、弟もやっと信頼してくれている。
家族が一体となって、本物になりつつある。
・・・・・でも。
「私は・・・・」
「ひゃあああ」
雷が鳴り響き、金髪の少女はカーテンにしがみついて、泣きじゃくっていた。青い目がエレクの目に飛び込んできた。少しも似ている所はないというのに、あーディアディトと劇場の控え室の中でであった時、ヴォルフリートの青い瞳を思い出した。流れるような金色の髪はキラキラと輝き、なんて綺麗だろうと思ったが、素直に口に出せば、負けたような気がして、エレ苦はむっとした表情になった。アリスの劇場の仲間が飛び込んできた。
「どうしたの?アリス!」
「かかかか・・・雷が」
声が震えていた。アリスはダンス用の衣装を身に纏っていた。ダンスを踊っているうちに時間がたっているのを忘れたようだ。
「ああ、アリス、雷が苦手だものね」
「ビーネアイト、どうしたの?こんな所で」
「別に」
いつものようにそっけなく答えた。
数週間後、王宮内に、何もかによる火事が置き、ルドルフはその混乱の中、犯人を追いかけ、討つ瞬間をアリスに見られた。
「お前・・・・」
その後ろには、ルドルフに憧れる、現在の聖女といわれる、白いドレスに身を包んだ、淡いプラチナブロンドを結いこんで赤いリボンの、線の細い少女がヴォルフリートに抱きついたまま、寝ていた。
卵型の彫刻のような顔立ちは、アリスに似ているようで、崇高で清らか、純粋で透明な美しさに満ち、長いまつげからは冷たい青の宝石がうっすら見える。
ルドルフがキスした少女、本当の意味での天使、男のようになったエルフリーデとは違う少女。こちらのほうが、あの貴婦人の娘にふさわしい。
ルドルフが、ヴォルフリートの協力で、狩猟の後、お茶に誘った貴族の少女は、皇帝の命令で中年の男爵に嫁ぐ運命にある。
カレンで守ってあげたくなるような、細い肩の華奢な少女。
「お手が寒そうですわ」
白い手袋を落としたとき、可愛らしい帽子をかぶった移民の少女、北欧の血が入った名家の令嬢、ローザリンデ・アルベルティーナ・リュービクラルがルドルフの手袋を拾い上げた。
・・・可憐だ。
ルドルフは正直にそう思った。
「ありがとうございます、君も狩猟の手伝いを?」
皇帝が主催の狩猟では、アルベルトの父の姿もあった。その中には、シャノンに言い含まれた従者の姿もある。
「・・・ええ、父や兄に手伝いを、本当はこんな恐ろしい事をおやめいただきたいのですけど、・・父は出世指向型核、本当に帝国の事を思っていますから」
冷たいアオの宝石のような瞳には、温かさと清廉さが漂っている。
「・・・・あら、すみません、これは失礼な事をしました、大臣ヴィルヘルム・りぇービュジクラルの次女ローザリンデ・アルベルティーナ・リュービクラルです、本日はフランツ皇帝陛下主催の狩猟にお招きありがとうございます」
「・・・いえ」
「お噂には聞いていますわ、この前も閣議で個人の自由の尊重を皇帝陛下や大臣たちの前で言ったとか」
「・・・旧来の法ではまかなえない事もあるといっただけですよ、貴方の父君には怒られましたが」
父親も口に出さなかったが、自分を複雑そうな表情で見ていた。
「権力は独り占めにすれば、これだけ巨大な帝国です、全部の反対勢力や不安を持つ国民を抑えるのは難しいですから」
「資本主義に走りたくないと?」
ローザリンザが厳しい表情を浮かべたようにルドルフには見えた。
「・・・リューゼクラル嬢、お言葉には気をつけるように」
「あははは~、僕っちには聞かないっすよ、情報や~」
馬鹿が絶対防御を数キロメートルまで広げながら、殺したくなるような高笑いを出して、帝国のお偉方を裏ルートから、エレクたちのマフィアの護衛集を翻弄していた。がらりと違う。
別人だった。銃や剣、ナイフ。いかなる通常攻撃も見えないシールドには聞こえなかった。
「さあ、行きますよ、大臣様」
「・・あ、ああ」
守られるがたも戸惑っていた。
「・・・ヤメロ、ローゼンバルツァー!!」
とぼけた表情でナイフをシャトルのように投げながら、オッドアイの少年は仔犬のような表情でエレクを見る。ヴォルフリートのはずなのに、全くの別人がエレクの前にいた。
だれなんだ、こいつは。
「ローゼン?だれですか?俺は二コル・ヴィジットだぞ☆間違えちゃ、だめ☆」
にっこりと笑うと、なおも二コルは護衛たちに襲い掛かってくる。
「バケモノだ!!」
その表情は嬉々として、戦うことを喜んでいた。
5
エドガーがお偉方を迎えに来たとき、事態は既に終わっていた。二コルは洗濯ものを下げる紐につっかかりながら、びよーんびよーんと飛び跳ねるのを楽しんでいた。レスラーに様な男や武術経験のある男達がボコボコにされ、ヴィルフリートが現れたのか、切り刻まれているものもいた。
「先輩、おそ~い。俺にむさい男の相手するなんて、罰点すよ」
「わりい、わりい、色々上官が煩くて、色々手続きで遅れちゃったんだよ。二コル、降りて来い」
「へ~い」
くるくると跳ね回りながら、二コルは地上に着地した。
「もーっ、俺、仕事しない主義なのに、こういう汚れ仕事バッカ」
二コルがぶーっぶーっ言う。
「ヴォルフリート、お前は仕事ばかりしてるだろ」
「先輩、めっすよ。俺は二コルだっての☆プロデューサー、総監督と全く違うイケメンなの☆」
気持ち悪い感覚を味わいながら、エドガーは笑みを浮かべる。
「そうだな」
「これが終わったら、俺と金髪巨乳か、黒髪スレンダーの子、チェキだぜ~」
「楽しそうだ、行こう」
エドガーの目が輝いた。
ルドルフがヴォルフリートを最近、放任しているのは、ヨハンも知っていた。変わりに、たくさんの取り巻きの中から、エルネストという少年をそばに置くようになった。
「ヴォルフリートは、僕がアリスを好きだと知った」
「何?」
無論、これは、ルドルフの嘘である。自分が気が付かないと思うのか。
ルドルフに酷い言葉をぶつけられ、疎まれる事に対して、どう思うのか、ヴォルフリートに聞いた事がある。
ルドルフは、冷静であり、帝国の為ならあらゆる手段も選ばず、行動し、幼い頃から数ヶ国語を操り、将来の資質が見え、しっかりと皇帝になる為の教育がされている。少々、自由主義に被れているとお堅い老人達には心配されているが。あらゆる人を欺き、本当の感情を表に出さない完璧な皇太子。
しかし、ヴォルフリートという友人だけは、ルドルフは進入を簡単に許してしまっている。宮殿に来た頃は、異能者としての能力の為に連れてきたのだろう、ルドルフもどこかしら緊張感をもって接していた。
内向的なようでいて、激しい感情を持つルドルフはプライドも高く、失敗する使用人をムチで殴った事もあり、厳しい態度もとる事があり、結果的に距離をとらざるを得ない。
6
アリスが家を出て、オペラ歌手リリー・アスマンが所属する有名なオペラ座に入ったのは、数日後であり、ヴォルフリートは後で知らされる事になる。しかし、エレオノーるはショックを受け、今、自室で休んでおり、何故、止めなかったのか、と親戚中に問い詰められ、責められた。姉は選んだのだ、自分の道を。
しかし、バレエは芸術品と数えておらず、劇場は上級階級の社交バ的な意味合いがまだ根強く残っていた。オペラ歌手は地位はあるものの、そういう意味では同じである。
ヴォルフリートの手紙には謝罪と歌への情熱があふれており、
「姉さん・・・」
動揺しつつも、姉の夢ならば、と思い込もうとしたが、不安にもなる。彼女の目指す世界は戦場だろうと。
アリスは、ヴォルフリートだけに所載を伝え、家族に謝罪の手紙を送った。
7
思えば、風変わりな姉弟だった。ローゼンバルツぁー家は、表向きは皇帝を政治の面で支える貴族の家柄であり、国の要職には就くのが義務であり、決まりごとであり、オーストリア・ハンガリーに銃帝国の敵を、闇で葬る、帝国のイヌだった。
暗殺以外のことは何でもやっている。迷宮入りの事件も賄賂も、あらゆる犯罪をどんな手段を持っても、解決に導いた。皇帝陛下の憂いを払う事、それがこの家の存在理由であり、それ以外の理由はない。
「行ってくるぞ、エルネスト」
「はい・・・」
漆黒の衣に身を纏い、闇に消えていく。そこには、エルネストの知っている父ではなく、教育された猟犬の姿があった。
そんな時に、アーディアディトとヴォルフリート、姉弟がローゼンバルツぁー家に現れたのだ。
親戚たちは騒然となった、後継者の証である指輪と懐中時計を持ったエレオノールの子供達が現れたのだから。
「本物ですの?」
「・・・はい、奥様」
「信じられん」
「我が家を狙う輩が、嘘を言っているのでは?」
「しかし、シスターチェルシーは信仰心深い、嘘をつけない方ですし、・・・エレオノール様の子供が行方不明になった時期も重なっています」
親戚中で、お互いの顔を見合い、騒然となる。
「―それでは、どちらかが、あの事件のときの子なのだね」
レオンハルトが静かに口を開くと、シーンと沈黙がその場を支配する。
「でも、アーディアディトがエレオノールの子供だとは思えませんよ、見た目は確かによく似ていますが」
ラインハルトが思い口を開いた。ローゼンバルツぁー家の後継者に一番近い男である。
「といいますと?」
「・・・我が父は昔から噂が多く、愛人も作り、問題を起こしている」
「つまり、庶子だと?」
「異能者が、帝国でどういう目で会うかは、我々がよく知っているではないですか、父上が異能者の女をかばった可能性もあるという事だ、私は知っている、あの日生まれたのは・・・、一人で、その後は・・・・」
うめき声がその部屋から聞こえた。
「ううう・・・・」
エルネストがであったのは、フリルの服を無理に着せられたヴォルフリートだった。教育係にダイブ、苛められたらしく憔悴している。母の話では、彼は勉強が駄目で、スポーツも平均波で、根性がない、駄目駄目な男で、ドジでのろまでボーっとしているらしい。平たく言えば、落第生で、頭が悪いバカ。
・・・こんな子が、皇太子殿下のお気に入り?
ここにくるまで、宮殿に囲われていたらしい。わからない、上の人間がすきそうな、美貌も品のよさも、何かの才能も、後見人もなさそうなのに。
「うわあああああ」
馬を操られず、川に落とされ。家の中では、よくこけている。メイドが落としたスープを頭から被り、イヌに追いかけられ、尻をかまれた。
シリアスがにあわない子である。
「きゃっ」
アリスは思わず、声を上げた。ステージが終わり、団長からエレク二伝言を伝えるように言われたアリスは、扉を開けた瞬間、舐めかまし息絶えられたエレ区の背中を見た。火傷のようなあとと魔女の刻印のような後があった。服を着ながら、無愛想で不機嫌そうな表情で
「何だ、あんたか」
アリスはハッとなった。
「ごっ、ごめん!!」
「へえ、男の裸をみるのは初めてか」
にやりと笑われた。
「・・・・その傷」
「ああ、前の彼女がかなりのSで独占欲が強い女だったんだ。俺が他の女を見るのは許せないといって」
「・・・そ、そうなんだ」
あの弟の姉にしては反応がうぶだな。からかいがいがありそうだ。
廊下の隅で、エレクは女の強い視線を感じた。エレクが好きな年上の女だ。
「アーディアディト、用件を言え」
「え、は、はい」
面倒くさいことになりそうだ。
8
「大丈夫かい?ヴォルフリート」
・・・噂どおりの人物だ。
正直、エルネストは、所詮、庶民かと馬鹿にした。
「は、はい・・」
エルネストの力で、ヴォルフリートは起き上がる。今日は雨雲が多く、不安定な天気だ。
「皇太子殿下がメインの乗馬に僕たちが出席しないとまずいだろう」
いや、庶民だからではない。ヴォルフリートが平凡なだけ、ただ、それだけだ。
「ハイ、エルネスト様」
緊張もしている、いつも突っかかってくる、あの少女とは対照的に、気も弱いのだろう。
「様はいいよ、従兄弟じゃないか、エルネストでいいよ、それに僕も君に近づきたいし、僕、ルドルフ様に憧れてるんだ」
怖いお化けが出るのは、こんな天気の時だろう。
「・・・憧れね」
「ねえ、ルドルフ様は普段はどんな方なの?」
「あ、ああ、ルドルフ様は・・・・」
ルドルフ様は、こいつのどこを気に入ったのだろう、興味もアル。
「凄い人で目立ちたがりで、ひねくれてて、ナルシストでいじわるで怖い子で、寂しい人だよ」
「はぁ?」
「いやいや、別に悪口言っているわけでは!」
「大丈夫、大丈夫だから!!」
ヴォルフリートはほっ、と胸をなでおろした。
「よかった・・・」
「君は殿下に気に入られているけど、どういう関係なの?」
「多分、ええと、恐れ多いけど、友達かな」
「・・・・友達?」
「うん、遊びにこいといわれて、宮殿にきたから」
「でも、そのときは君はこの家の子息とわかっていなかったのだろう、君の知り合いに貴族か、ハプスブルク家にかかわりがある人間がいたのか」
ヴォルフリートは首を振った。
「いないよ、いつの間にかつれてこられたから」
「・・・君は、何故、殿下に気に入られたと思う?」
「それが僕にも謎なんだ、凄く頭いいし、何でもできるから、僕じゃなくてもいいと思うけどなぁ、それでね」
その時、ヴォルフリートの襟元を後ろから掴んだ。
「ああ、僕がルドルフ様に珍しい生き物的な」
「あ・・・」
ルドルフが背後から現れた。
「疲れた、行くぞ、俗物」
「う~ん、それとなんだろう」
ルドルフは冷たくエルネストを見た。
「君、僕の所有物に触れる時は、周りのものに許可を取れ」
バシャァァァァ。
「この貴族やろう、ここはお前みたいな世間知らずが来る所じゃないんだよ!!」
お針子を世話する教育係のアンナが、アリスに水をかけた。
「何をするの!!」
「中途半端な年齢でたやすく歌手になれると思ってるのか!!皆、お前みたいに道楽じゃなく、それこそ血がにじむ努力で這い上がる為に生きているんだ」
背後からはクスクスと冷たい歌手志望の少女達が控えており、付けほくろをつけ、扇を広げた妖しい魅力の歌手たちのそばには黒い背広の男性の姿があった。
「出て行け、ここにお前の居場所はないんだよ!!」
「ひっ」
灰をぶっかけられた。
夜が明けようとした瞬間、新たな嵐がアリスを襲おうとしていた。
嵐がやってくる。激しい嵐が。
宮殿の奥で、愛犬のアレキサンダーと共にルドルフは不安定な天気を見ていた。
「外は荒れているよ・・・」
くうん、とアレキアンダーは静にうなる。
「中もめちゃくちゃだ」
ー1975年、トルコの圧政に苦しむダルね地あの使節団一行がオーストリア・ウィーンに現れ、皇帝フランツ・ヨーゼフに取るコ勢力の駆逐を嘆願する。
バルカン半島の嵐が帝国を巻き込もうとしていた―ーーー。
舞踏会の会場を抜け出した後、エルネストが待っていた。
「もう、貴方にルドルフ様の友人である必要はありません」
「は?」
さっきといい、急流だ。
「ルドルフ様は貴方を見限られた、これからは宮殿は仕事以外のときは来ないでくださいね、ルドルフ様も皇族として敬ってください」
エルネストの目には、少なからずヴォルフリートがショックを受けているように見えた。
「・・・・・」
「僕がルドルフ様を守ります、貴方には負けません」
「エルネスト、どうしたんだ?」
動揺し、困惑しているような表情だ。
「僕は、あのお方を尊敬し、皇帝にすると決めたんです、ルドルフ様を愛しています」
強い眼差しだった。
エルネストが去った後、ヴォルフリートはその背中が遠くなっていくのを呆然としながら、次の瞬間、凍りついたような、まるで別人のような大人びた表情を浮かべた。
長い宮殿の廊下を歩き、ルドルフは難しい民族問題、父親との言い合い、家族のことを考えた。エルネストは調子に乗っている、大人しい純粋そうな、利用される子息だと思っていた。ルドルフは、ローゼンバルツぁー家の存在の意味を知っていたが、正直好きにはなれなかった。
―真実ではないかもしれない。
ルドルフはアリスを疑う事はできる、彼ら2人が兄弟である証拠はエレオノール、あの家だが、実際はあの事件で誰かに兄弟だと仕組まれたものかもしれない。
舞踏会も、華やかな席でも、フランツやルドルフの妹のマリア・ヴァレリーには、日の届く場所で一番輝き、美しく華麗な兄が完璧に見えた。世の中の汚い場所や感情、絶望は彼には不似合いだった。
―お兄様は強いのね
―当然だ
ヴァレリーの後ろには、いつも笑顔のエリザベートの姿があった。庭園から見るシェーんぶるん宮殿は荘厳で、威圧的であり、ハプスブルク家の歴史差の重さを貴族たちに知らしめていた。無論、皇帝やルドルフの住む、ホーフブル紅宮殿もかなりのものではあるが。シェーんぶるん宮殿には、偉大なマリア・テレジアの姿や彼女の子供たちの肖像画があった。
謁見を許された人々の控えの間や謁見室を横目にルドルフは歩く。
皇帝の執務室には、皇妃エリザベートの肖像画は飾られている。
―痛い。
ルドルフはぎゅっ、と目を閉じた。望むべき評価で、それは当たり前で、自分はその声にこたえなければいけない。
「ルドルフ」
皇帝陛下がルドルフの前に侍従をつれて現れた。
「どうかしたのか?お前が辛そうな顔するとは」
「・・・・あ」
「ルドルフ?」
「大丈夫です、少し徹夜続きで・・・・」
「そうか、あまり無理はするな、お前の体にはこの帝国の未来がかかっているのだから」
「はい、父上」
ルドルフは真っ直ぐな眼差しで答えた。
フランツ・ヨーゼフ一家のダイニングルームである、マリー・アントワネットの部屋に皇帝と分かれた後、ルドルフは向かった。
鏡の間で、ルドルフは一人佇んでいた。正確には、アレキサンダーという愛犬を連れていた。人形のように坊立ちし、ギリシャ神話の彫像のように佇み、表情を緊張させていた。物憂げで、将来のことや民族、暗殺など、そんなことを考えていた。
大ギャラリーで、昨夜、舞踏会が行われた。長さ40メートル、幅10メートル、庭園側には大きな窓、その向かいの壁には同じ形の鏡が取り付けられている。壁に並ぶキンの蝕代、天上から下がるシャンデリア。
「くぅん・・・・」
「大丈夫だ、アレキサンダー」
旧王宮にはいつ戻れるだろうか。
「!」
切れ長の美しい高貴な、宝石のような瞳の視界の隅に見慣れたダークブラウンの髪が揺れた。凛々しく、穏やかな見慣れた容貌。ぴんと背筋を伸ばし、乱れのない歩き。警棒のようなものが音を鳴らしていた。
謝罪をしてきたのに、何故、自分は感情をぶつけた。
何故、話しかけないのだ。ただ、ヴォルフリートは仕える者としてそれに習っただけなのに。
意気地がない子供ではありまいに。
教会でオッドアイの少年が祈りをささげていた。
値踏みするような視線を教育係の軍人は少年に向ける。放置した。数えるほどの監視をつけて。いつだって自分はあんな子供一つ、始末することができるんだ。なんておバカな、裸の王様。
「―毎日祈っても、ここにお前の家族は来ないぞ」
「いいえ、皇太子殿下、昨日も生きられた喜びを神に感謝していたんです」
「ふんばか面だな」
「―そうですね、でも、宮廷の人と貴方には感謝しているんです、住む家と仕事、食べ物をくれて。それにもうすぐ姉さんにも会えますし」
まっすぐな目で優しくほほ笑まれる。
「だが神はお前の家族を奪った、食べるものも奪った」
本当に神が人を救うなら。
「神が与えた言葉で、これまでどれだけ歴史上戦争が繰り返されたと思っているんだ。人が救えるのは人だけだぞ」
考えるような顔になる。
「―それでも、僕は信じたいです、人の優しさを。殿下がいなければ僕はこの場にいなかった、有難うございます」
ア、こいつ馬鹿だ。
皇太子は確かにそばかすの少年にそう思った。利用されていることにも気付かない、このままではただくいつくされるだけだ。利用されていることにも気付かない、かわいそうな哀れな奴。外でどれだけ多くの血や涙があふれておることも知らない。心の中で唾棄した。こういう輩は嫌いだ、虫唾が走る。哀れな羊にしかならないのに。
神の祝福を得る、そんな式を迎えながら伝統と格式通りの司祭と神への忠誠を誓う。神聖な光を浴びて、まるで天使みたいという女官もいた。自分の演技にも気付かない女たち。
優等生の仮面に気づかない役人や使用人、戦争に見ないふりをする貴婦人たち。視線を教育係やエリアス卿に向ける。脳裏にエリザベートの姿が浮かぶ。その中で司祭の後ろに隠れた、この空間にふさわしくない痩せた少年の目に皇太子は気付いた。
ふっ、と笑う。少年の肩がびくっと震える。残酷な喜びに似た感情。かえが聞く存在だ、彼の今後は自分の手にかかっている。いつだって手を下すことはできる。自分の残酷さに、人間らしくない振る舞いにつくづく心の中が冷え込んでいく。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- GUNの世界
- SIG P210-6 エクセレントHW ガスBLK …
- (2025-11-17 13:05:50)
-
-
-

- フィギュア好き集まれ~
- 30MM 『ARMORED CORE VI FIRES OF RU…
- (2025-11-19 18:04:16)
-
-
-

- アニメ・コミック・ゲームにまつわる…
- ベジータとカイジがレトロゲーム実況…
- (2025-11-19 20:00:07)
-
© Rakuten Group, Inc.