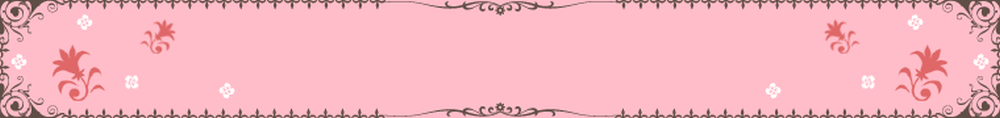第12章星の王冠
いまも僕はここから君を、繋いだ手を忘れられずに
「・・・・本当に行くの?」
正直、夜中に湖の上の古城ホテルなんていきたくないのだが。招待されたアリスは楽しそうだ。
「ローザリンデとか他の子は?」
「皆聞いたけど家族と旅行ですって」
ゆらゆらした感覚がなんとも落ち着かない。アンネローゼが姉さんに渡したカギは古びている。
「・・・・ひっ」
ナイフを突き付けられ、ヴァルベルグラオに侵入したものとりの男はヴリルの目の鋭さに恐怖を感じた。
「大丈夫か」
「え、ええ」
「おやすみ」
なぜか、周りから叫び声や羅嘘だろという声がわきあがった。
「・・・ええ、おやすみ」
「ヴォルフリート、お前ってやつは」
なぜか、カールから首を絞められた。
「何、イタイイタイ」
「何でお前アリスからキスされてんだよ」
「・・・・アーディアディト」
「あ」
その手をバルドぅーインがすくい取る。
「まだチャンスはある」
「先に言っておくけど、僕心弱いよ、人生相談聞けるほど経験していないよ」
通告はした。
「・・・・俺は卑怯者だ」
赤い髪に意思の強さを見せる少年は、ジ―クムント様は聞いていない。上流階級のノブレス・オブリージュ精神はどこに行ったのか。場所は伯爵家で、エリアス卿とは生まれる前からの家族ぐるみの付き合いらしい。
つたなくても言葉で伝えれば、ある程度伝わるはずだが、皇帝陛下並びに貴族たち、権力者は人の話を聞かない。こんだけ土地があれば村が二つ入りそうだなとか、田んぼとかで野菜育てられそうとか、姉さんは劇場でいじめられてないかなとか関係ないことを思う。
「俺はあいつを傷つけた」
「売り言葉に買い言葉だったんだろう」
年上といっても一つだけだし。
「だが、最後まで詰め寄ったのは俺だ・・・俺なんだ!!」
そう叫んで身体を丸めて顔を隠した。
「俺はどうすればいい、ヴォルフリート」
腕を掴んで、まとうように聞いてきた。
「・・・・」
無言だったのは、彼を思ってではない。
「責任をあいつに押し付けて、俺は逃げたんだ」
確かに残されたルドルフは怒りながら涙を浮かべていた。ギ―ぜラが慰めていた。そんなに大声で恥ずかしげもなく、役者やれよ、役者を。
「あれはいいだしたルドルフ様が悪いんだろう」
ジ―クムントが顔をあげた。
「君は悪くない、あの場は皇太子殿下が納めるべきだった」
「そんなことはない、だって俺は」
面倒くさい奴だな。
「王様だからといって、何でも思い通りという考えは嘘だからね・・・ルドルフ様は14歳の少年であることを見せる前に形を作るべきだった」
「でも、ルドルフ殿下、ちゃんと返してくださいね、私の弟なんですから」
「まあ、姉さんがそう思うなら」
「お前ら、兄弟の距離感ってなんか変なんだよな」
「そう?」
「アーディアディト花や実すぎるくらい悩む奴なのにお前は弟なのに違うんだな」
「よく言われる、僕も悩みあるんだけど、みんなには能天気で明るいと思われているみたい」
「実際そうだろ」
「優しい両親にかわい妹や弟がいれば、たいてい明るくなるんじゃないかな」
のホーンmと笑う。
「ほんと、能天気でうらやましい、・・・図太いな」
「いやあ」
「ほめてないから」
「ええ、そうなの!?」
くるくると表情が変わる。能天気で馬鹿みたいに素直で、危なっかしい。ジ―クムントはほおをつねった。不幸な生活から幸せになったんだなと思った。
・・・・大丈夫、大丈夫だ。
自分を見ると、不機嫌になるディートリヒと街中で遭遇する。
「でぃ・・・」
隣にはエレオノールの姿がある。自分を睨んだ後、すたすたと歩いていく。
当初はライバル心むき出しで、現在は休戦状態で、表向きには敬意を払いあっていると思っていたが、どうもはちょうが合わないというか、仲が悪くないが、アリスとディートリヒの中を考えると、距離があるようだ。
不気味に思われて当然か。嘘吐きだと思われたんだろう。
嘘をつきまくって、女性をあせる無神経な兄。偽善者ぶる兄。それがディートリヒの自分に対する評価だ。
「仲良くしなさいよ、将来、あの子がディートリヒと関わる時、どうするの」
自分以外には、母親の顔をエレオノーるはもっていた。
「精進しますよ」
「大変よ、あの子なかなか懐かないから」
「ああ、細かいですしね」
大雑把な自分とは違う。自分のようなタイプは理由がなくても、嫌いなんだろう。
月が出ている、涼やかな夜だった。
何だか、寝付けなくて。でも、隣の部屋の乳母を起こすのも悪い気がして。
カイザー・クラウドはランプを持って、柱が立つ長い回廊に出て、トイレに向った。広大な屋敷は幼い少年にとって迷路のようだ。冷え切り、全てが静まり返っている。最低限の灯で照らされたホールは二階まで吹き抜けになっている。階段の間をカイザーが降りていくと、その途中で普段は温室から出ることがない母親が、玄関先で漆黒のマントの少年と話をしていた。年はカイザーと同じくらいだろうか。
背格好もカイザーによく似ていた。
何となく、階段を音を立てずに、柱の陰に隠れると。
少年の方が口を開いた。肌の色が違う。エキゾチックな風貌から、トルコか中東のうまれのようだった。理知的な顔立ちをしていた。
「奥様、頼まれていた書簡です」
「まあ、いつも有難う」
穏やかな口調で母が答えた。
「ごめんなさいね、本当なら主人がもらうものなのに」
「いえ、だんな様もお忙しい人ですから」
お父様?
カイザーは首を傾けた。
「ですが、大丈夫なんですか」
「え?」
「交流を私を通して、続けるなど、模試、あの人の耳に入ったら、奥様やだんな様まで」
小鳥のさえずりが、カイザーの通う寄宿学校の周囲に広がる森の中から聞こえる。成績発表の張り紙を多くの生徒が見つめる中、友達のクラウスやシンドラーと共に美麗な顔立ちを、16歳のカイザーは見つめていた。カイザーの成績はまた、2位だった。
「くそっ、また負けた」
苦々しそうに顔をゆがめて。一番は、ジークベルト・フォン・ブッシュバウム、ディーター・フォン・ブッシュバウムの弟である。黒髪に眼鏡の穏やかで静かな少年。ジーくべるとは、カイザーの隣のクラスで、入学以来、カイザーは彼に成績で買ったことはない。
「ひゃーッ、サスは名門クラウド家」
「いつもながら、見事だな」
事情を知らない生徒達からは賞賛の声が聞こえる。そんな時、豪快な歩き方の、暁の目というマフィアの後継者だという、ヘルムート・デーアが筋肉もりもりのラクビー部の友人を連れてやってくる。
「マジュールの魔女の息子だ」
「違う、ウィーンの狂犬の息子だろ」
戦々恐々と言った様子で、派手に現れた黒髪の日に焼けた長身の少年に周囲の視線が集まる。
「カイザー!見つけたぞ!!」
大きな体でカイザーに抱きついてくる。クラウスやシンドラーはぎょっとした表情になった。
「でかい体で抱きつくな、気持ち悪い!」
クラウドの何傷がついたらどうする気だ、この男は。
「何だ、照れてるのか、それとも俺様と三日、離れてて寂しかったか?」
「息を吹きかけるな、気色が悪い」
「風邪治ったんだ」とクラウスが遠慮がちに聞いてくる。
「ああ、エリーの看病のおかげでな」
エリーとは、彼の教育係で母親代わりらしい。うっとおしい、双思いながら体を寄せてくるヘルムートの体を押しのけようとするが、運動が苦手なカイザーには難しい。
「デーア、また貴方ですか!」
「やべっ、風紀のコローナだ、それじゃあ、カイザー、また後でな」
「待ってくださいよ、デーアさん!!」
けたたましく、デーア派友人を連れて去っていく。ヘルムートが触れた部分のほこりを払いながら、カイザーはため息をついた。
「午後の授業、抜けるんだって、カイザー」
「・・・・ああ、母の体調が悪くて」
2
ジ―クムントはたいがい、挨拶を追えるときが合うのか、ルドルフ様と喧嘩をしている。ぶっきらぼうで怖い麗しの殿下は今日も口達者ぶりを見せ付けている。
「ふん」
「貴様、殺す」
「そんなにむかつくなら何で呼ぶんです」
「別に」
「君には関係ないだろう」
つーんと顔をそらされる。
「お前ら、何をして」
「おお、もう来たか」
「??」
何なんだ。
大広間でディートリヒやアリスと戯れるエレオノ―ルを見て、気のせいだったのか・…と思った。
昨日は結局、自分の部屋で寝ていたし。
「…環境が変わったせいかな」
その時、深い沼のような、飲み込まれるような、奇妙な感覚を感じた。エレオノ―ルが、母がこちらを見て、ほほ笑んでいる。慈愛のこもった、いつもの穏やかな。
ふ、と薔薇いろの唇が笑みを作る。
よどみなど一つもない。
エリクが知ったら、うらやましがるような理想的な母親。自分には分不相応な。
優しく、愛してくれることはわかる。
家に入って以来、母は良心に似ていない自分を一番そばにおいて、可愛がっている。姉さんとは違う意味で、息子を持てたという喜びで。
「ぼっちゃま?」
「すみません、少し外へ」
ただ、時折、妙な視線を感じる。熱を帯びるような、何か見てはいけないものを見た時のような、危うく、危険な、それでいて甘いような。
人の感情に疎く、頭が悪い自分でもわかる、息子に向ける母の感情や視線の意味は、なんだか違う。はっきりしないが、何か違う。
扉に向かい、開けようとした時、淡い色のウェーブヘアに、清楚な顔立ち、均整のとれた身体を青紫のドレスに身を包んだ親戚の年上の少女。
「私も一緒にいってあげる」
「え?」
優しく、おしとやかな笑み。
「貴方可愛いからどこかのいけない子にさらわれないようにね、私がそばにいて守ってあげるわ」
「可愛いって・・・うれしいですけど、そういうのは姉さんに言う言葉でしょう、僕が地味顔だって知ってて行ってます?あ、ユーリア様、でも」
「ユーリアでいいわ」
きゅっと手を握られた。
「行きましょう、ヴォルフリート」
「え」
ぐい、と引っ張られた。
「ちょっと」
時折、アリスは思う。エルネストのディートリヒの視線の意味を。
お互いを刺激し合う関係。
「君のおせっかいなところが苦手なんだ」
「いい~放っておいてくれ」
突き放したようにアリスにいう。遠くの方で母が咎めるようにエルネストの名を呼ぶ。そのとげの意味をアリスはよく考えた。
喧嘩しているわけでもない。
家の中での一番の相談相手のメイドの少女やダリルは今は放っておけという。
「でもよくないわよ」
「それはあんたの希望だろう」
ダリルを少女が肘でつつく。苛立ったようにダリルは声を荒げる。
「大体、あんたはいつも他人のことばかり気にしすぎなんだよ」
昼のチャイムを聞きながら、ヴォルフリート・・・いや、ここでの名前は商家の末息子、ハンス・アンデとして一つ気合が少なく大人しく控えめな生徒として、学園の片隅にある球形所で息を整えていた。今回のここでの仕事はジーくべるととともに、ある人物の品行を調査することだった。その人物は密輸事件で、大きな陰謀の言ってにからんでいるという。
隣のクラスが、渡り廊下を歩いていた。その中で輝くような、見慣れた金髪がいた。ベルンハルトの息子だ。アリスの本物の弟の。
カイザーに気付かれないように、日陰に身を隠す。
黒髪のロンゲのかつらを触りながら、ヴォルフリートは複雑な気持ちでいた。
バルコニーで休んでいると、ローウェン家のロッテ嬢がカクテルを持ってアリスに近づいてきた。
「相変わらず、凛々しく乙良くいらっしゃる、貴方も電化の優雅なお姿を拝見しに言ったら、どうですの」
おっとりとニコニコ笑いながら、ロッテはそういった。
「・・・・・いえ、私はそういうのは」
「そうですわね・・・ヴォルフリート様はまだ社交界に参加できませんの」
「一応、認められているのですが、弟はこういう華やかな席は窮屈だと、あまり行きたがらないのです」
「そうですか、せっかくあんな素敵ですのに。お家はアリスが継ぎましたから」
「本当にアリスは尾可愛らしいのですね」
「ロッテ・・・・」
会場の中からルドルフはその会話を聞いていた。
軍の建物の中で、ギルバートは苦手なディーターとベルクウェインに出会う。
「おーっ、あいかわらずちじれているな、泣き虫ギルバート」
ニヤニヤ閉じ割るじみた笑みを浮かべている。高慢な笑みが見下ろすように、ギルバートに向けられる。
「・・・悪いけど、僕は用事があるんだ、君の相手をしている暇はない」
ギルバートはそのまま、ディーターの横を通り過ぎようとする。
「何だ、お前の友人をかけの材料にしようとしたこと、まだ怒ってるのか?暗い奴」
「違うだろ、軍に入ってすぐにエドガー先輩とひと悶着を起こしただろ、アーデルはイトの兄気味は正義感が強いお方だから」
意地悪な笑みがニヤニヤと向けられ、ギルバートを不快にさせる。
「伯母様に報告の手紙は今週送らないのか?義務付けられてるんだろ、次期侯爵殿」
背が高く、漆黒の髪と整った顔立ち。ギルバートは訓練でディーターに腕を折られたことがある。ディーターには遊びでしかなかった。
ギルバートはきっ、とディーターを睨んだ。
兄貴分であり俺様で自分が世界中心で、軍の規律を破ってばっかりで、苛める相手にはとことん冷たい男だ。
「良かった、ここに痛んだね、ギルバート、オリバー次官が読んでるよ」
「ブレーズ」
友人の登場にギルバートはほっと胸をなでおろす。
音楽の神ミューズに支配された、愛と死が行き交う街、ウィーン。音楽は全てを支配する力を持つ。オペラや宗教音楽、フランスからはトルバドゥールと呼ばれる吟遊擬人、ドイツからは民ね全ガーやマイスタージンガー、オランダからは宮廷室内楽といった風に音楽は流れている。明日ペインは市の近くには、陸軍省がある。王宮近くにはオペラ座が。街のいたるところに、ハンガリー景気へい、チロル山岳兵が行き交っている。
・・・双頭の鷹は既に大長老で、外見ばかりが若者でしゃれていて、豪華で古めかしく形だけなしている。
―何故、こうもギルバートは純粋なのか、とヴォルフリートは不思議に思う。
「貴方は間違っている!!」
「何を、この帝国の狗が!!」
取り押さえながら、ギルバートは真っ直ぐな目で強盗犯を押さえる。日に焼けた肌に鳶色の巻き毛。
「訴えたいなら、正当な手段で訴えるべきだ!!」
ジプシーのコだ、と同じ軍の貴族の男が蔑みながらそういった。自分のように違う瞳を持つ人間よりもはるかな嫌悪感だった。
「はっ、それもどうせ、フランツ・・バイエルンの魔女に取り込まれたあの皇帝で押さえ込まれるだろうが!!」
「黙れ!!」
3
「俺たち、友達なんだよな」
その言葉をどう思ったのか、フォルクマ―は照れたように見るオルフェウスを見て、ああと答えた。利用し甲斐がある。
いずれこの国を導くリーダーになるために。ローゼンバるツァーを出し抜くために。
ドロテアは真っ向から兄弟を嫌悪し、一族のものと認めず、叔母のヘレ―ナも表面的にはやさしいものの一族のものと認めなかった。
「血のつながった家族、いとこ同士なんだから当然でしょう!!」
「いとこ・・」
ヴォルフリートの部屋。時折、自宅に戻るとエレオノーるの及びがない場合や他の用事がない場合、できる限り、資料や研究道具を使って、記憶のマップ作り、持続時間、どんな異能者ならば不安定な姉の記憶を安定させるかどうか。
「シェノル、その顕微鏡とって」
「はい」
「次は瓶を」
「はい」
壁に計算式や魔術の形式、赤の女王の血、様々な可能性をあわせていく。
「ヴォルフリート様、表の部屋に弟君が来ています」
隠し部屋の扉が開く。アリスの記憶探しに関しては両親も協力的だった。
「今、いく」
扉を開け、また扉を開けて、本棚を横にして、本棚を横にする。
「兄上、父が一緒にと」
「何か隠してるでしょう」
「な、なにがかな」
「さっきから行動が不審です」
じーっとディートリヒがヴォルフリートを見据える。
・・・であった当初が当初だけに、ヴォルフリート側は嫌いではないものの、ライバルでありつつ、仲のいい兄弟、優しい兄をこの弟相手に演じるのは困難だった。
嫌味のつもりはないんだろうが、弟は人の弱いところや駄目な所をずばずばと指摘してくる。どうもまじめすぎて、味方より敵を作るタイプらしい。
「気のせいだよ、どうしてそう思うんだい?」
書類を一枚見られても、魔術の方式が書いてあるから、オカルト趣味と言い張ればいいんだが、本物がこの家に住むときにその経歴が重なるのは何ともいえないんだがいけない気がする。
「目が泳いでいます。何か、後ろに隠してるでしょう、方や手の動きが不自然です」
背後にシェ乗るが現れ、後ろ向きのまま、渡す。有難う、監視役。有難う、従者。初めて、ヨハネスに感謝する。
「気のせいだよ、ホラ、何にももってないだろう」
「本当ですね」
まだ、じーっと見られている。ディートリヒがある事に気づく。
「後ろの本棚、びみょうにずれていませんか」
「気になります」
「直しておきますね」
「いいって、後で僕が自分で治しておくから」
「何故、慌ててるんですか?・・・何か、隠していますね」
。やばい、と思った。扉は鍵を着たときにアンジェルが閉めてるから入ってくることはない。
それはまるで天上の音楽を思わせた。深海にすむ人魚の歌声にも似ていた。メインボーカルとなった彼女に、14歳だった頃の自分を思い出す。であったときから彼女は明るい笑顔で、眩しいくらいにエレクを照らした。
暗闇としに満ちた世界で、蹴落とししあう世界でエレク派、歌う彼女に出会った。馬車に乗っている時は良く似た別人だと思っていた。
「ほんっとうに、こんなジプシー育ちと勝負するのか」
アリスが所属する座では、エオスは煙たがれていた。仕事が三流の劇場の歌手ということではないだろう。恐らく生えれ区のどぎつい過去を噂に聞いているのだろう。裏の人間とも顔なじみの自分をネズミのように嫌っている。
・・・だから、何だというのか。
雪が降った翌日の昼下がり、偶然、劇場内で、エレクはアリスとチェスのゲームをしたこととなった。手を組みながらニヤニヤと笑う。
「それで、あんたは何を賭ける」
「賭け事は卑しい人がすることだわ」
キッ、とアリスはエレクを睨んだ。
「挨拶代わりに誰とでもキスするなんて、最低」
かぁぁとアリスの顔が赤くなる。
「最低!!」
「チェスは俺とお前で盤上の駒を交互に指しあい、相手のキングを追い詰めるゲームだ。あんたが勝てば、俺はローゼンバルツァーとは縁を切って、あんたの弟とも関わらない、俺が勝てば・・・そうだな、あんたにキスしてもらおうか」
周囲もざわついた。
「・・・・・本気なの」
優雅に手を入れ替える。艶やかに優しく笑う。
「もちろん」
・・・ガタン。
息をついた。良かった、エレオノールはいったようだ。
「ふーっ」
「・・・・」
・・・・あ。
珍しく、青い瞳をきょとんと子供のように見開かせていた。不自然だ。ヴォルフリートはとっさに本棚の間にディートリヒを押し入れて、手で口をふさいだ。
「えええ・・と」
この状況は、ディートリヒの疑念を強くするな。
何とか、言い訳を、ええと、つまりだ。困った時は笑顔だ。
「本棚、直そうか」
「・・・兄上、やっぱり何かあるんでしょう」
「・・・いやぁ、以前、大人の本をお母様に見つかって」
世間的な言い訳をしてみる。
「嘘ですね」
「兄上は自宅にはそんなもの入れません。持っているなら確実に父上たちにはばれない所で見るはずです。私に正直に何を隠してるか、教えてください」
どうしたものかと考えていた時、不自然にディートリヒの体がはねた。
前にいたヴォルフリートの服を掴みかかる。
「どうしたんだ?」
「今、服の中に何か」
声が震えている。動揺しているようだ。
「服の中?」
見ると、子ネズミのようだ。
「何だ、ただのネズミだよ」
4
体が小刻みに揺れていた。いつものディートリヒらしくない。
「どうしたんだよ?ネズミくらい、自分で取れるだろう」
「・・・家、その、実はネズミが苦手で・・・」
表情が蒼白だ。取り乱している。
「すみませんが、とって・・・いえ、自分で取るので、しがみつかせてくれませんか?」
泣いていると、ますます女顔にみえるな。言ったら殴られるから言わないけど。
「わかった」
結構指が食い込んでいる。かなり、ネズミが怖いらしい。気分よくないな。
ディートリヒは自分の服の中に手を入れると、立ったまま、ヴォルフリートを本棚に預けた状態でネズミを取り始める。ネズミは手から逃れて、服の中を上に向ってはいずり始めた。
「ひぃぃぃ」
「痛い、ディートリヒ」
「ネズミがねずみが」
ぎゅううと腰をつかまれた。
「!」
記憶が、突如蘇る。
―ヴォルフリート。闇の中のアイツのチ。息遣い。圧倒的な筋力さ。匂い。
背中を這いずり回るような、あの感覚。何もできなかった自分。全てを支配された、殺されたあの感覚。
無力だと思い知らされた瞬間。
喉に吐き気に似たものが這い上がりかける。
「~~っ」
ディートリヒはなおもしがみついてくる。
わざわさとネズミが這いずり回る。
バカ、何故、今、この状況で思い出す。嫌な汗が体を伝う。恐怖が体を駆け巡りかける。心臓の音が煩い。落ち着け、落ち着くんだ。
もう、終わったことじゃないか。
カタカタ、と震えていることに気付いた。ディートリヒは顔を上げる。顔が蒼白だ。どうしたというのだろう。
「兄上?」
驚いた。今にも泣き出しそうな、16歳の少年の顔があった。初めて見る表情だった。ぼろぼろと涙をこぼす。
「う・・・あっ、ひっ」
・・・・兄上?
「ああ・・」
涙がこぼれる。
「兄上・・・」
肩を持つ。無意識に頭を預けそうになる。
「・・・けて」
「・・・・・助けて」
アルバートの声だった。ぐらり、となる。ディートリヒの肩にもたれかかる。
「・・・兄上・・・?」
「助けてくれ・・・」
「―-」
ディートリヒの方が震える。目が見開く。
「あ・・・」
はっ、となって、かぁぁ、となる。年下の前で取り乱すなんて。しかも弟の前で。
また、アルバートが勝手に・・・!
ディートリヒが意外な表情に驚いている。
「あの」
ディートリヒの腕が離れる。ネズミは走り去っていった。
「・・・・兄上、・・・・」
「触るな!」
手を弾いた。
格好悪い、最悪だ。
「待ってください、あの」
「来るな!!」
睨んだ。そして、そのまま、ヴォルフリートは走り去っていった。
ガタンッ。
「・・・・?」
ゴットフリートとアーディアディトの住居スペースは二階の西に位置する。
「・・・おはよう、ゴットフリート義兄様」
なぜか、ゴットフリートの頬が赤い。かんしゃくでも起こしたのだろうか。視界の隅には、事件でもあったように、レオンハルトとエレオノールがお互いの顔を見合わせて喧嘩していた。
今、出てきたのはアーディアディト、姉の部屋だ。
「?」
夫婦なのだから、朝から同じ部屋にいてもおかしくない。なぜか、部屋の前にはチェスのルークの駒が転がっていた。
「メイ、一体、何が」
「ヴォルフリート様、お姉様が・・・・」
身体中の血がざわめいた。
5
若き執事セバスチャンは、先代から次期クラウド当主カイザーの世話を任されていた。悪戯好きで気まぐれ、プライドが高く、女性には優しい。
「・・・・これは平価により授かったサラダとわかった上で割ったのか」
「・・・お父様」
完全に押されている。扉の間で、親子の緊張が続いている。
「すみません・・・・、妹がどうしてもこの皿を見たいと」
「お前がしっかり管理していれば、あの子も無茶な行動に出なかっただろう、お前はそういうことがわからないのか」
「・・・・・」
表情が青い。普段の生意気なカイザーの姿はそこにはない。父親を見ると、カイザーは恐れの表情をする。仕方ない、今の当主の教育は、スパルタで親子の情などはさまないのだから。
「私が家に帰ったら、挨拶に来るように、言いつけを守れなくて、何がクラウド家の男だ」
「・・・ご挨拶が送れて、すみません、お父様」
執事の立場を超えて、進言する。臆病なセバスチャンはカイザーを気遣いながら、それを行動に移す勇気はなかった。
4
穏やかな校舎の中庭でヘルムートが学校の生徒といさかいを起こしていた現場に隣のクラスの髪で顔を隠した地味な生徒ハンス・アーデがオロオロとヘルムートと殴り合いをしている生徒の間を行ったりきたりしている。
口数も少なく、主張が少ないハンスはカイザーは、数いる生徒の一人だった。商家の息子で、成績も普通。カイザーが一方的にライバル視するジークベルトと同室で、友人というわけは。
「ハンス、喧嘩の原因は何なんだ」
「クラウド委員、・・・それがヘルムートさんの実家の金銭トラブルのことで、カイがからかって」
「違うぞ、俺はそんなことを気にしていない、俺がこいつを殴ったのは、俺の友達を貧乏人だと責めたからだ、悪いのはこいつだ」
周囲で笑っている生徒もいる。増徴するようなことを言ったのだろう。
「カイ・バジル、ヘルムート・デーア、並びにルー度ヴィッヒ・シェイクスピア、カール・ザイル、お前達を懲役房に入れる」
「何故だ、俺は悪くないぞ」
ヘルムートがカイザーに抗議する。カイザーが指パッ陳する。
「先生方、頼みます」
「カイザー、話を聞け」
「神聖な校内で騒ぎを起こしたお前が悪い」
「委員長、それはないっすよ」
生徒たちは今日士達に連行されていく。カイザーは残されたハンスにじろりと見ると、にかっと笑顔をこぼした。
「俺の友人が君に迷惑をかけたな」
力なきものには優しさを、母の教育の賜物だ。
「は、はい」
ヘルムートの喧嘩がきっかけとなり、いじめっ子の標的にされやすいハンスと話す機会が増えた。
廊下を歩くと、カイザーを慕う下級生が冷たくハンスを見る。ハンスは教科書やノートを持って、肩を小さくして、クラウスや友人とカイザーの後ろを歩いている。
「なぁ、何で、あんな地味なの、俺たちのグループにつれてるんだ」
監督せいの一人が、カイザーに話しかける。
「アイツ、お前の嫌いなジーくべるとのおまけだろ、何であんな劣等生を」
「俺たちのレベルが疑われるジャン」
プライドと家の品格にこだわる貴族の子息らしい発言だ。
「不都合があるか?」
「ホラ、毎年の馬術大会や討論会も近づいて、監督せいで委員長のお前の評価が気になる時期だろ、それなのに金魚の糞みたいな、あんなのと」
カイザーが後ろのハンスに向けると、はわわとした表情になった。動作はとろく、頼りない。弱々しい印象だ。
「カイザー」
「ひゃあ」
ヘルムートがハンスの隣に現れると、ハンスが慌てて教科書やノートを床に落とした。
「なんだぁ、ああ、お前かよ」
ヘルムートがちっ、と舌打ちした。
「ひぃぃ・・・」
さっ、とハンスが慌てて、カイザーの後ろに隠れた。情けない奴、と友人達がささやく。
「ヘルムート、何のようだ」
「ラクビーのし合い、見に行こうぜ」
ガタガタと震えている。カイザーの方にしがみつくハンスは完全におびえていた。
「駄目だ」
「水曜日の午後からだ、その日はお前も外出ができるだろう、俺とデートしよう」
「駄目だ、その日は討論会の打ち合わせだ」
「さぼればいい」
むっ、となった。
「プライベートな用事が多いお前と違って、俺は忙しいんだ」
「むう・・・」
「長身の男がむくれるな、気持ち悪い」
「では、来週の火曜日、校内で2人で馬に乗るのは堂だ、2人が駄目ならお前のセバスチャンをつけてもいい」
「・・・・」
「・・・あ、あの、デーアさん。カイザーも予定があるから、その、争うというか、困らせることは」
「ああ?」
「ひっ」
5
ヘルムートはカイザーの一番がいい。
「ハンス、カイザーから離れろ」
「・・・・ご、ごめんなさい」
カイザーは、無理やり話そうとするヘルムートとハンスを見る。
「何で、お前みたいのがカイザーと一緒にいて、カイザーに気に入られるんだ」
「・・・ええと、その」
「男ならはっきり喋れ」
「ごめんなさい・・・」
しがみつく、頼りない腕。
「ヘルムート、ハンスに突っかかるな」
「カイザー?」
言われて、確かにいつもは気にしないタイプのハンスを自分が気にしてることにカイザーは内心戸惑った。だが、ヘルムートや友人たちの言うように、そんなことでハンスを区別したくなかった。
ハンスに同じような人間と思われたくなかった。
「こいつは俺の友達だ、そうだろう、ハンス」
「えっ、・・あ」
ハンスがヘルムートとカイザーの顔を見る。
「カイザー!」
カイザーはハンスの腕をつかむ。
「行くぞ、ハンス」
「あの、目立つから、一人で歩けるから、カイザー」
ガラの悪い男達との付き合いや県下、お金のトラブルに電話越しに言われ、カイザーは心を揺らしていた。理想や地位を求める父は誇り高き貴族の顔以外に、賭け事がすきという家族を困らせる必要がある。
「はぁ・・・」
中庭で社会の教科書を開きながら、堂対応すれば言いか、カイザーは頭を悩ませていた。
「また、家の問題かい」
「叔父上やセバスチャンがいるから、父も変名行動には出ないと思うが」
「やっぱり、心配?実のお父さんだから」
カイザーの表情が曇る。
「誕生日に帰るんだろ、実家」
「・・・・ああ」
母や妹は・・・・、そう考えた時、司祭の格好をした従者の心配性の青年、オリバーと自称カイザーのお庭番ディディが通りかかる。
二階にはカイザーに突っかかり、トリマ気をつけた美少年の下級生、フランシス・ルーカスの姿がある。
・・・・自分の周りは以前に比べると騒がしくなった。表情が柔らかくなった、と友人が増えたことにクラウスたちは喜んでいる。父との確執、後妻の母と幼い妹。恵まれた環境。周囲には自分は孤独でなくなった。
そう思われている。・・・・トラブルや悩みの種が増えた気がする。
カイザーは大きくため息をついた。
友人達と夜の校舎を歩いていると、旧校舎がカイザーたちの前に現れる。
「行くぞ」
「ああ・・・」
ヘルムートとディディ、オリバーが思い鉄の扉を開ける。オカルトや怪談話は信じないが、冷えた狭い校舎にカイザーの心は揺れる。
「怖いか?」
普段はふざけているくせに、こういう時だけまじめになるんだから調子がいい。
「ついてくるのは勝手だが、俺の邪魔するなよ」
「素直じゃない」
「カイザー様、ディディもついていますぞ」
「ディディ、暗器や鎌は持っていくなよ」
オリバーが先頭に、ランプも持って、歩く。
「行くぞ、カイザー」
カイザーはほっと胸をなでおろす。
「ああ」
その様子にヘルムートはむっとなった。
6
寄宿舎、新校舎の洗濯室。
寮の中で人の出入りが少なく、狭いスペースの中で、ジーくべるとはここ最近の怪談話やカイザー・クラウドに対する悪質な嫌がらせ、狼の鳴き声を照合して、まとめたものを書類に持ち、封筒に入れていた。
「つまり、生徒の郵便物は寮長と監督せい、クラス長の中でも月の一定数は超えておらず、目立った郵便物は東西南北の領にも届けられてないんだ」
昼間のジークベルトを知る者が見たら、ぎくりとなるだろう。南館から出入りしたジーくべるとのかたには黄色い粉のようなものがついていた。
几帳面で外見をそれなりに手入れしている、神経質なジークベルトには珍しい。
「西館は二週間、郵便物や外来の客人に、生徒の父母や兄弟以外はいない。君が外に出て調査している間、権力主義でスパルタ主義の3年担当の体育教師の遊び場に変化した」
「ゴールド、卿に君の部下を」
「余計な気を回さないでクレよ、リーダーの許可は得ているのか」
「貴様・・・、隊長に何を・・・」
ジーくべるとの部下の一人が、ヴォルフリートに掴みかかる、
「手を離しなさい、ゴールド」
「ですが、こいつは貴方の・・・」
氷のような、機械の目をした、冷え切った瞳。一ミリも眉は動いていない。
「卿は、仕官生でチームの大切さや銃の使用の意味も理解している。君は僕の指示を聞いていればいい」
「出すぎたマネを、すみません」
「・・・・」
「校長や理事長は何と?君のことだから、入った段階でもう聞いているんだろ」
「口は災いの元―・・・彼らは強欲な割に小心者のようだから、自分の領域からわざわざ出て、鉄の玩具も甘い薬も夜の花も一切やらないそうだ、北館と西館で馬術大会の賭け事をしているんだろう」
ヴォルフリートは不快感を出した。
「・・・悪い、ジーくべると」
「いや、僕は気にしていない、君は賭け事は嫌いだったな、君の前では避けるべきだった」
気を使っているつもりなのだろうか。
「・・・いや、毎年馬術大会は生徒の不敬も含んだ上流階級や金持ちが大勢で着て、その中にはせいとの将来につながる有力者が成績のいい生徒に援助するのが慣わしだったな。出るのは馬術は勿論、勉強やスポーツ、評判のいい生徒だとか。・・・ジーくべると、君はカイザー・クラウドへの悪質な嫌がらせをしたであろう生徒を揺らしてくれないか?」
リストをジークベルトに渡す。
「私は構わないが、いいのか?管理官にまた鞭でたたかれるんじゃないのかい」
「構わない、目標が姿を見せないなら、目標が今興味を持つカイザーを餌にして、表に出す」
「お祭り騒ぎの日に人は気は緩むものだ。怪奇現象は彼が領に戻ってきてからだったね。わかった、君のその考えに乗ろう。卿、日を起こすのは自由だが後始末は卿自身がするんだ」
「・・・了解」
朝の朝礼で、徹夜明けのカイザーは、睡魔と闘っていた。教会の中央には司祭とオリバーの姿がある。低血圧なカイザーには朝の眩しい光がきつい。
・・・結局、幽霊は現れなかった。
・・・・なんだったんだ、あの短い時間は。
ふう、とカイザーは息をついた。
「カイザー・クラウド」
学園の中で一番大きい図書室の螺旋階段の途中、円状の本棚に囲まれた階段の途中、乗馬用の制服に身を包んだカイザーに友人二人を連れたジー区ベルトが話しかけた。
「聞いたよ、馬が暴れたんだって?」
穏やかで柔らかい微笑み。カイザーの体に緊張が走る。
「ディディ君、また、君かい」
「カイザー様は具合が悪い、用事があるなら、まずはこのカイザー様のイチの子分、ディディ様に言ってもらおうか」
くしゃり、とした表情になる。
「困ったな」
柔らかく、優しい声。黒髪に眼鏡。周囲の視線もジーくべるとに信頼しきった視線を向けている。
「ディディ、いい」
「カイザー様、無理に立ち上がられては」
「大丈夫だ?それでブッシュバウム、俺に何の用事だ?」
「・・・君はいつも僕に対して険のある言い方だね・いつも言ってるけど、もう少し穏やかにしてくれないかな。成績が近い同士、君とは心地いい関係でいたいんだ」
清らかで澄み切っている。よどみなど一つもない。心からそう思っているのだろう。
「・・・用件は」
「いや、来月の委員会、僕は出席できないと担当のポール先生に伝えてくれないか」
「それなら、君のクラスの奴に」
「頼むよ、クラウド」
7
嵐が抜けた後、カイザーはランプを持って、月明かり、教会の近くを歩いていた。不気味だった、このところの相手チームの嫌がらせや家柄を妬む一部の生徒からの嫌がらせがぴたりと止まっている。
視界の隅で、洗濯籠を持ったハンスの姿を見た。
・・・・こんな時間にこんな場所で。
洗濯を?
不自然だ、とカイザーは思った。ハンスはすぐに寮の中に入っていった。
問いただすか、だが、・・・・・明日でもいいか。
カイザーは空を見上げる。
ワォォォ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ン。
「!?」
カイザーは身構える。別の方角からも同じ泣き声がした。身体がざわつく感じがした。
・・・・犬?
だが、泣き方が違う。この啼き方はまるで。
「馬鹿な・・・」
自分らしくない、何を非現実的なことを。
その時―ー
突然、背後に気配を感じて、カイザーは振り返った。寝付けなかった、それだけなのに。
まるで、鏡で反対にしたような、片方だけが違う色、そのオッドアイが驚愕に見開かれる。
「なーーっ!?」
胸元に、ダイヤのマークがついた漆黒のマントの少女。
その口の中には、吸血鬼のような牙が生えていた。フードの間からファースト・フロスト、グレー色の長い艶やかな髪が見える。仮面はオーがを思わせた。
暴力的な、美しい、女神のような少女。だが、それ以上に驚愕させたのは、少女が牙をむいていることだ。混乱がカイザーの体を硬直させる。
その一瞬が駄目だった。少女の牙が、カイザーの首筋に深く突き刺さった。
「ウ・・・・・ああああああああああああっ」
痛みがカイザーを襲う。だが、単純な痛みは一瞬で、その後は、目に見えない何かが、記憶やデータが、情報が進入してきて、精神を犯されていくような、得体のすれない恐怖。カイザーの意識は、闇の中に落ちていった。
同時刻、馬車の中でマリーベルと話していたアリスの身体が急にがくんと倒れる。
「!?」
「どうしたの、急に・・・」
「・・・・!??・・・わかんない、急に身体が・・・」
「足が震えてるわ、・・・・何、病気?」
マリーベルが心配そうに、アリスに近づくと、アリスの首筋に吸血鬼に咬まれたような、痕が現れた。
「アリス、貴方・・・首」
「・・・・・なに、急に・・・・・首・・・・・?」
アリスが自分の首に触れると、咬まれた後が浮き出ていた。いきなり、現れたのだ。そして、睡魔がアリスを襲う。
「・・・・・え・・・・・あ」
「アリス?」
ことん、とアリスが急に落ちた。アリスの身体が床に落ちる。
「え・・ええ・・え?」
マリーベルがアリスの体をさすると、アリスは寝ていた。
「・・・寝てる?」
8
朝起きたら、鏡の中にアーディアディト・フォン・ヴァルベルグラオがいた。
何事だ、と思って目を開けたら、見慣れない少女趣味の部屋に寝かされていた。令嬢が寝ていそうなレースや布やら、人形やらが置かれた女の子らしい部屋が。見慣れない長身の眼鏡のメイドに起こされた。クール系美人のお姉様だ。
「朝食になさいますか?それとも、台本を読みますか?」
何を言ってるんだと思いながら、洗顔しようと思い、隣の部屋に向い、洗面台の前に立つ。蛇口をひねって、顔を上げると、少女が覗き込んでいた。
年は、一つ上。輝くような金髪に愛らしい顔立ちにピンク色の唇。すっとした鼻梁に白い肌。美女というよりは美少女という言葉がふさわしい。
すぐに以前あったあーディアディトという少女であることはわかった。ただ、アリスと呼ばれる少女は自分に対して、酷く戸惑っているように見えた。
当たり前か、・・・これが現実かどうかは別にして、朝から見知らぬ男と鏡越しとはいえ、接近遭遇しているんだから。どうしよう、と思った。カイザーは朝が起きるのが苦手な上、クセ毛で寝癖がつくので、朝は大抵加味への対処に明け暮れている。
・・・トリックなのか。
昨日の夜のことは覚えていない。目の前の可憐な少女が現実のものとは思えない。
寄宿舎と彼女のいる部屋がなんらかのマジックで鏡でつながっている。技術的に手間はあるがありえないことではない。というか、カイザーは無理に今の現実に説明付け用としていた。
混乱する頭を整理しようと、不法侵入の疑いがある酷くおびえたようにも見える少女を前に、カイザーは流れる水に手を伸ばした。
すると、鏡の無効でも同じ動作をしていた。
「は!?」
カイザーが寝泊りする南館は日当たりがいい。一番、日当たりのいい奥の一人部屋で生活をしている。任務で潜入して、偶然彼が在籍をしていることを知った。彼に関わるな、トアリスの実の父親に言われていた。だから、カイザーに関わった後も正体がばれないようにアルバートに任せて、自分は夜だけ起きていたのだが。
扉を開けると、ジーくべるとがカイザーをなだめていた。
「・・・・・?」
ライバル関係のはずだが、そう思いながら、いつもいるはずのディディやオリバーの姿がないことに気付いた。
「ジーくべると、オリバー司祭は?」
「今日のカイザーの予定は病欠でキャンセルにしてもらっている、授業にも欠席だ」
「・・・病気って」
その時、ヘルムートが飛び込んでくる。
「カイザー、大丈夫か!?」
どけといわれたので、道を譲ると、ヘルムートはカイザーの肩をつかんだ。
「カイザー、熱はあるか、具合は!?」
「・・・っ」
「顔は赤くないが、どうした、腹でも痛いのか!?」
?いつもてきぱきしている駆れらしからぬ鈍い反応だ。だが、ヘルムートが肩を揺らし、大丈夫かと叫んでいると、いきなり平手打ちした。
「触らないで、誰なの、貴方!!」
キッ、トカイザーが睨む。ヘルムートはびっくりしている。
「・・・・カイザー?・・・お前」
「出て行って、早く!!」
カイザーが状況がつかめず、近づくヘルムートにモノを投げつける。
「止めろ、カイザー、どうした、頭にウイルスでも入ったのか?」
「誰よ、カイザーって!!」
「・・・・・デーア君、ここは僕と反すに任せてくれないか。カイザーは昨日の深夜から酷い風でね、頭が参ってるんだ」
「風邪?でも言葉遣いが」
「カイザーの親友だろう、それなら・・・ね?」
爽やかにキラキラしている。便利な仮面だ。
・・・・・噂では、女優をしているとか聞いているが。
偶然かな、と思いながら、鏡を見ると、アリスも口をハ、と形を作っていた。
悪い予感がよぎる。
いやいや、落ち着けよ、俺は将来議員か、さらに金持ちになる男だ。これくらいで動揺してはいけない。しかし、何事も確認が必要だ。
カイザーは恐る恐る、頬に手を伸ばした。パニックになりそうな心臓を押さえつつ、今度は右手で掴む。やはりアリスもつまんでいた。
予感は確信に似た思いになる。まさかまさか、もしかして、もしかして、アレはこれなのか。一度目を閉じて、深呼吸をする。一回、二回。心の中で唱えながら、息を止める。そして、力いっぱい、右の頬をつねった。
「いててててて!!」
絶叫して転げ落ちる。鏡の向こう側の女の子も転がる。起き上がり、自分の体を見下ろす。底には、巨乳と行かないまでも美しい女性らしい、豊かな胸が存在していた。
「ひいい!!」
カイザーはアリスになっていた。
「お姉様?」
扉が開き、車椅子を引いて、フィネが現れた。
芸術をサポートするドイツ系貴族であり、大家族の一員であり、だが過去は養子であり、アルベルトと兄弟であり、ローゼンバるツァーの組織に裏切り者の烙印を押されて父は処刑された。だから、レジンスタンスを支援する立場を持った。
「・・・・ごめんなさい、その火傷はおじい様が」
「アロイスに合うために戻ってきたのに」
「アリス」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ゲーム日記
- 商品到着【2025/09/18】
- (2025-11-29 00:10:07)
-
-
-

- 一口馬主について
- ロンパイア出走予定(11/29東京8R)
- (2025-11-28 23:32:36)
-
-
-

- 何か手作りしてますか?
- 良いお天気だというのに・・・・ミシ…
- (2025-11-28 23:04:10)
-
© Rakuten Group, Inc.