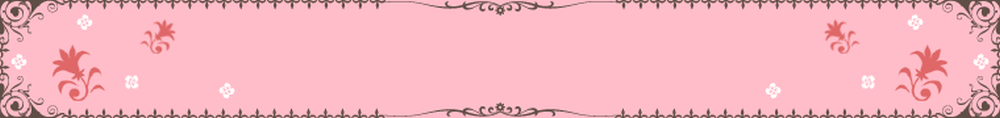第15章世界中で愛を叫ばない
「君のその能天気な頭が羨ましいよ」
「何よいいたくないの」
「僕にそんな暇はないよ、それにどこにいるんだ」
世間の女性は小さいころからそういうのが好きだ。理解不能だ。10歳ということもあるが、聡明なアリスなら自由にそんな真似できないのわかりそうだが。
「・・・孤児院の家族?」
アリスはきょとんとなる。
「そうだよ、アーディアディト」
「でも、エリクはそんな笑い方しないわ」
―永遠なんて、ないのに。
ダークブラウンの少年は去っていくローザリンデを能天気な笑みでお見送りながら引き裂かれそうな胸の内でそう語った。
炎の記憶は今もずっと縛っている。
「-なぜ、助けられたのにまんま、あの男を施設内に入れたんです?」
警備隊長の男は漆黒の闇の中、まだ12歳ほどの、いやそれよりももっと下に見える子供、少年に恐怖を怯えた。
「やめるんだ、こんなことしても君の兄弟は帰ってこない」
「院長が国政に、あの時の事業に絡んでいる可能性があったから?そのお金で村を救えたから?」
「…犯人は分かっているなら警察に」
「ただの若い警官一人にあんな、子供の顔を悪趣味な化粧させることが事故に見せかけることができると?単独の個人的な突発的な犯行なら、なぜエリクたちの死体を他の領地に移したんです、ただの村人で孤児なら近くの墓場でもよかったはずだ」
「…エレク、その背中・・・」
アリスは戸惑いながら、かばったエレクの背中を目をそらしつつ言葉を紡ぐ。
「誰にやられたの」
優しい、おとなしげな純粋な少女だ。本当に心から心配してるんだろう。
「私はあなたを信じます」
「馬鹿な」
「死ぬ気か」
アリスは前に出る。
彼は最大の反逆者であり、犯罪者であり、罪人だった。
ゴォォォォ・…ツ。
崩れ落ちる建物、かける黒衣の男、扉が乱暴に開ける。
炎に包まれた室内の中央に、使い古された軍服に漆黒のコートを着た男がいた。廊下には、彼の母親や妹、多くの銀の十字架の精鋭部隊が血だまりで倒れていた。
男の声が震える。
「お前さえ、お前さえいなければ・・・ッ」
なぜか、来るのがわかっていたように男はほほ笑んでいて。風で男の胸元からひび割れた十字架が現れて、揺れた。
「アリスを、この世界をお前に奪わせない・・・・!!」
「―そうだな、お前と俺の戦争を始めようか」
男は手を広げて。
「断罪を、おれたちの裁判を――、決着をつけよう」
「さあさあ、言ってみろ」
「言っておきますが、適当とかその場しのぎとか駄目ですから」
「姉さん、ルドルフ様・・・」
助けを求めるようにローザリンデをみる。
「ルドルフ様」
反対にいるルドルフをみる。
「楽しみだな、どんなセリフで女性をお前が酔わせるのか」
何そのロイヤルスマイル。
僕がモテるなんて思っていないのに、、なんだ、その態度。絶対零度の笑みで現実の残酷さを教えたのは君だろう、ルドルフ様。
「僕…11歳なのに」
うう、ああとか繰り返しながら、そばかすの少年は。
僕が言っても寒いと姉さん、いつも味方してくれるのに、なんで。
「何でいつも私だけ見ていればいいっていってくれるのに」
「貴方が妖精で天使で太陽でギリシャ神話のアポロンより輝いているのは当然だけど、貴方は王子様やホストになる才能があるから!」
いや、指差されても。
「姉さん、この前は田舎くさいとか言ってなかった?」
「さあ!」
じりじりとアリスが木側にヴォルフリートを押し付ける。吐息が届きそうな距離だ。
「言葉になんて表せないよ」
そんな表現力ないし。
視線をそらしながら、
「どういう意味ですの」
何故って僕が口下手なのは知っているだろうに、僕にそんなコミュニケーション能力ないぞ。
「君という存在を前にして」
いつもがみがみ、キ―キ―言っている怖い君の前にして。女性、女性している相手は苦手だ。
「僕みたいな存在がたやすく気分を酔わせる言葉を言えるわけないじゃないか、君が素晴らしい女の子なのはわかってるけど」
女性を口説くなんてできない。友達多くて、しっかり者で行動的で男前でうらやましいけど、そんな相手の気分をよくさせるなんて。
「僕なんかがほめなくても君は最初からお姫様であることは皆が知っていることだし」
視線を戻す。
「え、何で皆顔をそらしてるんだ?」
顔が赤い、風邪だろうか。
いらいらする。
奴当たりなのはわかっていた。ただ、宮殿にはいない目で見られるのが、負けを認めるのが怖かった。あいつは嘘をつかないで、本当に自分を心配してくれただけだ。
「僕に触れるな!」
「でも、僕は平気だ!」
「大丈夫じゃないじゃない、早くお医者様を」
「一人で戻れる」
父上たちがいる前で、最悪だ。みっともない・…。
意識がふらつく、たくさんの人がいる中で、階段を下りていると、足元を滑らせて、中段のフロアに落ちそうになった。
「あ・・・・」
貴婦人たちが冷たい目で嘲笑うように見ていた。
「やっぱり」
「エリザベート様は陛下を・…陛下の子なら、ねぇ?」
かぁぁとなる。
その時、腕を掴まれた。乱暴で無作法な、子供の手がルドルフの体を引き上げた。
「危ない、大丈夫!?」
「え・・・」
肩をつかまれ、自分の方に向かわせた。
「よかった、あと少しで床にぶつかるところだったですね、ルドルフ様、痛いところはないですか?」
「下がれ、ヴァルベルグラオ」
違う、こんなことを言いたいのではない。ルドルフは素直になれない自分の性格を恨んだ。
「ここはお前がいるべきところではない」
だけど、こうしたいい肩しなくては、ルドルフとしてはやっていけなかった。振り返ると、ヴォルフリートが目を見開いていた。
「何故、お前がここにいる」
甘えや架したい気持ちと、彼を咎めたい気持ちがルドルフの中でせめぎ会う。
「私にはお前は必要はない。立場をわきまえろ、退け」
じろり、とルドルフが睨むと、一瞬、戸惑ったものの、やがて、納得したのか、大人しく頭を下げて一例をした後、ヴォルフリートはヨハンに挨拶をして、上司の元に返っていった。
・・・・自分勝手なものだな。
「いいのか?」
「・・・ここで引き下がるなら、その程度の存在だった。それだけだ」
「そうか」
ヨハンも何もいわなかった。
・・・なんて、無力なんだ。ルドルフはこのとき、自分の生まれを恥ずかしく思った。頭を下げることが出来ない王族の生まれを。
列車での占領事件の後、深夜召集された軍人の中には、ノア少佐たちの姿があった。
・・・・父上・・・いや、議会のお抱えの特殊部隊か。精鋭が揃えられた遊撃部隊で帝国内の情報を集める諜報部隊とも、暗部とも言われている。具体的な人数は把握はしていないが、優秀な仕官生を何人か、後方支援として実技訓練といって連れて行っている。
軍で変わり者とも、エースとも扱われるエドガー大佐とノア少佐。出身の地区で動くことを決められる帝国軍人だが、彼らはそういった条件ははいじょされている。そのためなのか?
彼らが使い捨ての駒、有益な駒。部隊の数に数えられないのは。
その中に、ヴォルフリートはいる。彼が自分に情報を流しているのは、不穏分子や自由主義の人間など様々だ。その中には、異能者の起こす事件もある。
アリスはリビングでため息をついた。フィネは不思議そうに、姉の横顔を見ている。
前から行動を深く考えずに、誰にでも懐くというか、ある意味ではその行動が裏ましイが、弟の軽はずみな言動や行動は、自分の起こす問題以上に複雑さを本人の無意識で生んでいるのだから頭が痛い。
「はぁ・・・・」
「お母さんに怒られたの?」
「いや・・まぁ」
はぁ、とヴォルフリートはため息をついた。
「通りがかりの子がカタコトで暇つぶしに付き合ってくれるかと聞いたら、いいと答えたから暇つぶししただけなのに。言葉はドイツ語だからいいじゃないかよ」
すねた。
「でも、中には変な人や怖い人もいるかもしれないし、お母さんも心配になると思うよ」
「でも・・・」
「強情なんだから」
アリスは仕方ないな、と声を出した。
「姉さんはどうなの?」
「え?」
「言葉や姿が違うだけで、遊んではいけないと思うの?同じニンゲンで同じ子供だよ」
意味のない言葉だろう。
「私は、私だって、本当は仲良くしてみたいと思うわ。でも、・・・私には難しいわ、言葉無難しいし、ヴォルフリートはあの子達の言葉、わかってたの?笑って、話してたけど」
自分と違う文化を持ち、言葉を持つ。当たり前のことだが、アリスには苦手意識がある。だが、弟は?
村に住んでいた時だって、自分と同じように、クロアチア人やセルビア人の他国の人間を見てきたはずだ。見知らぬ人間が怖くないのだろうか?
ヴォルフリートも目や動作でむらの中の子供にいじめられたことがある。
「近づいて、怖くないの?」
教育を受けておらず、畑仕事やにもつ運び、基本的な言語しか習っていない環境だった。
「・・・・怖い?」
「言葉はわかってたの?」
「ううん。でも、手の仕種とか表情で何となくわかったかな、相手に敵意はなかったから大丈夫かと思って」
「ヴォルフリート・・・」
「・・・ア、ごめんなさい、姉さん」
思いつきの気まぐれな質問だったかもしれない。歌手という夢のことで両親ともめて、一時的に家を出ていたときに、ヴォルフリートは尋ねた。
「・・・姉さんは、貴族の今の両親をどう思っているんだ?」
「どういう意味?」
「理由はどうアレ、姉さんを捨てた人だよ・・・その、家に戻ってきたからって、自分たちの事情で連れ戻そうと思うのは変じゃない?」
アリスは目を見開かせる。誰にでも優しい温厚な弟が他人に対して批判じみたことを言うのは珍しい。こういう質問をぶつけてくるということは。
「・・・・ヴォルフリート、貴方はお母さんやお父さんを恨んでいるの?」
「本当の両親と思ってるよ・・・優しい人たちだと思う」
「それなら・・・」
「だからこそ、理由も聞かずに姉さんの夢を反対することに違和感を感じるんだ」
真っ直ぐな弟の目。
正直に言えば、母が歌手という職業に対して偏見を持っていることは違和感があった。美しく穏やかで時々活発で、自由で。
ショックだった。大好きだから理解して欲しい。けれど、両親にも譲れないものがあるんだろう。
けれど、アリスにも譲れないものがある。
「受け入れていけばいいの」
「え?」
「きっと私が今ぶつかっていることは、私にとって必要なこと。これは、私とお母さんたちとの戦いなのよ」
だからこそ、証明しなければいけない。
「今日、来てくれたことは嬉しい。ヴォルフリート」
アリスがヴォルフリートの手を握る。ヴォルフリートは頬を緩めた。
「貴方が私のこと思ってくれていること、私わかってるから」
「・・・姉さん、出来るだけ無理はしては駄目だよ、姉さんは夢中になるとすぐ周りが見えなくなるから」
「気をつける・・・」
ふふ、と笑いあう。
もしかして、ルドルフ様は姉を嫌っているんだろうか。アレは好きな子を苛める男の子の現象で、それが度を濃すぎて、嫌っているように見えているだけだと思うが。
「酷い・・・。私は殿下のために」
「こんな、うらまれることまで助けたのに言われるなんて」
頭を抱えながら、塔の階段を登っていく。
奥の奥の頑丈な扉の間から真っ白な手がひらひらしていた。エルネストは気付かれないように、物影に隠れた。
「アンネローゼ、久し振り」
グルルルル・・・。
ヴォルフリートは扉の前に座り、その白い手を優しく握った。傍目から見たらホラーの領域だ。
ガリリッ
頬を引っかかれた。
「駄目だよ、見てみなよ、この頭の包帯や目の怪我、治ってないんだから。乱暴は駄目だよ」
ガリガリッ。
さわさわさわ・・・・。
長い真っ黒な髪が扉の間から広がって伝っていく。
「もう、僕だって忙しいんだよ、そんな子といっても」
ガタンッ。
「いったーっ、入場拒否?酷いよ、友達が会いに着たのにその態度!!はぁ?だから、ひと科しかなれないって!!」
ザリザリ。
「アンネローゼはおてんばで凶暴だな。猫じゃないんだから舌で舐めないんだよ、地味に痛いんだよ」
髪の毛がヴォルフリートの足にからみつく。
「わかったよ、僕が謝ればいいんだろ」
ガタンッ。
「入るよ、アンネローゼ」
ガタン。扉が閉じられた。
「・・・・・・・・・・」
ホラーだ、何と話しているのだ、彼は。
「ええっ、ちょ、ちょっと、裸だったの?服、服!!」
「タイム、タイム!!のっかかってこないで!!」
「プロレスごっこは服着てから!!あ、噛まないでくれ!」
アンネローゼの声が聞こえた。
「おばかさん・・・」
扉が閉じる瞬間、白い身体がヴォルフリートに絡みついていた。
2
それはまるで魔女のサバとのようで。でも、いじめられて、つながれていたのは、悪とされたはずの同胞、異能者やデーモンだった。鬼のはずの異形の少年からは涙が流れ、鬼じゃないはずの慈善活動かは彼らから血を吸い、童話の中の吸血鬼のように吸っていた。
膝から力が抜けていく。身体中から血が抜けていく。
サーッ
ごぉぉ・・・ん。
「・・・・見てしまったんだね」
振り返ると優しい父、レオンハルトの姿があった。赤い目の少女は明らかにその顔を恐怖に染めていた。
どうして、彼女が父を?
「お父様、彼らが、彼らが・・・助けてください、これは・・・・明らかに虐待です!」
ヒュウウウ。
「・・・・・なぜだい」
地の底から響くような冷たい声。冷たい瞳。
「彼らはただの道具じゃないか?」
指から力が抜けていく。
「・・・・お父様?」
「見てしまったからには君にも、力を貸してもらうよ」
「・・・・・え?」
バドォール伯爵家の玄関にすぐに見える、ユリアの肖像画の前でヴォルフリートはいた。幼少期の母親との娘時代のものらしい。
「貴方に似ていますでしょう」
「アヴィスか、急に後ろにたつのはやめてくれよ」
「…申し訳ありません、それでは、坊ちゃん・・・当主が二階のリビングでお待ちです」
隙がないなと思いながら、ヴォルフリートはついて行った。表向きの従者やディーターをつれて、ヴォルフリートは上がっていった。
「大丈夫なのか、ヴォルフリート」
「何が?」
「この伯爵家、オヤジの知り合いだけど、結構悪いうわさが立っているんだぜ」
そそ、と口に手を当てて、ディーターがささやく。
もう一度、ユリアの肖像をみる。
・・・・・確かに少し似ているけど、美人だよな。
「よくお越しになりました、ヴァルベルグラオの子息殿、ブッシュノウムの子息殿、バドォール家の当主、ジ―クヴァルト・バドォールです」
つえを持って、優美な仕草でジ―クヴァルトが出迎える。
「今日は私の夜食の誘いをよく受けてくれました」
シスターアテナこと「騎士」のダンサーは、気まぐれでわがまま、感性で動くタイプだった。ダンサーの名前は紅のナイチンゲールと呼ばれる、イタリア人のミラーナ・ミケランジェロ。高い所に乗り、征服宣言するのが彼女の基本である。正面から名なしの魔王、ルドルフに立ち向かう。
「さぁ、ショーの始まりよ、雷撃の坊や」
イタリア語の流暢な口調で言われた。オレンジ色に似た茶髪、派手な化粧、露出気味の衣装。彼女のナイスバディな体は、ライトアップされている。場所は、この世ともあの世とも着かぬ第3世界。
「私たちの戦争を始めましょう」
零体魔双を纏った、白銀の騎士。軽快なステップがコロシアムの床を揺らす。鈴の音が鳴り響き、彼女はサークルを持ちながら、鈴を鳴らす。天女の羽衣のような薄い布を広げながら、名なしの魔王に襲い掛かる。
彼女には、友情や家族、恋人を奪う覚悟がある。ふざけた口調の中に確かな信念。彼女が望むのは、現在の持続。今の世界が続くことだ。
「空っぽの心か」
「貴方は私を革命できるかしら?」
戦いと踊る時こそ、彼女の感情が生きる時だ。
いい感じ、最高。しかも相手をしているのはいい男。いい男といい女が相対し、お互いの全てを見せ合う。何て最高なの。魂が燃え上がるこの瞬間。ああ、何て最高なの。人間同士の恋も、肌を見せ合い、命を掛け合うこの瞬間には叶わない。相手が強ければ強いほど、心がときめくのはマゾかしら?さぞかしら?
でも、引っ張るのは私。世界を動かしているのは私。何て、最高の舞台。この子の魂はどんな甘い声や悲鳴を私に聞かせてくれるのかしら。強い相手を自分の手の内に支配したあの瞬間。
どんなものにもかなうことは出来ない。
空間が捻じ曲がり、馬が現れ、ミラーナは騎兵のように飛び乗り、仮面をかぶる。槍を持って、コロシアムを走りまわる。
ゴゴゴゴゴゴ・・・。
コロシアムの外では鎖につながれたオリバーやヘルムート、アーデルハイト、エルフリーデの姿があった。
駆けるのは、毒で動けなくなった彼らの命とルドルフのプレイヤーとしての永久放棄。列車の後、突如この空間に呼び出された。王者たるもの、国民の命を守らなければならない。氏名以上にこんなふざけた手段をとる彼女にルドルフは怒りを感じずにいられなかった。
ズキン・・・。
「革命家」・・・エレク・ビーネアイトを追い詰めたというのに。
3
帝国内と外でも、今の時代、あちこちに争いの火種はあった。支配者と被支配者。特権階級と庶民。司祭と科学者。だが、同時に様々な芸術や技術が生まれたのも19世紀末問い言う時代だった。ヘレーネ・フォン・フランメクレーエは家柄に誇りを持ち、自分こそが正当なローゼンバルツァーの正当な後継者だと自負していた。幼い頃からラインハルトとライバルとして競い合ってきったことも、お互い、忌み嫌っていることも影響しているのだろう。
「まあ、お父様のご容態が・・・・」
「ええ・・このところ、肺のほうの調子が悪く・・・・」
「それでは、すぐに駆けつけなくては」
ヘレーネの瞳が炎で揺れる。お側月のメイドは揺れている。サロンを開き、華やかな生活を送る一方で、上流階級に生まれたものの宿命か、ヘレーネの稀少がこういったとき、いっそう激しくなるのを。彼女は一度怒りだすと、相手が手を引くまで決して、恫喝を止めない。その激しさや恐ろしさはお側月の自分がよく知っている。
長兄のラインハルトに負けたくない。
その考えは幼い頃から何の代わりがない。
「ヘレン、髪結い氏と新しいドレス、香水を用意して頂戴」
「お父様には、最高の自分を見せなくては」
同じコンラートを父に持つドロテアとマーリアは既に控え室に控えている。
「待ってくれよ、ヘレーネ」
「この愚図、さっさと荷物を持ってきなさい」
夫のランスが大きな荷物とバックを背負って、後から小太りの体を揺らしながら追いかけてくる。
「ヘレーネが早すぎるんだよ」
「ふん」
扇を翻して、ヘレーネは階段を上っていく。
「ディートリヒは確か、寄宿舎に戻っていったそうね」
「期末テストですって」
「去年、風邪をこじらせて入学が遅れたとか」
「まぁ・・・」
遠縁の親戚の貴婦人たちがささやき会う。
「相変わらず綺麗ね、ヴォルフリートはどうしたの?」
棘があるように聞こえるのは、気のせいだろうか。
「今日は宮殿に呼ばれていて・・・・」
視界の隅に、ディートリヒの姿がある。味方だと求めるように見るが、ディートリヒは冷たくアリスを睨むばかりだ。ライバルとしての考えが彼をそうさせているのだろう。強気なアリスはせめてもの抵抗ににらみ返す。
「そう、残念ね。せっかくの独特なあの顔立ちを見てみたかったのだけど」
「彼はエリザベート様に気に入られてますから」
「あんな田舎臭い庶民を何故、あのお方は気に入られているのかしら」
「お母様、ですが、ヴォルフリートのベートヴェンは捨てがたいですわよ」
かばったつもりなのか、ブリジットに睨まれると、言葉をなくし、ブリジットの後ろに隠れた。病弱で取り扱い中尉の少女は、こうした集まりでも、本当に年に一回くらいしか会わない。エルネストの手を握る美しい黒髪の少女は心配そうにあアリスを見る。
「・・・」
奥手なカイザーは慌てて目をそらす。
「今回はバレエダンサーやオペラ歌手も読んでいるんですって」
「まあ、素敵ですわ」
貴婦人が話しながら、カイザーの横を通り過ぎる。
始まるまでは、時間がある。
「セバスチャン、行くぞ」
「はい、坊ちゃん」
「庭を歩く」
森の中は閑散としており、小鳥のさえずりが聞こえた。
「眩しいな」
「ですから日傘を持つようにと」
「黙れ、お前は主人の俺に命令をする気か」
「そんな」
「黙って、ついてこい」
カイザーはすたすたと歩いていく。セバスチャンも慌ててついていく。しばらく歩いて、別の家の屋敷が見える。忙しいラインハルトは人が少ないこの場所を住居にしたのはこの静けさだろうか。
そう考えた時、森が抜けて、様々な花が咲き誇る花園が姿を出す。庭師もいるからラインハルトの持ち物だろう。
そんな時、オルゴールの音が聞こえた。
「何だ、この音楽?」
「は?音楽?」
「聞こえなかったのか・・・」
カイザーはその音がしたほうに歩き出す。
4
アリスが後からこの家に入ってきた時、ヨハネスは彼女を受け入れなかった。
「確かにこの懐中時計は我が家の紋が施されているが、お前が我が家の人間で、あの恥知らずの娘、エレオノーるの娘である証拠はない」
「お父様、何てことを」
エレオノーるのうでの中に、アリスの姿があった。大広間の中にはヨハネスに構えるレオンハルト、ディートリヒの姿、使用人の姿があった。
勿論、ヴォルフリートはアリスを弁護した。その真剣な姿にアリスは自分を思ってくれると胸に暖かいものを感じて、ディートリヒに疑いの言葉を向けられ、刃物のような目で見られて、涙目になってもなおも、娘であり血のつながった家族だという、正面から自分の為に当主のヨハネスに言葉をぶつける。
「野蛮なこと・・・」
「言葉も拙いし、発音も聞けるものではないわ」
「それに何なの、あの奇妙な目は。あの緑色の片目なんて気持ち悪い」
なんてことを、キッとアリスが睨むと親戚の貴婦人は押されたのか、数歩下がった。ヴォルフリートは物心つく頃から、ゲイ件のことをアリストは違う意味で注目された。村の子供達に狐つきとか、呪われた子だといわれた。アリスはそんなやからを一人残らず、正面から立ち向かっていったが。
「・・・・詳しくわかるまで、下がっていなさい、エレオノール、お前もそれでいいな」
「お待ち下さい、お父様!」
「私は忙しい、お前たちの問題はお前たちで片付けなさい。それの教育は、お前に任せる」
床に叩きつけられ、冷たい視線を浴びるヴォルフリートを一度たりとも見なかった。アリスを冷たく見据える。
言い返すことのできない、自分がいなくては生きていけない弟。優しい弟。エレオノーるのそ場に身をおきながら、アリスはそばかすがある弟の横顔を見た。
「ヴォルフリート、大丈夫?」
「ねえ・・さぁん」
「早く、顔を拭いて、立ち上がりなさい、私の息子だろう」
柔らかくも厳しい声で、レオンハルトがヴォルフリートに手を差し伸べる。レオンハルトの顔を見た後、周囲に視線を向ける。父の優しさに気付いたのか、ヴォルフリートは立ち上がる。
「・・・ごめんなさい」
アリスはそっと、優しくその肩に手を差し伸べる。ヴォルフリートが柔らかく微笑む。
「だらしない、これが僕の兄だとは」
ディートリヒはため息をついて、部屋を出て行く。
「?」
扉に向かう時、ディートリヒがアリスに視線を向けた。見据えるような目を。アリスには視線の意味がわからなかった。
アリスは、宮殿に上がる時、ギーゼらの遊び相手として、ルドルフの喧嘩友達相手として、レオンはルトから口々に言われていた。
「これは特別な待遇なんだ。だから、アリス、皇帝陛下一家にはくれぐれも失礼がないように」
心配性な父は、ギーゼらたちにおてんばな娘がなにかしないか不安なのだろう。
「大丈夫、ちゃんと心得ているわ」
「まあ、お前はそうだな・・・ヴォルフリート」
ヴォルフリートの方が揺れる。
「・・・は、はい」
「お前もだぞ」
「・・・がんばります」
妙に距離があるというか、親子に先に鳴っているのになじんでいないのだ。優しい父はいつも、男子でディートリヒと同じく、家督を継ぐ立場のヴォルフリートを気遣っていた。
背が低いヴォルフリートとルドルフはちょうど背丈が同じくらいだ。優秀すぎる頭脳を持つルドルフはギーゼらの話では、宮殿内でヴォルフリートを放置状態にしていたらしい。
「アーディ亜ディトの外見や正確はあのコ好みだと思うんだけど、あの子、愛情表現ひねくれてるから」
「確かに・・・」
「何だ、お前か、またヴォルフリートのお守りか、姉上のわがままに付き合いしにきたのか」
じろりと見た後、けんか腰に話しかけてきた。
「相変わらず、知性を感じさせない顔だな」
「こら、ルドルフ、女の子になんて子というの」
「ふんっ」
「アリスがせっかく来てくれたのに」
「こいつが勝手に着ただけだ、僕は頼んでない」
本当に嫌な奴。アリスはそう思った。
「大体、その格好は何だ、仮にも貴族の令嬢が」
「これは動きにくいから上着を脱いだだけで」
足から頭の先まで見る。ふん、と意地悪で美しい笑みを浮かべる。
「う・・・」
この笑顔はアリスは苦手だ。
「君の場合、中身を先にする方が先じゃないか?フランス語オール赤点のアーディアディト嬢」
アリスの顔が怒りで赤く染まる。
「なっ!!」
「年下の戯言だぞ、まさか本気で怒ってるわけではないだろう」
5
宮殿の長い廊下をひょこひょことした足つき、優雅で洗練された歩きで、ルドルフとヴォルフリートは歩いていた。あたまをばしばし、叩いて、嫌味を言ってるのだろう。意地悪な笑みを浮かべている。
「本当、憎たらしい奴・・・」
クスクスとギーゼらが笑う。
「あのコね、昨日言ってたのよ、アリスは唄や演技はすばらしいって」
「え、ええ?」
「民族的な唄は趣味じゃないけど、アリスの唄はすきだって」
「信じられません・・・」
「今日だって、貴方とヴォルフリートが来ると聞いて、そわそわしてたのよ」
「それならそうといえばいいのに」
「あのコ、貴方がうらやましいのよ、環境的にあの子は素直に感情出せないから、最も自分の方がうまいって言ってたけど」
「君、馬鹿なんだね」
翌日。憎まれ口で挨拶された。
「こんなものを読めないなんて、これだから庶民上がりは」
「く・・・っ」
図書館で、エリアスやハインリヒ、側に本を読んでいるヴォルフリートをつれながら、ルドルフがいった。
「そんな君にこれを貸してあげるよ、貴族の子供が最初に読む本だ」
「え・・・」
幼稚園レベルで書かれた礼儀作法の本だった。
「ルドルフ様、姉さんに失礼なことは」
「ああ、君はいいんだよ」
ルドルフとは当初、喧嘩友達といった感じで、ルドルフは従者のようにヴォルフリートを連れて、いじって、からかって遊んでいた。
昼下がりのある日。
「どこを気に入ったのかしらね、ヴォルフリートの」
「え?」
「貴方のことは可愛いし、歌も歌いし、貴重な喧嘩相手と思っているみたいだけど。ヴォルフリートは臣下みたいな扱いのようで、違うみたいなのよ」
「といいますと」
「あのコ、ちょっと苛めすぎるから、どういう存在なの、使用人なのかといったらものすごい剣幕で怒ってきて、あんな感情的なルドルフは実の所、初めてなのよ」
「私に喧嘩を売って、軽口叩いて、カインベルク卿のコにも」
「本人には違うらしいの、理由を言えといっても全然言ってくれないし」
アリストルドルフの関係が変わったのは、ルドルフに呼び出され、日記帳を見せられた時だった。
「・・・・その、何だ、僕もずっと君に喧嘩を売って、大人気なかった」
酷く、たどたどしい。
まとうようにルドルフが、弱気な表情でアリスを見てくる。
「?」
「・・・・これを」
日記帳を渡される。
「中身を見ろ、手紙がある」
開くと、一枚の手紙がある。
「見ていい、から」
「で、でも」
「見て」
「・・・・」
手紙からでてきたのはブローチだった。ルドルフには似合わない天道虫の姿を出した青い宝石の。
「・・・・母上がくれたんだ、どう思う?」
恐らく、ここが彼なりの友情の形だった。
「それは、僕にかな、姉上にだと思う?」
「不恰好ね、ギーゼら様にはにあわないかも」
「え・・・」
ルドルフの白い指が止まる。
空気を読めばよかった、後になってそう思う。
アリスが顔を上げたとき、ルドルフは以外にも傷ついた表情をした。だが一瞬だ。いつもの大人びた表情になっていた。
「・・・・え?」
「ごめん、そうだな、姉上には上げないようにしよう」
「ルドルフ様?」
6
「殿下、お待たせしてすみません、エリーゼ、大丈夫か」
「エリーゼ?」
「はい、オルフェウス様」
ゆるりとほほ笑む。
翌週、とあるお茶会でカインベルク卿の子、ジークハルトに呼び出された。
「ルドルフ様に何を言った」
「え・・・」
「あいつ、傷ついていたぞ」
ザァァァ。
「え?」
教会の中でルドルフは侍従も連れずに佇んでいた。
「気にしてない」
「でも・・・」
「昨日、母上の連れ添い殻電話があった。アレは、父上に送ったものだそうだ」
「え・・・」
「あの人らしい、すまないな、変に気を使わせて」
「・・・・」
「もう言っていいから」
「ごめんなさい、ルドルフ様」
ルドルフが笑顔を浮かべる。
「・・・いいんだ」
「受け入れてしまえば」
その時、扉が開く。
「すみません、殿下、ヴォルフリート様が・・・っ」
胸がざわついた。がやがやと大人が入ってくる。
「馬から転落して・・・」
アリスが隣に顔を向けると、ルドルフは走り出していた。
「・・・・いてて、あ。アーディアディト姉さん」
包帯を巻いていた。頬にはガーゼがある。
「ごめん、僕、ドジをしたみたいだ。頭から落とされて」
「アーディアディト・・・?」
「頭を少しうたれたようで」
看護婦が答える。
「大丈夫なの、馬から落ちたって」
「・・・・・・誰に乗せられた」
「え?」
アリスが振り返ると、冷たい表情でヴォルフリートをルドルフが見ていた。
「違いますよ、殿下」
「これは今日来ていたお客様とヴォルフリート様が」
墨で貴族の子供達が顔を引きつらせていた。
「・・・お前タチか」
「・・・すみません」
「・・・・・ヴォルフリート、お前は注目されやすい。僕のそばか、姉上の側に色といぅたは図だ、何故持ち場を離れた」
「それは・・・」
「お前たちの親には厳重注意させる、それでいいな」
15歳のヴォルフリートの部屋にアリスが入る。
「・・・え」
バンソウコを張ったヴォルフリートの傍らに、ルドルフが寝ていた。だらしなく唾液まで出して、足を広げている。それに対し、ルドルフは胸に顔を預けて、寝ていた。
まるで母猫の側に寝る猫のように。
「ザッハトルテ三箱はきつい・・・無理だって」
右手に口づけをしているようにも、片足をヴォルフリートの体に絡めているように見えた。まるで神聖な儀式のように眠りながらルドルフは自然に寄り添い、寝ていた。
「カッターナイフは禁じて、禁じてだよ、リング」
・・・弟は何の夢を見ているのだろうか。
噴水前で、アリスが泣いていた。
「泣かないで、姉さん」
「だって、だって・・・」
ぽんといきなり薔薇を出す。
「え」
「姉さんには笑顔が一番だよ」
7
お忍びで療養地に着ていたルドルフは、従者つきであったものの、森を散策中マリーベルと話す機会があった。アリスやアレクシスはからかうような笑みを、エリア巣は心配して、動揺していた。その周囲を、フォルクマやハインリヒ、近衛隊や皇族月の軍人達が警護に当たっていた。
アリスは空を見上げる。
「空が荒れてる・・・、雨になりそうね」
とまぶしいものを見る気持ちで2人の背中をアリスは見送る。
「行かせてよかったのか?」
「数分だけでしょう、それくらいの時間なら自由にしても」
皇子様だって息抜きは必要だ。
「・・・・アーディアディトがきになりますか」
我ながら、しおらしい声を出していると思う。隣に歩いてるのがルドルフ様で、このオーストリアの皇子様で、将来は帝国を背負って、エリザベート様のように、皇妃を貰う立場で。
「いや・・・」
美麗な横顔だ。立っているだけで王者の風格と気品がある。穏やかで知的で、時々冷たくて、どこか寂しそう。
こんな特殊な現状でなければ、話すことすらできない高貴なお方。今、隣で歩けるだけでどれだけ、贅沢で大変なことなのだろう。
「・・・・」
胸の奥が熱く、甘くときめく。
「今日は少し空気が乾いて、すっきりした青空ですわね」
「そうだな」
マリーベルに続いて、ルドルフが顔を上げ、微笑む。儀礼的な、作った笑み。細い肩。mだ、少年なのに、この方の背負っているものは私のもつものよりはるかに思い。
「森林浴というわけには行きませんが、殿下の日常や最近、興味をもたれていること、できれば、私目に教えていただけませんか?」
愛らしい、女神のようなスペシャルな微笑。ルドルフの曇った心を照らすには豪華すぎるものだ。
「・・・だが」
「私では不足でしょうか?」
しゅん、とした気弱な声にルドルフは慌てる。
「・・・負担になるかもしれないが」
「私がそうしたいのです」
酷く、作った声だ。演技がうまい問う言うことはプラスになるが、素直な自分を出せなくするのね。マリーベルはそう思った。いつもはあんなに自分は自身が会って、傲慢なこともいえるのに。
ゴゴゴゴ・・・・ザァァ。
林の中でマリーベルは花畑の中、ルドルフと世間話をしていた。
嵐が来た。
「マリーベル嬢」
「はい」
「行こう」
ルドルフはマリーベルの手を引いて、一行が待つ場所へ戻っていった。
雨が激しく降った。
休憩小屋で、ルドルフはルドルフを迎えに来たハインリヒや侍従と話し合い、マリーベルは隣室で濡れた服を着替えることになった。扉越しにアレクシスに聞いた。
「アリスの姿が見えないようだけど、どこに」
「それが途中で突貫工事があって、服を他の軍人と一緒にぬらしてしまってな、なんだっけ、フォルクマ杜か言うあの銀髪美形と別の場所で着替えに言ってる」
「・・・ああ、彼、なかなかいいわよね」
「変な家だよな、いる子供が皆美形ってのは」
「・・・層ね、確かに奇妙だわ、ア、覘かないでよ」
「・・・・安心しろさすがの俺も元鹿野の裸の賊ほど、落ちぶれていないぞ。あいつは姉好きのシスコンだからまずないなぁ」
「殿下、どこに」
「アリスを迎えに行く」
マリーベルの胸がざわめく。
やっぱり、殿下はアリスを。
浮いていた気分が急に沈んでいく。
「マリーベル、どうかしたのか?」
「・・・あんたに関係ない」
「ふうん?」
アレクシスは首を傾けた。
虹色に光る世界で、褐色に近い温かな大地の色を宿したくせ毛がちの髪、優しい青空とエメラルドグリーンの静けさと高貴さを宿した瞳、日に焼けた肌。華奢な、少女のような体型。整った、彫刻のような顔立ち。
その声は雲雀のように美しく、どこか清らかで力強く。ぴんと張り詰めたような、まっすぐな背中。
「・・・・すまない、変わりの紅茶持ってきてくれないかな」
戸惑ったような表情で不思議なオッドアイの瞳を目の前に座るアヴィスの主人であるジ―クヴァルトに向ける。小さな、少女のような中性的な容姿、人形のような顔立ち。眼帯と灰色の髪。子供と思えない冷徹な瞳。冷たい美しさが12歳の少年に漂っていた。
納屋にアーディアディトを閉じ込めた。
「貴方達は自分の立場をわきまえず、国の未来である殿下にけがを負わすところだった」
扇を手の中にしまいこむ。
「特に貴方は出しゃばりなようだから、一晩そこで寒い思いでもして、頭でも冷やせばいいと思うわ」
扉をアリスが叩く。
「ヴォルフリートは、ヴォルフリートは無事なの!?」
「自分の身が危険なのに、弟の心配?優しいこと」
意地悪に美しい顔を扇越しにゆがめる。
納屋の中で少女が信じられないといった表情でヘレ―ネをみる。
「どうして、私達、叔母さまに何もしていないのに」
何もしていない?この少女は本気で言っているんだろうか。
「どうして、信頼や愛を裏切るような、こんなひどいことを」
「さすがはお優しい殿下の親友であられるアーディアディトはお優しいことを言うのね、優しいエレオノ―ルがそんな戯言を教えたのかしら?彼女、いつもそうだもの、庶民と共に過ごすべきと女学校時代から人を陥落するのが得意だったもの」
「開けてください、お願い、弟にヴォルフリートに会わせて!!」
ヘレ―ネは背中を向ける。
「自分たちの今の立場が何えなりたっているのか、よく考えることね、皇妃さま主催の狩猟には私や息子が出るわ」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 何か手作りしてますか?
- ハムスターの革人形を作る その140
- (2025-11-19 19:53:17)
-
-
-

- FXデビュー!!!
- 今月は自慢できるほど稼いでもないし…
- (2025-11-16 21:10:09)
-
-
-

- 動物園&水族館大好き!
- 千葉市動物公園 風太くんお散歩タイ…
- (2025-11-20 00:00:09)
-
© Rakuten Group, Inc.