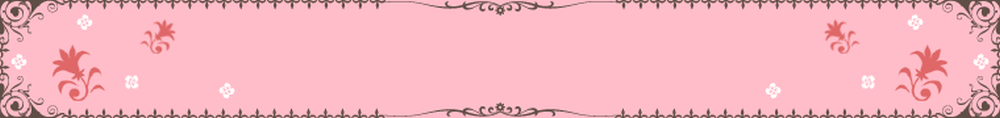第32話―正直者の偽善と悪
大嫌いだあの男。
ヴォルフリートはそう言える。
親友、いつか消えたら。
親友、いつか超えれたら。
ルドルフは思う。
―何というか、墓地のようではある。
最初は拾いだとか別世界だが、人間、いすぎると慣れてしまうものらしい。どこも同じなのだ。一番の強い人がいて、弱い者がいて、卑怯なのがいて。
自分がうとまれている、あるいは恐れられているのは姉さんの横にいる時、気付いた。とはいえ、そうそうルドルフの誘いを断ることはできない。
ここではずいぶん、えらい。当たり前だが彼は一番の責任が9歳で背負っている。正直村にいる時も、国家の父だの、麗しの皇妃ダの利く、皇太子も聡明だの将来が期待されていると聞いていたが、正直リアルさがない。だって、普通、一生かかわらない存在だ。会ったこともない、王族にどうして他人にどうして思いを抱けるのか、まあ、一つは僕は男だが軍人や警察が、先生とかが苦手で、大体怒られてきたからだ。大体暗い顔していれば、まああこがれない。威張る貴族や金持ちを見てれば、彼らも彼らで豪華な生活の代わりに喧嘩ばかりしている。ともかく、宮廷という場所では、尊敬され、傅かれている王子様は病弱で癇癪持ちで、女子的には高慢さもきゃあだが、エリアス卿もうっとりでみんなルドルフに崇拝していて。
国民である僕達も皇帝たちを崇めるよう、教えられるのだが、うん、ごめん、僕は無理。だからまあ、友達がいないんだけどな。
「しかし、ルドルフ様の家に他人がいるって変ですね」
「・・・・はぁ?」
何で神経質な野にこの人、僕を傍に置くんだろうな。連れてこられた理由は何かわかるが。死んでいた人間。そこに偶然この国の王子様が。でも僕何も見てないんだけどな。
さらにわからんのが、僕が名門貴族の子息という超展開だ。
「毛虫とかさわってどうするんだ」
「集めて、世話して、庭にリリースするの」
「楽しいか、それ」
まあ、家にいると空気扱いされるよりは。後、あのお母さん苦手。
「まあ家にいると勉強だの礼儀作法だのダンスとか、剣とかうるさいから勉強ッて無意味だよね」
「お前のためだろう」
ああ、そうあの美人のママに教育されたのか。
「ルドルフ様は楽しいの?」
「義務だ、僕はお前達の王になるんだから」
「ああ、それで外国から美人のお姫様と結婚するんだ、ならいいね」
確かにルドルフ様は僕に優しい。公私を分けて、いつも暗い顔してこの国のために勉強し、期待にこたえ、でもかかわるうちにアリスは姉さんはかわいそうだと言った。
「可哀想?」
「だって、まだ10歳よ、友達と遊んで、お母さんに甘えてもいい年なのに」
姉さんは家族というものにあこがれていた。ルドルフと知り合ううちに彼の異常な生活に暗い顔を見せるようになった。
「・・・」
わがままな王子様は姉さんといる時、いやな奴、意地悪な年下。知識を自慢してくる。「もう熱もあるのに無理して」
「うるさい・・」
アイスはルドルフに手を添える。
「心配しているのよ」
「悪い・・・」
姉さんは頭がよい。てきぱきとしている。正直言っていることの半分がわからない。
そんな二人の傍は、正直苦しい。イライラする。
「よいですか、貴方とあの方は違うのです、立場をわきまえ、適度な距離感を」
姉さんはまた女官に注意されている。家だと優等生だと姉さんの天下だが、ここではルドルフ様がメインだ。
「ああ、貴方は行っていいですよ」
「ヴォルフリートぉ」
泣きつかれても。
「弟に甘えてはなりません、そもそもレディーとして、あなたは・・」
くどくどとされている。
そのまま廊下に出る。確かに貴族といえど、ただの子供が宮殿を自由に歩けるのはおかしい。かって、エリザベート皇妃が来た時も、伝統と歴史の宮廷では騒がれたという。何百年の歴史、外国の親戚たち。
くすくすとした笑い、蔑む目。立場もわからぬ愚か者。多くの視線が無遠慮に投げられる。二階に行こうとすると、視線を感じた。
顔を上げると、軍服の優男。気高き顔立ちのルドルフの父が見ていた。だが興味はすぐに目の前の謁見した相手に移る。香水が鼻腔をくすぐる。
―猿が。
貴婦人の女性達、つまりは一日は皇妃がいるということだ。
「どきなさい、ミルクが運べませんっ」
「は、はいっ」
いきをついて、女官たちを見送ると、宮殿の奥に向かう。
「うえっ」
そもそも虐められるというのはある意味怖がられて、関心を持たれることだ。連れてこられたのが僕が先と行っても何かの事情だと切り捨て、本当のお気に入りは姉だと宮廷の人間は思っている。生まれやらにうるさい人達だ――どっちも事情があるとはいえ、母にも父にも祖父母にも似ていない、本当に不幸な僕には関わらないようにしていた。先日の儀式でも、斬り裂いたのは貴族たちではない。宮廷の使用人だ。オッドアイが不気味だと言ったのは、最悪な性格の貴族たちではない。多くの民族や純粋なここの生まれの人間も多く、エリートなのだ。
・・・どうでもいい。
扉を開く。
「ルドルフ様、まだ用事が」
扉の間から現れたのは日に焼けた少年だ。大きなオッドアイの瞳の純粋な目。ダークブラウンの髪。着ている服は上物なブラウスに革の上着だ。ズボンは上着に会わせて落ち着いたダークグリーンとしている。
・・・こいつがルドルフの友達?
傲慢不遜、優等生の嫌ないとこが傍に置いている奴?
「・・・知らない顔、お客さん?」
「悪いな、帰って・・・」
10歳か、11歳くらいか。年の割には背が低い。それにかなり痩せている。
「僕、家に戻ります?遊べないのは残念ですが」
だがルドルフは「そんなことない」と慌てて駆け寄った。
「無理しなくていいんですよ、ルドルフ様は忙しいんですし」
「問題ない、今日の予定は全て終わったからな」
すると、そいつは大きく目を見開いた。
「・・・・あの量を?ああ、何か途中で君のファンだってお姉さま方がくれたんだけど」
ヴォルフリートはルドルフに手紙やら嘆願書やら重要な機密の書類を渡された。
「あいつら、ヴォルフリートは使用人じゃないと言えば、何度」
はぁぁとため息をついた。
「悪いな、ヨハンお兄様、失礼するよ」
ルドルフは一見いつも通り、クールそうだが実に楽しそうだ。
「本当にいいんですか?というか多いですけど、これ魔法の呪文か何か、うわ、数字が多い」
「そうだな、お前にはわからない、魔法の呪文だろうな。僕もわからん」
嫌な笑みだが、俺に関する笑みとは違う。普通にすればあれは不敬罪だ。あいつの趣味は分からない。あれのどこがそんなにそばに置きたい奴なのか。ギ―ぜらいわく、家庭教師がいる時も、同じ部屋に椅子ですわらせているとか。弱みも見せず、言うならば面倒な奴だ。皇帝陛下いわく、ルドルフの小さなわがままだと許したとか。正直邪魔だと思うが皇帝の考えはわからない。
以外と優秀か、才能があるのか?
「よかった、ルドルフ様がいて」
「また問題があるのか、年上のくせに」
「ノンノン、友達に年齢も関係ない、兵隊の人形、今日こそもらいますよ」
「姉上にお前が勝てるはずないと思う、お前は馬鹿だからな」
「大丈夫、僕には未来の王様がいますから、字も算数も出来てすごいな」
「まあ、そうか・・・すごいのか」
英国の宮殿。どこもかしこも不穏な空気、不況だ。だがき飾り階級社会の人間は見下ろすことでごまかそうとする。
「あれがアーディアディト・・・」
周囲がざわめく。
「気にすることはない・・・」
ルドルフはそういうが、金髪の青年、アリスの弟だ。
「お人形遊びがそんなに楽しいかしら」
甘い、小鳥のさえずりのような声。周囲が少しざわめく。女王の娘、アリスだ。
「綺麗な公園でしょう」
「え、ええ」
「ねえ、アーディアディト、ヴォルフリート、貴方にこの国はどう見える?」
アリスは困ったようにヴォルフリートを見る。
2
きっと、能力も容姿もすべてが違う。違うからこそ、ひかれあうなどと姉さんの読む物語ではそう。けれど、自分の心を閉じている、こんなにも距離がある人間に、近付いてもおそらく傷つけあうだけの相手にどう愛せというのだろう。
本物の関係なんて、ぼくら三人にあるのだろうか。
踏み越えた先、その先が明るい未来なんて、なんであなたが言えるのだろうか。
―寝ている。
「・・・ヨハン、何の用だ」
何で誰も追い出すか、注意しねえんだよ。
「何、宮廷にようがあってな、本当にお前の部屋にあいつがいるのか」
「別に邪魔にはなっていないだろう」
まだ公務の最中か。
「一応聞くが、何のためにお前の勉強に部外者を巻き込んでいるんだ」
ルドルフが意味がわからないと言った風にヨハンを見る。
「文句でもあるのか」
部屋の片隅でヴォルフリートは寝ている。実に能天気で馬鹿そうだ。
「いらないリスクは止めろ、ヴォルフリート自身も迷惑だろう」
「何だ、今日はずいぶん素直だな、何か企んでいるのか」
「あ他、お前が公にわたくし事を入れていると俺も同じ目で見られるんだよ」
ああ、と頷くがすぐに目の前の紙に視線を戻す。
「お前は国を自分の個人的なことのために揺らがせるつもりか」
「大げさな、こいつはそもそも孤児だった、教育も受けていないやつだ」
「・・・ふん、ずいぶんお前、ただの平民に肩入れしているんだな」
ルドルフが顔をあげる。
「皇帝に友達なんていない、お前のせいでこいつが死ぬこともあるとは思わないのか」
ふぁぁぁ、と大きくあくびをする。
「・・・・・寝すぎた、・・・ああ、大公様か、おはよう」
きょろきょろと見ている。
「あれ、ベティ先生は?」
「もう、いない、お前は授業の途中で寝るのは止めろ」
よく見れば、黒板のようなものを持っている。青空教室ではない、断じて。
「だって、歴史だの処刑だの、何年だの、死んだ人のばかり聞かされても、生きるのに歴史とかいらなくない」
「お前みたいなのが僕の国民だと思うとすごく不安何だが」
だが、優雅さや気品もかけらもない、ついでに低能らしい馬鹿そうな少年は。
「お前、皇帝陛下の許可はあるんだな」
「はい」
少年は頷く。
「ここにはどういう理由で置かれていると聞いている?」
「えーっと、未来の王様には様々な人の視点が必要で、息子には社交性が必要で、息子の教師として、あるいは別の立場の者として支えてほしいとか、後、お傍づきとして無茶しないように世話してほしいとか」
「世話してるのは僕だがな、大体お前は他人の世話よりもお前自身を何とかした方がいい」
ああ、反面教師か。
「失礼な、三日に一度はお茶をかけなようにはなったよ、ローラにもほめられたし」
すると、メモ帳を取り出し書き始めた。
「ルドルフ、あれは」
「父上の侍従や大臣あたりがあいつに日記のようなものを書くよう、命じたそうだ」
利用されてるだろ、それ。
なるほど、一応体裁というか、後継ぎの傍に置くよう便宜を図ったのか。
「ああっ、そうだ、昨日の13時8分にルドルフ様、また熱出したのに医者呼んでないっ、僕が怒られるっ」
ちなみに書かれている内容は、覚えたての丸い文字で日記、その日あったことや余計なもの、知らない顔や食べたい店のことが書かれていた。
知らない派手な装飾や異国の人間やら、おそらく気になったことを細かく書いている。ルドルフといる時間のことだが、それ以外も書いている。見たことのない銃や軍服の肩のデザインやら。外国のお菓子を独占している大人が羨ましいだの。
まあ、子供だし、まとめて書けという方がおかしい。ただ絵日記は止めろ。
「しかし主義者が多いですね」
「革命とか、全く暇な奴らが」
本当にため息をつきたいのはこっちだ。
「誰のためのパーティーなんだか」
ゴットヴァルトは、会場の片隅で壁の花を決め込んでいた。
「おいおい、今日の主役が一人か?」
趣味の悪い香水、露出度の強い女性を連れて、エドガーがやってくる。
「これから戦闘に行くのに遊ぶ気分じゃないですよ」
女性達の視線が否応なく感じる。
「だから早く決めろよ、その方が周りも大人しいだろ、好きな子でもいるのか」
「僕はもう跡継ぎでもないのに」
だが、エドガーは笑う。
「それでもお前はあの人の息子だろ、それに諦めきれないんだろ、お前使えるし」
「愛してもいないスペアを?」
夜の風をあたりにバルコニーに出る。王宮近くを借りなくてもいいのに。
「はぁ・・・」
この前は驚いた。何だって、この国の皇太子があんなおふざけをしに来たのか。父や周囲に知らせると、面倒だから言っていないが。
「皇帝陛下は国家の父か」
つまりはあのイケメンが次の王で、細かいことは他の人が動かしてるか。人数が多すぎる。それに見てる方向もばらばらで。
・・・できれば、あの王子様とは戦いたくないな、勝てないし。
「ここもよく知らないし、知り合いも少ないし」
田舎の小さな事件は揉み消されて。エリク達の関係者はもう面倒ばかりか、放任主義で。いい加減諦めて、生きるべきか。
「うーん」
革命を起こすとか、でもこの前も軍のお偉いさんが飛ばされたし、時間も人数も。アーディアディトは・・・、彼女にはもう迷惑はかけてはだめだ。
「悪い、君、アルバートを呼んできてくれ」
「アルバート様は旅行中です」
またか・・・。
アリスとは昔にわかれたきりだし、あっちももう覚えていないだろう。
周囲が、女性が色めきだつ。
「やあ」
「ああ、アウグスティーンか、相変わらず派手ですね」
年上のはずだが、外見が変わらないんだよな。前は司祭で今は軍人か貴族化の実家で戻って、貿易系についているというが。
「アルバートはどこだい」
「僕が知るわけないでしょう、何か」
悪い人ではないが、どうもつかめない。
「年上の女性はもう怖くない?」
「もう時効でしょう、13歳の時のことなんて、細かい男は嫌われますよ」
3
司祭様見たいだなと、アウグスティーンとアルバートを見て思う。
「何か怖いわね」
「マリ―ベル、来ていたのか」
なぜ、こんなおふざけをするのか。
「皆不安何だよ、最近物騒だから」
街中に、サルヴァト―ル大公と軍人がいた。
「行くぞ」
「待ってくれ、兄さん」
公園のベンチの隣の彼女はどんなつもりだろうか。
「皇太子がイギリスに」
「ええ」
金の美しい髪が揺れる。
「意外だな」
「え?」
「君が僕を覚えていたことさ」
困ったようにありすは笑う。
「ヴォルフリートも君も僕のことなんか忘れていると思ってた」
「私は大切な人は忘れないわ」
今思うと、奇妙だった。
「君たち兄弟は目立つもんな、随分と大人っぽくなったね」
「あなたもね」
「君が貴族の奥さんか、時間が流れたんだな」
・・・。
「ヴォルフリートは、どんな様子?」
「変ったわ、いろいろと」
それは不思議な。
「あんなにシスコンだったのに」
ありすは同じ目の色と同じ青い空を見上げる。
「・・・正直、わからないわ、前はあんなに近かったのに、王宮に来てから、ここにきてから、一緒にいることが少ないし、ルドルフさまとも・・・」
踏み込みにくいな、それ。
「何というか、この前お会いしたけど噂とは違うな」
「え、あなたが?」
「ああ、もう少し常識人とかクールな印象だったけど、意外と行動はというか」
「まあ、確かに最近は前に比べれば・・・」
その日、軍内にいるときに皇帝に逆らったという皇太子のニュースが流れた。
「誤報じゃないか」
「ただの親子喧嘩とか」
「なんか、軍の作戦に参加するらしいぞ」
4
写真を見てもこれぞという人はいない。今回大きい作戦だからと身内が不安になったらしい。まあ、僕の所属する隊も参加することになったわけだが。
「はぁ・・・」
女性の写真を団扇代わりにする。
「人生の墓場か・・・」
街でもあるこう。まあ、どこも革命だのなんだので暗い顔多いし。
きゃっ。
「あ、すまない」
考えすぎて、前の幼女に気付かなかった、後ろからボーイフレンドか?
「もう、前を見なさいよ」
「ごめん、ごめん、ドレスに泥がついちゃったな」
安物のハンカチで大丈夫かとふき取り、ほこりを払い、それでは立ち去ろうとする。
「待ってください」
「何か」
偉い大人びた子だ。
「実は友達と二人で買い物に来たのですが、と・・・大人の人とはぐれてしまって、ご付き合いできませんか」
「はぁ?」
そのあと、高級な専門店に行き、靴や福屋ら、菓子を買い、どうも貴族の子のようだ。
マリーという少女は僕の手を離さない。難しい顔だが、嫉妬だろうか。
「この辺りはよく来るんですか」
「いや、派手なところは苦手で」
何やら驚いた顔をされるが、そんなに驚くことか。
「何ですか」
「いえ・・・・、意外だと思って」
「あはは、僕はそんなに遊び人に見えます?」
「どちらかというと振り回されるタイプに見えますね」
つぶれた店が目に入ったらしい。僕の反対の手を握る、男子が。
「まあ小さい店はつぶれるもんですよ」
「どんな不幸があったのかしら、せっかくいい場所なのに」
いい奴だな、この子、わがままだが。
「・・・ええ、上は何しているんでしょう」
「お父様が変えるわよ」
「マリーさまは侯爵か、政治家の娘なんですか」
大臣の娘かな、なんか命令するのに慣れているし。
「軍人さん、子供のためにお恵みを」
「はいはい」
ちゃりんとコインを箱に入れる。
「?」
何やら男子が不思議そうな顔をしている。
「なんでお金をあげるんです」
「ああ、ミルクが最近高いから、貧乏っていやですね」
5
「聞いたか、今回の作戦、皇太子殿下が考えたらしいぞ」
「へぇ・・・」
「まあ、いれ知恵はあのローゼンバルツァーだろうけど」
「おまえが」
「何のことでしょう、私はただ友人のパーティーに来ただけですが」
ヨハンはアウグスティーンをにらむ。
上官とルドルフの前にゴットヴァルトは躍り出て、敵に銃を向ける。
「お下がりを」
「おまえ・・・」
「皇太子殿下を早く」
「何のつもりだ」
銃を向けられるルドルフ。
「この手紙が殿下のものではない証拠がわかるまで、殿下は今の立場でおとどまりをお願します」
6
会ってもいない、ルドルフということを知らない、そんな人間のため、例えば多くの王宮の使用人、大臣、軍人、貴族、そんな人間の明日のことを考えるのは、想像ができない。ないからは想像する。
だからこそ、ヴォルフリートの見てきた世界は。
「パンの耳ってうまいんですよね」
「・・・・え、ああ」
自分に見合う人間、立場が近い人間。正直言えば、同じ立場でも、彼は大雑把に世界を見ている。食べられればラッキーで、さぼりまで、マイペースで。教会にそうそう行かないらしい。ヴォルフリートは村に孤児たち以外、友人がいないばかりか、アリスと最初から他人であることが分かっていた。宮廷では、自分のお目付け役、まあ従者か行儀見習いに来ているとか一応理由はついているが。
「砂糖とか超ぜいたく品ですし、すごいんですよ、兄弟多いと砂糖で取りあうんですよ、柔らかいパンは安息日に出るんですがそれも奪い合いで」
「そ、そうか」
エルネストにしたほうがいいという声は近くに会った。ただルドルフはヴォルフリートを近くに置いた。
「へえ、こんな石ころが」
「・・・まあ、鉱物という意味ではそうだな」
年上なんだけどな、一つだが。
「いやいや違うから、二人とも」
会えない時間は、つらかった。
孤独なんて馴れていたのに。アリスもあいつもいた。皇帝になるために。多くの国民のために。
「たかが、一人いないだけですよ」
「エリアス卿・・・」
「代わりのものならいますよ」
胸の奥が重くなった。
「貴方には彼以外にも、多くの国民も慕う女性もいます」
腕から流れる、服の下の流れる血。ヴォルフリートは自分の視線に気づき、ほほ笑んだ。
「もう大丈夫ですよ」
「・・・・お前・・・・」
その先の言葉が出なかった。いつもするする出てくるのに。
・・・・・友達が、おかしいことになっている。私の友達が。
「・・・・・信じたい?」
わからない、だが、その疑念の前にすることがある。大切にすべきはこの国の。胸が引き裂かれそうだ。私は父はもちろん、お前らを守るためにしたのだ。
「ルドルフ様、皇帝陛下はあなたを信じるといわれたのです」
本物だという金髪の美しい少年。映し鏡のように。優しく、ルドルフの心に寄り添ってくれた。
「お前達になぜわかるんだ」
我慢してきた、当たり前だと、いやではないと。神に選ばれた、役目だ、宿命だ。たとえ何と判断されようと。
「殿下も信じてほしいのです」
「何も知らないくせに、知ろうとしないくせに」
「殿下・・・・」
ヨハンが何か言っている。要求、要求ばかりだ。
「うん、実はですね、彼女ができたんです」
「まさか」
「ええっ、ひどくありません」
いちいち泣いて騒いで。
「お前は小さいことを大げさに騒ぐな」
でも追いかけてくる、絶対に。
「・・・・・いいえ、殿下は何も悪くありませんよ」
メルクでの一件。ふさぎこんでいた。
「しかし・・・」
謝ればいいのか、馬鹿で無神経で・・・・だが、傷ついている。
「本当にいいんです、もう」
――お前にとっては、どうでもいい思い出、忘れてもいいものだろう。私はお前が嫌いだった、何もかもが理解できない、都合も気持ちも考えない。手放したかった、代わりがいる存在だった。
だけど、私はお前を友達を守れない。お前の国の皇太子なのに。そばにいても慰めの言葉も知らない。頭がよくて、騙せて、だが目の前の友達がすくえない。お前は痛かっただろうに、お前も泣いていただろうに。もっといえばよかった、伝わらないとか、性格が合わないとか、あれこれ言い訳の前に。
一番大切な、お前を守れない奴が王なんて。お前の家族を見殺しにした国を、何もできない私を、僕をお前は恨む言葉もなく。
憎んでいただろう、苦しかっただろう。
「何一つ知らずに――」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- FXデビュー!!!
- 今月は自慢できるほど稼いでもないし…
- (2025-11-16 21:10:09)
-
-
-

- 寺社仏閣巡りましょ♪
- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…
- (2025-11-14 23:40:04)
-
-
-

- フィギュア好き集まれ~
- 30MM 『ARMORED CORE VI FIRES OF RU…
- (2025-11-19 18:04:16)
-
© Rakuten Group, Inc.