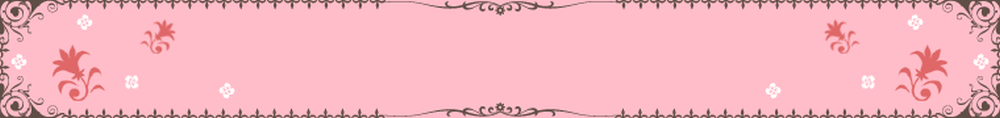第三章
ドストエフスキー
第三章―裏切りとは、仲間だったというあかしだが、少年に深淵は未だ見えない
1
「人を傷つけないのは当然だろう」
キルクスは目を丸くした。キルクスの知るヴォルフリートなら、自分の命最優先だし、何より自分を何より先にするはずだ。なのにヴォルフリートは女性をかばい、あまつさえ自分の友人たちの前に出ている。
「はぁ?」
「ふざけてんの」
イシュタルの尖兵をセシリアが蹴散らす。轟音。すさまじい音を立てて、敵を聖なる力で蹴散らす。
≪グローリーアロー≫
セシリアの得意技、百パッ百中、大天使の力を持って、敵を撃退する技だ。白フクロウの騎士団のシャンスはひくしかない。
「ちっ」
人は、習慣の生き物である。
≪ベルナール、大丈夫?≫
大地の精霊ノ―ムは愛らしい顔で自分を見上げてくる。童話に出てくる小人のような。「ああ」
―アンチ・サタン。村に来た魔術師がベルナールにいつか行った。その力は、精霊や天使と意思疎通ができること。習慣として、ベルナールは妖精の泉と呼ばれる場所で過ごすことが多い。
ー来ないで。
あの日のことは、ルージュ・アークタワーでの事故は今も鮮明にさっきまであったことのようにベルナールの脳裏によみがえる。
透明化魔法(ファントム・マギ)、魔法の種類としては新しいほうだ。17年前に、ベルナールの遠い、遠い親せきが、帝国の錬金術師であり、科学者であり、魔術師の男が、作りだした魔法だ。
実験は成功、今の妖精騎士(フェアリー・ナイト)、アスラン達も多くがそれを使っている。恋人や友人たちを助けるため、空気の精霊(エア)と同化した男。
パカンッ。
「無視しないでよ」
背中を豪快に叩く。どうやら、お客に運ぶタライのようなものでベルナールの背中をたたいたらしい。すねたような、涼やかな声だが、折れるか弱い花ではない。少女らしい高い声、大地に根をした鮮やかな花のようなアプリコットの声。ベルナールはどこにいてもその声を聞き取ることができる、それくらい馴れた声。
「アプリコット・・・」
アメジストの宝石のような豊かなウェーブヘア、長く美しい髪に灰紫の大きな目、白いエプロンにカチューシャ、宿屋の娘だ、少々ワンピースドレスのすそが膝あたりまであがっている。勝きそうな猫の雰囲気と少女らしいあどけなさが混在している。
「あんた、どうせ今日も引きこもるんでしょ、どうせなら手伝ってよ」
だがこのところ、女性らしさが出てきたので、適度な距離をおべてほしい。別にアプリコットに恋愛感情はないが、ベルナールは戸惑うことが多い。
「人前は苦手なんだ」
それはベルナールの深い闇のような短髪と紫の瞳、まじめで誠実そうな少年らしい顔立ち、着ているものも亡き父親のお下がり、この地方の男子なら着る純白のローブかかった服からも主張するタイプではないことがうかがえた。
「いいから、本なんて捨てて、うちに来なさいよ」
たとえ、どういう立場に置かれようと、生きている限り、続くものだ。
ウォーロックが二つの町を消した。場所はツヴァイトークの南西部。鉱山の町だ。けがれ切った場所は精霊もいない。冷え切った風が、ブレイヴの少年少女の間を吹き抜けていく。任務遂行率が高く、指揮能力も高く頭脳戦、近接戦、銃撃戦、剣戟。エースであり、数人の弟子たちを16歳ですでに持つが、協調性はゼロであり、他人に当たりがきつい。水と氷魔法、青の賢者の塔で短期で卒業、ランクはエトワール。魔術師であり、精霊術士。魔法剣士。
「卑怯者目が」
結果主義であり、一時的な感情で揺れることはない。ブレイヴの中では彼女にあこがれるものもいるが、同時に嫌う人間もいた。
「修行時代に・・・・」
「ああ・・・・」
「事件起こしたって」
シエラはその光景に厳しくなる。パンドラのチェス兵は不思議そうに見る。彼らは結果主義が多く、人間の正義や情を知らない。感情的な上官の振る舞いに迷惑だと言わんばかりだ。
「無法人は秩序を乱す、これは種族と関係なく守ることだろう」
「やめろと言ったのに命を何だと心得る」
するとげヒタ笑いが広がる。
「何がおかしい」
「命は勝者だけが持つものだ、負けたやつは屑、利用されるだけ、そんなにお友達ごっこしたいならママのところに帰れ、ばーか」
「馬鹿な奴め」
くくくく・・・、と邪悪な笑みをテロリスト、率いられているパンドラが銃を向けて笑う。悪党とはこんなものだ。
正義、ダヴィデはその言葉を薄気味悪いものに感じる。人に会わせるのも、人に自分の時間がとられるのも嫌いだ。自己中、薄情、その通りだ。
だが、お前らに何の権利がある。
ひねくれていた、ダヴィデ・オウルはひねくれていた。
マギア・ウォーに参加する理由はただ一つ、エリクサーを手に入れること。イフリート隊に所属するのは、エンペラーのクラスに行くためだ。
「君はあれかな、嫌われるのが趣味なのかな」
イフリート隊の上官がそういった。命令違反、独断の暴走行為、味方や他の騎士団とのトラブル、評判は悪い。いや、やればできる奴だ。
「何の事だか」
にらんだわけではないのに悲鳴を上げられかけた。だが自分は不細工ではない、目つきがほんの少し鋭いというか、悪いだけで、背だってそこそこで体も細い。戦闘能力、マナ、防御魔法も攻撃魔法も武どうも剣術も格闘術もできる。
「いいか、君は主義を捨てるべきだ」
「死ね、死ね、死んでしまえ」
「くそがっ」
「あははは、こいつよえええ」
崩れていくブレイクエッグ数体を悲しげにヴォルフリートは見ていた。まるで初めて、その現実的じゃない光景をみたように。ブレイクエッグは防御力、身体能力の高さ、回復能力の高さ、数が多いこと、使い勝手の良さで有名だ。
ペルソナが一定せず。ただ壊れていく。故にパンドラは彼らを軽く扱う。
キルクスは、そんな彼らをそば仕えにしていた。珍しいことではない。
パンドラは感情がない、そう言われていたが、ブレイクエッグ達は少し驚いた表情をしていた。もとよりレアなアイテム、奇妙なオカルト話、伝説にだらしない変わり者の王子。
帝国に来てからも、評判は悪い。
「お前は何者だ?」
短剣を押し付け、とある小国の王子と聞いていた少年が、金髪の少年に―正確にはその喉元に己の腰に控えさせていた短剣をつき当てた。
「冗談が過ぎるぞ」
声が震えているのがわかる。まるで無垢な少女のように。おびえた表情だ。
「俺がいつ冗談といった?」
軽薄さと傲慢不遜、うつけと呼ばれた灰紫の切れ長の鋭い眼光の瞳。黒髪の短髪、日の焼けた肌はエキゾチックな雰囲気を醸し出していた。
「なぜだ、俺に何でこんなことをする」
ディーター・フォン・ブッシュノウムの遊び仲間と聞いていた。キルクス・ヴィクトワ―ル・メフェケウス。
「―ロ―ゼンバルツァーだからだ」
無知や馬鹿でいられるのは幸福な環境、強いものだけだ。ただ弱いから、そんな理由でキルクスは大事な人をテロで失った。驚いた表情。
「何だ、それ・・・それだけでお前は俺を殺すのか?」
オレ・・・。ヴォルフリートなら、自分にそんな使い方はしない。
「最初の質問だ、お前、どこの手のものだ、なぜヴォルフリートの振りをしている」
幼い顔立ちの少年は激しくその時、驚愕した表情になる。
「お前、術にかかってないのか?」
「何だ、やはりそういうことか」
口調を変えてみることにした。
「は?」
「ジョークだよ、友達に赤の他人扱いされてはこういった遊びもしたくなるだろ、ヴォル」
こういうのは得意だ、嘘だらけの忠実な下僕、中のいい兄弟、気のいい民。嘘ばかりだ。帝国に加担して、自分では何もしない男が王で、父だ。
「な、。な、お前・・・」
たかが、百にも満たない人間が死んだくらいで、性格が変わるだと。ありえない。
そんな甘えん坊ならキルクスはこれほど執着しない。
「取り巻き達から聞いた時はまさかと思っていたが、お前まともすぎて薄気味悪いぞ」
ふざけて見せると、茫然とした後、にらんできた。まっとうな反応過ぎて、自分の中でヴォルフリートへの興味が薄れていく。
「国や恋人を踏み潰された恨みはどうした・・」
すると、キルクスはきょとんとなる。一瞬、おびえた表情を向けられた、え、なに。
「本当にどうした?お前が俺に関心寄せるとは、これもいつものおふざけか」
どういう付き合いしてるんだ、あいつ。だが心配そうに見てくる。
「そんなにひどいのか?」
キルクスは頷き、不安そうに見てくるのだ。
「ああ重症だ、お前という人間は、他人に関心を抱かず、嘘つきでマイペースで自己中で泣き虫で頑固で、ともかく今みたいに俺を心配するような可愛げがある奴ではない」
「へ、へえ・・・」
友達なのか、それ。
「根性も性格もねじ曲がっていて、頭がおかしい、それがお前だ」
もちろん恨んではいるがなぜそこまで追いつめられたのかが不明だが、同時にヴォルフリートのことを知らないのだ。聞いている分ではずいぶん個性が強いが。関係ない、関係ないのだが何だろう、むっとするのは。自分のことを悪く言われたようだ。
「いいすぎじゃないか、俺はひどくない」
あいつの仲間じゃないが、あいつのふりをしないとどうも周りが不安がるのだ。
「何より昨日から感じていたのだが、お前には魅力が感じられない、覇気がない、緊張感がない、お前は他人をいたぶることに喜びを感じる人間のはずだ、で、どうした、また誰かに詰られたのか?」
「・・・・私はあなたの下僕ですので」
ザファルートはヴォルフリートにいう。キルクスのもとを去ると、ザファルートの姿があり、馬車が用意されていた。
「無愛想な男だな」
「・・・・努力します」
気がきく男だと思う。何と、元々は大貴族だったという。だが戦争が起き、アルトメルデにわたり、レオンハルトに連れられて、ローゼンバルツァーの従者となった。今は帝国から貴族の地位をもらい、多くの使用人や騎士を与えられ、自分の戦闘部分の教師のような立場だが。
「質問はいいか、お前はキルクスがいうあいつを」
「五年前よりあの事件までお仕えしました」
はぁ、とため息をつく。
「わからないな、孤児から幸せいっぱいに生きてきたんだろう、素晴らしい俺の母のもとで」
「ええ」
「・・・・野心家だったのか」
「あの方は現世に何も期待しておりません」
顔を上げる。朝日が見えてきた。
「ただ、貴方には感情があったようですが」
それだけ言うと、ザファルートが黙る。
「お前、嫌いなのか」
うまくいえないが、何というか。
「・・・・右腕を切られたんですよ、ヴォルフリート様」
「それはあいつも事情が」
「どんな事情です」
そういえば、シェノルは殺せばよかった。
「ふむ」
スリエルの騎士団が動く以上、僕のせいで傾いても駄目だし。
上辺だけ装って、ごまかして、でも正直、離れてわかる。僕はあの男が嫌いだった。
自分の中のそういう怖い感情をいつも恐れていた。
「まあ、あっちも利用していたんだろうし」
そのうち、殺せばいいか。無用な殺人はだめというが、僕だって別に快楽殺人が好きなわけではない。記憶を書き換えるとか、まあ、できませんが。
雑草を手に、アマ―リエの屋敷をうろついていると、シーザーとぶつかりそうになった。
「ああ、すいま」
するとルヴァロアのランスがあわてて僕とシーザーのもとに入った。
「何をする気だ」
「はぁ?」
「怪物が、今シーザー様を襲う気だろう、冷酷なキメラが」
何か知らんがこのおっさんやルヴァロアは僕が嫌いだ。まあわかってはいるが、逆に新鮮さがないので笑ってしまう。
「やめてくれないか、俺の甥だぞ」
「偽物です、シーザー様」
うーん、乗りたいけど、今はなれるとカイザーが危ないし、かと言って、僕にお上品な貴族とか演じられないし。
「そんないい方はよせ、彼はヴァーヌスで多くの友達を失ったんだ」
ああ、そういえばそういう設定にされてたな、オルフェウスが言いふらしたのか。
「いえ、シーザー様、私はそのことは」
こんな感じかな、ええと、穏やかで優しい清らかな坊っちゃんね。
「侯爵家をだまして地位を手に入れる気だな、悪党が」
「・・・・ひどい、何でそのような悲しいことを言われるんです」
涙ぐみつつ、キモチ悪いな、そのアルバート君と思った。
「そんな軽い演技でだますな、ヴァンパイアが」
だめかー、ザファルートは割とだませたんだが。
「ですよね、ええ、僕もそんなヴァーヌスなんて言われましても」
シーザーが方を叩く。
「・・・・いいんだ、今は、今の君でいい、辛いことは思い出さなくて」
「・・・実は僕ホムンクルスでクローンでして、別人で」
「・・・・アリアは君を恨んでないから」
お前、僕嫌いだろ。
「それが、あなたの相棒なの」
シエラが元魔法剣≪スノーソード≫
「・・・・」
だが、シエラは、多くの騎士たちが投入され、自分の役目が終わったことを悟ると背中を向け、去っていく。
「愛想悪」
「噂どおりですね」
えれんはしかたないなぁと、柔らかく受け入れる。
「きゃあああああああああああああああ」
大勢の人たちとともに、悲鳴が鳴り響き、エレンたちのいるほうへ逃げてくる。
≪ギガスレイヤー≫
エレンの必殺剣が、衝撃波となり、家屋ごと魔女を吹き飛ばす。
「回復魔法・・・、精霊の力か」
エレンは可愛いなぁ、と思う。
「もう、カイザーったら」
「うーん、どこだろうなぁ」
エレン・レクスヴァリエ。フェンシング部の機体のエースであり、中等部では水泳部だった。アリシアの良き後輩でもあり、生徒会の手伝いもしている。マリアベルがアレクシス目当てかとやきもきしたが晴れやかな緑の草原を思わせる瞳はカイザーを探す。
「いつもさぼるんだから」
血が通っているのか疑いたくなるほどの白い肌、薄いブラウンの美しい髪を腰まで流し、どこか騎士のような凛々しさと少女のあどけなさを残す。
「今日もカイザーさぼり?」
「大変だなぁ」
≪フレイムラストブレイクッ≫
その瞬間、視界が一瞬で燃え上がった。突如飛来した炎の刃が、夜の闇を引き裂く、ウォーロックは無残に蹂躙され、赤い悪魔に巻き取られていく。
・・・ディートリッヒが捕らえた、ワ―ウルフとマルスの目の中核を一夜で滅ぼしたシルキーブルーの逆立った髪が特徴、鋭い瞳が特徴のベルツブルム街の悪夢か。ずいぶんと大男だが、年は15かそこらだ。いい加減だな。
元聖騎士、ラブリー村の少女を連れてか。
エース家の長女、シルフは人質にされたが、旅の黒魔術師に助けられたという。そいつはウサギを思わせるパンドラの少女を連れていたらしい。
エース家はブッシュノウム家の遠縁だ。
ミントは、あのかわいいことを自覚する、幻術師の少女はどこまで知っていたのだろう。
「・・・・いいや、一度地の底に落ちたら、もう終わりだよ」
カイは、その煉獄の谷で、ベルクウェインの土地で、その言葉を聞いた。乾燥した空気。
「ちゃんとした白魔術師や医者に見せれば」
「中央が本気でこんな僻地にまじめに何かすると?」
ディートリッヒの中に眠る、北の大女帝のくにで災厄をもたらした魔女の魂。青の賢者の塔の元講師エシャロットはかねてより、力による支配を求めていた。
故に少女は、公爵家での出来事だけでなく、さまざまな因果に縛られることになった。
マドレーヌは、ヴォルフリートがまるで人が変わったように努力しているのを見て、がく然とする。
「エルネスト、どういうことなの」
12歳の時、これほどいじめられっ子でドジで、さぼりまでドロテアは取り巻きとともにアリス、ヴォルフリートに何かと絡み、いじめていた。大人しいくせに意思が強い兄弟は。だが今日のヴォルフリートは何だ。
「あいつがいい返してきて、勝負ですって」
あまつさえ女の子に気遣いやフォローだなんて。
「イヒヒヒ、てめえらのお得意のナイトメアに対して何も対策しないわけがないだろ」
天魔落ち達は、サーウィンのエーファバの町で、ナイトメアが起動せず、全身をウォーロックの≪シュライ・ダーク≫によって貫かれる。
耐性呪術と、あらゆる魔術に対する防御効果が施された制服により即死は免れたが、左腕、右足、左足に一発、全身を穴だらけにされ、暗黒の雷によって激しく食い荒らされ、がくりと力なく膝をつく。
ディートリンデが幼さが残る顔を歪んだ笑みに染めていく。
「ほんっと、貴方は役に立ちませんね、ヴォルフリート」
多くの天魔落ちを連れて、アッシュグレイの長い髪が美しい背が低い魔術師の少女が自らが率いる冒険者グループ(ペーパームーン」を背後に控えながら、一方的にヴォルフリートに罰を与える。ルークエンジェルスという天魔落ちの部隊を。
「ディートリンデ・・・・」
緑色のウサ耳に見えるリボン、真紅のローブ、装飾が多い華美な服。アルフレートの実妹。
「ほん・・とに、わからないのか」
ディートリンデはわざとらしく大きくため息をつく。
「おバカさん」
「あなたがいるから」
少女が金の髪のヴォルフリートに懐にしまっていた魔法銃で殺害しようとする。
「きゃあああああ」
ヴォルフリートはあわてて後ろに逃げる。
「きみ、いきなり、何を」
もう一度、ヴォルフリートに銃を向ける。飛行タイプのウォーロックが其の時、両者の間に降り立ち、口から炎を出す。セレアがヴォルフリートの前に躍り出る。
「俺も加勢するぞ」
カイが剣を腰のさやから取り出す。
「ちっ」
「まて、待ってくれ」
ブランシェ、とその少年は言った。けれど明るいライトブラウンの髪の少年の顔をイフリート隊の女神といわれた少女はおぼえていない。
出身はサーウィン。アーディアディトのライバル。
ドワーフを従えた、ハイエルフの同盟者。
「ガーネット」
「アンネリース・ネーヴェ」
すべてのものを包み込むような笑顔、けれど、彼女がもつ魔法銃は彼女の人生を表している。
「スリエルの騎士団はわたくしが捕らえて見せますわ」
第13部隊(サーティン)の副隊長はゴースト・ブレイヴともいわれていた。レッド・ローズをまるで自分のチェスの駒のように、ブレイヴたちを危険な場所にばかり送り込むあの男の忠実な、いいや、彼自身が操っていたのだろう。
今のパンドラ絶滅を歌う集団にしたのは、サフィーロ、コーラルのブラン・レジ―ナの本家の人間といわれている。
「ルークエンジェルス・・・」
「変わらないな、アルヴィン」
レッド・ローズの屍は多く戦場で転がっているだろう。あらかじめ、孤独にして、自分のコマにする。
「大丈夫かい、ヴォルフリート」
「ロイド・・・・」
「ディートリンデはやり過ぎだよ」
手を貸し、心配そうに見つめる。彼のそばにはパンドラがいる。人間だけでは、パンドラを討伐するのは難しい。相手は回復能力も高く、戦闘スキルも高い。剣も銃もすぐには聞かず、油断すればすぐ殺される。では、ただのブレイヴで魔術師としてもランクが低い自分に守護者の彼女がなぜついたか。自分の部隊でも、自分の経歴や出自を調べられ、だがクリスタルの関係者ということで、彼女の監視役だろうというのが銀の十字架の見方だ。それはそうと、やばい連中を引き合わせてしまう運のなさで、正直まだ10歳かそこらのリリーシャを連れていきたくない。なぜか魔術軍曹の地位を与えられているが形骸化と、銀の十字架内での何かの事情で下士官レベルなら命令できるが、リリーシャを子弟制度で妹としていて、完全に他人の物の事件が自分のものとなっているが、アルヴィンとしては不服だ。が、部隊では扱いはあくまで前と変わらない。厄介事を押しつけるための生贄。
トラブルメーカー。劣等生。自分の感情を優先する馬鹿。一日は体調に文句を言われ、パンドラが出れば捕縛、上位ブレイヴから叱られる。学園ではその他大勢。
目つきの悪さと粗暴の悪さ、スパろうの養子。容姿もそこそこだが特別、学園では目立つことは控えているので、付き合いが悪い奴。
「行くぞ、アルヴィン」
「ああ」
場所は、北のツヴァイトーク。ファーストは、逃げるパンドラを追う。四季があるものの、場所によっては一年の半分は冬同然である。大地の実りも少なく、ゆえに国の重要施設や研究施設、錬金術師の学園都市がある。氷雪、世界中にあるあらゆる熱が最初から存在しない同等ではないという視線。天魔落ちとして存在する理由は異界からの侵略者、ウォーロック、帝国の敵を撃つこと、悪魔属への監視である。ゆえに金髪のきれいな王子様もここでは、力を示す以外、何の意味もない。地上のあらゆる罪を一人で受ける。
ヘレネの必殺技が、敵の頭上に降臨する。
「ほろびなさい」
悲鳴を上げ、アテナの剣の残党がはぐれパンドラとともに退避していく。
≪インティリア・フリ―オ・・・・ッ≫
天罰、たつことさえ許されず、次々に海の女神の加護の元、邪悪なものへの殺戮が遂行される。
絶大な力、タガ抜くことが許されない力は恐怖させる。背がほかの少女より高く、バッサリとした黒髪、目も切れ長。綺麗系ではあるが顔には傷がいくらか刻まれている。へそ出しスタイルにハーフパンツにマフラー、ワンピース風の上着。動きやすくブーツをはいている。アードラ―家の守護者。
帝都南西エリア、第一区。
まるで迷宮のようだ。貴族や金持ちも多い、科学と魔法、帝国のすべてがある場所。平和で安全な帝都。
ハイエルフを入れてのエルフ達の保護区もそこにあるが、天魔落ち達のガーデンと目と鼻の距離なのは仲良くするためではない。
森とともに生き、森とともに死ぬ。アールヴの里がああなった今、生き残りが移り住んできている。
多くはない。エルフは本来、人間を嫌う、他人を嫌う森の民だ。
「セラフィーナお姉さま」
後ろから小さな、黄金色のツインテールの小柄な少女が駆け付けてくる。彼女もエルフだ。
「また、貴方・・・」
だが、エルフがどうであれ、帝国臣民であり、セラフィーナは彼らを導かないといけない。彼女本人はそう思っていた。
だが王族も彼女もお互いがお互いをまるで見ていない、距離感を越えようとしていないことに気づいていなかった。地面に転がったアテナの剣のパンドラは彼女の弓によって命を失っている。助けられた臣民がセラフィーナに感謝の顔から別種の生き物w見る目で見ていることを彼女は意識すらしていなかった。
「カイザー、そこまでの力がありながら」
そのすぐ近くで黒魔術師の少女が驚いた声を上げる。
「えげつな」
「すげえ・・・・」
「怖い女だな」
パメラに対して、アルメルはカイザーに支えられながら、そう評した。
「ウロボロスの人間というのはみんなそうなのか」
「下賤なものには関係ないわ」
「あの、離して」
アルメルは、カイザーの姿を見て、自分の顔がどんどん赤くなるのを感じた。しかし当の本人には初めての、意味不明な感情の動きだった。
「お、おい」
「ともかく、うちに迷惑かけないでよね」
それだけいうと、あっという間に走り去ってしまう。
2
「かわいいいうな」
出席番号10番、ネネ・ミルフィーがまた、相方の喧嘩馬鹿の出席番号15番のローランド・ハントと痴話げんかしていた。
「ちっせえな、あいかわらず」
「なでるな、飴渡すな」
・・・・このクラス、授業するの嫌だな。
呪術の教師は思った。
アーロンが兎の耳を持つ人間の美しい少女を見つけた時、彼女はかなりの空腹だった。「・・・・おぼえていない?」
「はい」
スリエルの騎士団の起こした騒ぎに巻き込まれ、エデンに戻った時、気づけば、七〇〇キロも離れた荒野で倒れていたという。
「お前、本当にパンドラなのか?」
18歳くらいだろうか、何でアイドルみたいな服装をしているのか、しかもかなりボロボロだ。
「他に誰に見えると」
周囲の客がアーロンたちをみる。まあ、そうだな。どうするか、軍かギルドか連絡すべきか。
「で、どうするんだ、アテナの剣に戻るか、帝国政府に行ってどこかの家に」
「それはおやめください」
きりりとしているが、それはご飯粒をつけた顔でいうせりふじゃないな。
それはマナを壊す力。だが、青紫の長い髪の少女には生きるために必要な力だ。追手が顔をしかめる。
「態勢を立て直せ」
相手は、マルスの眼の精鋭処刑部隊。
≪オぷすくーりタース・アイム・スパエラスープラ・インヌメルム・レへーヴ≫
ネフィリアは目を閉じて、呪文を唱え始めた。ペルソナはマナとは違い、戦闘的で悪魔や魔王と同等の力を具現化するペルソナの魔力の総称だ。黒魔術師が己の目標のために使うものと似てはいるが、彼らは否定している。
≪ダークマルキオ―二・クピートルオアイムもルターリス・エクスパンシオ≫
彼女の周囲に赤の女王の奴隷である証の緋色の燐光が走る。虚空に直接存在する光は四方八方に分散し慎重し、複雑な紋様を描き始めた。せいぜい中級レベルの攻撃技だ。ペルソナを一定方向に向けて敵を線待つさせるための回路、異界に祝福されたものの力。
「迸れ・ザ・カリドゥス」
ゴォォォ、ズガァァァン。
「うわあああああああ」
追手は抵抗する間もなく、干渉できない大きな透明な壁にぶつかり、音もなく、彼らの体は歪んだ雷の鋭い刃に引き裂かれた。
「無理だよ、レイン」
「全員は無理だ」
多くのものを魔女の脅威から守りたい。
「ブレア・・・」
彼女は別の隊に移ってしまった。
カイザーはスリエルの騎士団を動かす時、切られる覚悟をしていた。冷徹な精神、そのあり方はあたかもアーデルハイトによく似ていた。
わたくしはやって見せる。
法や秩序の従順な僕、帝国臣民は誰でもそうだが、アーデルハイトは古い魔術師の家系であり、次々にパンドラたちの起こす暴力の火種を消す。指揮官は戦場に立つべきではない。
王は自ら道を示すものだ。フォボスは悪魔の力で、アーデルハイトはブレイヴという力で正義を示す。ディヴィドの魔法剣が、マルスの目の戦闘員に放たれる。
≪トード・ウラカーン・メ―チ≫
ズゴォォォォォォ・・・ン。
「な、なんだ?」
「これはわたくしの覚悟、あらゆる暴力や不幸を焼き払う≪荒野のリンゴ≫-ランド・メーラー、女神が地上に降りた時、あらゆる邪悪や不届きものをその美によって死や破滅に導く、必殺の剣ですわ」
ゴォォォォ・・・・ッ。
「愚かなテロリストや悪魔の僕たち、わたくしの美にひれ伏しなさい」
「ナターリャ、まさか大物が出てくるとは」
大勢の軍人たち、ヴィクトリアが抑え込まれていると気、カイザーが彼女を連れてきた。
「行こう」
「ああ」
吸血鬼の使い魔を追いかけた後、ヴィントはピジョンクラウンというパンドラに占拠された村にたどり着いた。
生きる気力を無くした村人たちはあちらこちらで座り込んでいた。
「暗いな」
パンドラは魔を引き寄せやすい。災厄の象徴といわれる要因は彼らが異界と接触しやすいからだ。封術士や召喚術士、異界と現実界の扉を管理する公爵家やウロボロスガいるのも、パンドラを狩るのもそういう一因もある。
そういえば、レッド・レジ―ナは何でピジョンクラウンを処刑しなかったのか。
ヴィントが冷酷だからの思考ではない。レッドローズに所属しながら、彼女は命令に逆らい、敵味方関係なく、遊び半分で殺し続けた。クルーエルエッグになり果て、テロリストのおもちゃだ。
ブレイクエッグは消耗品で大量に生み出され、最前線で突進して死んでいくザコモンスターだ。瞬間、風の精霊(シルフ)がざわめく。
・・・何だ?
≪わが半身よ、我があがめる全てを包みこむ姿なき大いなる風の主よ、偉大なる息吹を与えよ≫
ヴィントは精霊使い、精霊や神の力と己を一体化する系統の魔術師だ。敵の居場所を見つけ、攻撃手段としてはエレメントの中では低いとされる。塔で魔術師として鍛えられたが、昔ながらの面倒な呪文がヴィントには合うが、上級魔法や中流魔法も武器も使い、白魔術も使う。ただ炎系の魔法にだけは習得できないが。
二節、三節の区切っての魔法は殺し合う現場では、面倒なので使いたくないと思う。大体、修行が嫌いだったからな、誰かに従うのも。
攻撃魔法、メシュヴフィーアエックオルビ―タが、重量も質量も使い勝手もいい。
が、とっておきにしておくべきで無意識に使う技ではない。そもそも無関係の人間が巻き込まれたら、なんてお高い意識はない。
ヴィントの周りから疾風の渦巻きが巻き起こり、速度を上げ、襲撃者に青緑の光の剛速球の弾を放ち、決着とはならなかった。
強大な炎の壁が一瞬にして、目もそむけることも許されない、一切の闇さえ存在を許さない銀の十字架の紋章入りの制服を着た少女を守った。忌々しい大嫌いな緋色の一族本家の人間の象徴の長い髪、整った、気の強そうな瞳の少女。
まっすぐな目でヴィントをにらみ、歩み寄ってくる。
ゴォォォ。
炎の霊剣、あれを所有できるのは当主を守れる守護者の地位を約束された人間のみ。
「ヴィント、お縄につきなさい」
だが、ヴィントに罪はない、誰かがわかっていても、あれとともに会うことすらなかった人間だ。大きくなった、と思うが、自分の敵か、今必要なのはそれだけだ。噂は聞くが、緋色の方舟の魔女と戦ったとか、バベルタワーで決闘したとか。
「はぁ?お前、だれ?俺の追っかけ?」
「ごまかす気?」
さて、どうするべきかね。
彼はヴァルプルギスの夜、先のマギア・ウォーで数々の戦績を上げ、アルトメルデ帝国を守った一人だ。ロ―シュも元は先代のブラン・レジ―ナからアルトメルデ軍人からブレイヴとなった人物で、戦闘時はもさではあるが、人々を救済をしてより良き未来へ導く司祭という立場を全うしている。ゆえに天魔落ちには厳しい目を向けざるを得ない。第18部隊(エイティーン)の猛者達、精鋭のブレイヴたちが周りを囲っている。その様子を隊長ロ―シュは冷静な目で見ている。
「ふむ、どうだと思う」
「え、私ですか」
10歳前後に見える副隊長ネライダは愛らしい顔を傾ける。毒薬や魔法薬を扱う。
ザファルートの剣はいいわけも甘さも許さない。
今ではザファルートは、魔術師としてのランクを上げ、ヴォルフリートの教育係であり、二ケの肖像の重要人物で多くの手下を持つ。
冷たい仮面の下で激情を秘めた本性をかくしていたのか。クラウドの騎士が柔らかい騎士なら、ローゼンバルツァーは固い冷徹な騎士を持つ。
「立ち上がれ、ヴォルフリート」
「・・・くそっ」
「おかしい奴だな、ペルソナで誰かを助けようなんて」
「秩序と臣民を守るのが僕の役目なので」
そういいつつも、このところ魔獣になるものが多すぎる、近頃漂う瘴気のせいだろうか。
≪セラータ・クル―ス・・・ッ≫
ギギギ・・・ががが、ズドォォン。地面にものすごい速度と質量でアルトゥルが放つ地獄の焔の弾が十字架の形となって敵に激突する。一見すると乱暴だがコントロールと集中力が必要な攻撃魔法である。
「ぎゃああああああ」
直撃し、光の渦に魔獣が飲み込まれていく。
「ふう、やったか」
イフリート隊との合流地点、下のランクの使い走りとして、多くの小隊が集まっていた。誰もがシュヴァルツ・パラソルに嫌悪感を出す。マリアベルが所属するフェイトドレス、セシルが所属するア―べマフォンドレスの少女達も同様。ふと、死んだ魚のような目をした少年とアルヴィンは目が合う。格好からして、戦士タイプや剣士というより、ローブもつけているので法術士や黒魔術師だと思うが。アルヴィンを指差す。
「ああっ、あんた、あの時の」
あのバッジは第11部隊(イレヴン)の台風娘。自由の国ガ―トランド出身の優等生であり、問題児。よく、エルフリーデ、ぺとら、三人で指導室に送られている。犬の尻尾のような二つ結びの下に黄金色のくせ毛がちの髪。
「シスターヴァルトルート」
「ルーディ、その名前禁止よ、禁止」
顔は可愛いのだ。目も大きめでサファイヤのような色合いだ。
「あんたのせいで始末書、徹夜で書かされたんだから、責任とってよ」
「おお、残念落第生コンビが絡んでる」
貴族や金持出身の回復術師や召喚術師(エア)が軽やかに通り過ぎながら言った。
「知るかよ、大体お前誰」
「ルーディ・ランフォード」
相変わらず、ヘレナは痛烈である。名門の女子学校に通い、ブルー・ワイズタワーのトップとして、活躍している。魔術士の世界では自我が強く、個が強い方が愛される。「本当に庶民は浅はかで野蛮で・・・・醜悪だわ」
「それは言いすぎじゃないですか、彼らにだっていいところありますよ」
ヘレナの騎士である兄は軽くヘレナの肩を他叩く。
「お兄様は甘すぎます、間違いは正すべきだわ」
ヴィクトリアは恋愛においては、その並外れた容姿もあっていせいに人気があるが、潔癖な方だ。貴族はその立場上、同時に魔術師という闇の社会に属するものはその立場上、いつ死ぬかもわからない。マリアベルもそこは同じだが、ヴィクトリアは年相応に夢を抱いていた。もちろん、アマ―リエもその夫も冷徹な世界に属するもの、ノーマナの夫婦とはわけが違う。
「お嬢、発言には気をつけてください」
今はマリアベルやアルフレートを守らなきゃいけない。悪魔の手にわが主の家が壊されるわけにいかないのだ。
「ヴィクトリア、ゴットヴァルト様をそう悪く言うものではないよ、彼のおかげで今日助かったじゃないか」
あの冷たい邪悪な気配、人を人と見ない氷のような目。きっとカイザーが止めなければ、あいつは迷いなく殺していたに違いない。
「泥棒に気を許す趣味はないわ」
ふんっ、と鼻で笑う。
「能天気なのか、どこかねじが抜けてんのか」
はぁぁ、とヴィクトリアはため息をつく。ヴィクトリア自身にエレオノ―ル達に面識がないが、人の子だ、犯人が見つからず、家族以外も多くの人が死んで、遺族が哀しみ、それなのに涙一つ、死んだ人に対して何も言わず、へらへらと。
「あいつは、最低だわ」
ヴィクトリアの騎士は大きくため息をついた。
カイザーのエレメントを受け、マリアベルは自分と同等のものを感じた。奇しくもマリアベルの加護や属性、上に立つ者の自覚、高慢であり孤高。
その存在を認めるわけにいかない。
「まだ、やるか」
「・・・・・当然よ」
ここで彼を認めてしまえば、マリアベルは不届きものをクラウドに入れてしまう。自分を信じるヴィクトリアたちを裏切ることになる。
「え、おお」
シーザー、憎いあの男の実弟。つまりは、叔父にあたる。騎士団にも軍隊にも所属せず、だが魔術師だ。
「こんにちは、叔父上」
「ああ」
弟を実の子のように可愛がる、優しい人物。ぶつかったゴットヴァルトを気遣っている。
「ゴットヴァルト」
シーザーはゴットヴァルトを見る。
「悪いな、前を見てなくて」
「はぁ、どうも」
こんな好人物さえ、疑う自分が嫌になる。
「来い、ゴットヴァルト」
冷たい表情のカイザーが前方から話しかけてくる。大勢の護衛が二人を囲む。
3
「僕を睨むのはなぜかな、ジ―クヴァルト」
「いや、家が権力争いの時に一人だけ留学とは、どんな気分だろうな」
「自分のいとこが、リーゼロッテが行方不明なら探しに来るだろう」
「親せきづきあいがほぼないのだろう、それに7年前から人が変わったようだと」
「庶民は噂が好きだからね」
世間では、フォボスというスリエルの騎士団という輩が噂になっている。現れたのは、一年ほど前だ。彼らは不正を暴き、悪を暴き、アルトメルデ側からすれば叛逆者の集団だ。
アルヴィン・スパロウは帝国のあちこちで浮かぶレミエルに浮かぶ悪趣味な、どちらかというと悪魔をほうふつさせる姿にただでさえ目月の悪い目を傾けていた。
≪弱者の味方であり、我らは帝国の嘘を暴く正義の使者だ、一方的な価値観や強いものが弱いものを殺すことは許さない≫
≪我々はすべての平等と正義、自由を守るための剣である。傲慢な力があるものが私の愛する民に剣を向ける時われわれは現れるだろう≫
だが、道歩く帝国臣民が彼らに注目することは少ない。自分達は揺るがぬ帝国の信念と軍事力によって守られている。
でも、力で何かを為せば、誰かが犠牲になる。
アルヴィンは、青を溶け込ませたような髪を触りながら、考える。今の体制に問題があるのは自分でもわかる。マナを持たないものとわけ、必然的にマナを持たないものは忘れられ、利用され、すりつぶされる。
クララが、空から飛翔する。ウルリヒは困ったように笑いながら、駆けつけた。
「貴方はバカ?」
一人、敵の本陣に突っ込んで命令無視のトマトまみれのアルヴィンを冷たい目で見ながらエルフリーデはいった。
「いやぁ、英雄だな、アルヴィン・スパロウ」
振り向くと、今日は珍しく活躍の場を与えたスナイパーで遠隔射撃、チームで後方応援したアーネストが第6部隊【シックス】の戦司祭【ブレイヴ】とともに出てきていた。メインはローゼンバルツァーのフォルクマ―ル、少年当主様主導だった。
「これでお前も有名人だな」
好きな子に助けられ、リーダーに殺されかけた英雄だとアーネストはいっていた。
「なんか、言えよ、英雄アルヴィン殿」
男は高速用の高等魔法を受けながら。
「うわあ、恥ずかし」
「死んじゃえばいいのに」
聞こえないように言うがアルヴィンには聞こえていた。ふんとエルフリーデは魔道具をジュエルの中に治める。かぁぁ、とほおを染め、走り出す。
「ちっくしょおおおおおおおおおおお」
フォルトゥテのものには時折、妖精の血が目覚めるものがいる。
ゆえに、セシリアは期待された。おまけにブラン・レジ―ナの騎士。予言での災厄を退ける存在。だから誰かが言った。
「いいよな、名門の子は」
「魔法でずるをしている・・・」
故にセシリアの唯一のネックを、ちょうど猫のような耳を塔の魔術師は七月の魔女ーー、不吉の象徴とした。
なら、自分は偉くなる。兄達も家も関係ない。
立派な魔術師となり、見返してやる。
存在意義、思春期故の誇大化した自意識、半ば才能がある故、いつしか魔術で皆を幸せにしたい、そんなものは遠い記憶の海に消えていった。マギア・ウォーに自分から参加し、ただ貪欲に力を求め、友人たちの声さえ無視して、頑張って頑張って、ブラン・レジ―ナに謁見するまでになった。
故にセシリアは誇り高い優等生になったが、周りに気づけば誰もいなくなった。
ー何で、私が。
だが、北の大女帝への魔術名門大学に行くはずの彼女は、魔術協会や複雑に絡み合う魔術の塔の思惑により、魔術講師と学生を2年することになった。
ブラン・レクスの近くでよかったではないか。
これは厄介払いだ、セシリアはすぐにわかる。パンドラハンターの名門で、皇帝のクラスまで行き着いたとはいえ、セシリアの家のほうが格が高い。修行、なんの修行なんだ。
ご機嫌取りか、噂では、帝国の内側にまで権力を持つ家だという。学園長に推薦された。よほどの事情があるのだろうか。
ともかく、セシリアはクラウド家に行ったわけだ。
ゴットヴァルト・クラウド、16歳。出身は辺境の湖近くの村。魔術の知識があるが、世間知らずと人みしりのため、少々難しい。
写真だけ見れば上流階級のいいところのお坊ちゃん、いかにも能天気で苦労知らず。退屈しそう、セシリアはそう思っていた。
「ご主人様・・・」
宙づり状態で、ゴットヴァルトが現れる。
「・・・・誰?」
これで悲鳴を上げなかったのは、セシリアがある程度常識を持っているからだ。
「く、クロードさん・・」
震える声を押さえ、何とかクロードに目の前の少年が自分が家庭教師する相手でないことを祈ったが。
「御館様、昨日話した魔術の教師です」
クロードは書類を渡し、セシリアに一礼すると、去っていく。
「あああ・・・、神よ」
ゴットヴァルトは体勢を変え、セシリアを見ると壁に身体を預けていた。
「何してんです?先生」
「だ、だって・・・」
これが呪わなくてどうするか、と思ったが、ゴットヴァルトは首を傾けている。
「気分でも悪いんですか、イシュタルから結構な旅でしたし」
ゴットヴァルトは手を差し出す。はっとなる。行けない、と思いたちあがり、制服の埃を取ると、
「セシリア・フォルトゥテよ、よろしく」
お行儀よくかしこ持ってとも考えたが、自分の手札にするなら、親しい感じがいいだろう。
「二年だけだけど、親友と思って仲良くして頂戴ね」
上流魔術《ハイ・マギアス》。
中流魔術《ルホヴェー・マギアス》、そして魔術師たちがそのランクの一番初めに覚える基本魔術、下級魔術《パッサード・マギーア》。攻撃魔法と防御魔法、幻影魔法や暗殺魔術、そして、火、風、水、大地とそれぞれの属性のマナを使う。
「・・・あれは何というか、魔術師たちには嫌われるのよ、魔術への冒涜だって」
セシリアはホワイトボードを使い、
「とにかく、今戦場や一線以外は、程度の薄い攻撃魔法ね、これは私達や独立した魔術師が使うものよ、貴方はまず一節を覚えるべきだと思うわ」
「―まあ、魔術も人が作り出したものよ、普通はある程度マナ、魔術因子ともいわれるわね、その扱い方を親に教わるわ、ああ、あと、基本的に魔術は一般の人間には教えてはいけないわ、家の術式や本当の真名を教えるもなし」
「何で、便利なのに?」
スリエルの騎士団というものがある。その代表であり象徴。
フォボス。その正体は、ゴットヴァルトの異母兄でヴォルフリートの双子の兄だ。彼らの行動は、フォボスに従い、正義をなす。
人間とパンドえらの区別もつかない哀れなもの、帝国の平等と博愛を理解できない国王に仇をなす愚か者。
「シュヴァルツウルフはお前のファンなんだろうな」
赤い髪の少女はどこか他人を寄せ付けない。
「相変わらず怪我が治るのが早い」
見ていないだろうな、と思う。
2
革命はむしろ、世界中に広がっていた。ユリウスの周りだけ見ても、同じ人間同士でも価値観や志が違う。ヴィッターに放たれた刺客は、カラ―ル王国のパンドラハンター。建物が揺れる。当たり前の平穏な日常は当然だが維持しなければ壊れてしまう。無自覚ゆえ、彼らは自分を婿の民だと、善人だと信じて疑わない。
それゆえに黒魔術師の少年が自分の預かり知らぬところで始まり、すでに終わっていたことなど。
知る方法さえなかった。あいつは悪だ、あの人は正義だ。人はカテゴリーして考えるが当然だが一方だけでできているわけではない。
向けられたペルソナ、多くのチェス兵。
殺戮者が少年たちを見ていた。
ピジョンクラウンとは、エデンから追放されたパンドラだ。
「ふぅん、かわいい子じゃない」
吸血鬼の中でも最下位、裏の世界とつるむしかない連中はアトラスミュールの外、夜界にたどりつく。シュヴァルツウルフ。周囲はサイトに囲まれ、行き場のないものたち、穏健派のム―デの取り締まりがない今、無意味な権力闘争がある。ここはよく主義者やテロリスト、悪魔崇拝しゃがいるように思われているが、いるのは盗賊や敗北者だけだ。パンドラたちを決闘させ、お優しい貴族がパンドラをここから家族へと迎え入れる。
「まあ、関係ないな」
「でしょうね」
情報屋の女もわかっている。
一人、カラスの中にヒナ鳥がいた。
「あれ」
「ああ、例の」
からんと、グラスの中で氷が揺れる。
「よくあることだろ」
テレジアから見て、カイザー・クラウドという転校生は、マリアベルの兄というべき存在だった。イシュタルで育ったという話だが、顔を合わせる機会があるが才気、マナ、戦闘能力、人望、容赦のなさ。酷く似ているのに、どうにもマリアベルはカイザーとは相性が悪い。ただ諦めているというか、周囲と折り合いがついている、プライドの高い優等生、謎めいた雰囲気が女性を引き付けるのは自然だろう。
過去はその人の歴史である。アリ―シャの意外なほどの融通のなさ、わかっている、正しいのはアリ―シャやデヴィッドだ。
シエラが凍てついた雪なら、アウレリアヴィーナは淡い、春を告げる雪だろう。その中身は、目の前の金の髪の少年と同じだ。
・・・・メアリー、貴方ほどの冷徹さがあれば。
スリエルの騎士団、それにくみするパンドラたちに自分の声は届かない。フォース・ナイツの騎士団団長は暖かく、慈愛にあふれた少女であるという。
・・・・自分もしょせん、否定する輩と同じだ。
故に少女は仮面をかぶる。
「各員、スリエルの騎士団を鎮圧せよ」
声がわきあがる。
「殺したくないって」
まだこの現実が偽物だと思うのか。
「言っておくけどパンドラよりはかなり甘い地獄だぞ、あいつらはモンスター。殺されて当然だ」
昨日まで農民、あるいは金持ちでも今日が来ればクルーエルエッグと同じ大量殺人のいかれた野郎だ。
拳が、オルフェウスに向けられる。少年たちは感情的な生き物だ。習いたての格闘術、護身術、体術。副隊長に任せきりだが、自分がいると力を入れる傾向らしく。
「なんというか、つまんねえな」
「なら普段から来てくださいよ」
魔法を打ち、それぞれを磨き合う。アルフレートは、まあいつも通り。優等生で、どれもできるのはいいが愛想がなく、言葉を飾らない。潔癖で冷静、自制心が強い。アガットはやはりだが、読みやすい、成績も実力はあるが作戦がない。威勢がよく、実力はあるが、戦争には出せないだろう。
「もうなれた?」
エレン、シャーロット、グリシーヌ、ブレア。ディートリンデはあっという間にこの学園になじんでしまった。
「しかし叔父様も隅に置けないな」
「バルドゥル、やめないか」
ハイ・マギアスとは、とてつもなく破壊力の強い、世界そのものと干渉する、マナやエレメントをコントロールし、神や悪魔と同等の力を得る力だと思えばいい。
木々の間を切り抜け、リスに変身した魔術師は、ハイエルフの街を駆け抜けていた。「軍の敷地がまた増えたな」
「え、ああ」
ディーターは暇なようだ。
「消えた少女に、チェンジリングされた少年、孤児院、何かスレイマンの悲劇を思い出すな」
「映画か」
「ああ、古い映画だよ、何か当時、サーウィンかイ中で起きた猟奇事件をモチーフにした、ある日孤児院の子供が神各紙に会って、オ―ガがシスターたち孤児院関係者を喰ったんだと」
「おい」
「悪い、お前も孤児院の事故で家族を失ったんだったな」
バルドゥルに近づく足音がある。
「アガサか」
通り抜け、アガットの元に行き何かしゃべる。しゅん、と水面のような色合いの長い脚近くの三つ編みをゆらしながら、ソール独特の水色のリボンをつけた少女が愛らしさをふくんだ少女らしい顔を悲しみに染める。変な女。
アガットはその時、そう思った。
「・・・・アガット、君はわざとなのか」
「何がだよ」
「アガサのことだよ」
「あいつがなんだよ」
ルホヴェー・マギアス程のレベルの力だろう。このレベルの魔術となると、実戦向きと言っても差支えない。当然、戦闘技術も経験も少なくとも己の研究室を、弟子を数人もてるレベルだ。ランクが上がれば、当然ライバルも増えて、力ないものは淘汰される。己の横にたつのは良きライバルではない、敵だ。≪浄化≫≪不滅≫≪誓約≫、暁のテレジアと呼ばれる少女は光属性であり、臣民を革命家や他国の敵兵から守る。全てのスターレスを上昇させるテレジアの音声魔法。
「迸れ」
邪気が消えていく。
「行くぞ」
「連携を立て直せっ」
ヴォルフ・リーヴぁ二は声を荒げながら、不気味でありどこか神聖な雰囲気を醸し出す魔女の手下たちで、歪曲した大地の女神の神殿に使えるものだけが使用できる刀を取り出す。身体能力を著しく上昇させ、限界を超える操作系のマナを使い、下級魔法を敵にぶちかます。ちょっと気が多いな、とダヴィデは思う。だがそもそもイフリート隊はヤンキー体質か体育会系というか陰気というか、乾いた奴が多い。はきだめに鶴ではないが、それでもアリスは一種の清涼剤のように思えた。
――思わず、そのまぶしさに目を奪われるほどだ。
「君は目立ちがリヤなのか、アリス」
「お願い、帰して」
ただの非戦闘員の少女がアルムティ―の本拠地にくる。単独で。
「貴方も今の方法が間違いだというくらい、わかるはずよ」
闘争はイフリート隊、アーデルハイトの元に近くにあった。
「青の賢者ですか」
「ああ、聖女ルチア様をその・・・」
ああ、いやだなとイフリート隊の軍人はそう思う。特魔と連携し、テロリストや魔術組織と戦う。
「放っておきなさい、それは私達が関与することではありません」
アリスは驚いたように見ている。
・・・いい格好しいが。
アーロンは、学生が何でこんなところにと憤慨しながらも巻き込んだアルベルトやヴィクトリアに文句は言わない。
≪アギオ・コンヴィクション≫
まるで、別の空間がそこにいきなりパズルのようにはめ込んだような、軽い重量感と神聖な七色の神の恩寵たるヴンダ―の光。その力をふるうことができるのは神の力を使う法術士だけだ。七色に光る、閃光。視界を覆うあまりある神の威光は全ての邪悪を消し去る。駆ける。走る。飛ぶ。
純白のシスター服は、この世にはびこる邪悪なウォーロックを許さず。
その呪文と同時に、ウォーロックの体は勢いよく吹き飛び、魂ごと消失する。
「お前、その術、法術士か」
アーロンは驚いたようにフレーヌを見る。
「この場の邪気は私が沈めました」
「行くぞ」
襲ってきたパンドラを杖剣でアウレリアヴィーナが二人を守る。
「アウレリア様」
水魔法の最高攻撃魔法、≪ラミアーのためらい≫。守るものがいることにより、発動される打撃力抜群の軍用のアウレリアヴィーナの技だ。
「あ、ありがとう」
「・・・別にあなたを助けたわけじゃありません」
「セラヴィーナ、ごめんなさい」
「いいのよ、アリス」
素人は黙っていろという精神は彼女にはない。ナターリャは困ったようにアリスを見て、笑う。
・・・不思議な子。
「アルベルト」
「ああ」
天魔落ちの救世主のことを思う。あの預言の事はセラヴィーナも知っている。マリー・アンジェ様。
本当に彼らに重い使命を預けるのですか。
その剣は、堂々たる蹂躙する、威光を示す剣。かっての昔にいた神が人類の担い手のために残した剣。セラヴィーナはマルス・モアを守ることを使命とする。帝国の平和を守ることを。
行動の多くはレーヴェ、フェリクス、オーウェンとともにある。
「クロ―ディア」
「私を助けるためとか」
「心配だったのよ」
彼女はパルテノス学園の制服を身にまとい、腰にジャスティスの弓矢を持つ。
・・・かたいなぁ。
「うがぁぁぁぁぁ」
ウォーロックはたちまち、この世から消えていく。
「パルテノス学園の地下にこんなものがあるとはね」
クロ―ディアは制服を着ていない。小さな美しい少女は、そもそもだ、他者を必要とせず、また高い知能のため、高等教育を受ける必要もない。
「学校が世界の縮図といった言葉は正しいですね」
「え?」
ヨハンは聞き逃していた。
オーダーは、アンソニーが帰ってきたことにすべてを悟った。ああ、銃のロンドは、アデレイドの過去の亡霊は死んだのだと。パンタシアが腕をからめてくる。
「戻りましょう」
「ああ」
3
ライアーが忌々しげに、バーバラスをみる。標的はそのすきに逃げていく。本物の戦闘にセレストはすっかり体から力が抜けていた。
吸血鬼に選んだのは、ヴィントに合っていたからだ。熱が左腕に浮かぶ。
暁の刻印。
種族とか縄張りとか関係ない。
永遠に生きようと腐ったやつは腐ったやつだ。視界の隅の使用人と金持ちの男。忠誠進化絆でつながっているのだろうか。
時間どおり、ヴィントは飛行魔法で空から奇襲する。
ー存在を刻みつけたいなら、自分で証明しろ。
脳裏に、自分を地面に落とした細面の顔が浮かぶ。能面のような、鋭い眼光の男。
≪聖薔薇のロンド≫
イングリッドの剣が、その技命とともにテロリストに一閃、次々に体を横転させ、金色の光の嵐に巻き込み、かぐわしいバラのにおいが辺りに立ち込める。
「よくやった」
「いえ、国王陛下・・・」
「やりますね、先輩」
「先輩はよせ」
ハーフエルフか。
アルトゥルの細長い耳を見ながら、ご主人様に甘える犬のように、素直な横顔にあきれと憐れみを感じる。
「いい人なんですね」
「それはねえ」
≪天空の天使≫と呼ばれる有名な冒険者パーティーであり、イーグル隊の上部組織ウラヌスの騎士団の名前ではある。ナターリャやエイルはそこに所属している。中央にはアンジェロの姫がいる。
ヴァイオレット・ローズやブルー・ローズ、イーグル隊に命令をして、リーゼロッテ・オーウェンの捜索を探す。ウロボロスとも連携をとり、マルスの目のアジトを探す。
「悪魔属がすることはえぐいな」
「まあ、悪魔だからな」
実際、アーデルハイトは悪魔属に手出しはできない。アテナの剣があっても、悪を働くパンドラはうようよいる。
「気分悪いな」
喧嘩でもするかな。
パッサード・マギアはすべての魔術師の卵が覚えるものだ。塔の生徒、冒険者あたりが使う。騎士団や貴族おかかえの魔術師はこのレベルではまず相手にすらしない。それは戦士や剣士も同じこと。イングリッドは、クラウドの騎士が、フォルトゥナ騎士団の前、ルードヴィッヒの前で突然の訪問者に剣を抜いた瞬間を目撃する。
「二度とそのふざけたつらを私の前に見せるな」
・・・アンジュの騎士か。
「まさか、王宮の関係者までこんなたくらみに参加するとは」
「・・・」
イングリッドは黙り込む。≪崇拝≫≪憧れ≫≪王冠≫、闇と光の属性をもつ、絶対なる意志の剣、ブレ―シ―スソード。それがイングリッドの剣だ。
彼女の剣に耐えられるのは、レーヴェ卿の息女か、王宮騎士でも上のランクだろう。「帝都はまだ混乱しているだろうな」
「汚い蛇の下僕か」
帰ってきたヴィントに血のにおいを感じたのだろう、フィーナは多くの手下を連れ、嫌悪感を隠さないでいた。
「久しぶりだな」
「気易く触るな」
ヴィントの手を振り払う。
「いつもへらへらして、強いものにこびてあなたに志や愛する者はないのか」
「何千年かわからん予言を信じるよりはましだろ」
風の精霊達が少女の周りを行きかう。
闇夜の中で、少女の前にパンドラ達の集団が待ち伏せる。
「愚かな」
自然や精霊と行き、秩序を守る精霊術士には、魔術師タイプと精霊を宿すことで騎士の力を発揮するものがいる。銀の十字架は、本来の神の使徒ではない、国家の剣である。「おばさん」
「ガキ」
第20部隊隊長(ツェルブ)は天翼族(アンジェロ)とともに生き、黒い傘(ブラックパラソル)とともに行動することも多いリュンと競争関係にある、精霊術士(スピリット)の色合いが大きく、錬金術師では名だたるものが多く輩出している。王族よりはローゼンバルツァーに恩義を感じ、忠誠を誓っている。ロ―ティーンくらいの少女だ。
目もとには聖巫女(セント・ミディアム)の正当な子孫であり血縁者である独特のアイシャドウ、陶器のような白い肌、オーロラを思わせる均質な結われた髪。装飾が施された、呪術的なものもかけられた上等な短衣。大きい目は訓練された、それも上位のネコ科の動物を思わせる紫の瞳。一族のナイトの証の長身の剣。
対する第21部隊隊長はいかにも大人の女性、夜の女性と雰囲気の女性でありながら、どこか高貴さを醸し出している。20代の半ばだが、どこか少女らしさを残した女性だ。イグナスの姉の親友でもある。面倒見がいいが、目の前の少女だけは相性が悪い。出自にコンプレックスがあり、努力家だ。ツリ目がちでウェーブヘアの髪を揺らし、月夜が似合いそうな危ない雰囲気と慈愛が混ざった女性。だが、おそらく同い年でもこの二人は親友になることはないだろう。
それは誰もが同じ意見だ。
「発育不足」
「胸が垂れてる、嫁き遅れ」
ちなみにだが、少女は17歳になるはずだ。13歳にしか見えない身長と愛らしい人形のような体型だが。
「運命の男なんてゴリラ男女には縁がないわよ」
「そうだな、誠実で神経質なレディーよりは尻軽な女の方が男は好きなそうだぞ」
暗に、媚びる術でも学んだらどうだと言っている。
「・・・っ」
プライドが揺らされているが、何とかこらえ、女性は去っていく。
「お嬢、少しは優しくしてやれよ、大人の女性は繊細なんだぞ」
「知らん、あいつのほうがいつも突っかかってくるのだ、ならお前があいつのだんなになるのか?」
「え、イヤ俺、ロリ専門何で、隊長は色気がないんで範疇がいですが」
「奇遇だな、私も下品で無神経な男は嫌いだ、行くぞ」
「へえへえ」
アレであの二人は仲いいのだ。
「なぁ、やはりおなごはぜい肉がある方がいいのか、一般的には・・・」
「声が震えてますよ、お嬢、まあ思春期のガキならそうですね、俺もそんな時代ありました、胸はまあ、将来に期待でいいんじゃないですかね、何、好きな男でもできたんですか」
「そうではない、だがな、だが、ヴォルフリート様の病気を治すには情報が必要で」「ああ、女好きのエロ英雄の」
「違うぞ、あの方は高潔で優しい方だ、だが悪魔に呪われていて」
「そう信じたいんですね・・・」
「お前は低俗で下品で最低な男だが、そのあたりの情報は私より詳しいのだろう、治るのだよな、あれは一時のものなのだよな」
「・・・・ええ、まあ、・・・お嬢、主の特殊な性癖を認めるのも騎士の仕事ですよ」
「ナに積んでいるのか、あの方は終わりなのか?」
「英雄は高潔な人間より好色でその…、破廉恥なのもまあ、正統派な感じがしてもいいんじゃないんですか」
「私は認めぬ、いい解決策があるはずだ」
十六歳、帝国首都、とある名門校。
「また、あいつ・・・」
うーん、針のむしろだ。東方の血が強く、体格的には細くそこそこの筋肉質。顔立ちも同級生と比べるといくらか子供のように見えるらしく、なめられることも多い。
魔術の系統は黒魔術師であり、魔法騎士であり、聖騎士の方向もあるが、指揮官タイプ勝とうとそうでもない。戦司祭の最終試験で、ある事件を起こしていこう、実力があるものの、黒髪の悪魔だの、閃光の魔神だのがつけられている。
「近づかない方がいいよ」
王宮騎士の一人を後見人、庶民のでとは珍しい聖剣を所有することが決まっている。
教会の方へ、窓に向かい、ハルトヴィヒは外を眺める。
「まあ、気を落とさないように」
ヴィンスは微妙な笑みを浮かべる。いわゆる金髪の眼鏡男子である。
「皆、基本はいい子ばかりだよ」
担任のヴィンス・オセアン。22歳で、ヴォルフリートに魔術師の世界のことを教えてくれる。
「だから、まあ、気を落とさずに」
「はい・・」
コーデリアは侮蔑の眼差しを正直に金髪の少年に向けていた。
「最低・・・」
「触らないでくれる」
忌まわしいレッド・レジ―ナが愛する美しい帝国から消えてくれた。そのことを喜んでいたが、こんなトラブルの種がやってくるとはっ。傲慢でわがままなのは超名門の魔術師で、政治家の父を持つことが影響されている。ベアトリストは同じアースナイツ部であり、ライバル校同士の関係である。美人のたぐいだがいささか目元が鋭い、高慢なお嬢様という印象をぬぐえないだろう。同時にパメラは責任感や貴族故の間違ったセイギカンが強い少女だ。パメラが顔をひきつらせ、落し物を拾ったヴォルフリート(カイザー)に淑女らしからぬ乱暴なふるまいで手を弾き飛ばした。
「行きましょう」
「やだやだ、調子にのっちゃって」
「自分が特権階級とでも思っているのかしら」
取り巻きの少女ととともに、パメラはにげるように去っていく。ヒュウウウウ。乾いた風が廊下を通り過ぎる。
計画的に完璧に、時に子供っぽく。成績優秀、眉目秀麗。
自分で言うのもなんだが、主人公みたいだなと思うときもある。だが、こういう試練は求めていない。
―朝日がまぶしい。
騎士たちの掛け合い、お目付け役の執事と頭脳戦、面倒な妹と付き合い、優雅に名門の学園へ足に向ける。それがあの日まで清廉潔白な自分の日常だった。
「聞きまして委員長」
「聞いたよ、副委員長」
銀の十字架が経営する上流階級やブルジョア階級に向けられ、裏では魔術師も育成する学園に転校したわけだが。
制服も黒やダークグリーンを基本に上品な雰囲気にできており、女子の制服は肩に金の肩章に銀製のチェーン、銀の十字架を模した校章が背中、腕回り、明るい青の上着は司祭か、軍服の正装を上品さとともに出す。その下はブラウスで決めており、太ももより下のラインまでの盛り上がったスカート、ソックスは清楚な白かタンクトップかに決まっている。清純さと思春期の少女の危うい色香がセットというか。
「ふん、これだから下賤な生まれは」
呪いというものがあるか知らないが少なくとも今まで女子生徒とは男子部と女子部で分かれていたうえ、マリアベルや幼馴染の少女で幻想を抱いていない、自分は自粛していると思っていたがまさか、同い年の少女たちに嫌われることがこんなに打撃を与えると知らなかった。
「恐ろしいわ、あの人転校初日に女子の着替えに飛び込んだんでしょ」
言葉とは実ははかないもの。何より、ローゼンバルツァーの力がなければ、カイザーは何もできない。ある意味尊敬の目で男子生徒たちはヴォルフリートを見つめ、侮蔑と恐怖の目で女子生徒は遠巻きに見つめ、絶対にヴォルフリートに近づかない。
友達もそれなりにいて騎士たちにも慕われてきたヴォルフリートは転校三日目で見事に人気の的となっていた。
「あの、ヴァるベルグラオ君、これ」
テニスラケットで弱気そうな生徒がプリントを差し出してきた。
「次の授業、移動だから」
「あ、ああ」
びくびく震えているので安心させるため、ほほ笑んだのだが、少女はひっと叫び、すぐ近くにいた彼氏だろう生徒の後ろに隠れた。
・・・・転校三日目で見事に一人ぼっちになっていた。
おまけにそういう悪人の噂だけではなく、ヴォルフリートは生徒たちに嘘つきと思われているため敬遠されていた。
「大変だな、嘘つき英雄のヴォルフリートクン」
豪商の跡継ぎ、フぃラ―ト。友達も多く、いつも何人か男友達を連れて歩いている。
「気にするなよ」
アンドレ・ベリウォス。警察の家系だが噂好きだ。
友達はすぐにできた、孤独ではないのだ。ただ、女子生徒に敬遠され、舌打ちされ、青い顔をされるだけで。ごめんなさい、気持ち悪いですと・・…言われるだけだ。
昨日なんか不良女子にキモいではなく敬語で気分悪い気持ち悪いですとガチで言われたほどだ。
4
クララがカイザーに正座をして、剣を背中に背負い、待っていた。
「買い物に行くだけだぞ」
「私は騎士ですので」
誰に狙われるというんだ・・・。
「なるほど、鈴をつけるというわけか」
ルヴァロア家多くの協力者がアーク隊から出た。
「こんな身内に敵がいたなんて」
それもこんな大事な時に協力し合わないといけないのに、略奪行為なんて。
「天魔落ちのせいかしら」
「やめろよ」
正面から敵を叩きつぶす、衝撃と一瞬で検束によって地面が削られ、バーバラスの相棒にして得意技、一閃紅炎剣が繰り出され、炎の滝が生み出され、敵の大人数を一瞬にその魂ごと焼いてしまう。
「すさまじいな」
「相変わらず」
騎士とは、国家と国王、主を守り、弱者を守り、礼節を守るものだ。騎士を持つ貴族は、後継者にそれぞれ専用の騎士を与える。そして、バーバラスはカイザーの身の回りを守る騎士であり、クラウド家を守る。
傍にいてこそだが、それでは個人が戦力を持つことになるのでそれぞれ魔法騎士団に所属し、命令があれば、主のいない騎士と討伐や偵察任務に向かう。
「降参だ、降参」
銃や剣、ロッドを捨てて敵の勢力は投降していく。
コーデリアは勝者側の人間だ。だから、取り巻きもライバルもいる。そうした人間は、違う階層、ダヴィデのような人間は理解できないだろう。
「わーん、ブレアー」
エイルがまた泣きついてくる。
「もうどうしたの」
廊下では、楽しそうに今日も生徒達がいきかっている。どん、と駆けてくる男子生徒が悪い、とダヴィデに謝り、走り去っていく。
今日も平常運転、学園は平和だ。部活さえなければ。
ブレア・アリ―ズは、魔女部隊の一員である。成績は中の上。学校の成績はまあ、見た目という最強の可愛い系わがままボディという最強カードだが、後ろから数えた方がいい。友達はまァ、青春をまっとうに謳歌し、頭が軽そうな連中だ。だが彼女の最強の真の武器はその友達の多さだろう。優等生の美人と新聞部の眼鏡とタッグを組み、明るい学園生活ができるよう活躍している。というか生徒会といい、ここは光に満ち溢れている、スターばかりなのだ。きっと彼女が大人となった時、思い出す日々は輝かしいものだろう。まあ、だからといって俺が劣情やら憧れやら、身分不相応な抱いているかというと。
「うへえ」
である。親切、おせっかい。実に美しい。そこにある悩みもすれ違いすら光にあふれているのだろう。彼女はモテる。マリアベルほどではないが、距離が近く親しみがあるということで、だが俺に言わせれば冗談ではない。なぜか彼氏はいないそうだ。だが、どうせそこらの男と付き合う。
マナ。魔法の力。
だが全能の力ではない。
「・・・・うん、だからさ、相談に乗ってくれる?」
ダヴィデはここは園芸部で会って、つまりは草花を育てる部活だ。部長も自分も基本的に一人好きで、部室にいても花の品種がどうだの魔術の到達点だのを話している。新しい部員とか募らないのと一応聞いたら、役がたたない人間はいらない。彼女はクラスでも一人なんだそうだ。
「馬鹿な人間と付き合うだけ無駄」
この学園は銀の十字架、女神教会が運営する学園である。姉妹校でもあり、女性教師はシスター、男性教師は元ブレイヴが多い。アリシアが生徒会長になってからは、緑色のスカーフ、真紅の薔薇のようなネクタイを金持ち学校丸出しのセーラー服をベースにしながら優雅な花飾りがついたローブ、白いブラウスの上に紺のワンピースドレスを身につkr、背中には乙女らしくリボンだ。フリルやレースも多様に使われ、手元にはダークグリーンのリボン、ふわっとした袖は肩から少し丸い形態にしてバラを模した飾りとダークグリーンのリボン。女子の大多数は黒か白だが、二―ソックス、が―ダ―ベルトといささか、姉妹校よりは緩い。ああ、男の制服?黒や紺を基調にして、裁判かよと思うローブ、ブレザーベースで紺のズボンのまあお坊っちゃんらしい制服である。違いは向こうは装飾が多く、こっちはシンプルだ。だからこそ、差はでるんだが。まあ、どうでもいいよね。ちなみに小等部、中等部と制服が違います。あっちではどのクラスか明確に分ける肩章もあるとか。運命か、宿命か、あるいは乙女がいう運命の糸でもいい。ねえ、対等って何?
「お前さ、自分でやれよ」
自分で言うも何だが俺は奥手である。色々夢見る年ごろだ。女子と密接な距離があれば、ドキドキするものだ。それが普段なんとも思っていない相手でも。ましてシエラは好意的だ。あれ、こいつ好きじゃないと勘違いさせるほど、経験値がない男子なんてクールな女子が自分にだけ違う態度なら十分だ。男女に友情なんてないだろと一瞬戸惑ったのは仕方ないだろ、とつい信念を捨てそうになったが、すごい、全然ドキドキしない。この美少女先生はこびないのだ。甘やかさないし、修行に少年の夢なんて一かけらもなく、俺は順調にレベルアップし、パンドラを討伐していった。何手熱い師弟愛。
・・・・あれ、何か違くない?
すごい美人だ、まあスレンダーだけど。男前で女王様だ、師匠様だ。2人だけの時間、さすがのおれも恋をするかもと期待と不安に支配されそうだったが、今は一かけらもシエラに特に感じなくなった。むしろ、素敵、ついていきたい、貢ぎたいと思うくらい。いや、それ、俺の立場だろ。
「だって、緊張するんだもの」
イヤ、君今鏡見てただろ。髪の毛も整えて。はいはい、今日も可愛い。
「趣味悪いー」
「何、氷姫、そういうのが好みなの、ださーい」
一般科の生徒である。だがシエラは聞き逃さない。
「それはどういう意味かしら、私の部員が何かしら」
一応守ってくれるのかしら。
「だって、そいつ最悪の男だよ、お姫様の相手にはねえ」
まあ、今さら男女が二人いる、つまりは恋人であるという世間のそういうのに突っ込まないが悪いことしたなぁ、好きな男がいるのに、俺みたいなのが相手だと。
「あの・・・」
「確かにダヴィデ君は顔も性格も根性も悪いわ、好色な割に奥手で乙女だし適当で自分勝手で狂調整もない、社会性もない屑よ」
「可哀想、全否定じゃん、受ける」
「というかストーカー?下僕?こんな冷血女に惚れるとか見る目なさすぎ」
うーん、どっちに怒るかというと、まあ。
「別にお前らの評価なんていらないし、俺は俺が好きだから問題はない、そもそも顔面ならお前も俺と同じレベルで一生彼氏なしだ」
何でタコ殴りされるんだよ、真実だろうが。
「全く自由がなくなる生活がほしいなんて、あの女達おかしいな」
「普通はそれを欲しがるもの何だけど、同情や一時の気の迷いでも好きになってくれる子がいるかもしれないでしょう、貴方孤独で死にたいの?」
「シエラ、人間は一人で死ぬものだ、お前は分かってねえな、そもそもどちらも俺は女子に全員嫌われているから起きる心配はない」
「以外と自分の評価高いわね、まあ私は女子に大体距離を置かれているけど、真実の美は遠くに置きたいものだものね」
病んでるな、今日も。
5
≪ダスク・エステノル・・・・ッ≫
黒魔術の一緒であり、遠隔での攻撃がスリエルの騎士団に襲いかかる。属性は闇と時間。ダヴィデはイスリート隊の隊員とともに広範囲連続魔術を連続で敵に放出し、撃墜していく。
学生の本分は勉強である。けれどアウトサイダー、落後者、日蔭者において、学園とは牢獄と同じ。光があれば、影がある。背が低い、小太り、三代だけの魔術師の家系。
戦闘技化は実力主義の魔術、血統主義だ。ゆえに不良といわれる彼が苦手なタイプは一般科ならともかく、ここにおいての実力テストでは何の価値もない。
「あら、ごめんなさい」
隣のクラスのソフィアが友人を連れて、ローランドとぶつかりそうになる。
「いや」
一般といわれるものにも当然だが階級がある。自分のような誰からも相手にされないもの、優秀だが集団に属背ないもの、強いものに媚びる中クラスのもの。
「見て」
セシル嬢だ。彼女は戦闘技化に所属していたが今は一般科だ。
アウレリアヴィーナは今、王宮騎士属の戦隊にいるという。彼女はもともと優秀、自分と話せる身分ではない。それに他の仲間も分散されて。
「奇遇ですわね」
ツイツィーリアがハルトに話しかけてくる。
「おお」
彼女は切りだした。
「いまだに信じられませんわ、ローゼマリーがパヴォーネ学園の生徒だなんて」
ツイツィーリアは大きくため息をつく。
「君だって、女子高の生徒じゃないか」
「はぁ・・・、うちはうちで大変ですの」
アリエス女学院と違い、ツイツィーリアは基本は共学だが、男子部と女子部に分かれた魔術師の塔の出身者が多く入学するファザ―ン学園の一年生だ。
「いつから、君はカイザーについていたんだ」
「・・・二年ほどかしら」
だが赤い髪のメイドは目を閉じて、コーヒーを飲むだけだ。
今日は遅く、泊まることになったが。
「落ち着かなさそうね」
「・・・子供だけで住むには広すぎるな」
確かに、16年、彼らは何もされなかった。おそらくは有力者や貴族の養子になっていたのだろうが。
「ここは客とか来るのか」
機械的な使用人、見慣れた顔が多いが彼らは黙々と仕事をしている。
「ご当主様は自分の跡継ぎに余計なものはまとりつかせたくないのよ」
「あったのか」
「まさか」
7
額から血が流れていた。木々のにおい。泉の流れる音。
ルードヴィッヒが駆けてくる。
「なぁ、あれって女の子だよな」
「何で、男子の制服をきているんだ」
眼帯をつけた薄い青緑の長い髪の女騎士。
「そりゃ、君は伝説の男だからな」
地下室の天才魔術師、狂気の錬金術師で科学者の女性は言う。
「とくまのお偉いさんなのになんでこんなところにいるんだよ」
「うん、ついでに男爵でもある」
「世の中、与える相手間違えてんだろ」
「そうみんなは言うな、真の美は死の中こそあるのに、ああ小さい女の子は好きだよ」
すごい美人だが、その本人は天才で変人で大の男嫌いだ。
「ほんとうに、リリーシャの体見てるだけだよな」
「むらむらするだろう、わかるよ、パンドラこそ美の塊だからな、君のような女と縁がなく、無害に見えて有毒な犯罪予備軍には理解できないだろうが」
「先生は悪魔崇拝しゃじゃないんだよな」
「そうだよ、だが私は君のように人間は全員、前任ですという輩が吐き気がするほど嫌いなだけだ」
「ああっ、逃げた」
窓のガラスが割れ、クリスタルが叫ぶ。帝都は今表面上、平和だ。だが、その一方、アルヴィン達のような下のランクの戦司祭達は、はぐれパンドラの討伐とイフリート隊と連携を組むことになっていた。
「君は何でためらうんだ、レベルが上がるんだぞ」
「そうだ、そうだ」
臣民は今混乱に変化に不安を抱いている。自分達に叛逆者や革命家ガいると、単に帝国政府が双方どうしていた、多くの臣民はそれを疑うこともなかった。
それはそれとして、アルヴィンが問題児で仕方のない事情で降格処分、ぬるい学生生活と戦司祭としての任務が明け暮れている以外に今の立場に置かれるのは、パンドラを撃つのをためらってしまう癖があるからだ。
「君だって別にいつまでも馬鹿にされたいわけでも同情されたいわけでもないだろ」
9
「バドォール伯爵、と」
「お久しぶりですね」
黒髪の細面の気弱そうな執事はまだ20代前半。
「校長はどこか案内してほしい・・・、オスカー・クラウド」
「知り合いか」
「いや・・・」
魔術の教師は個人でもいたが、甘いと言われた。
「君は人でありすぎる、アルフレート」
剣の授業も同時に行い、その剣の教師も。
「貴方は選ばれた子なんですよ」
「・・・・はい」
魔術ガン、フランキーをスリエルの騎士団に向けていく。住民はすでに避難完了。
フォボス、お前は私の獲物だよ。
女性はにやりとルージュが添えられた唇をゆがめる。
その息吹は、帝国が平等と絶対平和を歌う前からあった。慈愛を理解せず、暴力的な手段に出るもの。戦場を放棄したと言っていい帝国軍人だが、イーグル隊やイフリート隊は革命家やテロリストの相手もするのだ。
5,56mmの弾が混乱した状況で飛び交う。
「あまり、無理するな」
フォルトゥナ騎士団は魔術ガンファマースを装備しながら、兵力を分断し、スリエルの騎士団以外のテロリストを追い詰めていく。
「助けてくれよ、フォボス、私と同じ立場だろ」
黒狼の黒衣の女は目にアイシャドウをして紫の口紅をつけていた。
「弱者を守るのが私の使命だ」
「だめですよ、救世主様」
ズゥゥン。バリ・・バリ・・・。
「何だ、空中から」
竪琴の音が鳴り響く。
「貴方に我らの黄金の夢を止めさせはしません」
その少女にオズはぎりっ、となった。
「エメロードぉぉ」
「あらあら、オズちゃん、久しぶりね」
ヴォルフリートはかくっ、となった。
「恥知らずの同胞殺しの魔女ですよ」
フォボスに見せられた、愛らしいほほ笑みのような女神の美貌を持つ宝石の魔女エメロード。
オズはヴォルフリートに苦々しく言う。
「今では、魔女の席からも外された」
薄紫の長い髪をアップにしたひし形の文様をつけたゴスロリ風の衣装を着た少女が映像として残っている。
「フォボス・・」
「フォボス・・・」
熱気する民衆、鬼族、オーク、革命家。帝国では悪の一味でも、彼らにとっては。
「・・・」
赤の王や帝国を倒し、共存し平和な世界。マリー・アンジェを救い、優しい世界をアリスとともに。
力ない自分がカイザーの支えになれるのか。
「フォボスぅぅ」
ピジョンクラウンが叫ぶ。
「させませんっ」
エメロードが前に出て、閃光。魔女文字を虚空に描き出していく。
「チ一、この恥知らずの魔女め」
震音。空気が激しく揺れて、エメロードが持つアヴラクオ―レガエメロードから放出され、膝に着用されたハート型の瓶からアニマジェムを取り出し、武器へと錬成させる。
ゴゴゴゴ・・・。
≪わが夢に酔いなさい≫
ア二ムスソード、エメロードの百発百中の得意技である。
そこへ、ヴォルフリート達が遭遇する。
仮面の中でカイザーが大きく目を見開くが、アレキサンダーが動き、カイザーたちを倒そうとする。
「止めろ、アレキサンダー」
「フォボス?しかし」
「無意味な戦闘は禁止だ」
アレキサンダーは納得できないが、頷き、もとの位置に戻る。ナイトメアガフォボスを襲い、鋭い眼光が向けられる。
「救世主殿のご到着か」
「俺は救世主じゃない」
細い剣をヴォルフリートはフォボスに向ける。
「だがお前の野望を止めて見せる、ピジョンクラウンを解放したのはお前だな、何でそんなことをする?なぜだっ」
「私はしていない」
だがーー
暗殺者が、フォボスを襲い、フォボスはゼウスの盾でその攻撃をふさいだ。
「暗殺者に狙われるやつが善人なわけがないっ」
「この馬鹿が」
ヴォルフリートは正面からフォボスをにらむ。
「なぜ臣民を恐怖させることばかり続ける、言いたいことがあるなら堂々と言ったらどう何だ、卑怯者っ」
「お前は・・・」
二人の声が重なりあう。ピジョンクラウンの部下、死神は飛び去ってしまう。揺れる地面。爆弾でも仕掛けていたのか。
漆黒の長い髪のワイルドエルフか、鬼がヴォルフリートに鎖を解き放つ。
「パンドラか」
金色に輝く鋭い目がヴォルフリートをにらむ。
「止めろ、俺はお前と戦う気は」
だがそのパンドラは何度も殴りかかり、体から緋色の焔を生みだし、ペルソナを放出させている。拳の一振りで大きな岩が焼けて、裂け目ができ、砕け散った。解けた。
「ウソだろ・・・」
口を大きく開け、鎖を大きく振り上げ鉄球が意志を持つようにヴォルフリートを襲う。
「どうあっても戦う気か、くっ」
パンドラの背後にまわり、鎖をよけながら後ろから頭をけり上げた。声をあげて、パンドラが倒れかけて――。
閃光。光が視界を遮る。
フォボスの仮面はずり落ち、フォボスの身を守ることまではできたが、全身に痛みが走る。
「何もこんな場所で秘密会議しなくても」
ズゥゥゥ・・ン。漆黒の長い髪がダークブラウンの短髪に変わり、自分と同じ顔の少年が呆れた顔で自分を見ていた。
『・・・・俺は帝国に追われる身だぞ』
フォボスの体には、《ゼウスの盾》と呼ばれるアイテムがある。
「フォボスっ」
エリスが駆けつけてくる。元パンドラ地区のレジスタンス。尖った耳が赤みがかった茶髪の髪から見える。
「大丈夫ですか、これは一体――」
『平気だ、けがはない、外部から攻撃されたようだ』
ほっ、とエリスは胸をなでおろす。「そうですか」という銃士の少女の声はフォボスに聞こえない。
「あっちは逃げたようだな」
おそらくこの攻撃魔法と騒ぎは、数いる敵の一つ。ピジョンクラウンだ。
「起こせ」
「自分でおきなよ」
エリスがゴットヴァルトを何やら咎めているが、フォボスはたしなめた。
「いいんだ、エリス、こいつは」
「ですが、立場をわきまえさせないと」
ズガァァァン。
「いったん、退却するぞ」
だが、ピンク色の髪の少女の攻撃魔法がフォボスとゴットヴァルトを話す。エリスが移動魔法で逃がす。
「行きましょう、とりあえず近くの仲間の元へ」
「待て、まだあいつが」
光の渦に飲み込まれていく。
「ゴットヴァルトぉぉ」
10
…最初から犯人扱いか。
共感はできない。生まれついて最初から手にしているというのは気分いいのか。奪われた時、昨日まで蝶よ花よと育ち、疑問さえ抱く必要もない。
「どうして、こんなひどいことができるんだ」
怒りに身を任せず、自制している。心配している。自分を陥れ、今の状況を生みだした人間に。
「お前は・・・っ」
胸ぐらを掴み、苦しそうに僕の気持ちになってつらそうに。
叩かれた頬はまだ痛みを伝えてくる。
「君はクラウド家に戻りたいのか」
けれど、僕はこの目の前の少年が選ばないことも知っている。
「俺はヴォルフリートだ、ヴォルフリート・フォン・ヴァルベルグラオだ」
「兄上・・・」
出会いがしらに、属性が知った。
ジ―クヴァルト・バドォール伯爵はマルスの目を追って、ピジョンクラウンのことはついでとか。
「はいはい、君の兄上ですよ」
反射的につい、不審者扱いしてしまった。いや、出会うなり、いきなり駆けよってくるから。
「再会した途端、ひどくないですか」
「ごめんなさい、ついヴォルフリート様を守りたくて」
解放すると、ジ―クヴァルトが茂みの中、隣に座る。
・・・ウルリヒ、こいつにいじめられてないだろうな。
そんな疑惑がふとヴォルフリートの脳裏にあがった。
「はい、下がって」
ゴットヴァルトはジ―クヴァルトの顔を木に押し付け、足でヴォルフリートを踏みつぶす。
「・・・・見回りみたいですね」
アヴィスは穏やかな笑みのままだ。自分の主が暴行を受けているのにな。
だが神経質そうなジ―クヴァルトはすぐにゴットヴァルトの横に座る。
「・・・ゴットヴァルト、あの男の元にいるのか」
「あの人のところだよ」
2人はどういう関係か、顔見知りなのか。ゴットヴァルトの態度はどうもはっきりしない。
「ああ、厳重だな」
かりかりする。
「憂鬱だな」
「・・・・・おい」
ヴォルフリートは肩を震えさせる。
「ああ、ごめん、つい足が先に出た」
ジ―クヴァルトは心からこもってない声で冷たい目でヴォルフリートを見た後。
「大丈夫か、カイザー?」
そういいながら、やたらゴットヴァルトに密着している。ゴットヴァルトは目の前の状況を注視することに集中していて、気にも留めていない。
「・・・大丈夫だ」
黒狼が乱入し、事態は混乱した。
11
「気がくるっている」
アルバートは、特魔のトップにそう言われた。仲間の表情が変わる。
「全てのサイトを閉鎖するだと、お前は平等と自由を誇りにする臣民を恐怖させたいのか」
聞けば、侮蔑的だが、帝国、いや人間ならば彼は一般的な人間だ。大事な全てを守りたい。
すぐにわかった。
だが、どこまでも自己本位な剣だ。
ヴィクトリアの洗練された一族に伝わる得意技《イ―グニス・ランヴォ≫と、緋の帽子らしいお行儀のいい技、まあガサツな乱暴者だ、天才肌だ。
だが、ヴィントは動き使い魔を放つ。
「また、同じ手を、馬鹿ね」
ヴィクトリアは単純な手と同じく、頭も単純だ。いつも戦う吸血鬼も同じようにタイミングよく現れてくれれば、あちこち探し回る必要もないのだが。
「馬鹿はお前だ」
閃光。地面の下からものすごい音、轟音を立てて、自分に正面から立ち向かってくる剣術馬鹿の足元を崩し、
「卑怯者、これは陽動?」
「気づくのが遅い」
精霊は姿を消し、緑色の旋風、いや、風の槍が一気にヴィクトリアを突き落とし、かく乱していく。
ズゴォォォォ・・・。
一気に凝縮させたマナを手持ちのナイフでヴィクトリアの首筋にあてる。
「ひっ」
「まだ続けるか?」
それだけでヴィクトリアは実力差がわかった。この戦闘中で自分の魔術に付き合いつつ、こんなものを生む策を考えたというのか?
東洋の妖怪、かまいたち――。
それに似た動物に似た姿の精霊こそがヴィントの相棒、契約した高位の精霊何だろう。自分のみの、自分だけを守るためだけの剣。
「・・・・あんた、それだけの力があって、弱い者のために使わないの?」
「あ?」
「その力があれば騎士団や侯爵家だって見逃すはず」
だがヴィントの鋭い眼光はヴィクトリアを追い払う。レベルが違うと。甘い考えを正面からなぎ落とす。まるで王者でも前にしているようだ。こんな男を従わせる人間が存在するのだろうか、少なくとも負ける気はないが、自分は頭を下に下げ、強い意志のこの男を曲げることなどできない。彼の心は固い。
「今は帝都では多くの術者が黒狼を追っているはず、お前は何をしている?」
「最悪・・・・」
こんなやつに借りを作るなんて。
「洞窟か、歩きづらいな」
鼻歌を歌いながら、ヴィントは先を歩く。
「おーい、まだ通信機回復してないのか?」
「もうすぐよ」
多分。こんな姿を、それも一族の嫌われ者といると聞いたら世話役のう―リアはまた雷を落とすだろう。
「あんた、大きいのね」
上着を貸してくれたのは親切心なのか。
「ん?」
「黙れ、変態っ」
剣を振り回すがヴィントはよけていく。余裕だ。
6
ドォォォン・・・・。
エドゥあるとが駆けつけた時、近衛騎士団の守護者、オールコットの関係者でパンドラの剣士の少女がすべてを終わらせていた。ゴブリンたちが駆けつけてくる。
「そうですか」
性格云々ではなく、アルフレートは貴族主義の母ときが合わない。元々は北の大女帝の古い名門貴族で父は帝国軍のトップでほぼ自分と顔を合わせない。カイザーの家とは違い、ここは一般的な貴族の過程で、魔術師で、使用人もその領域を超えてアルフレートを関わる必要がない。
「では」
彼ら両親はそもそも、本家の公爵家と折り合いが悪い。表面は仲いいが、実生活では関わらない。金色の天秤の塔に入れられ、才能や実績はあるが、やはり代わりでしかない。可愛げがない、人形のような子、周囲の人間がいい、両親も兄弟も否定しない。
ただそれよりも、特に母がクラウド家と関わることを快く思っていないのがわかっていた。
「基礎体力つけた方がいいんじゃないか」
「うるさい・・・」
他の冒険者たちを防御に使いながら、コーデリアの後ろで移動を続ける。
「敵はあまり潜んでないわね」
それにしても、ヴォルフリートね。
コーデリアはヴォルフリートを見る。魔法は素晴らしいが、実戦経験は少ないのだろう。
「あんた自分一人だけで倒しに行く気だったの?」
リュックを背負った小柄な少年が妖精たちに何やら聞いている。
鎧を身にまとい、剣は持っているが、狙われて終わりだ。
「パーティーを組む相手がいなかったんだ」
それでも武術系や剣士とめぐり合うのか。
「ま、いいけど、私の邪魔しないでね」
フレーヌは女神の像に向かって何やら唱えている。戦前に神頼みだろうか。
「行くわよ」
「あっ、コーデリア、待ちなさい、トラップがある可能性が――」
「大丈夫ですの?」
レガリアがゴットヴァルトをお姫様だっこしながら、やたらきらきらしたお―ラを出している。
「・・・ああ、ありがとう」
ぶしゅううう。
「赤い液を出すだけの魔物だったらしいな」
「練正反応・・・、錬金術師が絡んでんのか」
冒険者の一人がゴットヴァルトに言う。
「お前が門を開け」
「わかったよ」
バリィィン。
触れた瞬間、重層な結界が、扉が粉細工のように一瞬で壊れた。
「いくぞおおお」
「うぉぉぉ」
冒険者が一気に飛び込んで剣や銃を手に取る。
召喚魔法が作動し、中から次々とウォーロックや低級の悪魔が登場する。
「馬鹿な、こんな一気に」
レガリアから離れたゴットヴァルトはペルソナを展開し、ヴォルフリートだけを守る。
「お、おい、他のみんなも」
「君の命はここにいる全員の命よりも優先される、この場を離脱するよ」
「ふざけるな、助けるにきまってるだろ」
ボン、と行く手にゴットヴァルトが鬼火を出す。
「なんのつもりだッ」
「せっかくの好機だ、先に進もう」
乱暴に手を振り払い、ヘンゼルを助けに行く。
「ちょっ、馬鹿なのか、君はっ」
「ぎゃああああああああああ」
「グレーテル」
「・・・お兄様」
ミノタウロスは冒険者のほぼ半分を殺し、コーデリアは血まみれとなり、仲間の陽術士が。
「救世主様、先に」
「馬鹿を言うな、一緒に」
「僕達は別行動します」
だが答えるより先に、ゴットヴァルトがヴォルフリートの背中の服を掴んで、次の扉に向かう。
「コーデリア、みんなぁぁ」
頬を思いっきり叩く。
「いたいんだけど」
「最低だ、お前は・・・」
涙を浮かべ。にらんでくる。
「君がいても状況は同じだ、誘拐された娘を助けないと」
「わかっているよ」
きっとみんな、生きたかっただろうに、俺が不甲斐ないばかりに。
「ピジョンクラウンは自分の仲間に何でひどいことをさせているんだ」
「さあ、僕にはわからないな」
僕達に仲間意識求められてもなは言わないでいた。
「同族なのだろう」
「君はまさか人類すべてが知り合いとでも?」
はっとなる。
「馬鹿なこと言ったな、悪い」
「止まりなさい」
7
7
8
9
10
11
赤い髪の少年と背中合わせになりながら、魔女の配下とエルフリーデは戦う。
「ケイロス、あんたいつも誰かに狙われてるわね」
「まあ、人気者の常だな」
「ふんっ」
フードをかぶった、髪のひと房が薄紅色の少女が口から青い炎を出す。ケイロスの仕事は、パンドラハンター、冒険者の一形態である。
「・・・・・ジークフリート、真実なんてたやすく巨悪の前では塗りつぶされる」
「エレナ、お前にはそうでも」
「あまり深入りするな」
12
「ハンターとか、あんた裏稼業の人間が好きなわけ?」
アンティークの店に扮しているが、その実様々な情報を売り、冒険者にクエストを与える立場の緑のウェーブヘアの女性は、ドぅリという。
「イヤよ、そんな危ない奴」
くすくすと女性は笑う。
13
「セバスチャン~~」
つぎの瞬間、ヴォルフリートは意識を失った。
2
3
4
3
© Rakuten Group, Inc.