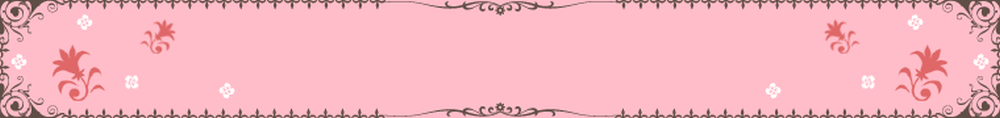第七章
1
「誰かを守るための嘘ならいいと思うんだよ、俺は」
その頃の僕はそいつとイツェン、三人いるのが当たり前になっていた。帝国側の死んで当然の作戦やレッドレジ―ナの作戦、必死に皆生き残ってきた。皆は家族のため、僕は姉さんのために。
「サクヤは正しいウソをついたんだ」
「だが彼女は死んだ、正しいことしたのに」
トマスは笑う。
「いいんだよ、それで」
「よくわからないぞ」
「その結果、多くのパンドラが俺たちは生き残れた、仲間っていいものだろ」
人は所属していないと不安になる生き物だ。友達思いで外で遊ぶのが好きなエリフリーゼはローゼマリーとともに、内向的ナリタと同じ雪の日、林の中で十フィートはあるトロールに襲われていた。
わからないものに恐怖するが、人は実は孤独が悪という概念さえなくせば、生きていける生き物ではある。
その時、空からシュテファン、手下たちが登場する。同じ姿のものに人は信頼を寄せる。深入りしない、考えすぎない、己のなすことだけ考えろ。
実に単純。
挑むこと。
英雄、弱いものは誰もが主人公を、神を求める。
最強を求める。揺らぎなきものを求める。
「皆がいるから俺は強くなれるんだ」
エルネストは勇気を与え、人々に希望を与える。迫る魔女たち。ああ、なんとグロテスクで醜悪な化け物か。
「無秩序は悪です」
「頼るべき国家がある、何と心強いでしょう」
ヴィクターは大人によって抑えつけられる。
「力ないものは価値がない」
恐怖や不安から逃れるため、挑むのだ。
「腹が減っては戦ができぬ」
「単純でうらやましいわ」
セレアはため息をつく。
「高貴なるものには、市民を弱いものを守る義務がある」
くどくどとジ―クヴァルト・オーウェンは妹やヘルミ―ネにいう。
「故に私達は何事にも揺るがぬ精神、誇り高くあることが重要だ」
ジ―クムントが笑う。
「女の子だろ、やめてやれよ」
「お前はまた適当に」
ワイズマンは、マギア・ウォーで敗北を決していた。あんな初歩的なトラップに気付かなかったとは。銀の頂の塔での勢力争い。
ドラゴン教。
「見つけたぞ」
あいつらの手のものか。
「はぁ、はぁ・・・・、出口までもうすぐよ」
ローザリンデは異界の中の迷宮の中で、敵に追いかけられながら恋人とともに逃げていた。
「どうして、こんなことに」
世界は常に流転する。
。血のにおいは濡れた身体にこびりついている。
「城が燃えてる・・・」
「デヴィッド、僕は・・・」
死んだ者には安らぎを。復讐を。パンドラを、弱いものを守る。
「お兄様・・・」
だが、少年が誓った日も、誰かが大きな希望を抱く日も、大きな唸りとは関係なく、同時に小さな混沌が、闇が、ある。
「ごめんなさい、弟が迷子で」
「いや、いいよ」
アレクシスは隣のローザリンデが不機嫌なのが気にかかっていた。
「大丈夫かしら、あのこくらいところ苦手だし」
「ほんっと、面倒しか起こさないわね」
後輩の言葉をトマスは魔術の実験の道具を運びながら偶然聞いた。
・・・・王国のスパイであり、帝国のスパイ。
結局、謀略やそういったことからは逃れられないのだ。
「・・・パンドラを使うのですか」
錬金術師でもある教師にセシリアはさすがに気まずそうに聞く。もちろん自分も真理を、神に近づくため、理を知るため、自分自身やパンドラも道具だと割り切る。
「ああ・・・」
情も厚い人間なのだ、ただ不器用なだけで。ここにいる者たちは、クラウド家と契約し、その一族を守り、代代その力を一族のために使ってきた。力を尊び、走り続けた。バーバラスは父にクラウド家に売られた。故郷は持たず、剣の道だけで生きる。
ーおまえはいらない。
なぜ反逆者、犯罪者になったのか。処刑される父、どういう人生なのか、ずっとスパロウ一派と同じく、親子の前に師匠と弟子、何かから逃げるように各地を旅して。自分を実際はどう思っていたか。
ー刃のようだな。
暴走するマナ、炎がバーバラスの体まで焼き尽くす勢いだ。ただ破壊し続け、強さを求める。壊れるだけ。
のあと何度か、剣で切りあう機会があった。主義が違うため、殺す剣であるノアやツヴァイリング、守る剣であるオーウェンやクラウド。拾われた命をオンで報いる。そもそも死んでいた命だ。
ベルンホルトに会ったのは17の時、これが自分の主だという。多くのルヴァロアが忌み嫌い、軽蔑し、打が納得せざる得ない男、自分は選ばれたのではない、あの男の数ある駒のひとつなのだ。そのあり方、姿勢は嫌いだ。守るべき人、自分が守るべき居場所。
「貴方は、誰?」
バーバラスはその時、終わったのだと思った。多くの人がテントの中で揺らめく。
「・・・いや、君の好きな人に頼まれてね」
「・・・・あの人が」
「幼いころから、ウリエルの禁術書を愛読する子供はどう育つのだろうな」
能力面は、文系理系、化学、精霊術、戦闘術やタイ術、指揮能力、マナの絶対的最高指数、知能は高い。
「だが愛想がない」
ギャップといえば、弱いものや動物に優しい。
トトの異界を引き寄せやすい体質。
「大人を負かすことに夢中になっては」
冷静なようでいて、ハインツには心に激しい炎がある。本人も気づいていない、神の血。
「苦手なものはないのか?」
その土地ののイチゴはハインツは苦手だ。この辺りは聞こうが変わりやすいうえ、霧も多い。神経質で外で遊ぶより、中で親しいものと遊ぶほうがハインツに合っていた。
「雷が本当に苦手ね」
「言わないでください」
自分を弱みを見せることは貴族のすることではない。妹が社交的、好奇心が強いせいか、役割、責任に囚われる少年だった。ナマジ女性の領主は周りになめられやすい。ゆえに、後継ぎのハインツは皆に尊敬される、公正な人間であろうとした。いずれ、皇族にもお目通りかかる、そう言われて。
イシュタルは封建主義、君主制国家で民主主義の国家である。国王陛下の子という考えが一般的だ、魔術師の名門の塔は軍国内の辺境に多く存在する。
もっともイシュタル軍は、錬金術を友としていた。
ハインツ・クラウドの一手が放たれる。首尾ができすぎている。復讐を黒髪の少年がやった。光のせいか、少年の目は獣の目に見えた。
背筋が凍るような、馬鹿な、相手はまだ11歳のこともじゃないか。だが裏切り者、手下は地面に冷たく倒れている。
本当の犯人は捕まっていないか。
フォールゴレ城女城主―ヴィクトワ―ルはしに、幼い兄妹は荒野に出される。
6年前のことだ。友人のフェリクス家でテロ事件が起き、その時ラストヴァーレという庶民の家で火事が起こり、フィリップはその事件の収束に明け暮れていた。
「私には理解できない」
貴族たちは何度か、舞踏会やらなにやらで集まる機会を作り、お互いを探り合う。若い令嬢たちがフィリップをみるが、今は目の前の女の友人の会話に耳を傾けた。
「エリーゼ、君は深入りしないほうがいい」
「何で、暴力に皆走るの」
それは違う、一面ではそうでも、理由は違うのだ。
貴族はただあんのんと生きることはできない。その豪華な暮らしを送る一方、必ず騎士団や軍、帝国のために生きることが運命づけられる。
すでに、エリスとエリザベートはオナシス家の領地、居城に行くまで好奇心と侮蔑の目で見られていた。
「マギア・ウォーのためとはいえ」
「あんなエルフもどきを調達する役目とは」
母親が死んだばかりの、ハインツがおのれの運命を決める3年前、二ケの肖像に双子のエルフ姉妹は送られることになった。
故に行儀見習いとして、城に来たエリザベートたちへの親切が、使用人と領民の不安を抱かせた。
「いい、アルバート、貴方はお友達を大切にするけど、ほどほどになさい」
領民からすれば、似ていない兄妹だ。アルバートはおとなしそうだが、馬鹿がつくほどのお人よしで、ハインツと同じく頭脳が素晴らしく、天才的に頭が良かったがマナの量だけ見れば兄弟でも随一、ハインツの片割れが天魔落ちでなければライバルだろう。
「ですが」
湖水地方でもあり、田園風景が多く、気候も安定しているものの、パンドラはトロールや妖精属がアテナの剣から送られ護衛している程。オナシス家がエルフと組んでいた事実は火種にならないか、けれどアルバートは幼く、先入観なくいもうとともに近づいた。
「貴方の欠点は他人の問題を自分の問題にすり替えて、自分をないがしろにすることです、なるべく距離というものを覚えなさい、皆が貴方ほど優しくも強くもない、お互いをお互いとして独立すること、でないと将来貴方が大事な人ができた時、破滅することもありますよ」
さとい子供は己を誇るか、謙虚になるか。ハインツほどではないものの、頑固者で趣味は祈り、友達と遊ぶこと、散歩。嫌いなものは喧嘩と卑怯なこと。ギャップは乳母が苦手なこと。好きな色は、意外にも赤だ。
「わかりません、さびしいです」
天使や精霊に好かれる体質、光属性であり、マナ欠乏症。
「いつもそばにいて、よりそう、愛し合う、ですが世の中にはできない人もいる」
「自分の世界を大事にして、自分を尊ぶこと、それがあなたの望む皆が幸せにという世界に帰属することと同じです」
少女は、その日壊れたことに気づく。
鮮やかな花、それも淡いピンク色の花を思わせる、箱庭で育てられた温室の花ではない。事実、少女は誰かのための姫君でいる気はない。
―貴方は、つまらない。
それが血を分けた両親がいうせりふだった。親だと思っていたエストカラス家の騎士。自分と似た顔の美しい魔術師、失望するヴァーチェナイト。
―私はは恥ずかしいわ。
侍女になるからとか、子息子女を守る守護者になるからと、フェリシアは剣術や銃、魔法と習っていた。青ざめた頼もしい父は地面にしがみついていた。
赤というよりは桃色に見えるウェーブヘアを腰まで伸ばしていた。アシュリー姫の異母妹。
そう男は、国王の弟。女王の義理の弟。
―いいわ、お前を私つきの魔法剣士にするわ。
男は、女王陛下を守る騎士を選び、アシュリーはフェリシアをただの騎士として扱う。「・・・・・・・・・いいや、フェリシア、僕に姉なんていなかったんだ」
高慢でプライド高い、わがままないやな女。それでも不思議だ、フェリシアはアシュリーを嫌うことはできない。自分のコマ、フレッドもそうだが、彼女は王女だ。国を民を思い、行動する。その姿、信念は王侯なのだ。
でも、フレッドが知らされた事実は、フェリシアよりも軽くない。アシュリーの自分への横暴は、ある意味では仕方ない。まじめで優しく、どこか危ないフレッドはある日、そう言った。自分とは何でも言い合える、気持ちいい友人で。
けれど、フレッドの中で何かが崩れ始めた。故にフェリシアは人の気持ちに少し鈍感という村の女性の言葉をこの後何度も思いなおす。アンジェリカ・フォン・エストカラス。彼女を慕っていた。そんなに会えない人ではあるが、ゆえにフェリシアはその事実をいまだ他人ごと、夢のようにとらえていた。エリックとどこに行くにも一緒で自分が追いかけて、喧嘩して、城に行けば彼の妹といたずらして。でも、家族は違う。
当事者で、被害者で、まぎれもない現実で。
大好きな哲学者との論争も剣の稽古もやめていること自体、フレッドには大事件だった。フレッドは笑う、どきりとする奇麗な笑顔で。アヴリルとも合わないで。
それ自体がいじょうだ、あんなに可愛がっていたのに、フェリシアは時間が過ぎれば強く気高い、生意気で面倒な優等生に戻る。フレッドは強い騎士なのだから、エリックと将来女王様の騎士になるのだからと、彼の恐怖や絶望はフェリシアよりも大きかったのに。
「え?」
「僕にはアヴリルや兄さん、フェリシアもいる」
大好きだった、尊敬し合える仲のいい美しい兄弟。お姉ちゃん子で、兄と同様、彼らにあこがれ。
「冗談よね、きっとすぐ」
「いいんだ」
「あの予言もあるけど、せっかく白の騎士に選ばれたし、夢もある」
当然抵抗した、訴えた。あの女のせいで・・・。
黒く濁った感情。本来なら天魔落ちだけでなく、それと同等、事件の陰のクルーエルエッグや魔術犯罪組織、貴族を恨めばいいが、天魔落ちへの憎悪がフレッドの中で勝った。ライトニング・ヴァリア女王陛下の居城、永久不滅の宮殿や様々な場所に呼ばれ、フレッドはすべてがアンジェリカにあることを知った。もちろん、家族だ。大好きな姉が急に極悪な犯罪者、人間以外と言われ。だが兄が妹の真実を隠すため、世界のために戦ったこと。母が姉のせいで死んだこと。
どうしようもないこと、手が届かなくなった、その人に対する尊敬と愛情。愛情はフレッドの中で憎悪へと変わった。天魔落ちだとて、騙していたとはならない。
化け物がいたせいで、彼はまっすぐでそういう区別を嫌う誠実で正義感のある、だが感情がそれまでの愛情も信頼も思いでも忌まわしいとゲヘ姿を変えた。
「でも、フレッド」
何か悪い人がいて、姉も兄も何の責任がない。そう真実を探すよう、父は教えた。だが、その父こそが反逆者の一味だった。
「これから、僕がエストカラスを守らないと、領民もいるし」
皆に優しい世界を、望めば夢がかなう夢。フレッドは納得するしかない。これから自分は彼らを守らないといけないのだ。
五年前、イシュタル中央付近の森林地帯、フォールゴレ城。
「デヴィド・・・」
その城をライトイエローの髪の少年が従妹とともに見ていた。デヴィッドは父の焔を止められなかった。トレイター、反逆者といわれるのに時間はかからなかった。グリーン色の青い瞳を、親友に向けられた悪意を恐怖せずにいられなかった。タイラント・ネイション―エンパイア、帝国と関係を持った。スパイ。王位継承争い、権力争いに夢中な人。淡い桃色の髪の幼馴染は、親切な人達に引き取られたという。
ヒュウウウ、ガタン、ガタン。
自分の体に流れる帝国の母方の血。蒸気機関、機関車も今日は動いていないだろう。女王の国はったんのこの大陸の移動手段。もっとも、旅行できるのは金持ちや貴族、一部の人に限るが。都会ではレミエルが発明されているが、都会から離れた場所はまだまだ牧歌的な光景が広がっている。
「ハインツ・・・」
―一年前だ。
ミリアリア・フォン・ランチェスター。
魔術師のクラスでは皇帝エンペラーのクラスまで言った女性。ブルー・ワイズ・タワーのトップまでいった一流魔術師。アルバートの母は白梟の騎士団(ホワイトオウル・ナイツ)でも、魔術師としてかなりの実力者だった。城の名前をベガという。ヴェーヌスでは、領主の一人に数えられる。ただアルバートの知る母は、貴婦人、賢い女性という雰囲気が強い。女騎士ビクトリアは常々、彼女から兄妹を守るよう言われていた。そんな彼女の後をパタパタと駆けつけてくる小さな足音がある。箱庭の姫君、甘えん坊。事実、彼女は領地とこの城の中でしか世界を知らない。アリア。
アリアは、ブラコンであり、ヴィオーラ・ローズに所属するパンドラの少女を天敵としてみていた。
ヴィントは、彼らさえ守り切ればいい、その時そう思っていた。ただ、モニカは革命自体、子供じみていると思うのか、今回は参加手いない。視線を前にいるアルバートに向ける。
「君まで巻き込む気はなかったんだ、リッド」
「ふん、今さらだろ」
リッドは鼻をならす。
「しかし不安だな」
中性的な雰囲気の騎士が、ぽつりとつぶやく。キツネ耳のパンドラの少女―カドナは首を傾ける。
「何で、準備万端じゃない」
ブルー・ローズ隊所属。彼女は落第生の暗殺者であり、槍使いだ。冷酷無比、任務遂行がパンドラのあり方だが多くの仲間のために帝国に逆らい、アルバートの元に来た。
「何というかスムーズすぎる・・・」
「大丈夫、俺達もいるだろう」
するとケンタウロス種を連れた青年剣士たちが近寄ってくる。
「ああ」
ヴィントが黒い馬に乗りながら、アルバートの横にたつ。
「俺達は革命を成就する」
アーロンは目つきの悪い褐色の目を迫りくるルーランの刃に向けて、とっさに魔術刻印を発動させる。マナを最大限に増大させる付属術式。
≪ハイ・ヴォレ≫
「きゃあああああああああああああああ」
「もう、大げさすぎ」
「だ、だって」
少女は涙ぐむ。
なんでも大げさで弱虫であわてん坊で。
「少しは余裕持ちなさいよ」
「はぐれパンドラの急増ですか」
「帝都よりは多いな」
数は30.帝都より数5百キロ。緑の箒の塔の魔術師たちが地元の名士に依頼され起きた怪奇現象。カラスがけたたましくなる。
「・・・・帝都で何が起きているんでしょう」
アーロンはちらとルーランをみる。
「その女に聞くしかないな」
「帝国に行く?」
「・・・ああ」
エリックは驚く。
「そうか、まあお前なら困らないよな」
「ああ、君もあまり無駄遣いするなよ」
笑いあうが、エリックは単純、明快に見えて人の感情に気付く才能がある。
「うるせえよ、まあお前と出会ったとき、いきなり殴ったのは悪かったよ」
「なら、いいけど」
何かがおかしい。
「なんかtラブルあったら呼べよ、助けに行くから」
「もちろんだよ」
フレッドはエリックに比べれば、大人だ、年齢とかではなく。ゆえにこれまで迷惑もヵけてきた。
「じゃあ、行くよ」
「おお」
学校は退屈だ。そこがい場所かといわれるとそうではない、あれはただ行くだけの。予定がなければ、人がいない場所や書庫、北庭にいた。
物語ではみ目のいい男女、明るいものが主役で多くがそういうものにあこがれるが自分はどうだろう。
世界も皆も平和も、お姫様との恋もいつも対岸の向こう側で。
手に入れれば、幸せなのか、それとも悩むか?
「いいかしら」
「ああ」
令嬢の誰かだろう、長い闇のような美しい髪が視界の隅で動いたが、柔らかい花のにおいも少しも興味がない。
ヴォルフリート・フォン・ローゼンバルツァーはただ一つ、天魔落ちという欠点があった。自分にはわからない感覚だなと思う。自分が弟にすべて押し付けた、カイザーはよくそう言っていた。
アルバートも、あってもいない妹をいつも思っていた。自分という不幸が彼女の人生の重みになる。誰かを思うことは愛することはこの世の自然だ。
「シエラ、あまり一人で動くのは」
扉が開く。
正義だ。法だ。
「何だ、君は」
アリスが笑顔を浮かべて、エレオノ―ルも笑顔で、ある日そのきれいな顔、きれいな服の少年を連れてきた。
「紹介するわ」
ああ、また姉さんの本物の兄弟か。彼女が、周りが光に包まれるほど、僕は今日も嘘をつく。
火の魔法で、フレッドは手紙の束を消す。
「・・・・」
命乞いなんて、まだ家族のつもりか。
破れた写真や手紙、思い出の一部を焼いた。
「悪魔のくせに」
何日か、閉じ込められたフレッドはシスターにようやく自宅に帰ることを許された。
「これでエストカラスも終わりか」
「しかし、15年も、なんであの死んだ女、すぐに殺さなかったんだ」
幼い金髪の兄と妹か。ユージーンはよくわかっていないのか、大人たちを見上げている。
「お母様を愚弄するな」
フレッドは叫んでいた。
「僕らは違う、違うんだ」
賢いフレッドは姉が連れていかれてから、捕まった父の代わりに事情を聞かれた。
「だろうな、お前らは悪魔に騙されていたんだろうよ」
「少年、天魔落ちがどういうものか知っているな」
「・・・・違います、そうだ、パンドラがパンドラが裏から操って」
涙が出た、でも何の涙かはわからない。
「う・・うっう・・・・」
ボロボロと、ただエリック達には見せたくない。
「うぅ・・・・」
揺れる汽車。姉さま、どうして・・・。
「うぇ・・・・どうして・・・・・」
第一区の遠縁の家は無人だった。
「どうぞ」
機械的な使用人の対応。寮に入ることも考えたが、今はまだ人前で普段通り振舞えるか。二階の隅の部屋。
「・・・よし」
アリ―シャはその日、父の友人の息子を町を案内している。ローザリンデはついてきてほしくなかったようだ。テレジアも来ていたが、派手な席は苦手なので散歩でもしているのだろう。
「紹介するわ、ローザリンデ、アレクシス」
扉が開く。
「私の弟、ヴォルフリートよ」
中にいたのは、目立たない地味な少年だった。あわてて、タナの後ろに隠れる。
なんか、野兎みたいだな、アレクシスはそう思った。
「ヴォルフリート、大丈夫、私の友達よ」
「・・・姉さんの友達でも怖くない可能性ないよ」
「来て」
アリスの後ろに隠れて。
「いいの、あんな子の世話任されて」
「別に嫌いじゃないし」
「あんたももの好きね」
ルドガーはアレクシスの後についていく少年にヒナ鳥みたいだと思う。普段はアリスの後についていき、彼女以外はあまり関心がない。世話を焼きすぎて、アリスに今接近は禁じられている。
アリスは人気者だ。ヴリルも無自覚に慕っているし、ランスも素直じゃないが彼女は好きだろう。ローザリンデはアリスが大好きだ、ヴォルフリートにはきつい態度が多い。嫉妬だ。アリスは皆仲良くがモットーなので表向き、そんな意地悪しないが。
「あの子に魅力なんてないわ」
「ドロテア様・・・」
だがすぐ立ち去る。典型的なわがままお嬢様だが、アリスの影響か、前ほど尖っていない、まあ手はやいた。アリスをその弟を取り巻きとともにいじめた。だが、真に彼女が恐れていたのはアリスだろう。
「ああいうの。ほんと、イライラするわ」
「まあ、少しは丸くなれよ」
「使用人がなれなれしくしないで」
そう言って、立ち去る。フェリクス卿をアリスに奪われたこと、気にしているのか。アリスはタフなので、ドロテアの嫌がらせもバリエーションないというだけだが。
ヴォルフリートに関してはいわゆるいじめられっ子タイプだし、ひどいかなと思うがドロテアは以外にも手を出さない。確かにすぐ死にそうだから面白みがないのは認めるが。
「お待ちを」
「君か」
守護者となるべくヴリル、ルドガ―、ケヴィン、バッハ、ランス、カーライル、ヘルマン、ウェイン、イリヤ、ビクトル、サミュエルという少年達はシェノルというリーダーがいた。
「はずかしいいいいいいいいいい」
いざべらは勢いよく走る、走る。
「退屈しないわね」
「ね」
どうせ、また教会に逃げ込むのだろう。
・・・・人生の鉄則、その一、主役級の人物には逆らうな。
「だ、だいじょうぶ」
何やらきらきら、華やかだが、大事な時こそその人物との関係がわかるという。大きい鉄球、北の大女帝の王子にいきなり鉄球を放たれました。後、反射神経、運動神経も鍛えましょう。
「ヴォルフリート」
姉さんが助けてくれたが、諸悪の根源は綺麗な笑顔を浮かべている。
「どうして、こんな」
アリスが睨むが、悪くないと言いたげだ。
「すいませんね、ヴォルフリート君に邪悪な気配を感じたので」
リリーナは目を開けると、アリスの姿があることに気づく。
「そうか、助けが」
「あなたはよくやったわ」
つまり、状況がよくなったのだろう。
回復魔法をカイザーに行いながら、アリ―シャは考える。
光のマナ、時間と法術、白魔法に近い魔術。
≪ハイ・トライアングル・サティスファクション≫
まったく、無茶をする。
「まったく、貴方といるとトラブルが多いですわね」
カイザーはむっとなる。
「何だよ、その言い方」
ブラン・ナイツ団長が領地に程近い場所で、キャサリン・フォン・アードラ―は、アリスに指をさして大声を上げる。思わず取り巻きの少女が止めるまでに。
「おぼえてらっしゃい」
キー、とヒステリックな声を上げる。余程負けたのが彼女のプライドを気づつけたのだろう。
「ええと、キャサリン」
カイザーはため息をつく。
「絶対お前を泣かせてやるんだからぁぁ」
「あの方の突入のタイミングは完ぺきだった」
それが、レーヴェ家の騎士であり、軍人の青年の言葉だった。鎮圧、武力による秩序、いつもクラウド家ばかり守るのではなく、必要であればアルトメルデ軍人として、投入される。
苦戦を強いられた戦いだった。
悪魔属の多くが目の前に迫る。卑怯ではない、戦場では生き残るものが真実で正義。ゴォォォォ・・・・。
「そんな・・・」
ヘレネは、一族を守る騎士達とともに、ッァバァイバスラ―家の屋敷がテロリスト、悪魔属の手に落ちたことに衝撃を受ける。
「突入せよ、生き残った者を助けるのだ」
キング・ナイト達が突入する。
翌日まで火が上がり、侯爵夫人テレ―ジア、その娘以外は全て炎が奪って言った。
そこへばたばたと、早馬だろう、オーウェン家の娘がグレース・ナイツの人間とともにやってくる。
「・・・う・・・」
天使がまるでこの世に生まれついたような、妖精にも似た姫君。リーゼロッテの親友。
五年後、15歳。
アールズの少女はその現場の中にいた。多くの貴族の席の中に。ツァイトフューリアの当主も、フェリクス家のエイルも。4年だ、母親は遠い場所で心の傷をいやし、アーデルハイトはその間、親友とともに親戚たちや魔術師たち、銀の十字架の人間と戦わないといけなかった。
だが、その間、アーデルハイトは小鳥から自ら空に飛び立つ白鳥へと成長を遂げた。「お久しぶりです、ベルンホルト閣下、国王陛下」
「国王陛下に剣を向けた小娘がよくぬけぬけと戻れたものだ」
だが、アーデルハイトはふっと思う。男は数秒、驚いた表情を浮かべた。
王宮騎士≪ゴッドナイト≫や軍の上層部、騎士団。
ゲームはまだ始まったばかり、そう自分自身が操り手となり。復讐を果たす。
「全ては女神様と崇高なる国王陛下、王子殿下の温情のおかげです、幼きころとはいえ無礼を働いたのは事実、心よりお許しいただいたことを感謝します」
「魔術師らしく、人の心を捨て自ら剣となったか、私をさぞ恨んでいるだろう」
「まさか、今日まで美しい我が国の皆が笑って暮らせるのも全て聡明な貴方達のおかげ、恨むなどあろうはずがありません、陛下がオ社ルように臨みは自分の手で、血に染まる覚悟でございます、銀の十字架の権限と支配権をお与えくださってありがとうございます」
「ならば言うこともあるまい、その力存分に使うがよい」
「御意」
7年前―。
世界の全てが灰色にみえる、虚ろな目で膝を抱えて座り込み、道歩く人を見ていた。
超モンスター級の嵐にみまれ、ぬかるんだ道には、驚くほどの人がいきかう。あるいは今だ、機能が続くと思いこもうとする人達が座り込んで酒に酔い、叫んでいる。
絶対強固な人類の最後の楽園。アトラスミュール。
だが、救う人間に対し、被害に遭う人間の多いこと。
帝都以外の要塞壁は密集しつつ、身を寄せ合うようにテントを張っている。
まるで黙示録――餓えた人間がいて、家屋は崩れる寸前で、だがそれでも帝国臣民はすぐに過ぎ去る嵐だと思っている。
生まれ持った満ちあふれた生活からこんな生活で、死ぬ人もいるがアルヴィンにはその勇気がない。全ての人に共通するのは土気色の顔で、絶望と先の見えない不安に心を腐らせて。全身をけだるさが襲い、意識が遠くなる。
アルヴィン自身、どうすればいいか、何にすがればいいのかわからない。帰る場所があればとっくに帰っている。
天魔落ちが最期を迎え、狂った卵と接触した。それで毎日、死者が出て、戦況は悪化していく一方だった。死んだ人間は焼かれるか、土をかぶせられる。母と妹は葬式を上げてもらえた、他の人間と合同でだが。
だからと言って、なんだか母達の死が簡単に扱われた気がして、そんなことを思ってしまう自分の心の狭さが無性に情けなくて、泣きそうな目元を何とかきつく締める。
静粛な、神聖な小さな教会でアルヴィンは最前列に座らされていた。色とりどりのきれいな花に柩がいくつか並べられて、泣いている人もいたがあれでは誰が母で妹の柩なのかわかったものじゃない。
司祭に黒い塊が入った四角い箱、小さい箱がアルヴィンの家族といわれ、触ることが許されたがすぐにそれは崩れた、細かくなり手の中からこぼれていった。
「やめなさい、なんてことを」
「うわあああああああ、違う、こんなの母さんじゃあいつじゃない」
暴れて、泣いて、喚き散らして。暴れん坊で乱暴者、だがその一方でアルヴィンは賢い子供でもあった。だってつい先日まで、二日前まで生きて、笑って、村はずれの家で暮らしてきたのだ。ご飯を作ってくれて、抱きしめてくれて。妹は人形がないと泣いて。喧嘩もしたが、次の日には謝ろう、そう思って、またいつもの仲良しの兄弟に戻る。
柩の蓋を蹴飛ばし、あるものを投げて。そして、お母さんや妹は生きてると叫んで外に飛び出した。そうして、南方の辺境、魔女の被害が多い、避難民のいる仮設テントにたどりついたのだ。
「聞きしに勝るですわね」
「ああ・・・」
なぜ、パンドラを排除する彼らが上の地位に天翼属を入れているかというと、ある戦いにあった。前の第二席は純粋な帝国市民で、金色の天秤、マリアベルのあこがれの戦司祭だった。帝国南部、山林地帯。天気は曇りに包まれていた。
第七席、アウィン・ソルはすでにこと切れていた。
「死んだか」
その当時、ヴィントは第7部隊の一員で、15歳。キャンサールやそのほかの仲間とともに、パンドラ全滅を目標にしていた。
「行きましょう」
ズガぁァァァン。
赤いしずくが、石畳の上を流れていく。
ゴォォォ。
「罪を犯した者はやり直してはいけないのか」
ハインツの登場に、ヘルマンは驚いたように目を見開く。
「何で、お前がここに・・・」
「やり返そうとかしろよ」
「止めろよ」
アレクシスの声に馬鹿にしていたヴィクター達が言葉を止める。
「彼はよくひきとめてくれた」
「アースラ・ティーアマリア、行くのか」
どこまでも青白い、幻想的で冷え切った夜だ。彼女はたぐいまれな女神のように美しく、黄金のウェーブヘアに青紫の瞳で、王族の末席の吸血鬼貴族で多くの兵士と領民を持つが今夜、全てを奪われた。
「私はもうアースラじゃないわ」
宗教画に出てくる天使か女神の清らかな雰囲気で、彼女も白を基調とした緩いドレスをよく来ていた。
「だが、それでも人間の世界に行かなくても、あいつらはぜい弱だが自分以外のものには大変冷酷な生き物だぞ」
「・・・でも、彼らと家族を作った女王もいたわ」
「ああ自らダンピール、ヴァンピールを作った、迷惑な女だ」
だが、宮廷住まいの男は心からそうは思っていない。珍しくもない、何せ吸血鬼は人生が無限にある。だがハーフヴァンパイア、あるいは純吸血鬼化した人間は多くない、その証拠にブラッディ・ローズは少数精鋭だ。腐敗した王族や貴族の意地悪ではない。姿や体格も似ているため、子を作るのは可能だ。だがどちらも吸血鬼の血に耐えられるもののみがなるものだ。数多くの異形の魔物との婚姻が人間の世界に物語としてある。人間はそれを可能にしたつもりだろう、だが彼らにしたらそれは子供の人形遊び、使えないおもちゃがどうなるかは学ぼうともしない。鬼族(オ―ガ)のごく一部の禁じられた事件。怪奇伝説も、失敗を認めず、見ないふりした人間の偽善にすぎない。
「彼らは方法を知らないだけ、だから私は」
「変わるものか、あいつらが、君があいつらの自殺ごっこに加わる必要はないと思うが、今ではギフトを与えた山猿や盗賊の子孫ですら、自分の罪を子供に押し付けるのだぞ」
彼は、今の女王のお気に入りのことを言っている。先々代の女王の肉親か、使用人か貴族カは分からない。だが、蚊の軍人であり魔術師の一族は正解を引き当てた。
ローゼンバルツァーは、見事なまでに隔世遺伝のようだが。アルバート、彼の予備のパーツのあの少年。
「あいつらは赤の王を滅ぼす」
ルードヴィッヒはよく夢を見る。
今は遠い、なつかしきとある昔日の夢を。
「アンジュ、ディートリンデ」
「いっておきますが、アリス、私は貴方の騎士達ほど都合よくありませんわ」
「厳しいこというのね」
その背中をセラヴィーナが見ている。
「なぁ、アーディアディト、君は無茶しすぎじゃないか」
アーサー城に、帰還するなり、ルードヴィッヒは、玉座に座る少女へと詰め寄って行った。
「あの大教主を仲間に加えたって」
「うん、みんな仲良しで、あの人も改心してくれて頼りになるし、私はうれしいなぁ」「また君は国王陛下を怒らせたんだな」
くすくすとどこからか笑い声が聞こえる。振り向くとエルフの剣姫、ルードヴィッヒの義理の母で二ある女性が笑っていた。
「リヒャルトがまたいを痛めるぞ」
「うん、それは悪いなぁと思っているわ」
「もう少し、君は人を疑うことを学ぶべきだよ、なあ」
フェリクス卿の横にはアレクシスの姿やヴィジット卿の姿もある。
「僕はアリスがいいというなら」
かぁ、とアレクシスは頬を赤らめる。
「きっとなんとかなるわ」
「また、それか」
「ルードヴィッヒもいてくれるんでしょ」
「しょうがないなぁ」
宗主もとものものを連れ、慈しむようにアリスにほほ笑んでいた。
・・・だが、実際は同じ村から来た金髪の弟である救世主と彼女は。
「ルードヴィッヒ様・・・」
ああ、同じ戦司祭の仲間が来たようだ。
「悪い、今、行く」
――夢の中でアリスは行動するとき、ある小鬼を連れていた。いつから傍にいたのか、ただアリスはまるで実の家族か兄弟のように笑顔で傍に置いていた。
黒い傘という戦闘集団の一人、チェス兵の。
―三か月前。エデン本部近く。地獄が広がっていた。
強ければ生き、弱ければ死ぬ。帝国臣民は過去の独裁を暴力を許さない。王族ともつながりのあるッァバァイバスラ―、レーヴェ、オナシス。アルベルトの家もそれに連なる。だが強すぎる光は力はただの市民ならともかく、同じような立場の者には恐怖を生む。ゆえに鎖を敷いて、できるだけ自分達の手のうちにしようとする。
死ねというのか。あるいは卑怯者にしたいのだろう。ばかばかしい。
≪世界≫≪太陽≫≪王者≫、水と光の属性を持ち、そのマナは父をも超える。今回の戦闘、討伐は大人数を要するが、それはアーデルハイト、白の騎士団団長に対する敵意で恐怖だった。
スかノハはスパロウ一派の直系の王宮にも使える、武術の使い手の一族であった。多くの影が、アルフレートを殺そうとしたレッド・ローズの戦闘員達を黒い刃で引き裂いた。
仮面をかぶり、道化師のような格好をした存在、それがスカノハだった。
「ひっ」
恐怖したものは二度と動けない。
アルフレートは。
今、そこには、応援で駆けつけた先輩たちの姿がある。
魔法騎士(マギア・エクエス)―実戦向きで、前衛に配置される魔術師の塔の出身の騎士である。
白魔術士―後方支援、仲間のけがを魔法で治し、全体を常にいい状態に保つ重要な立場であり。
多くの英雄の一人となって、アルフレートはその戦いにいた。
「姉様っ」
「大丈夫だ」
天魔落ちの少女達は、受け入れがたい現実に直面をする。パンドラは帝国に従うもの、彼女たちスレイヴ姉妹も茫然とそう思っていた。
多くのパンドラ達が軍を騎士を裏切り、敵側に寝返ったのだ。今までこんなことはなかった。
「ひでえ・・・」
「これ、全部紫の帽子がやったのか」
思い浮かべるのは、災厄の貴婦人、マッハの娘、戦争好きの絶大なる美貌と実力の代わりに悪魔に魂を売ったような、女皇帝のクラスにつくエリミア・ソラ―ヴァ。魔女部隊の指揮官の一人ではある。
カラスが泣いている。広がる戦司祭の死体。
夜の闇を溶かしこんだような髪に白い肌、イヤ少年は遠い茫然自失のアルヴィンは川の近くで、血で汚れた頬をゾフィーにハンカチで拭かれていた。
リディアが、キャるラインが、とる―バが死んだ。
「あああああああああああああああああああああああああああああああっ」
白魔術士に押さえつけられて、エルフリーデが後ろで叫んでいた。
「いやっ、いやあ」
抱えているのは仲間の死体だ。
「嘘よ、こんな・・・・」
「落ち着いて、エルフリーデ」
そんな彼女を見たくなくて、アルヴィンは世界から目を閉ざした。泣き叫ぶ彼女はいつもの戦乙女ではなくただの少女で無力な被害者だった。
「ごめん、ごめんなさい、私がわがまま言わなければ・・・・」
アルヴィンは手当てされたわが身を、ルードヴィッヒの言葉を信じた自分を恥じた。ダチに戻れる、俺を信じろと。
―4年前。
狂ったように、人が最大の愛の相手を失うとはこれほどの感情を慟哭を生むものなのか。その首を抱き、まだ少年だった兄は空に向けて声を荒げた。少女を殺した吸血鬼はすでに息絶えている。
赤の女王―レッド・レギ―ナに、その近衛にやられたのだ。兄は風使いであり、ルヴァロアの分家の人間ながら、炎に愛されることはなかった。銀の十字架の仲間の裏切り、ディアボロ家の策略。仲間や愛をこの時の兄は信じていた。だが、結局、家族以外にも国に裏切られたと思ったのだろう。
――だが、ヴィントは炎を抱いていたのだ。
精霊や神自体にはなくとも、その愛し方は炎のようでウルリヒにはそれが恐ろしかった。その炎は、ある青年が罪により身を大きな鳥に臓物を行きながら引き裂かれる、身をわきまえぬ罪を犯した時のものを思わせた。暗い。
漆黒の闇、夜の女神ニュクスが支配する世界の焔だ。
「待って」
ヴェーヌスの革命の中、アルバートをかばい、少女は命を落とした。
「・・・・兄さん」
鳳凰の巫女の墓は、山の頂上近くにつくられた。
だが、それは偽りの墓標だ。自分達が納得するためだけの亡骸溶かした少女の18年近くの人生など、死ぬ間際何を願っていたか。立派な葬儀だった。乾燥した空気や風が流れる中、多くの崇拝者が並び、誰もが涙した。国王の関係者でさえ、悲しみに涙で濡らして。
「待ってくれ、ヴィント」
オルフェウスがあわてて追いかける。
「そうですわよ、これはきっと事情が」
ウルリヒはひっ、と悲鳴を上げる。それほどの怒り、憎悪。兄はこの世で大事な人を失ったのだ。
「にいさ・・・」
拒絶、ではない、隔絶。般若のような、それでいて憎悪にみなぎった、嫌悪に満ちた表情。パメラの言葉も実の弟の声も届かない。
薄暗く、凍てつくように寒い。体の芯までウルリヒを否定する氷の瞳はその場全てをものを否定していた。
「お前たちの甘言など聞くものか」
そうして、兄は去っていく。軽やかな足音だけ残して。
少女のような、額の中央には花びらのような紋章、鏡のような大きな瞳、薄紫の長い髪を腰近くまで伸ばし、アリスに帝国の敵の場所を告げる。
「そうですか」
「できれば、パンドラを討伐するという使命は変えたいのですが」
「ああ、あんたが宮廷の穏健派のアズ―ル・アイスベルクか」
チェスを持ちながら、兄上達がまた厄介者を押し付けたと思った。
「お母君とはずいぶん、貴殿もやはり国王になられる気で」
「まあ、あの人はそのつもりらしいね、何せ小さいころから一族の期待背負ってるから」
ここにはオズワルドを慕う忠誠心のものはいない。みんな、誰かのものでおさがりだ。
「武術のけいこをしておられたのでは」
「必要ないよ、僕は跡継ぎじゃない、あの人、お母様はそこがわからないんだよね、だから僕が嫌いなんだ」
「勝つことで得られるものもあります」
「ごめん、僕は適当に生きる気だから、楽して、養われたい、昼寝して、面倒事は他人に任せたいんだ、お前も自分が不幸だと思っただろ、負け犬の僕の所に行かされてお先真っ暗だろ」
「そんなことは」
「僕は最初から負けている、決まっているんだ」
「?」
アリスの言葉で、カイザーの言葉で変わるアンジェロの統領にヴォルフリートは隅の方で首を傾けた。2人やアズゥ・ナイトは鎮圧しただけだ。お互いを認め合い、手を差し伸べる、だがヴォルフリートには皆が肯定する中、奇妙な不自然さを感じた。
「一つ忠告しておこう、この世に聖女がいれど、真に清らかなものなどいないのだよ」
「そんなことはありません」
「君はアリスを信じすぎる」
「ふん、どうせアテナの剣なんて、汚いことをしているのでしょう」
中等部一年、マリアベルはすでに魔術師から注目されていた。傲慢、女王様、自信家。実力があり、それ以外も優等生。
「・・・・ヘレネさんよ」
周囲がザワツクが、二人は挨拶はしないものの、会釈。
そもそもブレイヴにそれほど戦力が必要か、けれど、マギア・ウォー以外でも年々パンドラは増え続けている。そもそもである、彼らは同じように治世があり、それなりの戦闘能力、ペルソナを帝国の膝の下で彼らの安全を平和の名のもとに無視して、改造している。つまりはブレイクエッグが自然発生ではなく、だがその多くを生み出した研究者は認めなかった。
「ヘレナ♪」
「ルベンティ―ナ様?」
第一部隊隊長ラルフ・トランバぁ―スはジュレミア・ドーレスとともにその光景を見ていた。
フォルスが前に出ようとするがシフォン・アレイルに止められる。フィリベルト・ブリーゼリヴェ―レは騎士達とともに少女を連行する。
「待ってくれ、彼女は・・・」
ヘルミ―ネが叫ぶ。大勢の使用人、女友達、両親、だが、貴族の中からパンドラが出たなど知られるわけにいかない。
「アウレリアヴィーナ・・・・」
「ドロテア・・・」
妹とともに少女はエデンの大人の元に向かう。
一度はその考えに、自分は妄想して、エリク達は生きているんじゃないか、なら自分の幸福を考えてと、エレオノ―ル達の考えに従って。
だが、女神教会(ゴッドフラウ教会)の地下で、それだけは現実であることを思い知る。
ノア達の分隊で、訓練中に、柩の中の遺体を見る。
5年前――。
「まっすぐな奴だよ、アガットは」
「同じ村でしたっけ」
「小さいころから全然変わらないな」
持つものは持たざる者に妬まれる。それを体現したのが青の騎士アズゥ・カヴァリエ―レを親戚に持つアレクシス、ローザリンデの家だった。
栄光を持つものは打たれる責務もある。リーゼロッテと言えば、世界は正義と悪、貴族は弱きを守り、悪をくじく。ジ―クヴァルトにあこがれ、兄に近づきたいとよく次男坊の兄と騎士ごっこをしていた。
「クレイン家の」
「また金でもせぶりに来たのか」
「没落貴族が・・・」
金髪碧眼の弟はフィリップの変化に気づく。北方の生まれが色濃く出た養子で少し年上だが後継ぎはセアドアだ。彼は一般的な臣民で貴族で高いマナを持つ。
「気分良くないのですか」
純粋な温室育ちの上、パンドラを邪悪という一派の信仰者の家に育ち、だが帝国では一般的な善人の貴族の少年はプライドが高く自尊心が高いが、バルドゥルと比べて育ち、庶民だからと区別しない性格になっていた。
「・・・気のせいだよ、フィリップ」
・・・本当にパンドラはひどい。
アリスは極端な性格というが、自分はアリスこそ化け物たちと仲良くするという考え自体が極端だ、あいつらはこの世の悪だ、邪悪だ、いてはいけない。か弱き民を恐怖させ、自分勝手にふるまい、吸血鬼の手下として帝都内に入っている。
崇高で高尚な人間の慈悲深さを知らない最悪な奴らだ。
「そうだよな」
醜悪だ、最低だ、セアドアは負けず嫌いだが根は素直だ。今も兄を哀しい顔させている。孤児院であいつらは兄の家族を面白半分に殺したのだ。これを蛮行と呼ばず、何と呼ぼう。
「パンドラは貴方の家族を殺し国をだましている悪だ」
「自分を大事になさい、カイザー」
「グリム、でも俺は助けたいんだ」
「・・・貴方の美徳ですが、個人的なことでも、あまりマリアベルをかばうのはやめなさい」
「妹だ」
「・・・アンネリーゼが危惧するわけですね」
「彼女は最近イリスやアルバートと仲いいよね」
チェスではハインツが一位、アルバートが二位、カイザーが三位だった。
歌もうまく、詩の才能があり。
アーチェリーの腕前や剣術はヴィルフリートに迫るほどだ。
「俺達が帝国臣民に?」
アルバートやアリスは真剣だ。エデンのパンドラ達は、困った表情を浮かべる・
ドゥクス家は取るに足らない貴族で、子爵家であり、アルベルトの家と親交があった。
「伯父上が、魔物商の女なんかと」
よくある駆け落ち、けれど、魔術師の世界に飛び込ませたくない一族には不幸なことだ。
「嘘だ・・・」
「その女は、メイドの女の息子ですよ」
マーキュリーにしては、甘やかすリヒャルトと主をたしなめたつもりだ。
「そんなの関係ないわ」
「また、マイルールか、でも君はもう庶民ではない、身分は貴族で上に立つ立場なんだ」
面倒かけていた孤児たちと同じように、ありすを無意味ないさかいに巻き込まれないように。
「・・・それがレジ―ナとして必要なこと?」
「そう、君は親切と自己顕示をごちゃまぜにしている、そんなことは僕たちに任せるんだ」
「・・・アーデルハイト・・・」
だが少女はアルバートに気づかない。テレ―ジアも。
「行こう、ハインツ」
「ああ」
ズキン。なぜか胸が痛んだ。
優しくやわらかで、透明で誰かのことに一生懸命で。アリスはそんなアルバートが好きだった。
「武器を持つより、僕は皆と楽しく絵を描きたいんだよ」
「ヴぃ、ヴィンセント様・・・」
ミラージュは自分がその存在に委縮していることを自覚していた。ゴットナイトに何度も誘われ、国の重要な任務に就かれ、一年中平和のために動く騎士だ。
「アルベルトさまも」
「やはり、各地の混乱というか、抵抗運動は鎮静化しないのですか」
「まだな・・・・」
ローゼンバルツァー侯爵家騎士筆頭に尋ねてもそれだ。王宮内は、暇を持て余した貴族達、魔術師、軍人や騎士の勢力争いだ。
「間違いはないんですか?」
彼女たちは、女神の声を聞く宗主の言葉を直接伝える。
クラウド家にいる、金髪の少年が世界の命運を決める運命のメシアであることを。パンドラすべてを、トトの異界を救い、この世を混乱させ、破滅の世に導く悪魔を殺す宿命を持っていると。
「はい、神がそう予言されました」
「・・・悪魔は、誰なのです?赤の女王、それとも、人間のわたくしたちの誰か」
守るためにはj剣をふるう、それがアリスとアルバートが特に目立つ面だった。グリムと組み、帝国の敵を撃つ。
ヴィントは驚いたようにアルバートを見ていた。
「まだ、痛む」
「・・・意外と無茶するな」
柔らかく、ほほ笑む。
トトの異界から出没するウォーロックを討伐する役目を、ウロボロスの総統、ライナーに命じられ、寄宿学校に通いながらエルネストは送っていた。ローザリンデと出会ったのもそのころ。フィネとディートリヒを守るのはエルネスト、長男である自分だった。縛られることの嫌いなエルネストは時々、アーディアディトを連れて村に出かけたものだ。暗闇の中――。
「怖いよ、姉さん」
「もう怖がりなんだから」
弱虫目、情けなく思う。エルネストは行動派であり、思ったことはすぐする方なので、正直ヴォルフリートを情けなく思う。
「姉さんが唯我独尊というか、怖いもの知らずすぎるんだよ」
マナの瘴気が強くなっている。女神の精霊石の力が弱まっているからか。む、となる。
フォルクマ―ルがディートリヒをまた――。
近頃、師匠と弟子だからかあの二人は一緒にいることが多い。だがイライラする。自分はそんなに心が狭い人間だっただろうか。
「大丈夫、無敵素敵のお姉さんに任せなさい」
「意味分かんないよ」
「あんた、誰」
だがエドワードは餓えた少女に手を差し伸べる。多くのやせ衰えた孤児たちは餓死寸前だ。帝都からかなり外れた場所で、彼らは想像さえしない。
そう、クラウドの騎士、クラウド子爵の下の軍人の多くは孤児だ。貴族もいたが家を追い出されたもの、パンドラを人間といったもの、悪い子とか。
いつでも使い捨てられるか、将来便利な道具となる相手、おのれの利益のための材料。
ただ好意で助けるレオンハルトとは違う、最低な男。
バーバラス以外のそういった騎士達は、そこは感謝しており、日々クラウド家のために鍛錬を積んで勉学に励んでいた。
2
「うーん、僕はあまり役目のために生きる気がないよ、アプリコット」
「帝国に行かれるのでしょう」
「まあ、任務だからね」
花弁が散っている。
「しかし、わざわざあんな巨大な城での儀式とは」
「緊張してどうするよ」
「エリック、でもやっぱり姉さまの晴れ舞台だし」
「シスコン」
むっ、となる。
「フォルクマー殿」
「臆病者なところは変わらずか、アルフレート、ウルリヒ」
「お久しぶりです」
見下ろす要塞の下の街は平穏そのものだ。
「近頃、吸血鬼貴族にくみするものが増えているな」
「・・・フォルトゥスをお前が仕切ってんのかよ」
アルバートがにっこりと笑う。
「こう見えて、世渡り上手なんだ」
「・・・・回復魔法」
カイザーは驚いたように、二ケの肖像の姫、アンネリーゼを見た。
飛行船からそそがられる杖剣から、膨大な法術が、神の力がそそがれる。敵との戦闘で失っていた力をカイザーは、仲間であるアルベルトやアロイス、王宮騎士とともに彼女の人並みはずれた力で取り戻す。
「今ですっ」
ブラン・レジ―ナが兵士たちにげきを飛ばす。
レーヴェ卿の縁戚がアズゥ・ナイトにいた。オナシス家の遠縁が少女の騎士の中にいた。吸血鬼貴族は、その近の髪の結った髪の少年を見る。
「アルベルト、それにお前も私はお前が恐ろしいよ」
エドゥおアールは、弟とともに倒れている。
「どうして、わかってくれない」
≪慈しみの剣≫あるいは、≪妖精の閃光≫――レフミ―ムソード。苦しみを与えないよう、攻撃対象にこの世の罪から解き放ち、異界に送るローザリンデの剣。
その威力は、絶大だ。
「何というか怖いな」
「悪いことはできないものだ」
ヒュウウウウ、だがヘレネはその剣が恐ろしかった。
―アリスの左足のけがの後を、ヴィルフリートは知らない。
テントの中、アリスは囀るような声でヴィルフリートに言った。
「お願い、何も言わないで」
「そりゃ、いわないけど」
その時、誰かがアリスを呼びに来る。
「行きましょう」
「ああ」
ヴィルフリートは体を起こし、青の女王、青い戦闘衣(アズゥ・メディウム)のアリスの後を追いかけて行った。
テレ―ジア・フォン・フェリクスはこの戦いで、アレスの呪いをウォーロックから受け、テントの中で胸元のボタンをはずして、ヘルミ―ネの前で苦しそうに息を乱していた。無論、凛としたたたずまいのヘルミ―ネとて、無傷ではない。
「ヘルミ―ネ、貴方のマナが・・・」
「いいんだ、これくらい・・・」
顔立ちもどこかアリスに似たところがある。ヘルミ―ネのマナは《忠誠》《剣》属性の水属性のマナだ。
「今回は相手が悪かった」
「ブラッディ・ローズか」
その信念も相反する。恐怖、破壊のアテナの剣は恐怖と武力をもって平和を保つ、吸血鬼と人間の武装組織だ。テレ―ジあのフェリクス家と手、その実情はすべて把握していない。
炎の血族のルヴィーサ、大地のマナを持つ名家出身のガドール、水のシュテファンと従者のフェリスとネルケはその活躍の現場を確かに見た。
「撤回しろ、ヴィルフリート」
これが普通なのだとしたら、世の中がもう少し平和にいや、もっとすごいことになる。
「アンジェリカ・・・」
「アリシア・・・」
二人の少女は膜の中から、美しい天使のような、外見だけ言えば過言ではない姉と弟を見る。大胆不敵、悪く言えば頭がいい代わりに性格の悪い金髪の少年はまぎれもなく、アンジェリカを論破したハインツの双子の弟だ。
この国は薄暗く、住んでいる人も表情が薄暗い。
あのゾフィーと顔を合わせるよりましだが。アリスの弟たちはどれも美しく魔法の才能がある。ただ一人だけ、神は残酷なことをする。そう、天才すぎる上変人、唯我独尊、大変美しい兄弟の中での哀れな子羊。
その少年はそれゆえに注目の的だ。無論、姉とは哀しい意味でだ。白鳥の中のアヒル。青ざめた表情のオッドアイの少年は素材は悪くない。が、いかんせん周囲が特別すぎた。
「魔女と普通に会話してる」
姉さんとカイザーが。
「どういう神経してるんだ」
ある時は、ツインテールのとがった耳の少女が司祭の父とともにさらわれそうになり、「さぁ。悪党ども、私がせいパイしてやるわ」
「頼むから行動の前に考えるということしてよ、暴力はダメ」
紅茶色の長い髪の少女は茫然とアリスを見ている。
村のあちこちに、同じような、エルフの少年や大人がいる。アルトゥルは眩しい目でアリスを見た。
「何言ってるの、戦争や暴力を使うものにこの地球に生きる権利、いいえ、息する権利さえないわ、宇宙のチリに消えるべきよ」
悪人たちは茫然と少女を見る。
「無茶苦茶だよ、わぁ、ランスロット最大装備しないで、周りに村人もいるから」
その少女のことを言えば、大胆不敵。ふるうのは、闇も邪悪も許さぬ聖者の剣。
中東の小国にセレ―ズ卿は魔獣達に襲撃されていた。白い花が一面に咲いている。
「上見て」
セレ―ズ卿は、アリスに話しかけた。
「うわぁ・・・」
「あらあら、まあ」
王国の姫君は母親譲りの紫紺の髪にピンクの瞳、いかにもお姫様といった少女で独特の布地が少ない、ピンクの布を巻き付け飾り具で上の衣装とつけたような王族の衣装を着ている。母親が熱心ね二ケの肖像の崇拝者のため、浮世離れしている。
神纏いの少年は儀式によって・・・。
キルクスは黙示録を本気で信じる暇人達を思い出す。
ランタンが空に上がる。この世の栄華を不幸を知らぬ兄達。
根がひねくれているせいか、緊張感のある日常のせいか自分は歪んでいる。闇のマナ達、魔女達とつるんでいる方がよほど心地いい。
預言。
世界中に散らばれたもの。
この世の終末に悪魔達を滅びす予定調和。
キルクスは雪など見たことがない。王の子ではあり、あらゆる自由もてに入る。アリスの白い肌、綺麗な金髪は雪国を思い出させた。
けれど、自分は王子だと思ったことはない。衣食住は苦労したことはないし、教育もうけているが血の通わない冷血動物の巣。
それがキルクスの知る宮廷という大きな家だ。
魔術においては、抜きんでているが、アサシンの才能が自分にあると家庭教師が本人に言うような場所だ。王妃達は父のご機嫌とり、父は戦争狂、完全に外が見えない男だ。そんな奴の跡継ぎになりたい兄達は、おのれの徳しか考えず。
貴婦人達は、自国の民をその辺の獣とみている。将来の相手も決められている。皇太子の兄も自分も駒でしかない。
だが、民はその不満を王侯貴族ではなく、名前なき悪魔に向ける。
「宮廷に流血を持ち込むなど」
そういいながらも、帝国のようにローマ風の簡素な服に身を包んだ貴婦人たちは、見事なけんぎをふるうリーゼロッテとアリスを見る。
「全く、アリスといるとトラブルが絶えないな」
「リヒャルト、君も素直じゃないな」
―旅立ち前、白の女王と二ケの肖像に拝謁する。
「銀の十字架を拡大させよという声はありますが」
王宮騎士アロイスは頷く。
「ですが、させません」
3
表情が厳しいものであるティーナは、普段が見えない少女だ。使命と血族、帝国を守ることを重んじ、それゆえにか、優等生気質というか近寄りがたい。
「これまで」
「ありがとうございます」
武術の鍛錬や礼儀作法、貴族の心構えだの、のブレ李・オブリージュを教えてくれるが押しつけがましい。
「・・・ヴォルフリート様、少しお話があります」
長男であるエルネストを敬い、女性は後継ぎではない、そういう考えが彼女にある
。
額から血が流れている。テレジアがアリ―シャを見下ろしながら、泣いている。
「・・・・私は一体」
フェリクス家の屋敷。今はバラが一番の盛りだ。
「お兄様・・・・」
リヒトが泣き出しそうな表情をしていた。
・・・・何だろう。胸の仲がむずむずする。お兄様もアリスも大好きなのに。
「・・・・」
拳をギュっとする。別になんてことない。お兄様は友達が多い。それだけだ。
「頭おかしいか、クズだよな」
「いいすぎだ」
特魔の少年はルードヴィッヒの言葉にそう続けた。セシル達が入ってくる。
「見てみて、金色の蝶よ」
「姉さん、戻ろうよ」
「人生は冒険よ、本なんて無意味よ」
その緑色のコートの少年は、鉱物のような物体が身体の至る所についており、醜いというより、童話の中の悪魔に似ていた。孤児院の兄弟たちは警戒していた。
「はじめまして、私、アーディアディト」
「僕は・・・」
声が小さくてよく聞こえなかった。
「聞こえないわ」
「あっ」
綺麗なダークブラウンの、くせ毛かちの髪をしていた。
息が届きそうな距離で顔を近づけると、少年はあわてて顔を赤くして離れた。
「えっ、な、なに・・・」
逃げようとする手を強引につかんでほほ笑む。
「姉さんよ、あなた8歳なんでしょう」
「そうだけど」
「貴方を私の弟にしてあげる、きょうからここがあなたの家でここがあなたの家族や兄弟がいるところよ」
「木の上で本を読むの、意味があるの」
「だって部屋だと集中できないんだもの」
「ヴォルフリートか、天魔落ちかどちらか選べ」
「わたくしは・・・・」
銃口が震える。
「エレオノ―ル様・・・・」
「・・・家族を犯罪組織に」
死んだ少年は仲間とともに横たわっていた。
「ああ、まあ、・・・残念なことに失敗だね」
大人達は消えていく。嫌いだった。乱暴で下品でガサツで。
「何で、お前・・戻ってきたんだ」
真実は分からない。だがあるのは、子供を自分の目的のために切り捨てる誰かがいることだけ。
少年は最悪だが、金をためて、家族を取り戻すことに必死だった。それ以外必要なことなどない。頭も悪い、素行も性格も。だが少年には軍国の小さな町に帰ること、それでよかった。だから必死で、行儀などどうでもよい。
自分が彼にかなうはずもない。自分は必死になるほど何かを求めたことはない。
「トウモロコシの種なんて死んでいくときに守るものじゃないだろ」
「アルバートも姉さんもよくやるな」
「誰かが幸せだと嬉しいだろ」
「そうだ」
「ごめん、僕わからない」
「へえ、帝都にお姉さんが」
「それは初耳だな」
ハイエルフがよく来るな、ここは。
「紅茶に砂糖三個は甘すぎよ」
「何?」
「いや君のくせがでてるなって」
「小さいころからの癖で」
「切ればいいじゃないか、長髪にこだわりでも?」
「エレオノ―ル様がお好きでね」
「ああ」
「近づかないでくれ」
フロイデは女性達から慌てて離れた。戦闘では勇敢だが苦手なのだ。
「へたれ」
ヴィルフリートがきつく突っ込む。
「傍にいなくてよろしいのですか」
白の女王がアロイスの元に立つ。木の陰には、アリスがたっているがアロイスはあくまで騎士としての姿勢を保った。
「いや、ハインツを守ると約束したからな」
「英雄姫の御子息ですね」
「あいつは魔に惹かれやすいからな」
「またどこかで一人ふらついていると思ったらまたここか」
ヴリルとヴォルフリートは息を乱している。
「いや、しゃべっていただけでは、恋とは限らないわ」
「そうかしら」
4
「ワイバァン隊が通るよ」
「やだ血のにおいが」
アルフレートはその言葉に、軍の巨大化が原因で歯と思う。みんな、アテナの剣に報復されるのではと不安なのだ。オルフェウスがワイバァン隊に入った時にワイバァン隊は厳しいものになり、平和となった。
アデルを殺されて、エリーゼもパンドラを忌み嫌っている。アルフレートの叔父にあたるベルンホルトも本音は奴らを認めない。パンドラハンターの名門。流血は避けられないし、アルフレートもそのことは自覚していた。
聖者という言葉でアルバートを片づけていいのか。中央通りには人ごみがあった。庭園や市民の街を散策する。殿下は跡継ぎたる自覚がないと周囲の使用人や大臣はいう。賢王子。帝国のサーウィンの貴族の血を持つ大祖母の奇妙な死。
この時、11歳だった。大人顔負けの頭脳、可愛くない子供。冷めた天使。キルクスはいつ、刺客に命を狙われるかわからない。
・・・・アリス、お前はなぜ笑える。
アルバートのほほ笑みが癇に障る。
「イフリート隊ができたきっかけは、やはり」
ブラン・レジ―ナはッァバァイバスラ―と話す。バドォール伯爵は跡継ぎの幼子を連れて。役割を人生ととらえる。ゆえに違う価値観をブッシュノウムやグラヴィーダスは認めない。
「・・・・ああ、コウモリにいる」
その先は言わない。
「天狼撃滅波ッ」
アロイスの必殺技が、セラヴィーナやアリス、青の騎士を守り、敵の本拠地への道を切り開いていく。
「いくぞ、カイザー」
「ああ」
「アリス」
「ええ」
焔の結束【フレイム・フラル】――。
ウルリヒ・フォン・ルヴァロア。
「騎士道ですか・・・」
「ウルリヒ、お前もいずれ帝国と主を守るのですよ」
神殿から巫女姫とお傍づきが訪れていた。まだ春だというのに、日差しが強い日だった。
「できますかね」
「できるさ」
ヴォルフリートはピアノ以上に興味がないことには情熱が注げないらしく、騎士たちは怠惰な性格だと決めつけていた。
「決めつけるのは早いんじゃないか」
アルベルトが前に出る。
「無意味だよ、時臣、だれもが認めあうなんて」
黒の魔女、魔がんの魔女がつき世を見ながらそういう。グラヴィーダス家の追手が迫る。パメラは、時臣たちのリーダーと向き合う。
「それでも俺は」
金髪の美しい女性は、時臣に寄り添う。打ち合い、銃弾が流れ。パンドラによって多く、命が奪われる。アルフレートは仲間とともに住人を援護、マリアベルは魔女の手下を取り巻きとともに。
「結局、誰かの犠牲でどこも平和を保つんだ」
≪不屈≫≪友情≫≪絆≫、光と風の属性、ヴィクター。しかしあまりに強い力はアリスの力を持って制御できず、フェリクス卿は軋轢を生んだ。
「絶対に許さない」
「キャロル・・・」
鬼達の死体が女性が何をしたか示している。
魔女部隊の指揮官、エリーゼは厳しい顔つきで細身の女性の背中を見る。
崖の上の孤児院には異常なほど高い金属製の門がある。ナイチンゲール孤児院。アルベルトの家が、もっといえば、ローゼンバルツァーが所有していた個人経営の、孤児院だ。雑草が生い茂り、ブランコは壊れている。取り壊しが決まったその場所に赤毛の明るいライトブラウンの女性だ。灰紫の瞳だ。
「あれって、レにヴァト―ルの惨劇事件の」
「ええ、生き残りの・・・」
住民たちはかっての太陽の国の農村地帯で起きた悪夢を恐怖を忘れない。パンドラを使い、子供たちをトトの女神に送った黒衣の貴婦人の事件を。
「ローゼンバルツァー、オナシス・・・絶対地獄に送ってやる」
ひっ、と誰かが悲鳴をあげた。隠すことのない、憎悪が活発な雰囲気の21の女性の全身からこぼれていた。
「私は世界を家族を取り戻す・・・っ」
バーバラスのいた孤児院は絶望的な冷たさと乾いた空気の中にあった。
「もううぶなんだから」
「からかうなよ」
「お兄様も恋に策略を走らせばいいのに」
「・・・むう、いいだろ、別に」
光が強大であればある程、闇は深くなる。
血に濡れた女性の手には短剣がある。霧がある中、その様子をセレアは見ていた。多くの観衆が石を投げる。
「嘘つき、アンジェリカ」
「よくもだましやがったな」
舞台となったダンスフロアでは親戚、招待客全員が爆弾でも浴びせられたように、ものすごい表情で倒れていた。
「フレッドにいさま・・・」
「お姉さまは死んだんだ」
尊敬する二男が指揮を執り、醜い笑顔で取り仕切っている。フレッドは見たことがなかった。
「卑怯者・・・」
その中には、ドロテアの姿もあった。
「信じていたのに」
「ミラージュ・・・」
「魔女め」
一斉に石や卵、その場落ちるもので民衆はアンジェリカに投げつけ、アンジェリカを汚していく。額が流れても誰も気にとめない。
「何で、わたくしが・・・」
モノを動かす能力をアンジェリカは要していた。
そして――
「脱出したところで、無意味だ」
祖国を捨てられ、それまでの人生は捨てされ、髪は戦士に必要ないと切られ、アンジェリカはその身柄を軍国内の銀の十字架の審判者の前に渡された。
「二ケの肖像…お前がわたくしをはめたのね、恥知らずっ」
ちょうど、戦司祭として本国に候補生としていた時、二年前、アウレリアヴィーナが見たものだ。
「これが超トップクラスの天魔落ちの最終形態」
恐怖の権化、多くのウォーロックがひしめき合い、地獄の祭のようだ。強い結束が未来を拓く。フェリクス卿は、白の騎士団団長とともに、剣を構える。
「考えを変えないのね」
「ええ・・・」
シエラは先輩のブレイヴを曇りのない瞳でまっすぐ見る。
「後悔することになるわよ」
あらゆる賞賛や欲望、嫉妬、そういう感情を向けられるがアンネミ―ケはほこり臭い古書ばかりの地下室の一室で、アヒルを見つける。意識しなければ、気づかない。美しいものが好きで、耽美する癖があるアンネミ―ケはその痩せたそれがカイザーのレプリカであることは知っていたが、なぜわざわざこんな失敗作をあの男は作ったのか。
使用人たちも気にとめない。アリスの両親も兄弟もえてして美しい、輝きあるものが好きな傾向にある。白鳥の中のアヒル。
中身も粗末なものらしい。代わり者らしいがそれも別にいくらでもいる。ただ不幸なのは彼の種族だろう。身分違いの純粋な少年がほしがる時は最初から勝者の歪んだものよりも、そのエネルギーはすさまじい。
アルシオン・フォッリ―ア。
「エステルさん」
アリスが大きく見開く。
「アリス、貴方には死んでもらう」
そう言って、ロッドをアリスに向ける。
「気になるわ、ああ、気になる」
「姉さんとりあえず考えてからこうどうしようか」
「あまり無茶すると、西方の鬼が出るぞ」
「ああ、荒野に出る」
「昔どこかで子供を食べたんだっけ」
「イヤ殺人事件だよ、空想だよおになんて」
「おや、これは英雄の登場だ」
多くの賓客の中、時臣は、赤い髪の青年の貴族を見る。
「香水のにおいより、貴方は血のにおいが強そうだ」
来た理由はここの騒乱を収めに来たのだ。
「繊細な方なのね、サファイヤエル」
「私もそちらに向かいたかったのですが」
「いいの、グリムを頼むわ、私にはヴォルフリートがいるもの」
「シェノルにも見せたかったわね」
「あまり興味がなかったようだけど」
リーゼロッテは不満そうだ。
「どうする気だね、バルツァー」
「ディアボロか、どうもせぬよ」
「あの子はどうするのだ?」
アルヴィンをじっと見る。
「ローゼンバルツァーの実験体だな、全くアロイスも私を責めるならまずレオンハルトを責めてほしいものだ、だが、まあ、才能はあった、生かすことにする」
アルヴィンのそばにより、ひざを折る。自分達を悪だと屑だとよく言うが。
「アルヴィン、私がわかるか」
「・・・っ、あ、・・・母さんが妹が死んで」
「私はお前のなんだ」
「父さん・・・・」
「そうだ、お前の母親や妹には悪いことをした。私が憎いだろう」
短剣を与える。
「殺せ、そしてすべてお前らから全て奪ったものから奪い尽くせ、バルツァーとはそういうものだ、お前の祖父は私が手に掛けた」
5
「おかえり」
「・・・・・・・・きつかった」
「何、さっそくナンパされたの、あんた可愛いし」
出た、それ自分よりはまだまだだね、・・・・女の兄弟いるとわかるんだよな。
「違う、図書館の全種類の本とタイトル、人気作やマイナー本を言わされたのよ」
「ああ、本好きのオタクね」
「あれは変態よ、間違いなく」
「でも、新しい仲間だし」
すると、女子二人が俺をみる。
「じゃあ、あんたなじむよう、なんとかしてよ」
「・・・仲間だしね」
「イグナス、嫌われる勇気も必要よ」
フランシーヌのことをマリエル、いえ、エルフの巫女はおぼえてもいないだろう。
愛されていたが、自分個人をみられていなかった。いや、いい方を変えよう。私は誰も愛していなかった。膨大な力を放出させ、真上にいくつかの多面体、クリスタルをペルソナで生み出し、アズゥ・カルヴァリーレ、森の民を守る。呪いを振りまく、鬼と蜘蛛が混ざったような巨大な異界の魔物。
皆を救う、各地に散らばる瘴気やカオスコアを浄化する。
「すごいな」
「ああ」
微笑みの穏健派、ヴィオレ・ローズの上官の軍人はそんな男だった。
「人間がみんな隊長みたいだったらいいのに」
「それは無理ですよ」
「ああ」
全て、お前の思い通りか。
正しさの証のように。
「・・・」
彼女はきっとけがれることなく、生きるのだろう。何も奪われることもなく。
「行くぞ」
「は?」
弟を従者か。お前は自分の傲慢さを自覚しているのか?
特にそのおまけに興味があったわけではない。だが、帝国からの友人、その中では珍しい。
「待ってくれ」
アルバートが叫んでいるが、腕をつかんだまま馬に飛び乗る。
「門を開けろ、街に行く」
「は?」
お目付け役や従者がついてくるが無視した。
「とめ、とめて、ひぇぇぇぇ」
「大胆だな、王子の腰にまとりつくとは」
「いやいや、王子様、この馬早すぎる、止めて、止めて」
腰にしがみつき、泣き叫んでいる。
「街を案内してやろう、ついでにアークナイツを見に行く」
≪強欲≫≪忠誠≫≪誠実≫、フェリクス卿の剣をフロイデはついに最終決戦まで奪い取ることができなかった。外見は上流階級にいる明るい金髪碧眼、優美な青年だが自分の欲求に正直な男だった。
「君は甘すぎるな」
「・・・俺は」
「こんなもので、貴方の悲しみは満たせないでしょうけど」
「フィラン・・・」
「また、壁を見ている」
「貴族なのに気になるのかい、エデンが」
「あそこは金持ち、庶民階級が観光に行くところだ」
「ユージーン、リタ、どこ行ったんだよ」
≪勝者≫≪公平さ≫≪王冠≫、フェリクス卿が認める光魔法の選ばれし少年。剣術、戦術、魔術、あらゆる分野において全体的に、カイザーの次に強い。生まれながらにそうなので、彼の両親は王宮騎士、聖騎士の栄光の道を期待するのも道理だ。だが、憧れる英雄の気質は、同い年の少年や大人には化け物のように見えた。
・・・カイザーは何で、マナを使わないんだ。
ヴィクターにとって、アレクシスは都合の悪い相手だった。
確かに効果はある、だが赤の女王に手を貸すのは。
ヴィクターにとって、その少女は間違いなく、地獄から来た悪魔。人を破滅させる魔女だった。
黒髪の少女にとって、少年達は遊びでもなかっただろう。
またあの夢を見る。漆黒の闇に落ちる夢だ。叫んでも誰も来ない。
どんなにさびしくても。
―を殺し。
アリスを殺し。
炎が上がる。
エリクがカールがカリーヌが。
「・・・・あ、クロノ、二コル」
目を覚ますと弟たちの姿がある。
「私」
「姉ちゃん、泣いてたよ」
彼はのちにこの日のアリスとの会話を後悔することになる。称賛される金髪の少年に旗目で見て、黄金の髪のややゆるウェーブヘアと幼馴染に問い詰められている金髪の少年をはた目に、自分がパンドラであることで低位のパンドラは異界になかなか入ることができないのを忘れているんじゃないかとヴォルフリートは心配になった。
「でも真っ暗な暗闇に黄金の宮殿で誰もいない場所と聞いてるよ」
「止めないの、キルウス」
「いつものことだ」
「兄弟でしょう、喧嘩するなんて寂しいじゃない」
「・・・・あいつはいつも人を集めてるな」
「ああ、アルバート」
「何、神様かなんか」
6
「なんだ、やはりついてきたか」
服を着替えさせ、試合を見ている時、アルバートが飛び込んできた。
「君は高台から街を見下ろす趣味があるそうだね」
「貴様は血を分けた異母兄弟が使用人扱いを放置するのが趣味か」
果実をかじる。熱気のせいか、どうも楽しめない。突然の王子の訪問。急きょにしては十分。
「彼を返してくれないか」
「別にこいつはブルー・レジ―ナ専用の奴隷ではないだろう」
「君の不機嫌をごまかすためのものでもない」
「イヤ、二人とも喧嘩は」
「―アルバート、お前はなぜ、こんな無駄なことに付き合う?」
その少年は首を傾けた。何やら事情ありそうだが今は無視した。
「君は頭がよすぎるのが傷だと言われないか」
「アルバート、喧嘩は」
「いい方を変えよう、お前はあれが世界を救うなんて言う馬鹿な夢物語を叶えると正気で信じているのか?」
ああ、預言の、少年もわかったようだが。
「己は何者か、それをお前とあの女は他人に押し付ける気か、それがわがままだとなぜ疑わない?」
「・・・・何か、王子様、姉さん嫌いなんだ」
「ああ、お前は簡単でいいだろうな、他人に全て押し付け褒められて、自分一人満足させられない奴に世界が従うわけがない、お前はアリスに納得していないだろう?」
「それは・・・」
「ほしければ、頼るな、自分で選べ、挑め」
「ほうほう、つまり、王子様、アルバートと友達になりたいのか」
「僕はそれでも・・・」
王子はたちあがる。
「できなければ貴様は一生奴隷だ」
「そういう意地わるいうと、友達できないですよ」
「友達などいらない」
「守るべき民を守るために今日まで、王族は残るが過去を繰り返すことはあってはならない」
「同時に貴族も同じ、その権力は自分のために使ってはならない」
はぁぁ、とイシュタルの学生、ヴェデ―レは大きくため息をつく。
「おい、お前、放課後遊びに行こうぜ」
「たまにはかび臭い場所から脱出しようぜ」
―4年前。
ヴァンパイアに対する恐怖が軍国の民衆の中であった。
パンドラの魔獣兵はやはり、同胞ということでやりにくいらしい。
そもそも戦争の一端はもう何百年前からのことで、誰も知らない。王政であり、武力主義。気づけば、銃をとっていた。
人工的にホムンクルスや天使や神の力を持った兵士を生みだす。だがそれには民衆は反対だ。
だが、それでも、ヴェデ―レのハトコは、自ら名乗り出て、パンドラとなった。
フリッツたちに同じ道を行かせてはいけない。だが幼少時の恐怖はヴェデ―レを離してくれない。小休憩と言ったときは戦場で戦っている時よりも落ち着かない。
「聞いたよ、大尉に昇進だって」
「そうだよ、ゴッドスレイヴの実験に参加することでついてきたおまけのプレゼントだ」
「あまりうれしそうじゃないね、あと二年で戦争は終わるのに」
「プラチナ・ローズを全滅出来なかった、昨夜もまた」
「兵士は死ぬのが仕事だよ」
奴らの顔も名前も住んでいるところも知っている。精鋭の魔術士で軍人だ。
フェニックスの里と呼ばれる場所は、南方にある。そのおひざ元というわけではないが、ディアナの意識の中に鳳凰(フェニックス)の巫女の存在はあった。
神殿に行くのが病弱な母の唯一の楽しみだった。平和な場所だった。
「ディアナ様」
「安全がわかるまで、護衛役と一緒に」
ウォンに抱きしめられながら、誰かに雇われたリュンの暗殺者たち、父を殺害した軍人と手下たち。
「どうか、生き延びてください」
「・・・・第七王子?」
アリスはこんな夜更けにどこかに行く青年をハーモニーとともに見た。
赤い髪の小さな少年は好戦的で嫌われていた。だけど誰もが冷酷だと思わない。こんな国だ。雪と寒さと争い。強い奴が正義。
あの残虐さは、恐怖の裏返し、自分だって自分のためだ。彼女に出会わなければ、生きがいを戦いに見出してた。
「お前でも才能があったか」
「何の話?」
アリスが横入りするが無視した。
「他人を魅了する才能だ、だれでも一つは才能はあるものだが」
「もう一戦だ」
負けず嫌いだ、とヴィルフリートに思う。
「貴様も参戦しろ」
「僕そういうちまちましたゲーム嫌い、馬鹿だし」
アリスを見る。ぞっとした。なぜか睨まれた。
「重症だな、アーディアディトお前は」
「何で私よ」
「勝者、王子」
「よし、負けたっ、じゃあ本読めるな」
「なんてことを」
グレース卿は驚愕していた。
「アリス、君は僕と死んで呉れるだろ」
「友達だもんな」
「大臣たちのもくろみですか」
「おっと動くなよ」
「何で宮廷にダンピールがいるんだよ」
「・・・あ」
「大丈夫?姉さん」
アリスはほっとなる。
キルウスの頬を叩く。
「我慢を通すのもいい加減にしなさい」
フロイデは茫然となる。
「冷たいじゃない、頼ってもくれないなんて」
ヴォルフリートが貴婦人たちや王族を避難させている時、第七王子と立ち向かう。
8
「ユディっト」
獅子がテントの中の檻で寝ている。頬に火傷のある、紫色の長い髪に黒い水晶のような瞳、幻術使いのリ―ナ。
「スタンがどこに言ったか知ってる」
「さぁ、あいつも気分屋だから」
「双子でしょう」
ダインがまた、ドジを踏んだらしく、大人に追いかけられている。もっともこの歌劇団で異端なのは自分達双子だろう。本名はグローサー家に引き取られる際、捨てた。黒い髪に茶色の瞳だが肌は真っ白で、あまりに長い旅で、どこにも居場所はなく、東洋の人間といわれる外見だが彼女にはその自覚はない。本当の家族や仲間は旅している間、当然他国の人間と恋愛したり、人間同士、結婚もするわけで、背は高い方(ここでは低い)、手足も長い。スタンは鳶色の目と金色の目を持つユーリヒューマンで顔立ちも東洋の人間のように幼いが混血のにおいが強い。
「別にいつも一緒にいる必要ないでしょ」
「冷めてるのね」
「私はべったりする必要ないと思うわ」
それを聞いて、リ―ナは去っていく。薄暗い奴、いつもおどおどして。
「二コル、しつこい」
「いいじゃんよ」
「いいじゃんユージュニ―」
「私はユディット」
ある魔女によりテオドールは囚われていた。死の女神、殺戮の女神、黄衣の貴婦人。
「誓約・・・」
「ええ、可愛い人・・・」
「あはは、あの方に皇帝は無理だ」
「・・・正直言うな」
ちなみに軍学校、ヴァデ―レは閉鎖的な場所と思い拍子抜けした。
「だって18皇女だぞ、国王陛下は多くの妃を持つがその中の後ろだ、器量や能力見ても」
「冷たいんだな、貴族なのに、貴族は皇族を守るものと習ったのに」
「まあ、建前ではね、そういうのに必死なのは余ほど力があるものだけだ、後は諸侯として領地を治める。そして民主主義とのバランスをとる、まあ上といってもオズワルド殿下のような奇特な方もいる」
「冗談じゃない、ゲートを開けろ」
幻影魔法を利用したものらしい。
「イザべラ、見なくていいのよ」
「問題ない」
エイル、≪正義≫≪救い≫≪愛≫、風と炎の属性であり、召喚術士と魔法騎士の適性があった。
「・・・アルバート」
少女の視線にはあこがれの感情があった。
「貴方にはわからないわ、アリス」
アリシアが涙ぐんで、走り去っていく。
「アリシア」
ヴェーヌスのとある城で、大勢の人々がある少年の元に集まっていた。
・・・不気味な少年だわ。
タナトスの機密情報インの女性は、城の主が白梟の騎士団の人間であることは知っていた。
主君に手をかけ、権力を手にする。
よくあることだが、実際はそれだけではない。叛逆者となった領主は死んで、犯罪者の娘となった少女は守護者とにげたという。
権力を手にした軍人は別の災害のことも考えなければならない。別の革命でにげてきたソールの流民たち、彼らは盗賊となっていた。
「西の魔女の血か」
「大丈夫か、オルフェウス」
「・・・グレース?」
「・・・・ああ、あなた・・・」
すでに王子は臣下とともにこと切れていた。
「グレース卿?」
アリスがリーゼロッテとともに駆けこんでくる。
「そうか、グレース卿が」
「ローザリンデも辛いでしょう」
「・・・今は考えないわ」
「ディーター」
「二人とも気分転換しないか」
「・・・本当に来るし」
「いいじゃない、みんなで」
「そうだよ」
アリスとアレクシスはほほ笑む。
「お前は仲間に入らないのか」
少年の軍人が隣に座っていた。
「え、ああ」
「多分待っているぞ」
「僕はまだ、行けないから」
9
「吸血鬼もどきをお前の隊に入れると」
「ああ」
弟は事情がわからず、兄と父をみる。
「お前の居場所だろう、いいのか争いのもとを入れて」
「変革を求めろと言ったのは」
「ラインハルト様、ローゼンバルツァーは正しいのですか」
「さあな、ただ私は自分の道を進むだけだ」
「そうですか・・・」
聖女ルチア。
「あれが・・・」
「・・・・おにいさまがしんだ」
その日は冷えた日だった。だがウルリヒはよく覚えている。
「・・・・・エンヴリマ、本当?」
クララはよくわかっていない。
「いいえ、ハインツ」
「アンネローゼ」
「知らないわ」
「本当よ」
「ヴィーナ、駄目だろう」
「ごめんヴィルフリート」
「帰るんだ」
「アルバート」
「ああ、アリス」
「聞いたわ、ヴォルフリートに、実験で爆発事故があったって」
アルバートの前で女の子が二人――。
「ヴォルフリート、どうしたの」
「いや、なんか今日妙に気を使われるなって」
「そりゃあ大きな爆発事故だもの」
ローザリンデがアレクシスの頬を叩く。
「何かしら」
「フェリクス家に何かあったのかな」
「ヴォルフリート、じゃあ行ってくるわ」
「うん」
カイザーとともに、屋敷の森を散策する。
10
ヴィクトリア、≪調和≫≪命≫≪永遠≫、炎の精霊王と契約を結んだ娘は、兄と次期当主の座を争い合う関係だ。実際に強すぎる力は侯爵家でも扱いに困ったらしい。
ヴィンセント、炎と光属性、≪不滅≫≪鎖≫≪栄光≫、年の離れた妹と同じ精霊王と契約を結んだ、精霊剣士。あらゆる名誉と幸福を手に入れる絶対性の剣――グランツフレイムソード。
火の陰りは消えそうだ。だが、敵の一人はヴィンセントにかすれた声で。
「傲慢な、お前は聖人ではない、狂人だ」
「・・・」
アズゥ・ナイトやブラン・ナイトとも親交があり。
「その願いがどれほど罪悪か、自覚しているのか」
それは墓場、生命の気配がない匂いに似ていた。
「全てのものが安心して生きられる国だと、お前は俺より・・・・叛逆者だ」
「全員が幸福な、願いをかなえる場所だと、貴様は気がくるっている」
狐耳のパンドラの少女は涙を浮かべていた。
理不尽だ。
「アルバート」
「変えよう、この国を」
「え?」
「もう傷は治ったのに」
「回復したけど、休みなさい」
「いいな、フィネ達は誕生日パーティーで」
・・・セアドア?
何で、うちを見ているのかしら。
「メイドのマティアと」
「お父様?」
庭の奥でまるでデートみたいに。
「変なこといいますね、アリス」
「貴方のいた孤児院にシャノンなんて子供はいませんよ」
・・・そうか、あの場所ではまた孤児院が建てられて、家族が住んでいて。
きっと忘れているだけよね。
そう、村人も事情があった。
金髪の少年ヴォルフリートは自分を抱きしめる。
「いいんだ思い出さなくて」
「ヴォルフリート?」
「何もなかった」
平和な楽園のように見えた。
「私も協力するわ」
「イリス・・・」
「貴方達二人と、ここにいないあいつも入れて」
「空想かだな」
「でも嫌いではないでしょう」
「まあな」
鳳凰の巫女は愛らしくほほ笑む。
「ヴォルフリート、どうしたの?」
事件で両親を親戚を失い。
「アーディアディト」
11
「帝国に行こうと思う」
「え・・・」
けれど三日月を見る、王宮の中庭にいるフレッドは。
「なんか、いきなり・・・多くの事が起きて疲れたんだ」
「でもお前は俺とヴァ―ヴェナイトに、パンドラや他国から、貴族から皆を守るって」
「僕らの国だけじゃないよ、多くの国で間違った正義が横行して、罪もない人達への殺戮や略奪が起きてる」
「だから上にあがって」
「妹が神殿に移るんだ」
「え?」
「あの女が憎い、僕達をあざけり、カア様を利用したあいつが、父を自殺に追い込んだあの女が」
「止めろ、あの人はなにも悪くない、お前らしくない」
「そうさ、僕らは悪くない、悪いのは人の皮をかぶった悪魔だ」
「フレッド・・・」
「大丈夫、僕は君達と誓った夢を忘れない、それが僕の生きる理由、だからそのために僕は僕を捨てるんだ」
「再会できるか」
「ああ、三年後に帰るよ」
「アテナの剣に所属していないの?」
ユーリアはなぜアルバートが不思議そうに言うのか、疑問だったが。
「ええ、アリスの従者でもあるもの」
―5年前。
ヴァイオレット・ローズの隊長は前の隊長が戦死したことで、ユリウスかヴィルフリートかで決められることとなる。
「よいですか、セアドア、貴方もいずれパンドラを指揮する立場になるのです。あいつらを同等と思ってはダメ」
「わかっていますよ、お母様」
パンドラの子供たちに変化はない。ユリウスは納得できないでいた。
「ナイチンゲール夫人、それは間違いです、彼らも臣民です」
青の騎士とともにアリスが前に出る。
鮮明に聞こえるノイズを選ぶ
緑の箒の塔で、悪魔崇拝者が出た。
「見ろよ、あいつが」
「うそ・・・」
信じられないと、特魔の制服を着た少年達が男子生徒と悪魔が区の教師を連れていく。
ただし、現在において、悪魔とさされるのは亞人、特にパンドラと総称される魔物のことである。狩るものとかられるもの。
2人とも上流階級に近い立場の生まれだ。模範となるべき立場だ。ここで馬鹿にするなり、軽蔑するなりがバカな生徒でもすることだが、あまりの異常な状況に言葉も出ない。悪魔崇拝者はサイトといわれる兵士達の居住エリアの中の刑務所に送られる。だが珍しくもない。完璧な場所はない、例えばダヴィデは庶民の子だ、普通の家に生まれだ、ダメと決められた追放される。ノーマナには、マナを持つことが祝福と知っても理解できない。それでも、パンドラは魔物だと教わり、実際に魔獣園を今よりもチビな時に見せられた時、気を失ったものだ。
「いつもお姉さまはどこに行くのかしら」
「聞いてみようか」
「イヤいいだろ、世界征服クラブとかミ家の尻尾を追いかけたいとか」
「アロイスと行く所じゃないな、それ」
「・・・会わないのか」
「えっ、・・・いや、まあ、ほら、兄弟でもそれは個人というか」
「君は馬鹿だけど兄弟で誰よりも勘が鋭いのかもしれないね」
「そうか?」
「お父様はアルバートをどうする気だろう」
「ああ、親父様ね」
「アシュラ、また西方に行くのか」
「ああ」
「アリスが元に戻るまでは俺とお前で助けようぜ」
「軍に使えるの」
「まあ、才能は生かさないと」
「ヴォルフリート、いつか兄弟全員で、外国の海行こうぜ」
「君、虐めるだろ」
「一緒に過ごせば兄弟らしくなれるだろ」
「ヘンリーは、アシュラと」
「大丈夫、あいつらはやわじゃない」
カイザー、金髪、アルバート、ヴィルフリート、自分、クロノ、二コルで。
「俺らしくないかな」
「何だよ、弱気な声は君の毒舌はどうしたんだ」
「今は言えない、いつかエデンの地下宮殿の怪談は覚えてる?」
「ああ、姉さんやユリウスが言ってた」
「大丈夫、姉さんが何とかしてくれるよ」
「だな」
それを目撃した人々は言う。
アルバート。彼こそ、天使だと。
「どうなるのかね」
「まあうまくいくわよ」
湧き上がる歓声。
「過去はもう忘れましょ、ヴォルフリート」
「エリク達は帰ってこないわ」
自己犠牲、それはした本人はいいだろうが。
「これで全部か」
「ええ」
帝都以外の辺境では、比較的緩い。だが、貴族出身の男は、軍服と剣を持ち。
「国王陛下にあだ名そうとした賊たちは下の奴らばかりか」
「ラインハルト、貴様はこの民衆の戦争ごっこをどう思う?」
12
「そうね」
黒髪の長い髪の人並み外れた美貌、陶器のように穢れ一つない白い肌。人形のような整った顔立ち、女神の祝福を受けた少女は柔らかい桜色の唇を微かに動かし、ダレンの前で槍を取り出した。
「それは、村長の家に会った」
「僕もカイザーみたいに、正義の味方できたらなぁ」
「お前、人の苦労も知らないで」
王宮で、アリスは国王と面会している。周囲の貴族や騎士がなぜか驚いた表情をしていた。アズゥ・カヴァリエ―レはうんうんと頷き、アルバートやカイザーは頷いている。
「魔法か」
実を言うとだ、実際、剣術や戦術、そのすべてを傍観者、客のつもりで大体見ていたが存在は知るものの、マナ、魔法はこの時点ではあまり見ることが許されなかった。恐らく、守る意味もあった。アリスと自分との明確な区別を自覚していなかった。大事な使命だからとか適当に理解していた。
ハインツにそっくりな兄弟、レッド・レジ―ナも全て、深くは関わらずにいた。
魔獣園やエデンに言った後、馬車の中でこんな会話をした。アテナの剣は怖いところだ。だから知る必要もない。パンドラは何で残酷なんだ?
「姉さん、魔女も異世界も空想だよ」
この回答はアリスには以外らしく、驚いた顔をされた。イヤいや僕はオタクだけど、現実とフィクションわかっているよ。
「わぁ、冒険者だ、格好いい」
あれがパーティーという奴か。
ふと、ヘレネの後ろの少女を思い出した。アンネローゼとともに多くの友人に囲まれ、フェリクス卿の縁戚とも笑い合う姉の傍ら。
――僕はお前なんて未来永劫認めないからな、死ねっ。
セアドアといったか。どうも嫌われている。自然と自分は皆からはずされる。
――坊や、来なさい。
なぜか隅のベンチに座らされて、近くにいたエレオノ―ルが駆けつけてきた。少し前にエルネストに間違われ、さらわれそうになった、それ以来か、よくわからない立ち位置にいる。
姉の友人の少年、アルバートとアリス、たまにおまけで付いていくと、親切にされる。姉さんやハインツはすごく頭がいいし、ヴィルフリートもカイザーも皆に必要とされて。ただ、僕は姉に守られて。
いつか僕にできることもあるのだろうか、でも多分それはずっと先だろう。
「でも壁の外はわからないじゃない」
…嫌いではないが。
アロイスは何というか、苦手なんだよな。
「今日話していたユニコーンもライオンもしゃべるわけないよ」
それこそ自分はサーカスで出し物されていたが、一応は人間扱いだった。好奇心が強く、空想家。姉さんには作家の才能があるのかもしれないな。ただ、ジャンルを絞ってほしい。
「ようするにさ、姉さんの冒険譚ってダークファンタジー?」
日記帳はつけているが、エデンや魔獣園の魔物が人間とか。魔女や吸血鬼とか。いやにリアルで細かい。
「チェス兵に首切り女王って」
花が話しかけてきたとか。
「全部現実の話よ」
「ばかばかしい、ありえないよ」
アロイスが微笑んで、その笑顔にアリスはぱっト輝くような笑顔を浮かべる。それを受けてアファイヤエル達は複雑な表情だが、みな晴れやかな表情をしている。天気は嘘なくらい、雲ひとつない晴天で、鳥が鳴き、生命の讃歌が広がる。
「俺達は邪悪に負けない、これからどんな悪が来ても、強いきずなでこの美しい国を守って見せる」
ハインツとカイザーが手を握り合い、手を振り上げる。
「おお・・・っ」
帝都中が、臣民が悪夢から解放された。鳩が飛び去り、鐘の音が鳴り響く。
彼女の言葉はいつも正しい。姉のような存在のたおやかな青い髪の美女。目も琥珀を溶かしこんだように輝いている。
「アーディア、理想を語るだけでは臣下はついてきませんわ」
「・・・・え?」
けれど、その日々は彼らの仲間が奪った。ハイエルフ達はすでに逃げた。魔女が暴れ、一生でることがないさとは。
「お前はアテナの剣に行くんだ、もう必要ない」
「え、え?」
「・・・・・これは一体」
目をあけると、泣きつかれた姉さんやハインツ、カイザーの姿がある。
「動くな、君はテロに巻き込まれたんだ」
「先生・・・」
頭に包帯、両手にも包帯、パジャマの下も包帯で痛みが走る。
「何か覚えているかな」
「いや、確かフェリクスに行ってパーティーに参加して」
ズキンと痛む。全身が打撲しており、あちこちに傷があるそうだ。多くの人が死んで。
「駄目だ、全然入ってこない」
確かにそういうのは聞くが、僕がテロ?まさか、映画でもあるまいし。
魔女や異端者を拷問する司祭が、ミリアムにいう。
「お前の家族は天魔落ちのせいで、命を落とした」
奇麗なものが壊れた。愛していたものが嘲笑う。
「デッドドールで王宮を襲った・・・」
「そうだ、いずれかの魔術組織の仕業だが、操ったのは」
「天魔落ちやパンドラ」
真っ黒になる。ごうごうと何かが。
© Rakuten Group, Inc.