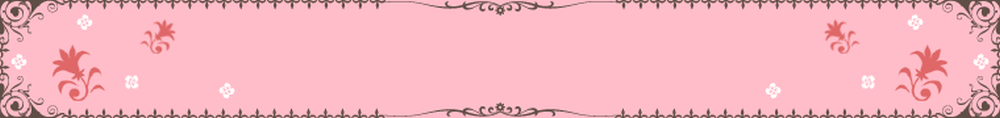第13章
1
可愛い。
「もう」
にらんでくる、可愛い。
・・・・・・・・・・・・・やばい。
イグナスは、自分の中の何かが壊れる音がした。俺はあれかな、実は浮気者というか、気が多いのか。何これ、アリスが可愛いんだけど。頬が熱い。
誘拐された令嬢の捜索を打ち切られたのは、エドワードが執事見習いから執事になった翌年のことだ。その次の年、エルネスト、ヘルミ―ネ、その次の年、フィネ、だが失った娘のことはエレオノ―ルの心の欠落を埋めることはなく。
異界が揺れる。
儀式によって、また現実界と異界がつながり、使い魔が現れる。12年の歳月を経て、娘は帰ってきた。
ロザリンドを、少年は不思議そうに見る。再会、数字で読んで、自分に剣を向ける。多くの屍、裏切りと策略、ナイトメア、ペルソナ。パキン、パキンと壊れる音が耳の奥でした。自分も彼に剣を、銃を、あらゆる手を使う。
躍進し、金属がかすりあう、引きずりあう音が強く響く。重たい細身の剣。人間離れして、建物の上を勢いよく、跳ねる。
「起きたのか」
紺青の海のような暗い色の髪を揺らして、その少年は自分を苛立ちながら見下ろす。
大きい音が鳴り響く、そうか、今は戦闘中か。もう嫌とは思わないくらい聞きなれた音。
「・・・・捕虜か」
テントの中にいるようだ。すると、一人の軍服の少女が入ってきた。
「・・・・アウレリア」
「はずしてもらえる?」
「信じるわけないだろう」
ラビッツはカイザーに警戒心を抱いていた。確かにカイザーとありすに近しいもの、懐かしい何かを感じるが。
「お前は性格悪いですね、色男」
世界が醜い、息苦しさを感じた人間はどうすればいいだろう。
「クロ―ディアにフォルデマールか」
身分制度は魂に身分というものをつけてしまう。
「・・・興味のない女を惑わせて、一体何が目的です」
歪み、醜く、すべてを腐臭があるものに変えてしまう。真実に気付いた人間はどう生きるべきか。
「バドォール伯爵か、君の知り合いだったね」
嫌われていることはわかっていた。けれどこの世界、停滞している。どこもかしこも嘘だらけだ。フォボスの誘いに乗ったのも、今を変えたいからだ。
「暇をもてあそび、女遊びして、世界征服クラブなんてものに入って、何でそんなふりを」
「家にいたくないんだ」
「君はアルバートと会うことを禁じられているね、何でだと思う」
ジュラルドが妙なことをいう。
「何でって、お父様が決めたことですし」
ラインホルトは触れてこなかったが、妙ではある。
「先日、友人になってね、16年ぶりに再会したあに何だろう、引き離すのは変だろう」
「さぁ、僕のそばだと変な菌が移るとか、価値が下がるとかじゃないですかね」
「双子というのは普通の兄弟より縁が深いというよ」
「今日も孤児院を回るの」
「えー、まあ」
変人だというが、自分と同じものを感じているとオスカーは思う。幸福なものがいれば、そうでないものもいる。
「僕に何かできることあるかな」
不幸なものを放っておけないのだ。結局は彼も。
「僕に取り入らなくてもカイザー兄さんは受け入れてると思いますが」
「気にしないで、これは僕が好きですることだから」
出席番号11番、ゴットヴァルト・クラウド。無欠だが、学校にはまあまあ来ているのだ。ただこのクラスが嫌とかいじめられているのではなく。
「では第一回、ゴットヴァルト君のパーティーのメンバー選出に入りたいと思います」
やべえな、このクラス。
「負けねえぞ、女子共」
「黙りなさい、男子風情が」
第一回って何、第二回もあるの、クラスにぼっちを出さないという姿勢は素晴らしいのだが、そこそこの戦力の僕に役目を与えよう、そういうことだがいらないです。
「ゴットヴァルトの前に立つのは俺達だ」
「はん、男子に彼を援護できるかしら」
ゴゴゴゴという声が聞こえる。
・・・・やっぱり、これはいじめ何だろうか。
史上最年少でワイバァン隊に入った幼馴染とぎりで入ったアガットは、ヴァーヌスの西端、フューマーズの村で生まれた。武器や工芸品を生み出す職人の町であり、独特の文様が描かれた機織りの乾いた空気の山に囲まれた、坂が多い場所。
「ふむ、この子には魔法と精霊使いの才能があるね」
鍛冶職人の父と元旅商人の母はお互いの顔を見合わせたが。
「じゃあ、俺達の子が国王陛下のために?」
およそ父達も祖母も村の人間も自由でのびのびして、冒険者用のクエストがあったせいだろう。閉鎖的ではない。
「ああ、君たちの子が英雄のひとりになるかもしれない」
「・・・・うちから魔法使いが」
「まあ、いいことよね」
アンジュは、誰よりも自信家で、ディートリンデ、アルフレートの妹は人前が苦手で他人に合わせる、自我が薄い少女だった。エイルは今でこそ、誰とでも仲良くできるが、小さい頃は人前に出るとあがってしまう奥手で清らかで、友達ができない。
その最たるものはシエラで人付き合いがこれまでかというくらい苦手で、あれで社交界で生きていけるか心配になるくらいだ。
最強なのがルベンティ―ナ、彼女はいかなる時も堂々としており、誰に対しても屈しなかった。
マリアベルは今でこそ女王然とした、堂々たる少女だが昔はカイザーの後ろに隠れ、派手なことは苦手だった。
ヴェーヌスの人間は、金髪でブルーの目のものが多い。ツヴァイトークもしかり。
残虐非道な悪行の数々。
ソフィアは部隊に配属される前から、家族に学校にと教え込まれた。
殺すしかない、悪の象徴。
ライバルいる人生は華やぐと言うが、南方(ヴェーヌス)遊撃魔法部隊から突如マーガレットに専属魔術師として選ばれた淡い金を溶かしこんだような髪を結いあげ、赤いリボンでまとめたソフィア・パシオンは隊長自ら、緋色の方舟(スカーレット・アーク)の優秀な生徒から選ばれた少女は、いずれフェイトドレスの隊長になる運命のはずだった。
「すごい混乱ね」
道中、どこかで革命が起き、周辺の住人達は対応に追われており、それはつまり渋滞、動けない状況に身をゆだねばならないわけだ。少女らしい可憐さと賢さ、年齢特有のずるさが全身を覆うほどのマントに身を包み、すらりとした脚をのぞかせている。
思えば奇妙な場所だと思う。貴族主義と平等主義。富めるものと貧者。ノーマナとマナを持つもの。例えばである、魔術師の多くは貴族が占めているようだが、マナを持つ子供を得た親は喜ぶか。アーロンは黒い髪に褐色の瞳、顔立ちもソールよりだ。だが、親の顔を知らない、腐抜けた貴族の子息、金持ちからは得体が知れないと孤児は馬鹿にされるが、それも当然だと思う。それにさらにマナを持つというのはいいことではない。自分はまだましだ。たとえば、パティエーンスヒューマンや遠い異国の血を持つ民族はマナを持つものをさっさと塔に入れる。
だが、なにも区別するのは上流階級ではない。
「気持ち悪い」
「でていけばいいのに」
皆が仲良く、別に臣民や貧民だけではない。彼らを下に見るものも願う平凡な願い。錬金術師はホムンクルスを作る、賢者の石を求める。
ユーリヒューマン、天魔落ちはパンドラとは違い、人間だ。だが、ルーツは魔術師も錬金術師もなぜ発生するのか、結論が出ていない。生きながらの亡霊。異端。結局は誰かを踏みつけないと秩序や平和はないのか。それでも人は夢を語る。願いを語る。妄想や理想なしには生きられない。
「ルドガ―、やめておけ」
闇が一切ないフォース・ナイツやフォルトゥナ騎士団。子供は少年や少女は諦めない。
「ひっ」
子爵位の貴族だ。悲鳴をあげて、孤児たちから離れていく。ルドガ―に負けただけだ。悪いことはしないが、あの男が庶民を理解する日は来ないだろう。
「なんで・・・」
レティシアは拳を抑える。フォルトゥナ騎士団の魔法剣士で、精霊使い。
「誰でもわかることなのに」
帝国の人間は、平和の中にいた。ゆえに敗北を知らない。アテナの剣がなくなり、アズゥ・カルヴァリエ―レもいない今、国と民を守るのは、人間達になる。敗北を知らない人間は自分のふがいなさ、力の無さが受け入れられない。怠惰で自分勝手なパンドラの方が多く、友人のパンドラが少なすぎる。今、多くが彼らだけではない、テロリストや魔女に脅されている。脅威にさらされている。とはいえ、日常は持続し、戦闘がある世界と平和な世界が同時にある。だが、死んでいく民がいるのも事実。叶わない願い。だがアーロンは、大事な人のために戦うことは時臣の正義であることは知っていた。
「行くぞ」
「俺はまた、大事な人を」
だがアーロンは時臣の親友でもない。一時の慰めこそ、軽薄なものもない。
「彼女はよく来るのか」
「まあ、本があるから」
ティーカップに紅茶を注ぐ。ディートリンデ、アレクシスは楽しそうだ。
「・・・・そうか、友達なんだな」
ゴットヴァルトは考える。
「どうだろう、大体僕叱られるか、意地悪なこと言われるか、冷たい目であきれられるかだから、あの人以外と感情豊かだよな」
「・・・・シエラがカ」
「そりゃ、彼女も人間だし」
ディートリンデが俺をみる。
「大変になりそうだね」
「何がだ」
「そうだな、シエラは苦労しそうだ」
「だから、何がだ」
出会ったのはほんの三回。いつも強くまぶしいカイザー様の後ろではかなげにか弱く微笑んでいて。兄思いの言い方だろう。
故に抱えてしまっている。大好きな人によく似ていたからかもしれない。だから一人になっている時、つい声をかけてしまった。
「お一人ですか」
「お兄様と会えないなんて」
大人びた外見と違い、マリアベルは弱気な女の子だ。
「大丈夫だよ、本の一週間じゃないか」
「でもあいつらがすむサイト近くを通るのでしょう」
「常勝の帝国軍がいつも通り守るさ」
「あの双子はいつも殺し合いをしているのさ、関わってはいけない」
ユニコーン属の少年が前を歩きながら、アリスに言う。
「なんで」
「理由なんてない、宿命だからさ」
勇気の聖女、癒しの聖女、掟の聖女、そしてソールの宿命の聖女。
彼女たちの存在は人々を導き、正しい道を目指すことだ。
「うぇぇぇぇ・・・」
ディーターが黙り込む。けれど、その一人が今、天空の神殿で気分を悪くして、死にそうになった。教訓、飲みすぎで死にません。
過剰な摂取は人をだめにします。
「世界なんて滅べばいいのに・・・」
変わらないものを人は求める。神様や聖女、そういったものはそういうものだろう。
・・・どちらも譲らないからなぁ。
また、カイザーとシエラが意見が衝突している。
「どういうことよ」
ヴィクトリアはウルリヒの顔を覗き込んでいる。シエラはヴィクトリアにとってマギア・ウォーにおける家同士でのライバルである。もっとも、シエラの父を一方的に敵視し、和解という言葉は両者にない。
「アデレイドがショタこんとはな」
「はぁ?何の話よ」
「照れるなって、そうだよな、お前も年頃だもんな」
「はぁ、イフリート隊って低能なのね」
「じゃあ、友達か?どちらにせよ、貴族様じゃ、無理だと思うよ」
「まだ友達じゃないわよ」
「え、マジ?お前、男に飢えているの」
「あんたたちみたいな変態相手にしていれば、オタクでも相手にするわよ」
「うーん、あいつも気の毒に」
「?誰よ」
「回復魔法が追い付かない、メルヴィ様、私はどうすれば」
エリザベートもエリスも頑張ってくれる。
「もう少し、もう少しだから」
パンドラハンターの人間はパンドラがいかに邪悪か、どう扱うべきものかを教わる。けれど、アテナの剣以外は、生息場所も行動理由も、不明で結界や変身など様々な術で姿を隠している。
ワイバァン隊での討伐任務で、アルフレートは仲間とともにゴブリンを囲んでいた。
「ちょっと、聞いてないわよ、こんなこと」
アーロンは深部下とため息をつく。カトリーヌは予想外のことが苦手なのか、唯我独尊、世界が自分中心なのか、魔女が結界を張らないわけもないし、トラップ魔法を仕掛けないのも道理だ。
・・・まずいな。
ここは神人の信仰が多く存在する地域だ。あまり騒ぎを大きくするのもまずい。
あんな迷惑娘を助けるのも癪だが。
「貴様も女だからと私を」
ネルケはオルフェウスをにらむ。
「はぁ?」
「自意識過剰か、馬鹿じゃねえの」
イシュタルと帝国は長年戦争状態である。スカーレットの初戦は、レッド・レジ―ナが奪ったイシュタルの貿易都市だった。
≪シャイン・リュジスモン≫
エイルはあわてて、反射的にエレクを守った。複雑な文様を描いた魔法陣。
「精霊術・・・、いや法術か」
ゴォォォ、ガラガラ。
「アレクシスッ」
駆けつけた時、アレクシスの家の別邸は燃えていた。燕尾服の紳士が多く運び出され、息はあるが酷いやけどの少女が二人、イザべラハディーターに保護されていた。
「しっかりして、アレクシス」
「僕は、僕は・・・」
リーゼロッテがアリスとともにセアドアと面会を許されたのは数日後だった。
「触るなっ」
「お坊ちゃま」
「化け物だ、あいつら全部、あいつも・・・皆ろくでなしだ」
「どうなさったのです」
「・・・執事さん、セアドアは」
ヴィクトリアも聞いていた。
「リーゼロッテ様、さっきはお坊ちゃんが無礼を」
アレクシスがローザリンデにほおをたたかれていた。中のいい幼馴染なのに。
「あ、いいんです、セアドアは何があったんです」
「ご友人が、その・・・旦那様がちょっとしたイベントでお客様と火をお使いになって、事故がおきまして、記憶が混乱しておられて」
モテル女子はつらい、男子も辛い。ついでにその周辺も辛い。
「あんたさ、勘違いしているんじゃないの」
全く、アルフレートのクラスが穏健だなんて誰が言ったのか。飛行魔法の授業はたまに参加する。ちなみに魔術の世界は古き良き文化、完全なる階級社会だ。
「何だよ」
人に尽くす子t、それを持って魔法使いは存在を許される。
「・・・・何で、園芸部に所属してんの」
まあ、ですよね。
「もしかしてなんか勘違いしてんの、ブレアがあんたを好きとか」
「キモチ悪い奴、同情で置かれていることなんでわかんないの」
「教師に無理やり入れられたんだよ、俺の意思はねえ」
「は?あんた程度が先生達の目に留まるわけないじゃん」
まあ、怒りやらなんやらが出るまで待とう。
「まあ、人付き合いとか、いろいろ」
「皆に迷惑かけてんの、自覚ないの?」
・・・・これはあれだ、すでに試合が終了している。
「キャロル、貴方達も馬鹿な子ね、逃げだそうなんて」
「くっ」
だがシスターはいっそ、清らかな笑みを浮かべる。
「地下には、崇高なる方々がもう今かと待っておられるわ」
ハルトヴィヒが行かされたかっての太陽王の国、レヴェイはアンジェロに対する偏見が強い場所だった。同時にイシュタルと長くかかわった場所であり、抵抗運動、革命が起きやすい場所だった。それでも、帝国はここが安全で平和な自由な国という。
「ひっ」
夜中、銃声でハルトヴィヒは目を覚ました。
燃え盛るルナーを、アルベルトが大きくフィ二スの横で目を大きく見開いている。
「なっ」
ガーネットは、セ―ラを連れてその光景を見ている。
「シュヴァルツパラソルに行くわよ」
「時臣・・・」
「ああ」
実際、臣民、さらにその下のものの声はきこえづらい。アールズやディアボロはバドォールの力の影響で動きづらい。
「だからあまり無茶なことは止めろと言っただろ」
「・・・もう来るのはやめるのです、ヘレネ」
クロ―ディアは静かにそういった。
駆け足で、少女は街中を歩く。聖騎士の少女だ。
「あっ」
ヒュウウウウ、下にはエレクが存在した。
「どいてください」
西の魔女(ウエスト・ソルシエール)は、魔女の中でも、魔術士の中でも嫌われ者でその名前を知る者はいない。だが高い魔力を持ち、直系の子孫はほぼ異端審問官、時の権力者に殺され、母は異界に落ちた。オルフェウスを助けるために。侯爵家は自分の才能を目的に自分を家族に入れた。でもただ一つの違いはルヴァロア家も兄弟も夫婦も受け入れず、駒扱いだ。壊れれば、他の駒を使う。いつも馬鹿にされた。意地になる、逆らえば罰が下る。でも自分ばかりだ。この家では間違いや弱者入らない。それは子爵家も同じだ。マリウスの上からのお恵み。だがある日、血縁だけの男、父がエデンに自分を連れていく。
「・・・ひっ」
たとえどう綺麗事や仲間や愛を語ろうと、これがこの世界の真実。イシュタルだろうと、暗殺者でもない、ただ彼らは語る。
パンドラは化け物だと。
デイジーは、その人の背中を追いかける。蝙蝠、他の生物に姿を変え、結局はなりきれない。横のマリエルに視線を向ける。屋根から屋根へ、獲物を追いかけて。
「・・・ご主人様はおられません」
扉を開けると、頬を真っ赤にしたアードルフの姿がある。
「そうじゃなくて」
ラフォール隊の活躍はデイジーの耳にも届いている。自分はゴットヴァルトの護衛であり、メイドであり、言葉にしてないが都合のいい駒かナイトにでも映っているのだろう。不服だ、実に気にいらない、道具扱いなんていや。
「君に会いたくて・・・」
純朴そうな少年だ。
コウモリの仕事の傍ら、ゴットヴァルトは、いくつかの別の人生を仕事柄しているので、前の人間達のようにこき使うとか…してないとは言わないが、どうもその方面にマリエルたちを強要するとか、他人にそういう振りさせるかは抜けているらしい。あるいはもともとは真面目で朴念仁というものだったのか、いや別に襲ってほしいわけではないが。いやな想定だ、なぜかそれを考えると大変苛立つのだ、赤の女王に遠慮している、あるいは恋慕の情が今だあるのか。
「すいません、仕える方がいるので」
ガ―ンとショックを受ける。自分の里や一部の世界しか知らないが自分は可愛い。
ともかく、ゴットヴァルトは自分やマリエルを連れ回す。まあ、仕えるのが仕事だから。
「君は、その彼が好きなのか」
「・・・意味がよくわかりませんが」
自分は巫女だ、神に帝国に仕える。だから、誰かと恋するとか、結婚するとか、そもそも同じ種族以外は選ばない。
「付き合ってはいないんだよね」
ここではだれもが好きな人と付き合う。勿論、階級もあるが、いくつか身分を越えての貴族とブルジョアとかの恋愛も結婚もあるのだ。
「ええ」
「じゃあ、僕とのこと、考えてくれるかな」
デートだの買い物だの、のんきな。
「それともゴットヴァルト君の許可、いるのかな」
「・・・聞いてみます」
「敵味方も愛し合いましょう?」
「な・・・んで・・・」
仮面をつけた魔女が青の聖剣で崩れ落ちる。
「ばかね、ありえないわ」
2
「気にすることないわよ、あの子もあれで周りの変化に敏感でライバルが増えると思ってんのよ」
「何のライバルなの」
「ほら、アテナの剣がゴッドナイトに鎮圧されて、普通に戻ったじゃない、でもやっぱり馴れてないから変になる人も当然いるわけよ、ローゼンバルツァーのテロもあったし」
「ああ、大貴族の」
「クラブハウスの奪い合いよ」
「アリシア先輩、いつもこうなんですか」
「まあね、うちはクラブ活動も盛んだから」
「少し、家庭教師の先生が厳しいのかもしれませんね」
「気が緩んでいるだけだ」
「こら、アルフレート」
がたがたとゆれる。戦争は終わる。
「そうだ、クラウド家はいつローゼンバルッいぁ―と休戦するんだ」
「戦争じゃない、仲があまり良くないだけだ」
シーザーは複雑そうな表情を浮かべる。
「魔法とかあればいいのに、あいつらもいるんだし」
だがローリナがカイザーの膝を手でたたく。
「坊ちゃん」
「悪い・・・」
「うわ、キモ」
彼はいわゆる社交的な、市民権のあるオタクではない。呪文も本当に魔術師の家系だがそれは、チャールズにおいて、夢をかなえるものではない。
「死ねばいのに」
リヒト・フォン・フェリクスは、主にサーウィンで活躍していた。属性は光と陽。四つの精霊を操る、(ブランアウル・ナイツ)のマギアナイトだ。マギア・ウォーに躍起になり、もともと大人しくできない性格なのだろう、けんかっ早く何かとうわさが絶えない少年だ。使用武器は剣と銃の両方の姿を持つサグラードロッドだ。女神がこの世に降臨とした際に、すくい上げたという高貴な大樹から生まれた聖なる剣だ。
「アテナの剣が?」
無鉄砲なようでその実、揺れやすいリヒトはその知らせに驚いた。
絶対に崩れない世界なんてない。
「すごい破壊力だな」
ベルクウェインがウルリヒに言う。ルードヴィッヒが苦笑するが。
「…命じられたので」
「謙虚だな」
「誇ればいい、堂々としていろ、お前は救ったんだ」
「・・・・・片割れを探しているのよ」
「こんな場所で」
「ええ、悪魔崇拝しゃのサタンなのよ、まだ家族が、愛し合える双子の妹がいると」
「まさか・・・」
「普通のことよ、誰だって、一人すきでも、最後にまとうのは友人ではなく家族だもの」
「種族も違うし、14年前のことなんて」
「信仰よ、あの子は最後まで捨てないでしょうね」
勿論、デイジー・・・ネフィリアも恋というものは知っている。帝国は自分達が情のないと思っているが、人を慕う感情、自分では制御できないもの、甘く素晴らしい、甘酸っぱい感情。
忘れていたが、自分はもう次の世代を生み出せる、恋というものが巫女ではないからできるのだ。
傍にいたくて、役に立ちたくて、相手に拒まれたらしさえ選んでしまう。
それさえ、服従と支配、アテナの剣では殿方を誘惑し、情報を引き出しと相手を意のままにすると、パンドラは種族で外見がはっきりしている、恐ろしい方はひたすら剣を磨くだけだ、だがそうでない側は恋愛でさえも戦う道具にしてしまう。そういう教育や授業も幼いころから受ける。
まあ、相手を疑えが基本だから、みんな打算だけではないと小さいころから気付いていた。では、間違いの自分達は恋の果てなのか、いけない、パンドラ共通の存在理由の悩みが出ている。
人間はただ子孫を生むだけではない。相手を尊重し、支え合う。恋とは、すべて一生を添い遂げるものではない。戯れの恋もあり、パンドラではないが、同じ性別で恋をするらしいのだ。
自分はできないが、恋は自由なもの、他人の意見なんてどうでもいい。決めるのは自分。
「失礼します」
「ああ、君か」
心臓がやはり跳ねない、頬も熱で上昇しない、ゴットヴァルトをよく考えると言った恋の症状はない、つまり、相手ではないのだ。
「あの、先日アードルフ様が尋ねてきまして、デートを申し込まれました、私が好きなそうです」
「ふん、おめでとう」
「それで、その行くべきなのでしょうか」
確かに自分は使えているので、貴族の使用人は恋愛は禁止らしいし、ゴットヴァルトの意見も聞くべきだろう。それ以外の意味はない。
だが傍にいるのは自分だし、ゴットヴァルトは自分のものに対しての執着が強い。嫌がってくれるのでは。
「大丈夫?男の子と話せる?」
「え・・」
「そうか、デイジーも女の子だもんな、今回は計算も含む意味もなく、君の初恋を応援する、恋の季節が来たんだね、ご主人様ぶるわけじゃないけど、うれしいよ」
「違います、相手が一方的なだけです、私は」
「でも恋愛経験ほぼない僕じゃ、君を助けられないな、庭師、庭師、ちょっと相談があるんだけど」
ぱたぱたと行ってしまった。
「・・・・待ちますか」
―ほんの少し前、ヴァうベルグラオ家でのテロ事件が起きる前、ある少女、シャーロットの言葉がヴィンセントにふとした疑問を抱かせた。
赤ん坊の彼がはじめて、アマ―リエに抱かれながら、騎士候補生だったヴィンセントの前に現れたのは16年前。皆から祝福され、カイザーはだれもが魅了された。
カイザーはすくすく育ち、だが、まだ貴族の使用人になれていない小間使いがふとメイド長にこぼしたそうなのだ。
―坊ちゃんは、奥様に似ていないと。
上流社会の事情など知らない少女だった。勿論誰も本気で気に留めなかった。上流階級のほとんどの人間にはメイドや執事、従者でさえも意識にすら上らない存在なのだから、いい悪いではなく、彼らに親しくする他の貴族すらそうは変わらない。その時は、クラウド家は黒髪か茶髪の方が多く、瞳も暗い青や緑が近い、金髪であるマリアベルの母も実家のものは鮮やかな金はむしろ珍しく、茶色に近い金髪の人間が多い、それに何よりオッドアイというのが少女に軽い違和感を覚えさせた。
心ない、身分だけしかないものや使用人、噂するしか時間のない貴族のもの、侯爵家の当主やベルンホルトは何かと注目され、おもだって活躍もしている。嫌いつつ、帝国のために行動していることは知っている。
「また、風邪をひかれたそうよ」
南方の親しい領主の屋敷で、シャーロットは、カイザーに出会う。
「大丈夫?」
ヴィンセントとシャーロットは、特殊な事情は抜いても身分も環境も違う。だから、会話する機会など本来ならない。六年前のこと、シャーロットは帝都で父について、第一区に移り住んだ。領主といっても、婿であり、引っ越した理由は母の事情である。
「ヴィンセント?」
ヴィクトリアの隣にカイザーがいる。
「お兄様、どうしたの」
「すまない、少し疲れていて」
カイザーが手を伸ばす。
祝福歳で、頬を染め、困ったようにシャーロットはカイザーを帽子越しに見る。
「なんとかかなえてやりたいよな」
他の騎士がヴィンセントに耳元でそう囁いた。
だが、笑顔を返しつつ、単純に目の前の光景が受け入れられないものがある。そうさせたのは、穏やかな色のおかっぱのような髪の少女。
「死ねばいいのに」
「ったく、いい御身分だな」
シャーロットはカイザーを慕っていた、だから彼の敵に、疑問を抱く存在にならない。だが、優秀なカイザーに、同じ学園の生徒にあこがれる者もいれば、単純に追い落とそうとする者がいる。マリアベルの兄であるだけとか、何でシエラやヴィクトリアと女ばかりが幼馴染とか、輝くものが多い、カイザーもその一人だ。だからその分、嫉妬もやっかみもある。別の面ではオルグやアレクシス、アルフレートにあこがれる生徒もいた。
だが、彼らはそういうことと同時に、カイザーの環境に首を傾けていたという。もっともマリアベルやアーデルハイトに近い庶民育ちに近いシャーロットも、マナの存在や魔術師、そういった世界を知るようになり。
「ねえ、騎士様、カイザーはいつマナを使うの?」
ただの貴族の人間が許されるのはなぜ?彼女からしたら、そうした状況はいずれよくないことにならないかという疑問だったのだろう。
恋慕に近い感情と同時に、彼女はある災厄で大事な人を失って、バラバラになった過去がある。ほんの一時だが、だがシャーロットは正しさと真実を求める、カイザーの友人でもある。ヴィンセントが傍づきを遠ざけたのを見て、聞いてきたのだ。
「それは時が来たらだと」
「カイザーのお父様が言ったの?」
すごい才能なのかしら、と少女は幼さが幾分か残る顔を眉を細めた。
「けど、カイザーはいずれ、軍人か国務に関わるんでしょう、なら早めにした方がいいと思うけど」
「そうしたいのは山々ですが、事情がありまして」
そういいながら、心の中ではて、と首が傾く。主側のことだと、その点は目上の騎士も触れていない。マリアベルは、物心つく前からアルフレートと同時に、貴族の勉強や礼儀作法とは別に魔術の修業も義務とされていた。アンジュやバルドォル、セレナもパンドラハンターの子だからと、大事な役目につかずともいずれ、そうした世界に近いものになるということで修業しているはずだ。
あまりに当たり前すぎて、特別じゃないので、だれもがマナを持っていて。
「騎士様?」
「すまない、考え事をしていた」
シャーロットを、友人らしい少女が遠くから話しかけている。じゃあ、と少女は去っていく。
ノーマナなのだろうか。
それなら、納得もしやすい。それにそれがなんなのだ、誰よりも優しく、まじめで、誰からも愛されている。それ以外に何が必要なのか。ただ、ベルンホルト様が息子に冷たい理由がそれならば、僕が支えないと。
・・・それは寂しいことだが、これ以上は個人としても踏み込めないものだ。
「・・・」
だが、一度胸に生まれた疑念はどこまでも伸びていく。当主とカイザー、周囲の事だけではない。アウグストは表面は優しく愛しているように見えるがいつも距離を保っていた。オルフェウスはカイザーを可愛がり、弟のように。だが、このところ、もともと家族愛は下の世代に向けられ、それ以外の家族とは一定の距離を保っていた。カイザー様が11歳になられた時、よく帝都や宮殿、貴族社会とかかわる機会も増えた。
忙しいから、いろいろ抱えているからとか二人に気遣って自分も接していた。表向きはオルフェウスは意地悪で冗談で仲間思い、同時に謎めいたところがあるところは前のままだ。以前よりカイザーに接しなくなった。
「見て、ッァバァイバスラ―家の紋章よ」
馬車が通りかかる。中はアーデルハイトではないが、公爵家は依然事件に遭遇して、かなりの遠縁、分家筋しかいないのでその誰かだろう。民衆は王宮に関わる有名人の貴族として彼らを知っているのだ。そういえば、カイザー様と同じ病院でアーデルハイト様もお生まれになったんだったな。あの時、同年代の少年によく、妖怪が街を周回したという怪談を聞かされたな。路地裏を抜け、いつもの通りを歩いている時馬車にひかれそうな幼女が目に入る。
「危ないっ」
だが、隣からほんの少し遅れて、黒髪の少年が登場し、ヴィンセントより先に幼女を助けにかかる。
「ふざけんな、よけろぉ」
横転、すごい勢いで追う点である。馬車は眼鏡の黒髪の青年が女子学生といたところ近くの鍛冶職人の工房に突っ込んで言った。
「よかった、無事でしたね」
「・・・あ、ありがとう」
カールスと幼女が驚いたようにヴィンセントを見ている。
「当たり前のことをしただけだ」
偶然だ。ヴィンセントは手をカールスに向ける。
「お兄ちゃん、大丈夫」
「私を憎みますか、マイマスター」
フロイデやサファイヤエルは、飛行魔法で駆けつけたアヴィスが死神に見えた。
「・・・・そんなこと、ありえないわ」
「セシル先輩」
皆生きているが目がうつろだ。
「一体、何が」
「助けてください・・・、鎖の魔女の手下が作った結界にまだ」
「ふうん、なくしものね」
ヘレナの後に続き、ルヴァロア邸に入る。
「ええ、貴方もせっかくの機会ですし、付き合いなさいな」
「な、なんで、黒の魔女の手下が」
「誰か、あ奴らに連絡を」
3
「・…まあ、アーデルハイト、君は氷山の一角を壊しただけだろうな」
「おい、そんな言い方」
「魔術組織はお前よりも知恵が回る」
彼女は否定しなかった。ルードヴィッヒはいつも彼女のためだ。アルヴィンは自分がある程度読めてしまうのが嫌だ。彼女がパンドラ嫌いだが、アテナの剣と手を組むこと、皇帝に逆らえないこと。冷徹な一面が強いがアーデルハイトは、なにもすべてパンドラが死ねばいいまでは踏み込んでいない、まあ思うが、現実は違う。子弟制度がある限り、善良なパンドラは手出しできない。
「そいつがハートの賢者か」
アントワネットが優美な横顔で、ハートオブクイーンのそばを控えていたが感情を読み取ることはできない。
「だから言っただろう、クラウド家にお前がいたという証拠も思い出もない」
アルフレートは困ったような表情をする。
「いい、ダヴィデ、貴方がどれだけ一人を愛そうが、人間は一人だけじゃ生きていくことは許されないの」
母の姉、宮廷魔術師はいう。ちなみに、外見は完ぺきに20代であり、奇麗な美人だ。女神といっても過言ではない。ちなみに未亡人だ。先生、上には上がいますよ。
「まあ、叔母・・・・フロールさんも一人すきじゃないですか」
ちなみに伯爵でもある。だが広い屋敷は俺の一人暮らしのいえ同然だ。家主の美しい魔術師は旅好きだ。まあ、それはいいが、たまに来る彼氏に、フロールの若い恋人扱いはきついです。
「そうだけど、あなたはオウル家の後継ぎよ」
「妹だよ」
「恋を知らないものは真理を得ることもできないわ」
・・・・やはり、恋愛教の姉だった。
「目が死んでる男に恋する女子なんてそうはいませんよ」
「男の価値は見た目ではないわ」
とろけそうな、色っぽい声だが気品もある、まさに傲慢な女神。
「なんですか」
「財産や才能よ」
「叔母さんのそういうところ大好きです」
よかった、うちのままん、つまりフロールの妹よりは普通の感性があって。愛が世界を救う前に、息子の精神を気遣う努力してください。
金色の三つ編みがゆらゆらと動く。
「しかし、君みたいな一流の剣士が何でこんな辺境にいるんだい」
少女はライトブルーの瞳を惜しげもなく陽光にさらし、細身の体を近衛兵の聖騎士の制服で見に包んでいる。
「お前こそ何で他国の辺境で供のものも連れずにで歩いてんだ」
サアラはそういいながら、フロイデがいつもと違うのに気付いていた。彼女はレイモ―ン。聖騎士フロレンティカ・レイモ―ン。王侯貴族を守る身分の騎士だ。好奇心が強くボーイッシュで飾らない主義で、街で出会ったフロイデ達にすぐに声をかけてきた。
「だってさ、こんなに気持ちい日じゃないか」
「…手を離せ」
「いいじゃないか、僕は友達に男も女も気にしない主義なんだ、気にいったらハグもキスもするよ、イヤお兄さん、いい筋肉してるね」
フロイデはあわててはなれる。
「絶対に近づくな」
「イヒヒ、抵抗されると余計そそるなぁ、実にいい、初々しい」
「お前、動き怖い・・」
そういいつつ、フロイデは頬を染めている。
」
「いがみ合っているね、カイザー」
「アレクシス、アリ―シャ、お前ら見てるなら止めろよ」
ちなみに男子の絶対王者、女子から告白される連続ナンバーワンはアレクシスだ。ラインホルトやカイザーも人気があるが新顔で性格もあってか、高根の花だ。美男美女が集まるのもこの学園やアーデルハイトの学園の特徴ではあるが。
「この学園、よく問題起きないな」
「まあ、ほら、アリシア先輩が慕われているから」
「ああ・・・」
女王が二人いるからか。
・・・しかし、アレクシスが彼女がいないのも妙だな。
「カイザー、お兄様に何か」
どきり、とする。だがなぜだろう、春の女神を思わせる少女の笑みが怖い。
「ん?俺が何か?」
「・・・まあ、なんだ、二人とも仲良くなるといいな」
「俺も言っているけど、やっぱり女の子じゃないから限度があるな」
「理由は明白だがな」
「ああ、二人とも性格が似ているから」
すると、アリ―シャがしら―ッとした目で自分達を見ていた。
「何だ」
「そのカイザー、お兄様本気で言っています?」
だだだだだだ、と駆ける音が聞こえる。
「先輩、これ受け取ってください」
フレッドやテオドールがにげている。アリシアは恋のキューピッドと親衛隊の女子たちとともにバスガールの格好で追いかけている。
「無理なんだ、見逃してくれ」
アレクシスには手を出せない。そうなると下のランクの男子に目を行く。彼らが薔薇いろの青春を味わっているかというと。普通のいわゆるモテない男子生徒が嫉妬と殺意を日々蓄積しているかというと。
「へえ、戦司祭って鍛えているんだな」
「モテるかな」
全力でアリシアの餌食にされないことを満喫、現実逃避していた。
「あ、ラファエル様だ」
「ラファエル様、こんにちは」
振り返ると、二年、三年のあこがれの令嬢たち―高嶺すぎて男子が近づかない女子生徒にぐったりしたゴットヴァルトが両手を拘束されていた。
「何で俺はカイザーなのに、あいつ妙なあだ名つけられてるんだ」
「まあ大人しい方ですから、読書家で人付き合いもあまり行わないでしょう、きっとお友達が自分のことで争うのを見たくない、心優しい方だからでしょう」
「まあ、優しいのは同意するが」
真実はぼっち好きなだけだぞ。
「あいつのオタク趣味とかたまにする奇行はどうなっているんだ」
生徒たちも見ているはずだが。
「・・・理由はお兄さんならわかるのでは、恋人を失ったのでしょう、きっと現実の女性が怖いんだと思いますわ」
「あいつそんな繊細ではないぞ」
「わざと女性を遠ざける、よほどその女性が好きだったんでしょう、カイザーは恋愛の経験は?」
4
「あんたさ、気味悪くないの」
「何がよ」
ここでは軍人だ。いくら16歳で、学生と兼ねての生活が認められてもキャナルは机並べてなんてしたくない。ダノンやアードルフも同席している。
「だって、単純にパンドラだけじゃなく、あいつ異常者じゃない」
「知らないわよ、隊長がお決めになったことだもの」
野菜中心もいいが、お肉もほしい。そう思い食べながら、ミリアムの姿を見つける。
「何で、あれに夢中になれるのかしら」
まあ見た目はかなりのものだ。自分のような男女でさえつい見とれるくらいだ。
「従士のテストに落ちなきゃな」
ずっと戦っていた、そういう風にしてきたが、ここが自分のい場所ではない、そう思っていた。
「戦争は終わらないだろうな」
「・・・・あの女の人は、家族と出かけているのか」
「大丈夫、遠い国に行っているから」
「あんたが俺を裁くのか、・・・・でも教えてくれ、俺は誰なんだ」
「キリヤ・ストーカー、人間ならそうなのっていただろう、どうして自分を取り戻した」
「わかんねえよ、ただ突然、頭の中がすっきりして、祭りでのここでのことが思い出して、頼まれてくれ、魔物商にこいつを、いい人間につけば、せめて15くらいまでは生存が許されるんだろ」
「ぶちょうの代理だ」
「へえ」
まあ、いいか。ええと、どこの棚だったかな。
だが園芸部員は一向に立ち去らない。
「生徒会長なら、あと少しで戻ってきますが」
「そうか」
勝手に椅子をとり、座る。
「じゃあ、僕行くので」
「そういうのさ、依存っていうんだぞ」
振り向くと、ダヴィデが僕を見ていた。
「は?」
「いくら兄弟でも、四六時中、つきまとうなよ、見てて薄気味悪いし」
「君には無関係でしょう」
4
その時の私は皆に褒められて、でもわかっていなかった。真の天才が現れるまで。
そう。
ヘレネが、自分の前に現れるまでは。アレクシスが手を振っている。
「・・・」
アリ―シャの唯一のネック。頑張っても、アリ―シャはアレクシスに負けているから跡継ぎになれない。
5
5
「よう、フレッド」
「四日ぶりか」
「お前、またあの劣等生の面倒任されているんだって」
む、となる。
「同級生だろう、そんな言い方はよせ」
ソフィアもみる。
「よせよ、いい子ぶるのは、あいつ一人のせいでお前のクラス、全体的に力が落ちて、一般科からも馬鹿にされてきてるんだぜ」
「違うさ、うちはもともと、そんなに実力がないだけだ」
「じゃあ、あいつに授業を教室で受けさせないのは、なんでだ」
「それは君のほうが知っているだろう、問題児が多いから彼に迷惑は」
「違うね、お前はもう見限っているんだよ、あれはブレイヴにも騎士にもなれない、家だってマリアベルたちがもしもの時の予備だと思ってる」
「ただ今、フィズ」
「ああ、おかえりなさーい」
今日も寝むそうだ。
「それにしても昨日は驚いたわ、地震でしょ、家には泥棒も入りそうになるし」
「いなくてよかったな」
カイザーは昨日も徹夜だ。革命組織と学業と。パンドラ狩りについての鍛錬と。
「遅かったな」
パタンと本を閉じる。
「やぁ、ヴァルト」
「アルバート、・・・と、あれ、なんで、君がここに?」
アルフレートは瞳を付して、
「何を言っている、パンドラのお前に惑わされないよう、いとこのカイザーを見守りに来たんじゃないか、夢でも見てるのか?」
そうよ、と反対方向から扉が開く。
「・・・・誰?」
「酷いわね、そりゃあ、過去には貴方といさかいがあったかも知らないけど、忘れるふりするなんて、今は仲間でしょう、なにもと泥棒は友達になれないというの?ジャスパー」
「シャルロット、突っかかるな」
「シャルロット?」
また知らないカイザーの部下?アルフレートも仲間に。
「・・・・寝むそうだな、寝たらどうだ」
「そうする」
いつものサイコホラーかよ。
「アルベルト、何を見ているんだ」
「エルネストか」
「いや帝都に帰るんだなって」
「すごい美人だな、ハートオブクイーン」
「ああ・・・」
けれど、太陽の恵みを知ったものは幸福になるのだろうか。かわいい女の子、理想的な主君、それゆえに彼女は誰のものにならない。
「同情かよ」
「いいえ・・・」
乾いた大地に水を与えるような。踏まれた花を手で覆うような。希望を与えられたものはどうするか。そのあり方は俺がよく知る女の子に似ている。
すべてを包み込み、受け入れる。背筋が冷たくなる。心臓が脈を打つが、それは俺が知る甘い潮騒ではない。
「ウルリヒ、だれもが幸せになる未来なんてない」
傲慢なエンヴリマがウルリヒに言う。
「そんなことありません・・」
アルベルトを支えながら、助けたエンヴリマに言い返す。
© Rakuten Group, Inc.