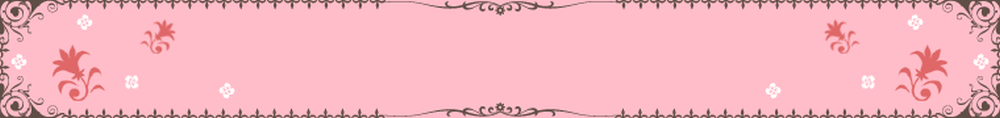第17章
1
ただ遠い日の誓いのために。
「行くぞ」
「ああっ」
ゴットヴァルトは、敵陣へとオルフェウス救出のため、セアドアとともに向かう。
ただ一人、姉を助けるために戦場にいるのだ。復讐も、フォボスへの協力も、失ったあの日のすべてを取り戻すために。
「なぜ来た、ゴットヴァルト」
やはり、不可解だった。何でこんなに違うのだろうか。
アリスは違うのだろうか。
本当は彼女のために行きたくなかった。ずっと、逃げたかった。
ゴットヴァルトはバーバラスに干渉しない。いや、たくさんいる騎士のひとりくらいの認識だろう。いつもカイザーの後を追いかけるか、屋敷にいても、一人で過ごすのだ。親戚も妹も、だれとも付き合わずに。あの方に悪意があるわけではない、彼にそんな力はないが。命令はされているのだろう、打がまるであれではかごの鳥のようだ。真実は違うが。
「ルヴァロア卿」
赤い髪が見える。美しい、細身の騎士だ。
「こんなところでは風邪ひきますよ、わが君」
「平気だよ、これくらい」
何か書いている。ヴィンセントは楽しそうに上着をかけている。
「いいんですか」
「後で構わないだろう」
このまま、スリエルの騎士団が大きくなれば、そんな不安を抱く。思えば奇妙な集まりだ。パヴォール家につぶされた勝手の改革者も変人も天才も、偉大なる精神の我が国をあの仮面の男が一つにする。ミカエラは、エリスを見つけたが、ゆうがにほほ笑んだ。
「大丈夫か」
落ちそうだったフィーネを、ジョルジュが拾い上げる。
「革命家の奴ら、派手なことするな」
「持ち上げてくれないか」
「全く、我が国に抵抗運動など」
「これも女たちがしっかりしないからだ」
無理もないことだ、ダヴェーりゃでは男より女の方が立場が強い。生まれてこの型、パンドラは見たことがない、ただの町の手芸屋の娘、マナを持ち、魔法騎士となり、アリスリーゼと動く。
「たまには娘らしく、町でも歩き、友達と遊べ、武術や魔法のけいこもいいが、民に触れるのも修行だぞ」
「しかし」
「行きなさい」
「・・・・ああ、君か」
「シェインレート様・・・・」
あこがれの最強の騎士、そうか戻ったのか。
「近く、帝国に行くそうだな」
「はい・・・」
胸がドキドキする、まあ恋ではないだろう。
ヴァーヌスの首都は穏やかな多くの商人や金持ち、帝国内で革命も起きない、パンドラの出現率が低い場所で、錬金術や東洋の魔術も盛んにおこなわれる場所で、ライトニング・ヴァリニアの留学生も多く学校にはいっている。帝都ほどではないが、安全ということで女子高や寄宿学校も多くつくられ、帝国を裏から支えるものも多い。軍人たちによって錬金術師は厚遇されている。
「北方の本部からは軍をやめる士官が増えているとか」
南部遊撃部隊隊長、少尉、ジェラルド・ヴァレンティアスはわざわざ帝都から来た使者に困ったような笑みを浮かべた。
「いやあ、俺は軍と銀の十字架をなだめるために入れられただけ何で」
「それは頭の固い冷徹なあの少尉も同じだ、ともかく君にはそれを防ぐため、士気を高め、結束を強化するように」
北はベテラン、西は能天気、東は扱いずらい、南はというと入れ替わりが激しい。平和な分、腐敗や競争も多い。だからまあ、適当な若者に高い地位をあげて、こんな場所に送り込むわけだ。リリのようなイタリア方面遊撃部隊と行動も共にしているが、西と同じくフランス遊撃部隊にも支持しないといけない。いや、経験のあるエリートが白よと思う。まあ家柄がある貴族だと問題が増えるから駒扱いできないのは分かるが何でメンバー、十代ばかり来るの?
梯子を使い、葉を整えている。庭師か、側に庭師が見ている。
「・・・・いいのか」
オルフェウスはメイドに聞くが。
「この家はお館様のものですから」
「・・・・従者」
アロイスはそれが友人でもなく、単なるお目付け役、監視役であることは、ダークブルーの髪の姉と弟のオパールとラエトゥスに対してわかっていた。
「よろしく頼むぞ」
書庫にその少年はいた。人間の小柄な少年だ。
無力であどけなく、おもざしがベルンホルトに似ている。錬金術師の仲間がいう。彼らは多分。
「・・・・ええと、あなたは」
すぐに走り出した。
「いやな人」
「ルーティちゃんはそれでいいのよ」
「投降を」
だがアーデルハイトは全員を討伐せよ、シュレアは違和感を隠せない。
「甘い野郎だな」
守るべき使命を放棄し、暴虐に走り、殺戮する。悪と正義。世界の事実ではあるが、近年は異端者、パンドラの研究者たちから異論が出てきている。そもそもダ当たり前だからどの国でも、彼らの命を奪い、魔法技術に使うことは正当とされている。確かに奪うが、彼らは物語の乱暴な悪魔だけではない、なぜ誰も彼らの命を勝手に奪うことに疑問を抱かないのか、悪人なら人間もいる、すくう価値もないげどうもいるが裁判も更生もある。いいわけもできる。
「もうやめるんだ」
シュレアは潜在的な悪魔崇拝しゃに近い、エデンの研究者が先祖にいたのもあるのだ。
ドッカァァァーん。
「あ、なんだ、ヴィクトリア様、着てたんですか」
ゴーグルを外し、部屋から出てくる。
「な。な・・・・」
「いやさぁ、パンドラでも錬金術や黒魔術使えるかなと思うんだけど、微妙に間違えちゃったわ」
まあ、いいよね、まだ若いし、と可愛く舌を出してきた。
「・・・・・・・あ、あんたね」
だが理解というものを自分はやめた。
「ああ、お母さまたちなら多分屋外じゃないですかね」
ぎぎぎ、とマーキュリーをみる。
「いつものことですから」
「止めないの、あんな・・・・頭おかしいの」
「いいえ、坊っちゃんは極めて利発な、一般的な思考の持ち主です」
現実見ることはあきらめたらしい。
「じゃあ、次は可愛い妹のために料理でも作るか」
鋸やハンマー、鉈を持ち出している。
その後の台所ではけたたましい音が鳴り響き。
「よし、できた、カフェラテ仕立てのロールケーキとクッキーが」
「何でっ」
「・・・・馴れているのね」
「まあな」
「下に妹がいてな、おてんばな子で」
上を見上げるとシエラはただ静かにカイザーを見ていた。
ヘレネと同じように。
「何かしら」
「いや・・・」
「アルバートたちも悪い奴じゃな、あまり嫌わないでくれよ」
「いつものことよ」
「え?」
彼女は窓の外を見る。
「自分の価値観に他人を巻き込んで、自分の善意が他人も同じと思って、そしていつも踏みつける」
「君は・・・・」
「そして、私を悪者にするのよ、なんてくだらない人たちかしら、気持ち悪い」
「それは君が認められないからだろう、皆は君が好きだろう」
「・・・・貴方とアルバートのいう、皆って何?」
なぜ、ただ一つの宝物を奪うのか。
だけど言葉にならない。
「あいつは敵だ、今はお前に笑顔を向けても、レッド・レジ―ナに従うようなそれだけの男だ」
「お兄様・・・・」
オルグも驚いた。ただ一つ、文句さえいわないシエラがにらんできたのだ。
「仲間などお前には必要もない、シエラ、あいつはお前をあいつのように利用して、陥れる気だ」
「お兄様に彼の何が否定できるんです」
背中の俺をにらむ。
「お前のその感情は恋ではない、単なる同情だ」
口出すべきだ、友達なら。
「あんた、いい加減に」
ブレアが俺の腕をつかむ。
「愛しています、愛しているんです、シエラはゴットヴァルト・クラウドを愛しています」
なぜだかひどく驚いていた。女性だとか、彼女への恋慕ではなく、シエラはそういうことを言わない人間、軽はずみに言わないだろう。俺にはできない。だが俺以上に動揺している男がいる。オルグだ。完璧な実力主義。いや、驚きすぎというか、そこまでショックうけるものかな。確かにオルグやヘレネは庶民だの、そういうのと関わらないし、奥手な人物と聞く。まあ、本妻の子じゃないらしいし、意味もなく嫌いなのだろう。汗を流し、目を大きく見開かせ、表情をこわばらせている。
いや、すごく失礼じゃないかな、シエラにもゴットヴァルトにも。あれか、シエラは自分のような完璧な優等生を好きになると、確かにナチュラルに俺を見下すが。だが、シエラはシエラの、オルグにはオルグの好みの違いがある。
「いいな、シエラ、お前は誰にでもなれる」
なら、認められなくても、好きにさせろよ。魔術師とか、家とかじゃなく。
「はい・・・」
「でも、あれはあきらめろ」
まあ、オルグとしてはこれが最後の決め手だ。
「・・・です」
「は?」
けれど、シエラはひかないのだ。
「私は彼とずっといたいです」
本当はずっと気づいていた。俺はその内側に入らないのではなく、入りたくなかったのだ。理想とは残酷だ。夢はいつも冷酷だ。真実とは常に、俺を屈服させ、俺の意思など関係なく、皆仲良くの概念のもと、目も耳もふさいで。そう真実臆病で卑怯で傲慢だったのは。彼女と彼女に頼られるたび、一人すきを歌いながら、俺は。眩しく圧倒的な青い光は闇の生存なんて許さない。ちっぽけな思いも飲み込んでしまう。
けれど、彼らを見ないふりをしたこと。たった壁一つ。いつだって俺が入れない世界。諦めた世界。
すきだ、愛してるなんて、それが本物なんて誰がわかるのだろうか。
彼女は俺に似ていない。いつも気高く、一人だとしても揺るがない。彼女はあきらめてしまえばいいのに、自分の卑怯さも醜さも肯定し、皆と正面から立ち向かう。
誰かと向き合うことは、なんて――。
「すまない、ハトコのフェイトだ、ブレアが男性と仲良く歩いているからつい」
ついで人に拳銃を向けるのかよ、というか何でハトコが聖騎士でイケメン?
「でも君も早く言ってくれればいいのに、学友だと」
あの後、警察やらみ周りの騎士に怒られた。俺のせいではないのに、イケメン無罪なの?精神鑑定しろよ。
「ごめんね、フェイト三、小さいころから妹みたいに可愛がってくれるから」
「しかしだ、一緒に私服ということは、君はただの同級生よりは、なんか距離も近いような」
チラチラ見られている。
「え?ああ、その、別にそういうんじゃなくて、つまり、ええと」
その迷い、なんか傷つくんだけど。
「ブレア、悪い、後もう少し離れてくれねえかな、香水か知らんがにおいがきつい」
殴るなよ、気遣ったのに失礼な。
「ただの同級生で部活仲間です、それ以上でもそれ以下でもありません」
腕をつまむのやめろよ、痛いんだけど。
「・・・そうなのか?」
「ああ、はい」
「そうか、君は苦労してるんだな」
涙ぐまれた、なんだろう今ナチュラルに下に見られたような。
「まあ、ブレアも少々思い込みが激しく後先考えないところがある困った子だが」
「お、おう」
何嫌いなの?
「頑張れよ、悪い子じゃない、君の思いもいずれわかってくれるさ」
面倒なシスコンではないようだが何だろう。
「誤解です、ブレアさんとは今後とも良き隣人で友人でいるつもりです」
「何で丁寧で敬語?私、そんなに魅力ない?」
「早いうちに素直にならないと成功しなくなるよ」
優しくなるな、違うから。
「ご気遣いありがたいですが、ブレアさんにそのような感情ありませんので」
「それにしてあの見た目に反して、アルバートは激しいな」
パーンは、助けに行くアルバートに対してそう言った。
「そんな、まさか」
「ブラン・レジ―ナ・・・」
「久しぶりね」
「その名前はもう死んだわ」
だが彼女は。
「あなたも置いていくのね」
「ええ、いとしいあの人をずいぶん待たせたけど」
「根性悪で疑い深い、貴方は男性の趣味悪いもの」
「そうね、私は不格好のほうが昔から、でもあの人にもいいところがあるの、私に一途なところ、だれかとは違う」
私は、彼らの笑顔など知らない。彼らの神を知らない。彼らが何を正義にして、なにを楽しみで生きているか。
彼女の眼光の先には、イシュタルの旗が遠く見える。そして、東の方角にサイトWがある。エデンやアテナの剣が統括する亞人達の居住区。
全てが平等、博愛、慈愛の理念、国王陛下に忠誠を。
「壁の外に行きたい?」
ワイバァン隊に入る前、キャナルは、ベルクウェインの領地で教師にそういった。
「はい」
彼女は帝国軍人の父を持ち、遺品が弓だった。平民の子だから、大人になり、ここで過ごすのだろう。キャナルは美人な方だ。クラスメイトが笑う。
「おかしいこというのね」
「何がよ」
まるで映し鏡だ。式典の中、アルバートとゴットヴァルトをフィリベルトは見る。
聖者と愚者。彼らは双子だという。
・・・・・だが、こうも円を感じないのは何でだ。
誘拐された少年。異母兄弟のカイザーとアルバート。
「反省を・・・・」
もうその女の顔は思い出せない。ヴィネッサは常に復讐と破壊願望で満ちている。
「ヴィッター…フィーネ」
もう、彼らに会えない。
「ブラン・レジ―ナの騎士をか」
「ディートリヒは駄目だ、あれは腕はたつが戦場ではまともに役に立たない」
ふむ、とうなずく。
「では、オーウェンの娘やミラージュはどうだ」
「イヤ、それは今ではない、それよりはレーヴェやフェリクスをつぶす方が先だろう」
「よくお前の仲間を殺せるよな、それも平気な顔で」
「こら、アガット」
性格が合わない、主義も戦い方も、皆それぞれ抱えているのに。
「うんそれは僕への挑戦かな?」
セアドアがにっこりとほほ笑み、穏やかなのにアガットは冷たいものを感じた。
「ともかく魔獣を手に掛けるの、お前は厭じゃないのかよ」
「まあ、討伐対象に区別つけたら、だめでしょ、それに僕と魔獣を同じ扱いやめてほしいんですけど」
「同じ生き物だろ」
「いやいや、僕まだ可愛いレベルですし、壊れてる失敗作だからなりませんし」
恐らくとは言わない。
「仲間同士で何で平気で、とても残酷じゃないか」
「まあ人類の歴史上、人殺しは消えたことないですね」
「・・・ゴットヴァルト、君は大丈夫か、ハルトヴィヒだろう」
「ええ、すごく大丈夫、後数メートル離れてください」
「僕は心配なんだ、君は優しいから」
お育ちがいいと目も腐るのだろうか。
「うん、ダレンクンにもいわれるな」
「お前か、・・・・よく参加したな」
「基本的に僕に拒否権は適応されないので」
「言っておくが手を抜かないぞ、途中で退場するなよ」
どこにも居場所がない。
それが当たり前の少年にとって奪われることが当たり前で、人がいなくなるのが当たり前で、―だけど、本当に大好きなものが奪われた時、怪物とされるあの少年は誰が味方してやるのか?何で無神経で笑っているようだからと、他人に彼の心を決める権利が、傷つけて壊していく権利があるのだ。
ヴィントにはそれがわかっていた、これもただのナルシズム、欺瞞かもしれない。
彼の心を決めるのは当然彼だけだ。
スパイや暗殺者は文明社会では当然といえる陰の存在だ。ゆえに彼らが使うものは目立たないものだろう。毒薬、隠し道具、一番進歩したのは黒魔術の技術だろう。意識操作系、魔法薬系、暗殺用の特殊な武器、幻術魔法。白魔術は法術、人の心を読むもの、霊的なものが多い。では誰が人間に教えたか。それは現在においてもわからない。古代の超文明か、昔いたという神とのハーフか。いずれにせよ、レオンハルトは遺跡周辺のダンジョンで今日も青の賢者の塔の制服を着て、友人とともに講師が隠したという巨人のいさんを探していた。
「まずいよ、帝国の許可なく」
「ああ、ありす、あなたは優しい」
村の教会だが、結界は間もなくとけるだろう。憎悪、えんおの念が強すぎる。それも人間のデッドドールではない。
「・・・・気持ち悪い」
「パンドラのデッドドールなんて・・・」
村人たちは恐怖でおびえていた。
「そうだ、ヴィンセント、お前は忘れていないだろう、バドォール家が止められなかったかの家の悲劇を」
フィリベルトはヴィンセントの親友であり、エンヴリマとはライバルだった。
「ああ、私が容疑者となった」
「いや君は正しい判断をしようとしただけだ」
「・・・違うよ、私は、僕は思いあがっていただけだ」
フォルクマ―ルは許さないだろう。
嘘つき、なにが聖女よ」
「私達を救うと言っておいて」
ディートリッヒが女性を助ける。
「やめろ」
「嘘つきの味方するのか」
「いい加減にしろ、何でカイザーを」
「お前は顔を合わせれば、そうだな」
シーザー様は兄と仲が悪い。自分は彼が好きだし、当主がこの人ならと思うが、本人は争いが嫌いでアーク隊の上官も嫌で。
「聞いたかまたパンドラを多く殺したそうだ」
「魔物だからな」
マリアベルが自分を見ていた。
「私、大きくなったらハンターになって、お父様みたいに全滅させる」
醜いものが嫌いで、アテナの剣自体、嫌いだ。
カイザーのことは分からない。消えた兵士。自分が革命を仲間とともに起こしていたと輝、彼は魔女殺し、賢者の石を探し求めていた。吸血鬼貴族と関与し、たくらんでいた。ローゼンバルツァーを裏切り、魔女と関わった。何より、アンネローゼを殺そうとして、自分のために聖なる乙女の十槍を探していた。
・・・赤の王も彼が、アテナの剣も?
「・・・・レッド・レクスを彼が」
「証拠もありませんよ、ここにいるものが本物とも限らない」
ブラッディ・ローズをアルバートは見る。
でも、あの姿はヘンリー。
「・・・・イヤ、アルバートが得意でしょ、慰めるの」
「僕では無理だよ」
確かにカイザーは落ち込んでいるが、何か、姉さんか、ヴィルフリートか、取り巻きの騎士とかにすればいいのに。
「頼むよ」
「何だ」
木立がささやく。小鳥が鳴り響き。
「ええと、お父さんと尊敬する先生に怒られたんだって」
「馬鹿にしているのか」
「帰りますよ」
「ああ・・」
ゴットヴァルトはそう一方的にいい、ダヴィデはカバンを持ち、ついていく。
歩いていく、あるいていく。
「え」
「何で」
周囲がざわつく。だが嵐もなれているのかゴットヴァルトはあるいていく。
「いいのか」
「何が?」
あまりに普段地味な生活なので忘れそうになる。こいつはスポットライトを浴びる側だ。
「お前の評判が下がるぞ」
「元からそんなものないですよ、途中までいいですよね」
「なぜ、テおドール何だよ」
「アリシア先輩の紹介よ、何か不満でも?はっ、やだ、ごめんなさい、いや、まぁ、貴方は奴隷・・・いい間違えたわ、いい友達と思うけど、貴方はタイプじゃないから」
「あのお邪魔かな」
ダヴィデは窓際をシエラは廊下側を見る。
「誰だよ」
「私達以外はいないようだけど」
テおドールは困ったように見る。
「・・ああ、うん、大体わかった、それで俺は何をすればいいかな」
「リヒャルト先輩っ」
ルーティがあわてて、鬼属の貴族に向けていた銃口を抑える。ヴァイオレットはこれ以上わかりやすい行動に深くため息をついた。
「自分の気持ち伝えたいなら、何で暴力に走るんでしょう」
気がつけば、奴がいる。というか、何で来るんだ。
「俺には理解できません…、正々堂々、帝国と戦えばいいのに、民衆を巻き込むなんて、間違った、人の死を軽んじる奴に世界を語る価値はありません」
「はは、耳が痛いな」
「こんなひどいことを平気で出来る奴の気がしれません、争いは涙しか生みません」
まあ、他人とかかわるからできる考えだな。
「無意味な戦いだ」
「―それは君が恵まれているからだ」
「え?」
「間違いでも無意味でも、それしか選べない時もある、君は彼らは理解できないよ、間違いなんて誰が決められるんだ?そんなのは君の考えじゃない、誰かのサルまねだよ」
「俺は・・・」
「犯人の意志は犯人のものだ、それが悪魔的でも人の道に外れたことでも、誰も彼らを支配することはできない」
「全てのカオスは私が飲み込む」
軍国の軍人少女のライバルとなる、バドォール家の親せき筋のベリエは甘いお菓子を食べながら、戦場にスパイや暗殺者を送り込む。
「・・・・まさか、ここに呼び出されると思わなかった」
アルヴィンに護衛を連れた貴族の少年が現れる。
「悪いな、危険な真似して」
はぁ、といきをつく。
「君って自分のこともおろそかな野に何でそう他人のトラブルに突っ込むのかね」
はい、と書類を渡す。
「聞かないでくれ、巻き込みたくない」
「で、今回もロリ趣味関連?」
「ばっ、・・・違うんだ」
ヴィントは仲間内では最低な実力者だ。最低だ、クズだ。レーヴェ卿と違い、縛りを馴れあいを嫌い。
「甘さはこの世のためにならねえぞ」
渋い顔である。エストに言わせると、ヴィントは偽悪的な振る舞いが多い。この世の正義が大嫌いな歪んだ人格だ。優等生が嫌いで、協力はするが助けはしない。男やガキが嫌い。自分のような貴族で理想主義が大の嫌いらしい。友情や愛も嫌いだ。好きな人間はエストのようなずるい女、都合いい女。自分の特になる相手。
「人ひとりでは生きていけないよ、君も僕も」
「忠誠とか主従とかするのはガキがすることだ」
「例外はいるだろう、友達も恋人も」
「はっ、おめでたいことで、ご気楽な身分だな、世界はお前中心ってか」
なんかいやな思いであるのだろうか。
「ただ一人、君もいつか特別な人できるよ」
「夢だよ、お前はそう思いたいだけだ、永遠の友情や立派な王様も愛もない」
「ふざけるな、くそがきが」
ヴォルフリートを、貴公子ぜんとした短髪の細い瞳の男によって殴られる。アレッシオはあわてて止めに入る。
「・・・何をするんだっ」
「―ああ、青少年の君か」
「その呼び方辞めろ」
「ブラックは何でいつも怒ってんの、心の病気?」
「それはお前に言われたくない」
「じゃあ、今日は君が容疑者を拷問する係か、はい」
地がついた黒い鞭を渡された。ほんのり白い頬に血がついている。
「弱いものを守るのはいいが、少しは自分を考えたらどうだ」
「ごめん、カイザー」
「まあ、いいが、気をつけろ」
警報が鳴り響く。
「また、ウォーロックが侵入だって」
「怖いわ」
テレジアが駆けてくる。
「貴方達、地下の避難フロアに移動しなさい」
「だから、どうか、俺の元に来い」
夜更けにいきなり、来たかと思えば、第8皇子は国王の地位がほしく、才能がある男だ。なにせ、オズワルドの元にいるのは宝そのもの。他人の弱点、負けを喜び、策略する。何度も帝国軍に敗北しながら、自分は誉れ高いと、常に国王になりたがる男。
「そうは言われましても」
「お前もあんな馬鹿の下ではその才能を生かしきれないだろ」
年中、兄弟同士で争い合い、内戦を起こすのだから困ったものだ。よくいる王子だ。
「でしたらオズワルド殿下のお母君やその一族に言われては」
「あの女狐が他人の意見を聞くものか」
ガウェインの母を敵視し、いつも堂々と倒しに行くような、虐める高慢な貴族の王妃達の中では、息子とは別の意味でずれているというか、堂々と虐めている、美しいが悪魔のような女性。ガウェインが彼女も許すことはないが陰湿な宮廷の中では、ある意味正面から庶民での王妃を蹴落とそうと相手にしていた。オズワルドは母と関係が冷えているが、それなりに敬意は払っている。
「ともかくだ、お前があいつをかばう理由もつく理由もない、あれは血統だけのお飾りの馬鹿だ、俺のところに来い」
ヒュウウウウう―・・・。
「こんな夜中に、ヴォルフリートはどこに」
馬車が屋敷から去っていく。
多くの観衆、巡礼の人々。
その中の一人、フードを脱いだ子供はフリッツに程近い。他国の旅行者だろうか。挑むように少女を見ている。
イヤ、正確には少女の横の首飾りを。
ヒュウウウ。
「なぜ、封印を解いた」
アーク隊の元仲間は。
「お前がなぜ、アレクシス」
「お兄様」
「・・・アーデルハイトさん?」
「お母様に会ってください」
「ずいぶん軽く見られたものね、私たちの命は」
ヴォルフリートはむっとする。彼らを魔術師同士、塔の権力争いにまきこんだのはアーロンも、スヴィンも悪く思う。
「貴方だけが危険な立場において、私たちが黙っていると思う」
アニスがヴォルフリートをまっすぐなまで見る。ランサ―ハばかばかしいというように、リウォード、ルードヴィッヒのもとを去る。
「エクリプス?そりゃあ、有名だから」
「お前を探偵役に名指ししてきたんだが」
「・・・何で、また」
マリウスも困っている。
「お前にお礼を言いたいそうだ」
「会ったことないのに?」
蜥蜴でつくる調味料
「・・・・イヤ、アルバートが得意でしょ、慰めるの」
「僕では無理だよ」
確かにカイザーは落ち込んでいるが、何か、姉さんか、ヴィルフリートか、取り巻きの騎士とかにすればいいのに。
「頼むよ」
「何だ」
木立がささやく。小鳥が鳴り響き。
「ええと、お父さんと尊敬する先生に怒られたんだって」
「馬鹿にしているのか」
鏡をアリスが見つめる。
「鏡よ、鏡」
ねえ、何で貴方がアリスなの?
アデルという最強の剣士がいた。
今でも目を閉じれば、その少女のことが思い浮かぶ。
期待のエースにして、帝国の反逆者。狂気に取りつかれ、禁忌の技術に手を染め、パンドラを解放しようとした悪魔。
「オルフェウス・・・」
彼女の恋人で彼女を殺した男。
帝国の敵を多く殺した黒衣の男がいる。ヒューストンの部下たちは、闇夜に大通りでパンドラたちに前を守らせながら、帝国の鬼達と構える。
「もう一度、いう」
ワイバァン隊のオルフェウス隊が来たということは殲滅ということだ。敵に情けなどかけない。たとえ、革命に参加する多くが民衆で、オルフェウスの候補生時代の中まで魔術学校での顔なじみでも。
「武装を解き、投降か」
「黙れ、俺達は檻に戻る気はない」
道は戻る道はない。
「そうか」
アルフレートたちが銃を構え、発射、パンドラたちも。
なぜ、お前らは我慢できるのだ。
彼らは皆、死を覚悟しながら、そう思っていた。
―思いだして、リーゼ。
「ディートリンデ?」
クラスメイトの少女が急に表情を変えたディートリンデを不思議そうに見る。
「今、誰か言わなかった?」
2
「ステラ・マリア」
アンナ・ジュリアの双子の妹は姉と同様、気弱ではかなげな少女だ。
「君も着ていたのか」
「ええ、お兄様がたまには宮殿の外に出るようにと」
「フローラも大変ね、あんな者にご機嫌取りして」
「アシュリー様・・・・」
「アニエスがまた戦功をあげたそうよ、ずるいこと」
くすり、とフローラは笑う。
「何よ」
「いえ、相変わらずだなって」
「デートじゃないんだからね」
「うん、知ってる」
シエラのあの表情・・・・嫌な妙なものが胸をくすぐる。
「ディートリンデは許してくれるかしら」
「何で、君達もめているんだ」
「ジュウ―ル・・・」
だが、封鎖された村で男はフロイデを見ても。
「呪いをかけられているのか・・・」
一体、何があったんだ。
「あまり人のことに関わりすぎるな」
「オルフェウス兄さん」
「絵が好きなんだろ、人のいうこと聞くのもいいが、お前はもっと自分を出すべきだ」
アルバートはほほ笑む。
「人に尽くすのが好きなんだよ」
「ルールなんてくだらないだろ」
「オウル、やめろ」
歪んだ笑み、味方を必要としない自己犠牲の結果主義。
「・・・・君は自分のやり方を通す気なのか」
アレクシスは厳しいが、完全に悪人とは決める気がない。
「これが正しいんだよ、お前らが変にこだわるから、違うか」
「貴方は・・・」
「結果が正しければいいなんて、お前は思ってないだろ」
ライトニング・ヴァリアの王宮近くには、魔女の心臓が置かれた博物館がある。
零の魔女、本物の魔女として多くの冤罪、無実の人間を殺した当時の正義を変えた存在。パンドラでも人間でもない、人に似た姿のモンスター。
けれど、ルナティックドレスに所属する少女は、ただ脅威を取り除くことしか知らない。
感じてしまう、ぼっち仲間。けれど、ダヴィデは関わらないことにした。
「会ってねえよ」
見慣れた顔だが、電波さんだな。ヴォルフリートに関してはいいうわさがない。国境沿いの湖近くの生まれ、誘拐されていた。後、無意識のリア充お―ラ、性格いいとか、天魔落ちで高い戦闘能力とナイトメア。うん、お腹一杯です。
「君の学園にいたんだ」
確か風紀委員の可愛い女子がこいつに困ったと言っていた。病気だと決めるのは楽だが。何でお前の人生舞台仕立てだよ、帝国が秘密裏にそんな魔術実験とか、昼にさく花とかいわれても、そのネタは少し無理がありますね。だがこの手のタイプはどんなことも都合よく考える。
「あのな、いくら魔術師の家が長男や長女以外ころころ駒を変えても、何で学校まで付き合うんだよ」
まあ記憶操作の魔法もあるが、それ俺には重要じゃないよ。
「大体ゴットヴァルト君とお前の人生、取り替えて何の意味があるんだよ」
まあ、彼が貴族ではなく孤児というもうそうは現実味がある、でもリスクありすぎるよそれ。
14. 自分自身を責める気分さえ存在して
繊細な少年というものは古今東西、鉄板らしい。
「見て」
「ミハエル様よ」
「楽しいのか、神なんか祈って」
「ああ、カイザーか、小さいころからの習慣だからね」
「・・・ヴィンセントとうまくいっていないそうだな」
「何でだろう、彼とは同じものを見ているはずなのに」
「確かに珍しいな」
かんかんとアレクシスとシエラが階段で行きかう。だが誰でも優しいアレクシスは彼女を見ることはない。
「お兄様」
「ああ、ごめん」
アリ―シャはサーウィンでの革命を知らない。
「・・・・こんにちは」
ダヴィデは小さい声でゴットヴァルトに話しかける。
「ああ、君か、どうも」
奇妙な光景だが、あるべきだろう。アリ―シャはそれでも、一人好きのダヴィデが悪い状況でも兄のように手を差し伸べない。彼自身も他人が踏み入ることは。
「・・・あのよ、その、なんだ、この前の本まだいいか」
「いいよ」
「うん・・・」
だからアリ―シャは彼が嫌いだ、とても。
「俺格好悪い・・・」
会話もつたない。いらいらする。
「そうだね」
「無理ね」
塩対応だった。自分の外見が評価されないことがいやだったのか。
「何でだよ」
「貴方、そもそも自分が愛される生き物だと思うの?」
これが俺じゃないならお前殺人者になれるぞ。思わず自殺するだろう。
「でも困っているし」
はぁぁぁと深くため息をつく。
「あけすけな嘘はやめなさい、どうせマリエルにいいところ見せて、彼女にしたいだけでしょう、無駄な夢を見るのは止めた方がいいわ」
「放っておけないだろう、お前は困っている奴放っておけるのかよ」
「だからって、何でもしてあげるのは、愛でも何でもないわ、自己満足よ」
「それはそうだが、ならどうすんの」
「彼女自身を動かすのよ、自分で決められないものに周りが動くわけないわ」
「変えられはしないさ、アレクシス」
「ヘルムート、俺はそれでも動きたい」
「・・・」
「後悔はしたくないんだ」
夢を見てるのさ、アリス、
だってしゃべるウサギもお茶を飲むネズミも本当はいないんだから。
≪バブル・スカンデレ≫
ディートリッヒがそう呪文を唱えた瞬間、ルードヴィッヒやヨハンは半透明な、人体を丸ごとを包む移動用の魔術の檻の中にいた。
「行きましょう」
「ああ」
アズゥ・カルヴァリ―レに会って見せる。
「ディヴィド、なぜお前がいる」
仮面の中でフォボスが驚きの声を上げる。
「何だよ、それ目の前で困っているのに見捨てるのかよ」
アラウンは思わず、ヴィンセントの胸ぐらを掴む。
「あんた、それでも騎士か、目の前の民を助けずして何がクラウドの騎士か」
「・・・すまない」
3
「・・・・下らない人たちだ」
ふりむくと、どこかの紳士か。貴族の子息のだれかだろう。金髪のショートに紫の瞳。長身だが細身で、だが柔らかい雰囲気だがどこか暗い。
「身分、古い血統、そんなもので物事を決めるとは」
たち振る舞いに無駄がない。軍人ではないようだが。
「君もそう思うだろう?」
「ゴットヴァルト・クラウドです」
頭を下げると、少年は手を差し伸べてくる。
「オーウェンだ、よrしく」
「大義とか、僕はどうでもいいんだ」
アンソニーの意外な言葉に、フロイデは顔を上げる。
「意外だな」
「この腕は偽物でね、僕はこれだけで済んだのだけど」
ガウェインはレッド・レクスの本部隊に遭遇したのは8歳のころ。古くからの盟約、約束。
「貴様・・・っ」
「早くそれをどけろ」
「ベルナール」
「エリック、久しぶりだな」
ヴァーチェナイトが勢ぞろいか。
「どう思う、最近の国外の動きは」
「皆、不安になっているよ」
「なぜ、こんなひどい真似ができるんです、答えなさいっ」
フェイトドレス部隊の少女、セリ―ナは仲間を抱えながら、近隣の村や町を襲い、家屋に火を放つ暗黒の魔女(ダーク・ウィッチ)に仕える壊れた卵と分類されるZ-003号、種族は天翼属(アンジェロ)の少女に当然の言葉をぶつけるが、黄金の翼、太陽の形を模したようなリングを背中に漂わす、鎧姿の異国のパンドラはセリ―ナをそこらのものと思っているのだろう。
足元には、高貴さと可憐さ、少女らしさを漂わせた少女―セラフィーナによって無残にエナジーを吸い取られた臣民の姿がある。
「パンドラ達には言葉も通じない、冷酷な生き物だ」
アテナの剣からこうして、時折暴走するパンドラが現れる。
「バーバラス、お前は迷うなよ、パンドラハンターの騎士なのだから」
「デヴィッドは私が嫌いなの」
一度、聞いたことがある。愛らしく、いかにもお姫様然とした箱庭の姫君の自分はアーデルハイトの役に立たないのか。
「まさか、僕があなたを嫌うはずがない」
「じゃあ・・・」
「君は騎士団団長だ、騎士団の顔だ」
満月だった。
「寒いな」
「まあ、夜は魔物の活動時間だしな」
銀の十字架の一部隊。その目的は帝国の敵となるパンドラ、それに関連した革命組織をせん滅すること。
「君が応援の」
「何よ」
アルヴィンはちらりとヴァイオレット、エルフリーデを見る。
「悪いな、クロウ」
「総隊長の決められたことですから」
雲雀が鳴いている。
「ディアナか」
「・・・・奇遇ね」
赤いウェーブヘアの少女はクロウに道を譲る。
ズガァァァン。森の中で獲物が追いかけられる。頭を銃弾で撃ち抜かれて。ダヴィデは覚えていない。第一区でそんな事件なんて起きるはずもない。ただ犬の鳴き声はよく覚えていた。
「つまり、原因も結末も知らないのね」
「まあ、ミステリーではあるな」
やはり居心地が悪い。このところ、ずっとだ。
「・・・・」
「・・・・」
「お前は・・・っ」
「止めなさい」
「手を離してくれますか」
「じゃあ」
「じゃあ、君なら何とかできるのか」
まっすぐに、アレクシスの青い目がヴォルフリートを見てきた。
「できる」
「俺は行くよ」
「アレクシスッ」
「そもそもサ、ヴォルフリート、君はどうやって赤の女王に出会えたんだ、宗主にも」ジ―クムントは何気なく聞いてきた。
「何だよ、いきなり気色悪い」
「寒いかなって」
セアドアは、イグナスの反応にふむとなる。
周囲がざわめく。
「フィリップさまよ、珍しい」
ヴォルフリートは不思議そうな顔をする。リヒトはヴリルとともに顔を合わせる。
「まあ、お前はこういう華やかな席に出ないもんな」
「ナイチンゲール家の長男だよ、近衛騎士団に今在籍してる」
「ごめんなさいね、アルヴィン君」
エルフリーデははかなげにアルヴィンに言う。
「どうしよう、フィラン」
「マリアベル、またなの」
4
「すごいな、二人は何も言わなくてもわかっちゃうんだ」
シエラとダヴィデがお互いをみる。
「そうか?」
「そうでもないけど」
ダヴィデが振り返るといつもの笑顔がある。
「みんなのところに戻ろう」
・・・・アルベルト、お前は何をしている?
「アスラン様」
「ああ、もう、謁見の時間か」
「いいんだよ、もう使わないし」
「でも・・・」
「僕にヴァイオリンは向いていないから」
自分をばかにしているわけでもない、兄の努力も知らないで、ローザリンデと馬鹿にしている。本当にいい人だった。
「許してくれるの?」
「僕も君を誤解させるようなことをしたし、僕達兄妹だろ」
クドラクの攻撃によって、コスモはピンチを迎える。背後にはまもなく、北の大女帝の本部隊が到着する。
「どうして、みんな仲良くできないんでしょう」
「・・・」
≪ファナティック・ラビリント≫
青緑の独特の文様の魔法陣がオルグのやりから放たれ、パンドラを一線、熱波が切り刻んでいく。
「お兄様・・・」
「大丈夫か、シエラ」
「何か」
ハルトヴィヒの姿もある。
「え、いや」
イグナスはゴットヴァルトがいるとはきかされていなかった。
「・・後でまた来るよ」
「何、あれ」
「お前、イグナスにいじわるでもしたのか」
「まさか、知らないよ、あんな人」
「アレクシス様、兄さんが、・・・・どうかしたんですか」
ベンチで一人で疲れを表情に宿していた。
「何でもないよ」
爽やかだ。
「そう」
「・・・・どうにもならないんだ、君ならどうする」
「何の話です」
「あっ、すまない、・・・・気にしないでくれ」
5
≪フレイム・シャール≫
いざべらの攻撃がいきなり、ヴァガットの手下に爆発音とともに攻撃の威力を発揮する。
「終わりです」
「ふぅん、仲いいんだね、アウィンと」
「え、ああ、レーヴェ卿か」
「仲良くねえよ、ただの舎弟だ、舎弟」
コレットがゴットヴァルトを話す。
「何だよ」
アウィンが引き離す。
「レーヴェ卿が来てくれて助かった」
「アウィンさん、あまり離してくれないから」
アデルと引き離されて、15歳、整理をしていた時、マリアベルとともに金髪の整った顔の7歳くらいの子がやってきた。
「オルフェウス兄さん」
「よう、カイザー」
違和感が自然と口元を緩めた。
6
「あなたはいつもさびしそうな表情をしていますから」
この男は何を言っているのだ。攻撃や仕返しは頭が悪い女がすること。だから謝罪にきた。
「やっと、僕に興味持ってくれたんですね」
「あなたは何を言っているのです、私は最初から」
「・・・だって、貴方はいつも苦しんでいたじゃないか」
「さっきから何を・・・」
「アニエス、貴方に似合うのは剣でも魔法でも権力でもない、ほら、ピンクのリボンのほうがやっぱりお似合いだ」
飾り気のないリボンが結われた髪に結ばれる。
何だ、この下民が好きそうな安い展開は。
「・・・・そう、貴方にはすべてばれていたんですね」
なるほど、とんだ狐だったというわけか。
「それではもうこの関係も終わりですわね」
背筋を立て、不遜に笑い、扇を広げる。
「それで、エストカラス家としてはどうなさるつもりですの、言っておきますがわたくしは貴方と婚約解消する気はありませんわよ」
「もちろん僕もです」
「まあ、そうでしょうね、天魔落ちなんかが血族にいたと知られればわたくし以外のものは貴方を選ぼうと思わないでしょうし、存外切れるようですね」
「理由は聞かれないのですか」
「聞かずともわかることでしょう、私はあなたに愛などという無意味なもの求めてませんもの」
「では、国王つきの魔法騎士となれば、どうでしょう、そうすればあなたは対等に僕を見てくれますか」
要するに高慢な世間知らずな女だと扱えると思っているのだろう。
「お前は弱者になれというのですか、そんな暇事をしたいならフェリシアとなさい」
「・・・・お母様はあなたを嫌いになったから、恋人と逃げたわけではありません」
「・・・・・・わたくしには、お父様と使用人とお姉さまだけですわ」
そう、民衆風情にわたくしが負けたわけではない。変な正義に目覚めて、家を捨てた女なんか最初からいなかった。
「ピンクはわたくしには似合いませんわ、好きな女性にあげなさい、わたくしは騎士団団長、この国の敵を殺す軍人ですわ、バラもドレスも恋愛も宝飾品も貴方が好きな守られるお嬢様にあげなさいな、わたくしが似合うのは血の色ですわ、赤です」
「ライアー」
レッド・レジ―ナ、赤い巻き毛の美しい少女が王座に座り、ライアーと下僕の前でたつ。
「これをかの国に」
「・・・御意」
それは後味悪いものだった。人は縁と思い出を重ねる生き物だ。
思い出したオリバーやクラウドの騎士、アマ―リエ夫人や妹達。全て元通り、というわけにいかなかった。
犯人のルイは野外劇場の舞台の上で、憎悪のまなざしをヴォルフリート、かってのカイザーを見る。
「ヴィンセントは君を最初から疑っていた、だから、術にかかったのさ」
「どうして・・」
「単純だよ、僕は君がずっと前から嫌いだった」
マリアベルは何言ってるんだという目で、ルイを見る。
「俺はお前にひどいことをした覚えはないぞ」
少なくとも人格や人生を奪われる覚えはない。
「ふっ、あははは、やっぱりだ、君は相変わらず何も分かっていない、何もしていない、それこそがお前の罪なのに、だからお前は平気で人を踏みつけにできるんだ、信頼され、愛されていると思っているんだな」
「それは・・・」
「恐怖でお前は僕達を支配しているにすぎないのに」
「何のことだ?」
7
「本当に忘れているんだね、ヴォルフリート」
「お前は誰だ」
「僕はアルバート、ベルンホルトの嫡子にして、真実を認めるもの」
8
「・・・赤の王は誰が」
正気をなくした魔女が声をあげて泣いている。
「ルイ、これは一体」
「アヴィス」
「アーディアディト」
「伯爵、これは一体」
9
「生きていたのか、母さん」
「ああ、カイザー」
「死体だよ、よく似た人形だ」
「骸骨卿」
「これはアルバート」
「僕たちじゃない、あいつが全部はじめたことだ」
10
「お前があいつを狂わせたんだ、僕のヴィントを」
「何を」
「パンドラの分際で」
10
「そもそも出会えるはずもないのだ」
「赤の女王も二ケの肖像の主も、アリス以外は」
「彼氏という話は?」
「僕は彼を救いたい、怠惰の魔女に彼はあの日壊された、何度も何度も」
全て空想?あいつが赤の女王に恋焦がれ、野望を持った。
「アーディアディト?」
「魔術の儀式だ、彼女はあの日、家族を奪った敵を討つため、禁断の魔術を使った。君は止めようとした、そして、アレクシスの家でアリスを殺そうとした魔術結社が魔女に襲われ、実験体とともに死んだ」
「アリスは助かった、でも僕は彼らとともに死ぬところだった」
狂ったようにゴットヴァルトは笑っていた。
「ゴットヴァルトは僕と生き残り、そのあと全員死んだ、そう彼が奇妙な遊びを施された後で」
「そして、彼は各地で魔女殺しを始める」
11
「そもそも彼は幼いころ、育ての父を死なせている、今度は赤の女王を手にかけて、何をたくらんでいるのだろうね」
「・・・馬鹿だよ、あいつは妹が吸血鬼だからって、パンドラまで」
「ダノン・・・」
ルーティは意外そうに見る。
「スヴィン様・・・」
「なるほど、ヴィクトリア、それが」
「ワイバァン隊総隊長、いいんだな」
「ダーウィンも」
「問題ない」
「ゴットヴァルト、何で」
「これしか方法なかった」
多くの躯の上であの女は。
帝国軍人は目撃する。
赤の女王は気がくるっている。
© Rakuten Group, Inc.