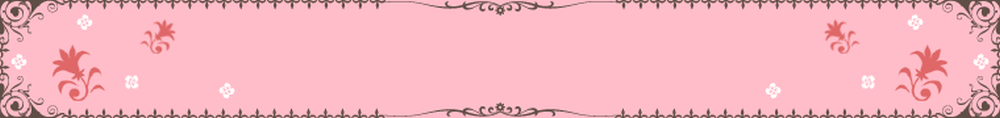第19章
1
ー全て、あの時に終わったのだ。エストカラスとしての自分も、婚約者との日々も。
「離しなさい、私を誰だと思っているのです」
すぐそばの守衛にこん棒で殴られる。
「天魔おちの分際で」
「私は天魔おちではありません」
悲鳴を上げて、大勢の前で服を着替えさせられる。まるでもう人ではないように。
「-Xー105号、きょうからお前は俺の部隊に配属となる」
アンジェリカは髪を切られ、衣装も鎧と戦闘いが混ざった衣装を着せられ、少尉であるカタリナの元に連れてこられ、大勢の天魔おちの前に引きずり出された。
「ウォーロックを、だヴぇーりゃのために倒せ、それが今のお前の使命だ」
「どうでしょう、クラスの女子と会話しないので」
「・・・・嫌われているの、判ってて相手にされてないの?」
ゴゴゴという音が聞こえるが無表情なので、何かそういう思い出があるのか、興味ないけど。
「まあ、おもちゃかなんかだと思われているんじゃないかと、だれかと組むことがあるたび、なんか僕を出しにクラスメイトみんなで楽しく会話してるので、あれは嫌いなのか好きなのか、どうなんでしょうか」
「性質が悪いのよね」
「だから、僕が同い年の女の子というのはないんじゃないだろうと思いますよ」
「・・・・メイドの女の子たちは」
「いやいやあんな美人が僕を相手にしませんよ」
光あふれた世界はジュラルドには恐怖だ。きっとかげなき世界は、恐怖しかないのだ。
「・・・アルバートは、やはり潔癖だね」
「え」
オスカーがほほ笑む。ジュラルドやマーティンもいた。
「世界は常に善人だけの世界とは限らない」
雪のように冷たくりりしく、冷たい美しさ。
「お兄様はダヴィデさまが嫌いなのね」
冷えた瞳。ヴァルトルーデはいつもこうだ。感情がない。
「え、いや・・・」
「ジ―クヴァルトも」
彼女は冷たいが、自分を嫌っていない。アルヴィン・バルツァー、アリスからみれば死んだ恋人の弟。スパロウ卿、その領地を受けて、立場が変わったが、それは死んだからだ。師匠が、その家族が。
「そんなわけねえだろ」
「貴方は無駄なことが大事だもの」
アロイスも彼女も、そもそもあの男は駒だろう。アルヴィンの母は魔術師だった、ずっとメイドとばかり、それがなんで冷酷なあの男の、アロイスの母と争う立場にいたのか。アロイスの母は、異界に行き、ヴァルトルーデは異界から生まれた。
「お前さ、寮に移れよ、じいさん・・・あの男といてもつまんねえだろ」
「・・・パンドラのあの子は元気でしょうね」
14歳なのに、これでは人形のようではないか。
「あ・・・」
ハルトヴィヒがディートリンデを受け止める。エレンが追い付く前に。
「あ、ありがとう」
悪魔属のハント、そこでセシルはヴォルフリートと出会う。
「行こう」
「何で、アースエンジェルスがここに」
「寝られたか」
「このところ、激戦続きだったしな」
フロイデはやはり、運命や使命でも幼い少女を戦わせるべきではない、マ―キューリーの意見もアヴィスの考えもわかる。
「劇場型犯罪者の犯罪を見に身に来るとはね」
ライトアップされた劇場の屋上でジュラルドはワイングラスを手に、ほほ笑みながらそういう。
「まあ、イベントとしては珍しいですから」
何でまぬかれているんだか。
「暇をもつと、人は悪趣味に走るのだろうね、人が殺されるかもしれないのに」
「その割に楽しそうですが」
「エクリプスの予告も、夜の女王という宝石も大きな悪の前では小さくなるものだね」
「ああ、あのきざな」
天使がささやく。異空間で、あるいはオルフェウスの作り出したその世界で。煉獄。異世界。呼び名なんてどうでもいい。
「君がようやく隙を見せてくれて、うれしいよ」
鎖で体を押さえつけられている。
「黙れ」
皮肉なことだ。ヴィッターは、それこそ死神を恋人にしたい日々、ペルソナを使い、剣を使い任務をこなし、実験に使われる日々。
ローズに所属していた時が、家族というものを実感できたのだから。
全て見るものを焼き尽くす背の高い兄貴分、生意気で気弱な天性のアサシンの姉き分、破裂音が怖い悪魔属の少年、盗み食いでママに怒られるイフリート属の年下の妹同然の少女。ヴィッター達は、帝国のために死ぬ。
全員が明日は敵、裏切る。逃げだすモノはノワ―ルローズがペルソナで殺す。
「破壊神の失敗作だよ」
破壊して壊す。すべて無に。
それだけだ。本当に意味があるものはない。
繰り返す。繰り返す。
永遠なんてない。
「貴方のようなサンプルはたまに出るの」
「だから早く、消えて頂戴ね」
パンドラを天魔落ち同様の力ができないか、自分は一応幻魔属とされていた。
ラビッツヒューマン属は、妖精属の一種だ。見た目がけもみみをつけた美人にしか見えないが、打撃力、魔法力、精霊魔法など以外とオールマーティ―に戦士として使えるらしい。
「に合うな」
冒険者の恰好させたが、普通に似合う。
「しかし、いいのか、俺なんかの使い魔で」
「いえ、私は・・・・」
その先は言わないが、しかしだ。
「お前名前とかは?」
「エデンで生まれまして、名前はありましたがそちらはあまり」
すると、いかれたパンクのファンがつけてそうな髪飾りを、どこに持っていたのか自分の髪につけた。結われていたので気付かなかったがかなり長い、兵士ではなくなんか象徴的な立場だったのか。
「はん、そんなもんかね」
柔らかい、どちらかというとカイザーは陽気な雰囲気だったが、彼は堂々たる王様。故にヴィクトリアは彼の先に行くことができず。使用人も家族もなかったことになり。おぼえているものは相手にされず。あの日はおぼえている。カイザーが助けを求めた日。
アリシアはア―ガンスはエイルは忘れ。
最初から彼はヴォルフリートにされ、ヴィクトリア達は手出しできない。
二人のカイザー。
「先輩・・・」
「マリアベルさん」
涙のようなものが見えた。
「これはどういうことなんだ」
使い慣れたインクのにおい。
五年前の帝国軍の記録の一部。
アリスは、アルバートに出会う。
ツヴァイトーク遊撃部隊隊長、ボードウィン中佐は、その時副隊長だったグリフロッド・カースルヴァン、大貴族の娘、アリスと歌手のステージも奪い合ったエリザベスも感動的な再会を目撃した。
エリザベス・フォン・ネス・パーシヴェルは助け出されたいリス、アンジェリカとともに美しい少女姫を見る。
メアリ―の異母妹で、後妻の一人娘で、幼少時はライトニング・ヴァリニアでお嬢様学校に通っていた。
「お姉さま?」
「アルバート、貴方が弟?」
ラビッツはゴットヴァルト、その時はヴォルフリートと呼ばれていたパンドラと見比べる。
リーゼロッテも兄弟もアルバートという存在に惹かれていた。
種族はパンドラ。ただし、神や天使の血を持ち、天使が人間の姿を持ったような、清らかな少年だった。
「ふん、あんな僻地の領民のために自分の身を出したか」
アルバートを二ケの肖像の司祭が細めで見下ろす。
「私がなすべきことだと思ったからです」
「卑怯な真似して、こそこそして、お前恥ずかしくないのかよ」
「アリスのやり方じゃその場しのぎなんだよ、別に問題ないだろ」
「な・・・っ」
ああ、やはり、アルヴィンは合わない。
「・・・・俺に触るな」
「…ヴィルフリート」
人ごみからダヴィデが駆け寄ってくる。
「大丈夫か」
「触るな、大丈夫だ」
≪ブレイヴ・デスペルタールセ・・・・≫
リヒャルトのマナが最大間で高鳴り、金色の光がリヒャルトから放出される。
「フィーネ、悪いな」
「お前は私が守る」
「ずっとずっとだ」
まっすぐなツリ目の青い瞳とブルーグレーのサイドテール。ここで親友や兄弟と言えるのは彼女だけだ。彼女はずっとじぶんだけを見ていた。父母に叩きこまれ、自分だけの剣だと。オーウェンやグラヴィーダスに剣を教わり、それゆえに少女らしさを削り取られた。
「わたくしは・・・」
愛も友情も知らず、天魔落ちにされた少女は珍しく実の親で育てられ、そして正しさだけの人間となった。
「それじゃあ、リーゼ」
「ええ」
本当は、この関係が永遠に続くなんて思っていない。父は五日クラウド家と同盟をやめて、自分たちはエリクサーを奪い合う。その人は一人、三人の生徒に囲まれていた。冷たく乾いた、何者も許さない瞳。自分に似ていると思った。友達、真実そんなもの信じていない、だれも信じていない私は誰にも選ばれなかった。同じになれば、私も変わると思った。そう、親友といいながら、私は彼の中身に何一つ興味がなかったのだ。あり方が似ていても、ダヴィデ・オウルは自分とは別の人生を生き、主義も価値観も近いだけで違う。自分が痛みを感じたからと誰かに押し付けてはいけない。
これは友情だ。
でも私は、友情なんて生まれてからヴォルフリート意外に教わった覚えがない。ブレア・アリーずは優しい、正直こんな私なんて無視されると思っていた。ヴィクトリアに言われなくても性格が悪いことは誰よりも知っている。
自分よりも本当は繊細で、不器用で、そんな二人は自分よりも強い。彼は気持ち悪い、受け入れられない、なぜ自分まで傷つけるのか、ヴォルフリートのようだ。
これは友情だ。
そんな彼が目が離せないのは――、その先はいらない。
「なぁ、師匠様、ゴットヴァルトって本当に一人が――」
「・・・・・・・私、別に昨日のことで怒ってないから」
「じゃあなんで見ないんだよ、罵言なら受け付けるぞ、馴れてるし」
しかし、ポップで女子らしいが、ピンクがメインとか、どういう色彩感覚だろうか。
「あまり見ないでよ」
「悪い、人にあまり家に誘われないものでな、なれてないんだ」
「そういうブラックなの控えてほしい、・・・・・シエラは」
「ああ、なんか、お前のハトコとしゃべっているな、あいつ普通にイケメンも好きなんだな」
「気遣うのやめてほしい」
「は?」
「いいよ、ダヴィデはわからないだろうから」
「謝る気がないが、お前なんで風邪ひいてんの?」
梨を借りてきたナイフで向いていると意外そうに見る。
「料理好きなの?」
「いや、好きではないな、叔母がいるんだがこれが天才的に料理できなくて」
「・・・・わかる、そうなるともうやるしかないよね、その昨日今日寝れなくて」
「エ、お前にそんな繊細な神経あるの」
「悪い、だがまあ、お前出てこいよ」
「はぁ?」
「お前が来ないとなんかテオドールがうるせえんだよ、それにシエラも」
「ダヴィデは?」
「まあいないならいないで快適だし、いたらいたらで面倒だなと思うが、まあ、お前の居場所だろ、花を育てる才能ねえけど」
「努力してるもん」
「大体な、俺だけに評価されてないからショックとか、お前馬鹿だろ、そんなわけないだろ、お前が好きなものすきいるに決まってんだろ」
「・・なんか慰められてる気しない」
「してねえからな、俺は性格が悪いし口悪いし、歪んでいるからな、一人でいると超幸せだし、まあお前はそんな変態じゃねえだろ、だからこんな狭いところいないででてこい、ブレアはそんなか弱い女で終わる女じゃねえだろ、知らんけど」
「・・・・・いいよ、もう、反省してくれてるなら」
「は?」
「明日、学校行くよ、そこまで言われたら行くしかないし」
「寂しいならそう言え、馬鹿っ」
「はぁ?意味わからないんだが、本当に」
「謝りなさい」
「そうですよ」
「何で」
部活をいつものように強制連行されているとき、部長と妹でしがそう言った。
「・・・・貴方、それだから生涯一人で死んで行くのよ」
「お前、超能力者かよ」
はぁぁとミントがため息をついた。
「駄目ですね、女の子の気持ち全然わからないんですから、たとえ何とも思ってなくてもですよ、男性に正面からお前は魅力がないなんて、あんた何さまですか」
「え、でも、別に怒らないでいつも通り笑顔だったし」
「そんなの先輩に気を使っただけですよ、ブレア先輩は女の子なんですよ、わかってます?」
「…でも、あいつのクラスも知らねえし、どうしたら」
「宿命かなんか知らんが、レッド・レジ―ナ、お前は何をかなえる気だ」
神か知らないが俺の運命を決めるなアホ。
一度潰えた夢、生きていた、それはうれしいが、もう一度、世界平和、それに乗ればどうなる。
「余が求めるのは変わらない」
「世界を壊すことだ」
「エドゥあると・・・」
黒いミニドレスの少女が暖炉に顔を突っ込んで死んでいた。
「私は悪くない・・・」
クロ―ディアは」
「アルフレート、誤解だ」
「黙れ、裏切り者め」
こんな感情的なアルフレートは珍しい。
「お前はなんで、そんな奴をかばう」
「だから、もう」
必死に抵抗して、階段の下で魔術師の男が死んでいる。
「ごめんな、助け出せなくて」
「何のこと」
「そうか、彼らはまた」
西方遊撃部隊は、銀の十字架の掲げる秩序と平等の精神をある意味、一番形どった第6、第7部隊の支配下に置かれた戦闘集団である。西方は独自の言語や歴史、文化を持つ帝国の支配地域ではある。東西南北とそもそも少数で形成される実験的な魔術と剣の部隊は軍と王宮騎士の指揮下で討伐することが多い。そもそもアテナの剣を頼りにしていた軍は白の女王と銀の十字架をよく思っていない。だが、同時に全てのパンドラを帝国は扱っているわけではない。
貴族は臣民を守るものだ。
常々、イングリッドはローザリンデに言う。
だが、貴族の少女が代表となった時、銀の十字架のお偉方は帝都とその比較的平和な地域を守る第一から第3部隊に有力者や貴族の子息たちをmとまてしまった。
「それは正しいことなのかしら」
「教官?」
オーウェン家の屋敷では多くの少年少女の姿がある。
今日も多くのオーウェン家の騎士公だったリーゼロッテ母を師匠とあがめ、あすの騎士や剣士を夢見る子供たちが集まっていた。
「弱いな」
セアドアは、友達を連れて去っていく。
「いい加減にしなさいよ、ジ―クヴァルト」
「うっ」
大好きな少女に怒られ、ジ―クヴァルトは弟を見る。
「アーデルハイト、アルバート」
「リーゼロッテ・・」
「私、どうすれば」
「ごめんなさい、やっぱり覚えていないわ」
アルヴィンとダヴィデは顔を合わせる。
「私の認識ではクラウド家はマリアベルたち姉妹で、学園のあの部にも生徒達の中にもいないのよ」
「何か事件とかで記憶を失ったとか」
「その可能性や大掛かりな組織とか、魔術テロとか考えたわ、私の知るヴォルフリートと違うもの」
「イシュタルの国境沿いの孤児院から帝都に来て、ヘレネ、お前と知り合ったと」
「でもよ、それにしても何で、犯人、そいつらは面倒なことしたんだよ、下手したら両家の諍いにもなるし、なにも予備とか使わないで最初からあいつを手元に置いてればいいだろ」
「おまえのおふくろさんだろ、何で知らねえんだよ」
例のチケットが5年前のものだった、そういえば今も学園でも最悪の勇者、悪夢の英雄だの、天魔落ちなんて関係なく、そこまでじゃないなと思っていた。
鬼属と神殿の関係者と絡んでいる時、ローゼンバルツァーの悪い噂も聞いた。
「俺は知らないから」
「何で、いつもそばに置かれるくらい仲良かったんだろ」
「だから・・・」
カイザー・クラウド、うちの生徒会の奴だ。これは単なる妄想よりも複雑なのか。
「・・・」
ヴォルフリートは、いらない、予定外の跡継ぎだったのか。何より両者は似ている。別に三つ子だの、5つ子だ野は珍しくないだろう。家が傾くから、取引に使われ、カイザーがヴォルフリートの双子の弟ということもあり、ごまかすために。真実にしても成人してからでよくないだろうか。何より、アリスまで巻き込む必要はあるのか。
預言を成就するために、彼と彼らの周りでそんな画策があったなら、ヴォルフリートを守るための予備がカイザーやアルバートなら、誰かがバツを食らう。
つまり、彼らはクラウド家の子ではなく、ヴォルフリートの兄弟なのだろう。ラブストーリーだの破滅だのよりは現実味がある。孤児ならば親などわからない、遊びの子だと言えば、そいつに逆らう権利はないだろう。
王女のお気に入りね、招き入れられたアリスの家は城というものだった。
「何かキャラと会ってねえな」
ヴォルフリートの部屋である。あの金髪オッドアイはどう見ても生まれも育ちもこちら側だ。平民よりで初めからあきらめられ、祖父母の家に逃げていた自分だからわかるがあれは農民や町の人間の生活も、銃も、帝国帝都の外も出たことがない。人様の家だから突っ込まないが6年も過ごした場所に慣れていない。
「・・・・地図に、本・・・本だな」
人付き合いが苦手で頼りきりのアリスをかばう時だけ強気で、魔術と無関係の学校に通い、家族ともかかわりがあまりない。意外とものぐさか雑か、何というか適当においている感じだ。天魔落ちでほぼ寮で過ごすからまあこんなものだが、スプラッターや地方のゴシップ記事が意外に好きなのか、本の間にはしおりやらなにやらが差し込まれた専門書や錬金術の本もある。本だなとはその人の過去、性格が出るという。なに、あの救世主、サイコなのん?
「読んでねえな」
普通の奴でも付き合いはご遠慮するだろ、暗い未来の去来を感じつつ、呪われた本から唯一機関車の本があり、抜き取り、ページをめくると、ピンクの可愛いチケット風の紙が落ちた。
「なんだ、これ」
絶句した。
「・・・・・・・・・・・・」
うん、俺はなにも見つけなかった。ゴミは捨てないとね、物増えても困るし。なのでポケットにしまい、外で捨てることにした。
近寄りすぎても騎士らしくないし、名誉を守るのが騎士だよね。
「セ―ラやアデレイドとはどうなっているの」
「普通にクラスメイトとして付き合ってますが」
「よかったわ、貴方みたいな凡人にあの二人ではつり合いがとれないものね」
余程僕と向き合うのがイヤらしく、首を逆方向グラウンドを見ている。
「話がそれだけなら、僕は行くので」
するとシエラが振り向く。
「ところでいつまで、人間の振りして学校に来る気なの、貴方のレベルじゃこの学園難しいと思うけど」
「まあ、家いても面倒ですし、飽きたらかな」
「そう、まだあなたと同級生しなければいけないのね」
「・・・・そんなに厭なら、部室の場所変えますけど」
「えっ、あっ、・・・まあ、それくらいは平気よ、その、だから、まじめに授業うけなさい」
「ああ、先生に言われたか」
「疲れた、貴方と話すってこんなに疲れるのね」
体力なさそうだしな。
「はい、飴、疲れた時は甘いのがいいよ」
「・・・・屈辱ね」
「どうしよう、ダヴィデ、私今日死ぬかもしれないわ」
「何が」
ボイスレコーダーを出され、音声が流れる。
「ふふ、声が…ウフフ、会話が成立できた」
「止めて、本当やめてください」
10年前、12歳だった。その日、山小屋を、どれほど走ったのかわからない、ともかく、自分の子供を平然と捨てる女、身勝手な男から逃れたくて山を村を超え、気づいたらどこかの壊れた山小屋でヴィントはその日はいた。
黒髪も、白い肌も目も全てが気持ち悪い。自分の構成する全部を否定したい、認めたくない、今までの甘い弱い自分が気持ち悪くて逃れたくて、何度も吐いた。
何が騎士道だ、正義だ、焔の結束、クラウド家だ。
そして、泣いた。悔しくて情けなくて。
下らない、くだらない、何が愛だ、友情だ。
・・・後悔させてやる。
お前らが僕を捨てるなら僕の方が捨ててやる。才能が何だ、ヴィンセント、オルフェウス。お前らはただ持っているだけじゃないか。
なら、僕は・・俺はお前らより強くなる。他人に依存しないと何もできない帝国もクラウド家も全てがクズだ。
自分で考えることも放棄した奴らに誰が餌など求めるか。奪い取ってやる。俺は俺の力でお前らを超えて、居場所を力を手に入れ、お前らの世界を否定し壊す。
その時に死なんて優しいもの与えてやらない。俺の屈辱を痛みを思い知れ。
「うるさい、うるさいっ」
雷が鳴っていた。
「俺に触るなっ」
マリウスは突然できた弟に戸惑いを感じた。母親が殺され、家族のだれもがオルフェウスに戸惑っていた。
イシュタルの男は、吸血鬼の女王の降臨に死を感じた。彼女を戦場に向かわせる時、敵国の人間に勝利はない。
「殺せ」
「殺せ」
「我ら女神と帝国、赤の女王に勝利あれ」
魔術師の本部隊が前にたち、最高の陣形をとり、始まれば血の殺戮が始まる。彼女の後ろの魔術師兵士達、ローズを名に持つ帝国の処刑部隊達。
「皆のもの、行くぞ」
ごくり、と喉を鳴らす。彼らの眼には精鋭の兵士達が見えていた。奴ら、眉一つ動かさず、銃を構え、剣を構え、実戦向きの魔法を放とうとしている。
「ああ」
「帝国の悪魔達を我らの国のため、殺すのだ」
「そうですか、お兄様は出会えていたんですね」
「何だよ急に」
「出会っているなら教えてくださればいいのに」
「だから、誰の」
「早いわね」
「ああ」
大勢の生徒がいきかう。いつも通りだ。
別に特別部活にも修行も執着していない。だって、それは結局自分に甘さを継続させることだ。意地も張っていないし、そもそも誰かと一緒なんて、それがなければ自分さえ保てないなんて、それこそ不健康だ。
「あの、ダヴィデ君」
白い腕、伸びる長い髪。ほのかに香る香水の匂い。
「私・・・・」
シエラは女性である。少女である。けれど守られる姫ではない。取り作っている。演じている。欺瞞を抱く。誰もがしていることだ。
「後で部活に行く前に職員室に行く」
「え、ええ」
誰もが恋を崇める。愛を尊いと歌う。支え合うことは素晴らしいと。自然なことだと。都合のいい相手を演じ合い、永遠と歌い、他人に振りまく。彼女達といることにいつの間にか慣れて、必要とされれば嬉しくて、でも決めつけられたくなかった。だって、それはつまり終わりがあるということだ。
だから今日も俺はエストさんの言葉を考えない。それが自分の嫌いな行為のはずなのに。女の子の2人なんて、俺は知らないのだから。
「・・・慣れ合いなんて、私達に合わないもの」
ごっこ遊びだ、といわんばかりに。
「そうだな、同情なんて一番最悪な欺瞞だ」
園芸部の扉が閉められる。
文芸部の扉を開けると、空気は乾燥していた。しかし、まあ屋上で泣きそうになるとかよほど暇なのか。
「何で、連れてきたんだ」
「ああ、だって高い所から落ちた死体ッて、いやでしょう」
椅子を男子生徒の前に置くと、自分をにらんで、座る。
「迷惑かけるな」
「いいですよ、今暇ですし、コーヒーはブラックでいい」
黙り込む。目の前の机にカップを置き、お湯を注ぐ、コーヒーを入れる。目つきの悪い男子生徒はおとなしく飲む。
「一応聞くけど、失恋でも?」
「…そんなんじゃない、お前には関係ないだろ」
「ですね」
本を読もう。
「・・・・」
「・・・・」
すると、男子生徒が口を開いた。
「お前、ここで一人か」
「え、今さら」
屋上で、黒髪の少年を見つけた。残念、絶好の読書日和だったのに。ご近所の部員。一般科の生徒。
誰にも頼らず、一人好きで問題児。これくらいで世界のどこにもいる、悪ぶりたい男子。普通の平凡な、善良な臣民の男の子。生徒会に立ち向かう、シエラの手下。
「ねえ、どれくらいいる気です?」
何やら自殺しそうな雰囲気だが、どうでもいいので声をかける。するとかなり驚かれた。うわあ、目が微妙。というか怖い。背も高い。ア、僕がチビなだけだ、それ。
「えっ、あ、あれ、俺?」
「君以外いませんけど」
すると、体を後退させた。
「・・・あ、ええと、何だ」
取り繕っても、絶望してたのみたんだけど。
「本を一人で読みたいので、君にここを去ってほしいんですが、で、どれくらいいるんです」
「・・・すぐ出る」
僕に視線を何でか向けてきたが、本を読むのが大事なので僕は座り、本を読んだ。
すると、しばらくして、園芸部部員が隣に座っていた。
「・・・」
頭を抱え込み、うずくまって。
「おい、あいつは」
「気にしなくていいよ」
本棚と本棚の間にダヴィデは椅子を置き、定位置らしく、そこに本を読んでいる。
「・・・そうか」
特に関わり合いも必要はないが。
「閉じるから」
「・・・ああ」
しかし僕の空間に他人がいるのは妙な気分だ。なにを絶望してるのか。
「オウル君、いつ隣に戻るんです」
「まだ・・・」
「そう」
―けれど、戦場ではルールもない。
「・・・アーディアディト」
秩序の騎士ラフォールが、初めての大型パンドラとの戦いで茫然としているのを見ながら、肩をたたく。
「・・・・あ」
「・・・貴方は、優しいのね」
靴ひもを結んでいると、セリシアが声をかけてきた。セリシアの見えない距離であざけるような表情。
「そうですかね」
だが、彼女達の視線は僕を超えて後ろの少年に向けられる。どこにいようと、人が集まる限り、階級は生まれ、お互いを傷つけあう。目立つものは攻撃され、才能あるものは足を引っ張られ、個性があれば排除される。
「関わるのは自由だけど、今は控えた方がいいんじゃない、ああいうのと関わるのは」「フォルトゥテ先生は区別しないと思ったんだけど、僕の勘違いですか」
少し怒ったような、引き締めた表情になる。
彼女と自分に関係性はない。
「行こう」
すると、オウルが迷ったように、だがやがては迷いなく、自分の背を見ながら追いかけてくる。
明るい髪の少女が校舎の二階から、視線を向けてきた。ゴットヴァルトはそれが自分ではないことに気づいていたため、自分を見て噂をする生徒達の間を抜け、校門に向かう。
「アリシア先輩・・・」
彼女にしてはひどく子供っぽい表情だ。失ったものを見つけたような。
「あの、・・あのね」
彼女の手が指が僕に伸びる。いきなり、部屋に投げ飛ばされた。・・・・あれで何で、過保護だと思われてんのか。まあ、アルバートよりはではないが、前と変わらない。
「きゃあ、可愛い」
後何で、両手を縄で縛られてぐるぐる巻き?
いわゆる年上の女性軍人のお姉さま方だ。アルフレートだろ、これ。
「綺麗、嘘、いいの」
「・・・・はぁ、どうも」
こういう交流系は美少年や美形とかするものだが。とはいえ、床に寝たママは失礼か。
「あ、あの、縄といてもらいます?」
僕にご機嫌取りは無理だと思うけど。
相変わらずぞろぞろと・・・。あれが全部ゴットヴァルトの護衛らしい。侯爵家に大事な予定の時にだけ集められる。正直、アルフレートはシエラは潔癖で正義感、常識的で、受け入れがたい。
従士になるとき、アルフレートは決まっていたが、最後の最後でゴットヴァルトにきまる。数人がかりの精鋭で、実力者で、本来の対戦相手は無視され。
そもそも楽をする主義である。ダヴィデは、一言国の大義とか勧善懲悪とかそんな薄っぺらいものは心底どうでもいい。なぜなら、自分には重大な使命は背負えないし、美少女がいきなり惚れるとかはあれは一部のイケメンに限る。
「君はあれだね、熱意というものがない」
急なアーク隊への入隊、名門校の入学にシスターは言われた。
「目も死んでいる、そんなにクラスにいるのが辛いのか?」
人とは簡単手に入れ、それが習慣化するとだ制する生き物だ。喜劇、醜悪。だが、権威だけの生まれだけの兄達には、悲劇である。
紹介された日は覚えている。
「貴方の一番の騎士です、どうか娘を好きなように」
「あ、あのっ、殿下お日柄もよく、和、私は殿下に会うために」
弟ともに自分の宮殿に住んで、頭は大人顔負けなのに父親の生まれる時より殿下の騎士になるのが使命という言葉を信じ、おばかな優等生は自分の後を追いかけていた。
「さぁ、僕は知らないから」
「ヴォルフリート・・・」
アルバートはヴォルフリートの顔を覗き込む。
二ケの肖像に、秘密の客人が来る。
「宗主・・・」
「今はだれもおりません」
フードとぬのをはずし、現れた顔は――
情熱とは狂気である。
恋愛とは熾烈な戦いの別名である。
「あきらめちゃだめだよ」
「え、いや・・・」
「がんばろう、私も応援するよ」
グラウンドって、あれ、いつから大告白する場所に変わったの?
結論からいえば、他の別人格の時のヒロインが出てきました。
「ヘンリー、私、頑張るからねっ」
学園に戻ると、アルバートの王国ができていた。
「やだやだ未練がましい」
「勘違いしちゃって」
「大体、前からうさんくさいとおもってたのよ」
「ショック受けてるだろうな」
「引くわ」
「虐めようぜ」
「お前、心強いな」
「…ええと、貴方誰でしたっけ」
「ラインホルトだ、クラスメイトだろ」
「ああ」
「お前も兄を見習い、生活態度を変えたらどうだ。彼女たちに引かれた理由、本当はお前は気づいているのだろう」
「すぐみんななれますよ」
「これ、やるよ」
「・・・・・は?」
「お前も大変だろうけど、無理して抑え込むなよ」
「うわぉ」
機関銃をプレゼントされたよ。
「・・・これ、誰かを暗殺しろってこと?」
「いえ、当主様が貴方が暇なときに使えと」
「へ、へぇ・・・」
(暗黒の魔女)
その存在をダイアナは知っている。世界各地でその支配下に悪魔属がいるとか。一人の魔女
。
「オルフェウスはアルバートによくつくな」
「まあ、長年探した親戚だし」
手の中の跡継ぎの指輪を見る。銀は体質が受けつかないので、金色の指輪である。ただし、アルバートのものに比べると古臭い。クラウド家の紋章が刻まれている。
「マリアベル様?」
継承権第一位はマリアベル、第二位がカイザー、第3位がアルバート、第4位が自分となった。僕の母方が難しい大変高い血統なのでバランスとったと、侯爵夫人代理が言っていた。子爵の寵愛はアルバートとカイザーという形だが、愛情が感じられない。まあ、子爵が今だ自分を置いているのはまァ、高貴なる事情なんだろう。
いずれにせよ、いやな気遣いはされている。まあ、貴族が庶民と恋愛なんて認められないのは分かる、それで嘘を作るのも。
「父上はその」
「何だ」
「お父様はまた出られるのですか」
クールな、冷えた空気である。
「貴様に意見など求めていない」
・・・イメージと違うな、女好きの支配者とかもう少し人間味ある悪党タイプを想像していたが。そのまま、二人は黙り込む。
「当主様、ワインを変えますか」
「任せる」
マリアベルが無言でトランプを差し出す。まあ、あの空間に入りたくないのは分かる。
「じゃあ一枚」
変な家だな、ここ。
マジであのクールな王様、完ぺきな支配者が僕の親なのかよ。
ちなみに僕は、子爵と会話していません。ホラ、生き物と価値観、人生が違うし。
2
才能はたやすく他者の人生を歪ますものだ。リヒトはヴィクターと違い、生まれついて、本物の天才と勝負し、負けてきた。
これでアレクシスに欠点があれば、リヒトだってこうも負けず嫌いにならないだろう。
「こんなところにいたのか」
「ジェード・・・」
「ワイバァン隊の敷地内に入るなんて、しかもこんな夜に、無茶する奴だな」
「しょうがないだろ」
ハルトはそのまま、進んでいく。
「仕方ない奴だな」
「いつも見ているのか」
カイザーはマリエルに尋ねた。
「・・・私は彼のメイドですから」
「そうか」
立ち去ろうとしたが、振り返る。
「何だ、その銃達は」
「・・・・父がくれた奴です、新型のプロトタイプと」
「人間関係に問題でもあるのか」
「僕があの人のことわかるわけないじゃないですか」
「馬鹿だ、フォボスを信じるなんて」
ルーティは黙り込む。
「こんなのだれも救われないじゃない」
掲示板でアムールバル祭、パラディ祭、ゴッデス祭のチラシを貼っていると、ディートリンデがやってきた。
「カイザーやアルバートは大変ね」
「・・・まあ、ナンバー2とナンバー3だしね」
ちなみにアムールバル祭、パラディ祭、ゴッデス祭とは、初代の白と青の女王が女神教会とともにはじめた三校、わが校、姉妹校、パヴォーネ学園で行われる春と秋に行われる二週間のイベントである。
「貴方もクラスの出し物に参加すればいいのに」
「いや、まあ、・・・やりにくいでしょう」
総スカンというわけではないが、クラスメイトから距離は置かれている。実にすばらしい日々、栄光の孤独の日々である。
「通してくださる」
「ああ、ごめんなさい」
グリシーヌが冷たい目で見る。ディートリンデは見るものの、ゴットヴァルトは目もくれない。彼女は颯爽と去っていく。
「怒っているわね」
「・・・だろうね」
気を使ったつもりか、ディートリンデが別の話題を切り出した。
「そういえば、貴方はダンスの相手、女神の黄昏の相手いるの?」
「いないけど」
「ふうん、じゃあ、私と出る?」
ゴットヴァルトは首を傾けた。
「ディートリンデさまって、ダンス好きでしたっけ?」
「貴方、ダンスは踊れるでしょう、ああ、例の風習なら気にしないで、ただ踊りたいだけだから」
「・・・もしかして、知らないの?」
「祭りの後のダンス大会でしょう」
「アリ―シャの気持ちは嬉しいけど、疲れるな」
「はぁ・・・」
「勿論嫌いじゃないんだ」
祭の実行委員ではないが、アレクシスは今日も兄と行動していた。
「シャルルも皆、頼られるのはいいんだけど」
「アルバート様と協力しては?」
このところ、これである。妙になれなれしい。
「そうか、ありがとうな」
「行くぞ」
「お前、アレクシスと何かあったか」
「さぁ、なんかああいう愚痴を僕にはいてはくるな」
「お前さ、どうせ相手いないよな」
「うん?」
「だからさ、俺達と屋上でカードゲームしようぜ」
「確か、僕は君たちの仲間にする気ないと言われた気がしますが」
「えっ、まあ」
「でもお前、今暇だろ」
「大丈夫、お前の兄ちゃんの人気も一時的だし、それにお前も俺達と同じだし」
「女子に嫌われても次があるよ」
「ああっ、お前が実はいい奴なの知ってるし」
「お前の気持ち、俺達にぶつけてこいよ、友達だろっ」
「うん、お前がさみしがり屋なの気づいているぞ」
「いい傾向じゃないか」
「今まで、相手もしてこなかったのに、・・・気味が悪い」
「放課後も誘われたんだろ、行くのか?」
「断ったよ、ここで人間関係作る気ないし」
「周りはそうは思ってないようだが」
「は?」
「ロザリア・エルフォードさん、何で僕が荷物持ちを」
「貴方、私の名前も覚えてないのね」
風紀委員で、いつも僕に文句言う女子である。
「中等部の生徒だったんだ」
「本当に他人に興味ないのね、だから嫌われたのよ」
苛立ちがすごい。
「大体、この数カ月の奇行を私たちは目をつぶってきたの、貴方が授業をさぼるのも人付き合いしないのも、でもあなたはいつもわたくしたちの気持ちを踏みにじった」
「・・・じゃあ、君も無視すればいいだけでしょう」
「ともかく、私は今日使える使用人がいないの、今まで嘘をついてきたんだもの、荷物持ちしなさい」
「わかったよ」
「アルバート様、ラファエル様にこれを」
中等部の生徒だ。
「渡してもらえませんか」
「君も彼の噂を?」
「・・・あっ、いえ、私は」
「でも私たちはお姉さま方が言うような詐欺師や嘘つきと思っていませんから」
「ラファエル様は誰も責めない、自虐的にもなりませんから」
「それに遊び人とか犯罪にかかわるとか、あの人はないと思うんです」
3
「アルフレート、学園に侵入者って、結構あるの」
「そんなにはないが、まあ、ここは魔術師や貴族の関係者も多いしな」
「イフリート隊だけど、俺を頼んなよ」
「総隊長の意外な秘密だな」
「返してきなよ」
「お前はワイバァン隊にこれ以上、馬鹿にされてだまっていられるのか」
「女子たちは君の何がいいんだか」
「ん?なんか言ったか」
「何してんです」
「ああ、ゴットヴァルト」
美形は風魔法がセットなのか、陽光が射し、風がアルバートの背後から吹きあふれる。天使の羽が飛び散っていそうだ。
「今日も皆が笑顔で過ごせたから神に感謝を」
清らかで厳粛な雰囲気が全身から漂う。
ほらな、これと僕を比べるとか、僕の方が選ばれてるとか、オスカーは見る目がない二違わない。
いつもいつも、なぜ平気で入れるのだろう。オスカーにとって一族の集まりは成長に伴い、安らぎから苦痛に変わっていった。ディートリッヒが顔を覗き込む。
「何でもないよ」
「ならいいが」
「・・・・貴様」
ダヴィデはあからさまな敵意を、はぐれパンドラのいるヴァーヌスの森の中で浴びていた。
「隊長」
「ああ、オルグ、今回だけだから」
ダヴィデは年下の少女に引っ張られる。む、となる。妹に友人ができるのはいいが男とは聞いていない。それもおウル家のはみ出し者とは。
「そうか、せいぜい、俺達の邪魔するなよ…シエラによからぬことはしていないだろうな」
「俺他に好きな子いるので」
いないけど、シスコン相手にはこれでいいだろう。
「信じられない、妹以外にお前は恋をするというのか、見る目がないのか、お前は馬鹿なのか」
「お、おう」
さすがあいつの兄貴だ。遺伝子って怖い。
「恨んでいるのだろう、シーザー」
「何の話だ?」
「レオンハルトだ、お前の友だったな」
「今もだよ」
「エレオノ―ルとあそこへいった画家というのはお前だろう」
「・・・ここです」
「あっ、来たんだ、ロザリア」
黄金の盾亭で少女が待っていた。
「・・・ええ」
「誰?」
「私の先輩ですわ、じゃあ私は行きますので、明日も同じ時間で」
「座って」
にこにこととろけるような笑顔を浮かべる。
「僕はアールグレイで」
店員が去ると、少女が前がかみで近づいてきた。
「少し無茶しすぎじゃないかな?かな?」
「・・・どこかで会いました?」
「また意地悪いう、ヘンリーは性格が曲がってるよ」
ああ、まあ。
「何で、貴族だって教えてくれなかったの、調べたら王子様みたいな生活してるし、女の子の知り合いばかり、作るし」
「セ―ラ・マディスか、錬金術師の」
「もう、まじめに心配してるの、何で連絡してこないの、ラドロたちも心配してるよ」
・・・そういえば、いい加減自分で自分の演技するの、疲れてたな。
「ワイバァン隊に入ったんだよ」
「・・・え、権力の狗は全員××だと言ってたのに」
「そのセ―ラさん、長くなるけどいいかな」
「全て話すわけにいかなかったから、まあ、今の僕になるまでの経緯はしゃべったけど」
「君は馬鹿なのか天才なのか、判断に困るな」
「他にどう説明するのさ」
「お前は、まあ、いいが自分の招いたことだ、自分で解決しろ」
4
タナトスの誤った情報、いいや最初からわかった上で。シャ―リぃは己の手を握る。クロ―ディアがドレスを翻し、骸骨の騎士を連れてくる。
「誰もが血を流さずに夢をかなえるなどできないのですよ」
「でも、でも私は」
ルーランは少女を見るがやはり表情はない。
「何者?」
セシリアはディートリンデとともに、黒づくめの男たちに襲撃されていた。
「アデレイド、何のつもりなの」
「何のことかしら」
「アルバートに近づいたそうじゃない」
「問題があるかしら」
「・・・アーデルハイト」
「通してくださる?」
「私、セシリアさんに負けませんから」
「な、何を」
「ゴットヴァルト様のことですわ、私、彼が好きなんです」
「転校してきて、何を」
「手加減しませんから」
5
「俺ができることはあるか」
「珍しいわね、やっぱり私が好きなのね」
「ごまかすなよ」
「貴方には関係ないことよ、それにそんなに親切だったかしら、余計な同情や好奇心は迷惑だわ」
「は、お前何言ってんの、俺が困ってんだよ、感じ悪いぞ、家族かなんか知らんがお前ピリピリして」
「・・・軍に行くのか?」
、先進的な軍国らしく、自分の好きなものになれる、だが孤児で何の後ろ盾もない、変人の自分を友としてくれた男子生徒が好き合っていた女性との未来を捨て、軍人になるという。
「ああ」
「止めておけよ、軍なんて俺達のことなんて見てない、一応の義務だけで」
「知ってるだろ、僕の半分は友人たちの血でできてること」
帝国のように区別などしない、恥じる必要もない、マナがないのも恥ずかしくない。
「ずっと嫌っていたじゃないか、親もお前がいつか・・・」
「君は知らないけど、絶望するとね、もうなにもないんだ」
「でも君は誰にも優しくて」
「そう見えていたら、僕も見どころあるんだな、だめだときらっていたものが僕を生きるものにするなんて」
全て、あいつが盗んだのに、ヴォルフリートから。
「エステル?」
はっ、とするとヘレナとヴィンセントがいた。
「カイザーに何を」
「あら、ゴットヴァルトじゃない」
「よお」
アリスがうれしそうにジークフリートと駆けてくる。
「何か用ですか、アーディアディト様」
「うふふ、セアドアとフィリップさまに誘われたの」
ジュリエットが前に出てくる。
「よろしく」
「ああ、どうも」
ジークフリートが笑みを作り、頭を叩いてくる。
「背が低いな、お前食べてんの」
「いきなり失礼ですね、ああ、君が兄と何かショーをやる」
「ジ―クだよ」
「後で、ハルトもイグナスもヴォルフリートも祭りの実行委員で来るんだよ」
「へえ」
「悪いね、ヴォルフリート、今日は運動部も祭の準備で人員足りなくて」
「・・・え、ああ」
「カイザー、ヴォルフリートが来たよ」
「え」
耳打ちしてきた。
「ハルトヴィヒ、そっちの人員はどうなっている」
「確保できてなくて」
「イグナス、アリシアとの連携は」
「大丈夫だよ、カイザー、その弟さんは」
「ヴォルフリート、お前には一番に動いてもらう」
「お前は一体・・・」
「誰でもいい、お前は動け」
「・・・・あの、うちの各部の申請書を」
「そっちへ」
「僕が担当するよ」
「・・・」
何やらイグナスの視線が向けられる。
「何か」
スィリィが飛び込んでくる。
「アルバート様、ピンチです、来てください」
「すぐ行くよ、任せていいかな」
「ああ、少しなら」
「ラファエル様、失礼します」
イグナスがなぜか残っている。
「・・・・まだ、何か」
「いや、その・・・ええと、相談があるんだけど、後で会えないかな」
「友達に相談すればいいじゃないですか」
視線を目の前の申請書やらなにやらに向けていると、また視線を感じる。
「君はやっぱり女神の黄昏出るんだよね」
「人が多いから出ません」
扉が開く。
「おい、イグナス、早く来い、・・・またこき使われてんのか」
「先生、ゴットヴァルトの知り合いで?」
僕とアウィンの顔を両方見る。
「少しな、ああ、アーディアディトがあとでこいだと」
「丁重にお断りします」
「・・・お前が好きな女の誘いだろ」
?何か引っ掛かりがあるな。
「いえ、兄に頼まれてるんで」
「行くぞ、イグナス」
イグナスをずるずると引っ張っていく。
「え、先生、まだ俺ゴットヴァルトに話が」
すると反対から、アレクシスが女子を連れてくる。
「いいかな」
「偶然だな」
「ヴォルフリート様もお元気そうで」
轟音が鳴り響き、戦場で膨大な光が放たれ、視界を包まれたかと思うと、予測範囲外の場所からジェニー達、本部隊は急襲される。
「ひるむな、撃て撃て」
「イエッサ―」
魔銃兵の最大の戦力を投入、それを呼んだかのように二つに軍を分け、銃撃され、日のペルソナが一気に放たれる。結界術士が全員で防ぐが、彼らはひるまず、空から、陸から、わずかな水辺から薙ぎ落とすように敵を蹂躙し、殺戮する。
「卑怯者、後ろから連続、二回連携攻撃魔法だと?こいつら、戦士の誇りがないのかっ」
命は尊いものだ。だが、帝国にそんな情の欠片もない。
ブラウン・ローズ、アッシュローズはイエロー・ローズと行動を共にしていた。
「今日の夜食は何かな」
思わず正規の帝国軍、魔術師でさえ吐き気を催す残虐極める光景が続いている。だが非難するものがいるはずもない。
隊長はハンドレッド。
「知りませんよ、目の前の敵のせん滅に集中してください」
マップ上に浮かぶ味方と敵の数を表した光を19歳の少年が見つめ、ハンドレッドの隣に立つ。副隊長はサタデ―。
ディメンション・ブレイク。
サウザンドの得意技が、地面を揺らし、隊のパーソナルを上昇させていく。赤い光が地面の割れ目から現れ、敵を切り刻んでいく、トラウマ必死の業だ。作戦を指揮し、全体を実際に戦闘させるのはサウザンド。
「結界は私にお任せください」
チェス兵を多く動かしつつ、絶対無敵の結界を放ち、敵をかく乱する、結界術士のペガサス種のXー002、
「右は任せた」
「了解」
探索と狩りの腕が得意なミノタウロス種のZー008、防御・幻惑が得意な戦士のケルベロス種のV-007、
「全ての情報は僕に任せて」
偵察や情報集が得意なキメラ、ヴァンパイア種の少年、
「うふふ、いらっしゃい、頼もしいお兄様方」
「うわああああああああ」
暗殺や毒の扱いが得意なメドゥ―サ種のY-0012、
「私は銃なら負けない」
銃撃戦や遠距離線が得意なQ-003、突進、
「しんじゃえ♪」
近接戦が得意なサイクロプス種のR-009、
「・・・・偶然ね」
「フォルトゥテ先生?」
「・・・・そ、その女神の黄昏なんだけど、相手がいないの」
「うん」
「一緒に出てくれないかしら、基本は全員参加でしょ」
6
「-では、お前の真実はどこにあるのかしら」
エルフリーデの首に、女王は白い指先をなでさせる。
「志も、夢も、お前の言う正義も皆誰かのまね、真実なんてどこにあるの」
「騒乱を起こして、多く死なせて、お前は」
だが、アンネローゼはほほ笑む。小さな駄々っ子でも見るような余裕のある笑顔で。
「それで過去と向き合った気?お前はアリスに守られたい、小さなプライドを守りたいだけよ、あなたは何者?」
「俺は・・・・」
悪魔属として、女王陛下にわが祖国に使える。
けれど、災厄なんてものは与えられない。自分達、亞人だけではない。革命の焔はいつの世も消えることはない。
「りんごか」
彼女にとって唯一の悩みは、悪魔属でありながら正義の女神の加護を受けて、神力を持つこと。
悪魔属は千年も前から人類とともに歩んできた。アンジェロはそれよりも古い。鬼属はごく九百年前に人と同等の権利を持つ。
卑怯者で冷酷で、嘘つき。大体、悪魔属は権力者の裏で暗躍することも多い。同時に彼らは人間を下に見ていた。
「困ったなぁ」
「スフィア様何を」
中庭でスフィアがたっていた。
「セアドアに誘われちゃった、でも行きたくないなぁ、都合のいい男子いないかな」
ちらちらとみられる。
「じゃあ、失礼します」
「ええっ、うそでしょ」
「ごめんね」
「おい、セアドア」
「行こう、ゴットヴァルト」
「・・・行けばいいのに」
「うん、もういいんだ」
・・・・金髪と関係がもつれてんのかな。
「いがみあってんの?」
「もう終わったことなんだ」
「仲良くすれば?」
「ないさ」
もしかして、あいつ人間関係作るの下手なのかな。
「どうせ非モテの貴方には相手もいないでしょう、私と踊りなさい」
シエラがきりっとした顔でヘレネとともに着た。
すたすた。
「ちょっと、ゴットヴァルト」
どん、と誰かにぶつかる。
ライトブラウンのショートヘアの女性だ。
「ごめんなさい、急いでいるんで」
「ああ、ごめん」
グラウンド前で、セ―ラがたっていた。
「ごめんなさいね」
「わぁぁん、ディートリンデもセ―ラもガード固すぎ」
あの男子、この前はヴィクトリアにも告白してたな。
「ゴットヴァルト、一緒に出てくれますよね?」
なぜか花びらが舞っている。
甘いと行き、ピンク色の唇、近い距離。背が高い丘の木の下で、セ―ラは頬を染めて、もじもじしている。
「貴方を一目見て、運命と思いました、付き合ってください」
セ―ラは自分を見ていた。真実であると目が語っていた。
「好きです、愛しています」
そして冒頭につながる。
「ごめんなさい、好きな人がいるので」
「え?」
「・・・信じてくれないの、ヘンリー」
「いやいや、女友達を狂気の世界に巻き込むほど神経太くないので」
夢の中では、ヘンリーはバトルファイターで女好きだった、が、セ―ラは友達だった。
「諦めないで、ヘンリー」
「あきらめちゃだめだよ、私も応援する」
「え、いや」
「愛はすべて時空も時間も超えるの、私と新世界作ろう」
木二背中を押しつけられる。
「私、頑張るからね、ヘンリー」
「とりあえずネクタイ、掴むの止めてくれます?」
「真実の愛で、本当の貴方を取り戻して見せる」
何かどこかで聞いたような。
「って、あの、何で顔を近づける?」
「キスよ、愛しているから」
「だめよ、セ―ラさん」
アリスが現れた。
「ごめんね、ゴットヴァルト遅れて」
「は?」
「待って、アリス、私は」
7
「・・・・ですが、アテナの剣、我が国はお前達に手を貸す気はありません」
レッド・レジ―ナはルナティつくドレスの少女たちに告げる。
「まあ、余裕ある人間なんてそうそういないんだけどね」
「あなたもですか」
「一生懸命、大人を演じているだけだよ、いつも怖くてたまらない」
深入りしない、熱くならないのは。
「それでも踏んばるのは、ここにいるのはお前と何も変わらないさ」
血が人を狂わせるのか。
グラヴィーダス、オーウェンが駆けつけた時、革命はピークを加えていた。
「そんな・・・・」
ミラージュやエルフリーデが彼らの元に戻った時は、民間人の方に被害が多かった。
「・・・オルフェウス」
「よう」
「お前もアリスの周囲を探っていたのか」
「・・・・」
ヴィントは答えない。
「アリスも気の毒だよな、痛いシスコンの弟がいて」
「ディーター、手が止まってるわよ」
「へいへい」
「でも、よく送り出しましたね、うちの女子が」
「最悪だからな、あいつの人気」
暗殺、騙しあい、ノワール・ローズ、ハ―ピ―属の自分にとって日常は疑いがない。感情を表に出すことはなく任務を遂行する。厳しい鍛錬も訓練も暗殺術も帝国のため。
「やめてくれ」
ドン、という音が鳴り響く。
露出がいくらか多い、飾り気のあるメイド2人、尖った耳の少女がいた。店の中で。けれど特に嫌悪感もない。誰もいやそうにしない。
漆黒の髪の美しい少年が出てくる。赤毛の繊細そうな少女とともに。怪人や鬼属、黒魔術師、魔術革命組織、悪魔属、怪奇事件。
表と裏。
「リーゼという女の事を考えているのですか、いやらしい」
「そうだな、最近会ってないな」
「フェリクスやお前のような男は、表向き好色な最低男よりも立ち悪いです、豆腐で頭がぶつければいいのに」
意外にこの子、潔癖だよな。
「さすがに、戦争中に、色気づく豪気はないよ」
「心配ですね、あんな世間知らずに帝国の未来とは」
「まあ、彼自身のというより、あれはまあ、呪術か何かだと思うよ、君なら解けるんじゃないか」
「以下に天才で超美少女の清楚な私でも無理なのです」
「それ、王宮の魔術士でも無理なのか、大変だ」
「ヴォルフリート、君の学校の生徒って」
「気にしないでくれ」
「面白いくらい、女子が近づかないな」
「いつものことだ」
「・・・ルヴァロア卿?」
「すいません、僕は」
慌てて肩から手をはずす。
「いきなり、何を」
「よかった・・、本当に良かった・・・」
はぁ、と自分の肩に両手を置く。なぜかほほ笑まれた。
「少し気が張っている状況が続いて、・・・失礼します」
セレナが追いかけていく。
「変な人だ」
「すいません、遅れました」
ゴットヴァルトが入ってきた。
「ごめん、あんた気味が悪いけど変態ではないわ」
「え」
「うん、そうね、貴方は女性の体に触れないものね」
「あの方に肘おくの止めて」
「アルバートのまねはいいけど、あいつのまねはだめよ」
涙を喉に詰まらせて
「・・・・・・・・・・・・・努力はするが」
「アルフレート、貴方もなの」
「だが、マリアベル、俺は得意ではないのだが、彼女には面識はあるが」
そもそも学園の女王、近づく男は身内かアレクシス達以外、というか親しい男子がいない。
どうしろというのか。
同格の身分さえ除けば、候補生はいそうだがそもそも彼らとはライバル意識というか、マリアベルも彼らも恋愛対象ではないし、頼んでも微妙な空気になるだけだ。
「フィシア?誰、それ」
今日も一人なのか。
「いや、いいわ、気にしないで」
相変わらずグロテスクというか、猟奇殺人やらおカルトやら哲学やら、分厚い本を読んでいる。文句が言われそうだが、気のせいか、周囲は微笑ましそうにゴットヴァルトを見ている。一連の事移行、立場も微妙なものになりそうだが、逆に固定ファンがついているらしい。一周廻れば、あれはあれで大変かわいらしいという評価に落ち着いたとか。中等部の女子生徒、高等部のお嬢様方、同級生の男女が熱を込めて視線を注いでいる。
「・・・いつも、こうなの?」
「ああ、あれか、まあいつもどおりかな」
「大変ね」
「うん、皆、パンドラだって気づいているんだろうね、よく殺すような目で見られるからね、正義感の塊だな」
「女子比率、高いね」
アルバートは苦笑した。
「俺達が説得したからな、あいつも根はいい奴だ、嘘も許してやれよ」
「僕は別に」
「・・・面白いくらい、女子が近づいていくな」
「いつものことだ」
「・・・・・あの、離れてほしいんだけど」
「何文句あるわけ?」
「これだから、女子にモテナイ奴は、変なところ触ったら殺すよ」
「男子があんたがいないなら退学するというから仕方ないんだからね」
「ラファエル、あんたも生徒を導くのよ」
8
「わが校のラファエル様とミカエル様、サラキル様とウリエル様です、どうぞ」
「どうも」
「うん」
「・・・・」
歓声が鳴り響く。
「ゴットヴァルト、手を振れ」
ウリエルことカイザーがそういった。
「僕は納得してませんが」
ラファエルことゴットヴァルトが。
「俺はするぞ」
ミカエルことヴォルフリートが。
パチパチ。音だけが聞こえた。
「あはは、楽しいな」
サラキルことアルバートが。
歓声がすごい。
「何だ、その格好は」
「ああ、人生相談のための衣装だと」
「お前がするのか?」
「笑って座っていればいいって」
「ラファエル様、私に悪魔が誘惑します、お導きを」
「自分で何とかしてください」
「彼女に違う男が」
「見る目がない女性です、次に行きなさい」
「好きな相手が二人なんです」
「地獄に落ちなさい」
「虐めたくなる人がいます」
「努力しなさい」
「お前導く気ないだろ」
「自分で物事片付けられない人間が何かを得られるわけないでしょうよ」
「お前、きついな」
「悪かったね、理想の王子様じゃなくて」
作戦行動後、いつもみたいになじみのルートを使い、サイトFに通りがかった時、探偵の助手を思わせる赤とストライプの帽子に、ダンサーか?黒い上着と首を隠すアンダーウェア、ズボンには黒いスカート、ブーツ。
よくわからないが女の子に丘の上の展望台に連れてこられた。
9
ヴォルフリートは、コウモリたちに囲まれて、その冷血動物のような、ただの狩る対象としての視線に背筋を冷たいものを感じた。
「・・・・・好奇心とは厄介ですね」
「いざべら」
「いくらけむ向いても、いくらでも群がって、広がっていく」
「命令通りに・・・」
南方女神教会の前で、ディートリンデは、クラスメイトの少女と待ち合わせしていた。
「北条、お前もやきが回ったな」
「ヴァガットの刺客か」
「その紋章はまさか」
男が蛇をイメージさせる呪印を両眼から見せる。
「貴方、大丈夫?」
クロ―ディアとアーロンの元に駆けつける。
貧民たちが次々に、戦闘に巻き込まれていく。
「アリス・・」
「ディートリンデ」
「危ないところだったな」
「貴方は」
イフリートの紋章が右腕に刻まれていた。
「リヒャルトさん、これは」
「大丈夫、仲間が助ける」
ワイバァン隊が、アリスの前に立ちふさがる。
「行かせない」
「動くな、動けば斬る」
倒れる幼女を魔術専門の警察が銃口を向けている。
「いひひひ、この悪魔が」
「手間かけさせやがって」
「俺を邪魔するなら、アルバート、お前でも攻撃する」
「・・・何で」
ヴィントは答えず、去る。
10
「貴方のやり方に前から反発していたからね」
「マリウス、それで貴方はどうするの」
「・・・」
「ここにいる連中を犠牲にするのか」
「軍人において、命令は絶対だ」
「助けるのはお前の仲間だけかよ」
オルフェウスは表情を変えない。
「やぁ、ゴットヴァルト」
「・・・フィリップさん?」
「少しいいかな」
「・・・ここは一体」
「驚いた、人間がここに来るなんて」
「貴方は?」
「女神のなりそこないよ」
「なぜ、だれも彼女を助けないの」
「勇者だからさ」
「そんな、女の子一人で」
「幻に心を奪われてはだめだ・・・」
目が覚めると、現実の世界、さっきと同じ場所だ。
「貴方は・・・」
「行くといい、友達が待っているぞ」
「お前、大丈夫か」
ラビッツがさっそうと登場する。ただし、フォルトゥナ騎士団の制服を着て。
「ええ」
「なぜ打ったの」
「撃たなければ、お前が死んでいた」
「なぜっ」
アリスはオルフェウスをにらむ。
「あんた・・・」
アルヴィンが銃口を向けたまま、飛び込んできたディートリンデを見て。
「思い出した、あいつが・・・」
「あいつがアーデルハイトを・・・」
「リーゼロッテ?」
「私はリーゼロッテ、リーゼロッテ・オーウェン」
バドォール伯爵家。
「・・・・・・・・・誰だ?」
「ジ―クヴァルト・バドォール、貴方に戦司祭として聞きたいことがある」
「お前が戦司祭?」
クラウド家別邸。
「ディートリンデ、いきなり来て何だ」
「カイザー、ゴットヴァルトはいる?」
「いるが、先に来客が来ているが」
「フォボス、お前の仲間になる」
ヒュウウ―・・。
「何をたくらんでいる・・」
「ウロボロスを裏切るのか」
「元々、そんな仲良しでもないだろ」
11
彼らの葬式は多くの民が来ていた。
柩の中にその人はいた。
そうか、やっと。
「ひっ」
「そうか、ゴットヴァルトはあいつにその時は心を汚されていたのか」
「・・・それは」
ああ、そうだ重荷だった。
ずっと、お前を憎んでいたとも。
目の前でユニコーンの背に乗り、ゴットヴァルトが怪しい悪魔のごとく、現れる。
バルドルの神殿で、聖巫女の少女は襲撃者の顔を見る。
「なぜ、貴方が」
アルフレートとともに、斬撃、攻撃魔法を敵に放つ。
救えなかったのは、救われたいのは俺自身なのに。
「馬鹿か、俺は」
だせえ。何、目の前のガキに押し付けようとしてんだ。
アデルがどうしようもない奴、クズな奴を命がけで救うほど聖女様か?救えない、気がくるっている殺人者?暗殺のためのロボットだと?
あいつがそんなのじゃないって、俺が信じると決めたんだぞ。あの時の病院で誘拐された二人の片方を選ぶなんて。
「馬鹿だ、大事にきまっているじゃねえか」
黒い長い髪が闇夜でうごめき、目が金色に。怪物の姿が現れる。
「オルフェウス様ッ」
ゴットヴァルトが悪魔の手を差し出す。
月に照らされた魔物は、邪悪ではなくて、天使に見えた。
フロイデはありすを見て、やっと会えたと頬をなでおろした。
「・・・ブルー・レジ―ナ・・・」
デッドドールが地面に転がっていく。
「今、何と言った」
「はい、父上、逆賊の第23皇子とその一味を打つ任務を私にお与えください」
そこまで驚くなや。しかしラインホルトが僕の家臣ね、どうみても無理があるが。
「おまえは後継ぎ争いやまつりごとに関心がないのではないのか」
「兄上たちは今帝国との戦争で多忙の身、私が国内の争いを鎮めたいのです」
ガウェインがひどくショックを受けているが無愛想男だから感情がわからん。だがチャンスである。僕がいかにだめで、特権にふさわしくないかをアピールできればこの男は皇族から僕を消すだろう。そのあと、ラインホルトはだれかに渡せばいい。
まあ僕もそのあと殺される可能性もあるが、そこは自分で何とかしよう。
「イヤ、僕がお父様に選ばれていたことはないけど」
本当に家族大好きだな、この一族。アルバートは慕われている、オスカーとはそういう機会でしか合わない。
「謙遜を、君が今もここにいるのは子爵家に興味があるからだろ」
「まあ、何かあれば後継ぎはいくらでも必要だからでしょうね、ただアルバート様への可愛がりブリは過保護な感じがしますが」
「単純に見ればそうだろうね、聞きたい?」
―4年前。
その手紙を破り、そのかけらをゴミ箱に捨てた。
「上からの同情か」
ヘレネがそこへ現れる。
「ヴォルフリート、友情をそんなに悪くするものではないわ」
彼女のことなど、僕が知るわけがない。
なぜなら、同じ神の血を持つ吸血鬼を僕は殺そうとしていたのだから。
「あのものを殺せ、狂っている」
なぜなぜ、なぜ。
「動くなっ」
侵入者は少女に掴みかかり、青の聖剣でその手で少女を。
―悪なのだから殺していい。吸血鬼だからこれは正義だ。姉の友だった、どちらを優先するかなんて。
「何で抵抗しないんだ」
臓器も、血も、ぬくもりも炎が。
「何でいつもみたいに殺さない、血を吸えばいいじゃないか」
まるで黒檀のように、あっさりと手の中に。
「なんで・・・」
赤い炎が今にも・・・・。
ひんやりとした手が頬を包む。
何で、死ばかりが現実なのだ。
「化け物のお前が生きて、僕の家族が殺されたんだ・・・」
もうそうでも何でもあの時、間違いで駄目駄目の魔物の僕が死ねば――。
エリク達に同じことした奴と僕は。
それ以上に、僕は、僕は薄情で最低で平気でこんなことできる。
「お前はもう十分なほど、焼かれているじゃない」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- アニメ・特撮・ゲーム
- 209
- (2025-11-20 22:06:06)
-
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- LEGO ‐ Star Wars ‐ | レゴブロック…
- (2025-11-15 21:55:46)
-
-
-

- 『眠らない大陸クロノス』について語…
- みみっちー
- (2025-11-22 02:38:23)
-
© Rakuten Group, Inc.