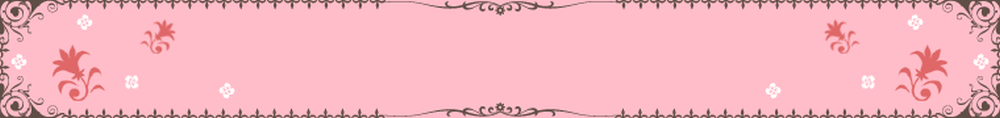第23章
1
ー乙女からしたら、うらやましいこの上ないだろう。
「すべてをあなたに捧げます」
長髪の騎士にすべてささげられるのだから、正しいかはともかく。
「サファイヤエル・・・」
僕はその光景をまぶしいと思った。でも、どこか、危機感のようなものを感じた。オリバーとカイザーだ。世話好きのオリバー、忠誠心が熱く正しさの象徴のようなオリバー。だが二人の関係が決めたのは階級だ。サファイヤエルにしてもそう、ただの孤児の少女でもあんなに忠義をささげるのか。
「私は何もしてないわ」
「構いません」
アルバートはどうして、世界は居心地悪いのか、自覚するまでわからなかった。ただどうしてほめられるのか、恵んでもらえるのか、不思議でならなかった。
「貴族ですから」
「当然だ」
「これは珍しい、家から逃げ出したお前の弟じゃないか」
フォルクマ―ルがアロイスとともに来る。
「久しいな」
「・・・ごぶさたです、兄貴…いえアロイス兄さま」
「まじめだな、相変わらず」
「嫌いじゃねえよ、ただ上辺だけ合わせて、あの結果を招いたのが前のお前らだろ」
「それは・・・・」
「大丈夫、役割は全うする」
フロイデはアルヴィン側だ。
「もうすk氏優しくできないか」
「仲良しごっこして、確かに楽だろうな」
「おそらく、帝国はチェス兵を多用してきます」
ディートリットの言葉にオズワルドははて、となる。
「まあ、そうだが」
ラインホルトの集めた情報、帝国軍はどうにもひとつにならない。
「ヘレネ姉さんは、そうでしょうね」
「はぁ?」
「あの人もエストさんも、エステル姉さんも自分が決めたことは曲げないから」
ブレアのハートの騎士でのトラブルをシエラは気にしている。
「お前と同じか」
闇に近い髪。冷たい冷静な瞳。
「ずいぶん関心があるのね、あなたはそんなに干渉するタイプだったかしら」
言葉がなくても通じる、友達。シエラやブレアでは難しいことではないが、俺とシエラでは共通項が多くても、対立が多い。
「まあ、少しな」
「姉さんもアーディアディトも自分でたてる人だから、私も同じ場所にいたいんだけど。難しくて」
マナ欠乏症ーー、それはノーマナに近い魔術士の家では、高位の法術師や白魔術士の手を借りない限り、カオスコアを引き寄せる体質になる。皮肉なことに、アルベルトの母はそんな人だった。厳しい夫に親戚たちは志や帝国を守ることを重んじる人である。それゆえに、アルベルトは自分で自分を縛ってしまった。
正しく、だれよりも強い、気高い人物でなければと。
「未来の皇帝陛下か」
アリスリーゼは、后妃の死を悼んだが、腕の中の皇子に未来を感じていた。魔術師の少女が扉をかけて入ってくる。
「余裕ね、明日はイシュタルとの戦闘が控えているのに」
「なぜ、貴方は騎士を?」
ヴィンセントをみるが笑うだけだ。
「いえ・・・・」
わからないな、少なくとも一連の日常を見て、カイザーはともかく僕につくのは。
「妹も少しショックなことが続きますし、家の中も落ち込まないので」
「僕といても、いやなことしか受け入れたくないことしかないのに」
扉を開く。金属製の大の上でまた十重の実験に使われたのだろう、ベルンホルトや侯爵は何を確認したいのか。
「ラファエル、起きて」
「ん、まだ眠い」
神の瞳といわれるものをドラゴンまがいのホムンクルスに守られながら、アンジェロの子供がアーロンをみる。
「くっ」
「これで勝負ついたな」
デスティネが駆け付け、男に剣で果敢に迫る。
「ばっ、デスティネ」
第六位純血の吸血鬼貴族は、絆の魔女の末裔に出会う。
「お前の負けです」
すべての家族、幼馴染、自分に関するものが黄昏のベーゼで倒れてしまった。
「私はまだ・・・っ」
「・・・・・・あの、人違いじゃないかな」
まさか、いきなり棚の中に閉じ込められると思わなかった。七人の子ヤギか。
「うんうん、君は7日前もそういったよ」
・・・・頭おかしいのか、すごいジョーク好きな人なのか。演劇系でお金持ちらしい。
「いや、二日前に来たばかり何だけど」
「大丈夫、もう怖い遊びはしないさ、鬼の坊や」
「・・・ここは一体」
大きい塔だ、古い。でもブリジット叔母さまの屋敷にこんな。
「・・・・え、薔薇?」
「-かわいそうに」
ヴィクトリアはフィネが自分と同じ狩人であることを知る。愛らしい微笑みを浮かべながら、残酷なことをする。
「僕はね、君のような中途半端が大嫌いなんです」
子猫のような。
「ん?」
何で、離れることができようか。
「ああ、違う、違う」
血まみれの恰好していても説得力がない。マリアベルは引いていた。
「僕、虐殺とか快楽殺人の変態じゃないから、うん」
「じゃあ、何で」
「いやぁ、偶然パンドラハンターにいつも通り、街中で襲われちゃって」
「・・・」
「僕平和主義の上喧嘩嫌いじゃん、怖い感じだし、臆病者だし、でもさ、正当防衛しないとだし、つい本気だしそうでてへ」
オルフェウス隊で活動する時、最近は僕を完全な戦力にする法に移行したらしく、夕方から深夜までアルフレートとコンビを組まされる。フレッドやセアドアは僕ではオルフェウス隊の戦力不足がよほど心配らしく、オルフェウスによく一兵士にするよう願い出ている。確かにイフリート隊と共闘するのでトラブルの種はないほうがいい。アルフレートは完ぺきなので、誰とも戦えるから不安はない。ただ、オルフェウスは兄の反逆、自分がブルー・メシアと対立しているような状況で、ヴォルフリートに懸念する親せきを心配している。まあ、ヴォルフリートとは戦わないし、アルフレートは上辺だけ僕を戦闘のパートナーに選ぶが絶対性はない。
―いずれ、彼はカイザーの敵になる。僕と殺し合う。
ただ面倒な敵だ。
「また明日」
カイザーはオルフェウスやアルフレートと戦う、国を壊す。ただ速度がいじょうだ。できるだろう、ただ情があることは。
「ああ」
「・・・・すいません」
セシルはウルリヒがまた無意味に親切を、面倒事を持ってきたことを知る。
「いいけどさ」
唯一の失点、くだらないがセシルはカイザーの護衛についていく。
「ウルリヒ、いい加減カイザーになれなよ」
「・・・・でも」
まるでいないもののように、存在は認識しているが、腫物のように触る。クララは不満だろう、役目とか義務は嫌いだが、多く護衛を彼ら二人に付ける理由はクラウドは目立ち過ぎる。
「幽霊なんかにとらわれるのは無意味だし」
リウォードはオナシス家が支配する水の都シランスの出身だ。
ハズモンドが頭を下げ、去っていく。
「あんな裏のものを使者によこすなんて」
「ねえ・・・」
取り巻きの少女達はくすくすと笑う。
家が商売人であり、四男坊だから跡継ぎとはされず、細身でありながら割と筋肉質で三白眼の眼だけが特徴で、生まれつき神や精霊を引き寄せる体質だ。
「まだ、その体質治っていないのね」
ガーネットの間。
オナシス家当主は彼女の幻の中にある。
「・・・」
フォルトゥテの魔術師はハートオブクイーンの手のひらの中にある。
「はい・・・」
かって、帝国を震撼させた悪魔帝(デーモン・エンペラー)の実の妹にして、軍事力の信望者。
緋色の聖女(ア―リィ・マドンナ)ともよばれる、マリ―ベルの実の姉。魔女部隊の司令官。フォボスの宿敵。
「―女王陛下にはまだ迷惑をかけると思いますが」
「いいのよ」
軽やかな鈴のような声。気品と威敬、聖者と悪魔、そう反する印象を与える女性を女性が見れば嫉妬せずにはいられない。男が見ればわがものとしようとするだろう。
「ハートオブキングは今日も不在なんですね」
控えているエレナがつぶやく。
「あっ、すみません」
「いいのよ」
女は少女の顎をその細い指で掴む。
だが、すぐに気付く。
「この悪魔の娘が」
乱入者が入ってくる。
「陛下、不埒者が」
ライナー達、ウロボロスのメンバーが前に出る。
「お前達、下がりなさい」
「しかし・・・」
「いいのよ、退屈も飽きていたし」
ピンヒールの音が大理石の床を鳴り響く。
「それでわたくしに何の用かしら?」
「お前に死んでほしい、お前は真実の神を民衆から奪う悪魔の化身だ」
「あら、わたくしは平等にお前達に接しているはずだけど」
2
「狂っているね、・・・・では君は正気なのかな」
銃口を向けられ、不遜な態度を崩さず。
「けがれはすべて消すべきなのだ」
「スパロウ卿、アリスのためだ、こいつを殺せ」
「ふざけんな、ゴットヴァルトを開放しろ」
「ダノン、コウモリにかみつくな」
アルフレートは身内びいきではないが、従士だ。まあ、死ぬ確率が強く、任務遂行率が高いが、オルフェウスの周辺を扱うのは、魔術師も軍人も適正高いアルフレートくらいだ、おまけに騎士団とも仲がいいと。
「うるせえな、帝国にまとりつく悪魔たちを倒すんだよ」
ラフォール隊がうらやましい、実力主義の内は年齢を気にしない。わけありだとかまあ問題児ばかりだ。クールだの大人びいているといわれるが、そんなことはない。幼いころから気の強いおてんばタイプ、バルドォルと何かとわがままなタイプになれているだけだ。
「お前の行動でうちが乱暴で無法だと思われる」
「いつもすませて、お前だってあいつらになんかあるからここにいるんだろ」
「待てよ、行くなよ」
「そうですよ、こんな・・・」
「大げさだな、ラフォール様の隊に移るだけだよ」
リオンは意味がわからない。
「みんなだって別にお前を責めてなんか」
「今までありがとう、リオン、メーデル」
何でだ、とライトニング・ヴァリニアの戦司祭≪エスピアツィオ―ネ≫マーレイと、相棒のヴァーチュナイトのベルナール。庶民のあこがれ、理想の英雄であった魔法騎士がゲイボルグを盗み、武力放棄したという。
「ベルナール、お前達は叛逆者、ティ―ルの盾の象徴、アプリコット・タ―クをまずは捕らえよ」
「奴は庶民に武器を発砲、最高司祭ゾンタ―ク様に刃を受けた大罪人だ、亞人や貧民を惑わし、おのれの野望をかなえようとしている」
「しかし、彼女はこいつの」
「できるな、ベルナール」
「パンドラを倒すのに、同じパンドラを使うって」
引き渡された少女は、戸籍上、アルヴィンの妹。確かに妹はいた。だがそれは幼いころ死んで、生きていたら二つ下。14歳くらいだ。エデンからの優等生。
「タッグを組むように」
ぎょっとした。彼女は10歳になったばかり。その時点で将来、どんな美人になるか約束されていた。パンドラは人並み外れた美貌か魔物かの両方どちらかだ。だが、アルヴィンはあまりにも大人びた、凍てついた表情、伸びた背筋に。
「GXー0012号、妖精と天翼属の合成体、必ずやお兄様の敵をせん滅するよう、役に立って見せます、さぁ、どのパンドラ達を殺せばいいでしょうか」
軍人、自分よりも上の年齢のせいかんな軍人を前にした気分だったが幼女だった。
「ん、どうした」
「・・・・あの女」
見るとみなりがいい少年とはかなげな異国の少女が歩いていた。
「ただのカップルじゃないか、彼女がどうかしたのか」
「チェスゲーム?」
白と黒の格好をした騎士達がチェス盤の上で、槍を持ち、死闘を繰り広げていた。
兄妹とは人間関係の一形態だ。姉弟とは必然的に上と下を分ける。
一人っ子のブレアからは甘い香水のにおいがする。テおドールの胸が微かに高鳴る。
「だからかな」
けれど、たんに好きな人とライバルで友達だけでなく、別の何か、暗く濁ったようなものが明るいはずのブレアの声に混ざる。
誰もが一番初めにする他人は親であり、兄弟だろう。しっかり者のシエラに元気なブレアは、姉妹のように見える。
「その先に行けないのは」
「焦らなくていいんじゃないか、可能性の一つだろう」
イリスの横顔を思い出す。平和を壊すモノは嫌いだ。ダヴィデは、シエラとヘレネ、オルグの問題に関わろうとしているがブレアが危惧するような理由ではない気がした。
オルグは集団を主に、臣民を守らんとする目標であらんとする。くだける幼馴染でもいれば、普通にいられただろう。
・・・確か、オスカーと同じ学園か。
「仲間意識・・・そういったものが近いんだと思うよ」
シエラはダヴィデの行動を喜ぶか、答えはノー、彼女は冷たい人ではない。こういうと輝、テおドールは彼らの気持ちに共感できない。明確なものなんて、どう示すのか。
ヴォルフリート、君はどうする?
「そう・・かな、それだけかな」
恐怖しているようにも見える。
何度も彼らは他者に裏切られている。孤高であろうとする。そんな二人にたちいることは下手したら、全て失う。けれど、二人のその形が友情やそういうものなら、祝福していいのだろうか。
「何でお前がいるんだよ」
「エドゥアルト、レディーに少しは取る態度を覚えたまえ」
「・・・・誰だ、お前」
まあね、お人形のように抱っこしていれば突っ込むよね。
「・・・・き、奇遇ね、ゴットヴァルト」
「え、ああ」
アラビアンな王様なのになんで、アルバートと僕だけ何か露出度が多いのだろうか。
「本当、ここは退屈しないわ」
シエラさんの声が震えている。ブレアとダヴィデがセットのようについている。
「毎日何かしらゲリライベントですしね、何か」
ところで道歩くたびに僕を指差して、叫ぶのは何なんだろうか。
「よく平気でそんな服、袖通したわね、あら、肩にゴミが」
するとブレアさんがいきなりシエラの腕をつかんだ。
「ぶ、ブレア?」
「あ、ええと、ほら、ね」
何やら目の前で百合的なイベントが発生している。なに、嫌がらせ?
「・・・・だって、だって」
「わかるでしょ」
キャラが違う、おかしい、シエラというのはもっと冷酷というか氷というか、こんな幼いキャラだっけ?
「全て最初から用意されていたのだ」
「はぁ?」
送られてきた、ライトニング・ヴァリアの少女は生気をなくしていた。
「では、ブリジット様、救いはどこにあるんですか」
「どこにもないわ」
「そんな・・・」
ヴァイオレットは悲しげに顔を歪めた。
「皆を守れる剣を」
オルグはそれを聞いて、アレクシスという対戦相手に疑問を抱いた。誰に聞いても彼を批判したり、馬鹿にする者はいない。純粋な戦闘能力の差。騎士達を連れ、士気を行い。
「アルベルト」
「君も着ていたのか」
全ての錬金術師の塔、軍の戦力、アベルタワー。彼らの多くは、軍服に身を包み、自然界の物理法則、四大要素、黒魔術や白魔術士のルートクロイツ教団や七星の聖者(スぃリオス・セイント)、国王とイシュタル自体に力を持つ金の聖十字架(アウレム・クロス)と聖女教(コスモ教)。
「・・・・オルフェウス・・・中尉」
フォルクマ―の意志か。
「サファイヤエル、わかるな、なにを優先すべきか」
「アルフレートやアードルフが危険にさらされているとわかって」
「敵をだますには味方からだろ」
アリスとヴォルフリートに視線を向けるが冷たいものだ。
「コウモリの一部だろうな、イーグル隊にも、銀の十字架にもそういう奴らはいる」
「人の命を道具にするなんて…アルヴィン、知って」
「オルフェウス・・・・ワイバァン隊隊長・・・・」
雨や霧があり、オナシス家の領地は今。コウモリたちは表に出ず、カードとして時折出る。卑怯者のワイバァン隊。
「大丈夫か」
ヴォルフリートは騎士団の制服のカイザー、その崇拝者だろう仲間に声をかけられる。誰もが二人を比べる。
「ああ、君はすごいな」
「さぼり魔じゃなければ、エースなのに」
クラウドの騎士の姿もある。カイザーは去っていく。あれがあいつの兄貴か。
イグナスやハルトヴィヒは当然のように時折、ワイバァン隊に来る。
「彼女との思い出?」
ハルトヴィヒはまあ置いておいて、イグナスは何というか気持ち悪い。二人がラフォールやオルフェウスと知り合いでそのついでにからかいにきているのだが、なぜイグナスは僕の手をいちいち握ってくるのだろうか。
「そうそう、君の空想の彼女の話、話せると子だけ話してよ」
いつも微笑み、優しい感じだが感情が読めない。手を外させて、距離をとり、セアドアが何やら楽しそうにイグナスと会話をする。何やら楽しそうだ、するとなぜかフレッドが飛んできた。
「君達、なにしてるんだ」
ハルトヴィヒはコミュ能力が高く、友人が多い。にやにやと笑うが、こういうのも親密になる手段だろう。
「でた、奥さん」
「あるいは保護者2」
「まさか、ゴットヴァルト様とじゃつりあわないよね」
笑顔で言われたがまあそうだろうよ。イグナスの邪気のない笑顔だがなんか不満そうだ。そして、フレッドは、ますます顔が赤い。
「彼と僕が、そんな、たちの悪い冗談はやめてくれ」
育ちがいいか、生真面目か知らないけど、湯沸かし器みたいだ。
「そうですよ、僕に迷惑ですよ、こんな可愛くない奥さん嫌ですよ」
「冗談だよ、男が奥さんとかないから」
セアドアもうなずいている。
「うんうん、ヘンリーは早いよな」
イグナスがにらんでいる、セアドアを。
「冗談?笑いどころ、どこなんです」
セアドアが肩をたたく。
「まだ理解しなくていいことだから」
「そう?」
「君たちも君たちだ、いまは隊の活動時間だろう、こんなところで」
いきなり肩を掴まれた。
「俺達は仲良く話してただけだ」
腕を組んでくるが、まだフレッドは赤い。というか怒っている。
「ゴットヴァルト、嫌なら嫌というんだ」
何だろうか、なぜこうもぴりぴりしているのか。
「別に平気ですけど」
女子ならキーと怒ってくる場面だ。
「君はもう少し、そういう意識を持ったほうがいい、普段から大体君は油断が多すぎる、この前も」
なんか、こいつ将来奥さんや子供に嫌われる孤独な爺さんになりそうだ。
「うざ・・・」
「うざい?悪いのは君だろ、そもそも、君は貴族という意識を」
耳元できゃんきゃんと。ミリアムのうそつき、これのどこがさわやかなモテ男子だよ。
「低俗な庶民育ちから言わせてもらいますが、相手を責めたてようという行為はその相手を征服したいというさもしい男の独占欲の表れだそうですよ、どうですか、将来ストーカーになるエストカラス卿」
「どくせ・・・っ」
相変わらず都合悪い言葉はする―らしい。傲慢な貴族か。
「僕は友達に間違った道に、ろくでもない連中と同じになってほしくないだけだ」
顔が真っ赤どころか、声が小さいが何なんだろうか。
「で、お前はどういう風に彼女とデートしたのかな」
「答えなくていいよ、君達も他人の過去に探りいれるなんて」
そういえば、あの人にもウザく怒られたものだ。
「君にはつらい恋だっただろう」
なんか背後で言っているが、そう、あれは。
「そう、あれは4年前、サーウィンの山岳地帯のことでしたかね」
・・・・話すのか。
ズォォォォン。
「あれが、ヴァガットに協力した裏切り者か」
イシュタルは、国王に絶対の忠誠を誓い、武力を尊ぶ。同時に亞人達(パンドラ)にも聖女たちの精神をもとに同じ軍国(イシュタル)市民として扱い、ともとする。
「全く、面倒なものだな」
「陛下もいい加減無意味な戦争をおやめになった方がいいのに」
高台にある黄金王宮(ゴルト・キャッスル)。
この世の春を謳歌している貴族達や錬金術師。乾いた風が、オオカミの横顔の光の結晶の旗をゆらす。
公開処刑―・・・。
どこにも主義者がいて、裏切り、だますモノもいる。それゆえに、フリッツは、尊敬する兄の死、友人達の革命行為、大嫌いな兄と巫女の反逆という複雑な立場でいた。
…父上は相変わらずか。
王族に仕える軍人で、その先祖は騎士の連隊を持つ家、つまりは王族たちの腐った貴族の争いの中に生まれてからフリッツはいるわけだ。
関心のない父、名ばかりの母。年の離れた兄達。だが王族となればさらに複雑だ。力がないものは遠慮なく潰される、血だけの王族はいらない、だからこそ暗殺者がガウェイン皇子に向けられる。
有力なのは第一皇子だが、そもそも四大王家とその傍系王族は、全てを持つ皇子を面白く思わず、軍人皇女や天才皇女、まじめ一筋の正義感の王子、才能や力を持つものは多い。
ずる賢さの皇子や皇女、ガウェインとは別の意味で暗殺者に狙われている無能皇子オズワルド・カフィールや慈愛の王子サイラスもいる。
己のよくしか考えない第4皇子は今も国を好きなようにしようとしている。
親友を守りたい。
だが、仲間の一人はヒルトルートはオズワルドの騎士の一人だ。おまけに国王の寵愛を受けたオズワルドは、どう見ても時代の王には合わないのに、担ぎこまれている。周囲が彼を囲み、自分達のお飾りにしようとしている。
「えー?王位?僕は楽しい方の兄さんや姉さんの元につくよ」
母親に忌み嫌われ、だが皇子ということで利用され、外見だけは女性受けがいいので、頭も悪くない、カミラを兄達に惑わされ、作ったのもこの皇子で、フリッツの天敵の軍人がついているのもこの皇子だ。
―あいつはいずれ、俺の最大の敵になるかもしれない。
「人生短いんだし、遊んで生きようよ」
ガウェインもだが多くの兄弟にオズは嫌われている。彼を担ぐ中にはこんな能天気には不似合な優秀な武人や知恵者も真に忠義な人間もいる。多くはほかの優秀な皇子や皇女に仕えたものだ。同時に自分の国に危険視される人間、犯罪者、変人もオズは楽しいからと家臣においている。
「皆と同じことして、お行儀よくすわる人生?ないない、楽して生きなきゃ」
謁見したことはあるが、オズは王位を継ぐ気はないが、庶民と接するのはガウェインと同じだが、自分の感情を優先する。
「ここではみんなが主役何だ、僕を楽させるためにいきたまえ」
ぞっとしたものだ。無能で権威にすがる貴族、それを体現したような少年、兄達に利用されている駄目王子。
「さぁ、みんな、ショーの始まりだ、存分に殺しあおうっ」
・・・うつけが。
ヒルトルートは、今日弟の墓にいっているという。戦死した少年はフリッツの同期の同級生で、帝国のナイトハルトにうたれたと聞かされている。
「テレジア・・・」
その炎が消える日はいつだろう。
意外な事実だがオーウェン家は帝都住まいだが、その領地、本来の故郷はツヴァイトークにある。風使いは各地に点在し、ラーファガはソール側に家族とともに住むが、リーゼロッテの縁戚だ。ウラヌスの神殿近くに、優秀な風のエレメントの魔術師を鍛える場所があり、ヴェーヌスとのかかわりは深く、場所はヴェーヌスに程近い場所にある。名門中の名門貴族、ヴェーヌスの騎士の中でも一番のグラヴィーダス家とは良きライバル関係だった。リーゼロッテ・オーウェン、彼女のことを知る人物から言えば、正義感のある、弱気を守り悪を倒す。明るく冒険家でおてんば娘。それはオーウェンが魔術師である以上にグラヴィーダス家と同じく、魔術戦争に否定的な良心的な、魔術師としては失格な一族であったにすぎない。
誰もが自分の主義を唱え、自由を得て、幸福に生きる世界を守る。誰もが幼少時思い描くはかない夢だ。実際は、どんなに全人で優しいとされる人物も生きていれば必ず汚れずにはいられない。が、幸か不幸か、少女は跡継ぎの兄達と公平に育ち、魔術も他者の幸福のために教え込まれた。そもそも聖杯や賢者の石への妄執は切り捨てている。弱虫だといわれた、格好がつけた衣偽善者だと、だが誰もそんな意見をものとしない。高貴な理想を唱える本家に不満を抱くのは当然の結果、リーゼロッテがそんな人の当然の暗い心を理解できないのは皮肉なことだ。公爵家とも旧友で、アルベルトの家やアーデルハイトともに古い魔術の世界を変えよう、そもそも低く見られがちな風のマナの魔術師は弱腰と見るのも仕方ない。だから結論から言えば、せめて、兄達と少女を区別、自分は劣等生だと彼女に自覚すべきだった。善と悪で世界は別れないと。
平等に、それゆえに少女は叔父たちと仲間に叛逆されることとなった。
いつか、悪人も正義や愛に気づき、世界はよくなる。リーゼロッテはアーデルハイトと帝国の剣として、悪を裁き続ける。
兄たちや主君である親友の気持ちもわかる。心配してくれるのはありがたい。
「今日気かしょう気かなど、誰にもわからないのだよ、ディートリンデ」
けれど、その名前は――
「つまり、あれか」
ベルンホルトは慈悲でも同情でもなく。
だがその答えはまた新しい疑問が浮かぶ。
「・・・・・それはどうかしら、ヴィクトリア、百パーセント間違わない、気持ち悪くない人間なんて、その方が怖いじゃない」
「あんた・・・」
「貴方は、彼の何を知っているの、強いから正しいから、貴方に彼の何が間違いだといえるのかしら」
「誘惑されたの・・・」
「さわんな」
「どうしたのよ、アンネローゼ」
「私はエルフリーデだ」
アルヴィンはあいた口がふさがらない。
「ひきょう者が」
「ありがとう、最高のほめ言葉だね」
ハートの騎士が一人、セアドア・ナイチンゲール。
彼の在り方は、純粋な神への崇拝に近い。だがハートオブクイーンへの勝利はささげるが、ワイバァン隊総隊長はセアドアはその心は盲目的な忠誠ではない。人間に関する絶望的なまでの嫌悪と憎悪、憐れみである。極端な正義の忠実な僕である。
独特な文様の魔法陣を浮かばせ、敵に攻撃する。地面が揺れ、割れ、激しい音とともに氷の悪魔が襲う。それはまさに悪夢の光景。氷の鋭い尖った串のようなものが敵を絶滅させる。
「ワイバァン隊に入るのに、悪魔族の罪人を手に掛けるか」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- GUNの世界
- Browning Hi Power【Commercial】HW…
- (2025-11-20 12:30:22)
-
-
-

- 何か手作りしてますか?
- ハムスターの革人形を作る その141
- (2025-11-20 19:44:38)
-
-
-

- 鉄道
- 東武鉄道 20000系(20000…
- (2025-11-21 00:10:13)
-
© Rakuten Group, Inc.