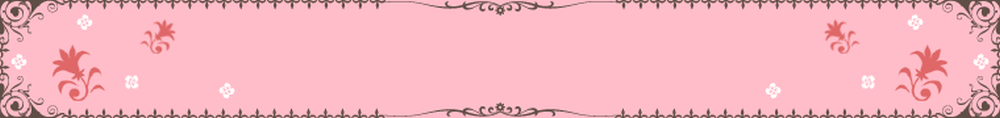第25章
1
いやがらせか、そうなのか、打が普通に話しているから普通の会話のつもりなのだろう。
「よくある、よくある」
「だよな」
離している内容が少々どころか、生涯レベルのトラウマになる内容である。二人は幼少時での思い出を語り合っているだけだが。
「まあ、斧や鉈は鉄板だよね」
「でも剣一つで一撃は馬鹿だよね」
ワイバァン隊は静まり返る。彼らにはもう軽い流行や世間話の扱いなんだろう。エリザベート、ゴットヴァルト、セアドアは楽しそうだ。
「最近のイシュタルのスパイって」
「あー、それは帝国軍最強のあの武器も」
「まあ、ぱくりだよね」
さらに静まり返る。
「まあとりあえず、すぐパラメータになるやつ馬鹿だよね」
「「超わかるー」」
「母親とかこの世で一番邪悪な生物に執着する奴も価値ないね」
「「わかるー」」
「あれが、侯爵家の」
アルバートは、ゴットヴァルトの周りにエンペラークラスの魔術師、錬金術師、権力者が集まっているのを見た。いや集めたわけではない。
「ペルソナなのか」
「残念だがあれは魔力じゃない」
きらきらと本についていっている。
手に入れたものは何なのだろうか。時折、そう思う。でも、心を失っている自分には想像でしかないけど。
「しつこい」
「お前は普段から」
くどくどと本当にしつこい。
確かに良くは来る、マリウスによると昔から子供好きで、世話好きでカイザーの面倒を見ていたとか。オルフェウスからすれば、まじめ人間で頑固で面倒で、優等生の兄と問題児の弟で、頭が上がらない相手。結構文句言い合って対等で。ブラコンなだけだと思う、あのおばさんのこではないらしいし、多分気を使っているのだろう。しかし20代の兄弟がそういう関係は、不気味だ。
で、カイザーを生意気と思いつつ、来るのはあの上官の複雑な感情で。
「オルフェウスの人生にお前の事情を入れるな、迷惑だ」
アウグストはあきらめているらしいが、いや、別にいらないから断っている。
「大丈夫ですと言っていますよ」
「俺がお前の言葉を信じるか、対処を考えろ、貴様が腑抜けのままだとあいつは変わらない」
「気にしなくていい、僕は好きでやりますといったけどしつこくて」
「もういい、お前は向きあう気がないんだからな、後悔するぞ」
「・・・・そんなにも大事でしょうか」
「え・・・・」
アデレイドはアルバートにいう。
「強くあろうと、生にしがみつくことは滑稽でしょうか」
「そんなことはないよ」
体せいか、反逆者か、正しさか結果か。フレッドやスフィア、クラスメイトの多くは自分に誇りに持ち、秩序や仲間、夢に従属し、冒険者は仲間と旅して、クルーエルエッグは危険生物らしい。まさか、立場逆の勉強するとは。
「・・・・」
体を伸ばし、腕を伸ばす。周りを見れば真剣に聞いて、情熱が顔に浮かぶ。
カイザーはまじめに受けないだろう。しかし、あの兄は、異常だ、能力的に頭脳面でも。頑張って、頑張って。復讐を、勝利を。
誰かを犠牲にして。本来は優等生でまじめだ、無駄に罪悪感に駆られ、行動し、後悔し、自分を嫌う。すごい人だ。
≪ダークリップ≫
マリアの得意技が、繰り出される。闇魔法の基本の技だ。
「すさまじいな」
「ええ」
ため息をつく。
「ジェードは馬鹿なんだから」
マリアは、制服姿のまま、あきれ顔で二つの斧を持つ。
「・・・・・どういう意味だ」
「アルバート、お前に何の迷惑があるというんだ」
「ライナー様・・・」
「彼が偽物でも何だろうと、お前は何にそんなに不安を抱いている」
「僕は・・・・」
「ベルンホルトが、彼に非道な儀式や実験を強いていることか、ゴットヴァルトにある数々の噂や奇行か、さてどれか一つでもお前に降りかかるか、違うだろう、確かめないとお前が不安なのだろう、相手は殺人鬼かテロリストかもしれないと」
「僕を愚弄する気ですか、そんな小さい男だと」
「・・・・違うな、お前はあいつに敗北しているかもしれないことが受け入れたくない、だがそういった弱いものがそういった犯罪にくみしていることはないと聞くが」
「・・・・後悔なんだろうな」
「え・・・」
マリウスの言葉に、アーロンは顔を上げる。失われた時間を忘れ、今を生きる。皆がすることだが、すべてそうではない。踏みいれれば、いい結果ではない。いつもそうだ。妹もオルフェウスも、死んだ彼女も。次に踏み込めないのは彼女を愛しているからではない、自分の嘘に気付かせないまま死なせたことだ。
「あんたって」
エストはため息をつく。父は、その人と、オルフェウスと生きる道があっただろうし。
死んだアデルは嫌いじゃなかった、オルフェウスはバカだ。あきらめること、忘れること、受け入れることを拒んで。二人のカイザーも結局は捨てられない。すべて愛して。
「おい、どこに行く」
「ああ、少し買い物に」
手に入らなかった時間は自分たちでは出来なくて。ゴットヴァルトにはもうその時間は戻らない。だがオルフェウスも受け入れればいい、お前のせいじゃないし、変な義務も愛情も責任もいらないと。たとえばあいつが背が低いこと、やせていること、門大事なことも、すべてオルフェウスには突き刺さることだ。幸せにしなければ、お前がやる必要もない。
「可愛くて仕方ないのよ」
「・・・・黙れ」
やはり、彼は嫌いだ。
「いいですか、君には計画性がないといつになったら自覚するのですか」
うわぉ、バイト先がばれてる。
「な、何の事だか」
はぁぁぁと深く、深くため息をつかれた。いい加減、彼女作れよ、22歳だろ。
「君には聞く耳がないのは十分承知していますが、大体、貴方はいつもいつも」
「そういえば、今バイトにスィリィとかいるんですが、すごい美少女で」
ところで君とか貴方とか、何で固定しないんだろう。ついでに僕の周りは異常に美形や美少女が多いが呪いなのかな?
「・・・・わかりました、カールス、貴方には反省という概念がないことが」
何の因果か、ミカエラはスリエルの騎士団のフォボスの頼れる仲間だ。
「貴方には基本から教育しなおさないといけないようですね、ええたっぷりと」
今日からできる悪の構成員、あるいは革命の戦士。確かに僕はフォボスの弟で戦闘要員だが、どうも完全犯罪者にしたいらしい。
「予定がぎっしり詰まってまして」
「貴方がそういうときはつまりあいているんですね」
「・・・・・え、うん、まあ疲れてはいるな」
王座に座る少女の王様に膝枕されるとか、何これ。
「寝心地はどうかしら」
手が氷のように冷たい、優しげな笑みだ。
「ええと、温かい」
撫で撫でしてくるが、バカにされてんのか。
「眠りなさい、ヒスイ」
「ヴォルフリートです」
「僕が戦闘の指揮を?」
不思議そうに見られている。セレストはすでにワイバァン隊で、アルフレートの指揮下にいた。ゴットヴァルト自身、自分がそんな役目を与えられる、そう思わない、そんな感じだ。
「ゴットヴァルト、君には戦略家の才能がある」
オルフェウス隊はオルフェウスの王宮入りを不安に抱く。副隊長は、彼らを指揮する者の、やはり思うようにイシュタルと戦うことはできない。
侯爵家は、バカでかい。カイザーがお父様と面談中、僕は大体この屋敷をうろつく。親戚も普段は予定があるので、ほぼフリーである。
まあ従者や護衛もいるが、僕の親せきの家なのか、ここでは行動同じではない。
「やあ」
なんか、背後から聞きなれた声がした。
「・・・ああ、フィリップ様か」
「挨拶はいいよ、いつも済ましていたら疲れるし」
年は20代前半。近く、レーヴェ家と縁戚になるらしい。
「話に聞いていたけど、君は御父君から遠ざけられているな」
「ええ、まあ」
「君とアルバートは血を分けた兄弟なのに何が違うんだろうね」
貴族って家族好きだよね、しかし。
「さぁ、僕にお父様の考えわからないので」
「・・・君はさっぱりしているけど、寂しいね」
「すごいだろう、もうあの女の子の頭の中はめちゃくちゃだ」
エデンの研究者がヴァガットにいう。
「それでどのくらい、異界とつないでいるんだい」
精神崩壊だけならいいが。
「人はもろい、特に精神面、他者とのつながりで簡単に瓦解する、君の姉のように」
「隣のあれは平気そうだが」
「・・・ああ、救世主様だからね」
ここに来るまでどれだけパンドラで試したのか。
心を怪物は折られていた。
。炎が上がる。
「まさか、僕は昔パンドラが大嫌いだったさ」
それこそ、当主としての教育、当然のように忌み嫌う両親や周囲に影響され、パンドラを絶滅する価値観を持っていた。
「なら、何で」
オリバーは顔を上げる。
「まあ、支えていたものが勝ちないって壊れたんだろうな」
貴族主義、権威主義、正しい道を信じる優等生。
「エルフも当然人間と思わなかったし」
エレクも当然、捨てられて当然と思っていた。
「―何かきっかけが?」
「貴方が親パンドラ派になったのは、一族に絶望したからですか」
リリはセアドアに問いかける。
ねじが抜けた、というか、フィリップの言う通り、まじめで反パンドラで頑固でいかにも育ちがよく、冷めた表情の人形のような坊ちゃんだった。
「ああ、そんなことか」
家を捨てた、と聞いている。ワイバァン隊の宿舎で生活し、コウモリとなり。
「確かにナイチンゲール家は腐っていましたがまだやりなおせるはずです」
エルフの自分がいうのも何だが。
「全て終わったことだよ、おれには必要ないんだ」
「でも両親は会いたがっています、お兄様だって、血のつながった家族でしょう」
「俺の家族はコウモリだよ、血じゃない」
「・・・ですが何も恋人まで私たち側にしなくても」
アルヴィン・スパロウ。
それが最終試験での、ハルトヴィヒの試合の相手。才能、属性、能力的にみれば、主義も似ている、彼らを組ませることも考えただろう。実際、彼らは身長、雰囲気、人生もどこか似通っていた。
だが、ハルトヴィヒは問題児でありながら人を引き寄せ、アルヴィンは己を貫く、だがそれは銀の十字架としての駒としては欠点でもある。
「もうよい」
上級司祭、権力が誇る公爵家、王宮騎士達(ゴッド・ナイト)は。
「両者を同時合格とする」
「そうだね、たいていの女性はパンドラだと分かった瞬間、選択を強いられる」
「でもよぉ、何であきらめられるんだよ」
「君は男だから言えるのさ、親子愛?博愛?そんなものは彼女たちの立場から言えばない、大好きな人との子がそれだとは、彼らが自分の子供なんて耐えられるはずがない、受け入れた場合は過剰に周囲から保護しようとする、だが結果は同じ、悲惨な結末かあるいは」
「何だよ」
「パンドラにはマザコンがいない、だから家族愛は同族や兄弟に向けられる」
「君がリリーシャちゃんに実の親捜させるのはいいが、母親だけはあきらめさせろ」
体中が熱い鉛でものみこんだようだ。暑い、暑い。
「う・・・あぁ・・・っ」
腹部から熱い熱が痛みが襲う。
「・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・あ」
目をあけると、見慣れた少女の顔がある。
「なんで、君なの」
だが少女には予想通りなんだろう。
「つれないわね」
冷えた手が片手を覆う。
「君がいるということは僕は死ぬのか」
柔らかい感触、白い肌が眼前に迫る。
「大丈夫、お前は助かったのよ、ヒスイ」
彼女が抱いていた、彼が受けたおもみはまだ半分も。
「ローゼ、眠りたい」
「いいわよ」
少女が顔を近づける。
「おかえり・・・、女王陛下・・・」
「・・・時臣、君はまるで純朴な乙女のようだね」
「ディアボロ・・・」
夜の闇に包まれた静寂な街、リ―ザには意味のないものなのだろう。名門ディアボロ家の人間とされているが、実際はどうなのだろうか。
「世界がまるできれいなおとぎ話のように君には見えているのだろう」
アリスリーゼは祖国といえる国を知らない。何でも自分は一座で、踊り子の娘らしい。けれど、7歳、船の上で、血の海で意識が戻り、稲穂のような金髪を、大きな青い瞳を虚空に向けていた。
魔獣。パンドラと呼べるもののなれの果て。
「・・・あ」
クルーエルエッグ達が血の祝宴をあげる。
「こんなのはオルフェウス兄さんに死ねと言っていると同じじゃない」
アンジェが叫ぶ。
イシュタルの前線における、総司令官、新たなアテナの剣の支配権と指揮権。
「意思を示せ」
「・・・・了解です、国王陛下」
オルフェウスは深々と頭を下げ、軍の正装に身を包む。
「・・・・あなた」
「すまないな、生まれつきま何弱い体質なんだ」
聞き覚えのある声。カツン、と音が鳴り響く。
「白の第一騎士、リーゼロッテ・オーウェン、ただ今、参上しました」
ラフォール隊では、ブルー・レジ―ナか、アーデルハイトにつこうという流れや空気ができていた。
「ルードヴィッヒ・・・」
「ウルリヒ、気にするな」
「お前は何をしている」
「・・・・・・おう」
「あんな騒ぎ起こして自分の感情ぶつけて、楽しいか?」
後ろにいるのはシエラか。
「そんなつもりはねえよ」
はぁぁぁと深くため息をつく。
「何だよ」
「ブラン・レジ―ナの次はあの女か、うらやましいな、俺には到底できない、実に楽そうでうらやましいよ」
「友達でしょう、そんな言い方」
「はは、このヒーローもどきのマゾととか、お前でも冗談を言うんだな、笑えないが」
「そんなつもりはないわ」
「そうだろうな、お前はそういう女だろうよ、悪いが隊に戻っておいてくれ」
「あなたは」
「少し、こいつに用がある、いつも迷惑をかけてすまないな、・・・なんだその顔は」
「ヴァイツェン」
ディヴィドの目の前で、少女のライトブラウンの髪がキツネ耳と見事な金と白の巨大な翼に変わる。
「ごめん、ディヴィド・・・」
他の子供たちも驚いた表情で彼女の髪が淡い桃色と白になっていくのを見ていた。
「・・・・カイザー」
迎えの中に金の髪の少年がいた。
「メシア様、早く、早くそのものを」
「異界にお送りください」
ディヴィドの白い頬に赤みが差す。
「彼女はなにも悪くないっ」
でもカイザーは彼女を正しい法の下で、裁かなければいけない。
「破壊の魔女に協力するなんて」
「・・・・どうだろうな、それ以外は考えたことない」
エレナは確かにエレクの妹のようだ。
「ああ、もう」
「?」
いつも表評しているくせに、大事な時はいつも。馬鹿にしているが、エレクはただ自分とは生き方が違う。ブレイヴだからと嫌われ、距離を取られている。
その二人の横顔はアルヴィンの知る誰かによく似ていた。
・・・学園の中は平和だな。
光の騎士団本部は第一区の城のような建物だ。今日も多くの関係者、騎士が集まっている。扱いは銀の十字架に比べれば、王宮騎士、アーク隊、光の騎士団、白梟の騎士団となる。元いた部隊は再編され、学校と騎士団を往復し、退屈で平和な日々が続いている。自分が遊撃部隊から追い出されたのは自分自身だ。
・・・イフリート隊の方が合うと思う。お飾りの騎士団、臣民を安心させるための騎士団は特権階級に染まっているようで、アーデルハイトの傘下だ。
「君は何者なんだ」
グレンは、不自然な光景の中、カイザーに銃口を向ける。
「この悲劇はお前が起こしたものなのか」
「あんたが人のいいフレッドを言いくるめて騎士団やエリックと関わらせないようしたんでしょ、卑怯者」
近接戦のプロか、ええ、あの細身な体のどこにこんな力があるんだ。
「そう言われましても、誤解、君誤解しているよ」
「まだごまかすか」
えっ、何でいきなり、法術や攻撃魔法?
「私は絶対負けないんだから」
「ちょ、ちょっ、ここ人が」
「黙れ悪党」
光熱波が一気に放たれる。
「ウソでしょ―」
「お兄様、わかって」
雪の中で踊る少年。
「わたくしには必要なの」
頭の悪い歌だ。
「なぜだ、お前を必要としているものは」
アンネリーゼは、ほほ笑む。
「彼を失ったら、わたくしは…、もう行きますわ」
「あんなのはごまかしだ、虚偽だ」
ダヴィデ・オウルはやたらと本物か偽物化を拘る。
彼の一連の学校内でのトラブル解決法、何というか学園内の探偵のような場所になっている。あるいは便利や。関わりたくないな、と思うので、距離を作ったのだが。
ゾフィー、一人の天才が園芸部に入った。
彼の行動は矛盾している。
「錬金術師が作ったおもちゃだろう」
「へ、へぇ」
なぜ僕はここにいるのか、よこでたばこを吸う金髪妖精がいるが。
「行くぞ」
「お前を苦しめるだけだぞ」
エレクは厳しい目でゴットヴァルトを見た後、
「また来る」
「そう」
そのクールな横顔は確かに異母兄のオルグと酷似していた。
兄は言う、愚かなイタチごっこだと、どうしようもなく、悲劇は繰り返されている。ヴォルフリートは言う、優しい明日を手に入れたいと。アルバートは言う、人は変わると。
パンドラは言う、被害者だと。復讐する権利はあると。アガットは言う、お前に志や理想はあるのか。
アルヴィンは言う、お前に守るものなんてあるのか。
あの男は言う、お前が助けるものは天使でも英雄でもない。アリスとヴォルフリートは。強大すぎる力は人は恐れる。
アーデルハイトの奪われた過去が間違いだというのなら、そいつはおそらく。
ーお兄様。
どこも似てなんかいないのに。ヒーローはだれがすくうのだろう。
「苦いなぁ」
病院の中庭で紙飛行機を空に浮かせていた時、クリスタル・クレインがいた。
でもにらんだ後、立ち去る。
「?」
まあ、いい、そう思い、ベンチで座っていると、ダヴィデがやってきた。
「・・・・・・今日は暑いな」
「まあ、そうだな」
「お前は間違っているぞ」
いきなり、妙なことを言う。
「ヴォルフリート・バルト、お前がブルー・レジ―ナの代わりなんてなれるわけがない」
「・・・・誰の話かな、意味がわからないよ」
紙飛行機の別のを形を整える。だが、まぁ。
「それは君個人からのことかな、それともヴォルフリート様の命令かな」
「俺のことなんてどうでもいい、死ぬところだったんだぞ」
顔を上げる。
「・・・・君は意外と泣き虫というか、器用だな、どの立場からそんなことを?」
「・・・・俺は、怖かった」
「お前が死ぬと思ったら、ほんと、マジで怖かったんだ」
ー僕が死ぬのが?
何をこの男は必死なのか。仲間でも見つけた気なのだろうか。
「ごめん、怖い思いさせて」
「・・・・・うん」
いや失礼だろ、驚くなよ。
「僕も自分がああするとは思わなかったよ、もっと冷淡とかクールだと思ってたから」
「お、おお」
「それと勘違いだよ、いくら僕でも、僕は自分以外になろうと思わないよ、彼女にはだれも馴れない、僕もこう見えて男だしね」
「そうだな・・・」
「で、本音は?ブルー・レジ―ナの騎士が僕を陥落して、何の得があるのかな」
「お前、性格実は悪いよな、ひねくれ者というか」
「もうローゼンバルツァーにかかわる気はないよ、アーディアディトはよく役に立ったし」
「・・・・そうかよ」
「だから、君が支えてやれよ、彼女馬鹿だから」
「お前、実はすごい馬鹿なんじゃねえの」
「?」
「いくら帝国に貢献しても、お前の両親とか惨劇で死んだ奴帰ってこないし」
「僕はいつでも僕のために生きているだけだよ」
「あ、すみません」
道具やでハルトヴィヒは亜麻色の女性と出会う。かなり多い荷物だ。
「どうぞ」
周囲の住人か。
「気の毒な人、家族を主義者に殺されたそうよ」
「弟だっけ、でもあの人、弟いたっけ」
「彼氏じゃない、あまり似ていない感じだったし」
「君は珍しいだけだよ、ダヴィデ・オウル、そんなのすぐに通り過ぎるものだよ」
「お前・・・っ」
「だから、友達ごっこはほかにしてくれないかな、いらないんだ君は」
「イリス様は優しい方ですわね」
「ベアトリス様?ありがとうございます」
けれどベアトリスは真剣な表情でーー。
「でも、とても残酷な人ね」
アイリスは大きく目を見開かせる。
「目の前に現れているものが常に真実とは限りませんのに」
「・・・・ミーティア」
ゴドウィンは家を出て以来、鏡写しのような女版の自分、けれど硬質な宝石のような女性をまたこの目で見るとは思わなかった。
「お久しぶりです、お兄様」
ゴドウィンは膝を折り、頭を下げる。
「お久しぶりです、エール・サテリット閣下」
「…よく帰還しました、このたびの活躍お見事です」
「彼はくるっている、だからヴィンセント、どうか彼を救うために」
炎が揺れている。
「・・・・何を証拠にそんなことを?」
「そんな、ヘンリーや他の彼が起こした悪事を貴方も知っただろう」
だがヴィンセントは表情を変えない。
「・・・ああ、誘拐事件を暴いたんですね、だとしても、彼はあなたの敵になるほどの人間ではないでしょう、次期子爵のわが主」
「秘密はいずれ気付かれてしまう」
ヴィンセントは涼やかな目で。
「彼は人間ですよ、何の変哲もなく、善悪もあり、未来を少し悪いほうに考えていませんか?」
「貴方は何で彼をかばうんだ」
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 動物園&水族館大好き!
- 千葉市動物公園 風太くんお散歩タイ…
- (2025-11-20 00:00:09)
-
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- LEGO ‐ Star Wars ‐ | レゴブロック…
- (2025-11-15 21:55:46)
-
© Rakuten Group, Inc.