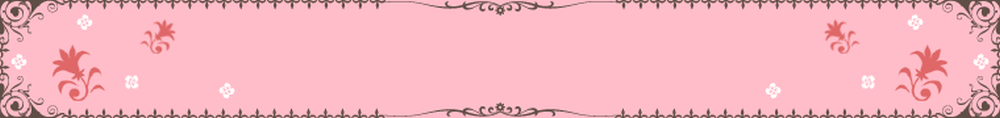第27章
1
故郷のエーヴィンを平定させるために。人々の平和のために。そのためにアリスリーゼは、皇帝陛下に使え、騎士たちの最高峰エトワールまで16歳でたどり着いたのだ。
・・・アニス、貴方を救い出すために。
それに幼馴染との約束のために。強敵シュテファンとの戦いを勝利するために。
ワイバァン隊、フォボスの騎士団、アズゥ・カルヴァリーレに勝つために。
ダヴェーリャト帝国の戦争は今は帝国を押しているが、将来はどうなるかわからない。
「陛下、自分を最前線に送ってください」
王座がざわついた。
「しかし、お前は余のそばに」
「この戦争を早く終結しなければ、我らに未来はありません。我が国に勝利を」
「彼らを切ろう」
「了解した」
胸の奥が痛んだ。結果がついてこなければ、すべてのことに意味がない。
「今日まで俺たちのために戦ってくれた人たちだ」
「足かせになるなら意味がない」
ー君はいつもこんな思いを抱いていたのか、姉さん。
「そんな冷たすぎる」
「勝利のためだ」
戦況は悪くなる一方だ、救援は来ない。飛び散る銃弾、襲いかかるイシュタルの軍達。
脳裏に姉の笑顔が浮かぶ。笑顔の裏でこんな思いを姉は抱いていたのか。どんな作戦も弱い帝国では被害者を生むしかない。
≪強き風よ、すべての目の前の敵を投げ払え≫
≪フォルス・リベルテ≫
アリシアとの合体技を繰り出し、イシュタルの軍勢を追い払う。
油断が生んだ犠牲を忘れようとは思わない。
いつも浮かぶは、苦楽を共にした多くのパンドラたちの笑顔と殺すのを目的とした作戦とはいえない作戦。
ブラウン・ローズとして、仲間を失うのは慣れっこだがそれでも指揮能力が高くても、仲間との連携が高くても、失う時は失うのだ。
「もういい、退陣しろ」
「しかし、あと少しで」
「引くのだ」
魔術式通信から指揮官から命令が届き、ヴォルフリートもこぶしをぎゅっと握る。
「勝つためにはなんでもしていいのかよ」
「結果が伴わなければ意味がないよ、何言ってんの」
「そいつの好きにさせろ」
先頭に立つオルフェウスがアガットに命令をする。
「しかし」
パンドラの多くが一瞬でオズワルドの魔法部隊にやられた音が届いた。
「お悔やみを」
スカートのすそをぎゅっと握る。
「いつも剣ごときに丁寧な対応ありがとうございます」
冷たい対応ではない、義務的な反応、アウレリアヴィーナは魔術式通信を通して、パンドラたち、戦場の狩人に対して戸惑う。
「死傷者には」
「剣が数本壊れただけです」
それでも、あの日のようにアンネローゼはほほ笑んでいる。
「・・・・アルバート、来ていたのね」
アルヴィンが倒れているのを見て、事態のすべてを読んだらしい。
「やめるんだ、アンネローゼ」
だが何もわかりはしない。アンネローゼの狙いなどわかりはしない。
「何を」
少女の空気が変わる。
「イシュタルと手を組んで、異界の力を手に入れる気か」
ヴォルフリートが立ちふさがる。
「・・・・・お前があいつをおかしくしたのか」
「どの子かしら?」
「ゴットヴァルトだ、あいつがおかしいのはお前が」
その先は言っていいのだろうか。
「・・・・惑わされたのね、あの子に」
少女は表情を少し無くす。
「アルバートから聞いた、お前が幾人の人間を実験体にして、錬金術師たちや悪い奴と」
「証拠もないのに、アルバートがあなたに真実を言うと限らないのに、それで悪人なの?」
肩が震えた。
「吸血鬼だから?私は無意味な殺戮はしないわ」
「信じられるか、あいつは今も苦しんで」
「ねえ、お前たちがあの子を無能扱いするのはなぜ?」
顔を上げる。
「いつもそう、みんなあの子がダメな子と決めつけ、ワルサするのもあの子だと決めつけるの、それとも頭が悪いダメな子の方があなたに都合いいのかしら、あなたのアリスのように」
「お前・・・ッ」
「でも、いいわ、理由がないとお前は動けないのでしょう、犯罪を行うのは怪物の特権ではないわ、魔女ですらない、お前たち人間は全員善良かしら」
「無理やり兵士にさせて、悪い奴と組んで」
「たかが駒の一つよ、ベルンホルトが作り出したたくさんのシリーズの一体でしかない、臣下たちはわざわざそんなこと報告もしない、私が彼が兵士になったのを知ったのはあの女に聞かされた後よ」
「誰だよ」
「そもそも奇妙でしょう、ヴォルフリートがクラウド家にいたのなら、あの子が出てくる前にアリスが来た時点で引き取り、あのこはサイトでも放り込むだけ」
「助けようとしたんだ、人間以外にさせないために」
「私を犯人扱いネ、お前はいつもそうなのでしょうね、言い訳して、先延ばしにして、私が無理やり自分の駒を剣に入れることはないわ、私はルールは守る女なの」
「じゃあ、あいつがお前を殺そうとしたとかだましたとか見捨てたとかは」
「あの子は確かに自己中ではあるわ、勘違いさんで、でもねあの子が動く理由は昔から決まっている、騙すのも見捨てるのも自分のため、生きるためよ、そして家族のためよ」
「は?」
「さぁ、続けましょう、いい加減私のものの周りにお前みたいな中途半端がうろつくのは嫌だもの」
「誰がお前のものだ、無理やりだろ」
「なれなれしく、あの子の名前を言わないで頂戴、私の彼に関わろうなんて図々しいわ、振られたら諦めるのが男というものよ、嫉妬しちゃって、お前があの子に相手されるわけないでしょう」
「・・・ホラー?」
スフィアは奇妙なことをゴットヴァルトに青ざめて言われたので、意外だがすぐに芽生えた疑念は打ち消した。きっと大事に大事に、それこそ温室育ちではないが、のんびりしているし、世間知らずなんだろう。
「私、何かおかしいこと言った?」
「・・・いえ、僕の思い違いです」
細い腕を抑えている。震えている、そうね、クラスのだれかが行方不明で不安におびえていることは、彼には不安で怖いのだ。時折、常識外なことをするが、基本は心優しく、臆病で。くすりと笑う。
「何でしょうか」
「貴方って、本当優しいのね、パンドラまで気遣って」
「ないですよ、僕はいつでも自分以外はどうでもいい、それだけの人間ですし」
男だもの、背が低くても、やっぱり強く見せたいのね。
「へえ、いとこがハトコが」
悪魔崇拝しゃ、まあシュテファンは便利そうな奴、オルフェウスは強気だがすぐにわかる。あいつは弱い。特に心が。
母親を死なせた、自分が力がないから。あの顔でマザコンか。いや色男だ。男前だ。15歳、その時はただのクラスメイトだ。失ったもの、かなわない者への執着、依存。
まあ侯爵家では、魔術師の家ではかなわない。それはじれったい、つらい、苦しい。
誘拐された貴族の子、いわくつきの。
「・・・・・・・・・・・・・・・キモ」
要するに甘えん坊だ、強い魔力があろうと、傲慢不遜は繊細な心を隠すための、バカな女の子が好きそうだ。そんなバカなら罪悪感は覚えないだろう。
噴水の前で、ゴットヴァルトは待ち人をまっていた。背後から、赤いバラの花びらが舞い散る。振り返ると、エクリプスが女神の像の上にいた。
「よう、久しぶりだな」
「・・・・・ええと、僕ですかね」
仮面越しに、シルクハットの男は僕を見ていた。マントが風で揺れている。現実的じゃない光景だ。エクリプスは地面に降り立つと僕のもとに来た。
「ずいぶん面倒事に巻き込まれているんだな」
「貴方こそずいぶん凝った靴をはいてますね、なんですか、身長をごまかしていたんです」
「大したことじゃない、どうして消えたんだ?」
少年の声に切り替わる。
カイザーは、おれより強い、本気にならない理由は。多くのパンドラ、帝国の敵から友達、家族、姉さんを守りたい。皆が言うほど、おれは立派じゃない。大切なもの、目指すべきもの。本物の天才はノア、オルフェウス、近くを見ただけでも多くいる。スヴェンと戦い合った時、テロリストやあくどい魔術組織、彼らと対する時、気づかされる。
・…だが、おれの剣では、親友を助けられない。
天魔おちだから、家から追い出され、双子の兄に立場を奪われ。あの惨劇、事件が起きなければ。何度も思う。
「帰るか」
感情で考えるな、冷静に。それが戦士で軍人だ。任務をこなし、剣や銃、魔法を扱えても、何をすべきか。自分は何をすべきか。兄たちならこんなことで立ち止まらない。今は変えられない、なら、外からカイザーを支えるべきだ。
聞き慣れてしまった、のびやかな、微妙に外れた優しい声。相変わらず護衛にガードされている。
「今、暇か」
理不尽だ、不条理だ、打が答えないだろう。打ちとけ合い、自分の手の内にする。苦手だ。アルフレートは苦手だ。
「ああ、僕か」
「剣の相手を頼む」
たとえ、カイザーがなくても、この少年と自分がわかりあうのは無理だ。
アルフレートには、彼の価値観、主義、性格が自分に合わない。だが彼が自分の不幸を種族を嘆くことはないだろう。マイペースで自分勝手でわけがわからない、子供で、冷酷で情が薄くて、一つも理解できない。あの男とこいつが親子だというのはどうもうまく受け入れられない、まあ当然ではある。
「面倒だしやだ」
なんとも自分本位だが、彼があんな惨劇の犯人ということはないだろう、人間関係をまるでわかっていないのだから、バカではないが、裏から誰かを陥れるようには見えない。無邪気なのか、違うのか。嫌われているというより、期待されていないのだ、別に受け入れられたいわけではないが。こいつからすれば納得できないのだろう。
「少しだけだ」
ほぼ今まで放置しておいて、都合悪くなったから呼び出すなんてのはずいぶんとバカにされた。まあ、権威がほしいだけの演技かもしれないが。
「・・・・仕方ないな」
イライラする。わざとか、普通か。
アルヴィンはダヴィデと別に険悪になりたいわけではない。ただアリスの騎士として誰かが厳しい役、嫌われ役が必要で。
「ダヴィデが役に立つかしら」
「うるせえよ、男女」
諦観、拒絶感、いや拒んではいない。主義のちがいだ。ぼっち同士であるが、どうにも生き方、振る舞いが違う。オウル家は魔術師にしては愛にあふれた家庭、いい師弟関係だという。踏み込むことはダヴィデの人生に踏み込むことだが、ダヴィデは許さない。
あらそいは苦手だ。どんな争いもだ。
繰り返してはならない。
「でも、君はアリスもブレアもシエラも助けるだろ」
フロイデにずいぶん高い評価だが、まさかそこまで自分を好人物と思わない。
「関係ねえよ、俺は俺がしたいことするだけだ」
あまり笑わないがいいやつだ、ヴォルフリートも、サファイヤエルも。だけど仲間だの選ばれただの、同じ時間をすごすが、やはり彼らと自分は違うのだ。
皆仲よし自体が、原因なのに。自分が選んだ居場所、そうではない居心地いい場所。
敵を倒す、言葉は簡単だ。けれど、現実だ。
「すいません、アルバート様」
「いいんだ、これくらい」
くすくすと笑う。頬をなでおろした。
「あ」
アルバートの視界の上に、バルコニーにスケッチブックをもったアルバートに瓜二つのそれがいた。コウモリの制服を着たままだ。本当に外見に頓着しないらしい。
・・・・・・変な奴だ。
「・・・・やはり、女性に無理やり、血を吸うのは君も罪悪感あるんだよな」
なんか高貴な騎士様が変なこと聞いてきた。別にセアドアにパンドラの個体から血をもらうからいいのにな。
「君は優しいから本当は罪の意識感じてきただろう」
生まれてからずっとなんて、とかいうが、僕は君の中の罪の意識が気になるな。
「辛いことなんだよな、血を飲むなんて、純粋な君が見知らぬ女性の首から血を吸うなんて」
「・・・・ええと、怖くないのですか」
すると泣きそうな表情だ。
「僕程度では君の辛さはわからない、一人で耐えてきたなんて、相談もできないだろうし、君はつらいよな」
肩を揺らされるが、まあ友情のシーン何だろうが。
「考えすぎですよ、血なんて馴れれば苦くなくなるし、というか人間の血だけじゃないし」
まあパンドラは亜人だから人間なのだろうが。まあ、引いてもらえばいいか。こいつなんか怖いし、よくわからないが怖いし。
「いやあ、戦争とか闘争とか超好きだし、引きこもれる種族でラッキーだし」
それでなくても、僕は君とは合わないぞ、敵対してくれないかな、危機感感じるし。
「・・・・・・無理しなくていい、神はなんてことをするんだ」
「・・・・・・・・・・・・」
本当だよ、何でこんな面倒なの止めないんだよ。
「・・・はぁ、気高い精神ね」
フレッドは暇なのか、わざわざ時間を作るのか、知らないが、宗教を布教しに来たらしい。きょろきょろする。
「セアドアは?」
「ああ、夕飯取りに行ってる」
もとい、パンドラの女性の血を取りに行っている。
「君はいつもあれだけじゃないんだろう、普通に食事も」
鳥の空揚げが刺さった棒を見て。
「・・・悪い、僕の人生でこうして吸血鬼・・・君と話す機会があると思わなくて、考えなしだった、ごめん」
「普通ないでしょうよ」
「それで、なんだけど、君はやはり神を信じるべきだと思う」
女神教会やら何やら、騎士や戦士が崇拝する神やら、どんな生まれだろうとか。
「神の愛を信じるだけでも、精神が安定して、考え方も変わると思うし」
「そんなに日頃の僕の言動や行動がいやなら、関わりたてば?」
「そんなの生きていけないから無理だね」
「いやアニエスという希望がいるじゃないか」
「それは僕の意思じゃない、彼女には僕では無理だよ、相手にならない」
まあ高根の花だが確かに。
「ああ、好きな女の子いるのか」
「君はもう少し考えられないのかな」
にらまれたが、無神経か?
「でも無理ですよ、十字架とか聖水とか触れないし、そもそも教会に入れないし」
「?吸血鬼だからか?」
「いや、入口付近はいいんだけど中に入ると意識失うんだ、教会には結界があるから近づけば弾き返されるし、前に侵入しようとしたけど足が吹き飛んだし」
「そうか、あまりにも神々しすぎると神も嫉妬するのか」
「それ、誰の話?」
「・・・・前と雰囲気違うのね」
「ああ、まあ、シリアスドないからなぁ、俺は」
二コルは困ったように、アリスをみる。
「・・・・・セシリア、理由を聞いても問題ないかしら」
「君には関係ないだろ」
フロイデからすれば、イシュタルとの戦争が持続中とは考えたこともない。
「なんだ」
サアラは、なぜだかブルー・レジ―ナとの再会以来、不機嫌だ。パンドラにもランクアップ、進化するシステムがある。ブレイクエッグ以外はそうらしい。なので彼女はマリー・アンジェに加護を受け、試練に挑戦中だ。
「いいえ、何も」
まあ、わからないではない。パーティーを色々組んできたとはいえ、自分が俺の一番の仲間、従者だと思っていた。リリーシャと関わるようになり、多少先輩の自覚もあるが。
「なんですか」
「案外、子供っぽいんだな」
「・・・・・・・そんな・・・じゃあ」
「ああ、カイザー、兄さん達は・・・」
炎が最後の命を現すように、ヒステリックに燃えている。
焼け落ちたアルフレートの家族が住んでいた屋敷でアルヴィンは死体をいくつか見る。「違う、こんなはずじゃない・・・」
「俺ははめられたんだ」
「ルベンティ―ナは最後に家の名誉を守ったんだな」
「あの人はそういう人だから」
「これがオグル属の禁術・・・・」
「大丈夫か、カイザー」
悪魔は奇麗な姿だという。カドナは、城の中で戦争を憂い、壊れていくアルバートの騎士夫人の姿に心を痛めていた。だが多くが、戦争は終わる。同時にアテナの剣は解体され、イシュタルを支配下に置くことを夢に見ていた。
予言は成就すれば、楽園が、この世の天国がある。
緑の貴衣の永久締結。
エレオノ―ルと起こした偉大な奇跡。
≪ナイトメアソード≫
ズガァァァン、ドォォン。鋭い剣筋だ。
「しつこい」
「俺だアリスリーゼ」
「黙れ」
アリスリーゼは、サイドテールを黒いリボンでゆって、腰まで伸びた結われた長い髪を揺らし、ブルー・メシアと剣を交わしあう。
「どうして・・・」
愛らしく少女らしい顔だが、凛然とした大人の女性を思わせる女神じみた美貌の鎧と軍服が混ざった制服。
オルグはりそうにつぶされることはない。だけどアルベルトはそんなオルグを外に連れ出した。けれどダダはコネない。世界になじめないから、自分の時間だけ生きていればなんて、不健康だ。
それでもだが、グループが作れないヴィクターにアルベルトは手を差し伸べる。あんな外れ者を。カイザーとは遊んだが、同盟が終わればライバルだ。
「君は清らかだから」
「そうか」
「でもみんながみんな問題に抵抗して解決できる人ばかりじゃないんだ」
いちいち、覚えるのも面倒で、でも死にとらわれるのもばかばかしく、モンスターたちが急に人間らしくなるのもどうでもよい。妖精属の化け物が笑いかける。
美しい、幻想的な少女だ。
「・・・・じゃあ、僕が助けていったら、助けにきてくれる」
あまり情報源としては彼らは役に立たないし、ご機嫌取りも辞めたい。
吸血鬼の女王も、その地のことさえなければ。
「え、ええ」
あまりにうれしそうで、それが前の僕みたいで。
「うれしい、君は最高の友達だね」
第18皇女ウイエリーデにも当然大貴族がついており、彼女は熱心ね二ケの肖像の信者であり、市民もパンドラも自分の民だという考えを持つ一方、貴族主義で血統主義、ゆえにヴァデ―レが自分が提案した部隊を希望したことを不思議に思う。
「なぜ、野蛮な戦場に行くのだ」
容姿は正直美しくない。年はヴァデ―レよりも一つ上。それなりの貴族と恋に落ちるなんて等に諦めている。華奢ではない。
「謁見を許されると思いませんでした、ですが殿下、私は今のバラバラな状況ではイツ帝国に牙を向けられるか」
「ふむ、成績、能力、マナも問題はないが後方ではよくないか、わざわざ危険な最前線を希望するとは、余は理解できぬが、いっておくが余は軍事や世俗は詳しくないただの貴族の小娘、その余を皇帝に担ぐものも特に名門貴族でもない、正直言えば無駄死だ」
「・・・どうか、私に姫殿下の剣となる道を」
「まあ、第一皇子殿下の兄上も優秀なものは求めているが、確認だが、お前は将来を誓った娘はいるのか?軍人となれば、恋愛も家庭も作れないが。庶民は自由に恋というものをする生き物だと聞いたぞ、パンドラと寝床を共にする時もある」
「それなら大丈夫です、自分は今まで色恋とは無関係でいましたから」
「・・・・・・皇族は周りに臣下か、ライバルしかいないのだ、諦めよ」
なぜだろう、街の女子生徒と同じ反応に見えるのは。
「まあ余も皇女でなければ聖女教に入ったであろう、お前も気にしないがよい、大丈夫、まだ18歳ではないか、それによく見れば、その、うん、個性的な顔で男前よ、すぐに相手もお前に目につけるであろう」
ハーモニーはピンチだった。軍国の天魔落ちの精鋭部隊の実戦用の攻撃魔法を逃げながら浴びていたのだから。
小さかろうと、国家間だろうと、争いは平和の陰にある。イグナスは自分が世間知らずだと思わないが、温室育ちだということは感じていた。例えば、帝国は旅に出ることはできるし、何でもなれるし、何でも手に入る。穏やかで誰にも温かい性格もその環境だからだろう。彼の父がヴァーヌスの方で戦死したと聞いたのは、12歳の時。ヴァーヌスの領主の一人、ジャーノ。帝国に反逆し、異端の魔術に手を染めた異界に落ちた男。
「ティアナ姉さん」
「いいのよ、お前は知らなくて」
「おもしれぇ、また大きな戦争ができそうじゃねえか」
黒獅子、・・・・よりによって、この男か。
暴虐の覇王、居剣と数千の兵士を持つものがレッド・カルヴァエ―レ。
「何だ、色男、文句があるなら言えよ」
「メルキュール」
アンソニーはいつもながら、フレイアを招くクロ―ディアが理解できない。従順な従者、年上の友人。ラフォールはにこにこと食卓を囲っている。アンソニーをにこにことみていた。
「リヒト、悪いな」
「いいよ、別に」
「何、もう交代?」
「いや・・・」
アルフレートが隣に座る。
「ふぅん」
双眼鏡見ても変わりなしか。
「これからまた多く死ぬだろうな」
「だろうね」
「朝が来たら始まるのか」
「うん」
「ヴォルフリート・バルト」
「うん?」
「俺はお前と同じ従士で仲間だ、背中を借りるぞ」
「何をいまさら」
「・・・・どれくらい経験したら、死に馴れるんだ」
「ないですよ、ただ誰かを数えなくなるだけ、簡単に馴れます」
「そんなにか」
「いやになるくらいに」
「おかしくならないのか、普通なら」
「弱い奴は死ぬ、生きるものが正義です、当たり前のことでしょうよ」
「ああ、だが俺は生きて帰る、あいつらも」
「でしょうね」
「お前もだ、お前の日常はここじゃない」
ゴットヴァルトが振り返る。
「は?」
ローリナがなぜ、ここに・・・。
「ああ、いいんですのよ、貴方はここで死ぬんですから」
「お前はうつろね、ヴォルフリート」
エルフリーデはにらむが、アンネローゼは相手にしない。
「本物が何一つとしてない」
アルヴィンは、人並み外れた美貌、だが背筋の奥まで凍りつくような寒気を感じていた。
「シエル、シェーリぃ、来なさい」
「・・・・なんだ、それは」
「にわかには信じたかった、だがお前の祖父の正体は・・・・ライトニング側のスパイだった」
「馬鹿な、ありえない」
「お前は、アリスとともに帝国の敵と戦い、ある日を境にすべて忘れた」
「だが、当然だといえばそうだが、そいつらの手下は多くいて、騎士団だけでは何ともない、民衆の支えがなくなったと分かったお前の一族や王宮は、アテナの剣にあいつを差し出し、お前とアリスの代わりに兵士にして戦わせた」
「え?」
「頼む、カイザー、あいつを救ってやってほしい、今のままではあいつはきっと悪いほうに行ってしまう」
「アルフレート、お前・・・あいつに操られて」
「違う、俺は・・・ただ、これ以上あいつのあんな姿をみるのは、お前の兄だって」
「・・・・アルフレート、ダメだよ、俺にはできない」
「何でだ」
「わかるだろ、仕方ないこともあるんだ」
「仕方ない?」
「・・・・あいつは誰にも止められないんだ」
「カイザー・・・」
「あいつが勝手にしたことだ、俺は知らないし、頼んでない」
「・・・・・悪いな、わがまま言って」
「アルフレート?」
「・・・そうだな、俺がお前に期待しただけだ、お前はローゼンバルツァーなんだな」
「え?」
「正気を失ったのか」
「俺は冷静だ、すごく」
「何で、お前が俺に剣を」
「あいつは何度も何度も貴様に助けを求めた、だがお前はやっぱり見捨てるんだな」
「だから記憶が・・・・」
「そうか?本当はお前のことだ、面倒事をあいつに押し付けたかったのだろう、悪いのはあいつ、いい加減なのはあいつ、だから見殺しにしていい」
「何を言って」
「お前もあの男も、正気とは思えない、いいだろう、お前が英雄気取りならおれが否定してやる」
「アルフレート、お前」
「冷酷で卑怯者で怠惰で・・・・だが貴様のどこに誠実さや正しさがある、悪いものなら踏みつぶしていい、お前はそういうんだな、よく許されるなんて思えるな、俺はお前に失望したよ」
「・・・・お兄さん達のことで、そんなに」
「俺は、お前達姉弟の敵だ、これから未来永劫、ずっとな」
© Rakuten Group, Inc.