節分
■■■ 鬼は外!福はうち!節分特集 ■■■
節分は、季節の分かれ目の意味で、
元々は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の
それぞれの前日をさしていた。
節分が特に立春の前日をさすようになった由来は、
冬から春になる時期を一年の境とし、
現在の大晦日と同じように考えられていたためである。
立春の節分に豆をまく「豆まき」の行事は、
「追儺」と呼び、中国から伝わった風習である。
「追儺」の行事は、俗に「鬼やらい」「なやらい」
「鬼走り」「厄払い」「厄おとし」「厄神送り」と呼ばれ、
疫病などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式で、
文武天皇の慶雲3年(706)に宮中で初めて行われた。
鰯の頭を、柊の小枝に刺して戸口に挿す風習は、
近世以降行われるようになったもので、
これも魔除けのためである。
また、節分に巻き寿司を食べる風習は、
福を巻き込むという意味と、
縁を切らないという意味が込められ、
恵方(えほう)に向かって巻き寿司を丸かぶりするようになった。
節分に巻き寿司を食べる風習は、
主に関西地方で行われていたものだが、
大阪海苔問屋協同組合が道頓堀で行った
「巻き寿司のまるかぶり」の行事をマスコミが取り上げ、
それを見た全国の食品メーカーが便乗し全国へ広まっていった。
元々は「立春」「立夏」「立秋」「立冬」の
それぞれの前日をさしていた。
節分が特に立春の前日をさすようになった由来は、
冬から春になる時期を一年の境とし、
現在の大晦日と同じように考えられていたためである。
立春の節分に豆をまく「豆まき」の行事は、
「追儺」と呼び、中国から伝わった風習である。
「追儺」の行事は、俗に「鬼やらい」「なやらい」
「鬼走り」「厄払い」「厄おとし」「厄神送り」と呼ばれ、
疫病などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式で、
文武天皇の慶雲3年(706)に宮中で初めて行われた。
鰯の頭を、柊の小枝に刺して戸口に挿す風習は、
近世以降行われるようになったもので、
これも魔除けのためである。
また、節分に巻き寿司を食べる風習は、
福を巻き込むという意味と、
縁を切らないという意味が込められ、
恵方(えほう)に向かって巻き寿司を丸かぶりするようになった。
節分に巻き寿司を食べる風習は、
主に関西地方で行われていたものだが、
大阪海苔問屋協同組合が道頓堀で行った
「巻き寿司のまるかぶり」の行事をマスコミが取り上げ、
それを見た全国の食品メーカーが便乗し全国へ広まっていった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- モバイルよもやま
- [ウイルスバスター クラウド]「お…
- (2025-10-31 06:43:08)
-
-
-
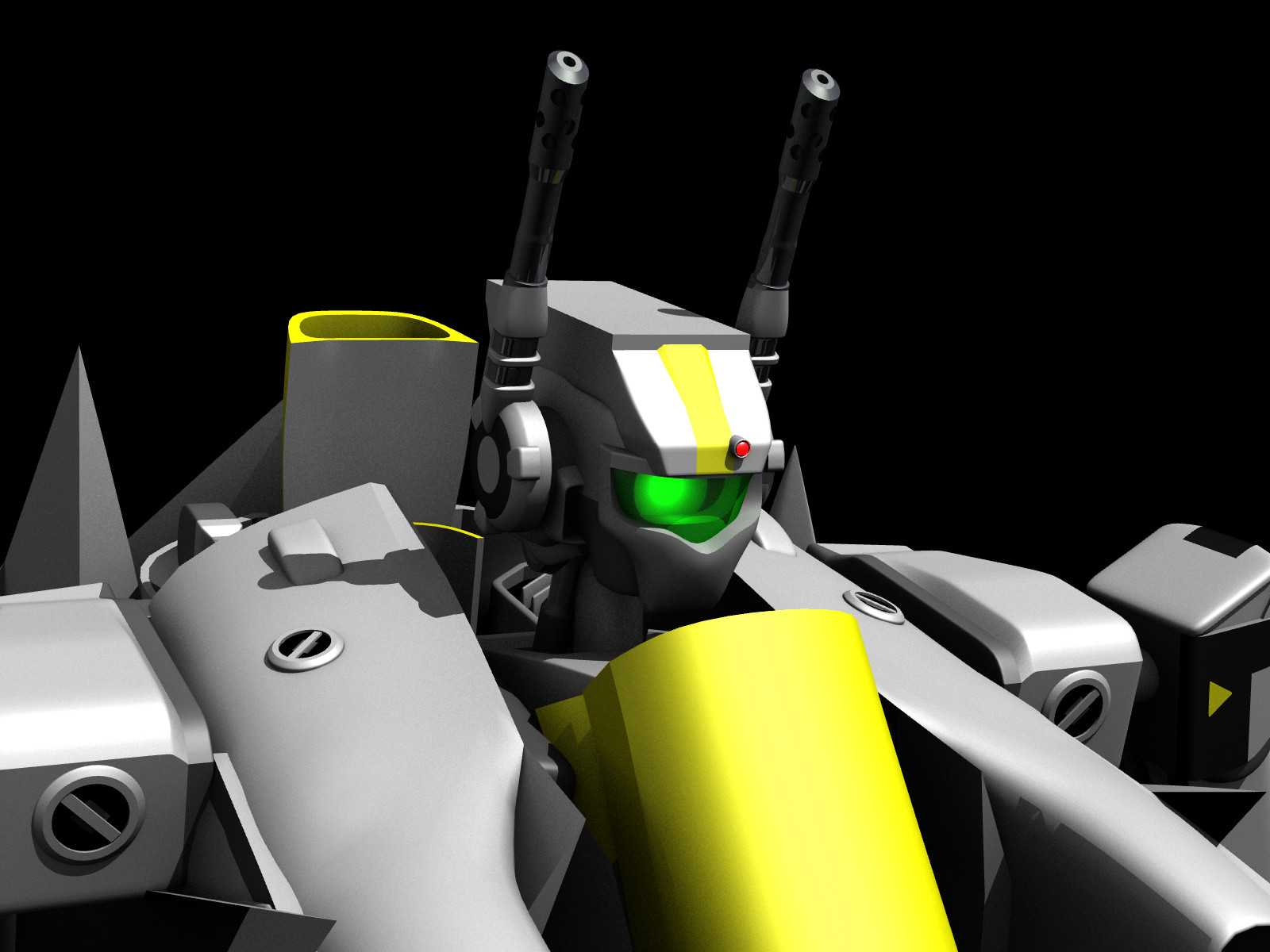
- 3DCG作品
- 続・初めての飛行機プラモ 17
- (2025-11-09 06:30:05)
-
-
-

- 楽天アフィリエイト♪
- [楽天市場] 雑誌 ・ ムック | C…
- (2025-11-13 20:45:15)
-
© Rakuten Group, Inc.







