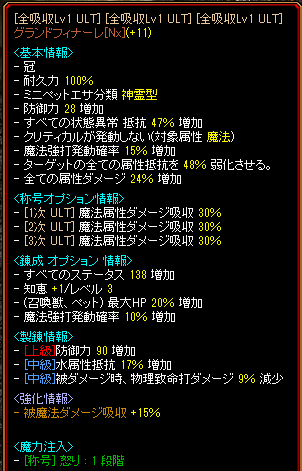眼鏡小噺
川面は柔らかな陽光を受けてきらめき、土手では子供たちが歓声をあげて走り回っている。
春学期は始まったばかりで、今日は午前授業の日だったのだが、うっかり者の僕はそれを知らずに弁当を持参してきてしまった。
折角良い天気だし、昼下がりの土手で弁当を食べようと思い立ち、少し遠回りをしてここまで来たわけだ。
「あー、やっぱり桜は散っちゃってるなぁ。」
両岸には立派な桜の木が何本も植えられているが、どれもこれも葉桜になってしまっている。
花が見れないのは少し残念だが、青々とした新緑を見るのは、これはこれで楽しい。
一際大きな桜の木の下に入り弁当を広げようとした時、土手の上から僕を呼ぶ声がした。
「メガネー!」
走りよって来たのは幼馴染の大輔だった。
浅黒い肌と人好きのする笑顔が特徴の、大きな柴犬みたいな男だ。彼の手には、ペタンコの鞄と一緒に弁当包みが提げられていた。
こいつも弁当を持ってきてしまったらしい。
「お前も朝弁当持ってたから・・・ぜってーここだと思った。」
軽く息を弾ませながらそう言うと、大輔は僕の隣に腰を下ろした。
僕の弁当を覗き込み、唐揚げいいなー、一個くれ。なんて言いながら、大輔も自分の弁当包みを解いた。
「メガネここ好きだもんな。」
メガネ、と言うのは僕のあだ名だ。由来は単純明快、いつも眼鏡をかけているからだ。風呂の時と、寝る時以外は外さない。
柔らかいフォルムをした黒いセルフレームの眼鏡で、自分で言うのもなんだが僕に良く似合っている。
「大輔だってここ好きだろ。この前見たぞ、一人で黄昏てんの。」
「バカヤロー、見てたんだったら声かけろよ。」
人懐っこく、運動神経抜群でクラスの人気者の大輔とは違い、僕はどこか色素の薄いおとなしい、クラスでも目立たない存在だった。
そんな僕と大輔は何故か小さい頃から仲が良かった。家が近いせいもあるが、それ以外にも何かある気がする。
クラスの話、先生の話、宿題の話、他愛のない話を僕と大輔は弁当を食べながら話した。
その間、僕の弁当箱から食べてもいない唐揚げが消えてた。
「おい、メガネ。あれ何だ?」
ふと、大輔が話の途中で前方を指差した。指の先に目をやると、青々した草の上にちらちらと何かが立ちのぼり、向こう側の景色が歪んで見えた。
「ああ、陽炎だよ。」
「虫か?」
「・・・・・・。」
運動は出来るが勉強はいまいちと言う、お約束を地でゆく大輔に僕は脱力した。あれがどうやったら虫の仕業に見えるのだろう。
「陽射しで熱くなった空気で光が屈折して起こるんだ。」
「ふぅん。」
自分で聞いたくせに、気の抜けた返事を大輔は返した。なんだか真面目に解説してしまった僕が馬鹿みたいじゃないか。軽い脱力感に襲われ、僕はメガネを外してレンズを拭いた。こうすると気持ちが落ち着くのだ。
「あのさ、俺思ったんだけど。」
興味は陽炎から弁当に戻ったらしい大輔が、箸に突き刺した卵焼きを振り回しながら言った。
「眼鏡とか、コンタクトを通して見える世界って、本物なのかな?」
「・・・はぁ?」
今度は僕が間抜けな声を発する番だった。大輔は少しムッとした顔で僕を見、話を続けた。
「だってさ、陽炎を通して見た景色って歪んでただろ。目で見てるのとは違うじゃん。窓だってさ、あ。曇りかー今日。なんて思って外に出ると、ガラスに色がついてただけだったりしてさ。俺は視力2.0あるからさ、眼鏡とかコンタクトとか、人工的なモン?通して見たことないから知らないけどさ。やっぱ裸眼とかとはちげくね?と思ってひゃ。」
そこまで一気にいうと大輔はばくりと卵焼きを頬張った。
湿ったような、押しつぶされたような独特の草の匂いが風に巻き上げられ、鮮明に匂った。
「ちょっとメガネ、眼鏡貸せよ。」
固まる僕の手から、大輔は眼鏡を奪い取った。
・・・考えた事もなかったが、大輔の言うことも一理ある気がする。眼鏡をとられ、膜が張ってしまったような視界を見ながら僕は思った。
そう考えると、眼鏡無しで見ていた風景なんて僕はもう思い出せなかった。かける前とかける後、何か違うトコロはあるのだろうか。
「ひゃー、景色ぐにゃぐにゃ!!すげー。」
何がそんなに楽しいのか、大輔は眼鏡をかけたり外したりしながらしきりに歓声をあげている。ぼやける大輔の横顔を見ているうちに、何でコイツと僕が仲が良いのか、解った気がした。
「おい、メガネ。何笑ってんだよ。」
「いや、別に。そっちの景色はどう?」
「てんで駄目だな。酔いそうだ。」
俺はこっちでいいや。と言いながら、僕の方に眼鏡を差し出す大輔に我慢できなくなり、僕はふきだしてしまった。
「うわ!!なんだよ?!何がおかしいんだよ?」
空は相変わらず藍玉をぶちまけたような良い天気で空には雲ひとつ見つからなかった。
僕は笑い転げ、大輔は困惑し、執拗に説明を求めている。
それでもやっぱり陽射しは柔らかく、空気は湿ったような押しつぶされたような草の鮮やかな匂いに満ちていた。
この分だと明日も、晴れるだろう。そしたら明日も大輔と昼をここに食べに来よう、と僕は思った。
© Rakuten Group, Inc.