全231件 (231件中 1-50件目)
-
【重要?】ブログ移転のお知らせ
えーと、さとーです。重要でもなんでもないかもしれませんが、このブログを移転します。半年ちょっと使ってみましたが、楽天のブログはちょっと使いづらいのでやめます。新しいブログは以下のとおりです。タイトル等はそのままです。2010年4月1日から以下のURLに移りますので、今後ともよろしくお願いいたします。(新)非電化工房 弟子入り日記http://hidenkanodeshi.v-kei.net/2009.3.31 sato
2010年03月31日
コメント(0)
-

風呂小屋テレビデビューの日
さとーです。今日が撮影当日=一番風呂の日となりました。なんとか撮影ができる程度には間に合ったところです。現在の風呂小屋はこんな感じ↓今日は休みの日だったのですが、結局、あれこれやることがあり、朝の8時くらいから風呂小屋の中の掃除やすのこ敷き、昨日修繕した水道の水漏れ箇所の確認などをしていたところ、別の水道の配管で水漏れ発見!さらには昨日急造した風呂釜用の栓を一度外してもう一度つけたところ、ここも水漏れ発見!そういうわけで、午前中はまるまるそうしたことの対処に使いました。お昼すぎにちゃんとお湯が沸くか確認するために着火式を決行。水から熱したところ1時間足らず(時計を見ていないのではっきりしませんが・・・)で、熱くて入れないくらいの温度になりました。撮影隊は午前中には到着し、非電化工房内の各所で撮影をしてまわり、そして夕方ついに風呂の撮影が始まりました。今回は大阪の朝日放送の環境特番の撮影らしいです。師匠が、ミサイルマンというコンビ名の2人組みの芸人さんを風呂小屋まで案内してきて、その二人が文字通りの一番風呂に入りました。コンビの一人の岩部さんは、小学6年まで五右衛門風呂に入っていたそうで、とても懐かしい気分になっていたようです。ウグイスの声と小川のせせらぎを聞きながら、また薪の匂いが漂う中入るお風呂に満足されているようでした。細かくはまだまだやることがある風呂小屋ですが、とりあえずは一段落。今後はアースデイ那須の関連作業と平行しながらの作業になりそうです。あと次の投稿で重大発表があります。2010.3.31 SaTo
2010年03月31日
コメント(0)
-

27~30日の風呂小屋作業ダイジェスト
さとーです。26日以降、今日までブログがストップしていたので、遅まきながらこの間の出来事をお知らせいたします。まず27日。この日はお日柄もよく、作業するにはなかなか良い日でした。この日は東西の外壁に杉板を張ったり、タイルを張るところの水勾配をとったり、天井を塗ったりという作業をしました。次に28日。この日は寒かった。この日は壁塗りとタイルの貼りつけ、水道工事、階段工事などを実施。壁塗りは夜の10時ぐらいまでかかったのでした。で、撮影前日の魔の29日(月)。この日は全国的に寒かった日ということで、こちらは雪。しかし、どうも雪が降っているのはも那須だけで、10kmほど離れた隣町に行けば降っていなかったとか。ちなみにもみがらハウスの時も初回のワークショップ前日は雪と雨で最悪の天候でした。この日はその再来でした。朝、昨日、足りないことが判明した外壁材の杉板を、いつもお世話になっている材木屋さんの谷地木材に朝一で注文し、無理を言って昼過ぎまでに材を削って用意してもらう一方で、一人は、タイルの目地材を塗りこんでいきます。もう一人はドアの製作、もう一人は階段作り、更にもう一人は材木の受け取りとそれぞれがそれぞれの仕事を進めました。午後には屋根にあがって温水器用の枠の取り付けとトタン板の貼りつけをしていたのですが、暗くなったためトタン作業は明日へ持ち越し。夕方に既につららが垂れるほどの寒さでした。ドアの製作などが終わらなかったため夜も作業を続行。結局、夜中の2時くらいまでドア作りなどをしていました。こうして向かえた30日の撮影当日。水が入っていたボックスには分厚い氷が…まずはドアの取り付け。すんなり行くかと思いきや意外と苦戦。うまく閉まらなかったりして、何度も修正しました。昨日の残りのトタンも無事貼り終わり、あとは煙突をつければと思ったら、煙突の金属パイプ?の半径が違うものが一つだけあり、うまくつながらないことが判明!どうも買い間違えたらしい。そんなわけで、ちょっと師匠に相談にいくと、なんと撮影は明日! になったとのこと。そんなわけでドアの色塗りが終わったところで作業終了。午後は休息となったのでした。
2010年03月30日
コメント(0)
-
【ボランティア募集】4/18 アースデイメインイベント
どもさとーです。来月4月18日(日)に非電化工房で開催されるアースデイ那須のメインイベントのボランティアスタッフを募集しています。お時間のある方はぜひ一緒にやりませんか?■■【募集】アースデイ那須 ボランティアスタッフ■■※ボランティアスタッフ募集HPhttp://www.earthday-nasu.org/?cat=12日時:2010年4月18日(日) 9:00~会場:非電化工房(栃木県那須町)最寄り駅:JR東北本線黒田原駅から5km、黒磯駅から10km地図:http://www.hidenka.net/atelier/map.htm【ボランティア内容】餅つき、総合受付、会場案内、駐車案内など※餅つき経験者歓迎!【ボランティアスタッフ申し込み先】アースデイ那須実行委員会事務局FAX :0287-37-5833Email :info(アットマーク)earthday-nasu.org【参考】アースデイ那須HPhttp://www.earthday-nasu.org/非電化工房HPhttp://www.hidenka.net/jtop.htm
2010年03月30日
コメント(0)
-
土の日時計ワークショップ参加者募集
Satoです。直前ですが参加者募集のお知らせです。以下、アースデイ那須HPより転載----------------http://www.earthday-nasu.org/?p=472『アースデイ那須2010』企画、土の日時計づくりアースデイ那須の第一回記念モニュメント。晴天時、太陽の動きとその影から時間を知ることができる大きな日時計を、土でつくります。大人も子供もいっしょになって、土の温もりを感じながらみんなでワイワイ楽しみましょう。1回目は、期日間近!!たくさんのお申込みお待ちしております。 1回目 土台作り・土塗り(粗塗り)4月2日 金曜日 10:00~16:00 場所 非電化工房 (地図リンク)定員 20名(それ以上可)参加費 大人 1,000円 (食事代込み) 子供(小学生) 500円 (食事代)幼児 無料 ※ 子供・幼児の参加は、保護者同伴。 持ち物・服装 :汚れてもいい服装、着替え、長靴、頭を覆うもの(帽子や手ぬぐいなど)。 2回目 土塗り(仕上塗り)4月17日 土曜日 10:00~16:00 場所 非電化工房 (地図リンク)定員 30名(それ以上可)参加費 大人 1,000円 (食事代込み) 子供(小学生) 500円 (食事代)幼児 無料 ※ 子供・幼児の参加は、保護者同伴。持ち物・服装 :汚れてもいい服装、着替え、長靴、頭を覆うもの(帽子や手ぬぐいなど)。詳細は、申込受付後、非電化工房よりご連絡いたします。 申込み・事前のお問合せ先: Email:infoアットマークhidenka.net Fax:0287-77-3198
2010年03月30日
コメント(0)
-

本日も雪なり、でも風呂小屋作ってます。
どもサトーです。天気予報では、今日からは天気が戻るとあったのに、裏切られました。いや信じたのが悪かったのかもしれません。天気予報以上に天気をよめるようにならないといけませんね。そんなわけで朝は窓からあられのような雪が降るのを見ながらの朝食。そんでもって雪の中作業開始。佐々木氏は頼んでいた材木を材木屋さんに取りに行き、残り組みは階段を作ったり、ひさしを作ったりして午前中終了。午後はひさしを作る組と洗い場関係のもの作りとすのこ作りに別れそれぞれ作業を進めます。ひさしはこんな感じです。↓ひさしはトタンを貼れば終了というところまでこぎつけ、すのこ作りも完了、天井のペンキ塗りも9割がた終わり、あとは洗い場のタイル貼りや内壁塗り、水道・排水などなどが残っています。撮影まであと3日。果たしてどこまでできるか?2010.3.26 SaTo
2010年03月26日
コメント(0)
-
風呂小屋階段等設計、部材切り出し
どもさとーです。いやぁ、春は遠いですね。25日の今日は午後から小雨、そして夕方前から雪でした。いよいよ風呂小屋がクライマックスということで、だんだん終わりに近づくほどにあれこれと、不明な点が出てきまして、そのため午前中は細かい点が未決だった風呂小屋の階段や踊り場、ひさしなどの設計に費やしました。午後から作業だったのですが、もろもろの買出しに一人が行き、残り三人で主に屋内作業。一人はすのこ作り。もう一人は階段用の部材の切り出し、もう一人はあれこれの段取り作りなどをしただけで日が暮れてしまいました。いやぁ、思ったようには進みませぬ。2010.3.25 SATO
2010年03月25日
コメント(0)
-

弟子的 Before-After 風呂小屋外壁編
こんにちは、TAKEです~本日も昨日に引き続きましてお休み返上で作業です。といっても天気がよくないので先ほど終了したところなのですけどねとりあえず、今日のBefore今日も外壁貼りの続きで、南壁、東西壁を貼っていきマシタ。杉板をスコシずつ重ねながら下から順にはっていきます。Before 南壁After 南壁最後に釘できれいにとめます。今日はこんなところで終了デス。予報では明日雪との予報もありまして、もう春分の日も過ぎたのに今年は当たり年ですね~さてさてどうなることやら2010/3/24 TAKE
2010年03月24日
コメント(1)
-

薪ハツデン!
こんばんは、TAKEです~本日はお昼まで作業の後、弟子4人でどこへおでかけしたかとイウト・・・たどりついた先は「アジア学院」!!今日は『薪発電』のプロモーションをする方がいらしているとかで、我々も興味津々で見にいってきたというわけでして。これが本体で、細かく切った薪を燃やします。ここで燃された薪はあら不思議、一酸化炭素と水素となって、その後いくつかのフィルターを通して発電機に入って、ここで燃やされて発電する、ということのようですね。アジア学院の皆さんも熱心に聞いていました。要するに薪のガス化装置というわけなんですけどなかなかフシギな装置。いったん燃やして二酸化炭素と水になるのですが、さらに高温の状態ではこれが一酸化炭素と水素になって最後にまたこれを燃して二酸化炭素と水になって、このとき発電機で電気にする、というわけで。原理自体は昔日本で走っていた木炭自動車の原理で、アトリエに戻ってから調べてみると木炭自動車は戦後の時代20年ぐらいは活躍してたというからある程度の年齢以上の方はご存知かもしれないですね。ちょっと制御がムズカシイみたいでしたが、薪で発電、というテーマ自体はとてもおもしろいですね。電力会社に依存しない「独立電源派」を目指すTAKEとしてはモウスコシつっこんでみたいなと思っています~おまけココでも薪を割る男2010/3/23 TAKE
2010年03月23日
コメント(0)
-

弟子的 Before-After 風呂小屋ファイト編!
こんばんは、おひさしぶりのTAKEです~。先週はおなかをこわしまして2日ほど寝込んでおりマシタ。モウ完全復活しましたので今週はばりばり!?がんばりたいと思います~サテサテ、いつもなら今日はお休みの日なのですがいま取り組み中の風呂小屋のTV撮影が今月末にありまして、それに間に合わせるべくの休日出勤!?です~というわけで、今日のBeforeから外装の杉板が見えますねものすご~く、注意深く見ると分かるのですけど屋根の左側が黒いルーフィング(防水シート)がなくなっているんです。ジツは先日の強風でびりりとやられちゃいまして。トメが甘かったようですなそんなわけで、TAKEの病み上がり初仕事はルーフィングはり直しから。今度ははしごを他で使っているので、足場に開いたキャタツを固定して、いざ天空へ・・・一方、SASAKI氏は出っ張った軒部分の細工です。ここは師匠から垂直に切り落とすように指示がアリマシテ。まず糸につけた重しで垂直を測って、のこぎりで切り落としていきます~SATO氏とSUYAMA氏は外装の杉板を貼っていきます。貼ったらこんな感じSUYAMA氏得意の立て斬り!そしてルーフィングの修正を終えたTAKEは下のほうの軒を垂直に落とす方にとりかかりマシタ。こちらは上部と違って、ベニヤごと切らないといけないので、マッテマシタ!の丸ノコ君登場です~今回は斜め切り、かつ不安定な高所作業、かつ直線切り・・・難易度高いですねぇBeforeAfterとりあえず、なんとかなりましたが・・・消耗シマシタ・・・ここで、お昼を回ったので作業は終了。これから4人であるところへおでかけに~さてどこへ行ったのでショウ?待て!次号2010/3/23 TAKE 本日の体重 48.5kg(RED ZONE!)
2010年03月23日
コメント(0)
-
第1期 地方で仕事を創る塾 1日目に紹介された詩
どもさとーです。今回は地方で仕事を創る塾の1日目に紹介された詩をご紹介。イントロダクションとして藤村さんが敬愛する詩人の長田弘氏の詩とレイチェルカーソンの文章が紹介されました。そのうち長田弘氏の詩を以下に紹介します。あべこべの国にまつわる詩です。---------------------いまはむかし あるところに あべこべの くにがあったんだはれたひは どしゃぶりで あめのひは からりとはれていたそらには きのねっこ つちのなかには ほしとおくは とってもちかくって ちかくが とってもとおかったうつくしいものが みにくい みにくいものが うつくしいわらうときには おこるんだ おこるときには わらうんだみるときには めをつぶる めをあけても なにもみえないあたまは じめんにくっつけて あしで かんがえなくちゃいけないきのない もりでは はねを なくした てんしをてんしをなくした はねが さがしていたはなが さけんでいた ひとは だまっていたことばに いみがなかった いみには ことばが なかったつよいのは もろい もろいのが つよいただしいは まちがっていて まちがいが ただしかったうそが ほんとうのことで ほんとうのことが うそだったあべこべの くにがあったんだ いまは むかし あるところに----------------2010.3.21 sato
2010年03月21日
コメント(0)
-
第1期 地方で仕事を創る塾 1回目の2日目
どもさとーです。本日は地方で仕事を創る塾の1回目の2日目でした。朝方は雨が降っていたものの午後にはあがり、そこそこいい天気になりました。昨晩は参加者みんなで温泉に行き、今朝はみんなで朝飯を食い、そんでもって9時から講義が始まったのでした。今日の1日の流れはこんな感じ↓でした。8時 朝食(の予定が30分ほど遅れる)9時過ぎから 講義12時40分頃~ 昼食13時半~ 午前の講義を受けてグループディスカッション14時半~ グループディスカッションの結果を各グループから発表 & 師匠からのコメント16時すぎ~ おやつ休憩16時45分~ 宿題の説明17時 終了どんな講義があったのか? と気になる方もいるかもしれないので、ちょっとだけ紹介します。講義では今の時代や社会をどうみるかという点がメインテーマとなりました。昨晩師匠から4種類の文章が配布されたのですが、主にそのうちの2種類を使っての講義になりました。ちなみに4種類の文章のタイトルは以下の通りです。(1)「社会はどこに向かっているのか?」(2)「競争社会を愉しく生きる」(3)「自分の物語を書けない日本人」(4)「自由を阻む20の呪い」このうちの(1)と(2)をメインに話がありました。師匠の位置づけでは(1)は社会レベルの話を、(2)は個人レベルの話をしています。物事を考えるときには社会レベルと個人レベルで考えないといけないということで、この2つがメインとなったのでした。それではそれぞれについて、簡単に内容をご紹介。「社会はどこに向かっているのか?」では、こんな話が出ました。※「」内は文章からの引用で、あとは私の要約です。データなどは私が補足している部分もあります。「自分(or自国)の欲望を満たすために、論理力と軍事力と経済力を武器に、分断・対立・競争を原理として、人(or他国)や自然を支配するという特徴を持つ「アングロサクソン・システム」が世界の中心となるべく発展し続けた2千年という時間」、今日ではそのシステムは、経済のグローバリズムとして世界に広まり、競争の激化や格差の拡大、環境負荷の増大などが進んでいます。こうした現状に不安を抱いている人はいっぱいいる。例えば日本では、1998年以降自殺者が3万人を超えて高止まりしている。10万人当たりの自殺者数はアメリカの2倍(日本23.7人、アメリカ11人)。日本人の6割が日常生活で強く/やや強くストレスを感じている。参照:「平成20年版国民生活白書」http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/h20/01_honpen/html/08sh010302.htmlこうしたことから考えると、今はアングロサクソンシステムを基本とした文明の端境期にあると言えそう。けれど、多くの人は現状を黙認して今の生活を続けるしかないと思っている。言い換えれば、他に選択肢がないと思っている。人は追い詰められれば選択肢を選べなくなる。例えば、結婚願望がありながら、結婚せずに年齢を重ねていくと、あちこちからプレッシャーがかかり、最後には“(相手は)誰でもいいや”となるように(笑)。もしあなたがこんな社会の行く末に明るい希望を見出すのなら、何もしなくていい。でも「明るい希望が見出せない人は、自分ができる範囲内で何ができるかを考えて行動すべきだ。どんな小さいことでも構わない(大きなことを言って何もしないのがよくない)。それが子を持つ親、孫を持つ親の責任だ。それを愉しく実現するのが知性だ。それが新しい選択肢の提供なら、それは発明家・起業家の仕事だ。」と、まぁ、こんな話があったんです。(2)の「競争社会を愉しく生きる」では、こんな話がありました。「競争社会は、競争が好きな人のみで構成されるわけではない。他人の犠牲を代償として初めて自分の仕合せがあるという社会を好まない平和主義者が少なからず共存する。」例えば、感受性の強弱を横軸に、逞しさの強弱を縦軸にして4象限(4タイプ)に分類してみる。つまり、1.繊細(感受性が強い)で逞しい人、2.繊細で逞しくない人3.鈍感(感受性が弱い)で逞しい人、4.鈍感で逞しくない人の4タイプに人を分けて考えてみる。この4タイプで考えると、競争社会のリーダー(勝ち組)になる人は、3.鈍感(感受性が弱い)で逞しい人だ。競争社会の中では平和主義者は負け組みになる。けれど「人の痛みがわかる感性を持った平和主義者が劣等者であるわけがない」では、競争を好まない平和主義者が激しい競争社会の中で心愉しく生きていく道はあるのか?1つの答えは、繊細さを捨てて鈍感になることだろう。「鈍感力」なる言葉が流行るような時代だ。鈍感になる方法はいくらでも巷にあふれている。しかし、この方法には賛成できない。だって「鈍感な人ばかりで構成される社会はおぞましい」から。では、別の答えを探さねばならない。もう一つの答えは、「繊細さを維持したままで逞しくなることだ。」つまり、1.繊細(感受性が強い)で逞しい人になる。こうした人は共生社会のリーダーになれる。では、どうしたら繊細さを維持したままで逞しくなれるのか?ヒントはネイティブアメリカンの社会で伝え続けられていたことにある。つまり、「知性を高めること、テクニックを身につけること、役割意識を持つこと、仲間を持つこと」。この4つを磨いていけばいい。と、まぁ、こんな話がありました。こうした話を受けてのグループディスカッションでは、各グループいろいろな話が出たようです。講義中の緊張感と休憩時間は和気藹々(わきあいあい)感がなかなか心地良かったですね。次回は4月の初め。次の回も楽しみです。2010.3.21 SatO
2010年03月21日
コメント(2)
-

風呂小屋壁ルーフィング貼り、地方で仕事を創る塾始まる。
どうもSaToです。本日は晴天なり。今日は午後から第1回の地方で仕事を創る塾が始まるということで、午前中だけ肉体労働をしました。風呂小屋の壁にルーフィング材という防水シートを貼っていきます。そんな中、ハプニング発生。パワーショベルで整地をしていたところ、なんとキャタピラが脱輪(?)。下の写真で確認できますか? 向かって右手のキャタピラが外れています。というわけで、作業を中断してキャタピラを元に戻す作業を始めたのですが、これがなかなか手ごわい。一時は無理かと思いもしましたが、自転車の外れたチェーンを戻すのと同じような原理でなんとか元に戻したのでした。やれやれ。ほんでもって午後からは第1回目の地方で仕事を創る塾がありました。今日は第1回目ということで、工房の見学や参加者の深い自己紹介、詩の朗読などをして終わったのでした。明日も引き続き塾ですが、明日はちょっと勉強するようです。では。2010.3.20 sAtO
2010年03月20日
コメント(0)
-
冷蔵庫発送、風呂小屋内壁修正作業
SaToです。本日は写真なしですが、悪しからず。というのも、今日の仕事は昨日の中途半端になっている作業の続きでございまして、朝食後から非電化冷蔵庫の材料を梱包して発送する作業を行いました。それが15時過ぎくらいまでかかり、そこから風呂小屋作業に突入。これまた昨日、中途半端で終わってしまった内壁の隙間埋めのためのベニヤ貼りや天井貼りを今日は一気に(?)仕上げたのでした。地味な作業ですが、ちょっとずつ進んでおります。明日は写真入りでアップしたいと思いますので、乞うご期待。2010.3.19 sAtO
2010年03月19日
コメント(0)
-

風呂小屋内壁修正、発送、アースデイプレイベント
どもSaToです。春が来たかと思いきや久しぶりの雪でした。夕方までは明るい曇り空だったのですが、夕方前から雨が振り出し、夜には雪となりました。春は名のみの…というやつですね。さて、今日はあれこれとばたばたした日でした。朝食後、まずは風呂小屋作業の続き。内壁の修正作業をします。天井となるベニヤ板を張ったり、隙間が見えなくなるように板を張ったりといった作業をしました。そうした作業をしていると非電化冷蔵庫の部材を発送する準備の準備が整ったということで、風呂小屋作業は中断して、発送作業にかかります。そんでもって夕方からは本日の夜に行うアースデイのプレイベントの準備。たくさんの人が来るということで母屋の中にスペースを作り、ベンチを用意したりしたのでした。アースデイのプレイベントでは、いろいろな人が音楽や朗読などをしたのですが、100名(スタッフ含む)ほどの方がいらしてけっこうな賑わいでした。アースデイの方もメインイベントまで1ヶ月ほどなりました。これから本格的な広報になるのですが、みなさんもぜひいらしてくださいね。メインイベントは4月18日@非電化工房です。では。2010.3.18 Sato
2010年03月18日
コメント(0)
-
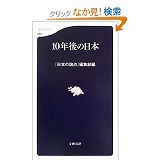
書読ミテ語ル:『10年後の日本』
こんばんは、TAKEです~。続きましての課題図書は・・・書名:10年後の日本著者:「日本の論点」編集部出版:文春新書------------------------------------------------本書はざまざま今の日本の問題、課題について分かりやすくまとめられていて読みやすい本のように思います。消費税、高齢化、団塊世代の動向、少子化、学力低下、離婚、環境問題、家庭内暴力、グローバル経済、安全保障、と、問題は多方面で山積みですね。その中で、ちょっと知らなかったのでビックリしたのが非婚化、晩婚化が進む中で、既に出生児の90人に1人が「試験管ベイビー」であること。そして、AID(非配偶者間人工授精)によって誕生した子供がすでに1万人を超えている、という事実。なんだかSFの世界みたいな印象です。モウそんな時代なんですね。本書はさまざまな問題・課題を淡々と述べ、10年後を予測する、というスタンスなので、読み終わると「ああ、問題だらけで息がつまりソウダ」となってしまうのですけど、要するに社会の進む方向が全くもって明確でない、ということなのかなと思います。師曰く、「これまで日本の世論は政治家と学者とジャーナリ ストがつくってきたけど、いまはそれも弱くなっ て世論そのものがなくなっている」というわけで、この国ではこの先どうなるのか、どうしたいのか、ということを責任もって示せる人がいないわけですね。そもそも考えてもイナイというのが大部分なのかもしれません。それは不安になるわけで。おそらく、答えは簡単に出るものではなくて、「事実を知る」「考える」「伝えて」「繋がる」という段階を経て、市民の世論をつくりあげていく必要があるんじゃないかと思いますけど、いずれにしても今までと同じマインドセットで考えていてはいい世界は描けないような気がします。今までの文明から全くチガウ見方で新しい価値、文明を定義する必要があるように感じました。まずは「事実を良く知る」ことからはじめていくとしましょう~2010/3/17 TAKE
2010年03月17日
コメント(0)
-
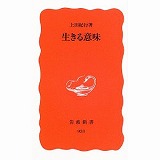
書読ミテ語ル:『生きる意味』
こんばんは、TAKEです~。しばらく滞っていた課題図書をちょっと読みましたのでご紹介したいと思います!今回はこれ。ながながととりとめなくなっちゃいましたけどスイマセン書名:生きる意味著者:上田紀行出版:岩波新書---------------------------------------------------------著者は今の時代は「生きる意味」が見えない社会であり、これこそが「今の社会を襲っている問題の本質」であると指摘しています。著者によれば・・・物質的には豊かになった今の日本で、「何故自分が生きているのか分からない」「何が幸せなのかがわからない」そんな「生きる意味の不況」が起こっているといいます。そして、その原因は「他人の欲求を生きてきた時代背景」と「日本特有の『恥の文化』」が大きく関わっている、と指摘しています。右肩上がりの経済成長の中で電化製品をはじめとして便利で文化的なものが次々と市場に出て、皆がそれを欲しがる、だから自分も欲しい、と思う。そんな時代が長く続きました。だから自分の欲求ではなく、「他人の欲求を生きた」わけですね、その時代は。でも、バブルがはじけてそれが一瞬でなくなってしまった。ホントに自分がしたかったことが何なのか、わからなくなってしまったわけですね。これが1つ目の原因。2つめの『恥の文化』はちょっと分かりにくいですけれど、日本の伝統として「他人からどう見られているか」を軸に自分の行動を決める、という行動形式があるそうです。たしかに思い当たるフシはありますね。世間様に顔見世できない、から高校に行かせる、大学にいかせる、いい会社にいかせる。そんな感じでしょうかね。その中で子供は「親に受け入れられやすい」「周りに受け入れられやすい」「どこにでもいそうな」「あたりさわりのない」人間になろうとします。その結果、個性がなくなり自分が「どこにでもいる」人間、著者はこれを『交換可能』という言葉で表現していますけれど、結局自分の存在価値、かけがえのなさ、が感じられなくなってしまった、というわけです。自分のやりたいことがワカラナイ、そもそも自分の存在価値がみあたらない。だから「生きる意味」がワカラナイ。そんな状況が今の社会の状況なのだ、と。さらに著者はこのようにして育った子供は、自分は社会の「被害者」であり、すべて「他人のせいだ」としてしまう傾向が強く、この傾向はいまや若者だけでなく、幅広い年齢層で起こっているといいます。著者の言葉によれば日本全体が「アダルトチルドレン化」している。そして、これに追い討ちをかけているのが、「グローバル化」「金融社会化」「数値化」の3つ。グローバル化する中で、文化は画一化することが求められ、金融社会化のなかでますます社会は複雑化、距離の感覚が失われていきます。そしてなんでも数値化し、評価する、という文化の中で多様性は失われ、よりいっそう画一化が進んでいます。つまり、イロイロなものが地球規模で「交換可能」になってしまった。どこにいっても同じような社会・・・。ハタシテ、この「生きる意味」をとりもどすにはいったいどうしたらよいのか?その問いに著者は次のように答えます。「内的成長」が不可欠であり、それにはコミュニティの復活が必要である、と。物質的、経済的な成長ではなく心の内面の成長。そこから「生きる意味」が分かってくる。これを成し遂げるには著者は「ワクワク」と「苦悩」が必要だといいます。「ワクワク」は自分が好き、オモシロイと感じることを大切にする、ということ。じゃあモウひとつの「苦悩」とは?一見ネガティブに見えるこの言葉ですけれど、著者は苦悩とは自分の感覚と周りの環境が合わない、そういったときの「違和感」からの悩み、と捉えているようです。つまり「自分」と「周り」とのチガイに違和感を感じ、悩む。だからこそ、その悩みに真剣に立ち向かって自分なりの答えを出したときに、自分なりの生き方、すなわち「生きる意味」が分かる、ということのようですね。そして、大事なのは「ワクワク」も「苦悩」も一人で対峙するには大きすぎるものである、というコト。支えあう仲間が必要だと著者は言います。ワクワクすることをともに愉しみ、苦悩することをともに受け止める。そんな仲間。ゆえに著者は「コミュニティ」の復活がトテモ重要な役割を果たす、と述べています。個々の多様性があることを認めた上で、自分の考えを「伝える」コト、そして相手の考えを「聴く」コト。そしてともに支えあう、だからそれぞれが「交換不可能」な「かけがえのない存在」になる、そんなコミュニティ。この例としてNPOやNGOの活動に著者は注目しているようですね。それで、この本を読んでの僕の意見としては、自分自身がどちらかというと昔から周りとだいぶ違っていたし、違っている方がイイ、という考え方でしたので、一般的にはこうなのかな?という印象がしました。「違和感」という点では、人と考えが違っていることが多かったのでいつもイロイロ違和感はあって、そんなわけでまあ今非電化工房にいる、というこのなのかな、と思いますね。この現代社会に対する違和感、これまでは周りでそれを感じて声に出す人があまりいなかったのですけど、非電化工房を知って、仲間ができて、そして師匠の弟子になって工房を訪れる人の声に耳を傾けてみると、違和感を感じて、どうにかしたくて何かしている、という人がトテモ多いことが分かってきました。師匠の言葉を借りれば「今は文明の端境期」。アングロサクソン主導の今の文化は終焉を向かえて新しい文明に移ろうとしています。「違和感」を感じた人たちが新しい文化を模索しているのだと思います。だから本書のような社会状況は、これからだいぶ変わっていくように思うし、変えていけたらいいなと思います。最後に著者はNPO、NGOがコミュニティとして大きな役割を果たす、としていて、この部分は大いに賛成なのですが、多分この前段階としてインターネットによるコミュニティがあるのではないか、と思います。インターネットの中でさまざまな意見が飛び交い、哲学、思想に共鳴し、ワークショップなどを通して実空間で出会う。そんな形なんじゃないかと思います。このブログではまだ情報発信一方ですけど、ネット上でモウスコシ情報や意見を交換したりして愉しいコミュニティ、ネットワークが広がっていくようにできたらいいな、と近頃考えています。2010/3/17 TAKE
2010年03月17日
コメント(0)
-

師のコトノハ:『電気自動車の罠』
こんにちは、TAKEです~。今度は電気自動車のお話。米国オバマ大統領がグリーン・ニューディール計画を打ち出し、金融危機を克服する切り札として、クリーン技術に世界的な注目が集まる中、次世代自動車産業をめぐる世界の覇権争いが熾烈さを増しています。昨年は三菱自動車からi-MiEv、スバルからプラグインステラが市販されました。経済産業省も力を入れて電気自動車社会へのシフトを応援しているようです。富士経済の調査によれば、2010年に世界市場が立ち上がり、2020年で13.5万台、インフラが整備され、本格的導入が始まるのは2020年代後半以降との見通しのようです。→http://www.group.fuji-keizai.co.jp/press/pdf/090508_09040.pdfまあいずれにしても世界は「走行中に二酸化炭素を出さない」「自然エネルギーで電気を作れる」というふれこみで電気自動車社会に足を踏み出しました。この流れは止まることはなさそうです。しかし、ちょっとマテ。それだけの電力はどこで作るの?ということなんですけど、またまたここで例の表を取り出すと・・・自動車用ということで運輸(ちょっとおおざっぱですけど)用を見てみると、2006年では電力は少なくて、ほとんどLPG+石油ですね。この値が209GP。だからこのときの電力の総量202GPより大きいですね。電気自動車社会では余剰の深夜電力を使用する、との報道もあるようですがはたしてほんとうにそれで足りるのでしょうか?師匠はこれも原発政策にはまった『罠』だとおっしゃいます。サテサテ、やっぱり原発から逃れることはできないのでしょうか?師匠は「電気自動車社会はもう「リアリティ」として受け止めざるを得ない。」その上で電気をどこから得るか、自然エネルギーをうまく使えないか?とおっしゃっています。2010/3/17 TAKE
2010年03月17日
コメント(0)
-
師のコトノハ;『オール電化の罠』第3回
こんにちは、またまた続く「オール電化」のお話。前回はオール電化が太陽電池とセットになっている、というお話でした。太陽電池は晴れた昼間でないと発電できません。家庭の電気使用は昼だけではありませんね。それにたくさん発電してもそんなに使わない日もあるし、反対に雨の日は発電できません。つまり、需要と供給がうまくマッチしないのでどこかに貯める必要がありますね。そこで電力会社は「じゃあ買いましょう」ということで発電して使わなかった分は電力会社に「売電」するシステムができています。そして昼間余った分を高く売って、深夜の安い電気料金で電気を買うことができる、といいます。「これはオトクだ!」というわけで「じゃあオール電化」ということになるわけです。ジツはここにもモウひとつの『罠』が・・・太陽電池を使って電気を電力会社に売るこのシステムを導入するともう電力会社から離れられなくなるんですね。デモ次世代の家庭用エネルギーの本命はジツはガスなんですね。昨年度からガス会社が燃料電池を使った「エネファーム」の売出しをはじめました。これは都市ガス(メタンガス)から水素を取り出して電気分解の逆の反応で酸素と水素で水を作ってこのときに電気を発電します。おまけにこのとき出る熱も利用して給湯などにも使う「コージェネレーション」というシステムでエネルギーの利用効率が80%と格段に高いシステムになります。発電所で発電する場合、遠距離送電するので末端では37%程度しかエネルギーが利用できません。東京ガスのWEBサイトによれば・・・→http://home.tokyo-gas.co.jp/enefarm/enefarm03.html-------------------------------------------------------「従来のシステムに比べて、一次エネルギー消費量を 約33%削減、二酸化炭素(CO2)排出量を約45%削減 することが可能です。」「エネファームなら、各家庭まで100%の状態で供給 される都市ガスを使用して発電を行います。電気を 「つくる」場所と「使う」場所が一緒。だから発電 時に出来る熱も、お湯にしてムダなく利用でき、暮 らしを快適・便利にします。エネルギー効率は80%!」-------------------------------------------------------まだイニシャルコストは高いようですけど、補助金も多く、これから広がる可能性が高いですね。デモ、東京電力の「オール電化」で太陽電池を導入すると結局東京電力から離れられないようで・・・つまりいまの電力会社の「オール電化」攻勢は消費者の「囲い込み」の様相が強いわけですね。サテサテ、今後の家庭エネルギーの供給体制はどうなっていくのでしょう?いずれにしても目先で判断するのは『罠』にはまる可能性がありますので、ご注意を。まあナンダカンダいわずにエネルギー消費量を減らすか自分で作るかしなさい、と師匠は言いそうですね。だいたい田舎はプロパンですし。2010/3/17 TAKE
2010年03月17日
コメント(0)
-

弟子的チャレンジ:非電化洗濯機
おはようございます、TAKEです~。今日はいいお天気なので洗濯しよ~と思って洗い物をもって土間に出たら・・・洗濯槽に汚れ水がたまってイテ脱水をかけても脱水されません故障!!!この洗濯機は昨年4月にまだ会社に居た頃、会社が不況と社員数減少で独身寮を維持できなくなって追い出されたときに寮で使ってた古いものを頂いたものなんで、たしかにボロなんですけど・・・う~ん、ショック!でも、ここでハタと・・・そうです、今月の目標はインプロの「Yes,and・・・」でアリマシタ。ポジティブ思考でいきましょう~ということで、インプロ的に「それはちょうどいい」と言って、「じゃあ前からやりたかった非電化洗濯機を試しちゃおう!」てなわけで昨年末の大掃除のときに物置に埋まってたのを許可を得まして合宿所にもってきておいた非電化洗濯機「ワンダーウオッシュ」を試してみることにシマシタ。こんなやつですなかはこんな感じこれに洗物と洗濯石鹸とぬるま湯をいれて、蓋を閉めます。つぎに取っ手を回してくるくるまわすのですけど、これがなかなかイイ!はじめの数回転はちょっと抵抗があるのですけどリズムに乗るとぜんぜんチカラがいりません。いいリズムで2分ほどまわして終了。排水します。排水は下にある排水口に排水用パイプをぎゅっと押し込むと排水されるというオモシロイ方式。だけどずっと押すのがなかなかたいへん。排水口排水パイプデモ、「それはちょうどイイ」、「筋力トレーニングにしよう!」と前向き思考でがんばります。排水できたら、きれいなお水にいれかえてくりかえします。あとはしぼって干すだけ。う~むなかなツカエル。できれば非電化脱水機も欲しいな~ちゃっと作れないもんじゃろか?今後の課題ですね。2010/3/17 TAKE
2010年03月17日
コメント(1)
-
師のコトノハ:『オール電化の罠』第2回
こんにちは、TAKEです~。前回に続きましてオール電化の話。前回はオール電化で単純に原発68基分の新たな電力需要が増える、というようなことでした。こんなことを言ったら「マテマテ、うちはオール電化だけど太陽電池を 使ってますから原発とは関係ないデスヨ」という方もいらっしゃるかと思います。たしかに最近はオール電化と太陽電池はセットで導入されるケースが多いようです。でも師匠はここにも『罠』があるとおっしゃいます。非電化工房WEBサイトから引用しますと・・・→http://www.hidenka.net/energy/gp4.htm----------------------------------------------太陽電池は、製造過程で最も電力を消費する工業製品の一つです。 EPT(Energy Payback Time)というのは、製造過程で消費されるエネルギーを、自らが生み出したエネルギーの何年分で取り戻せるかという意味ですが、太陽電池のEPTは、太陽電池に注がれた太陽光がフルに電気に変換され、変換された電力がフルに使われたと仮定しても、約5年(3年と言うメーカーや10年と言う学者もいます)です。 つまり、初めの5年は、太陽電池の設置により、発電所の電力需要はかえって増えます。 太陽電池の効果がでてくるのは理想的な場合でも6年目以降です。 ですから、電力需要を増やし、それを太陽電池で賄おうとすると、一時的には電力需要が増え、火力発電所や原発の余分な増設を招きます。 いったん電力供給能力を増やしてしまってから、後で電力需要を減らすのが困難なことは、歴史が示すとおりです。----------------------------------------------ナント!太陽電池ってつくるのにそんなに電気を使うのですか!!!ということはオール電化に太陽電池をくっつけるというのはエコというより、ますます電力需要を増やして原発建設!ということになりかねないわけなのですね。エコなつもりで太陽電池にしたらまたまた『罠』が・・・世の中表面だけ見ててはだめですね、ホントに。2010/3/17 TAKE
2010年03月17日
コメント(0)
-

師のコトノハ:『オール電化の罠』
こんにちは、TAKEです~。最近流行の「オール電化」。調理はIHクッキングヒーターで、給湯は深夜電力を使った「エコキュート」でというやつですね。2008年度の調査結果ではオール電化設置実績は前年度比4.2%増の59万400戸。累計設置戸数は330万2000戸となり、全世帯における普及率も6%を超えたそうです。→http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0909/11/news066.html前々回から出てきました『GP』でみてみると・・・家庭用消費全体が125GPで、このうち電力が56GP、ガスが22GP、石油・LPGが46GP、太陽熱が1GPですね。オール電化は暖房、給湯、厨房といったこれまでガスや灯油などで行われていた部分を電気に移すことになりますから、単純計算で68GPの電力需要が増えてしまうわけです。で、この電気ドウヤッテツクルノ?といったら「そりゃゲンパツでしょ」というわけです。「オール電化の国」=「原発の国」安い深夜電力を使って経済的でエコ。そもそも一定の発電量を維持する原子力発電所を前提とした考え方ですよね。オール電化という名につられていつのまにやら国の原発路線にのってしまっているわけですね。だから師匠は『罠』だと。国のエネルギー政策を牛耳る政治家、電力会社にも問題はありそうですけど僕たちも自分たちの行動の先にあるものを良く見据えて行動する必要がありそうです。まずは「知ること」。これが大切ですね。2010/3/17 TAKE
2010年03月16日
コメント(0)
-

師のコトノハ:『GP』 第2回
こんばんは、TAKEです~。前回でてきました『GP』。今回はこれを使って家庭のエネルギー消費を見てみるとしましょう。非電化工房WEBサイトから引用シマシテ・・・→http://www.hidenka.net/energy/gp3.htm全体の消費エネルギー125GPのうち56GPが電力によるものです。さらに細かく内訳を見ると、第一位はTVと照明で 10GPずつこの次が冷蔵庫で 5GP。冷房は意外と小さいですね。これは年中動く冷蔵庫とは異なり、季節が限られているからですね。TVはブラウン管のものに比べると液晶などの方が消費量は少ないのでしょうけど、その分近年は大型化が進んでいますから消費量が大きいのでしょうね。確かに画面サイズをあらわす「インチ」は対角線の長さなので、これが2倍になれば面積は4倍。電気消費量も単純計算で4倍ということになるのでしょうね。この表を見れば、みんなが電気炊飯器をやめておなべでご飯を炊いたら原発2基がなくせるし、ポットをやめてそのたびに沸かせば原発3基がなくなる、掃除機をやめて箒にしたら原発2基、除湿機を非電化除湿機にしたら原発1基なくせる、というわけでこれだけで日本から原発8基なくせるじゃん!というわけなのです~ちなみに「非電化ポット」は量産検討中、「非電化掃除機」は開発中みたいですね。原発反対!と声をあげるのも大切ですけれどまだまだ自分たちでも電気使用量を減らすコトができそうですね。2010/3/16 TAKE
2010年03月16日
コメント(0)
-

師のコトノハ:『GP』
こんばんは、TAKEです~。先週に続きまして原発つながりで今回は『GP』。非電化に詳しい方はもうおなじみですが「ゲンパツ」からとった師匠提案の新しい単位ですね。ナントワカリヤスイ!原発立国日本の現状を分かりやすくするために師匠が考え出したこの単位。どういうことかというとエネルギーの量を「原発何基分か?」という形で考えちゃおうということ。 1GP=50億KWH(キロワット・時)/年これは原子力発電所が1年間に末端に供給する電気量の平均(04年実績)一般的に知られている単位との関係は次の通りです。 1GP = 50億KWH(キロワット・時)/年 = 43兆kcal(キロカロリー)/年 = 180兆kJ(キロジュール)/年 = 石油換算43億キロリットル/年自然エネルギー発電との関係は次の通りです。 1GP = 大型風車25基分 (直径10m、風速10m/s換算稼働率50%、平均機械効率30%の場合) = 太陽電池200万世帯分 (1世帯平均2.5KWの設置、直射換算年間日照時間=千時間の場合)これを使うと何に対して原発何基分のエネルギーが使われているか分かるのでイメージがつかみやすいですね。非電化工房のWEBサイトから引用しますと・・・--------------------------------------------------------------------例えば、「04年に、日本全国で、家庭用として消費された電力量は 約56GPでしたが、この内、電気炊飯器用に消費された電力量は約2GPでした」というように、GPを使います。 このように表現すると、「電気炊飯器だけで、原発2基分の電力を消費している」ということが理解できます。すると、「半分の世帯が電気炊飯器をガス+圧力鍋に替えるだけで、原発1基分の電力を減らすことができる」ということが理解できて、希望がわいてきます。→http://www.hidenka.net/energy/gp.htm---------------------------------------------------------------------さらに上記サイトから日本のエネルギーについての表を引用しますと・・・ これによれば日本全体のエネルギー消費は850GPでこのうち、電気は202GP。このなかで家庭用は56GPとなっていますから電力の25%は家庭で消費されていて、これは原発56基分というわけですね。電力を発電形態別にみてみると・・・*このデータは2004年度となっていますから、202GP中原発によるのが50GP。ということは・・・家庭で全く電気を使わなければ原発はいらないということですね。(ありえないことですケド・・・)エネルギー問題を考えるときこの『GP』はトテモ役に立ちそうです。2010/3/16 TAKE
2010年03月16日
コメント(0)
-

弟子的 Before-After 非電化冷蔵庫発送準備編
おはようございます、TAKEです~。昨日は夜遅くまでの作業で、ばたんきゅ~でしたので今頃昨日の分をアップです昨日はKensukeリーダーの下、非電化冷蔵庫の発送準備となりました。発送もどのような状態で発送すべきかという議論が師匠とKensuke氏の間で行われまして、最終的には冷蔵庫上部の枠、中蓋はこちらで製作し、ざぐり穴やヒンジ用の穴などもこちらで開けておくこととなりました。そんなわけで丸1日の作業と相成りました。ひたすら枠と中蓋を作っていきマス。枠は最後に本体に取り付けるのですけど、コーススレッドがでっぱると閉まらなくなっちゃうのでざぐり穴を開けマシタ。このほかヒンジ(蝶番)の穴あけやでっぱったナット用のざぐり穴などもあけていきます。こんなときにはいろいろなビットが役に立ちます。「ビット」というのはドリルドライバーやインパクトドライバーなどの先に取り付けるものですね。ビット取付状態今回使ったビットは6種類!左から・でっぱったナット用の穴を開けるちょっと大きな 穴があけられるビット・通常のプラスドライバーのビット・鉄鋼用にも使える丈夫なビット。割れ防止のための下穴用・これも下穴用のビットですが、奥に行くほど太くなる テーパービットというものです。先が細いので下穴が開け やすいのですけど、折れやすいのが難点ですね。・コーススレッド用のざぐりビット。下の拡大写真のように 根元が円錐状になっていて、この部分でコーススレッド のアタマが収まる穴を開けることができます。・最後が今回初めて使ったヒンジの下穴開け用のビット。 ヒンジのねじ用に穴にあてて、押し込むとドリルが出てきて 穴の中央に下穴を開けることができます。 これがないとねじが真ん中にこなくて斜めになったり、 ヒンジがずれたりして苦労します。どれも根元が六角になっているので交換もスムーズですね。↓コーススレッド用ざぐりビット↓ヒンジ用下穴ビット押し込むとドリルが出てきます!いやはや便利なものがあるものですね。道具は見てるだけでも面白いですし、使うとこんなに便利!とおどろいたりで、なかなかいいものです~こんな道具たちを使いながら、なんとか作製、仕分けをほぼ終了しました。もうちょっとやることがあるそうなのでお休み明けにちょっと作業して、梱包、発送となりそうです。前回ワークショップ参加のみなさま、お愉しみに~↓一人分まとめた状態。釘なども揃っています2010/3/15 TAKE
2010年03月15日
コメント(0)
-

弟子的 Before-After 風呂小屋修正編
南側はこんな感じ。黒い防水シートがとりつけられましたね。朝ごはんの後、師匠の現場チェックがありました。まずは内装ですが、屋根と壁の間の隙間を埋める必要があるとの指摘でイロイロ議論した結果、屋根が高い北側は天井を張って隙間をなくすことにして、天井をつけると頭をぶつけそうな南側については内壁を延長して隙間をなくすことに・・・。というわけで、天井張り用に間柱をなんぼが取り付ける作業と内壁を修正する作業となりました。天井の方は今日は間柱の取付までで終了。ちょっと写真が分かりにくいですけど・・・南側は母屋(もや:屋根をのっけるための梁みたいなもの)がでっぱっていて内壁が延長できないので、かんなで削っていきました。なんだかんだで最近かんなにお世話になってイマス。けっこうかんなって気持ちいいんですよね。仕上がりがきれいですし。朝の師匠のチェックでは床の方はタイル張りと風呂釜周りの処理についても指示がありました。いよいよタイル張りなどにも入っていくのですね~愉しみ!!2010/3/14 TAKE 本日の体重 50.8kg
2010年03月14日
コメント(0)
-

弟子的 Before-After 風呂小屋内壁編
こんばんは、TAKEです~。今日はSato氏とSasaki氏は師匠とともに埼玉での講演におでかけしましたので、Suyama氏との2人作業です~まずは今日のBefore屋根はこんな感じ。下1段分だけルーフィング(防水シート)を張ってありますね。今日は屋根のルーフィング張りと内壁張りをしました。内壁はこんな感じで12mmのベニヤを貼り付けていきます。またまた丸のこくんが大活躍デス!BeforeAfterそして、ルーフィング張りの方はというと・・・さすがに足場だけではてっぺんまで届かないので、はしごをかけての作業です~おおうっ、めがくらむ~よたよたしながらもなんとか防水シートをてっぺんまで張ることができました。ヨカッタ。明日は外壁ルーフィング&杉板張り、といったところかな?お愉しみに!2010/3/13 TAKE 本日の体重 51.8kg
2010年03月13日
コメント(0)
-

弟子的 Before-After 風呂小屋屋根張り編
こんばんは、TAKEです~明日は師匠が埼玉で講演される予定でして、同時に非電化製品の販売もする計画です。今日は遅くまで明日の準備となりました。Sato-Sasakiのツートップが販売員として参上いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします!サテサテ、風呂小屋のほうは数々の苦難を乗り越え!?ついに屋根張りとなりました!まずは今日のBeforeから。脚立やはしごを使ったり、垂木によじのぼったりして屋根を張っていきます~途中まで張られたのがこんな感じ。内壁も張り始めました。屋根がついて内壁もついてくると、なんだか「新築!」というかんじがしてきますねいい感じですね~むふふふふふ・・・夕方から僕とSASAKI氏で谷地木材さんに外壁に張る杉板を買いに出かけました。途中で不足していたベニヤと内装用の珪藻土なども購入しましたので明日屋根と壁にルーフィングを取り付けたら、イヨイヨ内装と外装の仕上げに入っていく感じですね。がらっとステキステキ風呂小屋に変わっていくのでしょうね~、愉しみ!谷内木材さんではまたまた社長さんからロープワークを2つ伝授していただきました。次うかがうまでにマスターしておきたいですね~では明日もがんばりましょう~2010/3/12 TAKE
2010年03月12日
コメント(0)
-

風呂小屋 屋根作り(母屋、垂木)
SatOです。火曜、水曜と降り続いた雪は、今朝も残っていました。しかし、本日は晴天なりというわけで、作業はいつもどおり。朝はこんな感じ↓本日から屋根作りに入りました。まずは横に母屋(もや)と呼ばれる横柱?をかけて、それから縦に垂木と呼ばれる部分をかけます。一方で、温水器で暖めたお湯を溜めるための貯湯槽のパイプが長かったのでプラスチック用ののこぎりで20cmほどカットしました。あとパイプを買ってきて足場も作ってみたのですが、なかなかきれいに作るのは難しいんですね。きれいにできず。暗くなる頃に垂木の上にベニヤを試しに一枚貼ったところで今日は終了。明日には屋根がかかる予定です。2010.3.11SAと
2010年03月11日
コメント(0)
-
師曰く:「民主党がすすめる原発技術の輸出はトテモ残念」
師曰く、「民主党がすすめる原発技術の輸出はトテモ残念なこと。」------------------------------------------------------師匠は原子力発電の最近の動きには大変憂慮されています。このごろは二酸化炭素削減の切り札ともいわんばかりに世界中が原子力発電に偏り始めている感じがしますね。政権交代した民主党は二酸化炭素排出の大幅削減を掲げ、原発の推進、その技術の海外への輸出を進めています。輸出する「原発の技術」、これがどこまでをさすのか分かりませんが、ついこの間九州電力の玄海原子力発電所3号機でプルサーマルの商業運転が開始されました。プルサーマルは通常のウランに使用済み核燃料から抽出したプルトニウムを1割加えています。プルトニウムは原爆の材料になるものですね。本来の「核燃料サイクル」は高速増殖炉「もんじゅ」でプルトニウムから投入量以上のプルトニウムが不思議なことに出てくるというもので、これを燃料に使えば夢のサイクルができる、というものだったようですがご存知のとおりの事故で頓挫しています。プルトニウムは前述のように原爆の材料なので国際的に余剰分を持たないことになっているそうで、そうすると再処理して抽出しちゃったたら使うしかないわけで。そういうわけでプルサーマル。あと40年は高速増殖炉は稼動しないようですし。むむう、なんだか原子力と心中する感じですな・・・まあ、それはいいとして国内の原子力関連メーカーは今やっきになって海外への売込みをしているわけなんですけどプルサーマルを軸とする日本の考え方がそのまま輸出されるといろんな国でプルトニウムができちゃう可能性はないのでしょうかねぇ・・・。心配。僕は原子力のことはまだ良く分かっていないのですけど、ここのところは師匠もだいぶ危惧しているようです。最近になって脱原発を決めていたドイツやスウェーデンでも脱原発政策の見直しがされるようになってきました。世界はやはり原子力を選ぶのでしょうか・・・いずれにしてもドイツやスウェーデンでは一度は市民が原発にNOをつきつけて政府を動かしてきた経緯があります。その点では僕も含めて日本では世論がまだきっちり形成されないまま産業界と政治家の思惑で進められているような感じがします。まずはよく「知ること」、そして「考えること」その意見を互いに「表現」し、市民が「つながる」こと。これが大事なんじゃないかと思いますね。こうしてできた「市民のチカラ」が世の中を動かしていくのだと思います2010/3/10 TAKE
2010年03月10日
コメント(2)
-
師曰く:「ペレットはグローバル化しやすい燃料」
師曰く、「最近流行のペレットはグローバル化しやすい燃料という 点でひとり反対キャンペーンをはっています」-----------------------------------------------------間伐材などをうまく利用しようということでペレット燃料が今、注目を集めていますね。木質ペレット推進協議会のWEBサイトから引用しますと・・・「ペレットは、再生可能で地球環境にダメージの少ない木材 を原料にした新しい燃料エネルギーです。原料には、間伐材 や製材端材が使われ、乾燥→破砕→圧縮することで小粒状の 固形燃料になります。また、灯油のような液体燃料と違い、 漏れたり染みたりする心配がなく、嫌な臭いもありません。 CO2削減に大きな効果が期待できるペレット燃料は、再生可能 な地上資源として、地球温暖化問題の解決策としても注目 されています。」 →http://www.woodpellet.jp/wppc/pellet01.htm国内の間伐材などを利用し、灯油よりも安く、扱いやすい。そして温暖化問題の解決にも貢献する・・・この意味で全くすばらしい燃料だと思うのですが・・・師匠は何を気にされているのかというと、この扱いやすさだと今は国産が中心でもそのうち例によって価格競争となって、そうすると外国、特に発展途上国の森林を食いつぶして輸入するという、いわゆるグローバル化が進む可能性が高い、という点なのですね。そのあたりを当事者の方々がよく理解し、何らかの歯止めをかける対策をしていればいいのですが、歴史を振り返るとたいていの場合、このままグローバルの波にのまれてしまうことが多いので、今からひとり警告をしている、ということなのですね。ですから、今ペレットストーブなどを使われている方、これから設置を考えている方には、ペレット燃料のバックグランドにあることをアタマの隅にでもおいておいていただいてグローバルの価格勝負にのらないようにしてもらえたらいいな、と思います。2010/3/10 TAKE
2010年03月10日
コメント(0)
-
師のコトノハ:『薪山』
こんにちは、TAKEです~那須では今日も雪が降り続いています。だいぶ積もりましたね。ホント今年は雪が多いですね~サテサテ、温暖化問題から森林の話が出てきたので師匠の提案する『薪山』をご紹介。これは薪を取るための山をつくろうということなんですけどこの『薪山』を作るメリットというのは1つにはエネルギーを薪から得て自給する、ということがありますけど、温暖化という点では前回書いたように循環型のカーボンニュートラルな燃料にできるということがありますね。具体的には麓から近い住居に近い付近の森林を薪用にします。薪程度の太さであれば6年程度で育つので、森林を6箇所に分けて、1年目は6分の1を使って、切り倒したら植林します。次は次の場所を切って・・・というふうにしていくと一回り回るときには最初の場所がちょうど育っている、というわけですね。昔はこれと同じようなものを『薪炭林』といって管理していたそうですね。「使った分植える」これが大切ですね。以前材木屋さんにお邪魔したときに「国産材が高いのは日本の森林が傾斜が大きいので搬送に コストがかかるから」そんなこんなで国産材が売れなくなり、間伐しない荒れた森林が増えちゃったわけですね。でも、これは住宅を作る材料として使おうとするからかなり太い木を切り倒してえいやこらさと引っ張り出さなきゃいけないからなんですね。この「薪山」のように麓でしかも薪程度に使うそんなに太くない木だから比較的簡単に運べるわけですね。この薪山に関連して師匠は薪利用を勧めるNPOを構想しています。これは師匠と辻信一氏の共著『テクテクノロジー革命』にも書いてありますのでそこから引用してみるとしましょう~「NPOで薪ストーブをつくる計画を進めています。ワークショップ で、間伐、薪割り、ストーブの設置、あるいはストーブでおい しい絶品の料理をつくるところまでトレーニングする。 検定 試験をして4級から1級までつけて、その後、実際の薪作り作業 という、生産のプロセスに移る。その生産では、4級の人は 自給600円、3級の人は自給800円、と実際にお金を支払う。 技を磨いて1級までいけば自給1200の仕事が得られる。 そういうふうにして薪を生産して、薪を1束200円で消費者に 売るんです。すると今は500円なんだけど、200円になれば ガスよりも薪ストーブのほうが安くなります。このビジネスを NPO法人でやれば、計算上はきっちり利益が残ります。地方の 若者は1級まで腕をみがいて、ローカルアントレプレナーとして、 地域ビジネスを展開していってもいいわけです。」エネルギーを自給しつつ、環境にも配慮、そして利益を出す地方特有のビジネス。すばらしい発想ですよね。将来こんなビジネスをする人が増えたら、なんかいい世界になるような気がしませんか?2010/3/10 TAKE
2010年03月10日
コメント(0)
-
師曰く:「成長した森林に二酸化炭素吸収効果はない」
師曰く、「成長した森林に二酸化炭素吸収効果はない」--------------------------------------------昨日はスコシ温暖化問題にふれました。温暖化問題が取りざたされるときに森林の二酸化炭素吸収の効果というのがでてきます。このときアタリマエのことなんですけど、多くの人がカンチガイしちゃっていることに「森があれば二酸化炭素が固定化される」という『誤解』なんですね。たしかに『森が育つ』ときには二酸化炭素を使って光合成をして炭化水素などのかたちで二酸化炭素が固定化されます。だから薪を燃やして二酸化炭素が発生しても「もともと森林が固定化した二酸化炭素だからプラスマイナスゼロだ」ということになるんですね。これを「カーボンニュートラル」というそうです。このWEBサイトがわかりやすいですね。http://www.wood-stove-life.org/eco/ec02.html『森が育つ』ときには二酸化炭素を吸収しますけどただ森があればいい、というわけではないのですね。師匠と辻信一氏の共著『テクテクノロジー革命』から引用すれば・・・「成長しちゃった杉の木を手付かずでほうっておいても、 昼間吸った二酸化炭素は夜に吐き出すだけだから、 二酸化炭素吸収効果なんてこれっぽっちもないんです」というわけ。そしてモウ一つ大事なのは、たしかに薪はカーボンニュートラルな燃料なんですけど、これが未来まで続くためには薪にしたぶん、また植えて、「成長する」=「二酸化炭素を固定する」期間を作ってあげないといけないわけですね。そうでないと大昔に固定化された化石燃料と同じで昔固定化した分を食いつぶしているだけ、ということになっちゃいます。だから、「使った分以上植える」これが大切なんですね。昔はこういう哲学が日本人にはあった、と師匠はよくおっしゃいます。技術はイロイロ進歩したけど、その分人間の知性や哲学は低下しちゃっている、そんな気もしますね。2010/3/10 TAKE
2010年03月10日
コメント(0)
-
師のコトノハ:『大気の窓』続編
こんばんは、TAKEです~。那須はだいぶ雪が積もっています。3月でも今年はまだまだ寒い日が続きますね。さてさて、前回の『大気の窓』の続編ということで、また師匠と辻信一氏の共著『テクテクノロジー革命』から放射冷却によるビルの冷房についてご紹介。これは非電化冷蔵庫と同じ原理でビルを冷房しちゃおう、というアイデア。引用しますと・・・「たとえばビルでは、夏は暑くてたまらないから冷房する。 これまでは否定しません。でも、どういうふうな冷房を すればいいかは、選択肢がたくさんあります。たとえば、 ビルの屋上は空が見えているわけだから、夜の間に放射 冷却を起こして、どんどん宇宙に熱を捨てるようにして 冷たい水を作っておいて、昼間の冷房に使うとかね。 あるいはビルを建てるときに真ん中に空気の通う道を 作り、自然対流の力で冷たい空気を吸いあげて、各部屋を 通過させるとかね。」むむう、ビルレベルの放射冷却冷房とは!デモこんなビルがたくさんできたら都会のヒートアイランド現象も緩和されそうな気がしますね。そういえば冷却水を天井に流すことでゆるやかに冷房する「放射冷房」なんていうのもあるそうですね。一般のクーラーのように風を起こして冷たい空気を送るよりカラダにいいみたいですね。サテサテ今年の夏は暑くなるのでしょうか?暑がりのTAKEには暑い夏はツライ季節ですね。2010/3/9 TAKE
2010年03月09日
コメント(0)
-
師のコトノハ:『大気の窓』
こんにちは、TAKEです~。今朝は『星空発電』をご紹介しました。これに関連しましてお次は『大気の窓』をご紹介したいと思います。非電化冷蔵庫も星空発電も放射冷却現象を利用したものでした。これらは10ミクロン程度の波長を持った遠赤外線としてエネルギーを宇宙へ放射しています。ちょっと大きなスケールで考えると地球全体としては太陽からのエネルギーを吸収してこれをまた宇宙へ放出する、ということを常にしています。スコシ前にブログでも取り上げた「ウィーンの法則」にしたがって6000℃弱の太陽からは0.48ミクロン程度の短い波長の光が放射されていて(これが可視光線ですね)、一方、地表の平均温度が15℃程度の地球からは11ミクロンをピークとした赤外線として放射しています。最近話題の二酸化炭素を主とした温室効果ガスは地球から放射されるこの赤外線を吸収して、また地球に戻してしまうので地球がこれまでよりあたたまる、というのが大まかな話ですね。じゃあ、非電化冷蔵庫や星空発電で赤外線を宇宙へ放射してもまた二酸化炭素が吸収して戻ってくるのでは?地球は冷えないのでは?という疑問がわいてきます。しかし、ジツは二酸化炭素の吸収波長は2.5~3ミクロン、4~5ミクロン付近にありますので11ミクロンぐらいのいわゆる遠赤外線であれば二酸化炭素をすり抜けて宇宙へ飛んでいくことができるのです。だから「地球を冷やせる」。地球温暖化問題で一番大切なこと、それを師匠は「大気の窓をふさがないこと」とおっしゃいます。これが塞がれてしまうと地球は冷えることができません。ここをよく理解しておかないと、たとえばオゾン破壊で問題のフロンが使用禁止になりましたが、代替フロンをさがして新しく作った物質がジツは大気の窓をふさぐものだった、なんてことになりかねません。地球を冷やす「大気の窓」、いつまでも開けていられるようにしていきたいものですね。くわしくは師匠と辻信一氏の共著『テクテクノロジー革命』を見てくださいね。2010/3/9 TAKE
2010年03月09日
コメント(0)
-
師のコトノハ:『星空発電』
おはようございます、TAKEです~。今日は師匠の言葉をご紹介。今回は「星空発電」。なんだかトテモロマンチックな名前ですね。この前ワークショップが行われた非電化冷蔵庫は「放射冷却現象」を用いてものを冷やす技術が使われていましたね。師匠はこの放射冷却に注目していまして、このエネルギー移動の力を利用したらどうかと考えています。その一つがこの「星空発電」。これは放射冷却によって起こる下向きの風を利用して風力発電するもので、星空が見えるような晴れた夜は放射冷却が起こりやすいので「星空発電」。師匠と辻信一氏の共著『テクテクノロジー革命』にも「地球を冷やす発電法」として紹介されています。具体的には・・・「高さ4メートルぐらいのガラスのピラミッドをつくって、 そこに20メートルの煙突のような筒をつける。昼間は 太陽熱で空気があたためられて、上向きの煙突効果とい うのが生まれ、煙突内に風速10メートルくらいの風が 吹くことになる。それで風力発電のタービンを回して発電 できる。 ~中略~ 昼は太陽熱、夜は放射冷却を使えば、稼働率がものすごく 大きくなるでしょう。夜は放射冷却で下向きの煙突で風を 起こし、昼は上向きの煙突で風を起こす。この風で発電をする。」 『テクテクノロジー革命』より引用このとき、放射冷却で宇宙へ放射されていく遠赤外線は約10ミクロンなので温室効果ガスの吸収波長とは異なっています。ゆえにエネルギーは宇宙の果てまで飛んでいくわけです。ということは、「発電しながら地球を冷やすことができる」訳ですね。なんだか希望がわいてくるお話ですね。ちなみにこの発電を山一つでやっちゃおう、という提案を師匠はアフリカ諸国に対して提案されています。標高1000mの禿山の中腹の1平方キロメートルを黒く塗り、その上にガラスをかぶせます。そしてその上下に500mの溝を掘り、蓋をして簡易の煙突にします。この斜面煙突に風力発電のタービンを設置すると昼は5万キロワット、夜は3万キロワットの発電ができ、たとえばセネガルの首都の使用電気量の半分がまかなえるそうです。砂漠が広がる国だからこそできる発電ですね。太陽光パネルを置くよりもずっと安上がりな発電。うまく広がってくれるといいですね。また、那須でもこのスモールタイプのものができたらトテモ愉しいことになりそうです~2010/3/9 TAKE
2010年03月09日
コメント(0)
-

弟子的 Before After 風呂小屋壁建て編
こんばんは、TAKEです~。今日は久しぶりに良く晴れて暖かな1日デシタ。風呂小屋建設も佳境に入ってまいりましたよ!今日の仕事っぷりをご紹介します~まず今日の朝の状態は・・・Before風呂釜もとりあえずの仕上げが終了しました。そして・・・夕方ごろあの林の向こうに見えるのは・・・ナンダコレハ!!今日は屋根までは時間が足りず、お休み明けに屋根を上げる予定デス。屋根が上がったらついに温水器が南向きの屋根に設置されるというわけですね。本日はまず南側の壁を上げて、その後時計回りに西→北→東と壁を次々とつなげていきました。南と西壁そして北と東壁南西角にお風呂があるので、その下が焚き口になります。温水器ではぬるいときはここで薪を焚きます~北側正面はこんな感じついに我々の手で小屋の骨組みまでできました!なかなか感慨深いですね。さすが2×4工法。くみ上げたらモウびくともシマセン~スバラシイ!休み明けは屋根上げて、太陽熱温水器、貯湯槽設置、それからタイル張りとつづいて、あとは内壁塗り、外壁づくり階段作りといったところですね。まだまだ先は長いです~建設の様子はまたブログにてお伝えしていきますのでお楽しみに~2010/3/8 TAKE 本日の体重 50.4kg
2010年03月08日
コメント(0)
-

風呂釜縁塗り、すのこ作り、見学会
Satoうです。本日も非常に微妙な天気でして、予報では雪と言っていたものの朝方みぞれがさらっと降った後は小雨が降ったり止んだり。本日は見学会なので、午前中は非電化工房のあちこちの掃除をし、昼食後、作業に入ったのでした。中途半端な天気のため、どうするか悩んだのですが、昨日も天気予報が急変していたので、作業を決行することに。2組に別れ、一組は風呂小屋のモルタル塗り。昨日塗った部分で足りない部分を重ね塗りし、釜を入れ、縁をまたモルタルで塗りました。一方の組はアトリエ裏の新倉庫設置予定地に砂利を敷く作業を決行。以前買った砂利が山盛りになっている場所から軽トラに積んで移動し、砂利敷きをしたのでした。しかし、4人もいるからいずれの作業もはやばやと終わってしまい、手が余ったので、すのこ作りも決行。すのこは脱衣所の床として使うものです。すのこ作りは時間切れで中途で終了。夕方からは見学会参加者の方たちとの交流会でした。参加者の中には田舎で暮らしたいけど仕事がないと、ちょっと悩んでいる方もいました。いずれはそうした人たちの力に我らがなれるようになるといいのですが、今は修行中の身で、まだまだ力が足りませぬ。修行も残すところあと半年。どこまでいけけるのやら。今は外で雪が降っています。明日は曇りの予報ですが、果たしてあたるのかな?2010.3.7 Sato
2010年03月07日
コメント(0)
-

弟子的 Before-After 風呂小屋編
こんばんは、TAKEです~最近は夜遅くまで師匠の哲学講義が続くことが多いですね。気がつくとモウこんな時間に・・・修行も半年が過ぎ、折り返し地点を回りマシタ。あとの半分も悔いのないようにイロイロ吸収していきたいと思いマス!サテサテ、今日はちょっと雨も降りましたがなんとか風呂小屋建設ガンバリマス。朝食後、昨日燃やした耐火モルタルを師匠がチェック。ちょっとボロボロですけどなんとか師匠のGOサインが出ましてこれでいくことに。耐火モルタルは未だイマイチ使い方がよくわかりませんね。もともと耐火煉瓦用をコンクリートブロックに使うのが無理があるのかな?風呂釜は丸いので四角いコンクリートブロックの塀の4隅をブロックとモルタルで埋めていきます。(そうしとかないと下で火を焚くと炎で火あぶりに・・・)というわけでまたまた登場ディスクグラインダー!コンクリートブロック切断用のディスクに交換します。刃の交換とセッティングもすばやくできるようになりました。今回は4隅にブロックをおいて、その上にモルタルをつんでいくことにしましたので、ブロックが釜に当たらないよう斜めに切ります。斜め切りだと奥までは完全に切断できないので、切れ目をたくさん入れて、あとはカナヅチでたたいて壊していきます。BeforeAfterなかなかなできばえ!とりあえず今日はモルタルが乾燥しないと次に進めないとのリーダーの判断で細かい残り仕事を片付けることに。TAKEはゲルの扉の補修をすることに。モンゴルから輸入したこのゲルは多湿な日本では木材が変形してしまって扉が閉まらなくなっていたんですね~Before大きくなってしまった分をかんなとやすりで削っていきます~モウスコシ!結構削らないとだめなんですね~2時間半ほど格闘しましてようやっと!!!ぴったんこ~明日の見学会にいらっしゃる方は扉の閉まり具合を体感ください(なんちゃって)。その他電動工具台もいくつか新設したりしました。こんなのもちゃちゃっと作れるようになりました。ほんと、修行の成果です。明日は予報では雪になるとか。見学会にいらっしゃる方はお気をつけていらしてくださいね。2010/3/6 TAKE 本日の体重52.4kg(復活してキマシタ)
2010年03月06日
コメント(1)
-

弟子的 Before-After 風呂小屋編
こんばんは、TAKEです~本日は久々にすっきり晴れましていいお天気でした!モウ春が来た感じですね(でも来週は雪だとか・・・)~いいお天気なので今日は風呂小屋建設日和です。まず朝の感じはこんな感じBefore今日は根太の上に乗っけるベニヤとその上のスノコ用の材木の切り出しをしました。平行して耐火モルタルの焼成です!いよいよですね~燃え上ガレ!(←危)しかし・・・な~んかボロボロきてますねどうしたもんでしょうね~耐火モルタルはなかなか大変そうですずっと火を焚いていたのでベニヤもスノコものせるのは明日になりますね。カマができあがれば壁がはれるのですけどねサテサテどうなることやら?2010/3/5 TAKE
2010年03月05日
コメント(0)
-

報告会&風呂小屋根太がけ・耐火モルタル
ども、satoです。本日(3/4)は、午前中から報告会がありました。2月分の報告ということで、それぞれがまとめたものを発表します。同じことを学んでいるし、発表内容も指定されているので、いろいろかぶる部分はあるのですが、誰かが発表したものと同じ内容でも省略せずに発表するというスタイルをとっているので、けっこう時間がかかります。今回は9時半頃から始めて4人の発表が終わったのが13時半。一人あたり1時間くらいかかっています。その後、昼食をとったらもう15時になっていて、作業はそれからとなりました。本日も引き続き風呂小屋作業。今にも雨が降り出しそうな天気でしたが、なんとか2時間ほどは作業できました。まずはこの間塗った耐火モルタルがどうなっているかを確認。今回はしつこくこすりつけるようにして塗ったところ、うまく塗れているところは壁にだいぶ張り付いていました。しかし、パネルを作って流し込んだところは、ぜんぜんダメ。もともと耐火モルタルは普通のモルタルと違って水硬性(水と混ぜることによって固まる性質)ではないらしいのですが、パネルを剥がすと木のパネルの方にくっついて見事にコンクリ壁から剥げてしまいました。モルタル自体もまだまだやわらかかったので、パネル方式はやめてこれもこすり付ける方式に変更。再度塗りなおしたのでした。一方、土台の方では、土台の上に根太を固定していく作業をしました。根太には2×4を縦に使ってコーススレッド(ネジ式の釘)で土台に打ち付けます。こういった作業は慣れたもんなのでさっさとできてしまいました。その他、壁パネルの仕上げをしたところで、降雨になったので作業終了。明日も風呂小屋の続きです。2010.3.4 sato
2010年03月04日
コメント(0)
-
師曰く:部下の法則
師曰く、「会社で研究室長をやっていたとき部下をつけて欲しい、という研究員が 多くいたけれども、部下を増やすとたいていの場合は効率が下がってしまった」-------------------------------------------------------------------------ふつう、部下を増やしたら効率よく仕事が回って成果が上がりそうですけどなぜなのでしょう?部下を増やした際に起こることは、部下の仕事をマネジメントする、という仕事が生じてしまうことなんですね。これがジツは結構大変なんですね。自分ひとりでやる分にはとても効率の高い仕事をする研究員でも自分の部下に自分と同じ効率では仕事をさせることが難しいのです。自分が思っていることを部下が完全には理解してくれませんし、思い通りには動いてくれません。そして、マネジメントに時間をくわれてしまい、自分自身の効率は以前より下がり、思い通りにあがらない業績に上司からプレッシャーがかかり・・・だから、部下を増やす場合にはこれをうまく使う方法論が必要なんですね。ただ増やしただけでは効率は落ちてしまうのです。上記は競争社会の話で僕も会社員のときは実験の助手の方などいましたけれどなかなかうまく仕事をしてもらうのは難しかったですね。翻って共生社会では、リーダーはいつもスタッフがあそばず、いい雰囲気で最大の仕事ができるように目配り、気配りをしなければいけません。このときは自分では仕事はせずに周りがうまくいくようにすることに意識を集中する、というのが師匠の方法論ですね。2010/3/3 TAKE
2010年03月03日
コメント(0)
-
師曰く:『愉しさ』を提供するには
師曰く、「ビジネスでは『愉しさ』の提供を第一に考えないといけません。 『愉しさ』を提供するには次のような順番で考えるといい。 1)ぬくもりのあるイイ人間関係、 2)おいしさ 3)心地よい作業 4)達成感 」-----------------------------------------------------------師匠は『愉しさ』をイツモ第一にもってきますけれども、じゃあ『愉しさ』というのはどうやってうまれるのだろう?というギモンの答えが上記のことばですね。愉しさを生じさせるための第一はやっぱり人間関係。そしておいしさ。感性に訴える部分ですね。ここはトテモおもしろくて、師匠が昔空気清浄機を販売していたときに集めた人の6割に買わせるというスゴイ営業販売をする人が居たそうなのですが、その手法は会社のお昼時にお弁当を無料で配布して話を聞いてもらうというものだったそうです。そのお弁当が!!!!!!というぐらいウマイのだそうで!師匠がうなったぐらいなので相当なものなのでしょう~それを食べちゃうとみんな買う気になっちゃうというすごいマジック。食後という時間はただでさえおおらかな時間でそこに食べたこともないウマイ弁当が出てくると・・・まあ、そのくらい「おいしさ」というのはスゴイ要素なんですね。ワークショップなどでもおいしいお昼やおやつをだすとみんな気分がよくなってやる気と愉しさがわいてくるのでしょう~そして、ここちよい作業と達成感。体全体、感性でもって体感できること、そこに愉しさのエッセンスがありそうですこんなビジネスが増えたらほんといい社会になるのになぁ2010/3/3 TAKE
2010年03月03日
コメント(0)
-
師曰く:支出を4割、収入を半分にする工夫をする
師曰く、「今の社会では実質経済が全世界で40兆ドル、これに対して金融経済が630兆ドルで これが平和を乱す大きな原因になっている。経済そのものをもっと 小さくしていったほうがいい。個人レベルで言えば、10年間で 支出を4割に、収入を半分にする工夫をしたらどうかと思っています。」--------------------------------------------------------------------収入を半分にする工夫!?なんだか不思議な言葉ですね・・・デモよく話を聞いてみると、ジツはこういうことなんです。都会の生活は高収入、高支出なんですね。だからがんばればお金はたまるけど誘惑も多いので結局とんとんもしくは赤字になる。特に収入がこれ以上伸びがたくなってきた今の社会ではこれまでどおりの支出をしていては全く生活していけません。これに対して、例えば田舎にある資源をうまくつかえば、食料やエネルギーなどを自給できるので低収入ながら低支出、うまくやれば貯金ができるそんな暮らしができるのではないか、と師匠はおっしゃいます。そして支出を4割に減らしていくことは愉しくできる範囲ではないか、とも。これから日本経済は縮小していく方向で、これはドウニモ変えようがなさそうです。そんな中で愉しく生きていく方法がいま求められていますね。そういう暮らしをこれから自分で実践して、皆様にもお伝えしていければいいなとおもいます~2010/3/3 TAKE
2010年03月03日
コメント(0)
-
師曰く:フェアトレードの原則
師曰く、「フェアトレードには3つの要素が不可欠。1つは公平、2つ目は公正 3つ目が持続性。この3つ目がなかなかムズカシイ」---------------------------------------------------------------昨今では途上国のものを対等な立場で購入する、といういわゆる「フェアトレード」があちこちで行われるようになってきました。でもこれ結構うまくやらないと途上国に大きなダメージを与えてしまうことがあるので注意が必要なんですね。それは前述の3つの要素の3つ目。『持続性』が維持されないから。例えば「ナタデココ自殺」。日本で一時期爆発的なブームになった「ナタデココ」。当時日本の会社は競って途上国からナタデココを買い漁ったそうです。10必要なら15、15必要なら20、というように・・・これを受けた途上国の方は伝統農業をやめ、ナタデココの製造・販売をするようになりました。その結果、ブームが去った後、借金と在庫だけが残り不幸にも自殺者が増加してしまった、というわけです。フェアトレードも需要を常に一定に維持しないと、大きさはともあれナタデココと同じ運命をたどることになります。10の需要には5を供給し、イツモ品薄な状態にするぐらいがちょうどいい、そう師匠はおっしゃっています。2010/3/2 TAKE
2010年03月02日
コメント(0)
-
師曰く:芸者の着物と農家の機械
師曰く、「芸者の着物と農家の機械」------------------------------------------------------------今の農業の限界を説明するときに師匠が良く使われることばです。まあようするに今の農業というのは大型機械を買って、農薬、化成肥料、種を買って成り立っているわけで、全てに莫大なお金がかかっています。大きな機械を買ってしまった以上もうそこから抜け出せない、借金地獄になってしまう、というわけですね。これからの農業はこうではいけない、分を超えた技術を導入するのはあまりよろしくない、適正な技術の利用形態が必要だ、と師匠はおっしゃいます。師匠は現代の技術を批判されることが良くありますが、イツモその際に付け加えるのは「技術そのものを批判して、昔に帰れ、といっているわけではない」トイウコト。『非電化は否電化に非ず』とはそういうことですね。技術には人を幸せにする側面と不幸にする側面があります。どこまで使うべきか、どうあるべきか「適正」なラインをどこかにひかなければいけません。その目安が「環境負荷」であり「循環型であるか?」という視点。例えば耕運機でも手押しタイプのものなら安く手に入りますし、エネルギー使用量もさほど大きくありません。師匠の計算であれば畑のごく一部をサトウキビにしてバイオエタノールでもちゃっとつくれば補えるレベルだそうです。しかし、これがあるかないかで作業にかかる負荷は天と地との差がるんですね。これがあればツライ労働が愉しくなる。この「手押しタイプの耕運機」レベルがまさに『適正技術』というやつなんでしょうね。そういえば視点を他に転じてみると、「借金で縛られてしまう」という点では「サラリーマンの住宅ローン」というのも同じ部類に入りそうですね。2010/3/2 TAKE 本日の体重 50.4kg
2010年03月02日
コメント(0)
-
師曰く:結果を見てものをいえば人は神になれる
師曰く、「結果を見てものをいえば人は神になれる」-------------------------------------------やる前には何も言ってなかったのにやった後に「あ~俺もそう思ってたんだ~」とか「それじゃ失敗するでしょ」とか言う方たまにいらっしゃいますね。ソウイウコトは先にいえなければ全く意味がありません。結果が出てからなら誰でも物知り顔で批評できます。答えがもうでてるんだから当然ですよね。まさに『神様』になれる。まあ世の中そういう人は多い、というのが「リアリティ」なので神様気取りでなんかいってるな~ぐらいに思っておくのが吉ということでしょう~2010/3/2 TAKE
2010年03月02日
コメント(0)
-
師曰く:発明家と学者の物事に対するスタンスのチガイ
師曰く、「学者は狭い領域をどんどん掘り下げて新しい原理、法則を『発見』する。 これに対して発明家はアルモノとアルモノを組み合わせて新しいものを 産み出す。だから発明家はつねに物事を『組み合わせが生じやすいように』 インプットしていくのです」--------------------------------------------------------------------発明家と学者は似て非なるものなんですね。発明家は新しいものを産み出しますが、原理、法則を『発見』するわけではないのです~。師匠は大企業を出て発明家へ転身したときからずっと上記の方法でインプットをされてきました。インプットのときに大事なのは「メカニズム、本質をきっちり正確に理解するということ」と「五感で感じられる作業を付け加える」ということなのだそうです。アタマでの理解とカラダでの理解。これがあってこそ『感性』を第一とする発明が生まれてくるのですね。師匠は「発明家なんて誰でも簡単になれる、ただ『組み合わせが生じやすいように』インプットすればいいだけなんだから・・・」とおっしゃいますが、その「だけ」がいかに難しいことか・・・・師匠の知識、知恵の量とアタマの回転力は半端ではありません。とりあえず僕は発明家にはなれそうにないですけどたま~に発明家的な考え方をしてみるのは有用な方法な気がしますね。まあ、まずは発明家師匠のことばをみなさんにお伝えしていくこと、それが今の僕にできること、デスネ2010/3/2 TAKE
2010年03月02日
コメント(0)
-
師曰く:試作品に対する技術屋と発明家のチガイ
師曰く、「技術屋は試作品は新しい機能を示すだけ、みてくれは最終品でどうにかする というスタンスだけれど、発明家は演出を一番大事にする。試作品でも ステキステキなものをつくる」----------------------------------------------------------------------僕もついこの間まで技術屋として製造業の会社に居たので技術屋の気持ちは分かるんですね。これが新しい機能なんだ!ここをみてくれ、みてくれはあとでど~にでもなるデショ!と。デモ発明家は「試作品」だからこそ見てくれも含めた「演出」に力を入れます。古来どの発明家もそうなんですね。エジソン然り、東京電灯の藤岡市助然り・・・新しいものを世の中に提供するとき、一般の人はそれがなんなのか、どんな価値を生むのか、それが全く分からないわけですね。そこに機能がどうこうといっても理解してもらえないわけで上手に演出して「感性」に訴えるコト。これが発明家のすることなんですね。2010/3/2 TAKE
2010年03月02日
コメント(0)
-
師曰く:決めるのは感性、否定するのは理性
師曰く、「ものを買うときは、まず「すごい」「ステキ」という感性があって「これが欲しい」となる。けれどここで「お金が・・・」「時間が・・・」という理性による否定が生じる。ものを買ってもらうにはまず感性に訴えることと理性による否定を否定する、つまり買わない理由を否定する事がトテモ大事」------------------------------------------------------いわれて考えてみるとまさにそうなんですね。うぉおお欲しい!という想いは師匠言うところの『作り手と買い手の感性の共鳴現象』で、これがないとものは売れないのでしょうね。そして忘れてはいけないのが、その後に来る理性による否定をどうにかしないといけない。あらかじめそこを考えた商品設計というものが必要なのでしょう~シカシ、理屈は分かってもなかなか『感性の共鳴現象』を起こす商品を生み出すのは並大抵ではないですよね2010/3/2 TAKE
2010年03月02日
コメント(0)
全231件 (231件中 1-50件目)
-
-

- 今日のこと★☆
- 11月14日のツキアップ
- (2025-11-14 08:50:52)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-13 18:39:04)
-
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 9~10店舗目 ロイズガーデン2026カレ…
- (2025-11-14 14:35:53)
-








