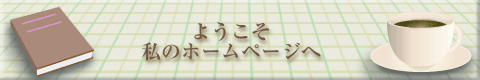天体写真1
天体写真を初めておこなったときからこれまでに撮影した天体写真を、スキャナーでとりこみ撮影時の感想等とともに時系列で掲載してあります
スキャナーで取り込んだ画像は多少の画像処理をしてあるので、微光星や星雲などは実際の
写真より良く見えているものもあり、これは新たな発見でした
ハレー彗星 1986.3
[ 50mm F2.0 P-2赤道儀+FC-65で手動ガイド 露出約5分 ISO400]
 上の写真で気を良くして、回帰中のハレー撮影に挑みました今度は固定撮影ではなく、
上の写真で気を良くして、回帰中のハレー撮影に挑みました今度は固定撮影ではなく、
P-2赤道儀にカメラを乗っけて、FC-65で星を確認しながらの手動ガイド撮影です。
極軸のセットや、ガイドずれの許容量等詳しく知らなかったので、適当な間隔で
ガイドしましたが結果は以下のとうりで、星が流れてしまってます。
ガイドって結構こまめにやらないとだめってことを初めて知ったのでした。しかし
右下になんとかハレーが写っていたので(わかりますか?)取り合えずは満足
百武彗星 1996.3.27
[ 50mm F1.4 固定撮影 露出1分 ISO400 ]
 さて、期待はずれに終わったハレーにもう大彗星は見れないのだろうと思っていた
さて、期待はずれに終わったハレーにもう大彗星は見れないのだろうと思っていた
ところにまさに彗星のように現れ、そして駆け足で去っていった大彗星でした
自宅からでもそれなりによく見えた彗星でしたが、この夜は暗い場所を求めて近く
の山に入りました。真っ暗な空で見た彗星の姿は無気味な化け物のようでもあり、
彗星が古来より不吉の象徴とされていた事に納得してしまいました
さらに条件の良い場所では写真左に見えている北斗七星を突き抜けて、この画面の
2倍くらいの長大な尾が見えたということでした
夏の天の川 白鳥座付近 1996.9
[ 50mm F1.4 P-2赤道儀+HD-5+FC-65で電動ガイド 露出30分 ISO400]
 百武彗星では準備不足で固定撮影しかできなかった為、次のヘール・ボップ彗星
百武彗星では準備不足で固定撮影しかできなかった為、次のヘール・ボップ彗星
に備えて、P-2赤道儀にモータードライブ(HD-5)を追加して電動ガイドに対応しました
電動ガイドでは星の動きに合わせて赤道儀が極軸を中心に一定速度で回転しますので、
ガイド修正が非常に楽になり、30分とかの長時間ガイドが労せずできるのです
しかし、意に反してなかなか思うような出来にはならず、星を点に写すことは一筋縄に
いかないことを実感しました
M45 すばる 1996.9
[ FC-65(500mm F8.0)直焦点撮影 P-2赤道儀+HD-5で電動ノータッチガイド 露出30分 ISO400 ]
 FC-65に使われているフローライトレンズは写真撮ってこそ意味があるものなので、なん
FC-65に使われているフローライトレンズは写真撮ってこそ意味があるものなので、なん
とかこの鏡筒で直焦点撮影をしたかった
直焦点撮影とはカメラレンズの代わりに望遠鏡の対物レンズを使う撮影のことで、通常
望遠鏡を覗く時に使うアイピース(接眼レンズ)をはずし、そこに1眼レフカメラ本体を
取り付けることで、撮影行います
当時はガイド鏡を持っていなかったので無謀にもノータッチガイドを強行しました
P-2赤道儀ではノータッチは200mmまでなので、無茶は承知の上でした。
これはその中でなんとか見れる貴重な1枚ですが、ガイドさえ成功すれば雑誌で見たよう
な写真を自分で撮ることが出来ることに(レベルは違いますが)それなりに満足しました
月 1996.9
[ FC-65(500mm F8.0)拡大撮影 P-2赤道儀 露出1/125??? ISO400 ]
 ガイド撮影にそれなりに満足していましたが、やはり1枚撮るのに30分近くかかるのは
ガイド撮影にそれなりに満足していましたが、やはり1枚撮るのに30分近くかかるのは
大変であるので、時間的には短時間で済む月の拡大撮影に挑みました
拡大撮影は直焦点撮影と違いアイピースはつけたままで、その後ろにカメラ本体をセット
して撮影するもので、直焦点撮影より拡大率の高い撮影ができます
しかし、拡大撮影ではピントあわせが非常にシビアで満足できるレベルにピントをあわせ
る事はできませんでした
これまではカメラファインダーでピントだしをしていましたが、やはりそれではダメで、
ナイフエッジ法とか、さらに高精度のピントだし方法が必要なのだと思ったものでした
最近では拡大撮影はデジタルカメラで行うのが主流で、デジタルカメラの場合ピントを
確認しながら撮影が出来るので、簡単で綺麗に撮影できるとのこと、今後やってみようと
思っています
へール・ボップ彗星 1997.3.30
[ 105mm F4.5 P-2赤道儀+HD-5+FC-65で電動ガイド 露出約5分 ISO400 ]
 百武彗星より先に発見されていて、大彗星となる事が早くから予想されていた彗星です
百武彗星より先に発見されていて、大彗星となる事が早くから予想されていた彗星です
天文界では期待とは裏腹にという事が多々あるのですが、この彗星は期待にたがわず
世紀の大彗星となりました
尾の長さでは百武彗星ほどではなかったのですが、市街地や車を運転しながらでも見える
という非常に明るい彗星で、写真では青く写るイオンテールと白いダストテールが綺麗
にV字となった姿を1ヶ月以上にわたり夕方の西の空に見ることが出来ました
電動化したP-2赤道儀にカメラ2台を載せて、約1ヶ月間撮りまくりました
[ 28mm F3.5 P-2赤道儀+HD-5+FC-65で電動ガイド 露出約5分 ISO400 ]
 この時期たまたま東京に出かけることがあったのですが、都内でも肉眼で彗星を確認でき、
この時期たまたま東京に出かけることがあったのですが、都内でも肉眼で彗星を確認でき、
彗星の明るさを再認識したのですが、同時に都会の空はこんなに星が見えないのか、とい
うことも実感したのでした
画面中央右よりにW字のカシオペアが見えていますので
彗星の大きさを想像してみてください
スキャナーで取り込んだ画像は多少の画像処理をしてあるので、微光星や星雲などは実際の
写真より良く見えているものもあり、これは新たな発見でした
北斗七星
1986.3
[ 50mm F2.0 (F5.6?) 固定撮影 露出約5分 ISO400 ]

来るハレーの回帰に備えて初めてカメラを夜空に向けて撮った写真で、
私の天体写真の原点といえる写真です
1眼レフに50mmの標準レンズを三脚に固定しての撮影(=固定撮影)
できたプリントを見て、星って以外に簡単に写ることにびっくりしました
[ 50mm F2.0 (F5.6?) 固定撮影 露出約5分 ISO400 ]

来るハレーの回帰に備えて初めてカメラを夜空に向けて撮った写真で、
私の天体写真の原点といえる写真です
1眼レフに50mmの標準レンズを三脚に固定しての撮影(=固定撮影)
できたプリントを見て、星って以外に簡単に写ることにびっくりしました
ハレー彗星 1986.3
[ 50mm F2.0 P-2赤道儀+FC-65で手動ガイド 露出約5分 ISO400]
 上の写真で気を良くして、回帰中のハレー撮影に挑みました今度は固定撮影ではなく、
上の写真で気を良くして、回帰中のハレー撮影に挑みました今度は固定撮影ではなく、P-2赤道儀にカメラを乗っけて、FC-65で星を確認しながらの手動ガイド撮影です。
極軸のセットや、ガイドずれの許容量等詳しく知らなかったので、適当な間隔で
ガイドしましたが結果は以下のとうりで、星が流れてしまってます。
ガイドって結構こまめにやらないとだめってことを初めて知ったのでした。しかし
右下になんとかハレーが写っていたので(わかりますか?)取り合えずは満足
百武彗星 1996.3.27
[ 50mm F1.4 固定撮影 露出1分 ISO400 ]
 さて、期待はずれに終わったハレーにもう大彗星は見れないのだろうと思っていた
さて、期待はずれに終わったハレーにもう大彗星は見れないのだろうと思っていたところにまさに彗星のように現れ、そして駆け足で去っていった大彗星でした
自宅からでもそれなりによく見えた彗星でしたが、この夜は暗い場所を求めて近く
の山に入りました。真っ暗な空で見た彗星の姿は無気味な化け物のようでもあり、
彗星が古来より不吉の象徴とされていた事に納得してしまいました
さらに条件の良い場所では写真左に見えている北斗七星を突き抜けて、この画面の
2倍くらいの長大な尾が見えたということでした
夏の天の川 白鳥座付近 1996.9
[ 50mm F1.4 P-2赤道儀+HD-5+FC-65で電動ガイド 露出30分 ISO400]
 百武彗星では準備不足で固定撮影しかできなかった為、次のヘール・ボップ彗星
百武彗星では準備不足で固定撮影しかできなかった為、次のヘール・ボップ彗星に備えて、P-2赤道儀にモータードライブ(HD-5)を追加して電動ガイドに対応しました
電動ガイドでは星の動きに合わせて赤道儀が極軸を中心に一定速度で回転しますので、
ガイド修正が非常に楽になり、30分とかの長時間ガイドが労せずできるのです
しかし、意に反してなかなか思うような出来にはならず、星を点に写すことは一筋縄に
いかないことを実感しました
M45 すばる 1996.9
[ FC-65(500mm F8.0)直焦点撮影 P-2赤道儀+HD-5で電動ノータッチガイド 露出30分 ISO400 ]
 FC-65に使われているフローライトレンズは写真撮ってこそ意味があるものなので、なん
FC-65に使われているフローライトレンズは写真撮ってこそ意味があるものなので、なんとかこの鏡筒で直焦点撮影をしたかった
直焦点撮影とはカメラレンズの代わりに望遠鏡の対物レンズを使う撮影のことで、通常
望遠鏡を覗く時に使うアイピース(接眼レンズ)をはずし、そこに1眼レフカメラ本体を
取り付けることで、撮影行います
当時はガイド鏡を持っていなかったので無謀にもノータッチガイドを強行しました
P-2赤道儀ではノータッチは200mmまでなので、無茶は承知の上でした。
これはその中でなんとか見れる貴重な1枚ですが、ガイドさえ成功すれば雑誌で見たよう
な写真を自分で撮ることが出来ることに(レベルは違いますが)それなりに満足しました
月 1996.9
[ FC-65(500mm F8.0)拡大撮影 P-2赤道儀 露出1/125??? ISO400 ]
 ガイド撮影にそれなりに満足していましたが、やはり1枚撮るのに30分近くかかるのは
ガイド撮影にそれなりに満足していましたが、やはり1枚撮るのに30分近くかかるのは大変であるので、時間的には短時間で済む月の拡大撮影に挑みました
拡大撮影は直焦点撮影と違いアイピースはつけたままで、その後ろにカメラ本体をセット
して撮影するもので、直焦点撮影より拡大率の高い撮影ができます
しかし、拡大撮影ではピントあわせが非常にシビアで満足できるレベルにピントをあわせ
る事はできませんでした
これまではカメラファインダーでピントだしをしていましたが、やはりそれではダメで、
ナイフエッジ法とか、さらに高精度のピントだし方法が必要なのだと思ったものでした
最近では拡大撮影はデジタルカメラで行うのが主流で、デジタルカメラの場合ピントを
確認しながら撮影が出来るので、簡単で綺麗に撮影できるとのこと、今後やってみようと
思っています
へール・ボップ彗星 1997.3.30
[ 105mm F4.5 P-2赤道儀+HD-5+FC-65で電動ガイド 露出約5分 ISO400 ]
 百武彗星より先に発見されていて、大彗星となる事が早くから予想されていた彗星です
百武彗星より先に発見されていて、大彗星となる事が早くから予想されていた彗星です天文界では期待とは裏腹にという事が多々あるのですが、この彗星は期待にたがわず
世紀の大彗星となりました
尾の長さでは百武彗星ほどではなかったのですが、市街地や車を運転しながらでも見える
という非常に明るい彗星で、写真では青く写るイオンテールと白いダストテールが綺麗
にV字となった姿を1ヶ月以上にわたり夕方の西の空に見ることが出来ました
電動化したP-2赤道儀にカメラ2台を載せて、約1ヶ月間撮りまくりました
[ 28mm F3.5 P-2赤道儀+HD-5+FC-65で電動ガイド 露出約5分 ISO400 ]
 この時期たまたま東京に出かけることがあったのですが、都内でも肉眼で彗星を確認でき、
この時期たまたま東京に出かけることがあったのですが、都内でも肉眼で彗星を確認でき、彗星の明るさを再認識したのですが、同時に都会の空はこんなに星が見えないのか、とい
うことも実感したのでした
画面中央右よりにW字のカシオペアが見えていますので
彗星の大きさを想像してみてください
© Rakuten Group, Inc.