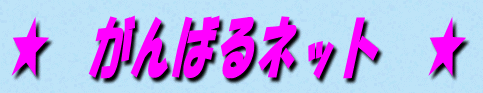「自己責任論」批判 決定版
http://plaza.rakuten.co.jp/ksyuumei/diary/2004-04-18
「自己責任論」批判 決定版 05月19日(水)
昨日発売の「サイゾー」6月号に、宮台真司氏と宮崎哲弥氏の対談が掲載されている。ここでは、「自己責任論」批判の決定版を語ると、宮台氏は予告していたが、予告通りの見事な論理展開をしていると僕は思った。
批判のポイントの決定的な点は、宮崎氏の次の言葉だろうと僕は思った。
「そう、結局、ヴォランティアやジャーナリズムが、この国では重視されていないんです。特に個人やフリーでやっていると、趣味以外の何ものでもないと看做される。おカミや会社の「仕事」や「用」だけがパブリックで、いかに公的な動機に駆動されてやっていたとしても、個人でやっている限り私的趣味なんですね。私的趣味で、おカミやお役人様に迷惑をかけ、血税を無駄に浪費させて、まことにケシカランと言うわけですね。欧米とは「公私」の観念が逆になっている。
ただし、日本的なコンテキストを解説すれば、人質連中は「自分探し」というウルトラ・ブライヴェートな理由でやってる自己満足野郎だろ、と言うふうに見えてしまう。実際、彼らの甘さ、未熟さは覆いようがない。しかし、リベラリズムが可謬性を前提とする価値である以上、少なくとも公的に彼らの「愚かさ」を非難することは出来ないはずです。」
今回のばかげた「自己責任論」の特徴は、一度としてまともに人質たちの責任が論議されたことがなかったことだ。宮崎氏も指摘しているように、人質たちに甘さがあったことは確かで、それがなければ拘束ということは避けられただろう。しかし、その甘さは、積極的な公的目的(パウエルさんが言うところの「良い目的」であり、自分だけのためにやるのではなく、多くの人の利益につながる目的)を持つもであれば、「可謬性を前提とする価値」で許容される甘さであり失敗だったのではないだろうか。
だから、たとえ甘さがあろうとも、人質の無事を願い、その救出に全力を尽くすというのが、民主主義国家としての民度を表す態度だったはずだ。救出の論議はそっちのけで、甘さだけをたたくなんてことは、先進資本主義の民主主義国家ではあり得なかったことだ。
このようなことが起こった背景には、日本社会における「公私」の考え方と、欧米社会のそれとが全く逆だということが指摘されている。その指摘はまことにもっともなことで、そう考えると、一連の「世論」(僕は、これを必ずしも本当の意味での多数者だとは思っていない。神保哲生氏が語るように、ラウド・マイノリティ(声が大きいだけの少数者)ではないかと思っているので、「」付きの言葉を使っている)が人質バッシングに動いたのが理解できる。
高遠さんがイラクへ向かったのは、イラクで高遠さんを待っている子供たちがいたからである。高遠さんは、子供たちのために働いていた。そこに、自己満足が全くないとはいわない。でも、自己満足があったからと言って、子供たちのために働いたという価値が減るものなんだろうか。子供たちは、心から高遠さんの無事を願っていた。それだけ、高遠さんの活動は彼らに受け入れられていたのだ。たとえ自己満足であろうとも、これだけ感謝される活動が、なぜ批判されなければならないのだろう。
そのような活動をしたいと思いながらも出来ないでいる人間よりも貴い行為ではないか。ましてや、そんな活動をしようとも思わない連中よりも遙かに立派ではないか。そんな連中は、一度も自己満足を得ようとせずに生活しているのだろうか。立派な目的のために自己満足を求めることこそ、パウエルさんが言うような賞讃されるべき行為ではないのか。
今井君の行動も、今井君自身の自己満足にとどまるものではない。たとえ自己満足があったとしても、彼の報告する「劣化ウラン」の問題は、多くの人に役に立つものであるはずだ。ジャーナリストの郡山さんの活動も同じだ。その後拘束された安田さんや渡辺さんにも、すべて共通してこのようなことが言える。
彼らの甘さをたたくのは、他人事として冷たい目で眺めればいくらでも出来るだろう。結果的にミスを犯したのだから。しかし、上のように考えれば、彼らのミスは、積極的な良い目的の過程で起こった、前向きのミスであって、これからの活動の参考にすべきミスなのだ。ただたたくためにそれを分析するようなミスではない。
宮台氏によれば、今井君と郡山さんの記者会見は2回行われたそうだが、その二つにははっきりと違いが見えたということだ。最初の記者会見では、日本のマスコミ記者が中心で、「迷惑をかけやがってこの野郎、おまえらに責任はないのか」という雰囲気だったらしい。それに対して、2回目の記者会見は外国人記者クラブだったらしいが、「危険を逃れて本当に良かった。ご苦労様。君たちの経験を僕らの参考にさせてくれ」という、共感を呼ぶような雰囲気の中で行われたらしい。これが世界の常識だろう。
日本社会の背景を語って、補足するような考えを述べている宮崎氏の次の言葉も印象的だ。
「こういうことを考えてみたらどうでしょう。もし人質が商社や石油会社なんかの社員だったらどうか。日本中から同情が寄せられたんじゃない?彼らがヴォランティアやジャーナリストだったから、こうも非難される。「用もないのに、自分の信念とやらのために危険地帯でのたくってるようなバカを救ってやる必要なんかあんのかよ」というわけ。ところが会社員ならば「仕事中、災難に遭われてお気の毒」となる。
パウエル発言にも「ル・モンド」紙の記事にも見えるように、「世界の常識」では評価が逆です。会社員ならば詰まるところ私利私欲のため、利潤追求の行為ですから普通以上には評価されないが、ヴォランティア、ジャーナリストの行動は価値あるものとされる。」
全く見事な論評だ。佐高信氏は、日本は会社社会で、サラリーマンのほとんどは、その意識に毒されて社畜になっていると指摘している。社畜になってしまった人間は、自らの価値を低めるようなヴォランティアを持ち上げるなどということが出来なかったのだろう。私利私欲の追求に過ぎないことに人生をかけていることの卑小さが、ヴォランティアに命をかけている人間の姿で、あまりにもはっきりと見えてきてしまったのではないだろうか。
本来なら、社畜意識を脱して、本当に尊敬できる存在への共感という世界の常識を獲得するチャンスだったはずだ。それが出来なかった日本社会と、その非常識を代表する人間たちが今の政府中枢に溢れていることを、今回の人質事件はよく分からせてくれた。だからこそ、人質の批判をするよりも先に、このばかげた「自己責任論」を批判する必要があったのだ。
人質たちのミスは、これから、彼らと同じように良い目的で危険をあえて選ぼうとする人たちの間で、真っ当な議論のもとに正しく評価が出ることを期待している。人質バッシングが、なぜ「バッシング」と呼ばれているかというのは、それがまともな批判ではないからだということを反省しなければならないのである。
この対談は、他にも非常に豊富な内容を持っていて、まさに「決定版」にふさわしいと思う。次回は、「自衛隊の撤退」に関する議論を紹介しよう。これは、あの事件では自衛隊の撤退は「論理的に」あり得ないという見事な証明だ。長くなりそうなので、次回にまとめたい。
「自己責任論」批判 決定版 その2 05月20日(木)
昨日の紹介では、日本社会の持っている「公私」の概念の狂いが人質バッシングを増加させたという宮崎氏の論評を紹介した。これは、正しくとらえられていたら、人質たちのミスも正しく批判できただろうと思うが、それが狂っていたために、正しく批判するよりも、単にたたいて潰してしまえという力が働いたように僕には感じた。
宮崎氏は、この対談の冒頭でも「国家理性や国家原則を顧慮する姿勢がまるでない」と、人質擁護派も批判派もともにその欠点を指摘している。ということは、宮崎氏自身は擁護派でないはずだ。僕には、中立的な立場で論評しているように見える。しかし、批判の度合いは、政府を始めとする「自己責任論」を言い立てる「批判派」の方をより強く批判している。僕も似たような立場で、人質たちを擁護したいわけではなく、正当に批判するべきだと主張している。つまり、今の批判は全く正当でなく、言いがかりのようなものだと批判しているのだ。ところが、その立場は、なぜか人質擁護派になってしまうようだ。論理というものを理解する人間がなんと少ないものかと思う。
それでは、宮崎氏の言う「国家理性」や「国家原則」というものを、宮崎氏自身の言葉を引用して考えてみよう。
「この場合の国家理性とは何か。言うまでもなく「その人間の属性の如何にかかわらず、日本国籍を有する人間は最大限救出、保護する」です。そしてもう一つ、「脅迫行為によっては、国策を寸毫も変更することはない」です。この当たり前を当たり前として貫く自身がないから、「自己責任」論などというわけの分からない、虚偽の論点について、猿(ましら)のごとくにけたたましく騒ぎ、こづきあい、絶叫しあうことになる。愚の骨頂とはまさにこのこと。」
全く明快な論理で、このことが常識になっていたら、人質事件もまともな論評が出たことだろうと思う。「政府にたてついた人間は助けなくてもいい」などという妄言は、さすがに無教養な人間からしか出てこなかったが、救出・保護するのが当たり前なのに、あたかもたいへんに恩恵を与えたかのように言い立てるのは、この国家原則を知らない無教養をさらけ出しているに等しい。
そして宮崎氏が指摘するもう一つの問題、「脅迫行為によっては、国策を寸毫も変更することはない」ということも、これを当たり前のこととして主張すればいいのであって、人質の責任論と絡める必要は何もなかったのである。これも、宮崎氏が指摘するように、「当たり前を当たり前として貫く自身がないから」、世論の目をそらすために論点のすり替えをしたのだろう。これも無教養の表れだ。
ただ、宮崎氏のあとの指摘については、僕も最初勘違いしていた部分があったので、自己批判をするためにももう一度深く考えてみたい。僕は、「小泉内閣は」自衛隊の撤退など出来ない、というふうに受け取って、今回の事件で撤退はあり得ないだろうと考えていた。つまり「小泉内閣」という条件付きで「撤退があり得ない」と考えていたのだ。しかし、これはかなり一般論として語れる論理だと言うことを宮台氏が明快に指摘している。
「「一私人が人質に取られた」は撤退理由には絶対になり得ない。なぜか。「一私人のどうたらこうたら」のリスクを織り込み済みで派兵決定した「はず」だから。仮に「一私人のどうたらこうたら」で兵を引いたら、「おまえら、そんなことも考えないで出兵したのか」と国際的な恥辱となる。」
小泉政権は、アメリカ追従をしていた政権であるから、その小泉政権だったら、追従の意志を貫くために撤退はあり得ない。これも一つの真理であるとは思うが、この場合の宮台氏が語る撤退があり得ないという論理は、小泉政権のように、アメリカ追従ではなくても、一度派遣を決定したら、その決定の責任として、「この事件(脅迫)」での撤退をしてはいけないという論理だったのだ。もし、形として民主主義的に多数の意見で派遣を決定したのなら、この事件で撤退したら、その決定に対する無責任を批判されなければならないからだ。
上の論理は、人質たちに対してはかなり厳しい論理かもしれない。しかし、論理というのは普遍性を持つものであるから、人質たちの条件の如何にかかわらず、成立せざるを得ないものだと思う。感情的に反発する人はいるかもしれないけれど、政府の側が上のように説明していたら、論理的には間違いはなかったと思う。政府の側に、宮崎氏や宮台氏のように、論理的センスの水準の高い人がいなかったのだろうか。
このほか、まだこの「決定版」は深い内容を語っている。イラクに自衛隊を送ることが、どうしてNGOやNPOを危険にさらすのかという論理についても語っている。人質たちを批判する人間は、危険になったことと自衛隊派遣の関係性を認めないものが多いように僕は感じているけれど、これは時間的な因果関係があるだけでなく、論理的な因果関係のある事柄なのだ。また次回紹介しよう。
その他書き残しておきたいことは、またまたもう一つ、強者の論理による「自己責任論」を見つけたのでそれを批判しておいた。日記にしようかとも思ったのだが、日記では宮台氏と宮崎氏の「決定版」を紹介したかったので、左のページ一覧に書き記しておいた。長い文章だが目を通してもらえれば嬉しいと思う。
「山形浩生(評論家)氏の「自己責任論」批判」
また「現代」6月号では、立花隆氏の「イラク撤兵の時」という文章を読んだ。僕は、立花氏を全面的に信頼しているわけではない。文春の立場で文春を擁護する記事を書いたときは、かなり批判的にその文章を受け取った。しかし、第三者的立場でものを書くときは、たいへんすぐれたジャーナリスト感覚を持った文章を書く人だと思っている。
立花氏は、絶対に左側の人ではない。しかも高遠さんを擁護する立場に立つ人でもない。高遠さんと何らかの共通の利益を持っている人ではない。その立花氏が、この「イラク撤兵の時」という文章では、実に見事な高遠さんの擁護を展開している。高遠さんの支持者がこのような文章を書けば、それは差し引いて受け取らなければならないが、立花氏が書いているということで、僕はこれはたいへん信頼できる擁護論ではないかと思った。高遠さんにはとりわけバッシングがきつかったが、それへの見事な反論だと僕は思った。今後の日記で紹介していこう。
「自己責任論」批判 決定版 その3 05月22日(土)
「サイゾー」6月号の宮台氏と宮崎氏の対談によるこの「決定版」に、宮台氏の次の発言がある。
「まず、事実関係としての前後問題がある。以前から国会で問題になっていたんだ。ペシャワール会の中村哲氏が、米国のアフガン攻撃を支援するテロ特措法の衆議院審議に参考人として呼ばれて「日本が米国に追従すれば、現地に入ったNGOの人々の命が危険にさらされる」と発言したし、米国のイラク攻撃を支援するイラク特措法の衆議院審議に呼ばれた放射能研究者の藤田祐幸も同意見を述べている。自衛隊が行く前から現地で活動する人間はたくさんいるわけ。人質になった高遠菜穂子さんも、自衛隊派遣のずっと前から現地で活動してたしね。こうしたNGOの人々の命を危険にさらすのが所属国の軍隊派遣だというのは国際常識で、それを知りつつ「あえて」軍隊派遣した国民的決定の自己責任こそが問われるんだよ。」
ここで語られている「こうしたNGOの人々の命を危険にさらすのが所属国の軍隊派遣だというのは国際常識」だと言うことがよく分かっていない人がたくさんいるのを僕は感じた。人質たちを批判する人の中には、人質たちの危機管理の問題と自衛隊の派遣とは違う問題だから一緒に論ずるべきではないと考える人が多いようだが、これは、論理的つながりのない問題ではないのだ。これがつながっているのが「国際常識」なのだと言うことがよく分かっていない人が多い。
この二つは、確かに文字の上では異なっている。別々に切り離して論ずることが出来るだろう。危機管理として、危ないことが分かっていたのにその対処が足りないなどという批判が出来るのは、これを切り離して考えることが出来る場合だ。しかし、自衛隊の派遣によって、より危険が増して、今まで行っていた活動が出来なくなっているとしたら、その危機管理は、自衛隊派遣をした側にも責任が生ずるというのが「国際的常識」なのだ。
この「国際的常識」が理解できない人間は、自衛隊の派遣が危険の増大に結びついてくるという論理的なつながりが理解できないのだろう。それは、「観念論的妄想」というものがあるせいだと僕は感じている。その具体的な中身は、「自衛隊の人道復興支援」という観念の中にしか存在しない「妄想」が、実際に現地で行われていると思い込んでいるから、自衛隊の派遣によって日本人そのものが恨まれたりするはずがないと思うから、自衛隊の派遣によって危険が増大すると言うことが理解できないのだろう。
「観念」というのは客観的に存在するものではない。脳の働きによって生まれた、実体のない存在だ。その観念が描いた「像(実体ではなく、存在を模倣したようなもの)」と結びつく実体が、実際に現実に存在するのは、観念が現実を正しく反映したときだけなのである。反映ではなく、想像で加工したものは、現実には存在しない。それは「観念論的妄想」になるのである。
たとえば、柳の木に引っかかった洗濯物が羽ばたくのを暗がりでみたときに、現実の正しい反映だったら、観念の中に「洗濯物が揺れているな」という象が生まれる。しかし、これを「お化けがそこにいる」という観念が生まれたら、それは「観念論的妄想」なのだ。「お化け」などという存在はそこにはないからだ。
自衛隊の働きが形としては本当に「人道復興支援」で、米英の占領軍のように軍事的な弾圧でなかったら、「観念論的妄想」にならずに、現地の日本人が危険にさらされないかというと、それもまた難しい。現地の日本人が危険になるかどうかは、イラク人がそれをどう受け取るかと言うことがもっとも重大な問題になる。たとえ実際に「人道復興支援」だったとしても、当のイラク人が「アメリカの占領に加担している」と見ていたら、日本人も敵だと言うことになる。
日本人の頭の中に、「自衛隊は人道復興支援をしている」という観念があっても、それをイラク人が、同じように受け取っていなければ、それは「観念論的妄想」になってしまうのである。そして現地の日本人が危険にさらされることになる。
マスコミの宣伝では、サマワでは自衛隊が歓迎されているというニュースばかりが流れてくる。だから、そのニュースしか見ていない人間は、「観念論的妄想」が生まれてきても仕方がない面もある。しかし、今一度自分の無知を自覚して、他の情報を求めて欲しいと思う。昨日の日記でも紹介したとおり、それはサマワ市民の大いなる勘違いだ。サマワ市民にも「観念論的妄想」がある。だから歓迎しているのだ。立花氏が言うように、その勘違いに気づいたときに現実に直面することになる。
立花氏が、高遠さんの仕事を高く評価していたのは、イラクの人々の本当の声を記録していたからこそそれを評価したのだ。これがジャーナリスト・センスというものだ。政府の立場からの発表をそのまま垂れ流すマスコミ記者の感覚では、そのような評価は出来ない。それでは、月刊「現代」6月号から、立花氏の記事からの孫引きの形で、自衛隊の人道復興支援が、いかに日本人の頭の中にある「観念論的妄想」であるのか、その証拠を見てみよう。
「自衛隊が来て、物資の輸送や水や食糧の供給をすれば、我々の得るはずの仕事がなくなる。この国は貧困で困っているわけでも人手が足りないわけでもないのだ。とても裕福な国だけれど、今する仕事がないのだ。我々は我々の手で立て直すことが出来るのだ。またアメリカの要請でくるべきではない。イラク政府(が出来たら)の要請でくるなら分かる。」(産婦人科外科部長の声)
「日本の自衛隊はくるべきではない。まずこれはアメリカによる罠である。なぜなら、日本人がアーミールックでいるならば米軍と一緒と見なすであろう。物資の輸送や水の供給は日本人がやるべきことではない。我々は自分たちでやるべきなのだ。我々は今仕事が必要なのだ。俺たちの仕事を取るようなことになる。日本人はよい人たちなのに、なぜアメリカの見方をするのだ?」(病院付近の住人)
「イラクで一番の戦闘地域でインタビューをしたとき、こういったイラク人がいました。「日本の自衛隊?シロウトだろ?やめとけ。殺されるのがオチだ。」以前にもここに書き込みましたが、軍服を着た者はみな占領軍と見なすと、彼らは言っています。占領軍とは米英軍です。フセインの残党のような言い方をされていますが、ほとんどはそうではありません。普通の人たちです。派閥を越えて、反米という名の下に団結をしているのです。(それを陰であおる外国人グループがいるのも事実ですが、基本的にアメリカ人の強引なやり方にうんざりしているのです)」(高遠さんの言葉)
これらの高遠さんの報告をすぐには信じられない人もいるだろう。批判するのは自由だ。しかし、批判するのなら、その反対の証拠をちゃんと提出しなければならない。高遠さんは、実際にイラクに行って、自分でこれらの声を集めて発信している。だから、それに反対し、批判したいと思うなら、やはり現時の実際の声を集めてくる必要があるのだ。それは自分でやらなくても、誰かがやったものを引用してもいい。しかし、そのような確かな証拠もなしに、上の報告を否定するのなら、それはそのような論理を展開する人間の、論理に対する無知と無教養を語っているだけだ。
イラクの人々は、日本の自衛隊を米英軍と一体化してみている。勘違いしているのは、直接の利益がもたらされるサマワ市民のごく一部だけだ。この観念論的妄想がいかに危険かというのは、アメリカに対するイラク人の見方が次のようなものであることを見れば一目瞭然だ。
「「米軍は解放者」と見るイラク人、7%に急落」
イラク人の多くは、
「米国を解放者と見る国民は半年前の調査で回答者の40%強だったのが、わずか7%。さらに「米軍が今撤退すればより安全になる」と答えた人は4割以上にのぼった。」
と報告されているような状況なのだ。
自衛隊は米英軍と一体化されてイラク人には見られている。米英軍に対する感情が自衛隊にも重ねられている。そして、その感情が日本人自身にも向けられているのだ。だから、自衛隊の派遣が、イラクにいる日本人たちの危険を増大させたのである。だからこそ、いっそうの厳しい危機管理を強いられることが生じてきたのである。それまでの危機管理以上の厳しさを要求する原因を自衛隊の派遣が生み出したのである。危機管理を、自衛隊の派遣と切り離して論じることの詭弁が分かっていただけただろうか。人質たちの危機管理が足りなくなったことの責任は、自衛隊を派遣した政府が負うべき部分があり、その政府を支持した国民が負うべき部分があるのである。
それがどの範囲まで責任を負うのが妥当かというのは議論をしなければならないが、その責任がないと主張することは出来ないのだ。危機管理のすべてを人質たちにかぶせる「自己責任論」は、この意味で、政府の「無責任論」になるのである。
「自己責任論」批判 決定版 その4 05月23日(日)
「サイゾー」6月号において、宮台氏は、本質論からその周辺まであらゆる部分に渡って、「自己責任論」批判の決定版を語ると言っていた。その部分を見ていこう。まずは、人質への救出費用の請求の問題だ。宮台氏は次のように語る。
まずは冬山登山の遭難に関して、遭難者に請求される費用に関して、それが請求されるようになったのは、「自分が拠出した金の使い道をコントロールしようとする意識の高揚という点で、タックスベイヤー意識の向上にもつながる」と評価している。それは、ずさんな計画に対しては、責任を取らせるという意味での、使い道を考えようと言う意識だ。どんな事態であっても、遭難したのだからかわいそうだと言うことにはならないという意味での、「意識の向上」だ。
しかし、それが、今回の人質事件では、すぐに「人質たちにも費用を請求すべきだ」とはならない。それは、使い道を考えた上で出す結論だからだ。そこのあたりの論理を宮台氏は次のように語っている。
「歌舞伎町が危険だと知って出かけて犯罪にあう場合、「危険と知って出かけた以上、自己責任だから費用を払え」という議論は、普通出てこない。寝たばこで失火した場合もそう。なぜか。要は「明日は我が身」の立場可換性が想像されるからだね。アダム・スミスが「道徳感情論」で言う「テオーリア(観照)的態度における同感可能性」や、ロールズの「無知のベール下での態度」に相当する。立場可換性や同感可能性を支えるのがコモンセンス(共通感覚)。
ヒューマニタリアン的動機に基づく海外活動について、「今回は行けなかったが、自分もいずれは行くだろう」「私も本当なら行きたかった」「周囲に行っている人が多数いる」という共通感覚があれば、「費用を払え」はあり得ない。つまりこの場合の民度とは、共通感覚に基づく同感可能性・立場可換性のことなんだ。」
宮台氏は、「かつては冬山登山の遭難者にずさんな振る舞いがあっても、さして非難されなかった」と、この文章の前に語っている。それは、「遭難してかわいそうだ」という同感可能性があったからだろう。普通の人は登山のことなどあまり知らないから、遭難するのは、やむを得ないことで、危険がいっぱいのことに挑戦しているのだから、それは仕方がないのだと受け取っていたのだろう。
しかし、中には非常にずさんな準備や計画で、無知によって遭難したという例が知らされるようになると、「遭難してかわいそうだ」という同感可能性が薄れてくる。そんな無知なヤツが厳しい山へ行くことが間違いなのだという感覚が生まれ、遭難した人間との立場可換性が生まれてこなくなる。そうなると、自分で責任をとれということになってくるのだろう。
今回の人質の場合は、この同感可能性と立場可換性が生まれなかったことが、人質たちに救出費用を払えという声が挙がったことの原因だと宮台氏は分析している。「共通感覚があれば、「費用を払え」はあり得ない」と語っている。なぜなら、人質たちは、ずさんな計画で冬山登山をしたのと同じではないからだ。
冬山登山なら、専門家はたくさんいるし、どうするのが定石なのかが分かっている。それに比べてずさんかどうかという判断をすることが出来る。しかし、今回のイラクでの拘束に関しては、どういう準備・計画をするのが定石かというのはなかったのだ。しかも、自衛隊の派遣によって危険が増しているのであって、彼らの責任で危険を招いたのではない。
このようなことに関する同感可能性や立場可換性を感じる気持ちがあれば、「共通感覚があれば、「費用を払え」はあり得ない」と言うことになるのである。結果的には、共通感覚がなかったので、「費用を払え」の大合唱になったわけだ。それでは、なぜ共通感覚がなかったのか?それに対しては、宮崎氏が次のように分析していた。
「そう、結局、ヴォランティアやジャーナリズムが、この国では重視されていないんです。特に個人やフリーでやっていると、趣味以外の何ものでもないと看做される。おカミや会社の「仕事」や「用」だけがパブリックで、いかに公的な動機に駆動されてやっていたとしても、個人でやっている限り私的趣味なんですね。私的趣味で、おカミやお役人様に迷惑をかけ、血税を無駄に浪費させて、まことにケシカランと言うわけですね。欧米とは「公私」の観念が逆になっている。
ただし、日本的なコンテキストを解説すれば、人質連中は「自分探し」というウルトラ・ブライヴェートな理由でやってる自己満足野郎だろ、と言うふうに見えてしまう。実際、彼らの甘さ、未熟さは覆いようがない。しかし、リベラリズムが可謬性を前提とする価値である以上、少なくとも公的に彼らの「愚かさ」を非難することは出来ないはずです。」
佐高信氏は、会社から自立できない会社人間を「社畜」と呼んだが、そういう人間は、自らの尊厳を保つためにも、「仕事でやる人間の方が偉い」と思わないではいられない。仕事ではなく、個人的な理想で動いたりする人間の方が偉いとなったら、会社のために滅私奉公する人間はいなくなってしまうと恐れを抱いているようだ。会社に人生のすべてを捧げさせるためには、そのような価値観を国民に持たせないとやっていられないだろうと思う。その日本社会の、会社中心主義のような弊害が、見事にこの人質バッシングでは現れていたのではないだろうか。
会社から自立できない人間が多いというのは、日本人の生き方の中に、主体性を育てるという機会が極端に少ないからではないかと僕は思う。自己決定をするという機会をほとんど奪われて成長するような気がする。
まだ能力の低い子供の時代は、いろいろとやってもらうことが多いので、自己決定が出来ない場面があっても仕方がない。しかし、ほとんどすべて親に当たる存在が決めてしまい、それをいつまでも続けるのが日本人の育ち方の中にあるような気がする。
親との関係も、どちらかというと支配されるという感じを受けるが、学校での子供の存在も、自己決定の場面はほとんどなく、判断は指導する側(教員)にほとんどゆだねられている。たとえ疑問を抱いていても、疑問を抱くことがいけないとされることがなんと多いことかと思う。もしも主体性を育てる教育をしようと思うなら、子供の判断がたとえ間違っていようとも、疑問を持ったことを自分の頭で考えて、結論が間違っていることを自らが知るような経験をして成長させなければならないと思う。
学校教育の場面では、子供の疑問の方が正当性があっても、権力によってそれが押さえられて、自分が考えるよりも、権力に従う方が正しいという場面が展開される場合が多い。意味のない校則に従うと言うことはこの最たるものだろう。これでは主体性が育つはずがない。「社畜」を育てるにはまことに都合のいい教育だが、人質たちとの共感可能性は持てなくなる。今回の人質バッシングは、このような日本社会の問題も鋭い形でクローズアップしてくれたのではないだろうか。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- ウォーキングダイエット日記
- ばんぶーさんの朝散記録 〜2025秋本…
- (2025-11-16 06:30:06)
-
-
-

- ダイエット日記
- ダイエット食事日記3118日、長女…
- (2025-11-27 01:45:59)
-
-
-

- 心の病
- 深淵なる聖堂 (Remastered)
- (2025-10-18 14:20:02)
-
© Rakuten Group, Inc.