[邦書] カテゴリの記事
全140件 (140件中 1-50件目)
-

なみだ学習塾をよろしく!/鯨統一郎著
サイコセラピスト探偵波田煌子シリーズ第3弾。 警視庁プロファイラーを務めた事があるサイコセラピスト波田煌子が、新たな勤め先の学習塾で起こる次々起こる事件を解決していく本格推理連作短編集。粗筋: 教育こそが日本を変える、と希望に燃える波田信人(ハタノブト)は、勢いで学習塾を開く。 事務員として、波田煌子(ナミダキラコ)を採用。 信人は、親しみ易い名の学習塾にしたかった為、平仮名にしよう、と考え、自身の名を冠した看板を立てるよう、煌子に命じる。煌子は、自身の苗字と、信人の苗字が偶々同じ漢字だったので、読み方も同じだと勝手に判断し、「なみだ学習塾」の看板を掲げてしまう。それを知った信人は直ちに「はた学習塾」に直そうとするが、「なみだ」を可愛いと思った学生らが次々訪れて来て塾生となった為、そのままになった。 何とか始まった学習塾だが、一癖も二癖もある塾生ばかりで、奇妙な事件が起こる。 それらの真相を、煌子が解いていき、信人はその度に感動して涙を流す。第1限 路線図と涙 信人は、ある日、授業を受けていた一人の男子生徒に、夢を持て、教室から飛び出して世界を見ろ、といった説教をしてしまう。 その直後に、その男子生徒は行方をくらます。 男子生徒の親は、一応連絡があり、広尾にいる、府中にいる、港区にいる、といった情報を伝えてきている、という。それらには親戚がいるので、訪ねたのかと思ったが、そうではなかった。 信人らは、もしかしたら男子生徒は誘拐されていて、自分の居場所を、誘拐犯が油断している隙を見計らって伝えているのでは、と推測する。 しかし、煌子は、男子生徒が発する連絡の内容を見て、これは誘拐ではない、と明言。男子生徒の現在地を言い当て、男子生徒と再会を果たす。 信人らは、広尾、府中、港区といった東京都内の地名が連絡内容にあったので、男子学生は都内にいる、と早合点していたが、実際には北海道や広島等、全く別の地域へ一人旅していた。 男子生徒は、授業で東京と同じ地名の場所が全国にあると知って、興味を持った。その直後に信人の「教室から飛び出して世界を見ろ」の説教で刺激され、それらを訪れてみよう、と思い立ち、実行に移したのだった。第2限 相似形と涙 男子生徒が、試験で低い点数を取る。男子生徒の親が心配し、信人の下へ相談にやって来た。 信人も、男子生徒はいつもは好成績だったので、不思議に思っていた。 話を訊くと、男子生徒は塾に通う女子生徒に一目惚れした。その女子生徒は携帯電話を持たせてもらえていなかったので、男子生徒は彼女の自宅へ電話を掛ける。女子生徒本人が電話に出たので、思い切って告白したが、にべも無く断られた。 男子生徒はフラれたショックで勉強に身が入らず、低い点数を取ってしまったのだった。 信人は、その女子生徒を呼び出し、交際を断ったのは事実か、と問う。 女子生徒は、交際を断っていない、と明言。そもそも、電話にすら出ていない、と。 信人は、どちらかが嘘を吐いている、と思った。 男子生徒が嘘の言い訳をしているのか、女子生徒が怖じ気付いて嘘を吐いてしまったか。 が、煌子は女子生徒の自宅に連絡し、彼女の母親と話した時点で、真相は明らかになったと宣言。 男子生徒が女子生徒の自宅に連絡した際、女子生徒本人が電話に出た、と思ってばかりいた。しかし、実際に電話に出たのは女子生徒の母親だった。親子なので、声が似ていたのだ。母親は、学生の身である娘が異性と付き合っている暇なんてない、と判断。電話で応対しているのは娘だと男子生徒が勘違いしているのをいい事に、娘の振りをして交際を断ったのだった。第3限 清少納言と涙 ある中学校で、クラス全体の国語の成績が上がっていた。 教師としては喜ばしい事なのかも知れないが、上がり方が異常だった。しかも、上がっているのはそのクラスだけで、同じ学年の別のクラスは、国語の成績は寧ろ下がっていた。 クラスの成績が上がっている理由の一つが、問題児だった男性生徒の成績が上がっている事だった。 問題児の成績がいきなり向上するのは有り得ない、何か不正があるのでは、と教師は疑い始めた。 問題児とされていた男子生徒は、なみだ学習塾の塾生でもあった。 中学校での異様な成績向上のニュースは、信人の耳にも入っていた。 信人としては、男子生徒が不正を働いているとは思いたくなかったが、状況からすると、何らかの不正を疑わざるを得ない。 信人は、男子生徒に不正を働いていないか問う。男子生徒は否定した。 話を聞いた煌子は、推理を展開。 男子生徒は不正は働いておらず、信人の授業に触発されて純粋に勉学に励み、成績を向上させた。問題児だった男子生徒の変貌振りに、クラス全員が影響され、その結果成績が向上した。 他のクラスの成績が下がっていたのは、時間割が原因、と煌子は論じる。 国語の授業を担当する教師は声が小さく、生徒らからすると何を言っているのか聞き取り難かった。そんな事もあり、国語はとにかく退屈な授業だった。それに、給食後の午後という、最も睡魔に見舞われる時間帯が国語の授業に割り当てられていた為、クラス全員が居眠りしてしまっていた。 一方、問題児のクラスでは、国語の授業は午前に割り当てられていたので、退屈しながらも、居眠りする生徒はいなかったのである。第4限 疑問詞と涙 なみだ学習塾に通う女子生徒が、自分は虐めに遭っている、と悩んでいた。 女子生徒は、教師から、テストがある事を掲示板に書き込んでくれと頼まれたので、そうした。 翌日、掲示板で書いてあった通り、テストを実施する、と教師は宣言。 掲示板にそんな事は書かれていなかったと、一部の生徒は反論するが、教師は耳を貸さず、テストを実施した。 テストについて知らされていなかった生徒らは、女子生徒を仲間外れにした。 仲間外れにした生徒も、信人の塾に通っていたので、何故仲間外れにするのだ、と彼は問う。 生徒は、掲示板にはテストについて全く触れておらず、お蔭でテストで低い点を取ってしまった、と答える。 女子生徒は、掲示板にテストについて書き込んだ、と言い張った。 どちらかが嘘を吐いている、と信人は思った。 話を聞いていた煌子は、どちらも嘘は吐いていない、と指摘。 テストを実施した教師はパソコンにはまっていて、今時パソコンを所有していない学生なんていない、と信じ込んでいた。 しかし、女子生徒はパソコンを所有していなかった。「掲示板に書き込んでくれ」と教師に頼まれた時、ネット上の掲示板だとは思わず、自分が住む団地の掲示板の事だと勘違いし、そこにテストについて書き込んでしまったのだ。第5限 月の満ち欠けと涙 男子生徒が、マンションのエレベータから消えるという、マジックを披露すると宣言。 学校の同級生や教師らは、そんな事が出来るものかと疑っていたが、男子生徒は乗った筈のマンションのエレベータから消えていた。 別の階で降りたのか、と単純に考えたが、階と階の間の移動や停止時間を考えると、エレベータが途中の階で停止したのは有り得ない。 どこに消えたのだ同級生らが探し回っていると、携帯電話に連絡が入り、自分は宇宙空間にいる、という。 そんな馬鹿な事がある訳無い、と思いつつも、携帯電話の指示通り動く。 そうこうしている内に、男子生徒から学校にいる、という連絡が入り、同級生らは男子生徒と再会する。 このマジックはナミダ塾でも話題に。 信人は、そもそも何故男子生徒はこんなマジックを披露したのかと不思議に思う。 男子生徒の動機を読み切った煌子が、真相を明かす。 男子生徒は勉強のストレスから、学校にあった問題用紙を盗んだ。が、考えを改め、元に戻そうとしたが、人がいるので戻したくても戻せなくなってしまった。そこで、マジックを披露して、同級生や教師らを学校の外に誘い出し、その隙に問題用紙を元に戻したのだった。 エレベータには、担架で横になった者を収容可能にする為のスペースが奥に設けられていた。男子生徒は通常は塞がれている空間に隠れ、エレベータが空になった様に装ったのだった。第6限 確率と涙 なみだ学習塾のある男子生徒は、嘘を連発していた。 日本からアメリカまで1時間で行ける、老人ホームに女子大生が入居している、等々。 見え透いた嘘ばかり吐くから、周囲から嫌われる羽目に。 しまいには、自分は空を飛んで宇宙旅行へ行く、と言い出した。 その話を聞いた煌子は、顔色を変える。ビルから飛び降りるつもりだ、と。 煌子と信人は、問題のビルを特定し、男子生徒の自殺を未然に防ぐ。 男子生徒は嘘を吐いていたのではなく、変わった視点で物事を見ていただけ、と煌子は指摘。 小笠原諸島からアメリカ領のマリアナ諸島までは、300キロ程度しか離れておらず、ヘリを使えば1時間で行けるので、「日本からアメリカまで1時間で行ける」というのはあながち嘘ではない。 また、老人ホームの入居者に、放送大学に通っているのがいた。それなら、老人ホームの入居者に女子大生がいる、というのも嘘ではない。 宇宙旅行に行く、と聞いた煌子が顔色を変えたのは、地球も宇宙にある以上、どこからか飛び降りれば「宇宙旅行した」事になる、と読んだからだった。第7限 基本的人権と涙 卒業シーズンを迎えたなみだ学習塾では、塾生に対し、テストをする事にした。 信人は、テストに載る問題について講義し、後にテストを実施。 すると、塾生は全て同じ点数を取った。 成績があまり良くない塾生らは通常以上の点数を取る一方で、成績が良い筈の塾生らは、何故か凡ミスを犯し満点を取っていなかったのだ。 偶然にしては出来過ぎている、と信人は思った。塾生らの不正を疑う。 テストを確認した煌子は、塾生らは不正等していない、と論じる。 成績があまり良くない塾生らは、講義の通りに解答し、通常より高い点を取った。 一方、成績が良い塾生らは、問題を深読みし過ぎて、信人が想定していた解答以外の答えを記入したので、いくつかの問題が「不正解」とされてしまっていたのだ。 その結果、偶然にも全ての生徒が同じ点数を取る羽目になった。 煌子は、塾生らに対する誤解を解いた時点で、塾を退職する。解説: 推理小説というと、殺人等の重大な犯罪を取り扱い、警察が関わってくるのが当たり前。 本書は、それを否定するかの様に、警察が関わらない、重大な犯罪も起こらない謎を描いている。 試みとしては面白いが、こうして連作短編集として1冊の本に纏められ、それをぶっ通しで読むと、どれも小粒過ぎて、物足りなく感じてしまう。 いくつかの「謎」は、一々謎として取り扱うべきだったのか、といった内容。「塾が舞台だから」という事で、本編に端的に関係している豆知識を延々と取り上げ(しかも図解入りで)、それが終わった後に漸く核心の「謎」の部分に入る、といったストーリー構成になっていて、間延び感がある。 豆知識の部分を完全に省くか、省略すれば、本の厚みは半分以下になっていただろう。 執筆した時点での流行や著名人を「最新情報」として取り上げている為、現在読むと古臭く感じるどころか、何の事だがさっぱり分からない読者もいると思われる。 登場人物の設定も、読んでいる側からすると理解し難い。 主人公である波田煌子は、作中では物凄く魅力的な人物で、人が何故か彼女の周りに集まる、という事になっている。 読んでいる側からすると、そこまで魅力的な人物として映らない。 発想や言動も、常人と同じではないが、奇人・変人のレベルに達している訳ではなく、極めて普通で、地味な存在。 彼女が展開する「名推理」も、単に周囲の者が無能過ぎて鮮やかに見えるだけ。 大抵の人間ならそれくらいの推測は出来る、というレベル。「サイコセラピスト探偵」といった看板を大々的に掲げる程ではない。 ストーリーも強引に「謎」を演出しているものが多く、真相が明かされても、登場人物らが受ける程の感動は無い。 第1限 路線図と涙 東京都内の地名と同じ地名の場所が全国にある、というのは、大抵の人間なら知っている事なので、特に驚きは少ない。 また、東京都在住の者でないと、東京都内の特定に地名を述べられても、イマイチぴんと来ないし、それらと同じ名前の地が全国にあると教えられても、その地域の者でないと矢張りぴんと来ない。 東京都内の地名も、地方の地名も、本作の為の創作ではないかと疑ってしまう。 一方で、地方の地名を知っていた者からすれば、それと同じ地名の場所が実は東京にもある、と教えられても感動は無い。地方に住んでいる者からすれば、東京も一地方に過ぎないのだから。 本作では、男子学生は北海道や広島まで飛行機を使って移動し捲っていた、という事になっている。が、背が高くて大人っぽかったという設定になっていたとしても、中学生が親の承諾抜きで飛行機の切符を買って搭乗した、というのは無理がある。 第2限 相似形と涙 携帯電話やスマートフォンの普及率が高い現在では、時代を感じさせる一遍になってしまっている。 女子生徒とその親の声を区別出来なかった、というのも強引。第3限 清少納言と涙 給食後の退屈な授業だったからといって、クラス全員が居眠りし、成績が下がってしまう、というのは無理があり過ぎ。 一方で、問題児が勉学に励む様になった事でクラス全体の成績が上がった、というのも都合が良過ぎる。第4限 疑問詞と涙 パソコンの掲示板と、団地の掲示板を勘違いする、というのも、時代を感じさせる。 パソコンも、今となっては古くなっているが。 今ならタブレットか。第5限 月の満ち欠けと涙 エレベータからの消失トリックで、漸く本格っぽい一遍になるのかと思いきや、「このエレベータには偶々隠し部屋がありました」という肩透かしの真相。 動機も、アッと驚かされるものではない。第6限 確率と涙 日本とアメリカは、実は1時間で行ける程近い、との事だが……。 マリアナ諸島はアメリカの領土ではあるが、アメリカそのものではないので(アメリカの州ではない)、「日本からアメリカまで1時間で行ける」というのは正確ではない気がする。 それを言ったら、日本国内にある大使館も「日本国内にある外国」だから、東京都内ならどの国も1時間程度で行ける、という事になってしまうだろう。第7限 基本的人権と涙 成績が良い方は問題を深読みし過ぎて不正解となり、成績が悪い方は講義通りに回答した結果、全員点数が同じになってしまった、というのは偶然にしては出来過ぎ。 また、「最後の晩餐」はキリスト教において重大な出来事。ダ・ビンチ以外にも様々な画家が描いているというのは、西洋美術を少しでもかじった事がある者なら誰でも知っている。 塾長たる者が、「最後の晩餐」を描いたのはダ・ビンチが最初で最後と信じて疑っておらず、その間違いを塾生らから指摘される、というのはおかしい。「今でしょ」の台詞で全国的に有名になった塾講師からすれば、教育者の資格は無い、て事になりそう。 本作を読む限りでは、本格推理小説は矢張り重大犯罪が起こらないと、成り立たないようである。なみだ学習塾をよろしく! サイコセラピスト探偵波田煌子 (Non novel) [ 鯨統一郎 ]価格:905円(税込、送料無料) (2018/5/7時点)
2018.05.07
コメント(0)
-
信州長姫殺人物語/秋月達郎著
民俗文化専門調査員の竹之内春彦が探偵役を務める旅情ミステリー。粗筋: 旅雑誌の記者・胡桃沢くるみは、飯田線を取材する為、長野県飯田市へ向かう。途中で、編集部が手配した民俗文化専門調査員の竹之内春彦と合流。 くるみは、竹之内と共に行動する事は全く知らされていなかったので、反発するが、上司の意向なので、仕方なくコンビを組んで飯田市を取材する事に。 飯田市では、古くから伝わっていた長姫人形劇が、近々復活するという事になっていた。その舞台となる神社を訪れると、桜が青い照明で照らされていた。竹之内とくるみは、演出の一環と思っていたが、案内していた町の者は何故か不安な表情を見せる。 すると、直ぐ側に、男性のバラバラ死体があった。 死体は、伊那谷グループ会長熊谷直道だった。 地元の名士が殺害されたと知って、町は騒然となる。 それ以上に、熊谷家が騒然となった。 熊谷直道は、自ら築き上げた莫大な資産を文化活動に投入したいと考えていた。長姫人形劇が復活する事になったのも、そのお蔭だった。公開された遺言状も、遺産の大部分を文化事業の為に使う、という趣旨のものになっていた。 様々な事業を手掛けている伊那谷グループも、斜陽産業や、軌道に乗り切れていない新事業が多く、遺産の大部分が採算性が無いと思われる文化事業に回されてしまったら、経営難に陥るのは目に見えていた。 文化事業を取り仕切る遺族と、それ以外の事業を取り仕切る遺族の間で、不穏な空気が流れる。 竹之内は、そもそも何故熊谷直道は殺されたのか、誰の仕業か、の調査を個人で進める。飯田市に伝わる長姫と青い桜の伝説が絡んでいる、と感じるようになった。 青い桜は、熊谷直道の遺体が発見された神社にあったという事実を掴む。神社は元は城跡だった。戦国時代、長姫がそこで非業の死を遂げ、それを機に青い桜が咲くようになり、地元の者に恐れられていたいう。しかし、いつしか青い桜は無くなり、人形劇でしか語られなくなっていた。 竹之内は飯田市内を巡り、関係者から話を聞く。 そして、漸く青い桜の行方を掴む。 明治に入ると、城は封建時代の象徴となり、西洋化を推し進める政府にとっては無用のものとなった。長姫の城も廃され、神社へと変えられる。 恐れの対象であるのと同時に、地域の守り神にもなっていた青い桜を絶やすまいと、当時の町民らは青い桜を移植し、その存在を隠す事で守ってきた。 が、時代の流れと共に、問題が。 青い桜の移植先となっていた土地を代々受け継いでいた旧家が破産し、土地は伊那谷グループに乗っ取られてしまった。青い桜の事等全く知らない熊谷直道は、その土地を文化事業の為に開発しようと考えた。 熊谷直道からすれば、一代で財を成した際に手を染めた悪行に対する罪滅ぼしの為の町興し事業だったが、青い桜を秘密裏に代々守ってきた者らからすれば、町を滅ぼしかねない冒涜だった。 青い桜の秘密を知っていて、元々熊谷直道を快く思っていない者が、殺害するにまで至ったのだった。解説: 大富豪の遺産を巡る遺族の複雑な関係が殺人事件の中心にある、という描き方で始まるが、実際にはそれよりもっと大きな、町に関わる歴史が事件の背景にあった……、という展開になっている。 横溝正史の世界と、歴史ミステリーを掛け合わせた感じ。 描き方によっては非常に面白いものに成り得たのだが……。 そこまでには至らなかった。 冒頭で被害者の遺族がガンガン登場して、訳が分からなくなってしまう。その上町の歴史を巡る謎が加わるものだから、更に登場人物が増えてしまい、収拾が付かなくなる。 どの登場人物も、特に特徴がある訳ではないので、覚え難い。 主人公ですら、これといった特徴が無い。 遺産問題のゴタゴタが延々と描かれている為、間延びしてしまい、本筋の青い桜を巡る謎解きに達する頃には飽きてしまう。 話の途中に挿入されている歴史情報(史実とは無関係)も、物語深みを持たせるより、物語のペースをますます落としているだけ。 何故もう少し登場人物を減らし、遺産相続に関する部分は省略して、短くまとめられなかったのか。何でもかんでも盛り込んで無駄に長くすれば名作になる、という訳でもないのに。 主人公の竹之内も、著者は物凄く興味深い人物だと思って書き綴っている様だが、読んでいる側からすると退屈な中年男性。 作中では色々行動を起こすのだが、イマイチ興味を持てない。 事件の解決にも何となく関わっているというか、著者が強引にそこまで持って行った、といった感じで、何故こいつが探偵役なのか、本当に主人公なのか、と終始疑いながら読み進んだ。 低予算テレビドラマの原作本としては申し分無いのかも知れないが、読み物としてはきつい。
2017.11.18
コメント(0)
-

化生の海/内田康夫著
内田康夫の浅見光彦シリーズ作。粗筋: 5年前、三井所剛史という男性が加賀の海から他殺体として発見された。彼の住まいは北海道にあった。北海道から遠く離れた加賀へ何の目的で訪れたのか、家族すら知らなかった。この点が事件捜査最大のネックとなり、犯人はおろか、事件の背景すら掴めぬまま、迷宮入りとなった。 知人からこの事件について知った浅見光彦は、事件捜査を開始。 浅見は、三井所剛史の娘園子から話を聞く。 5年前、園子は就職するか、大学に進学するかの岐路に立っていた。進学するにも学費を捻出するのは経済的に難しかったので、諦めていた所、三井所は「何とか工面するから心配するな」と言い出した。園子は、父がどこから工面するのかと不思議に思う。三井所はその直後に家族に何も告げないまま外出。それから間も無く死体となって発見されたのだった。 園子は、父親が学費を工面する為に何か危ない事に首を突っ込んだ結果、殺されたのではと考えたが、それでも自宅から遠く離れた加賀へ父が向かう理由は思い付かない。 浅見は、三井所が孤児で、自身の生い立ちを探っていたのを知る。娘の学費の工面するのと同時に自分の生い立ちを探っている内に、何らかの理由で加賀へ出向き、そこで殺されたのでは、と推理する。 三井所は、孤児院に預けられた時から持っていたという素焼きの人形を残していた。浅見が、三井所が失踪直前に訪れたのが確認されていた松前を訪れた所、その人形とそっくりのものが、資料館に収められていた。人形は、明治時代から昭和初期まで加賀から北海道へ物資を運んで売る商船「北前船」からもたらされたもの、となっていた。 浅見は、これで北海道と加賀が繋がったと確信し、加賀へ向かう。 加賀で、浅見は三井所の殺害事件捜査の進展具合について問い合わせる。芳しい答えは返って来なかった。 北前船は、九州で仕入れた物資を加賀経由で北海道にまで輸送して売り付ける、という商いだった。明治時代は大いに栄え、営んでいた者に莫大な富をもたらした。が、交通網が整備され、通信が発達すると、仕入れ値から大きく上乗せして道民に売り付けるという手法は通用しなくなり、衰退。北前船の運営者は他業種へとシフトしていった。 北前船の中でも特に栄えていた宇戸家は、商売以外の事でも有名だった。往年の大女優深草千尋の生家だったのだ。 深草千尋は戦後の映画全盛期時代、大いに活躍していたが、テレビ時代に移行すると徐々に姿を現さなくなり、ある時期から全く姿を現さなくなった。現在、80代になる彼女は加賀で暮らしている事が分かっているが、誰とも会う事を拒否していた。 浅見は、三井所と宇戸家は何らかの形で繋がっていると考える。 深草千尋が渡米していたという時期は、三井所が生まれた時期に近かった。深草千尋こそ三井所の母親で、この時期に出産していたのではないか、三井所は実の母親に会いに行き、娘の学費を工面しようとしたのではないか、と浅見は考える。 浅見は、園子を伴って深草千尋の住まいを訪れる。 二人は難無く通され、深草千尋と対面する。 浅見は、三井所の母親はあなたですね、と切り出すと、深草千尋はあっさりと認めた。 深草千尋は妊娠した頃、女優として絶頂期にあった。子の父親である男性は、彼女との関係を認めなかったので、たった一人で生む羽目に。世間体を考えて、一人で育てるのは無理だと判断した彼女は、知人のつてで北海道の孤児院に生まれたばかりの子を預けた。それから数年後、彼女は孤児院を訪れ、三井所を引き取ろうとしたが、今更母親だと名乗られても困る、と三井所自身から拒否されてしまう。彼女はそれに傷付き、女優業を続ける気を失い、加賀に引き籠る事になった。 話を聞いた浅見は、指摘する。それだったら、何故自ら母親に会いに来た三井所を殺したのか、と。 深草千尋は、事件については全く知らなかった。引き籠ってからは、外部とは接触しておらず、新聞もテレビも無い生活を送っていたのだ。会いに来てくれたなら、歓迎した筈だと。息子が殺されていたと知って、彼女は大いに驚く。 浅見は、この時点で事件の全貌を知る。 三井所は、実の母親に会いに行く為、加賀を訪れた。母親の生家である宇戸家に、母親の居所を問い合わせた。 宇戸家当主で、深草千尋の兄である武三は、突然目の前に現れた妹の子に驚き、殺意を抱く。妹が三井所を実の子として認知したら、彼女の財産は三井所が相続する。そうなったら、妹の資金援助で何とか事業を継続していた自分は破産する、と武三は早合点した。 武三は三井所をその場で殺害し、死体を遺棄したのだった。 浅見は、武三の下に出向き、警察に真相を全て語る、と告げる。 武三は、共犯者と共に海へ船出し、遭難を装って自害した。解説: 他の著作の例に漏れず、低予算ドラマの原作本の域を超えていない。 本作は文庫本で600ページにも及ぶが、内容は薄い。 浅見光彦が偶然見付けた証拠を基にあちこち出向き、最後に初対面した人物が犯人、という、これまでのシリーズ作の流れを踏襲していて、新鮮味は無い。 ただ、ダラダラと長い。 警察が事件の全貌を掴めなかった為に迷宮入りした、という割には、事件の真相も動機も平凡で、驚きが無い。この程度で殺すか、と思ってしまう。 計画的とは言い難い犯行にも拘わらず、迷宮入りさせてしまう警察は、ひたすら無能。 素人探偵を煙たがる余裕があるなら、その素人探偵の出番を無くす程度の捜査をしたらどうか、と思ってしまう。 本作の世界では、浅見光彦は警察本部が一目を置く優秀な名探偵、という事になっている。 ただ、読んでいる側からすると優秀さが全く伝わらない。 あちこち出向いては、著者が用意していた証拠を偶然を装って見付け、次の場所へと移動する、を繰り返すだけ。「名探偵」を名乗るには直観力や閃きが必要だと思うのだが、浅見光彦にはそうしたものは見られず、素人探偵に過ぎない。「名探偵」だったら直ぐ思い付くであろう事実を何十ページも割かないと思い付かない。 本作では、何十年も前から隠匿生活をしている伝説的な女優深草千尋を取り上げている。 何十年も外界と接触していない、という奇妙な設定になっているので、読んでいる側は「もしかして深草千尋はとっくの昔に死んでいて、その事実を何が何でも隠したい関係者が、彼女について探りを入れていた三井所を殺害したのでは?」と想像を膨らませるのだが、本作後半で「誰とも会わない」という設定だった筈の大女優はあっさりと姿を現す。 事件の真相も、もっと平凡なのであるのが分かり、肩透かしを食らう。 生死すら不明であるかの様に語られていた謎の大女優深草千尋をあっさり登場させてしまうのだから、もしかしたら三井所は実は彼女と血の繋がりは無く、彼女がそう臭わせていただけで、武三は完全な勘違いで殺す必要が無い者を殺してしまった、という皮肉な結末を期待した。 が、本作の著者はその程度のどんでん返しすら用意出来ないというか、思い付かないらしい。 推理小説を名乗っている割には、読者が読みながら頭の中で巡らせる推理を常に下回っていて、意外性が見受けられない。読んで得した、という気分にはなれない。 仕掛けが無いのが最大の仕掛け、意表を突かない事自体が意表を突いている、という事か。 他の著作と同様、著者が自ら後書きで本作が苦労の末に生み出された大傑作であるかの様に綴っているのも異様に映る。 本とは文字で埋め尽くされた紙を束ねた商品。 小説家とは本という商品の為にひたすら原稿用紙を埋めるだけの作業者。 出版社とは本という商品をひたすら乱造するだけの業者。 書店とは本という商品をひたすら陳列するだけの商店。 小説家は原稿料さえ支払われれば問題無しと見なし、出版社は本という商品が書店に陳列されれば問題無しと見なし、書店は本という商品が売れさえすれば問題無しと見なす。 本を買った者が実際に本を読み、批評する事は全く想定していない。 ……この認識で日本の出版業界は回っているのか。 出版業界が斜陽と見なされているのも当然。化生の海(新潮文庫)【電子書籍】[ 内田康夫 ]価格:896円 (2017/8/6時点)
2017.08.06
コメント(0)
-

夢にも思わない/宮部みゆき著
「今夜は眠れない」の続編。 緒方雅男と島崎俊彦の中学生コンビが、クラスメイトが絡む殺人事件の捜査に挑む。粗筋: 僕(緒方雅男)と友人の島崎が住む町には広大な公園があり、そこでは毎年秋の夜にある催しが行われていた。前から気になっていたクラスメイトのクドウさんがその催しに参加すると耳に挟んだ僕は、催し自体には特に興味の無かったものの、行く事に。 公園に入ると、女性の死体が発見されたとの報が。 僕がその死体を確認すると、クドウさんだった。 警察がやって来て、大事になる。 翌日、学校に行ってみると、クドウさんは生きていた。前日殺されたのはクドウさんではなく、クドウさんの従姉だった。歳は離れていたものの、姿恰好が何となく似ていたので、僕が勘違いしてしまったのだった。 警察は既に死体の正しい身元は掴んでいて、捜査を開始していた。 被害者の亜紀子は、まだ二十歳という若さにも拘わらず、カンパニーと称される売春組織に属していて、少女を組織に勧誘する役割を果たしていた。 カンパニーは、元は堅気の人間が売春婦を使ってケチな小遣い稼ぎする目的で設立した組織だったが、暴力団が絡むようになってからは体質が変わり、警察に目を付けられていた。 警察は、カンパニー絡みの動機で亜紀子は殺されたのではないか、という推論を立て、捜査を進める。 亜紀子は、従妹のクドウさんも組織に勧誘していたという。当然ながらクドウさんは嫌がっていた。警察は、クドウさんにも亜紀子を殺害する動機があると見なすようになった。 クドウさんに好意を寄せている僕は、嫌疑を晴らす為に、島崎と共に独自の捜査を開始。 ただ、警察は徐々に事件の全貌を掴みつつあった。犯人はどうやらカンパニーに属していた畑山という男性だった、と。 畑山はカンパニーから脱退したがっていた。亜紀子に好意を寄せていた彼は、彼女にも脱退を促していた。しかし、カンパニーにどっぷりと浸かっていた彼女は、そんな気は毛頭無かった。その絡みで、畑山は亜紀子を殺すに至ったらしい。 警察は、カンパニーに属する者を殆ど検挙。しかし、検挙から逃れた者もいた。残党は、行方をくらました畑山を執拗に追う。カンパニーの重要情報を持ち出して姿を消したからだった。 そうこうしている内に、畑山の死体が発見される。自殺の様だったが、カンパニーの残党によって殺害された可能性も充分あった。 カンパニーの残党は、畑山が持ち出した重要情報が見付けられないと知ると、僕と島崎に牙を向ける。畑山が何らかの理由で二人に託したのでは、と思い込んだのだ。 僕と島崎はその危機をどうにか乗り越え、残党の検挙に貢献する。 しかし、僕は重大な事実を知る。 カンパニーが作っていたチラシには様々な少女の顔写真が載っていた。その中の一部は、クドウさんが亜紀子に提供したものだった。畑山が亜紀子を殺すに至ったのも、その顔写真に写っていた少女を巡る勘違いからだった。 僕が、クドウさんに対しこの事を問い詰めると、クドウさんは言う。自分に執拗に迫ってくる亜紀子が怖かったので、知人の写真の中から売春に手を出しそうな顔立ちの子を選んで渡さざるを得なかった、と。 これを聞いて、クドウさんに対する僕の思いは一気に冷めた。解説: 典型的な宮部みゆきの小説。 小さな、どうでもいい事が、実は小説そのものの鍵を握っているかの様に延々と描くのだが、真相が全て明らかにされると、矢張り小さな、どうでもいい事であったのが判明し、肩透かしを食らう。 他の宮部みゆきの小説と同様、事件の犯人探しそのものは警察に任しており、主人公は事件の背景にある真相を掴む事に終始している。二人の主人公は中学生なので、「警察を出し抜いて何もかも解決」ではリアリティに乏しくなってしまうので、当然のストーリー構成である。 本作では、亜紀子を殺した張本人が誰で、どこに行方をくらましたのかの捜査は警察に任されていて、主人公らはその犯人(畑山)が何故亜紀子を殺さざるを得なかったのかの究明に力を注いでいる。 が、いざ全てが究明されると、犯人の正体も、犯人の動機も、結局は大したもので無かった事が判明。 これが50ページ程度の短編ならまだ許せるが、300ページにも及ぶ長編を読まされた上でこの結末では、頭にくるというか、呆れてしまう。 もう一捻り、二捻り出来なかったのか。 今回の事件被害者は、亜紀子という女性。 二十歳にも満たない女性が殺されたのだから、本来だったら悲劇の人となる筈。 しかし、売春組織に属し、少女を斡旋し、組織が警察に目を付けられていて終わりも近かったにも拘わらず甘い汁を吸い続けたかったが故に脱退を拒否していた。 不幸な家庭で育ったという事情はあるものの、早かれ遅かれ殺されるか、それに準じる目に遭っていただろうと思ってしまい、関心が湧かない。 真相がラストで明らかにされても、「はい、そうでしたか」で終わってしまう。 推理小説の被害者は善人でなければ成立しない、という訳ではないが、少なくともある程度共感出来、捜査の展開に興味を持たせてくれる人物でないと。 本作が最も強調したかったのは、「主人公が好意を寄せていたクドウさんが、自己保身の為に売春を斡旋する亜紀子に対し、別の少女を押し付けるという、残酷な一面を持っていた」の点らしい。清純に見えていたクドウさんは、実はそうでなかった、と。 主人公の僕は、この事実を知ってクドウさんとの交際を諦める、という結末で本作は終わる。 残念ながら、その事については読み進む内に何となく分かってしまうので、真相が明らかにされた所で「衝撃な事実」にはなっていない。夢にも思っていなかったのは主人公だけ。 どんでん返しにしては力不足。 主人公がクドウさんに電話し、この事実を彼女の口から引き出そうとする下りも、蛇足の感が。 寧ろ、電話する前の時点で主人公はクドウさんがやらかした事は知っていたのだから、何故わざわざ電話をかけたのか、分からない。 クドウさんに自分が犯した罪を思い知ってもらいたかった、という事なのかも知れないが……。彼女が犯した「罪」は、作中ではまるで彼女自身が殺人に手を出したかの様な追及の仕方だが、彼女はあくまでも暴力団の影をちらつかせながら迫って来る従姉の接近を遮断したかっただけ。自身の行為が、後々殺人事件に発展する等、と予想すらしていなかっただろう。 主人公は、黙っていればいいものを、幼稚な正義感を振りかざして、勝手に落ち込んでいるだけの感じ。 読後感がひたすら悪い。著者が意図していなかったであろう意味で。夢にも思わない価格:691円(税込、送料別) (2017/5/27時点)
2017.05.27
コメント(0)
-
義経/宮尾登美子著
宮尾登美子による、源義経に関する随筆。 義経の誕生から、その死に至るまでの経緯を、独自の解釈と共に綴っている。 小説ではなく、著者本人が読者に語り掛けるようにして義経の人生を辿って行く、という内容になっている。 NHK大河ドラマ「義経」の原作となった。粗筋: 源氏の頭領義朝は、平氏との権力争いに敗れ、関東に逃げ戻る途中で謀殺される。 義朝の子供も捕えられ、殺されるが、幼かった頼朝や義経は命を助けられ、各地に追放される。 実権を握った平氏への不満が京で高まると、源氏を復活させようとの声が上がり、成人していた頼朝はそれに応じる。 頼朝の元に駆け付けたのが、奥州に追放されていた弟の義経。 義経は平氏滅亡の為に奮闘するが、あまりの活躍振りに頼朝に疎んじられるようになり、奥州へと逃亡。 しかし、奥州でも疎んじられるようになり、31歳の若さで自害する。解説: 本書は小説ではなく、義経の生涯について、私見を絡めて長々と綴ったもの。 歴史的な資料に基づいた見解ではなく、著者が女性として、母親として思いを馳せて、導き出した解釈を押し通そうとする部分が何か所も見られる。 その解釈に納得出来れば問題無いが、納得出来ないというか、感情移入し過ぎだろうと感じてしまうと、その世界に入っていけない(壇ノ浦の戦い直前に、義経が平家に嫁いだ妹に対し手紙を送り、命が助かるよう手続きしておく下り等)。 たった1冊の本(小説では無いので、台詞は無い)が、放送期間が1年間にも及ぶ大河ドラマの原作になれたとは驚く。どれだけ膨らませたのかと思ってしまう(別の長編著作平家物語も絡めたというが)。 本書を読む限りでは、義経は戦闘の天才というより、まぐれで勝ち続けたラッキーな武将で、運が尽きた時点で慌ただしくあの世へ旅立った、といった印象を受ける。 一方、兄である頼朝は、武将というより「政治家」で、戦したのは生まれて初めて挙兵した時と、義経没後の奥州征伐の時だけで、それ以外は「征夷大将軍としての政治基盤を固める為」を理由に一向に鎌倉から動かず、親族や臣下らに戦わせている。初の挙兵直後の戦に負けて、絶体絶命の危機に陥っているので、政治的手腕はともかく、戦は下手だったのだろう、と思わざるを得ない。本書を読む限りでは人間的な魅力に乏しく、源氏の頭領の嫡男、というだけで周りによって祭り上げられていただけの印象を受ける。実際、幕府の体制が整いつつあった時点で、最早用済みと言わんばかりに急死し、北条氏による執権政権を許してしまっている。全てが北条氏による陰謀だったとしても、不思議ではない。 義経は判官贔屓の代名詞にもなっており、奥州では死んでおらず、大陸に渡ってチンギス・ハーンになったのでは、という説も流れている。 しかし、本書ではその可能性を否定している。父親代わりで、後ろ盾だった藤原秀衡を亡くした時点で、庇護を受けていた奥州の地でもお尋ね者状態となってしまい、自分の命運は尽きたと悟り、あっさりと自害した、と。 これだったら、奥州から頼朝の元に駆け付けてきた義経は秀衡が送り込んだ偽物で(本物はとうの昔に死去)、それを知っていた頼朝が戦闘が上手かった偽義経を利用するだけ利用した後、あっさりと見切って死なせた、という説の方が納得がいく。本書では、それに関しては一切触れておらず、平家滅亡の為に奮闘した義経は、正真正銘の頼朝の弟、という事になっている。
2017.04.09
コメント(0)
-

我らが隣人の犯罪/宮部みゆき著:粗筋
宮部みゆきによる短編集。 5編から成り、表題作がデビュー作。粗筋:我らが隣人の犯罪 中学一年生の誠は、家族と共にタウンハウスで暮らしていた。 住まいそのものに不満は無かった。が、問題はあった。 隣のタウンハウスに住む橋本という女性が飼っている犬である。鳴き声がとにかくうるさく、昼夜問わず泣くのだ。お蔭で、母は不眠症になり掛けていた。 橋本という女性自身にも好意が持てなかったので、誠はどうにか仕返ししたい、と思うようになる。 ただ、橋本は独身だが、愛人がいて、その愛人がどう見ても堅気とは思えない。迂闊に手を出せなかった。そもそも、中学生が出来る仕返しなんて、限られている。 誠は、この事について叔父に話す。叔父は、犬が鳴くのは、一日中住まいに閉じ込められていて、散歩にも連れてもらえず、ストレスが溜まっているからだろう、と言う。 誠と叔父は、話し合っている内に、犬を攫うのが犬の為にもなり、鳴き声からも解放される唯一の解決法だという結論に至る。 しかし、橋本は犬を家の外から全く出さない。どうやって犬を攫うのか。 誠と叔父は、タウンハウスが屋根裏で繋がっている事を知る。屋根裏伝いに移動し、隣の橋本の住まいに侵入し、犬を攫ってしまおう、と計画した。 まず誠が、橋本の留守を狙って屋根裏に上がり、暗闇の中を進み、隣人の屋根裏までの道しるべを設け、天井パネルを直ぐ外せるようにした。 後日、叔父が屋根裏に上がり、隣のタウンハウスに侵入する。 しかし、叔父は犬ではなく、銀行通帳を持ち帰って来た。 誠が何故銀行通帳なんて持ち帰って来たんだと問うと、叔父は言う。 天井パネルを外したら、部屋ではなく、銀行通帳の隠し場所になっていた、と。 銀行通帳を屋根裏に隠すのは、尋常ではない。多分、脱税目的だろう、と叔父は言う。橋本は、愛人の脱税に協力していたらしい。 誠は、脱税について通報しよう、と叔父に提案。橋本が脱税で逮捕されれば、引っ越すだろうから、犬の問題も解決する、と。 しかし、叔父は言う。そのまま通報したら、不法侵入についても説明せねばならず、それだと自分らも捕まる、と。 誠の妹が、二人が話し合っているのに気付く。犬を攫うつもりが、銀行通帳を盗む羽目になった、と説明せざるを得なくなる。 妹は、そんな事しなくても、合鍵を使えば楽に侵入出来るのに、と呆れる。彼女は、橋本が合鍵を隠す場面を目撃していたのだ。 誠と、妹と、叔父は、橋本の留守を見計らって、犬を攫う。 橋本は犬がいなくなった事に気付き、警察沙汰になるのではないかと思われる程大騒ぎするが、その内騒がなくなった。 叔父が、銀行通帳をネタに、強請りの連絡を入れたからだ。犬の件で下手に警察沙汰にしたら、脱税がばれてしまう可能性がある、と橋本は恐れ、騒ぐのを止めたのだった。 叔父は、橋本と愛人が脱税で確実に捕まる一方で、自分らには被害が及ばない方法を編み出す。 叔父は、ある看護婦から嫌な目に遭わされていた。彼女に脅迫めいた手紙を送り付け、警察に相談させるよう仕向けた。 看護婦と警察は、脅迫者を炙り出す為、その脅迫者にある場所で会おう、と提案する。その場所には警察が張り込んでいて、現れてきた脅迫者を捕まえる、という手立てになっていた。 同時に、叔父は橋本にも強請りの連絡を入れ、金を出せば通帳を返すと言った。金を渡す場所として、看護婦と警察が張り込んでいる店を指定する。 橋本は、叔父の策略にはまり、看護婦と警察が張り込んでいる場所にのこのこと現れ、捕まってしまう。 看護婦への脅迫は濡れ切れだったが、言動が怪しかった為、橋本は警察から取り調べを受ける羽目に。その結果、脱税が発覚。 ただ、脱税したのは犬の首輪に仕込まれた宝石で、銀行通帳は無関係だった。橋本が犬を外に出さなかったのは、首輪を紛失させない為だったのだ。 銀行通帳は、実は橋本ではなく、タウンハウスの反対側の隣人のものだった。 誠は、屋根裏に上がった際、橋本の住まいへ向かったつもりだったが、暗がりで方向感覚を失い、もう片方の隣人の住まいに侵入していた。 要するに、両側の隣人がそれぞれ脱税を働いていたのだ。 そちらの方にも警察の捜査が入り、誠のタウンハウスでは両側が空き家となった。この子誰の子 中学生のサトシが一人で留守番していると、恵美という女性が訪ね、家に勝手に上り込む。 サトシが呆然としていると、恵美は抱えていた赤ん坊を見せびらかし、この子は自分とあなたの父親の間で出来た子だと言い出す。この子とあなたは兄妹だ、と。 サトシは、恵美の言葉を信じられなかったが、彼女があまりにも堂々としているので、もしかしたらと思い込むように。 恵美は、サトシの家で一晩過ごす事になる。 しかし、父親がそろそろ帰って来るという段階になって、恵美は赤ん坊がサトシの父親とは全く無関係だという事実を自ら認め、去っていく。 それから間もなくサトシの両親が帰宅。サトシは、恵美の訪問については何も話さなかった。 サトシは、少ない手掛かりを元に、恵美の住所を探し当て、彼女と対面。 サトシは、自分の父親は子を作れない身体で、自分が人工授精から生まれた子である事を告げる。したがって、恵美の赤ん坊が父親の子でないのは、初対面の段階で知っていた、と。 が、サトシには引っ掛かる部分があった。赤ん坊が、自分に似ていたのだ。 恵美は認める。彼女には事故で亡くした夫がいた。その夫は、過去に人工授精の為にと精子を提供していた時期があった。サトシは、その夫の精子によって生まれたのだ。 サトシが怪我で病院に搬送された際、看護婦だった恵美の目に留まる。サトシが死んだ夫にそっくりだったので、夫の子ではないかと思うように。 夫を亡くし、子育ての心労からノイローゼになり掛けていた恵美は、サトシの家に推し掛け、自分の赤ん坊がサトシの父親との間に出来た子だと言い掛かりを付けた。しかし、押し通せず、退散したのだった。 赤ん坊がサトシの遺伝学上の妹だというのは事実だった。 サトシは、遺伝学上の父親について知る事が出来た、と恵美に感謝し、妹の存在も分かった事についても、恵美に感謝。時折妹に会いたい、と申し出る。サボテンの花 卒業間近の6年1組の生徒らが、卒業研究として「サボテンの超能力」を取り上げたいと言い出す。 堅物として知られる担任教師の宮崎は、猛反対。他のクラスの様に、もっとまじめな研究をやれ、と。 しかし定年間近の権藤教頭は、生徒らの好きなようにやらせてみろ、と言う。まじめではあるがありきたりな卒業研究しか発表されない事に、疑問を抱いていたからだ。 生徒らは、研究と称して次々に騒動を起こすようになり、権藤教頭は対応に追われる羽目になる。 漸く漕ぎ付いた研究発表会で、6年1組の生徒はサボテンを使った実験を実施。サボテンには超能力がある、と教師らも認めざるを得ない結果に至り、発表会は終わる。 後に、生徒が実験は単なる手品で、サボテンに超能力は無かった事を、権藤教頭に対し認める。生徒らが起こしていた騒動は、権藤教頭へのプレゼントを作る為に起こしていた行動だった。祝・殺人 刑事の彦根は、担当している殺人事件に関して、ある女性から接触される。 日野明子というその女性は、結婚式場を運営する会社に勤めていた。 殺人事件の被害者は、彼女の会社が担当した結婚式で、司会を務めたという。 殺人事件とは、佐竹という営業マンがバラバラ死体で発見された件だった。派手な死体になっていた割には、手掛かりが少なく、捜査は行き詰っていた。 明子によると、佐竹は知人の式場で、司会役を務めた。プロの司会者ではないが、過去に何度もやっており、慣れていたので、新郎の高崎から頼まれたのだという。 式場で、明子は奇妙な行動を目撃する。佐竹は、式場に届いた祝電を一通ずつ読み上げる、という催しを担当したが、一通だけは読まず、それどころか秘密裏に処分した。 何故佐竹は独自判断で祝電を握り潰したのか、という疑問が上がった。 明子は考えた。佐竹が処分した祝電は、式場で読み上げるべきでない内容だった。だから読まなかった。秘密裏に処分したのは、強請りに使えるのではないかと考えたからではないか、と。 彦根は、その考えは突飛過ぎないかと言いそうになったが、思い当たる節があった。 事件現場となった佐竹の住まいを捜査した所、衣類からある町のスナックの名刺が入っていた。わざわざ行くにしては遠い町なので、調べた所、そこで勤めていた秋崎みちよという女性が殺害されていた。 偶然にしては出来過ぎていたが、みちよが殺害された日時には佐竹にアリバイがあったので、この二つの殺人事件は無関係だろうという結論に至っていた。 明子は言う。みちよと、新郎の高崎は、どうやら知人だったらしい。みちよは、高崎の結婚式直前に殺されていた。祝電は、結婚式のかなり前から申し込まれていた可能性が高い。みちよこそ読まれなかった祝電の送り主ではないか。みちよは、結婚を破談に追い込もうと嫌味たっぷりの祝電を送る手続きをした。その直後に殺害された。佐竹の機転で、死者が送った祝電は握り潰された。しかし、佐竹はそれをネタに高崎を強請った。みちよを殺したのはお前だろう、と。困った高崎は、佐竹も殺した。 ただ、殺害方法からして、単独犯行とは思えなかった。共犯がいる。それは誰か。何故共犯となったのか。死体をバラバラにしてどうするつもりだったのか。 明子は自身の推理を述べる。 佐竹が高崎だけを強請ったとは考え辛い。高崎はただのサラリーマンで、出せる金は限られていたからだ。しかし、高崎は富豪令嬢と結婚する予定だった。佐竹は高崎だけではなく、高崎の結婚相手の親も強請っていたのではないか。佐竹は、強請りの材料を勤務先のロッカーに保管していた。ロッカーは、指紋認証によるロックが掛かっていて、高崎や新婦の親が簡単にアクセス出来ないようになっていた。そこで、高崎と新婦の親は佐竹を殺した。指紋認証ロックを解除する為、佐竹の手を切り取り、佐竹の勤務先に忍び込み、切断した手を使ってロックを解除し、強請りの材料を盗んだ。佐竹の死体がバラバラだったのは、手だけが切断された状態だとそこから犯行の全貌が掴まれてしまうからだった。 彦根はその推理を元に、捜査を見直し、高崎と、新婦の親を逮捕するに至った。 高崎の結婚式が間近に迫る中、みちよは高崎に対し別れたくないと言い出した。困った高崎は、みちよを殺した。これを知った佐竹は、それをネタに新婦の父親を強請る。 娘を溺愛する父親は、娘の夫が殺人犯として逮捕されたら不味いと思い、強請っていた佐竹を殺す。そして、脅迫の材料であり、殺人の証拠でもある品を盗んだのである。気分は自殺志願 推理小説家の海野の元に、中田という中年男性が声を掛ける。 中田は言う。海野に自分を殺してもらいたい、と。彼は本当は自殺したかったが、自殺で片付けられると不味いので、殺人として処理される方法で死にたい、と。 海野は言う。自分はただの作家なので、そんな方法は知らない、と。とりあえず、中田の話を聞く事に。 中田はレストランでボーイ長を務めていた。しかし、病気を境に味覚障害に悩まされるようになった。どんな料理もゴミの味しかしなくなったのだ。 治療の為にレストランを辞めたいが、突然辞めたら不審に思われる。中田は、業界では一応名が通っていたからだ。また、病気の事は隠し通したかった。息子が料理人で、自分の病が息子の将来に影響を与える可能性が高かったからだ。 海野は、中田の為に、オーナーからも業界からも怪しまれない方法でレストランを辞めさせる方法を編み出す。解説はこちら我らが隣人の犯罪 [ 宮部みゆき ]価格:529円(税込、送料無料) (2017/3/3時点)
2017.03.03
コメント(0)
-

我らが隣人の犯罪/宮部みゆき著:解説
宮部みゆきによる短編集。 5編から成り、表題作がデビュー作。解説:我らが隣人の犯罪 片方の隣人の犯罪を暴いたつもりが、もう片方の隣人の犯罪まで暴いていた、という手の込んだどんでん返し。 この点に関しては面白いと言える。が、それまでの過程がほぼ主人公の思惑通りに進んでいて、最終的には何の傷も負う事無く切り抜ける、というのは出来過ぎ。 特に、叔父の言動や発想は、堅気とは思えない。寧ろ彼こそが大犯罪者なのでは、と思ってしまう。叔父があまりにも犯罪に手馴れている様子だったので、実は叔父が脱税の黒幕だった、なんてオチが用意されているのではと予想したくらい。が、そこまでのどんでん返しにはなっていなかった。 もう片方の隣人も脱税を働いていた、との事だが、実際には無実で、叔父が罪を擦り付けたのでは、という解釈も可能(銀行通帳を叔父が天井裏から盗んだ場面を他が目撃した訳ではない)。 タイトルは「隣人の犯罪」だが、結局タウンハウスの三軒が全て犯罪者である。この子誰の子 あまりにも出来過ぎた話で、リアリティが無い。 人工授精で生まれた子と、その精子提供者の妻が偶然にも顔を合わせる、という確率は低いだろうに。 遺伝学上の親子だからといって、一目見て「この子は夫の子だ」と恵美が思える程顔立ちが似るとも思えない。サトシが赤ん坊を見て自分と似ていると感じるのもおかしい。 恵美は、サトシの住所を調べ上げ、意気込んでサトシの家に上り込んで嘘を並べ立てながらも、一晩経ったら「全て嘘でした」と自分から認めて退散している。この展開も、意味不明。 その程度で怖じ気付くなら最初から何もするな、と思ってしまう。 ポテンシャルは高かったものの、一番有り得ない、低いレベルの結末で纏められてしまった感が否めない。サボテンの花 何をどうしたかったのかが分かり辛い小説。 生徒らが生意気で鼻に付き、感情移入を妨げたのも助けにならない。 ハイライトのサボテンを使った実験も、結局は子供騙し(正確には子供が教師を騙している)の手品という事で終わってしまっている。手品はテレビや実演で観る分には面白いが、小説で描かれているのを読んでもあまり驚けない。 本作は、生徒と教頭との交流について描きたかったらしいが、もう少し分かり易く描けなかったのかね、と思ってしまう。祝・殺人 短編小説というより、長編小説の粗筋を読まされた気分。 短い割には登場人物も多く、いくつもの事件を扱っていて、全体が把握し辛い。 探偵役の明子の思惑通りに捜査が進み、彼女の無理のある推理通りに犯行が実施された、という結末になっていて、違和感が。 ちっとやそっとの事では解除出来ない高度な指紋認証ロック、という設定なのに、切断された手を使えば解除出来る、というのも分からない。高度な指紋認証ロックなら、指紋そのものだけでなく、体温も感知出来るようになっていると思うのだが。 警察は、事件捜査に関しては完全な素人の明子に指摘されるまで、事件の全容をまるで掴んでいなかった事になる。いくら何でも無能過ぎ。 5篇の中で最も推理小説っぽくなっていて、それなりに読めるが、内容的には平凡というか、心に残らない。気分は自殺志願 これも、意味がよく分からない小説。 何故ボーイ長がレストランを辞める為にここまで苦労せねばならないのかが全く不明。 業界で名が通っている、というのも中田の勝手な思い込みにしか思えないし、料理人の息子に将来に影響を及ぼす可能性がある、というのも考え過ぎだろう。 腑に落ちないまま物語が進み、腑に落ちないまま勝手に終わってしまった感が。 5篇ともイマイチ感が否めない作品集。 一部は面白くなりそうにスタートするのだが、終わる頃には失速しているというか、面白くない方向にあえて舵取りしている印象を受ける。 著者の初期の作品なので、習作的要素もあり、プロット作りに甘さがあった、と言えなくもないが……。 それから後に書かれた小説も、読んでみると矢張りイマイチ感が否めないのが殆ど。スタートが良くても、結局失速する。 デビューから現在に至るまでこうしたイマイチに終わる小説しか書けない作家らしい。長々とした小説にする技術は身に着けたらしいが。 にも拘わらず、世間の評価は異様に高い。 単に作風がこちらの好みに合わない、て事か。粗筋はこちら我らが隣人の犯罪 [ 宮部みゆき ]価格:529円(税込、送料無料) (2017/3/3時点)
2017.03.03
コメント(0)
-

100万回生きたねこ/佐野洋子著
佐野洋子による絵本(文章と絵の双方を手掛けた)。 1977年出版。 200万部以上発行されたという。粗筋: トラ猫は、輪廻転生を繰り返していた。 王様、船乗り、手品師、泥棒、老婆、少女等、様々な飼い主によって飼われては死んでいき、100万回も生まれ変わっていた。 飼い主はいずれもトラ猫の死を悲しんだが、当のトラ猫は悲しまなかった。トラ猫は、飼い主らが好きでも何でもなかったのだ。 トラ猫は、誰の猫でもない野良猫として生まれ変わる。 漸く自分の為だけに生きられるようになったトラ猫は、100万回生きてきた事を周囲の猫らに自慢。 雌猫らはその自慢話を聞いて言い寄って来るが、自分しか愛せないトラ猫は、それらを適当にあしらう。 トラ猫は、一匹の白い雌猫と出会う。白猫は、トラ猫に全く関心を示さなかった。白猫の興味を何とか引こうと画策している内に、トラ猫は白猫の側にずっといたいと思うようになる。そこでトラ猫は、白猫にプロポーズ。白猫はそれを受け入れた。 白猫はトラ猫の子を沢山産み、育てる。子は立派な野良猫として自立していった。 トラ猫は、それを幸せに感じた。 白猫は年老いていき、やがてトラ猫に寄り添う様にして死ぬ。 トラ猫は、100万回生きた中で、初めて悲しんだ。100万回泣き続け、泣き止んだ後には白猫の隣で死んでいた。 これを最後に、トラ猫は生き返る事はなかった。解説: 何にも心を動かされなかった無敵の主人公が、漸く心を動かされた時点で無敵でなくなり、本当の意味で死ぬ。 絵本にしてはやけに哲学的というか、深く考えさせられる。 子供の頃に読む時の印象と、大人になってから読む時の印象はかなり異なると思われる。 子供は、単に絵を見たり、様々な飼い主に飼われては不慮の出来事で死んでいくトラ猫の有様を読んだりして楽しむだけなのだろう。 大人は、絵の裏にある、猫の心の揺れを読み取ろうとする。 作者がどういう意図で本作を書いたのかは分からないけれども。 100万回生きる、というのもかなり大変な気がする。 毎日死んで、毎日生まれ変わったとしても、100万回生きるのに2500年以上掛かってしまう。 成長する暇が無い。 100万回も生まれ変わりながら、100万回目で漸く飼い主のいない野良猫として生まれ変わる、というのも奇妙。野良猫に生まれ変わるのはそんなに難しいのか。 また、100万回生まれ変わりながら、心を奪われる別の猫に出会えたのは最後の1度だけ、というのも不思議。トラ猫は、そこまで他人(他猫)に興味が湧かなかったのか。そうだとすると、特段珍しくはない白猫にそう易々と心を奪われる筈が無いと思われるが。 所詮絵本なので、細かい部分を突くのは無意味か。100万回生きたねこ [ 佐野洋子 ]価格:1512円(税込、送料無料) (2017/2/21時点)+
2017.02.21
コメント(0)
-

隅田川殺人事件/内田康夫著
著者を代表する浅見光彦シリーズ作。 本作では、地元の東京が舞台となる。粗筋: 浅見光彦の母親雪江は、知り合いの池沢英二という男性の結婚式に出席する事に。 結婚式といっても中年カップルの結婚なので、そう派手ではなく、唯一のハイライトが、新郎・新婦が家族や親戚と共に水上バスを利用して会場にやって来る、というものだった。 水上バスは無事会場に到着。乗船していた新郎や家族らは下船し、会場に入る。が、新婦の津田隆子の姿が見当たらない。 何らかの理由で水上バスは隆子を乗せたまま戻ってしまったのでは、と思い、直ちに水上バスの運営者に問い合わせる。乗船者と同じ数の半券を下船の際に回収しているので、隆子が下船したのは間違いない、との返事が。 隆子はそのまま行方不明となってしまった。 雪江はこの件について息子の光彦に話す。光彦は、関係者を訪ね、事情を訊くが、隆子の行方は分からずじまいだった。 それから数日後、廃業したボートクラブの解体工事現場で、女性の他殺死体が発見される。行方不明になった隆子ではないか、と光彦は思ったが、そうでない事が判明。佐々木辰子という、別の女性だった。 しかし、光彦は辰子の死と隆子の失踪は関係がある、と感じた。何故なら、辰子は水上バスの売店に会社で派遣され、勤務する事があったからだ。しかも、池沢はボートクラブの理事を務めていた過去もあった。偶然にしては出来過ぎだった。 警察は、池沢が結婚する間際の隆子と、辰子を何らかの理由で殺害したのでは、と疑うようになる。辰子は、死去した池沢の先妻の知り合いで、池沢を恨んでいたらしいからだ。しかし、池沢と何度か接触していた光彦は、それを信じられなかった。 隆子の死体が漸く発見される。警察の嫌疑は、ますます池沢へと傾く。 光彦は、隆子の勤務先であった信用金庫を訪れる。上司だった安藤が応対するが、これといった情報は得られなかった。 が、光彦は初対面だった筈の安藤を、どこかで聞いた事がある、と感じた。思い返してみると、廃業したボートクラブの最後の理事だった。信用金庫の係長に過ぎない安藤が何故ボートという、金の掛かる趣味を持てたのか、不思議に思う。 光彦は、安藤を疑い始めるが、隆子を殺す動機が思い付かない。が、隆子が結婚を機に退社するつもりだった、と聞いてある推論を立てる。安藤は勤務先の資金を横領していた。隆子はそれを知っており、結婚・退社の際にそれを暴くつもりだったのだ。安藤は、それをさせまいと、殺す事に。 安藤は、池沢を恨んでいた辰子に協力させる。辰子は水上バスの従業員だったので、下船していなかった隆子の分の半券まで回収出来たのである。辰子は池沢を恨んでいたが、殺人にまで手を貸すとは思っていなかったので、怖気出す。そこで、安藤は辰子も殺さざるを得なかった。解説: 相も変わらず、低予算テレビドラマの原作本の域を超えていない。 浅見光彦シリーズの多くの例に漏れず、ラスト辺りで光彦と初対面する人物が犯人、という結末になっており、推理小説本来の醍醐味である意外性は全く無い。無論どんでん返しも無い。 真相が明らかにされても「ああ、そうかい」程度の感想しか思い浮かばない。 このレベルのものを「推理小説」として書く方も、読む方もどうかと思わざるを得ない。 警察も、真相に全く近付けないひたすら無能な機関として描かれている。 そんな複雑な事件ではないのに。 廃業したボートクラブの建物から死体が発見された際、過去に理事長を努めていた池沢は執拗に捜査するのに、最後の理事長だった安藤はノーマーク、というのはおかしい。 マークしていれば、勤務先での資金使い込みが明らかになり、最有力容疑者になっていただろうに。 浅見光彦は本作でも名探偵扱いされているが、特に当ても無く関係者の間を嗅ぎ回っているだけで、優秀さは感じさせない。 漸く辿り着いた真相も、何の根拠も裏付けも無い。偶々当たっていただけ。というか、当たっていたのかも定かでない。 犯人の安藤がもう少し冷静だったら、単に否定するだけで済んだだろうし。 動機とストーリー構成も一致しない。 安藤が今回の犯行に及んだのは、勤務先の資金の使い込みがばらされては困る、という有り触れた動機から。 にも拘わらず、安藤は他人を引き込んで殺害の対象者を水上バスから消滅させる、というやけに手の込んだ方法で殺害している。 それだったらもう少し手の込んだ動機を用意出来なかったのか、と思ってしまう。 冒頭の「水上バスから新婦が消失! 新婦はどこに消えた? 何故消えた? 生きているのか?」という奇妙な謎も、結局「水上バスの運営者に共犯がいただけ。消えた新婦は案の定殺されていました」という呆気無い真相で済まされているし。 本作では、他のシリーズ作より光彦の母親雪江が登場する。 上流振っているだけの口煩い婆、という印象しか受けない。登場する度にさっさと引っ込め、と思ってしまうキャラ。 雪江は、いつまで経っても結婚しようとしない光彦を駄目息子扱いしているが・・・・・・。 相手の女性からすれば、こんな面倒な姑は嫌だ、と考えて光彦から去っているのも充分有り得る。 自分こそ息子が結婚出来ない最大の理由なのかも知れない、と、この盆暗婆は考えないのか。隅田川殺人事件【電子書籍】[ 内田 康夫 ]価格:454円 (2017/1/16時点)+
2017.01.16
コメント(0)
-

金沢殺人事件/内田康夫著
内田康夫の長編本格推理小説。 浅見光彦が登場する。粗筋: 金沢市で、女子大生の北原千賀が、石段から何者かに突き落とされて死亡する、という事件が発生。千賀は東京在住で、正月に偶々金沢を訪れていた所、殺されたらしい。 石川県警は千賀の身辺を捜査。どうやら彼女は東京で起きた殺人事件に関わっているらしいのが判明した。 東京の神社で商社マンの山野稔が何者かによって殺害された。この事件では、通報者は女性という以外、何も分かっていなかった。後にこの通報者は、「山野稔は死ぬ直前に『オンナニ・・・・・・ウシク』という謎の言葉を残して死んだ」と改めて警視庁に電話していた。警視庁は、通報者が事件に関わっていると思い、捜査していたのだ。 山野稔殺害事件に偶然関わる事になったルポライターの浅見光彦は、北原千賀の死を知り、この二つの殺人事件は繋がっている、と確信。北原千賀は、神社で瀕死状態の山野を発見し、謎の言葉を耳にしたものの、事件とは関わりを持ちたくなかったので、匿名で通報した。警視庁の捜査が行き詰っている事を知り、山野が口走った謎の言葉について、再度匿名で伝えた。その後、彼女は金沢へ旅行で向かった。そこで、彼女は山野を殺した犯人とどういう訳か再会し、殺されてしまった。もしかしたら、北原千賀は知らずの内に犯人を目撃していて、その犯人に追跡され、金沢で口封じされたのでは、と浅見は推測した。 浅見は、警視庁刑事局長である兄のコネを駆使し、単独での捜査を開始。 事件解決の鍵は山野にあると感じた浅見は、山野の身辺を調査。 山野は考古学を趣味としていて、考古学愛好家のグループに属していた。グループには、他に高校の美術教師である永瀬という人物がいた。山野は、グループでは必ずしも評判が良くなかった。他人の研究を横取りし、自分のものとして発表してしまう事がよくあったのだ。永瀬も、その被害に遭った一人だという。 北原千賀は、永瀬の元教え子だった。浅見は、これは偶然にしては出来過ぎると思い、永瀬を身辺を洗ってみたが、アリバイがあり、犯人なのは有り得なかった。 山野は、商社マンとして、織物の仕入れを仕事としていた。浅見は、「牛首袖(ウシクビソデ)」という着物が石川県で生産されている事を知る。山野が死ぬ間際に口走った「ウシク」とはこの事を指すのではないかと思い、牛首袖を手掛ける数少ない問屋玉野繊維を訪れる。そこの専務である芳崎潔が応対する。山野は、芳崎が手掛ける牛首袖を仕入れたいと交渉を試みていたが、牛首袖は生産量を無闇に増やせるものではないので、新たな取引先を開拓するのは無理だと伝えた、と芳崎は話した。 浅見は、山野がプライベートと商談を兼ねて行っていた旅行について調べる。彼が宿泊していたホテルに、芳崎が偶然にも宿泊していた事を知る。 浅見は推理する。 山野は旅先のホテルで、男性と女性が宿泊するのを目撃した。それから数日後、山野は商談の為玉野繊維を訪れた所、男性と再会。専務の芳崎だった。妻を紹介されるが、それはホテルで見掛けた女性ではなかった。要するに、山野は芳崎の不倫現場を目撃したのだった。山野は、それをネタに、商談を有利に進めようとする。 芳崎は、それを強請りと受け取った。牛首袖は生産量が少なく、山野が進めようとする商談を成立させるには、従来からの顧客を切り捨てなければならない。それは出来なかった。 芳崎は、山野を殺す事を決意。一人では実行に移せないので、不倫相手である女性(永瀬の妻)に加担させた。山野を東京の神社に誘き出し、殴打して致命傷を与えたまではよかったものの、即死には至らなかった。瀕死状態の山野は、現場に居合わせた北原千賀に、牛首袖の取引相手に殺された事を部分的に伝え、絶命。 北原千賀は、事件との関わりを出来る限り避けたかったので、匿名で警察に電話を入れた後、金沢を訪れる。そこで、高校時代の教師だった永瀬と、その妻と再会。 永瀬の妻は、神社での犯行の目撃者が、夫の元教え子と知って驚く。 その場で、北原千賀は、永瀬の妻に対し、以前お会いしましたねと口走ってしまう。彼女は、学生時代に会った事がある、と述べただけだったが、永瀬の妻は「犯行現場で会いましたね」と言ったと早合点。芳崎に伝えた所、北原千賀も始末しなければならないと慌てた彼は、彼女を石段から突き落としたのだった。解説: 低予算テレビドラマの原作本、といった感じ。 そういった小説でも、やりようによっては面白いものに成り得るのだが、本作にはそうした創意工夫は一切見られない。 締め切りに迫られて、創意も工夫も無くとにかく書き飛ばし、既定の枚数に達したので適当に広げていた風呂敷を強引に畳んで終わらせ、編集者に渡したかの様である。 本格推理小説、と名乗っている割には推理小説の醍醐味である筈のトリックや、意外な犯人や、どんでん返し、といった要素が見られない。 探偵役の浅見が当ても無く関係者(実際には事件とは無関係の者が殆ど)の元を訪れては話を聞いて帰って行く、という展開を延々と読まされるだけ。 浅見は、本作というか、本シリーズでは警視庁刑事局長の弟で、優秀な探偵で、数々の難事件を解決した事になっている。 が、何故そうやって持ち上げられるのか、読んでいる側からすれば全く分からない。 特に賢い訳ではないし、閃きがある訳でもない。 やる事といえば、兄の七光りで警察官をあしらうだけ。 この程度の探偵に出し抜かれる警察は、相当無能としか言い様が無い。 本作の警察は、とにかく捜査が徹底していない。 北原千賀は、東京在住。金沢は偶々訪れていた。 金沢で殺されたとなれば、金沢で出会っていた人物に殺された可能性が高いと考え、永瀬教師の身辺を洗っていれば、その妻が不倫していた事等、怪しい点をいくらでも掘り出せた筈。永瀬の妻の線を追及していれば、北原千賀殺害だけでなく、山野殺害の真相も芋づる的に解明出来ただろうに。 何の勘も働かなかったらしい。 事件は単純な内容で、真相も驚きに値しない。 こんな特徴の無い事件に、文庫本で300ページも費やさないと解決出来ない、というのは探偵や警察の無能振りを現している。 タイトルは「金沢殺人事件」となっているが、金沢で起こる殺人事件は二番目の被害者である北原千賀の件だけ。 発端となる山野の殺害現場は東京。 浅見は金沢市を何度か訪れる羽目になるが、それ以外にも能登半島等、石川県各地を訪れている。金沢市にずっと留まっていた訳ではない。 何故こんなタイトルになったのか。 著者は、大掛かりなトリックを駆使する推理小説を「ご都合主義」として馬鹿している。 したがって、本作にも大掛かりなトリックは無い。 これによりご都合主義の要素は排除されているのかというと、そうではない。 寧ろご都合主義だらけ。 北原千賀が偶々神社に入った所、瀕死の状態の山野を発見。山根は考古学愛好家クラブに属しており、北原千賀の高校時代の教師もメンバーに名を連ねていた。 北原千賀はその直後に金沢を訪れ、恩師と再会。そして神社で犯行を手伝っていた恩師の妻とも再会してしまい、その結果殺される。 事件そのものがご都合主義なのである。 山根の殺害方法も、ご都合主義。致命傷を与えるものの、即死には至らなかったので、偶々現場にいた北原千賀に、謎めいた言葉を残すのを許してしまう。 石段から突き落とす、という不確実な方法で北原千賀を殺せたのも、ご都合主義。 主犯が物語の後半で登場する人物なのも、共犯がラストでやっと登場する人物というのも、ご都合主義だろう。 ご都合主義を批判出来る推理小説にはなっていない。 物語の中で殺人事件が発生し、それを探偵役に調査させ、犯人が作中で特定されれば「本格推理小説」として成り立つ、という程度のご都合主義的な認識で著者は小説書き飛ばし、その産物をいわゆるファンらが「これが本格推理小説なんだな」というご都合主義的な認識で読み漁る。 こうしたご都合主義的な構造が改められない限り、日本の推理小説は低迷するばかりである。金沢殺人事件【電子書籍】[ 内田康夫 ]価格:486円 (2016/11/30時点)
2016.11.30
コメント(0)
-

誰かSomebody/宮部みゆき著
宮部みゆきによる長編ハードボイルド風ミステリー。 杉村三郎が初登場する。粗筋: 梶尾信夫という人物が、事故死する。歩いていた所を自転車に追突され、転倒。その際に頭を打ち、亡くなってしまったのだった。自転車で轢いた者は通報せず、現場から逃走し、どこの誰なのか分からなかった。 梶尾の娘であった聡美と梨子の姉妹は、父の半生を描いた本を出版しよう、と考える。万が一それが話題になり、大きく取り上げられれば、轢き逃げ犯が名乗り出てくるかも知れない、と思ったのだ。 梶尾は、巨大企業グループ・今村コンツェルン会長の個人運転手を務めていた。その伝を頼り、会長の娘婿である杉村三郎を訪れる。彼は、今村コンツェルンの広報誌の編集部に属していたのだ。 杉村は、姉妹から話を聞き、協力する事にする。 聡美は、もしかしたら父は事故死に見せ掛けて殺されたのかも知れない、と杉村に打ち明ける。聡美は、浜口という男性と結婚する予定でいた。梶尾が娘の結婚の前に自分が「やっておかなければならない事がある」といった類の事を言っていたのを思い出したのだ。もしかしたら父は過去に危険な連中と関わっていて、それを清算するつもりが、殺されてしまったのではないか、と。 杉村は、聡美の考えは突飛過ぎると思った。が、梶尾は若い頃に実家を飛び出してからは職を転々とし、妻と巡り合い、娘を授かっていた。職を転々としていた間――1960年代――に、危険な事に首を突っ込んでいた可能性が無くもない。 事故現場辺りで情報を求めるチラシを配れば、何か反応があるのでは、との提案を杉村は受け、そうする。また、杉村が現場を何度も訪れて訊き回っている内に、轢き逃げ犯は未成年である可能性が高い、というのが判明。事故については既に学校で話題になっているという。その時点で、杉村は考える。警察は、轢き逃げ犯が誰なのか、知っているのではないか、と。未成年なので、学校や親と慎重に接し、轢き逃げ犯が出頭してきた、という形で事件を締め括ろうとしている、と。すると、間も無く警察から連絡があり、それを裏付ける。轢き逃げした少年が近々出頭するので、姉妹に伝えるのはもう少し待ってくれ、と。 梶尾信夫の事故死は、轢き逃げに関しては解決の方向に向かっていたが、彼の過去を探っていた杉村は、そもそも何故彼が事故現場となってしまった辺りをうろついたのか、解明出来ないでいた。 聡美が、父親が危険な事に首を突っ込んでいた可能性があるかも知れない、と考えたのは、幼かった時、女性に誘拐され、監禁された記憶があったからだ。誘拐した女性は、父のせいだ、といった言葉を述べていたという。暫くすると母親がやって来て、彼女を連れ出し、事無きを得たが、これにより彼女は臆病な性格になっていた。 杉村は、梶尾とその妻が勤めていたトモノ玩具という会社を探し当てる。30年近くも前の出来事だったが、当時について記録している者を見付ける。その記録によると、梶尾と、その妻と、別の事務員の女性が同じ日に退職したという。聡美が「誘拐」され、無事保護されてから数週間後の出来事だった。 一方で、轢き逃げした少年は出頭。本を出す必要は無くなった。 杉村の電話に、ある女性から電話があった。トモノ玩具を、梶尾とその妻と同じ日に退職した事務員だった。その女性は、梶尾の過去について、重大な事実を告げる。事務員の女性は、トモノ玩具で働いていた30年前、酒乱の父親を死なせてしまっていた。その女性と親しくしていた梶尾は、「出頭しても警察は君を父親殺し扱いするだけだ」と主張し、妻と一緒にその死体を山奥に埋めて、処分してしまう。幼い長女――聡美――を一緒に連れて行く訳にはいかなかったので、梶尾は事務員の女性に長女を預けた。幼児の扱いに不慣れで、精神的に参っていたその女性は、「こうなったのは父のせいだ」と喚き、聡美をトイレに閉じ込めた。これが「誘拐」の真相だった。聡美は何日も監禁されていたと思っていたが、実は一晩の出来事だった。梶尾とその妻は、事務員の女性と同じ場にいられなくなり、三人ともトモノ玩具を退職し、散った。しかし、連絡は取り合っていた。 梶尾は、近々結婚する聡美に自分が「やっておかなければならない事がある」と言っていたのは、この事務員の女性と直に会い、過去にお世話になった女性として結婚式に出席してもらう事だった。過去を完全に断ち切りたい、と梶尾は願っていたのだ。事務員の女性は、聡美の幸せを祈りつつも、出席はとてもじゃないが出来ない、と断る。梶尾は、返事を受けたその帰りに、少年が漕いでいた自転車と衝突し、事故死したのだった。 梶尾は、この真相を姉妹に話すべきか迷っている間に、姉妹の重大な事実についても知ってしまう。 聡美の婚約者である浜口は、妹の梨子と不倫関係にあったのだ。結婚までの関係だ、と。聡美は、妹が同様の事を過去にもしていたので、既に疑っていたが、見て見ぬ振りをしていた。それを、杉村はわざわざ暴いてしまったのである。 聡美は、それについて杉村を責める電話を寄越すものの、最終的には静かに謝り、電話を切る。 今村コンツェルン会長は、杉村から全ての話を聞く。梶尾が犯した罪については本人が死亡しているし、事件も時効を過ぎているから今更公にする必要は無いだろう、という。また、聡美と梨子の姉妹に関しても、若い者同士で揉めている内に自分らで解決するだろう、と諭す。 杉村は、それに同意し、自分自身の人生を歩み続ける事にする。解説: 小さな事件が、大きく広がり、途轍も無いスケールの陰謀が明らかにされるのではないかと思いきや、本線も複線も小さく纏まって終わってしまっている。 轢き逃げは、結局は単なる轢き逃げ。事件捜査が進展していない様に見えたのは、犯人が未成年で、警察が事を慎重に進めていたからだけ。一般市民の杉村にとっては、解決不可能な事件に見えたが、警察の観点ではほぼ解決していた事件だった。 梶尾とその妻が背負っていた暗い過去とは、30年前に死体遺棄に手を貸した、という事だけ(犯罪行為ではあるが)。梶尾は、闇の組織に消された、という陰謀めいた動機で死んだ訳ではなかった。 聡美と梨子の姉妹は、歳の離れた仲の良い姉妹に見えたが、実は互いを傷付け合いながらも互いに頼っていくしかないという、愛憎が入り混じった関係にあった。 一編の長編に纏めてしまうと、物凄く複雑な人間模様を描くストーリーに見えるが、3つに分けて捉えると、案外シンプル。 特に轢き逃げの件に関しては、探偵役は真相を知らないまま捜査していたが、警察は何もかもお見通しだった。通常のミステリーとは逆パターンになっている。要するに、探偵が何もしなくても、この件に関しては解決していた事になる。未成年が犯人、というのも、著者がよく使うパターンの感じがするので、意外性は無い。 梶尾の死体遺棄の件も、山中に埋葬したとされる死体が誰にも発見されず、事件化されないまま30年以上経ってしまった、というのも不自然。ずぶの素人がそこまで完璧に死体を遺棄出来るなら、世の中の行方不明者のほぼ全ては人知れず遺棄されている事になってしまう。梶尾が、親しくしていたとはいえ、何故赤の他人の死体を、妻に手伝わせてまで遺棄したのかも分からない。 聡美と梨子の姉妹に関しては、聡美の婚約者浜口と、妹の梨子が不倫関係にあり、それについて聡美も薄々気付いているのでは、というのは大体読めてしまう。膨大な情景描写により、浜口と梨子の携帯電話の着信メロディーが同じだった事や、聡美が婚約指輪をしていない事を埋没させようと試みているが、この2点はやけに目に付くので(著者も目立たせようとしている)、読めてしまう。ラスト辺りで探偵役の杉村が「実は浜口と梨子は不倫関係に合った」という事実を知っても、読んでいる方は「何を今更」と思ってしまう。 登場人物の描き方も、複雑に見せながら実は単純なのが殆ど。 杉村に関しては、妻帯者で、子持ちなのに、まるで子供並みというか、子供以上の純情振り。ラストに至る時点で物凄く落ち込むが、「所詮赤の他人の事だから」で処理。自分自身は傷一つ負う事無く切り抜け、「今村コンツェルン会長の娘婿」という羨ましい立場に安住していられる。 個人的には、宮部みゆきという作家は、赤川次郎の女性版というか、物凄くくどい赤川次郎といった感じ。 赤川次郎並みにすらすら読める文体。 一方で、情景描写においてはあえてスカスカにして読者の想像力に任せがちな赤川次郎に対し、こちらは情景を事細かく描写。児童文学「スプーンおばさん」の訳文や、美空ひばりの曲も引用している。文末では著者が引用について謝辞し、巻末にはJASRACから許可をきちんと取り付けている事を記している。 物凄い作家なのか、ただそう見えるのか、本作を選んでしまったのが間違いなのか、よく分からない。誰か Somebody 文春文庫 / 宮部みゆき ミヤベミユキ 【文庫】価格:724円(税込、送料別) (2016/10/21時点)
2016.10.19
コメント(0)
-

怪死/南英男著
《警視庁特務武装班》シリーズの一つ。 特別に武装訓練を受けた捜査官浅倉と、彼が率いる捜査班が、事件を捜査する。粗筋: 警視庁特務武装班の主任浅倉と、彼が率いる捜査班は、ある事件の捜査を命じられる。 山中という人物の死体が自宅で発見される。一見他殺の様だった。が、山中は自身に多額の生命保険を掛けていて、しかも仕事上のストレスで鬱病と診断されていた。自殺だと生命保険が降りないので、他殺に見せ掛けて自殺したのではないか、という説が有力視される。しかし、ベテラン捜査官は他殺を装った自殺ではなく、他殺そのものだと主張。 上層部が検討した結果、他殺の可能性が高いと判断された。初動捜査班は既に解散されていたので、「支援捜査」の名目で、浅倉が捜査する事になったのだ。 浅倉達は、山中の殺害の動機を二つに絞る。仕事上のトラブルと、恋愛上のトラブル。 山中は、いわゆるブラック企業で勤務していた。労働条件の改善を会社側に訴えたが、会社の顧問弁護士の意見により、完全に無視されていた。そこで、「東京青年ユニオン」という労働者支援団体に相談する。「東京青年ユニオン」の代表長坂は、山中の勤務先である「くつろぎ商事」に押し掛け、交渉のテーブルに着くよう、迫る。しかし、「くつろぎ商事」はこれを渋っていた。 また、山中には別れたばかりの恋人理恵がいた。別れた理由は、山中が多忙過ぎて全く会えないから、だった。そんな事もあり、山中にはまだ未練があり、理恵に対しストーカー紛いの事をしていた。理恵の新しい恋人である田浦はこれを腹立たしく思い、山中を殴った事もあった。 仕事上のトラブルが動機だとすると、「くつろぎ商事」は山中に何らかの弱みを握られ、それに危機感を抱き、殺害したという事になる。 恋愛上のトラブルが動機だとすると、理恵と田浦は、ストーカー行為を止めない山中に対し、手を下したという事になる。 浅倉達は二手に分かれ、双方の線を洗い出しする。「くつろぎ商事」では、専務が納入業者から巨額のリベートを得ているらしい事が発覚。山中がこの事実を掴み、労働条件を改善しろと脅していたら、専務が何者かを雇って殺させた可能性が高くなった。 一方、理恵と田浦は、ネットのサイトで、交換殺人をしないかと持ち掛けていたことが発覚。理恵と田浦が殺させた可能性も高くなった。 浅倉達は捜査を進める。理恵と田浦の線は、捜査が進むにつれ薄くなっていた。 しかし、「くつろぎ商事」の線は、専務を事情聴取した直後に浅倉が暴漢によって襲われる等、濃くなっていった。 暴漢を取り押さえた浅倉達は、暴漢から証言を得て、専務を拘束する。 専務は、巨額のリベートを得て、自分の懐に納めていた事、浅倉が「支援捜査」の目的で事情聴取に来た事を脅威に思って暴漢に襲わせた事を認める。しかし、山中の死には関与していない、と主張する。 裏付け調査も、専務が山中の死に関わっていない可能性が高い事を示していた。 浅倉は、「くつろぎ商事」でリベートを得ていたのは専務だけでなく、会社そのもの、つまり社長も一枚噛んでいたのでは、と考える。 この事実を社長に突き付けるが、社長はリベートについて全く知らず、山中の死にも関与していない、と主張した。 捜査は完全に振り出しに戻る事となった。 その時点で、浅倉は新たな線を見付ける。「くつろぎ商事」の顧問弁護士が、実は女装マニアだったのだ。顧問弁護士は、この弱みを何者かに握られ、悪事を働いているようだった。 浅倉は、顧問弁護士の身辺を洗う。 また、山中の身辺も再度洗う。すると、山中は「東京青年ユニオン」があまり助けにならないと感じていて、学生時代の先輩小池にも相談していた事が分かった。小池は顧問弁護士の周辺をうろつき、彼が女装マニアである事実を掴む。 小池こそ、顧問弁護士に悪事を働かせていた人物だった。若者を集め、集金車強盗をしていたのである。 山中は、この事実を知った為、小池に殺された可能性が高くなってきた。 浅倉の部下らは、小池を確保すべきだと主張するが、浅倉は、小池が全てを計画したにしては若過ぎる、黒幕がいる筈だ、と考え、捜査を継続させる。 すると、また新たな事実が発覚。小池の伯父は、「東京青年ユニオン」の代表長坂だったのだ。 浅倉達は、漸く事件の全貌を掴む。 山中は、労働条件を改善して貰う為に、「東京青年ユニオン」と接触している内に、そこの代表が甥で学生時代の先輩である小池と、「くつろぎ商事」の顧問弁護士と結託して集金車強盗をしていた事実を知ってしまったのだ。 その為、頼っていた筈の長坂に殺されたのだった。 浅倉は、長坂を確保する。解説: 物凄い安っぽい刑事ドラマのノベライズみたいな小説。「特務武装班」として、刑事らを必要以上に武装させて、格好良く見せかけているものの、事件そのものは小粒。国際的テロ組織と対峙するならともかく、何故この程度の犯罪者を取り締まるのに武装させるのか、と思ってしまう。 作中では、一般の犯罪捜査でも刑事を武装させるべきだといった論争が繰り広げられるが、本作の捜査手法を読む限りでは、こういう奴らに武装させては不味い、と寧ろ思ってしまう。 浅倉は、特務捜査官という立場にありながら、物凄い女好きで、女を次々と取り替えては情事に及んでいる、という設定になっている。現実では、この手の者は、特務捜査官に適していない、と検討段階で真っ先に撥ねられそう。ハニートラップに引っ掛かり易い、という理由で。何故こんなキャラ設定にしたのか、さっぱり分からない。 捜査班全員が、浅倉の上司である班長を含めてやけに和気藹々とやっている姿も、作り物っぽい。警察官というより、刑事捜査も行う仲良しクラブの雰囲気。 一企業の重役が殺し屋を当たり前の様に雇えたり、銃を手に入れたり出来るのも、異様な感じ。 銃刀が厳しく取り締まられている日本を舞台にしているとは到底思えない。 もし、作中の様に一般市民が銃器を手に入れられるなら、刑事を武装させたがるのも当然か。 捜査手法も、仮説を立てては容疑を向けられた者の下に押し掛け、自供を促すというもの。 仮説が完全に正しければそういう捜査手法も問題無いが、裏付けもなく、見切り発車で容疑対象者の下へと走るので(無論、武装して)、部分的にしか合っていない、もしくは完全に思い込み違い、という例が多い。容疑対象者を「シロ」と判断する材料も、相手の反応と自分らの直感だけで、科学的根拠に基づいたものではない。 何故この班が有能扱いされるのか、さっぱり分からない。 今回のケースでも、ある企業の汚職問題を副産物として暴いたが、その企業は本来の事件には全く関わっていなかった。「くつろぎ商事」の仕業である可能性が高い、と散々掻き立てながら、実は全く違いました、という結末は、どんでん返しのつもりらしい。 ただ、被害者山中の先輩で、「東京青年ユニオン」の代表の甥である小池は、「くつろぎ商事」が山中殺害に関しては完全に「シロ」だというのが判明したラスト辺りにやっと登場するので、どんでん返しというより反則っぽく、白けてしまう。「東京青年ユニオン」の代表が山中を殺した、という真相も、意外に思うより、取って付けた印象しか残らない。 何故初動捜査班は、この程度の真相も暴けなかったのか、と警察の捜査能力を疑ってしまう。普通に捜査していれば、小池という存在に直ぐ気付く筈だし、その伯父が「東京青年ユニオン」の代表であり、この代表が胡散臭い人物である事も掴めた筈。「くつろぎ商事」のリベート問題は暴けなかったとしても、集金車強盗の方は充分暴けた筈なのだ。 本作は、構想を練りに練って書かれた小説、というより、出版社が書店のスペースを確保し続けたいが為にお抱えの作家にそれっぽいのを書き飛ばさせた、といった代物。「捜査班」ではなく、「一人の捜査官が単独で捜査する」という設定にし、無駄な銃撃シーンは省略し、被害者の元恋人の線も省略し、「くつろぎ商事」の腐敗の線だけに焦点を当てる内容にしておけば、より引き締まった小説になっていただろうに、と思う。怪死 [ 南英男 ]価格:702円(税込、送料無料) (2016/10/21時点)
2016.10.18
コメント(0)
-

ポイズン毒POISON/赤川次郎著
主にユーモアミステリ作家として名を馳せている赤川次郎のオムニバス短編集。 4篇から成り、1つの長編としても読める様になっている。「完全犯罪」を約束する毒薬を巡る人間ドラマを描く。粗筋:第一章 男が恋人を殺すとき ある大学研究室の松井教授は、アフリカから未知の毒薬を持ち帰った。その毒薬は、僅か1滴で致死量に達し、現在の医学では検出不可能で心臓麻痺としか診れず、しかも効き目は摂取から24時間後という、驚異的なものだった。しかし、松井教授はあくまでも研究の対象として持ち帰っただけで、研究室に閉じ篭もりで研究に没頭していた。だが、毒薬の存在は、大学内では次第に知られるようになっていた。 松井教授の助手の笹田直子は、この状況に危険を感じていた。毒薬が万が一盗まれ、使われてしまったら、松井教授は大学を追われてしまう、と。そこで、彼女は、毒薬についてマスコミにリークしてしまおう、と考える。毒薬の存在が明らかになってしまえば、仮に盗まれても使われる事は無いだろう、と。 直子は、恋人で、雑誌記者である秋本にこの毒薬について語る。秋本と直子は、松井の下へ向かい、毒薬について公表する事を迫る。助手の熱意に、松井は折れる。秋本が、松井に指示された通り毒薬の保管場所に向かった所、毒薬の入った瓶は消えていた。 毒薬が盗難に遭った事は、マスコミに取り上げられ、大騒ぎになる。 しかし、毒薬を盗んだのは、実は秋本だった。保管場所の中を覗く振りをして瓶を取り出し、最初から無かったかの様に装ったのだった。 秋本には、殺したい相手がいた。直子とは別の愛人だった。愛人の真由美は秋本の子を宿していて、結婚を迫っていた。秋本は、それを重荷に思い、毒薬で殺そうと決めたのだった。幸か不幸か、真由美は秋本という恋人がいる事を周囲の誰にも知らせていなかった。したがって、真由美が死んで、不審死と見なされても、警察の手は自分には及ばないだろう、と考える。 秋本は、食事に毒を盛る事に成功。真由美は、24時間後に心臓麻痺で死亡した。 しかし、真由美が付き合っていたのは、秋本だけではなかった。真由美は、別の男とラブホテルにいた所、心臓麻痺で死んだのだった。その場にいた男は、真由美の死体を放置して逃げた為、警察が事件と見なして捜査を開始。毒薬についてはマスコミを通じて知っていたので、この死はそれによるものではないか、と見なした。 秋本は、真由美が自分以外に二人の男性と付き合っていた事、そしてど二人の男に金を貢がせさせていたのを知り、驚く。 真由美の死について、中野刑事から知らされていた直子は、真由美と秋本が同郷だと知り、これは偶然ではないと悟る。 同じ頃、秋本は真由美の別の恋人だった男の一人と揉み合いになり、死なせてしまっていた。 真由美にとって、本当の恋人は秋本で、他の二人はあくまでも金をせびり取る為だけに付き合っていた。真由美は不治の病を患っていて、秋本に金を残す事が彼女にとって唯一の愛情表現だったのだ。 全てが裏手に回ったと悟った秋本は、直子の下を訪れ、自分が毒薬を盗み、それで真由美を殺し、更に自分自身にも毒を盛った事を告げる。直子の目の前で、毒による心臓麻痺で死ぬ。 毒薬の入った瓶は、捜査の課程で秋本の住居を訪れた中野刑事に盗まれる。第二章 刑事が容疑者を殺すとき 毒薬を盗んだ中野刑事には、何が何でも許せない男がいた。 原田である。彼は、中野刑事の捜査によって幼女誘拐殺人の容疑で逮捕されたものの、証拠不足で不起訴処分となっていた。しかし、世間は彼を犯人扱いし、社会的制裁を受けていた。 ただ、中野刑事は、それだけでは満足していなかった。犯人は奴以外には有り得ない、自由の身でいる事が許せない、と。 中野刑事は、原田と再会。近所に越してきたという。 中野刑事は、原田は自分の娘を狙っている、と確信する。 直子は、毒薬の入った瓶が秋本の住居から見付からなかった事を不審に思っていた。秋本は、死ぬ直前に、瓶は自宅にある、と告げていたからだ。誰かが盗んだとしたら、それは秋本の住居を出入りしていた警察関係者しか有り得ない、と感じていた。 中野刑事は、原田に、毒を盛る事に成功する。後は24時間後に死亡するのを待つだけとなった。 が、原田は、予想外の行動に移る。中野刑事の妻を殺し、娘を攫って殺したのだ。その直後に毒による心臓麻痺で死ぬ。 中野刑事は、自分の娘と、原田の遺体を発見し、激怒。原田の遺体に銃弾を撃ち捲る。それを阻止しようとした別の刑事の銃弾を浴び、中野刑事は死亡する。 毒薬が入った瓶は、偶然その現場付近でロケをしていたアイドルの牧本弥生が手にしていた。第三章 スターがファンを殺すとき アイドルの牧本弥生は、悩んでいた。 ある「ファン」が、時折電話を寄越し、業界の者でしか知り得ない情報を提供してくるのだ。「ファン」によると、弥生が所属する芸能事務所は弥生を最早落ち目だと見なし、次のアイドルの売り出しに掛かっているというのである。 その新アイドルの名は、南星久美子。 弥生は、「ファン」の情報を無視しようとするが、所属事務所が南星久美子を推しているのは、疑いようの無い事実だった。これに苛立った弥生は、大杉マネージャーに辛く当たるようになる。 弥生は、ライバルの南星久美子は勿論、「ファン」も恨むようになる。「ファン」を毒薬でどうにか殺せないか、と思うようになる。毒薬の効果は、自身の目障りな付き人を死なせる事で、確認済みだった。 直子は、弥生の付き人が心臓麻痺で死んだ事、そして中野刑事が死亡した現場付近で弥生がロケをしていた事を知り、弥生が毒薬を持っているのではないかと疑うようになる。 弥生は、「ファン」に贈り物という形で、毒薬を届ける事に成功する。同時に、ライバルの南星久美子の弱みを握れた、と確信する。弥生はその弱みを利用して、南星久美子をアイドルの座から蹴落とそうとする。 が、南星久美子はその弱みは事実でない、と告げる。弥生は、その時点で「ファン」は弥生をライバル視していた南星久美子だった事、そして「ファン」による一連の行動は南星久美子とその愛人である大杉マネージャーが仕組んだ事だったと知り、発狂する。 大杉は、その後弥生が「ファン」に贈った毒入りの菓子を食べ、死亡する。 毒薬が入った瓶は、弥生が潜伏していたホテルのボーイが手にしていた。第四章 ボーイが客を殺すとき ホテルのボーイである笹谷は、過激派組織の元メンバーだった。 組織は壊滅され、既に存在していなかったが、笹谷は要人暗殺の野望をまだ捨てていなかった。そんな事もあり、政治家がよく利用するホテルの従業員になり、機会を待っていたのである。 そんな所、毒薬を手に入れた。しかもホテルでは、近々大物政治家が出席する結婚式が催される予定だった。 笹谷は、毒薬を使って、政治家らを纏めて殺してしまおう、と企む。 丁度その時、邪魔が入る。組織の元指導者で、現在はただの浮浪者の柴田が、金をせびりに、彼の下を訪れたのだ。柴田は警察からマークされているので、接触した者は全て調べ上げられる。柴田に下手に接触されては不味いと悟った笹谷は、同じ組織の元メンバーで、同棲していた浩美に、毒薬を使って殺させる。 直子は、弥生が潜伏していたホテルの存在を知り、毒薬の瓶が無かったかを問い合わせる。ホテルは、毒薬の件が公になると、式がキャンセルになり、大損害を被ると危惧し、直子を拘束する。直子の監視役を命じられたのは、偶然にも笹谷と浩美だった。直子は、笹谷と浩美の企みを知り、止める様、説得を試みるが、笹谷と浩美は頑として応じない。 一方、警察は、柴田が心臓麻痺で死亡した事と、死ぬ直前にホテルの名を挙げていた事から、ホテルを内偵していた。笹谷の存在を知り、式を阻止しようと動く。 笹谷は、結婚式の食事に毒を盛る事に成功。出席者が毒入りの食事を食べたのを見届けると、浩美と共に自殺する。 直子は、警察に救出され、笹谷と浩美の自殺を阻止しようとするが、手遅れだった。 毒薬を盛られた筈の結婚式出席者は、どういう訳か一人も死ななかった。ただ、出席していた大物政治家らは、自分らが助かりたいが為に他の出席者よりも自分らの解毒を優先させた為、社会から非難を浴びるようになる。解説: 完全犯罪を可能にする毒を巡る人間ドラマを描いている、というのが本作の売りらしい。 確かに、様々な人間を描いている。 ただ、全編を通して読んでしまうと、全登場人物が救いようの馬鹿か、屑ばかりで、共感に値する者が一人もおらず、不満ばかりが募る。 ストーリー展開も、各編ごとに起承転結があり、サスペンスに満ちているが、どんでん返しらしきどんでん返しは無く、尻すぼみに終わる。風呂敷を広げられるだけ広げたはいいものの、どうやって畳んだら良いのか分からなくなってしまい、適当にというか、強引に畳んで無理矢理終わらせたかの様。 素材は極上なのに、調理の仕方がイマイチで、結局普通に仕上がってしまった料理を食べさせられている気分になる。 本作の最大の馬鹿は、大学教授の助手で、本作全体の主人公といえる笹田直子。 敬愛する松井教授を守る為、という自分勝手な行動により、毒薬が盗まれるきっかけを作ってしまう。松井教授を「研究の虫で世間知らず」と間抜け扱いするが、もし彼女が詰まらぬ行動を取らなかったら、一連の事件は発生していなかっただろう。別の形で発生していたかも知れないが。 本作では、著者の趣味なのか、彼女をやけに優秀扱いするが、その優秀さがこちらには全く伝わって来ない。 恋人の秋本には二股を掛けられる程鈍感だし(男性は女性の浮気にはなかなか気付かないが、女性は男性の浮気に直ぐ気付いてしまう、という定説が当て嵌まらない)、その秋本が死亡すると、敬愛しているだけの筈だった松井教授と肉体的関係を持つ様になる。 ただの阿婆擦れ。「最終的には松井教授と結ばれる事になりました。めでたしめでたし」で終わられても、読んでいる方からするとちっともめでたくない。 第一章の主人公である秋本は、どうしようもない屑。 直子という恋人がいながら、真由美という幼馴染みとも付き合っていた。真由美が妊娠して結婚を迫ると、毒薬を使って始末しようと考える。 こんな屑だと、仮に真由美の始末に完全に成功し、直子と結ばれたとしても、また浮気に走り、その相手に飽きた時点でまた殺す、という行為を繰り広げていただろう。 真由美も、秋本という恋人がいながら、他の男とも付き合い、違法行為までさせて金を貢がせるという、最低の女。 何故本編では、男女問わず、浮気性の者ここまでが登場したのか。 第二章の主人公である中野刑事は、どう考えても優秀な刑事とは思えない。 娘が一度攫われ、辛うじて無傷で戻って来て、攫った相手が分かっている筈なのに、妻に対し「注意しろ」くらいしか言わない。 もし妻に対し、娘を連れてどこかへ行っていろ、とでも命じていたら、妻は原田によって殺される事は無かっただろうし、娘も二度も攫われて最終的には殺される事は無かっただろう。 ストーリー展開も、「中野刑事が怪しいと最初から睨んでいた原田は、案の定殺人犯でした」というもので、どんでん返しは無い。「娘を狙っていたのは、実は別の人物で、原田は娘の命を救った恩人だった。しかし、中野刑事の勝手な思い込みにより、毒殺されてしまう。中野刑事は、自身の間違いを思い知らされ、大いに悔やむ」 ……という展開に何故出来なかったのかね。 第三章へと無理矢理繋ぐ為、強引というか、後味が悪いだけの一編で終わってしまっている。 第三章は、始めから第二章と強引に結び付けられている感じ。 強引過ぎて、乗り込めない。 主人公の弥生を悩ませていたライバルと、情報を次々提供する事で彼女を悩まさせていた「ファン」が実は同一人物だった、という真相が唯一の読み所。 しかし、そのライバルが何の制裁も受けず、のうのうとアイドル路線を走れる、という結末は後味が矢張り後味が悪く、すっきりしない。ライバル同士で潰し合って、最終的には誰も残りませんでした、という結末にしていたら、納得がいくものになっていただろうに。 第四章で、毒薬が漸く本領を発揮する場が与えられる。 様々な邪魔が入るものの、テロリストの笹谷は政府要人の大量虐殺に成功する。 ……と思っていたら、これまで物凄く効果を発揮していた毒は、この時だけは何の効果も無く、誰も死なない、という尻すぼみのオチで終わる。 松井は「化学反応を起こして無害になったのだろう」としか言えない。散々研究していて、その程度の見解しか出せないのかよ、と思ってしまう。 四篇には、いずれも直子と松井教授が関わってくる。 松井教授は、作中ではひたすら冴えないオッサンとして描かれている。 実は松井教授はとんでもない食わせ物で、一連の事件は全て彼が意図したものだった……、という大どんでん返しが用意されている、と思いきや、そんな手の込んだ展開にはなっていない。 松井教授は結局最後まで冴えないオッサンで、どういう訳か直子と結ばれる、という結末になっている。「夢の完全犯罪を成し遂げられる!」が売りの毒薬の筈なのに、最初の一編でその存在がマスコミを通じて世間に知られてしまい、心臓麻痺に見える突然死には全て警察の手が入ってしまっている。この時点で、「夢の完全犯罪を成し遂げられる!」という設定がそもそも崩れてしまっているのはおかしい。 これだったら何も「未知の毒薬」にしなくても、普通の毒薬で充分だろうに、と思ってしまう。 現在の医学では検出不可能な毒薬という設定自体、説明不足。リアリティに乏しく、ファンタジーの域に入ってしまう。ファンタジー小説として読め、という事か。 様々な人間模様や展開が描かれているが、小説自体は低予算メロドラマの脚本に手を加えてノベライズしたかの様で、厚みが無く、読後は何も残らない。一度読めば充分といった感じ。 赤川次郎の著作は、文体が軽く、ガンガン読み進められるので、読書の習慣を身に付けたい、と思う者にとっては入門書として打って付け。 ただ、いざ読書の習慣が身に付き、目が肥えるようになると、作品の厚みの無さ、構成力の無さ、そして後味の悪さばかりが目に付くようになり、離れて行ってしまう。 本作も、例外ではない。毒 集英社文庫 / 赤川次郎 アカガワジロウ 【文庫】価格:562円(税込、送料別) (2016/10/21時点)
2016.10.17
コメント(0)
-

秋田殺人事件/内田康夫著
著者を代表する浅見光彦シリーズの一つ。 主人公の浅見光彦が、副知事の秘書として、秋田へ飛ぶ。粗筋: 浅見光彦の兄で、警察庁刑事局長の陽一郎は、文部省の望月世津子と知り合いだった。世津子は、秋田県で起こった県営住宅建設会社の汚職事件をきっかけに、副知事に就任する事か決まった。 そんな彼女に、脅迫めいた手紙が届く。事実、彼女が調べると2つの死亡事件が当初は殺人事件として捜査されていたのに、いつの間にか自殺として処理されていた。何か大きな力が動いていると察した彼女は、陽一郎に相談しに来たのだった。 警察組織の幹部とはいえ、県警レベルで「事件性が無い」と判断を下したものを何の根拠も無く覆す事は出来ないし、表立って捜査する事も出来ない。そこで提案する。探偵めいた事をやっているルポライターで弟の光彦を秘書として起用し、捜査に当たらせてはどうか、と。 彼女はそれに賛成し、光彦は秋田へ向かう。 秋田は、汚職事件で大きく揺れていた。秋田県が出資した住宅建設会社が、欠陥住宅を売り捲っていたのだ。被害は数百件にも及び、額も百億近くになっていた。大元とされる元社長は行方をくらましていた。 自殺したとされる2人は、その後始末の為に奔走していた人物だった。多大なるストレスを抱えていたのは事実だが、焼身自殺する程とは思えない、と遺族は訴えていた。 秋田県庁も県警も、汚職事件をさっさと過去のものにしたいと考えており、光彦の捜査にはあまり協力的でないのが殆どだったが、どうにか疑問を抱く協力者を探し出し、捜査を続ける。 最終的には行方をくらましていた元住宅会社社長を探し当てる。元社長は、自殺したとされる者の遺族に対し、2億円の「示談金」を支払うと切り出す。 遺族は、光彦の予想を裏切り、見舞金を受け取ってしまう。 光彦は、「自殺者」を殺した実行犯の暴力団を探し当てた時点で捜査結果を全て警察庁に報告。警察庁も、漸く本腰を揚げる。 流石の秋田県警も警察庁の圧力に耐えられず、多数の者が左遷させられ「自殺」も殺人事件として本格的に捜査される事に。秋田県庁にもメスが入る。 それを見届けた光彦と副知事は、退任する運びとなった。 秋田を去る直前、何者かが住宅の件で被害を受けた者らに対し2億円が寄付されていたのを知る。光彦は、遺族が元社長から金を受け取ったのはこの為だったのか、今更気付いた。解説: 本作は、秋田で実際に起こった県営住宅建築会社による不正をきっかけに書かれたらしい。 いわゆる社会派小説、という事になる。 不正を世間に訴えたい、正したい、という著者の思いは痛い程理解出来るが、小説そのものは著者の自己満足に終わっていて、何も響いてこない。 主人公の光彦は警察庁刑事局長の兄が一目を置く程優秀な探偵、という設定になっているらしいが、その優秀振りが発揮される事は最後まで無い。何かあると、「私はあの警察庁刑事局長の弟です」という事実をさらけ出し、警察関係者から情報を無理矢理引き出すか、嫌がらせする警察関係者を引き下がらせるだけ。兄の七光が無かったら、何の動きも取れないと思われる。 光彦の探偵としての作法は、事件関係者の元に足を運んで、ひたすら質問するだけ。 必ずしも間違っている訳ではないが、やり方を見る限りでは、何度か足を運んでいる内にその中の誰かが「分かりました。私が犯人です。全てをお話しします」と認めるのを期待しているかの様で、探偵ならではの閃きや推理というのは一切無い。 光彦の無能振りを象徴するのが、遺族が元社長から金を受け取ると、「遺族は金に目がくらんでしまったのか」と勝手に判断し、失望して、それまで密に連絡を取っていたのに、関係を一切絶つ場面。 後に新聞で2億円が寄付されたのを知って、遺族が自分らの為に金を受け取ったのではない、と気付くのである。 様々な人間と接している筈の「ルポライター兼名探偵」で、「勘が良い」と兄から評されているのに、この程度の読みすら出来ないのはおかしい。 光彦の実家は、警察組織の官僚を輩出しているものの、昔からの名家という訳ではない。にも拘らずお手伝いさんがいて、そのお手伝いや母親が「スーパーマーケットはお坊ちゃまが行く様な場所ではない」と光彦を諌める等、妙に名家ぶっているのも、嫌味にしか見えず、キャラの好感度を下げている。 推理小説、とはなっているが、圧倒的なトリックは無く(謎めいた2つの殺人事件は、結局暴力団関係者が直接手を下しただけ)、ラストでのどんでん返しも無く、物語の展開も先が読めてしまう。 無駄に長いだけで、何の驚きも感動も無い代物に仕上がっている。 出版社の事情で書店の棚を埋める為に、著者はその原稿を埋めているだけで、技巧を凝らしている余裕なんて無い、といった感じ。 社会派小説は、本来は社会の問題点を小説という形で炙り出し、世間に訴え、世論がそうした問題の解決へと動くよう、促す為のもの。 しかし、本作は全て著者の自己満足・自己完結で終わっている。 作中の住宅汚職問題も解決する流れへと向かう形になっているし、殺人事件も解決するし、罰せられるべき者は罰せられ、称賛されるべき者は称賛される。 著者は、本作を読んだ読者が何をする事を期待するのか。大抵の読者は、本作を読む事で本作のベースとなった実際の事件も「解決した」と見なし、それ以上追及しないだろう。 社会派小説が、現実問題が小説の様に見事解決していると読者に錯覚を与えるようでは、本末転倒なのだが。 錯覚を与える社会派小説も、フィクション上のカタルシスを与える程度なら問題は無い。 本作の問題は、秋田県警の腐敗振り、そして日本の警察制度の問題が炙り出したのに、その事については軽くしか触れておらず、「悪いのは秋田県庁と暴力団」とされ、秋田県警の処分は主要人物の左遷や降格人事でお茶を濁している事。 光彦も、それを良しとしている。 ルポライターで、ジャーナリストの端くれの筈なのに、警察組織の腐敗振りは弁護しながら、県庁や県職員の腐敗振りには執拗に批判するダブルスタンダード。一番ライターに適していない人物である。 作中で、光彦は「警察という組織は強いが、個々の警察官は弱く、組織の意向に従わざるを得ない飼い犬的な存在」と評している。 この発言は、警察という組織に直接属していないにも拘わらず、身内が警察官という事で、光彦自身が警察に飼い慣らされた飼い犬である事を示している。 もし光彦の発言が正しいとするのなら、ナチスのメンバーが犯した犯罪は、幹部以外は無罪放免にすべき、という事になってしまう。 本作では、二人のヒロインが登場、という事になっている。 一人は副知事に任命された望月世津子。 もう一人は、自殺者(実際には殺人被害者)の娘で、元社長の「示談金」を受け入れてしまう留美子。 望月世津子は、美人で、やり手の官僚で、正義感が強い……、という「善い人」を漫画風に描いたキャラで、深みが無く、リアリティに乏しい。 にも拘わらず、作中で何度も登場させ、彼女がいかに魅力的であるか、読者に訴えようとするのだが、全く伝わって来ない。 留美子は、最初は光彦に警戒感を抱きながら、徐々に信頼していき、協力していく。こちらの方が、キャラとしては深みがある。しかし、「示談金」を受け入れた時、光彦が「金に買収された」と勘違いした結果、物語から退場してしまう。 何故光彦が留美子に対し「示談金」を受け入れたのか、と訊いて、理由を知って納得する場面や、謎の寄付金が贈り付けられた後に「示談金はこの為に受け取ったんだね」と話し合う場面を盛り込まなかったのか、よく分からない。 魅力に乏しい望月世津子は執拗に登場させているのに、若干だが共感出来る留美子は扱いが雑という、著者の意図が分からない。 本書は、巻末に、「ファンによるコメント」らしき雑文を掲載している。女性の副知事、という点以外はこれといった特徴の無い女性キャラを本書におけるヒロイン扱いして見せたり、本書のとるに取らない場面を、まるで手汗握るサスペンスに満ちたシーンであるかの様に絶賛したりしている。 本シリーズがいかに人気であるかをアピールするかの様に。 児童文学ならともかく、大人向けの読み物とは思えない。 本シリーズに人気があるとすれば、それは低予算でテレビドラマ化し易く、その手の物を有難がって観たがる視聴者がいるからだろう。 冷静に考えてみれば、人気となる要素は何も無く、出版社や放送局によって都合よく「作られた人気」であるのがよく分かる筈なのに。【中古】 秋田殺人事件 長編推理小説 光文社文庫/内田康夫(著者) 【中古】afb価格:108円(税込、送料別) (2016/10/21時点)
2016.10.16
コメント(0)
-

中央アルプス殺人事件/梓林太郎著
自身の登山の経験を活かして小説を発表する梓林太郎の長編ミステリー。 当然ながら、登山がストーリーに深く関わっている。粗筋: 旅情報誌の記者小池南海子が、取材旅行に出掛けた後、消息を絶った。 出版社の話では、編集部に女性のシルエットが写った写真と、この女性は何者か調べてもらいたい、といった匿名の手紙が送り付けられて来た。消印では、諏訪市から送られた、となっていた。 手紙の内容そのものが記事になるかは疑問だったが、諏訪湖周辺を取材する口実にはなる、という事で南海子は取材旅行へと発った。 初日は、問題の写真は当初思われていた諏訪湖で撮られたものではないらしい、といった報告があったが、それ以降は連絡が無い。 出版社は心配になって、南海子の自宅に問い合わせるに至った。 家族にも連絡が入っていないのを知り、警察に通報する運びとなったのだった。 兄の克人は、旅発つ際に妹に不審な部分は見受けられなかったし、仕事を放棄して行方をくらます理由も思い付かなかったので、事件だと確信する。が、警察からすればこの程度の事態は日常茶飯事なので、訴えても家出人として受理するだけだった。 克人は、南海子の同僚の鎌田と共に、南海子を探す事に。 南海子が取材に訪れたと思われる場所を訪ねると、確かに南海子が訪れた、という情報が得られた。が、南海子が言っていたのと同じ様に、問題の写真の撮影場所が分からない。 手紙の封筒に書かれていた住所も、現在は市町村合併に伴い使われていない地名だった。 克人と鎌田は、近くの別の湖を訪れると、漸く写真に写っていた女性を発見。宮島沙絵という名の女性だった。話を聞くと、この湖をよく訪れているという。しかし、写真に撮られていた事は知らず、その写真が出版社に送られていた事も知らなかった。 ここで、捜査の糸が途切れる。 手紙を送り付けた者は、南海子を何らかの理由で誘き出して拉致した、というのは分かったが、誰が、どういった理由でそんな行動に出たのかは分からなかった。 警察も、相変わらず単なる失踪事件としか見なさず、本腰を入れて捜査しようとしない。 克人は、あらゆる手段を使って妹の行方を捜すが、決定的な情報は得られなかった。 数週間後、能登で女性の遺体が発見された、という情報が入る。克人が確認しに行くと、南海子だった。何者かによって殺害されたのは明白だった。 南海子の葬式が営まれ、友人知人が多数集まる。その中に、克人の登山仲間の細野と三上もいた。細野は南海子に好意を寄せていた事もあり、落ち込んでいた。 細野は、その後登山中に消息を絶つ。数日後、遺体となって発見された、当初は滑落による事故死と思われたが、登山用具で殺されていたのが判明。 それから間もなく、三上も登山中に行方不明になり、その後遺体となって発見される。彼も、何者かに殺害されていた。 一連の殺人事件が互いに無関係とは思えず、克人は一体誰が妹と友人二人を殺したのか、と思う。 そしてついに、克人も何者かに狙われるように。 要するに、何者かが南海子、細野、三上、そして克人に恨みを抱き、殺害に及んでいるらしい。 克人は、自分らに殺される程恨まれる様な事をした覚えは無かった。あるとしたら、共通の趣味である登山関連の事である。 そもそも、細野も三上も登山中に殺害されているので、犯人が登山経験者なのは疑いようが無い。 その時点で、克人はある事件を思い出す。 少し前、克人、細野、そして三上の三人は雪山を登山した。雪に阻まれ、予定が狂ったものの、三人は救助を要請する事無く自力で下山した。 それとほぼ同時期に、別の登山グループが同じ様に雪に阻まれ、救助隊へSOSを発信し、救助されていた。 話によると、この登山グループは大した雪でもないのにSOSを出してしまい、救助されていた。 この事に克人らは憤りを感じた。何故なら、救助を要請したのが自分らだと勘違いされてしまったからだ。南海子は、易々と救助を求めたがる者は登山すべきでない、SOSを要請したのは何か別の理由があったのではないか、といった趣旨の記事を雑誌に載せた。 この記事が怒りを買ったのでは、と克人は考える。 克人は、SOSを出した登山者の身元を特定。奥村という人物だった。 奥村は結婚していたが、順子という愛人がいて、現在はその女と夫婦同然の生活をしていた。が、つい最近、会社を辞めていた。順子も、数ヶ月前から姿を現さなくなっていた。 奥村の周辺を聞き込み調査したところ、彼にはまた別の愛人が出来たとの事だった。 順子の行方は、彼女の親すら知らなかった。 怪しいと感じた克人は、警察に通報。 警察は、奥村から事情聴取し、事件の全貌が漸く明らかに。 奥村は、結婚している身で、順子という愛人がいながら、また別の女と付き合うようになっていた。 順子は、奥村と正式に夫婦になれない事に苛立ちを感じ、奥村をなじる。 口論になり、奥村は順子を殺してしまった。 奥村は、登山仲間と登山に出掛ける直前だった。土壇場でキャンセルしたら怪しまれると思い、順子の遺体を自宅に残したまま、登山に向かった。いざ山に登ると、今度は自宅に残した遺体が心配に。急いで帰りたい、との思いから、SOSで救助を要請してしまった。 SOSで「救助」されて自宅に戻ると、遺体はそのまま残っていた。取り越し苦労だった。 奥村は、遺体を山で処分する事に。 遺体を車に乗せて山道を進んでいると、女性がヒッチハイクしていた。奥村はどうしてもその女を無視出来ず、乗せてしまう。その女性は、雑誌記者の南海子だった。 南海子を乗せた結果、その時は遺体を処分出来なくなった。 南海子が登山関連の記事も書いている記者だと聞いて、彼女の記事が載っている雑誌を入手。すると、登山でSOSを発して救助されたグループを批判する内容の記事が載っていた。記事は、SOSを要請したのは何か別の理由があったのではないか、で結んであった。また、克人、細野、三上も、同様の内容の投稿をしていた。 記事を読んだ奥村は、南海子があの時ヒッチハイクしていて、彼の車に乗ったのは、「別の理由」を探る為に、彼の周辺を嗅ぎ回っているからではないか、と早合点。 口封じの為に、4人を殺さなければ、と思うように。 奥村は順子の遺体を処分した後、南海子を誘き出す方法を考える。偶々撮った写真を出版社に送り付け、誘き出す事にした。 南海子は思惑通り誘き出され、奥村は彼女を拉致。話を聞いてみると、あの時彼女がその場をヒッチハイクし、奥村の車に乗ったのは単なる偶然で、記事の「別の理由がある」といった文句も、確信があった書いたのではないのが分かった。が、今更解放する訳にもいかず、殺害。 他の3人も、やはり何か知っているのでは、という考えも捨て切れず、SOSでの救助要請について小馬鹿にされたもの許せなかったので、殺す事に。 その結果、細野と三上は殺せた。が、克人は何度か試みたものの失敗し、逆に追われ、逮捕されるに至った。解説: 日本のミステリーで発表される例に漏れず、低予算でテレビドラマ化出来そうな内容。 奇想天外なトリックも、ラストでのどんでん返しも無く、ごく普通の事件を坦々と追うだけの展開になっている。 本作は、事前に裏表紙の粗筋を読んでいるか、いないかで、大きく評価が変わる。 裏表紙を読んでいない場合、何の事前知識も無く物語が進んでいくので、「主人公の妹は無事なのか? ・・・・・・無事じゃなかったか。残念。じゃ、犯人は誰だろう?」という風に読める。 が、裏表紙を読んでいる場合(大抵の読者はそうするだろう)、主人公の妹が他殺死体となって発見される事も、主人公の登山仲間が次々死んでいくのは既に分かってしまっている(そういう内容の粗筋)。したがって、失踪した妹が死体となって発見されるまでの経緯や、登山仲間が次々と殺されるまでを延々と引っ張られても、間延び感しか抱かない。 漸く妹の他殺死体が発見され、登山仲間が殺される頃には、物語の大半が終わっていて、後は主人公が別の登山グループを疑い、犯人に行き着くほんの僅かな展開しか残っていない。 著者が裏表紙の粗筋を書いたのではないと思われるが、何故物語の殆どをばらしてしまう内容にしてしまったのかが分からない。「妹が取材旅行中に突然失踪し、兄が行方を捜している内に、過去の事件との関係が明らかになっていく」・・・・・・くらいの粗筋に出来なかったのかね。 あまりにもスローペースな展開なので、粗筋を担当した編集者(だろう)は、ネタバレしない粗筋を書けなかったのか。 よく分からないのが、奥村が愛人を殺害した後登山に行き、SOSで救助要請を出して急いで帰宅し、死体を捨てに行くまでの期間。 死体が腐敗する事を考えると、そう長い期間とは思えない。数日、長くて1週間だろう。 が、奥村が死体を捨てに山に向かうと、そこで奥村がSOSで救助要請を出して下山した事を非難する記事を書いていた南海子がいた、という展開になっている。 登山中に起こった事件が、そんな短期間の内に記事になり、奥村本人が「これは俺の事を書いている! 俺の事を疑っている!」として読む事が出来るのか。 犯人の奥村も、行動に一貫性が無い。 結婚している身にも拘わらず愛人を作り捲くり、その内一人を行きばったりで殺してしまうのだから、かなりいい加減な性格。殺した直後に登山に参加しながら、山中では自宅に残した死体が心配になって、嘘のSOSで救助を要請し、なるべく早い下山を試みる無計画振り。その場しのぎで人生を歩んでいる様である。 ・・・・・・と思いきや、南海子、細野、三上の殺害では、顔見知りでない3人の身元を探し当てて徹底的に調べ上げ、住所や行動を把握する等、やけに周到に計画して実行に移している。 やけに周到に計画して実行に移した犯行の動機は、本人の勘違い。必要の無い犯行に手を染め、自滅している。 賢いのか、鈍いのか、さっぱり分からない。 警察がひたすら無能なのも気になる。 2件の殺人は登山中に起こっている遺留物が色々残っているし、そもそも重装備が必要となるレベルの登山となれば容疑者も限られてくるので、直ぐ特定出来るのではないかと思いきや、克人が奥村を突き止め、通報するまで、誰が犯人なのか検討も付いていなかったらしい。 事件捜査をした経験が無い素人探偵がどうにか行き当たった真相を、何故警察が全く掴めなかったのか。 複線の意味も分からない。 写真に写っていた宮島沙絵を探し当て、彼女が湖に毎日の様に立っていた理由を追及する場面にかなりのページが割かれているものの、殺人事件には全く関係が無い(この部分が本書の展開のペースを落としている)。 彼女は浮気をしていて、その浮気相手が登山中に失踪した為、その山を見つめていた、浮気相手は実際には死んでおらず、別の場所で偽名で働いていた・・・・・・、といった事実が明らかになるが、読者からすれば「だから何? 殺人事件の方はどうなってるの?」といった感じ。 著者が登山経験が豊富な事もあり、本書にはその知識が至る箇所に散りばめられているが、それが面白い小説を成立させているのかというと、そうでもない気がする。【中古】 中央アルプス殺人事件 桃園文庫/梓林太郎(著者) 【中古】afb価格:198円(税込、送料別) (2016/10/21時点)
2016.07.05
コメント(0)
-

伊豆の踊り子殺人事件/島田一男著
推理小説家島田一男による長編推理小説。 1994年に、単行本書下ろしとして出版。粗筋: 会合に出席していた科学警察研究所の岩谷警視と、八島技官は、伊豆で発生した変死事件捜査に加わるよう、要請される。 岩谷は以前伊豆の警察署に赴任していた経歴があり、適任だと思われたからだ。 地元の警察と接触した岩谷は、変死したのが美人で知られていた旅館の女将杉野真美と知って、驚く。旧知の間柄だったからだ。 遺体の状況から、事件性が高い、と岩谷は判断。薬物が検出された事から、殺人事件である事はほぼ確定的となった。 岩谷は、何故真美が殺されたのか、と不思議に思う。 殺されるとしたら、真美より、その夫だろう、と思ったのだ。真美の夫杉野正夫は、様々な女を連れ込んでは肉体関係を結んでいた。レイプも当たり前の様にしており、それらの後始末は決まって真美に押し付けていたのだ。 岩谷は、杉野正夫が5年前に亡くなっていた事を知らされる。妻との情事中の腹上死だったという。レイプ魔らしい死に方だ、と妙に納得する。 真美の葬式が営まれる。 それに出席していた芸者百々子が、突然死亡。毒を仕込まれていた。百々子も、杉野正夫にレイプされた経験があった。百々子はそれを良い事に、金を搾り取るだけ搾り取ったという。真美はこれについて怒るどころか、同情し、二人は姉妹の様な仲だった。 それから間も無く、近くの病院の婦長三沢良子が死亡する。良子も、杉野正夫とは旧知の間柄だった。 更に、杉野正夫の顧問弁護士だった大屋勝美も死亡。 5年前に死去している杉野正夫と関わりのあった女性が、何故短期間の内に次々死亡しているのだ、と岩谷は不思議に思っている内に、20年前のある事件を思い出した。 20年前、杉野正夫は旅芸人の女性をレイプした。女性はその際現場に居合わせた百々子に助けを求めたが、彼女は助けるどころか扉を閉じて、女性が逃げられないようにしてしまった。事が終わった後、真美は女性に金を渡して追い出した。この時代では、女性の旅芸人は売春しているのも多かったので、真美は女性をその類として扱ったのだった。女性は病院に駆け込むが、婦長の三沢良子に適切な処置をしてもらえず、妊娠してしまう。女性は弁護士の大屋勝美に相談するが、取り合ってもらえないどころか、勝美はそれをネタに杉野正夫を強請って顧問弁護士の座に収まった。 この旅芸人の女性が、どういう訳か20年後の今になって復讐として殺し捲っている、と岩谷は考える。恨みの最大の対象となる杉野正夫はとっくに死去しているから、他の4人に矛先を向けたのでは、と。 岩谷は、旅芸人の女性の身元を突き止める。中川万喜子という女性だった。記録を頼りに彼女の住まいを訪ねる。すると、万喜子はかなり前に死去していたのを知る。これで捜査の糸が途切れたと思ったが、万喜子が双子の娘を産んでいた事実を掴む。杉野正夫の子だった。 生前、万喜子は双子の娘に父親について恨み節を聞かせていたという。 岩谷は、二人の娘が母の代わりに人を殺しているのでは、と考えを改める。 二人の娘は、現在20歳前後になっている筈。 そこで、岩谷は旅館で水中バレーのショーを披露している一行を思い出す。20歳前後の女性が多数いた。その中に双子の娘がいても不思議ではない、と。 岩谷は、水中バレーの一行を調べると、万喜子の双子の娘の一人が紛れ込んでいたのを知り、事情聴取するが、彼女は殺人に加わっていない、と言い張る。 実際に殺人に手を染めていたのは、万喜子の妹だった。双子の娘を母親に代わって育てた彼女は、姉をレイプした杉野正夫や、レイプを手助けしたも同然の女性4人を許せず、双子の娘が成人し、独り立ち出来たのを機に殺し捲ったのだった。粗筋: 島田一男というと、本書が書かれた時点で半世紀近くに亘って小説を発表してきたベテラン作家。 ノーベル文学賞受賞者の川端康成氏の代表作である「伊豆の踊り子」にインスパイアされて本書は書かれたと聞いて、どんな深みのある物語に仕上がっているのかと期待していたのだが……。「伊豆の踊り子」を下敷きに執筆されたのは分かるが、ストーリー展開や、登場人物の描写がやけにお粗末。 全体的に薄い。 締め切りに迫られて、苦し紛れに書き飛ばしてしまい、推敲を重ねられる前に出版されてしまった代物としか映らない。 ストーリー展開に、合理性が見受けられないのが最大の問題点。 犯人は、警察が殺人事件の捜査をしている最中に次々と人を殺している。 目と鼻の先で犯行が次々と重ねられるのを見て、警察関係者は相当悔しがり、犯人の特定に躍起になるのかと思いきや、「あ、また事件か。何故こんなに事件が続くんだろうねえ」くらいにしか思わない。捜査ものんびりと進められる。この程度の緊張感だから、犯人も甘く見たのか、次の犯行を躊躇い無く実行に移す。警察という存在がありながら、何の抑止力にもなっていない。 一方、警察が大勢ウロウロしているのにも拘わらず尚犯行を繰り広げなければならなかった犯人の心理も充分説明されていない。 テレビのサスペンスドラマでも、もう少し掘り下げて描写していると思うのだが。 4件の殺人は、小説の最初の1/3くらいで一気に描かれる。 一連の事件が、20年前のレイプ事件と関わりがある、というのも直ぐ判明。 この段階で事件は一気に解決になだれ込んでも良さそうなのだが、4人の遺体を解剖したり、レイプ事件の被害者の身元を掴んで現住所を訪れるのに相当時間を食ったり、主人公が旅館で飲み食い入浴して「伊豆の踊り子」に関する考察を述べたりと、無駄な描写が続く。 読者からすれば真相はほぼ分かっているのに、このダラダラした展開は何なのかと思ってしまう。 主人公は、被害者全てを知っていて、20年前のレイプ事件についても知っていた。 にも拘わらず4人が殺されるまで真相に行き着かない。 今回の事件は、より賢明で、より行動力のある探偵だったら、最初の2件くらいで真相に気付いていただろうし、機動力を活かして更なる犯行が起こる前に犯人を検挙していただろう。小説そのものが中編で済んでいたかも知れない。 作中で描かれた社会情勢もよく分からない。 川端康成氏が「伊豆の踊り子」を執筆した時代は、伊豆の旅芸人や踊り子が売春めいた事もしていた、というのは有り得そうだが、本作の「20年前のレイプ事件」が起こったとされるのは、1970年代。 旅芸人の女が営業先でついでに売春もしていたり、旅館の主人が女をレイプし捲っても何のお咎めも受けず、その妻が「仕方ない」と後処理に徹していたりしていたとは思えない。 それとも、1970年代の伊豆はそこまで時代に取り残されていたのか。 主人公の岩谷は科学警察研究所の特捜部長で、警視という階級にある。優秀な捜査官の筈なのに、才能を発揮しない。 よくこの程度の人物が警察官になれるな、と呆れる。 そんなものだから、キャラとして魅力的に映らず、小説を面白くしていない。 岩谷の補佐役として、女性捜査官の八島技官が登場するが、存在感がまるで無く、何の為に登場していたのかがさっぱり分からない。 推理小説というからには、驚愕の真相や、物凄く大胆なトリックや、ラストで全てが覆されるどんでん返しを期待するのだが、そういうのは無く、「20年前のレイプ事件が発端でした」という中盤で提示される推理のままラストを迎える。 著者からすれば、杉野正夫の腹上死は妻が仕組んだ、双子のすり替えがあった、双子ではなくそれらの叔母が犯行を繰り広げていた、というのが驚愕の真相や、大胆なトリックや、どんでん返しに相当するのかも知れない。が、推理小説を既に何冊も読んでいる者からすれば、それら程度は最早驚愕の真相でも、トリックでも、どんでん返しでもない。 本作は、1990年代に書き下ろされた。 この時代はこの程度のものでも「推理小説」として成り立ったのかと驚かされる。 そう古い作品でもないのに。伊豆の踊り子殺人事件【電子書籍】[ 島田一男 ]価格:432円 (2016/10/21時点)
2016.06.21
コメント(0)
-
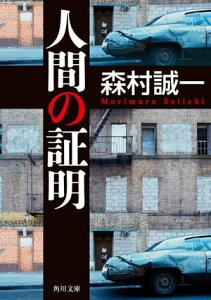
人間の証明/森村誠一著:粗筋
社会派推理小説の第一人者森村誠一による長編推理小説。 著者の代表作「棟居刑事シリーズ」第1作。 1975年に雑誌で連載。後に単行本化され、700万部を超えるベストセラーになっているという。 度々映画化・ドラマ化されている。粗筋: 舞台は1970年代。 棟居は刑事。子供の頃、目の前で父親が米兵に暴行されるという悲惨な過去があった。父親が若い女性にちょっかいを出していた米兵を諌めた所、米兵の怒りを買ったのだった。米兵は父親を散々殴った後、小便を浴びせ、その場を去ってしまう。父親は、暴行で負った怪我が原因で数日後に死亡。棟居の母親は既に彼を捨てて家を出ていたので、彼はその時点で両親を失ってしまった。棟居は、自身を捨てた母親、父親を殺した米兵、そして父親が暴行を受けるのを黙って見守っていた群衆に恨みを持ち、人間を信用しなくなっていた。刑事になったのも、正義の為ではなく、犯人を追い詰めて苦しませる為、という捩れた欲望を満たす為だった。 そんなある日、事件が発生。 黒人男性が、高級ホテルの最上階にあるレストランに到着した時点で倒れる。胸にナイフが刺さっていた。黒人はそのまま死亡した。 黒人の身元は間もなく判明する。ジョニー・ヘイワード。アメリカのニューヨークから訪日していた。 外国人が死亡した以上、国際事件になりかねない、と警察は危機感を抱き、慎重に捜査を進める。 記録によると、ジョニーは今回が初の訪日だった。にも拘らず、片言の日本語が喋られた。タクシーに乗り込んで、あまり名の知れていないビジネスホテルを指定して移動し、そこにチェックインしていた。外出中、何者かに刺され、死亡した。更なる捜査で、ジョニーは公園で刺され、瀕死の状態で高級ホテルにタクシーで向かい、力尽きたのが判明。公園から、ジョニーの所持品と思われる古い麦藁帽子が発見された。 何故ジョニーは刺された直後に助けを求めなかったのか、何故高級ホテルに向かったのか、そもそも訪日の目的は何だったのか、麦藁帽子は何の意味があるのか・・・・・・等、様々な謎が浮かび上がる。 警視庁は、インターポールを通じて、ニューヨーク市警に、ジョニーの身辺調査を依頼する。 ニューヨーク市警は、ケン・シュフタン刑事に、ジョニーの身辺調査を命じる。シュフタンは、ジョニーと同じハーレム出身なので、適任だと。シュフタンは、何故アメリカ人とはいえ日本で死んだ奴の為に動かなければならないんだと疑問に思いながらも、調査を進める。 ジョニーは、ハーレムの貧しい地域で、父親と共に暮らしていた。シュフタンは、その日暮しの生活をしていたジョニーが、どうやって海外渡航の資金を捻出したのか、と不思議に思い、更に捜査する。すると、ジョニーの父親が富豪の車にわざと接触し、慰謝料をせびり取っていた事が判明。ジョニーの父親は、それによる怪我で間もなく死亡。ジョニーは、自身の父親がまさに命懸けで得た金で日本に行き、殺された事になる。ジョニーは、旅発つ前、「日本のキスミーに行く」と知人に伝えていた。シュフタンは、調査内容を日本に報告する。 棟居は、ニューヨーク市警の調査報告を元に捜査を進めるが、「キスミー」がどこなのか分からず、行き詰っていた。そんな所、ジョニーをビジネスホテルまで乗せたタクシーの運転手が、ジョニーが車内に置き忘れたと思われる落し物を提出。西條八十の詩集だった。詩集の中に、「霧積(キリヅミ)の渓谷に麦藁帽子を落とした」といった内容の詩があった。「キスミー」とは、霧積の聞き間違えではないかと棟居は思い、群馬県の霧積温泉に向かう。捜査した結果、ジョニーは霧積と過去に関わりがあったのではないか、という断片的な情報が得られるが、鍵を握っていると思われた老婆を訪ねようとした所、老婆の死を知る。殺害された可能性が高かった。これで、また捜査の糸が途切れる。 ニューヨーク市警のシュフタンは、興味本位でジョニーの捜査を継続していた。ジョニーの写真を入手したところ、ジョニーの父親は純血な黒人なのに、ジョニーはどうやら別の人種の血が混じっている様だった。ジョニーの父親は、兵役で終戦直後の日本にいたという。シュフタンは推理する。ジョニーの母親は日本人だったが、何らかの理由で父親と母親は別れた。ジョニーは父親にアメリカに連れられ、育てられた。ジョニーが父親を犠牲にしてまで日本を訪れたのは、母親に会う為ではないか。日本に、ジョニーを殺害する動機を持つ者がいたとしたら、それは母親しかない。母親とは誰なのか。シュフタンは、これについても日本に報告する。 警視庁は、ニューヨークからの報告を受け、ジョニーの過去の洗い出しに全力を注ぐ。 棟居は、ジョニーがビジネスホテルを指定して宿泊したのは、彼の意思ではなく、何者かがそのビジネスホテルを指定したからだと推理。ビジネスホテルのオーナーは、実業家で代議士の都陽平だった。その妻は、家庭問題評論家として名を馳せていた八杉恭子だった。恭子は、霧積出身だった。 棟居は確信する。八杉恭子こそ、ジョニーが会いに行った母親だと。若い頃、兵役で日本にいたジョニーの父親と関係を持ち、ジョニーを出産。しかし、当時の社会背景から関係は認められず、分かれる羽目に。恭子はその後政治家の妻となり、家庭問題評論家としてマスコミの寵児となった。そんな中、ジョニーが母親に会いたいと訪日。隠し子の存在は、夫に知らせていなかった。知られたら破滅すると慌てた恭子は、我が子を殺した。ジョニーを生んだ直後、恭子はジョニーの父親と共に霧積を一度だけ訪れていた。それについて覚えているのは、今となっては旅館の従業員だった老婆だけ。この老婆も、恭子は谷に突き落として殺害した・・・・・・。 状況証拠は揃ったものの、決定的な物証は無い。 そこで、棟居はジョニーの所持品だったとされる麦藁帽子を恭子に突き付ける。麦藁帽子は、ジョニーとその父親と霧積へ旅行に行った際、買い与えてやったものだろう、と。ジョニーは、麦藁帽子を、母親の形見として持ち続け、日本を訪れる際にも持参した。ジョニーにとって、麦藁帽子は強烈な印象を残していて、麦藁帽子の詩を掲載した西條八十の詩集も、母親の記憶を蘇らせるものとして、ずっと持ち続けていたのだ。 棟居は、西條八十の詩を朗読。それを聞いた恭子は、動揺し、自分がジョニーを刺し、老婆を殺した事を自白。 自白によると、恭子はジョニーをナイフで刺したものの、最後の最後で躊躇いが生じ、即死には至らなかった。しかし、ジョニーは夢にまで見た母親が、最早自分を邪魔者としか見ていないと悟り、刺さっていたナイフを押し、自ら致命傷を負わせた。恭子に逃げるよう促した後、最後の力を振り絞って現場の公園を抜け、タクシーを拾い、高級ホテルで力尽きたのだった。 棟居は、事件当初から、ビジネスホテルで見かけた恭子を怪しいと思っていたが、その理由を思い出す。彼の父親は、ある女性にちょっかいを出していた米兵を諌めようとした結果暴行され、死んだ。その女性こそ若き頃の恭子だった。恭子は、父親が暴行を受けている間にその場を逃げ出していた。現場に居合わせた棟居少年に、強烈な印象を残していたのだ。「家庭問題評論家」のイメージを守る為に犯行を重ねた恭子だったが、ほぼ同時期に息子が女性を轢き逃げしていた事が判明。娘も覚醒剤使用で逮捕されていた。夫からも離婚を突き付けられ、完全に地に落ちた状況で逮捕される。 事件解決の報告を聞いたシュフタンは、ジョニーの住まいに向かうが、途中、暴漢に刺され、致命傷を負う。走馬灯の中で、シュフタンは自分が過去に犯した罪を思い出す。兵役で日本にいた頃、現地の女性にちょっかいを出そうとした所、子供連れの日本人男性に諌められた。シュフタンは激怒し、男性を暴行し、小便を浴びせた後、その場を後に。暴行した男性の子供が後に刑事になり、日本とアメリカを跨ぐ事件の捜査捜査に関わり、その事件捜査に偶然にも自分も関わっていた事等知る由も無く、シュフタンは絶命する。解説はこちら人間の証明【電子書籍】[ 森村 誠一 ]価格:778円 (2016/10/21時点)
2016.05.17
コメント(0)
-
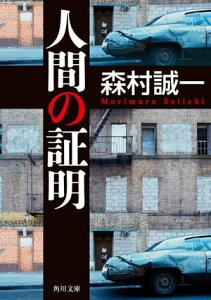
人間の証明/森村誠一著:解説
社会派推理小説の第一人者森村誠一による長編推理小説。 著者の代表作「棟居刑事シリーズ」第1作。 1975年に雑誌で連載。後に単行本化され、700万部を超えるベストセラーになっているという。 度々映画化・ドラマ化されている。解説: 森村誠一が作家として飛躍するきっかけとなった小説だという。 幾度か映画化・テレビドラマ化されてもいる。 当時の時代背景からすると、それも納得出来る読み物になっている。 しかし、今の時代、事前知識抜きで読むと、単に古臭いだけの小説に感じる。 本作は「推理小説」となっている。 ただ、冒頭では興味深い「謎」が提供されるものの、捜査の過程であっさりと解けてしまい、「普通の事件」になってしまう。後は主人公である刑事らが事件をひたすら追って解決するまでの経緯を描いているだけ。「推理小説」の言葉でイメージする意外な展開や、奇怪なトリックや、ラストで全てを覆す大どんでん返しは無い。大抵の読者なら予想するであろう展開から逸れる事無く、物語は進む。 要するに、物足りないのである。 この物足りなさが、最大のトリックとも言える。幾度も映像化されている「大傑作」が、まさかこんな物足りない終わり方になるとは、と。 当時はこの程度で「推理小説」を名乗れたのか、と驚いてしまう。 物足りなさの最大の理由が、捜査が全てご都合主義で進み、解決に至る事。 ジョニーは、瀕死の状態で突然高級ホテルに現れ、息を引き取る。1970年代の日本では非常に目立つ黒人が、どこからやってどうやって来たのか・・・・・・。 ・・・・・・捜査の過程で、タクシーで近くの公園から移動して来たのが、あっさりと判明。 ジョニーは、アメリカでは裕福とは言い難い家庭の出身。そんな者がどうやって訪日の為の資金を捻出したのか・・・・・・。 ・・・・・・ニューヨーク市警の刑事が、ジョニーの父親が当たり屋をやって金をせびり取ったのが、あっさりと判明。 ・・・・・・・現場の公園で麦藁帽子を発見。これは事件と結び付くのか? はい、そう。ジョニーが落としたもの。ジョニーが麦藁帽子に相当の思い入れがあった事も、来日当日に利用したタクシーで紛失した詩集により判明。詩集は、まるでこのタクシーに置き忘れる為だけに長年大切に保管されていたかの様。 ジョニーは、アメリカから日本へ到着してから間もなく殺されている。国際的な陰謀なのだろうか? ・・・・・・ジョニーは単に生みの母親に会いに来ただけ。殺したのはその母親である可能性が高い。国際的な陰謀でも何でもない。 ジョニー殺害の犯人は、家庭問題評論家として名を馳せている八杉恭子の可能性が高い。しかし、決定的な証拠は無く、彼女の夫は代議士。迂闊に手を出せない・・・・・・。 ・・・・・・ジョニーの持ち物とされる詩集に収録された詩を刑事が朗読したら恭子は狼狽し、全て自白。 日米を跨る、国家が絡んだ大事件であるかの様な描き方で始まるのに、蓋を開けてみると近親者による殺人事件。 大風呂敷を広げながら、著者が自ら小さく小さく畳んだ感じ。 無駄なストーリー展開も多い。 本作では、ジョニーの殺人事件だけでなく、失踪した不倫女性を探す夫、そして堕落した生活を送る男性の行動を描く場面に相当のページ数が割かれている。 この二つのサブプロットは、堕落男性が不倫女性を車で轢き殺してしまい、死体を山中に埋めた、という展開により一つのサブプロットへと集約される。 集約されたサブプロットは、メインプロットにどう結び付くのかと思っていたら、堕落男性はメインプロットの加害者恭子の息子でした、というだけ。 堕落男性が恭子の息子である事は、早い段階で明らかにされる。堕落した生活を送っているのは、母親の恭子が息子を踏み台にして「家庭問題評論家」を気取っているからだ、という事で。 恭子が逮捕される頃には、息子の方も轢き逃げ・死体遺棄で逮捕される、という展開になっている。 このサブプロットは、メインプロットそのものには特に影響を与えておらず、無くても本作は成り立つ。 勝手に展開しているだけで、「推理」「謎」の要素は無く、結末も読めてしまうこのサブプロットに、何故ページを長々と割いたのかが分からない。 登場人物も、魅力に乏しいというか、共感に値しないのが多い。 主人公の棟居は、幼少期のトラウマを今も抱えている、という点は理解出来るものの、刑事になった理由、捜査に没頭する理由が捻じ曲がっていて、共感出来ない。刑事の肩書きを持つサイコパスに過ぎない。 何故こんな捻くれた人物にしてしまったのか。 事件は棟居の活躍によって解決に至った、といった描き方になっているが、実は殆どが著者のご都合主義の賜物。 優秀な刑事とは言い難い。 相当なページ数が割かれている恭子の息子は、ただの屑。 こちらも共感出来ないので、興味が沸かず、女と共にニューヨークへ逃亡したものの、日本からやって来た素人探偵に捕まった、という展開を読まされても何の感情も沸き起こらない。 人間を次々登場させて、深く掘り下げて描けば「人間を描く」事になり、小説に深みが出る、という考えなのかも知れない。が、共感に値しない、その上退屈な登場人物の言動をいくら詳細に描いたところで、小説は面白くならない。 犯人の八杉恭子は、現在の名声を守る為、若い頃生んだ実の息子であるジョニーを殺害する事を決める。いざ実行に移す時は躊躇いが生じ、致命傷を負わせるには至らなかった。 刺されたジョニーは、漸く会えた実の母親に「僕は邪魔なんだね」と言い残し、傷を致命的にし、彼女にその場から去るよう促し、現場を離れ、別の場所で絶命。 実の子を死に追いやったのだから、恭子は懲りて、無謀な犯行を重ねないだろうと思いきや、昔ジョニーとその父親と共に訪れた霧積の宿で働いていた老婆を殺害。 実の子と、自分にとって不利な証言をする恐れがある老婆を死に至らせた冷酷な女、と言える。 警察は逮捕に持ち込むまで相当苦労するだろう、警察と恭子はどんな攻防戦を繰り広げるのか、という読者の期待に反し、恭子は刑事が朗読した詩を聞いて狼狽し、全てを自白してしまう。 この結末もまたご都合主義的。 最近では下手な刑事物でもやらないであろう展開。 これだったら、老婆はとうの昔に死んでいて、その方面での捜査は無駄骨に終わり、恭子は実の息子の死が大事件に発展してしまった事を知って、一人で苦悩する、という風にしていたら、整合性が取れただろうに。 本作で、著者は二つのどんでん返しを用意している。 一つは、八杉恭子が、棟居の父親が死ぬ原因となった事件に関わっていた事。 もう一つは、捜査に協力したニューヨークのシュフタン刑事が、棟居の父親を死に至らせた張本人だった事。 一つの殺人事件の捜査で、ここまで偶然が重なり合うのは有り得ない。 どちらか一つだけに留めていたら、インパクトが強烈になっていただろうに、両方とも盛り込んでいる為、ストーリー展開そのものが強引に映り、リアリティを失わせてしまっている。 棟居が刑事となるきっかけとなった事件の顛末を、本作で丸く治めたかった、という事なのかも知れない。 ただ、それだったら、幼少期の棟居を捨てた実の母親は、恭子に殺された老婆だった、という風に更に強引に持って行けば良かったのに、と思ってしまう。 本作では、アメリカと日本の社会情勢を描いている。 ・・・・・・アメリカは退廃した国家。人種のるつぼと化し、拝金主義が蔓延し、貧富の格差が大きく、富豪が暮らす地区から僅か数百メートル離れた所にスラム街があり、窃盗程度の犯行は最早警察も犯罪と見なしていない・・・・・・。 ・・・・・・日本は優秀な国家。単一民族の為互いに支え合って、敗戦から蘇った。経済を復興に導いた国民の勤勉さは、アメリカも一目を置く・・・・・・。 現在読むと、笑い話になってしまう。 アメリカの拝金主義は相変わらずだが、日本もアメリカ同様金満主義に走った結果、30年間に及ぶ、未だに終わりの見えない低迷期に入ってしまった事を、作者は予想していただろうか。 社会派小説を名乗りながら、実際の社会の読みが浅いように感じる。 本作は、何度か映像化されている。 現在の低予算刑事物原作本のルーツと呼べる作品。 功罪は、あらゆる意味で大きい。粗筋はこちら人間の証明【電子書籍】[ 森村 誠一 ]価格:778円 (2016/10/21時点)
2016.05.17
コメント(0)
-

終幕<フィナーレ>のない殺人/内田康夫著
著者を代表する浅見光彦シリーズの一つ。 浅見光彦シリーズというと、素人探偵の浅見光彦が旅の過程で事件に巻き込まれ、解決の為に奔走するという、いわゆる旅情ミステリが当たり前だが、本作は、その殻を破る目的で古典的なミステリに仕上げられている。粗筋: ルポライターで素人探偵の浅見光彦は、大物俳優加堂孝次郎の別荘で催されるパーティに招待される。 不審な死亡事故が二年続いて起こっていたので、加堂が浅見に監視を依頼したのだった。 僻地にある別荘には、12人の有名芸能人が招待されていた。芸能人とあって、いずれもひとくせもふたくせもある輩ばかり。互いの腹を探り合う。 しかも、別荘で執事とメイドを務めていたのは、加堂によって芸能界を追放された元俳優夫婦だった。 浅見は、この状況では事件が起こらない方がおかしい、と感じるようになる。 招待客らは主催者の加堂が現れるのを待つが、なかなか姿を現さない。 主催者の加堂の姿が無いまま、晩餐を始める羽目に。 その直後、男優永井が何者かに毒殺される。 警察に通報しようと考えるが、電話はいつの間にか外部に通じなくなっていた。 乗って来た車で助けを呼ぼうとするが、招待客全員の車が跡形も無く消えていた。しかも、外に出ようとすると、何者かが空気銃で狙い撃ちしてきた。 どうやら、誰かが招待客全員を別荘に監禁したいらしい。 打つ手が無いので、招待客は別荘に留まる。芸能人なので、一日でも行方が分からないと、所属事務所が不審に思うので、いずれ助けが来てくれるだろう、と。 招待客は、それぞれに割り当てられた部屋に入る。 すると、招待客が次々毒殺されていく。 残った招待客は、加堂の仕業だと判断し、主催者の部屋に突入。それと同時に銃声が。 加堂の射殺死体が発見される。 因縁のある芸能人らを道連れにする為、別荘に招待して次々殺害した後、自ら命を絶った、と判断された。 警察に通報する事が可能になっていたので、通報する。 警察がやって来て、芸能人が何人も死んでいる事実に驚く。 浅見は、執事とその妻が死んだ事を知って、真相が分かったと宣言。今回の事件は加堂が仕組んだのではなく、執事とその妻が仕組んだ、と。 加堂は例年通り様々な芸能人を招待してパーティを開催するつもりだった。が、自ら芸能界から葬り去った元俳優夫婦を執事とメイドとして雇う、という悪戯心が運の尽きだった。 元俳優夫婦は、これを機に積年の恨みを晴らし、命を絶つ、という計画を立てたのである。 元俳優夫婦は、加堂から手渡された招待客のリストを無視し、恨みを持つ芸能関係者を加堂の名の下で招待。招待客は加堂から送られたものだと疑わず、加堂も元俳優夫婦に全て任せ切りだったので、本来の招待客が呼ばれていない事に誰も気付かなかった。加堂が唯一自身の手で招待状を出したのは浅見だけで、彼も本来の招待客の情報は与えられていなかったので、居合わせたのが本来の招待客だと判断するしかなかった。 俳優夫婦は加堂を自室に監禁した上で招待客を受け入れ、次々殺害。加堂も殺害した後、自ら命を絶ったのである。解説: 本作は、旅情ミステリしか書けないと一般的に思われている著者が、古典的なミステリも書ける事を世間に知らしめる為に書き下ろしたという。 著者本人は良いものに仕上がったと自画自賛しているが……。 ミステリアニメの脚本を、文系の大学アルバイトがやっつけ仕事でノベライズした代物を読まされた気分。 古典的な「閉ざされた状況下で発生した事件」のミステリとして成立しているとは言い難い。 登場人物も、きちんと書き分けが出来ていないのでどれも印象に残らず、区別するのに苦労する。 結末も、「枚数に達したからここで終わらせないと」と判断したかの様にとって付けられているだけで、納得のいくストーリー展開になっていない。 主人公の浅見も、作中では「名探偵」として名が通っているという設定になっている割には、やけに無能。 実兄が警察庁の幹部で、それを盾に事件捜査にやって来る警察関係者を適当にあしらうだけ。 兄の七光りが無かったら、ただの一般人でしかない。 無能であっても、キャラ的に魅力があればまだマシなのだが、それも無い。無能で退屈という、読む側からすれば苦痛でしかないキャラ。 執事とメイドの元俳優夫婦が一枚噛んでいて、加堂が全く事件に携わっていないのは、途中で読めてしまう。 ラストで、こちらの読みを、浅見がまるで読者が誰一人予想もしていなかった大どんでん返しであるかの様に語る場面に達した時は、呆れるしかなかった。 僻地でも携帯電話が全く通じない場所は国内で少なくなっている現在、古臭さも感じる。 芸能界に関する雑学でも盛り込まれていれば、その手の読み物として成立するが、そうした要素も感じられない。 今となってはミステリとしても、キャラ小説としても、描かれている時代を楽しむ小説としても、雑学を得る書物としても読めないのは、とにかく残念。 著者が本作以降旅情ミステリ作家としての殻を破っておらず、低予算サスペンスドラマの原作に徹しているのは、正解だったと言える。終幕のない殺人 [ 内田康夫 ]価格:616円(税込、送料無料)
2016.04.24
コメント(0)
-

犯罪待避線/島田一男著:粗筋
シベリア抑留から日本に帰国した都野医師が、数々の犯罪に巻き込まれ、それらを解決していく様子を描いた連作短編集。 初版行は1959年。 そんな事もあり、まだ経済成長期に入っていなかった日本の、のんびりとした様子と殺伐とした様子の双方が描かれている。 8篇から成る。粗筋:第一話 瓶詰めの拷問 シベリア抑留から日本に帰国した医師の都野は、東京のある病院で医師として復帰。 院長から、夫人の堕胎手術を行うよう、要請される。都野は、命じられた通り手術を実施。無事完了した。 その直後に、院長夫人がやって来て、都野を殺人者呼ばわりする。何故なら、堕胎は夫人が望んでいた訳ではなかったからだ。 院長は子供を作れない身体なので、胎児の父親は院長でないのは明白だった。院長は、胎児を「望まれていない子」として処分させたのだった。 胎児は、院長により、アルコール入りの瓶に詰められた。夫人の出身校である医大に寄贈する、と院長は言い出す。夫人と離婚すれば院長の座を失う立場の弱い婿養子として、せめての抵抗のつもりらしい。 都野は、いくら何でも酷過ぎると思ったが、これには院長の別の思惑があった。寄贈された後に胎児を取り返すのは困難だが、その前だったら盗み出すのは可能、と見せかける事で、胎児の父親を炙り出せる。院長は、その思いを都野に長々と話す。 しかし、相手はその策略に乗らず、胎児は盗まれなかった。が、直後に院長夫人が自殺しているのが発覚。側に、若い医師がいた。その医師こそ夫人の浮気相手だった。 夫人は堕胎によるノイローゼで自殺、として片付けられるが、都野はふとした事から真相に気付く。 院長は最初から夫人を殺害する予定だった。胎児の父親に関しては事前に知っていたというか、興味が無く、アリバイ工作の為に利用しただけだった。都野に院長が「思い」を長々と話していたのは、アリバイ作りの為だったのだ。 都野は、それらの事実を院長の愛人で、殺人に加担した看護婦に突き付けると、病院を去る。第二話 首を縮める男 都野は、東京の下町で診療所を開く。 小野小枝子いう患者が頻繁にやって来るように。自分は近々死ぬかも知れない、と言い出す。都野は、そんな事は有り得ないと一蹴し、彼女を送り出した。 都野が、知り合いの警官がいる派出所にいると、男女が現れる。小枝子を訪ねに来たという。警官は、住所を教えてやった。が、暫くすると、男が一人で戻って来て、再び小枝子の住所を訊く。川島というその男は記憶が飛ぶ病を患っており、ふと気付いたら連れの女の道子とはぐれてしまったという。 都野は、川島と共に、小枝子の住まいを訪ねる。 すると、そこには道子の死体があった。死体は首が切り落とされていて、生首が胴体の側に転がっている状態だった。 通報で駆け付けた警察は、小枝子の行方を捜す。 すると、近くの線路で列車に何者かが飛び込んだ、との情報が。 急行すると、また別の死体が。小枝子だった。こちらも首を切り落とされていて、側に生首があった。 警察は、小枝子が訪れてきた道子を殺害し、自ら命を絶った、と考える。 都野は、身元確認の為、検死を要請される。すると、死体には、彼が施した注射の跡が見当たらなかった。首こそ小枝子だが、胴体は小枝子のものでなかった。 その時点で、都野はカラクリに気付く。川島は道子と共に小枝子を訪れ、小枝子を殺害。首を切り落とした後、今度は道子を殺害。小枝子の首と道子の胴体を線路の側に置いた後、「道子とはぐれた」と言い訳して派出所に戻り、都野と共に小枝子の住まいに戻り、死体を発見した様に装ったのである。第三話 或る暴走記録 都野が、最近引っ越してきた吉岡勝美という女性の訪問診療に向かっていると、知り合いの警官と遭遇。 警官は、勝美の隣人であるクリーニング屋に用事があった。勝美とクリーニング屋の主人が、土地を巡っていがみ合っていたからだ。 勝美は、クリーニング屋の隣の空き地を購入した。もう少し広い土地が欲しかったので、クリーニング屋に土地を売ってくれと持ちかけるが、クリーニング屋は拒否。勝美は、市場の倍の価格で買い取ると申し出たが、それでもクリーニング屋は応じなかった。 勝美は、仕方なくそのまま家屋を建て、引っ越す。が、土地を売ってくれなかった腹いせに、自宅を囲む塀を通常より高くする。それにより、クリーニング屋は日当たりが悪くなり、洗濯物が干せなくなってしまった。クリーニング屋は営業妨害だと憤るが、勝美は自分の土地に何を建てようとこっちの勝手だ、と譲らない。 すると、クリーニング屋は物干し用の柱を立てる。なるべくボロボロの衣服を干し、勝美の家から丸見えになるようにした。 勝美は、庭で焚き火をする、という手に出る。クリーニング屋の洗濯物は、風で舞い上がった焚き火の灰で汚れるようになってしまった。 クリーニング屋は、更に高い物干し用の柱を立てる。 すると、勝美は犬を飼った。犬は庭に穴を掘り、クリーニング屋の庭に侵入。飼っていた鶏を噛み殺す。 クリーニング屋は、穴にトラバサミを仕掛けて対抗した。 ・・・・・・以上がこれまでのいがみ合いの経緯だという。 都野は呆れるしかなかった。 警官がクリーニング屋を訪れるのは、自宅の庭とはいえトラバサミを仕掛けたら危険だ、と忠告する為だった。 都野は、勝美を診察。隣人とのトラブルについて、悪びれる様子は全く見せなかった。 診察後、都野は警官と再会。クリーニング屋は、トラバサミを撤去する事に嫌々ながらも同意し、更に庭の穴を板で塞ぐ事にも同意した、と報告する。 その翌日、勝美が死体となって発見される。クリーニング屋の仕業かと思われたが、クリーニング屋には勝美の家に侵入する手段が無い。庭の穴から侵入したのではと思われたが、板で塞いであり、行き来出来ない。 警察は、勝美宅の内部犯行を疑う。勝美の使用人の男が、行方不明となっていたからだ。 都野も、当初は勝美宅の内部犯行だと思っていたが、クリーニング屋の庭の穴を塞ぐ板がネジで固定してあったと聞いて、真相に導かれる。 事件当日、勝美の使用人は、彼女の気を引こうと、穴を通じてクリーニング屋に忍び込もうと企んだ。トラバサミが撤去されている、と聞いていたからだ。しかし、その時点ではトラバサミはまだ撤去されておらず、使用人は死亡してしまう。クリーニング屋は慌てて死体を隠し、穴を約束通り板で塞ぐ。ただ、使用人だけが行方不明になったら自分が疑われると判断したクリーニング屋は、勝美を殺害する事に。使用人の行方が分からないままだったら、使用人が勝美を殺して逃走した、と警察は判断するだろうと読んだのだ。 クリーニング屋は、一旦塞いだ穴の板を外して隣の家に侵入し、勝美を殺害。穴を通じて自宅に戻る。再び穴を板で塞ぐ必要があったが、最初の時のように釘を使うと金槌の音が辺りに響き、2度塞いだのがばれるので、ネジを使って塞いだのである。 使用人の遺体は、物干しの柱に掛かる大き目の洗濯物の中に隠してあった。第四話 蜉蝣機関車 都野の下に、ヘロイン中毒の女性旗江が患者としてやって来る。彼女に対し、都野はヘロインを止めるよう忠告するが、旗江は今更止められないという。 それから間もなく、旗江の夫詮造が駆け込んで来て、妻が死んでいると訴える。 都野は、旗江の死を確認。 詮造によると、旗江はヘロインを絶つ事にしたが、病院で治療を受けたくなかったので、自宅でヘロインを身体から抜く事にしたという。家政婦の川瀬キミが、それを手助けする事になったが、ふと目を離していた隙に死亡していたという。 都野は、禁断症状による嘔吐で、嘔吐物が喉に詰まり、旗江は死亡した、と診断する。 翌日、詮造は、妻の死亡診断書を受け取りに、都野の下へやって来る。都野は死亡診断書を渡し、詮造を帰した。 その直後に、隣の地区で開業している知り合いの医師と出会う。彼は、旗江が死亡したのとほぼ同じ時刻に死亡した女性の死亡診断書を書いたという。その女性の名は、川瀬キミだという。 都野は、詮造が一つの死体で2つの死亡診断書を作らせた、と判断する。旗江の家の周辺は地区の境界線が入り組んでおり、2地区の役所を利用出来た。それを悪用し、2つの役所に内容の異なる死亡診断書を提出する事にしたのだ。別の地区なので、管轄が異なり、気付かれないだろうと。2つの死亡診断書で、保険金を2重取りするつもりだろうと思い、詮造の自宅に急行。棺を開けさせる。中にあったのは、旗江の遺体ではなく、川瀬キミの扼殺死体だった。 都野の推理は外れたが、観念した詮造は全て自白する。 詮造は、都野の当初の推理通り、妻を殺し、同時にキミも死んだ事にして、保険金を2重に受け取るつもりだった。キミにそうするよう、迫られていたからだ。 が、いざ実行に移ると、詮造は躊躇う。それを見かねたキミは、代わりに旗江を殺害。これに怒った詮造は、キミを殺害してしまう。 これにより、一つの死体で2つの死亡診断書を作らせたかのように見せかけて、実は死体は2つある、という状況になってしまった。第五話 顔のある車輪 都野は、知的障害を持つ女性のノブ子と遭遇。 ノブ子は秋田から何者かによって東京に連れて来られたが、捨てられ、警察に保護された。 下の名前こそ分かっているものの、それ以外の情報は得られず、故郷に帰す手立てが無い。捜索願も出されていなかった。 そんな所、警察を定年退職する須貝が、ノブ子を引き取ると申し出る。知的障害者でも、簡単な家事手伝いなら出来る筈だと。それから4ヵ月後、ノブ子は妊娠させられていた事が発覚。既に妊娠8ヶ月で、堕胎するには遅過ぎた。須貝は、ノブ子と、生まれてくる子供の面倒を見る覚悟を決めた。 それから数日後、須貝の住まいの直ぐ近くにある教会から、保呂神父が都野を訪ねる。保呂神父は、須貝とノブ子が如何わしい関係にある、と訴える。ノブ子の子の父親は、多分須貝だろう、と。 都野は、須貝がノブ子の子の父親である可能性が無い、と反論。警察に保護された時点で既に妊娠していたからだ。保呂神父は言う。そもそもノブ子を秋田から連れ去った人物こそ須貝ではないか、と。 都野は、何故保呂神父が須貝を毛嫌いするのか分からない。 その段階で、連絡が入る。須貝が死んだ、と。毒殺だった。 ノブ子の姿が見えなかったので、探し回ると、側の線路で礫死体となって発見された。 ノブ子が須貝を殺し、自殺した、と保呂神父は訴えるが、都野は保呂神父の言動の違和感を抱く。 保呂神父は、礫死体の胴体を見ただけで、ノブ子だと言い切った。が、ノブ子が着用していた妊婦服は前日に購入したばかりで、その妊婦服を見た事があるのは都野と、須貝と、ノブ子だけだった。保呂神父が妊婦服だけでノブ子の遺体だと言い切れるのはおかしい、と都野は指摘。 保呂神父は、その証拠を突き付けられて自白する。彼は、学生の頃、刑事だった須貝にスリの容疑で補導されていた。それにより、保呂は学業を断念し、教会に入り、神父となった。数十年振りに須貝と再開した彼は、積年の恨みで須貝を殺害。ノブ子はその巻き添えを食らったのだった。 第六話 座席番号13 都野の診察所を、好子が訪ねる。 堕胎手術をしてほしい、と訴えた。望まれていない子だから、と。子の父親は、夫ではなかったのだ。 都野は手術は出来ないと伝え、彼女を帰す。 それから数日後、都野の下に電話が。好子だった。子の実の父親である学生を殺したので、これから自殺するという。都野は思い留まるよう説得するが、その直後に警察から電話があり、好子が自殺したと伝えた。 警察は当初事件は好子の告白通りに起こったとして処理するつもりだったが、都野はある疑問を抱き、真相を導き出す。 学生を殺害したのは好子ではなく、その弟だった。学生が姉を妊娠させたにも拘わらず責任を取ろうとしない事に腹を立て、殺害。好子は、弟をかばう為、自分が殺した事にして、自殺したのだった。第七話 機関車は偽らず 都野の診察所に、女子大生の陽子が訪ねて来る。妊娠中の子を堕胎してほしい、と。 しかし、妊娠から既に4ヶ月経っていたので、堕胎は危険だ、と都野は諭し、そのまま帰した。 それから数日後、陽子の遺体が発見される。列車に飛び込んで自殺したと思われた。 警察は、陽子と一緒に暮らしていた3人の学生から事情を聞く。 都野は、3人の発言の中から矛盾点を見付け、犯人を指摘する。第八話 ノイローゼ殺人事件 都野の診察所に、みさおという女性が訪ねて来る。 知人の医師である麻実子によりヒステリーと診断されたが、それは有り得ない、とみさおは言い張る。何故ならヒステリーは女性の病で、自分が発症するのは有り得ない、と。 都野が何故だと問うと、みさおは答える。自分は男だと。 単なるオカマかと都野は思ったが、事情はそう簡単なものではなかった。何故なら、みさおは戸籍にも女性として記録されていたのだ。 話によると、みさおの父親は彼が生まれる前に大陸で戦死していた。みさおを身ごもっていた母親は、そのまま彼を出産。女児を期待していたが、生まれたのは男児だった。男児だと育てても徴兵されて父親と同様、死ぬだけだと悲しんだ母親は、みさおを女子として育てる事に。 母親は地方を巡る劇団の一員だった。そんな母親と共に育ったみさおは学校に行けず、他人と殆ど接触しなかった事もあり、自分を完全に女だと思っていた。十代半ばに、漸く自分が女ではなく、男だという事実に気付くが、今更男として生きれないと思い、女性として通した。結婚もしたという。無論、男性と。その男性は、彼を女性だと思って結婚していた。 都野は、その身の上話を聞いて驚く。 みさおが都野を訪ねたのは、身の上の相談ではなく、最近身の回りで感じている事だった。誰もいない筈の部屋で人が話す声が聞こえるという。 都野は、単なるノイローゼだろう、と診断。更に、女でない以上、夫とは離婚すべきだと進言する。 それから数日後、警察から連絡が入る。みさおらしい人物の死体が発見されたので、身元を確認してほしいと。 都野は、下着姿の死体がみさおである事を確認。自殺か事故死だと推測する。 しかし、みさおが死の直前にクロロホルムを嗅がされていたらしい事を知り、真相に気付く。 みさおの夫と、愛人の麻実子医師は、財産目当てにみさおを殺す事に。二人は、みさおが男である事は、とっくに知っていた。みさおがノイローゼになるよう、麻実子は彼をヒステリーだと診断。夫はみさおの部屋にスピーカを仕掛け、誰もいない部屋から声が聞こえるようにした。 みさおがノイローゼの兆候を見せた時点で、二人はみさおをクロロホルムで寝かせ、3階に移動させ、下着姿にして放置。 クロロホルムが切れて目を覚ましたみさおは、下着姿の自分を見て、男である事が皆にばれたと思い、窓から外へ逃げ出そうとするが、まだ意識が朦朧としていたので、自分が3階にいる事に気付かず、転落死した。解説はこちら【中古】 犯罪待避線 / 島田 一男 / 徳間書店 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】価格:210円(税込、送料別)
2016.04.08
コメント(0)
-

犯罪待避線/島田一男著:解説
シベリア抑留から日本に帰国した都野医師が、数々の犯罪に巻き込まれ、それらを解決していく様子を描いた連作短編集。 初版行は1959年。 そんな事もあり、まだ経済成長期に入っていなかった日本の、のんびりとした様子と殺伐とした様子の双方が描かれている。 8篇から成る。解説: 有名な架空の探偵というと、シャーロック・ホームズの名が必ず挙がる。 何故19世紀末に誕生した探偵が、未だに読まれ続けているのか。 ホームズ以降、探偵小説や推理小説が全く発表されていなかった訳ではない。 寧ろ、推理小説としてホームズ物を上回るものはいくらでもある。 にも拘わらず後発のは時代と共に廃れ、ホームズ物は推理小説の代名詞になり続けている。 最大の理由は、後発のは技術革新や社会情勢の変化により、単に「古臭い」ものになってしまうからだろう。 20世紀に出版されたものだと、電話や自動車等、現在でも通用する通信手段や自動車が登場する。しかし、名称は同じでも、現在とは用途や技術が異なる。「当時、固定電話はあったが、携帯電話は無い」「当時の自動車にカーナビは無い」等、注釈が一々必要になる。 一方、ホームズ物は19世紀末のロンドンが舞台。 通信手段は電報で、乗り物といえば馬車。 異次元の世界に等しい。 推理小説として純粋に読まれているというより、現実から遠く離れた世界を舞台で活躍するヒーロー物として読まれている側面が大きい。 本作は20世紀に出版されたので、純粋な推理小説としては、本来成立し難い筈だが、一応読めるものになっている。 主人公が、大戦後のシベリア抑留から日本に戻って来た、という設定になっているから。 たったこれだけで、本作は現在とは異なる異次元の世界での物語になる。 第一話の瓶詰めの拷問では、院長の妻が妊娠。院長は、子供を作れない身体だった。となると、妻の子の父親は誰だ? ・・・・・・で物語は始まる。結局、院長が邪魔な存在だった妻を始末しただけ、という事に。 第二話の首を縮める男は、2つの遺体の首を入れ替える、というのがメインのトリック。DNA鑑定が当たり前の現在では、一発で偽装がばれそう。当時でも、血液鑑定はそれなりに導入されていた筈なので、偽装をやり通せたかどうかは疑わしい。 第三話の或る暴走記録は、撤去すると約束した筈のトラバサミを撤去していなかったお陰で、起こるべきでなかった事件に発展してしまった、というのがミソ。ただ、一人が死んだとはいえ事故だった。素直に通報すれば、過失は事故死した方にあった、となった可能性が高い(隣の家に不法侵入しようとしていた)。にも拘らず、事故を隠す為に殺人という罪に手を染めるか、という疑問が残る。 第四話の蜉蝣機関車は、管轄が異なる為に連絡が行き通らず、1体の遺体に関する書類が2箇所で受理されてしまう、となっている。現在は電子化されているので、こういう事は有り得ないと思ってしまうが、電子化も完璧でないので、予想外のすり抜けられそう。 第五話の顔のある車輪は、神父が罪を犯す理由が良く分からない。また、キリスト教では堕胎は殺人と見なされている筈だが、本編では神父が胎児について「望まれていない」として堕胎させる事を主人公の医師に提案している。当時のキリスト教は堕胎についてそこまで意識が高くなかったのか、この神父の異常さを描く為にあえてそうさせたのか、著者がキリスト教について無知だったのかどうかは不明。 第六話の座席番号13も、また堕胎が絡む物語。当時は堕胎がここまで一般的だったのかね、と思ってしまう。 第七話の機関車は偽らずも、やはり堕胎が絡む。犯人が被害者を殺す理由が、やけに安易。他に問題を解決する方法はあっただろうに、と思ってしまう。 第八話のノイローゼ殺人事件は、男性として生まれながらも事情により女性として生きている人物が登場。ただ、いくら女性として育てられてきたとはいえ、ある程度年齢のいった男性が、医師の目や、「夫」の目を欺ける程女性の格好を出来るのか。性転換手術を受けたり、ホルモン剤を投与されていたりした訳ではない様だし。 現在の観点で読んでしまうと、推理小説として成立していないのが大半を占める。 堕胎手術が当たり前の様に実施されているのも、気になる。 ただ、終戦から間もなく、高度成長期はまだまだ先、という時代の東京の、人々の生活振りを推理小説っぽくして描いた、と考えれば許せるから不思議。粗筋はこちら【中古】 犯罪待避線 / 島田 一男 / 徳間書店 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】価格:210円(税込、送料別)
2016.04.08
コメント(0)
-

QED 出雲神伝説/高田崇史著
高田崇史の代表的シリーズ作「QED」の第17弾。 漢方薬剤師桑原崇と棚旗奈々のコンビが、古代の神話が絡んだ奇妙な事件に巻き込まれ、真相を暴いていく。粗筋: 奈良のマンションで、OLの八刀良子が殺害される。刀で首をほぼ切り落とされるという、惨い殺され方だった。 警察が駆け付け、現場を検証。壁に奇妙な模様が描かれていた。それを見た警察は、ただの殺人事件でない事を察する。何故なら、それとそっくりの模様が、2週間前に発生した轢き逃げ事件の現場にも残されていたからだ。模様が残されていた事実は公にされておらず、限られた者しか知らない。したがって、連続殺人の様相を見せてきたのである。その上、今回の事件現場は密室状態だった。 死体の発見者の一人である五十嵐彩子に、模様について訊く。何も知らない、と彼女は答えたが、何か隠しているのは明らかだった。 殺人現場は、被害者の自宅ではなかった。フィアンセとされる野川達夫が所有していたマンションだった。問題の模様を見せると、野川は知っていると認める。出雲神流という、神話の時代に存在していたとされる忍び集団の紋章だという。警察は、何故そんな模様が2つの現場に残されていたのか、さっぱり分からなかった。 2週間前に轢き逃げされて死亡した黒坂洋は歴史研究家だった。殺人現場のマンションの所有者である野川達夫も歴史研究家。紋章以外にもこの二つの事件は繋がりはある、と警察は見て、捜査を進める。 同じ頃、雑誌記者の小松崎も、この事件について調べていた。出雲神流という謎の集団が関わっている事を知り、知人で、古代の歴史に詳しい漢方薬剤師桑原崇を加わらせ、取材を進める。 第二の事件の被害者八刀良子は、発見者の五十嵐彩子と、別の友人の雲居麻也と共に、出雲神流に興味を持ち、それについて詳しいとされる占い師稲瀬葵の元を頻繁に訪れていた。警察は稲瀬葵に事情聴取するが、彼女はこれといった証言はしなかった。 警察は、雲居麻也からも事情聴取しようとする。そもそも五十嵐彩子と八刀良子が出雲神流に興味を持ったのも、歴史研究家を父に持つ麻也が、友人である二人を誘ったからだった。が、彼女は失踪していた。第二の事件前後から行方が分からなくなっていたのが判明したので、行方を捜す。 それから数日後、麻也の死体が発見される。側には、例の模様が描かれていた。 更に、野川達夫と稲瀬葵が、それぞれ自殺する。模様を残して。 警察は、一連の事件が単なる殺人事件なのか、組織ぐるみの犯行なのか、判断が付かなくなっていた。 そんなところ、事件現場をうろついていた桑原崇と棚旗奈々と遭遇。 桑原崇は、事件の真相を暴く。 黒坂洋は、轢き逃げに見せかけられて殺されるが、即死でなかった為、犯人である野川達夫の名を残せた。現場に戻った野川は、自分の名前が、出雲神流の模様となるよう書き足し、現場を後に。 八刀良子は、野川達夫が轢き逃げの犯人であるという真相を掴み、脅迫する。その内、野川は良子の知人である麻也と知り合う。麻也は野川に好意を抱いていたが、野川は彼女に興味が無かったので、男性とも女性とも付き合える良子に押し付ける事に。 第二の事件が起こった日、麻也は野川がいると思って現場となるマンションを訪れたが、いたのは良子だった。良子は自分の思いを麻也に伝えるが、麻也は受け入れず、口論になってしまった。その際、良子は、麻也の出生の事実を告げてしまう。麻也は雲居家の実の子ではなく、稲瀬葵の娘だった、と。これにより口論は激化し、麻也は現場にあった刀で良子を殺害してしまう。 我に返った麻也は、彩子に連絡した後、窓から飛び降り自殺する。マンションに急行した彩子は、自殺した麻也の死体を発見。それを隠すと、管理人と共に野川のマンションに入り、良子の惨殺死体を発見。管理人が警察に連絡を入れている間に、密室を完成させ、壁に書かれてあった麻也本人の名前が入った血文字に書き込みし、出雲神流の模様にした。 若い時に生んだ実の娘である麻也が死んだのは、野川のせいだと知った稲瀬葵は、彼を毒殺し、自ら命を絶った。 これで一連の事件は解決したように見えたが、桑原は、更に黒幕がいる事を指摘する。雲居麻也の育ての父親雲居泰治がその黒幕だと。彼は、「出雲」は元々現在の奈良県内にある地名で、そこの住民が大和朝廷との戦いに敗れ、現在の島根県に移動し、新たに「出雲」を築き直した、という説を唱えていた。その説が話題になるよう、「出雲神流」を利用して、一連の事件と結び付けたのだった。解説: 大和朝廷の誕生の謎に絡む謎の忍び集団「出雲神流」が現在も存在していて、事件を起こした……。 ……という膨大なスケールのストーリーになると思いきや、結局事件は過去の「出雲神流」とは全く無関係。 密室事件そのものは、発見者の一人が、別の発見者が警察を通報している隙を狙って現場に踏み込み、密室を完成させた、という単純なもの。 ストーリーの内容はシンプルなのに、ストーリーとは間接的にしか関係していない(事件の真相を暴くのに特に必要とされない)神話の情報を満載している為、ノベルス版で350pという長さになってしまっている。 神話について物凄く興味がある、という読者からすれば楽しい情報なのかも知れない。が、ミステリー小説として単純に読みたい読者からすれば、興味の無い情報を散々読まされた後で「事件解決には特に関係していません」では、脱力感しか味わえない。 本書で描かれている警察は、現場に残された模様(実は雲居泰治の創作で、実際の出雲神流とは無関係)を過大解釈し、振り回されただけの感じ。 模様は、一連の事件に関連性がある、という点だけを認識する為の証拠として取り扱うだけに、何故留められなかったのか。模様の件を排除し、密室現場を冷静に検証すれば「これは発見者による工作だ」という結論に至っていただろうに。 雲居泰治の思惑も理解出来ない。 出雲は奈良県が起源だ、という持論を世間に広める為、事件を利用したというが、仮にその説が大々的に取り上げられ、検証されるようになったら、出雲神流の模様は自分の創作でした、といずれ認めざるを得なくなる。そうなった場合「偽考古学者」の汚名を着せられ、持論の「出雲奈良県起源説」も完全に否定される事になってしまう。 主人公(というか著者)は、事件には特に興味が無く、あくまでも出雲神話について調べたかった(述べたかった)だけの様である。現に、事件が解決した後、エピローグとして主人公らが出雲大社等を訪れる場面が延々と描かれる。 何故著者が、小説の形を取ったのか、分からない。そこまで神話について述べたいのなら、ミステリー小説仕立てにせず、論文として書けば良かったのに、と思ってしまう。 シリーズ作とあって、最初の部分はレギュラーキャラとされる人物の日常が延々と描かれる。が、いずれも魅力に乏しいキャラなので、初めて本シリーズを手に取った者からすれば、内輪で勝手に楽しんでいるだけの様に感じる。キャラの日常を描いている余裕があるなら、ストーリーをさっさと進めてほしい。 キャラの近況や、神話のレクチャー等、無駄な部分を省き、純粋なミステリー小説にしていれば、厚みも半分で済んだだろうし、より読み易いものになっていただろうに。 著者の取材力は買うが、その取材力が面白い小説に繋がっているかというとそうでなく、寧ろつまらなくしている。 やり方によっては面白い小説になっていたと思うのに、残念な結果に。QED出雲神伝説 [ 高田崇史 ]価格:1,080円(税込、送料込)
2016.04.01
コメント(0)
-

南アルプス鳳凰三山殺人事件/柊治郎著
元警察庁外事捜査官の経歴を持つという著者による警察小説。粗筋: 新米警察官の島村は横浜市内勤務から、津久井署への転勤を命じられる。「国境警備隊」と揶揄される程辺鄙な地域だった。 転勤から間もなく、医療ミスに端を発した病院立て籠もり事件に遭遇。犯人の檜山は、手榴弾を自ら爆発させて死亡した。 島村は、津久井署の主的な存在である熊井係長と共に、死亡した檜山が訴えた内容を調べる。檜山の幼い娘は津久井湖総合病院で手術を受けたが、夜になって様態が急変。看護師が担当医の菊地原医師を直ちに呼び出したが、菊地原は朝まで姿を現さなかった。檜山の娘は死亡した。檜山の妻は病院の不正を訴えた後に自殺。娘と妻を失った事から、檜山は立て籠もり事件を起こす、という凶行に走ったのだった。 檜山の訴えが全て事実だとすると、津久井湖総合病院の落ち度は重大だが、医療ミスの捜査は一筋縄でいかないのが常であり、しかも当直の看護師だった梨本千恵子が病院を辞めた事もあり、捜査は暗礁に乗り上げる。 それから暫く経った後、若い女性の全裸遺体が発見された。津久井署は、久し振りの殺人事件で大騒ぎする。遺体には身元を確認出来るものは無かったが、島村と熊井の粘り強い捜査の結果、女性暴走族のメンバー佐野恵子である事が判明。女性暴走族はヤクザとの繋がりがあったので、ヤクザ絡みの事件かと思われた。 すると、隣の山梨県でも身元不明の女性の全裸死体が発見された、との情報が入った。偶然にしては出来過ぎているので、2つの殺人事件は繋がっているのでは、と島村と熊井は考える様に。 佐野恵子が行方不明になる前後について、再度聞き込み捜査をする。急に羽振りが良くなった、という証言が得られた。誰かから金を貰っている様だが、誰かからは分からなかった。 山梨の殺人事件にも進展があった。身元が津久井湖総合病院を辞めた筈の梨本千恵子と判明したのだ。 島村と熊井は真相に行き着く。 菊地原医師は、医療ミスを隠滅する為、証言者に成り得る梨本千恵子を山奥で殺害した。が、その場面を女性暴走族に目撃されてしまった。菊地原は、顔こそ見られたが、互いに名前を知っている訳ではないので、問題無いと高をくくっていた。が、佐野恵子は、偶々津久井湖総合病院を何度も訪れていて、菊地原の顔も名前も知っていた。 佐野恵子は病院にやって来て、口止め料として現金を要求。無論、1回では済まず、要求額も増えていった。 堪り兼ねた菊地原は、自分を可愛がってくれている祖母に打ち明ける。すると、その祖母は佐野恵子を誘い出して睡眠薬で眠らせた上で絞殺。死体の処理を別の男に押し付けたのだった。 島村と熊井は、菊地原医師とその祖母の逮捕に動く。 菊地原医師の立件まで持ち込めたものの、祖母の方は自供に応じず、物的証拠も無い為釈放となる。解説: 元警察庁外事捜査官という肩書を持つ著者にしては、国際性が全く見受けられない小説に仕上がっている。 一方で、警察組織や、警察官の日常に関する描写は当然ながら説得力がある。 ただ、あまりにも長々と描かれているので、退屈してきて、最終的にはどうにもよくなってしまう。 事件そのものは大したものではない。 医療ミスを犯したとされる、悪徳と思われる医師が、本当に悪徳だった、というだけ。 どんでん返しも捻りも無く、真相が明らかになっても驚きは無い。 主人公と同様、読者も淡々と事件を追う事を強いられる。 全裸死体だからといって、身元の特定にこんなに手こずるのかね、と不思議に思わないでもない。 島村は若手警察官、熊井は師となる熟練警察官、という、テレビドラマみたいな設定になっている(作中では、「当直時間の関係で、実際には同じ刑事がずっとペアを組んで捜査に当たる事はまず無い」と何度か述べられているにも拘わらず」)。 いずれも物凄く優秀には見えない。 菊地原医師は胡散臭い人物だ、と医療ミスの件で判明していたのだから、ずっと監視していれば良かったのに、そうしなかったから梨本千恵子が殺され、佐野恵子も殺されるという大失態を犯すが、これについては特に言及されていない。 本作は、日本の警察捜査や検察の公判の進め方の問題点を浮き彫りにしている(著者が意識していたのかどうかは不明だが)。 要するに、犯人の自供が無いと何も出来ない、という事。 島村と熊井は、菊地原医師の祖母を佐野恵子殺害の容疑で逮捕し、取り調べするのだが、祖母が頑として認めず、代りに容疑が掛っていない梨本千恵子の殺害を認める。梨本千恵子殺害は菊地原医師の犯行であるのは疑いようが無いので、調書を作っても意味が無い。必要な調書が得られない為に証拠不充分として釈放せざるを得なくなる、というラストになっている。 日本の警察は科学捜査のレベルが世界屈指とされるので、物的証拠はいくらでも得られそうだが、何故か自白や自供を「決定的な証拠」というか、「信頼に値する唯一の証拠」と見なす傾向が未だに強い。時代劇で悪人の自白を「証拠」と見なして裁くのと全く変わらない。 20日間も拘留された上での自白調書なんて、まともな法事国家では「信頼に値しない」として証拠に成り得ず、検察も受け付けない。が、日本では何故か検察が率先して採用したがる。 いい加減、自白が無くても立件出来る捜査体制・公判体制を整えたらどうか。 それでなくても最高裁で死刑判決が下されたケースが、再審で冤罪として覆されるケースが多いのに。 元警察庁捜査官(という事になっている)の著者として、実情から離れ過ぎた警察の捜査は描けないらしい。 警察の無能振りや、不効率さが目立つだけの小説になってしまった。 内情を知り過ぎる著者というのも、困りものである。【中古】 南アルプス鳳凰三山殺人事件 / 柊 治郎 / 学習研究社 [単行本]【メール便送料無…価格:258円(税込、送料別)
2016.02.05
コメント(0)
-

越冬卵―蝶(ゼフィルス)の告発―/平野肇
昆虫巡査こと向坊一美が、昆虫の知識を元に事件を捜査して解決する、というシリーズの第4弾。 元プロドラマーという著者の経歴が反映されている。粗筋: 九重山の山中で、吉木という人物の死体が発見される。山や昆虫に詳しいという理由で、昆虫巡査こと向坊一美が捜査に借り出される。死体は、貴重な蝶の越冬卵を手にしていた。 向坊は、越冬卵は高価で取引されており、密猟の対象となる事がある、と何気無く口走る。 それを聞いた捜査責任者は、吉木は越冬卵を密猟中に滑落し、死んだ、と判断。要するに、事件性は無く、単なる事故死として、捜査を打ち切った。 向坊は、吉木が密猟者扱いされる事に納得がいかなかったが、自身の発言がきっかけであった事もあり、それ以上追求しなかった。 数ヵ月後。 人気ロック歌手の久我卓馬が、公演直後に機材を積んだ11tトラック7台と共に姿を消す。世間は当然ながら大騒ぎし、警察は大捜査を開始。向坊も借り出される。 懸命の捜査にも拘わらず、警察は久我の足取りを全く掴めないでいた。久我自ら姿を消したのか、もしくは何者かに拉致されたのかも不明だった。 そんな頃、向坊は手紙を受け取っていた事を思い出す。吉木が越冬卵の密猟をしていたとは考えられない、何かの間違いだ、事故死も有り得ない、殺人だ、と訴える内容だった。 向坊は手紙の差出人を訪ねる。吉木が発起人となった蝶の愛好家サークルの一員だった。愛好家サークルには、どうやら久我もメンバーらしかった。 向坊は、吉木の身辺を改めて調査。 吉木は、死の直前、広大な土地を相続していた。自然を愛する彼は、自然を守る為に土地を所有し続けるつもりだったが、ある建設業者がその土地を狙っていた。前の所有者は、土地を建設業者に売却する方向で合意していたのだが、急死。相続人の吉木に対し、建設業者は前の所有者の規模通り売るよう迫っていたが、吉木は拒否していたのだ。 蝶の愛好家サークルは、事件の背景には建設業者が絡んでいると睨み、探偵を雇って調査していたが、その探偵は何故かダム建設の為廃村となった地区で、重症を負った状態で発見されていた。 向坊は、建設業者の背景を調べる。建設業者には、彼が幾度も対峙してきたヤクザ羽生田が絡んでいた。事件は、かなり危険なものになってきた、と向坊は悟った。 向坊は、ダム建設で廃村となった地域に向かう。 そこで、久我を発見。彼は、自身の行動が吉木を死に追いやった事を悔やみ、その事実を世間に訴える計画の一環として、雲隠れしたのだった。 警察は、失踪した11トントラック7台が一同に移動している、と読んでいた。が、久我は下積み時代に運送会社で働いていて、その運送会社に頼んで同様のトラックを全国に動員。7台のトラックは、それらに紛れて分散して移動。だから見付からなかっただけだった。 重症を負った探偵は、当初は蝶の愛好家サークルの為に調査を進めていたが、背景に建設業者や、久我の失踪が絡んでいると知ると、建設業者側に寝返り、建設業者の為に久我を追うようになった。久我と接触する直前、久我を匿っていた仲間に呼び出され、重症を負わされたのだった。 向坊と久我に対し、羽生田が手下を放ち、襲い掛かるが、二人は仲間の助けを借りて廃村から脱出。 久我は、建設業者の不正を公にする為、コンサートを開催。ラストで、所属事務所の社長が計画に加わっていた事を観客の前で明かした。 この告発により、建設業者や、羽生田の手下が芋づる的に検挙される。吉木の死も実は殺人であった事が漸く明らかになった。しかし、羽生田本人はトカゲの尻尾切りで難を逃れる。解説: 著者の趣味や経歴が存分に反映された小説。 ただ、「活かされた」とは言い難い。 昆虫巡査こと向坊が登場するとあって、昆虫に関する情報が随所に散りばめられているが、昆虫そのものが事件の鍵を握っていた、というまでにはいかず(第1作では、昆虫がまさに事件の鍵を握っていたらしい)、昆虫情報が盛り込まれていなくても充分成立するストーリーになっている。 本作の最大の謎は、人気ロック歌手がどうやって11トントラック7台と共に失踪したのだ、というものだったが、真相は単純過ぎて(分散し、他のトラックに紛れただけ)、肩透かしを食らった気分。 監視カメラやETCが無かった時代だったからこそ成立するトリックで、現在だったらたちまち発覚してしまう。 現在を舞台にしていると臭わせながら、本作が発表された時代と現在の技術水準のギャップを読者側で考慮しなければならない、という点では、最早本格推理小説として成立していない。 キャラも、魅力に乏しい。 主人公の向坊は、元々警察組織のエリートコースを進んでいたが、ある件をきっかけに失望し、エリートコースから身を引き、地方警察の巡査に留まっている、という設定。 著者は自身が創造した主人公が物凄く優秀で、作中に登場する他の人物も主人公が物凄く優秀であるかの様に接するが、読者にはその優秀さが伝わってこない。 自身の都合でエリートコースから離脱した割には、未練たらたらの言動が目に付き、好感が持てないのである。 エリートコースとは無縁の、田舎生まれの田舎育ちの、田舎の派出所の冴えない容貌のお巡りさんが、田舎にいるからこそ活きる知識を駆使してエリート気取り共を出し抜いて難事件を鮮やかに解決、という設定に出来なかったのか。 ストーリ展開も、よく分からない部分が多い。 ・・・・・・事故死と思われていた死が、実は殺人で、それに伴って人気ロック歌手が失踪。それらの事件の裏には、ゴルフ場開発を手掛ける建設業者が絡んでいて、更にその背景には主人公と幾度も対決してきたヤクザがいた・・・・・・。 ・・・・・・要約すると有り得そうな展開だが、地方警察の一巡査に過ぎない主人公に、007のブロフェルドの様な宿敵(陰謀を実行に移そうとするが、主人公に阻止される。主人公に後一歩のところまで追い詰められるが、トカゲの尻尾切りで辛うじて逃れ、次回作でまた登場)がいる、というのはやり過ぎ。 推理小説(のつもり)なら、真犯人が1冊ごとに捕まって裁きを受ける様にした方がすっきりすると思う。 著者が元ミュージシャンという事もあり、本作にはロック歌手が登場し、音楽活動が重要な鍵を握る展開になっている。 音楽にも興味がある読者なら、「音楽と推理小説の融合!」というのは喜ばしいのかも知れない。が、音楽に特段興味が無い読者からすると、命を狙われている筈のロック歌手が警察に出向いて保護を求めるよりライブを開催する事に執拗にこだわり、警察もそれを後押しするストーリー展開や、上手いのか下手なのか分からない歌詞を文中に挿入する作風は、理解し難い。 どんな読者に狙いを定めているのかも分かり辛い。 本格推理小説にしては、推理の部分が殆ど無く、物足りない。 環境保護を訴える社会派小説にしては、訴えの内容に新鮮味が無い。 音楽を絡めているが、音の出ない本で歌詞を挿入したところで、あまり意味が無い。 ヤクザを絡ませてアクションシーンを盛り込んでいるが、これも場違いな感が否めない。 ロック歌手やヤクザの部分を省いて、「単なる密猟者の事故死と思われていた件は、実はゴルフ場開発を巡る陰謀だった」というストーリーにしていた方が、シンプルでリアリティがあるものになっていたと思われる。 かなり月並みの、著者の経歴が全く活きない小説になってしまうけれども。 月並みの小説になるのは嫌だからこそロック歌手やヤクザの部分を盛り込んだのかも知れないが、それだったらもう少し上手いやり方がなかったのか、と思ってしまう。越冬卵 [ 平野肇 ]価格:864円(税込、送料込)
2016.01.08
コメント(0)
-

紀の川殺人事件/梓林太郎著
旅行作家の茶屋次郎が、殺人事件に巻き込まれ、自ら捜査し、事件を解決する模様を描いている。粗筋: 旅行作家の茶屋次郎は、諸越真奈美という女性から手紙を受け取る。彼女は、以前は茶屋が編集者と打ち合わせするのに利用していた東京のホテルで勤務していたが、現在は故郷である和歌山のホテルで勤めているという。是非和歌山を訪れてほしい、で結ばれていた。 この手紙を読んだ茶屋は、次の記事の取材で和歌山に行く事を決める。 真奈美とも会う約束をした。 茶屋は、和歌山のホテルにチェックイン。真奈美と会おうとするが、会えない。何者かによって客を案内中に殺害されていた。犯人らしき男が客を装って殺害したらしい。 茶屋は、まるで真奈美が自分と会うのを誰かが阻止したかったかの様なタイミングで殺害されたのを疑問に思い、独自で捜査を開始。地元警察は、東京からやって来た旅行作家の行動を疎ましく思う様になる。 真奈美が東京から故郷に戻った背景を、茶屋は知る。銀行員で、真奈美の父親である諸越佳孝は、ある事件に巻き込まれていたのである。 その事件とは、会社の同僚で、愛人関係にあったとされる矢内千雪と一緒にデパートを訪れた所、千雪が試着室で自殺した、というものだった。 諸越佳孝は千雪とは愛人関係には無かったと主張するが、世間体を考えて勤務先の紀南銀行は責任を取らす形で退職させていた。 諸越佳孝という人物は、「愛人」の自殺と、実の娘の殺害という、2人の女性の死に直面した事になる。 偶然にしては出来過ぎ、と考えた茶屋は、更に捜査を続ける。 すると、退職させられていた筈の諸越佳孝は、紀南銀行の関連会社で、かなりの好待遇で再就職している事実を掴む。 ますます不審に思った茶屋は、紀南銀行を調べる。 紀南銀行が、防衛庁関係者の接待に携わっていた事を知る。接待で起用されていたコンパニオンの一人である寺森京子が、現在行方不明になっていた。 茶屋は、寺森京子がカギだと感じ、行方を追う。 京子の唯一の肉親である弟の徹郎を訪ねようとするが、彼も行方不明だった。 茶屋は、徹郎を追う。真奈美を殺害した人物の容貌が徹郎と似ている、感じたからだ。 偽名を使って雲隠れしていた徹郎を発見した茶屋は、真奈美と千雪を殺したのは貴方だと指摘。更に、背景には紀南銀行と防衛庁との癒着が絡んでいる、とも指摘した。 徹郎は、茶屋が読んで来た警察によって逮捕される。解説: 二番煎じか三番煎じの2時間サスペンスドラマのノベライズ、といった感じの小説。 とにかく低予算で映像化出来そうな内容になっている。 本作はシリーズ作らしい。 そんな事もあり、お馴染みらしいキャラ達がお馴染みらしいやり取りを繰り広げた後、漸く核心部分である事件に入るのだが、このシリーズに馴染みが無い読者からすれば、魅力に乏しいキャラらが魅力に乏しいやり取りをするのを延々と読まされる羽目になるので、出だしからつまらない。 小説を本当に面白くさせたいなら、出だしで主人公が事件のど真ん中にいる様子を描いて読者の興味を引き、次の章でその場面までの経緯を遡って描け、と言われるが(要するに、小説が時系列に展開する必要は無い)、本作はその法則を完全に無視している。アマチュアがやりがちな小説作法なのである(時系列にしない、というのもやり方を間違えるとアマチュアっぽくなってしまうが)。 主人公である茶屋は、著者は優秀な人物だとして描き、他の登場人物も彼を物凄く優秀な人物だと思い込んでいる様だが、読んでいる側からすると、その優秀さが伝わって来ない。 旅行作家という肩書を盾に、事件の関係者を巡り歩いて質問するだけ。作中では誰もが知っている著名な作家、という設定になっている様だが、旅行作家如きでそこまで一般に知れ渡るのか、そこまで横暴な態度に出られるのか、と思ってしまう。 ストーリー展開も、茶屋が事件関係者を一人、また一人と訪ねていく内に事件のカギを握る人物に行き着き、その人物がそのまま犯人だった、というもの。奇怪な謎やトリックは一切無く、無論茶屋が不可能トリックを大胆に暴いてみせる場面も無い。 この程度の真相にすら辿り着けない本作の警察は、ただただ無能としか言い様がない。 本作が発表された当時は防犯カメラがまだ一般的では無かったが、現在だったら殺人現場となったホテルやデパートの防犯カメラに映像が確実に残る。映像から徹郎は直ちに特定され、指名手配され、逮捕されていただろう。その程度の事件なのである。 殺人事件は大した事ないのに、その発端となる陰謀だけはとにかくでかい。本来はそちらがメインの事件となるべきなのに、著者の力量不足なのか、著者が重要ではないと勝手に判断したからか、殺人事件が解決した時点で小説は終了、となってしまう。陰謀の方は尻切れトンボで終わっている。 そもそも、何故今回の件が殺人事件に発展したのかが不明。 犯人の徹郎は、コンパニオンを務めていた姉が、防衛庁絡みの接待で機密情報を知る事となり、命を狙われる様になった事に腹を立て、接待の仲介役を担った紀南銀行の担当者である諸越佳孝を恨む。恨みを晴らす為、諸越の同僚と娘を殺す。が、何故恨みの矛先がこの二人に向いたのかが全く説明されていない。常識的に考えれば、諸越本人を狙えば済む事。 諸越佳孝も、単に勤務先が防衛庁との関わりが深く、接待の担当を任されただけに過ぎない。彼自身が京子の命を狙った訳ではなく、指示した訳でもない。 犯行の動機に何の合理性も見受けられないのである。 本作は、旅行作家を主人公としているので、舞台となる和歌山の観光情報を写真入りで掲載している。 が、事件そのものには全く関係していない。 舞台が和歌山でなくでも充分成り立つ。 観光情報も、パンフレットかネットで調べた情報をそのまま載せているだけ。著者が一帯を実際に巡った、という印象は受けない。 登場人物に魅力は無く、ストーリーにこれといった特徴は無く、推理小説を名乗りながらトリックと呼べるトリックも無く、観光情報も大した事無い。 誰に対し、どういう目的で書かれたのかがさっぱり分からない小説。紀の川殺人事件 長編旅情推理価格:905円(税込、送料別)
2015.11.30
コメント(0)
-

魔界探偵冥王星O:ジャンクションのJ/越前魔太郎著
覆面作家越前魔太郎によるメタフィクションシリーズ魔界探偵冥王星Oの1冊。 魔界探偵冥王星Oが活躍する(らしい)短編を、強引に一つの長編にまとめている(らしい)。粗筋:第一章 絵里香は、学校での振る舞いが問題視され、両親に注意される。が、自分は悪い事は何もやっていないと言い張り、家出を宣言。家から飛び出す。 森の中で、「脂を絞る男」と、その人物と敵対する「冥王星O」と出会う。「脂を絞る男」を以前から慕っていた絵里香は、「冥王星O」とされる生き物を倒す。 しかし、「脂を絞る男」と思っていた人物こそ「冥王星O」だった。 また、絵里香とは、牧場で飼われていた家畜だった。第二章 OLの「あたし」は、ある日目を覚ますと、素っ裸の状態にあった。 何が起こったのかと不思議に思っていると、脳内から「冥王星O」の声が響く。「冥王星O」は、「正常なる男」という存在を追っていた。実体を持たない「冥王星O」は、「あたし」の脳に乗り移り、「あたし」が泥酔状態になって意識を失った時に「あたし」の身体を動かし、活動していた。「正常なる男」を捕らえるには、皮膚と皮膚との接触が必要なので、一番効率が良い素っ裸の状態で街中を巡っていたのだ。「あたし」は、否応無しに「冥王星O」の活動を手助けする羽目に。「正常なる男」が乗り移っている人物を見付け出し、接触を試みるも、上手くいかない。 最終的には、「あたし」の脳内には「冥王星O」と「正常なる男」の双方が乗り移る。解説: 本作は四章から成り、その前後と合間にprologue、interlude、epilogueが挿入されている。 四章は、それぞれ独立した短編で、「冥王星O」という存在(人間かどうかも不明)が登場する以外には、互いに何の繋がりも無い。 四章は、prologue、interlude、epilogueで繋げられ、1編の長編になっている(らしい)。 第一章、第二章、そして複数のショート・ショートから成る第四章の一部は「オバカなSF小説」として辛うじて読めるものになっているものの、大部分は支離滅裂の文章の羅列で、読めるものになっていない。 辛うじて読めるものも、読める文体になっているだけで、大した展開もオチも無く終わっており、「これは面白い」と感じるのは1編も無い。「メタフィクションだから、意味不明・理解不能なのは当然です」で逃げているだけ。 文体も、章ごとに異なり、複数の作家が、訳も分からぬまま交代で書いた印象を受ける(覆面作家なので、それも充分有り得る)。「冥王星O」は、一人の人物というより、特定の条件をクリアした者に与えられている称号で、時代や時空を超えて存在するので、他人には永遠の命を授かっている様に映るらしい(詳細は不明)。 ただ、その真相が明らかにされたところで、何の感動も無い。 本作は「冥王星O」シリーズの一冊で、他を読めば本作の意図も分かるようになっている、との事。 残念ながら、他のシリーズ作を読んでみたいという気は全く起こらない。 というか、本作を読むのに費やした時間を返してほしい。 日本では、SFが小説のジャンルとしては低く見られ、なかなか根付かないという。 本作の様な意味不明・理解不能な、著者の自己満足に過ぎない代物が「SF」として出版されていれば、それも無理は無い。【日時指定不可】【銀行振込不可】【2500円以上購入で送料無料】【新品】【本】魔界探偵冥王星O...価格:972円(税込、送料別)
2015.10.29
コメント(0)
-

零崎双識の人間試験/西尾維新著
西尾維新の代表作『戯言シリーズ』の外伝。 殺人鬼集団「零崎一賊」に属する一人で、自殺志願(マインドレンデル)の使い手である零崎双識を描いている。粗筋: 無桐伊織はごく普通の女子高生だったが、ある日、正気を失ったクラスメイトにいきなり凶器で襲われてしまう。伊織はクラスメイトを返り討ちに。正当防衛だったとはいえ、人を殺した事にショックを受ける。 その時、殺人鬼集団「零崎一賊」に属する零崎双識が現れ、伊織に対し「君は自分と同じ殺人鬼になった。自分の妹となり、零崎一賊になれ」と訳の分からない事を言い出す。 伊織はその場から逃げ出し、自宅に戻る。 自宅で待っていたのは、「零崎一賊」と敵対する殺し屋集団早蕨三兄妹の一人早蕨薙真だった。薙真は、伊織を敵対する零崎一賊の一人だと勘違いしていて、伊織の家族を殺害していた。 ますます訳が分からなくなる伊織。 そこにまた双識が現れ、薙真とのバトルを繰り広げる。伊織はまたもやその場から逃げ出す。 双識は、実は弟分である零崎人識を探す旅の途中にあった。 伊織は人識と出会い、零崎として覚醒。零崎一賊の一員となり、早蕨三兄妹との死闘に敗れた双識の凶器を受け継ぐ。解説: ……やっつけ仕事で製作された対戦RPGがやっつけ仕事でアニメ化され、それがまたやっつけ仕事で漫画化され、更にやっつけ仕事でノベライズ。 そんなものを読まされた気分。 対戦RPGやアニメや漫画が大好きで、そういった世界に説明抜きで入れる者なら堪らなく面白いのかも知れない。 が、そういったものに針の先程の思い入れの無い者からすれば、ひたすら退屈。 というか、訳が分からない。 こちらはSFやファンタジーはそれなりに読むので、フィクションで描かれている空想の世界や設定が一から十まで全て説明されていないと全然入り込めない、という事は無い。 それでも、本作で描かれている世界や設定は理解不能だった。 本作は外伝だから仕方ない、読む順番を間違えた、という考えも出来なくはない。 が、たとえシリーズ作でも第一作から順に読み進み、その後に外伝を読まないと全く理解出来ない(正確には興味を持てない)、というのはシリーズ作としては失敗だろう。読む側がシリーズ第一作から入手出来るとは限らない。偶々入手したのがシリーズ作の外伝だった、という場合もあるのだ(カバーには、本作がシリーズ作の外伝である事を知らせる表記は無かった)。 作中で描かれている世界や設定が理解し難くても、ストーリーや登場人物が魅力的であれば、何とか読み進められる。 残念ながら、いずれの条件も満たしていない。 本作には、ストーリーといったストーリーは無い。 奇妙な性癖を持つキャラが現れては、奇妙な凶器を駆使して互いに対戦。勝ち、負け、もしくは引き分けになり、キャラは次の対戦へと進む。 対戦の描写はまさにRPGで、解説本の如くルールや凶器に関する説明があった後、バトルが繰り広げられ、時折解説が入る。ゲーム好きには常識に沿った対戦の描写なのだろう。が、ゲームをしない者からすれば、臨場感に乏しい。 ラストに至るまでに「衝撃の真相」や「どんでん返し」がある様だが、最早どうでも良くなってしまう。「零崎双識の人間試験」というタイトルだけあって、双識は出会う人物に対し「合格」だの「不合格」だのと決め付けるが、その基準というか、そんな事をする根拠が不明。これもまさにゲームの世界。 登場人物は、いずれも名前だけ個性的。「後はイラスト(非常に漫画チック)が挿入してありますので、読者が個々で想像して下さい」といった感じ。ゲームやアニメや漫画に慣れ親しんだ者ならそれだけで充分想像力を膨らませられ、空白部分を埋められるのだろうが、そうでない者からすると紙人形同然。 性格描写も一定していない。 双識は最初は無敵のキャラの様に描かれているのに、弟分の人識が登場すると一気に雑魚に近い扱いになり、あっさり死亡。何故タイトルになっているのかが不明。 人識は、呼吸する様に人を殺す人物という設定だが、それ以外に何の特徴も無く、登場するのと同時に小説そのものが一気にパワーダウン。 伊織は他人に突き動かされて行動するだけ。当初は「殺人鬼となったお前は零崎一賊だ」という言い付けに納得しないが(当たり前)、最終的には零崎一賊の一員になる事を受け入れる。が、その心情の変化の過程がよく分からない。 ストーリーが破綻していて、登場人物に特に魅力を感じられなくても、文章自体が面白ければ、まだ小説として読める。 が、本作は、著者が対戦ゲームをしながらその過程を口述したものを、また別の者が書き起こしたかの様な文体。 登場人物の視点によるダラダラした、独りよがりの描写が延々と続く。一句一句読むには辛く、読み飛ばしてしまう。 300ページある書籍なのに、内容的にはスカスカに感じる。 本作(そして本シリーズ)は、生と死がテーマらしいが、生も死も、平和ボケした日本人らしくゲームの如く軽々しく扱う。 登場人物は人をバサバサ殺し、自らも死んでいく。 にも拘わらず、悲惨さはあまり無い。「所詮紙面での人殺し。実際に人が死んでる訳じゃないから、何も大事にしなくてもいいじゃん」と、著者自身が割り切っているかの様。 同じ平和ボケした日本人の読者なら、このゲーム感覚的な割り切りは共感出来るのだろうが、海外の者、もしくは日本の平和ボケ教育を受けていない者からすれば、理解不能。 小説は、どんなにつまらないものでも、どんなに好みに合わないものでも、ストーリー・登場人物・文体のいずれかにおいて褒められる部分がある筈。 本作は例外中の例外。 褒められる部分がいくら探しても見付からない。 シリーズ第一作を入手し、シリーズを読破した上で外伝である本作を読み直せば、本作の内容を理解出来、褒められる部分を見出せるようになるのかも知れない。 残念ながら、本作を読み飛ばした時点では、そんな賭けに出てみよう、とは思えない。 とにかく自分の嗜好から外れた小説。【楽天ブックスならいつでも送料無料】零崎双識の人間試験 [ 西尾維新 ]価格:1,404円(税込、送料込)
2015.10.03
コメント(0)
-

脳は語らず/渡辺淳一著
医師から作家に転身した渡辺淳一による医療小説。 実際にあったロボトミー手術を巡る訴訟をヒントに書かれたという。 本作は、1974年に雑誌に連載されたものを大幅に加筆している。粗筋: 週刊誌記者の池谷は、ロボトミー手術によって夫を廃人にさせられた、という訴訟を取り上げる事に。 悪徳病院が、不要な手術を断行し、手術費を患者の家族や保険当局から不当にせびり取ったのだろう、と池谷は読み、特集する。 記事は大いに反響を得たので、池谷は更に取材を進める。 患者の家族を取材すれば、病院の悪徳振りが聞けるだろうと予想したが、患者の妻である相田久子は、弁護士に一任してある、と述べるに留まり、取材に一切応じない。 患者側の弁護を担当する五十嵐弁護士を取材する。病院がいかに悪徳であるかを唱えるが、池谷はどことなく不自然さを感じる。 池谷は、相田久子に見覚えがある、と思っていたが、暫くして思い出す。数年前訪れたキャバレーのホステスだった。ホステス上がりの女が、夫が廃人にされたからといって、弁護士の門を叩いて裁判に打って出るか、という疑問が湧く。 患者の取材も行う。ロボトミー手術を受けて廃人にされたとされる相田義男は、手術前から酒癖が悪く、ロボトミー手術も止むを得ない問題者だった。福祉事務所によると、ろくに働きもせず、妻を困らせていたという。ロボトミー手術も、患者の妻の希望によって実施されたというのだ。 池谷は、悪徳扱いした病院も取材。院長の河原も、ロボトミー手術は相田久子の希望によって行われたものであり、病院側が勝手に行ったものではない、と主張。手術が行われたのは2年も前で、その時は何も言って来なかったのに、何故今更訴訟を起こされたのか分からない、と言い張る。 実際に手術を担当した佐伯助教授も取材する。ロボトミー手術は正規の手段で行われており、何の落ち度ないと主張。冷静に見れば、訴訟は言い掛かりに近く、病院側が勝つのは目に見えている、と。 池谷は、佐伯助教授の秘書が何となく気になった。誰かと雰囲気が似ている、と。そして気付く。五十嵐弁護士の秘書と面影がそっくりだったのだ。調べてみると、二人の女性は姉妹だった。訴えを起こした弁護士の秘書と、訴えられている医者の秘書が姉妹というのは、偶然にしては出来過ぎていた。 この時点で、池谷は訴訟は単にロボトミー手術の可否を巡っているのではなく、裏がある、と悟った。 そんな中、佐伯助教授の秘書が自殺する。 佐伯助教授の秘書は、助教授と不倫関係にあったらしく、それを苦に自殺したらしいが、ロボトミー手術訴訟との関連性があるのか、ないのかは不明だった。 池谷は、今回の件の鍵を握るのは佐伯助教授だと感じ、周辺を取材。 すると、佐伯助教授が新たに設立される大学の医療学部教授の有力候補であるのを知る。大学側は、ロボトミー訴訟が結審してから佐伯助教授を教授に指名する予定だった。 しかし、指名を長引かせるのはまずい、と各方面から声が挙がり、梅沢という対立候補が教授に指名される。佐伯助教授は、医療関係者からの評価は高かったものの、訴訟により左遷された形となった。 池谷は、五十嵐弁護士の秘書であり、自殺した佐伯助教授の秘書の姉から漸く話を聞く事が出来た。 そして、一連の件の真相を知る。 新たに設立される大学の教授は、佐伯助教授でほぼ決まっていた。それを阻止したかった梅沢は、知人である五十嵐弁護士に相談。偶然にも、佐伯助教授の秘書と、五十嵐弁護士の秘書は姉妹だった。その繋がりを利用して、五十嵐弁護士は佐伯助教授に探りを入れる。 佐伯助教授は、教授に指名されるに当たって、秘書と不倫関係にあるとなっては不利になると考え、秘書との関係を清算するつもりだった。秘書は、それを不満に思っていて、丁度探りを入れてきた五十嵐弁護士に、佐伯助教授が2年前に行ったロボトミー手術の結果を気にしている事実を告げてしまった。 五十嵐弁護士は、チャンスとばかりに相田夫妻の元に走り、「訴えれば金になるから」と持ち掛け、訴訟を起こさせる。五十嵐弁護士からすれば、訴訟を起こす事自体が目的であり、勝訴を勝ち取れないのは百も承知だった。 梅沢と五十嵐弁護士の思惑通り、佐伯助教授は訴訟により教授指名の有力候補から外され、代わりに梅沢が教授に指名される。 佐伯助教授の秘書は、自分の告げ口により佐伯助教授の教授指名がふいになった事を苦に、自殺した。 池谷は、この事を記事にしようと考えるが、下手に記事にしても自殺した秘書に鞭打つだけだと気付き、思い止まる。解説: 渡辺淳一は、現在は中年向けエロ小説作家に成り下がってしまっているが、元はかなりシリアスな医療小説を書いていたんだな、と本作を読んで思い知らされた。 本作は、ロボトミー手術の有効性を巡る訴訟を描いた社会派小説かと思いきや、実は裏があるとなった時点で全く別方向に展開。最終的にはロボトミー手術を絡めなくても良かった、という内容になってしまっている。 ロボトミー手術を巡る訴訟以上に重要な「裏」とは何かというと……。 ……医大の教授の椅子を巡るバトル。 医療従事者からすれば、医大の教授の椅子を巡るバトルは重要なのかも知れない。が、医療従事者でない者からすれば、熾烈な抗争には見えず、物語が尻すぼみに終わっている。 物語は、主人公の池谷が関係者を巡ってひたすら話を聞く、という展開になっていて、サスペンスに乏しい。 何人もの人物が登場するが、禅問答みたいな返答を繰り広げ、情報が小出しにされるだけで、なかなか核心に迫っていかない。 最後の最後になって、梅沢という、佐伯助教授のライバルが現れ(登場人物の話の中で述べられるだけで、本人は登場しない)、全て彼の仕業ですとなり、終了。 推理小説だったら反則とされても仕方ない。 本作は推理小説として書かれたのではないが、その要素が盛り込まれている。 ただ、著者は推理小説作家ではないので、展開に無理があるというか、ご都合主義的な部分が多い。 池谷は、訴えを起こした患者の妻の写真を見て、見覚えがある、と感じる。数年前、キャバレーで働いていたホステスだ、と気付くのだが……。たった一度しか会っていない女性を、そこまで鮮明に覚えていられるか。仮に覚えていられたとしても、そんな状況下で顔を合わせた女性が、数年後に訴訟を起こして、池谷の注意を引く事になる、なんて展開は都合が良過ぎ。 別の場所で会った二人の女性が、何となく雰囲気が似ていると思っていたら、実は姉妹でした、という展開も無理がある。 舞台となっている東京は、こうも狭い街なのか、と思ってしまう。 池谷が、佐伯助教授と梅沢の教授の椅子を巡って争っているのを知るのも、丁度上手い具合に投書が送られて来て、その出所を調べ、取材してみたら梅沢側の医療関係者で、内部事情に詳しい者だった、という、これもまた物凄く都合のいい事になっている。 本作は、始まりから真相に導かれるまで、数ヶ月掛かっている事になっている(ページ数にすると300ページ超)。 敏腕とされる記者(数年前に一度だけ会ったホステスの顔を覚えている、別の場所で会った二人の女性を姉妹だと見抜く)が、本作程度の「真相」を導き出すまで、何故こんなに掛かってしまったのか。 執念で真相を暴いたにも拘わらず、「記事にしたいが、それでは死者を鞭打つ事になる」として身を引く事にするラストも、尻すぼみ感を後押しする。 ロボトミー手術(前側頭部の頭蓋骨に小さい孔を開け、脳の一部を切開し、精神的疾患を治療)は、本作が発表された時点では、アルコール依存症等の精神疾患の治療に効果があるとされていた。が、現在は薬物治療の発達により、実施されなくなっている。本作でも、有効性を疑問視する声が挙がっているのを踏まえつつ、まだまだ正統な治療法であるとされている。 ロボトミー以外にも、電パチ(電気ショック療法、電気痙攣療法)も、精神疾患の治療において有効な手段、となっている。現在では治療法というより、拷問の手段と認識されているので、これも時代を感じさせる。というか、1970年代の日本でまだこんな「治療法」がまかり通っていたのか、と驚かされる。 本作を読む限り、著者が何故中年向けエロ小説路線に走ったのかも理解出来る。 作家に転身した時点では、元医師という肩書きを最大限に活かした小説を書けたが、日進月歩の発展を遂げる医療の世界では、知識も直ぐ古くなる。最先端医療を学びながら小説を執筆するにも、「元医師」では、得る知識は所詮「読んで学んだもの」に過ぎない。実際に医師として勤務して得る実践的な知識には遠く及ばない。 古い時代の医療の知識や経験しか持ち合わせていない以上、別ジャンルに移行せざるを得ず、それが中年向けエロ小説路線だったらしい。クーポン配布中 【新品・本】 送料無料脳は語らず <渡辺淳一>価格:3,240円(税込、送料込)
2015.09.15
コメント(0)
-

紅玉の火蜥蜴/秋月涼介著
デビュー作「月長石の魔犬」の続編。粗筋: ある県で、放火が立て続きに発生していた。 警察や消防局は必死に捜査していたが、手掛かりは全く掴めなかった。 そうしている内に、連続放火事件は殺人事件に発展。 全焼した家の中から、死体が発見されたのだ。しかも単なる焼死体ではなく、ワイヤーで縛り上げられ、油を掛けられていた。放火が目的ではなく、殺人の手段として放火が使われたのである。 キャリア警視鴻薙冴葉は、石細工屋風桜青紫の協力を仮り、犯人を追い詰めようとするが、逆に有力容疑者と目された者が次々焼死体となって発見される。 警察がなかなか真相に近付けない中、鴻薙冴葉の知人で、嘱託解剖医嘉神沙遊良は、犯人らを突き止める。 放火魔と、放火殺人犯は別人だった。放火殺人犯の少年は、「自殺を手助け」するつもりで、被害者を縛り上げ、油をかけ、火を放って家屋ごと焼いていた。最後の殺人の対象は、放火魔である女性だった。 嘉神沙遊良は、放火殺人犯の少年を、同じ手口で焼き殺す。解説: アニメのノベライゼーションを読まされた気分(カバーもアニメ調のイラストになっている)。 370pと、分厚いのに、中身は薄い。 とにかく無駄なキャラクターが多過ぎ。 本作はシリーズ作で、キャリア警視鴻薙冴葉、石細工屋風桜青紫、そして嘱託解剖医嘉神沙遊良が大活躍するのかと思いきや、嘉神沙遊良以外はこれといった動きは見せない。正確には、キャリア警視鴻薙冴葉は動く事には動くのだが、物語の展開に殆ど貢献しておらず、登場していなくても充分成り立っていた。 大した活躍はしないのに、いずれもやけに凝った名前になっていて(苗字は珍名で、下の名はいわゆるキラキラネーム)、パッと見ても苗字なのか、下の名なのか、男なのか、女なのかも分かり辛い(ちなみに、鴻薙冴葉(コウナギ・サエバ)は女性、風桜青紫(カザクラ・セイシ)は男性、嘉神沙遊良(カガミ・サユラ)は女性らしい)。 珍名・キラキラネームキャラがこの三人に留まっているのなら、まだ救いがあるが、他にも同様の名前のキャラが何人か登場するので、訳が分からなくなってしまう。 ストーリーも、シリーズレギュラー(と思われる)のキャラの日常がひたすら描かれているだけ。 シリーズレギュラーのキャラの視点で、それぞれ一章を割いて描かれているので、ストーリーが全く進展しない。 同じ場面を、2人のキャラの視点で描き、それぞれ一章割く、という無駄な部分も多い。 放火殺人事件が発生しているのに、それに関しては「本遍にとって特に重要ではない」と言わんばかりに、キャラ達の会話で軽く触れられているだけ。 進展が全く無いのに、本のラストに差し掛かってきたので、もしかしたら本書は二部作の第一巻で、解決は次巻になるのか、と思っていたら、いきなり「放火魔と、放火殺人の犯人は同一人物でない。放火魔は、放火殺人の犯人に殺された」という真相が明らかにされる。 真相こそ明らかにされるものの、あまりにも唐突で、「推理」の部分が全く無い。犯人らがどういう手口で犯行を繰り広げたのか、どうやって警察の捜査を欺いたのか……、等々についての説明が無いのである。 まず「事件」がある事を示し、その後シリーズレギュラーの事件とは無関係の近況を長々と述べ、原稿枚数が残り少なくなったので事件のネタバレを著者自ら断行したかの様。 放火魔は、時限発火装置を百個以上作成し、それを市内に設置し捲り、一晩で十数か所の放火を何度も発生させた、という事になっている。が、百個以上の時限発火装置を作るのは相当な作業だし(材料集めだけでも大変)、それを設置するのも相当な作業になる。犯人がどうやってこの大事業を単独で、目撃者一人残す事無く成し遂げたのか、という謎は明らかにされない。 放火殺人の犯人は少年。少年が殺人対象者の家に忍び込み、被害者をワイヤーで縛り上げ、油を掛け、家屋ごと焼いた、という事になっている。が、これに関しても、ここまでの大事業を単独でどうやって成し遂げたのか、という謎が明らかにされない。「著者である自分が犯人だと言ったのだから犯人なんだ」 ……という、著者の理屈だけで「犯人」が決まり、物語は終わってしまう。 推理小説の体を成していない。 推理小説としては失敗としても、面白いキャラが興味深い言動で読者を楽しませる、という内容だったらまだ救われるのだが……。 いずれのキャラも、興味深いのは名前だけで、言動はひたすら退屈。 省いても良かったのでは、と思ってしまう。 本書が、どういう小説になる事を狙って書かれたのか、さっぱり分からない。 盆暗キャリア警視の鴻薙冴葉が、ハチャメチャな捜査と推理を展開し、周囲を呆れさせるが、最終的には本人ですら予想していなかった形で事件を解決してしまう、というユーモア小説……、にしては、鴻薙冴葉が登場する場面以外は小説のトーンは暗い。陰湿と言い切っても良い。 連続放火魔と、それを追う警察の死闘を描いたサスペンス小説……、にしては、鴻薙冴葉という、アニメみたいなキャラ(若い女性のキャリア警察官で、既に警視の階級にある)を登場させている。事件に渾名を付ける事に執着し、それにわざわざ一章を割いている。しかも、警察はただただ無能で(放火に至っては、何十箇所で放火されているのに、目撃者一人すら見付けられない)、連続放火魔対警察の図式になっているとは言い難い。 ユーモア・サスペンス小説というジャンルもある事にはあるが、本作はそれにも該当しない。 本作は、デビュー作の続編。 そんな事もあってか、前作について触れている。 触れるのは結構だし、シリーズ作として継続性を持たせるのは重要なのだろうが、事あるごとに前作に触れて、宣伝し捲るのはどうかと思う。 逆に興味を失う。 というか、前作を宣伝し捲る前に、本作をどうにかしてほしい、と思った。 推理小説には特に興味は無いが、出版社に言われるまま書いてみたらこんなのが出来上がってしまいました、といった内容の小説である。【楽天ブックスならいつでも送料無料】紅玉の火蜥蜴 [ 秋月涼介 ]価格:1,058円(税込、送料込)
2015.09.04
コメント(0)
-

平和を愛する世界人として 文鮮明自叙伝/文鮮明著
世界基督教統一神霊協会(統一教会)の創立者文鮮明の自叙伝。 自身の生い立ちから、統一教会の創立、そして布教活動について述べている。 文鮮明本人は、2012年に死去している。解説: 自叙伝であり、しかも「世界平和に貢献した偉大なる宗教家」に関する書物とあって、都合の悪い事は一切記されていない。 まるで本人が一度として過ちを犯した事が無い聖人君子であるかの様になっている(もしくは、全て前向きに捉えられる様になっている)。 ただ、統一教会はキリスト教を名乗ってはいるものの、他のキリスト教宗派からは認められてはいない。 一部の国では、カルト集団扱いされている。 そもそも統一教会は、長い歴史の間にカトリックやプロテスタント等に分かれてしまったキリスト教、キリスト教の元となったユダヤ教、そしてキリスト教の原点回帰を掲げて始まったイスラム教の「統一」を最大目標としている新興宗教なので(当然ながら文鮮明の下での統一)、どこからも認められないのは当たり前。 文鮮明本人も、神学校でキリスト教・ユダヤ教・イスラム教について学んだ経験は無い。聖書を「真っ黒になる程読んだ」だけで教会を勝手に立ち上げてしまっているのである。キリスト教が根付いていなかった朝鮮ならではの荒業である。 本書では、妻韓鶴子についてかなり詳細に述べているが、これが公式に認めれている限りでは4度目の結婚で、それ以前にも結婚し、子供をもうけている事については一切触れていない。まるで韓鶴子が唯一の伴侶であるかの様になっている。 統一教会は夫婦愛・家族愛の重要性を訴えているので、創立者本人が結婚・離婚・再婚を何度も繰り返しているという事実が知れ渡るのは拙いらしい。 幼少期について述べている部分は、太平洋戦争前の朝鮮半島の一般庶民の暮らし振りが分かるようになっていて、興味深い。 平壌からソウルを行き来する等、南北に分かれてしまっている現在では想像出来ない事も、さらりと述べている。 ただ、終戦後に「イエス様直々のお告げ」により韓国へ渡って布教活動を始める下りになってからは自慢話や持論がひたすら続き、退屈になる。 自叙伝といっても、一応宗教家で、布教活動に精を尽くした筈なのだから、多数の人物と関わりを持っていなければおかしい。にも拘わらず、本人以外は殆ど登場しない。したとしても、軽く触れられるだけで、次のページではまるで存在していなかったかの様な扱い。共産国での布教の為に命を落としたされる女性に関しても、突然述べられ(この女性がいつ、どういう経緯で入信したのかは全く知らされない)、数回名前が繰り返された後、一切述べられなくなる。 あくまでも文鮮明が主役なのである。 主役を引き立てる脇役として、金日成やゴルバチョフ等の政治家が述べられる。 本書によると、朝鮮半島の南北統一の動きは文鮮明が金日成と会談した事がきっかけで、冷戦が終了したのも文鮮明がゴルバチョフと会談した事がきっかけらしい。 南北統一は未だに成し遂げられていないので、文鮮明が南北朝鮮の融和に多大なる貢献をした、というのは誇張し過ぎ。 ゴルバチョフは、ソ連大統領として、世界各国の「著名人」と会っており(統一教会の仏教・日本版ともいえる創価学会創立者池田大作とも会談しているらしい)、文鮮明はその中の一人に過ぎない。文鮮明との会談が世界情勢を左右した、というのも誇張し過ぎだろう。 日本では、統一教会というと、数千人の男女が一堂に会して挙式する「合同結婚式」と、それに参加して芸能界を休止した桜田淳子の件で有名。 しかし当然ながら、本書ではそれに関して一切触れていない。 その意味でも、本書は綺麗事に終始している。 聖書を数回読み通しただけで自身をイエス様の再来と見なして教会を自ら立ち上げてしまう思い込みの激しさ、後に北朝鮮となる地域での強制収容所の過酷な労働すらも前向きに捉えられる楽観主義(生き残ったからこそ、楽観的に回想出来るのかも知れないが)、その強制収容所から何とか生還出来る強運振り、教会の資金源の為に様々な事業を立ち上げるビジネスセンス(全て成功したとは思えないが)、成功を全て自分の手柄にする傲慢さ、色々遭ったにも拘らず(遭ったからこそか)90を超える長寿を維持する健康振り、そして自身を賞賛する本書の編纂を許す(というか、指示したのだろう)厚顔無恥振り。 ある意味、文鮮明の人生は、生き馬の目をも抜く現在を生き抜くビジネスマンの手本にはなっている。 尊敬する人物にも、近くにいてほしい人物にもならないが。 ちなみに、自分が読んだのは、信者らしいオバサンらが無料で配布していたもの。 わざわざ買って読む代物ではない。平和を愛する世界人として 文鮮明自叙伝 / 文鮮明 【文庫】価格:842円(税込、送料別)
2015.08.31
コメント(0)
-

我が標的は日本/桑原譲太郎著
ハードボイルド作家桑原譲太郎によるバイオレンスアクション小説。「日本」シリーズの第1作。粗筋: 伝説のテロリスト・ゴーストが、師と仰ぐ元大物テロリストに呼び出される。元大物テロリストは、不治の病を患っていた。死ぬ前に世界をもう一度混乱に陥れたいが、最早自身が動き回る事は出来なかった。そこで、愛弟子に資金を与え、好きな場所で、好きな様にテロを行え、と言う。 ゴーストは、世界各地からテロリストを集め、テロリスト軍団を結成。標的を日本に定め、日本へと向かう。 各国の諜報部は、この動きを早々とキャッチ。しかし、テロリスト軍団を拘束するまでには至らず、日本当局にテロリスト軍団が向かっている事だけを伝え、丸投げする。 平和ボケしている日本政府は、テロリスト軍団が何故日本に向かっているのか、理解出来ないし、理解しようともしない。偽情報ではないかと。 が、危機感を抱いた警察幹部の一部は、アメリカの特殊部隊デルタフォースで訓練を受けていた小山田を呼び戻し、対応に当たらせる。 小山田は、対テロ部隊を結成し、テロリスト軍団を迎え撃つ事に。 テロリスト軍団は、予想以上に早く日本に上陸する。 小山田は、上陸の情報をキャッチすると、直ちに現場へ向かう。 目撃者の証言で、テロリスト軍団が福井県の敦賀原発を標的にしている、という情報を掴んだ小山田は、福井県警の応援を仰ぎ、包囲網を敷く。 しかし、これはテロリスト軍団が仕掛けた罠だった。 テロリスト軍団は小山田率いる対テロ舞台に大打撃を与え、逃走する。解説: 日本という国がいかに危機管理の意識に欠けているかを訴える為の小説らしいが……。 結局、お人好し対テロ部隊と、馬鹿正直テロリスト軍団の、低レベルな化かし合いを披露しているだけの感じ。 アクション物を書きたいなら、それに集中すればいいのに、著者は本書を日本政府がいかに汚職に塗れていて、危機管理が出来ていないかを訴える媒体にしてしまっている。 そうした訴えも、皮肉をこめてさらりと述べればいいのに、怒りをこめてというか、ムキになって何度も何度もくどく述べるので、読む側からすればウンザリしてしまう。 著者は、日本政府の腐敗振りを、国民が知らなかった衝撃の事実であるかの様に取り上げているが、本書で取り上げられている程度の腐敗は、ニュースに頻繁に触れている者なら誰でも知っている。「聡明な著者が無知なお前ら(読者)に知恵を授けてやろう」みたいな口振りで説教されても困るのである。 そんなに日本政府の腐敗振りを訴えたいなら、小説で架空の腐敗なんて書いてないで、ジャーナリストに転じ、政治家や官僚らの実際の腐敗を炙り出して、世間に訴えた方が、余程も世の中の為になるだろうに、と思ってしまう。 本格的なテロへの備えが出来ていない日本警察は、アメリカの特殊部隊デルタフォースで訓練を受けていた小山田を招集し、対テロ作戦に当たらせる。 小山田は、デルタフォースでは凄腕として名を馳せている、という設定になっている。 が、本作を読む限りでは、ただの見掛け倒し。 要するに、訓練では優秀な成績を叩き出せるが、いざ現場に出るとまるで使い物にならない、といった奴なのである。 本人がそれを理解しているならまだマシだが(実戦経験はまだ浅い)、どういう訳が自分は優秀だと信じて疑っていない。彼を味方する者が、「こいつはデルタフォース帰りの猛者だ。大活躍してくれるに違いない」と信じてしまっているのも、始末が悪い。彼の能力に疑問を持つ者も何人か現れるが、「無能な、危機意識の無い、低レベルな官僚」として描かれ、排除されていく。 デルタフォースの訓練を受けた者として、戦闘能力は凄いのかも知れないが、どこにいるか分からないテロリストを探し出す、という捜査能力はまるで無い。 ゴーストを何度が目撃し、その度に何となく怪しいと思うものの、結局逃し、事態が急変してから「やはりあいつだったか!」とのたうつ。 ここまで勘の無い者が、そもそも何故警察官になれたのかね、と呆れてしまう。 ――テロリストが上陸した、目撃者がいた、その目撃者は「敦賀」と相手が喋っているのを聞いた……。 冷静に考えれば、冷酷非道のテロリストが、目撃者を生かして残す訳が無いし、その目撃者に自身の行動を告げる訳が無い。 罠かも知れない、と思うのが普通だが、小山田はこの目撃者の証言を疑う事無く鵜呑みにして、敦賀へと向かう。 他人を無能だの、危機意識に欠けるだの散々馬鹿にしておきながら、あまりにもお人好し過ぎないか。 結局、本作ではゴーストを取り逃す。それどころか、ゴーストを主役としたシリーズへと発展するので、小山田はいつまでもゴーストを取り逃がす、という運命になるらしい。 ゴーストも、冷酷非道の、伝説のテロリスト、と述べられてはいるものの、こちらも見掛け倒し。 彼くらいのレベルの国際的テロリストになったら、最早個々の国々の政治体制に不満を抱く事は無いだろうと思ってしまう。が、ゴーストは何故か日本の政治家や官僚制度の腐敗振りに物凄い憤りを感じていて、それを正さなければ、という幼稚な理念を抱いている。 何故ここまで日本へのこだわりを持つのか、本書では明らかにされない(日本人らしいが)。 冷酷非道な筈なのに、上陸の際の目撃者は殺さない。代わりに「敦賀」と告げ、警察に証言させる。 ――目撃者を殺さず生かしたのは、警察への陽動作戦の一環だった。警察の目を敦賀に向かわせ、実際には全く別の場所を襲撃するのだ! ……と思いきや、北陸への上陸が思いの他早めに済んだので、観光にでも、と言わんばかりに北陸でモタモタし、あろう事か敦賀に向かう。「敦賀」は警察への罠ではなく、予定そのもので、それに沿って馬鹿正直に動き、自身を無駄に危険に晒す。 馬鹿正直にも程がある。 本作は、冒頭は欧州が舞台。イギリス・フランス・アメリカの対テロ当局の者が続々と登場し、世界を股に掛ける国際アクション小説の様相を見せる。 が、ゴーストが「標的は日本」と定めた時点で、国際的な要素は排除され、日本が舞台になり、一気にスケールダウンする。 映画は、製作するとなると予算が限られるので、下手に国際アクションにしてまうと、チープさが滲み出るだけになる。したがって、国内を舞台とせざるを得ない。 一方、小説は、そうした制限は無い筈。 何故著者は、わざわざスケールダウンしたのか。 スケールダウンしてまで、「日本政府の腐敗振り」を訴えたかったのか。 上述した様に、それだったら小説家ではなく、ジャーナリストになっていればよかったのに、と思う。 本作は、小渕首相や藤原紀香等の日本人著名人(名前は若干変えてある)や、アラン・ドロンやカトリーヌ・ドヌーブ等の海外の著名人(名前は変えていない)が登場。 日本人著名人の登場のさせ方は、本作が発表された当時の世相を皮肉って描いた、と言える。が、外国人著名人の登場のさせ方は、そういった意図は読み取れず、訴えられないかと心配になってしまう。許可を得て登場させたとは思えないし。 著者は、2010年に病没している。 現在の日本を観て、どう思うか。 ますます怒りを感じていただろう。【楽天ブックスならいつでも送料無料】我が標的は日本 [ 桑原譲太郎 ]価格:1,007円(税込、送料込)
2015.08.26
コメント(0)
-

続・星守る犬/村上たかし著
村上たかしによる漫画。「星守る犬」の続編。粗筋:「双子星」 ハッピーの弟犬の「チビ」の話。 チビは、一人暮らしの老婆「長野さん」に拾われる。「長野さん」は人との関わりを避けていたが、チビが心臓病を抱えている事を知り、治療の為に奔走している内に、様々な人と接触する様になり、世間との関わりを取り戻していく。「一等星」「おとうさん」から財布を盗んで逃げた少年の話。 親の元で虐待を受けていた少年は、祖父の家に帰る。 祖父は、少年が数々の軽犯罪を犯していた事を知り、共にお詫びの旅に出る。 少年は、様々な人に対しお詫びするが、既にこの世の者ではない「おとうさん」の行方はなかなか掴めない。 途中で、「長野さん」と出会う。少年は、チビをハッピーと勘違いする。「星守る犬/エピローグ」「長野さん」とチビが、「おとうさん」の娘「みくちゃん」と元妻「おかあさん」と偶然出会う。 二人は、「おとうさん」とハッピーが既に死んでいる事を全く知らなかった。みくちゃんは、チビをハッピーと勘違いする。解説: 既に死んでいる人物とその犬の話の続編とはどういうものかと思っていたが……。「おとうさん」とハッピーと関わりがあった人を描いている。 これなら、元のストーリーの主人公が死んでいても描ける訳である。 本作の登場している人物が、「おとうさん」とハッピーと関わりがあり、中には捜し求めているのもいるのに、誰も既に死亡している事に気付いていない、というのは残酷な話。 特に、「おとうさん」の元妻と娘が、何事も無くそれなりに幸せな生活を送っている様に描かれているのは悲しい。 柔らかいタッチなので、その残酷さが増す。 前編と同様、考えれば考える程読後感が悪くなる。3,000円以上お買上げで送料無料!!【漫画】続・星守る犬 全巻セット (全1冊) / 漫画全巻ドット...価格:905円(税込、送料別)
2015.08.21
コメント(0)
-

星守る犬/村上たかし著
村上たかしによる漫画。粗筋:「星守る犬」 山中で、ボロボロの車が発見される。車内には、男性の遺体があった。死後1年は経っていると思われた。隣には、犬の死骸があった。犬は死後数ヶ月と思われ、男性との死亡時期と差がある。捜査に当たった警察は、飼い主が車内で死亡したものの、飼い犬はそれを理解出来ないまま側に留まり、間も無く死亡したのだろう、と推測する。 身元を証明出来るものが見付からず、遺体は身元不明のまま処理される事に。 子犬が、小学生女子の「みくちゃん」によって拾われ、「おとうさん」の家で飼われる事となる。「ハッピー」と名付けられた子犬は、「おとうさん」の家で育っていき、一家を見守る。「みくちゃん」は、成長と共に素行が悪くなる。「おとうさん」は病を患い、職を失う。職業安定所で再就職先を探すが、持病を抱えている身では思う様にいかず、職に就けなかった。 見かねた妻は、離婚を突き付ける。「おとうさん」は、家族も家も財産も失う羽目に。 唯一残ったハッピーと共に、旅に出る。 が、あるトラブルから救った少年に持ち金を盗まれる等、苦難が続出。 乗って来た車が山中でガス欠になるが、給油も出来ない。「おとうさん」は持病により、車内で死去。 ハッピーはその場に留まるが、怪我を負って死亡。その直前に、「おとうさん」が迎えに来る幻想を見る。「日輪草」 ある町のケースワーカーが、山中で発見された「おとうさん」の遺体の処理を任される。 ケースワーカーは、当初は「よくある話」として、淡々と処理を進めていた。が、遺体の側に犬の死骸があった事を知り、自分も昔犬を飼っていた事を思い出す。「おとうさん」の身元を突き止め、死までの経緯を調査する事になる。解説: ごく普通に暮らしていた男性が、ふとした事で人生の歯車が狂い、普通の生活が出来なくなってしまう。 妻から離婚を突き付けられ、自身の人生に絶望したというか、興味を失う。「旅」を装って死に場所を捜し求めて、その希望通り死んでいった。 表紙はやけに暖かみのあるタッチの絵なので、ページを開いていきなり「車の中で男性の遺体が発見された」といった下りになっている事には少々驚く(遺体そのものは描かれていない)。 飼い犬の「ハッピー」を残したまま死ぬ「おとうさん」は無責任、という考えも出来なくも無い。が、何もかも失い、最早死に場所しか求めていなかった「おとうさん」からすれば、少なくとも自分より先に死ななければOK、という考えしか出来なかったと思われる。 絵と、話の深刻度に物凄くギャップがある。劇画タッチだったら、重くなり過ぎていただろうけど。 考えれば考える程読後感が悪くなる。【日時指定不可】【銀行振込不可】【2500円以上購入で送料無料】【新品】【本】星守る犬 村上...価格:822円(税込、送料別)
2015.08.20
コメント(0)
-

セカンドタウン/嶋戸悠祐著:粗筋
島田荘司氏が選者を勤める福山ミステリー文学賞でデビューした嶋戸悠祐による長編作。粗筋: 日本国内にありながら、街の全体が塀に囲まれ、自治権を得ている「セカンドタウン」。 セカンドタウンの住民は、塀の外に出る事は許されていなかった。塀の外に「外界」という世界があるのは理解していたが、誰も見た事は無く、特に見たいとも思っていなかった。セカンドタウンは長年外界からの訪問者を拒んできたが、最近は教員等として外界の者が採用されるようになっていた。ただし、「セカンドタウンに一度入ったら二度と出られない」が鉄則なので、わざわざやって来る者は少なかった。 セカンドタウンに警察は無いが、「自治体」と呼ばれる組織が治安を管理していた。 最近の関心事は、女性が4人行方不明になっている、という事くらいだった。 郊外にある井戸から、高校教師の中山が、教え子の戸丸とペットのジョンによって救出された。中山は、井戸の底での恐怖体験を戸丸に語る。その恐怖体験は、実際に起こったとは到底思えない内容だったが、中山の様子からして、嘘とも思えない。 戸丸は、中山が話した体験について、友人の祝詞に話す。中山も祝詞も実は外界からやって来た者なので、何か掴めるかも知れない、と思ったのだ。 祝詞は、中山の恐怖体験を全て嘘だ、と一蹴し、自身の推理を述べる。 中山は、女子寮の側にまで忍び込み、覗きをしようとしていたが、見付かりそうになったので、逃げた。慌てていたので、井戸に落ちてしまった。このまま発見されたら、覗きをしようとしていた事がばれてしまうと考え、起こりもしなかった恐怖体験をでっち上げ、戸丸に語った、と。 戸丸は、中山の表情からして、恐怖体験がでっち上げとは信じられなかった。 それから間も無く、中山は投身自殺する。 戸丸は、この事について祝詞に直ちに教えなければ、と思うが、祝詞は「推理」を述べた日から登校していなかった。 気になった戸丸は、祝詞の住まいを訪れるが、そこには誰もいなかった。奇妙な本を見付ける。そこには、祝詞が戸丸宛に残したメッセージが挟んであった。「お前を含め、この世界が『ソニー・ビーン』で、洞窟の外が『外界』だ」と。 戸丸は、祝詞が残してくれた本を読む。 16世紀のスコットランドに実在したとされるソニー・ビーンという人物の話だった。生活に困窮したソニーとその妻が、旅人を殺しては金品を奪い、人肉を食して生活を立てるようになる、という内容だった。子や孫を作り、共同で旅人を襲っては殺し捲っていたが、最終的には捕まって一族もろとも処刑された、と。 戸丸は、本の内容と、祝詞が残してくれたメッセージとの関連性が分からなかった。 そんな所、外界からやって来た数多という探偵と出会う。女性行方不明事件を調査に来たという。戸丸は、セカンドタウンを案内するのと同時に、中山の恐怖体験、そして祝詞の失踪と彼が残した本について語る。 数多は、何故か中山や祝詞の件に興味を持ち、本を預かる。 数日後、戸丸は数多と再会。 数多は、自身の推理を述べる。祝詞は、本で述べられていたソニー・ビーンの末裔で、人を攫って食べていた。それに気付いた中山は、祝詞を阻止しようとしたが、祝詞に逆襲され、井戸に落とされた……。 戸丸は、数多が全く見当違いの推理を述べている事に、直ちに気付いた。そして思う。所詮「外界人」だ、と。中山や祝詞と同様、愚かな存在だと。 しかし、その時点で戸丸は考える。何故数多という探偵は、子供でも見当違いだと分かる推理を堂々と発表したのだ、と。 ペットのジョンを、戸丸は数多に見せる。 数多は明らかに動揺した。 戸丸は、その時点で気付く。セカンドタウンの常識は、外界では非常識なのだ、と。 クローン人間の出来損ないをペットにするのも、クローン人間を食すのも、セカンドタウンでは当たり前だが、外界ではおかしいのだと。 その時点で、祝詞が残したメッセージや、本の意味を、漸く理解する。 一方、外界では、探偵の数多が、影武者としてセカンドタウンに送り込んだ自身の偽者が消息を絶った、と記録係の六村に報告する。多分、生きていないだろうと。 六村は驚く。セカンドタウンとは結局何なのだと。 百年前、核戦争を目前にした日本政府は、巨大なドームを築き、そこに日本の人口の大半を避難させた。 核戦争により、日本は壊滅状態に陥るが、ドーム内の世界はセカンドタウンとして繁栄した。が、これといった産業が無かったセカンドタウンは、主幹産業として、臓器移植用や食用のクローン人間を増産。輸出までする様に。 当然ながら、セカンドタウンの者は誰もが人肉を食べていた。戸丸が、影武者数多の推理を「子供騙し」と思ったのも、人肉を食べたいなら、何も人を攫わなくても、レストランに行けばいくらでも食べられるからだった。 セカンドタウンの実情を知ろうと、外界の日本政府は、スパイを送り込んで、調査する。中山と祝詞は、実は外界からのスパイだった。更に、行方不明になったとされる女性らも、実はスパイだった。 スパイに気付いた「自治体」が、抹殺していたのだ。 数多は、六村に対し、セカンドタウンと、その状況を見て見ぬ振りをしている日本政府の告発に動く事を決意する。解説はこちら【はじめての方限定!一冊無料クーポンもれなくプレゼント】セカンドタウン【電子書籍】[ 嶋戸...価格:810円
2015.08.15
コメント(0)
-

セカンドタウン/嶋戸悠祐著:解説
島田荘司氏が選者を勤める福山ミステリー文学賞でデビューした嶋戸悠祐による長編作。解説: 推理小説と最初は思わせておきながら、徐々にホラー小説になっていき、最終的にはSF小説になっているという、てんこ盛りの内容。 構成がしっかりしていれば、物凄い傑作に成り得るのだが……。 本作はそれを感じさせない。 作者が、読者を置いてきぼりにしながら風呂敷を広げて持論をガンガン展開し、読者がそれを飲み込める前に風呂敷をさっさと畳んで「ハイ、おしまい。ではさようなら」と宣言している感じ。 推理小説にしては、「推理」の部分が独りよがり過ぎて説得力に乏しい。ホラー小説として読みたくても、「名探偵の推理」の部分が恐怖の部分を薄めてしまっている。SF小説にしては、科学考証に難がある。 推理・ホラー・SFのいずれかにおいて突出した部分があれば、それがメインで、他はサブなんだな、と納得出来る。が、どれも中途半端なので、結局何を読まされたのかが分からない。 冒頭で、中山は、この世の出来事とは思えない恐怖を体験する。 島田荘司の流れを汲む推理小説だったら、「この奇怪な、非現実的な体験は、実はこの様に物凄く論理的に説明出来るんですよ」となるのだが、結局この「体験」は、中山の創作、という事になっている。これでは夢オチと大して変わらない。 探偵が現れ、行動を開始。これで推理小説っぽくなるのかなと思いきや、早くも無能な偽探偵である事が明らかにされる。 ……と思っていたら、ラストで本物の「天才探偵」が颯爽と登場し、これまでの出来事を安楽椅子探偵(本人はセカンドタウンに行っておらず、偽探偵から報告を受けていただけ)の如く全て総括して「真相」を導き出し、それを記録係にペラペラと語り、物語は終了。「推理」の部分は全て「天才探偵」の押し付けで、推理小説の体を成しているとは言い難い。 作中では、食人鬼「ソニー・ビーン」の生き様を、メインストーリーの間に分割した状態で描いている。 この作中作は、祝詞によって書かれた、となっている。セカンドタウンの実情を、オブラートに描くつもりで書き残した、と。 何故祝詞がこんな回りくどいやり方でセカンドタウンの実情を訴えようとしたのか、結局明らかにされない。 セカンドタウンの異常さを知らしめたかったなら、他にもっと効果的で分かり易い方法があったと思うが。 この作中作は、単体で読むとそれなりに面白いので、セカンドタウンの部分を全て削除して、これだけで本にすればいいのに、と思った(作品として売れるかどうかは疑問だが)。 近未来の日本を描いていたと思われていた本作は、実は核戦争が起こってから100年も経った後の世界を描いていた、となっている。 クローン技術が確立され、人間のクローンが当たり前となっている、と。 にも拘らず、クローンの技術は人間以外には転用されておらず、家畜を増やせないので人間のクローンを食用として大量生産している、という設定は突飛過ぎる。クローン家畜を増産した方が、クローン人間の増産より遥かに楽だろうに。「食人」を押し通したいが為の設定になってしまっていて、読んでいる側からすれば、「食人」の必然性を感じさせない。 本作は、大部分は戸丸という高校生の視点でストーリーが進み、最後になって「天才探偵」が現れ、真相を暴く、という構成になっている。「天才探偵」を排除し、戸丸をサブキャラにした上で、スパイ中山を主人公としたサスペンス小説にした方が良かった様な。 ……塀に囲まれた謎の街セカンドダウン。中山は、「セカンドタウンの実情を暴け」というある組織の密命により、高校教師として潜入。しかし、謎に満ちていると思われていた街は、いざ歩き回ってみると何の変哲も無い普通の生活が営まれていた。住民も、おかしい所は無い様に映る。が、何かが引っ掛かる。裏側を調べていく内に、街全体が食用クローン人間の大工場で、住民全てが食人鬼だったという真相が明らかに……。 こちらの方が遥かにサスペンスに満ちていただろう。 何故「大部分はセカンドタウン内の高校生の視点で展開。ラストで全てお見通しの天才探偵が真相を語る」という構成にこだわったのか、理解出来ない。 作中の大半を占める戸丸というキャラの言動も分かり辛い。 見ず知らずの外界からの「探偵」に、中村の恐怖体験や祝詞の失踪についてかいつまんで話し、「証拠」となる本も渡してしまう程のお人好し。 ……と思っていたら、「探偵」が見当違いの推理を述べ始めると、途端に中山、祝詞、そして「探偵」ら「外界人」に対し軽蔑の思いを露わに。 まるで別人に豹変してしまったかの様な感じ。 セカンドタウンにやって来た「探偵」(実は、天才探偵の身代わりとして送り込まれた、探偵気取りの浮浪者)の豹変振りにも驚く。 戸丸と会い、話を聞いている時は人がやけに良さそうなのに、「探偵」の視点を描いた「探偵日誌」では戸丸の事を邪魔だと思い(無論中山や祝詞の件についても特に興味を示しておらず、演技だった、という事に)、雇い主である「天才探偵」をも馬鹿にしているという有り様。 裏表があり過ぎ。 戸丸は、「探偵」が推理を述べた時点で、「こいつは無能だ」と知るが、読者はそれ以前に無能振りが分かる構成になっている。 アレクサンダー・“ソニー”・ビーン(Alexander "Sawney" Bean)は、16世紀のスコットランドで、旅人を狩っては食していたという、歴史上の人物とされる。イギリスではかなり有名な残酷話。 妻を娶り、子を産み、その子らに更に子を産ませ、最終的に一族は48人にもなったという。一族で人を狩っては食べていたとか。 作中作の通り、最終的には犯行が発覚し、一族全員が捕らわれ、裁判を経る事無く処刑されている。 ただ、記録がきちんと残っている訳ではない。そんな事もあり、実在の人物や出来事ではなかったのでは、もしくは誇張された形で伝承されているのでは、と考える歴史学者が多い。 したがって、本作の「幼い時に幼馴染や両親を殺して殺人や食人に目覚め、食人一族を築くに至った」という経緯は、あくまでも本作独自の見解である。粗筋はこちら【はじめての方限定!一冊無料クーポンもれなくプレゼント】セカンドタウン【電子書籍】[ 嶋戸...価格:810円
2015.08.15
コメント(0)
-

殺竜事件a case of dragonslayer/上遠野浩平著
魔法や魔術が常識となっている世界で起こる事件を、戦地調停士の探偵役が解明する、というファンタジーとミステリーを融合させた「戦地調停士シリーズ」の第1作。粗筋: 魔法や魔術こそ「科学」であり、「兵器」でもある世界。 竜もいた。強力な、人間を超越した存在である竜は、世界中にも6匹しかいない。その中で人間と常時接触出来るのは、ロミアザルスという村にいる竜だけだった。村民は竜を大切にしており、結界を敷き、人間が無許可で竜に接触出来ないようにしていた。 竜の存在により、ロミアザルスは寒村にも拘わらず周辺諸国から一目置かれており、和平会談の場となっていた。 戦地調停士のエドワース・シーズワークス・マークウィッスル(ED)、風の騎士のヒースロゥ・クリストフ(ヒース)、そしてカッタータ国の特務大尉レーゼ・リスカッセの三名が、ある戦争の和平会談をセッティングする為、ロミアザルスを訪れる。会談を行うには竜の許可が必要なので、会いに行く。すると、竜は死んでいた。鋼鉄らしき物体が突き刺さっていて、明らかに他殺だった。 竜の死を知った村民は怒り、誰がどういった理由で竜を殺したのかが解明されない限り、和平会談の場は提供出来ない、と言い切る。 ED、ヒース、レーゼの三人は、「殺竜事件」の謎を解明しなければならなくなった。 竜との面会は許可制になっていた。許可が無い限り、村民ですら接触出来ないし、しない。竜が生きているのが最後に確認されてから死体発見までの間に面会したのは、6名。 容疑者は、6名に絞られた。 ED、ヒース、レーゼは、各地に散らばる容疑者ら6名を一人一人訪れる旅に出る。 容疑者らは、いずれも竜との面会で人生観が変わった、と口を揃えた様に言う。竜が死んでいる事は全く知らず、当然ながら竜を殺害した犯人ではなかった。 最後の容疑者が犯人でないと判明した時点で、EDは事件の真相に気付く。 竜は、ロミアザルスの村民全てによる策略によって殺されたのだ、と。 本来、竜は人間と接触したがらない生物であり、人間も余程の事が無い限り竜と接触する真似はしない。そんな状況の中、竜の側にロミアザルスという村が出来たのは、村自体が竜を殺す為に立ち上げられたからだった。 村は、何世代にも亘って竜と接触。竜の信頼を獲得し、警戒を解く事に成功。竜を殺すチャンスを窺っていた。 が、世代を下るにつれ、竜を殺害しなければならない根拠は不明になっていった。村は、「竜のいる村」として重要視される様になり、竜がいなくては存続出来ない状況になっていたのである。 その均衡も、時代の変化によって崩される。竜が住む場所には地下資源があった。村自体の存続も、周辺勢力によって保障される事に。こうなると、竜の存在は得どころか、損だった。 村民は、数世代振りに、村が立ち上げられた原点に回帰し、竜を殺害する計画を実行。開いた竜の口の中で銃を発砲する、というものだった。鋼鉄は、外から突き立てられたものではなく、体内から飛び出した銃弾の先端部分だったのだ。 竜には、村による殺害計画を跳ね返す魔力はあったものの、数世代に亘って信頼関係を築いていた筈の人間らに裏切られた事に絶望。村民による殺害計画に屈する事を自ら選び、「自殺」したのだった。解説: ファンタジーRPGを小説化した様な内容。 ファンタジー小説として読む分には問題無いが、やはりミステリーとして読むと、その展開に首を捻ってしまう。 魔法や魔術が当たり前、という世界で、まともなミステリーが成立すると期待する方がおかしいのかも知れないが。 探偵役のEDは、「6名の容疑者」が犯人でないのは、旅に出る前から知っていた。 6名に会いに行っていたのは、時間稼ぎに過ぎなかった。 ファンタジー小説の場合、6名に会う事自体が「冒険」を構成するエピソードになるので、問題は無い。 一方、ミステリーとして読んだ場合、作中の謎を構成する重大要素であると匂わせながら、最後になって「別に無くても成立していた」では、裏切られた気分になる。ミステリーは、無駄な部分は可能な限り省くのが鉄則だから。エピソードの為のエピソード、作中の謎とは無関係な「文学」的描写は、必要無い。姑息な陽動と映る。 キャラ設定も、ゲーム化やアニメ化を意識した部分が多い。 登場人物が無駄に多いのである。 6名の容疑者(いずれも少し登場するだけだが、無駄に個性的)も、結局キャラを増やす為の措置に過ぎない。 メインとなるED、ヒース、レーゼの3キャラも、本作の展開を見る限りでは、2人くらいに集約出来た感じ。3人にしてしまった為(この内2人はほぼ無敵のスーパーキャラで、切迫感を抱かせない)、持て余している印象を受けた。 ラストで明らかになる「真相」も、何となく予想出来てしまい(村民以外で犯人は有り得ない)、驚きは少なかった。 寧ろ、「その程度で折角の竜を殺すか?」と疑問に思う。 人間を超越した、全知全能の存在である筈の竜が、人間に裏切られたくらいで絶望的になって自ら死を選ぶ、というのもおかしい気がする。人間より遥かに長生きする竜が、たった数世代分の人間と接触した程度で警戒を解く真似はしないだろうし、村の存在の目的だって、そもそもお見通しでなければならない筈。 ファンタジー小説のファンからすれば、「魅力的なキャラ満載の、シリーズ第1作!」という事になるのかも知れないが、ミステリー小説として読む者からすると、無駄が多く、「真相」も練られておらず、イマイチ感が否めない。 本作は、シリーズとなる舞台設定を説明する為のものといえる。 キャラや設定に興味を持ち、全作を通して読みたい、と感じられる読者からすれば有難い一冊なのだろう。が、キャラにも設定にも特に興味を持てないと、これ一冊でお腹一杯になる。殺竜事件 a case of dragonslayer-【電子書籍】価格:864円
2015.08.09
コメント(0)
-

扉は閉ざされたまま/石持浅海著
倒叙形式と本格物を掛け合わせた実験的な推理小説。 殺人犯と、殺人事件を解明しようとする探偵役との攻防を描く。粗筋: 大学時代に同じサークルにいた7人が、同窓会の為に、高級ペンションに集まる。 その中の一人の伏見が、サークル仲間の新山を殺す事に。 ペンションで行われる同窓会は、殺害するのに打って付けのチャンスだったのだ。 伏見は、新山が宿泊する部屋に忍び込み、殺害。ある理由から(というか、殺害に至った理由から)、部屋を密室状態にした上で、部屋から出る。 ペンションに集まっていたサークル仲間は、食事会を開始。 が、いつまで経っても新山が姿を現さないので、不思議に思う。 同窓会は、ペンションの大掃除も兼ねていた。その作業に疲れてしまって眠りこけているんだろう、と最初は気楽に考えていたが、流石に何時間も目を覚まさないのはおかしい、と思うようになる。 新山は寝ているのではなく、事故死しているのでは、確認の為にドアを破ろう、という提案が出されるが、却下される。ペンションは一時的に借りているだけで、オーナーは別にいる。ドアは高価な年代物で、破壊した後に「実は眠っていただけで、ドアの破壊は早とちりでした」では取り返しがつかない、というのだ。 ただ時間が過ぎていく中、サークル仲間の一人の優佳が、新山は殺されているのでは、と疑い始める。 優佳は、容疑者でもある同窓会参加者らの言動を見て一人一人除外していき、最終的には伏見に行き着く。 しかし優佳は、新山を殺したのは伏見だと知りながらも、追及するどころか、伏見に犯行のミスを伝え、その証拠を消す機会を与える。 殺害した張本人である伏見(優佳以外の同窓会参加者は、まだ殺人に気付いておらず、伏見が犯人だとも気付いていない)により、閉ざされた扉が開けられ、漸く新山の死体が発見されるに至る。解説: 本格推理とは、基本的に読者にも探偵役にも真犯人が冒頭では明らかにされておらず、探偵役が事件を捜査する事で意外な犯人が明らかにされる、というミステリー。 倒叙物とは、冒頭で真犯人が犯行(大抵は殺人)を実行する場面が描かれ、読者は勿論、探偵役も犯人が分かっているが、決定的な証拠は無いので、探偵役がいかに真犯人の完全犯罪を崩すのかに焦点が当てられるミステリー。 この2タイプのミステリーは、相反するものなので、組み合わせる事は出来ない筈。 本作は、それにあえて挑戦している。 犯人が人を殺し、その死体が発見される前に、探偵役が犯人を断定する、という展開も斬新である。 残念ながら、成功しているとは言い難い。 本格推理物として読んだ場合、犯人が冒頭で明らかにされるので、いわゆるネタばれ状態になっていて、探偵役がラストで「犯人は貴方ですね」と指摘する場面に至っても、意外性も何も感じない。 倒叙物として読んだ場合、本来なら犯人対探偵役の一騎ちとなるべき展開が、探偵役が犯人探しの為にまごまごするという場面が延々と描かれ(くどいが、読者は既に犯人が誰か分かっている)、歯痒さしか感じない。 小説の設定も、「死体が発見され、正式に殺人事件と認定される前に探偵役が犯人を特定する」という展開の為だけのもので、舞台も、登場人物の言動も、常識離れしていて、リアリティを感じない。 元サークル仲間が集まり、一人が部屋に閉じ篭もっていつまでも姿を現さないのに、他の参加者があれこれ理由を付けて部屋に突入して確認しない、というのは異常。 ドアを破って開けない理由が、「ドアは年代物で、無闇に破壊出来ない」となれば尚更。そこまで高価で、代替不可能なドアがあるとは思えないし、全損させずに開ける方法だってあった筈(作中では、ドアを破るとなったら斧で破壊するしかない、としか述べられない)。 窓を破壊し、鍵を開けて侵入する方法も提案されるが(最終的にはこの方法で進入する)、当初は警報ベルが鳴り響いて近所迷惑になるから駄目だ、という訳の分からない理由で却下される。 本作の為だけの、現実性に乏しい設定としか言いようが無い。 犯人が冒頭でネタばれされてしまう「本格推理」なので、最大の謎は、犯人が殺人に手を染めざるを得なかった動機となるのだが……。 これもまた現実性に乏しい。 サークルのメンバーは、全員が臓器移植のドナー登録をしていた。しかし、新山は、海外を訪れては性風俗で遊んでいた。 性感染症を患っている可能性のある者がドナー登録し、万が一臓器を提供する羽目になったら、移植を受けた患者が性感染症を患ってしまう可能性がある。ドナー登録の精神に反すると感じていた伏見は、新山に対し性風俗通いを止めろと忠告したが、拒否されたので、殺す事にしたのだった。 伏見が部屋を密室にしたのは、死体の発見を遅らせ、腐敗を進ませ、臓器が移植される可能性を無くす為だった。 ……いくら何でも独りよがりな、身勝手過ぎる動機。 性風俗通いするからといって性感染症を必ず患うとは限らない。患ったとしても、不慮の事故で死ぬとは限らない。死んだとしても、臓器を提供出来る状況で死ねるとは限らない。臓器を提供出来る状況で死んだとしても、臓器が性感染症に犯されているとは限らないし。そもそも臓器提供がすんなりと進むとは限らない。 不確定要素がとにかく多いのに、伏見はまるで新山が確実に性感染症を患っていて、今後臓器を提供出来る状況下で確実に死ぬと信じて疑っていない。 仮にそうだったとしても、何故伏見が「俺が新山の『悪行』を阻止しなければ!」という身勝手な「正義」を実行するに至ったのかが説明されていない。 犯人の伏見と、探偵役の優佳の頭脳戦、という構図も、成立しているとは言い難い。 伏見はただの素人だし、優佳もごく普通の女性(作中では、優佳が物凄い観察力を持つ女性だ、伏見が感心する場面があるが、読んでいる側にはそれが伝わらない)。 凡人同士の腹の探り合いに終始していて、それが200ページも続くのだから、中ダレする。 ……探偵役の優佳が伏見を犯人だと断定した上で(他の参加者には伝えない)、「トリック」の欠陥を指摘。伏見は窓を破って部屋に進入する際、その欠陥を「正した」上でドアを開け、死体を「発見」。漸く参加者全員が新山が死んだ事を確認し、警察に通報する段階になった……。 この時点で、200ページにも及ぶ本作は終了。 要するに、警察による捜査はまだこれからなのである。 伏見は、優佳の助けもあり、完全犯罪を成し遂げた、と満足している様だが、警察を欺けるとは到底思えない。 ……ある者が部屋を偶々密室状態にして閉じ篭もっていたら、事故死してしまい、それを同じ建物にいた旧友らが、数時間にも亘って何の手も打ちませんでした……。、 ……と、警察に説明した所で、「はい、そうですか。これは事故死でしょうな」と納得するか。 何故被害者は部屋を必要も無いのに密室にしたのか、何故旧友らはドアを破壊して中に入らなかったのか(ドアが年代物だった、なんて言い訳を警察が易々と受け入れるとは思えない)、等々、警察は色々追及するだろう。 伏見が思いもしなかった側面から、新山の死は殺人だ、と断定される可能性が高い。状況からして部外者による犯行とは考え難いので、当然ながらペンションに集まった者らに容疑が向く。 警察が総力を挙げて捜査すれば、素人の工作くらい難無く見破られる。 伏見はそこまで見越して犯罪に手を染める事を決めたのか。 倒叙形式と本格物の融合、という事で、こちらとしては、伏見が殺人を実行に移す様子が冒頭で描かれるものの、「実は新山はその時点では死んでおらず、別の同窓会参加者によって殺された」「新山だと思って殺した人物は、実は新山ではなかった」といったどんでん返しを期待していた。 が、冒頭通り伏見が犯人で、新山が被害者、という、「本格物」の割には捻りの無い結末に、驚いた。 要素を個別に見れば、面白くなりそうだな、と思わせる小説だが、全要素をまとめた上で見ると、無駄や矛盾が多い。 倒叙の要素を排除し、探偵役の優佳が、久し振りに集まった旧友の内誰が閉ざされた扉の向こうの新山を殺害したのか、扉が開かれる前に密かに追及する、という本格推理にしていたら良かったのに、と思う。 殺人の動機はもう少し練らなければならないが。【楽天ブックスならいつでも送料無料】扉は閉ざされたまま [ 石持浅海 ]価格:905円(税込、送料込)
2015.08.06
コメント(0)
-

人のセックスを笑うな/山崎ナオコーラ
女性作家山崎ナオコーラのデビュー作。「人のセックスを笑うな」「虫歯と優しさ」を収録。粗筋:「人のセックスを笑うな」 19歳のオレは、美術専門学校に通っていた。そこで、講師を務めているユリと出会う。 ユリは、オレより20歳年上の人妻だったが、ふとした事で肉体的関係を結んでしまう。 ユリの夫は、更に年上の50代の男性だった。彼は、ユリとオレの関係に気付くか、咎めるどころか公認する態度すら取る。 が、ユリは講師を辞職し、夫と共に海外へ旅立つ。 オレは、喪失感を味わう。「虫歯と優しさ」「私」には、伊東という恋人がいたが、関係は上手くいっていなかった。 歯医者に通いながら、「私」は伊東との関係が上手くいっていない理由を思い返す。 最大の理由は、「私」が男として生を受けながらも、今は女性の格好をしているからだ、という結論に至る。「私」は、伊東から最後に優しい言葉を掛けられ、泣く。解説: いずれもスカスカの、中身の無い短編。 女性作家特有の極端な自己満足が行間から滲み出ていて、読んでいるだけで腹が立ってくる。 ここまでイライラさせられる本も珍しい(本書より先に読んだ「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」もイライラさせられたが、本書を読んだ後はそれが寧ろ大傑作であるかの様に思えた)。 タイトルのみに、人の気を引くセンスが感じられる。 表題作の「人のセックスを笑うな」は、19歳の学生の視点で、年上女性との関係を描いているが……。 リアリティが無さ過ぎ。 19歳の若い男が、特に魅力的でも無い39歳の女性に恋心を抱き、肉体的関係を持つとは思えない。また、その若い男が、関係を持った年上の女性に捨てられてもただ泣くだけで済ませる、なんてのも有り得ない。 更に、妻が若い男と不倫関係に陥る事を、男が笑って許すとも思えない。 本作は、色ボケしたオバサンのファンタジー(妄想)を描いているといえる。 特に美人でもない、性格が良い訳でもない人妻の自分が、若い男と肉体的関係を持てて、年上の夫には笑って許してもらえ、若い男に飽きて捨ててもその男はメソメソ泣くだけで何も言ってこない、という奇想天外のファンタジー。 これが、男女が逆転した状態で書かれていたらどうなるか。39歳の妻帯者が19歳の女子大生と関係を持つが、年上の妻は笑って許し、やがて女子大生に飽きて捨てるのだがその女子大生は何も言ってこない……。こんなのを書いた所で、「妄想にも程がある」と一刀両断されるだろう。 何故女性作家だと許されるのかね。 仮に色ボケオバサンのファンタジーであっても、最後のオチで全てが引っ繰り返される、という展開にもなっていれば、まだ納得出来る。「実は色ボケオバサンのファンタジーなんかではないのです」と。が、それも無い。 ただの色ボケオバサンのファンタジーに終始。 どんでん返しも無く、オチも無く、新たな見識を得たという気分にもさせてもらえない。 読むだけ無駄な一遍。「虫歯と優しさ」は、「私」が女性の格好をした男性である、というのが最大の「トリック」らしいが……。 その事実は「私」の口から早々と明らかにされてしまうので、意外性はその時点で消滅。 後は、「私」が歯医者に通っては伊東との関係について悩む場面が描かれるだけ。 どんでん返しもオチも無く、ただ終わる。 日記にちょっと手を加えて小説っぽくした感じ。 表題作と同様、スカスカの、自己満足の産物。 女性作家、てこんなのでもやっていけるんだ、と羨ましく思うだけの1冊だった。 【新品】【書籍・コミック 文庫活字】人のセックスを笑うな価格:432円(税込、送料別)
2015.07.28
コメント(1)
-

東京タワー オカンとボクと、時々、オトン/リリー・フランキー著
イラストレーター、絵本作家、俳優、作詞作曲家等、多方面で活躍している著者の半生を、母親と父親と本人の関係を軸に描いている。粗筋: ボクは、福岡県の寂れつつある町で誕生。 物心付いた頃には、母親(オカン)と父親(オトン)は別居しており、ボクは母親の元で暮らしていた。別居しているといっても、オカンとオトンは非定期に会っていて、ボクとオトンの間にも繋がりはあった。 暮らしは楽でなく、オカンとボクは親戚らの間で住まいを転々とする事を強いられるが、そんな生活が当たり前だと思っていたボクは、特に不自由を感じる事無く育った。 高校を卒業したボクは、東京の美術大学に入学。堕落した生活を送りながらも何とが大学を卒業すると、仕事を見付け、東京で暮らし続ける。 福岡に残っていたオカンは、癌を患う。ボクはオカンを東京に呼び寄せ、同居生活を開始。手術と治療により、癌を克服出来た。 オトンも度々東京にやって来ては、オカンとボクと適当に絡んではまた福岡に帰る、という関係が続く。 ボクは徐々に仕事で成功を収めるようになっていくが、オカンを楽させるまでには至らない。 そんな中、オカンはまた癌を患う。転移や再発ではなく、新たな癌だった。治療は不可能な癌という事で、オカンの体調は悪化していく。 ボクは奇跡が起こる事を願うが、適わず、オカンは亡くなる。 オカンは、生前得意な料理をボクの友人や関係者に振舞っていた事もあり、葬式にはボクが想像していた以上の人数が参列。オトンは、ボクの前で初めて涙を見せた。解説: 母親や父親の記憶を詳細に綴った記録。 個人の日記を整理し、他人が何とか読める様に直した感じ。 著者本人も、母親や父親も作中で老いていくので、当然ながら死を迎える、という場面が描かれる。 悲しいといえば悲しいが、誰の記憶も、結局はこういう結末に至るだろう。 著者が生まれたのは1960年代。 この時代、母親が一人で息子を抱えて育てるのは大変だったと思われる。 ただ、それ以前の戦時の動乱期、終戦直後の混乱期、そして激動の経済成長期の時代を生きざるを得なかった母親らからすれば、まだまだ楽な方だっただろう。 21世紀の現在でも、戦乱で祖国を追われ、子供を抱えながら命辛々逃れる母親だっている。 その意味では、「普通の母親」を描いているだけ。 著者からすれば、書かずにはいられない、唯一無二の存在であるのは痛い程理解出来る。が、読む方からすれば、「自分の母親も大体似た様なもんだよ」という事になってしまう。 本書は、500ページの前半を、著者が母親の元で育ち、地元を離れて東京で暮らすようになる経緯を、母親とのエピソードを交えて描いている。 散発的な、オチの無いエピソードが殆ど。 子供時代の記録は、古きよき昭和を描いていて興味深い。雰囲気からして終戦直後かと思わせるが、実際には1970年代初期頃の出来事なので、同じ日本でも首都圏と九州では経済成長にかなりの差があった事を窺わせる。 が、著者が中学生になると、学校でのエピソードがメインになり、退屈になっていく。 著者からすればおもしろおかしな体験なんだろうけど。 著者本人も、作中で度々登場するオトンも、まともそうな人物でないのも、読む側のテンションを下げる。中途半端なワルの中途半端な武勇伝が続くだけ。 癌を患った母親を東京に呼び寄せて同居する後半辺りから、漸く再始動する感じ。 ただ、母親との係わり合いを描く事に焦点を当てているので、著者本人の私生活についてはあまり触れられていない。そんな事もあり、大学を何とか卒業しながらも仕事に有りつけず、その日をどうにか食いつないでいる生活をしていた筈の著者が、いつの間にか様々な仕事を手掛けていて(仕事の内容は明らかにされない)、芸能界との繋がりも出来ていて、自身の事務所を構えるまでに成長している展開は唐突に感じた。 仕事の内容や、その苦労等も一緒に描いていれば、著者の人物像にも納得がいく(九州の田舎から大都会にやって来た若者が、仕事でもまれていく内に自己中心的な人物になっていく)。が、そうした要素が全て排除されているので、単に嫌味な男のマザコン日記になってしまっている。 ごく普通の人生を描いただけの記録が本として出版され、それが「感動作」として取り扱われる日本は、とにかく平和である。東京タワー オカンとボクと、時々、オトン価格:810円(税込、送料別)
2015.07.27
コメント(0)
-

聖者の異端書/内田響子著
C★NOVELS大賞特別賞受賞作。 異端書として礼拝堂に封印されていた手稿、という形で、「名も無き姫」の冒険を描く。粗筋: 遥か彼方の遠い昔。 ファルゴという小国の姫である「わたし」は、近隣の小国アイルトンの王子パジルファルと結婚する事に。 が、結婚式の真っ只中、式場に雷が落ち、「わたし」は気を失う。 目を覚ますと、パジルファルは死んだと伝えられる。納得がいかない「わたし」は、パジルファルの遺体がある棺の中を確認する。空だった。この事について、父親である王に問いただす。パジルファルは「わたし」と二人きりでいた所、落雷があって、姿が消え失せていたという。「王子が魔術で消えたらしい」となっては内外で宗教を絡めた大問題に発展するので、単に「死んだ」という事にしたのだという。 納得がいかない「わたし」は、真相を知りたいが故に、幼馴染の見習い坊主イーサンを伴って、旅を始める。 まず母方の祖父を訪ねる。祖父から、北の大国マドックにいるとされる魔法使いセラフなら何か知っているのでは、と教えられる。「わたし」とイーサンはマドックへと向かい、そこの王子マンフレートと出会う。 三人は、魔法使いセラフと接触。 セラフは、パジルファルについての真相は知っていると言いつつも、直接教える事は出来ない、という。真相は、ファルゴ・アイルトン・マドック等の小国を束ねる大帝国に伝わる御伽噺の中にある、とだけ伝える。また、マンフレートに対しては、王位継承の試練として、「わたし」の供をして目的を探すよう伝える。 こうして、三人一緒で旅を続ける事に。 御伽噺に関する書物を調べている内に、帝国そのものの歴史を辿る事になる。 帝国を統括していた筈の皇帝は、現在は異民族の地へと亡命していた。配下の諸侯の反乱から逃亡した、という。「わたし」は、この皇帝が何らかの理由でパジルファルをさらったのでは、と判断し、イーサンとマンフレートと共に異民族の地へと向かう。 いくつかの試練を経て、「わたし」は皇帝の居城へ辿り着き、皇帝と接触。 亡命した皇帝は、十数年前、「わたし」の母親との結婚を切望していた。そうすれば帝国の崩壊を食い止められる、と信じていたのである。が、「わたし」の母親は、皇帝ではなく、配下の小国ファルゴの王を選んだ。その結果、皇帝は諸侯の反乱を抑え切れず、亡命を余儀無くされる。 が、皇帝は諦めた訳ではなかった。亡命中の十数年間で魔力を蓄え、「わたし」の母親をさらう事に。しかし、「わたし」の母親は、既に亡くなっていた。そこで、その血を継ぐ「わたし」を結婚式でさらおうとしたのだが、手違いで同じ場所にいたパジルファルをさらってしまったのである。「わたし」は、復活を目論む皇帝と、皇帝の実子でありながら皇帝を恨む子息との戦いに巻き込まれるが、それを乗り越え、パジルファルを取り返し、イーサンとマンフレートと共に帰還する。 後年、教皇にまで上り詰めたイーサンに、「わたし」からの手稿が届く。既に故人となっていた「わたし」の手稿では、今回の冒険により、神の存在を疑う行為を行っていた事が明らかにされる。 イーサンは、「わたし」の遺書でもある手稿を、「異端書」とし、聖者でもある教皇の権限で封印する。解説: RPGのノベライズを読まされた気分。 RPGは、プレーヤーがある程度物語の成り行きを変えられる。が、本作は小説なので、著者が示す通りにしか物語は進まない。展開に納得がいかなくても、その通りに進むしかないのである。 本作の大部分は、主人公である「わたし」の一人称で描かれている。 そんな訳で、魔法や魔術が当たり前の世界にも拘わらずやけに「現実的」な思考を持つ「わたし」の主観や世界観が随所に盛り込まれている。物語は淡々としていて、しかも進行のペースが非常に遅い。 ストーリーも、様々な人物と会っては真相について問いただすものの、「私の口からは教えられない。でもヒントは与えよう。後は自分で考えろ」といった禅問答ではぐらされ、たらい回しにされるだけの展開がひたすら続く。核心に迫っていかない。 その割にはラストに差し掛かると「真相」がバタバタと明らかにされ、エピローグへとなだれ込む。 婿の魔術めいた失踪の真相は早期に明らかにされるが、実はより大きな陰謀のほんの入り口に過ぎず、真相がまた新たな謎を生み、「わたし」一行は冒険を続ける……、というスピーディーな展開を期待していたこちらとしては、中ダレ感が否めなかった。 結局、婿の魔術めいた失踪が最後まで最大の謎で、読み手は主人公が同じ質問を何度も問いただし、禅問答で返されるのを見守るだけ(しまいには「わたし」までもが禅問答を繰り広げる)。 賢者か魔法使いか何か分からないが、「わたし」と接触する数々の登場人物の内誰か一人が「実はこうでした」と単純に教えてやればよかったのに、と思う。 最後の最後で、婿の魔術めいた失踪の真相が明らかにされ、「わたし」が冒険中に接触した登場人物の多数が陰謀に関わっている事が明らかにされる(だからこそ尚更「わたし」に真相をさっさと教えてやればよかったのに、と思ってしまう)。 が、その時点では、読み手のこちらは最早興味を失っていて(さっさと読み終えたいだけになる)、「あ、そうでしたか」くらいの感想しか思い浮かばなかった。 一人称なので、主人公である「わたし」についてはくどい程描かれているが、それ以外の登場人物の描写は薄い。 無駄な登場人物も多く、名前(片仮名ばかり)を追うだけでも一苦労になり、中ダレ感を後押しする。 ヒーロー役である筈のマンフレートも、結局何の為に登場していたのかが分からない。彼がいなくても物語は充分成立していただろう。 物語のメインとなる『「わたし」の手稿』そのものが、教皇となったイーサンによる『覚書』の形態をとったエピローグで、一つのトリックになっているのが何となく明らかにされる。 が、そのトリックを楽しむ為だけに長々として抑揚の無い手稿を読む事を強要されても、と思ってしまう。 調理のしようによっては物凄い物語になっていたと思われるのに、様々な事情(著者の力量、賞を開催した出版社の事情)により、本書を手に取った段階で抱く期待より遥かに小さくまとまってしまった小説。 それでも中ダレするのだから驚き。【楽天ブックスならいつでも送料無料】聖者の異端書 [ 内田響子 ]価格:972円(税込、送料込)
2015.07.15
コメント(0)
-

彼女の嫌いな彼女/唯川恵著
直木賞作家唯川恵による恋愛小説。粗筋: 総合燃料会社のM物産。 ガソリンを手掛ける第一販売部と、プロパンを手掛ける第二販売部があった。 どちらかというと第一販売部が花形部署で、第二販売部は日陰的な存在だった。 35歳の瑞子と、23歳の千絵は、第二販売部で勤務するOL。先輩・後輩の関係だが、表立ってではないものの反目し合っていた。 そんな中、アメリカ帰りの沢木が、第二販売部に配属される。日陰部署への配属には勿体無いエリートの登場に、第二販売部のOLらは色めき立つ。瑞子と千絵も、沢木を狙って画策する。 M物産では、第一販売部は早坂部長が率いていて、第二販売部は須崎部長が率いていた。二人は、近々行われる重役選で、重役のポストを巡って競っていた。が、順調に行けば、重役のポストを得るのは第一販売部の早坂部長だった。 そこで、須崎部長は、起死回生を図る。ガソリン車に替わる、エタノール車の普及である。これで第二販売部が花形部署に躍り出れば、重役のポストも夢ではなかった。第一販売部に知られてはまずいので、ごく少数で計画を進める。 瑞子は、須崎部長直々の指名により、エタノール車計画を補佐する事に。彼女は、沢木を狙うのと同時に、仕事も精力的にこなさなければならなくなる。 千絵は、猛アタックの末、沢木と付き合うようになる。これにより、彼女はそれまで付き合っていた俳優志望のヒモ男と別れようと考えるようになる。 沢木を後輩にさらわれた形になった瑞子だが、仕事で沢木と付き合っている内に、プライベートでも付き合うようになる。実は、彼女は、妻子持ちでM物産の総務部に所属する史郎と不倫関係にあった。が、この関係も限界に近付いていたので、沢木との付き合いをきっかけに別れる事を考え始める。 一方、第二販売部は危機的状況に陥っていた。エタノール車に興味を持った取引先との契約が、締結直前に次々と破談になったのだ。第一販売部が、取引先に対しガソリンをより有利な条件で売る話を持ち掛け、エタノール車導入を断念させていたのだ。取引先は、極秘に選択し、交渉を進めていた筈なのに、何故か第一販売部に筒抜けになっている。第二販売部に、内通者がいるらしい。 瑞子は、第二販売部の様子からして、沢木が内通者である事に気付く。沢木が彼女に接近したのは、彼女が持つ情報を盗み見る為だったのだ。が、確証は無いので、誰にも打ち明けられず、一人で抱え込む羽目になる。 千絵は、先輩に沢木を奪われたのではと悩み始めていた。何故沢木みたいなエリートが年増の先輩なんかに近付くのだと探りを入れていると、沢木についてある事実を知る。 沢木は別の女性と婚約していた。その女性とは、早坂部長の娘だった。何故第二販売部所属の者が、第一販売部部長の娘と婚約しているのだ、と不思議に思う。その時点で、沢木が早坂部長によって送り込まれたスパイで、千絵は単に自分が遊ばれていた事に気付く。 千絵は、嫌っていた先輩の瑞子の元を訪れ、沢木と早坂部長の関係について打ち明ける。 瑞子にとって、千絵がもたらした情報は驚きの内容ではなかったが、求めていた確証となった。 瑞子と千絵は協力して、沢木を陥れる事にする。 沢木に偽情報を掴ませ、それを元に動いた第一販売部に大打撃を与えたのだ。 沢木は左遷され、早坂部長の重役就任の野望は崩れる。 が、それによりM物産そのものが損害を被る。 責任を感じた瑞子は、自ら退社する事を決意。史郎との関係も清算する。そんな彼女を哀れに思った史郎は、次の就職先を紹介する。 千絵は、ヒモ男も沢木と比べればまだマシ、と思うようになり、関係修復へと動く。解説はこちら【楽天ブックスならいつでも送料無料】彼女の嫌いな彼女 [ 唯川恵 ]価格:555円(税込、送料込)
2015.07.07
コメント(0)
-

彼女の嫌いな彼女/唯川恵著:解説
直木賞作家唯川恵による恋愛小説。解説: 薄い恋愛ドラマのノベライズ、といった感じ。 実際に、テレビドラマ化されたらしい。 男性社員を主人公とし、男性視点で描いていれば、重厚な企業小説に成り得たかも知れない。が、女性社員を主人公とし、女性視点で描いているので、結局は薄っぺらの恋愛ドラマに成り下がっている。 大企業で勤務した経歴の無い女性作家なので、仕方ないと言えば仕方ないのだが。 舞台となるM物産(会社名を省略してイニシャルで済ませている点からも、著者の真剣度が分かる)は、どうやって存在し続けているんだろう、と不思議に思ってしまう程のポンコツ会社。管理職からOLに至る社員までもがポンコツ。 そもそも、同じ会社の販売部二部門が、互いの足を引っ張り合うどころか、妨害工作に出る、という展開自体異常。販売部同士の不毛な争いで、M物産は未来の自動車産業分野に進出し、事業を拡大するきっかけを失った。一部門(正確には、一部門の長)のエゴで、会社全体の利益を損ねてどうするのか。そんな状況で「有利」を保ったところで他社にやられるだけになるだろうに。 何故第一販売部の早坂部長が、第二販売部に対し露骨に妨害対策に打って出たのかが不明。 第一販売部は花形部署とされ、真面目に勤め上げていれば、重役になるのはほぼ確実だった。にも拘わらずつまらない工作に打って出た為、重役の椅子をふいにした上、会社に損害を与えた。下手すると、経営不振に陥る可能性も。そんな会社の重役になったところで、甘い汁が吸えるとでも思っているのか。 今回の件か、株主の耳に入ったらどうなるのか。経営責任を問われかねない。 第二販売部の須崎部長も、相当無能。 ライバル視する早坂部長よりも先に重役のポストに就きたい、という考えが先走りし過ぎ。早坂部長をとにかく出し抜きたいが故に、社運を賭けるべく大プロジェクトを極秘に進めてしまい(手柄を独り占めにする為)、ライバルに妨害されてしまう。もし須崎部長がエタノール車計画を社内で大々的に発表し、進めていれば、早坂部長も妨害工作には出られなかっただろう。エタノール車計画を成功に導き、第二販売部を花形部署に昇格させ、早坂部長には遅れを取るものの「やり手」として重役のポストに就いた方が、長期的に見れば社内での影響力を高められる、と考えられなかったのか。 極秘にプロジェクトを進めると言いながら、専門外の瑞子をメンバーに加えたり、経歴不明の男が自身の部署に配属されるのを許す等、詰めが甘い。人を読む眼力が無いとしか言い様が無い。同期をライバル視する暇はあるのに。 本書で描かれているエタノール車計画、というのも、検証してみればおかしい。 ガソリン車に替わる次世代自動車なのだから、中堅燃料会社のM物産1社だけで進められる事業では無い。 国家レベルのプロジェクトになるだろう。 複数の企業(M物産より規模の大きな企業)が絡む筈で、中堅会社の一部門の工作で全てが失敗する、といった流れになるとは思えないし、それ以前に失敗させよう、という発想すら生まれない筈。 著者が、ちょっと齧った未来技術の情報を、その重大性を理解しないまま執筆中の小説に盛り込んだだけの感じ。そんな事もあり、「エタノール車」といった言葉は作中に何度も登場するが、詳細は描かれていない。本当にそんな事業を進めていたのかね、と疑ってしまう。「エタノール車」は単なる社内暗号で、実際にはもっと小規模(中堅会社1社だけでも進められる)なプロジェクトだったのかも知れない。 本書の主人公は、35歳のお局OL瑞子と、23歳の腰掛OL千絵。 いずれも共感に値しない盆暗女。 瑞子は適齢期を逃した事を、同じ会社の男性と不倫する事で紛らわせているとんでもない尻軽女。 千絵は、ヒモ男の言いなりになっている事実、そして会社では後輩が続々入社してきている為以前程チヤホヤされなくなっている事を人生の最大の悩みとする阿婆擦れ。 いずれも世界で悩みを抱えているのは自分らだけで、他を自分より格下だと見下している。 そんな中、沢木という、ちょっと格好いいエリートっぽい男が配属されただけで、色めき立つ。経歴や背景等全く知らないにも拘わらず、である。 瑞子も千絵も、大して無い魅力を前面に押し出して、沢木と親交を深める。 沢木が実はライバル部署からの回し者で、二人を利用していただけで、しかも別に婚約者がいた、という事実を知って、二人とも怒り狂い、共謀して彼を陥れる。 瑞子は自身は別の男と不倫していて、千絵も別の男(ヒモ)と付き合いながら沢木に接近した事を棚に上げて。 何故二股を掛けていた女が、相手の男に二股(三股)を掛けられていたくらいで怒るのか。 自分勝手も甚だしい。 もう一人の主役である沢木も、作中では「エリート」と連呼されるが、それを全く感じさせない。 ただの欲馬鹿。 彼は、ライバル部署の内情を知る為に送り込まれた筈。 瑞子や千絵の売り込みを受け入れたのも、部署で働くOLなら、内情に詳しいだろう、と判断したから。千絵はただの無能OLで、大した情報は得られなかったが、瑞子は重要な情報を入手出来る立場にいた。 この時点で千絵とは距離を置き、瑞子に集中すべきだったのに、「肉体関係なら年増の瑞子よりまだ若い千絵の方が良い」と言わんばかりに、千絵と瑞子を二股に掛ける。 その結果、千絵は彼には別の婚約者がいる事を知り、怒って本来は反目し合っていた瑞子と手を結んで彼を陥れる。 何故部長の娘という婚約者がいながら、盆暗OLと肉体関係を持つ事に固執したのか、全く分からない。 婚約者の存在と、スパイ目的で第二販売部に配属された事が千絵にばれた時の対応も、理解出来ない。 沢木は、千絵に対し、自分に婚約者がいる事、スパイ目的で第二販売部に配属されたのは全て事実だと認めた上で、お前みたいな盆暗OLがそれを知ってどうなる、と開き直るのである。自分には早坂部長という後ろ盾がいるので、千絵が二股を掛けられたと騒いだところで全て千絵の言い掛かりだと突っ撥ねられる。重役選は間近に迫っているので、第二販売部が動こうにも手遅れ。早坂部長の勝利は確実で、自分のスパイ行為が公になっても、その頃には海外部署に栄転しているので問題ない、と。 千絵は何の手も打てないだろう、瑞子は自分が早坂部長からの回し者である事に気付いていないだろう、と心底から信じていた様である。 だからこそ千絵と瑞子が仕掛けた策略にコロッと填まり、破滅する。 何故早坂部長はこんな欲馬鹿に自身の娘と婚約させ、ライバル部署へスパイとして送り込んだのか。人選を誤った為、重役の椅子をふいにし、自身の会社に損害を与え、自身の花形部署の地位も危うくしてしまった。 本作の登場人物で、得したのは誰か。 瑞子は、退社を余儀無くされる。 千絵は、ヒモ男と寄りを戻す羽目になる。 沢木は左遷。 早坂部長と須崎部長はいずれも念願の重役のポストをふいにする。 誰も得していない。 ……と思っていたら、一人いた。 瑞子の浮気相手の史郎。 彼は、そろそろ手を切るべきだと考えていた瑞子と、手を切る事に成功。彼から別れを切り出していたら、瑞子に訴えられ、浮気が妻にばれ、大問題に発展していただろう。しかし、瑞子から別れを切り出させている。彼は、身銭を切る事無く、次の就職先を紹介してやるだけで、「良い人」の印象を瑞子に植え付け、浮気関係に終止符を打っているのだ。作中で、史郎は瑞子に対し、沢木は怪しいから気を付けろと忠告しているが、これも瑞子が自ら別れを切り出させる為の布石だったのでは、と思ってしまう。 もしそうだとすると、史郎は早崎部長を遥かに上回る策士、という事になる。 本作は、ストーリー構成が弱い。 ……反目するOL二人。 会社がプロジェクトを立ち上げるのと同時に、登場した時点で怪しいと分かるエリート男が配属される。 OL二人は会社の事情や、自身らのプライベートはそっちのけで、エリート男にぞっこんになるものの、裏切られる。 そこで、OL二人は手を組んで、エリート男を成敗。 めでたしめでたし……。 裏表紙の説明だけで結末が想像出来てしまう、何の捻りも無いストーリー。 流石にそこまで単純なものではないだろう、最後の最後でどんでん返しがあるのでは、と思って最後まで読んでみたが、そんな期待は裏切られた。 こんなのでも小説として成り立つとは驚き。 所詮恋愛小説。 文章に読み辛さは無いが、所々に読んでいてウンザリさせる部分が。 本書は、テレビドラマ化を意識してか、もしくは著者がテレビドラマに感化されたのかは不明だが、OLらが長々と互いについて非難したり反省したりする下りがある。 女性の本音を描く事で、小説に「厚み」を持たせる目論見なのだろうが……。 野郎からすれば、女性の自分勝手な退屈な主張(愚痴)を延々と聞かされている気分。 共感出来る部分が無い。 本書は、あくまでも「女性の、女性による、女性の為だけの小説」と言える。 この程度に共感出来る女性という連中は、本人らが思っている程賢くは無い。あらすじはこちら【楽天ブックスならいつでも送料無料】彼女の嫌いな彼女 [ 唯川恵 ]価格:555円(税込、送料込)
2015.07.07
コメント(0)
-

十八の夏/光原百合著
広島県出身女性作家光原百合による中短編集。 本書に収録されたタイトル作「十八の夏」は、日本推理作家協会賞(短編部門)を受賞している。粗筋:「十八の夏」 高校を卒業し、大学を受験すべきか悩んでいた信也は、自宅の側の土手で、絵を描いている女性を見掛ける。何となく気になり、声を掛けると、その女性は紅美子というフリーのデザイナーだった。近くのアパートに住んでいるが、気晴らしに外に出て絵を描くのだという。 紅美子に興味を持った信也は、家族に対し「勉強に集中出来る環境が欲しい」と言い訳をして、久美子と同じアパートに住み始め、親交を深める。 信也と紅美子は、互いを知るのと同時に反発もする様にもなるが、信也は何故か彼女から離れる事が出来ない。 そんなある日、紅美子は信也に睡眠薬を飲ませ、眠らせる。信也が目を覚ますと、紅美子の姿は無かった。 実は紅美子は、信也の父親の浮気相手と疑われていた女性だった。信也の姉が、父がこの女の為に金を使い込んでいる、と言い張るのだ。信也は姉の言葉を信じていなかったが、ある日自宅近くの土手で彼女を見掛けて、偶然を装って近付く事にしたのだった。 信也の父親は、紅美子とは仕事上付き合っているだけで、浮気はしていなかった。金を使い込んでいたのは事実だが、仕事の関係で使い込んでいたのが判明。紅美子は信也の父親に好意を一方的に抱いていた。だからこそ、信也の自宅の側のアパートに移り住んだのだ。 紅美子は、好意を抱く男の息子である信也を眠らせて危害を加える事は考えていたものの、彼との付き合いで気分が吹っ切れ、彼の前から完全に姿を消す。「ささやかな奇跡」「僕」は、八歳の子供を抱える書店の主任。5年前に妻を亡くし、男手一人で息子を育てていた。 そんな中、明日香という、同じく書店で働く女性と出会う。 紆余曲折の末、彼女と付き合うようになり、息子の同意も得て、プロポーズするに至る。「兄貴の純情」「オレ」は、役者志望の兄を持つ中学生。教師の一人が前島先生だった。 前島先生には、病死した前妻との間に生まれた芽久美という娘がいた。現在は、元教え子だった美枝子という女性と再婚していた。 兄は、どういう訳か前島一家に興味を持つようになり、挙句の果てに役者の夢を捨て、安定した職に就き、美枝子にプロポーズする、と言い出す。「オレ」は前島一家の経緯を知っていたが、兄は知らなかった。前島先生と美枝子の関係を夫と後妻ではなく父と娘、美枝子と芽久美の関係を義母と義娘ではなく歳の離れた姉妹だと勘違いし、美枝子は独身だと早合点した事から今回の騒動に発展した。「オレ」が兄の誤解を解くと、兄は美枝子を諦め、また役者への道を歩み出す。「イノセント・デイズ」 浩介は、学習塾を営む一家の一員。彼自身、塾講師として勤務していた。 そんなある日、塾生だった相田史香と再会する。 史香は、浩介から見て、まだ若いにも拘わらず不運な人生を歩んでいた。父親が事故死し、母親は旧友の浜岡氏と再婚する。浜岡氏も妻を最近亡くしていて、一人息子の崇と二人暮らしだった。史香は崇を慕っていた。四人で新たな家族として人生を再スタートする筈だったが、間も無く食中毒で母親と浜岡氏は死亡してしまう。史香と崇は、それぞれ親戚に引き取られ、塾を辞める羽目になったのである。 史香は、最近崇がオートバイで事故を起こして死亡した事を、浩介に伝えた。 悲劇にも程がある、と浩介はその時点では思っていた。 が、史香の父親が死亡した経緯、浜岡氏の妻が死亡した経緯、そして史香の母親と浜岡氏が食中毒で死亡した経緯について知る内に、驚愕の真相に辿り着く。 史香の母親と、浜岡氏は学生時代から交際していて、ゆくゆくは結婚すると思われていたが、両家の事情により許されず、それぞれ別の者と結婚し、家族を築く。しかし、二人の愛情は冷めた訳ではなかった。寧ろ維持されたままだった。二人は、経済的に安定してきて、両家から邪魔されなくなった段階で、史香の母親は夫を、浜岡氏は妻を死に追いやる。それぞれ伴侶を処分した二人は、晴れて再婚したのだった。 何十年も掛けて実行に移し、成功した筈の「完全犯罪」だったが、誤算があった。 娘の史香からすれば、実の母親の身勝手さによって父親を殺された形になったからだ。同時に、浜岡氏の息子の崇からすれば、母親を実の父親に殺された事になる。 史香と崇は結託し、食中毒を装って、二人を殺害するに至る。 娘と息子が、親を葬るという、「完全犯罪」をやってのけたのだ。 が、この件を境に優等生の筈だった崇は荒れる様になり、最終的にはオートバイで事故を起こして死亡。 全てを失った史香は、自ら命を絶つ事を決める。 浩介は、それを必死の思いで阻止する。解説: 本書に収録されたタイトル作「十八の夏」が日本推理作家協会賞を受賞しているくらいだから、世間では「光原百合は推理小説作家」として認識されているらしいが……。 それが本人の希望だったのかね、と本書を読み通した限りでは思う。 デビューのきっかけとなる小説に、偶々推理小説っぽい要素が含まれていた為、出版社が「これは推理小説だ! 貴方は推理小説作家だ!」と勝手に祭り上げてしまい、現在に至っている感じがする(一般的には、大衆小説より推理小説の方が売り易いとされる)。 著者本人は、小説家にこそなりたかったが、推理小説には特段の思い入れは無いので、「推理小説だ! 推理小説家だ!」として売り込まれている事に戸惑いを感じながら、小説を発表している、という印象を受ける。 本書には4篇収録されているが、推理小説と呼べるものは最後の「イノセント・デイズ」だけで、他の3篇はただの大衆小説。日本推理作家協会賞を受賞したタイトル作も、推理小説の色は薄く、「日本推理作家協会賞受賞作」の文句に釣られて期待して読むと、肩透かしを食らった気分になる。「十八の夏」のポイントは、信也は自宅近くの土手で紅美子と初めて出会ったという風に物語はスタートしたものの、実はそれ以前から彼女を知っていた、という事。紅美子の一般的とは言い難い苗字を難なく読めた事が、彼女を以前から知っていたのを暗示している。 物語は、信也と紅美子が出会って奇妙な付き合いを進める模様、そして信也と父親のやり取りが延々と描かれるだけで、間延び感がある。 ラストに差し掛かった段階で、睡眠薬で眠らされていた信也は目を覚まし、紅美子が姿を消したのに気付く。その時点で「信也の姉は、父親が紅美子という女性と浮気していると疑っていた」「信也は久美子をかなり前から知っていた」「実は信也の父親は紅美子と浮気なんてしていなかった」「『浮気』は、紅美子の一方的な感情だった」という事実が次々と明らかにされ、物語は終わる。 本来は信也と紅美子の付き合い(そして別れ)を描くだけのつもりだったが、出版社に「これだと推理小説にならない。貴方、推理小説作家でしょ? 推理小説っぽく直してほしい」と要望され、急ごしらえで浮気部分を追加したかの様。 それくらいストーリー構成に不自然さを感じる。「ささやかな奇跡」は、完全に推理小説では無い。 あくまでも妻を失った男性が、悲しみを乗り越え、別の女性に好意を抱き、勇気を振り絞って交際を申し込み、再婚を決意するまでの経緯を描いているだけ。 男性の息子が相手の女性について「便所の臭いがする」と否定的と聞こえる意見を述べるが、それは彼女が使う香水が、家のトイレの芳香剤と似た香りがしたから発した言葉で、彼女を否定した訳ではなく、寧ろ再婚する事を望んでいた、という下りが「推理小説」の演出らしい。 が、その下りは100ページ近くにもなる中篇の中で埋もれてしまっていて、トリックにもどんでん返しにもなっていない。 全体的に単調で、読み進むのが辛い一遍。「兄貴の純情」は、夫・後妻・子の家族構成が、父・長女・次女と勘違いされてしまう、というのが最大のトリックと言える。 調理法によっては、物凄い「推理小説」に成り得たのだが……。 主人公とその兄の青春物語として小さくまとまっているので、折角のトリックもインパクトが薄い。 役者志望の兄に主人公が振り回されるだけの人情劇として描き、その様に売りに出されていた方が、素直に楽しめた様な。 本作も、例の出版社により「推理小説っぽく直してほしい」と要望され、急ごしらえでプロポーズのエピソードを追加したかの様。「イノセント・デイズ」は、本書で唯一推理小説っぽい作品で、トーンも暗い。 元塾生の悲劇の人生は、実は元塾生自身が仕組んだ事件だった事を、塾講師が暴いていく……。 ……というストーリー展開にすれば、シンプルでインパクトあるものに仕上がっていたのに、塾講師本人の夫婦関係の模様を描き、人情ドラマの要素を加えた結果(この部分がやけに長い)、2時間サスペンスドラマのノベライズみたいになってしまった。 女性作家となると、どうしてもこういう展開になってしまうらしい。 本書に収録された最初の3篇は、いずれも単なる人情ドラマとして書かれ、発表されていたら、読む側もそれを念頭に読むので、それなりに楽しめるものになっていたと思われる。が、変に「推理小説」として書き直された結果、それを期待して読む側からすれば物足りないものに。 ラストの1篇になって漸く推理小説っぽいものに行き当たるが、これも人情ドラマ部分が邪魔をして純粋な推理小説として楽しめない。「推理小説作家」の看板を下ろし、大衆小説作家として活動した方が、良いのではと思う。 著者本人がそれを希望しても、出版社がそれを許さないのか。
2015.07.06
コメント(0)
-

Twelve Y.O./福井晴敏著
福井晴敏のデビュー作。 第44回江戸川乱歩賞受賞作品。粗筋: 米国海兵隊が突如沖縄から撤退する、と宣言。 日米共に混乱に陥る。 ……と思われていたのだが……。 平は、陸上自衛隊でリクルーターの仕事をしていた。以前はヘリ部隊に所属するパイロットだったが、墜落事故をきっかけに精神上の問題で操縦桿を握れなくなってしまい、リクルーターの仕事へと飛ばされたのだった。 ある日、平は、元自衛官の東馬と再会。平と東馬は、防衛省が編成を試みていた自衛隊版海兵隊のメンバーだった。が、平がそこでの訓練中に起こった墜落事故で入院している間に自衛隊版海兵隊は解体されてしまい、東馬とも連絡が取れなくなっていたのだ。 平は、その時点では東馬との再開に特に疑念を持たず、そのまま別れた。 それから間も無く、平は何者かに拉致される。 拉致したのは、同業者である筈の自衛隊に属するスパイ機関だった。そこで、機関に属する由梨という女性と会う。 由梨は、米海兵隊が沖縄から撤退したのは、東馬の仕業だと説明。コンピュータウィルス攻撃で在日米軍施設を無力化し、米軍が撤退せざるを得ない状況を作り出したのだ、と。 それだったら東馬をさっさと拘束しろと平は疑問に思うが、状況はそう簡単なものではなかった。東馬にコンピュータウィルスを持たせたのは、日本の軍国化を狙う防衛省の一派だという。また、東馬は米国政府そのものを揺るがす情報を握っていた。東馬は、日本側も、米国側も、自分に迂闊に手を出せない状況を作り出した上で、テロリスト「トゥエルブ」として、コンピュータウィルスによるテロを繰り広げていたのだ。 東馬の行動は防衛省によって監視されていた。これまで誰とも特に接触していなかったが、ふとした所である人物と接触。それが平だった。東馬の手にあるコンピュータウィルスの回収を任務としていた由梨は、平を人質にすれば東馬が何らかの行動を起こすのでは、と期待した。 東馬は、その期待に応えるかのように、平を奪還する計画を実行。実働部隊の先頭に立っていたのが、東馬の「娘」とされる少女の理沙だった。理沙は、その見掛けからは想像出来ない戦闘能力を発揮し、平を奪還。東馬の元に連れて行く。 平は、自分の意思に反してあちこちに連れて行かれるのを、許すしかなかった。 東馬と再会した平は、彼や、日本側や、米国側が何を企んでいるのか、どういった思惑で動いているのか、と問いただすが、明確な返事は得られない。東馬が日本の欠陥だらけの防衛政策や、それを許す日本政府、更にその状況を受け入れている日本国そのものに対し不満を持っていた。その上米国政府にも嫌悪感を抱いており、たった一人で日米双方を相手に戦いを挑んでいたのだ。 東馬の生い立ちも明らかになっていく。 東馬は、実は後に米国大統領にまで上り詰めた情報局員と、日本人女性との間に生まれた子だった。大統領に混血の隠し子がいて、しかもその隠し子にスパイ活動させていた、というのは米国にとっては表沙汰に出来ない弱みで、それこそが東馬に迂闊に手を出せない理由だった。 が、流石の米国も業を煮やし、ついに実力行使に打って出る。東馬の隠れ場所を襲撃したのだ。 そのゴタゴタで平は再び自衛隊スパイ機関に拘束される。 一方、東馬は理沙と共に命辛々逃げ出し、最終目的地である沖縄へと向かう。 沖縄では、唯一残っていた米国の特殊部隊が東馬を迎え撃つが、周到に準備していた東馬の奇策により壊滅状態に陥る。 東馬は、沖縄の普天間基地の奥底に隠されていた化学兵器「GUSOH」へと向かう。これを使うと、沖縄は全滅する。日米共に混乱に陥る。これは、日本の軍国化を狙う防衛省の一派にとって、願ってもない事だった。だからこそ東馬を「利用」していたのだ。 そこへ、ヘリを再び操縦出来るようになった平が、ヘリを飛ばして到着。 東馬を阻止するのと同時に、軍国化を狙う防衛省一派の野望も打ち砕く。解説: 日本ではなかなか有り得なかったミリタリーアクション。 血湧き肉躍るサスペンスを期待して本を開いたのだが……。 不完全燃焼のまま最後のページを迎えてしまった。 冒頭から小難しい文章が延々と続く。 それはそれで、ハードなテクノスリラーとしては悪くない。 が、それから間も無く物凄い戦闘能力を持つ美少女戦士理沙や、美人の女性自衛官由梨が登場する。 この時点で、シリアスな筈の小説が、ただのミリタリーオタク向け漫画のノベライゼーションに。 ミリタリーオタク向け漫画のノベライゼーションも、そうと割り切って書かれていれば、読む側としてもそれなりに楽しめる。 しかし、美少女戦士・美人自衛官登場後も文体はテクノスリラー振っており、小難しい軍事用語、そして著者個人の押し付けがましい国家論と防衛論が延々と続く。 ストーリーそのものと、文体のバランスが取れていない。 著者は、自身は物凄くシリアスな内容の小説を書いているのだと信じて疑っていないらしい。が、読む側は「結局ミリタリーオタク向け漫画ノベライゼーションでしょ?」と一歩引いた目で見てしまうのである。 シリアスなアクションが続き、漸くテクノスリラーらしくなってきたかなと思うと、また例の美少女理沙が現れて超人的な戦闘力で敵をバタバタ倒す、美人女性自衛官由梨が登場して男勝りの大活躍をしてみせる、といった場面が挿入され、ミリタリーオタク向け漫画ノベライゼーションへと引き戻してしまう。 それの繰り返し。 作中の米国の描き方も、あくまでも反米思想を持つ(らしい)著者の視点に立ったものに過ぎず、アメリカの実情を正確に捉えたものとは言い難い。アメリカ人寿司職人がカリフォルニアロールを「正統な日本の寿司」と称して出すのと同じ。当の寿司職人は真剣なのかも知れないが、日本人の感覚からするとずれている。本作の「アメリカ」も、アメリカ人の感覚からすれば物凄くずれたものになっている。 そもそも米軍が、日本で作り出されたコンピュータウィルスによる攻撃で完全に不能に陥り、沖縄からの撤退を余儀無くされる、という事態は有り得ない。 サイバー戦争においては、昔も今もアメリカは最先端にあり、日本如きに振り回される程弱くは無い。「技術大国ニッポン」の虚構を未だに信じているのか、と呆れてしまう(本作は発表されてからかなり経っているので、現在だったらこの手のものを書かなかったかも)。 テロリスト「トゥエルブ」である東馬は、米国大統領にまで上り詰めた人物の隠し子だった、というのが本作の鍵の一つとなっていて、この事実は日米関係は勿論、米国政府をも大きく揺るがず、とされているが……。 大統領に隠し子がいた、戦後間も無い日本で駐在中に現地の女性との間に生まれた、しかもかなり後にその隠し子と再会した時、スパイとしてリクルートし、利用した、という事実は、あくまでも大統領個人のスキャンダルに過ぎない。国家元首とはいえ、超大国アメリカが、一個人のスキャンダルを隠蔽したいが為に長期的国家戦略を大転換する、というのは有り得ない。下手に隠すより、事実を全てさらけ出してやり過ごす方が得策だ、と考えるだろう。よくよく考えれば、米軍兵が他国に駐在中に現地の女性と深い関係に陥り、子を作ってしまった、というのは珍しい出来事ではなく、それが大統領であったとしても、国家を揺るがすスキャンダルとして騒がれるか、というと疑問である。 たったこの一つの「事実」により、米国は迂闊に東馬に手を出せない、という設定になっている。が、様々な特殊部隊を有する米国が、サイバーテロ攻撃を慣行した犯人が特定されているにも拘わらず、平が関わりを持つまで何の手も打てなかった、打たなかった、というのは有り得ない。海兵隊を沖縄から撤退させる労力を考えれば、東馬一人をさっさと確保した方が早い、と判断する筈。 日本側も、東馬を利用する側と阻止する側に分かれて戦う、というグダグダ状態。 それに「同盟国」である筈のアメリカが「敵」として加わるから、一層グダグダ。敵味方が裏切りや「予想外の展開!」でガンガン入れ替わるので(東馬も極悪人として描かれてはいない)、最終的にはどうでも良くなってしまっている。 勧善懲悪とまではいかなくても、敵味方はある程度固定し、シンプルに進めてほしい。 これといったサスペンスが無いのも問題。 ……米国を沖縄から追い出したテロリスト。 その正体とは……? こうして、謎のテロリストとそれを追う防衛省の攻防を描くのかと思いきや、テロリストの正体は冒頭で明らかにされてしまう。よく分からない「協定」の為、身元が分かっているにも拘わらず当局は手を出せない(出さない)。テロリストは、美少女戦士の手を借りて、最終目的である沖縄攻撃を実行。 あるテロリストがとんとん拍子で計画を実行する模様(多少の犠牲は払うが)と、それに対しろくな手を打てない政府機関の無能振りが描かれているだけで、「この後どうなるのか?」と期待させる部分が無い。 主人公・準主人公クラスのキャラが無駄に多いのも問題。 悪役の東馬、それに従う美少女戦士理沙、二人を阻止しようと動く平、自身の思惑で東馬を追う美人自衛官の由梨。 美少女戦士と美人自衛官を省いて、東馬と平という男同士の命懸けの戦い、という構図にしていたら、もっと分かり易い、シリアスなものになっていたのに、と思う(ミリタリーオタク向け漫画ノベライゼーションにもなっていなかっただろう)。 何故著者は美少女・美人を挿入する事にこだわったのか(他の著作でも同じ構図になっている)。 本作のタイトルの「Twelve Y.O.(12歳)」は、戦後日本を統治したGHQ司令官マッカーサーが、日本について述べた言葉を基にしている。 日本の精神年齢は12歳で、昔も今も大人になり切れていない、日本は国防や主権について真剣に取り組んで、「大人」へと成長すべきだ、が本作のテーマらしい。 ただ、マッカーサーの「12歳」の発言は、日本における民主主義の成熟度についてそう述べた、というのが一般的な見解で、日本や日本人そのものを「12歳」と貶した訳では無い。戦後のマスコミにより「日本」「12歳」に本来無かった尾頭が付けられて一人歩きし、「日本人の精神年齢は12歳」報道へと繋がったとされる。 著者は、「大人になり切れていない日本」をテーマに様々な小説を発表している様だが……。 シリアスな筈の小説に美少女や美人を当たり前の様に登場させる矛盾からすると、本人も完全に大人になり切れていない感じ。 結局小説家(というか人間全体)なんて皆そうだろうと言ってしまえば、確かにそうななのだが。 本作は、江戸川乱歩賞受賞作品。 江戸川乱歩賞は、国内では最も歴史があり、権威のあるミステリー小説文学賞。 ただ、受賞作そのものは、受賞作であるという事以外はこれといった特色の無いものが殆ど。 本作も、その例から漏れない。
2015.06.12
コメント(0)
-

イン・ザ・プール/奥田英朗著
神経科医伊良部一郎の活躍(?)を描く短編集。 5作から成る。粗筋: 伊良部総合病院の地下に、神経科があり、そこには肥満で薄汚い神経科医伊良部一郎と、スタイル抜群だが無愛想な看護婦のマユミがいる。 ここを訪れる患者は、通常では有り得ない精神疾患を抱えているが、いずれも伊良部一郎の、医師らしからぬ言動に翻弄される。【イン・ザ・プール】 大森は体調不良で、下痢ばかりしていた。総合病院を訪ねると、そこの神経科を訪れるよう、指示される。 神経科医伊良部一郎は、下痢は精神的なもので、根本的な治療法は無い、と言い張る。ストレスが原因と思われるから、運動でもしたらどうだと提案。 大森は、若い頃やっていた水泳をやってみる事に。すると、体調は少しずつだが改善。それをきっかけに、毎日水泳するようになり、一日でも水泳しないと体調を崩す程の「依存症」になってしまう。 公共プールでは、一定時間水泳すると強制的に休憩を取らされる。それに不満を持っていた大森に、伊良部が提案。夜間、公共プールに忍び込めば、監視員がいないので好きなだけ泳げる、と。 公共施設に不法侵入する訳にはいかない、と躊躇する大森に対し、伊良部は無理矢理公共プールのある建物に連れて行く。二人で忍び込もうとするが、失敗。不法侵入未遂で逮捕されるのでは、と大森は恐れながら、伊良部と共にその場から逃げ出す。【勃ちっ放し】 田口は、局部が常に勃っているという、奇妙な症状に悩まされていた。 精神的な病という事で、神経科を訪れた。 神経科医伊良部一郎は、ショック療法を試みたりするが、全く効果は無い。 そこで、大学病院を紹介する。 大学病院で、田口は医師に問題の部分を見せる羽目に。が、そこでも治療は出来ないという。症例の記録として残す為に、田口を呼んだのだった。 これを聞いた田口は、怒り狂って大学の設備を破壊。警察に逮捕され、2日間拘留される。 その間に問題の症状は収まってしまった。【コンパニオン】 広美は、芸能事務所に所属するタレント。といっても、売れてはおらず、コンパニオンが主な仕事だった。 彼女は、最近ストーカーに狙われている、と恐れるようになっていた。が、どこの誰にストーカーされているのかは分からず、不眠症に悩まされるように。 ストーカーらしき人物の存在が確認出来ない以上、単なる被害妄想ではないか、と疑う友人の勧めで、神経科を訪れる。 神経科医伊良部一郎は、彼女に対し、ストーカーを幻滅させる行動を取ったら、と提案。 広美は一応そうした行動を取ってみるものの、被害妄想は拡大していき、周りにいる者全てが自分を狙っているのでは、と疑うようになる。 それと同時に、自分はタレントとしての素質があるのに妨害を受けているから成功していない、という妄想にも陥る。 映画会社のオーディションを受けるが、同時にアクションスターのオーディションを受けた伊良部と共に「悪ふざけ」扱いされ、会場から放り出される。 それをきっかけに広美は芸能事務所を首になり、タレントではなくなる。すると、憑き物が落ちたように妄想癖が無くなった。【フレンズ】 雄太は高校生。携帯電話を一時でも手放すと手が震える、という携帯依存症だった。 心配した母親が、彼を神経科に送り込む。 神経科医伊良部一郎は、雄太の症状は「命に別状は無い」と判断。逆に、携帯電話についてあれこれ雄太に問い、携帯電話を購入。取るに取らない内容のメールを、雄太に送信する様になり、雄太をウンザリさせる。 雄太は、携帯電話を通じて様々な人間と交流関係を深めているつもりだったが、いざとなると友人は一人もおらず、一人ぼっちになっていた。 クリスマスの夜、一人でいた雄太はあれ程面倒に思っていた伊良部からの誘いを受ける。【いてもたっても】 義雄は、雑誌のライター。外出の際も何度も家に戻っては煙草の吸殻をきちんと始末したか確認するという、強迫神経症に苛まれる様に。神経科を訪れる。 神経科医伊良部一郎は、煙草の不始末を心配するより、ガス漏れを心配したらどうだ、漏電を心配したらどうだ、と色々入れ知恵する。お陰で、義雄は煙草の不始末は勿論、ガスの元栓や漏電まで心配するようになってしまう。 そんな所、自身が手掛けた記事で取り上げたホームレスが、女子大生に痴漢行為を働いた事を知る。責任を感じた義雄は、姿をくらましたホームレスを探し当てる。すると、ホームレスは実は麻薬の売人であった事が判明。義雄は、ライターとして花開く。 義雄の強迫神経症は改善しなかったが、ライターとして飛躍するきっかけは掴む。解説: 藤子不二雄Ⓐブラックユーモア漫画「笑ゥせぇるすまん」の精神科医バージョンと言えなくもない。 笑ゥせぇるすまんでは、ある者が喪黒福造と関わりを持った事がきっかけで奇妙な体験を経験し、最終的には身を破滅させる、というのが基本パターン。 本作も、様々な精神的な病を抱えた者が神経科医伊良部一郎と関わりを持った事がきっかけで奇妙な体験をし、人生の転換期を迎える、というパターンになっている。 喪黒福造は人間ではなく、超常的な存在だが、本作の伊良部一郎は、あくまでも言動が常識から外れた男に過ぎない。「笑ゥせぇるすまん」では、喪黒福造と関わりを持った登場人物は超常的な力により奈落の底に突き落とされる(場合によっては命を落とす)。本作では、伊良部と関わりを持った登場人物は、伊良部の常識外れの言動(中には犯罪ではないかと思われる行為も)に振り回されるものの、あくまでも人生の転換期を迎えるだけ。見方によってはハッピーエンドになっている場合も。元の精神疾患は結局改善していない事も多いが。 伊良部の言動は一般常識からは外れてはいるものの、重大な罪を犯すまでには至らない(もっと奇怪な言動を見せる人物は、現実世界でもフィクションの世界でもいくらでもいる)。 最初の1篇では精神科医らしからぬ奇妙な言動に驚かされるが、それ以降は慣れてしまう。また、精神疾患を抱える登場人物の運命も、何となく想像出来る様になってしまう。 その結果、どんでん返しは無く、捻りも無く、オチすら無い短編になってしまっている。 ユーモアに満ちた、比較的読み易い文章で、ガンガン読み進められるが、1篇1篇を読み終わっても深い感動や驚きは無く、「そうでしたか」といった感想しか思い浮かべられない。 伊良部は極悪人ではないが、善人でも無い。 小説の登場人物が善人でないと魅力的に見えない、という訳ではない。寧ろ悪人だからこそ面白いと感じる場合がある。が、善人であろうと、悪人であろうと、何か光るものがないと興味を保てない。 このキャラクターにいたっては、光っている部分が無く、通いざるを得ない作中の患者らと同様、読む側も勝手な言動にウンザリしていき、1篇読み終えるごとに興味を失う。 伊良部の元を訪れる患者は、精神的に病んでいる部分はあるが、それ以外は普通の人間。 捻くれた性格の持ち主ばかりで、読んでいる側としては共感し辛く、読み進むのと同時に関心が薄れていく。 伊良部の言動に振り回されても、同情出来ない。一方で、逆に「いい様だ」とほくそ笑む事も無くなってしまう。 伊良部が登場人物らに対し用意していた(と思われる)最終展開を迎えても、「ふうん。そうでしたか」といった感情しか浮かばない。 伊良部という存在に対しても、患者らが抱える悩みに対しても、読み終える頃には興味を失っているので、読後感が物凄く悪くはない一方で、何故時間を割いて読んだのか、という理由も見出せない。 ここまで特徴的なキャラやストーリー設定なのに、強烈な印象は無く、何の感想も思い浮かべられない事が、本作の最大の特徴と言える。 社会や医学に対する新たな知識を得られた、著者の博学振りには舌を巻いた、という実感くらい湧けばそれだけでも「読んだ甲斐があった」と思えるのだが、それすらも無い。「昔読んだ覚えがあるけど、どんな内容だったのかは覚えていないし、特に興味も無い」といった本になりそう。【はじめての方限定!一冊無料クーポンもれなくプレゼント】イン・ザ・プール 【電子書籍】[ ...価格:560円
2015.06.03
コメント(0)
-
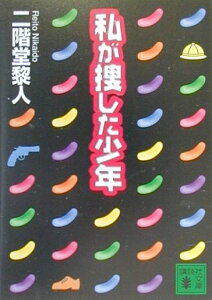
私が捜した少年/二階堂黎人著
二階堂黎人によるハードボイルドのパロディ短編集。 ハードボイルド風に物事を捉える自称私立探偵の幼稚園児・渋柿信介(シンちゃん)が、刑事の父親健一(ケン一)が抱える事件を、元アイドルの母親瑠々子(ルル子)と共に解決へと導く。粗筋:【私が捜した少年】 渋柿刑事は、麻薬売買に携わる暴力団員を追っていた。暴力団員は、愛人の女性が住んでいる女子寮に逃げ込む。 警察は女子寮を監視下に置き、1週間後に逮捕状を得て中に突入。しかし、暴力団員の姿は無かった。 女子寮の隅々まで捜したが、足跡すら発見出来なかった。 シンちゃんは、現場を別件で歩き回っている内に、女子寮では生ゴミをまとめて出している事を掴み、そこから真相に気付く。 逃げ込んだ暴力団員は、愛人によって殺害され、解体され、ゴミ袋に詰められて生ゴミとして出されていたのだ。警察も、まさか追っている容疑者が殺されて解体されているとは想像していなかった。【アリバイのア】 不動産屋が殺害される。最有力容疑者は、不動産屋に管理を委託していた土地を勝手に処分された女性漫画家だった。しかし、彼女にはアリバイがあった。締め切り間際の彼女は自宅で原稿を書いており、家の中には編集者もいたのだ。その編集者は、漫画家が部屋に閉じ篭もっていた時間を、クラシック音楽の楽曲の長さで記憶していた。漫画家に、それを聞いて部屋の外で待ってろ、と命じられたからだ。その楽曲の長さの時間では、仮に漫画家が編集者の目を盗んで自宅から抜け出せたとしても、不動産屋を殺して戻って来るには時間が足りない、という理由でアリバイが成立していていた。 編集者が聞いていたと証言した曲には国内盤と輸入盤があり、ボーナストラックの入っていた輸入盤の方が遥かに長かった。しかし、編集者は短縮バージョンの国内盤を聞かされている、と信じ込まされていた。この時間差を利用して、漫画家は自宅から抜け、不動産屋を殺し、自宅に戻っていたのだ。【キリタンポ村から消えた男】 中堅ヤクザが殺される。被害者は、フィリピン女性を斡旋して国内で働かせる稼業に手を染めていた山下というヤクザと険悪な仲だった。山下が最有力容疑者となるが、山下については「若い」以外に情報が殆どなく、どんな容貌なのかも分からなかった。山下の愛人とされる女性を突き止め、話を聞き、山下の故郷である寒村へ向かう。そこには、山下の父親がいた。山下とは長年会っていない、とその父親は言う。 ケン一とシンちゃんは、諦めて引き上げる所で、東京ナンバーの車がある事に気付く。「山下の父親」と思っていた人物こそ山下本人だった。「若い」というのは、ヤクザ稼業に首を突っ込んでからまだ日が浅かった、という意味で、年齢的に若い、という意味ではなかった。【センチメンタル・ハートブレイク】 シンちゃんは、元アイドル歌手だった母親の伝で、幼児番組に出演する事に。テレビ局を訪れると、そこに勤めるOLの殺人事件に遭遇。OLは、番組プロデューサーの愛人だった。が、その番組プロデューサーには新たな愛人が出来、OLとの関係を清算したがっていたという。警察は、番組プロデューサーを最有力容疑者と見なす。しかし、犯行時刻にはパリへと向かう飛行機で移動している最中で、アリバイがあった。 番組プロデューサーの新しい愛人とは、彼と体格が似ていた男性だった。番組プロデューサーは、自分名義の飛行機チケットを新愛人に渡し、飛行機に乗せた。番組プロデューサーはOLを殺し、別の飛行機に乗って出国。親愛人が乗っていた旅客機は、給油目的で香港の空港に立ち寄っていた。番組プロデューサーは香港の空港で、新愛人が残していた飛行機チケットを回収し、そのままパリに向かい、まるで最初からずっとパリ行きの旅客機で移動していた様に装った。一方、親愛人は、別の飛行機に乗って日本にとんぼ返りしていた。出国・入国では身元確認はそれなりに厳重に行われるが、給油目的で立ち寄った際の空港だと搭乗者が入れ替わってもパスポートと実際の搭乗者との照らし合わせは厳格に行われない、という盲点を突いたのだった。【渋柿とマックスの山】 スキー初心者の女子大生が、ゲレンデで、別の女性と衝突してしまう。衝突した相手は、脳震盪を起こす。その女性の恋人らしき男性は、女性大生に対し、ゲレンデ下の救難小屋に戻って救助隊を呼んでくるよう、要望する。女子大生は言われるまま救難小屋まで下り、救助隊を伴って衝突現場に戻る。すると、衝突した女性は、首を絞められて殺されていた。また、女性の恋人らしき男性の姿は無かった。 現場に偶々居合わせたケン一とシンちゃんは、調査を開始。 殺された女性と、衝突して脳震盪を起こしたとされる女性は、別人だった。殺人の被害者は、衝突前に既に殺されていた。姿をくらました男性とは、実は女子大生らが連れ添ってきた救助隊員の一人だった。犯人は、自身を強請っていた女性を殺害。アリバイ作りの為、死亡時刻をずらす工作を決行。自身の愛人に殺した女性のスキーウェアを着せ、偶々いたスキー初心者の女子大生と衝突させた。犯人は、女子大生らに対し救助小屋へ戻って助けを呼んで来いと命令。パニック状態に遭った女子大生は言われるまま救難小屋へ向かうが、スキーの初心者なので、下山に時間が掛かった。犯人は当然ながらスキーの上級者なので、救難小屋へ先回りする事が出来た。着替えると、救助隊として女子大生を迎え入れ、「救助要請」に基づいて衝突現場に戻り、死体を「発見」したのだった。スキーウェアを着ていると中の人間が入れ替わっても気付かれ難い、同じ人間でもスキーウェアを着替えるとそうと気付かれ難い、という状況を利用したのである。解説はこちら:関連商品:人気blogランキングへ【楽天ブックスならいつでも送料無料】私が捜した少年 [ 二階堂黎人 ]価格:637円(税込、送料込)
2015.06.01
コメント(0)
-
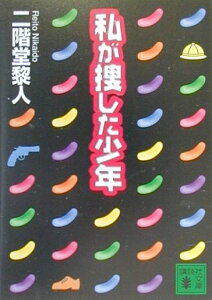
私が捜した少年/二階堂黎人著:解説
二階堂黎人によるハードボイルドのパロディ短編集。 ハードボイルド風に物事を捉える自称私立探偵の幼稚園児・渋柿信介(シンちゃん)が、刑事の父親健一(ケン一)が抱える事件を、元アイドルの母親瑠々子(ルル子)と共に解決へと導く。解説: 本短編集の最大の「トリック」は、渋い口調で一人称を展開する私立探偵は、実は自称「私立探偵」の五歳児、という点にあるらしい。 人気漫画「名探偵コナン」の変則型、といった設定と言える。 この「トリック」も、最初の1篇目の10ページ目で解明されてしまう。そうなると、後は五歳児の「渋い」描写が延々と続くだけで、単に鼻に付くというか、読み辛いだけ。 特異な設定の為、1篇ごとに「渋い声で語っているのは、実は五歳児でした!」という「トリック」が披露される。これらの短編がそれぞれ雑誌に連載されている段階では特に気にならないのだろうが(というか必要不可欠だったのだろう)、こうして短編集として1冊の本にまとめられ、通しで読むと、単にくどいだけ。特に好きでもない芸人のどこが面白いのかさっぱり分からないギャグを繰り返し見せられている気分(好きな芸人で、面白いと思っているギャグでも、不必要に繰り返し見せられたら、飽きる)。 もう少し抑え気味に出来なかったのか。 このお決まりの「トリック」の他、主人公の父親が刑事で、母親が元アイドル、という登場人物の説明(まさにアニメ化か、テレビドラマ化を目論んだかの様なキャラクター設定)も毎回行われるので、なかなかストーリーの核心部分に入っていかない。入ったと思った瞬間、アッという間に「解決篇」に入っていて、終わっている。 登場人物が全て普通だったら、本の厚みは半分以下に収まっていたと思われる。 というか、大半は2分間ミステリ(問題篇5ページ、解答篇1ページ)のクイズレベル。それを気取った描写や現実性に乏しいキャラ設定で50~100ページの中短編に引き伸ばしている。 そんなもんだから、いずれにおいても間延び感があり、退屈してしまう。折角の興味深い謎、そして折角の驚愕の真相も、知らされた所で「はいはい、そうでしたか」くらいの感想しか思い浮かばない。 ガンガン読み進めるのは事実だが、それは読み易い文体だとか、軽く読めてしまう内容だからではなく、単に蛇足的と感じる部分を読み飛ばしてしまうから(後になって重要だと知らされて、とりあえず読み返してみる、という状況に何度か遭遇)。 作中には、様々な芸能人の名が述べられ、自動車の描写があるが……。 本作は、元は1996年に出版されたもの。連載は、それより更に前だと思われる。 名を挙げられている芸能人は、当時は誰もが知っている大スターだったのかも知れないが、今となっては「あの人は今……」で辛うじて取り上げられる輩ばかり。 作中で登場する自動車も、当然ながら古い。 著者は、流行を精一杯調べ上げて、作中で連ねてみせたらしいが、今読むとただただ古さしか感じず、注釈が必要になってしまっている。 流行・最先端は、アッという間に過去のものになってしまう。当然ながら、それを満載したフィクションも僅か数年で古臭くなってしまうのは、悲しいばかりである。 1篇1篇を検証すると、おかしい部分も多い。【私が捜した少年】では、警察が追っていた容疑者は、愛人によって殺され、解体されたという。 愛人は風呂場で男を殺害して解体し、ゴミ袋に詰め、踏み込んできた警察がそれに気付けない程完璧に痕跡を消し去っていたという。同様の行為を何度もやっていたならともかく、完璧過ぎないか。 追っていた容疑者が愛人が住む女子寮に逃げ込んだという情報は掴んでいたのに、警察は女子寮を監視するだけに留め、1週間後に逮捕状を得て漸く踏み込む(その間に容疑者は殺され、解体され、数回に亘って生ゴミと共に処分されていた)、というのはのんびりし過ぎ。監視していた刑事は「容疑者は女子寮から出ていない」と豪語していたらしいが、無理を感じる。【アリバイのア】では、アリバイの決め手となったのは、楽曲の長さだったという。 警察がそんなアリバイを、受け入れるとは思えない。仮に国内盤・輸入盤の違いに気付かなかったとしても、「似たような別の曲を聴いていたのでは」と思うだろうに。 こんな奇妙なアリバイになったのは、容疑者である漫画家が、アリバイを証明してくれる事になる編集者から腕時計を取り上げ、楽曲でしか時間の経過が分からない状況をわざわざ作り出したから。ただ、現在は携帯電話があるので、腕時計を取り上げても時間が分からなくなる、という事態にはならない。腕時計と携帯電話まで取り上げなければならないが、それだと編集者も、警察も不自然に思ってしまうだろう。「小説が発表された当時はまだ携帯電話は広く普及していなかった」という注釈が必要になっている。【キリタンポ村から消えた男】では、ヤクザが使う「若い」という表現が、一般的に使われる「若い」の意味合いとは異なる、というのがメインのトリックとなっている。 ただ、警察が「山下の年齢は?」という初歩的な質問を関係者の誰にも訊かない、というのは有り得ない気がする。もし訊いていたら、警察は早い段階で山下の人物像を掴んでいただろう。 ヤクザを取り締まる警察が、ヤクザが使う表現を全く理解していなかった、というのもおかしい。【センチメンタル・ハートブレイク】では、男性の新たな愛人は男性だった、というのがメインのトリックになっている。「この業界では珍しい事ではない」と作中で示されているが、女性の愛人を何人か抱え、妻もいる男性が、「実は男色でした!」というのは唐突過ぎる。 本作では、旅客機を使ったアリバイトリックも使われている。 トラベルミステリーでありがちだった「列車を乗り継いで、時刻表の盲点を付き、アリバイ工作をする」という展開でさえリアリティに乏しいのに、旅客機となると、よりリアリティに乏しい。 旅客機は分刻みで離着陸出来る代物ではない。必ず遅れが生じるし、天候にも左右され易い。欠航も頻繁にある。フライトスケジュールの盲点を突いてアリバイ工作しました、と説明されても「所詮フィクションでの出来事だからね」と思ってしまう。【渋柿とマックスの山】では、犯人は偶々現場にいた女子大生をアリバイ工作に利用している。犯人はスキーの上級者だったので、初心者だった女子大生より先に下まで降りられた、との事だったが……。 そこまで上手い具合に初心者を見付けられるとは思えないし、先回りしようとしている段階で別の人に目撃されてしまう可能性も高かったと思うが。 衝突現場に居合わせた男性と、下の救難小屋にいた救助隊員を、スキーウェアを着替えただけで「別人だ」と勘違いしてくれるだろう、と期待するのも危険過ぎるし。犯人が自身が思っている以上に特徴的であったり、もしくは女子大生が予想以上に冷静で観察力があったりして、「あれ? さっきお会いしませんでしたか?」といった展開になってしまったら、どうするつもりだったのが。 何故死体を隠しもせず、手の込んだ形で「発見」させ、事件とした理由も分かり辛い。粗筋はこちら:関連商品:人気blogランキングへ【楽天ブックスならいつでも送料無料】私が捜した少年 [ 二階堂黎人 ]価格:637円(税込、送料込)
2015.06.01
コメント(0)
-

世界の自動車オールアルバム 2015年
43カ国にある247の自動車ブランドを、写真入で解説。 日本に輸入されていない自動車ブランドも取り上げているのが最大の特徴。 日本は「自動車王国」と自称しているが、本書を読む限りでは、自動車ブランドを抱える多くの国々も同様に「自動車王国」を自称しているのが分かる。 少なくとも、規制塗れでろくな自動車メーカーしかいない日本より、新興メーカーが続々誕生する土壌のある国の方が、「自動車王国」を名乗るに相応しいような。 ただ、海外も、一昔前と比べると大手・新興メーカーに関係無く小粒になりつつある。国際的な規制の表れか。 本書は、元は海外の雑誌を翻訳したものらしく、一部の解説は欧米寄りの視点(ドイツのメーカーに特にその傾向が)が入っている。日本メーカーの解説も、日本人からすると首を捻ってしまう見解や表現になっている部分が散見する。【楽天ブックスならいつでも送料無料】世界の自動車オールアルバム(2015年)価格:1,880円(税込、送料込)
2015.05.26
コメント(0)
-

ランチパスポート広島版Vol.7
88店舗のランチが、500円から540円(税込み、税別あり)で提供される、というもの(新コーナーとして、ちょっと贅沢な1080円ランチも)。 同じ店を3回まで利用出来る。 中には、通常1000円前後のランチが、500円台でいただけるお得な店も。 一方で、通常は800円台のものが500円台で提供されている、と記載されているものの、実際に行ってみると同様のランチが「ランチ特別価格」としてランチパスポートとほぼ変わらない料金で提供している、お得度がやけに低い店も。それどころか、出版直前になって「事情によりランチを提供出来ません」と表明して、掲載されてはいるもののランチパスポートが全く使えない店もある(要するに、本誌に載りたいだけだったらしい)。 それでも、大半のランチが500円台でいただけるのは有難い。 ただ、平日しか利用対象になっていない、行き難い場所にある、数量限定等、定休日が不定等、店によって条件が異なるので、事前に把握しておく必要がある。 有効期限は2月25日から5月24日で、それ以降は次のを購入し直さなければならない。【楽天ブックスならいつでも送料無料】ランチパスポート新宿(3)価格:1,000円(税込、送料込)
2015.05.25
コメント(0)
-

宇宙探査機 迷惑一番/神林長平著
SF作家神林長平によるSF長編。粗筋: 遠い未来。 地球は月面に基地を築くまでに至っていた。 地球連邦軍の月面基地に所属する迎撃小隊――通称「脳天気小隊」――が、未確認飛行物体に遭遇。それは、見る者によって全く異なる物に見えるという、奇妙な物体だった。脳天気小隊が迎撃した所、物体は月面に墜落。脳天気小隊は破片を回収し、月面基地に戻る。 すると、脳天気小隊らは衝撃の事実を知らされる。全員に生命反応が無い。したがって、死んでいる、と。 一連の事態は敵対する水星軍の陰謀だ、と月面基地の責任者は判断。地球が存亡の危機を迎えているにも拘わらず、基地を民間に売却するという政策を推し進めようとする地球連邦軍に対し反旗を翻し、クーデターを宣言。 脳天気小隊は、クーデター首謀者により始末の対象となる。脳天気小隊らは、自分らが生きている事を証明するのと同時に、生き続ける為に、基地からの脱出を試みる。 月面に墜落した未確認飛行物体は、水星軍が開発した平行宇宙移動探索機マーキュリーと思考装置・迷惑一番だった。その影響により、脳天気小隊は平行宇宙へと飛ばされてしまう。 その世界では脳天気小隊は難無く水星軍に受け入れられ、事を無きを得る。 元の世界では、クーデターは脳天気小隊の働きによって失敗に終わった事を知らされる。解説: 宇宙が舞台となっていて、主人公は軍に所属しているので、ハードなSFかと思いきや、タイトルから想像出来るように、ハチャメチャなSFとなっている。 軽く、密度の低い文体なので、ずんずん読み進められる。 ただ、一人称で書かれているので、主人公の視点を描いた無駄な描写が多く、展開が遅い。 ページ数こそ進んでいるのに、ストーリーは全然進まない(まさにSF的な感覚)。 脳天気小隊が未確認飛行物体と接触し、破片を回収して戻るのに100ページを割いていて、自分らが死んでいるのを知らされるまで50ページを割き、基地側が反応するのにまた50ページ、脳天気小隊が基地から脱出するまでまた50ページ。基地から脱出してどうなるのかと思っていたら、別の平行世界に飛ばされていて、物語は終わってしまう。 文庫本のカバーの裏に記された簡単な説明文で、物語全てが語られてしまっているのである。 舞台設定の大まかな説明と、主人公の独り言ばかりでいつまでも核心に迫らないと思っていたら、物語が終わってしまうのだから、呆れるしか無い。 著者が面白がって色々描写するのは結構だが、独りよがりの産物に付き合わされる読者からすれば堪ったものでは無い。 SFとあって、凝ったメカニックの描写があるが、興味が持てる内容にはなっていない感じ。 というか、軽い文体(にも拘わらず読み辛い)と同様、延々と続くだけで、飽きてしまう。 登場人物も、何となく区別出来る程度で、どれも印象に残らない。 何となく親近感が湧いてきたなと思ったら、物語は終わっていた。 本作は文庫本で270pで、大長編、という訳ではないのだが、展開が遅いので、やけに長く感じた。 無駄と思われる部分を省いて、150-200p程度に抑えていれば、テンポの速いものに仕上がっていたのに、と思う。 宇宙を舞台にしたストーリーには、読み始めは興味を持てるのだが、著者の文体や作風、そしてストーリー展開(の無さ)で興味が萎んでしまい、最終的にはどうでもいい良くなってしまっている気分。 調理の仕方によっては面白いものになっていただろうから、勿体無い。 日本では、SFは他のジャンルと比較して軽く見られがちだが、本作を読み終えた限りでは、それも仕方ない、と諦めるしかない。宇宙探査機 迷惑一番-【電子書籍】価格:525円
2015.05.23
コメント(0)
全140件 (140件中 1-50件目)
-
-

- 東方神起大好き♪♪ヽ|●゚Д゚●|ノ
- ZONE (2CD+スマプラ)<JACKET(B)>(…
- (2024-11-11 00:00:15)
-
-
-

- 台湾ドラマ☆タレント
- 「個人授業」メイキング
- (2024-11-15 22:30:09)
-
-
-

- 海外ドラマ、だいすっき!
- 🎬 韓国ドラマ『仮釈放審査官 イ・ハ…
- (2024-11-20 07:15:02)
-








