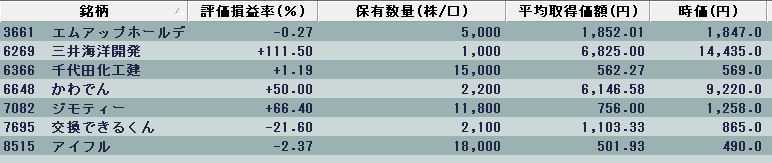2016年09月の記事
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
続けることの大切さ
「いかなる難所もお通りなされ候」。江戸後期に全国を歩き、日本最初の実測地図を作成した伊能忠敬の測量隊を目撃した人の記述だ。雨、風、雪をものともせず、海岸の危険な場所も果敢に挑戦してく姿に、驚きを隠せない様子が伝わる。 伊能が55歳から16年の歳月をかけて歩いた距離は、実に地球一周分に相当する約4万キロ。今年は最後の測量から200年になる。完成した地図は極めて精度が高く、欧州において高く評価され、明治以降、国内の基本図の一翼を担った。 「歩け、歩け。続けることの大切さ」との彼の言葉は、並外れた勇気と行動に裏打ちされているだけに重みを増す。「後世の役に立つような、しっかりとした仕事がしたい」。その熱意に打たれて弟子となる間宮林蔵との出会いをはじめ、行く先々で支援者が現れ、世紀の偉業が成し遂げられた。 【北斗七星】公明新聞2016.7.28
September 30, 2016
コメント(0)
-
自身のルーティンをもつ
創造的な人生を送りたいなら、型にはまった生活を送ることが助けになる。逆説的に聞こえるが、一つの真理である ラグビーの五郎丸選手がボールを蹴る前の“合掌ポーズ”、野球のイチロー選手が、打席でバットを高く掲げる姿――スポーツの世界でも、周囲の環境に惑わされず、集中を高めるための「ルーティン」の効用に注目が集まったが、何かを創造するために、一日の使い方を固定することは、一般生活にも必要な作業だろう 各分野の天才161人が、どんな“ルーティン”をもっていたかを調べた『天才たちの日課』(金原瑞人・石田文子訳、フィルムアート社)によると、仕事に集中する時間は、ゲーテは朝型だが、親友シラーは夜型だった。ユゴーは夜明けとともに起き、午前11時まで執筆した。反対にバルザックは午前1時に起き、朝まで書く“深夜型”の生活だったという 御書に「朝朝・仏と共に起き夕夕仏と共に臥し時時に成道し時時に顕本す」(737頁)と。私たちにとって、朝夕の勤行・唱題こそ、仏の大生命力をわが身に顕し、大宇宙を貫く根本のリズムである妙法に合致して、人生を価値的に生きるための、最も大切な「日課」である 弾むような朗々たる祈りを根本に、健康・成長・勝利の夏を。 【名字の言】聖教新聞2016.7.27
September 29, 2016
コメント(0)
-
充実した有意義な老いのために
精神科医 伊佐 文子 高齢化が進む中、脳血管障害や認知症など、神経内科領域の疾患が、よく見られるようになっていきました。私たちの日々の動作は全て、悩、脊髄、神経等がしっかりしていないと、普段のようにはできなくなります。患者さんから、こうした身体の不調やしびれなどの訴えを聞いて、神経学を踏まえた診察をして、疾患を特定するのが神経内科です。神経疾患の中で生活習慣病といえば、の脳血管障害が第一に挙げられます。その危険因子となるのは、高血圧、糖尿病、脂質異常症、心疾患、肥満、多血症、喫煙、飲酒などです。私は多数の脳血管障害の患者さんと接してきましたが、これらの危険因子を多く持てば持つほど、脳血管障害が起こりやすくなります。よい生活習慣は、喫煙をしない、飲酒はほどほどにする、毎日朝食を食べる、適度の睡眠をとる、適度に労働をする、週1回以上の運動をする、栄養を考えた食事をとる、自覚的アウトレスを少なくする、塩分を控えめにする、規則的な生活を送る、趣味を持つなどです。こうした生活習慣を心掛け、脳血管障害の危険因子を一つ一つ減らすことが予防になります。 心と体は密接に関係 病気全般に通ずることですが、一例として脳血管障害が起こった場合、人間は強いストレスを受けます。人間は、強いストレスを受けると、その反応で体内の血流が通常の3倍にも急増し、高血圧などの異変を起こすとされています。しかし、これでは悪循環となり、病状を悪化させかねません。心と体は、やはり密接に関係しているのです。日蓮大聖人は、病気を患う女性門下に、どうして病が癒えず、寿命が延びないことがあろうかと強い思いをもって、御身を大切にし、心の中であれこれ嘆かないことですと励まされています(御書975頁)。病状は病状として正確に知る必要があります。しかし、この仰せからも明らかなように、決して嘆いたり悲観したりせず、病気を前向きに捉えていくことも、病気と戦う上で大切なことです。ここで、心と体の相互作用の悪循環を断ち切る人体のメカニズムとして、「リラックス反応」を挙げることができます。心身には、ストレスがない状態の時、疲労を回復させるために休息をし、新たなエネルギーを取り入れる仕組みがあります。これが、リラックス反応です。リラックス反応は、深呼吸などによって、一層、増大するといわれています。こうしたことも、病気への予防・対処の観点の一つでしょう。今まで見てきたように、心の安定、健康は、肉体にも大きな影響を及ぼします。また、脳梗塞や脳血管障害を患った場合の予防についての、心がどういう状態にあるかが、回復を左右します。例えば、リハビリテーションの際、病気を隠さずに“自分”を表に出して、人の中に入っていくことが回復を早める場合があるのです。 社会への参加が高める“満足度” さらに、患者さんが、どういう“環境”にいるかも、広い意味での健康の大きな要素です。以前、ある患者さんたちの生活満足度と睡眠の関係について、調査したことがあります。結果は、生活の不満度と、眠れないという“不眠度”が比例するというものでした。また、同じ調査で、生活の満足度は、その社会参加の度合いと比例していました。ということは、能動的な社会参加が、生活の質を向上させ、ひいては“健康でいられる寿命”を延ばす要因となる可能性があると考えられるのです。現在、最も注目されている疾患に認知症があります。代表的な認知症としてアルツハイマー病がありますが、糖尿病を患っている場合、通常の2倍の確率で発症するとのデータがあります。アルツハイマー病の予防としては、生活習慣病の改善が大切です。医学的には、脳の機能が部分的に失われているのがアルツハイマー病ですが、それが原因で家族が最も困る症状に、幻視・幻聴、妄想、徘徊があります。例えば、自らのものを盗まれたと妄想する症状のある場合があります。実際は患者自身が、置いたこと自体を忘れていることによるのですが、一方的に叱るのではなく、相手に寄り添いながら一緒に探してみることも必要です。 一個の人格とて患者に向き合う 認知症も、相手の合わせた対応が求められます。誰かに愛されたい、誰かと一緒にいたいという欲求は、人間の基本的な精神的欲求だからです。心身の関係の上からも、アルツハイマー病の患者さんが、よりよう老いを過ごせるように、その心が満たされることが重要です。家族、周囲から、患者が一個の人格として認められる必要があるいうことです。現代医学は、ともすると、病気が重く、苦しんでいる状態のままでも、単に寿命を延ばそうとする傾向があります。もちろん、寿命を延ばすことが悪いということではありません。これに対し、仏法は、人間の内側に秘められた「生命力」を涌現させるものであり、豊かな生命力で健康と長寿を実現することを目指します。池田SGI会長は、「高齢化が進む現代にあっては、ただ寿命を延ばすということより、いかにして心身ともの、健康を回復し、有意義に生きていくかが、重要な課題」と指摘しています。日蓮大聖人は「年は・わかうなり」(御書1135頁)と仰せになり、年齢を重ねても、ますますの生命力で人生を歩んでいけることを教えられています。何歳になっても、自他共の幸福を願い、前向きに生きていこうとする人は、人生の年輪を重ねても、若々しく、はつらつと生きていくことができます。このことは、私の身内も含め、数多くの患者さんを診てきた実感の上からいえることです。高齢者は、家族、周囲の支えも必要ですが、生き方次第で老いの人生をさらに有意義なものにできるのです。 いさ・ふみこ 神経内科専門医。医学博士。神戸大学医学部付属医院、東京都立神経病院、都立北療育医療センターに勤務した後、内科クリニックを開院。1967年(昭和42年)入会。婦人部副本部長。東京女性ドクター部長、北総区ドクター部長。 【紙上セミナー「生活に生きる仏教」】聖教新聞2016.7.26
September 28, 2016
コメント(0)
-
桃栗三年 柿八年 柚の大馬鹿 十八年
「桃栗三年 柿八年 柚の大馬鹿 十八年」――これは、小説『二十四の瞳』の作者である壺井栄氏が生前、好んで色紙に書いた言葉である。 モモ、クリ、カキに比べ、ユズは成長が遅いため、時に周囲から見下される、という意味。だが長い歳月をかけて実をつける姿は、下積み時代に耐える人の愚直さを思わせる。そこに氏は、いとおしさを覚えたのだという。 広島東洋カープの黒田博樹投手が23日の阪神戦で、見事、日米通算200勝を達成した。プロ入りして20年の右腕が、「かけがえのない財産」と語り続ける思い出がある。それは、万年補欠だった高校時代の日々。ひたすら草抜きをした日もあった。それでもめげず、必死に走り、投げ込み、誰より練習に汗した。「あの3年間を思い出すと勇気が湧く。どんな苦しみにも耐えられる」と。 努力は、すぐに結果に表れないこともある。だが、歩みさえ止めなければ、実を結ぶ時が来る。“青春の原点”を胸に鍛錬を重ね、球界を代表する大投手となった彼の姿が、それを物語っていた。若き日に、「これだけ頑張った」といえる“財産”を持てた人は強い。苦難に打ち勝つ勇気になるからだ。この“努力の醍醐味”を、未来を担う青年と分かち合おう。鍛えの夏本番である。 【名字の言】聖教新聞2016.7.25
September 27, 2016
コメント(0)
-
笑顔になればポジティブな情報が入りやすくなる
まず笑顔や姿勢を意識 坂本九さんの歌「上を向いて歩こう」の作詞などでよく知られる永六輔さんが亡くなった。以前に通っていた理髪店のラジオから流れてくる永さんの軽妙な語り口が好きだっただけに、とても残念な思いがする。 「上を向いて歩こう」というのは、心の健康にとっても大切な発想だ。悲しいからといって下を向いて歩いていると、ますます気持ちが沈んでくる。上を向いて歩けば心が強くなる感じがする。 ある本にシンクロナイズドスイミングの選手の笑顔について書かれていた。選手は、会場に入るときに満面の笑みを浮かべている。演技をする前にさぞ緊張しているはずなのになぜあのような笑顔になれるのが不思議思っていたが、その本によると、意識的に笑顔を作っているのだという。 逆に、そうしなければプレッシャーに押しつぶされてしまう。そうならないために笑顔を作る。笑顔になれば緊張が和らいで、演技で本来の力を発揮できる。 これは「外から内へ」と呼ばれるこころの働きだ。一般に私たちは楽しいから笑うと考える。悲しいから泣くというのも同じだが、これは内(こころ)が外(表情や態度)に影響するという意味で「内から外」への影響と呼ばれる。逆に、表情や態度がこころの状態に影響することが研究からわかっている。 笑顔になればポジティブな情報が入りやすく、緊張が和らぐ。背筋を伸ばして前を向いて歩けば、気持ちも前向きになってくる。まさに「笑う門には福来る福来る」だ。だからこそ「上を向いて歩こう」の歌に励まされた人がおおかったのだろう。 (認知行動療法研修開発センター 大野裕) 【こころの健康学】日本経済新聞2016.7.24
September 26, 2016
コメント(0)
-
「暮らしの手帖」刊行に奮闘
「とと姉ちゃん」モデル 大橋鎭子と花森安治 出版ジャーナリスト 塩澤 実信 NHKの連続テレビ小説「とと姉ちゃん」は、連続週間視聴率二〇%を超えたまま、今日に及んでいる。家族ぐるみで女性生活情報誌を創刊した大橋鎭子と、編集長を担った花森安治の二人三脚で、鎭子の自伝『「暮らしの手帖」とわたし』が下敷きになっている。大橋鎭子は十一歳で父を失い、戸籍上の戸主となって、“父(とと)”姉ちゃんと呼ばれるようになったが、母と二人の妹の上に立って、昭和の戦前・戦中下の窮乏時代に耐え抜いた。戦後、昭和二十年、「女の人の役に立ち、生活に少しでも明りを燈すような雑誌をつくりたい」と、紹介された花森に肉薄。一筋縄では行かない彼を編集長に迎えた。花森は「一銭五厘」とヤユされた赤紙一枚で招集された軍隊経験を持ち、病気で除隊後、大政翼賛会宣伝部に勤め、戦意昂揚のスローガンづくりに献身した。それが戦後の思いトラウマになっていて、雑誌に協力する条件に「もう二度とこんな恐ろしい戦争をしないような世の中にしていくものを作ろう」と鎭子に約束させた。こうした経緯は、拙著「大橋鎭子と花森安治『暮らしの手帖』二人三脚物語」で紹介させてもらった。僅かな資金でスタートした「暮らしの手帖」は、三号で危機を迎えたが、昭和天皇の長女、東久邇(ひがしくに)成子(しげこ)さんに原稿を書いてもらうなど、鎭子の体当たり的企画で蘇生。さらに、広告を一切掲載しない雑誌のメリットを武器に、日用品や電化製品を徹底的に検証する「商品テスト」を誌上に発表することで読者の信頼をつかんだ。それは「消費者よ、メーカーに騙されるな」の姿勢ではなく、「メーカーよ、消費者を騙すな!」の視点にたっていたからだ。この目玉企画で部数は伸びつづけ、絶頂期には百万部に達するまでになった。花森はその一方で、大政翼賛会時代の贖罪(しょくざい)の意を込めて、読者から募ったのが一冊まるごとの大特集『戦争中の暮らしの記録』。「暮らしの手帖」創刊から、二十三年間に同誌に掲載した自らのエッセーから、二十九本を選んでB5判型三百五十頁の箱入り本に収録。『一銭五厘の旗』のタイトルで面を上げて国の姿勢を問い、読売文学賞を受賞した。私が大橋鎭子と取材を通じ交流を持ったのは、昭和五十三年、花森が心筋梗塞で急死した後である。表紙、原稿、カット、レイアウト、写真と、すべてを仕切ったスーパーマン編集長の後を一任された鎭子は、「花森さんのものすごく厳しい教育を受けて来ました。その厳しさは並大抵なものではありませんでした」と前置きした上で、日々、戦場に臨むような覚悟で仕事に取り組んできたから、花森の生前そのままのフォームは継承できるとの自信を披瀝してくれた。鎭子の時代はさらに、三十年余つづいたのである。(しおざわ・みのぶ)【文化】公明新聞2016.7.22
September 25, 2016
コメント(0)
-
原発事故と学術界の立場————誰のための学問か
木原 英逸 初動対応の特徴 2011年3月11日の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故に、科学者や技術者が集まる学術界はどのような立場で対応したのだろうか。今も、誰のためかを忘れた対応が学術界で繰り返されていないだろうか。震災後、学術界は、シンポジウムや講演会、提言や報告、被災地域での支援、学術調査などさまざまな活動を展開した。一方、「事故に関して、科学者・学会等の専門家・専門家集団としての意見表明を聞きたい」とした市民は、当時、6~7割にも達していた。それにどう応えたのか。学術学会が表明した声明や提言に注目して、その初動の対応をいくつか振り返ってみよう。震災直後の学術学会の声明や提言には、整理すると三つの特徴があった。第一に、研究・教育の職責を果たすとしたものがあった。理学系学会が約半数を占める、「34学会(44万会員)会長声明」(「日本は科学の歩みを止めない」4月27日)は、「高度な研究と人材が日本を支える礎」であるから、今こそ日本の復興・新生のために「我々は、被災した大学施設や研究施設の早期復興及び教育研究体制の確立支援を行い、科学・技術の歩みを続ける」とした。しかし、「国家社会」に、研究・教育で貢献するという認識は、被災「地域社会」の復興・新生に、役立つ科学・技術で貢献することを求める震災後の人々の認識とは、ずれていた。「国家、国民のため」といっても、それはいったい誰のためなのか。「国家、国民」に名を借りた、自分たちの既得権益擁護ではないか。そう見られて批判された。社会貢献の在り方を問われたのである。 問われた社会貢献の在り方 提言・声明には人々とのズレが 責任不問には批判も 第2に、被災地域の復興に貢献するとするものも多くあった。そこでも誰のためなのかが問われた。土木学会は関連学会と共に、「会長 共同緊急声明」(3月23日)及び「会長 共同アピール」(3月31日)で、被災地の暮らしと経済の復興を実現するためになすべきことは、「震災の調査分析」であり、「今までに積み重ねてきた対策の再評価」を行うことで「より信頼性の高い基準や指針の構築につながる」とした。土木学会は、想定を低く抑えた津波の基準(「原子力発電所の津波評価技術」2002年)を作った当事者であった。しかし、「積み重ねてきた対策」への評価はなかった。議論は、もっぱら、情報の信頼性の高さは手段としての確実性を高めることだとする方ヘ向かった。情報の目的の信頼性を問う声は弱かった。学術学会は「独立した第三者」の立場で貢献する、その前提が問われることはなかったからである。自立した学術・科学の立場は、誰もの利益、公共の利益に貢献する。だから、目的が信頼できる情報を作っていることに違いはなかったからである。しかし、現実はそうではなかった。その点では、日本原子力学会も同様であった。しかし、それは誰の責任かを問うという形で現れた。原子力学会は、政府の事故調査委員会の調査に、「関与した個人に対する責任追及を目的としないという立場を明確にすること」、また「設置者[東京電力]のみならず規制当局等も含めた組織要因、背景要因」を明らかにすることを求めた(7月7日「福島第一原子力発電所事故『事故調査・検討委員会』の調査における個人の責任追及に偏らない調査を求める声明」)。本来、組織の問題として取り上げられるべきことまでが個人の責任に帰せられることを恐れて、関係者の正確な証言が得られない。そうなれば、「事故原因の徹底的解明」ができないというのが、その理由であった。しかし、学術学会は組織としての責任を問われるべき対象であった。が、科学の立場・中立の立場から関与した学術学会に責任はないとして、もっぱら他の組織の責任に焦点を当て、自らの責任を不問にしようとした。そう理解され、また、関与した学術会員個人の責任の減免を求めるものだと理解され、自己免疫だと批判された。ここでも、学術学会の立場、それが誰に貢献しているのかが問われることはなかった。 忘れてはならない事 第3に、信頼できる科学情報を、学術学会が独立した自律的な研究者コミュニティーとして、住民・国民や政府へ発信していくとする対応も多かった。やはり、ここでも、学術学会が前提とする立場は十分に問われなかったその結果、情報が誰のためにどう作られているかは問わず、作られた情報の発信の仕方の良しあしに、もっぱら対策の焦点が集まることになった。しかし、情報発信の良い在り方を実現するには、良い情報が発信されているか、情報がどう作られているかを問わざるを得ない。しかし、そこを問わない議論が大勢を占め続けていたのである。結局こうして、いくつかの学術学会の初動対応を検討して分かるのは、学術界は、独立した第三者の立場に立っていることを前提、出発点にしてはいけないということである。独立した第三者の立場、公共の利益の立場とは、出発点ではなく、学術界が到達すべき不断の目標点なのである。学術界はそれを忘れてはならないだろう。(国士舘大学教授)【文化】聖教新聞2016.7.21
September 24, 2016
コメント(0)
-
スイカのお話
文芸評論家 持田 叙子 さいきんの列島の夏の暑さはすさまじい。海や山へ行く楽しさより、どうやって熱中症にならずに乗り切るか、が大きな課題になってしまった。 大阪に暮らす友人が、大阪にはとうとう砂漠のサソリが棲息するようになった、と騒いでいた。本当かしらん? しかし東京だって、燃える熱さのビル群とアスファルトはまさに砂漠。どこにサソリやガラガラ蛇がいたって驚かない。起きるなり太陽にクラッとするこの頃、三角に切り分けた紅いスイカをタッパーに入れ、つねに冷蔵庫に冷やしておく。 何しろスイカはポカリスエットの成分に似るよき水分。ちょこちょこ食べる。熱中症除け。 スイカ。西瓜。頼もしい大きさも、母性的な丸さも、みどりと紅の鮮やかな模様の大好きだ。みんなに愛されるおやつ。叩くと楽器にもなる。 しかし江戸時代、スイカは庶民しか口にしなかった。貴族や武士の家では食べる習慣がなかった。その代わり、切ったスイカをお皿にのせて部屋に置く。いい匂いで蠅をおびきだす、蠅取りとして使ったとか。いまは亡き国文学者・池田弥三郎先生のお話である。 明治になって、スイカへの軽べつは解除された。森鴎外は二度結婚した。初めの結婚のお相手は、男爵家のお姫さま。 新婚の家へ鴎外の友人がドッと遊びに来たとき、お姫さま奥さんは何でもてなせばよいか解らず、立ち往生。世なれた鴎外の母が大きなスイカを手早く切って砂糖をふり、これを出しておけばよござんす、と助けた。 スイカは夏の輝くシンボル。あの大きな玉には、それぞれの夏の思い出がつまっている。 わたしの父はスイカのアイスクリームが大好きだった。祖母のお手製の味だったという。戦前のちょっとハイカラなお母さんと、小さな息子の夏の風景が透けて見える。 【言葉の遠近法】公明新聞2016.7.20
September 23, 2016
コメント(0)
-
トルコクーデター
吉田松陰や橋本佐内が斬罪に処された「安政の大獄」は、連座したものが100人余にのぼる尊王攘夷派への大弾圧だった。活動家たちの命を奪っただけでなく、関係者への処罰は島流し、追放、押込、手鎖など多岐にわたったという。藩主級も隠居謹慎の憂き目を見た。 勅許を得ないで米国との条約調印に走るなどあいた幕府への反発を、大老の井伊直弼は情け容赦なく抑え込んだのである。不穏な企ては徹底的に摘み取るのが強権維持の要諦であろうから、古今東西、この手の謀反つぶしは枚挙にいとまがない。とはしっていても、いま進行中のトルコの大獄のすさまじさには言葉をのむ。 軍の一部によるクーデター未遂に対し、政府は関係者の身柄を大量拘束し、解任された公務員も県知事を含めおびただしい数に達するという。摘発はさらに広がる見込みで、エルドアン大統領は死刑の復活にも言及したそうだ。民主的に選ばれた政権を暴力で覆そうとは言語道断だが、この反応も異様というべきだ。 桜田門外の変につながった安政の大獄ではないが、力まかせの処断が新たな混乱を生むのは歴史が教えるところである。クーデター失敗からわずか数日、これほどの粛清を推し進める政権の早業を世界はどう見よう。こんどの騒ぎでは、たくさんの市民が勇気を振り絞って軍に立ち向かった。その精神を汚してはなるまい。 【春秋】日本経済新聞2016.7.20
September 22, 2016
コメント(0)
-
悔しさも成長のバネになる
ネガティブ心理のもつポジティブパワーとして、悔しさの心理をあげることができる。 苦労の末に何かを成し遂げた人が、「あの時の悔しさをバネに頑張った」と言うことがあるが、悔しさというネガティブ感情がモチベーションの原動力になるのだ。 バスケットボールの天才的プレーヤーとして大活躍したマイケル・ジョーダンは、大学時代にレギュラーになれず悔しい思いをしたことを何度も噛みしめたという。 きつい練習に挫けそうになると、その悔しさのエピソードを思い出して自分を奮い立たせたそうだ。悔しさをバネにモチベーションを高めるということを、ごく自然にやっていたのである。 イチロー選手も、悔しさというネガティブ感情から目を背けずに、悔しさと向き合うことでモチベーションを上げてきた。 日米通算4000本安打という大記録を達成した瞬間、試合は一時中断され、一塁ベースを回ったイチローの周囲にチームメイトが駆け寄り、祝福の輪ができた。 「僕のためにゲームを止めて、時間を作ってくれる行為はとても想像できるわけがない。うれしすぎてやめてほしいと思った」(読売新聞2013年8月23日付朝刊) このように喜びを表現したイチローだが、じつはそれまでいい思い出はほとんどないという。 「4000の安打を打つには、8000回以上は悔しい思いをしてきている。それと自分なりに向き合ってきた。誇れるとしたらそのことではないか」(同紙)と言って、失敗の記憶を大切にし、それと向き合うことでここまで来られたと種明かしをしている。 ただし、ネガティブ感情をバネに建設的な方向に頑張っていく人もいれば、ネガティブ感情に負けて開き直ったり人を恨んだりという非生産的な方向にいってしまう人もいる。ネガティブ感情をモチベーションにつなげるコツがあるのだ。 ポイントは「見返しの心理」と「中和の心理」だ。 マイケル・ジョーダンは、レギュラーになれなかったときの悔しさをエネルギー源として頑張ることができた。そこにあるのは、「なにくそ」「負けるものか」「絶対に這い上がってやる」といった「見返しの心理」である。 ここで注意しなければならないのは、見返しと仕返しの区別だ。「見返しの心理」は建設的な行動に向かわせるが、「仕返しの心理」は非生産的な行動にエネルギーを費やさせる。 たとえば、頑張っているのに上司から評価してもらえないというとき、「こんなに頑張っているのに、全然認めてくれないなんて」という気持ちが高じて、やがて「許せない」と恨みが募り、その上司の悪口を周囲に触れ回ったり、ネットに不満を書き込んだりするなら、そこにあるのは「仕返しの心理」である。そんなことにエネルギーを費やしても、ますますネガティブな感情が膨れあがるばかりで、何も良いことはない。 それに対して、「見返しの心理」によって動く人は、「あの上司が無視できないように成果を出してやる」というように、相手を恨むのではなく、自分を成長させるといった方向に自分自身を駆り立てることで状況を変えようとする。それによって上司がちゃんと評価してくれるようになるかどうかはわからないが、自分自身が力をつけていけるわけだから建設的な動きといえる。 一般に、「仕返しの心理」に陥りやすいのは、仕事そのものよりも人間関係が気になるタイプと言える。仕事で成果を出すことよりも、人からどう評価されるか、好意的にみられているかどうかが気になる。そのため、評価が思わしくないと自分の仕事ぶりを振り返るよりも、評価者を憎む。 一方、「見返しの心理」に駆り立てられるタイプは、待遇に対する不満や人間関係の葛藤も仕事面で成果を出したり力をつけたりすることで解決しようという思いが強い。ゆえに、評価者を恨むものではなく、自分自身の能力向上を目指す。 同じく「悔しさ」に端を発するネガティブな心理であっても、「見返しの心理」と「仕返しの心理」が決定的に異なる方向に人を駆り立てることがわかるだろう。 イチローのエピソードからわかるのは、ネガティブ心理を意識しないようにして心の中から排除するのではなく、ネガティブ心理を意識しつつ、ポジティブな経験によってそれを中和しようとすることが向上をもたらすということである。 野球では、首位打者でさえ3割台なのだから、嬉しい思いをするよりも悔しい思いをすることの方が圧倒的に多い。その悔しさから目を逸らすのではなく、その悔しさを絶えず意識しつつ、何とか悔しい思いを少しでもポジティブな方向に中和させようと技術向上に燃えたり打席で集中力を高めたりする。 そのようにネガティブ感情を中和しようという動きが、悔しさをバネにして成長することにつながっていく。 いずれにしても、ネガティブ感情は決して排除すべきものではないことがわかるはずだ。 【ネガティブ思考力】榎本博明著/幻冬舎
September 21, 2016
コメント(0)
-
貧困対策の基本は就業対策
明治大学大学院教授 青山 やすし 貧困とは、貧しくて困窮していることをいう。貧しくとも困窮していない場合も多い。これについて、幕末に日本を開国しようとして米国から来訪したペルリ提督は「下流の人民は例外なしに、豊かに満足して居り、労働もしていないようだった」と記している。戦国時代の末期や江戸時代の初期に来日した欧米人も日本人は質素な生活をしているが困窮はしていないという趣旨の報告を書き残している。 全体としては食料も衣類も豊富で、住宅の数が世帯数を上回っている今の日本で貧困が問題となるのはなぜか。 失業や病気など、貧困になる原因はさまざまであり、多様な対策が求められ、一般的に社会保障政策の充実は大切だが、貧困対策の基本は就業対策の充実である。人それぞれの状況に応じて可能な仕事が得られるようにする政策が重要である。 大企業に雇用の増大をあまり期待できない現代では、工業、農業、商業、各種サービス業を含めて自営業を創業しやすいように政策を充実するのが現代的である。そのための政策メニューは既にたくさんあるが、職を求める人々に全面的に届いているとは言い難い。 技術を身につけたり資格を取得したりするための支援策が単に用意されているだけでなくこれらの政策が実際に困窮者に広く活用されるよう、政治や行政の努力や工夫が求められている。 ちょうど3年前の参議院選挙のころ、生活保護改正案と生活困窮者自立支援法案が国会で成立した。この二つの法律はセットであり、働ける人は生活保護を受けずに済むよう、従来の職業紹介制度にとどまらず、就業のための多様な支援を行おうという考え方である。根底には、生活保護の受給者が増え続けているという状況があった。 この画期的な政策はまだ実施の緒についてばかりである。今回の参議院選挙で新たに国民の信託を得た人たちには、貧困対策を実効あるものにしていくことも求められていると思う。 【ニュースな視点】公明新聞2016.7.18
September 20, 2016
コメント(0)
-
勇気こそ人間の最善の徳
マサチューセッツ大学 学事長 ウィンストン・ラングリー博士 原水爆禁止宣言の卓越した理念 1957年―—冷戦の渦中に、核兵器廃絶を叫んだ人物がいたことに驚きました。当時の西洋社会にあって、その平和の理念に注目する人は少なかったのです。この歴史を学んだ時、私は戸田会長と、その遺志を継ぐ池田会長こそ、私たちがあまり目を向けてこなかった、人類の「最善の徳」を示す人であると深く感じました。その徳とは勇気です。時代の流れに逆らい、平和を叫ぶことは大いなる勇気を要します。核廃絶のための主張と行動の一貫性は、池田会長の思想が、全ての生命の尊厳に立脚していることの表れです。生命の尊厳を中心に置かずして、人権文化の確率はあり得ません。そしてその「生命の尊厳」は、ただ抽象的な主張を繰り返すだけで、正しく認識されるものではありません。具体的な行動が必要なのであり、とりわけ自分と他者との関係性の中で、実践されなくてはならないのです。この「具体性」と「日常性」もまた、会長の思想の根幹であると理解しています。 自らの振る舞いに誇りと確信を 私たちがしばしば、自らの行動に引け目を感じるのは、思い描いていた理想とはかけ離れた自分―—他者への最善の行為を知りながら、それを実践できない自分自身に気づくからです。ここで私が思い起こすのは、仏法が説く「全ての人は仏になれる」との教えです。そこでは、私の中にも、あなたの中にも、自分自身が目指す理想型〈=仏性〉があると説かれます。そのことを信じ、広く他者に語っていく行為自体が、生命尊厳の思想を実践することになるのです。 私は先ほど、人間の徳としての「勇気」に触れました。池田会長の類いまれな対話を可能にしているのは、宗教や思想の違いを受け入れ、感謝できる勇気ではないでしょうか。さらに私は、会長が、異なる文化を学ぼうとする勇気にも感銘を深くしています。会長は相手の国の文学や歴史、芸術、習慣などを事前に学び、自らの知識として、惜しみなく語るのです。例を挙げればブルガリアやロシアなど、日本とは全く異なる文化の知識人とも対談してこられました。相手にとっては“専門分野”である内容を、その相手の前で披露するのは、容易なことではありません。会長が示す、相手から「学ぶ勇気」と「受け入れる勇気」。ここに、ここにどんな人とも心を開き、分かち合っていく道があります。 【グローバル・インタビュー「世界の指揮者の眼」】聖教新聞2016.7.17
September 19, 2016
コメント(0)
-
江戸が東京になった日
「東京都は東の京都である」―—いまでも京都の人の話によく出てくる説らしい。維新後、江戸に置いた「東の京」なので的外れでもない。でも、なんだか妙だ。「千年の都」にとって、新参者の首都・東京はあくまで出先という意識がかいま見えるからかもしれない。 明治の初め、日本の首都は京都で、江戸は第二の都だった。歴史学者の佐々木克さんの著書「江戸が東京になった日」によると、東西2都になる可能性もあったらしい。大久保利通が大阪への首都移転を提案したことで、国中に衝撃が走る。そこへ、江戸が名乗りをあげ、3都市が競い合う。結局、東への遷都が固まった。 新政府は改革を急いでいた。古くて閉鎖的な京都を脱し天皇親政の新体制を作ろうとしていた。そのため世界に通用する立派な首都が必要だった。明治元年7月17日、何の前触れもなく「江戸を東京にする」という詔書を出した。そして江戸は突然、東京になった。明治天皇が東京で暮らすようになるのは翌年3月からだ。 混乱の中でなし崩し的な遷都だった。新参者でも150年近く役割を果たしてきた。世界にも浸透した。「千年の都」にひけをとらないほどだ。たびたび移転話が浮上しても、なかなか代わりが見つからない。だが、最近、トップが冴えない。不祥事などで混迷が続く。明治に学び、急ごしらえでも立派な顔を選びたい。 【春秋】日本経済新聞2016.7.17
September 18, 2016
コメント(0)
-
価値創造の教育は人間と社会の関係性を豊かに
アメリカの池田国際対話センター(マサチューセッツ州ケンブリッジ市)で行われた「教育講座」(6月17日)。ここでは、登壇者の一人、アメリカ・デューイ協会元会長で南イリノイ大学名誉教授のラリー・ヒックマン博士の講演の要旨を紹介する。 南イリノイ大学カーボンデール校 名誉教授ラリー・ヒックマン博士 快楽は幸福ではない アメリカの教育哲学者デューイ、創価学会の牧口常三郎初代会長、池田博士の3人の教育哲学に共通しているのは、人間と多様な事象との「関係性」を非常に重視している点です。関係性とは、例えば、子どもたちの過去の経験、学習環境、育った文化背景、友人関係などです。3人はまた、関係性という視点から、「地理」と「歴史」をカリキュラムの重要な基礎と見なしています。牧口会長は、個人の関係性を地域そして社会全体へと結びつけることが大事であると訴えています。その意味で「地理」の学問は、子どもたちの日常生活を出発点とし、社会とのつながりの意識を世界へと広げていくものなのです。もし今、デューイと牧口会長が生きていれば、池田博士が創立した多くの教育機関で成し遂げられている業績を、心から称賛するに違いありません。池田博士の言う「価値創造の教育」とは、まさに個人と他者、個人と環境、個人と歴史など、さまざまな関係性を豊かにしていく教育にほかなりません。なお博士は、公共教育においては、宗教教育を行うべきではないと述べています。なぜなら、そうした教育は「信教の自由」を踏みにじるものだからです。博士はまた、デューイや牧口会長と同じく、現実の社会と関わりながら学ぶことを提唱しています。ボランティア活動などは、単発的でなく継続的に取り組むべきであり、社会貢献の充実感や目に見える結果が大切と呼びかけています。 人間と社会の関係性を豊かにする教育実践の模範例として、池田博士が創立したアメリカ創価大学を挙げたいと思います。この大学では、学生と教員が一体となって、「人間として生きる意味」をはじめ、「自然環境」「文化背景」「国際問題」など幅広く探求しています。デューイ、牧口会長、池田博士にとって、教育の評価を決定する要素は、人間と社会の関係性の豊かさにこそあります。標準化されたテストを過度に重視することは、悪しき教育の手法につながります。テストの推進は、医療診断のように、子どもたちを比較するというより、各人の状況と、それぞれが必要としているものをもつけるためにこそ、行われるべきではないでしょうか。デューイは、テストそのものを完全に否定したわけではありません。しかし、テストはあくまで教育の道具の一つにすぎないと考えていました。牧口会長もまた、テストばかりの教育や、単に知識を伝達する教育に批判の声を上げていました。池田博士も、いわゆる知識の「詰め込み型」の教育には鋭く反対しています。博士は、牧口会長の思想を受け継ぎ、“教育者とは権力者でもなく、単にテストのために教える存在でもない。真の教育者とは、子どものパートナーとして共に成長していく存在”と結論しています。最後に、教育の目的についてですが、牧口会長、池田博士は共に、「幸福」を「価値創造」と定義しデューイは「成長」と名付けました。ここで重要なのは、3人は、いずれも、決して「幸福」を快楽とは捉えていない点です。3人は共に、「学び」それ自体を「手段」であり、「目的」と見ています。そして、「学び」とは、変化してやまない環境や、人間と社会の関係性に適応していく挑戦であると訴えているのです。 【アメリカ池田国際対話センター「教育講座」での講演[要旨]】聖教新聞2016.7.16
September 17, 2016
コメント(0)
-
“差異から学ぶ勇気”育む教育を
池田SGI会長のコロンビア大学ティーチャーズ・カレッジでの講演20周年、そしてアメリカの哲学者ジョン・デューイの著作『民主主義と教育』発刊100周年を記念し、池田国際対話センター(マサチューセッツ州ケンブリッジ市)で行われた教育講座(6月17日)。ここでは、登壇者の一人、米デューイ協会元会長でバージニア工科大学教授のジム・ガリソン博士と講演の要旨を紹介する。 バージニア工科大学教授 ジム・ガリソン博士 20年前の講演で池田博士は、「教育は、永遠なる人道主義の推進力になっていかねばならない」と訴え、続けて、教育こそ人生の最重要の事業だと語りました。博士は、その言葉通り、これまでの数十年間、教育と青年の育成に人生をささげてこられました。創価学会が「創価教育学会」として発足して以来、その目的は常に、現実からかけ離れた理想でもなく、単なる個人の利益でもありませんでした。創価学会の目的は、全ての生きとして生けるものの幸福であると理解しています。 池田博士とデューイ、またウォルト・ホイットマンに共通する思想として、「宗教的な人間主義」が挙げられます。3人が目指す“人間性”は、最終的に到達するものであったり、固定的であったりはしません。(ホイットマンはアメリカの詩人。デューイはホイットマンの民主主義思想に共感を寄せ、池田SGI会長も青年時代からホイットマンの詩を愛読していた)また、3人の哲学は、世界の多くの人が抱いているであろう“人間は宇宙的なものとの関わりなしに、科学的、論理的な思考の力だけで全ての問題に対処できる”という思想とも、一線を画します。「宗教的な人間主義」は、人間の脆弱性や環境との関係性を、正しく認知しています。すなわち「宗教的な人間主義」とは、“人間の救いは神によってもたららされる”という妄信でもなく、“人生は理想の力だけでコントロールできる”という過信でもない、まさに「中道」の思想なのです。 仏法では、人間の生命には「仏界」が存在するとされていますが、この人間性の追求は、一生で終わるものではなく、世代を超えて続く挑戦です。良い人間になるためにはよい教育が不可欠です。それは同時に、悪い教育が悪い人間をつくるともいえます。20年前の講演で池田博士は、牧口初代会長が、教育の目的を「児童や学生の『生涯にわたる幸福』」とし、「真の幸福は『価値創造』の人生」と定義していたと言及しました。 そして、「価値創造」とは、「いかなる環境にあっても、そこに意味を見いだし、自分自身を強め、そして他者の幸福へ貢献しゆく力」だと強調しました。さらに博士は、世界市民の資質として、①あらゆる生命の相関性を認識する「智慧」②差異を恐れるのではなく、尊重し、成長の糧とする「勇気」③物理的な距離にもかかわらず、他者の苦しみに同苦し、連帯していく「慈悲」、の3点を挙げています。 残念ながら今の教育界では、こうした資質を育む取り組みは欠如しています。生命のつながりを学ぶどころか、国家主義が再びはびこり、人間の「分断」がより強調されているのが事実です。 学校や社会では、多文化への意識は高まっていますが、他者との差異を「受け入れる」までにとどまっています。 しかし忘れてはいけないのは、池田博士とデューイが共に、差異から積極的に学びながら、新しい意味や価値を創造していくことを呼び掛けている点です。二人のように、「差異」を「価値を創造していく共同作業の原動力」と見なす慧眼は、現代の教育界では非常にまれです。 ここ数世紀において、人類は、自然資源を、経済生産のため単なる部品と見なしてきました。そして人間の21世紀の今では、私たち人間自身が部品となりつつあります。 私たちの未来のために、池田博士が提唱する「智慧」や「慈悲」の思想が不可欠なのです。 【アメリカ池田国際対話センター「教育講座」での講演】聖教新聞2016.7.13
September 16, 2016
コメント(0)
-
健さんは座らない
今も思い出す言葉がある。生前、高倉健さんが北野武氏と共演した芸能ニュースで取り上げられた時のこと。「武ちゃんが『健さんは座らない』と言ったから、僕は座れなくなったんだよ」と北野武氏に声を掛けたのだ。 以前から“伝説”とされていた、「健さんは座らない」。自分の撮影が終わっても、共演者の撮影が終わるまで立ったまま待っている。寒い日でもストーブにあたらない。誠実でいちずな人物像が浮かぶが、逸話の真偽は定かではなかった。放送を見た人の受け止め方もさまざまだろう。 ところが事実は他人に言われたから座らなくなったわけではなかった。「どうか先にお帰りになって」「せめてイスにでも腰かけていらしてください」と言っても、立ち続けていたらしい。浅丘ルリ子さんが『私の履歴書』(日経)で証言している。 「大勢の人たちに慕われている理由がよく分かった」とも綴った浅丘さん。人は言動を見ているものだ。(略) 【北斗七星】公明新聞2016.7.16
September 15, 2016
コメント(0)
-
まとまりのない第3次世界大戦
1878年7月14日、パリ市民は圧政の象徴、バスチーユ監獄を襲撃したが、わずか7人の囚人がいただけだった。それでも、勝利の行進を果たし気勢を上げている。民衆が蜂起したとの意味でフランス革命の画期だ。赤青白の三色が国民衛兵の帽章に採用されている。 ぜいたくにふける王族や、特権にあぐらをかいた聖職者、貴族、一方で、庶民は過酷な労働と重い税に苦しむ。そんな深刻な社会の矛盾を正すため、今に受け継がれる自由、平等、法の支配といった理念で戦いを始めた記念日が14日だ。それを祝う南仏ニースで無差別テロは、近代の矛盾や価値観への重大な挑戦である。 いったい、フランスは何度涙にくれるのか。昨年来、新聞社襲撃、同時テロ、そして今回と犠牲者は230人を超えた。他にもベルギーやトルコの空港で、バングラデシュの飲食店で、無辜(むこ)の市民が爆風や銃弾に襲われている。ローマ法王はパリのテロを「まとまりのない第3次世界大戦」と表現した。まさに、戦時下だ。 パリ市の紋章に帆船の絵とともに、ラテン語の一節が書かれている。「たゆたえど、沈まず」。セーヌ川を中心としたかつての水運の街での船乗りの自負だ。数々の政変や戦乱をくぐり抜けてきたこの国の人々の誇りもにじむ。それにならい、世界に分断と恐怖による支配を持ち込む勢力に「沈まぬ」心意気を示したい。 【春秋】日本経済新聞2016.7.16
September 14, 2016
コメント(0)
-
信仰とは星のようかもしれない
信仰とは、星のようなものかもしれない。星は常に、空に光っているが、日が沈まないと目に見えない。順風満帆な人生の昼間よりも、逆境の暗闇の中でこそ明るく輝き、幸の人生航路へと導いてくれる。 ◇ 地上の人間の喜怒哀楽を見つめながら、きょうも壮大な星々の運行は続く。その根本法則である妙法と共に生きる私たちは、「苦楽ともに思い合せて」(御書1143頁)、祈り戦い、三世の幸福へのドラマをつづっていこう。 【名字の言】聖教新聞2016.7.15
September 13, 2016
コメント(0)
-
ボリビアの黒人共同体
探検家、医師、武蔵野美術大学教授 関野 吉晴 ボリビアの首都ラパスから百キロ前後、アンデス東斜面の標高千~二千メートルのユンガといわれる高地には、いくつかの黒人の共同体がある。急斜面に栽培されているコカの葉を夫人や息子夫婦と摘みながら、黒人のホセ・サパラさん(六六)は話した。「最近はコカ栽培に対する政府や警察の圧力が強くなっているんですよ。祖先の代からコカで生計を立ててきたのに、アメリカ政府の圧力があるといって簡単にやめられませんよ。高地ではコカをかまなければ生きていけない人がたくさんいるのです。私達に干渉するより、アメリカは国内での取り締まりをきっちりとすればいいのです」。柔和な顔でゆっくり話すホセさんの顔がきつくなった。ユンガには一万七千人の黒人が住んでいる。十六世紀に標高四千メートルのポトシの銀山で働かせるためにアフリカから連れてこられた。ところが高度に順応できないために、コカ栽培をさせようと気候の温暖なユンガに移された。みなコカ栽培をして生計を立てている。年四回収穫できるうえ、単位面積あたりの収穫率が米などよりはるかによい。また雑草のように強く、病気もない。黒人の多くはアイマラ族の服を着て、土地のインディオに完全に同化している。ホセさんの息子はアイマラ族の娘と結婚した。混血も増えている。「私達の祖先はアフリカからやってきたが、パトロンに逆らわないように、同じ言葉を話す者、つまりアフリカのルーツを持つ者は別々に離されました。だから実際のところ祖先がアフリカのどこからやってきたのかわからないのです」。 【すなどけい】公明新聞2016.7.15
September 12, 2016
コメント(0)
-
傲岸と馬鹿
「できるだけいんぎんにし、威に打たれたごとくおびえ、小心にしろ」といった。そうすればただでさえ傲岸なあの男だけにず(、)に乗り、羽柴方を軽侮し、いい気持になるであろう。「春まで、あの男を馬鹿にしておくのだ」秀吉のいうところは、傲岸とは馬鹿の別称であるという。傲岸にかまえた心根から知略などは思いうかばないという。春まで、できるだけ勝家を北方の覇王としてふんぞりかえしておかねばならない。 【新史 太閤記】司馬遼太郎著
September 11, 2016
コメント(0)
-
不安に駆り立てることの大切さ
最近世の中に流布されているポジティブ信仰は、ネガティブな出来事については考えず、ネガティブな感情は捨てるようにいう。 たとえば、不安を悪いものとみなし、不安などない方がいいとして排除しようとする。だが、不安というのは、現実の状況に適応していくために必要不可欠の感情なのである。不安になるから、どうしたら状況に自分を適応させることができるかを慎重に検討することになる。 不安がないとどんなことになるか。それは、これまでにみてきた通りだ。気が大きくなって軽率な行動が目立つ。つい気が緩んで準備不足で失敗する。いくら言っても、人の言葉が染み込まない。失敗しても行動が修正されず、同じ失敗を繰り返す。周囲の人の気持ちを配慮せずに、相手を傷つけるような発がんをしたり、周囲の人の反感を買うような言動を取ったりして、無用のトラブルを招く。 一方、不安が強ければ、先の展開についてあれこれ創造せざるを得ない。相手の受け止め方についても、いろいろと想像をめぐらせる。それで用意周到に準備したり対処すりわけだが、それでも実際には何が起こるかわからないため、先のことを考えて不安になる。うまくいかなかったらどうしよう、こんな展開になったらどうしたらよいのかなどと、ネガティブ思考が活性化され、万一の事態をいろいろ思い浮かべては、その場合の対処法をシュミレーションする。 それによって万全の準備ができる。配慮の行き届いた対応ができる。また、想定していた事態が生じた場合の対処も考えてあるからうまくいくし、想定外の事態が生じた場合も比較的スムーズに対処できる。 このような用意周到さと対処能力の高さをもたらしているのが不安というネガティブ感情だと言える。 【ネガティブ思考力】榎本博明著/幻冬舎
September 10, 2016
コメント(0)
-
非現実的楽観主義と防衛的悲観主義
ノレムとキャンターは、過去のパフォーマンスについての認知と将来のパフォーマンスに対する期待を組み合わせて、楽観主義・悲観主義に関する4つのタイプに分けている。ここでは、そのうちの非現実的楽観主義と防衛的悲観主義を取り上げることにしたい。 非現実的楽観主義とは、これまで実績がないのに、将来のパフォーマンスに対してはポジティブな期待をもつ心理傾向を指す。 防衛的悲観主義とは、これまで実績があるにもかかわらず、将来のパフォーマンスに対してはネガティブな期待をもつ心理傾向を指す。 実際に成果を出していないにもかかわらず、自分はできると楽観視する非現実的楽観主義は、ポジティブなのだが、じつは適応的ではない。 たとえば、いくら注意したりアドバイスをしたりしても、その内容が染み込まない。 「わかりました」「わかってます」 などと言うものの、懲りずに同じような行動パターンを取り、似たようなミスを繰り返す。ポジティブすぎることによって、慎重さが足りないのだ。 一方、実際はちゃんと成果を出しているのに、今度もうまくいくとは限らないと悲観的になる防衛的悲観主義は、ネガティブだが適応的と言える。 以下の項目で具体的にみていくように、防衛的悲観主義者の成績が良いことは、多くの研究により証明されている。悲観的だからこそ慎重になれる、用意周到に準備する。不安が強く、楽観的になれないことが、高いパフォーマンスにつながっているのである。 ポジティブ信仰が広まり、周囲にポジティブすぎて残念な人が目立つ現在の状況をみると、ポジティブの効用にばかりとらわれずに、防衛的悲観主義の心理メカニズムの効用にもっと目を向けるべきではないだろうか。 【ネガティブ思考力】榎本博明著/幻冬舎
September 9, 2016
コメント(0)
-
感性仕事術
結果を出せるかどうかは「こうなりたい」という欲が深いかどうか 全国で数々の大型商業施設を成功させてきた商業コンサルタントの島村美由紀さん。今回のスタートラインでは、働くことに関する書籍を著し、セミナーの講師も務める島村さんに、仕事に向き合う姿勢について話を聞いた。 商業コンサルタント 島村 美由紀さん 待ってはいけない ―—「仕事は決して、自分のほうに歩み寄ってくれないもの。特に、能力も経験も十分でない若いうちは、自分から仕事に歩み寄って引き寄せない限り、何も始まりません」著書『30歳から自分を変える小さな習慣』の中で、仕事の姿勢について、こうかかれていた。 若手社員を見ていると、“待っている人”が結構多いような気がします。「私はここにいるから早く誰か、私に気がついて」と、まるでシンデレラのように(笑い)。子どものころは皆、何かあると競うように「やりたい! やりたい!」って手を挙げていたのに、大人になるとそれがなかなかできない。そんな姿勢で、仕事は来ることはないですよね。タクシーでも、空車の表示がついているから、乗りたい人が手を挙げて止めてくれる。表示が出ていないタクシーは誰も止めてくれません。上司は「仕事をやらせてください」という“やる気”を見て、仕事を任せるもの。時には、望んだものとは違う仕事を頼まれることもありますが、「何かお手伝いをすることはありませんか?」と“御用聞き”を日々の習慣にすることから始めるだけでも、変わってくるものです。また、待っているうちは、仕事が楽しくなるということはないんじゃないんですかね。今つらいと感じている仕事が劇的に楽しく変わることはないかもしれませんが、そんなちょっとした姿勢の変化によって少しは楽しさが見つけられるはずです。 ―—感性は観察力だと島村さんは言う。そして、観察力が磨かれていくと、それによって“気づき”が増え、新しい発想や課題の解決策が生まれる。 例えば、同じ時間、同じクライアントさんと商談していても、私と、連れて行った新入社員とでは気づきの量は違います。それは観察力の違いなのですが、気づきの出発点は「面白がる」ことだと思うんです。自分が面白い、楽しいと思う感覚を信じて、ひたすら目の前にある仕事をやり続けていくことが結果としてキャリアアップにつながるのではないでしょうか。面白がることは自分に気づきのチャンスを与えていくことになります。いろんな視点から面白がることができれば、その分だけ気づきが増えるということなんです。 感性は誰にでもある ―—さらに「感性とはすべての人に与えられた力」と強調する。 感性がない人はいないと思います。仕事では頼りない人でも、コーヒーのことになると、とても研究熱心な人っていますよね。また、仕事は半人前だけど、釣りに関してはプロ並みの人もいるかもしれません。感性の生かし方とは、自分の感覚から出発してかまわないので、観察し、気づき、考え、そして行動に移すこと。例えば釣りであれば、風向きを観察し、どんな場所でどんな道具を使うかを考え、実際に釣りに行きますよね。そんなことは教わらなくてもやっているでしょう。同じプロセスを少しでも仕事で意識してみると、なにかかわるんじゃないかと思うんです。 ―—著書の中では「少しでも心に引っかかったことがあれば、それを見逃さずに一歩足を踏み出す。たったそれだけのことですが、これを実行するかどうかで人生は変わってきます」とも記す。 何かをやろうとする時、できない理由をたくさん並べる人っていますよね。例えば、太り気味の人がジョギングを決意したとします。しかし、いざ走ろうとすると走りたくないので「雨が降ってきたから」「暑いから」「明日は大事な会議があるから」などと理由を並べ、結局走らない(笑い)。そんなにできない理由を考えられるエネルギーと能力があるんだったら、さっさとやってしまった方が早いと思うんです。私も、原稿の締め切りがあったりすると、書かない理由を山のように頭の中で考えるんです。でも、書かない理由を考えている途中で、「こんな無駄なエネルギーは人生にとっていいことはない」って気づいて、「ちゃっちゃとやっちゃおう!」と。毎回そうなんです。 伸びる人と伸びない人 ―—経営者として社員と接する中で、「伸びる人と伸びない人」には、どんな違いがあるかを聞いてみた。 伸びる人は自分に対する欲が深い人。「自分はもうちょっとこうしたいな」とか「こうなりたい」という欲は誰にでもあります。それを外に出せる人ほど、何かをやらせてみた時に食いついてくるんです。また、そういう人は成功した時も、失敗した時も決して漠然としておきません。失敗した時は、どうしてそうなったのかを徹底的に検証し、改善する努力をします。また、成功した時は、ただ喜ぶのではなく、どうしてうまくいったのかを振り返ることで、次の仕事を、さらに質の高いものにすることができます。自分への欲が少ない人ほど、勝っても負けても漠然とさせちゃう。そこが伸びる人とそうでない人の違いだと思います。仕事に対して、誰もが自分への欲が深くなければいけないとは思っていませんが、一緒に仕事をするなら、自分への欲が深い人がいいですね。 ―—その上で、小さな成功体験の積み重ねが大事だと島村さんは言う。 うまくいった時に、うまくできた自分に“うっとり”するこっとってあるじゃないですか。それはすごく重要なことで、心の中で“ドヤ顔”するような感覚を味わうと、人はその感覚を味わうために頑張れる。そうなれば、仕事は断然面白くなると思いますよ。 しまむら・みゆき 神奈川県出身。商業コンサルタント。株式会社ラスアソシエイツ代表取締役。ダイヤモンド社にて雑誌編集に携わった後、ダイヤルサービスグループにて小売業のマネジメントを経験。1986年、ダブルスマーケティングで、都市開発、大型商業施設開発、業態開発に携わる。90年、株式会社ラスアソシエイツ設立。都市計画、商業施設計画、業態開発等のコンセプトワークやトータルプロデュースを手掛ける。著書に『30歳から自分を変える小さな習慣』(プレジデント社)、『感性仕事術』(産業編集センター)がある。 【スタートライン】聖教新聞2016.7.9
September 8, 2016
コメント(0)
-
モハメド・アリ
“まさか”が現実になった舞台はアフリカのど真ん中だった。老いたモハメド・アリが、若き無敗の王者フォアマンを倒した、ボクシングの「キンシャサの奇跡」である。 沢木耕太郎氏の『深夜特急』に、中東の子どもたちが街頭テレビに群がり、アリの勝利に熱狂する場面が印象的に描かれている。黒人差別と戦い、ベトナム戦争の徴兵を拒んで王座を剥奪されたアリ。ふてぶてしいまでの強気の言動に眉をひそめる人もいたが、彼のそうした態度は常に、自分より強い存在に向けられた。 権力を恐れない。権威に卑屈にならない。だから弱い者、虐げられた者ほど、アリを英雄と慕った。死して1カ月の今も追悼の声は続く。 (略) アリの名言に「人間が困難に立ち向かう時、恐れを抱くのは信頼が欠如しているからだ。私は私自身を信じる」と。その言葉は、今、戦いすべての人間の胸に、拳(こぶし)のように突き刺さる。 【名字の言】聖教新聞2016.7.9
September 7, 2016
コメント(0)
-
鳥居信二郎と松下幸之助2
松下幸之助の生涯は、鳥居信二郎との出会いを忘れることはなかった。幸之助は鳥居信二郎を商いの先輩としてだけではなく、その人柄に魅了され、尊敬し続けた。幸之助の事業が成長し始めた時期も、鳥居信二郎に相談し、信二郎は十五歳年下の幸之助に助言を惜しまなかった。その二人の関係を物語る逸話がある。 二人の出会いから七十四年後のことだ。昭和五十六年(一九八一)二月一日、大坂、築港のサントリーのプラント工場の中に、鳥居信二郎の銅像が完成し、その除幕式がとりおこなわれることになった。信二郎没して十九年後のことである。信二郎は、生前、自分の銅像を作ることを嫌っていた。「あんなもんを作る金と暇があったら、格別美味しいビールの開発に精を出す方がよっぽどましや。目の黒いうちはそんなもん許さへんで」しかし信二郎が没して、二十回目の供養の年を迎える昭和五十六年、命日のある二月に初代社長の偉業を讃えて、二代目社長、佐治敬三以下、全社員が銅像の完成を願った。銅像を建てる場所も、鳥居商店、寿屋、サントリーの最初の工場であった大阪築港工場の敷地内に決定した。各所に除幕式の案内状が送られた。その中に生前、信二郎と懇意であった松下幸之助の下にも送られたが、この年すでに八十七歳になる幸之助は、商いに関わる席に一切出向くことはなかったし、公の席にもほとんど姿を現すことはなかった。そのうえ、体調を崩していっときは話をするにも側近がかたわらで言葉を訳さねばならないという噂まであった。此の前年、松下グループで全国販売店の代表を集めての恒例の決起集会が行われ、そこに幸之助が久しぶりに出席し、一言も発せずとも、じっと鎮座していただけで社員一販売店の人々が涙したことがマスコミに大きく報じられたほどだった。ところがサントリー本社に、松下幸之助、喜んで出席させて頂きます、の返書が届いた。社内が大騒ぎになった。誰より驚いたのは、社長の佐治敬三である。「まさか幸之助翁が……、そこまでオヤジのことを……」準備万端で社長以下が幸之助を迎えることになった。――体調の急変もあるかもしれない。幸之助を乗せた車が築港工場の玄関に到着した。敬三社長自ら出迎えた。 【琥珀の夢(7)―鳥居信二郎と末裔】伊集院 静著/日本経済新聞2016.7.7 参列した出席者全員の目が久しぶりに公の場で見る八十七歳の松下幸之助に注がれた。事前の打ち合わせで、幸之助が望んでスピーチをしたい申し出があったのだ。壇上に立った幸之助は顔色も良く、この式典に出席するために当人は勿論、周囲の人々がよほどの準備をしてきたことが伝わって来た。「本日は鳥井信治郎さんの銅像完成、誠にお目出とうございます・・・・・・」そこまで言って幸之助の言葉が途切れた。皆が翁を見守る中で、幸之助は、遠い目を懐かしむように語りはじめた。 「私が鳥井信治郎さんと初めてお逢いしたのは、今から丁度、七十四年前の春のことでした。私は当時、和歌山から大阪、船場に出て、二つ目の店へ丁稚奉公に出ておりました。そこは堺筋淡路町にある五代自転車店と申しました。五代自転車店と申しましても、主に舶来の自転車を扱う店でございました。自転車と申しましても、今と違って自転車に乗れる人は少くのうございました。それもそのはずで一台が百円から百二十円するという高級品で、今のお金に換算すると、五十万円をゆうに越える値段でした。その五代自転車店の上得意に鳥井信治郎さんの“鳥井商店”がございまして、鳥井信治郎さん、店でも格別高級なピアス号に乗って船場の街を疾走していらっしゃいました。或る日、丁稚だった私は、そのピアス号の修理が出来上がったのをお届けに行ったわけです。そこで私は初めて鳥井信治郎さんからよく来たと迎えられ、暖かい大きな手で頭を撫でられたことを今でもはっきりと覚えております。坊(ぼん)、気張るんやで、と励まされた時の、信治郎さんの笑顔が、今も目に浮かびます・・・・・・」会場は水を打ったようにシーンとして皆が幸之助のスピーチに聞き入った。社長の佐治敬三は幸之助のスピーチの途中で大粒の涙を目に浮かべた。「今日の銅像の見事な出来栄えと、あの空に“赤玉ポートワイン”をかかげた姿は、私が丁稚の時代に見た信治郎さんそのものです」この日の幸之助の恩義を忘れぬ出席に、佐治敬三は感激し、幸之助の葬儀の折は、その棺を自ら抱えている。“経営の神様”、世界でトップの家電製品の企業を築き上げた人物が、生涯その恩を忘れず、“商いの師”とした鳥井信治郎とはいかなる人であったのか。その話は、明治の初期まで戻さねばならない。 【琥珀の夢(8)―鳥居信二郎と末裔】伊集院 静著/日本経済新聞2016.7.8
September 6, 2016
コメント(0)
-
鳥居信二郎と松下幸之助1
松下幸之助の生涯は、鳥居信二郎との出会いを忘れることはなかった。幸之助は鳥居信二郎を商いの先輩としてだけではなく、その人柄に魅了され、尊敬し続けた。幸之助の事業が成長し始めた時期も、鳥居信二郎に相談し、信二郎は十五歳年下の幸之助に助言を惜しまなかった。その二人の関係を物語る逸話がある。 二人の出会いから七十四年後のことだ。昭和五十六年(一九八一)二月一日、大坂、築港のサントリーのプラント工場の中に、鳥居信二郎の銅像が完成し、その除幕式がとりおこなわれることになった。信二郎没して十九年後のことである。信二郎は、生前、自分の銅像を作ることを嫌っていた。「あんなもんを作る金と暇があったら、格別美味しいビールの開発に精を出す方がよっぽどましや。目の黒いうちはそんなもん許さへんで」しかし信二郎が没して、二十回目の供養の年を迎える昭和五十六年、命日のある二月に初代社長の偉業を讃えて、二代目社長、佐治敬三以下、全社員が銅像の完成を願った。銅像を建てる場所も、鳥居商店、寿屋、サントリーの最初の工場であった大阪築港工場の敷地内に決定した。各所に除幕式の案内状が送られた。その中に生前、信二郎と懇意であった松下幸之助の下にも送られたが、この年すでに八十七歳になる幸之助は、商いに関わる席に一切出向くことはなかったし、公の席にもほとんど姿を現すことはなかった。そのうえ、体調を崩していっときは話をするにも側近がかたわらで言葉を訳さねばならないという噂まであった。此の前年、松下グループで全国販売店の代表を集めての恒例の決起集会が行われ、そこに幸之助が久しぶりに出席し、一言も発せずとも、じっと鎮座していただけで社員一販売店の人々が涙したことがマスコミに大きく報じられたほどだった。ところがサントリー本社に、松下幸之助、喜んで出席させて頂きます、の返書が届いた。社内が大騒ぎになった。誰より驚いたのは、社長の佐治敬三である。「まさか幸之助翁が……、そこまでオヤジのことを……」準備万端で社長以下が幸之助を迎えることになった。――体調の急変もあるかもしれない。幸之助を乗せた車が築港工場の玄関に到着した。敬三社長自ら出迎えた。 【琥珀の夢(7)―鳥居信二郎と末裔】伊集院 静著/日本経済新聞2016.7.7
September 5, 2016
コメント(0)
-
おごれる人も久しからず
平安中期の実力者、藤原道長が摂政に就いたのは1016年、いまからちょうど千年前のことだ。「御堂関白」とよく称されるが、関白にはならなかったので、摂政就任が人生の絶頂である。有名な「この世をば わが世とぞ思ふ」との和歌を詠んだのは2年後だ。 さぞや幸せな一生を送ったかと思いきや、晩年は糖尿病を患い、痛みに苦しみながら亡くなったとか。禍福はあざなえる縄のごとし。盤石にみえた摂政政治も道長の死から半世紀あまりで白河上皇による院政に取って代わられた。上皇は思い通りにならないことを「賀茂川の水」になぞらえた。権力は所詮は水ものである。 実力者が失脚するパターンはいろいろある。シーザーや織田信長は側近に裏切られた。権力の乱用が人心の離反を招く例も多い。ちやほやされて自分は特別な存在だと思い込む。「おごれる人も久しからず」。政治学者出身でこうした法則に通じたはずの前都知事でも暴走したのだから、権力はよほど蜜の味なのだろう。 権力乱用といえば、ヒラリー・クリントン前米国務長官の私用メール使用問題が新展開を見せている。米連邦捜査局(FBI)が「訴追を求めない」と発表したが、直前に夫のビル・クリントン元大統領司法長官と会ったことが政治圧力と批判されている。何かしら口を挟まずにいられない。これも権力の一症状か。 【春秋】日本経済新聞2016.7.7
September 4, 2016
コメント(0)
-
道理の力
「道理の力」とは、いかなる権力であっても、認め従わざるを得ない普遍的な力です。それを無視して、横車を押すことをすれば、自分を損ない、滅びの道を歩んでしまいます。道理にかなっているということは最大の力なのです。しかし、正義を明確に力強く示す勇気がなければ、正義の力は現れません。だからこそ、大聖人は、金吾に、いかなる不当な仕打ちにも決して負けてはならない、と激励されているのです。 大白蓮華2016年7月号
September 3, 2016
コメント(0)
-
組織と将器
新選(撰)組のことを調べていたころ、血のにおいが鼻の奥に留まって、やりきれなかった。ただこの組織の維持を担当した者に興味があった。新選組以前には、日本に組織といえるほどのものはなかったのではないかと漠然と考えていた。あらためていうまでもなく、組織というものは、ある限定された目標をめざしてナイフのようにするどく、機械のように無駄なく構築された人為的共同体である。江戸期の藩というものはそうではない。 『ある運命について』(「奇妙さ」) *土方の新選組における思考法は、敵を倒すというよりも、味方の機能を精妙に、尖鋭なものにしていく、ということに考えが集中していく。これは同時代、あるいはそれ以前のひとびとが考えたことのない、おそるべき組織感覚です。個人のにおいのつよすぎるさむらいのなかからは、これは出てこないものです。 『手掘り日本史』(「歴史のなかの日常」)*騎兵というものを考えてみたいと思います。これは、集団的に使うと非常に強い力を発揮する。そして、その機動性を生かすと、思わぬ作戦を立てることができる。半面、騎兵はガラスのようにもろくて、いったん敵にぶつかるとすぐ全滅したりもする。ですから、この機動性を生かして、はるか遠方の敵に奇襲をかけるという場合には、よほどの戦略構想と、チャンスを見抜く目をもたなければならない。天才だけが騎兵を運用できるわけです。『手掘り日本史』(「歴史のなかの人間」)*「敵の動きは、本能寺ノ変により浮足立っております。これ自然の理ではありませぬか」「敵のみを見ている」「とは?」「味方を見ぬ。そなたは敵という一面しか見ぬ。味方が見えぬのか。物の一面しか見えぬというのは若いのだ」 『夏草の賦 下』*徳川体制というのは人間に等級をつけることによって成立している。身分(階級)を固有なものとし、それを固定することによって秩序を維持した。その人間が生まれついた固有の階級からそれより上の階級にのぼることは、ヨーロッパの封建体制ほど厳しくなかったにせよ、極めてまれな例外に属する。ただ、ぬけみちがある。庶民から侍階級になろうとおもえば、運動神経のあるものなら剣客になればよい。そういう志望者のうち何万人に一人ぐらいというほどの率で、どこかの藩が剣術師範として召抱えてくれぬでもない。 『花神 上』*兵法の真髄はつねに精神を優位へととってゆくところにある。言いかえれば、恐怖の量を、敵よりも少ない位置へ位置へともっていくところにあるといえるであろう。 『十一番目の志士 上』 【人間というもの】司馬遼太郎/PHP文庫
September 2, 2016
コメント(0)
-
祈りから始まる
頭をふればかみ(髪)ゆるぐ心はたらけば身うごく、大風吹けば草木しづかならず・大地うごけば大海さはがし、教主釈尊をうごかし奉れば・ゆるがぬ草木やあるべき(日眼女造立釈迦仏供養事、1187頁) 「我らの題目は、諸天善神を動かし、我らを、そして一家を、社会を守り、栄えさせていく。強い強い信心があれば、必ず一切の道が開かれていく。たとえ、苦しいことや嫌なことがあっても、いかなる状況になろうとも、題目を唱え抜いていくのだ。御本尊に語りかけるように祈るのだ。目には見えなくとも、願いを叶えるために、全宇宙が動く。一番、悩んだ人が、一番、偉大な人生となっていくのである。祈りから、全ては始まる」(「名誉会長と共に 新時代を開く」) 【SGI会長の指針】大白蓮華2016年7月号
September 1, 2016
コメント(0)
全30件 (30件中 1-30件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 「届くのが遅すぎて使えない…」楽天…
- (2025-11-14 22:00:05)
-
-
-

- 株主優待コレクション
- 3玉がオトク!旨辛豚つけ汁うどんを…
- (2025-11-15 00:00:05)
-