2008年02月の記事
全59件 (59件中 1-50件目)
-
割れ煎(われせん)
営業活動の一環として、金沢の引き合い先へ。とてもいいなので、帰りは下道で富山へ。その場合、金沢から森本へでて、そこから砺波へ抜ける。本当にもなく、ゆったりとした気分で運転ができた。砺波を過ぎて、ふと思いついて、ちょっとだけ寄り道。御菓蔵さんへ寄って、割れ煎を買う。最近は、いろんなところで、割れ煎を売るようになっているが、自分が最初に知ったのはここ。はじめて買いに行った時、現物を見て、これはいいと思った。確かに、割れてしまったものではあるのだが、味も変わらないし食べてしまえば同じ。しかも、安い。こんなお徳なものはない。で、いろいろあったのだが、黒糖と海苔と山葵の3つを買った。しめて、¥1860円なり。いやあ、これは食べがいがあるぞ~そうそう、形にこだわらなければ、断然お徳。野菜も果物もそうなのだ。
2008.02.29
コメント(0)
-
名札作り
ママより先に帰宅。と、帰ってくるなり「こんなんで名札作ってよ」と。ママが働いている(?)児童クラブの名札。指導員の分。いつもの調子で、よく使う素材集やネタを使いながら、いくつか、サンプルを作ってみたのだが.....もう、あ~だのこ~だの、もっと○○○にしてとか、このデザインは合わないとか...結局、そのあと20分くらいかけて、サンプルを3つ作成。プリントアウト。明日、持っていって決めてくるようだ。いやはや、毎度のこととも言え、娘の分も含めて最後は後始末係りだ。この点においては、息子のほうがはるかに上をいっている。自分で最後まで作ってしますからなあ。しかし、たかが名札とはいえ、感性ってものがあるからな~。はてさて、どんな結果になるのやら。-------------------------------------アラスカでは、歌が歴史の教科書です。(特定非営利活動法人 ECOPLUS)
2008.02.29
コメント(2)
-

【瞳みつめて】北日本新聞社
富山からはじまった、高校の未履修問題。本当に、そのときは信じられなかった。今でも、そう思いたいのだが、紛れもない事実だ。しかも、全国的に蔓延していたのだ。北日本新聞で連載されていた記事が単行本となったので、再度、読み直した。ここでは、未履修問題だけでなく、いじめや教師を取り巻く問題なども取り上げられている。子どもは、社会の鏡。大人の世界を映す、しかも、凝縮された形でだ。本当に、義務教育の義務の意味を履き違えている親の多いこと。何でもかんでも、自分たちが提供を受けるサービスだと思い、過度な消費者意識だけを持っている。おそらく、そんな親たちは、義務を果たさないで権利ばかり主張するのだろう。もちろん、そんな親たちは、ほんの一部だとは思うが、確実に増えているのだろうと思っている。子どもたちは、寂しさの裏返しとして、いろんな形でそれを表現している。自分たちで気づかないまま。そこを考えたい。
2008.02.28
コメント(0)
-

お菓子の家
お菓子の家。息子をの練習に迎えにいって戻ってみると、食卓でママが奮闘中。児童クラブでやってみるつもりなのだ。その前に1回、練習を....さすがに、息子も興味を持ったようで、見つめながらあ~だこ~だと口をだす。そのうち、こわれたもののお菓子に本当に口をだして食べたり。まあ、食べた量は私のほうが多いのだが。で、う~ん、どうみても顔に見えてしまうのだ。そういうと、ママも息子も『本当だ』平和な時間が過ぎてゆく~-----------------------------------5人に1人は、小学校に行っていません。(社団法人 シャンティ国際ボランティア会)
2008.02.28
コメント(4)
-
模倣品対策セミナーin富山
中部知的財産戦略本部のセミナー。最近、特に多くなってきている模倣品対策のセミナー。ほとんど、この方面の知識はなかったので、結構、わからないことが多かった。しかし、模倣品については、決していいことではないと思っている。が、リバースエンジニアリングによるものは、合法的な模倣であるというのにはそう、模倣品には合法的なものもあるのだ。しかも、最近は意図的に一部の機能を落としたりして、法の網の目をくぐるものもあるとか。確かに、特許権、商標権などに代表される権利関係をきっちりしておくことが第一。ただし、相手の国の法律や文化にも精通していないと、難しい場面が多いそうだ。ただ、たまに、それでかえっていい結果になる場合もあるということだ。中国、台湾、香港などをめぐるあたりがそうだ。ただ、紛争(訴訟)になった場合に費用的な問題がでてくる。裁判費用だけでなく、デイポジット。まあ、それもあるが、時間がかかるということが一番の問題なのかもしれない。それにしても、人間の弱い部分の典型かもしれないと思う。
2008.02.27
コメント(0)
-

【図書館革命】有川浩著
ついに完結。ついにゴールインって感じかな。相変わらずのぶっとび感のあるストーリー展開。いやあ、あきませんねえ。一部、予想がつく部分もありますが、まあ、それは自分を褒めておくか。しかし、そんな一方で、この本は今の時代へおアンチテーゼかと感じたのも事実。テレビを代表とするマスメデイアの姿勢や、それを受け取る今の日本。自分に直接影響がでるまでは、所詮、他人事という風潮。まあ、ある意味、想像できないのかもしれない。いや、想像できないように飼いならされてきているのかなとも。まあ、この本の主人公である郁。かつと、同僚だったある子に雰囲気が似ていて、ついつい思い出してしまう。もちろん、今はいいお母さんになっているようだ。単なるエンターテイメントとして読むのもいいのだが、そんなふうにも読めるのではないだろうか。-----------------------------------地雷は1個300円。除去は、1個10万円。(地雷廃絶日本キャンペーン)
2008.02.27
コメント(2)
-
上州牛チップス
「早く、食べられ~」息子が遠征の時に買ってきたお土産の一つ「上州牛チップス」。前回買ってきた時は、息子の友達がほとんど食べてしまったのだ。そう、一口も口に入らなかった。それを覚えていて、今回も買ってきてくれた息子。今回も、お小遣いを見ながら、いろいろ悩んだらしいのだ。そして、今のうちにパパ食べたほうがいいよということ。その気遣いが嬉しい。お言葉に甘えて、ママと一緒に食べた。ほんとうに、美味しかった子どもたちが買ってきてくれたお土産。本当のお土産だ。はてさて、どんな顔をしてお土産を選んで買ってきたのやら。
2008.02.26
コメント(0)
-
NHKプロフェッショナル アンコール「羽生善治」
とても好きな番組の一つが、NHのKプロフェッショナルだ。アンコールとして棋士の羽生善治さんだった。有名になり始め、7冠をとったころは、正直なところ羽生さんがあまり好きではなかった。へそまがりな性格のためか、あまりにも強すぎる羽生さんには、応援しずらいなあ~というのがあった。しかし、その後、時を経るとともに、そんな思いも変わってきた。羽生さんの本を手に取ったり、また、脳の研究の題材としてとりあげられたり。特に、右脳が活発に動くことが、羽生さんの特徴でもあり、それの意味するところは...のくだりが、大変興味深かった。ちょうど、右脳ブームの頃だったかもしれない。今回、再放送を見て改めて、羽生さんの一人の人間としての面がでていて、たいへん、面白かった。ここぞという時には手が震えるというのにも、人間くささを感じた。が、一方で、やはり勝負師の世界にいる人の凄さも感じた。その中で、生涯のライバル森内名人との闘い。お互いに高めあってここまできたというは、本音なのだと思う。ライバルの大切さだ。そして、羽生さんのいくつかの言葉。才能は、頑張り続けることができることだという主旨には納得。1日1時間、同じことを20年、30年やり続けえることの凄さの話とかもだ。それができる人が、いろんな世界で名人と言われるようになるんだと思う。なにがなく垣間見える表情は、どこにでもいる一人の悩み多きヒトであった。それが、親近感に繋がる。-----------------------------------熱帯雨林が問題になるより前に、インドの森はなくなっていました。(特定非営利活動法人 ソムニード)
2008.02.26
コメント(4)
-
報告書作り
明日使う報告書。しかし、その作成期限は今日の12時。まあ、監査のために使うのは15時以降とのことなのだが、その準備もあるし、何とか12時までにという依頼。土曜・日曜でやっつけようかと思ってはいたのだが、ほとんどできなかった。やっぱり、自宅で仕事はするもんじゃないよなあ~。以前は、よくやったもんだが。一応、それでも、日曜の夜に少しだけイメージ(ストーリー)を頭の中で作っておいた。ということで、会社にでてから、本当に集中したこんなに集中したのは、久しぶりかもしれない。実質3時間。以前に作っていたものも合わせながらではあるが、パワーポイントで全体で100ページほどになった。一応というか(当然というか)100ページの内容は頭のなかにある。今回の報告書は、顧客の分析とそれに対する提案。提案の骨子は、的を外していない自信だけはある。細かい点では、つめきれてはいないと思うが、限られた時間で得た情報からは、いいところかなと。お題は、IT経営に関する成熟度分析なのだが、それを考えていく中で、大抵は組織・ヒトにいきあたる。その企業の企業文化・風土といった点になる。どんなしかけを使っても、最後はヒト。ヒトが道具を使い、ヒトが判断する。そこがブレていると、どうしようもなくなる。ところが、そこが認識できていない、あるいは認識できていても対応するパワー・ノウハウがないところが多いと感じている。そこに大きなテーマがあり、と同時に、やりがいも感じるそれにして、12時にできて提出(送信)した時には、ホッとしたのが本音だった。
2008.02.25
コメント(0)
-

つらら
朝、外の軒先を見ると、つららが。長さは20センチくらいだろうか、久しぶりだ。かつては、1メートル以上のものも、結構見た記憶がある。しかし、最近は本当に稀。それだけ、気候変動の影響なのだろうかと思う。やっぱり、あるものがないとおかしい。ママの「ご飯ですよ~」の声。「は~い」と息子。一緒に、2階から台所へおりてく時に、息子と一緒につららを見た。「あっ、ほんとだ」息子の目がちょっとだけだが-----------------------------------日本の森林の8割は、手入れを必要としています。(特定非営利活動法人 ドングリの会)
2008.02.25
コメント(2)
-
おねえ と 息子
金曜の夜からおねえと息子は全く顔を合わせていない。理由は簡単、息子がの遠征に行ったから。今回は、埼玉での大会ということや開始時間のため、金曜の夜10時に(その頃は、いい気分で飲みまくっていたのだが)ニュースでもやっていたように、全国的に強風が吹き荒れたのだが、影響を受けていた。大会は、初日のみで2日目は中止。よって、群馬で練習試合に変更になっていた。そのため、富山に戻ってくるのも夜8:30で、予想よりも早かった。大会は、全国から強いチームがたくさんきていたそうで、結果はよくなかった。それでも、1試合だけだが、まるまるでたこともあり満足感はあったようだ。とにかく、風が強くて、砂が俟っていたようだ。そして、一所懸命考えてお土産を買ってきてくれた。前回の時、前々口にできなかった上州牛チップスと、銘菓高崎だるま焼き(だるまの形をした人形焼)。素直に、嬉しい。おまけに、さっさと食べたほうがいいよとアドバイス付きで。泊まったホテルはよくなかったらしいが、まあ、いろんな経験をしてきたようだ。朝はバイキングだったとか、泊まるホテルと別棟で食べたとか(本館・新館かな)。最後の夕飯は、蓮台寺SAで、ラーメンAセットを食べたとか。一方、おねえは、月曜からの期末試験モードで120%集中状態。周囲の友達に、期末試験の目標を口外して、自分を追い込んでいる。ママに言わせると、おねえのいつものやり方だそうだ。まあ、それで、何とかクリアしてきているからいいのだが。はてさて、と言いながら、夜は更けていく。
2008.02.24
コメント(2)
-

【地球人記&地球生活記】小松義夫写真集
ただただ、圧倒され、魅入られてしまった。あわせて約700頁。いったい、何枚の写真なのかまさにヒトの歴史そのものであり、今でもある。家(うち)は、その地域の人々の歴史と文化の表れでもあり、今の暮らしも表している。そう、家は巣でもあるという言葉が目からウロコだった。人々の暮らしの様子も面白い。同じカテゴリーで集めてみると、違いもはっきりするが、それ以上に同じなんだな~と思う。例えば、脱穀。同じ風景がそこに広がる。着ているものは違っても、感じるものが同じ。そう、ヒトはヒトなんだ。とにかく飽きない。何度でも見てしまう。------------------------------------アイヌ語の地名には、当時の暮らしが反映されています。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2008.02.24
コメント(2)
-
北日本新聞ニュース『県内企業、エコ事業化へ着々 間伐材を有効活用・森づくり勉強』
地元紙である北日本新聞のニュース。森づくり、エコに対する企業の取り組みの紹介記事。キーとなっているとやま森づくりサポートセンターには、個人登録と団体登録をしているので、馴染みやすい。タイワ精機さんは、工場が比較的近いところにあったり、以前、高井会長さんの講演をきかせていただいたり、とても企業としての取り組む姿勢が素晴らしいと感じている。もちろん、紙の使用枚数を減らすとかの取り組みも大切。しかし、もっと、外へでての取り組みが増えることを願ってやまない。
2008.02.23
コメント(0)
-

【ぐるぐる猿と歌う鳥】加納朋子著
装丁の絵を見ても最初はその意味がわからなかった。が、読みすすめるうちに、なんだナスカの地上絵がモチーフなのかと。ただ、あくまでモチーフであって、それが象徴するものは一体なんだろうはある。友達を守るという子どもたちの世界。そこには、子どもたちだけ、仲間だけの秘密を共有するというトキメキもある。そうそう、子どもの頃はそれだけで、なんか一著前になったような気にもなっていた記憶がある。「これは、絶対秘密だぞ。誰にも、言うなよ。」それと、夜遅くの外出。といっても、8時くらいなもんだったが。夏休みの行事とかで、そんな時間におおでをふって出られることが、とても興奮したものだ。そう、子どもには子どもの掟があるんだ------------------------------------勉強しようとしても、考えることができません。(日本国際飢餓対策機構)
2008.02.23
コメント(2)
-
飲みました!!
富山県新世紀産業機構のインターネット活用研究会の方を中心とした交流会に参加。午後にあったセミナーの講師、関口むつみさんも出席。40名近くの参加で、とっても盛り上がった会場は、なんとバンビーノナポリ料理のお店。いやあ、たくさん飲んでたくさん食べてたくさん喋った。その後、二次会でせんへ。そして、○年振りに、駅前ラーメンひげでラーメンそして、三次会へ。お店にいたのは、若い人ばかり。ちょっと、ギャップを感じてしまった。しかし、その中で、一緒にいった人(私より若い)が元気よく歌いまくった。それが、初恋はまあまあとして、なんと「憧れのハワイ航路」までいやあ、こんなに飲んだのは、久しぶりだ~仕事を離れた人たちとの飲み会は楽しい。しかも、勉強熱心な、熱い思いを持った人たち。こちらまで、元気になる。
2008.02.22
コメント(0)
-
会議のデザイン
いたるところで、たくさん開かれている会議。果たして、そのうち本当に成果のあがっているものはどれくらい社内でのある会議に、急遽召集されたのだが。時間通りに始まらない。メンバーもバラバラと。中には、何故よばれたのか知らされていない人も。途中から会議の方向もブレはじめ、何となく終わってしまった。これでは、召集をかけた人の個人的な満足()だけか。本当に、会議の生産性ということを、どれだけの人が考えているのか今、クライアント先で実践していることを勉強して、内部へフィードバックするかだ。-----------------------------------毎年200万人が、今も結核で亡くなっています。(特定非営利活動法人 国境なき医師団日本)
2008.02.22
コメント(4)
-

【さよなら、そしてこんにちは】萩原浩著
愛すべき市井の人々。う~ん、何ともなあ~、いやに親近感を感じてしまうのだなあ~。どこにでもいそうで、自分自身の中にも似たような面を見出してしまいそう。そうそう、そうだよね~と思わず声がでる。公式の顔を本当の顔。外面と内面...ではないのだが、人ってだから面白い。自分の家族を見ていてもそう思う。もしかすると、うちの家族は特別なのかな...なんて。どこか無理して突っ張ってして、ちょっとしたはずみでボロが出る。日々の暮らしのなかで、(よ~く)見かける。さてさて、今度はどんなものが見れるやら。
2008.02.21
コメント(2)
-
公開セミナー「チームづくり・人づくり」
所属しているNPO ITC富山の公開セミナーの日。今年は、富山サンダーバーズの鈴木康友監督に基調講演をしていただき、全体のテーマは「チームづくり・人づくり」。やはり、どんなしかけを入れるにしても、それを使う・作るのはヒト。ヒトができていないと、どんな道具もただの役立たずになる。鈴木監督の話は流石に面白かった。中学から高校へ進学するころからの御自分の歴史を話していただいた。全国区の高校からの勧誘の話。PL学園、浪商、天理、東海大附属.....そうそうたる高校ばかり。それから、プロ野球に入るとき。入ってから、いくつかの球団をトレードでまわり、やがて指導者となっていく。やはりその中で、長島監督と星野監督の話が多く、かつ、面白かった。もちろん、裏話も。やっぱり、星野監督は凄い。その一言に尽きる。そして、いいところを鈴木監督は吸収して実践しているとのこと。最後には、持ち歌「♪あなたの風になりたい」を1曲。高原兄さんが作曲しがつかささんが作詞した歌。1枚売れると、サンダーバーズの練習ボールが2個買えるそうで、鈴木監督には1銭も入らないのだとか。本当に、監督、選手、スタッフ全員苦労しているのだ。応援したくなった。セミナー終了後の懇親会も楽しかった。いやあ、それにしても、何かに熱中している人はカッコイイ~------------------------------------火ぶり漁では、かご1杯以上の魚は獲らないことがルールでした。(特定非営利活動法人 ECOPLUS)
2008.02.21
コメント(0)
-

【ラスト・イニング】あさのあつこ著
中学生から高校生になる頃のこと。正直、あまり思い出せない。しかし、小さな中学校から進学した高校へは自分一人。しかも、通学に1時間はかかるところ。それでも、気がつくと、学校になれ友人もでき楽しんだ3年間だったように思う。じつは、この本がバッテりーのその後...なのだとは知らずに借りて読んだ。バッテリーも気になりながら読んでいない。しかし、これはこれで単独でも十分面白い。きっと、こうなんだろうなあ~と想像しながら読むことができた。それも一つの読み方だと思う。不器用な天才と、器用するぎる秀才とでも言えばいいのかなあ。そんないろんなキャラがいい味を出している。
2008.02.20
コメント(2)
-
プロの運転?
朝、通勤の途中、会社近くの交差点。片側2車線で、交差点の中央側は右折車線。なので、左側車線が通行車線となっている。ところが、その信号のかなり前から明らかに右側車線をつっきろうとする勢いの大型トラックがバックミラーに見えた。そして、案の定その交差点の右折用の車線を凄い勢いでつっきっていった。車には丹保運輸という文字が.....あれだけ、大きく書いてあるのにトラックなので、運転席も高く交差点のラインなどもよく見えるはずなのだが、最初から止まろうとする感じは、微塵もなかった。ふと、プロの運転ってと思った。トラック、バス、タクシーだけでなく、営業車両はもちろんのこと。一般の我々も、ある意味プロに近いのかなと思ったり(通勤)。そういえば、携帯電話を操りながら運転している大型トラックもよく見かける。もちろん、一般車両はしょっちゅうなのだが。プロの運転とはと考えた瞬間。以前にも、すごい運転をしていた営業車両を見て、その会社の車を見るたびにその時のことを思い出してしまう。ひとりひとり。たった一人の行動が、すべてを決め兼ねないのだ。------------------------------------自動販売機1台は、家庭の電気の半分以上を使います。(エコプラットフォーム東海)
2008.02.20
コメント(2)
-
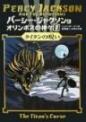
【パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々(3)タイタンの呪い】リック・リオーダン著
ついに、このシリーズの3作目。読むほうとしても、キャラクターが頭の中にあり、読みやすくなってきた。あまけに、出版社サイトの中に専用サイトまで立ち上がっていた。世界の空を支えるという役目。果たしてどれくらいのものなのだろうかそんなことなど、微かな記憶として神話の一端が脳裏をかすめる。神に仕える身。それをよしとする世界もあるのかもしれない。そんなことを考えつつ、果たして、ギリシアの神々は何を象徴しているのだろうかと考えたりもする。今の人間の驕り昂ぶりが目に付く今こそ、パーシーの出番かもしれない。
2008.02.19
コメント(0)
-
過信
朝の通勤。いつものルート。対向車線の流れが、いつもと違う。婦中大橋西詰め。片側2車線。反対車線の路肩に、4輪駆動の車が車の後ろをこっちにむけ、路肩に乗り上げ亀の子状態になっている。おまけに、車のヘッドライトの1個が、こっち側の車線にまで飛んできている。状況からみて、事故が発生してからあまり時間がたっていないようだ。おそらく、交差点をまがってスリップなのかどうなのか...という風に見えた。ただでさえ混雑する路線・時間帯だ。雪が少なくなり、天候もよく、しかも4駆ということなのか。慣れからくる気の緩みなのか、過信なのか。9時頃、顧客先へ行く車のなかでラジオを聞いた。交通情報でその事故のため、知覚が混雑していると言っていた。ちょっとしたことが、大きな影響になる。慣れた頃が一番危ない。-------------------------------------見えないプランはないのと同じです。(特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会)
2008.02.19
コメント(2)
-

【ぼくの家は「世界遺産」】小松義夫著
私の住んでいる家は木の家だ。だから、家全体が生きていて、何故かホッとする気分がする。以前、2年程だが、大阪は森之宮の公団住宅に住んでいたことがある。もちろん、冷たい感じがした。空気自体が、冷たいように見えるのだ。この本に出てくる家。1 楕円形の家/2 森に浮かぶ大きな家/3 壁のない家/4 壁絵のある家/5 泥の厚い壁/6 曲がったことが好き/7 移動する家/8 泥の空間/9 目がある家/10 ワラの家でれもこれも、文化の現われでもある。長年の暮らしの中で残っている家。残るということは、残るだけの理由がある。一言で言うと、快適なんだと思う。人が住んで快適でないと残るはずがない。もちろん、快適さの意味するところは、いろいろあるとも思う。しかし、それ以外に表現する術を見出せない。やっぱり、木の家が一番だ。------------------------------------一つの家には、一つの世帯が住むのがふつうでした。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2008.02.18
コメント(0)
-
NHKスペシャル「謎の海洋民族モーケン」
NHKスペシャル「謎の海洋民族モーケン」を見て、やっぱり人間は海からやってきたのだと再認識した。数少ない海洋民族。生物は、母なる海に発生し、やがて陸にあがってきたのだ。海の中を自由自在に泳ぎまわるをみていると、一層その思いが強くなる。何千もの島々を、その形だけで覚えていると言うのも凄い。そして、どこに何があるのかも。自分たちが生きるためだけに、獲物をとる。「海は生きていくのに必要なものを与えてくれる」という主旨の言葉が耳に残っている。そんな彼らの暮らしも、世界経済(特に中国)の影響を受けてきている。商業主義に走っている大型漁船がやってきて、ごっそりとっていってしまう。そんな姿をみると、憤りすらかんじてしまう。確かに、海の皆のものではあると思うが、だからといってとったもの勝ちみたいなものはどうなのだろう。もちろん、そんな彼らも生きていくために漁船を出しているのだ。そんなことを考えると、なんとももどかしい。「今の暮らしを変えるつもりはない」というモーケンの人たちの言葉が痛い。
2008.02.17
コメント(0)
-

雪すかしとトンカツ
少し冬らしくなって、雪が積もった。さすがに、雪すかしをしないといけないくらいになった。朝、ママに「着替えられ」と言われていた。そう、パジャマのまま。「出番だよ~」と息子に言うと、「わかった~」と返事。外にでで、除雪機を動かしていると、万全の装備で外へでてきた。そう、みなまで言わなくても、わかってくれたのだ。息子ももう2/3人前くらいの働きをしてくれるので、大助かり。それに、いくらでもやっているのだ。をやっているので、体力もついたよなあ~。1時間あまりやって終了その御褒美か、夜はトンカツに。ということで伊志井へ買出しに。暖簾をくぐると、マスターがいつもの調子で。で、特大トンカツ2人前、ヒレトンカツ1人前、エビフライ1人前、しめて5300円。帰りの車の中は、いい匂い。やっぱり、美味しかった息子も、エビフライを食べ、トンカツもぱくぱくぱくと....
2008.02.17
コメント(0)
-

【うちへかえろう】小川内初枝著
目に飛び込んできた装丁。黄色いバス、それも小さな子どもが書いたような。「家」でなく「うち」という言葉にも反応してしまった。小さい時、1日外で遊びつかれて「うちへかえろう」っと言った記憶。独特に響きと、家族の温もりがそこにあるからだろう。人という字に成り立ちはよく言われるが、やはり一人ではないのだと思う。ふれあい、支えあい、励ましあいなどがあるからこそ、生きていける。もちろん、一人でも立派な人は沢山いるだろう。しかし、自分はそうではない。周りに沢山の人がいて、家族がいるからこそだ。------------------------------------食べる量は40パーセント減りましたが、穀物の輸入は6倍に増えました。(日本国際飢餓対策機構)
2008.02.17
コメント(0)
-

メタルクラフト(折り鉄)
昨日から新川文化ホールで開催されていた「2008ポリテックビジョンin新川」。北陸職業能力開発大学校の研究発表を中心としたイベント。今日は、「ものづくり体験フェスタ」があるので、息子と出かけた。が、昨日は乗り気だったのだが、いざとなると、面倒くさそう。何とか受付開始の9:45過ぎに到着。しかし、既に長蛇の列ができていた体験できるのは、メタルクラフト(折り鉄)、メタルパズル、フォトカレンダー、写真入り缶バッジ&クリアキーホルダー、アルミ製ロボットハンド、ふりふりカード、メロデイ雪だるま、電子鉄琴、超音波探知機、私だけのオルゴール、ライントレースカー、LED点滅回路の12種類。狙っていたのは、アルミ製ロボットハンド。しかし、受付の時点でそれだけが定員完了となっていたのだ息子と同じくらいの子も多かったからなあ。で、結局、メタルクラフトに挑戦。型抜きされている金属の板をペンチで折り曲げて熊を作るのだ。北陸能開大の学生たちが、サポートしてくれる。まずは、金属片を紙やすりでこすって、バリを取る。やり始めるやいなや、息子の顔が真剣な顔つきに変わった。なれないペンチを使って金属片を曲げて...完成品のサンプルをよ~く見て...最後に胴体と顔の部品を合体して...本当に、途中から、真剣ななかにも笑顔も混じって楽しんでいた様子。学生さんたちも、小さな子どもたちに丁寧にサポートしてくれ、とても好感がもてる。ものづくりに励む学生さんたちに、明日の希望を感じた。息子も、なんのかんのと、やりはじめれば楽しむ。そこまでが、億劫なようだ。(と、自分でも言っているから間違いない)そのあと、ロボット対決を見ようかと思ったが、時間があいてしまい、練習風景を少しみてかえることに。丁度、お昼頃だったので、近くのアピタへいき、麦の屋さんでお昼。私は、カレーうどん、息子は天ざるそば。う~ん、美味かったおまけに、たいやきも今年初めての参加だったが、来年もまた来よう。
2008.02.16
コメント(0)
-

【いま伝えたい大切なこと】日野原重明著
医師として70年。日野原先生の本を久しぶりに読んだ。70年という経験の重みと思いの深さが伝わってくる。文章は、とてもわかりやすく平易なのだが、それがかえって先生の思いをよく伝えてくれる。いのち・時、そして平和。実は、どれもとても伝えることが難しいテーマだと思う。果たして、自分が自分の子どもたちに伝えるとしたら、どんな言い方になるんだろういのちは、自分だけのものではない。生き物という全体の中の流れの中に存在するもの。過去からきて、未来へ繋がるものだ。時。そんないのちの発現が時なのかな。そして、平和。いのちを考えれば、おのずと平和についても考えることになる。日野原先生は、反戦ではなく非戦とおっしゃっている。非戦は、反戦以上に厳しい。表現がまるっきり反対だと思う。果たして、この日野原先生の言葉に反論できる政治家・官僚・財界人はいるだろうかきっと、いないんだろうと思う。まずは、自分から------------------------------------人から人へ、1万年です。(おかざき匠の会)
2008.02.16
コメント(6)
-
海老天(Jupitor)
最近、息子がはまっている替え歌。もちろん、毎回即興なので、同じ歌詞は二度とない。もとの曲は、平原綾香さんのジュピターなのだが。最初の「everyday」が、息子には「エビテン」に聞こえるらしいのだなるほど、そう聞こえないこともないか。そして、そのあとは天丼、テンプラの具シリーズとなる。例えば....「海老天、イカ天、天丼、シシトウ、サツマイモ、・・・・・」となるのだ。こればまた、不思議なくらい曲にあっている。そう、原曲の惑星-木星に。当分、続きそうだ
2008.02.15
コメント(2)
-
泥んこ雪合戦
今日は、小学校の授業参観のため、帰宅が少し早かった息子。で、同じ学年の中でも大柄な子が3人遊びに来ていたらしい。息子のそこに混じると、チビすけになってしまう。そして、雪合戦をしていたとか。まあ、ゲームばかりしているより、ずっとマシだと言うのはそこまでだった。確かに、雪はあるのだが、今年はあんまり積もらない。そのためか、気がつくと、家の周りの田圃を走り回っていたのだ。おかげで、全身とまではいかないが、泥んこだらけでズボンとかもズクズク状態。そのまま玄関に来たらしく、玄関は泥の足跡だらけになっていた。でも、まあ、それぐらいエネルギーを発散するので丁度いいのだ。最近は、泥んこだらけになることも、めったにないだろうし、まあ、洗濯が大変なだけかな。遊びにきていた3人のうち2人がもう1人に集中攻撃をしたらしい(もちろん、お遊びで)。が、少しだけ、度がすぎたのか、その子がメソメソ状態に。それを見たのか、その2人も直ぐにやめ、そのあとは随分と優しくしていたらしい。基本的に、もともと仲のいい子たち。そこで、直ぐに止めることができるのだ。そんな気持ちを持った子どもたちであることが嬉しい。そんなこんなを、後から聞いたのだが、もっともっと田圃の中を走り回ってほしいくらいだ。
2008.02.15
コメント(2)
-
息子の創作童話(ショートショート)
風呂に入りながら、息子から聞いた。「朝ね、創作童話、おねえちゃんとママにバカ受けしたよ」と。「どんなの」「むかしむかし、あるところに、誰もいませんでした。おしまい。」な、な、なんと、表現のしようがないのだ。とにかく、おねえとママは大爆笑だったらしいのだが....う~ん、もしかして、この面白さがわからないというのは...なのかも------------------------------------緑のボランティアを、育てています。(特定非営利活動法人 地球緑化センター)
2008.02.15
コメント(0)
-
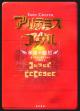
【アルテミス・ファウル(永遠の暗号)】オーエン・コルファー著
やはり、英国系だからなのか、ハリー・ポッターとも相通ずるところがある。妖精とか.....あいかし、味わいはかなり違う。天災少年と言ったほうが正しいくらいの天才少年とその周囲を飾るキャラクターは、何ともいえない味わいがある。その姿を想像しながらファンタジーを読むのも、醍醐味の一つかもしれない。この本は発売されて直ぐ買った。そして、おねえが読んでから、ずっと読む対象になりながら、なかなか手をつけていなかったのだが、ようやく、出張の汽車でといういい機会に読むことができた。なんか、肩の荷が一つ無くなったようにさえ感じてしまう。おっと、そんなやつが、まだ何冊かあるのだ。さっさと、片付けてしまわないと。と、思いながら、このシリーズを第4作を買ってしまったのだ
2008.02.14
コメント(2)
-
東京まで日帰り(セミナー受講)
セミナー受講のため東京まで日帰り。の影響もあんまりなくてほっとした。中小企業基盤整備機構の虎ノ門セミナー。「中小企業のための実践的なASP・SaaS活用法セミナー」で、これからの流れの一つとして知っておくべき。特に、今回はユーザーからみた視点での内容でもあり、関心を持った。ASPが始まった頃とは比較にならないほど、その多様性が拡がっている。業務的にも、提供されるサービスの種類(カテゴリー)も、カスタマイズ性、導入スタイル、相互連携、ビジネスモデルなどなど。これも、いろんな意味でITの技術的な面での進歩があるからだと実感。ITのビジネスにおける役割(考え方)の拡がりとも繋がっている。今回、アワードを受賞したサービスを見ても、面白い。個人的に面白いと思ったのは、積載シミュレーションだ。荷物の寸法と重量を入れると、コンテナへの最適な積載を返してくれるというもの。なんだか、ゲームのようでもある。あとは、やはり携帯を使ったもの、トレーサビリテイ、CRMあたりが耳に残った。それとネーミングも面白い。バイバイタイムカードなんて、わかり易くて最高だこの動きを注視していかないとそれにしても、行き帰りの列車では、いくつか気づいたこともあった。1番目は、やはり受験生の姿だ。思わず、がんばれよと念じてしまった。ほとんどが、お母さん方と御一緒のよう。自分は、一人でいったけどな~2番目は、グループで大きな声でワイワイの人たち。聞こえてくる会話からすると、富山県内の市町村の職員のようでもあった。市町村名や部署名、関連団体名や事業名などがポンポンとでていた。そんなことを列車の中で大声で喋るというのは、信じられないのだが....
2008.02.14
コメント(6)
-
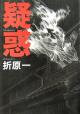
【疑惑】折原一著
短編集。ミステリーになるのか、どういえばいいのか。まあ、スラスラと読めたのだが、読めてしまったというところ。なるほどねえというオチなのだが、ああ成る程ねと。ただ気になったのが一つ。石田黙という画家。不思議な絵。-------------------------------------いのっていれば、平和はやって来るものでしょうか。(財団法人 世界宗教者平和会議日本委員会)
2008.02.14
コメント(2)
-
おねの格闘 午前様
帰宅すると台所からシャカシャカと音がする。んっ この音は案の定、おねえがケーキ作りに励んでいる。先日から、何回も練習。ママに言わせると、以前はもっと上手だったのに、集中していやってないから...なのだ。友達同士でそれぞれ作ってくることになったのだ。そのうち、部屋へやってきて今度はにへばりつく。吹奏楽部の定期演奏会(3月末)のパンフのメンバーの名簿作り。これも、途中まで少しやっていたやつ。「パパ、あとでこれCDに入れといてね」の一言付で。そのうち、12:00近くになり、風呂入るからと「あと直しといて。課題もせんなんし...」の言葉をおいて行ってしまった。一応、気のつくところは直したのだが、確認が必要になったので...おねえは風呂からあがり、台所でケーキの後始末に入った。そして...最終的にCDに名簿をおとしたのが午前1:30。いやはや、眠いのなんのって
2008.02.13
コメント(4)
-
補導員研修
19:30より、富山市補導員連絡協議会第8ブロックの研修会。今回の主題はケイタイにかかる件について。何かと話題にのぼるケイタイ。いまや、ケイタイ依存症の人が圧倒的におおくなってきているのではないかと思う。片時も手放すことができない人。そのケイタイを経由した犯罪の恐ろしさだ。富山南警察署からもきていただき、お話をうかがった。全国、県内、管轄内の犯罪の状況についてもあった。平成9年をピークにして件数自体は減ってきているということだった。ただ、マスコミにとりあげられる内容にもあるのだが、やたらセンセーショナルに伝えられる傾向もあるのだと思う。それが、さらに、同様の犯罪を誘発するのかも。一方、自分だけは大丈夫という過信も。さて、意見交換の中でもいろいろ意見もでた。・取り締まりを強化する⇒罰則の強化・親自体が問題である・メーカー自体の姿勢 などなどふと、司会者から自分にも意見を求められた(よく知っている人なので)。自分は、正しい使い方を知らせることから始めたいと。知らせることもなく禁止するだけでは、いい方向にはいかないのではと思う。また、大きな課題として、PTAとかでもそうなのだが、学校にこない親御さんたちへ、どう伝えるかのだ。こちらへ向いていただける人を、一人ずつどう増やすかだ。そんなことなどを述べさせていただいた。一番の課題。具体的な行動をどう起こすかだ。-----------------------------------爆撃訓練で、島の3分の2が消えてしまいました。(東アジア環境情報発伝所)
2008.02.13
コメント(4)
-

【激走福岡国際マラソン】鳥飼否宇著
凄い臨場感がある。息遣い、足音、思考、精神、肉体。そして、隠された人間ドラマまでも。それにしても、最後のオチは想像できなかった。果たして、人はそこまでふんぎることができるのだろうか。あくまでフイクションの世界か。しかし、時として、真実はフィクションを超えてしまうこともある。中学の頃、陸上競技をやっていた記憶が蘇った。年齢的に言うと、長距離の種目。マラソンの感覚(この本の中)も少しは感じ取れた。-----------------------------------8秒に1人。汚れた水が原因で、子どもの命が失われています。(日本トイレ協会)
2008.02.12
コメント(2)
-

【いつか、キャッチボールをする日】鯨統一郎著
キャッチボール。たま~にだが、息子とすることもある。息子はなので、あまりは上手くない。が、それでも、やはり男の子だけあって、投げる球は結構力がある。ただ、捕るのはいまいちかなあ。をする時もあるが、やはりキャッチボールは一味違う。心と心が通い合うみたいなところがある。それにしても、切ない物語だ。父と息子の関係は、こんなふうになるのかもしれない。そんな父親でいるようにしたいものだ。最後の最後には、本当に涙が出てしまった。
2008.02.11
コメント(4)
-
映画「earth(アース)」
一番初めの時間帯を狙って、映画「earth(アース)」を観にいった。思ったより人がいて、素直に嬉しくなった。それぞれ、どのような思いを持っているのかはわからないが、地球を大切にしたいという思いは共通していると考えている。見方によっては、淡々とした描写が続く映画で終わってしまうかもしれない。とにかく、画像が綺麗なのだ。これが、本当の色なのかもしれない。もちろん、そんな綺麗事だけの場面ではない。ママには多少不満だったようだ。おそらく、もっとメッセージ性を表に出していることを想像していたようだ。しかし、途中、つまらなそうにしていた息子も、キッチリと観るところは観て、感じるものも沢山あったようだ。もともと、動物がでてくるものは好きなのもある。この3連休の宿題の一つに日記があったのだ。その日記に、この映画のことを書いていた。その日記を読んで、感動してしまった(親バカかも)。映画「earth(アース)」を観て、厳しい大自然の中で動物たちが一所懸命に闘いながら生きている。サバンナでの生死をかけた闘い。南氷洋ではオキアミやプランクトンが、温暖化の影響でおおきな影響を受けている。本当に、地球を守るためには、温暖化を止めなければならいと思った。と書いていた。数年前から、森を守る活動にも、一緒に参加したりしている。息子は大いに楽しみながら、これからも行くと言ってくれる。そんな気持ちをずっと持ち続けられる人であってほしいと願っているし、そのためには、自分も続けていくるもりだ。この映画は、観る人によって、随分と感じるものも違う映画だと感じている。
2008.02.11
コメント(2)
-

【林住期】五木寛之著
四。不思議な数字。起承転結、東西南北、春夏秋冬、四天王...もちろん、他の数字でもいろいろある。古代インドでは、人生を四つの時期にわけているのだという。学生期・家住期・林住期・遊行期。それぞれが約25年。つまり、今のこの国で、いい意味でいわれていない第3の時期「林住期」こそ一番大事な時。最初のふたつは、その準備の時期なのだと。ちょっと前に、会社の上司から「定年後のことも考えて、いろいろ準備をしようと考えたりもしている...」というような言葉を聞いた。もちろん、ほんの少しではあるが、地域とのつながり、地域以外のこれまでと違う人たちとのつながり、もちろん家族のつながりをひろめてきているつもりだ。そんな一旦を話すると、「そのエネルギーが凄いね...」と言われた。そう、そうなのだ。仕事やその延長線上だけでは、つまらない。まさに、いいタイミングでこの本で出合えたように感じる。-------------------------------------マンモス以降、絶滅の原因は人間にあります。(特定非営利活動法人 生態教育センター)
2008.02.11
コメント(2)
-

白鳥
昨年の冬から来ている白鳥を見に行った。自宅から3キロほどの田圃。3枚に水がはってあり、立て札もたっている。最初は乗り気でなかった息子も、いざ実物を見ると興味深く見ていた。丁度、朝、所さんの目がテンで白鳥を取り上げていたので、グッドタイミングだ。実際に目にすると、やはり思っていた以上に大きい。それと、首がやたら長いのだ。勘定してみると、約55羽。いろんなやつがいるようだ。まだ、寝ぼけているようなのもいれば、じっと周囲をみているもの。つがいかと思われるものや、背伸び(?)をしているもの。やっぱり、実物が一番だ。これからも、毎年きてほしいものだとこころから思う。
2008.02.10
コメント(4)
-
古老の島 祈りの島 ~沖縄西表島 都会の青年と伝統の暮らし~
NHKのETV特集の短縮版再放送を見た。東京出身の若者が、西表島に移住してからの記録。沖縄県西表島。イリオモテヤマネコが脳裏に浮かぶ島。そこに移住して、少しずつ島の人間になっていく様子がよくわかった。そんな暮らしの中で、移住してきた中坂さんと奥さんの言葉が印象的だ。「おじいに怒られてばっかり。若者は怒られるのが仕事だから。何にも知らないから。」それに耐え切れず、元に戻っていく人が多いのだという。「ここはコンビニもなんにもない。だからいいのかも。」という奥さん。「何にもないから、身体を動かさないと生きていけない。そうやって、少しずつ覚えてきたんだ。」「ここで子どもたちが生まれた。その子どもたちに、ここの素晴らしい景色を見せてやりたい。それが自分たちの責任だ。」観光客もいなく、自分たちのために祭りをやる住民。そして、その裏方の中心になっている中坂さん。「少しずつ、村の人たちの中に入れたかなと思う。」どれもこれも、重い、実体験からきている言葉だ。だからこそ、こころに響いてくる。
2008.02.10
コメント(0)
-

【このくにの姿】筑紫哲也対論
読後感は、今このくにの方向を決めている人たちは、実感を伴わない人たちだということ。だからこそ、おかしなふうになっているのだ。正直、あまり知らないままではあるのだが、個人的に好きでない人もいる。しかし、ここで述べていることには、賛成できる部分もたくさんあることに、自分自身驚いている。例えば、中曽根康弘さん、渡邉恒雄さんがそうだ。その主張には納得できない面もあるのだが、お二人の根っこにあるのが、戦争経験だ。そこから今の風潮に危惧を発している。いま、戦争のことを是とする人たちに、真っ向から反対している。それも、実体験からきているものだけに、説得性がある。養老孟司さんのは面白かった。目からウロコ。フランス(ヨーロッパ)では自由・平等・博愛を訴えているのだが(トリコロールでもある)、そもそも、それらがないからこそ、そう主張しているのだと。確かにそのとおり。他の方々のも面白い。知的刺激に溢れている。そして、一番驚いたこと。立花隆さんとの対論の中のこと。安倍政権は長く持たないかもしれないということだ。実際、そのとおり、予言のごとくだ。全体を通して感じたことがある。このくにの姿を決めるのは、自分たちだということ。そして、子どもたちにつなげていかなくてはならないということだ。森のゆめ市民大学の学長でもある筑紫さんからいただいた本(私の名前と筑紫学長のサイン入り)、ようやく読むことができた-------------------------------------リサイクルは進みましたが、ごみの量は減りません。(国際環境NGO FoE JAPAN)
2008.02.10
コメント(0)
-
位置づけ
夜9:30。毎月の定例ミーテイング。昨年の7月より始めた。年があらたまり、新年度の計画もスタートし、日々の事業は進んでいる。昨年の秋から年度計画作りが中心のテーマだったが、今期の計画作成とはまだまだ融合していないまま。このミーテイングの性格も改めて定義しなおす必要もある。昨年の結果を踏まえてでもある。前半は、あいまいなままの内容に終始した感は否めない。ただひとつ、社長の思いを再度語ってもらい、メンバーの意識あわせはできたように見えている。そこを我慢して、今日の本当のテーマにふった。このミーテイングの位置づけ。いろんな意見がでた。が、最終的には、メンバー全員での意識あわせができた。それまで、ちょっと淀んだ感じの空気が、確かに変わったのを感じ取れた。一緒にサポートしてもらっている人も、そんな顔つきである。おおむねの目的は達成できたとは思う。しかし、一番大事なことは、次回以降、キッチリとその方向性を守ること。確実に行動につなげること。そんな意味で、100%よかったと思って終わることはできていない。それが、自分の役目だとも思う。
2008.02.09
コメント(0)
-

【パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々(2) 魔海の冒険】リック・リオーダン著
第1巻の勢いそのままに、第2巻に突入。気がつくと、最後のページに達していたストーリー展開はそのまま、ワクワクドキドキ感が堪らない。そして映像を想像しながら読むのも、とても楽しいし、映画化されるようなので、是非見てみたいものだ。神々がどのように描かれるのだろうか、興味は尽きない。ダレン・シャンとハリー・ポッターの味わいも少しあるのかな~と勝手に思ったりもする。まあ、これは100%個人的な読み込みの仕方(解釈)によるものだから、あてはまらないかもしれない。
2008.02.09
コメント(2)
-

【パーシー・ジャクソンとオリンポスの神々(盗まれた雷撃(ライトニングボル)】リック・リオーダン著
ギリシア神話のオリンポスの神々が今もいる、しかもアメリカにという設定からして面白いんだろうなあと思った。それにしても、このスピード感はいいなあ。ただ、これを読みながらついついハリー・ポッター、ダレン・シャンなどを思い浮かべてしまう。ファンタジー。少年・少女を主人公に(当たり前か)、その成長とともにストーリーが展開する。まあ、この本の場合は、設定が現在のアメリカということもあり、最近の出来事やいろんなものがとりばめられていて、イメージがわきやすい。実感とまではいかないが、距離感がぐんと近いのだ。しかし、本当に、オリンポスの神々がこんな感じだったらと思うと、楽しくなるかもしれない。まあ、このての本を読んで楽しめるというのは、こころが健康な証拠かもしれないなんて思ったのだが。------------------------------------火ぶり漁では、かご1杯以上の魚は獲らないことがルールでした。(特定非営利活動法人 ECOPLUS)
2008.02.09
コメント(0)
-
弁当
去年の4月から弁当を持つようになった。ママが作ってくれている。「一つも三つも一緒だから...」と。最近、仕事の関係でお昼が外のことが多い。午前中、お客さんのところで打ち合わせなどをして、移動の時間帯が丁度、お昼の時間。会社に戻るには、時間が遅いし...という頃合が多い。結局、公園の駐車場とかを止めることができる場所で、食べることになる。まあ、まわりをみると、結構同じように車の中でお昼を食べている人も多い。工事関係の人だけでなく、営業の途中みたいな人も。しかし、最近は外気温も低く、弁当は冷たくなってしまう。(保温付きではないので)それでも、会社の食堂やコンビニの弁当よりは、美味しいと思う。自宅というか、ママの味付けに慣れている(当然なのだが)こともあるし、まあいろいろだ。そう思いながら、はてさて高一のおねえは、どう思っているのだろうかと考えてしまった。-------------------------------------日本を食べさせるために、世界の水が使われています。(日本国際飢餓対策機構)
2008.02.08
コメント(2)
-
中小企業BCP策定セミナー
中小企業向けのBCP策定セミナーを受講。サブタイトルは~中小企業の事業継続と社会的信頼性向上のために~。BCP。事業継続計画。昨年春に、会社のセミナーでこれに関することで、セミナーの講師役を務めたこともあり、概要は理解している。ただ、あくまで概要でもあるし、いろんなセミナーに出ることで、理解も深まるし違った視点を学ぶことにもなるので、参加してみた。少しではあるが、新しい視点をえることができたのは収穫だ。いろんな要素がある。ここ数年であれば、両隣の県で地震が続いている。また、インフルエンザやいろんな病気のこともある。天災、人災いろんなことが可能性としてある。そのうち、どこまで考えて対応策を考え手を打っておくかがポイントだ。備えあれば憂いなしではないが、考えておくことの意味はあると思う。実際、その場面になった時、どこまで有効であるかは実際のところはわからない。ただ、何も準備しないでいるよりは、いいのではないかということだ。例えば地震。工場がつぶれる。道路が寸断される。ライフラインがやられてしまう。事業を継続する以前のこともたくさんある。しかし、人は生きていくためには、生産活動が必要。それを、いかに速やかに復旧するか。大きなテーマではある。が、少しずつでも、考えることだと思う。
2008.02.07
コメント(2)
-

【なんで子どもを殺すの?】猪熊弘子著
哀しいことではあるが、「子殺し」「親殺し」のニュースも珍しくなくなってしまったこの国。そんな中で「スズカ」を題材にして、そこに潜むものについての考察がされている。実は、誰にでもあるもの。心の中で「子殺し」をしている場面も、実はたくさんあること。ただ、その時に、実際の行動としてどうするかで、その後が一変する。キーワードとして『乖離』と言う言葉がでてきている。乖離。自分が自分でなくなる、本当の自分がわからなくなる。自分を子どもに投影したり、自分が受けていることを投影したり。自分自身との乖離状態。いいふるされた言葉だが、自分を見つめることからしか始まらない。そして、夫婦の役割・関係。劇薬ではなく、抗生物質のようなと書いてある。そう、じんわりと効くという言い方が、一番フィットしているのだと実感。何事も、ゆっくり、さりげなく、日常的にが一番だと思う。-----------------------------------一つの家には、一つの世帯が住むのがふつうでした。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2008.02.07
コメント(2)
-
クローズアップ現代「ソフトウエア危機」
昨日の夜に放送されたNHKクローズアップ現代。テーマはソフトウエア危機~誤作動相次ぐハイテク製品~IT業界に身をおくものとして、身につまされる内容だった。朝、出社してみると、その話題も結構でている。が、違和感があった。最後のほうは、メンタルヘルスに関するほうへシフトしていた内容について、面白くなかったというような評価が多かったのだ。正直、愕然とした。ソフトウエア構築のための手段とかルールのことばかりが頭にあるのだろうと思った。それをつくるのは人であり、人に優しくないものは、必ず綻びがくると考えている。そんな自分の思いと、反対側にいるのだろう。ますますIT業界自体への疑問も感じている今日この頃。人間を基本に考える姿勢がますます薄くなってきていると感じてしまう。効率化・ルールというお題目の前では、すべてが無視されてしまうのだろうかそんな空気の中でも、そまるつもりはない
2008.02.06
コメント(0)
全59件 (59件中 1-50件目)
-
-

- 今日どんな本をよみましたか?
- 『人生後半の働き方戦略』(都築辰弥…
- (2025-11-14 21:00:06)
-
-
-

- 読書
- 「今、読んでいる単行本ですぅ ㉓」
- (2025-11-14 21:14:19)
-
-
-

- 人生、生き方についてあれこれ
- 過去への思いと現在を生きる意義
- (2025-11-13 12:41:44)
-








