2008年03月の記事
全68件 (68件中 1-50件目)
-
アンケート結果
おねえの部屋の床にほってあった(置いてあったのか)1年4組の文集。2年になるとクラスも変わるので、みんなで思い出づくりかな。同じ様式を使った一人1ページのプロフィール。自筆なので、それぞれの子の個性もにじみでている。おねえのは、いやまあ、すっとんでいた。本当に、クラスが学校が楽しくてどうしよーもないのが、あらわれている。そして、そのあとが面白かった。クラス40人(女子のほうが若干多いかどうかくらい)のアンケート。いろんなテーマで人気投票した結果だ。カテゴリーは、いやまあ、笑ってしまうくらい楽しい。そして男女それぞれベスト3までの名前がでている。おねえの名前がのっていたカテゴリーは次のとおり。優しそうな人 2位料理上手そうな人 1位やさしい母になりそうな人 1位母にするなら 1位姉にするなら 1位どげんかせんといかん 2位アジアンビューテーな人 3位そう、かわいい人とか、そんなのはなくて、どう思われているかハッキリわかる。ママと2人で見ていて、同じ感想を持った。みんな、勘違いしてるねえ~。外面いいからなあ~。さてさて、そんなふうに育ってくれればいいのだが。
2008.03.31
コメント(0)
-

【イカの哲学】中沢新一・波多野一郎著
イカの哲学そのタイトルに惹かれた。新聞の書評欄で紹介されていた中の1冊。読んだ感想。難しい本だ。しかし、難しいながらも、伝わってくるものは、とても深い。生命の根源からくるもの。生きとし生けるものすべてを尊重することに始まるのではと思う。動物、植物、鉱物、そんな区分はちっぽけなもの。存在するすべてのものを尊重する。こんな本を、よく中沢さんが世にだしてくれたと感謝する。机上の、理屈だけの戦争論・平和論は、この哲学の前には跡形も無く消え去るのみだ。-----------------------------------この世界は、人とカムイが互いに関わり、成り立つものだと考えられていました。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2008.03.31
コメント(0)
-
送り迎え
いやはや、ようやく送り迎えの慌しさが終わった。金曜日。夜7:40 息子をから迎えに。夜10:05 おねえを近くのバス停まで迎えに。演奏会前日の練習。土曜日朝4:40 息子をの遠征のため送る。朝7:35 おねえを演奏会本番のため、最寄の地鉄電車駅まで送る。おねえの定期演奏会のため、15:10に自宅でて帰ったのが21:30。夜11:40 おねえを迎えに富山駅まで(なんと、全員で打ち上げだと)日曜日朝7:35 おねえを最寄の地鉄電車駅まで送る。(後片付け+αだと)夜8:30 息子を遠征からの迎えに。いやはや、子供たちが揃ってイベント。まあ、これも親の定めか....
2008.03.30
コメント(2)
-
倉庫開き
息子たちが遠征に行っている間に、倉庫開き。大山FCが管理を任されている殿様林グランド。その倉庫とトイレを開け、沢山あるサッカーゴールにネットを張る。これが生半可な数ではない。一方、お母さん方は、トイレ掃除とかブルーシートとかの虫干し。9:00から始まり、約2時間ほど、ママも一緒に参加した。ごみ拾いもしながら、いよいよシーズンインだ。お父さん方も12人くらい参加されていて、顔あわせにもなった。しかし、大山FCで管理していたとは知らなかった。お父さん方の中にも、今日初めて同級生だったことがわかったり、同じ中学校の卒業生だったり、思いがけずいろんなことが判明。これはこれで、いいタイミングだ。トイレも交代で、これからずっと掃除をしていく。それも、素晴らしいことだと思う。息子も、しっかりしたクラブに参加できて、いい経験を積んでくれることと思う。
2008.03.30
コメント(0)
-

【子供に大切なことは、「食卓」で学ばせたい。】大野誠著
我が家は、朝食だけは家族が揃ってすませている。夕食は、なかなか揃わない。私は仕事など、娘は部活、息子はサッカー。それでも、朝食で顔を合わせる習慣があるだけ、随分と助かっている。今日も、元気にスタートの気持ちになる。もちろん、ママの手作りの料理がそこにはある。まあ、たまには買ってきたものが並ぶこともある。しかし、基本的に手作りが主。当然、箸の持ち方とか、食べ方とか.....それよりも、手作りという気持ちが伝わる。一番早い人の時間帯にあわせるのだ。もちろん、頑張って早起きするとかいうこともあるし、いろいろある。しかし、言葉は少なくても、顔を合わせることの意味は大きいと実感している毎日だ。--------------------------------まちの中の庭に、24種の野鳥がいました。(特定非営利活動法人 生態教育センター)
2008.03.30
コメント(2)
-
第56回スプリング・コンサート
いよいよ、第56回スプリング・コンサートの本番。保護者のスタッフとして、16:00に現地へ。保護者スタッフ15人ほどのうち、親父は私ともうお1人の2人。やはり、お母さん方が中心。会場のオーバードホールの裏に入るのは3回目。なので、わりと馴染みがある。5時頃から一般受付に、お客さまが並び始めている。くじ引きの結果、自分の持ち場は2階の左後部の会場係り。2階席といっても、実質は1階2階がフラットなので、全体がよく見える。5:45開場。そして6:30開演。4階までほぼいっぱい。5階席にもちらほらとお客さんがいらっしゃた。第一部 オープニング・ステージ・オープニング(マップ・オブ・ザ・ワールド)・ブライアンの休日・ハイランダー・タナバタ第二部 クラシカル・ステージ・クラリネットのための小協奏曲・第六の幸福をもたらす宿第三部 ポピュラー・ステージ・パート紹介・ダンシング・クイーン・メモリーズ・オブ・ユー・ハピネス・シャンソン・メドレーアンコール・蘇州夜曲・????2曲客演の大浦綾子さんのクラリネットのソロは、本当に心にしみた。ホール全体が水を打ったような静けさで聴き入っていた。パート紹介も、各パートが趣向を凝らして楽しい時間だった。三部の頭で12人くらい、ダンシング・クイーン、ハピネスのところで、40人くらいの部員が、ステージやフロアで踊る。おねえも踊っていた。自分の席からは、ちょっとハッキリしなかった。だが、ママは1階の前列から7番目の席にいたらしく、よ~く見えたのだ。もう、楽しくて楽しくてどうしようもないという顔をして踊っていたそうだ。自分の妹も見に来ていて、3階にいたらしいが、ちょうど良く見えたらしい。「とっても、かわいかった」とか。流石に部員が104名もいると、いろんなことができる。40人くらいが踊っていても、60人が演奏。それだけいれば、音に厚みもある。9:00終演。がんばったおねえに当日の様子はこちらに少し。来年は中心メンバーだ。この日のために、一所懸命に練習をしていた。バテバテでキツイ時もあったようだが、これで、報われただろう。
2008.03.29
コメント(2)
-

【さようなら、コタツ】中島京子著
部屋。人は部屋で生活を営む。もちろん、部屋にもいろんな形がある。例え、薄い壁であろうとも、障子1枚であろうとも、仕切られることで一つの空間ができあがる。それだけで、随分と気持ちも変わる。そこには、人と人の営みもあるし、変化もある。予想外のことも沢山起きる。部屋を変わるだけでも、見える景色も空気も変わる。そんな不思議な力が部屋にはある。------------------------------------日本で児童虐待の存在が知られるようになったのは、1990年頃からです。(特定非営利活動法人 子どもの虐待防止ネトワーク・あいち)
2008.03.29
コメント(0)
-

【話すことが苦手な人のアサーション】平木典子/伊藤伸二著
自分を尊重し、相手も尊重する。相手の反応も「YES」も「NO」もあることを前提とする。アサーション。この2点が大切なポイントだと思う。しかし、これができている人は意外に少ないのではないだろうか。最近のパワーハラスメントではないが、それを考え直す視点がここにある。また、この本の副題として『どもる人とのワークショップの記録』とある。どもりも、一つの個性として捉えることで、随分と考え方が変わるものだ。すらすらと話す人よりも、遥かに沢山のことが、その人の思いや人間性までも伝わることもある。そう考えた時、本当のコミュニケーションとはと考えざるを得ない。一方的に流すだけではコミュニケーションではない。そんなことを考えた。
2008.03.28
コメント(2)
-
離任式
息子の通う小学校での離任式。今回の先生方の異動は、ここ数年では一番少ないものだった。ただ、小学校・中学校とも校長先生が揃って変わる。これは、珍しい。息子は、学級代表ということで、なんと校長先生に花束を渡す役目。なかなか経験できるものでもないぞ。他の異動の先生も、長い方が多かった。もうそろそろかなと思っていた、おねえが担任をしていただいた先生は異動にならなかった。とってもいい先生。ずっと、5年を担任し、そのまま6年へ繰り上がりを、これで3回。きっと、4月から5年担任で....と、勝手に想像しているのだが。中学校のほうは、校長先生と一番長い先生だけ。あとは、用務員の方と給食の方。まあ、そうだよなあ~とは思った。ということは、来年は....そんな時期になってしまった。新聞にも、自治体を中心として異動の記事が毎日のように掲載されている。これも、風物詩の一つ。春はそこまで来ているのを実感する。------------------------------------カンガルーケアを知っていますか。(特定非営利活動法人 自然育児友の会)
2008.03.28
コメント(0)
-
事前打ち合わせ
夜7:30から打ち合わせ。土曜日、おねえの高校の吹奏楽部の定期演奏会がある。昨年の反省を踏まえ、今年は吹奏楽部の保護者にもスタッフの依頼があったので、手をあげた。3月末にスプリング・コンサートとして定期演奏会を実施している。卒業式を終わった3年生も参加する。今年は、部員も100名を超えている。昨年から大々的にやり始め、いろいろ課題が残ったということが発端。OB,OGも手伝いには来てくれるが、手が足りないのだ。今回は保護者の方で18名が手伝っていただけることになった。その事前打ち合わせ。都合がつかなくて出席されない方もいらっしゃたが、なんと、親父は自分だけだった。まあ、PTAの役員もやっていたので、こんなのには慣れているので、あまり気にはならない。打ち合わせが終わったのが8:45。同じところでリハーサルをやっていたおねえを乗せて帰宅。1年前に、入学前の立場で演奏会を見て、凄いと思った。そのステージにおねえがたつのだ。今年は、オーバードホールの5階席までを使う。昨年は、能登沖地震の影響で落下物があったということで、4階席までだった。オーバードは立ち見は禁止されているので、会場に入りきれない人もいたとか。果たして、今年はどうか。------------------------------------勉強しようとしても、考えることができません。(日本国際飢餓対策機構)
2008.03.27
コメント(2)
-
捜索
夜8時から、補導員として校下を巡回。最後に地区センターに戻る時に、小学校のグランドの照明がまだ点いていたので、ちょっと行ってみた。と、そこにパトカーがいた。しかも、小学校の教頭先生と知っている先生と、お巡りさんが話しをしていた。なんと、小学校の子どもが行方不明になっているという8時頃に近くの交番に、お母さんが相談にこられたとか。偶然ではあるが、知ってしまたからには、帰るわけにはいかない。寒い雨模様の空。しかも、こんな夜遅くに、小学校の3年2年と4歳の兄弟。学校の先生方も集まってこられた。地域の消防団にも声をかけた。やがて、その子のお宅の近くの団地へいき、皆で捜した。も風も酷くなってきて、随分濡れながらも、皆で捜した。そして、10時20分頃。一緒に捜している人のに連絡が入った。5キロほど離れた別の交番に保護されたという連絡が。ほっとした。嬉しかった。これほど、安心したことはない。事情は多少は聞いたが、とにかくよかった。見つかるまでは、帰れないと思ったし、小さな子どもたちが3人だ。いろんなことを考えた。本当によかった。
2008.03.26
コメント(4)
-

【モンスターペアレント!?】諸富祥彦著
耳にしてはいたが、改めて驚き呆れ悲しくなり、哀れみすら感じてしまった。モンスターな親の登場。教師にばかりキツイ視線が集まり、資格の更新だとか、研修だとかマスコミも一緒になって煽っていた。それであれば、ここの出てくるような親たちも同じではないかと思う。人間としての再教育が必要だと思う。給食費は払わなくていい。子どものことで早引けしてきたから、その分の給料を払え。石を投げて窓ガラスを割るのは、そこに石があるのが悪い。箸の持ち方を教えてくれないのはどうしてだ。などなど、反吐がでる。そして、何かあれば徒党を組んで、相手の人格や生活を踏みにじる。幸いに、今のところ、うちの子供たちの同級生の父兄には、そのような方はいない。しかし、違う学年では耳にしないこともない。子どもが荒れるのは、基本的に家庭の問題も大きい場合がある。親が、いろいろ吹き込む場合すらあると聞いて、愕然としてしまう。著者は、そんな中で、先生方の援助もされている。もちろん、父兄の援助もされている。そんな先生のホームページはこちらとにかく、自分の子どもたちの周りにいる父兄には、このような人たちがいないようにしたい。
2008.03.26
コメント(0)
-
息子からの電話
夜7:15頃が鳴った。「もしもし、○○です」「もしもし、パパ」一瞬、言葉が出てこなかった。あっ、そうか、息子の声だ...と頭が回り始めた。息子は、じじ・ばば、従兄弟(自分から見たら甥姪)たちと。息子も電話をかけてきたのはいいのだが、言葉がなかなか続かない。ご馳走何食べたお風呂入った何して遊んでるとか、月並みなことしかでてこない。「あおのね、ビリヤードやったんぜ」「誰と」「○○兄が教えてくれた」「....」電話を通して聞く息子の声は、随分、大人びて聞こえる。それにしても、おやじと息子の会話ってこんなものかなあ。ママとだと、随分違うんだろうけど.....----------------------------------私が欲しいものは3つ、仕事、教育、車いすです。マラリー(地雷廃絶日本キャンペーン)
2008.03.26
コメント(2)
-

【なぜマネジメントが壁に突き当たるのか】田坂広志著
実感している。確かに、よくはなっているのだろうが、同じ失敗がなくならない。いや、かえって増えているのかもしれない。納得した点がたくさん。ベストチームを作ってもダメ。原因をたどっていってもダメ。(まあ、これは対応はまずいのだ)なぜ、人が育たないのか。(育てるという視点がないのだ)確かに、原因をつぶしていても、もぐらたたきと同じレベルが多い。なんと言っても、人。そして、どれだけ我慢できるかだと思うのだが。
2008.03.25
コメント(0)
-

【小学五年生】重松清著
息子も丁度、小学5年生。読んでいて、何となく息子のこの1年間の様子ともだぶってくる。そう、少し大人に近づき始める頃。身近にいる息子を見ていると、逞しくなった~と、まだまだというのが同居している。びっくりしたり、あきれたり。そんな空気を、とてもよく表している。-------------------------------------ごみを減らす、気持ちは大切。減らす人を増やす、仕組みも大切。(特定非営利活動法人 中部リサイクル運動市民の会)
2008.03.25
コメント(0)
-

【無防備な日本人】広瀬弘忠著
まさに、無防備のかたまりだと痛感。熱しやすく冷めやすい文化そのもののあらわれ。リスクそのものもわかっていない。しかし、この中で一番強烈だったこと。それは、何を信用し、何を信用しないかの結果。日本政府やマスコミのことは、信用しないものの1番目、2番目。それも、断トツで。一番信用するのが、国際的な機関だという。ここに、今の状況があらわれている。
2008.03.24
コメント(0)
-
バイパス
金沢へ行く道。15日に開通した倶利伽羅峠~津幡町の間の8号線バイパス。初めて通った。快適そのもの。信号も少なく、山間を下りると片側2車線。途中も、信号ではなく誘導路で車が出たり入ったり。距離的には若干遠回りなのだろうが、時間的には短縮されているのだろう。8号線バイパス。と、最近話題の道路特定財源云々が頭をよぎる。ニュースで偶然みたのが、どこかの自動車専用道路。3400台通行の予想が600台。しかも、在来の道路とあまり時間が変わらないのだという。一方で、ガソリンの暫定税率の件で、道路補修の発注をストップしているとか。これは、完全に、優先順位の考え方がおかしいのだと思う。関連する道路族国会議員などの力関係なんだと思ってしまうし、それは、哀しいことでもある。それにしても、この快適さのウラにあるもの。つぶされた田畑。移転させられたお宅。そのあたりのことを、全く考えれなくなりつつある自分。いろいろ考えさせられるバイパス道路。
2008.03.24
コメント(2)
-
終業式
姉弟そろって今日は終業式。ということは、学年末の通信簿の日。姉は高校1年『成績通知表』、弟は小学5年『あゆみ』。まあまあ、2人ともほどほどの成績だった。姉は何とか目標をクリアしたが、弟が可もなく不可もなくといったところか。姉は皆勤賞、弟はインフルエンザで出席停止の3日間を除いて皆勤賞。このあたりは、2人ともえらい本当に休むことは稀だ。学校へ行くのが楽しくてたまらないようで、それが一番2人とも、新学年からの課題もはっきりしているし、そのあたりをどうフォローしていくか。ここが、親の腕の見せ所だ。2人とも、あんまり手がかからないので、まあ、ラクなんだが。強いて言うと、結構マイペースな姉弟。特に、弟のほうがその傾向が強い。目立つこともあまり好きでなきのもあるし、やればできるのがわかっているので、積極性が課題となってしまう。そこさえ、姉のようであれば、随分と変わるんだがな~。まあ、自分に似ているところでもあるのだが....さてさて春休み。姉は29日の定期演奏会の追い込み、弟はの本格的なシーズンin。楽しみだ-------------------------------------男性の5割、女性の7割は、読み書きができません。(特定非営利活動法人 シャラプニール=市民による海外協力の会)
2008.03.24
コメント(2)
-
田圃と畑仕事
朝からまずまずの天気。午前中は、じゃがいもの植え付け。肝心の息子はの練習でいない。例年どおり2畝に、約110個の種いもを植える。久しぶりに鍬を持つのと、土が結構湿っていて鍬に着くので、最初は少し手間取った。まあ、それでも、少しやっているとすぐに調子がでてきたので、意外に楽だった。と、その間にの行き来が...ママが出て行って、少しして戻ってきた。そして、妹がやってきて、叔母さんもやってきた。妹には、甥っ子の高校入学祝いと、姪っ子の中学就学祝い。叔母さんには、従姉妹の子どもの小学校入学祝いを、それぞれ。そう、ママが走っていたのは、お金をおろしにだったのだ。『丁度、急いで行ってきてよかったわ』というのが、あとの感想。午後は、田圃にでた。道路拡張で少し田圃が削られたのだが、その分の土が野積みのまま。一度には無理なので、少しずつと思い、田圃の低いところへ土を入れる。石を取り除きながらでもあるので、なかなかはかどらない。それでも、少しは野積みの山が減ったので、まあ、やったかなと。あとは天気の具合を見ながら、毎週の土日をかけてやらないと。遠征がなければ、息子も手伝ってくれるだろう。
2008.03.23
コメント(0)
-

【やまこし復興】中越地震特別取材班+北陸地域づくり研究所著
中越地震は未だ終わっていない。新潟県山古志村。棚田と闘牛、美味しいお米は、まだまだ帰ってきていない。その後の中越沖地震などもあり、忘れ去られているのではと思う。その山古志村の復興を丹念に追った記録。人の力強さを改めて認識した。山へ、故郷へ一日でも早く帰してあげたいという、官民を超えた人々の熱い思いが伝わってくる。そして、新しい発見があった。いわゆる工事関係者など土木技術者の意味だ。英語ではcivil engineerとなる。civil つまり市民。そこには、日本における土木技術者のイメージとは随分異なるものがある。よくよく考えてみる必要があると実感している。また、山古志村の歴史にもふれられている。以前読んだ掘るまいか-山古志村に生きるを思い出した。-----------------------------------探していたのは、生きることの充実感だったのかもしれない。(特定非営利活動法人 ホールアース研究所)
2008.03.23
コメント(2)
-
勉強会&懇親会
午後いっぱい、所属しているNPOの勉強会。基本的にはITに関するNPOではあるのだが、最近はヒューマン系のほうへ関心が行っている。今回は4時間で3テーマ。『ファシリテーションの紹介と実践』『移行システムについて』『やってみましたコーチング』3つのうち、2つがヒューマン系になる。ただ、やはりどんなシステムを導入するにしても、やはりそれを受け入れる土壌・人間系のところができていないと、効果が半減する。ぎゃくに、そこができていることで、システム構築に対する考え方も随分と変わってくる。システム自体の位置づけが変わる。システムに依存してしまうのか、システムを使いこなすのか。この差は、予想以上に大きいと感じている。そして、その後懇親会へ。やはり、この会のメンバーとの飲み会はこころおきなく飲むことができる。職場の飲み会は、やはりどこか落ち着かないところがある。どうしても、相互の関係が色濃くそこに持ち込まれるからだと思う。所属する会社も立場も違う。ただ、同じ思いを持って集まっているからこそなのかもしれない。帰りのバス。本を読んでいたのだが、チラッと目を掠めたものがあったのだが、気にしなかった。降りるバス停が近くなった時に、『100円玉ある』の声が。やっぱり、娘だった。目を掠めたのは、娘のマフラーの色だったのだ。帰宅して、娘がママに『バスに乗ったら、パパがいたからビックリした...』と。まあまあ、こんなのもいいもんだ
2008.03.22
コメント(2)
-
遠征
息子は、今日日帰りで遠征。群馬まで往復。しかも、3年生も今回は同行するのでで。朝5時に出発。そして、帰宅したのが午前0時を回っていた。流石に疲れはあるようだが、バスの中で結構寝てきたようだ。汗もかいていたあとがあるので、シャワーを浴びて、しばらくは起きていた。今回は練習試合のための遠征。それなりに試合には出たようだ。ポジションは、右のバックスと左とトップ。監督・コーチもチームづくりの最終段階だろうと思う。おまけに、息子はチームに参加してまだ3ケ月ほど。適性もあるし、伸び具合もある。きっと、そんなこともあり、いろいろ試しているのだと思う。今回の遠征をとおして、また一回り成長したように思う。なんと言っても、表情がだいぶんいい方向へ変わってきているのだ。--------------------------------------黄砂の発生回数は、50年で36倍になりました。(東アジア環境情報発伝所)
2008.03.22
コメント(0)
-

【選挙トトカルチョ】佐野洋著
そうかあ、そういう深謀遠慮があったのか。つかり、オチ。なるほどなあ、でも、そうだったら凄い参謀になれるだろうと思う。そんな短編集。実は、佐野洋さんの名前は知っていたのだが、読んだのは初めて。なんとなく、読まず嫌いみたいなところがあった。短編ということもあり、スラスラと読める。ただ、あまりに上手すぎて、ちょっと物足りないような気もしたのもある。ただ、次も読んでみようかなと思ったのも事実。-------------------------------------アイヌ・ネノ・アン・アイヌ。アイヌ語で、人間らしくある人間。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2008.03.21
コメント(2)
-
大島町絵本館
おねえは部活、息子は友達が遊びに来る。ということで、ママのリクエストに答えて大島町絵本館へでかけた。バムとケロで有名な島田ゆかさんの絵本原画展を開催していたのが主な理由。行ってみると思いのほかが多い。丁度、イベントを開催していた。JBBY全国リレー講演会として、末吉暁子さんの講演と~ざわざわ森のがんこちゃんのおはなしとペープサート上演~小さな子供たちも一所懸命に人形劇を見ていた。講演の時間になると、子供たちはいなくなったが、お話自体は、大変興味深く聞かせていただいた。その後、島田ゆかさんの原画をじっくりと見た。絵本では見ていたのだが、やはり原画となると、細かな筆のタッチも見えて随分と感じが変わって見えた。少しは、ママのガス抜きにもなったようで、行った甲斐もあった。まあ、絵本を見ることは嫌いではないので、まあ、いいのだが。
2008.03.20
コメント(0)
-

【チェスト!】登坂恵理香/横山充男著
チェスト!読み始めてようやくわかった。そうだ、鹿児島の武術の気合だ...と。遠泳大会。それをめぐる子供たちの成長。いや、子供たちだけではなく、親も先生も成長する。実際、自分もあまり泳ぐのは得意でないので、身につまされるところもあった。子供は時として残酷なものだとも言う。しかし、それは大人の残酷さとは、かなり違うものだと思う。それを乗り越え、ともに成長していくのだ。う~ん、やっぱり、友はいいものだそして、何よりこの装丁の3人の姿。もう、これがすべてだ。
2008.03.20
コメント(2)
-
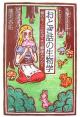
【おとぎ話の生物学】蓮実香佑著
確かに言われてみれば不思議なことがてんこ盛りのおとぎ話。実際に、そんなことがありえるのかと考えてはいけないのだろうが、考えてみると面白い。と言うか、ありえないことも。桃太郎はどうして鬼退治に出かけたのか?ウサギはなぜカメに負けたのか?竜宮城はどこにある?などなど、確かに小さい時に不思議に思ったこともあるような。ウサギとカメ。短距離選手のウサギと長距離選手のカメ。そこには、カメの深~い戦略があったのだ。そうなんだ、そうかもなあ~。こんな発想も面白い------------------------------------アフリカでは、6千万人がねむり病の危険にあります。(特定非営利活動法人 国境なき医師団日本)
2008.03.20
コメント(0)
-
もつ鍋
午後は代休。息子を矯正歯科に連れていった。いつもは、岩峅寺に歯医者に土曜日にいくのだが、今度はの遠征があるため、日を変えてもらった。が、そのぶん、和合までいかないといけない。で、その帰りに、買出し。の前に、どうしてもと言うのでマックへ。そして、すぐ近くにある自家焙煎珈琲彩々へ。豆を買って、1杯を御馳走に。息子は、アップルパイをモグモグ。まずは、酒屋でビールと焼酎。そして、スーパーでもやし、ニラなどを。目当てのもつがあったのだが、いつも食べるやつと違うメーカーのだったので、違うスーパーへ行って、ようやく購入。これで、準備万端。夕方、NPOの理事会に出席し、時間がきたので集合場所へ。ほぼ時間とおりに集合。そこから車で15分あまりで、自宅へ。そして、3人で飲み始めた。20代、30代、40代と年代も違う3人。2人ともまず感心したのが、我家の静けさ。そう、道路から少し田圃の中に入っていることもあり、あんまりの音がしない。他の2人の家は、道路に面していたり、街中にあったりとかで結構うるさいらしい。しばらくして、もつ鍋がでてきた。具も白菜、もやし、ニラ、しいたけのみ。あとは、もつと味噌。いやあ、薄味気味で、もつのだしがたっぷりでていて美味かったゆっくり、飲んで、食べて、喋って...夜は更けていった。
2008.03.19
コメント(0)
-

【グループ・コーチング入門】本間正人著
かねてから関心もあり、多少は本を読んだり、実践で気をつけたりしていたコーチングスキル。そこに、このタイトルだったので、惹かれた。コーチングから連想するのは、どうしても1対1というイメージが強い。しかし、実際、それだけではクリアできない要素も、多いのかとも思っていた。グループのミーテイング等で、コーチングの考え方をどう適用するか。これは、十分に勉強する必要がある。もちろん、基本的な視点は変わらない。「傾聴」「観察」「承認」「質問」の4つの視点を持ちながら、グループ・ミーテイングをデザインする。そして、振り返りと、グループ・メンバーの成長。さて、4月からまた新入社員研修の講師も始まる。今年は、昨年より人数も多いし、たずさわる日数も増えた。今から準備しておくとともに、新入社員にもこんな視点を持ってもらおう
2008.03.19
コメント(0)
-
二十四の瞳
病気で入院のため、遠くの病院へ。そんな子供たちもたくさんいるのだろうと思う。そして、卒業の季節。できれば元の学校で、一緒に卒業したいと思う。そんな記事が、掲載されていた。まさに、今の時代ならでは。ITの技術を使っての卒業式だ。小さな小学校での卒業式。小さい頃からの友達。全員で12人。まさに、二十四の瞳。新聞記事を読みながら、胸がじ~んとなってしまった。こんな友達は、一生の友達になるんだろうな。-----------------------------------人は言葉で説明できるよりも多くを感じとることができます。(財団法人 世界宗教者平和会議日本委員会)
2008.03.19
コメント(2)
-
名付け親
本気で儲ける会のネーミング。今期も終わろうとしていて、メンバー各位の参加度合いや思いなど、いろいろ課題もでてきた。また、この会の名称自体も、そろそろ変えてみてはどうかとなった。そこで、メンバーやオブザーバーから新しい会の名称を募り、その後投票となった。集まった名称は20を超えた。そこで、投票。もちろん、webでの投票だ。結果、なんと、私が提案したのが1位になってしまった。その後、決戦投票をするかとか、いろいろ案もでたり、他の課題もあるので、幹事+オブザーバー(参加できる人のみ)で協議。結局、そのまま、私の案が通ってしまった。もちろん、そこに込めた思いは沢山ある。嬉しいようは、恥ずかしいようなまた、4月以降の会の取り組みの方向性などについても協議した。いい方向へ進んでいると思っている。熱い思いを持った人たちが、お互いに切磋琢磨することで、より高いレベルを目指す。さてさて、どうなるか、楽しみだし、自分もオブザーバーではあるが、力を注ぎたい。
2008.03.18
コメント(2)
-

【東京公園】小路幸也著
ちょっと不思議な、それでいて清々しさと、ほのぼのとしたぬくもりを感じる恋物語。小路さんというと、東京バンドワゴン。その著者の人柄なのか、人情味溢れるぬくもりの世界。そんな一端を感じる作品でもある。カメラのファインダーって、そんな不思議な力を持っているのかもしれないなあ。世界のある一面を切り取ってみる。そこに見えてくるものへの思いみたいなものが、対象となっている者・物にも伝わるのかも。写真はたまにしか撮らないが、素人なりに『あっ、このアングルだ』というの感じる。その時は、被写体との一体感を感じる(こともある)。そう、ファインダー越しに、一本の糸で繋がるような。-----------------------------------日本の森は豊かに見えて、危機は静かに進んでいます。(特定非営利活動法人 地球緑化センター)
2008.03.18
コメント(2)
-
アフリカ 森の政権争い ~長老チンパンジー 大活躍~
見入ってしまった。これこそが、社会のあるべき姿ではないか。長老サルの知恵と存在意義がここにある。変な例えなのだが、よほど今の人間社会よりも、社会としての秩序・思いやりに溢れているのではないかとさえ思う。やはり、チンパンジーのほうが先輩なのだ。集団で生活し、群れを構成する。必然的に、そこには秩序・掟が必要となり、社会が形成される。そして、その社会を維持するためにも、長老たちの経験と知恵が大切になってくる。今の自分の周囲を見ても、やはりそう思う。特に、地域での生活を考えると、年配の方々の知恵と経験にはかなわないと思う。それを次代に引き継ぐのも大切なこと。もちろん、そのままでいいとも思わないが、蓄積されたものの意味は大きい。しかし、この長老チンパンジーは、いい表情をしている。もう、仙人のようですらある。
2008.03.17
コメント(2)
-
旅立ち
今日は、中学校の卒業式。そ~かあ~、もう1年も経ったのかと感慨深い。おねえも、もう高校の3分の1を終了してしまったのだ。明後日は、小学校の卒業式。いよいよ、息子も最高学年になる。朝の集団登校の班長だ。と、言っても僅か4人での登校。6年生が2人卒業して、新1年生も、もう1年後だ。何となく、登校班長ということで、その気になっているようなふしもある。寂しいのは、となりの町内の小学生が0になることだ。15軒ほどの小さな町内ではあるのだが.....そういえば、近くにいた白鳥たちも、越冬を終わって旅立っていった。きっと、2,3日前に行ったようだ。今は、その越冬していた田圃も、水を抜かれている。確かに、1週間ほど前から、集団で飛ぶ練習をしていたようにも感じていた。来年もまた、来てほしいものだ。そう、その頃には、息子もあと少しで小学生も終わる頃か。早いもんだなあ~と、今だから感じるのだろう。春。命の芽吹く、ステップアップする季節だ。-------------------------------------私は、よく見て、よく聞きます。そしてみんなと、仲良くします。(社団法人 ガールスカウト日本連盟)
2008.03.17
コメント(0)
-

【東京大学応援部物語】最相葉月著
東京6大学野球の中継でよく見る応援部の姿。相手に向かって拳を投げる。応援席をリードする。そして、試合終了後のエールの交換。独特のものを感じる。その陰に、こんなドラマがあるとは。特に、トレーニングの過酷さと、半ば不条理のような世界。そして、下級生の不出来の責任はその上級生へというしくみ。いろいろ、えっと思うところもあるが、なんとなく、うなずけるところもある。そして一番感じるのは、メンタル面の強さになるのかと思う。いやあ、本当に凄い。そして、これだからこそ、濃密な人間関係もできあがるんだろうと。東京大学運動部応援部早稲田大学応援部法政大学応援団立教大学体育会応援団明治大学応援團慶応大学応援部のhpは工事中???
2008.03.16
コメント(2)
-
飯の支度
昨日の昼前から、ママと息子はお出かけ。昨年暮れに解散した旧サッカーチームの5,6年生で恒例のお泊り。場所は、昨年と同じ飛騨まんが王国。きっと、夜遅くまではしゃいでいるんだろう。と、言うことで...昨日のお昼・夜・今朝とごはんの支度だ。夕べは、さしみと、久しぶりにホルモンを食べた。以前は、よ~く家でも食べていたのだが、最近は減ってきた。やっぱり、美味しかった~今朝は、魚を焼いて、味噌汁も作って.....意外なほど時間もかからんかったし。これも、毎週1回以上は、ご飯の用意をしているおかげか。ママに感謝せんといかんな~なんて。まあ、たまにだからいいので、毎日やっているのは、エライと思う。毎日続けることの大変さを感じるのだ。なんか、感謝の意を表しないといけんかな~
2008.03.16
コメント(2)
-

【塩の街】有川浩著
塩の街の風景って、どんなだろうそう思いながら、いろんな場面を想像した。そして、塩が象徴しているものは何見ただけで感染する。ただ、全員がそうでもない。その差はどこからくるのか。その人の心根の違いからくるんだろうなあ~と思った。それにしても、有川さんのはスラスラ読めるなあ。ただ、図書館シリーズから読んだこともあり、どうしてもそのキャラクターが脳裏をよぎってしまう。ただ、どこか共通点があるのは、気のせいかなあ。でも、好きだな。-----------------------------------家庭の電力消費は、30年前の4倍です。(自然エネルギー推進市民フォーラム(REPP))
2008.03.16
コメント(0)
-

【メンタル・コーチング】白井一幸著
北海道日本ハム・ファイターズの躍進の秘密がここにあった。確かに、ヒルマン監督の手腕もあるだろう。選手の力もある。もちろん、ファンの力もある。が、ここだったのだ。メンタル面を重要視したコーチング。なるほどと唸った最近のマイ・ブームの言葉は『納得性』と『内発性』。これがないと、本当の意味で長続きしないし、自分のものにもなりえない。そんなことを理解したうえでのコーチング。テーチングではなくコーチングなのだ。その、あるべき場所まで行くようにサポートすることだと思う。そんな意味で、今までの画一的な考え方では対応できない。だからこそ、理論も必要だし、人間性も必要になってくる。そして、一番共感した言葉。コーチが目立たない状況が一番いい
2008.03.15
コメント(0)
-

【大人の見識】阿川弘之著
軽躁。今の日本はますますそうなっているように感じている。それだけでなく、最近感じていることを、阿川さんがキッパリと言い切っている。本当に今のテレビは見るに耐えないものが多すぎる。歳をとったせいと言われるかもしれない。でも、それでも構わない。どのチャンネルをひねっても、同じ顔、同じトーン、同じ構成、そして作り手・出演側の自己満足の世界が蔓延っている。すべてがそうだとは思わないが。そんな中からの引用になるのだが、武田信玄の遺訓1.分別あるものを悪人とみること2.遠慮あるものを臆病とみること3.軽躁なるものを勇猛とみることまさに、今の日本そのもの。イギリスの文化。高い身分の人ほど、前線に立とうとする意識が強いどっちつかずの状況に長く耐えることが大切熱しやすく冷めやすい文化。我慢できずに、極端に走る文化。自分は安全なところにいて、一般に人たちを極限の状況に陥れるひとたち。確かに多面的な文化の1つの切り口ではあるが、学ぶべきところが多い。------------------------------------50年、緑の募金を続けてきました。(社団法人 国土緑化推進機構)
2008.03.15
コメント(1)
-
後片付け
今日は。それでもの練習はグランドだ。多少のでも外で練習。実際、試合は余程でない限り実施される。そんなの中でも、ボールの泊まり具合やスリップ、いろんな意味もあるし、何よりやはりグランドのほうがやりやすい。練習も終わり、後片付け。ゴールを片付けたり、グランドをならしたり。息子は大抵、一番最初にやり始め、一番最後のほうまで後片付けをすることが多い。このあたりは、自分と同じだ。自分のことは後にしても、先に後片付けをやってしまう。う~ん、これも遺伝それとも、背中を見て...なのか。しかし、そんな息子の姿を見るのは、とても嬉しいことだ。チームも変わり、グランドも変わったこともあるのか、また、今のチームの指導のあり方だろうが、子供たちも皆で準備や後片付けをやっている。もともとの息子の性格に合っているのかもしれない。そんなところも含めての習慣になってくれればいいと思う。
2008.03.14
コメント(0)
-

【人の痛みを感じる国家】柳田邦男著
時々、柳田さんの本は読みたくなる。そして、自分の目線の位置を確かめる。ほっとする時、愕然とする時いろいろ。今回も、いろいろ気づきがあった。人は、自分の痛みは我慢できないが、他人の痛みはいくらでも我慢できるのだ。この一言に今の日本は尽きるのかもしれない。ニュースを見ても、そんなのばかりだ。また、匿名のマイナスの部分もクローズアップされている。そんななか、心の分娩には3年かかるというくだりが心に沁みた。非行とかいろいろあるかもしれないが、抱きしめることでクリアできる部分も多い。そんな例も載っていた。あの、諏訪中央病院の鎌田先生もそんな経験をされているのだ。なるほどと思った。我が家は、子供たちを抱きしめることが珍しくない。別に照れもわざとらしさもない。今の子供たち(娘と息子)を見ていて、間違っていなかったと思えることが嬉しい。-----------------------------------昔々は、一人の子どもを一つの地域社会が育てていました。(特定非営利活動法人 子どもの虐待防止ネトワーク・あいち)
2008.03.14
コメント(0)
-
言葉の意味
最近、言葉の意味って何だろうと、ますます思うようになった一度、発せられると、どんどん意味が拡大解釈されてしまうこともある。もちろん、人によって理解も異なるのは一定いたし方ないと思う。言葉。伝えるためにあるのだと思う。伝える。問題は、どう伝えるかだ。もちろん、伝える側の能力もあるし、受け取る側の能力もある。能力だけでなく、経験やおかれている環境にも影響を受ける。そんなことを、痛感する毎日。事実をありのままに伝えるのは困難だ。ただ、よりわかりやく伝えることに意味はあると思う。が、脚色が過ぎると、どんどん事実と離れていく。脚色⇒加工⇒それをする人の解釈が入ってしまうのだ。そのあたりを、職場でいろいろ耳にすること、目にすることで、おやっと思うことが増えてきている。最近の世の中に目を転じてみると、ガソリンの暫定税率のことが話題になっている。ある番組で言っていたのだが、ある人の痛烈な言葉。『暫定』税率といわれながら、恒久的なものになっているガソリンの暫定税率。『恒久』減税といわれながら、軽く廃止されてしまった所得税減税。いつから、言葉の意味が変わってしまったのだろうかガソリンの暫定税率については、道路特定財源云々とことと、いろんなことがゴチャマゼにされて、感情論になってしまっている。現実は、かなり複雑なのものだと思っている。道路特定財源⇒道路建設⇒公共事業⇒それに依存している業界⇒と考えると、そんな簡単なものではないと思う。それこそ、長いスパンでの目線が必要。本当の意味での戦略なのかもしれない。話がそれてしまったが、そんな状況の中で、ほんの一部の情報のみが、曲がったように伝えられているのではないかという気持ちもある。一般受けのみを狙っているマスメデイア。言葉の意味が、今ほど大切になっている時はないのかもしれない。------------------------------------水俣病には、48年たった今も2万人以上の潜在患者がいます。(東アジア環境情報発伝所)
2008.03.13
コメント(0)
-
さんぽ(息子の替え歌)
となりのトトロの挿入歌でもある『さんぽ』たまたまの気まぐれでyou tubeを見ていた。もののけ姫に行き当たり、となりのトトロ、そしてさんぽへ。と、息子がPCに合わせて歌いだしたアルコール、アルコール、私は便秘歩くの大嫌い、どんどん戻ろう坂道、坂道、坂道、坂道(あとは坂道の繰り返し)いやはや、何とも、リズムには合っているのだが....坂道も、あとはリズムに合わせて歌うだけ。誰かに教えてもらったのかと聞いたら、自分が作ったのだとか...それにしてもだが、まあいいか------------------------------------人は一生に20万回、トイレに行きます。(日本トイレ協会)
2008.03.12
コメント(2)
-

【空をつかむまで】関口尚著
仲間って何だろう約束って何だろうそんなことを考えながら読んだ。最近、俗にいう青春物語関係を読み続けている。偶然半分、意図半分(ある賞の受賞作)。懐かしいなあ~、こんなんだったんだろうなあ~と思うこともある。話の筋としては、途中からだいたい先が読めた。まあ、100%ではなかったが、それはそれで安心感もあった。いつから、仲間になるんだろうなあ、ほんとに。気がつくと、そう思っている、そう感じたというのが実際。稀に、エポックメイキングなことがあるかもしれないが、自分にはあんまりそんな記憶がない。同じ思いを持つとか。同じことをやってきたとか。まあ、それはひとそれぞれだ。いやあ、青春だったんだねえ~------------------------------------自然に親しむ方法を知っています。(社団法人 ガールスカウト日本連盟)
2008.03.12
コメント(2)
-
NHKプロフェショナル『向き合うのは、命の鼓動』
NHKプロフェッショナル延吉正清さん。神の手をもつ、心臓内科医。ただただ、感動した。もちろん、そんな延吉先生のスタートは、救えなかった命にある。それから、自分の信ずる道を歩んでこられた結果が今。何より考え方が素晴らしい。『何も教えない。たくさん見せて、自分で盗めと。』そして、学閥に関係なく、意欲のある人にはどんどん手術の様子を見せ、面倒を見る。そして、『命を背負うのは、自分』という思い。
2008.03.11
コメント(2)
-
ハイテンションな姉と弟
今日と明日、県立高校の入試。と言うことで、おねえは学校が休み。なんと、クラス解散(1年生も終わり)の打ち上げだとかで、出かけていた。夜がなった。「もしもし、どなた様でしょうか。只今この電話は使われておりません。」とママ。「あのお~、娘ですけど~」とハイテンションなおねえの声が電話越しに聞こえる。結局、終バスで近くのバス停までくるからと迎えにいって自宅に戻ってきてからも、ママとハイテンションのまま.....一方、息子の方。今日もの練習。迎えに行った時は、丁度、センタリングからシュートの練習の最中。生真面目な息子だけが、自分の番の時に手を上げている。見ていると、結構上手くこなしている。全般的に、どの子もセンタリングの精度はまだまだだが、一連の流れはできているようだ。そして、練習の最後。センタリングにいい感じのボールがあがった。息子がシュートの番で、うま~く、ヘデイングシュートが決まった。と、監督コーチから「おお~っ」という声と拍手が。帰りの車の中、息子はご機嫌で「また、褒められた」と。そう、最後のシュートは本当に褒めてもらったのだ。家に帰ってからも、ママにニコニコ顔で報告していた。だけでなく、いろいろ喋り捲っていた。こんなにハイテンションな息子は、そうそうない。この調子でいってくれ~
2008.03.11
コメント(2)
-

【種まく子供たち】佐藤律子著
小児ガンを体験した7人の物語。亡くなったお子さんもいれば、克服したお子さんもいる。そんな7人の物語。自身の物語もあれば、周囲の人の物語もある。だが、不思議に悲壮感はあまり感じない。救われたという思いがよぎる。それはどこからくるのだろうか。きっと、明日へつながる物語だからかもしれない。種まく子供たち------------------------------------アイヌ・ネノ・アン・アイヌ。アイヌ語で、人間らしくある人間。(社団法人 北海道ウタリ協会釧路支部)
2008.03.11
コメント(0)
-

【わたし8歳、カカオ畑で働きつづけて。】岩附由香、白木朋子、水寄僚子著
児童労働。今まで、知らなかった言葉とその現実。世界で2億1800万人の子供たちが労働させられている。学ぶ機会もなく、過酷な状況の中で。そこには、貧困であるとか、学習の欠如であるとかいろんな要素もある。もちろん、搾取という許しがたい状況もある。しかも、これは全世界にある。地域による偏りはある。その2億1800万人の中には、少年兵たちも数多くいる。企業の社会的責任の一端として、児童労働に関係のある製品を扱わないというのもある。精神論だけでは解決できるような課題ではない。多くの要素が複雑に絡んでいる問題だ。しかし、少しずつでも、運動をしていかなければならない。そう、まずは知ることから、知らせることから。ILO駐日事務所児童労働のページ児童労働反対世界デーキャンペーンコードプロジェクト日本ユニセフ協会児童労働ネットワーク国際子ども権利センターフリー・ザ・チルドレン・ジャパンACE
2008.03.10
コメント(2)
-

【翼はいつまでも】川上健一著
『お願い、お願い、私』そう、ビートルズのプリーズ・プリーズ・ミーだ。これが、最初の1歩を踏み出す勇気の源。自分らしく。中学生。ある意味、一番成長する時期なのかなと思う。そんな日常の中で、なかなか殻を破れないもどかしさ。そして、1歩踏み出すことで、その殻を突き破り新しい空間が目の前に拡がる。そんな切なく、甘酸っぱい世界を軽快に描いている。途中、でてくる先生たちには辟易することもあった。が、先生たちも実は....そして、主人公の親父さんのかっこよさ。ほんの少ししかでてこないのだが、とても、重要な役割を果たしている。自分も、そんな親父なんだろうかと自問したりする。-----------------------------------桜の開花が、50年前より5日早まっています。(特定非営利活動法人 ドングリの会)
2008.03.10
コメント(0)
-
優秀選手賞
息子が、昨日からの群馬遠征から帰ってきた。日中のメールで、ママが大喜び。息子の名前が初めてメールの中にあったのだ。唯一の点のアシストをしたというのだ。夜8:30。集合場所にが戻ってきた。皆が降りてきて荷物を降ろし解散。一番最後にやってきた。やけに、荷物が多い。『優秀選手賞をもらった』と、疲れの中にもニコニコ顔。凄いじゃないか主催の前橋エコークラブのマーク入りのサッカーボールが御褒美だ。前橋エコークラブは全国レベルのチームのようだ。サッカーボールにしっかりマークが入っているのも凄い。初日の予選リーグは4チーム中2位で、2位トーナメントへ。今日のトーナメントは、結局、0-1、0-2、1-3の3戦全敗だったのだが、その唯一の点のアシストをしたということでなのかもしれない。息子に聞くと、その試合の後半だけの出場で、左のトップがポジション。それで、うまくアシストできたのだ。『左足で蹴ったんぜ』と。練習でも、結構、前のほうをやることも多いようだ。家についてその話をすると、もう皆、大喜び。息子も、まんざらでない顔。おまけに、山のようなお土産。横浜キャラメルケーキ、川越いものお菓子、そして新潟限定のチップス。赤城峠のSAで買ってきたらしい。もらったお金で一所懸命選んで買ってきたのだ。それもまた嬉しい一回り大きくなったように見えた。
2008.03.09
コメント(2)
-

春まちコンサート
春まちコンサートにママと出かけた。自宅から近い、大山文化会館で午後2時から開演。地元出身のプロの声楽家・ピアニストによる演奏が第1・2部。馴染みのあるメジャーの選曲でもあり、とても聞きやすい。それにしても、プロの声量は凄い。曲としては「さくら さくら」が、春らしくてちょうどよかった。これ以上ないというくらいの暖かな天気のためもある。第3部は吹奏楽。富山国際大学を中心に、付属高校、そして地元の上滝中学校・片山学園中学校の子どもたちも含め、総勢70名あまり。ステージが溢れんばかり。さすがに、これだけいると、音の厚みも違う。指導の先生絵もお話されていたが、大学生と中学生が一緒に演奏。両方にとって、いい経験にもなる。そして、最後は、会場の小学生もステージにあがり、皆で歌こんなに楽しいコンサートも久しぶりだ。小さな町の手作りコンサート。今年で4回目になるそうだが、はじめて聴いた。来年からも行くぞ。
2008.03.09
コメント(4)
全68件 (68件中 1-50件目)











